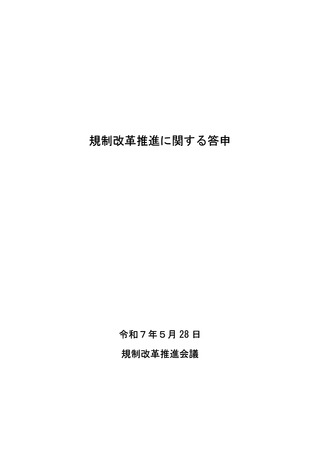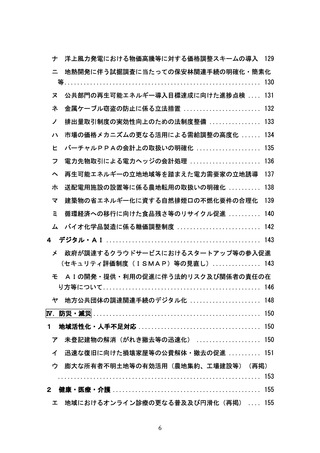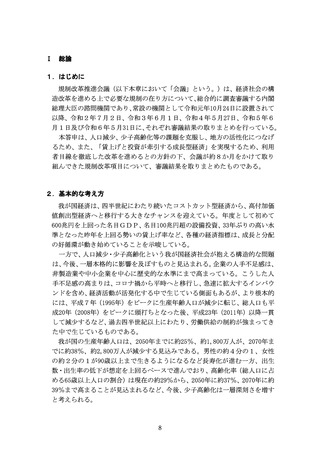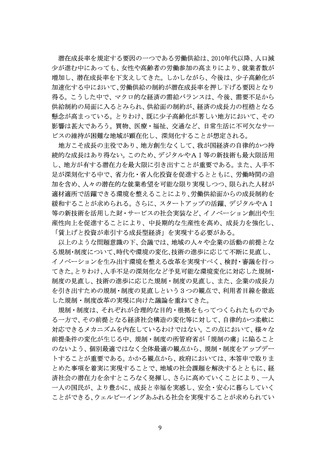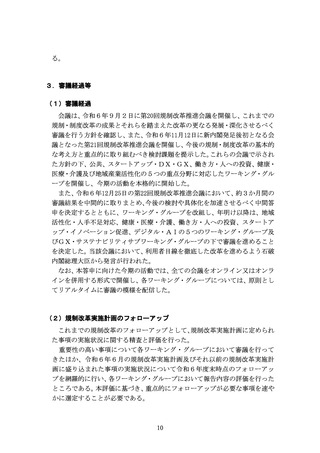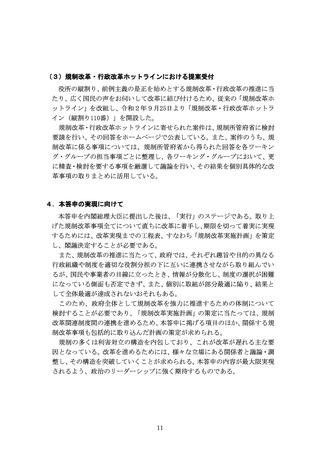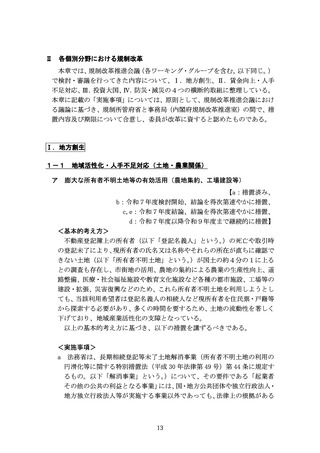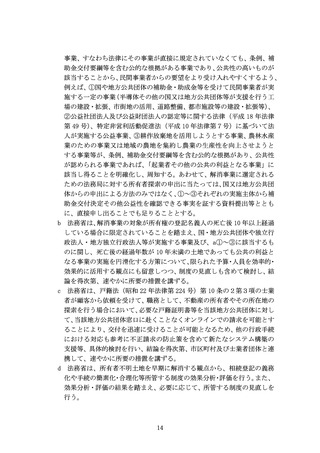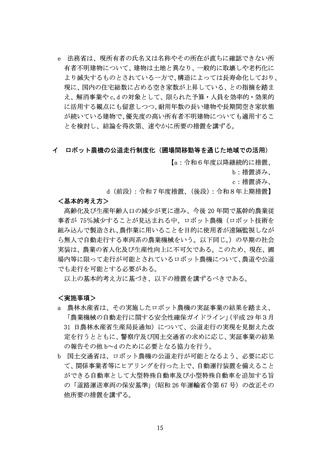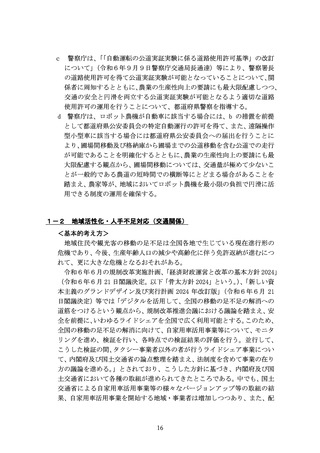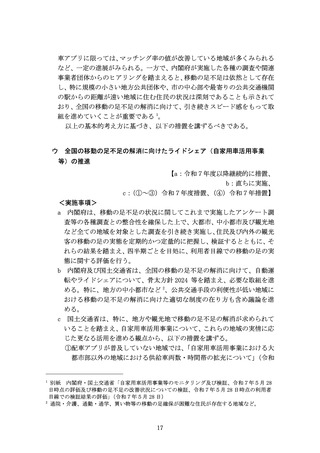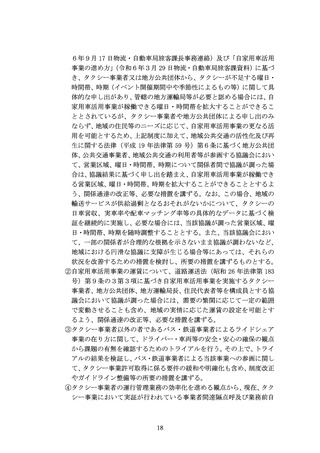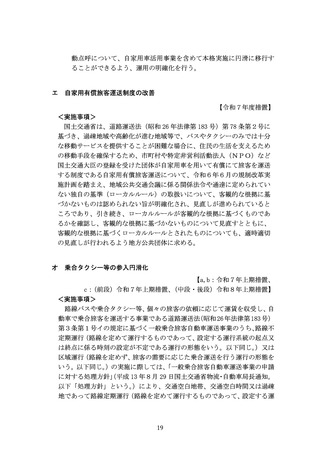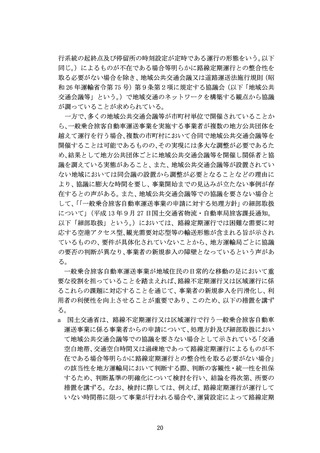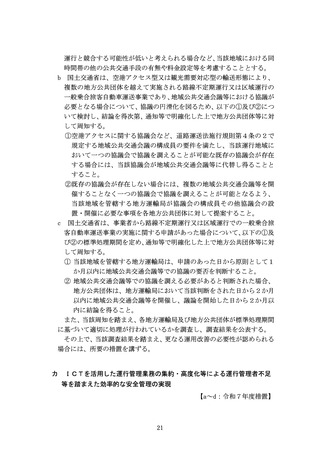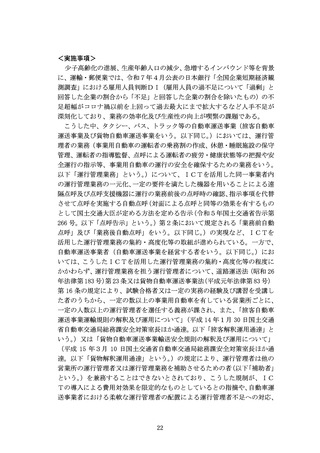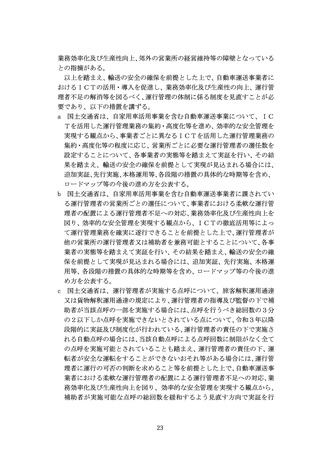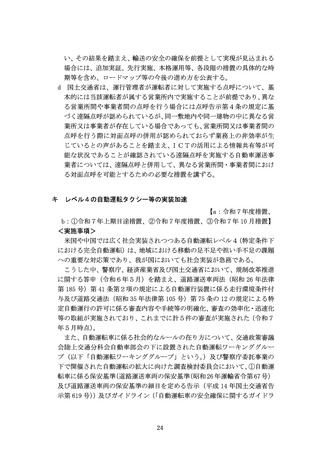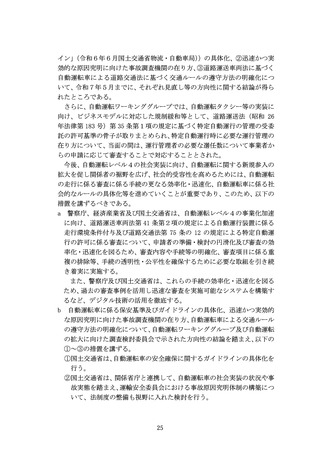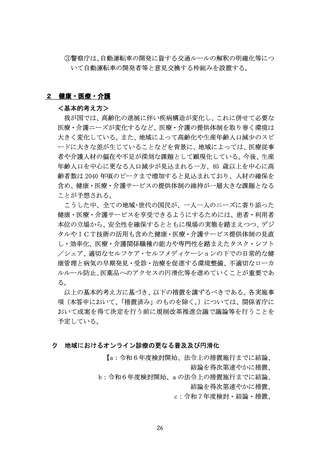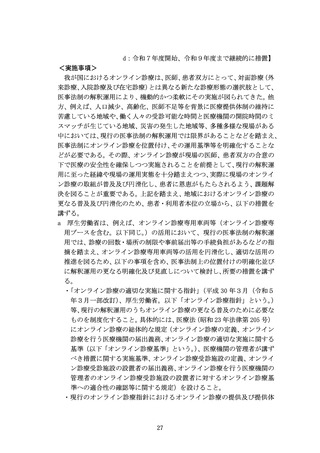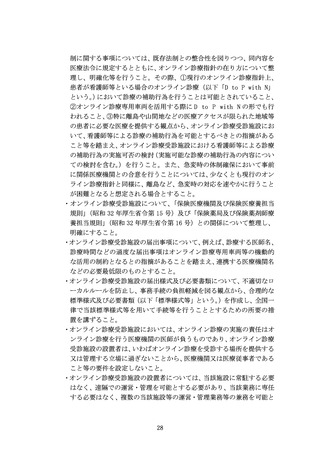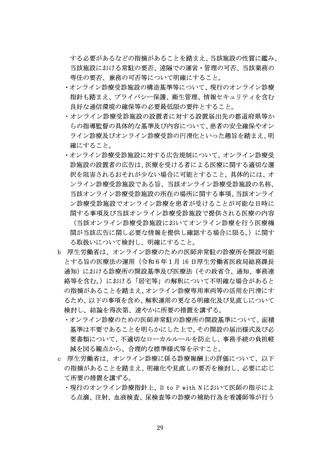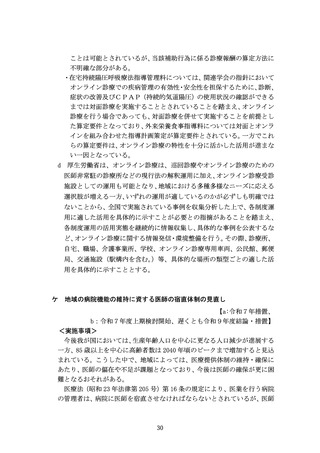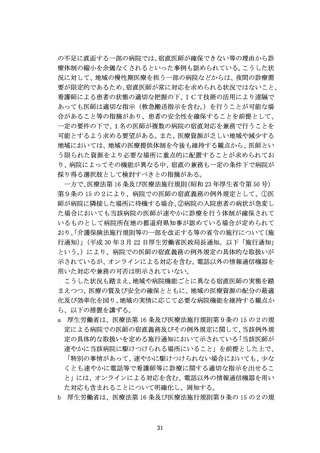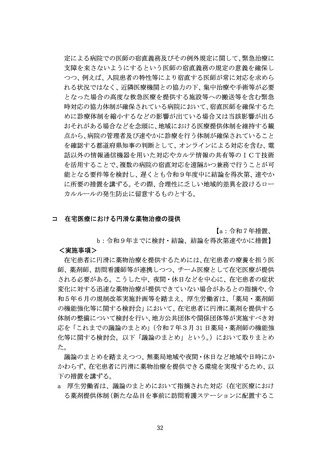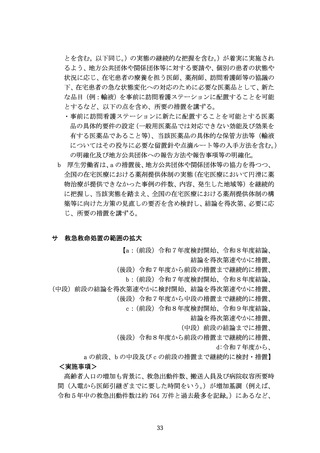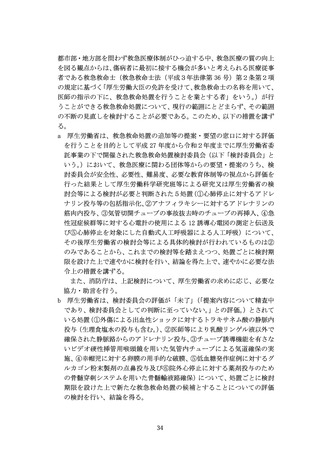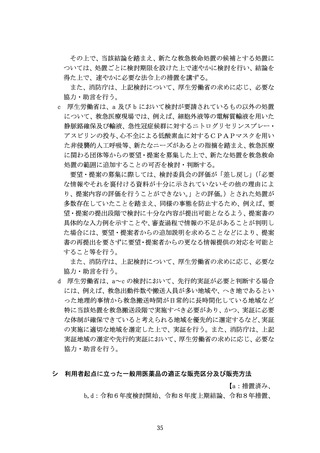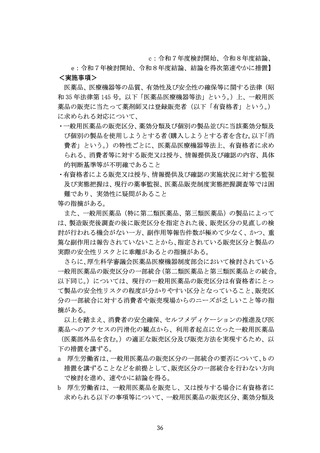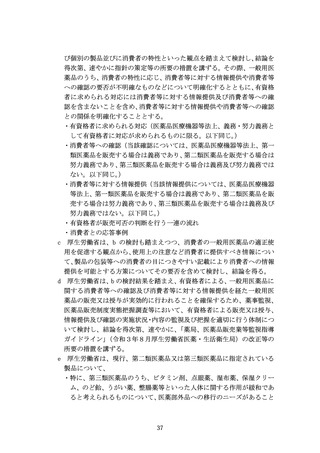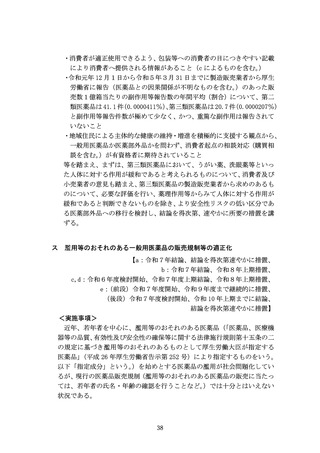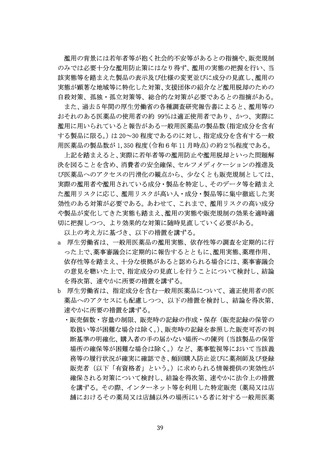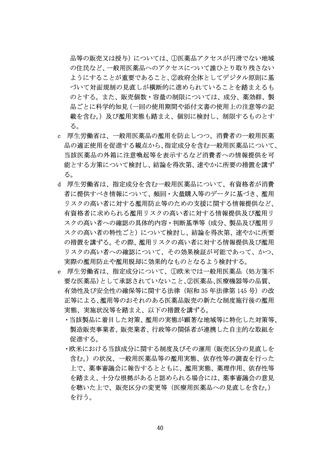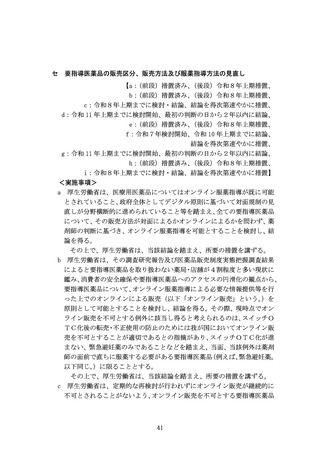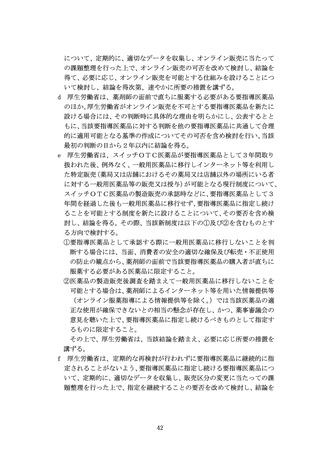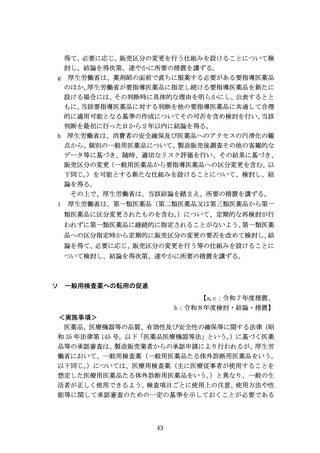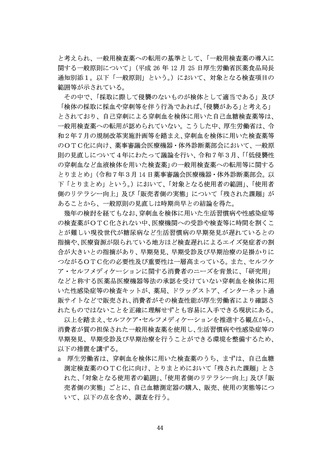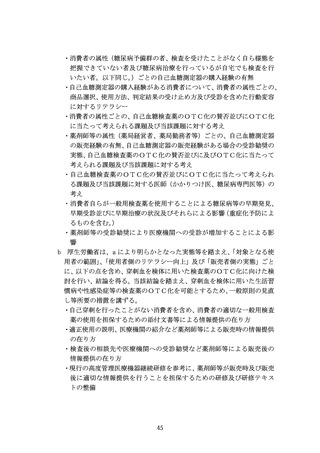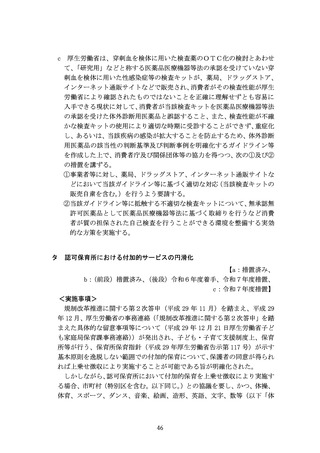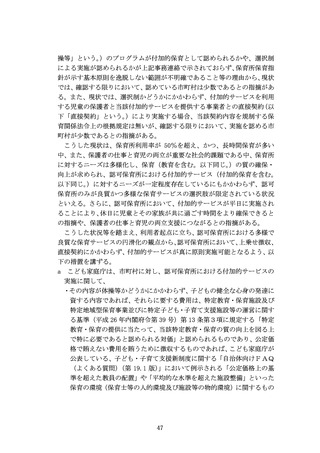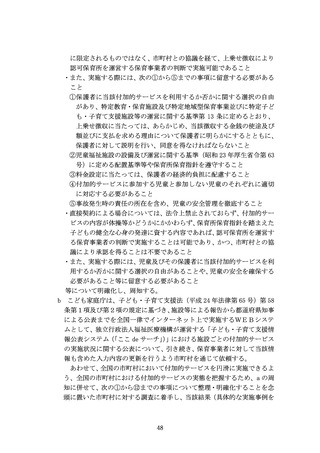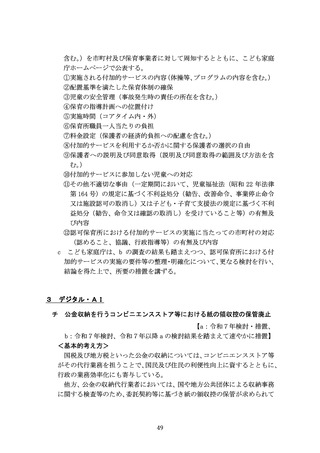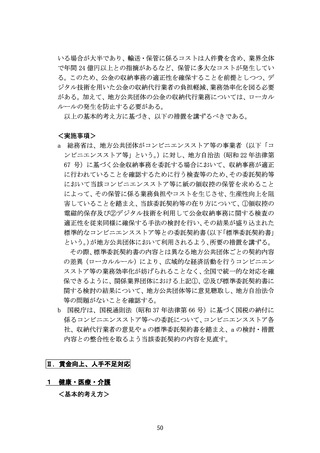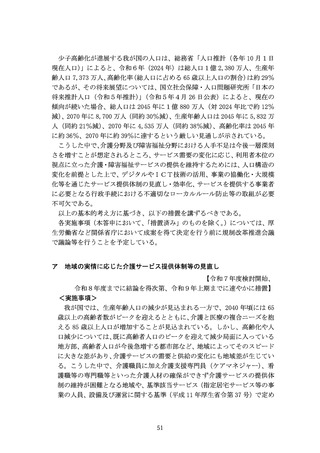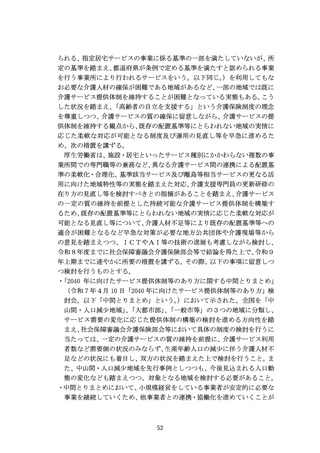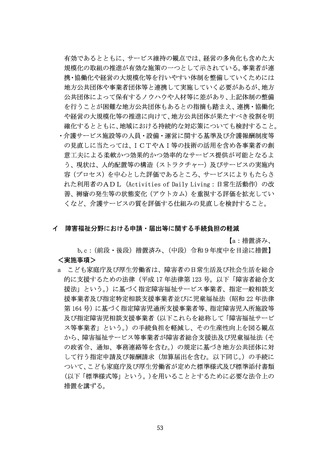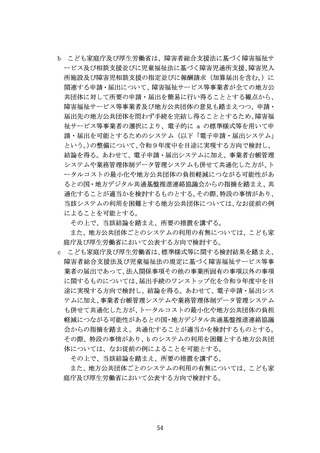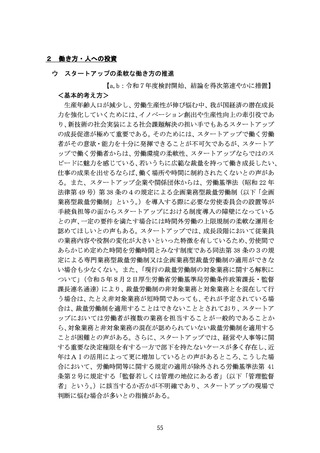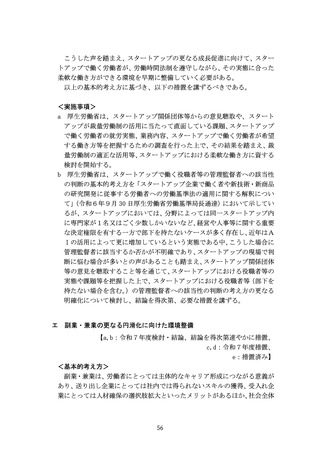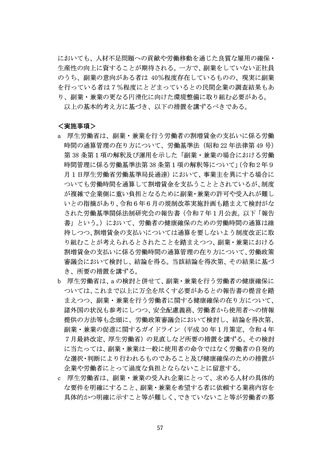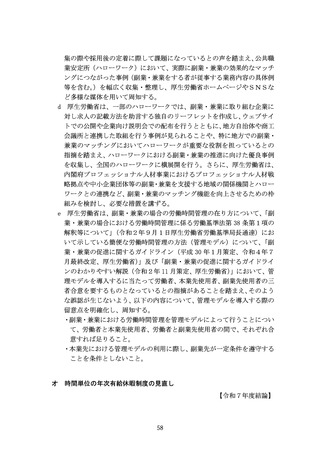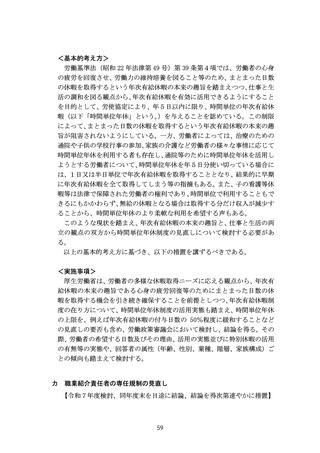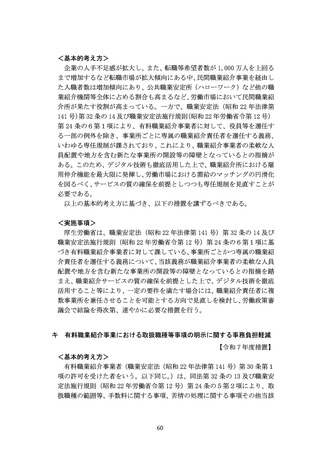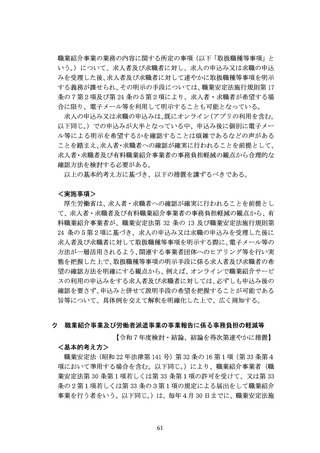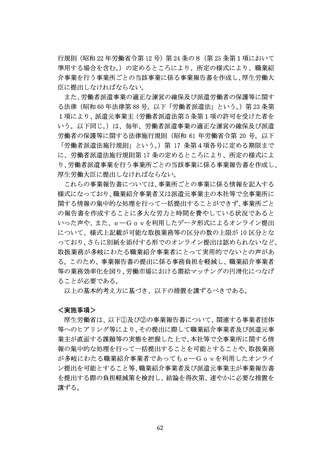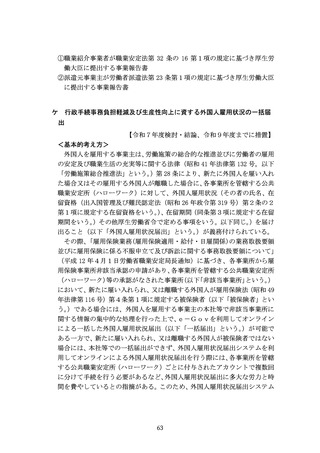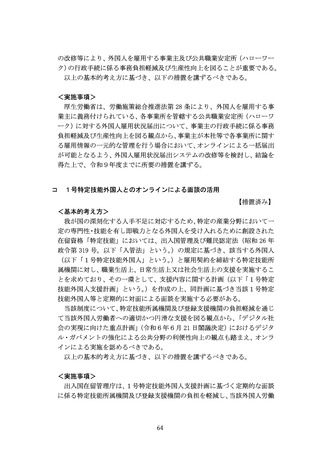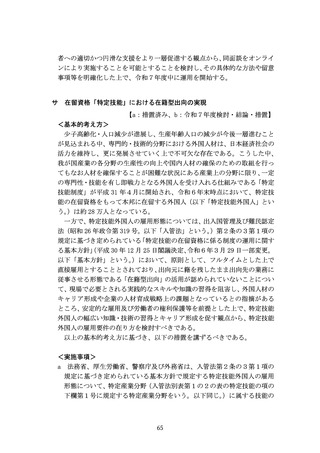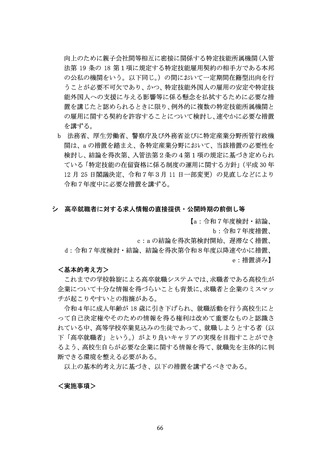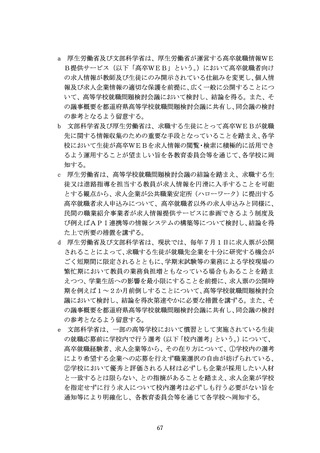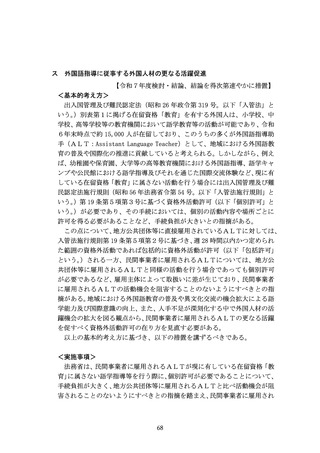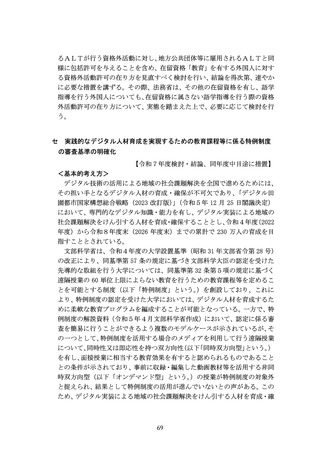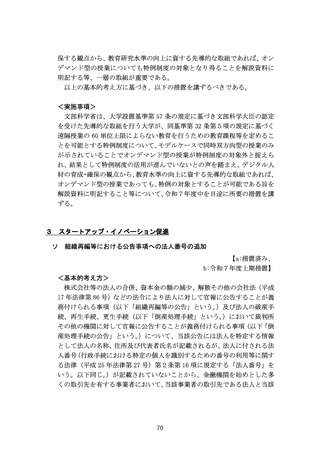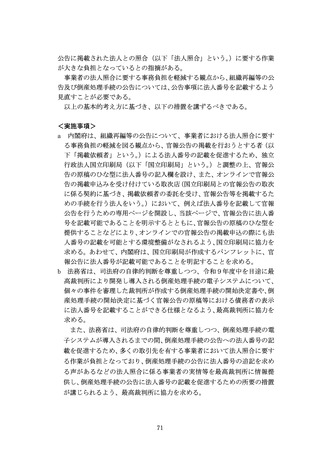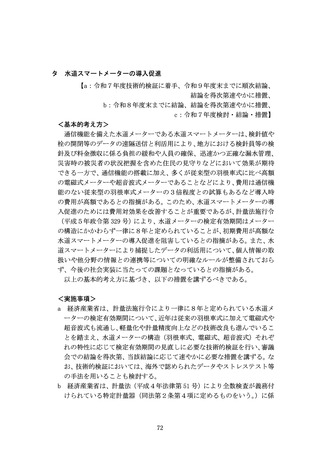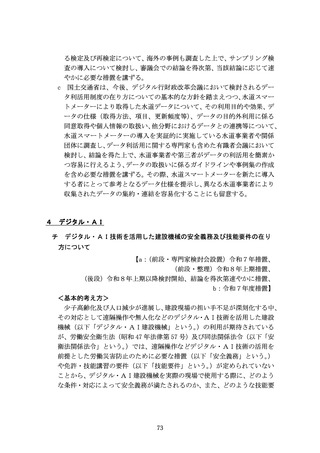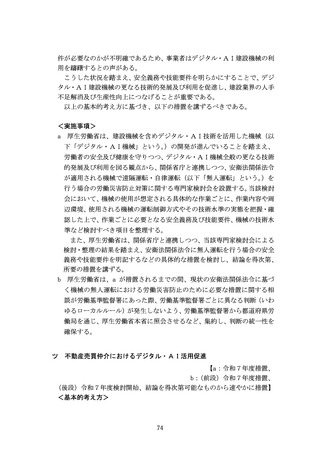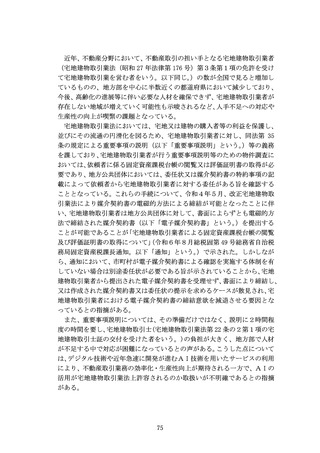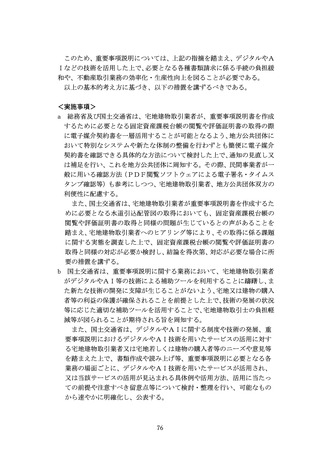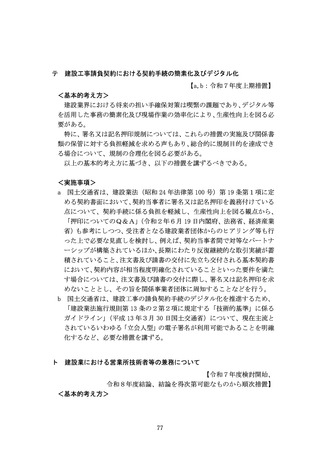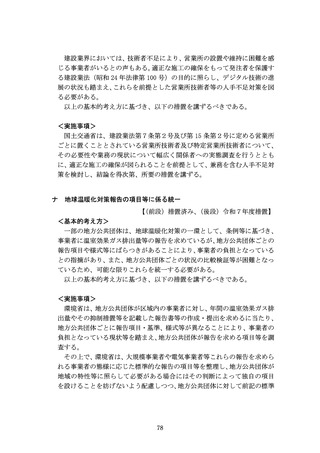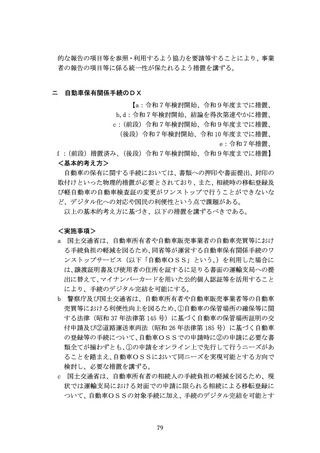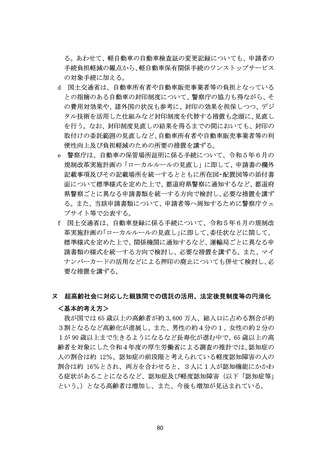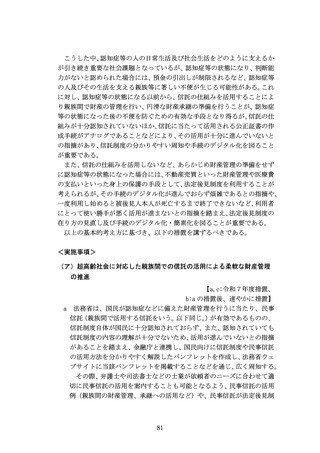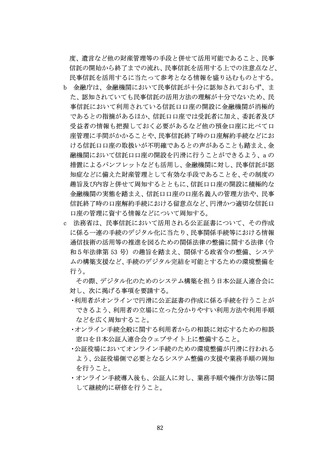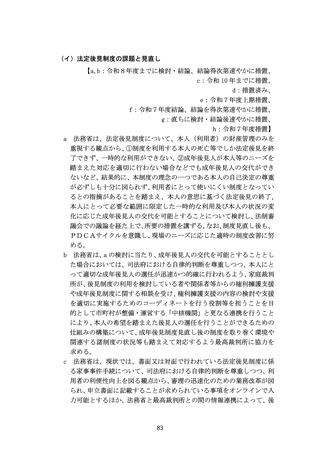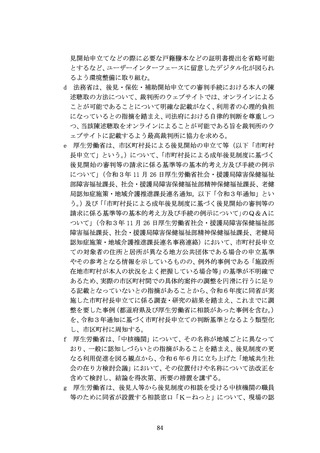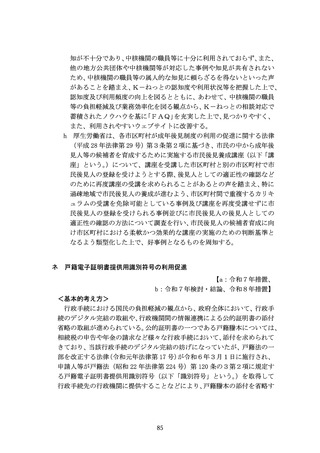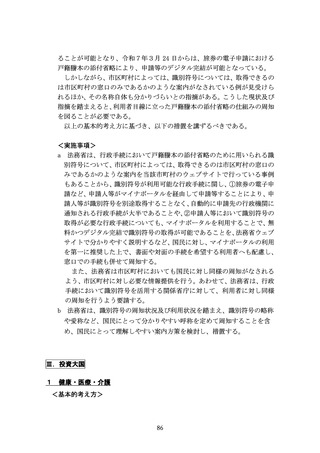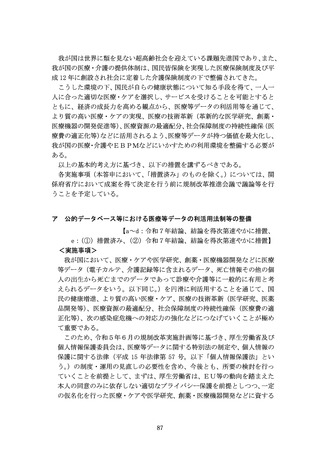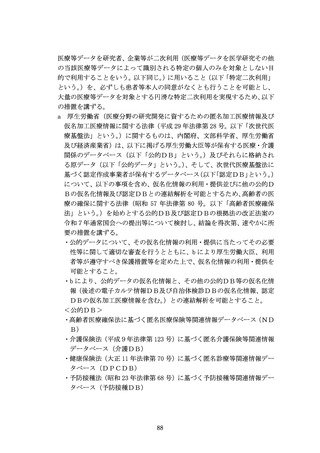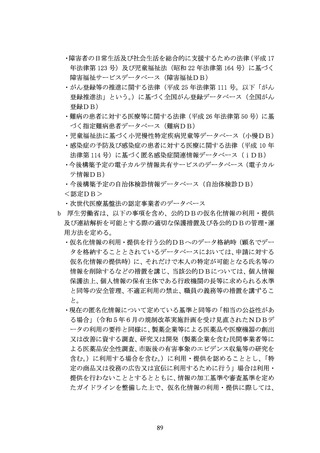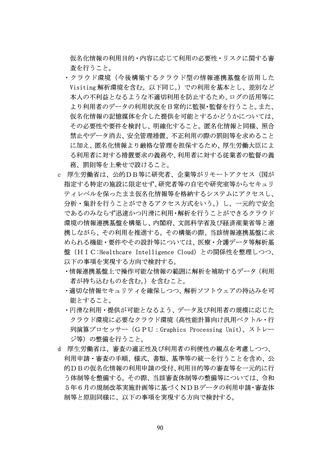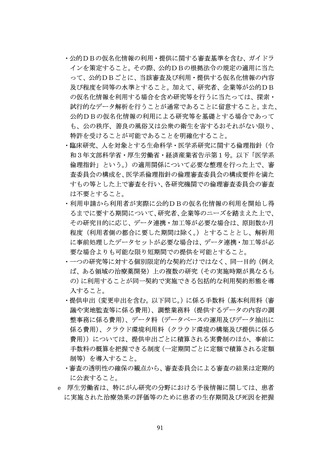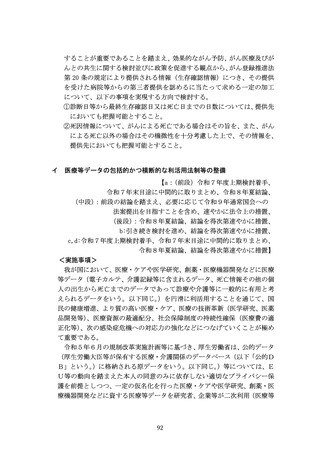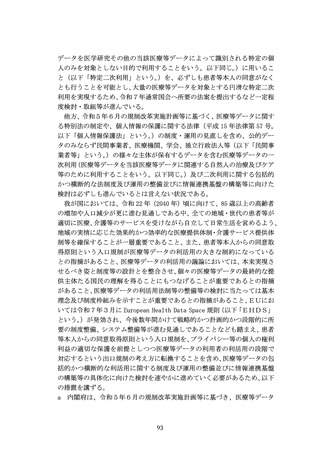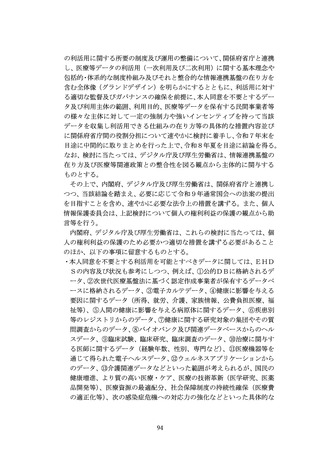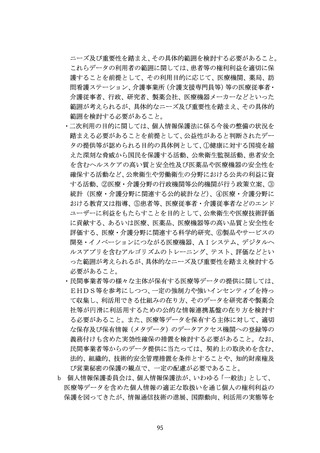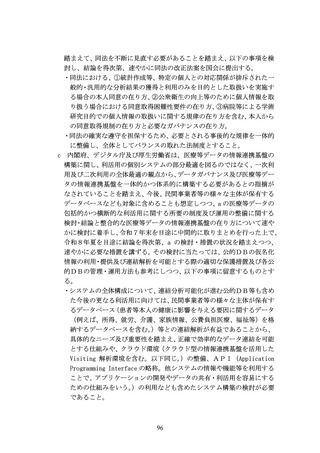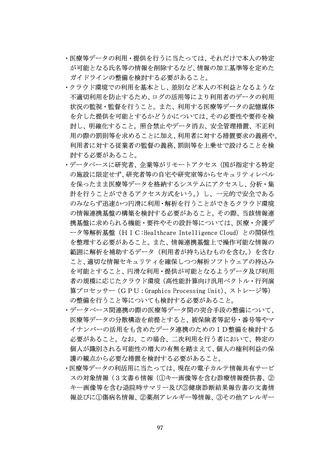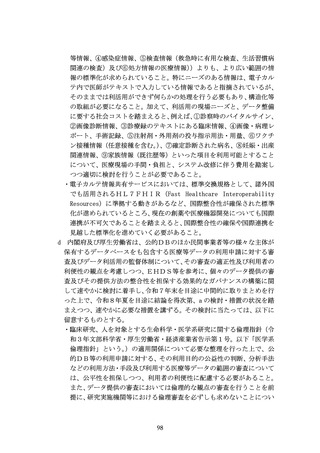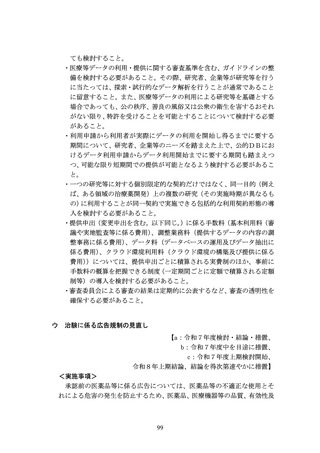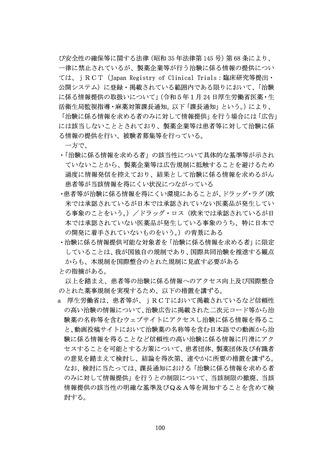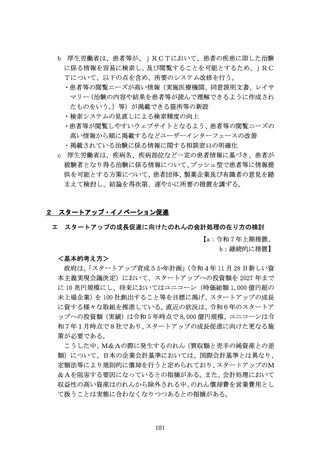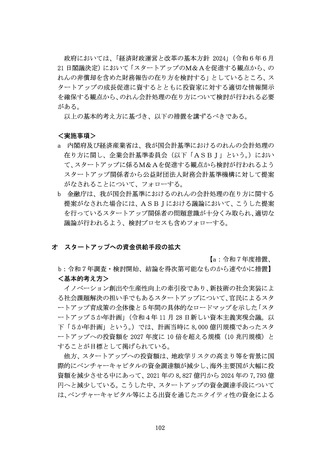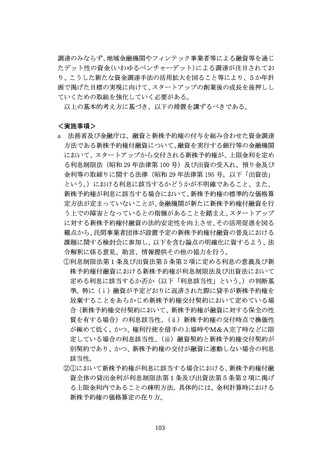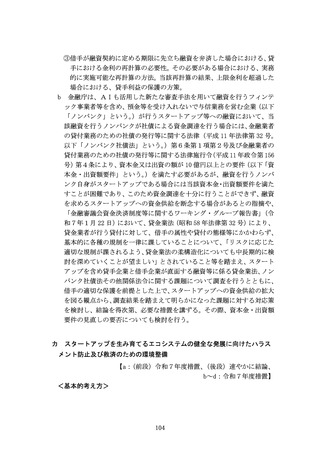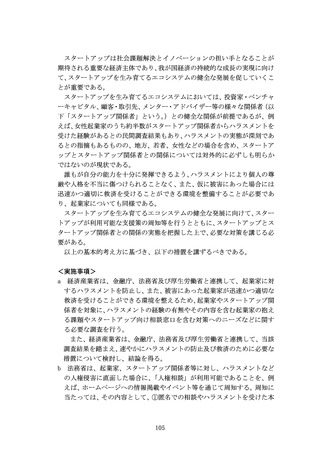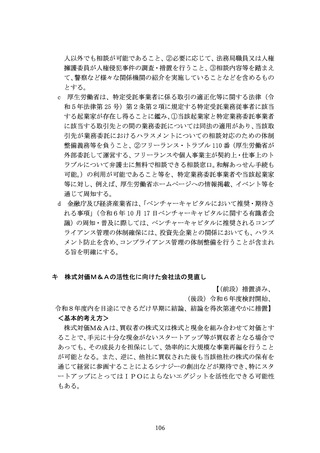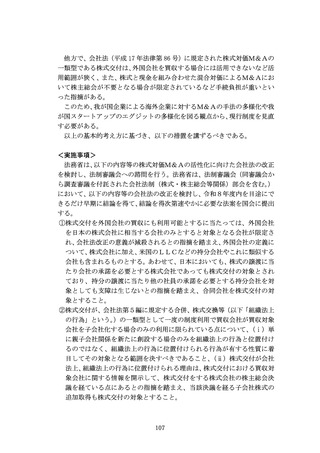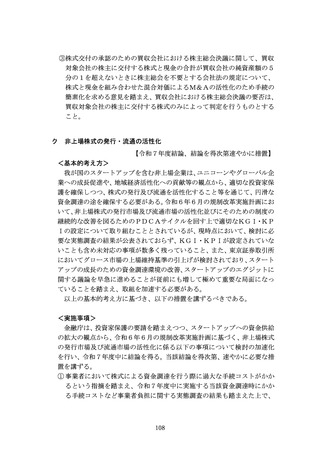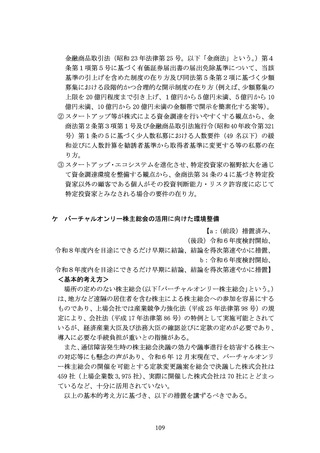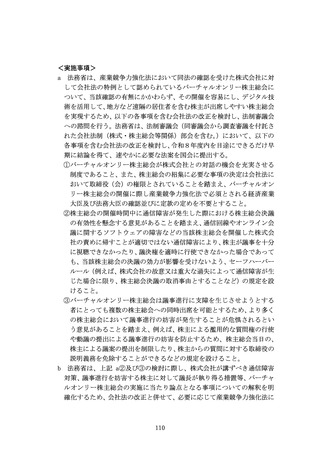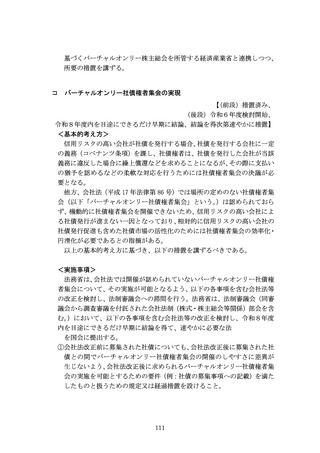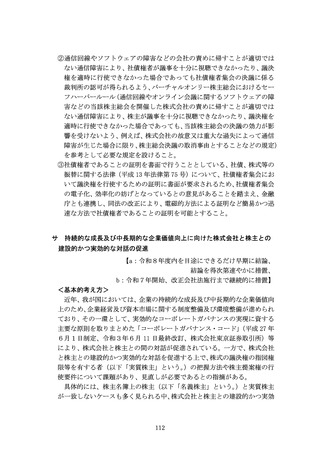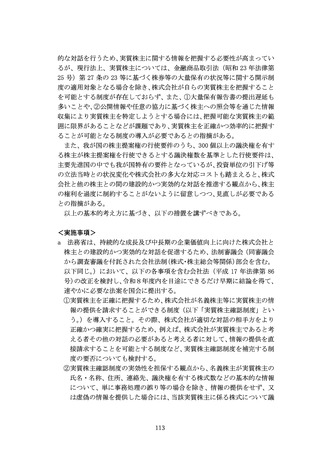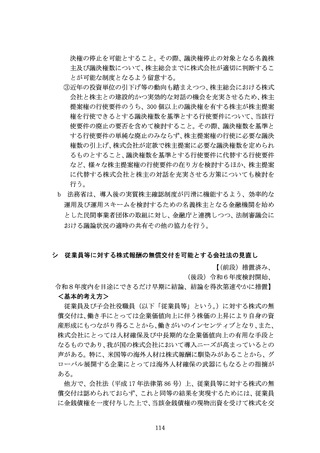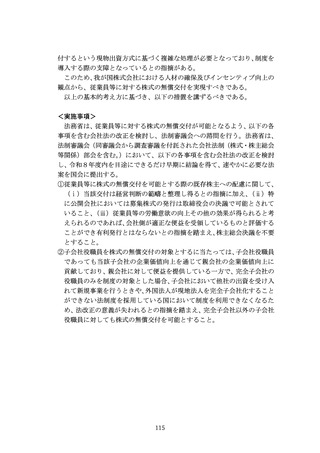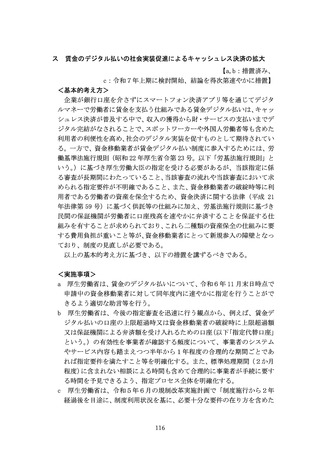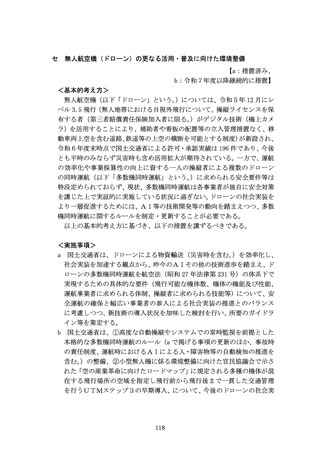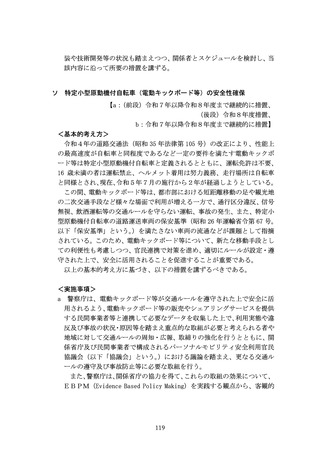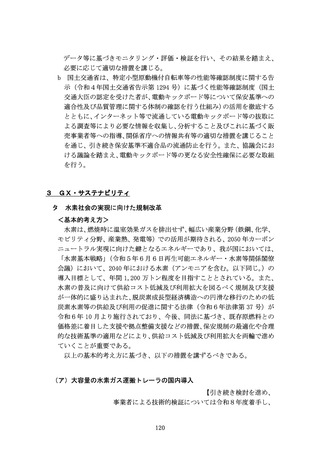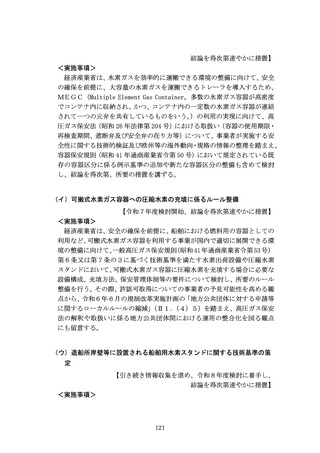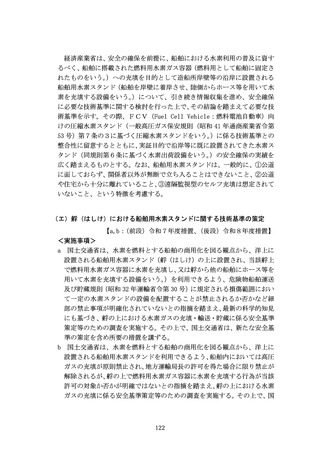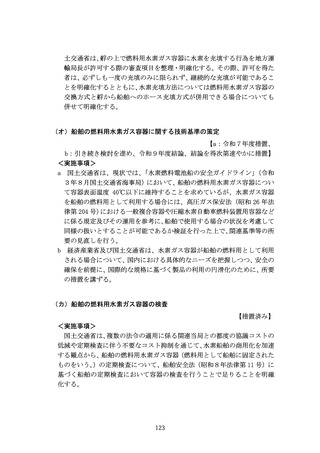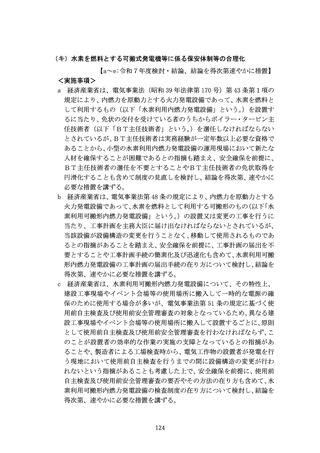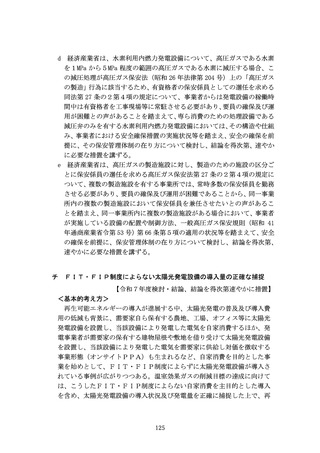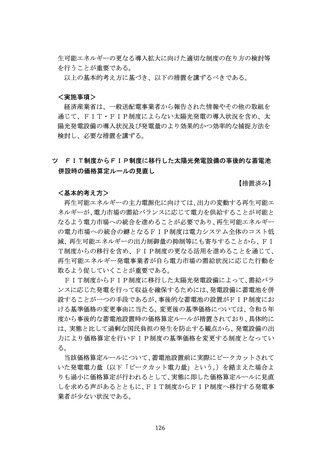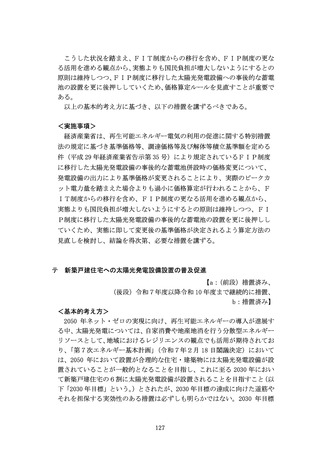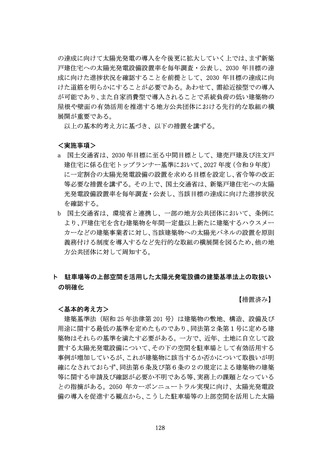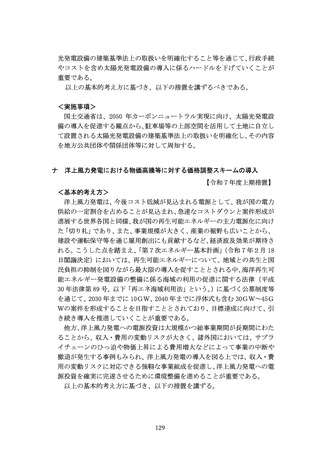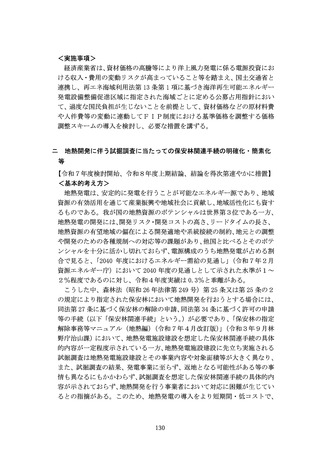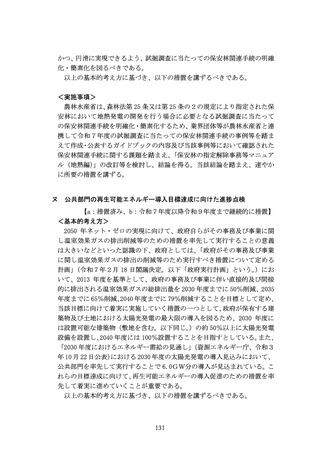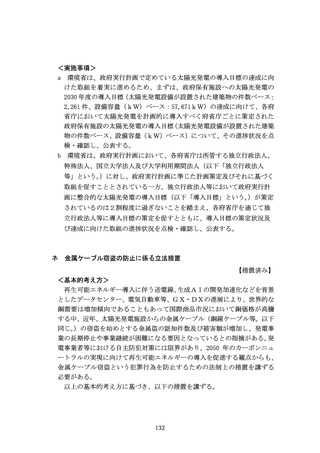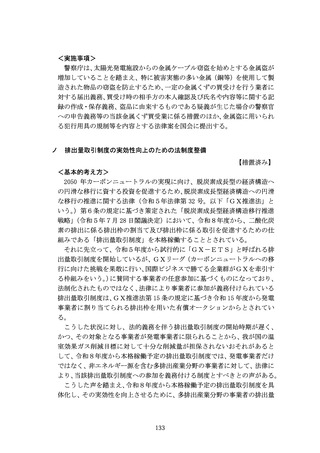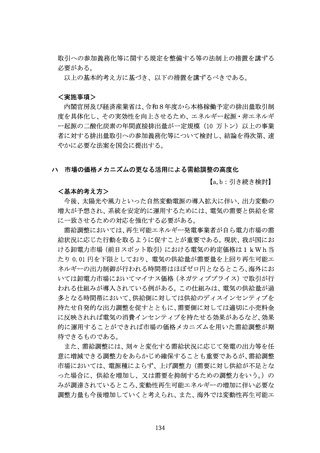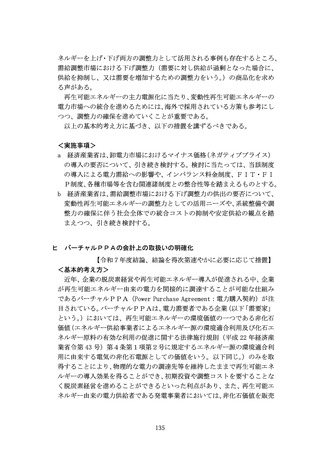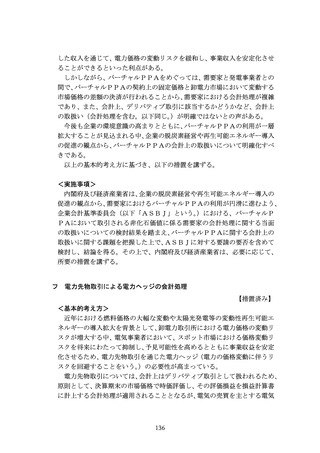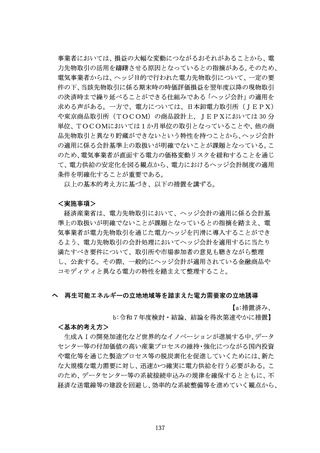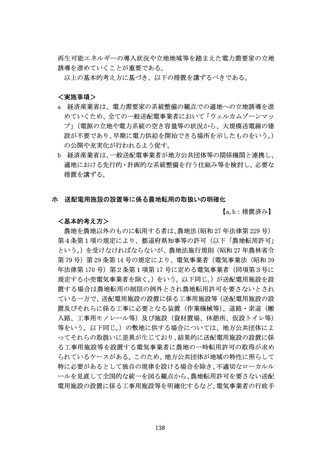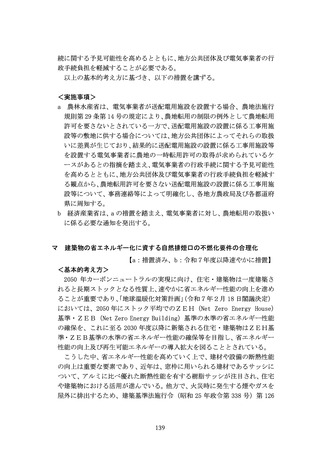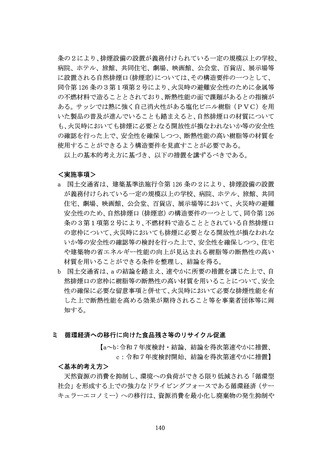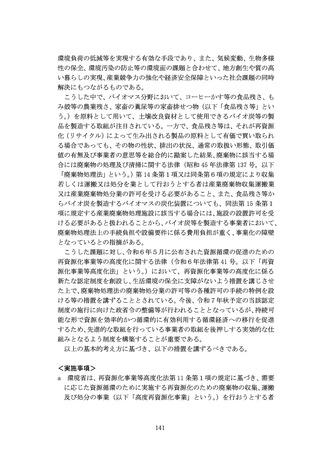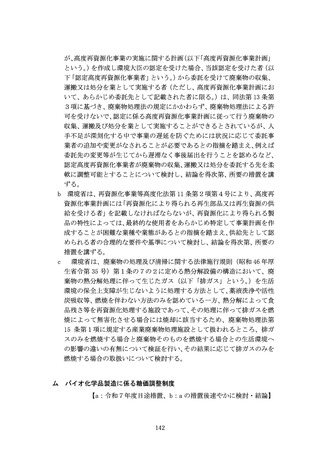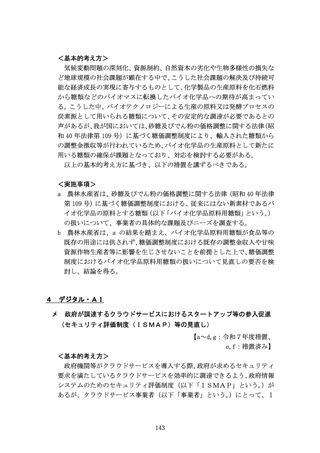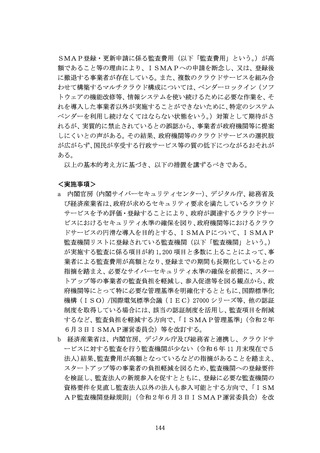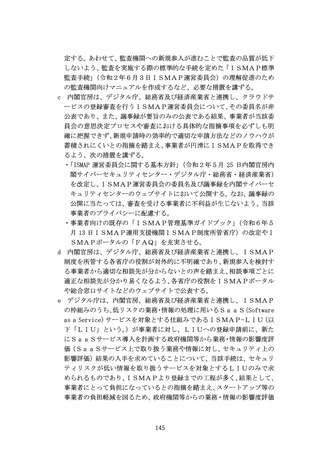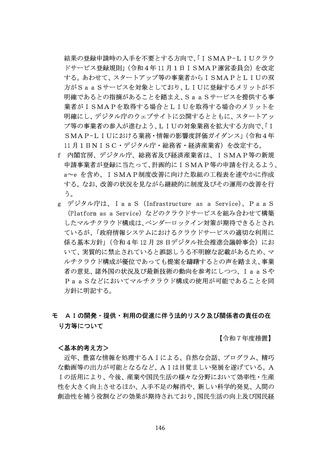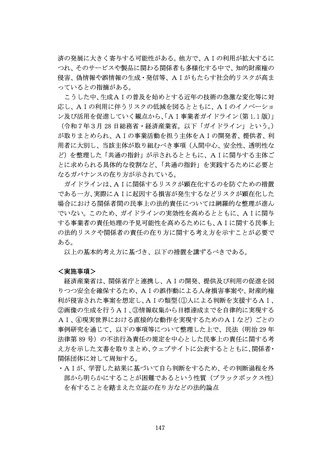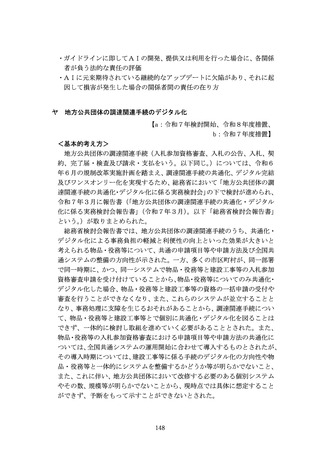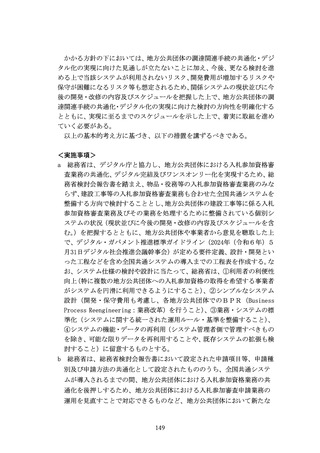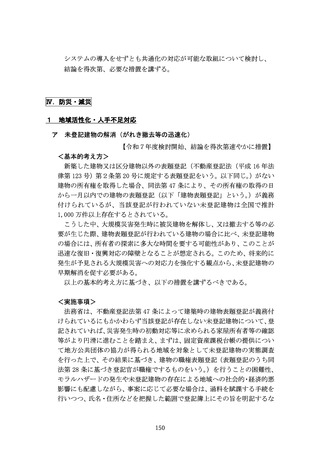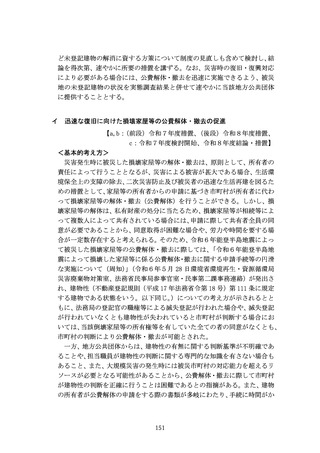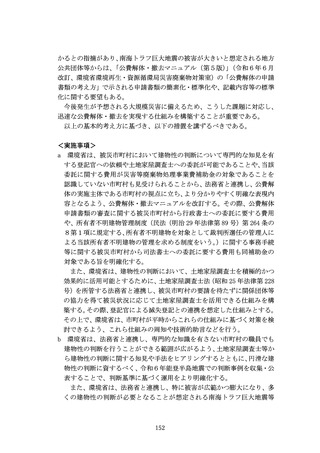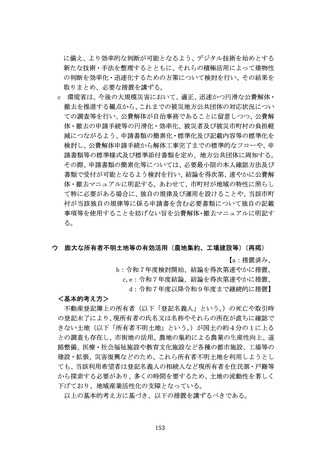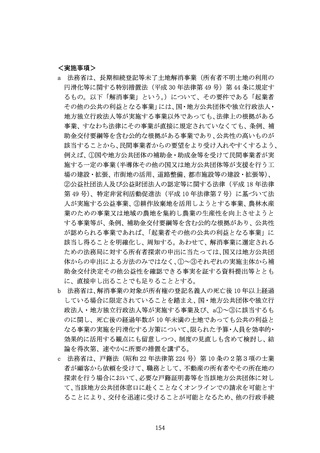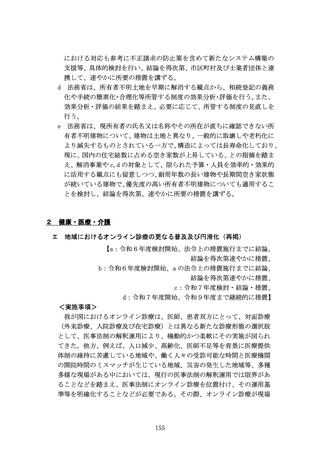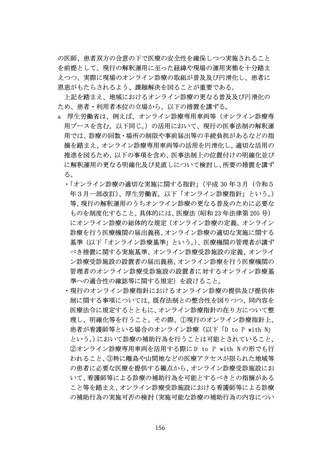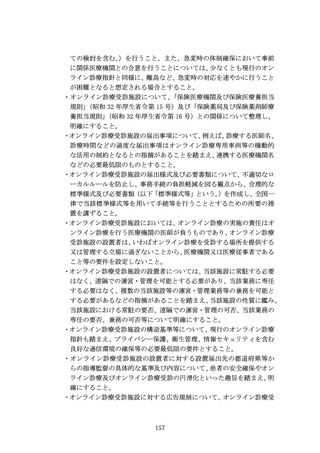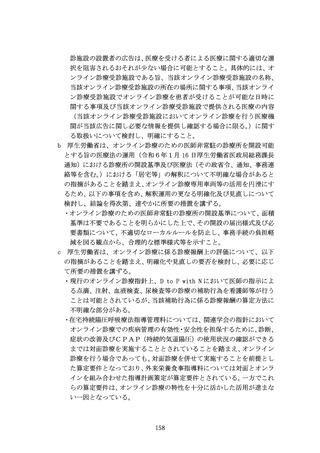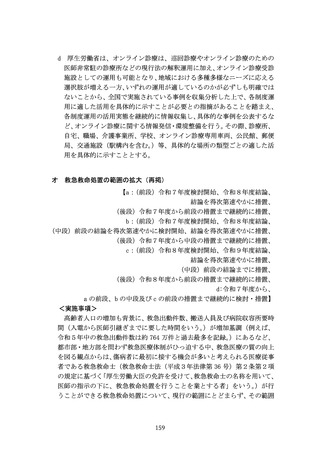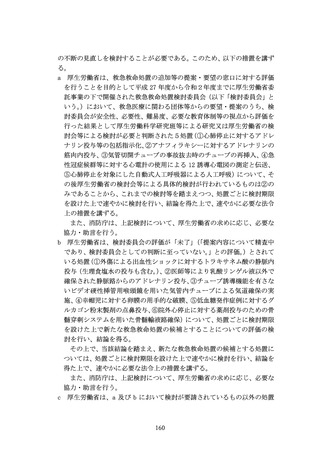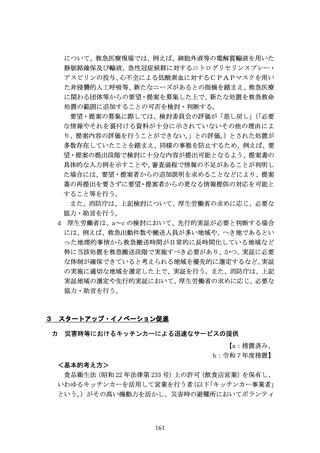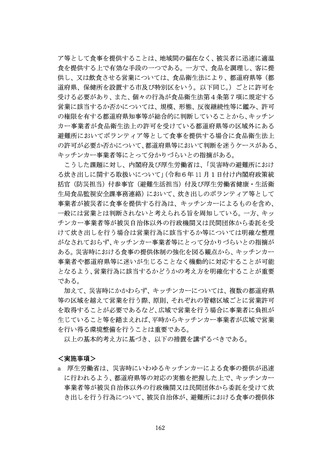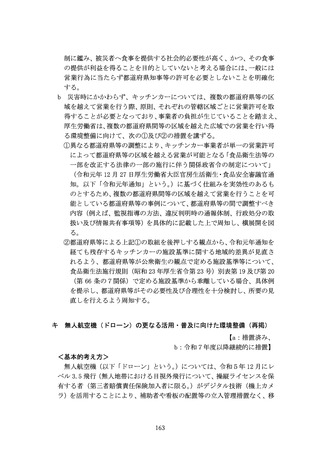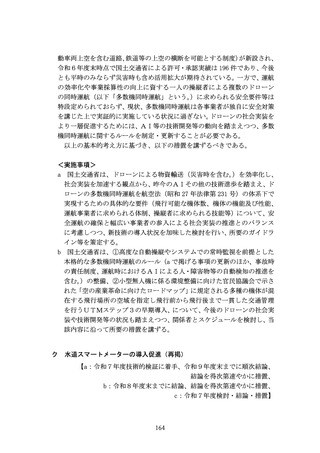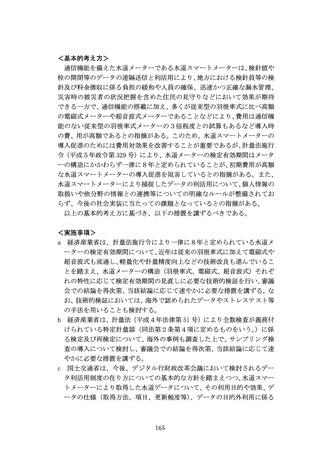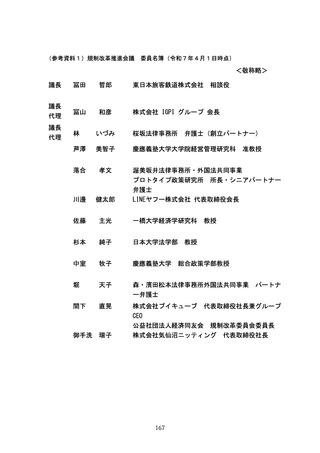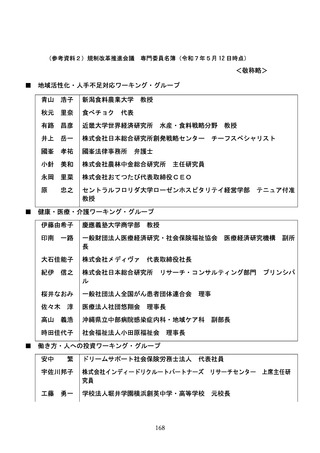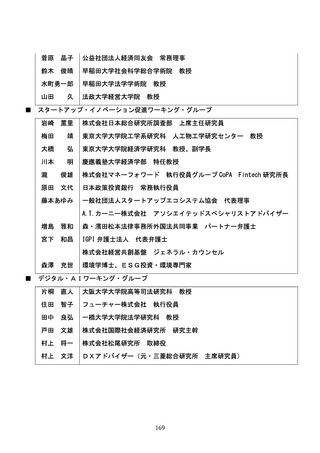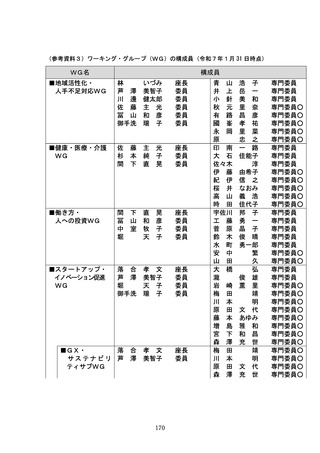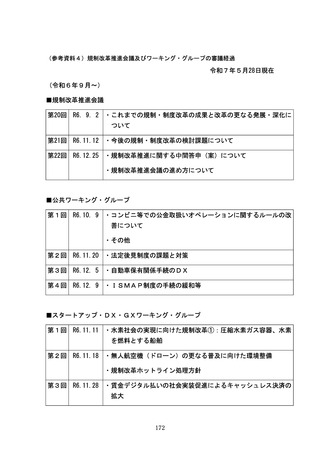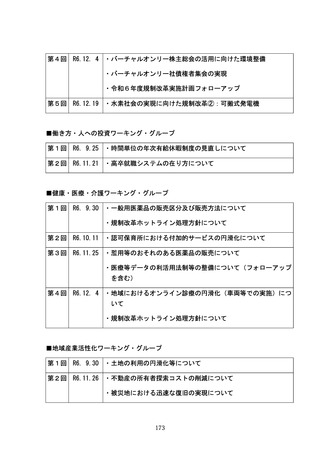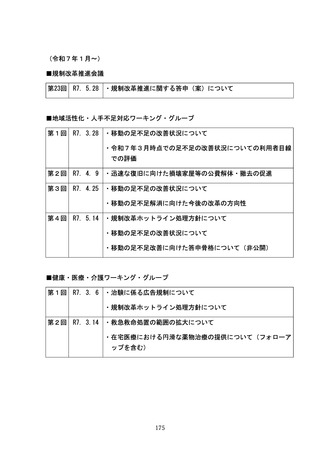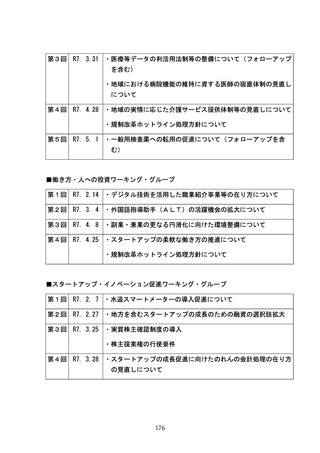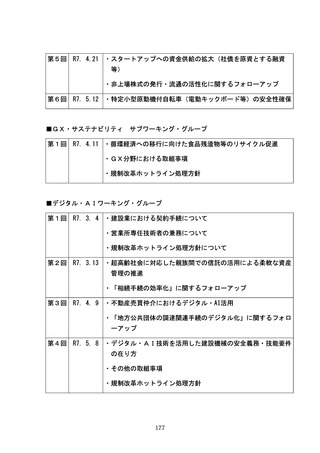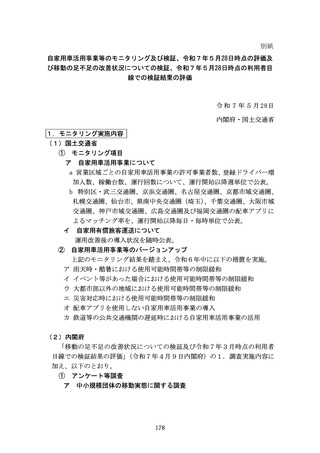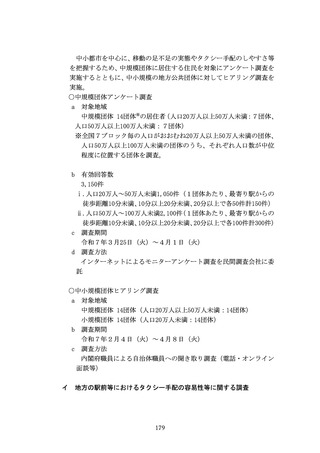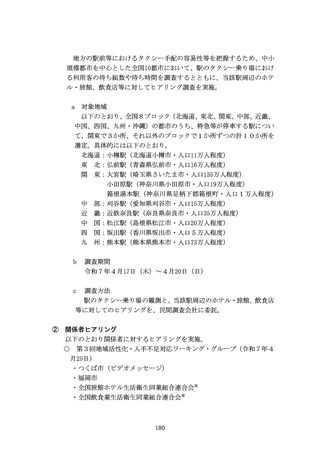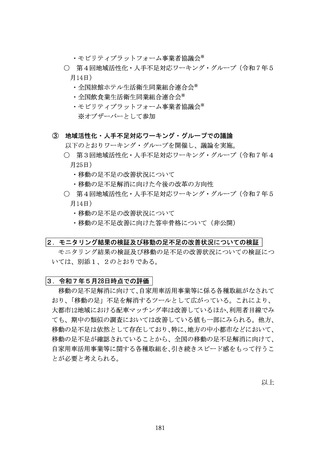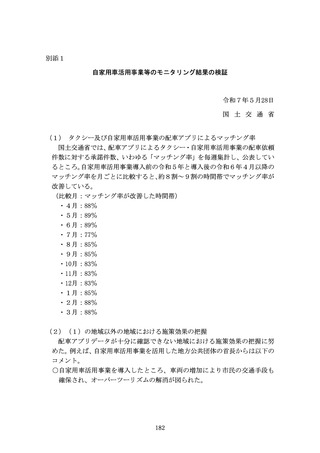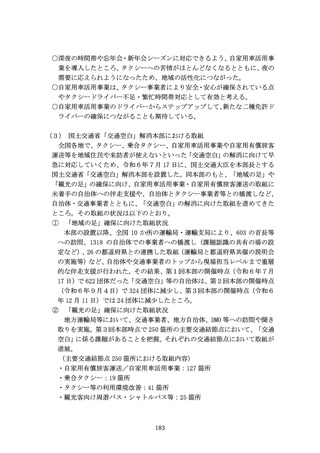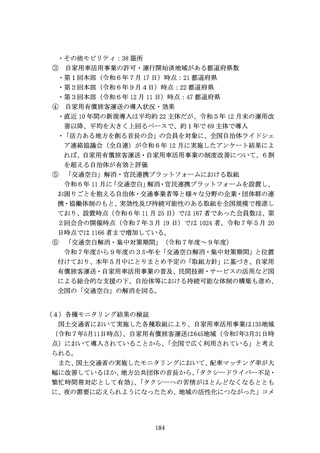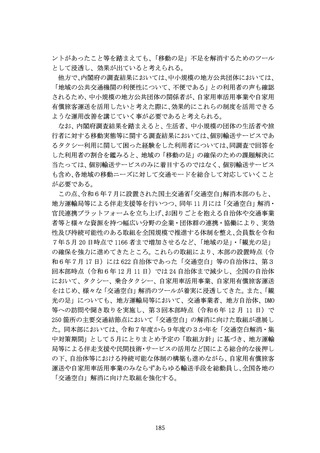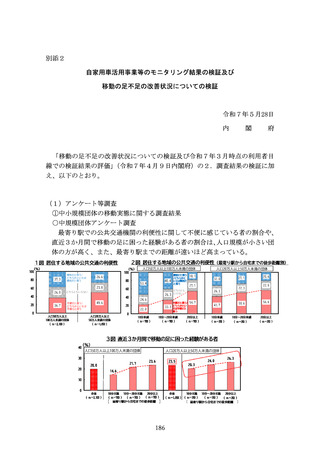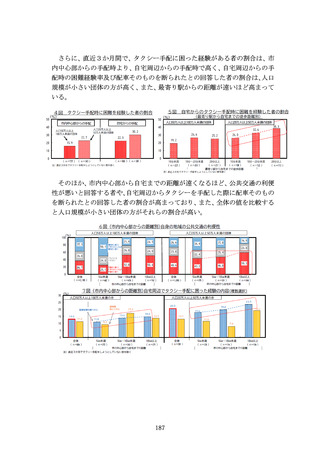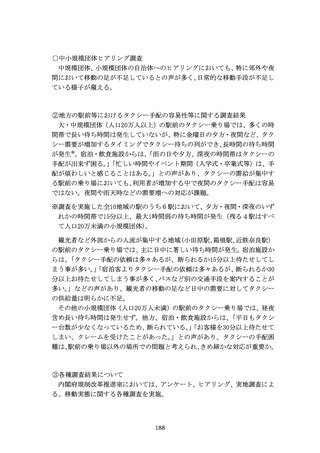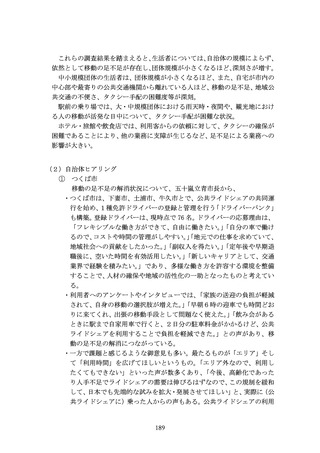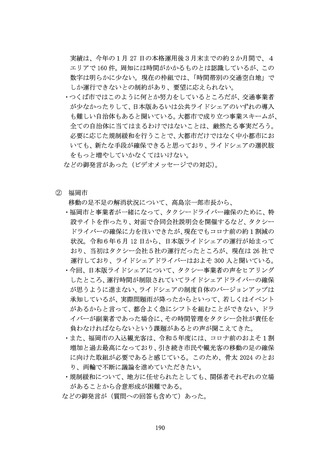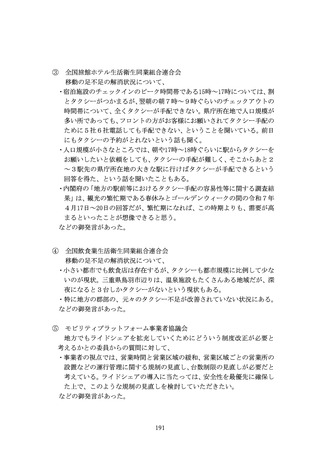規制改革推進に関する答申 令和7年5月28日 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html |
| 出典情報 | 規制改革推進に関する答申(5/28)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
法務省は、現所有者の氏名又は名称やその所在が直ちに確認できない所
有者不明建物について、建物は土地と異なり、一般的に取壊しや老朽化に
より滅失するものとされている一方で、構造によっては長寿命化しており、
現に、国内の住宅総数に占める空き家数が上昇している、との指摘を踏ま
え、解消事業や c,d の対象として、限られた予算・人員を効率的・効果的
に活用する観点にも留意しつつ、耐用年数の長い建物や長期間空き家状態
が続いている建物で、優先度の高い所有者不明建物についても適用するこ
とを検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
イ
ロボット農機の公道走行制度化(圃場間移動等を通じた地域での活用)
【a:令和6年度以降継続的に措置、
b:措置済み、
c:措置済み、
d(前段):令和7年度措置、(後段):令和8年上期措置】
<基本的考え方>
高齢化及び生産年齢人口の減少が更に進み、今後 20 年間で基幹的農業従
事者が 75%減少することが見込まれる中、ロボット農機(ロボット技術を
組み込んで製造され、農作業に用いることを目的に使用者が遠隔監視しなが
ら無人で自動走行する車両系の農業機械をいう。以下同じ。)の早期の社会
実装は、農業の省人化及び生産性向上に不可欠である。このため、現在、圃
場内等に限って走行が可能とされているロボット農機について、農道や公道
でも走行を可能とする必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 農林水産省は、その実施したロボット農機の実証事業の結果を踏まえ、
「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」
(平成 29 年3月
31 日農林水産省生産局長通知)について、公道走行の実現を見据えた改
定を行うとともに、警察庁及び国土交通省の求めに応じ、実証事業の結果
の報告その他 b~d のために必要となる協力を行う。
b 国土交通省は、ロボット農機の公道走行が可能となるよう、必要に応じ
て、関係事業者等にヒアリングを行った上で、自動運行装置を備えること
ができる自動車として大型特殊自動車及び小型特殊自動車を追加する旨
の「道路運送車両の保安基準」(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の改正その
他所要の措置を講ずる。
15