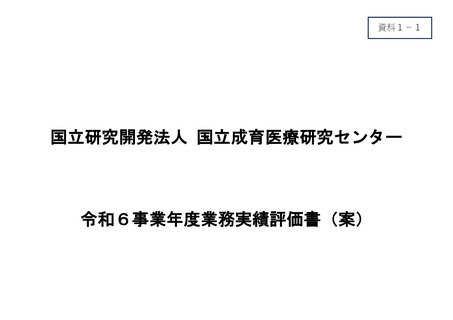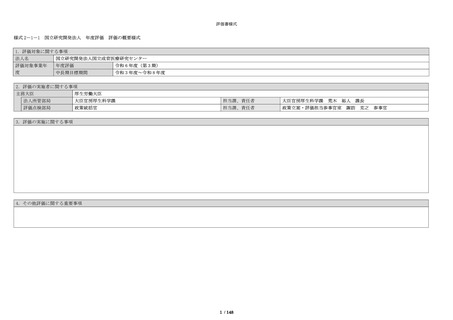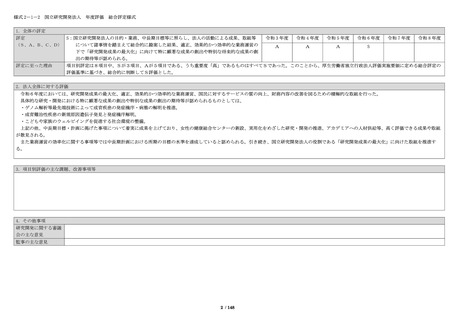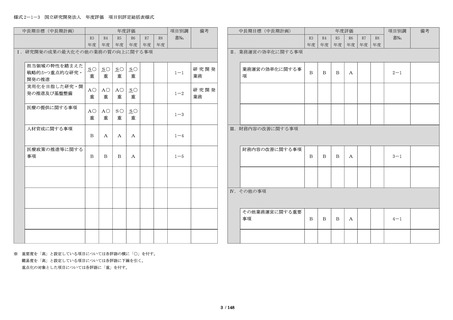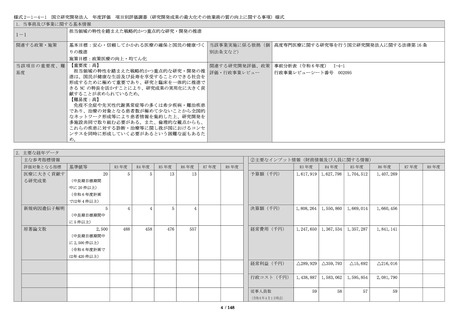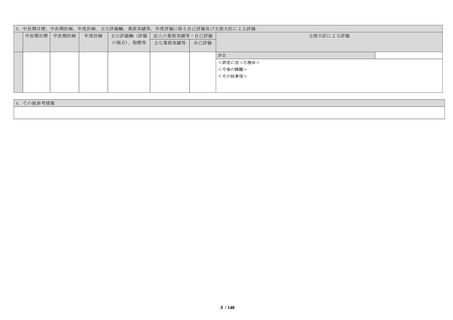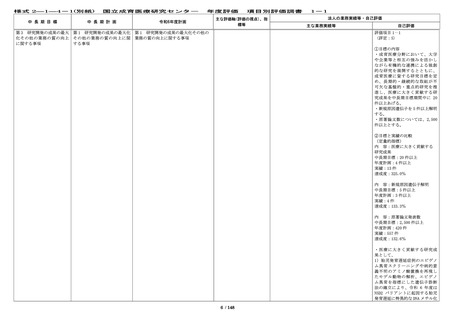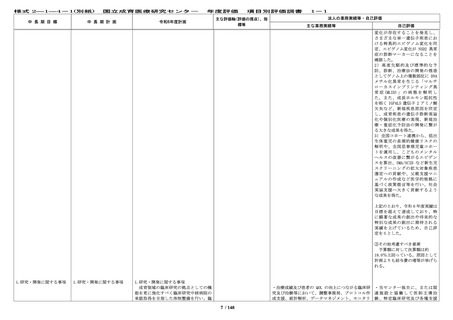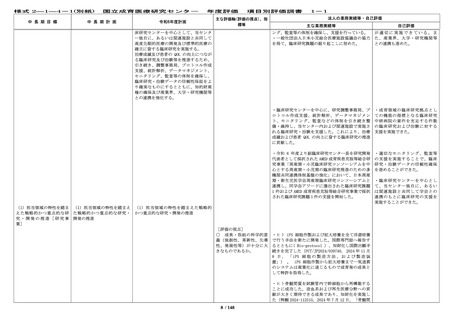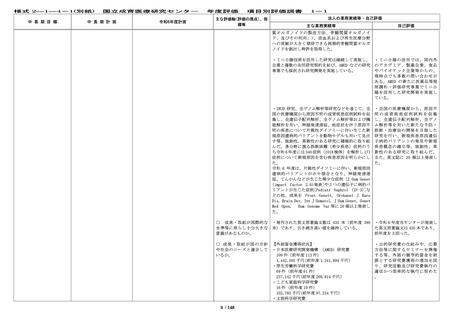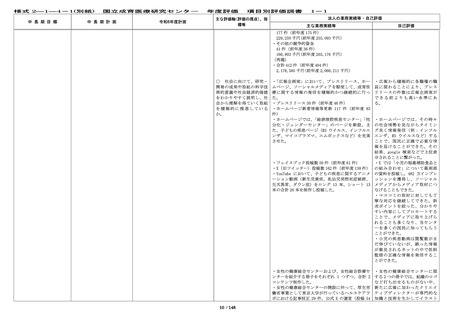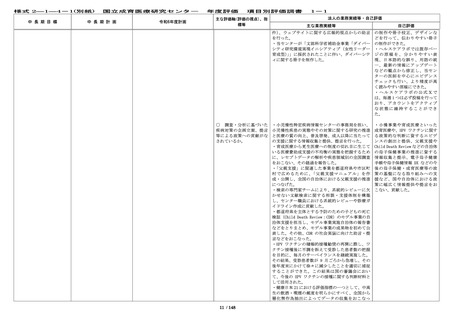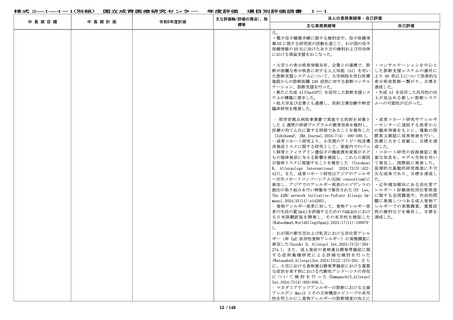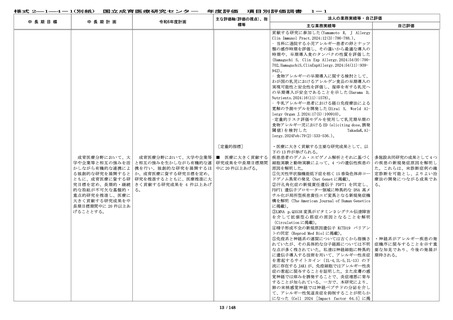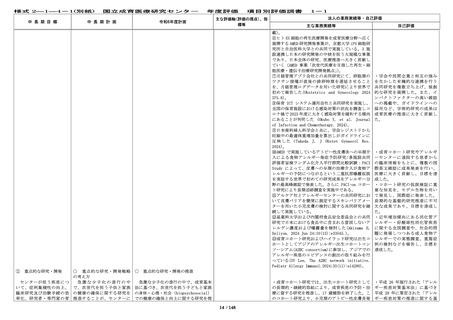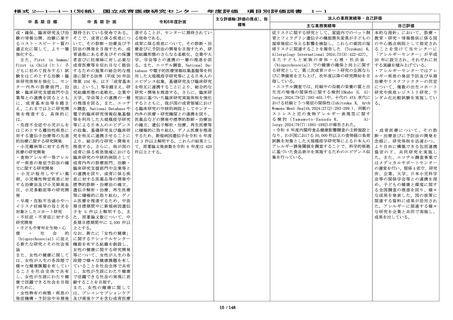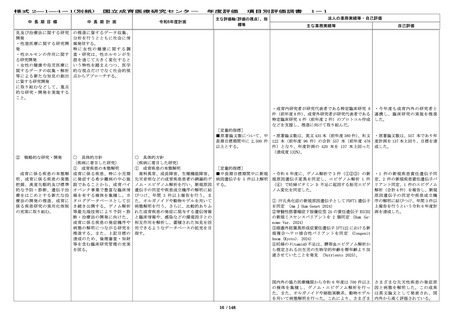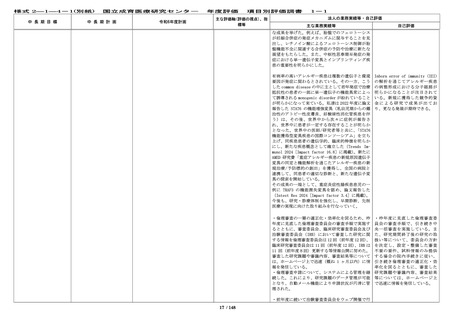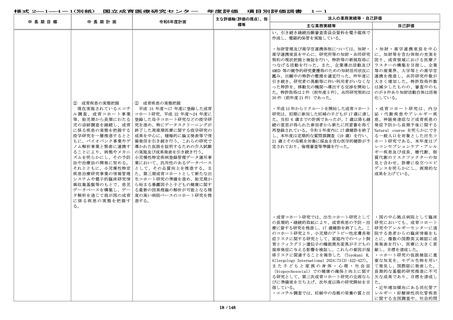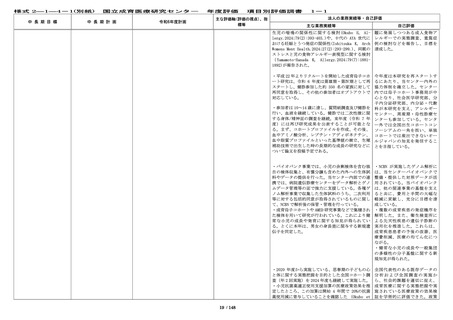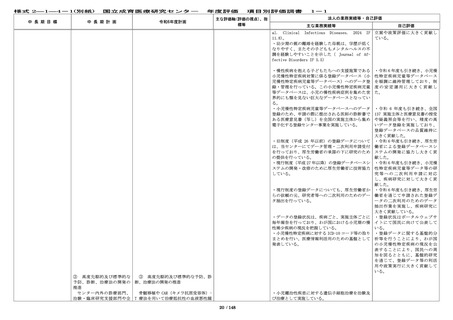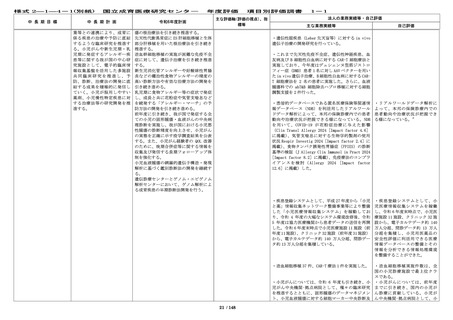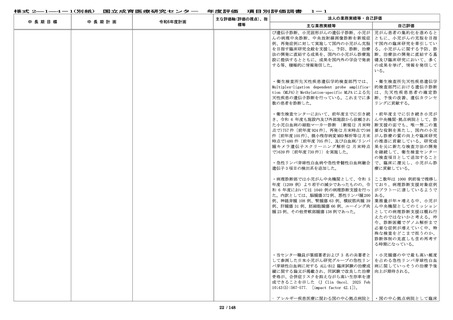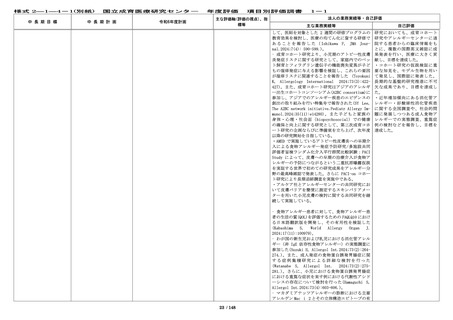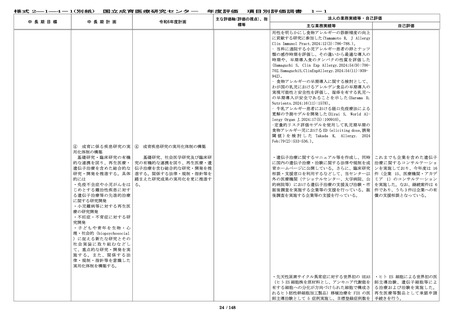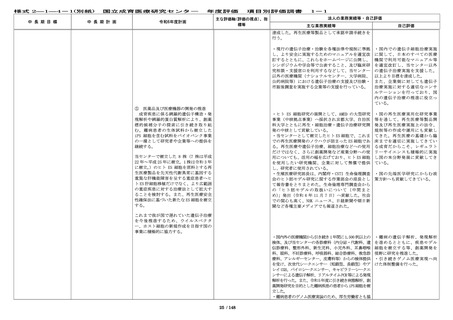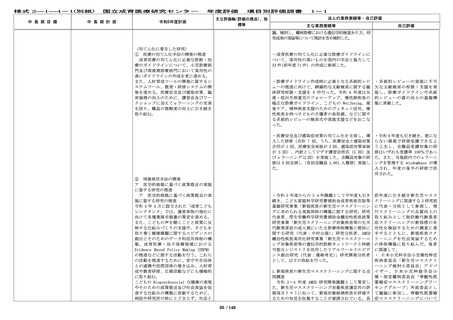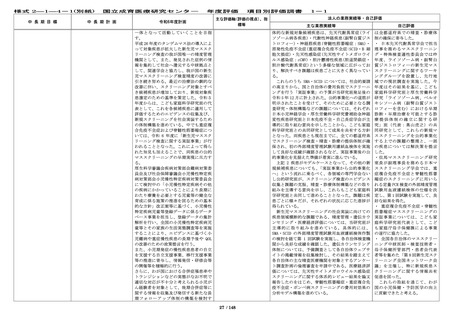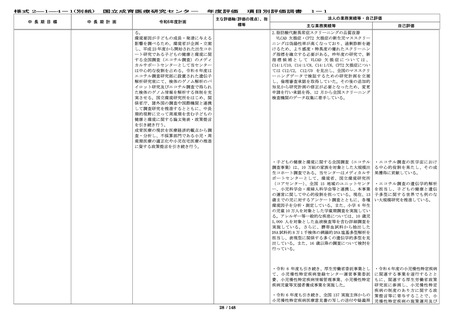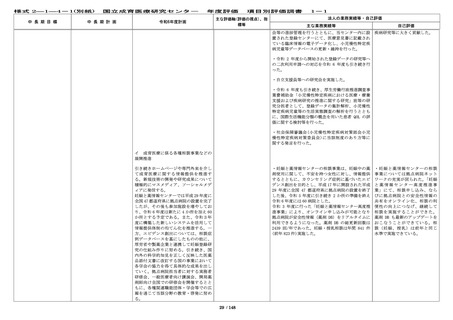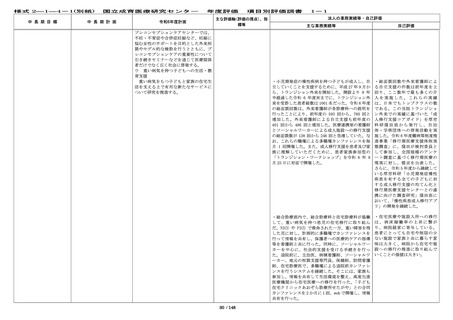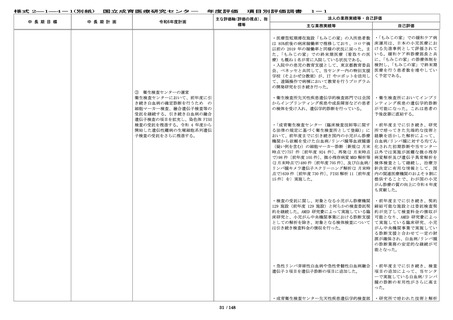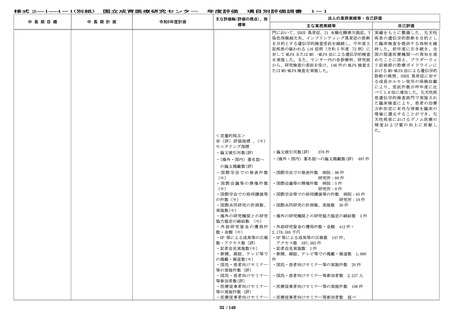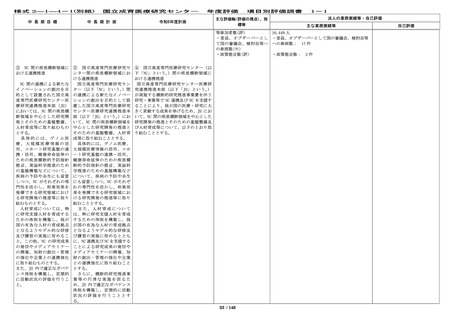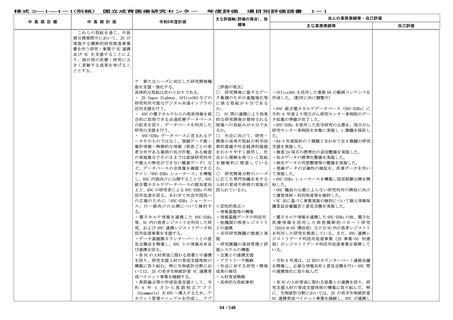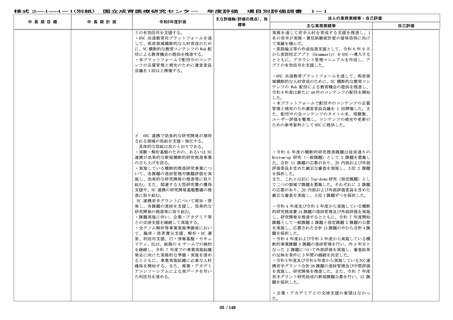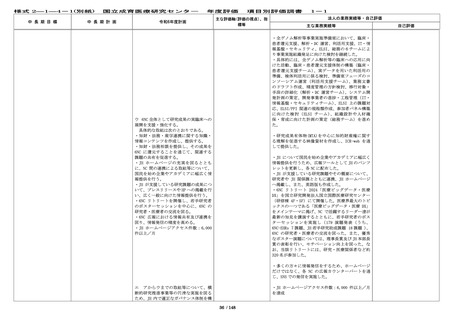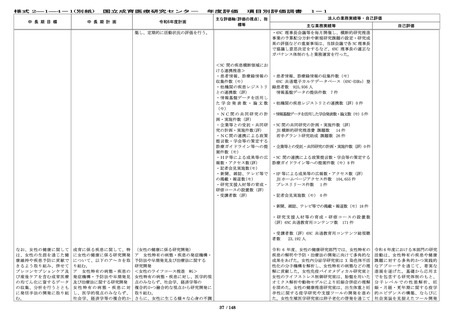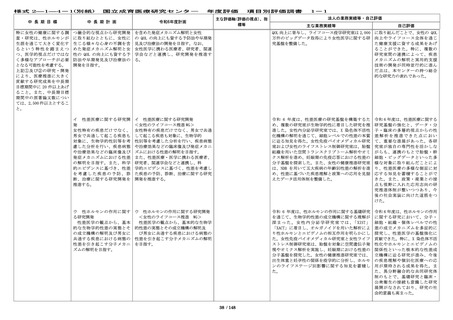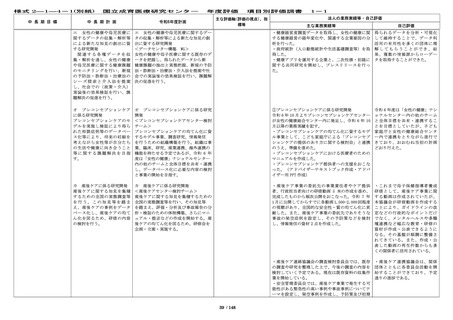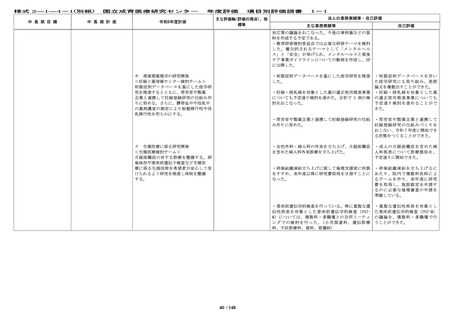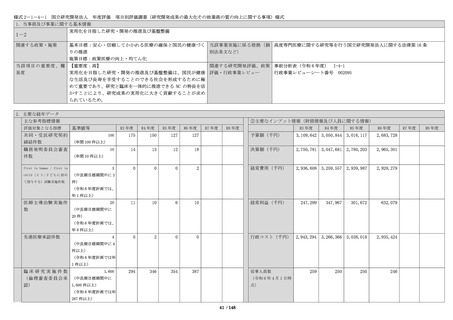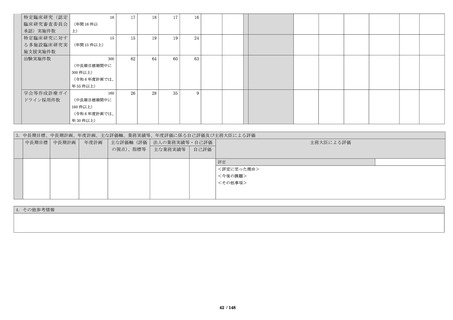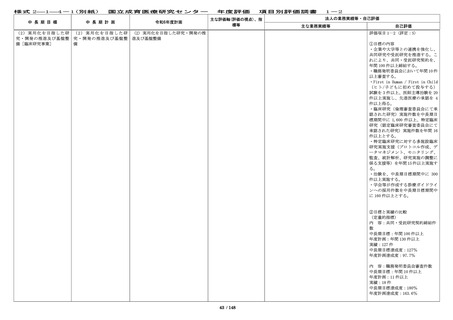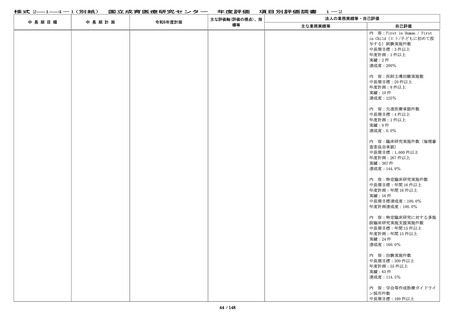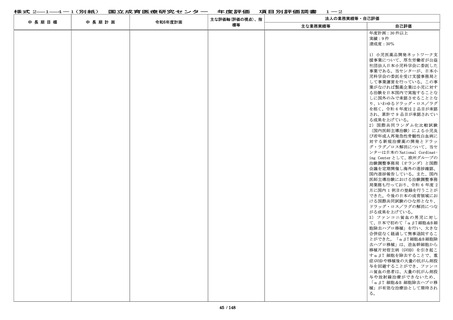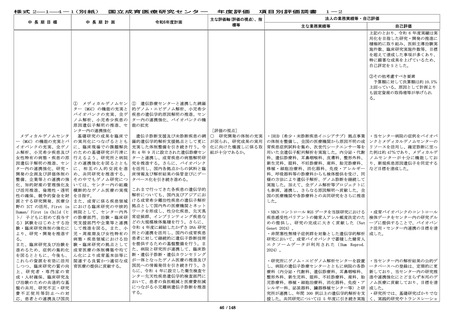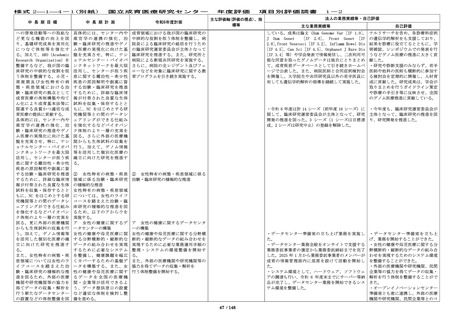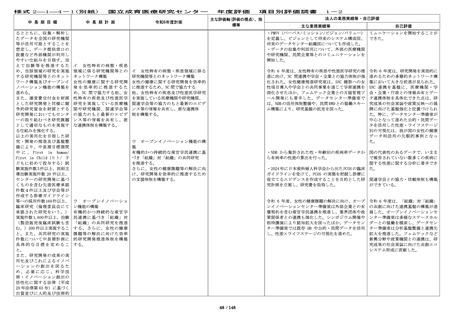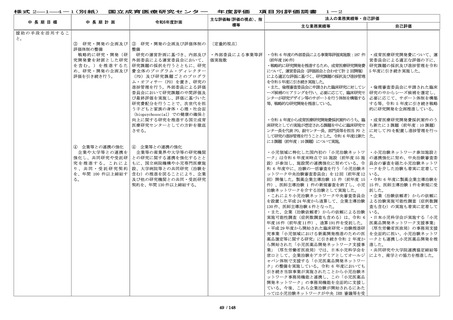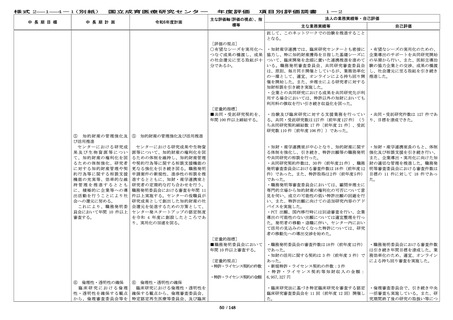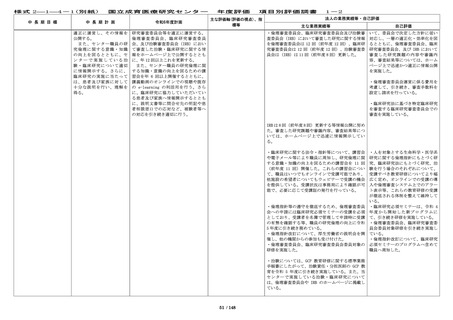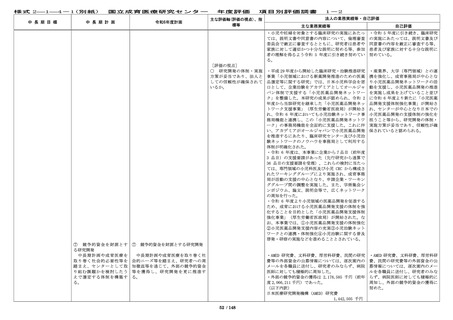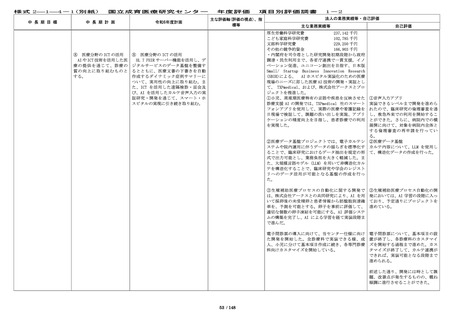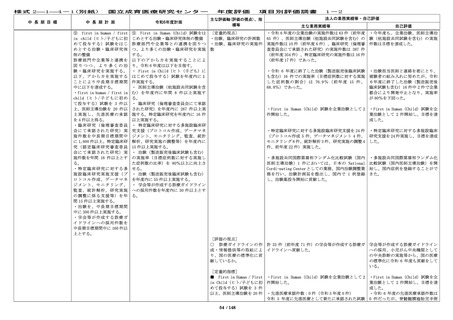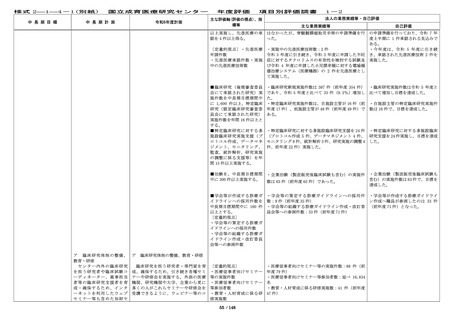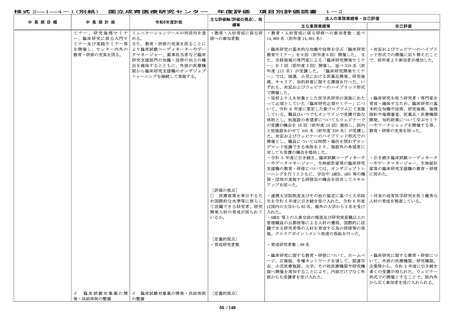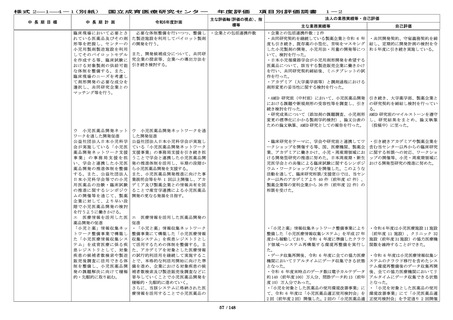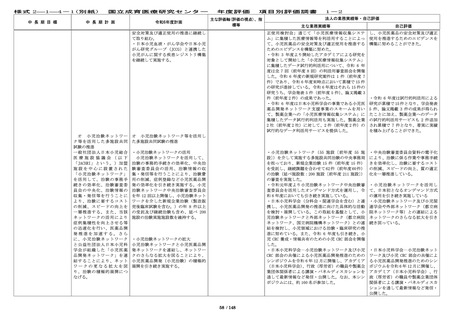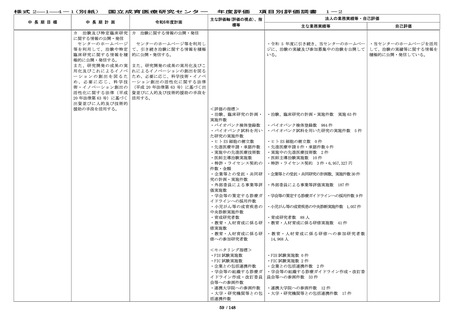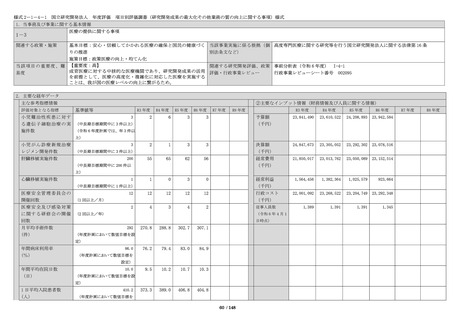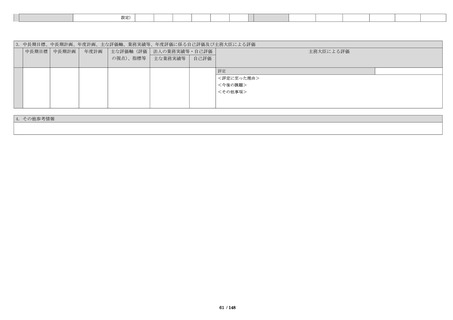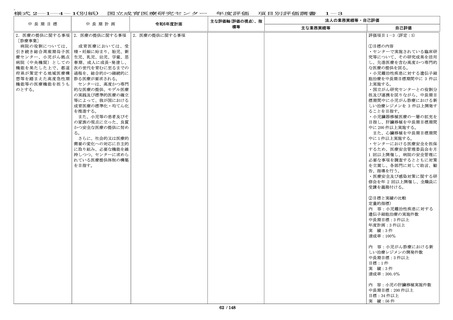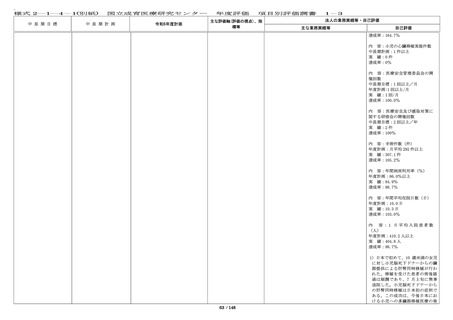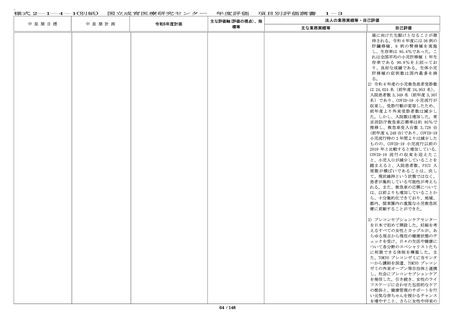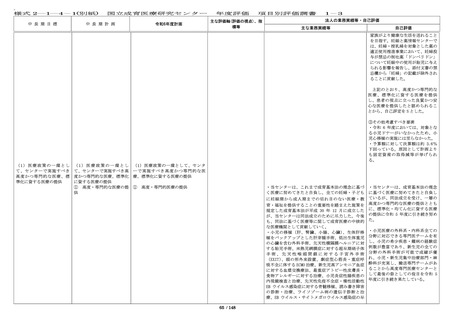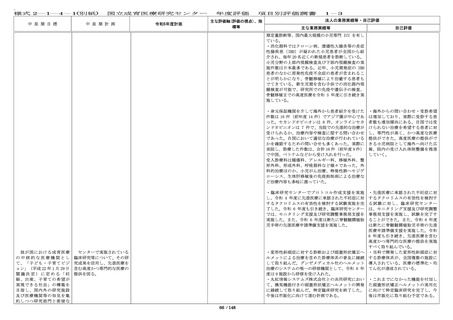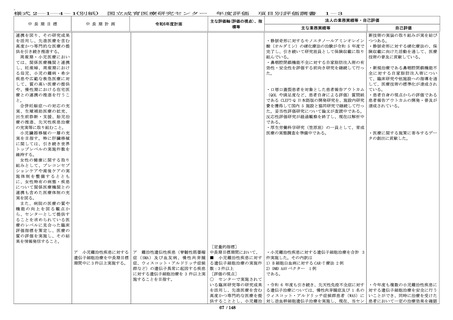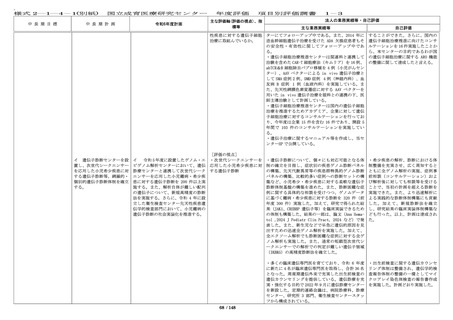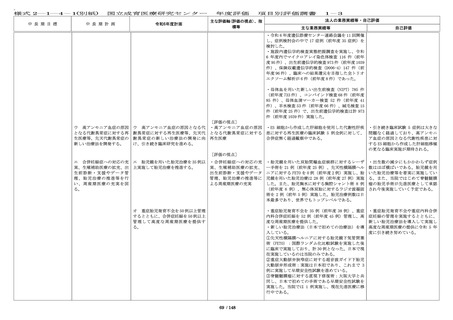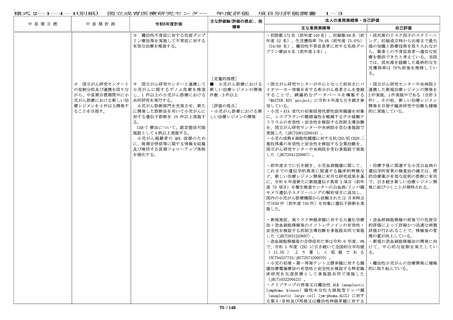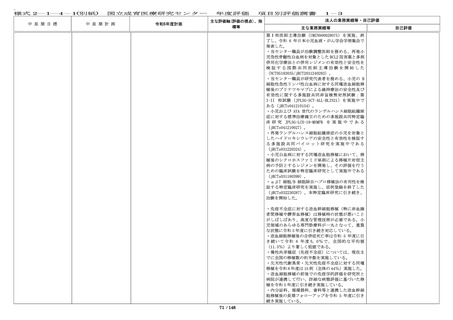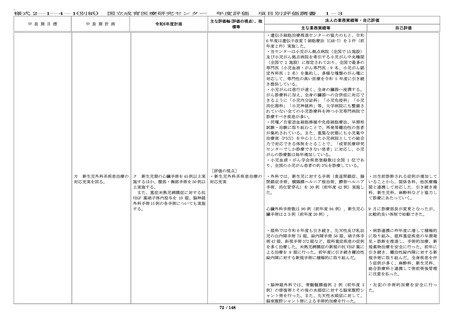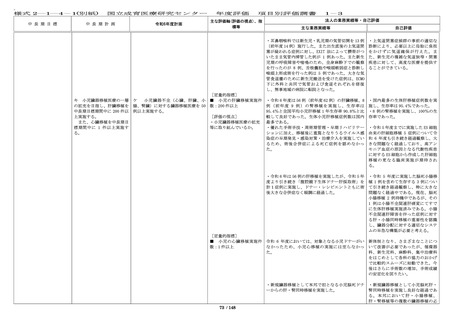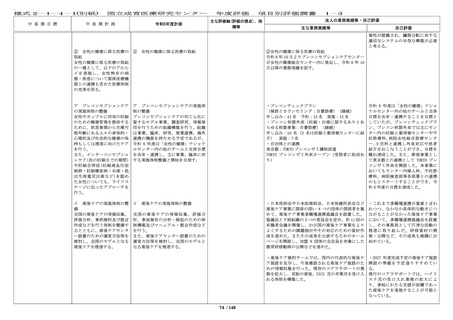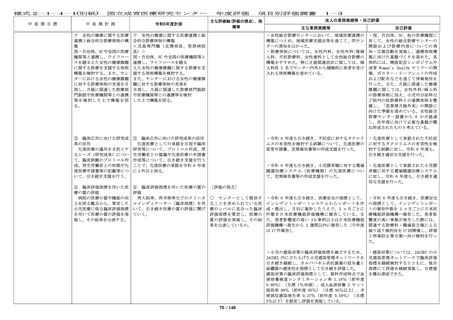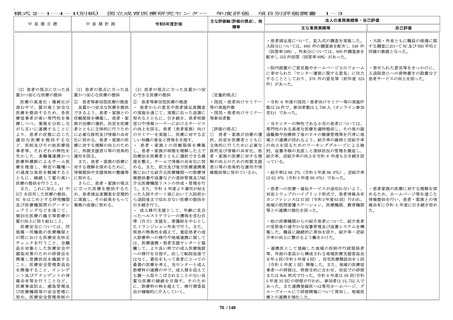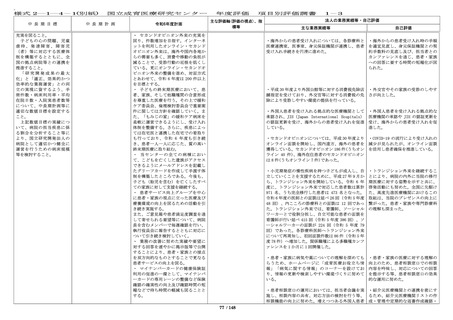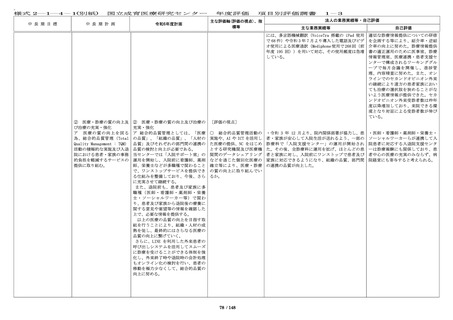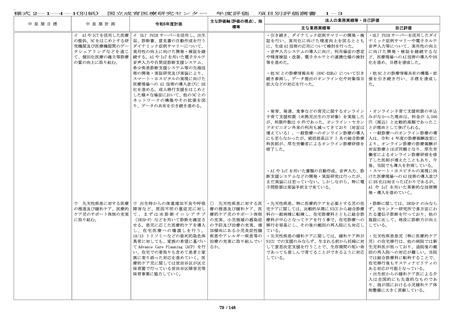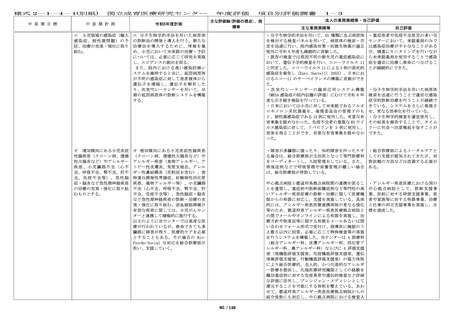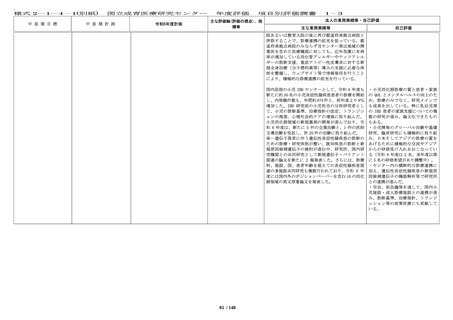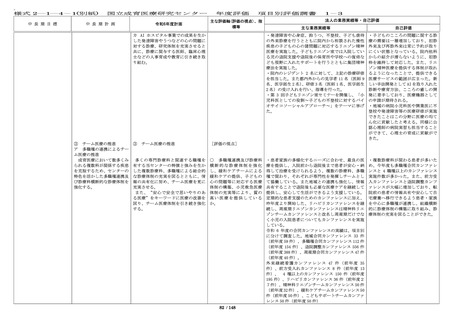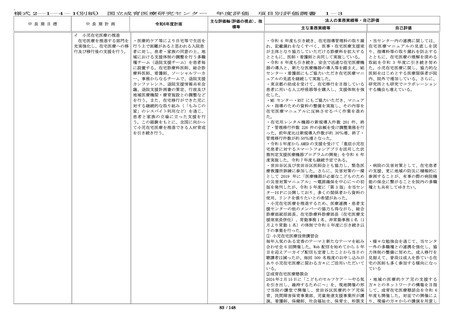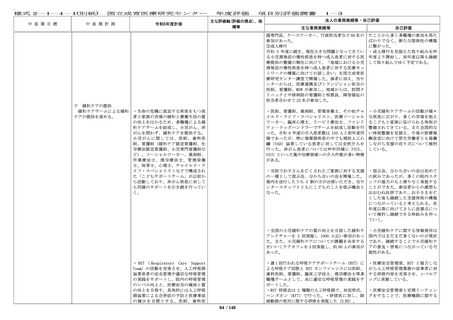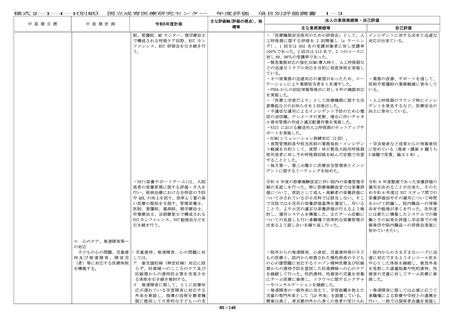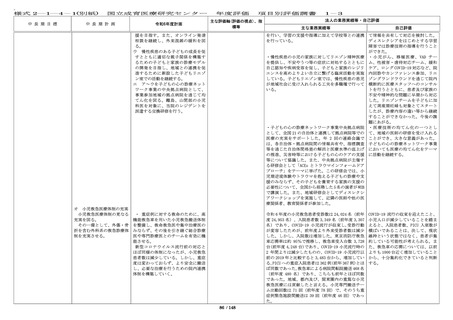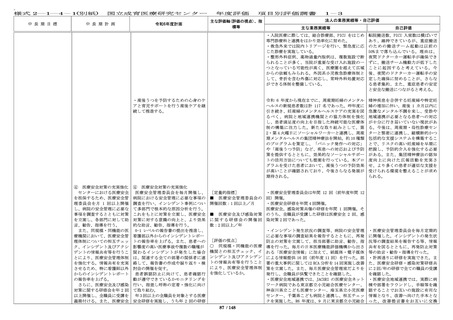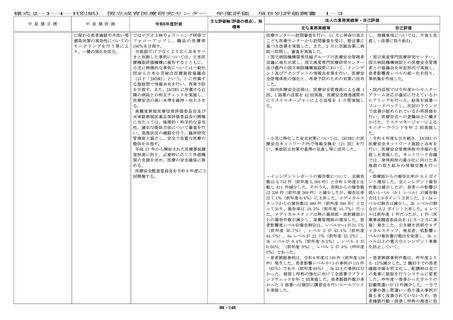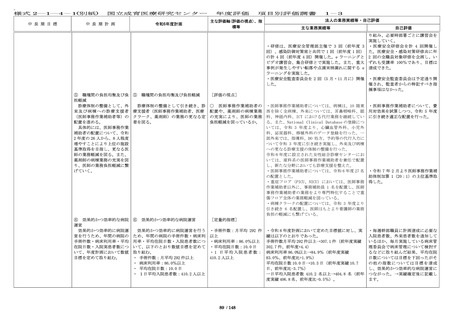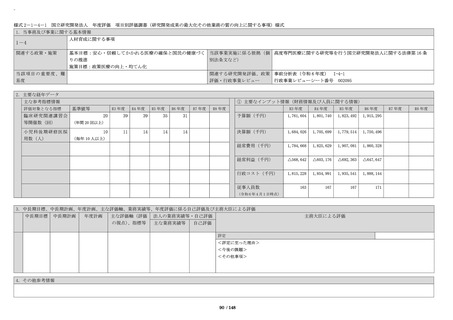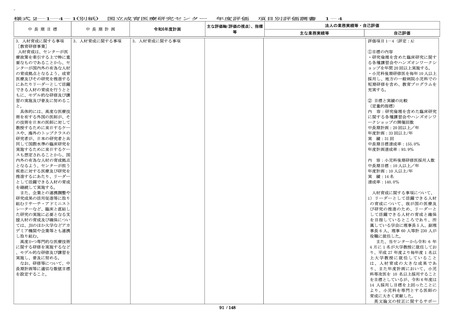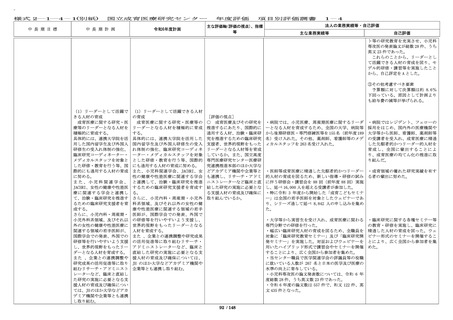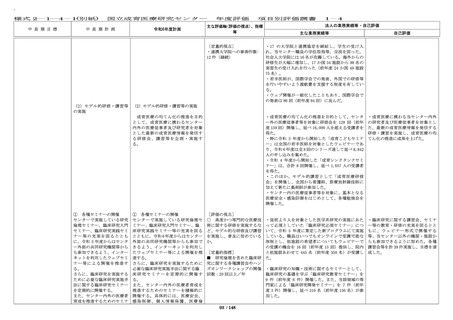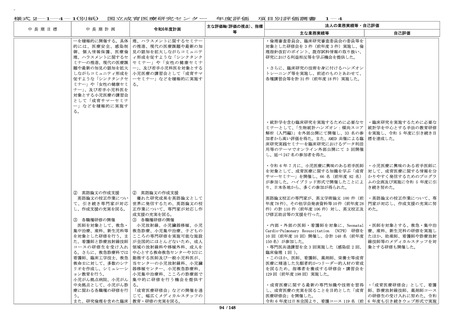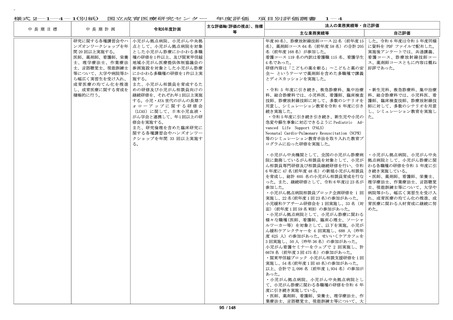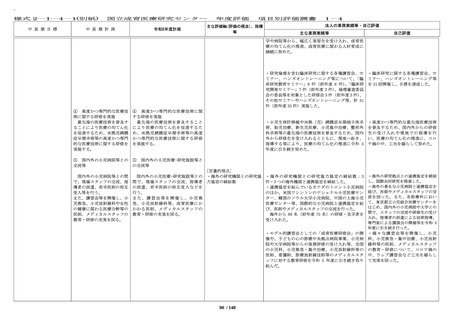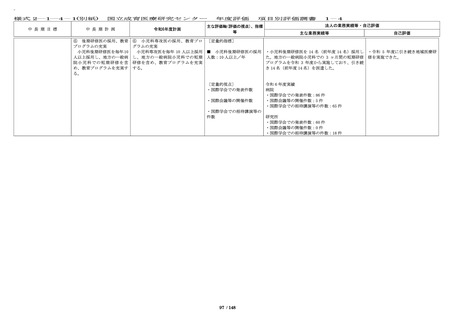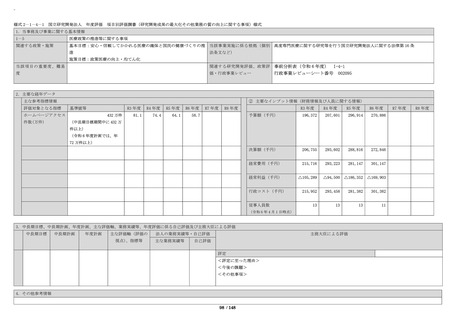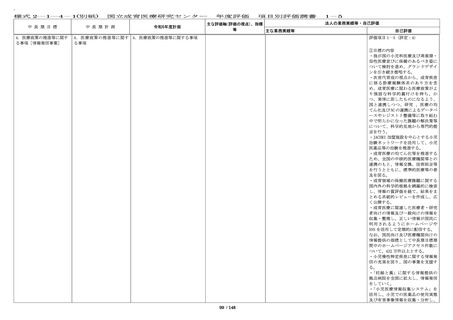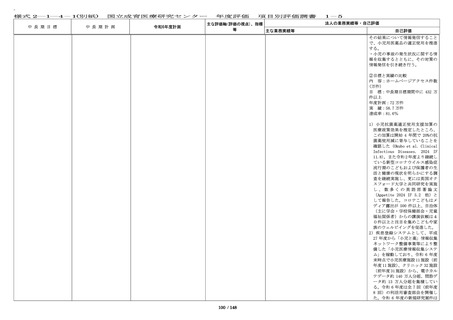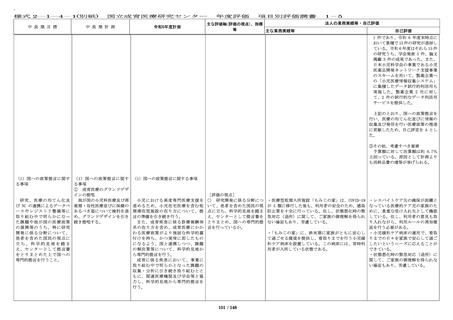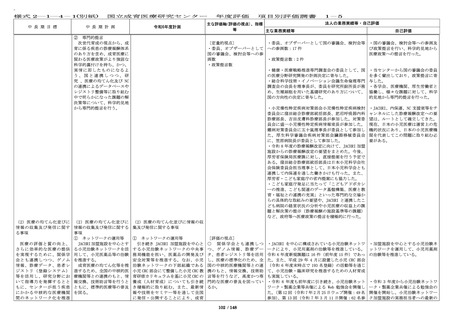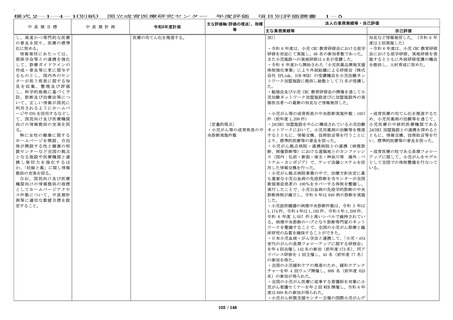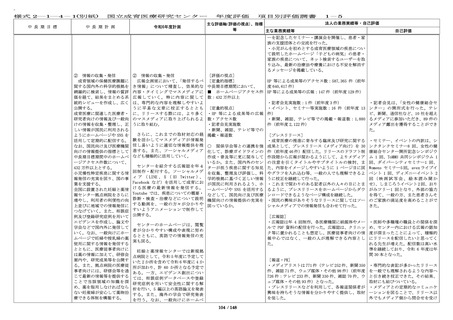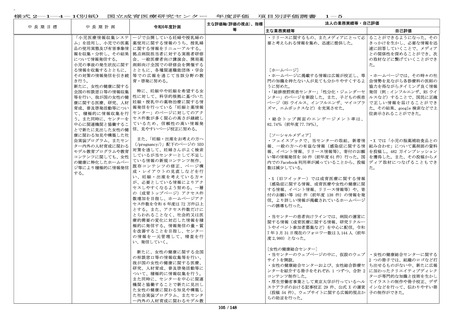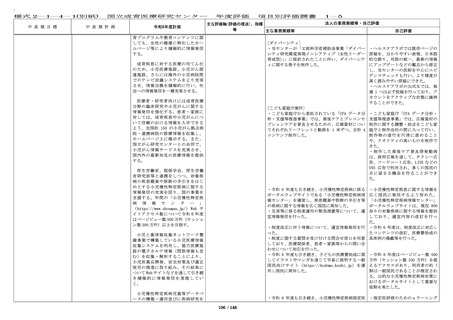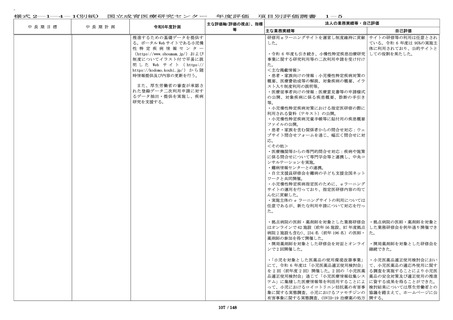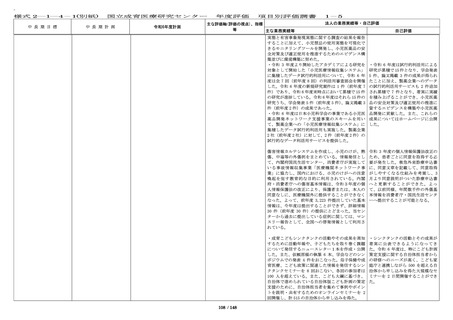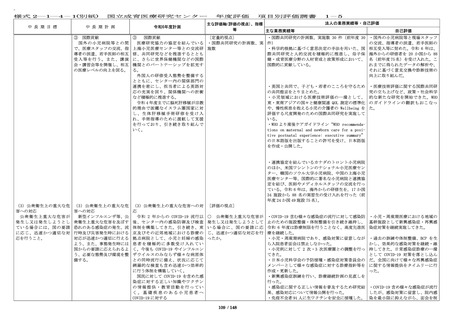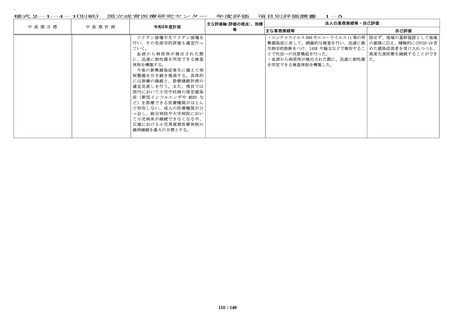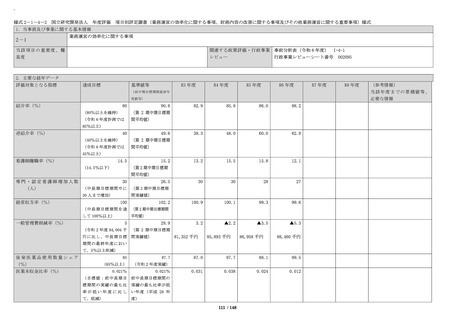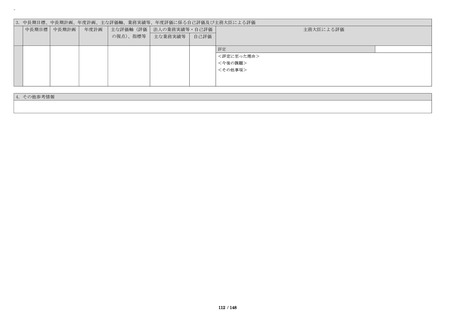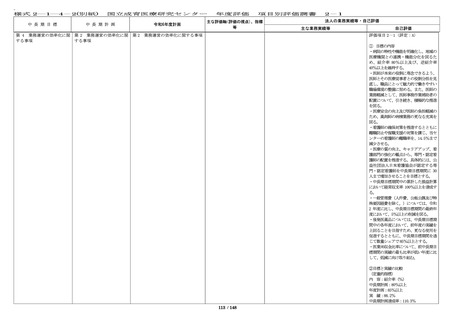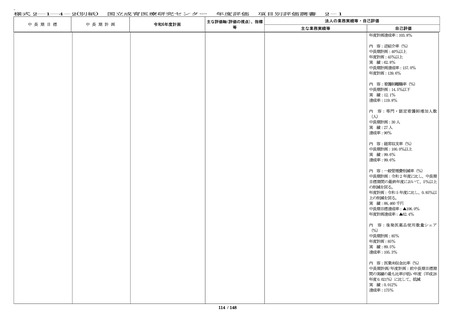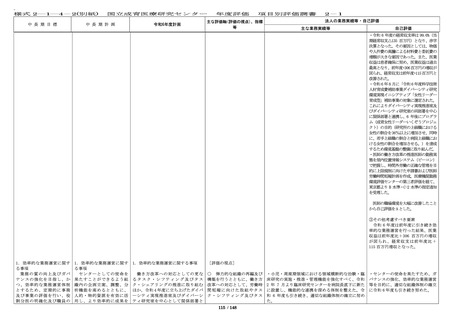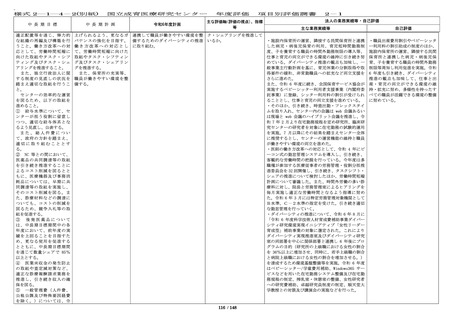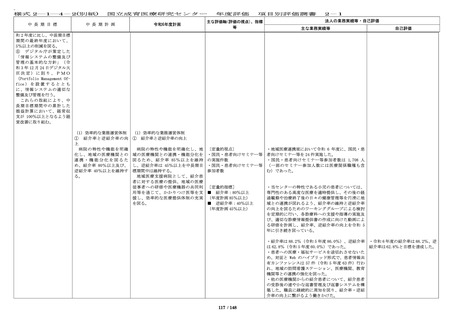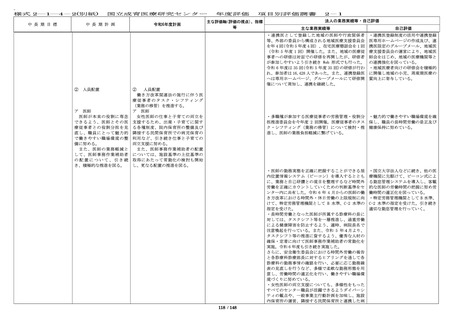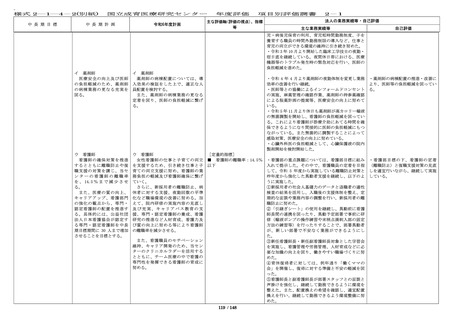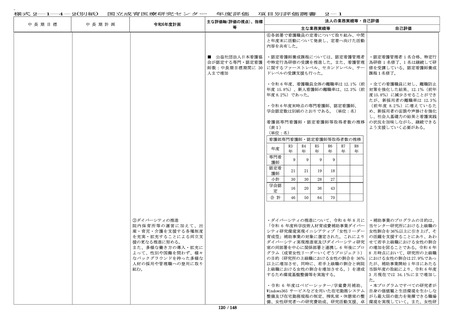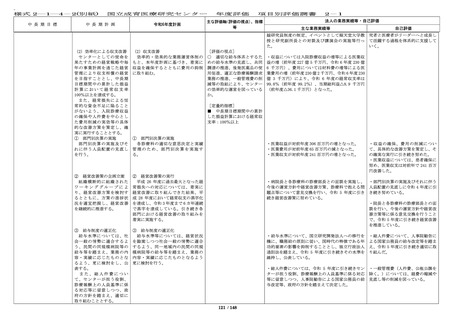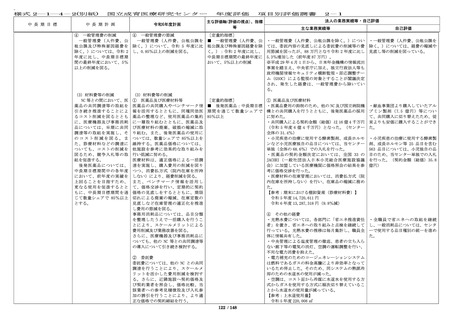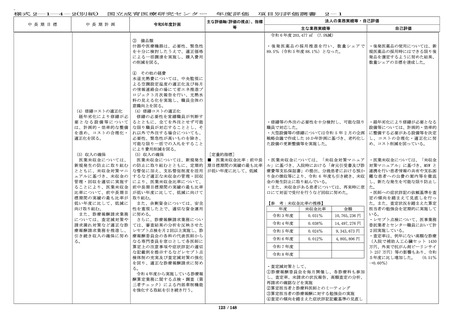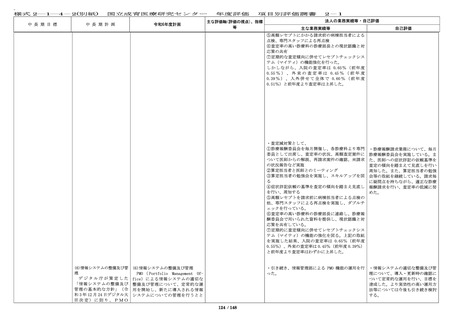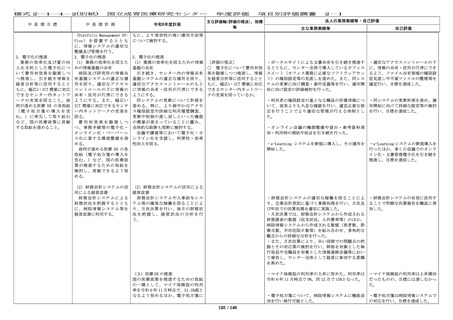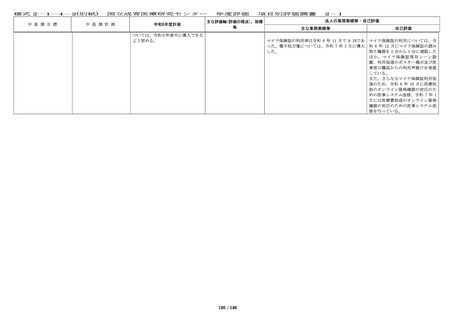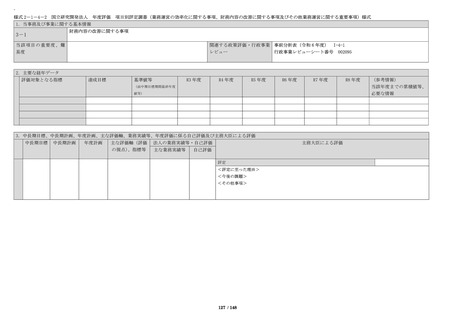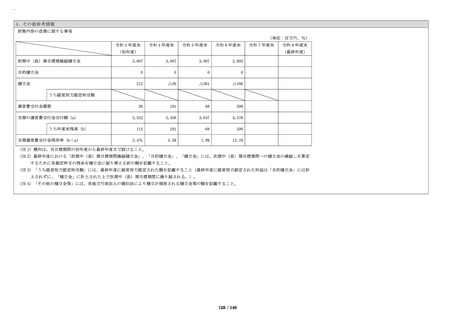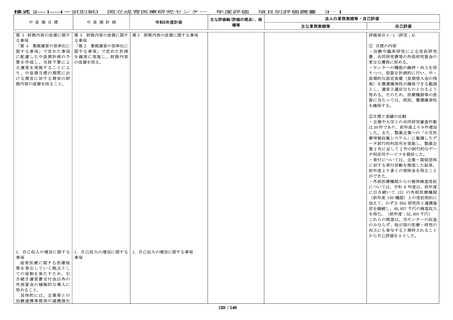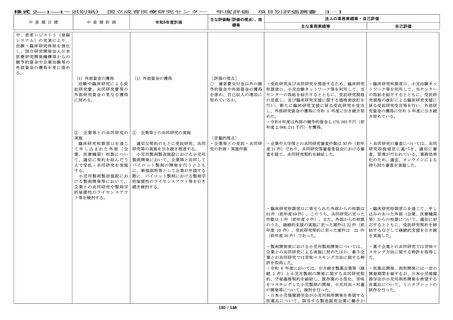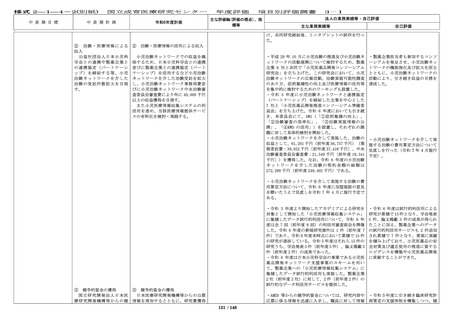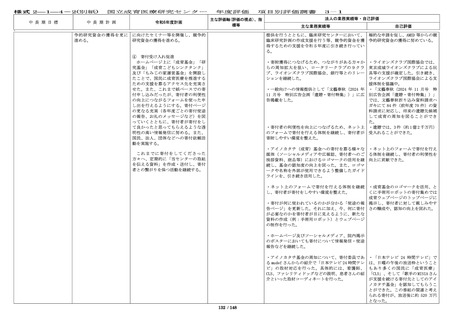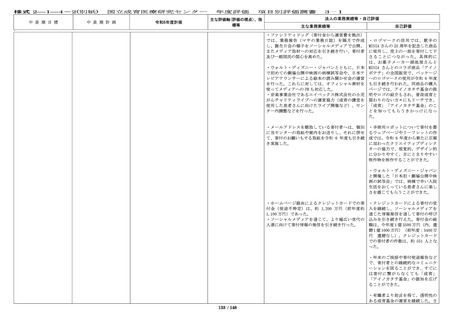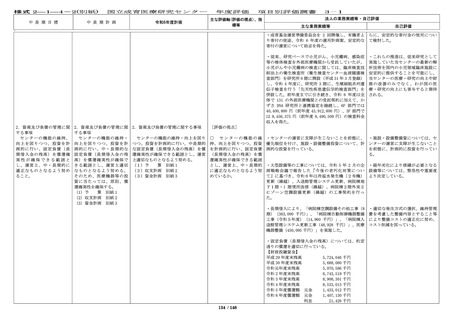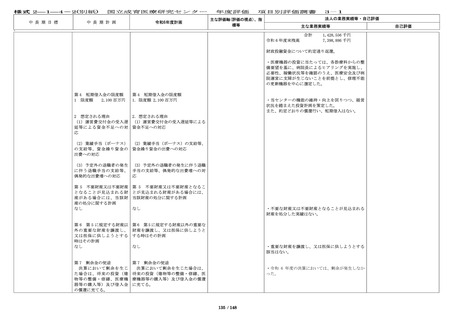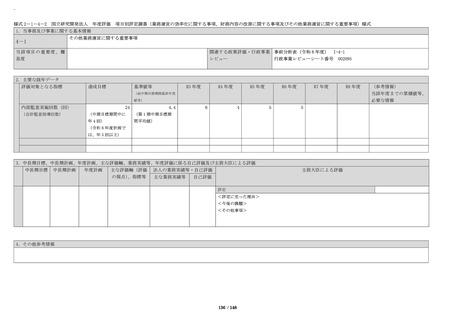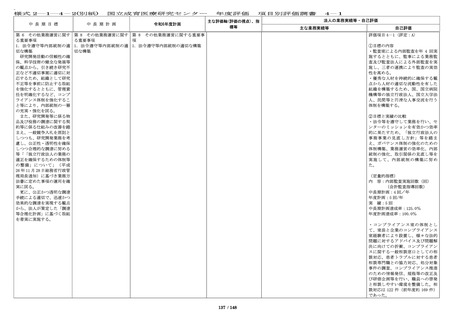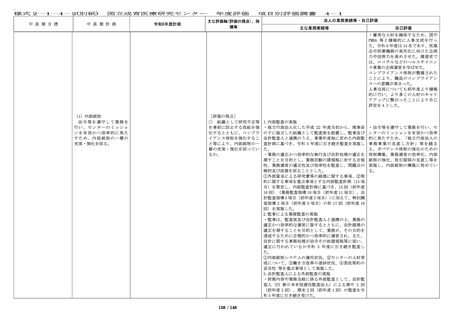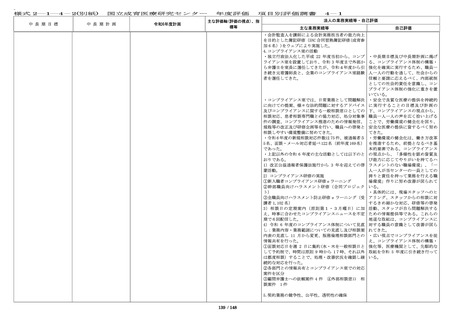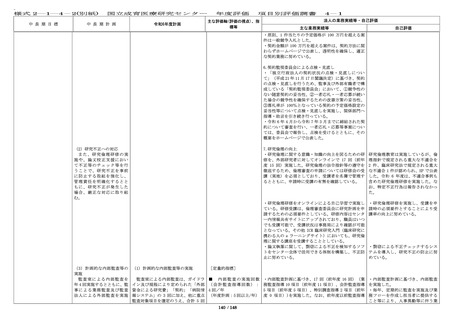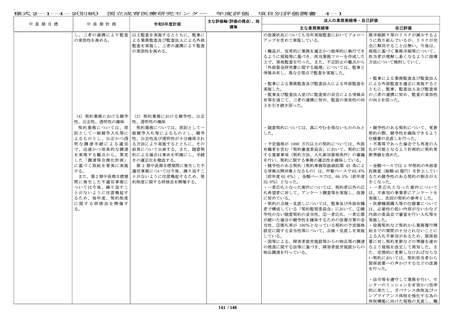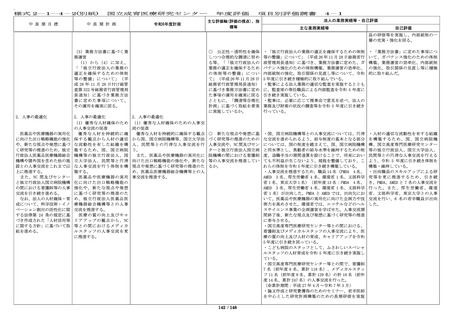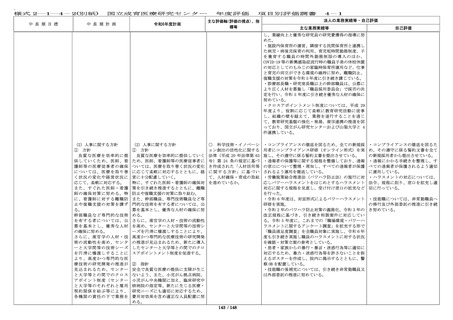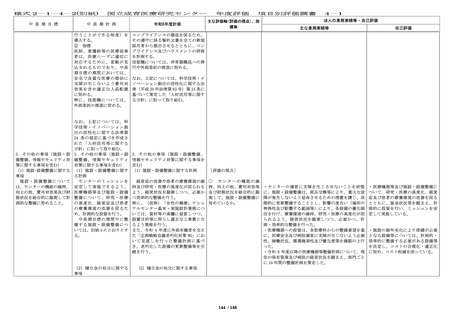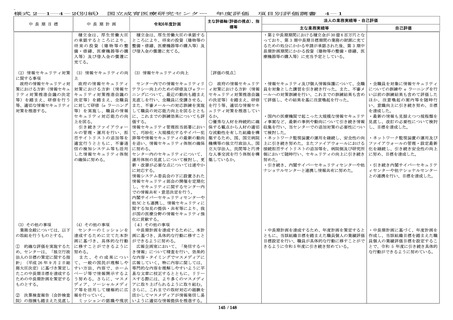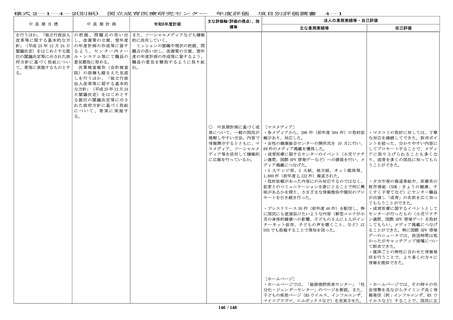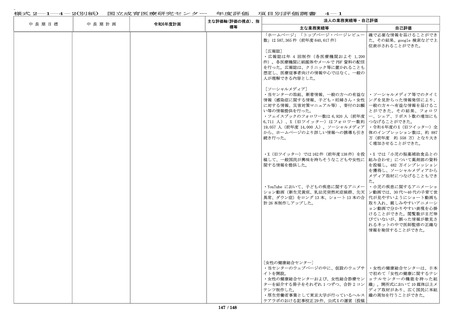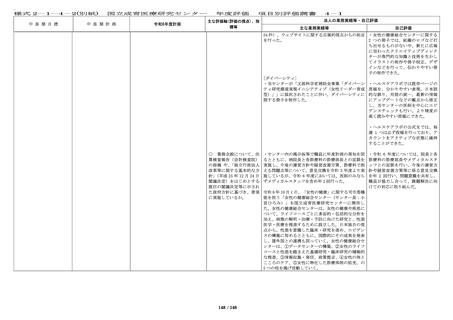資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59553.html |
| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第40回 8/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中 長 期 目 標
国立成育医療研究センター
中 長 期 計 画
令和6年度計画
エ 女性の健康や母児医療に
関するデータの収集・解析等
による新たな知見の創出に資
する研究開発
関連する各種データを収
集・解析を通し、女性の健康
や母児医療に関する健康課題
のモニタリングを行い、新規
の予防法・診断法・治療法の
シーズ探索と介入法を提案
し、社会での(政策・介入)
実装後の効果検証を行い、課
題解決の促進を行う。
年度評価
項目別評価調書
主な評価軸(評価の視点)、指
標等
1-1
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
自己評価
エ 女性の健康や母児医療に関するデー
タの収集・解析等による新たな知見の創
出に資する研究開発
<データセンター構築 WG>
女性の健康や母子医療に関する既存のデ
ータを把握し、得られたデータから新
健康課題の抽出と実態把握、新規の予防
法・診断法・治療法・介入法を提案や社
会での実装後の効果検証を行い、課題解
決の促進を行う。
・健康経営度調査データを取得し、女性の健康に関
する健康経営の経年変化や、関連する企業要因の分
析を行った。
・政府統計(人口動態統計や生活基礎調査等)を取
得した。
・健康アプリを運用する企業と、二次性徴・初経に
関する共同研究を開始し、プレスリリースを行っ
た。
得られるデータを分析・可視化
して維持することで、データ利
活用の有用性を多くの団体に理
解してもらうことができ、結
果、複数の情報源からローデー
タを取得することができた。
オ プレコンセプションケア
に係る研究開発
プレコンセプションケアのモ
デルを実施し検証により得ら
れた相談症例等のデータベー
ス化等により、将来の妊娠を
考えながら女性等が自分たち
の生活や健康に向き合うこと
等に関する課題解決を目指
す。
オ プレコンセプションケアに係る研究
開発
<プレコンセプションケアセンター検討
チーム>
プレコンセプションケアの均てん化に資
するモデル事業、調査研究、情報発信
を行うための組織構築を行う。組織は事
業、臨床、研究、産業連携、海外連携の
機能を持たせる予定であるが、令和 6 年
度は「女性の健康」ナショナルセンター
内の他のチームと全体目標を共有・連携
し、データベース化に必要な内容の検討
と事業の開始を目指す。
①プレコンセプションケアに係る研究開発
令和 6 年 10 月よりプレコンセプションケアセンター
が女性の健康総合センター内に発足し、令和 6 年 10
月以降の業務実績を記す。
・プレコンセプションケアの均てん化に資するモデ
ル事業として、こども家庭庁による「プレコンセプ
ションケアの提供のあり方に関する検討会」と連携
のうえ、準備を進めた。
・プレコンセプションケアにおける医療者のための
マニュアルを作成した。
・プレコンセプションケア提供者への支援をおこな
った。(アドバイザーテキストブック作成・アドバ
イザー用 PPT 作成)
令和 6 年度は「女性の健康」ナシ
ョナルセンター内の他のチーム
と全体目標を共有・連携するこ
とを目標としていたが、子ども
家庭庁と女性の健康総合センタ
ー内で連携をとりながら進行で
きており、おおむね当初の計画
どおり行えた。
カ 産後ケアに係る研究開発
産後ケアに関する知見を集積
するための全国の実態調査等
を行う。この知見等を踏ま
え、産後ケアの事例をデータ
ベース化し、産後ケアの均て
ん化を図るため、研修の内容
の検討を行う。
カ 産後ケアに係る研究開発
<産後ケアセンター検討チーム>
産後ケアに関する知見を集積するための
全国の実態調査等を行い、その知見等
を踏まえ、評価・分析及び事故報告の分
析・検証のための体制構築、さらにマニ
ュアル・提言などの作成を開始する。産
後ケアの均てん化を図るため、研修会を
企画・立案・実施する。
・産後ケア事業の委託先の事業責任者やケア提供
者、行政担当者向けの研修動画 5 本の作成を進め、
完成したものから順次公開をおこなった。令和 7 年
1 月に公開してからすでに各動画 1,500-2,000 回程度
の視聴があり、全国的な安全性・質の均てん化に貢
献した。また、産後ケア事業の委託先でありそうな
事故の架空症例を設定し、その予防策などを検討
し、情報発信の資材 2 点を作成した。
・これまで母子保健指導者養成
研修として、産後ケア事業に関
する動画は作成されていたが、
本協議会が研修動画を作成する
ことにより、ガイドラインの改
定などの行政的なポイントだけ
でなく、メンタルヘルスや多職
種連携など幅広な教育・研修の
資材が作成・公表できるように
なる。その基盤が順調に整備さ
れてきている。また、作成・公
表した動画の再生件数からも多
くの関係者に活用されている。
・産後ケア連絡協議会の調査検討委員会では、既存
の調査や研究を整理した上で、今後の調査の内容を
検討していく予定である。現在は既存資料の収集作
業を開始している。
・安全管理委員会では、産後ケア事業で発生する可
能性がある緊急性の高い事例や事故事例についてテ
ーマを設定し、架空事例を作成し、予防策及び初期
・産後ケア連携協議会は、関係
団体とともに各委員会活動を開
始することができており、予定
通りの進捗である。
39 / 148