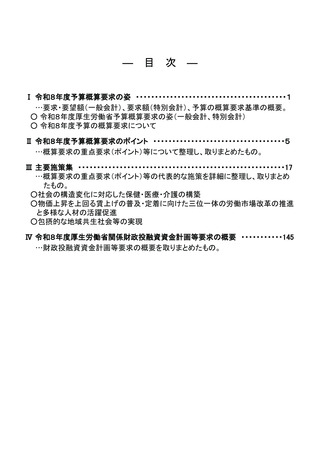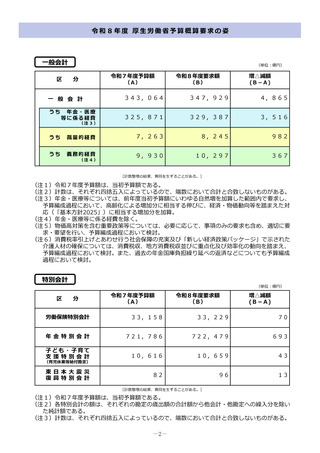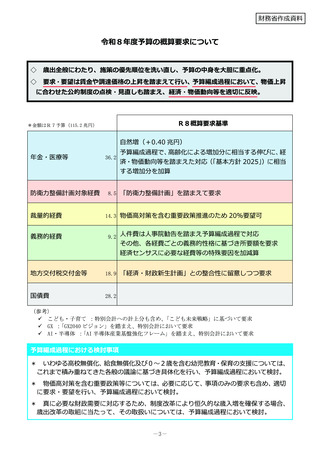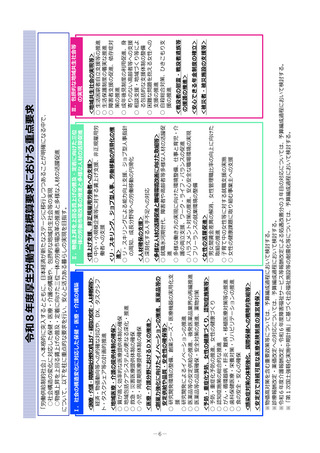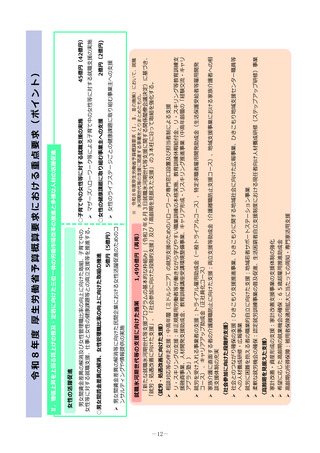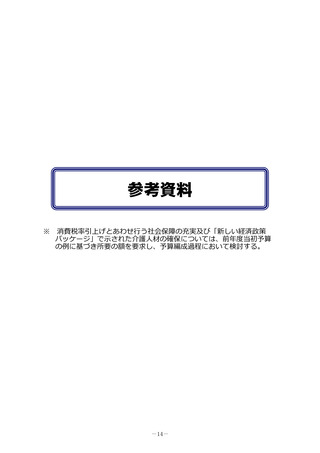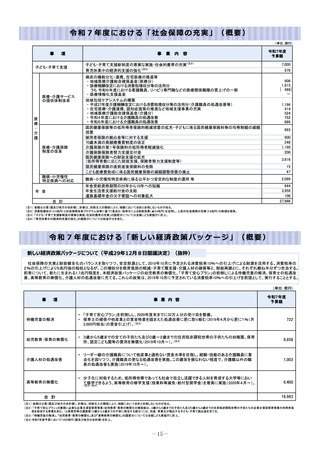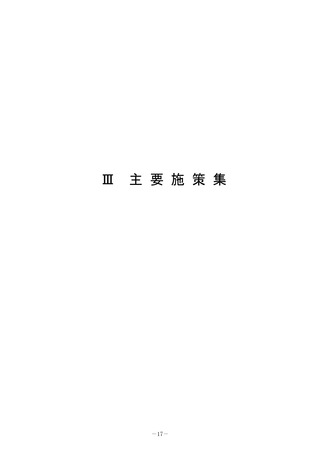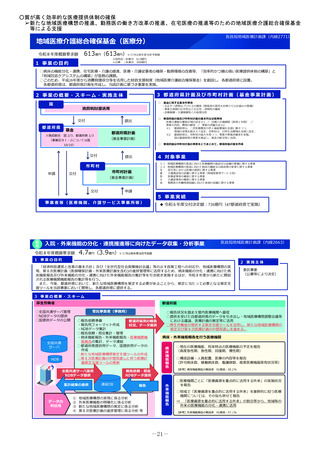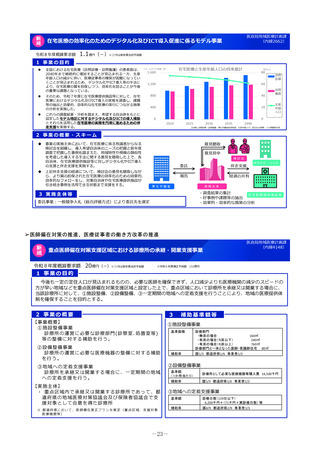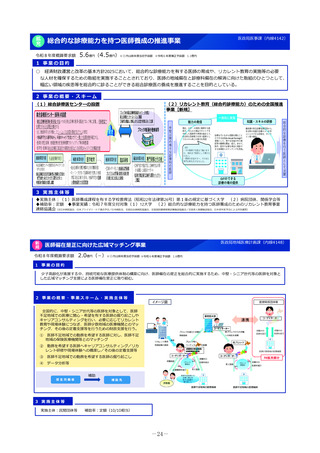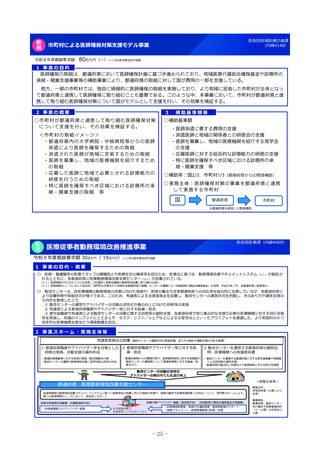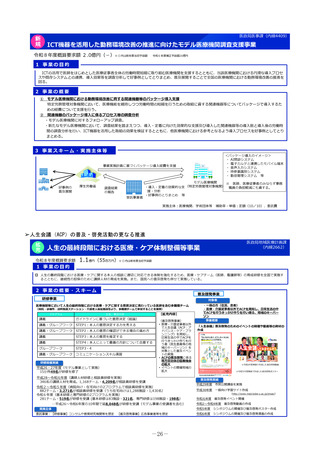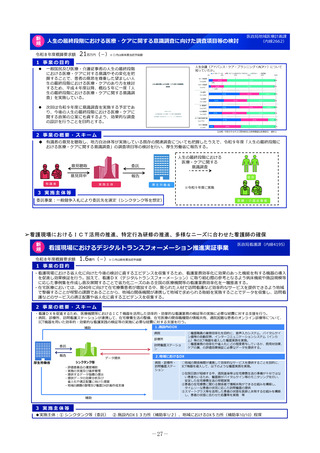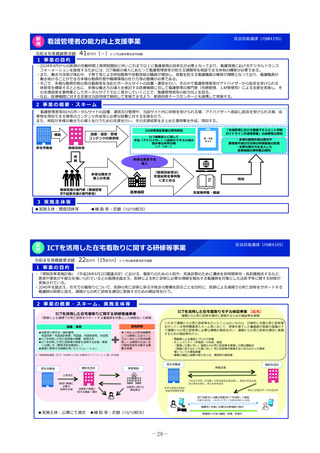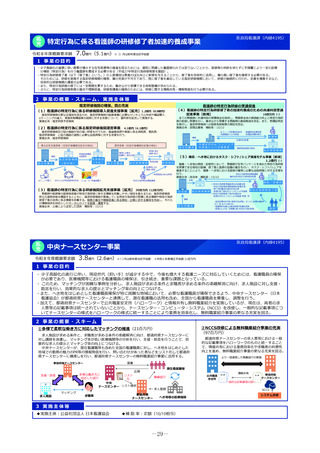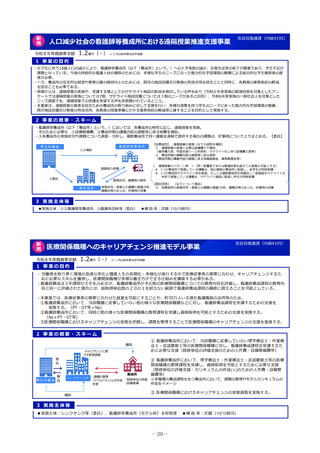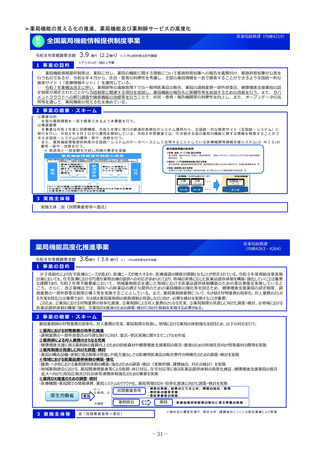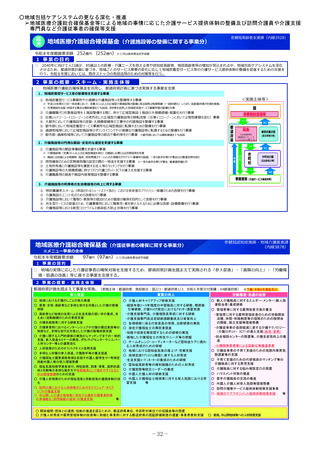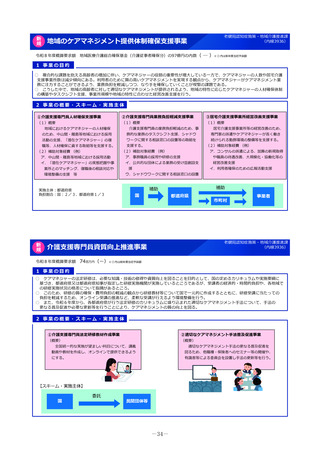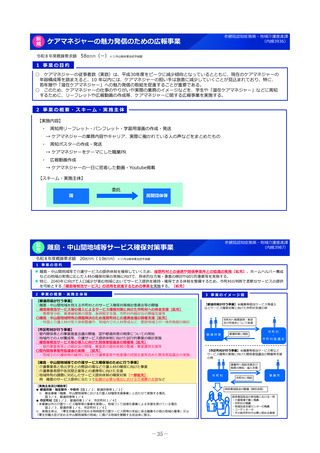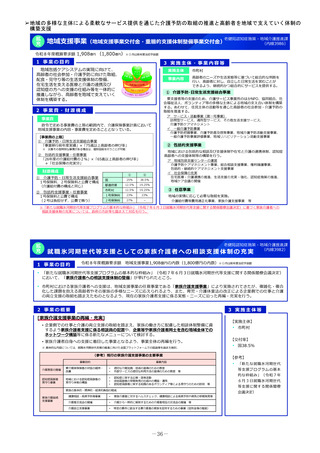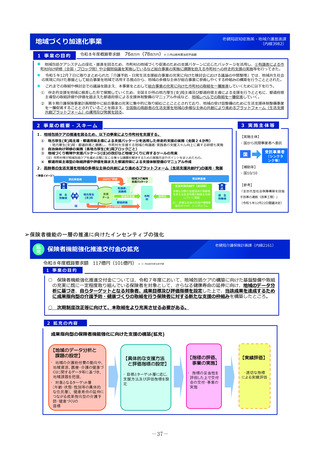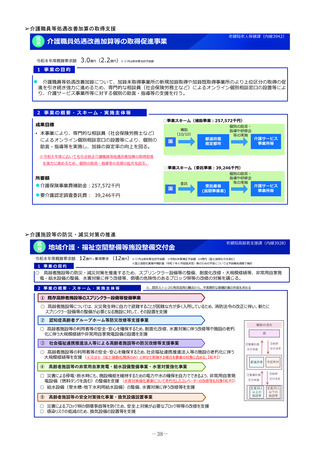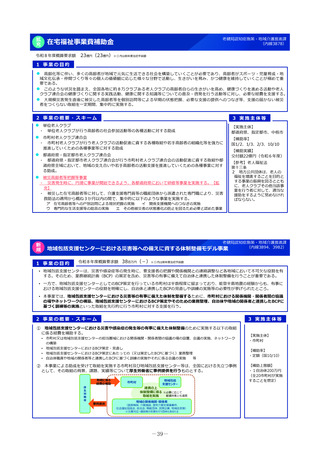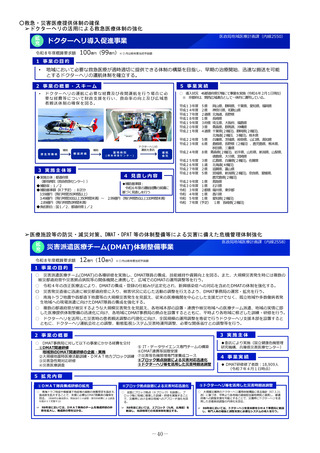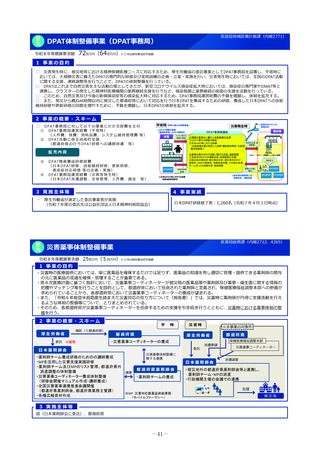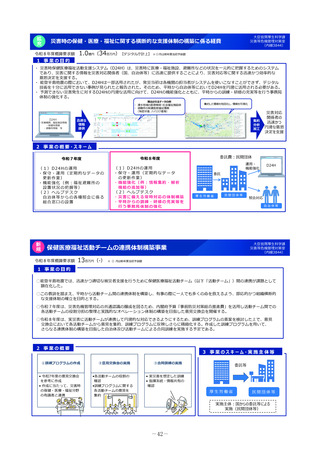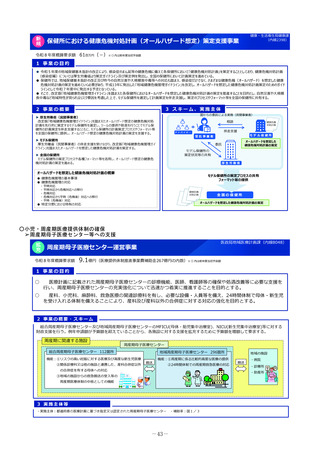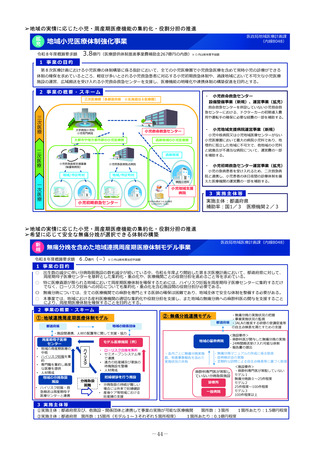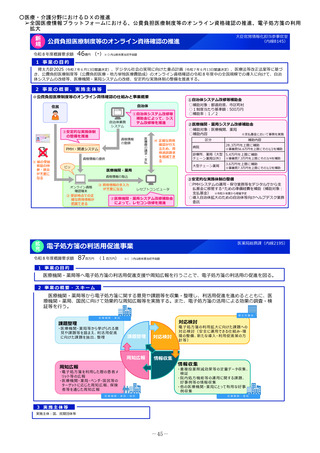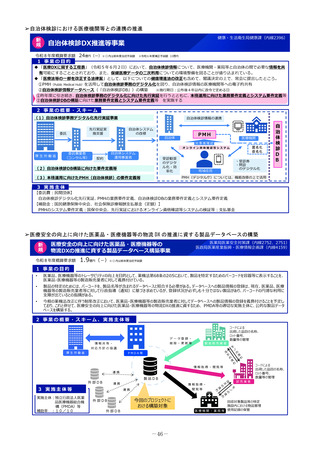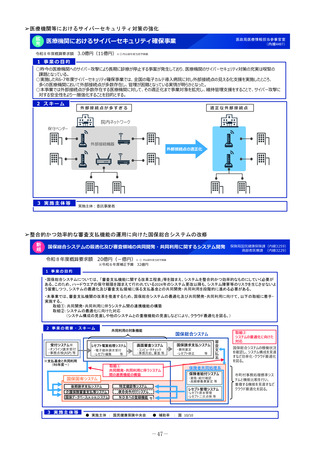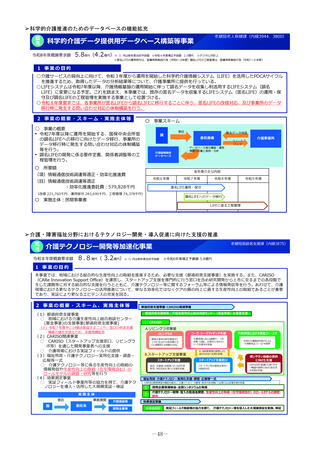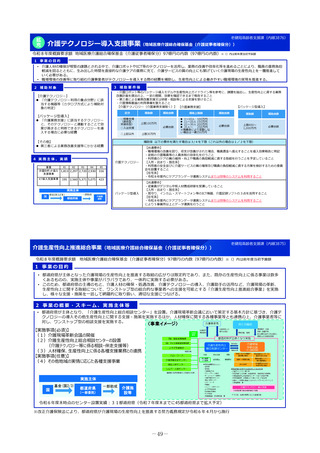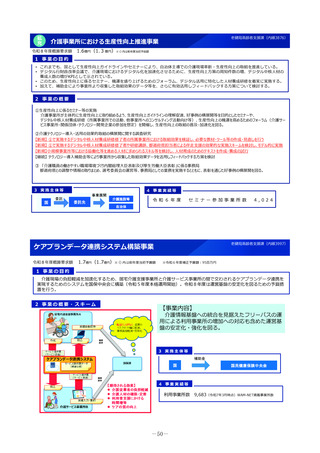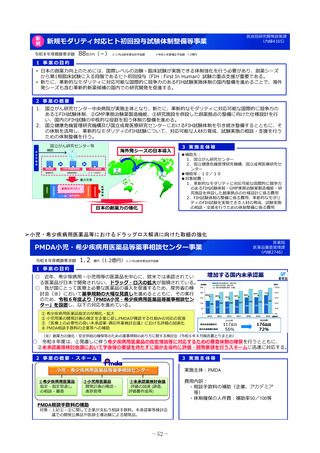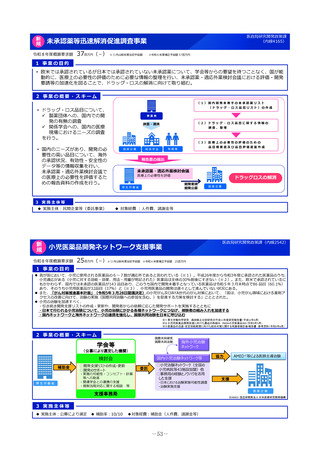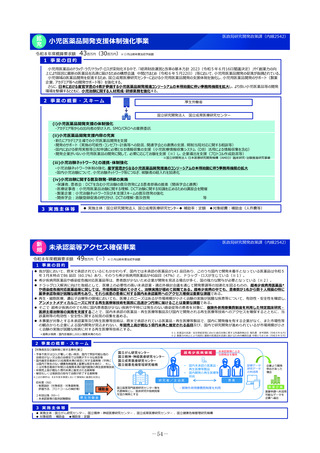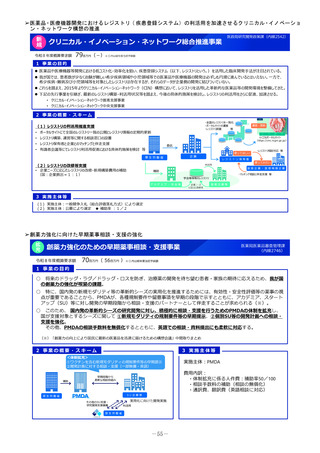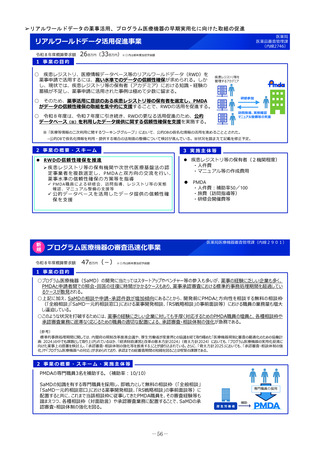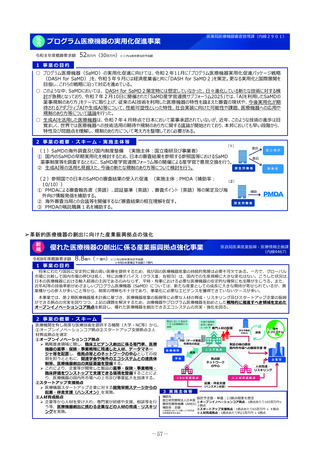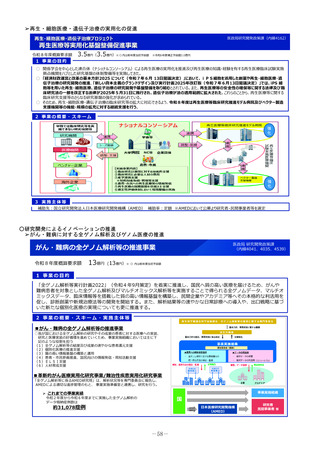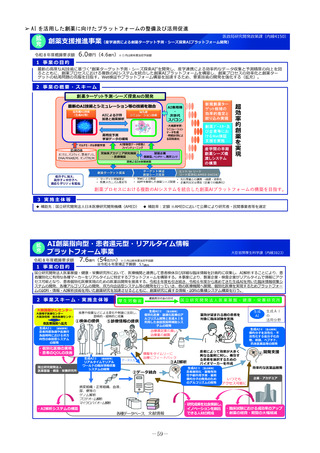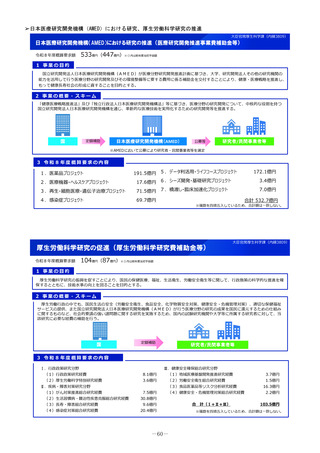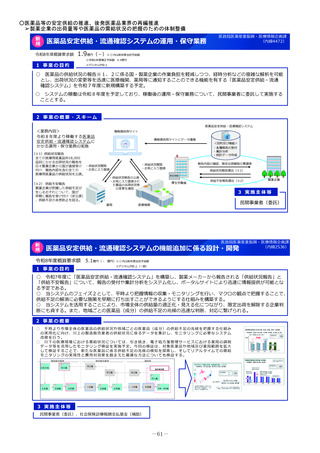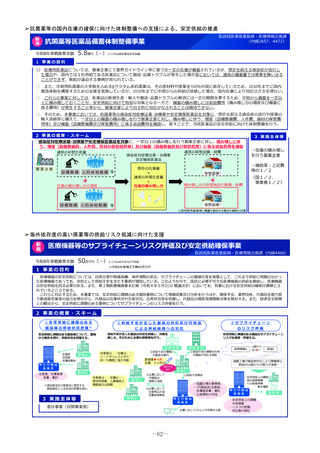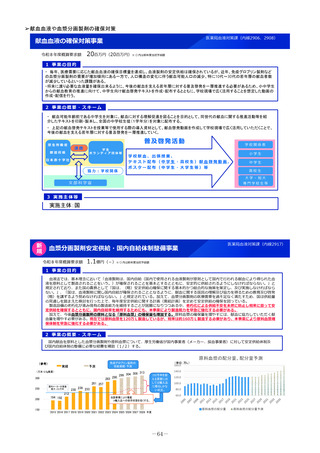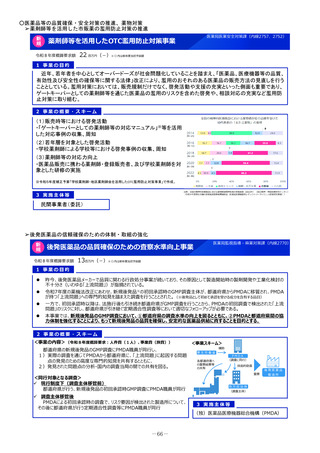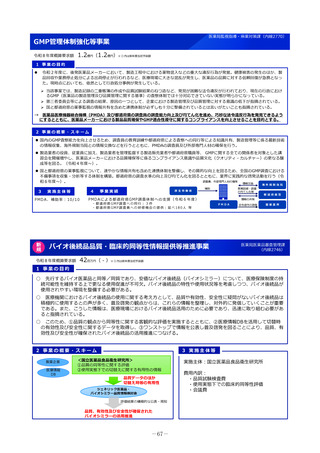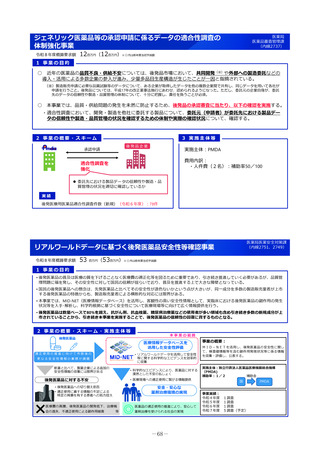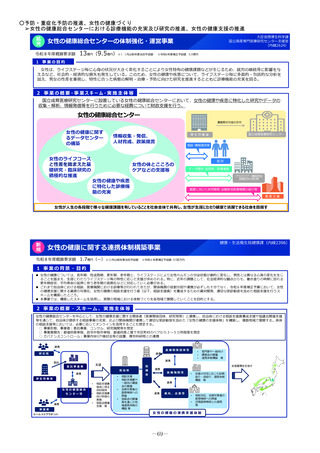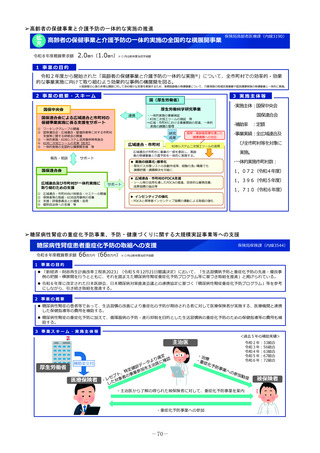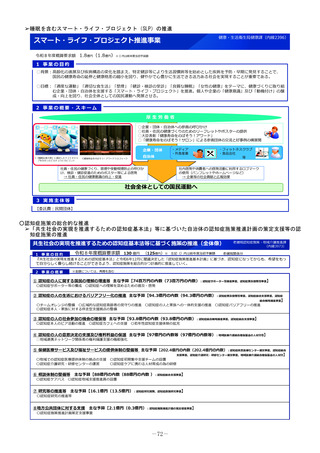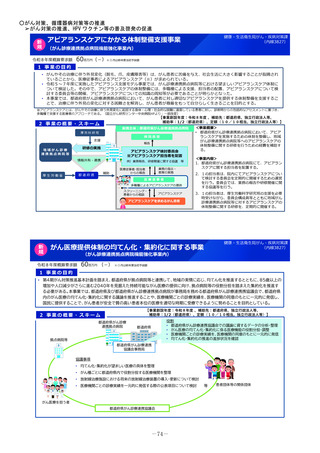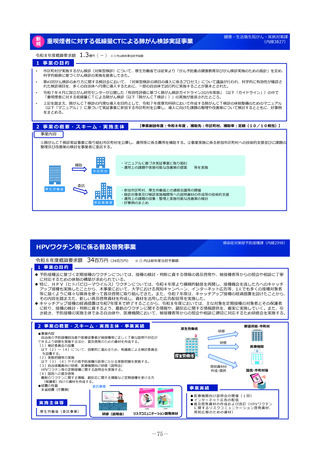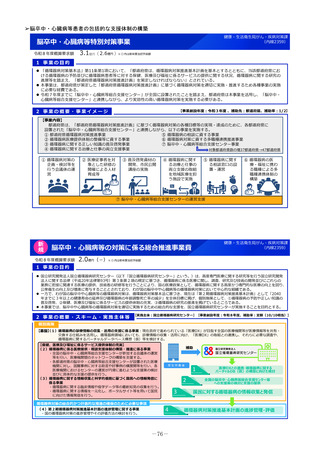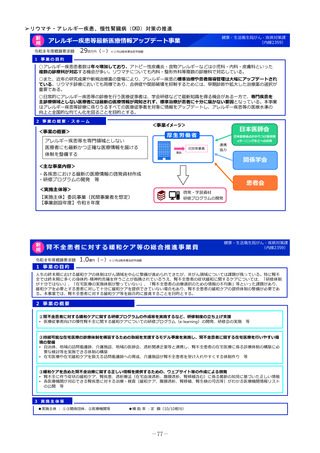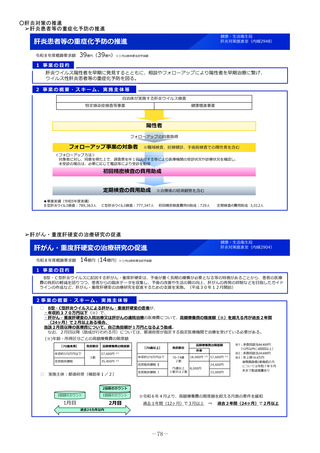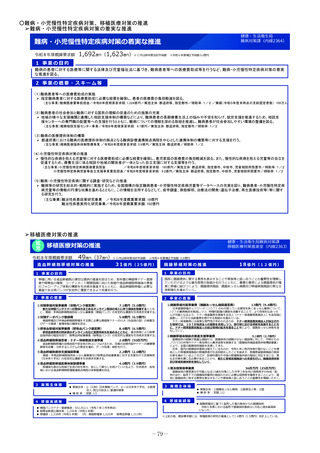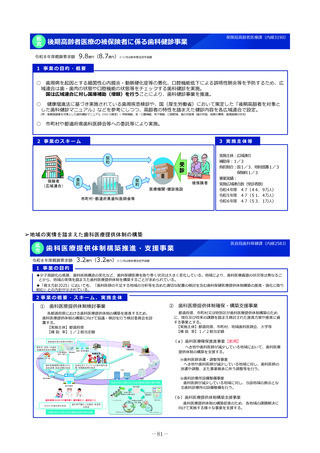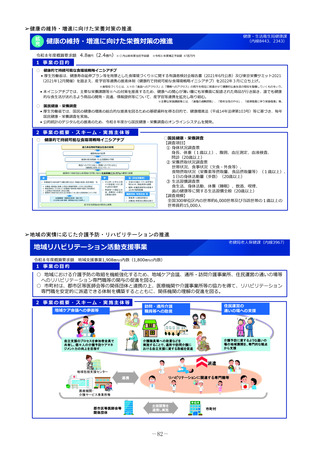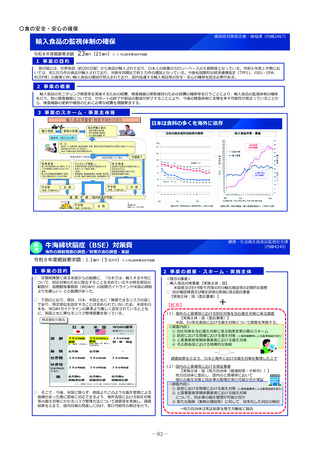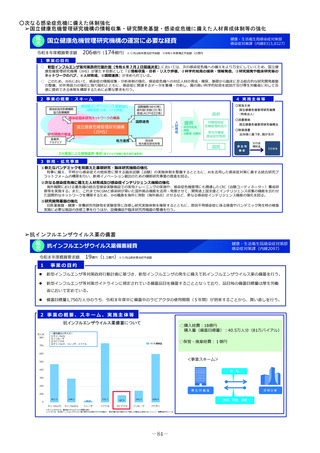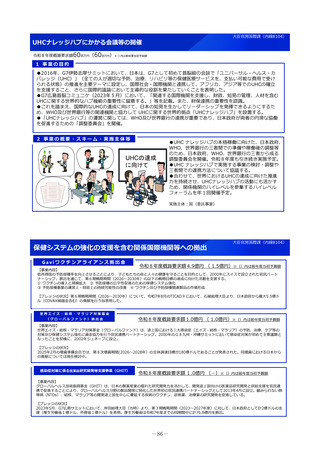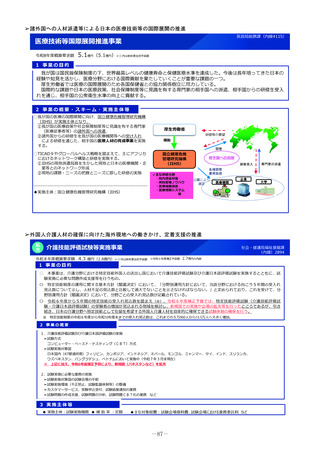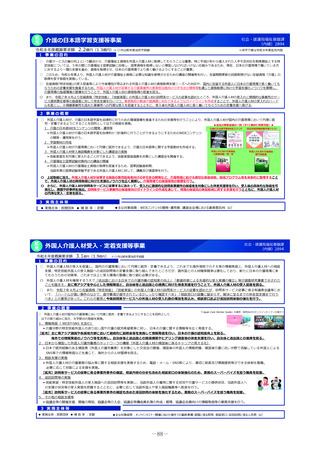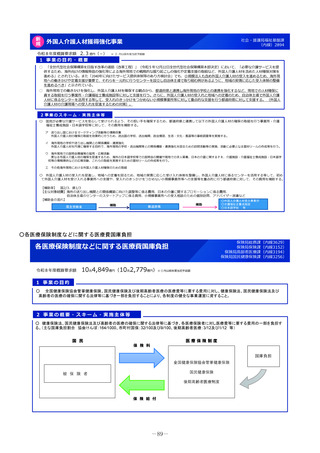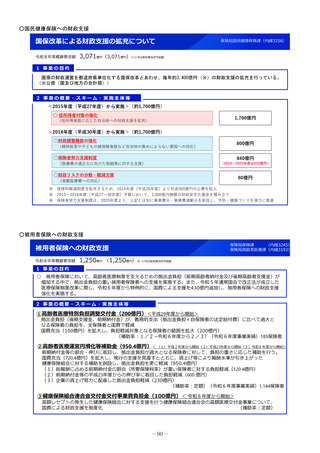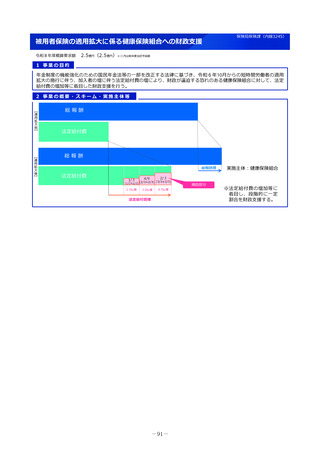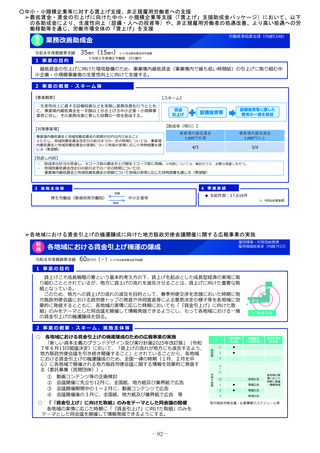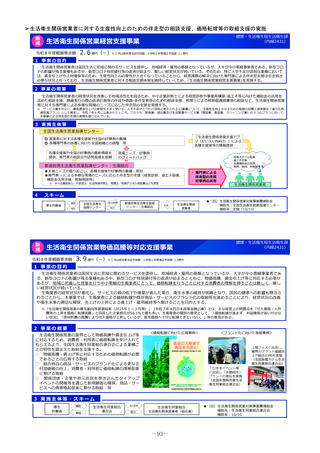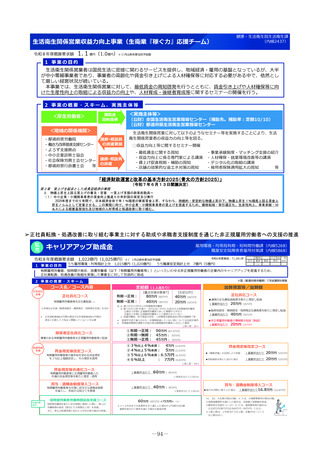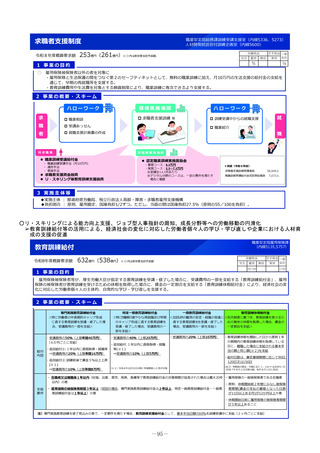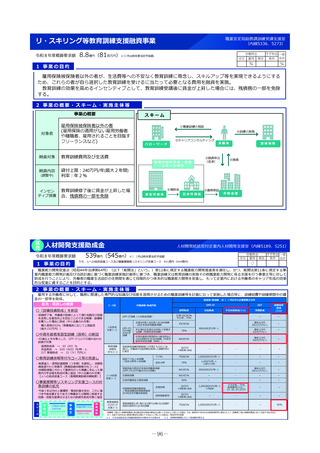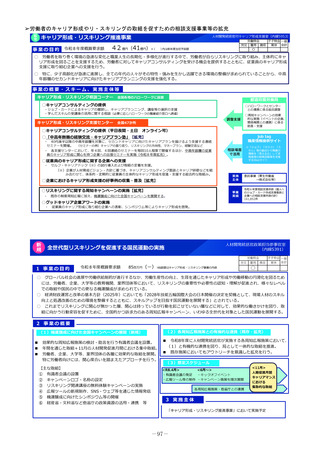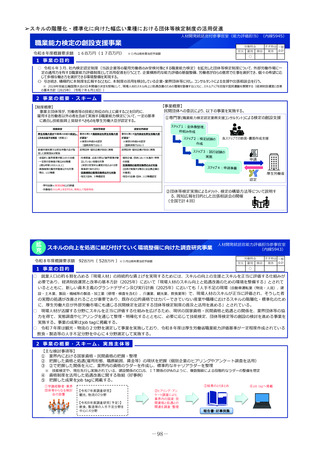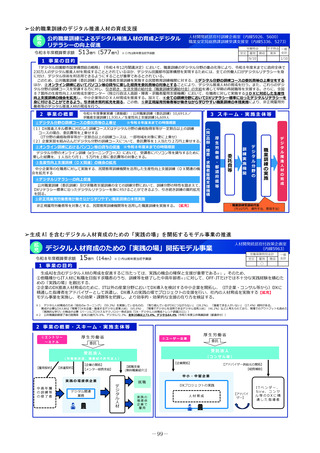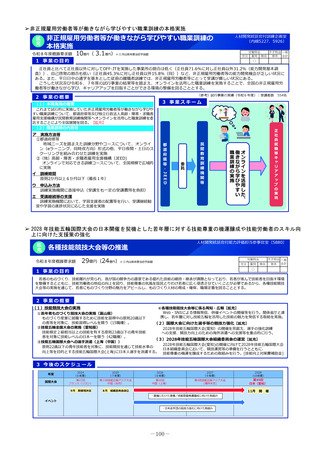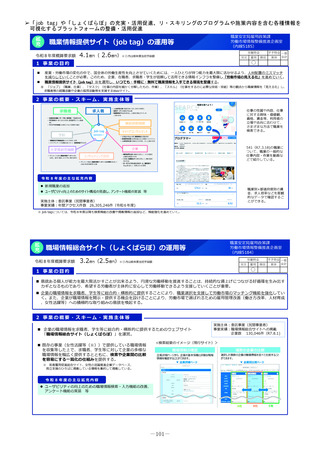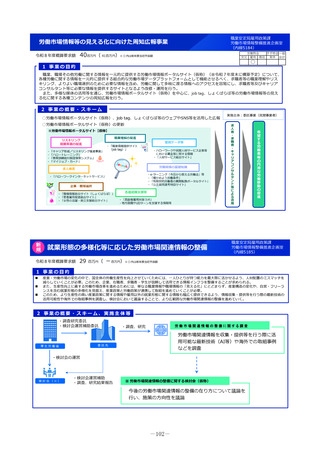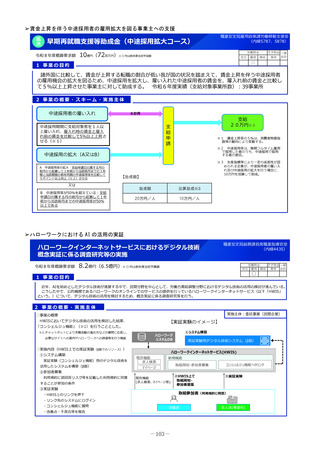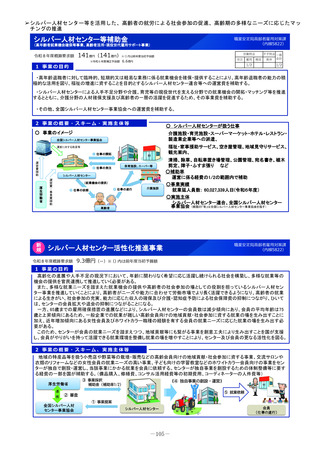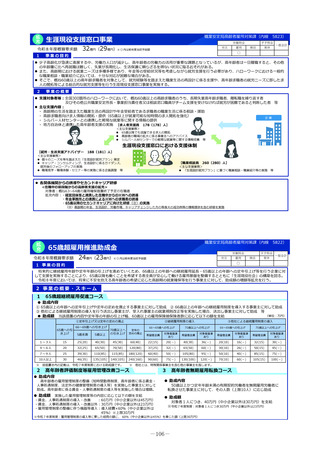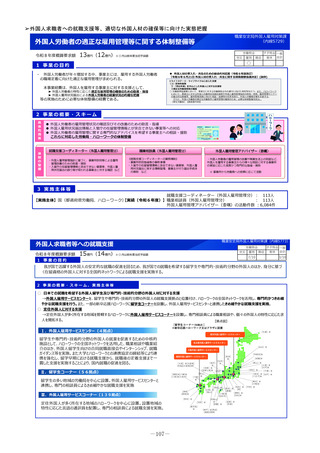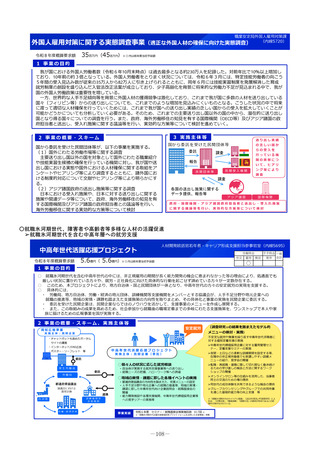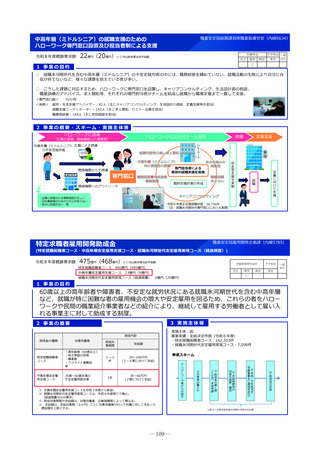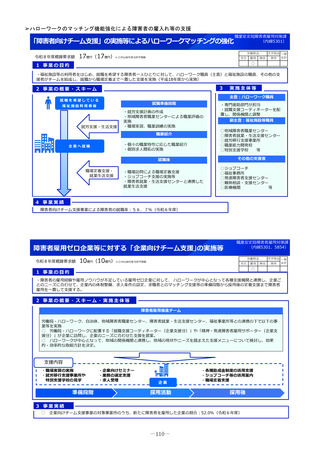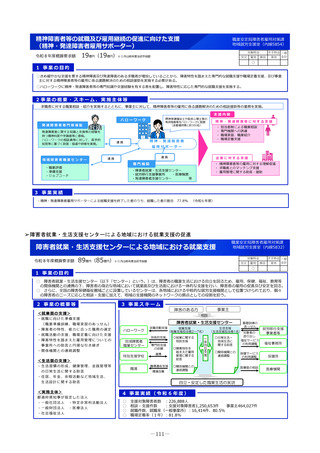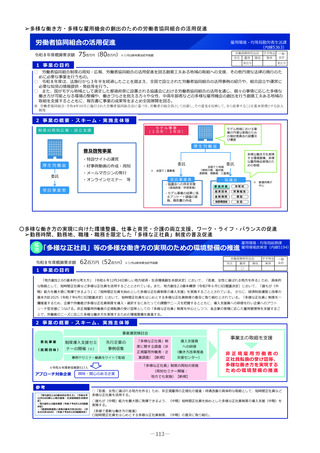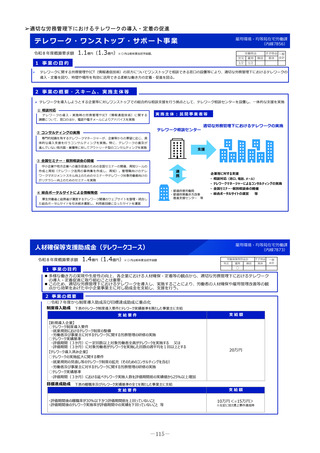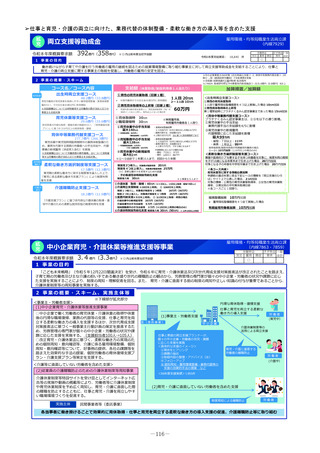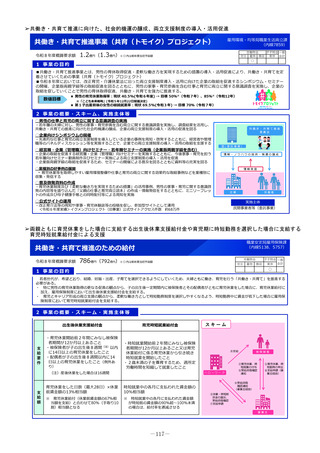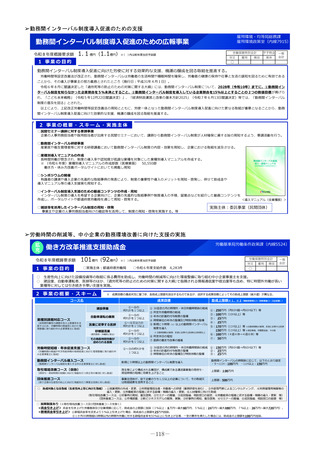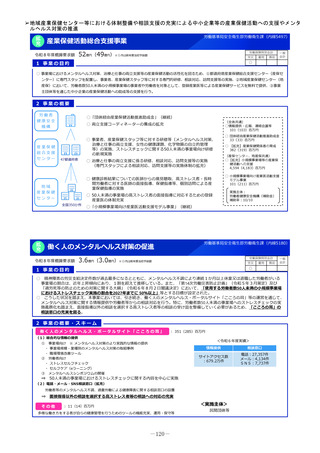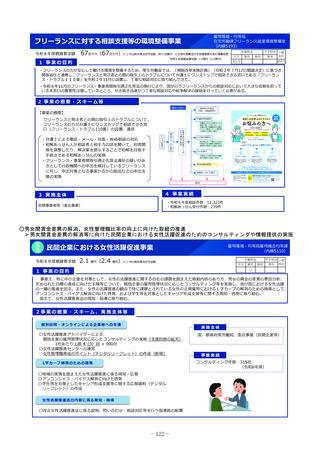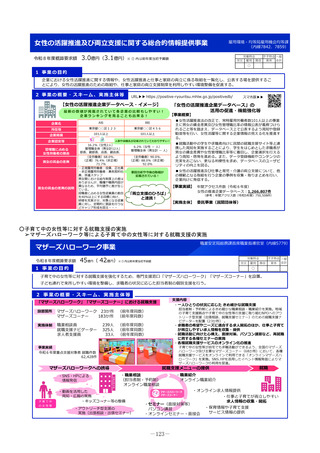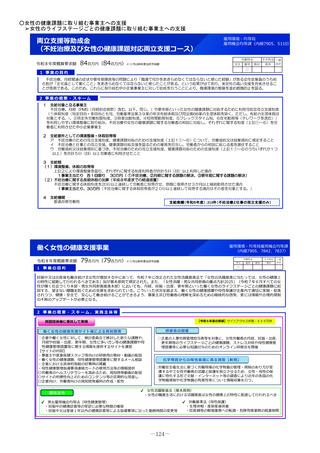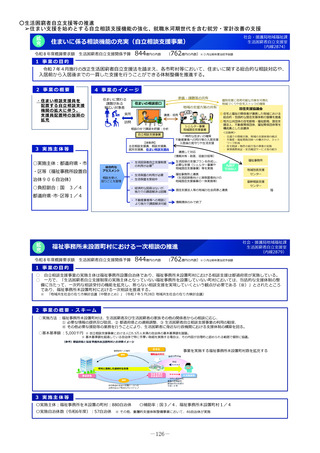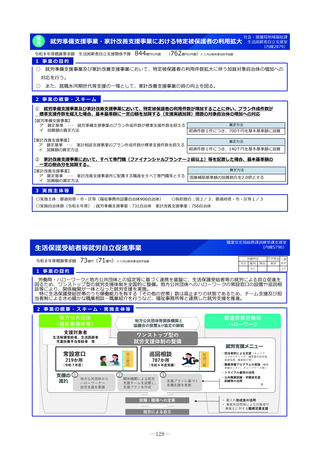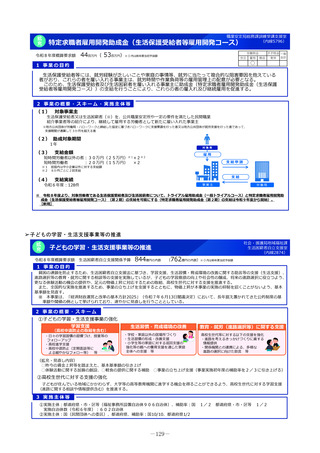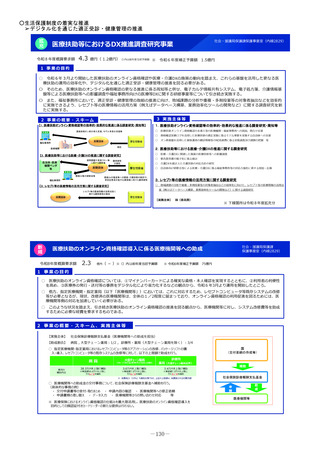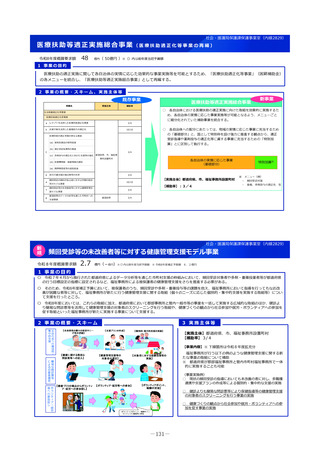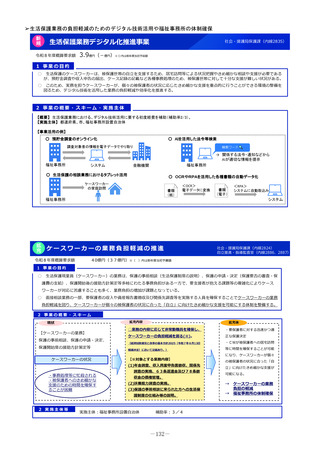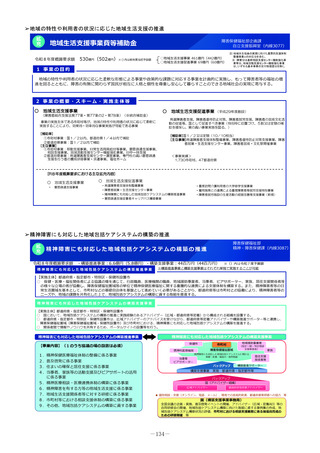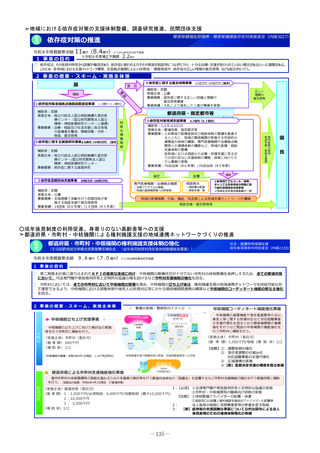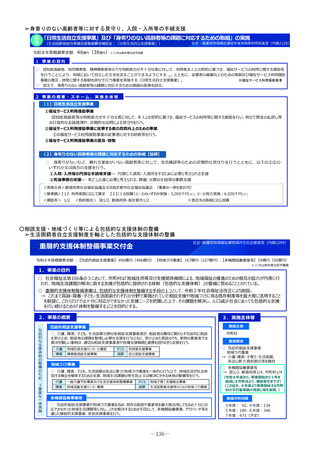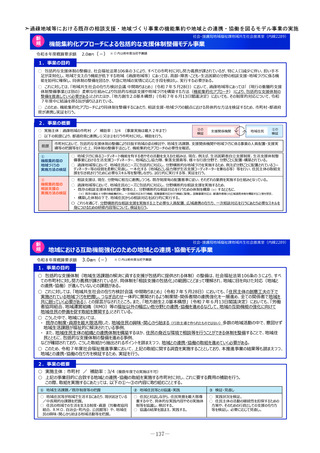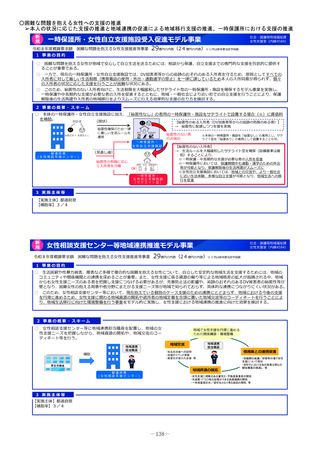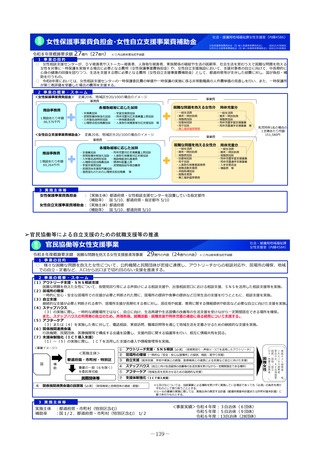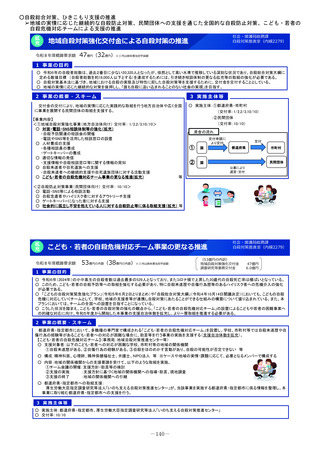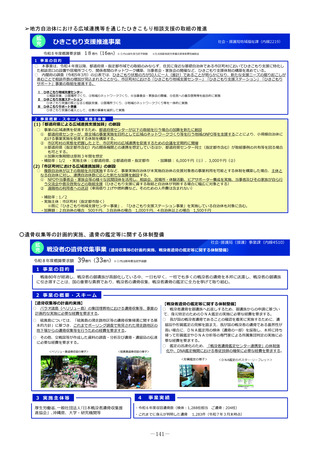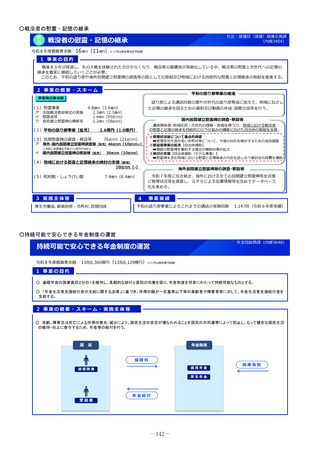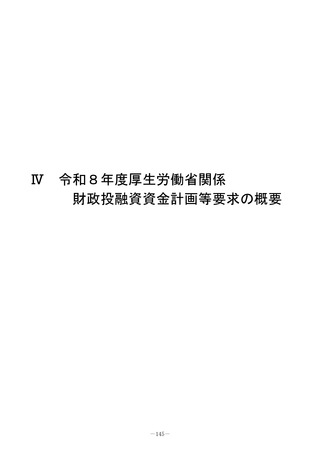令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (68 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/ |
| 出典情報 | 令和8年度厚生労働省予算概算要求の主要事項(8/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
➢薬剤師等を活用した市販薬の濫用防止対策の推進
医薬局医薬安全対策課(内線2757、2752)
薬剤師等を活用したOTC濫用防止対策事業
令和8年度概算要求額
22 百万円(-)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
近年、若年者を中心としてオーバードーズが社会問題化していることを踏まえ、「医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律」改正により、濫用のおそれのある医薬品の販売方法の見直しを行う
こととしている。濫用対策においては、販売規制だけでなく、啓発活動や支援の充実といった側面も重要であり、
ゲートキーパーとしての薬剤師等を通じた医薬品の濫用のリスクを含めた啓発や、相談対応の充実など濫用防
止対策に取り組む。
2 事業の概要・スキーム
(1)販売時等における啓発活動
・「ゲートキーパーとしての薬剤師等の対応マニュアル」※等を活用
した対応事例の収集、周知
(2)若年層を対象とした啓発活動
・学校薬剤師による学校等における啓発事例の収集、周知
(3)薬剤師等の対応力向上
・医薬品販売に携わる薬剤師・登録販売者、及び学校薬剤師を対
象とした研修の実施
※令和5年度補正予算「学校薬剤師・地区薬剤師会を活用したOTC濫用防止対策事業」で作成。
出典:全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査(2022年) (国立精神・神経医療研究センター)
(令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(医薬品医療機器等レギュラトリ-サイエンス政策研究事業))
3 実施主体等
民間事業者(委託)
➢後発医薬品の信頼確保のための体制・取組の強化
後発医薬品の品質確保のための査察水準向上事業
令和8年度概算要求額
医薬局監視指導・麻薬対策課(内線2770)
13百万円(-)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
昨今、後発医薬品メーカーで品質に関わる行政処分事案が続いており、その原因として製造開始時の製剤開発や工業化検討の
不十分さ(いわゆる「上流問題」)が指摘されている。
令和7年度の薬機法改正にあわせ、新規後発品※の初回承認時のGMP調査主体が、都道府県からPMDAに移管され、PMDA
が持つ「上流問題」への専門的知見を踏まえた調査を行うこととされた。(※後発品として初めて承認を受ける成分を含有する品目)
一方で、初回承認時以降は、法施行後も引き続き都道府県がGMP調査を行うことから、PMDAの初回調査で検出された「上流
問題」のリスクに対し、都道府県が引き継ぐ定期適合性調査等において適切なフォローアップが必要である。
本事業では、新規後発品のGMP調査において、①都道府県の調査水準の向上を図るとともに、②PMDAと都道府県間の協
力体制を強化することにより、もって新規後発品の品質を確保し、安定的な医薬品供給に資することを目的とする。
2 事業の概要・スキーム
<事業の内容>(令和8年度概算要求:人件費(1人)、事業費(旅費))
都道府県の新規後発品のGMP調査にPMDA職員が同行し、
1)実際の調査を通じてPMDAから都道府県に、「上流問題」に起因する問題
点の発見のための高度な専門的知見を共有するとともに、
2)発見された問題点の分析・国内の調査当局の間での共有を図る。
<同行対象となる調査>
現行制度下(調査主体移管前)
都道府県が行う、新規後発品の初回承認時GMP調査にPMDA職員が同行
調査主体移管後
PMDAによる初回承認時の調査で、リスク要因が検出された製造所について、
その後に都道府県が行う定期適合性調査等にPMDA職員が同行
-66-
<事業スキーム>
厚生労働省
各都道府県へ
の査察結果等
の共有
補助
PMDA
(調査に同行)
技術的助言
査察
後発医薬品
製造所
地方自治体
(調査主体)
3 実施主体等
(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)