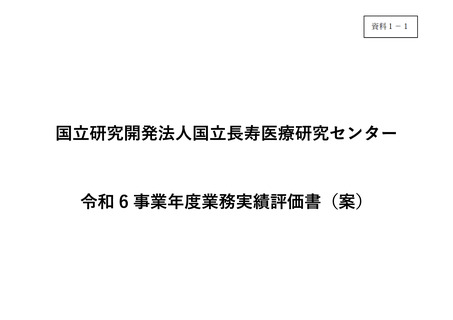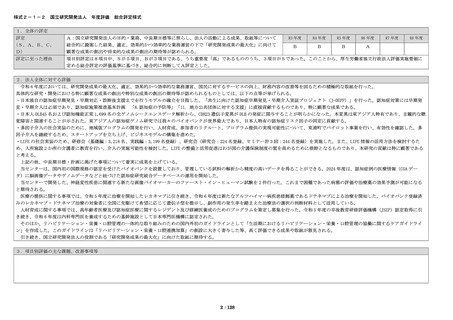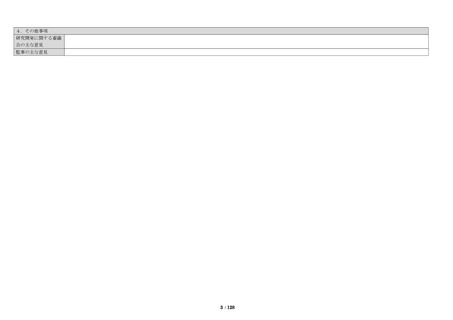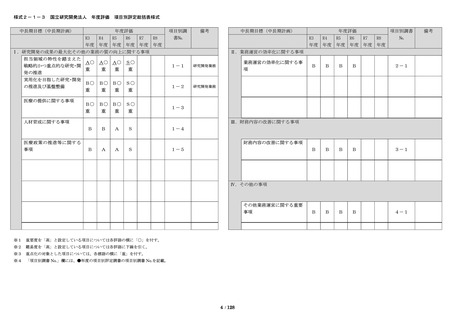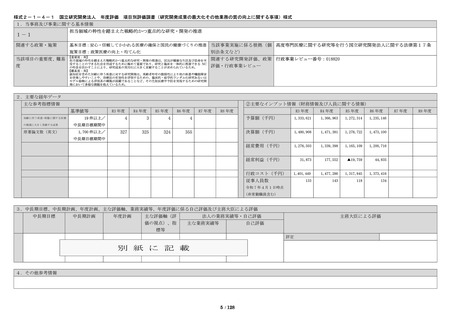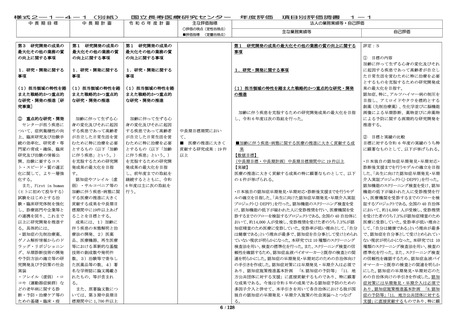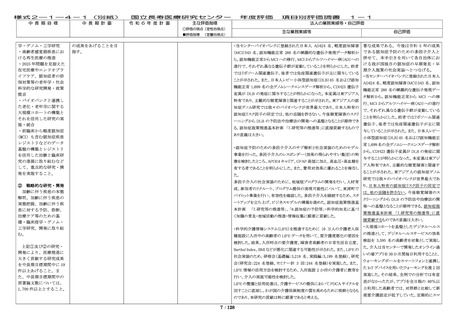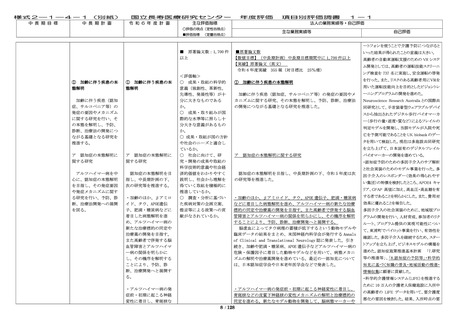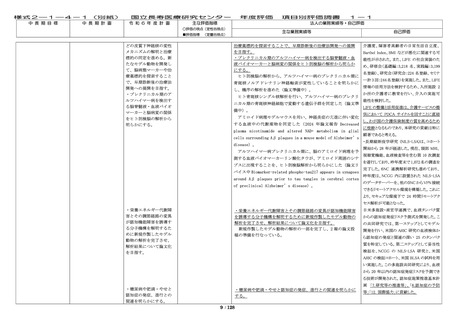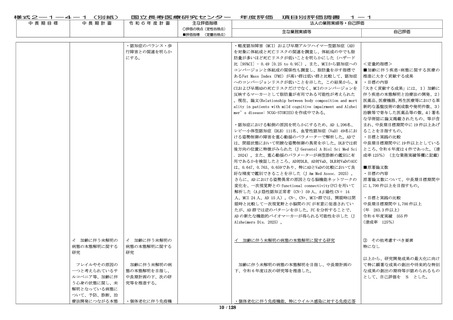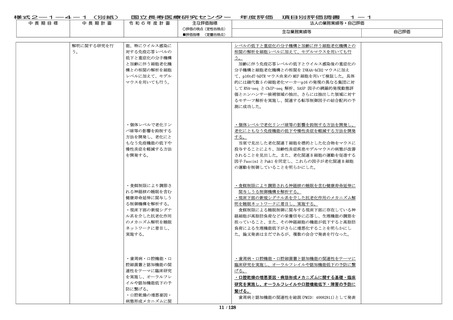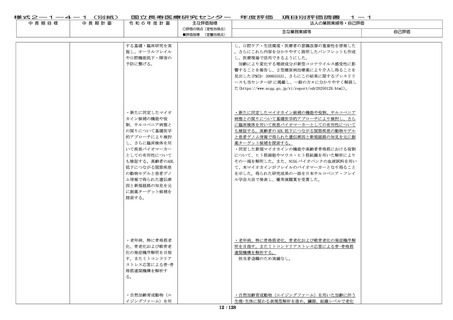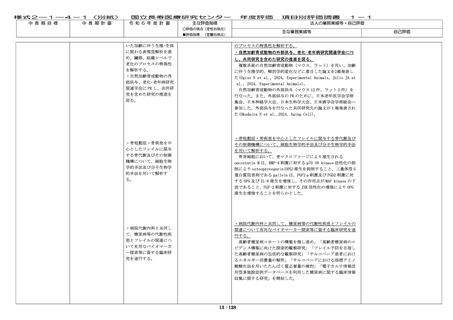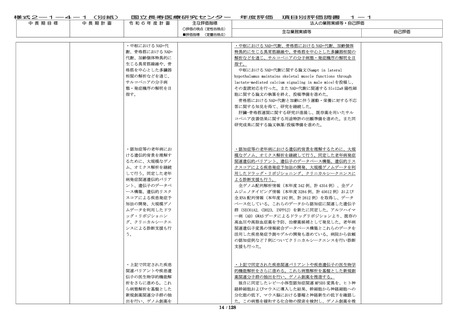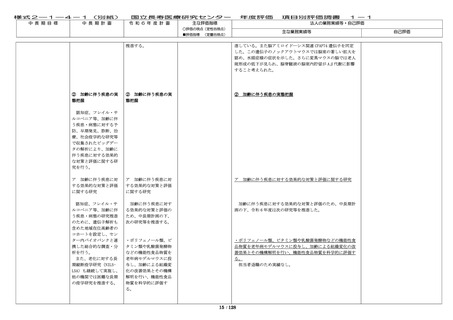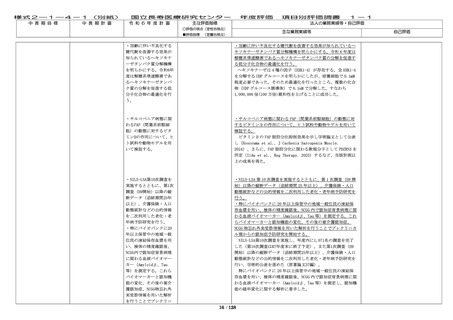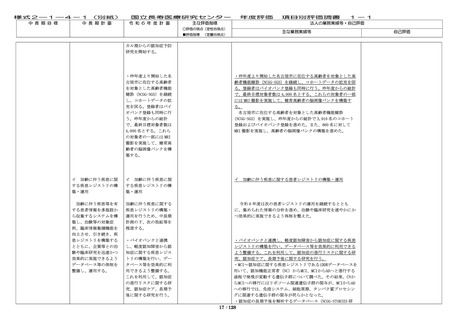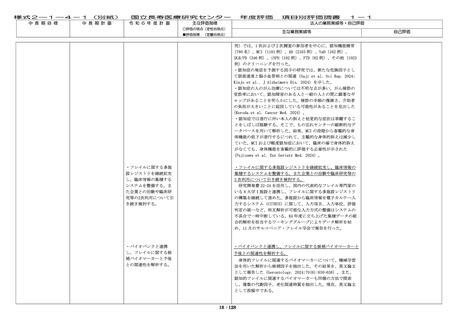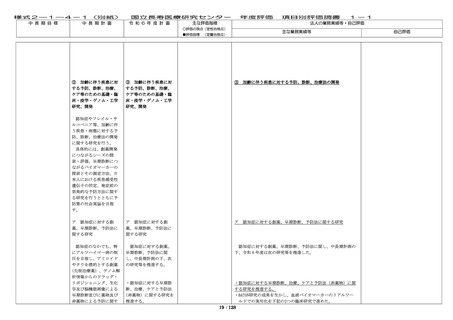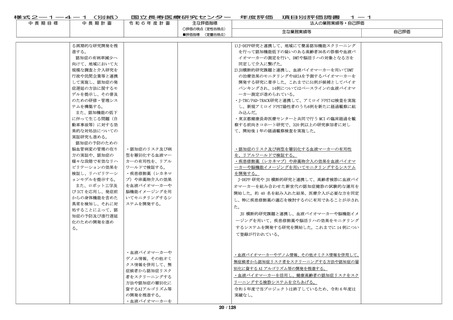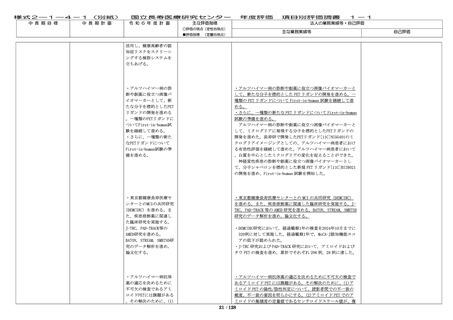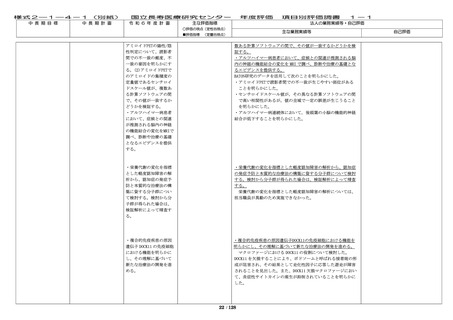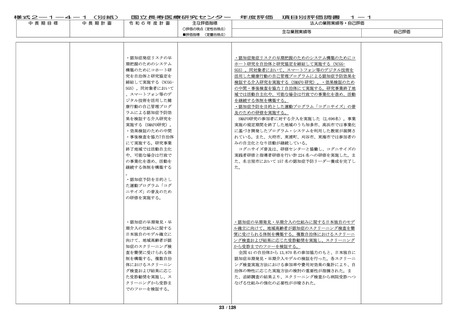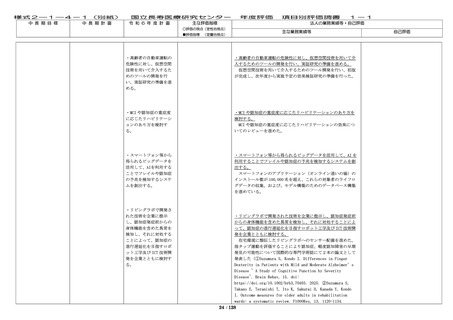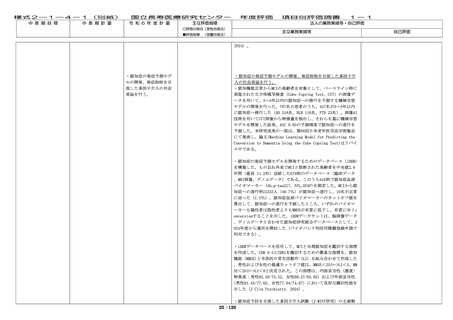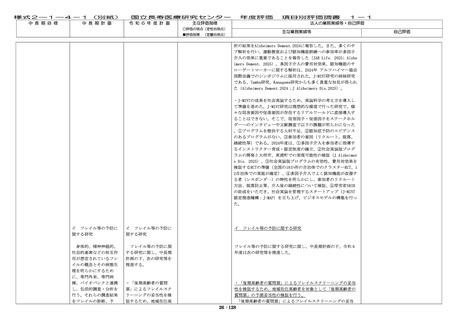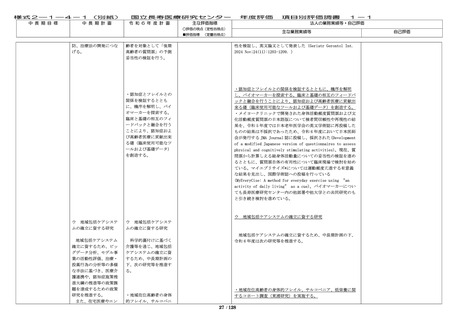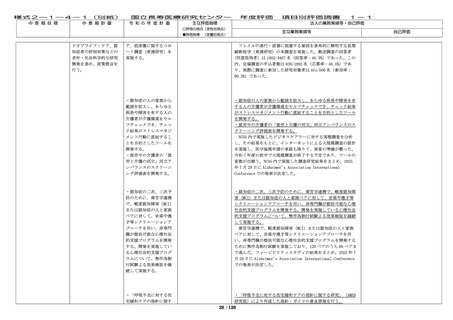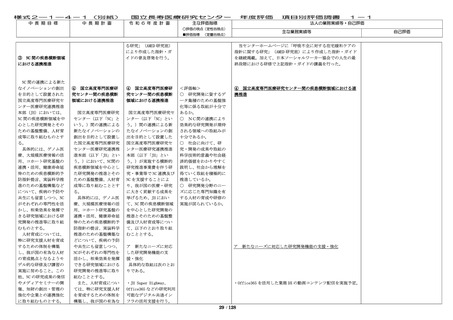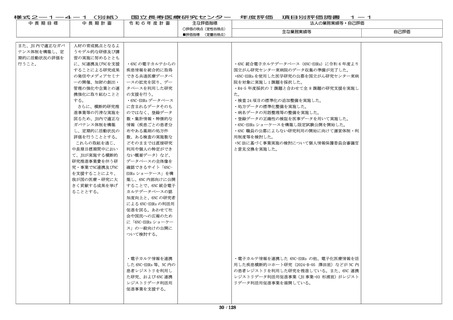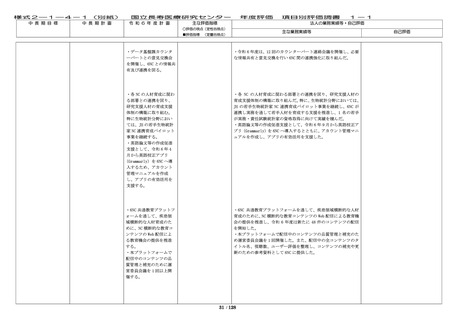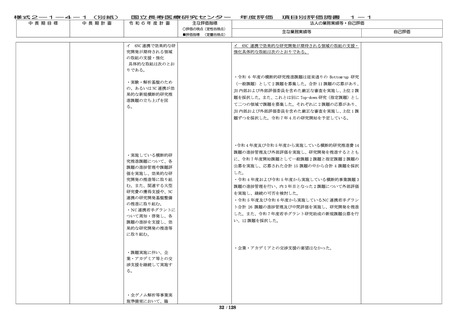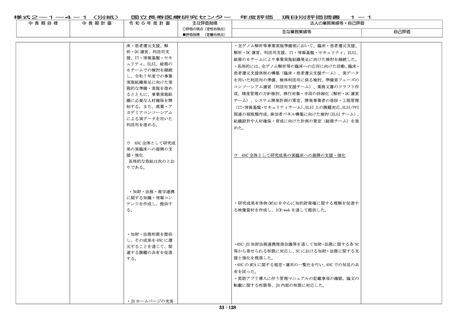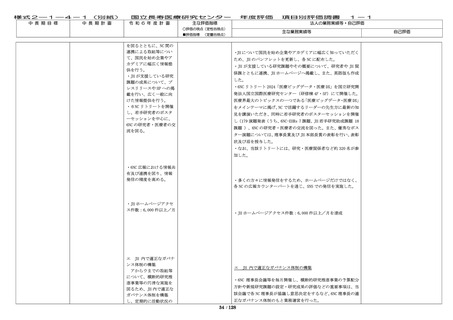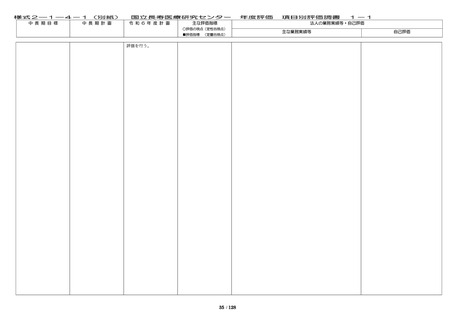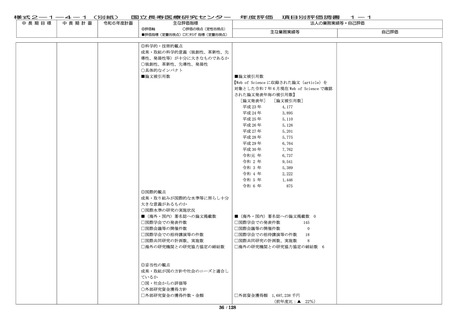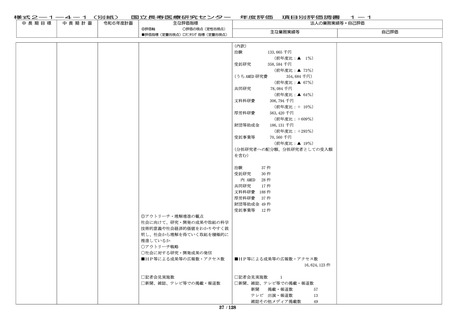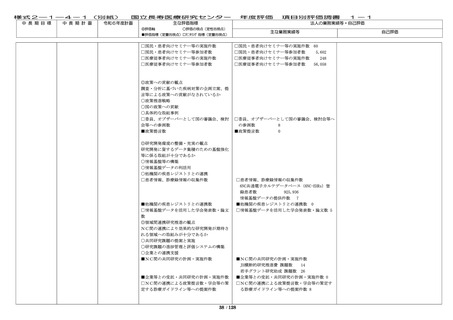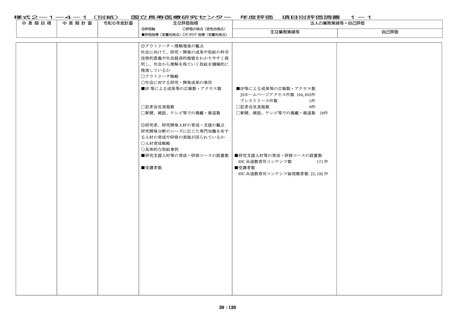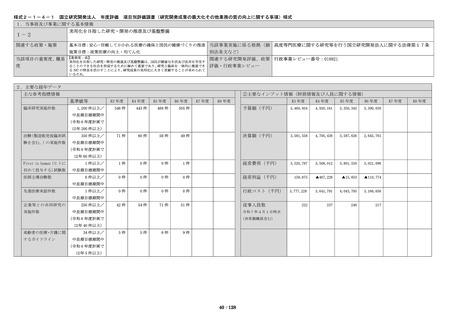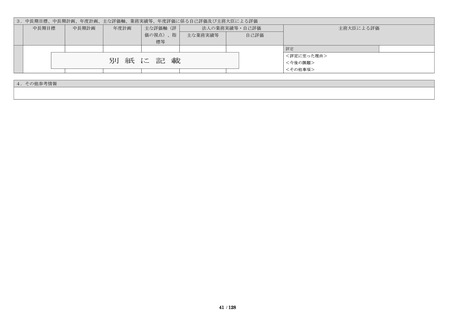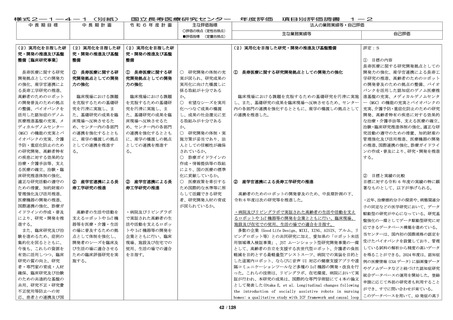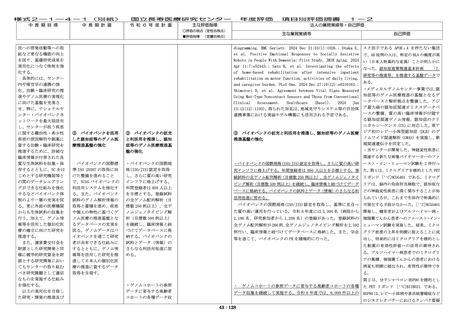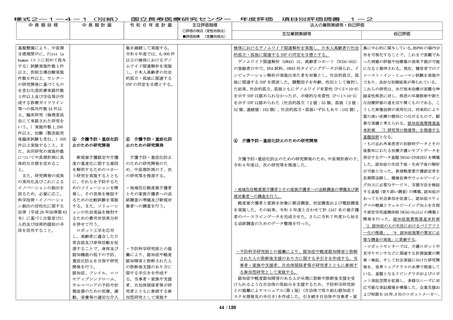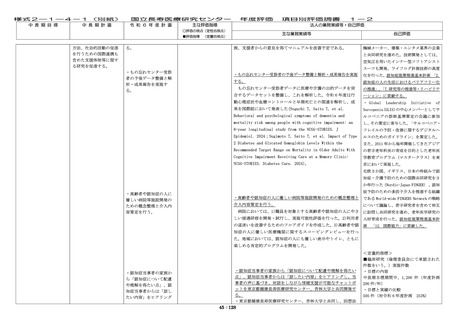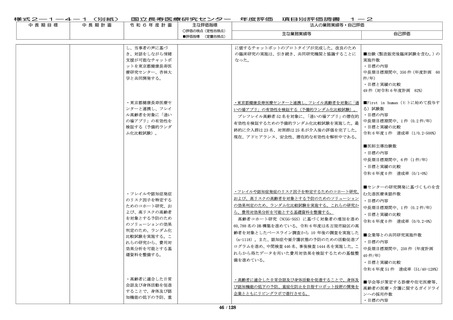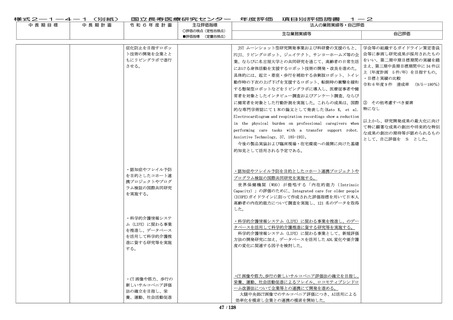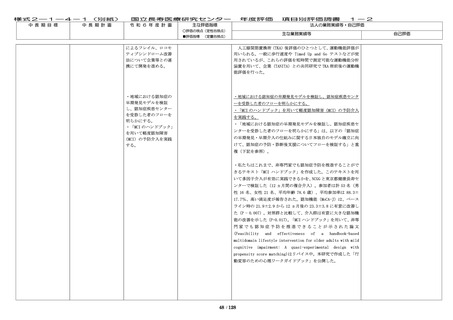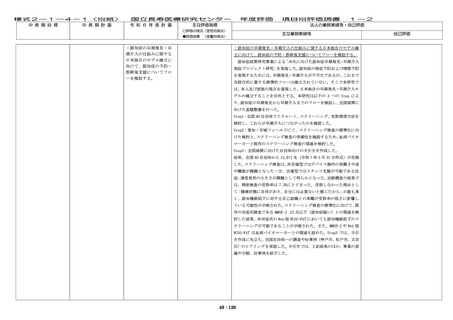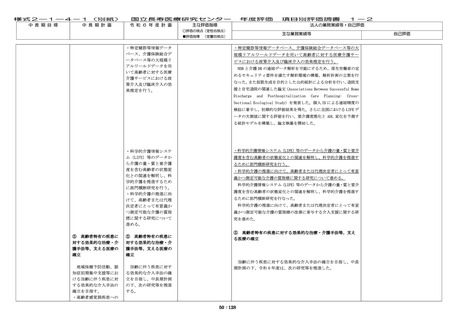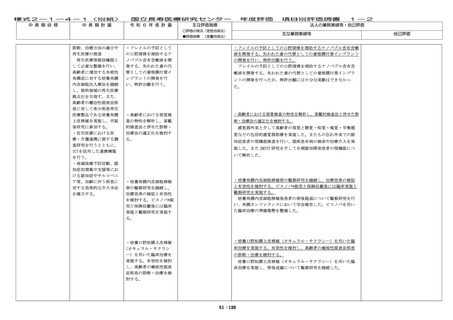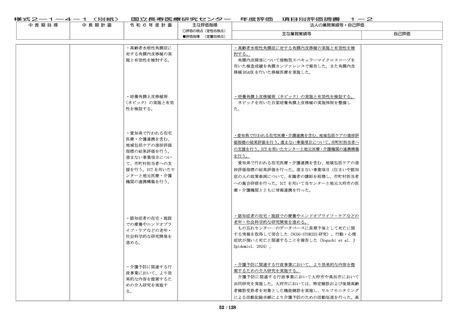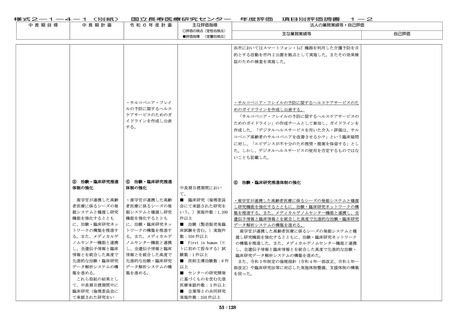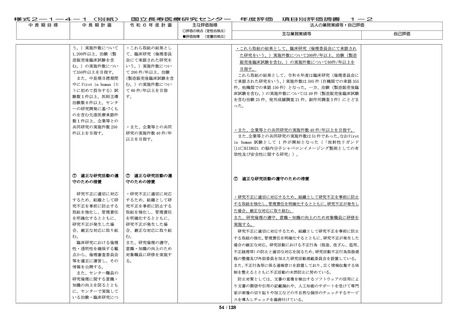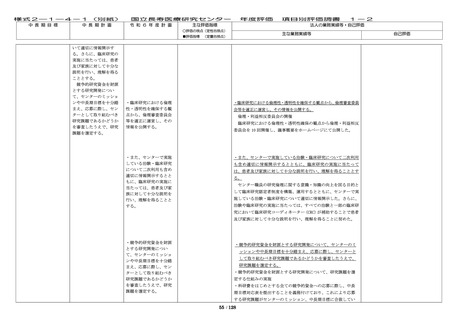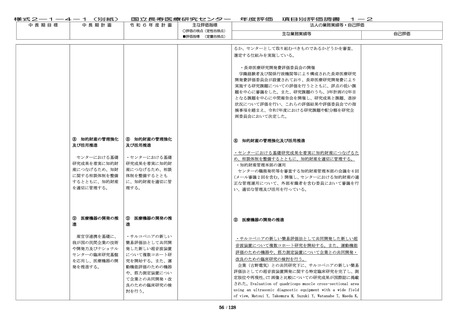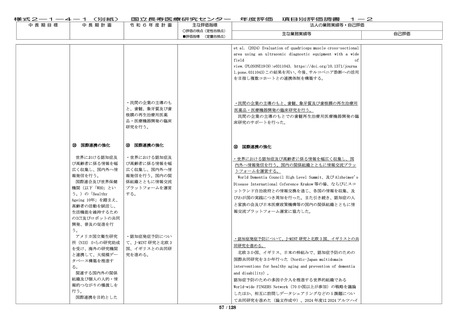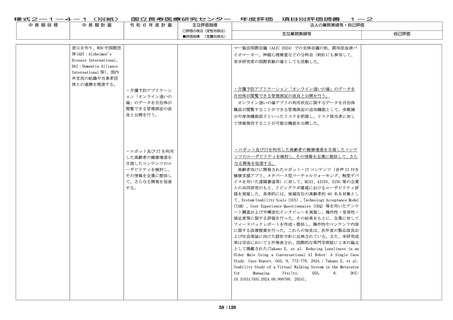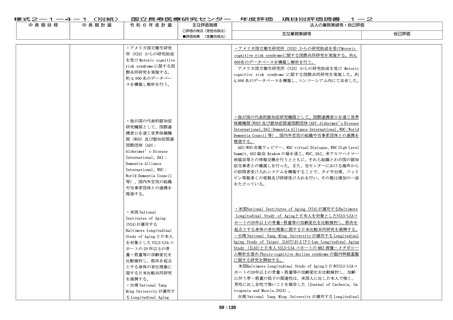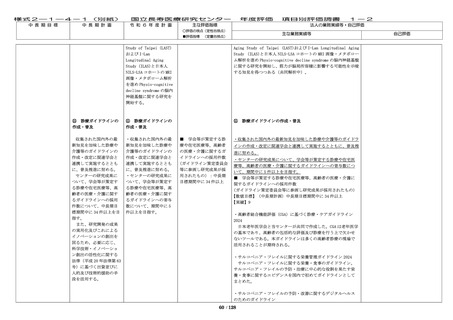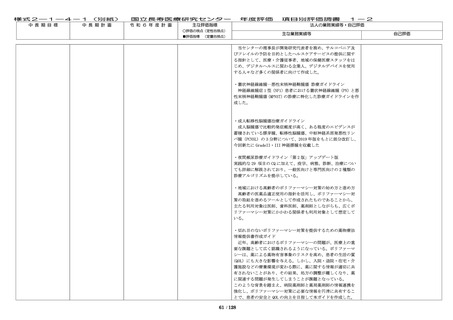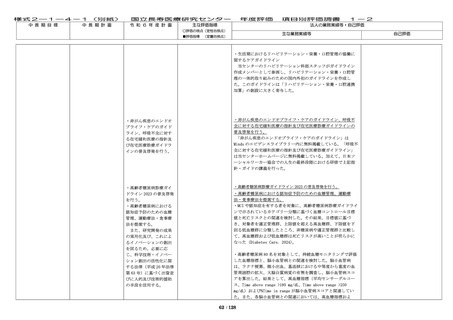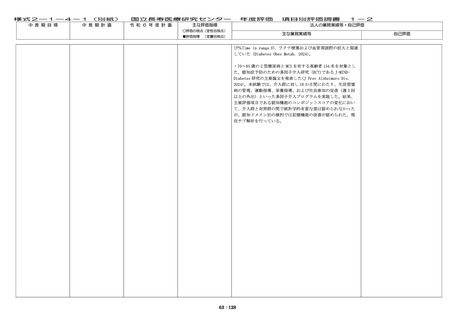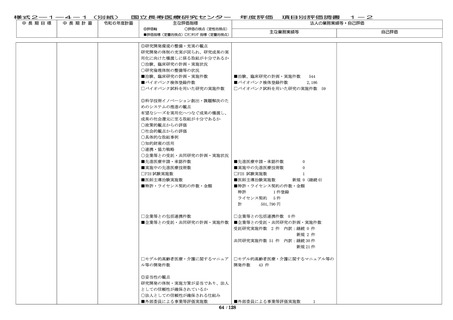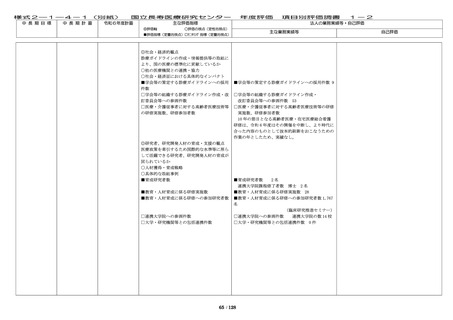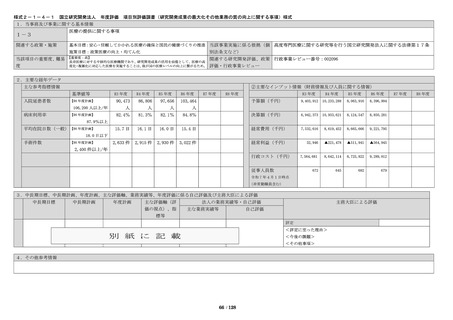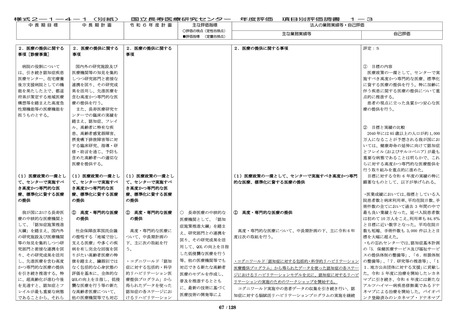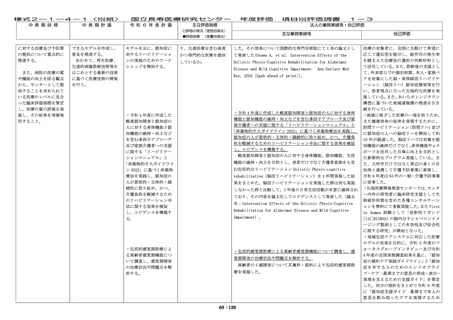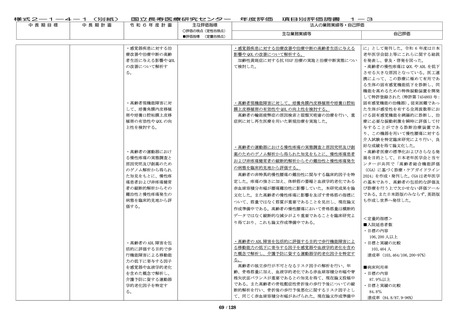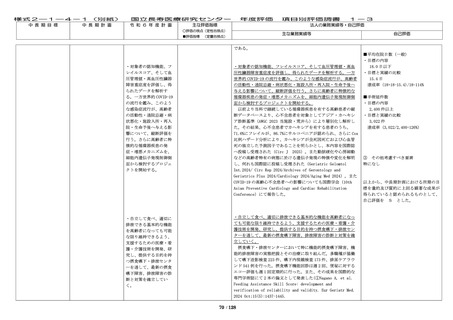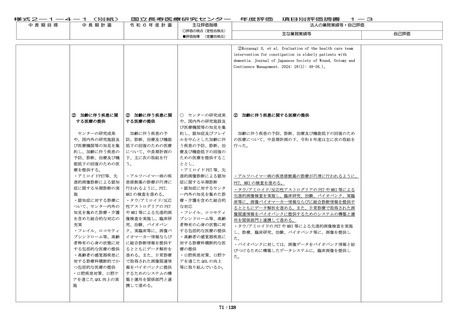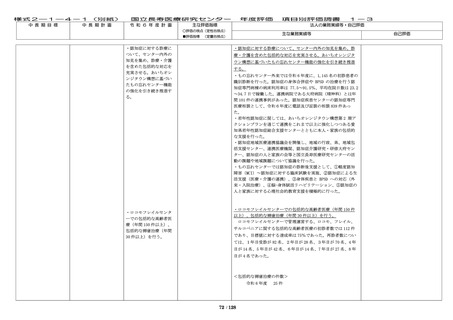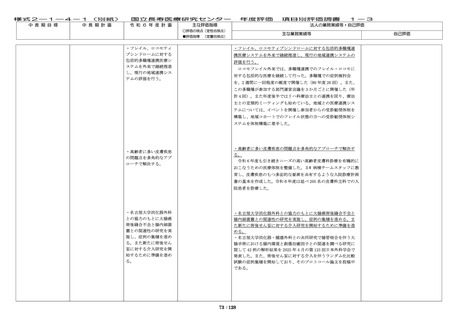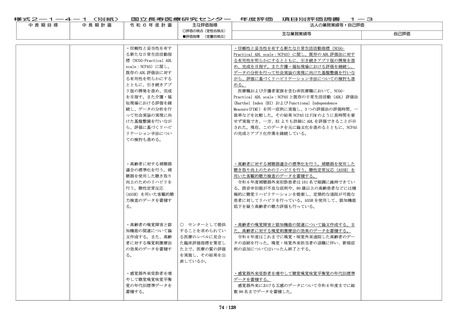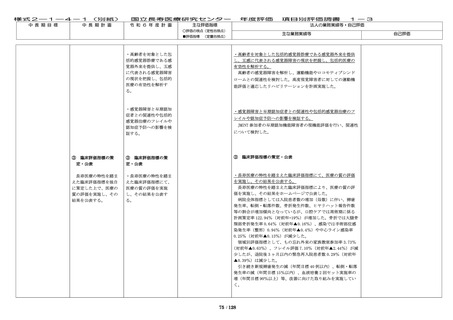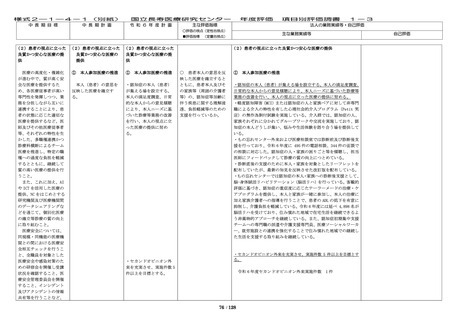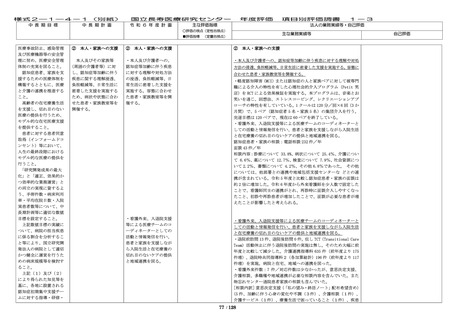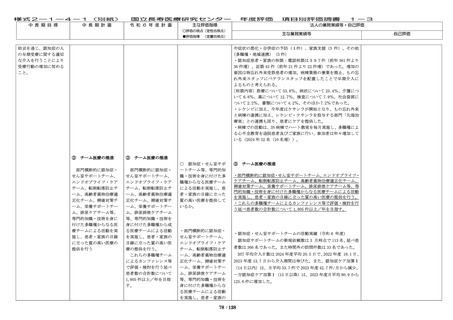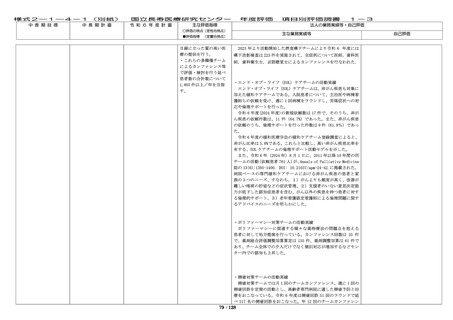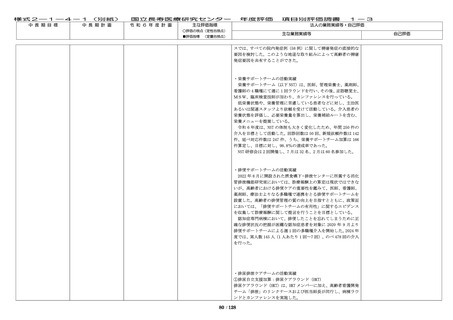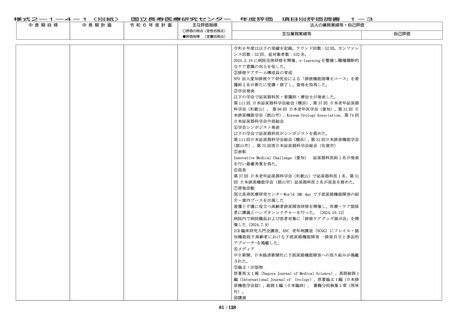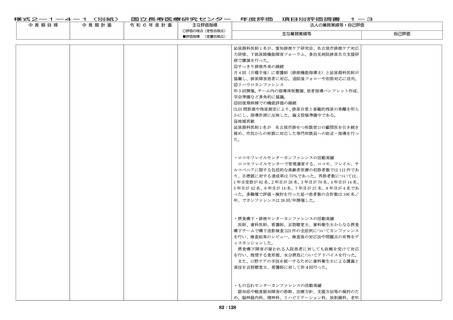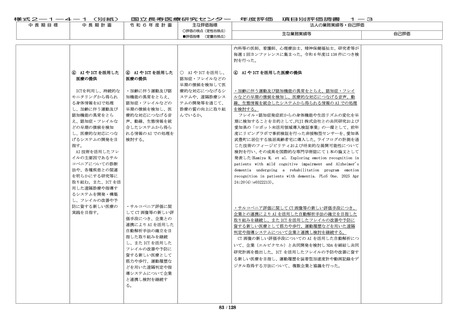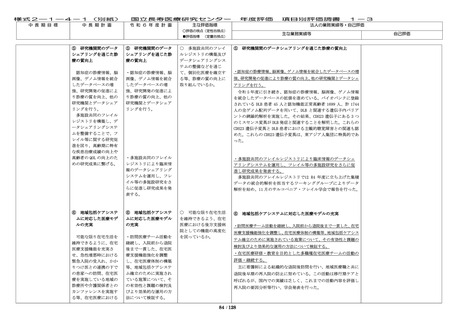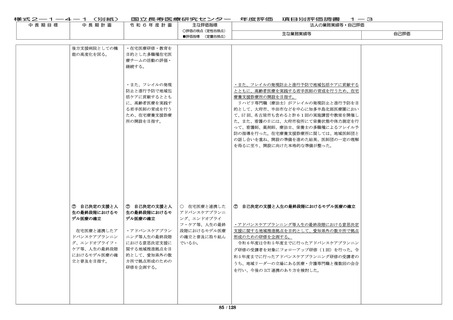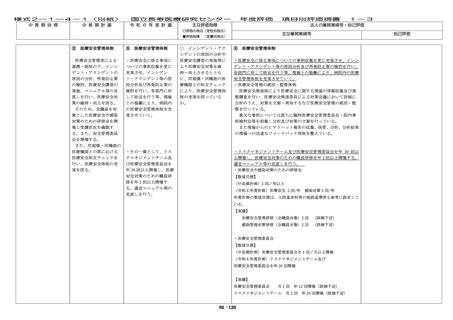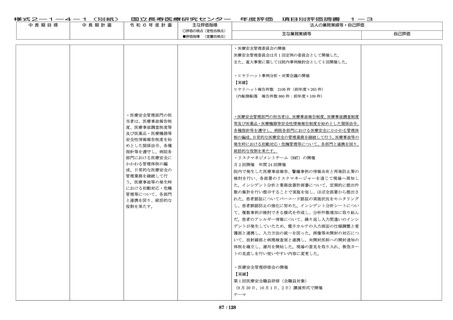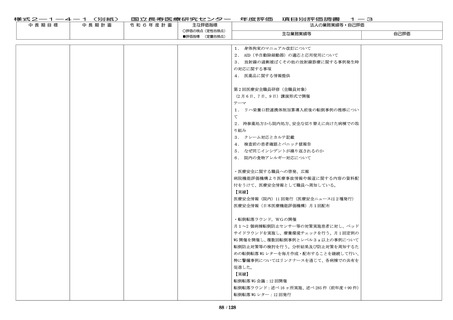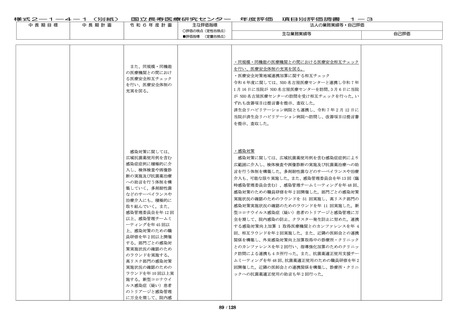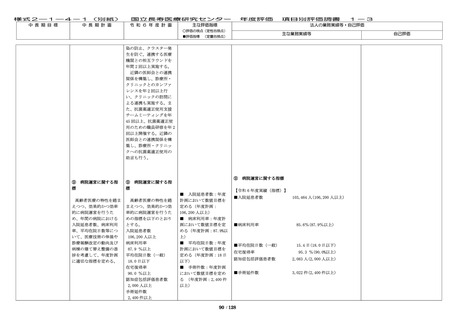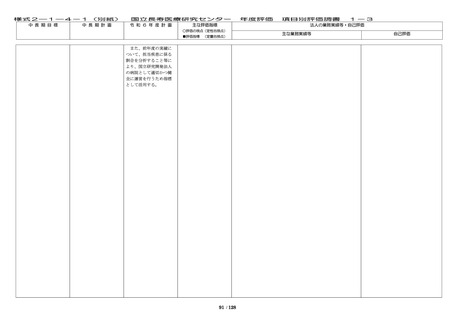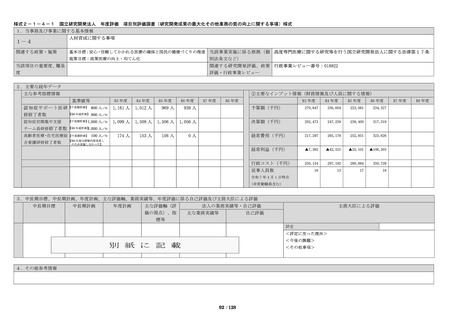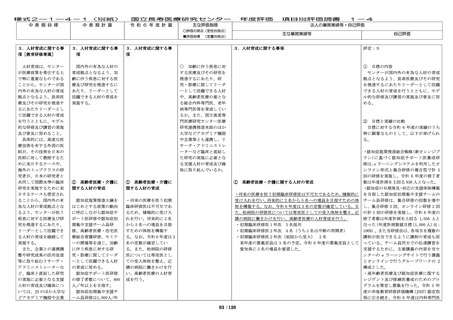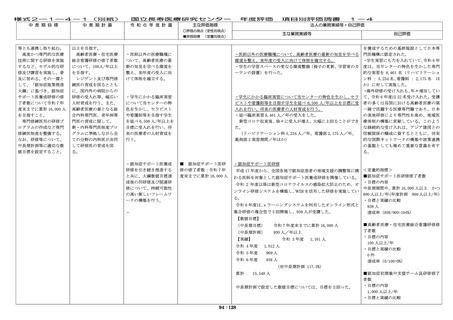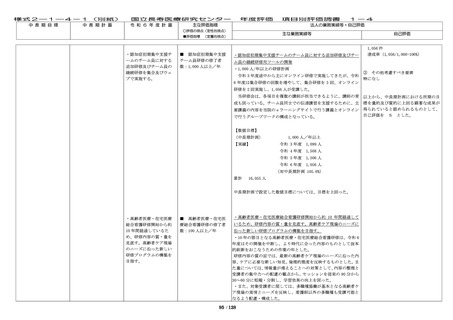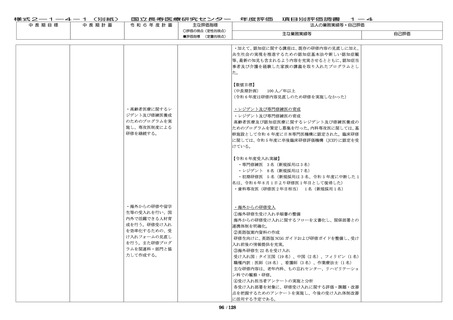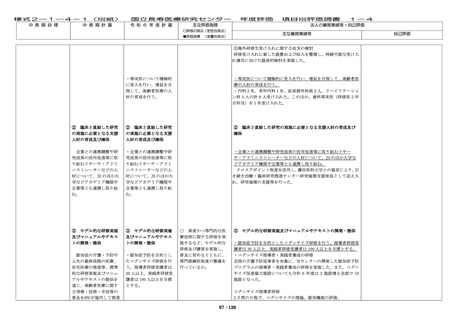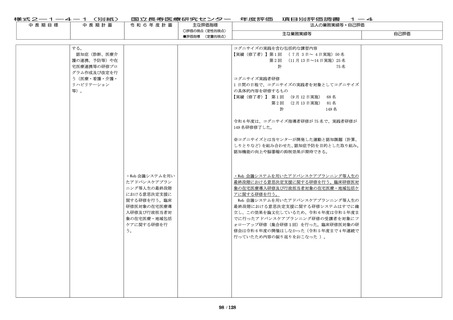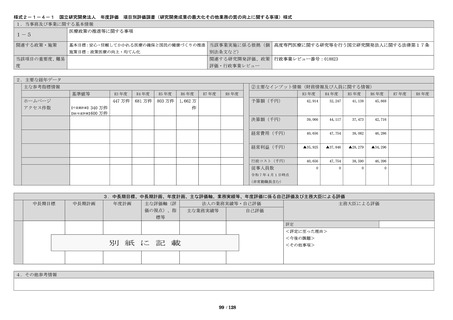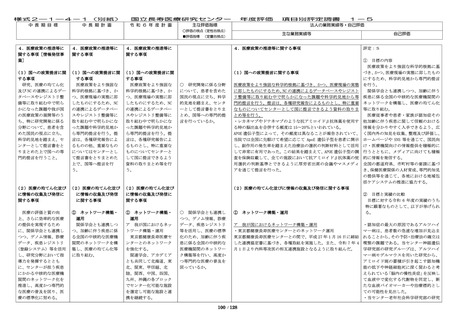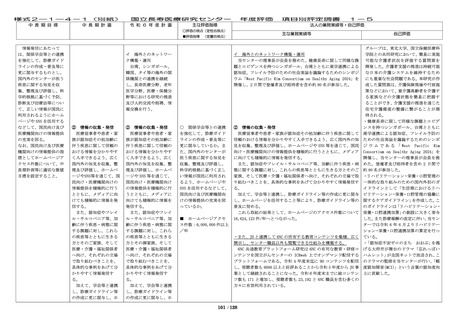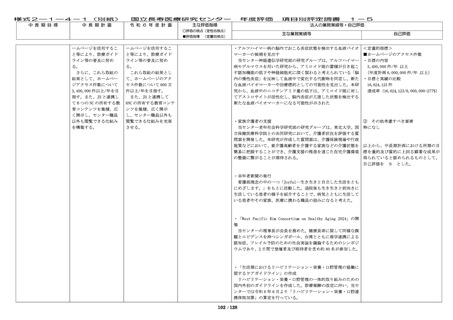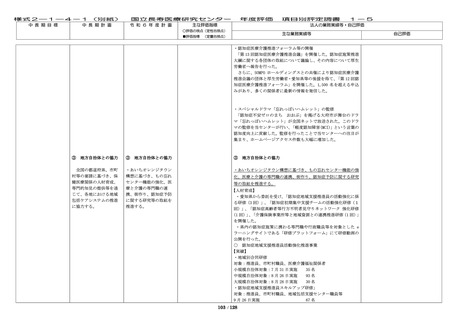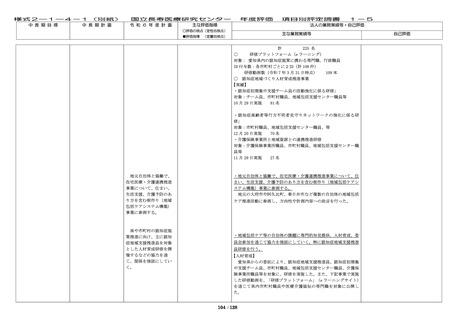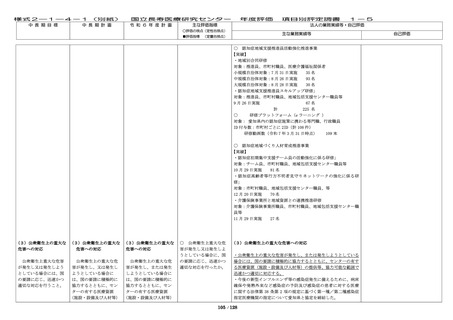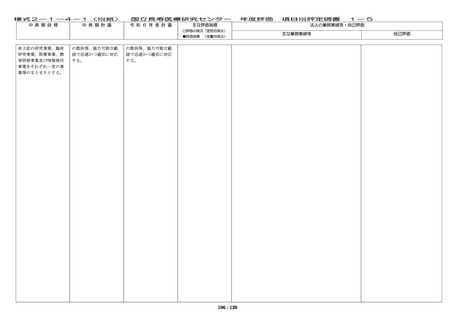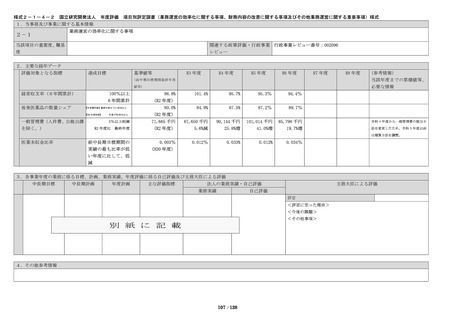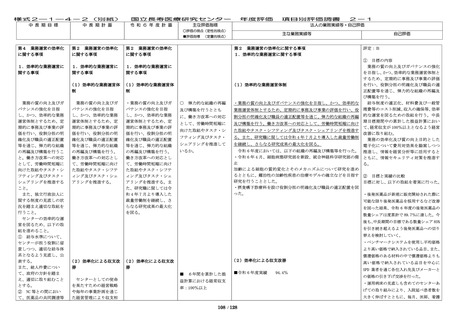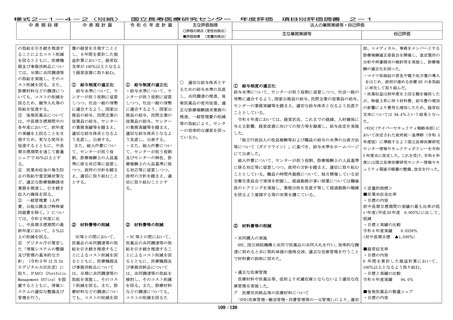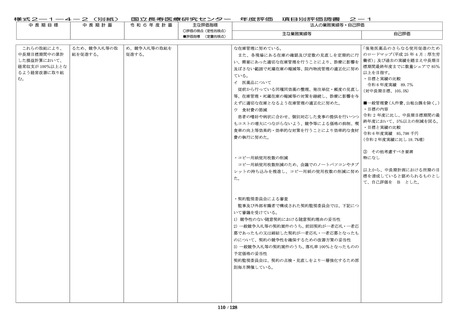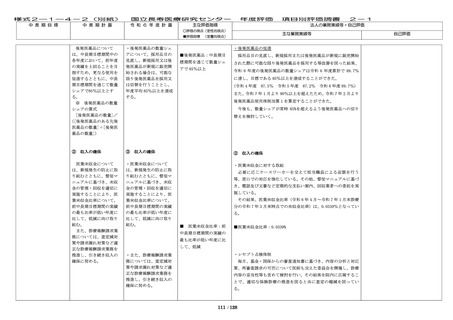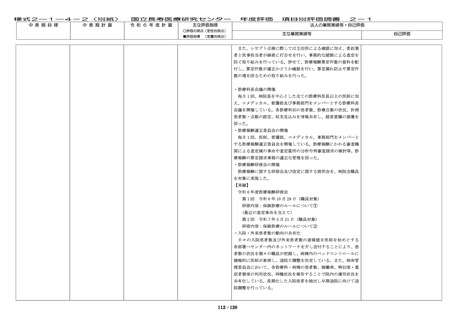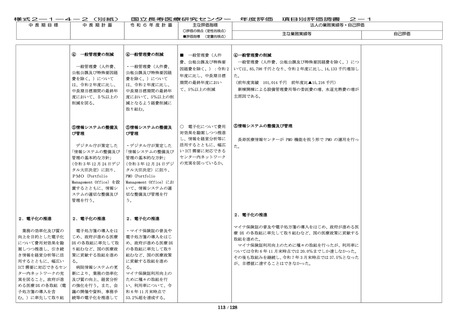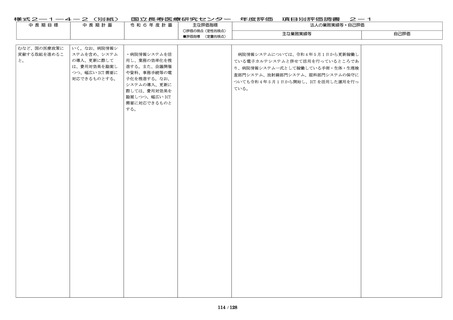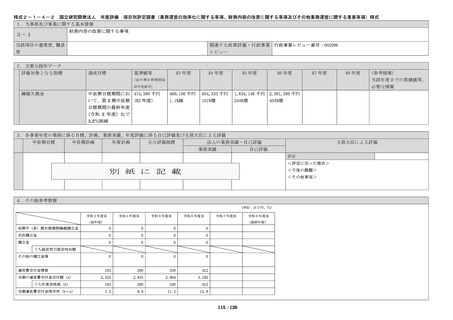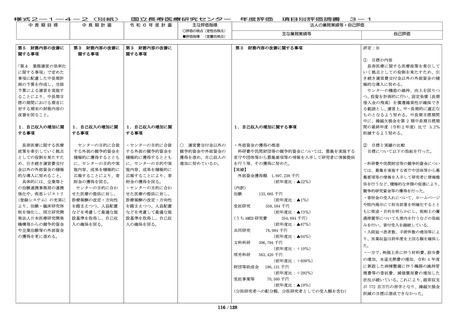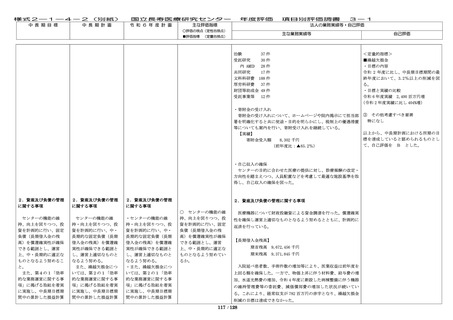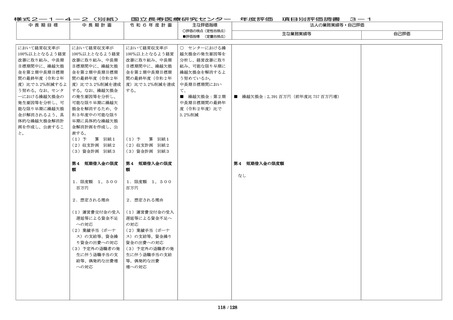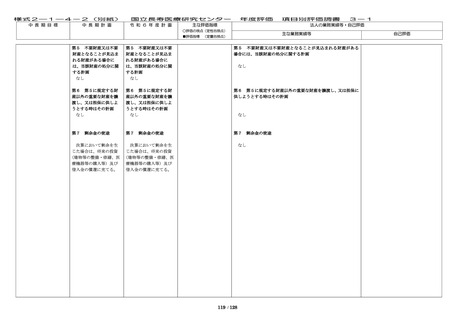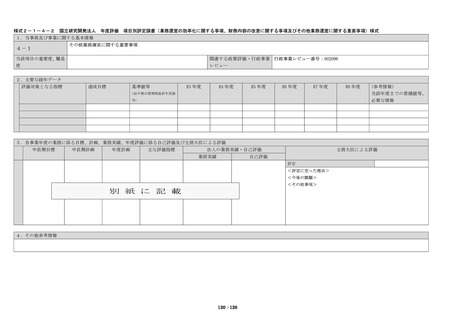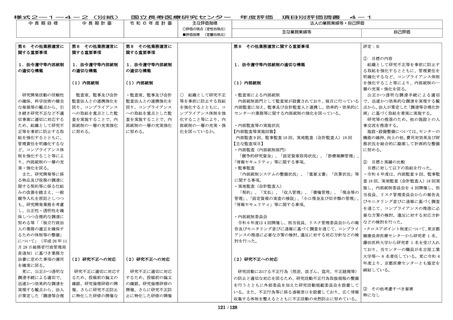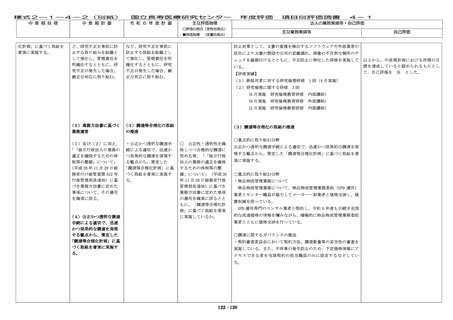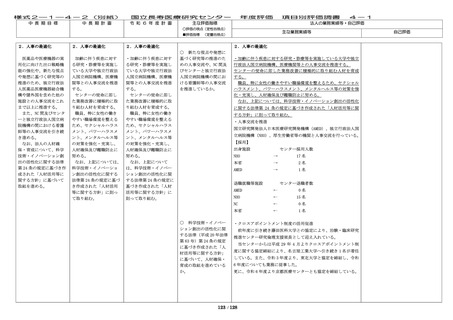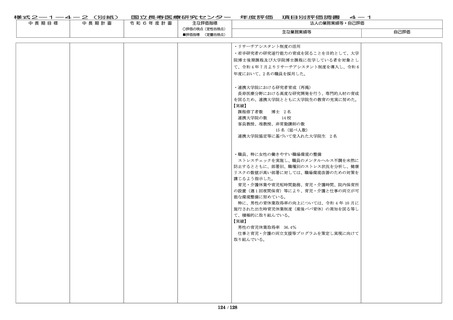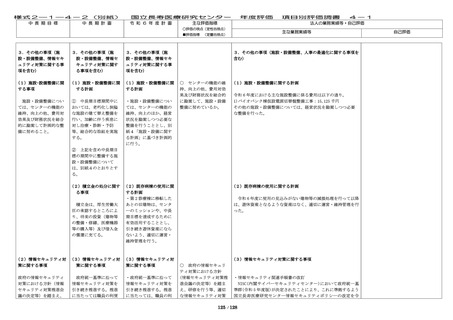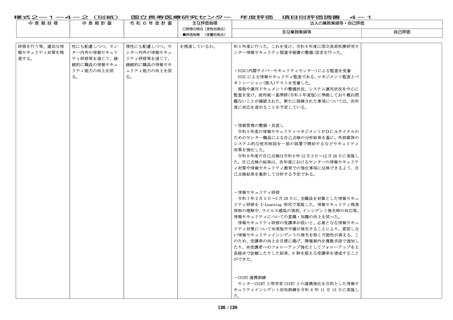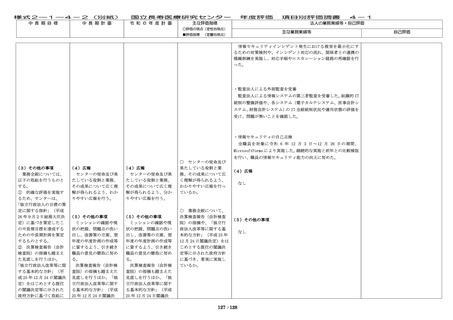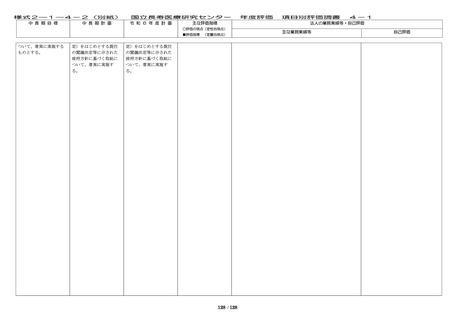資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (77 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |
| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中 長 期 目 標
中 長 期 計 画
国立長寿医療研究センター
令 和 6 年 度 計 画
主な評価指標
年度評価
○評価の視点(定性的視点)
■評価指標
医療の高度化・複雑化
が進む中で、質が高く安
全な医療を提供するた
め、各医療従事者が高い
専門性を発揮しつつ、業
務を分担しながら互いに
連携することにより、患
者の状態に応じた適切な
医療を提供するなど、医
師及びその他医療従事者
等、それぞれの特性を生
かした、多職種連携かつ
診療科横断によるチーム
医療を推進し、特定の職
種への過度な負担を軽減
するとともに、継続して
質の高い医療の提供を行
うこと。
また、これに加え、AI
や ICT を活用した医療の
提供、NC をはじめとする
研究機関及び医療機関間
のデータシェアリングな
どを通じて、個別化医療
の確立等診療の質の向上
に取り組むこと。
医療安全については、
同規模・同機能の医療機
関との間における医療安
全相互チェックを行うこ
と、全職員を対象とした
医療安全や感染対策のた
めの研修会を開催し受講
状況を確認すること、医
療安全管理委員会を開催
すること、インシデント
及びアクシデントの情報
共有等を行うことなど、
①
本人参加医療の推進
① 本人参加医療の推進
本人(患者)の意思を
反映した医療を確立す
る。
・認知症の本人(患者)
が集える場を設立する。
本人の満足度調査、日常
的な本人からの意見傾聴
により、本人ニーズに基
づいた診療等業務の改善
を行い、本人の視点に立
った医療の提供に努め
る。
・セカンドオピニオン外
来を充実させ、実施件数 5
件以上を目標とする。
主な業務実績等
(定量的視点)
(2)患者の視点に立った (2)患者の視点に立った (2)患者の視点に立った
良質かつ安心な医療の提
良質かつ安心な医療の
良質かつ安心な医療の提
供
提供
供
項目別評価調書
1-3
法人の業務実績等・自己評価
(2)患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供
○ 患者本人の意思を反
映した医療を確立すると
ともに、患者本人及びそ
の家族等(周囲の介護者
等)の、認知症等加齢に
伴う疾患に関する理解浸
透、負担軽減等のための
支援を行っているか。
①
本人参加医療の推進
・認知症の本人(患者)が集える場を設立する。本人の満足度調査、
日常的な本人からの意見傾聴により、本人ニーズに基づいた診療等
業務の改善を行い、本人の視点に立った医療の提供に努める。
・軽度認知障害(MCI)または認知症の人と家族ペアに対して非専門
職による介入の特性を有した心理社会的介入プログラム(Petit 笑
店)の無作為割付試験を実施している。介入群では、認知症の人、
家族それぞれに分かれてグループワークや交流を実施しており、認
知症の本人どうしが集い、悩みや生活体験を語り合う場を提供して
いる。
・もの忘れセンター外来および医療相談室では診断前及び診断後支
援を行っており、令和 6 年度に 495 件の電話相談、344 件の面談で
の相談に対応した。認知症の人・家族の困りごと等を傾聴し、担当
医師にフィードバックして診療の質の向上につとめている。
・診断直後の支援のために本人・家族を対象としたリーフレットを
配布していたが、最新の知見を反映させた改訂版を配布している。
・もの忘れセンターでは認知症の本人・家族への診断後支援として、
脳-身体賦活リハビリテーション(脳活リハ)を行っている。客観的
評価に基づき、認知症の重症度に応じたテーラーメードの治療・ケ
アプログラムを提供し、本人と家族が一緒に参加し、本人の治療に
加え家族介護者への指導を行うことで、患者の ADL の低下を有意に
抑制し、介護負担を軽減している。令和 6 年度には延べ 4,898 名が
脳活リハを受けており、住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよ
う非薬物的アプローチを継続している。また、認知症初期集中支援
チームへの専門職の派遣や介護支援専門員、医療ソーシャルワーカ
ー、就労施設との連携を強化することで住み慣れた地域での継続し
た生活を支援する取り組みを継続している。
・セカンドオピニオン外来を充実させ、実施件数 5 件以上を目標とす
る。
令和 6 年度セカンドオピニオン外来実施件数 1 件
76 / 128
自己評価