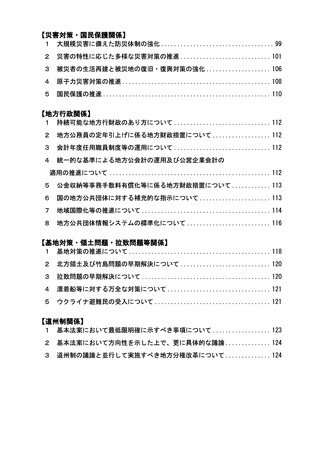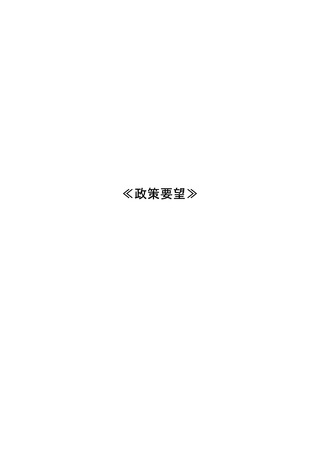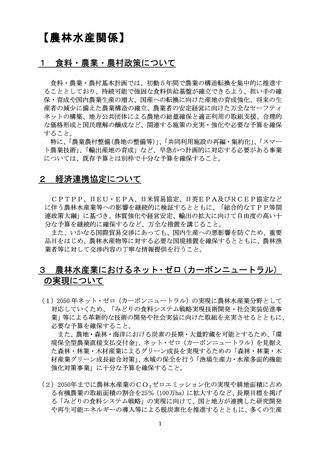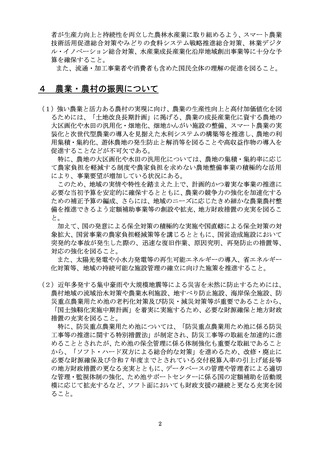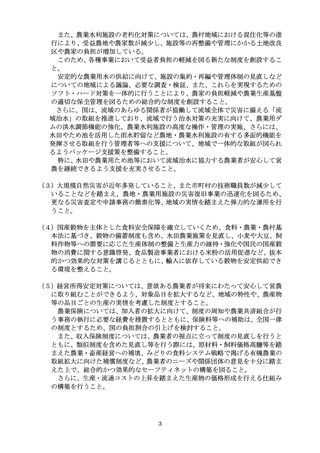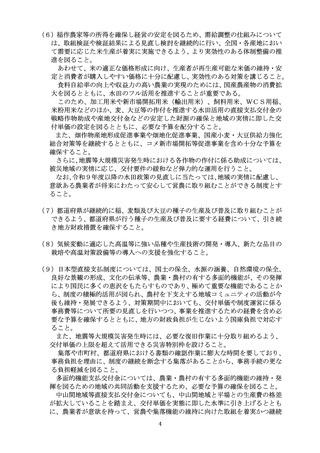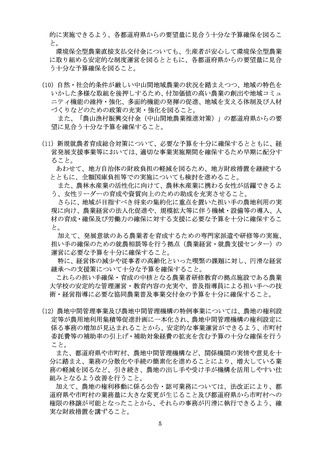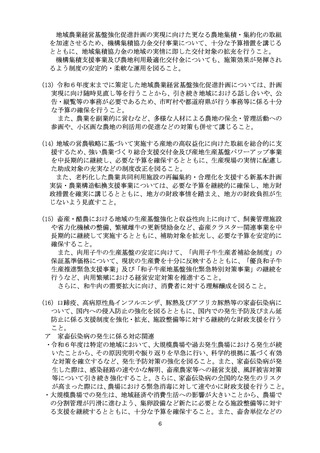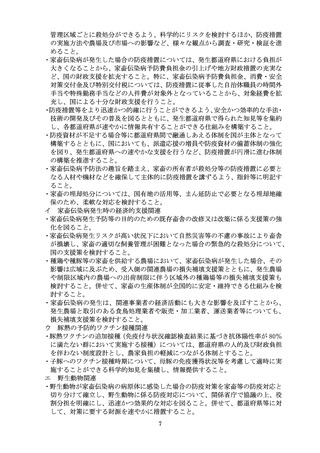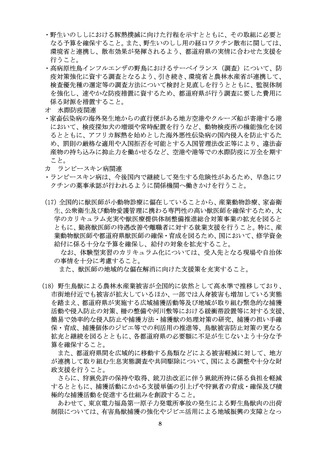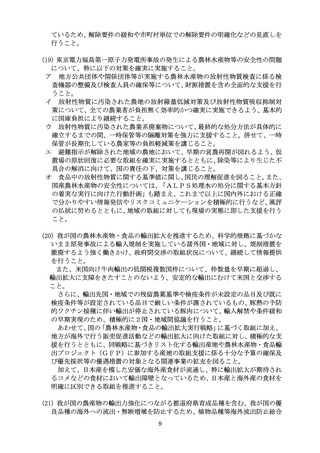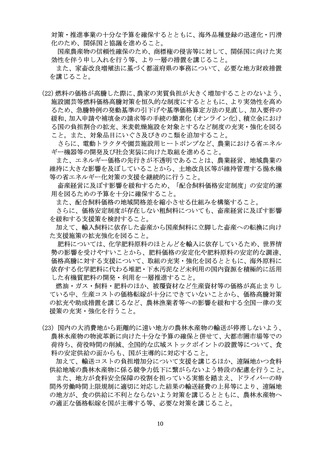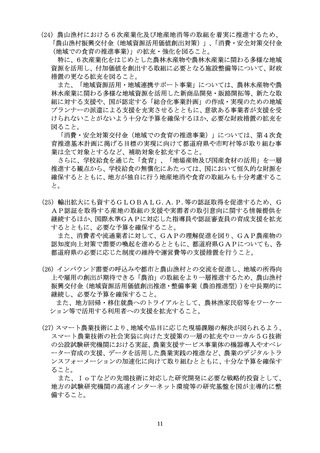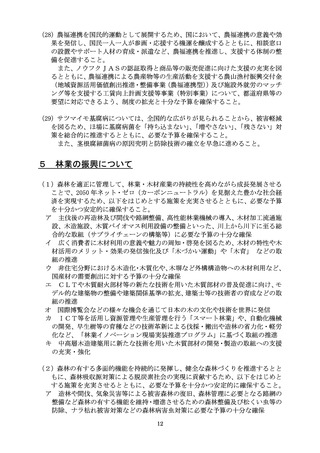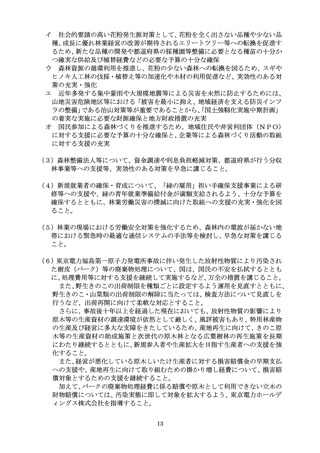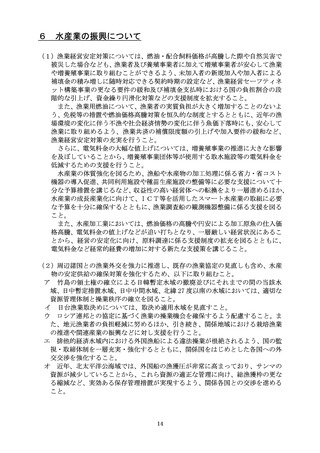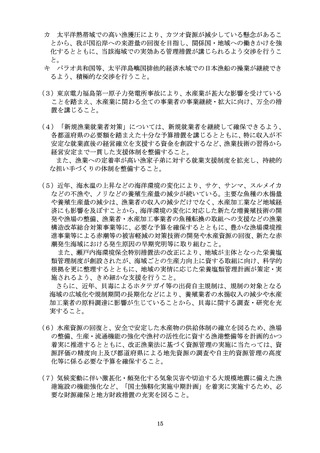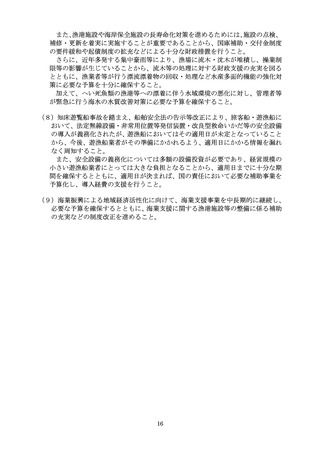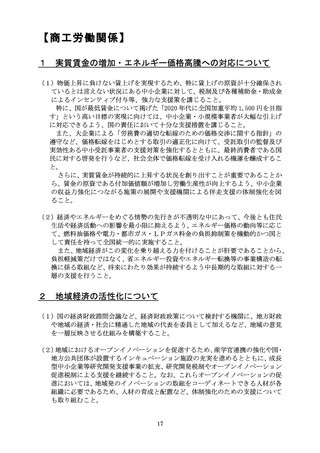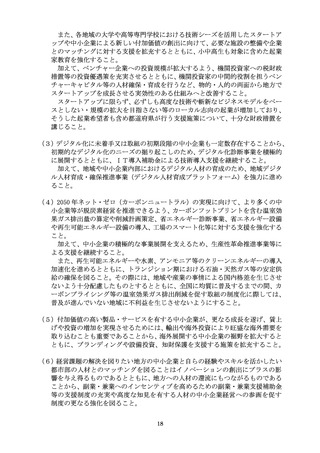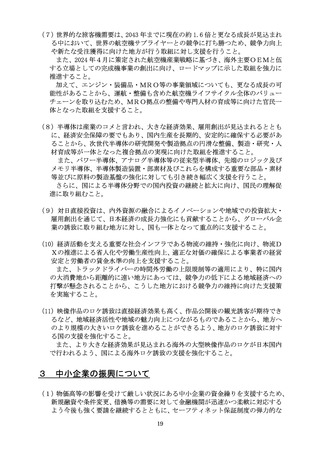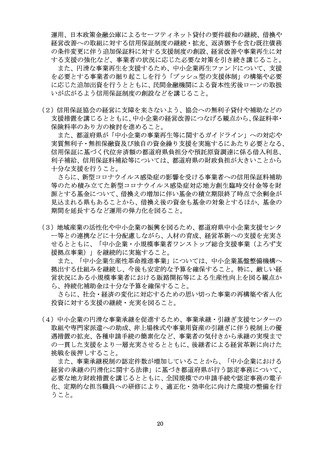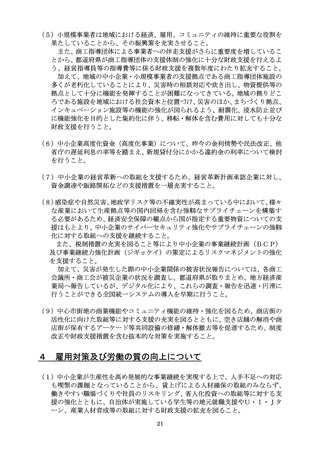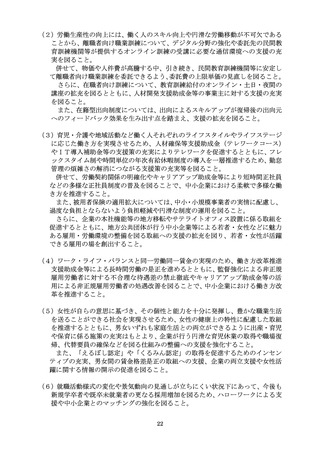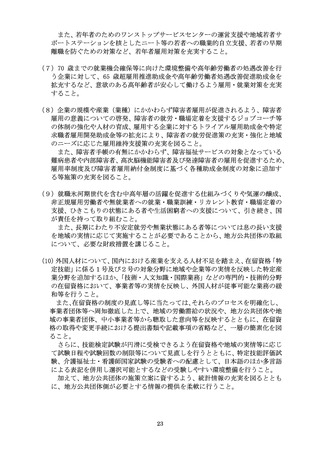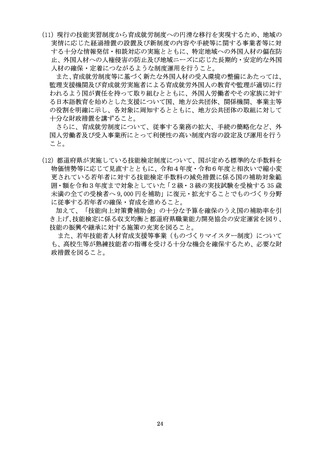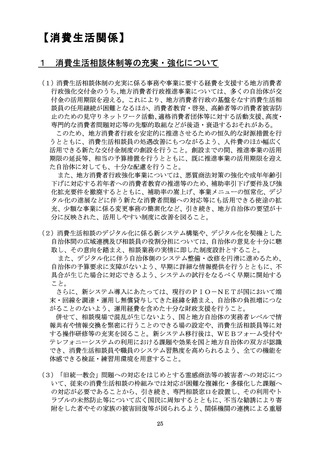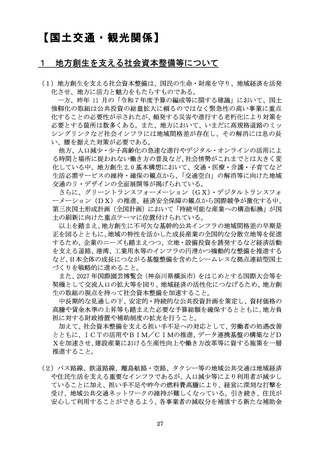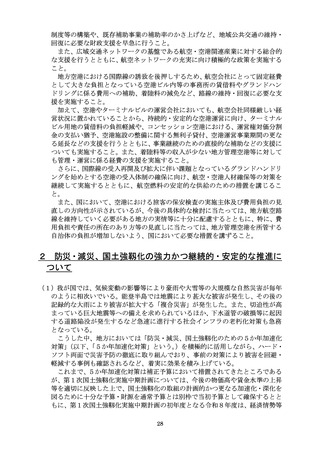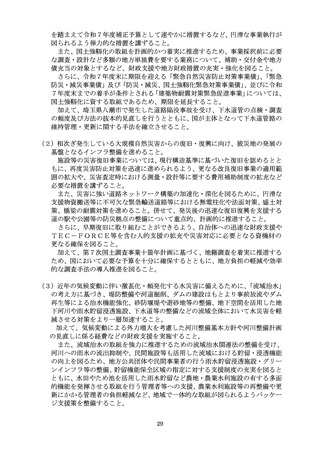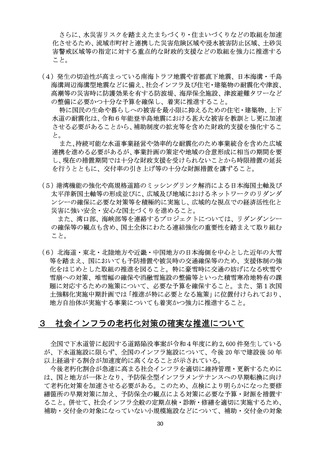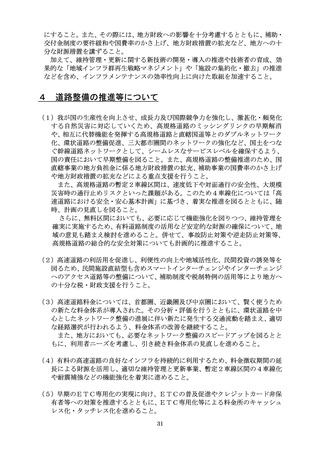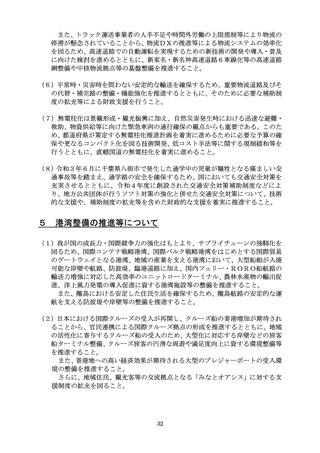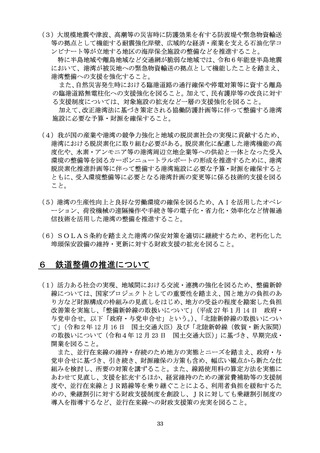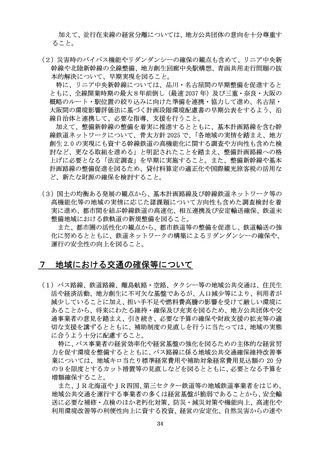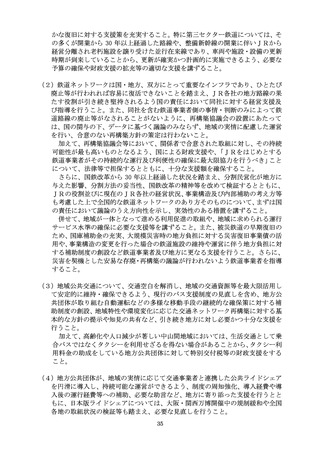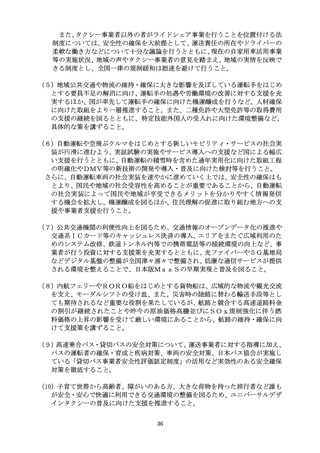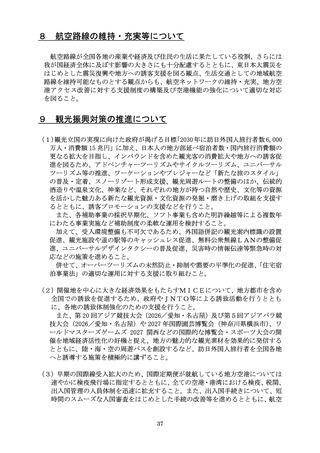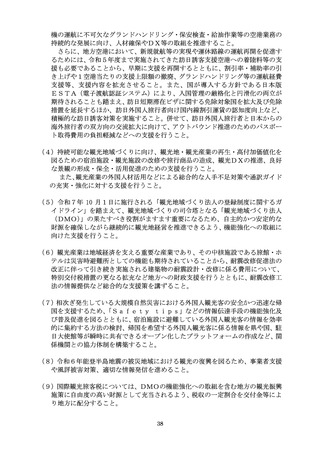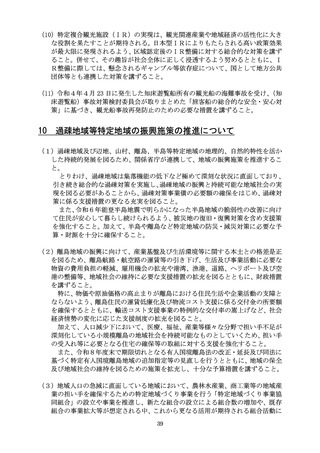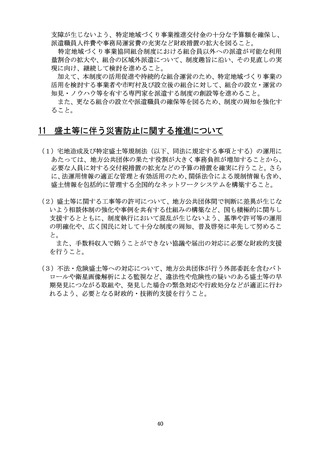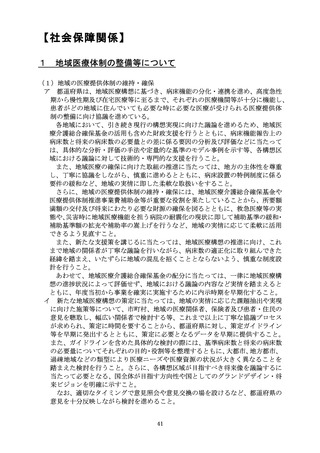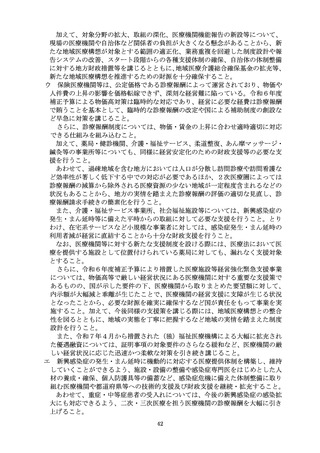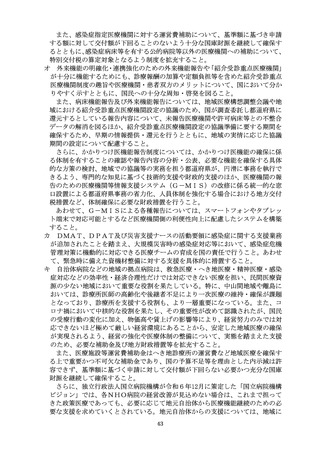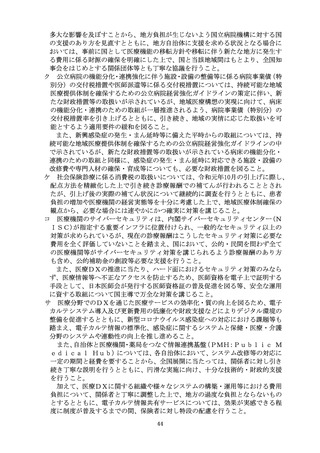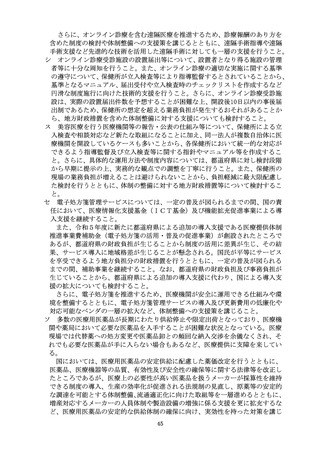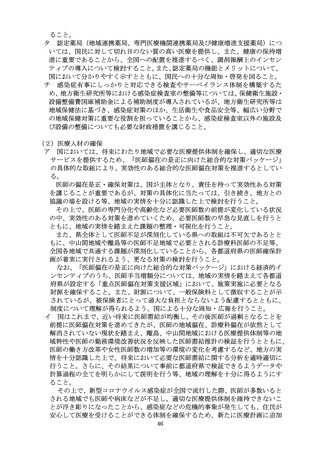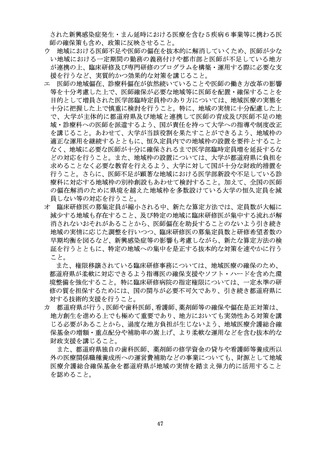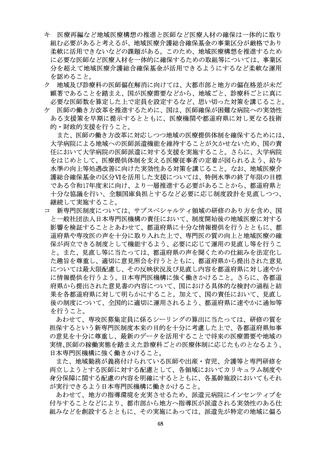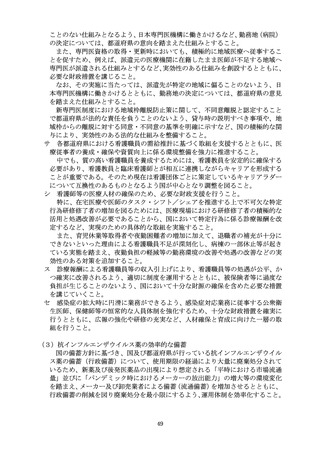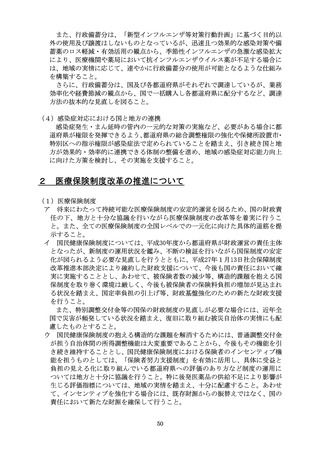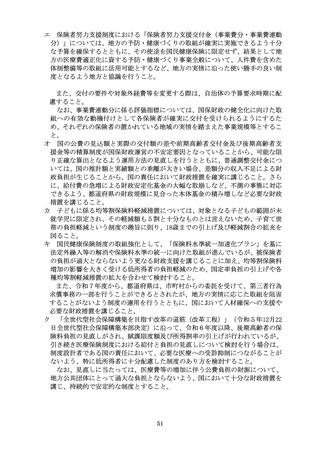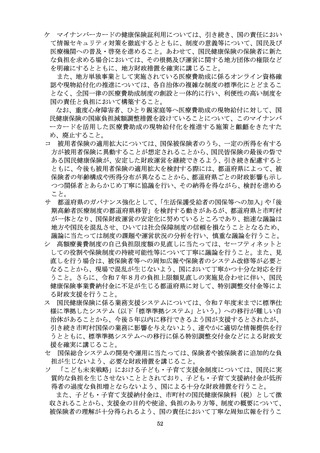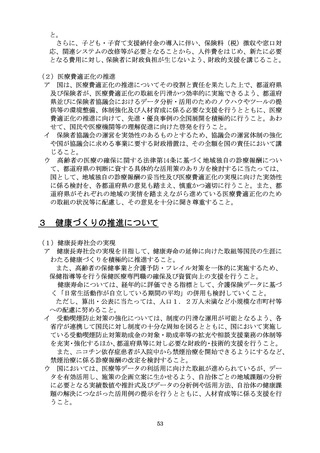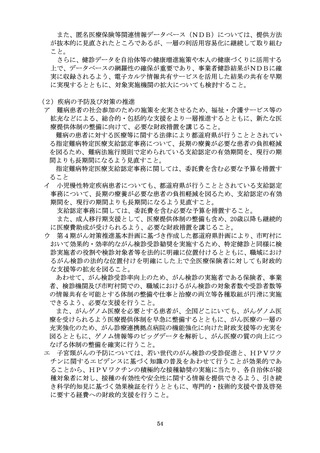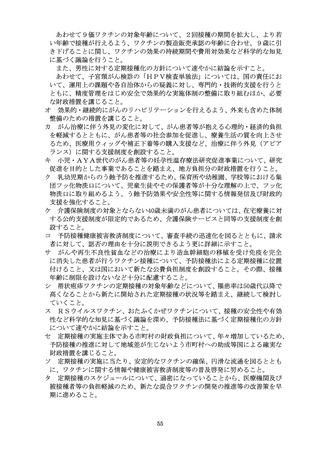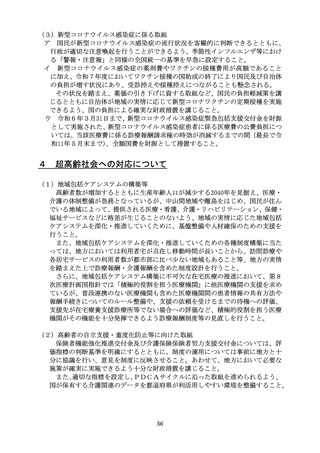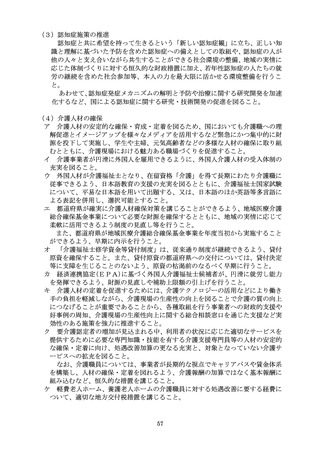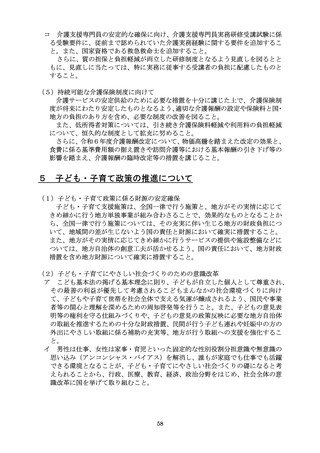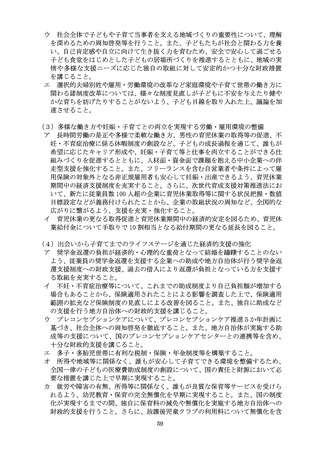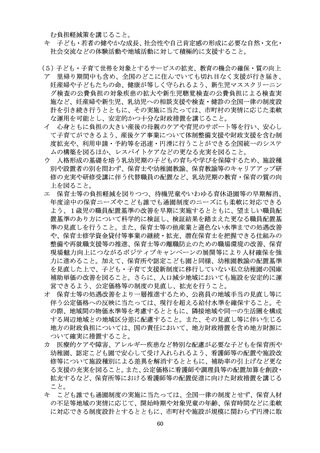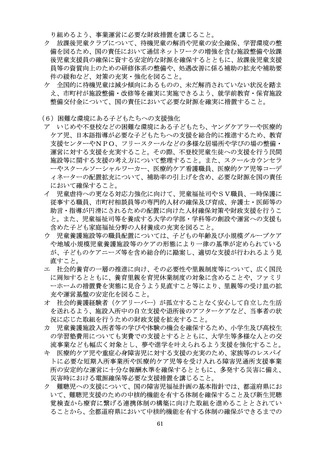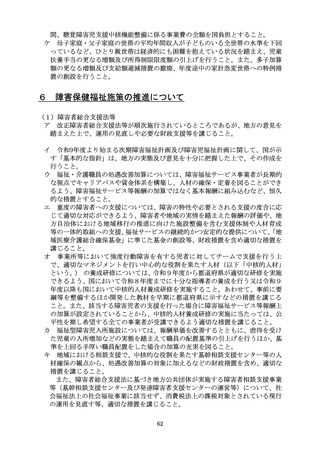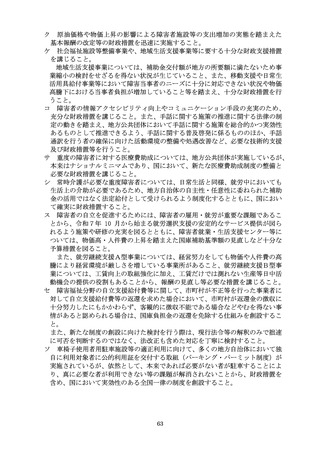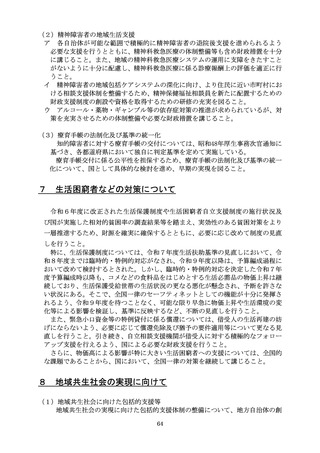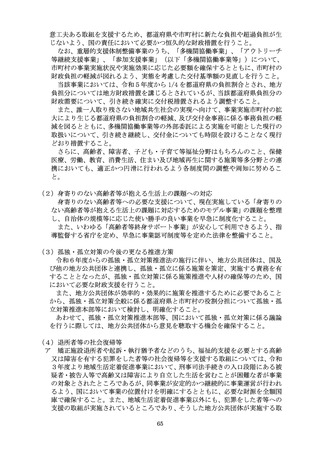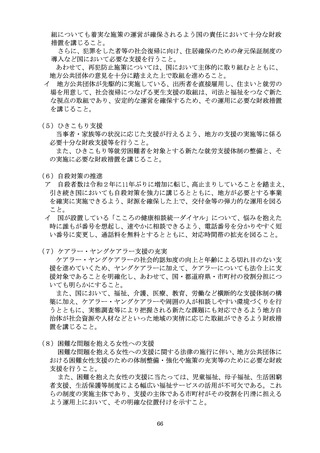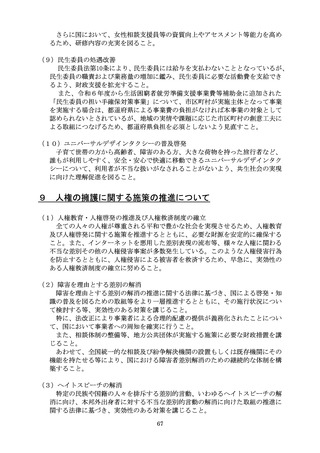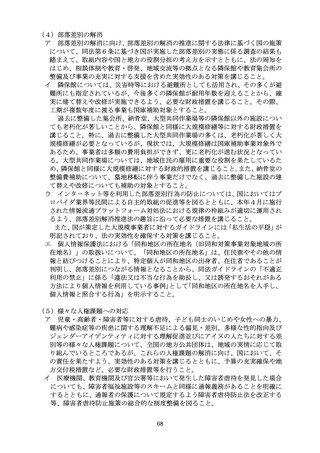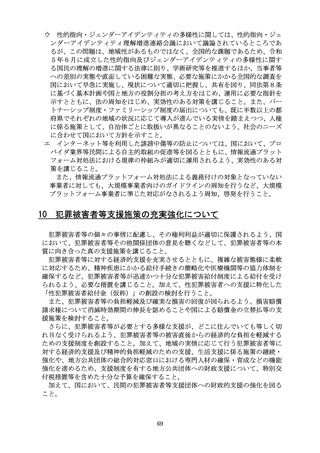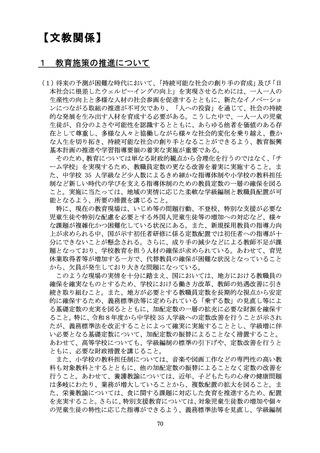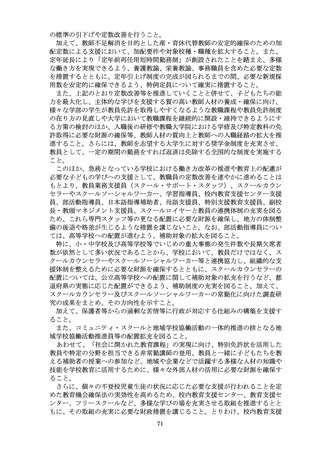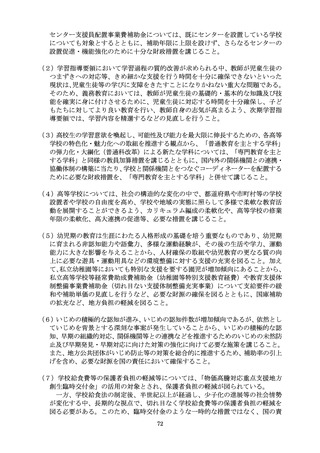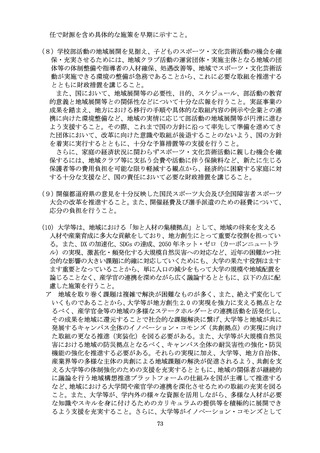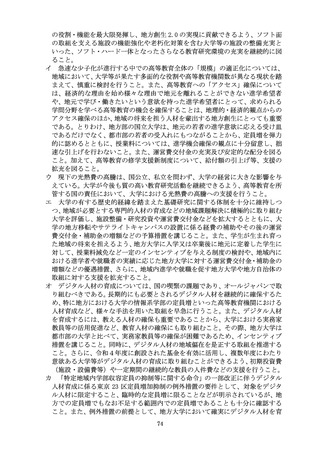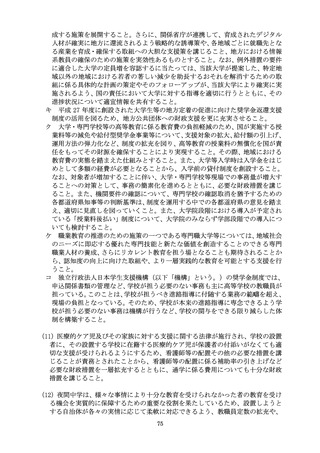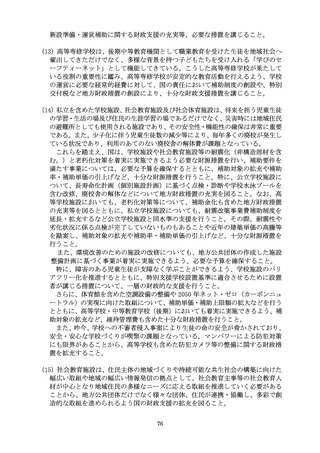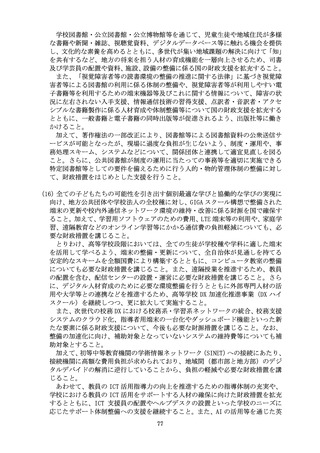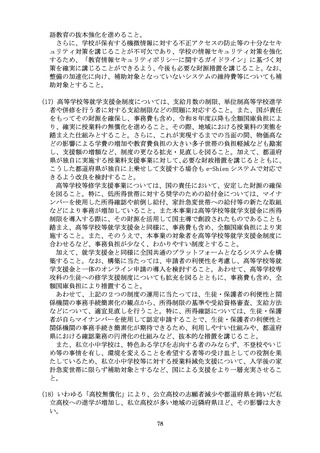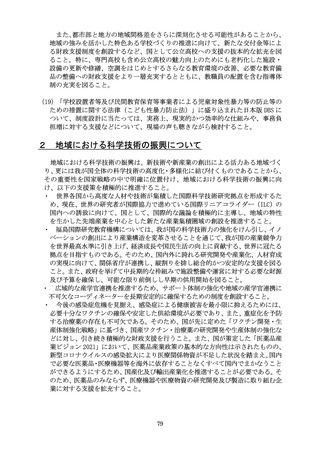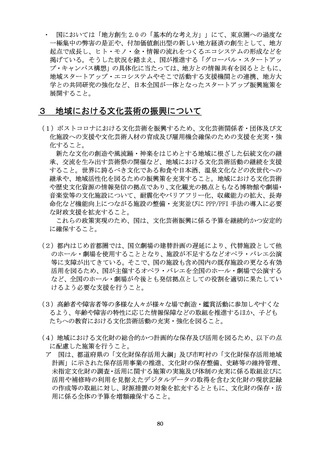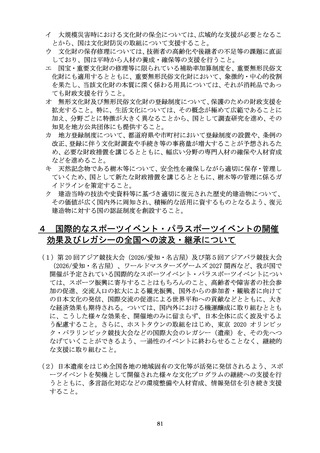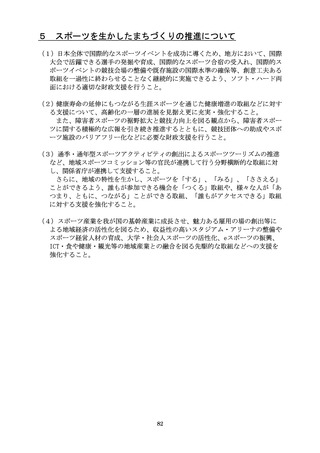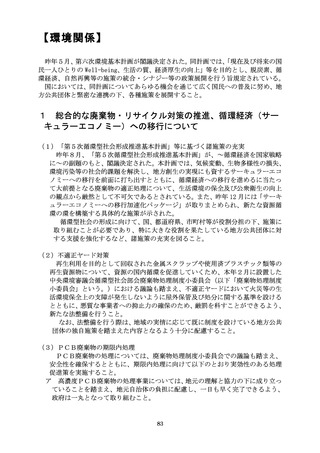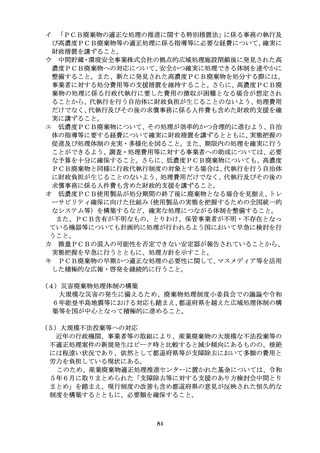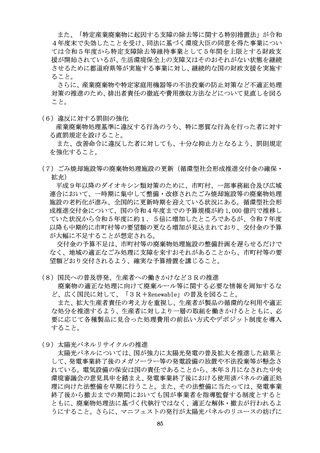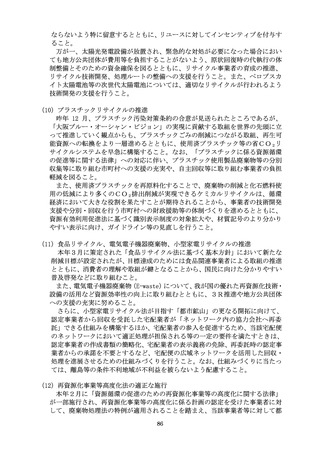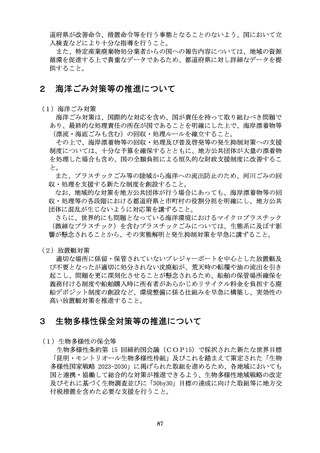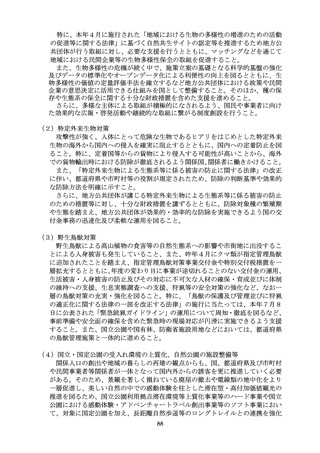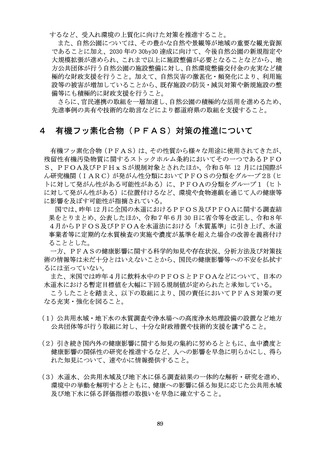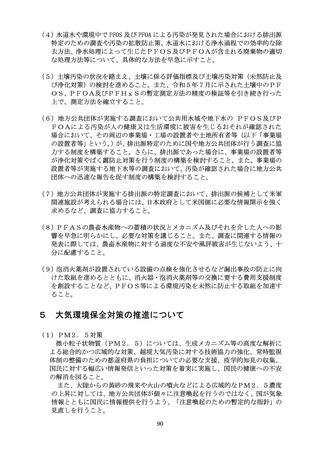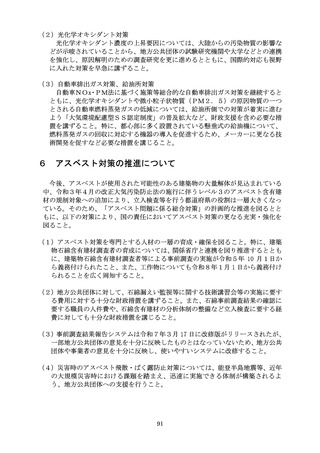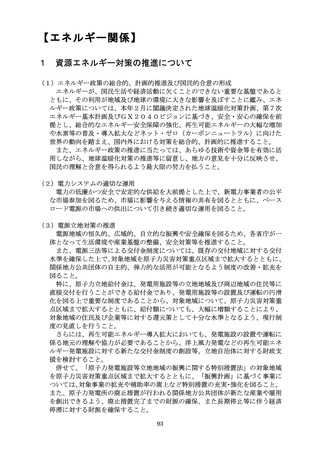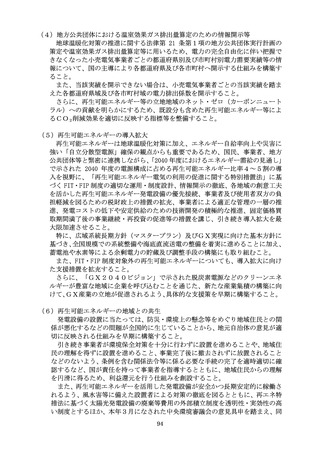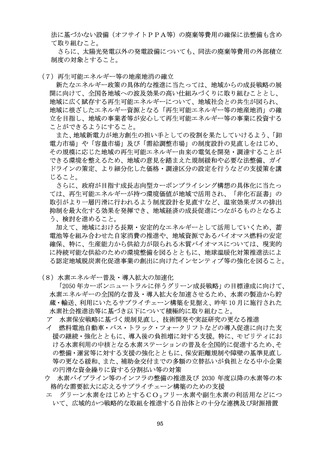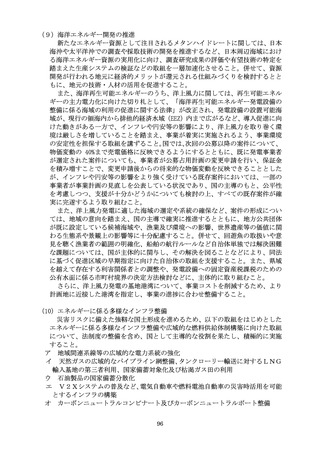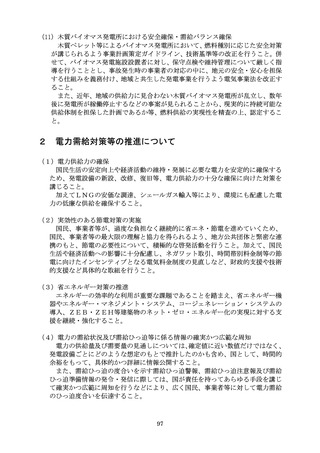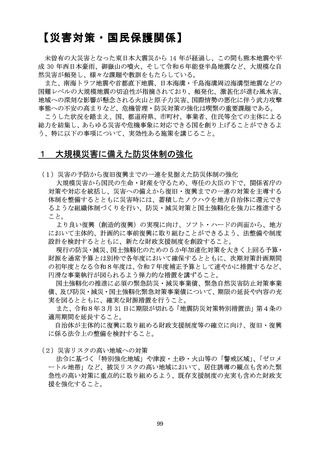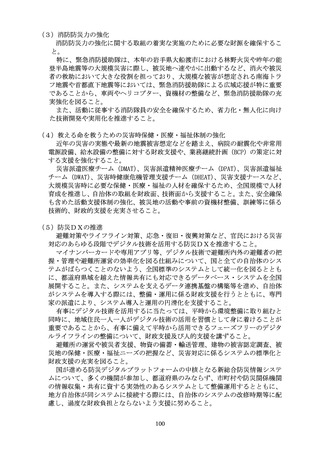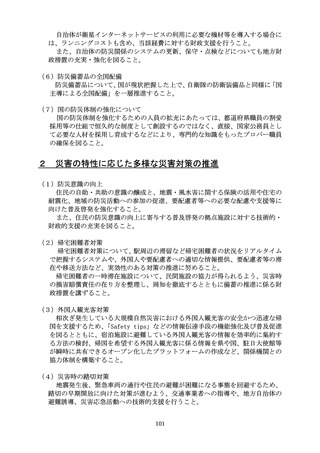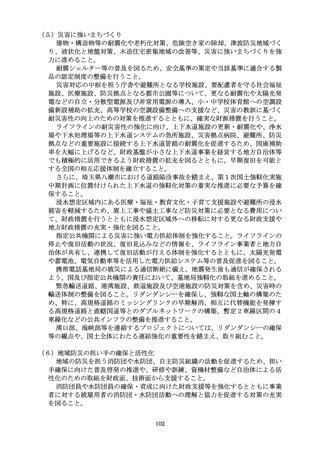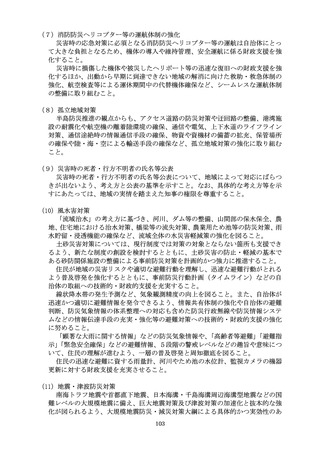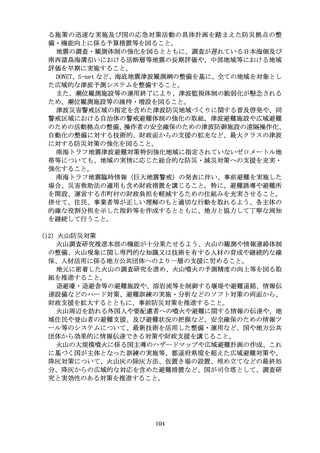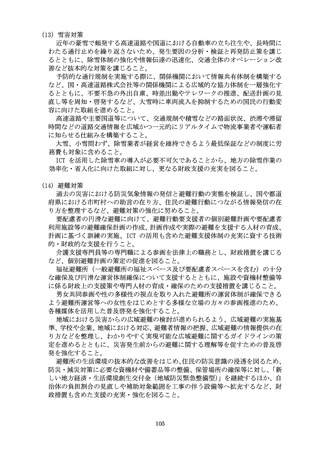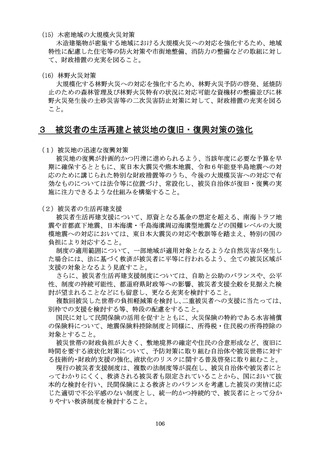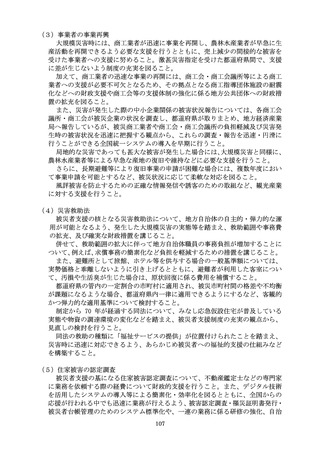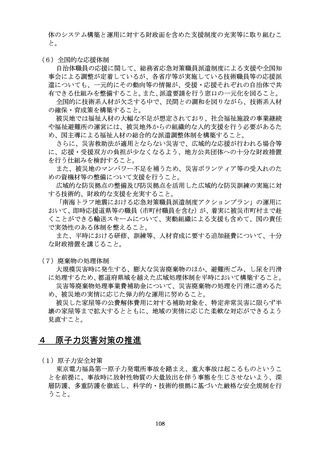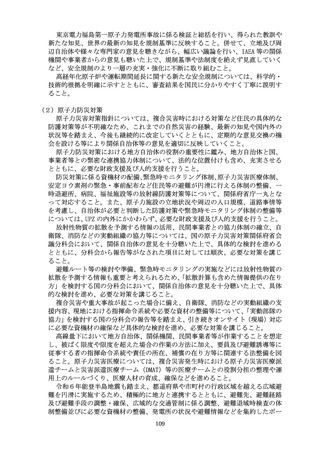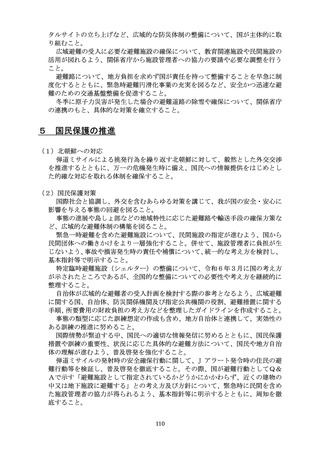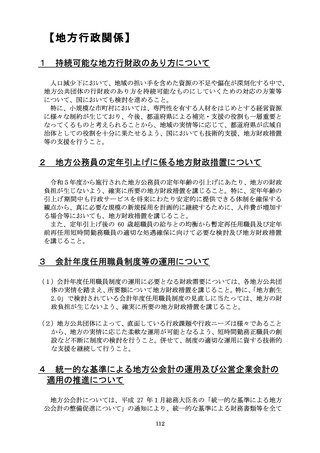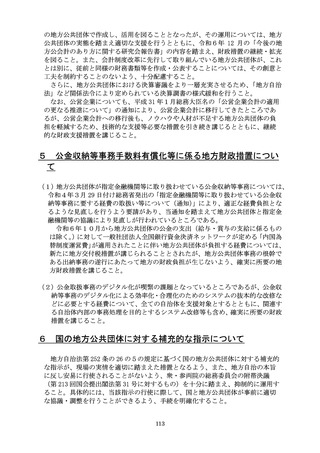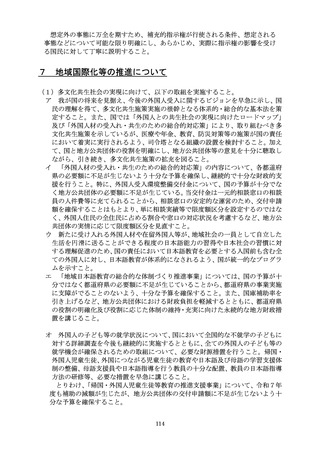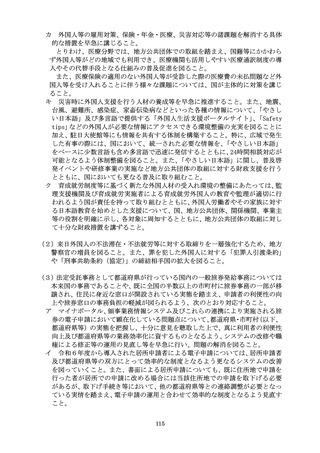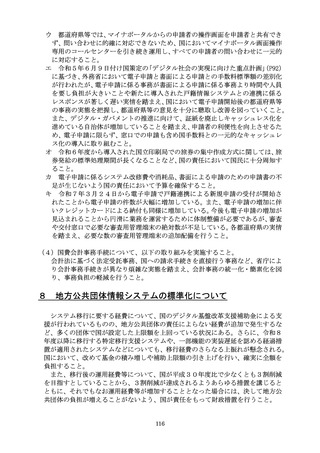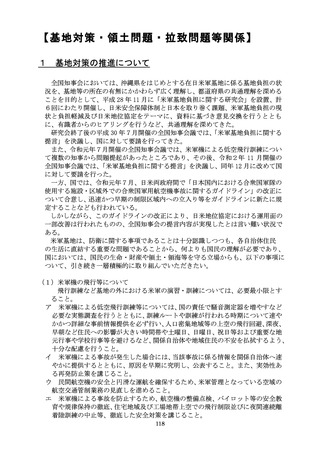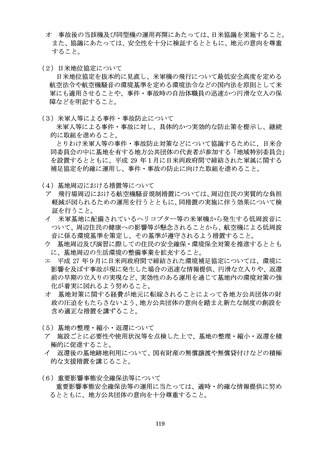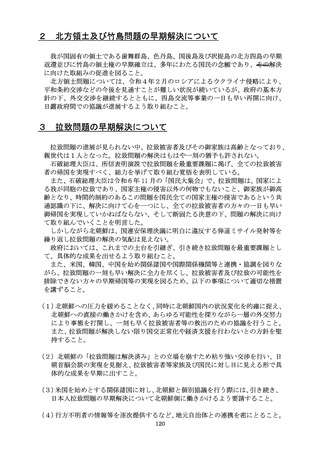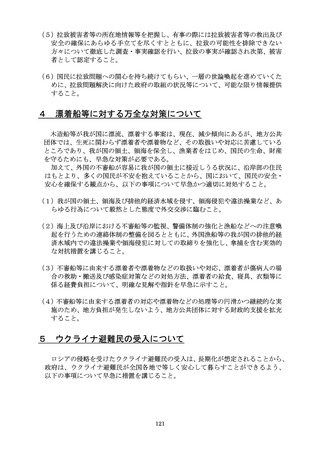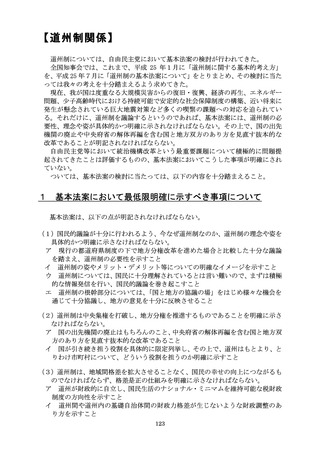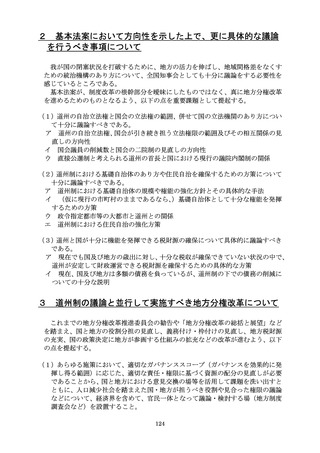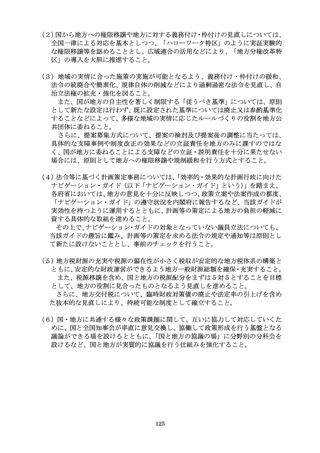【議題(21)資料21】令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 (119 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
| 出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
事態などについて可能な限り明確にし、あらかじめ、実際に指示権の影響を受け
る国民に対して丁寧に説明すること。
7 地域国際化等の推進について
(1)多文化共生社会の実現に向けて、以下の取組を実施すること。
ア 我が国の将来を見据え、今後の外国人受入に関するビジョンを早急に示し、国
民の理解を得て、多文化共生施策実施の根幹となる体系的・総合的な基本法を策
定すること。また、国では「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」
及び「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」により、取り組むべき多
文化共生施策を示しているが、医療や年金、教育、防災対策等の施策が国の責任
において着実に実行されるよう、司令塔となる組織の設置を検討すること。加え
て、国と地方公共団体の役割を明確にし、地方公共団体等の意見を十分に聴取し
ながら、引き続き、多文化共生施策の拡充を図ること。
イ 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の内容について、各都道府
県の必要額に不足が生じないよう十分な予算を確保し、継続的で十分な財政的支
援を行うこと。特に、外国人受入環境整備交付金について、国の予算が十分でな
く地方公共団体の必要額に不足が生じている。当交付金は一元的相談窓口の相談
員の人件費等に充てられることから、相談窓口の安定的な運営のため、交付申請
額を確保することはもとより、単に相談実績等で限度額区分を設定するのではな
く、外国人住民の全住民に占める割合や窓口の対応状況を考慮するなど、地方公
共団体の実情に応じて限度額区分を見直すこと。
ウ 新たに受け入れる外国人材や在留外国人等が、地域社会の一員として自立した
生活を円滑に送ることができる程度の日本語能力の習得や日本社会の習慣に対
する理解促進のため、国の責任において日本語教育を必要とする入国前も含む全
ての外国人に対し、日本語教育が体系的になされるよう、国が統一的なプログラ
ムを示すこと。
エ 「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」については、国の予算が十
分ではなく都道府県の必要額に不足が生じていることから、都道府県の事業実施
に支障がでることのないよう、十分な予算を確保すること。また、国庫補助率を
引き上げるなど、地方公共団体における財政負担を軽減するとともに、都道府県
の役割の明確化及び役割に応じた体制の維持・充実に向けた永続的な地方財政措
置を講じること。
オ 外国人の子ども等の就学状況について、国において全国的な不就学の子どもに
対する詳細調査を今後も継続的に実施するとともに、全ての外国人の子ども等の
就学機会が確保されるための取組について、必要な財源措置を行うこと。帰国・
外国人児童生徒、外国につながる児童生徒の教育や日本語及び母語の学習支援体
制の整備、母語支援員や日本語指導を行う教員の十分な配置、教員の日本語指導
方法の研修等、必要な措置を早急に講じること。
とりわけ、
「帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業」について、令和7年
度も補助の減額が生じたが、地方公共団体の交付申請額に不足が生じないよう十
分な予算を確保すること。
114