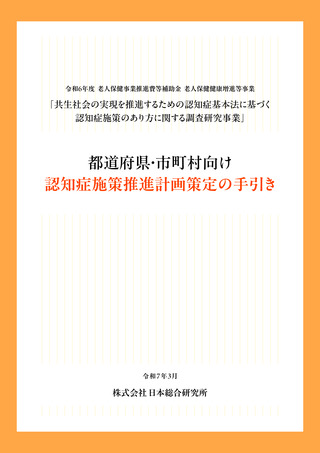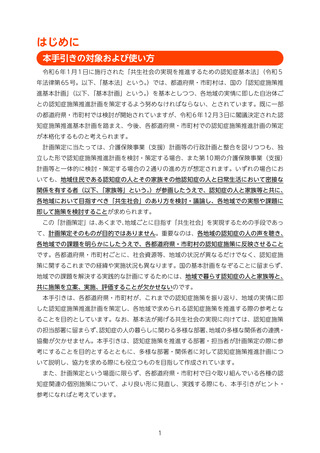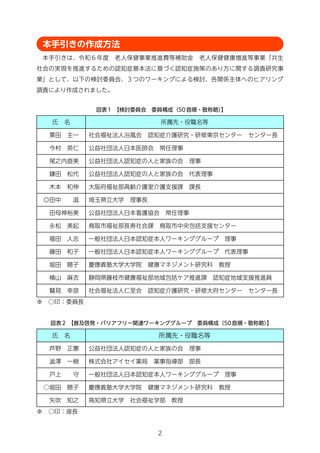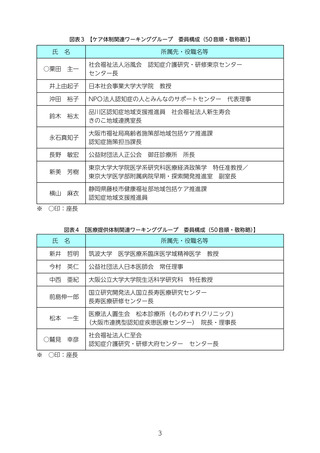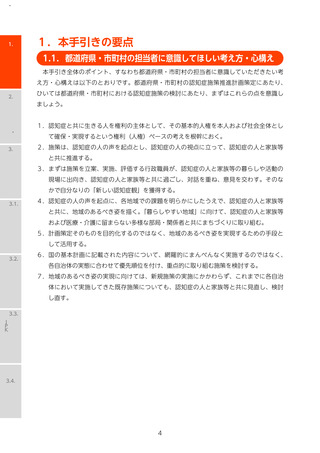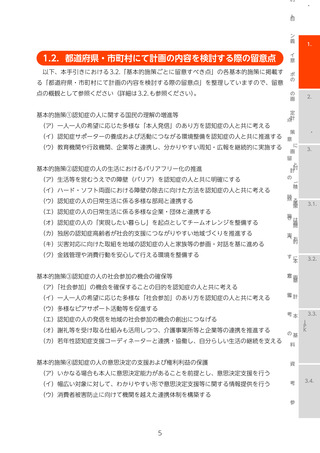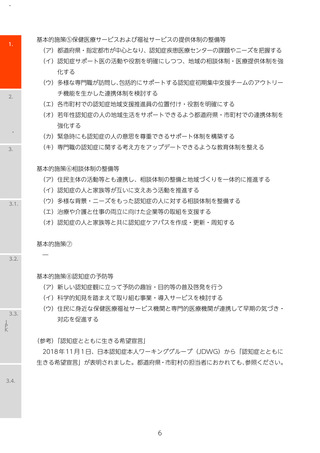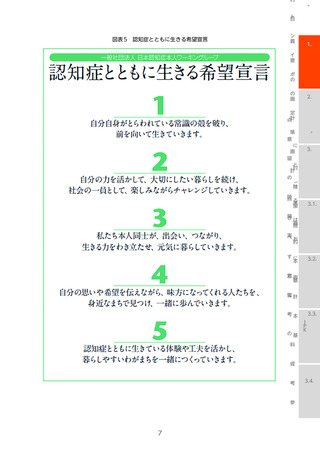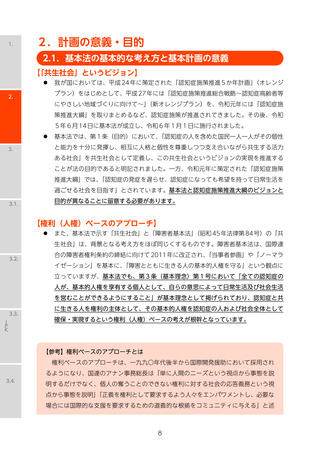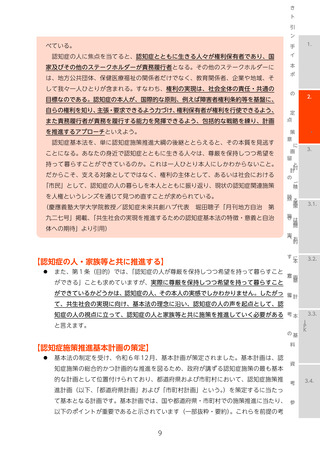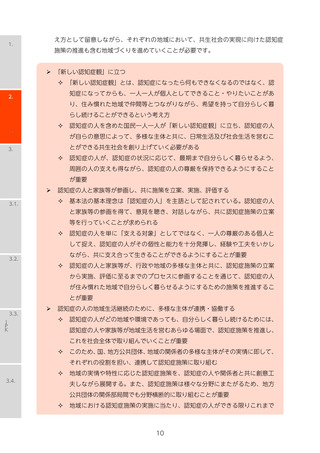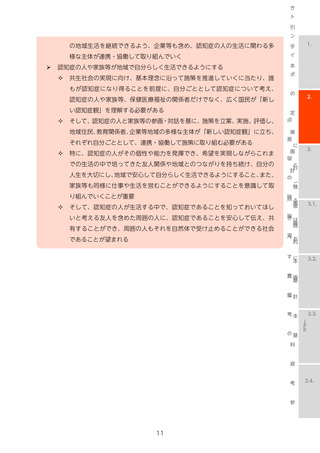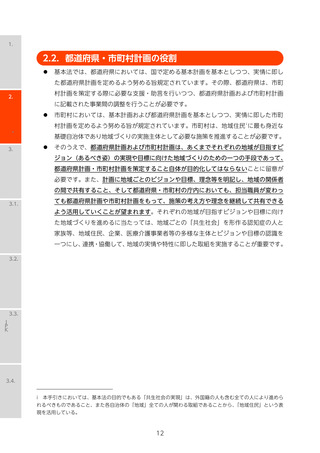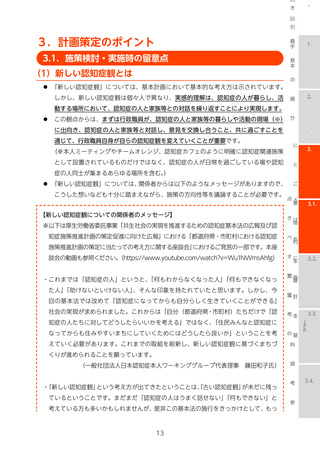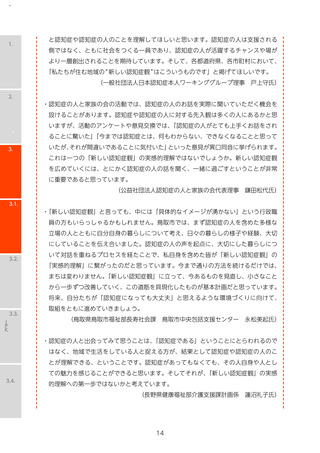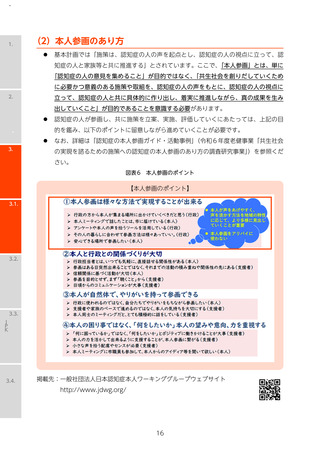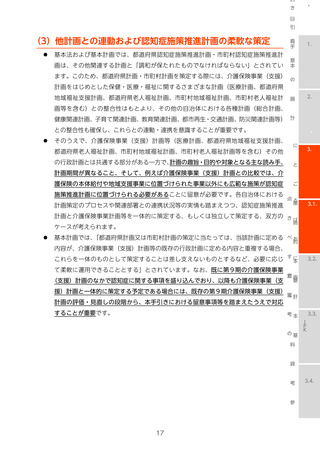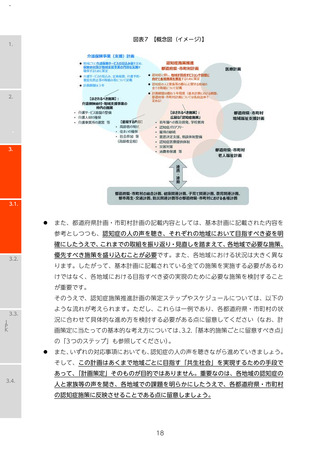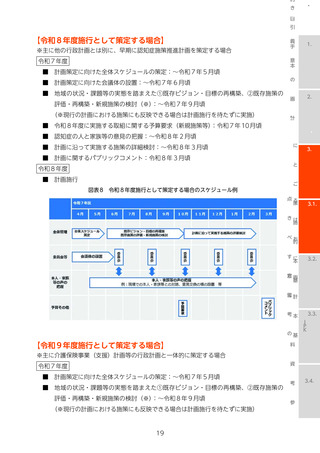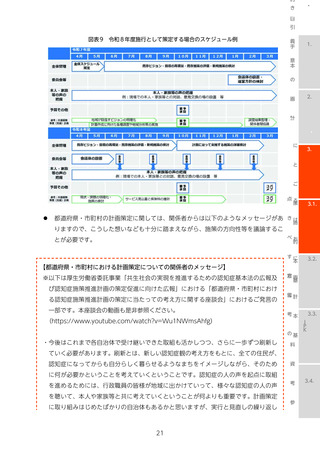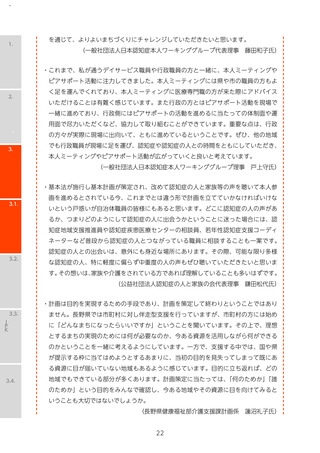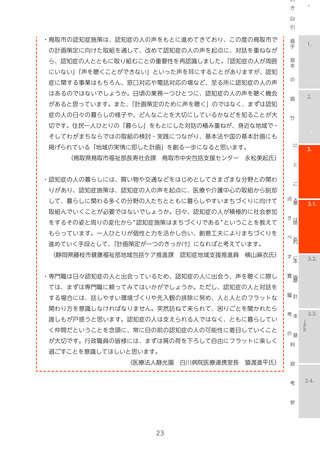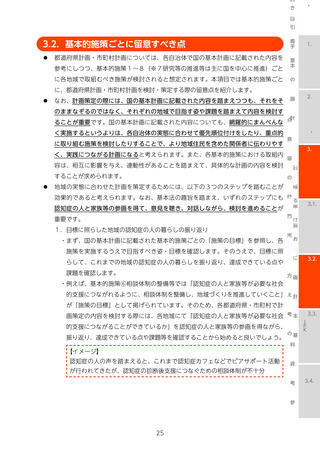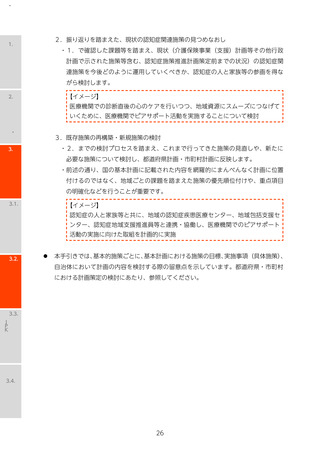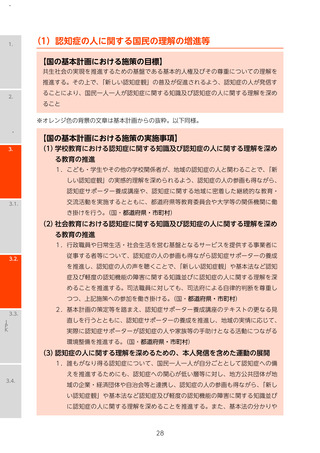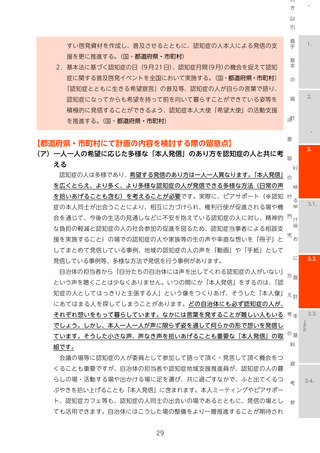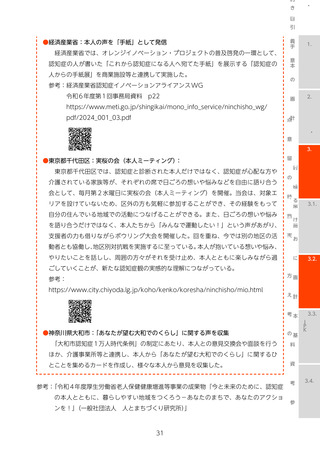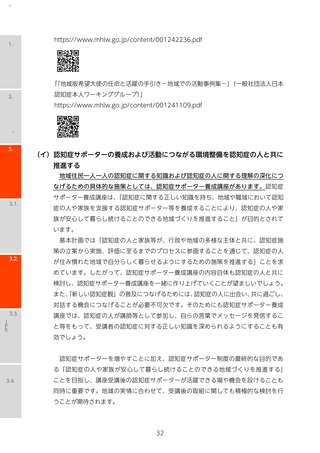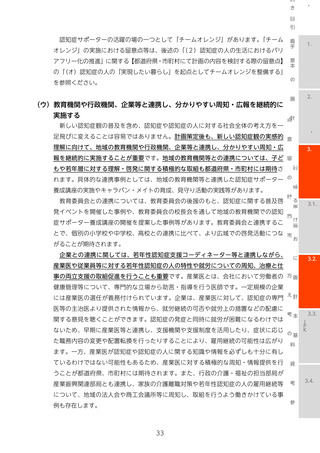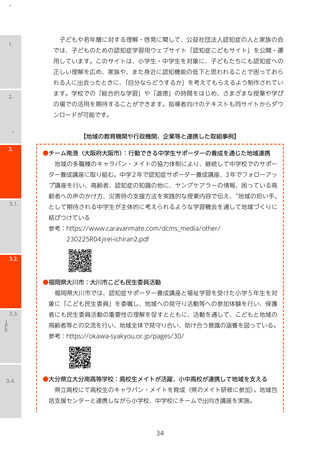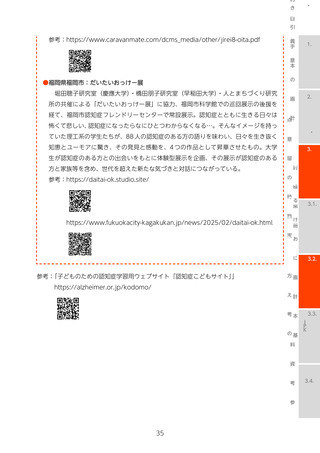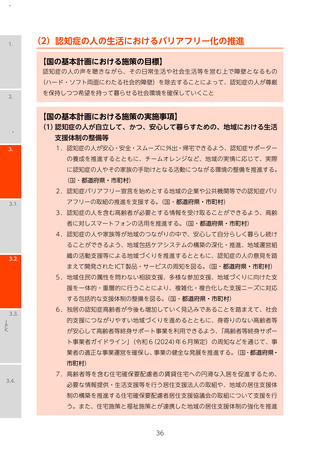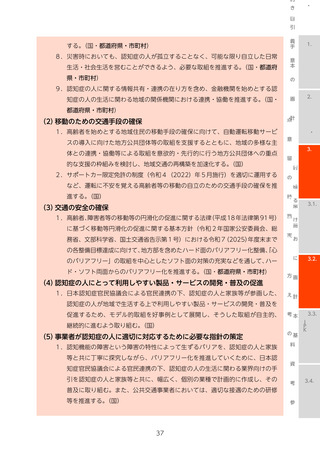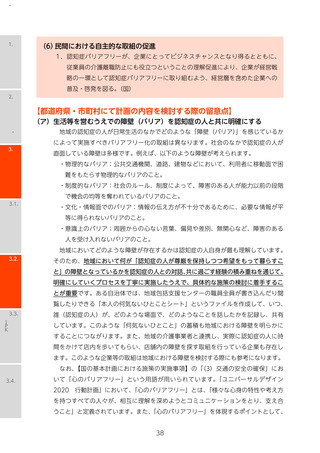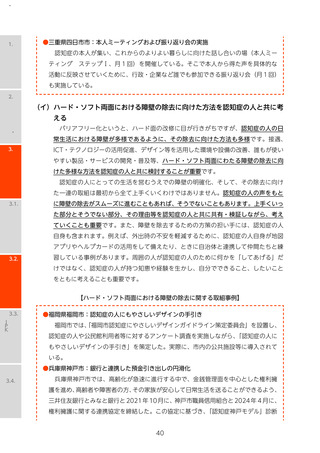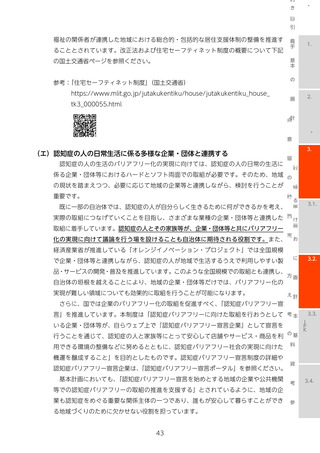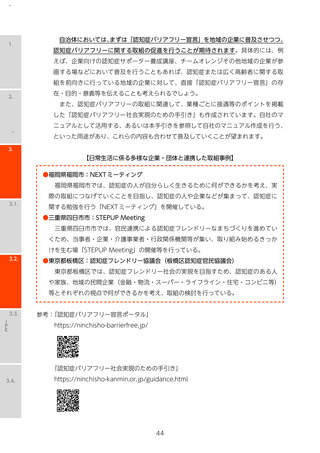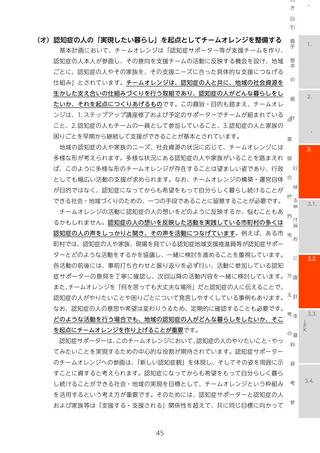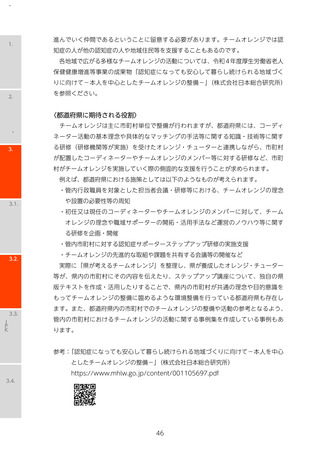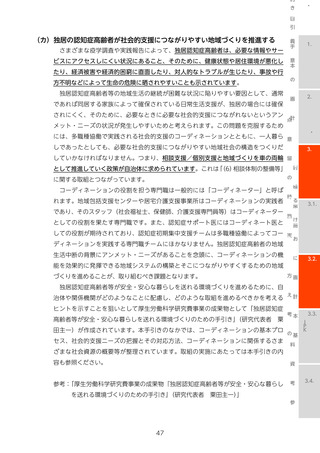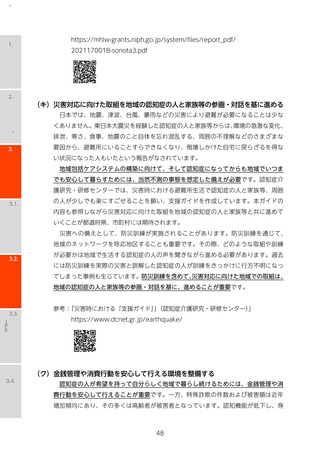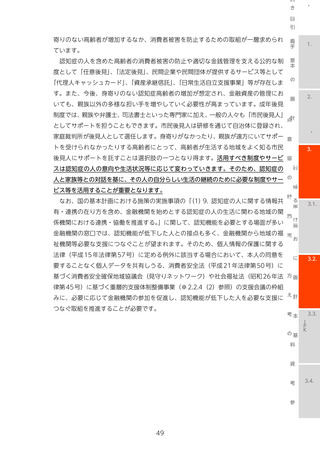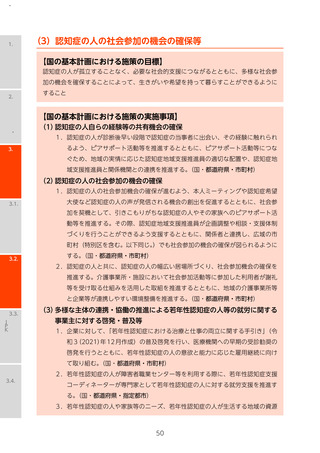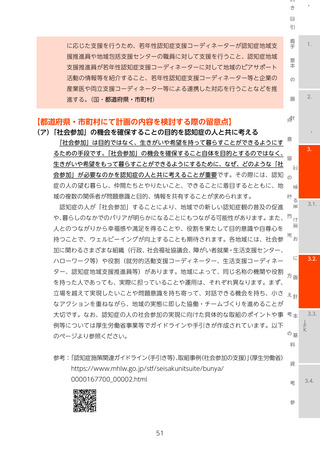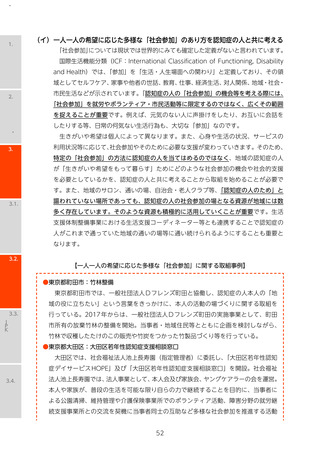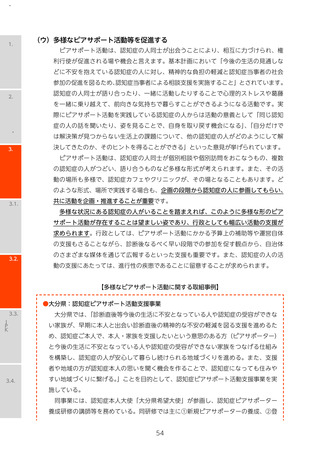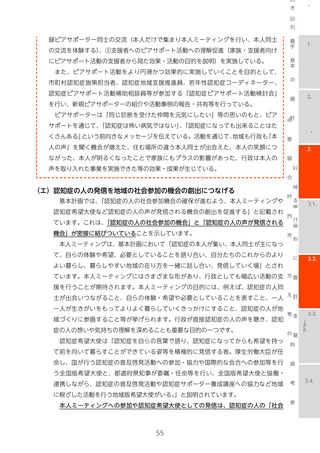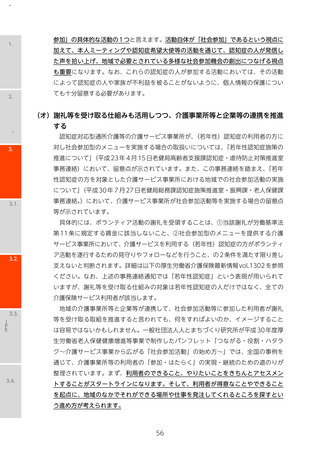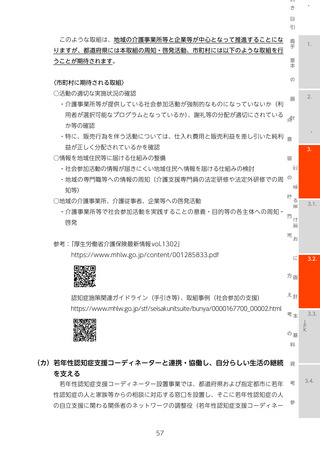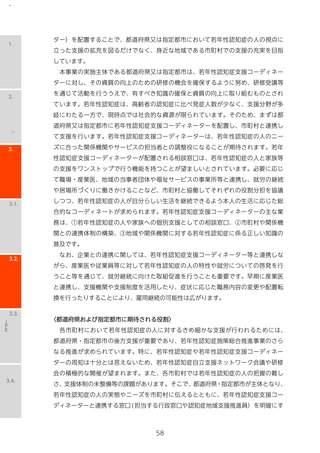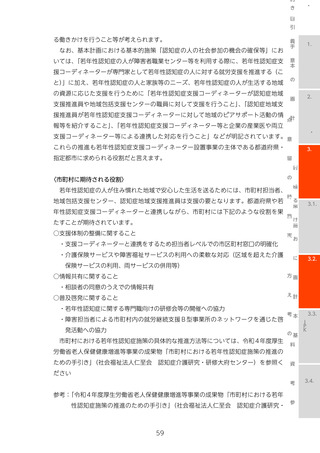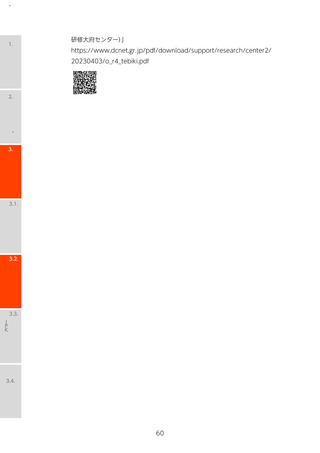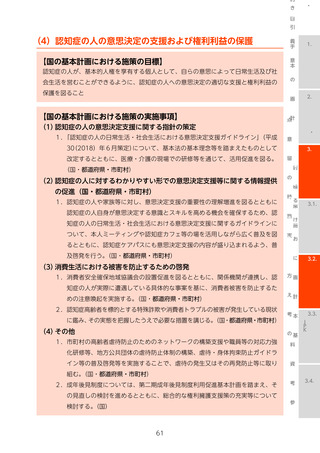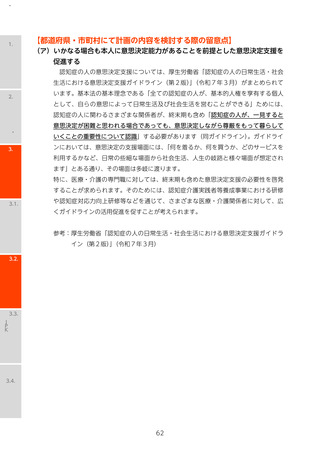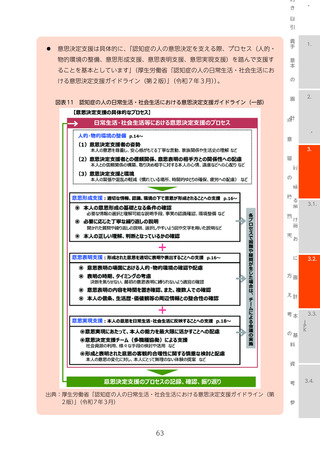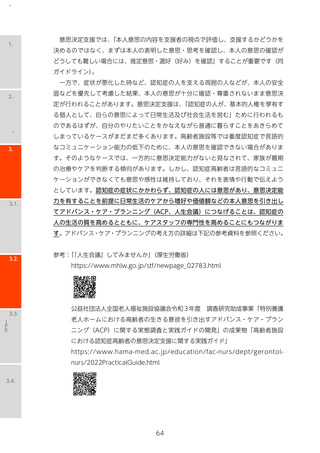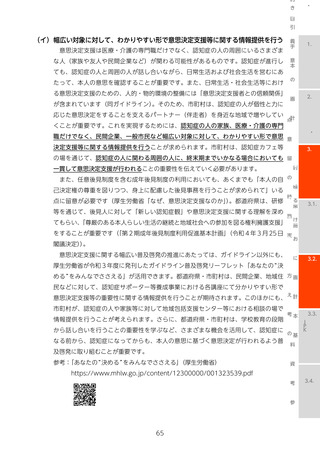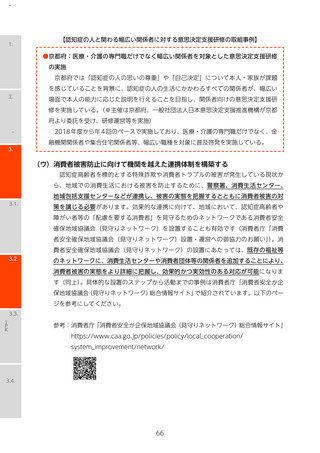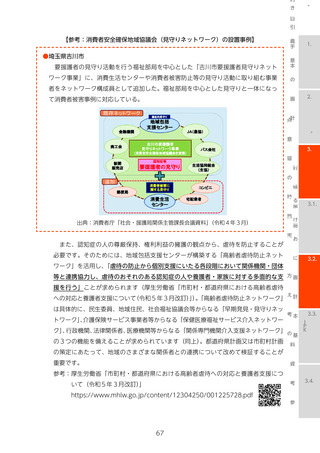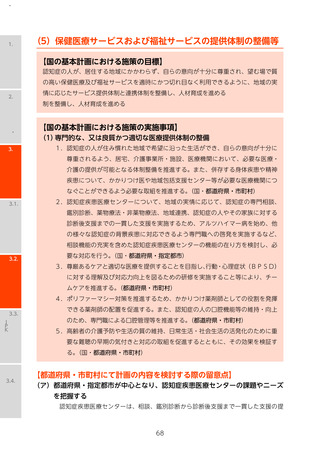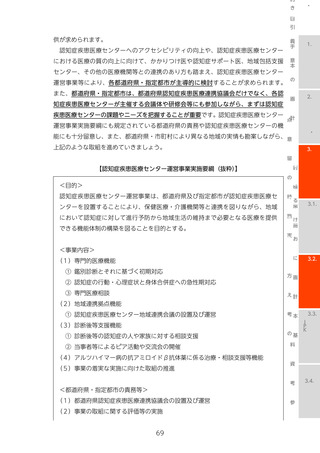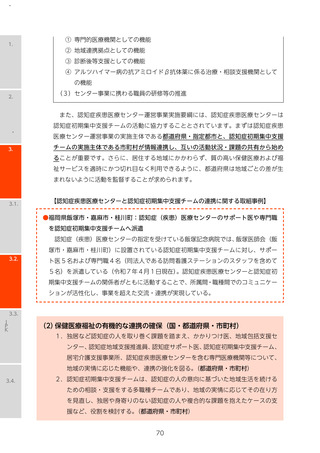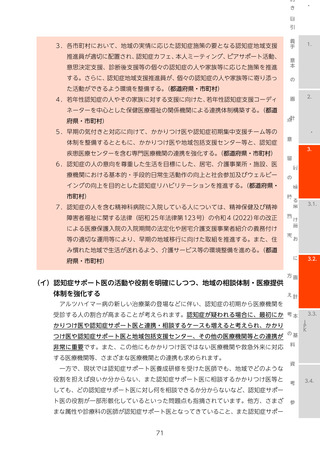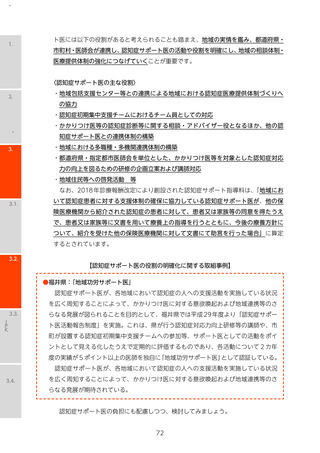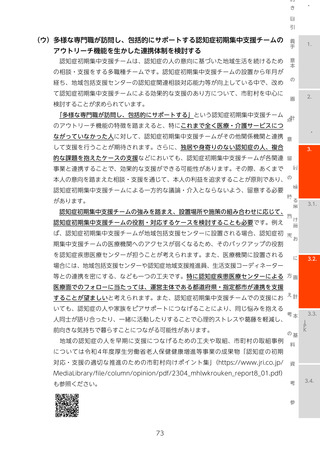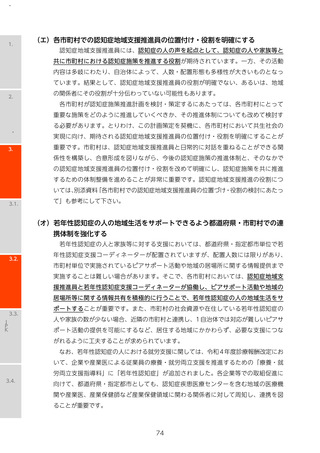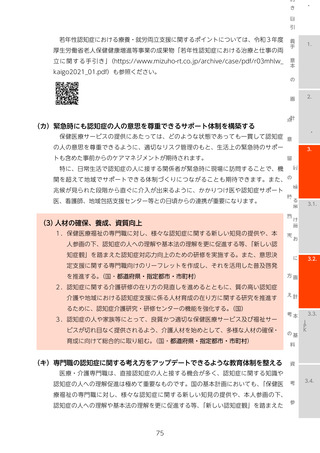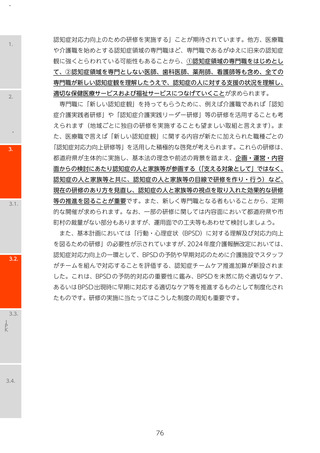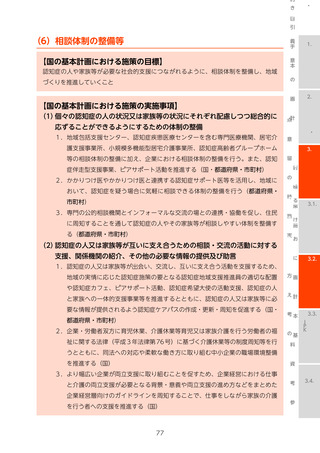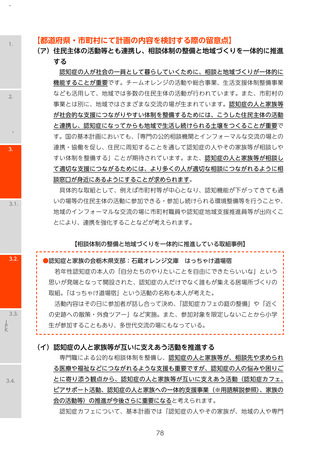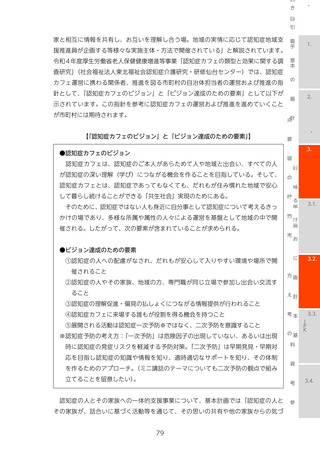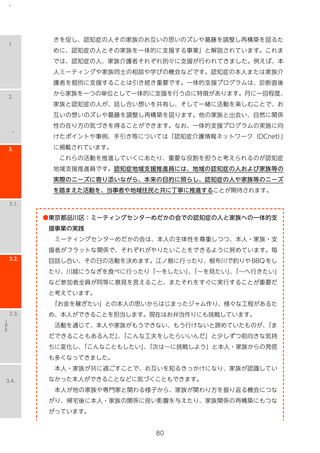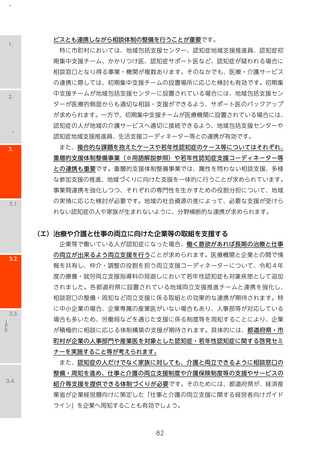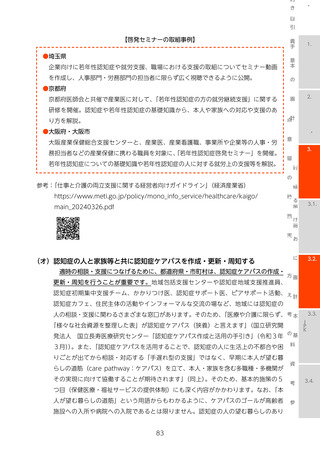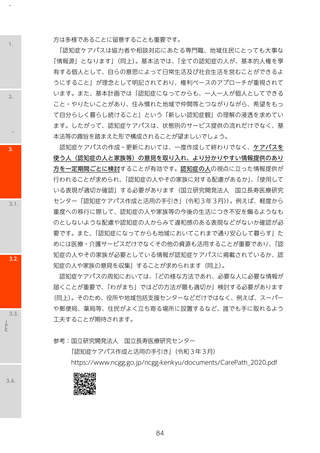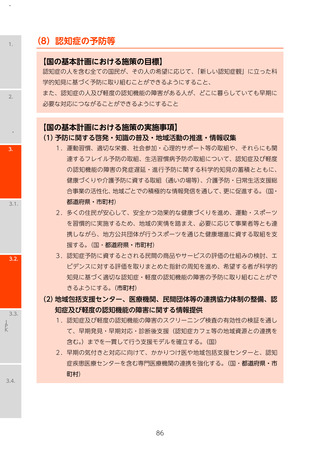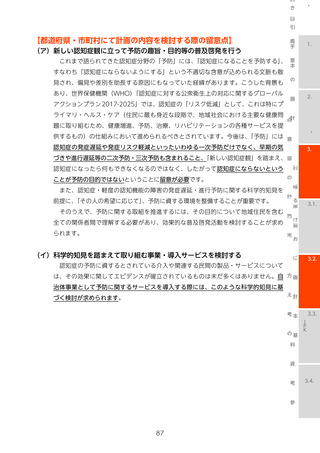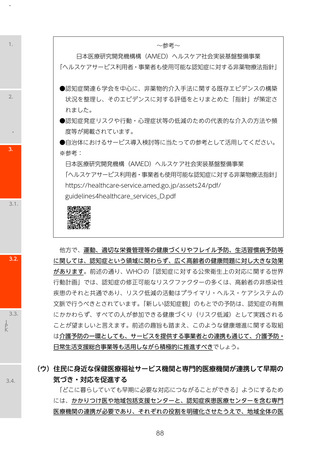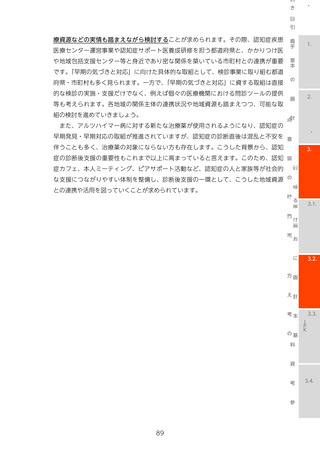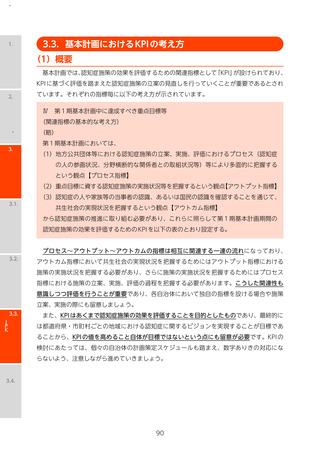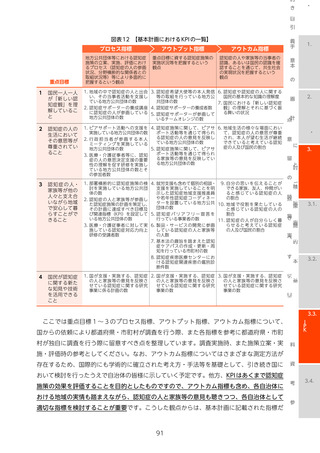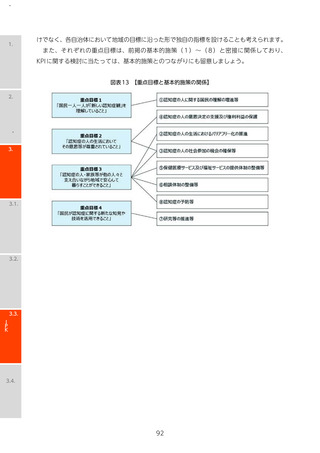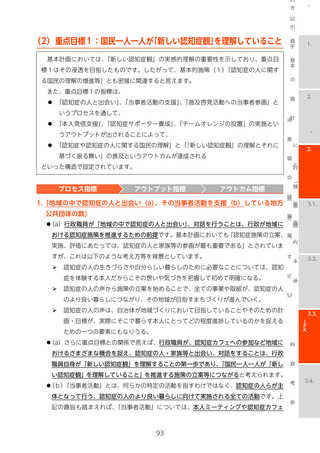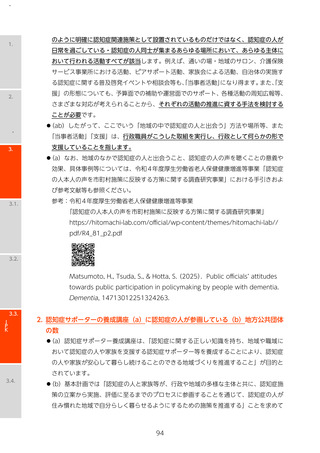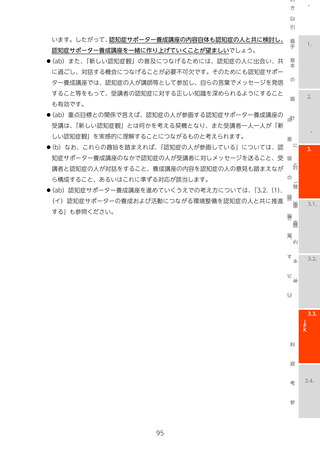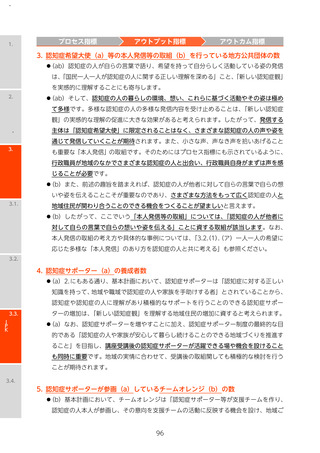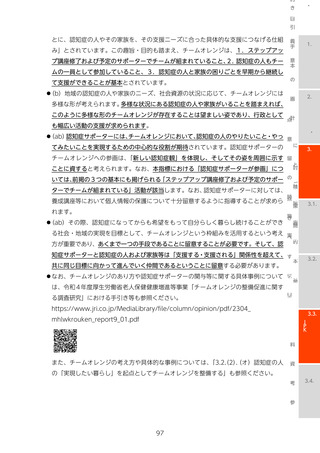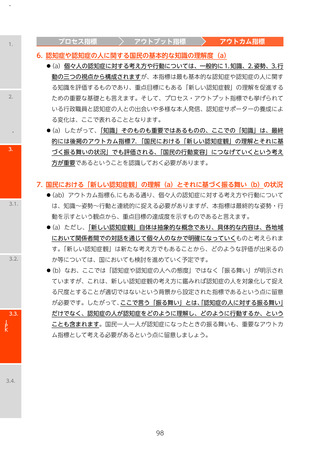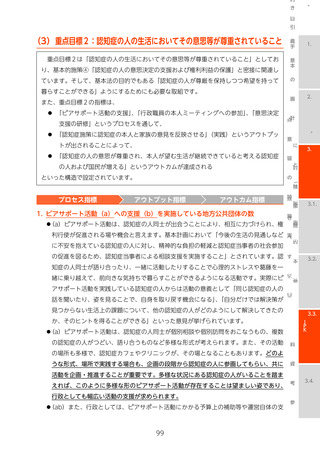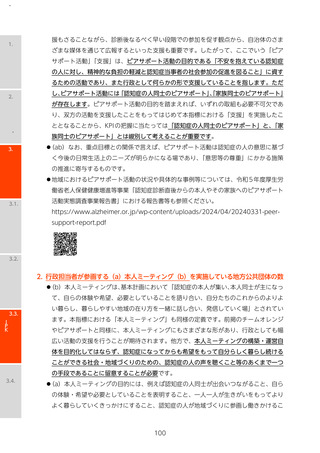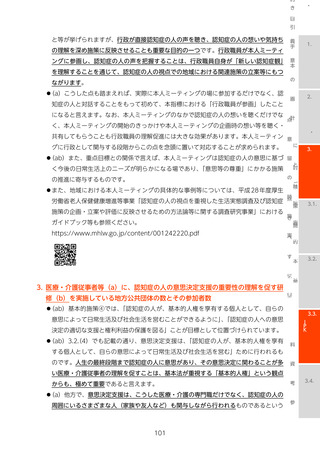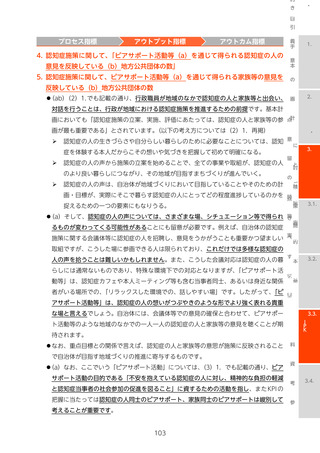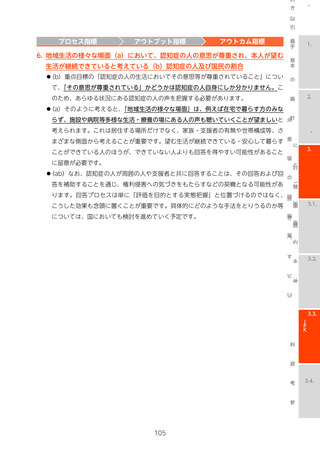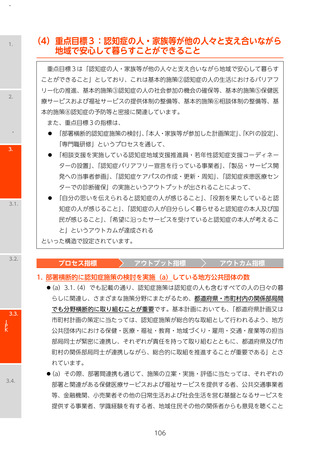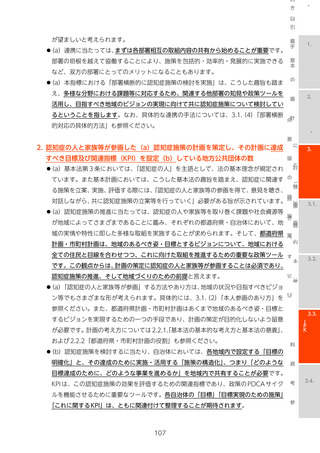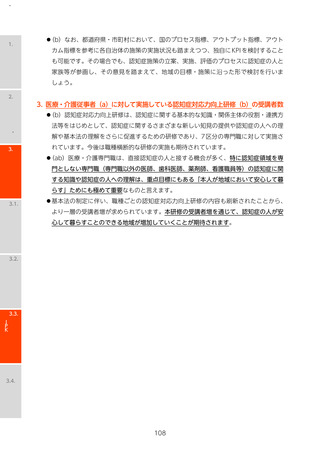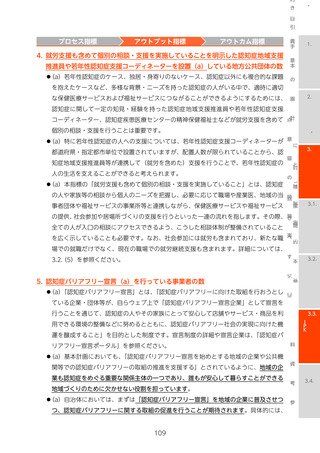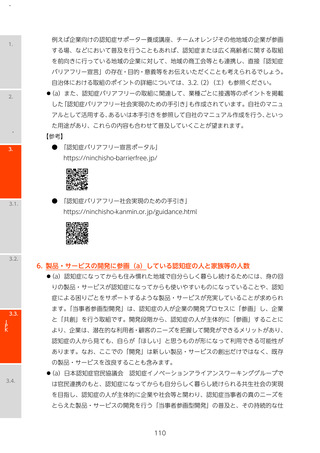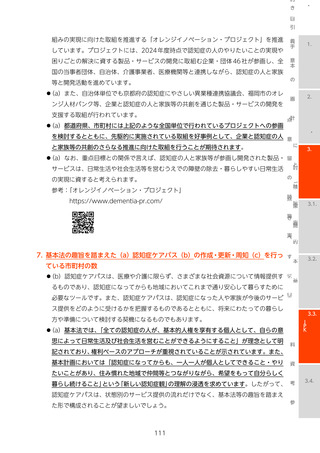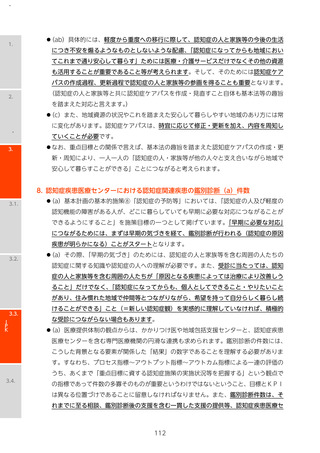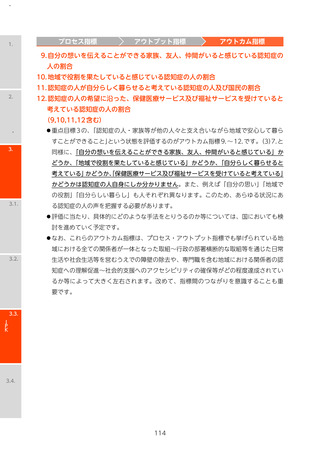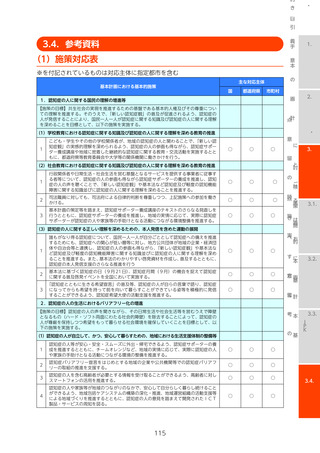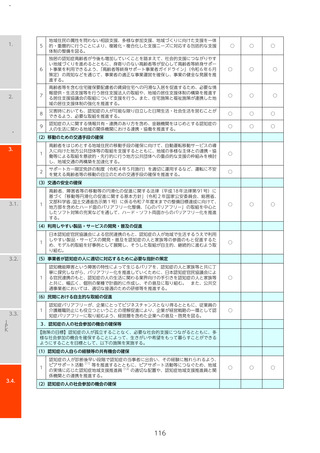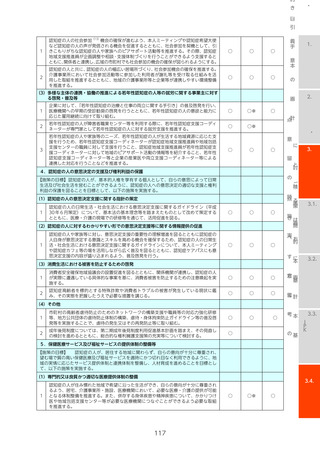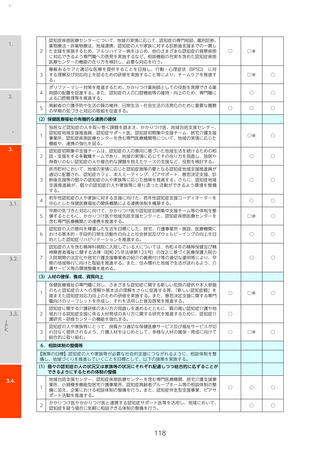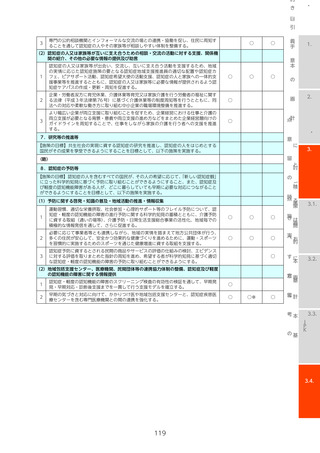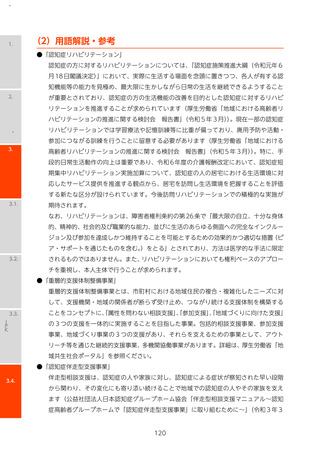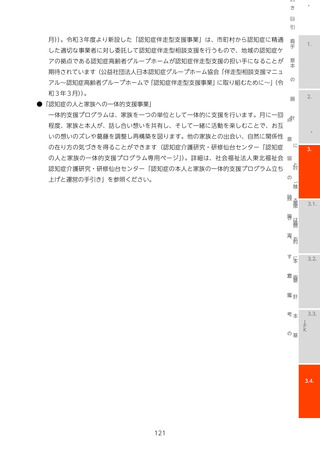都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |
| 出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
本手引きの対象および使い方
令和 6 年 1 月 1 日に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(令和5
年法律第 65 号。以下、「基本法」という。)では、都道府県・市町村は、国の「認知症施策推
進基本計画」(以下、「基本計画」という。)を基本としつつ、各地域の実情に即した自治体ご
との認知症施策推進計画を策定するよう努めなければならない、とされています。既に一部
の都道府県・市町村では検討が開始されていますが、令和 6 年 12 月 3 日に閣議決定された認
知症施策推進基本計画を踏まえ、今後、各都道府県・市町村での認知症施策推進計画の策定
が本格化するものと考えられます。
計画策定に当たっては、介護保険事業(支援)計画等の行政計画と整合を図りつつも、独
立した形で認知症施策推進計画を検討・策定する場合、また第 10 期の介護保険事業(支援)
計画等と一体的に検討・策定する場合の 2 通りの進め方が想定されます。いずれの場合にお
いても、地域住民である認知症の人とその家族その他認知症の人と日常生活において密接な
関係を有する者(以下、「家族等」という。)が参画したうえで、認知症の人と家族等と共に、
各地域において目指すべき「共生社会」のあり方を検討・議論し、各地域での実態や課題に
即して施策を検討することが求められます。
この「計画策定」は、あくまで、地域ごとに目指す「共生社会」を実現するための手段であっ
て、計画策定そのものが目的ではありません。重要なのは、各地域の認知症の人の声を聴き、
各地域での課題を明らかにしたうえで、各都道府県・市町村の認知症施策に反映させること
です。各都道府県・市町村ごとに、社会資源等、地域の状況が異なるだけでなく、認知症施
策に関するこれまでの経緯や実施状況も異なります。国の基本計画をなぞることに留まらず、
地域での課題を解決する実践的な計画にするためには、地域で暮らす認知症の人と家族等と、
共に施策を立案、実施、評価することが欠かせないのです。
本手引きは、各都道府県・市町村が、これまでの認知症施策を振り返り、地域の実情に即
した認知症施策推進計画を策定し、各地域で求められる認知症施策を推進する際の参考とな
ることを目的としています。なお、基本法が掲げる共生社会の実現に向けては、認知症施策
の担当部署に留まらず、認知症の人の暮らしに関わる多様な部署、地域の多様な関係者の連携・
協働が欠かせません。本手引きは、認知症施策を推進する部署・担当者が計画策定の際に参
考にすることを目的とするとともに、多様な部署・関係者に対して認知症施策推進計画につ
いて説明し、協力を求める際にも役立つものを目指して作成されています。
また、計画策定という場面に限らず、各都道府県・市町村で日々取り組んでいる各種の認
知症関連の個別施策について、より良い形に見直し、実践する際にも、本手引きがヒント・
参考になればと考えています。
1