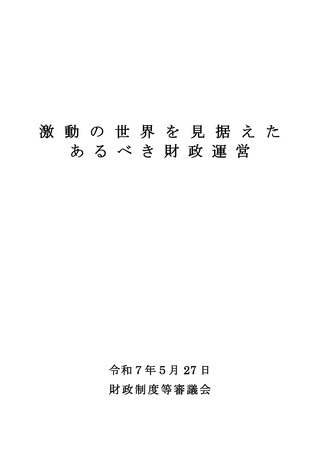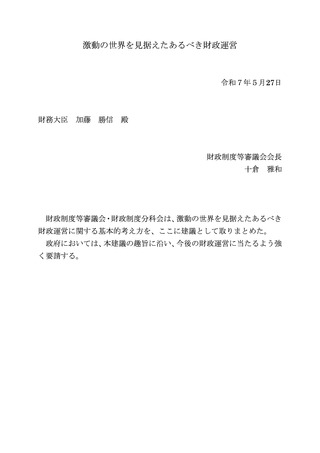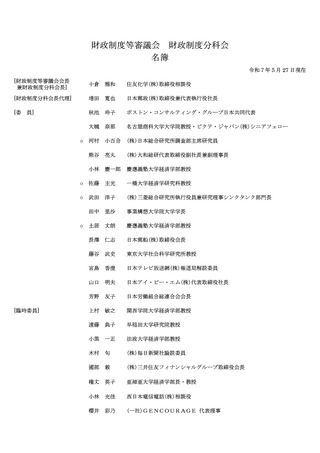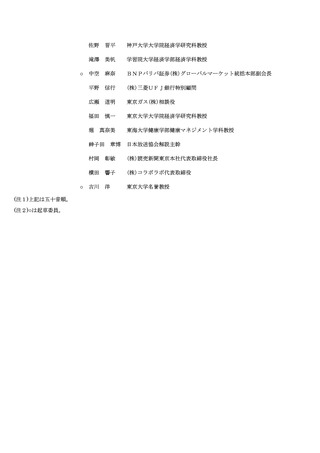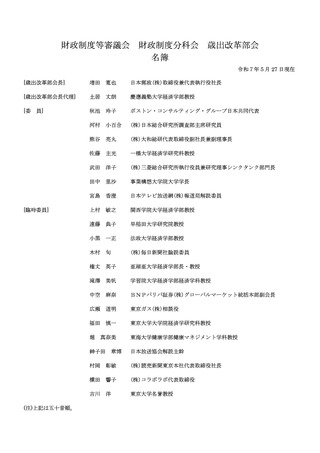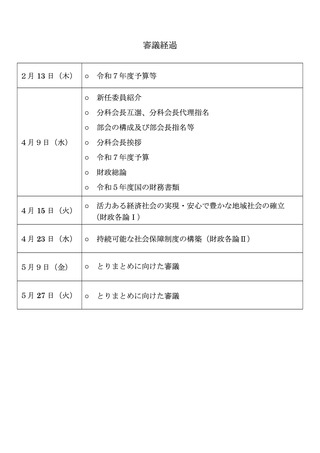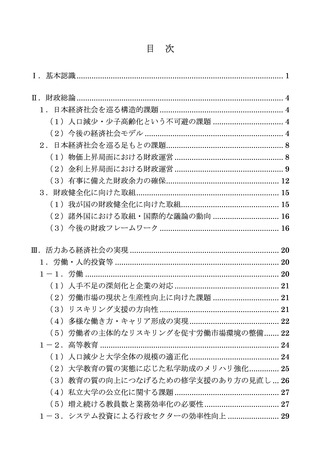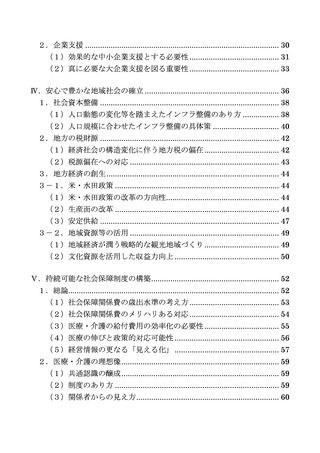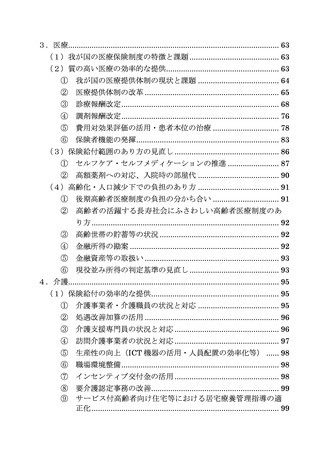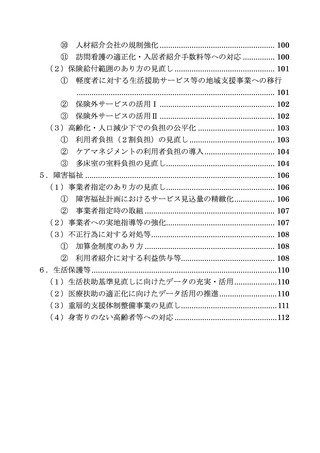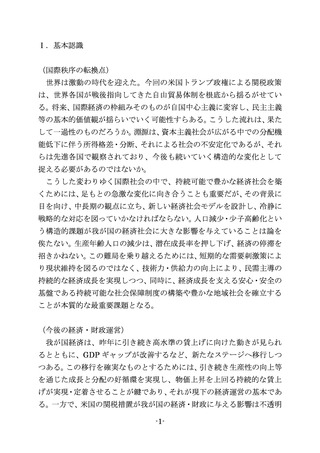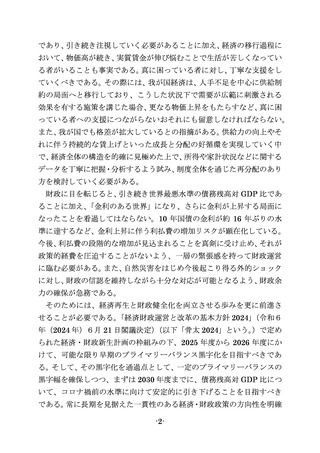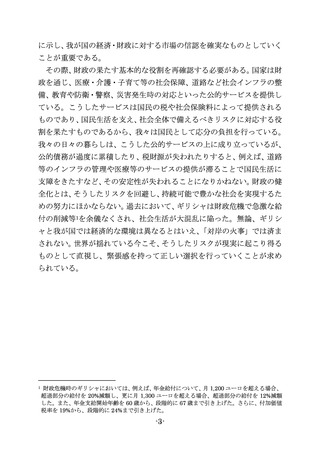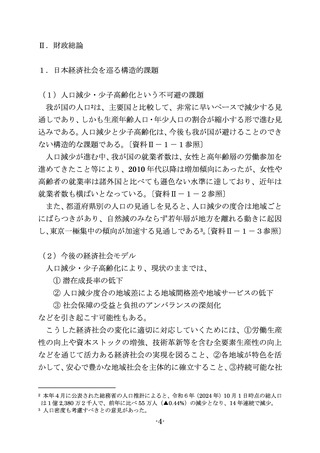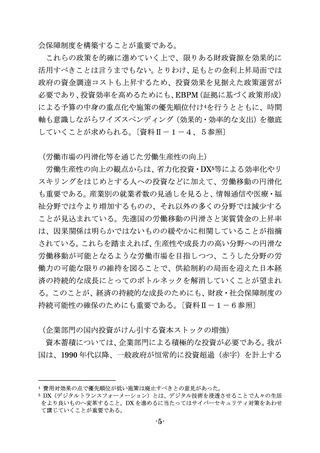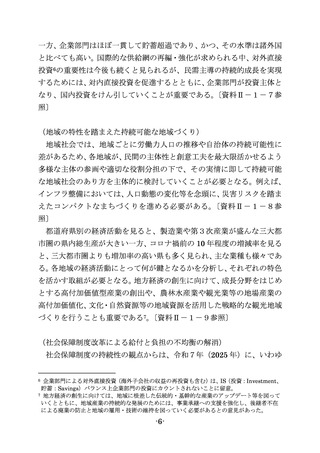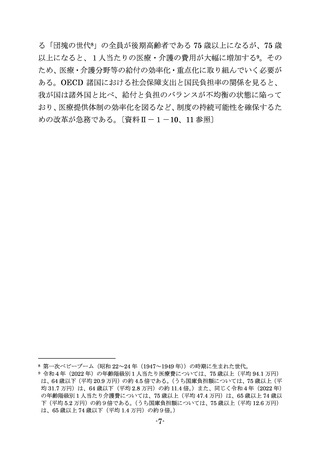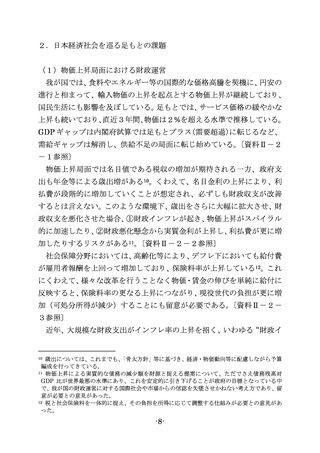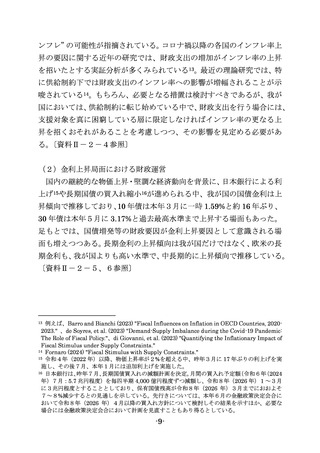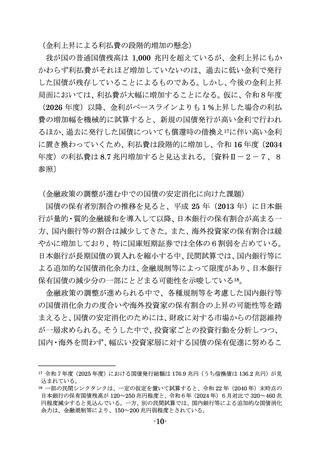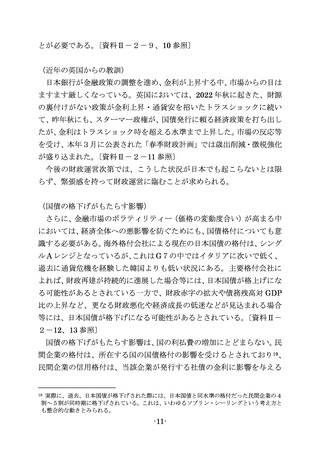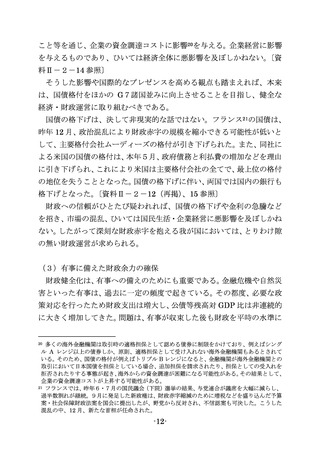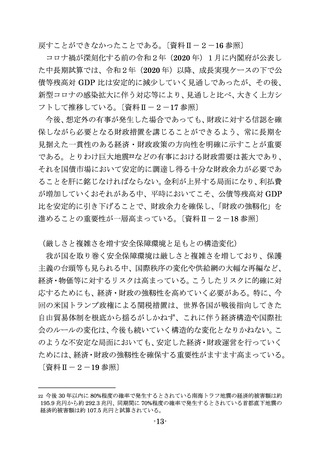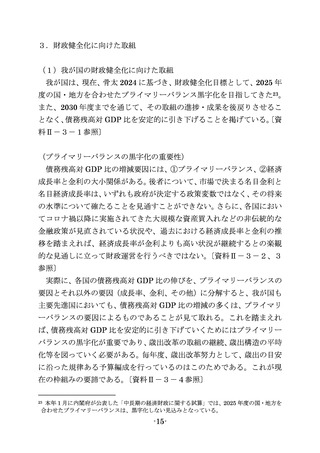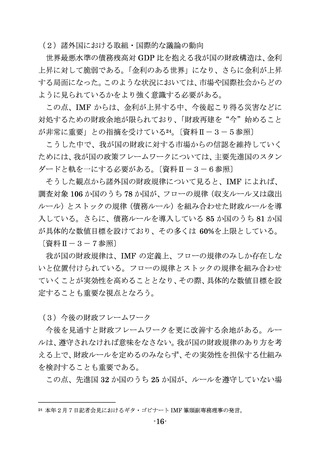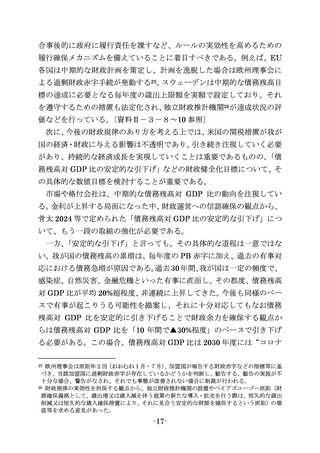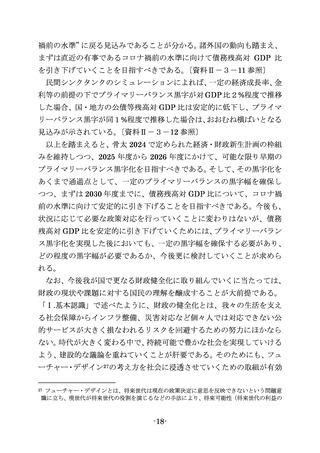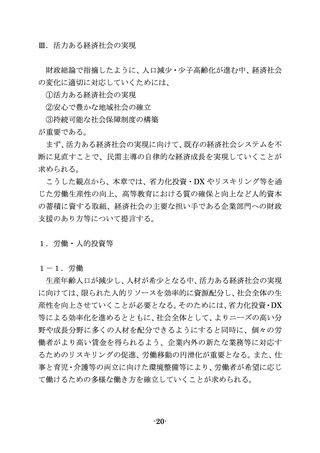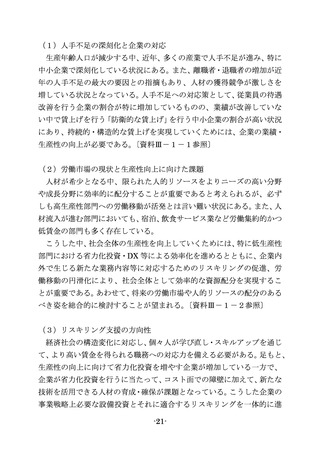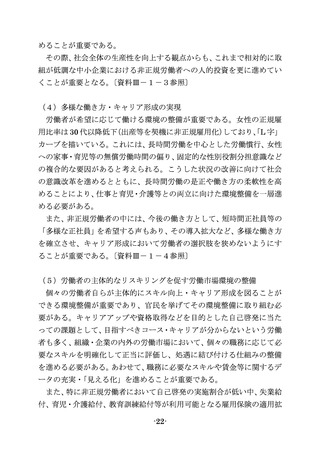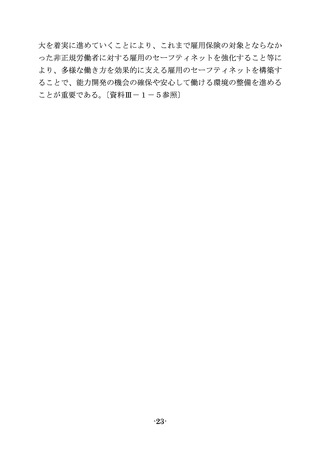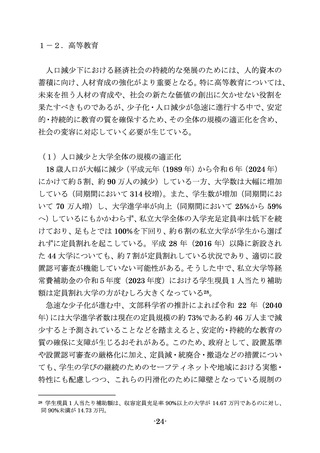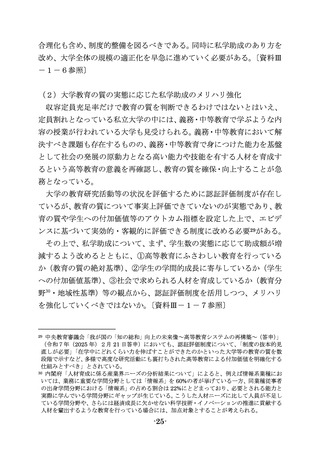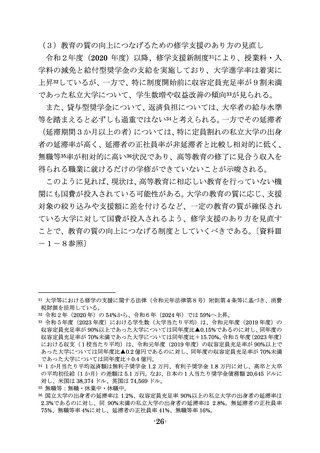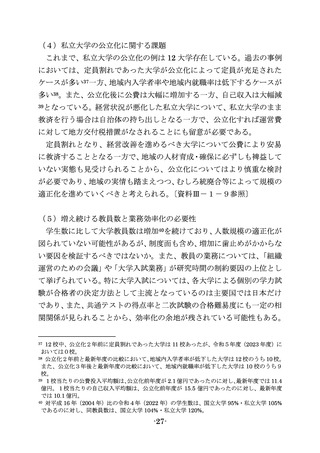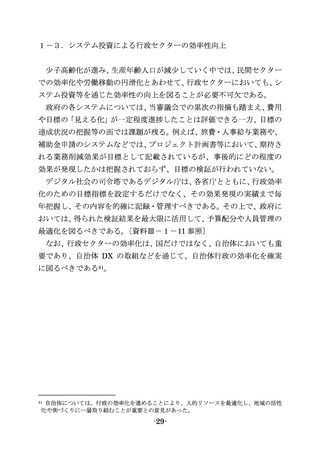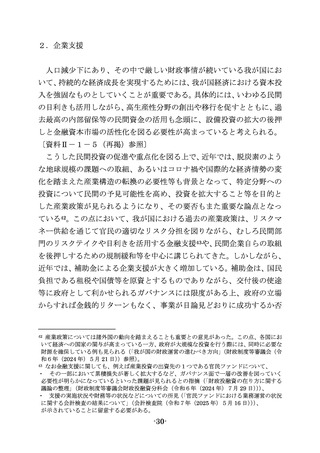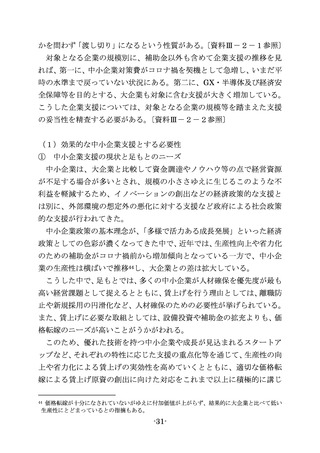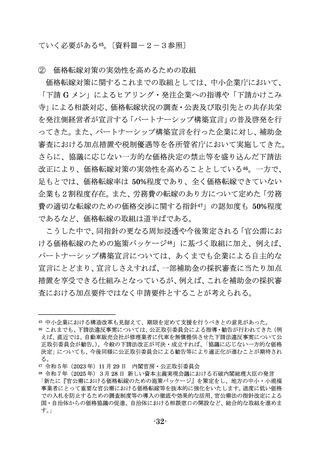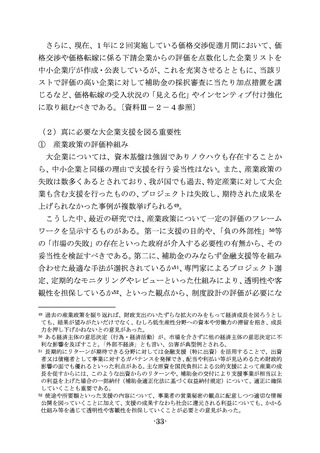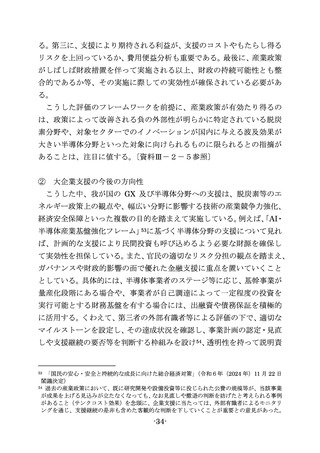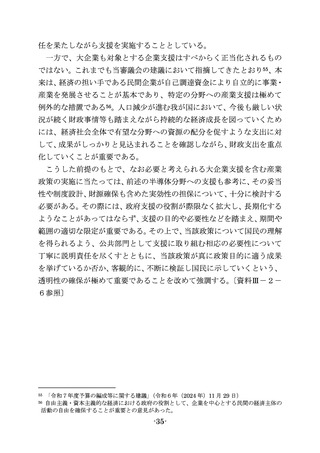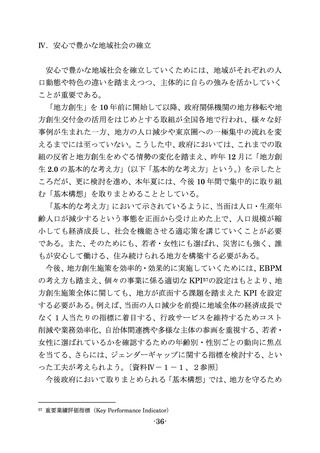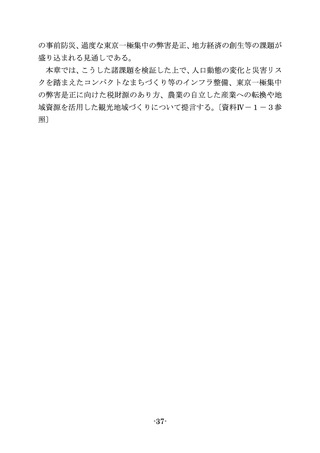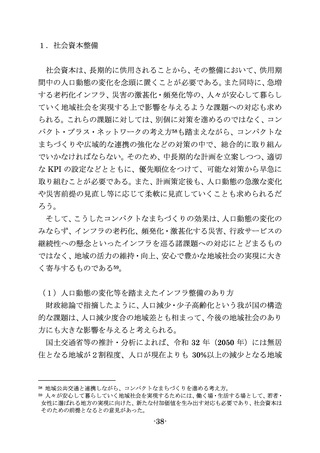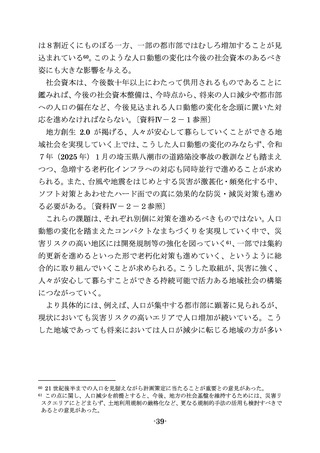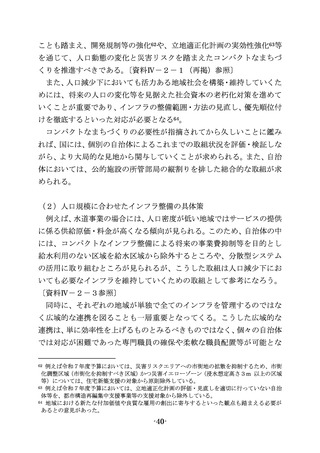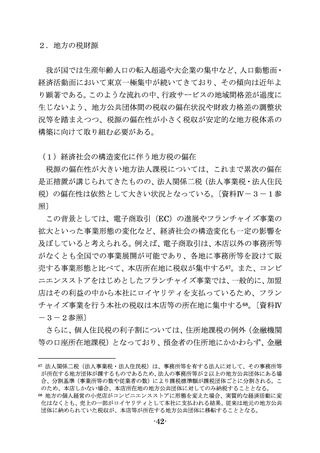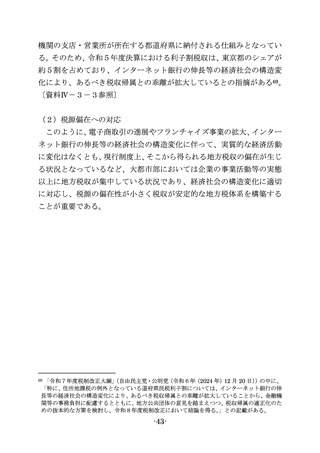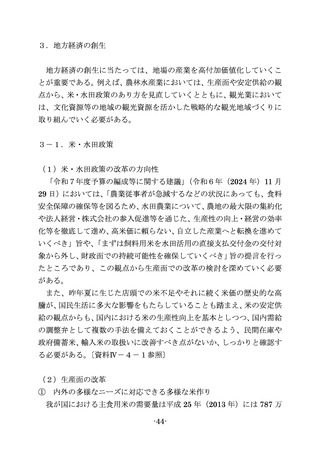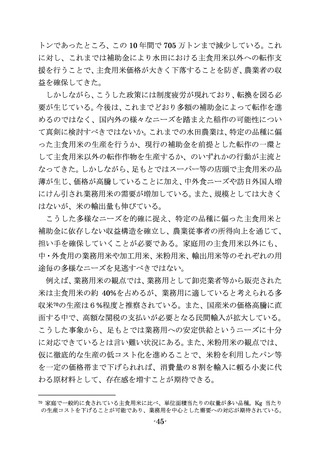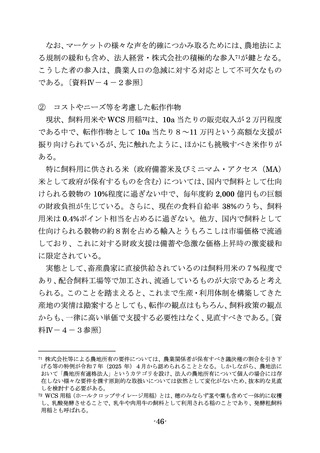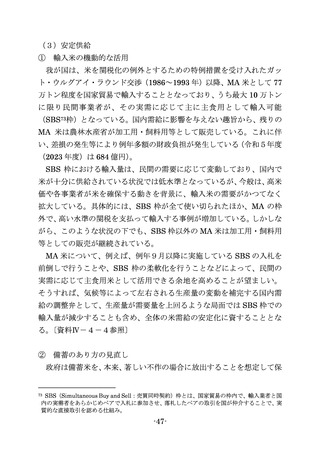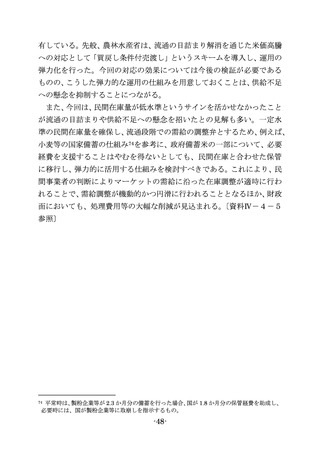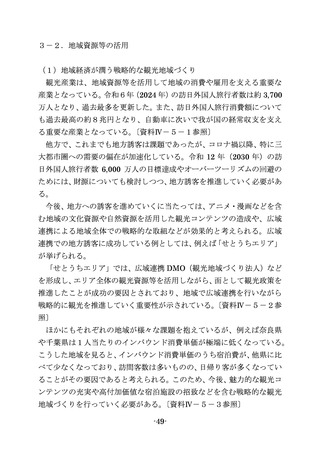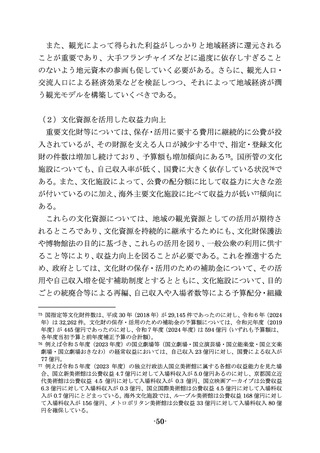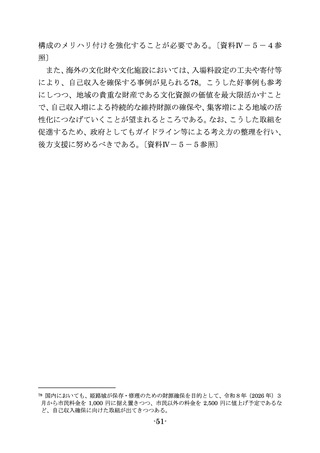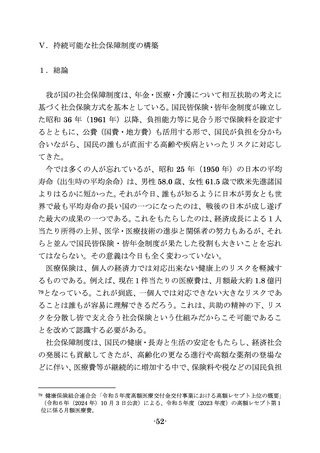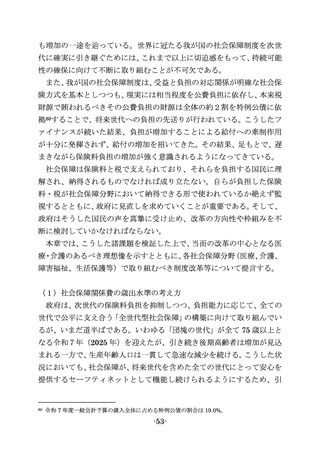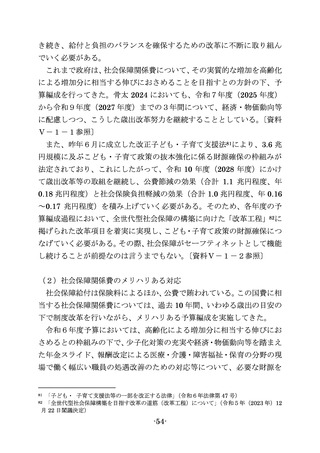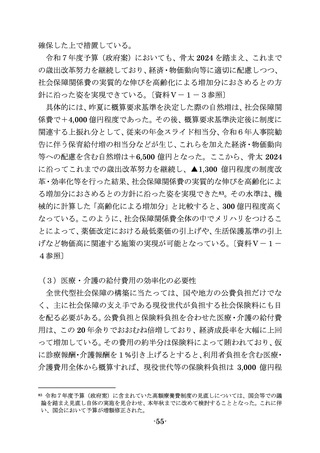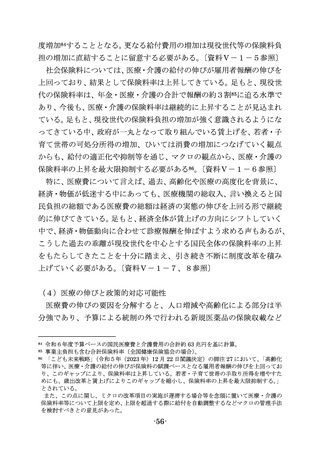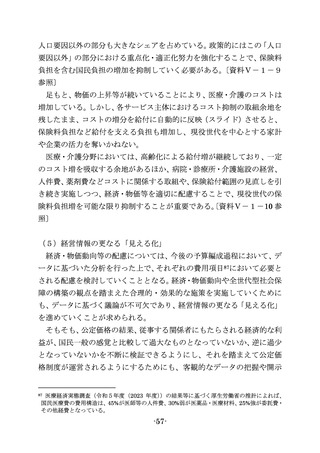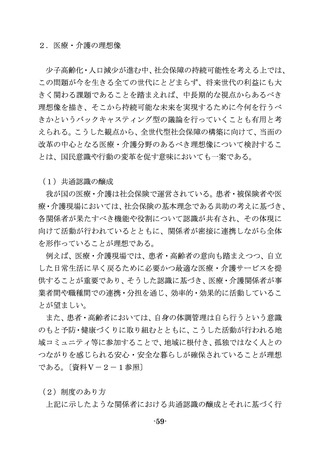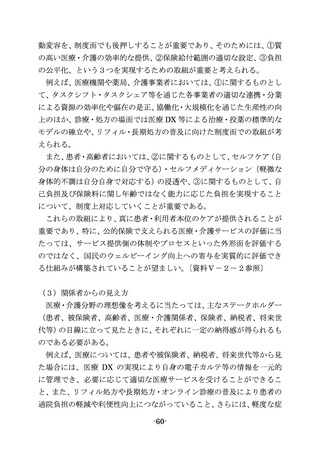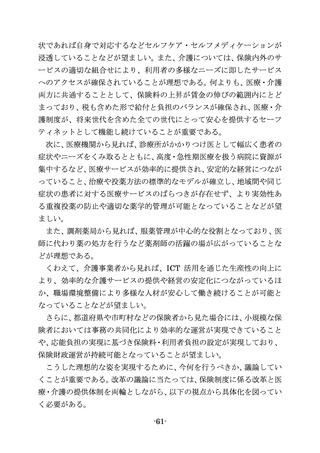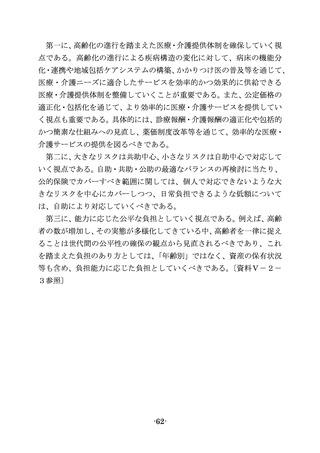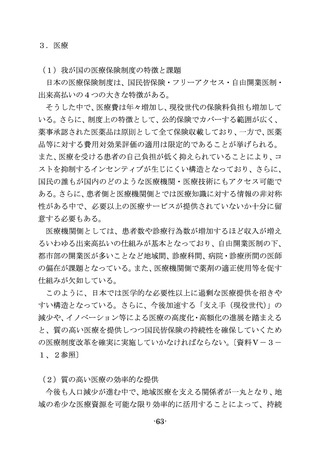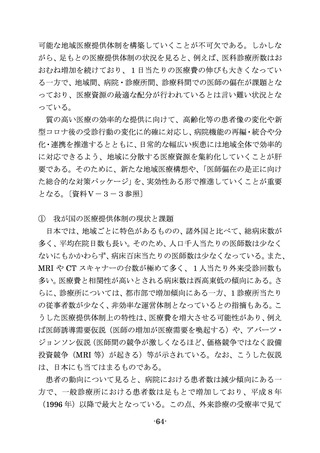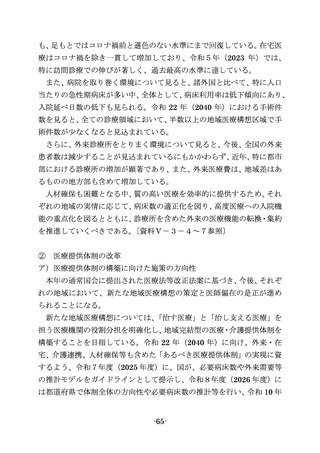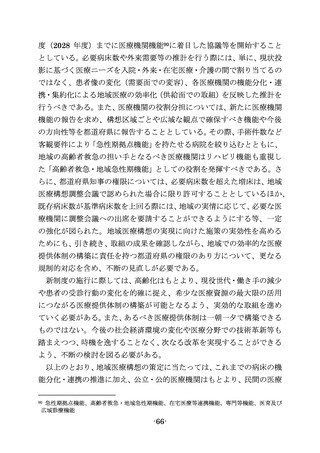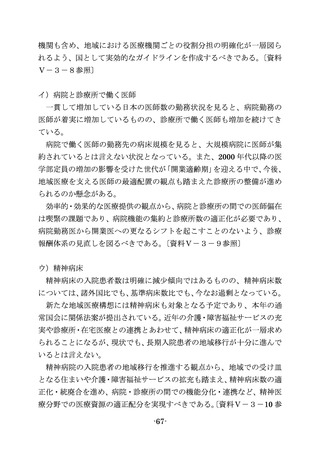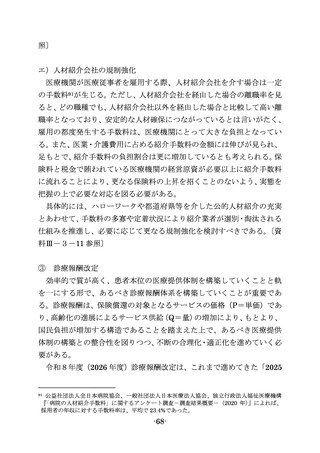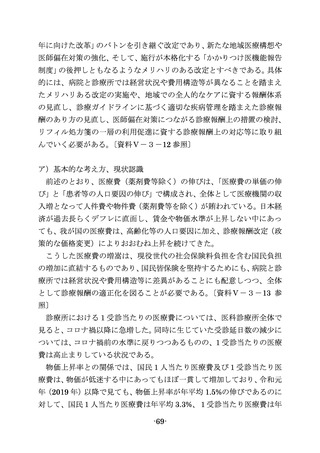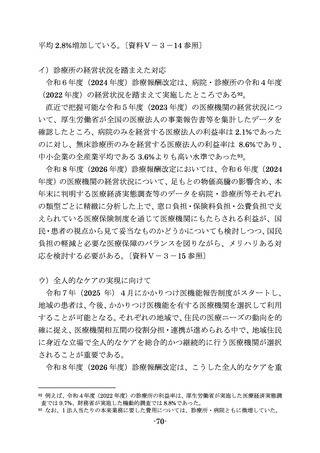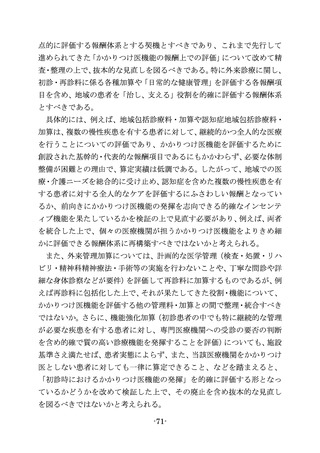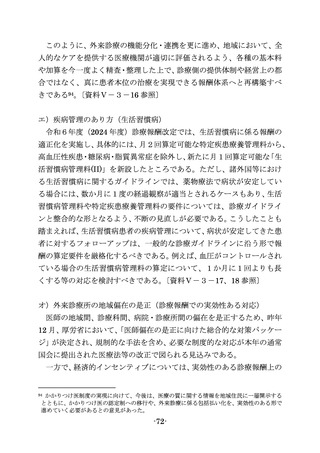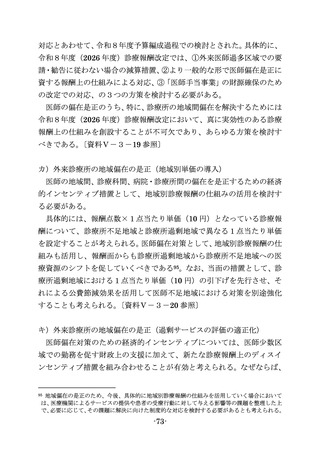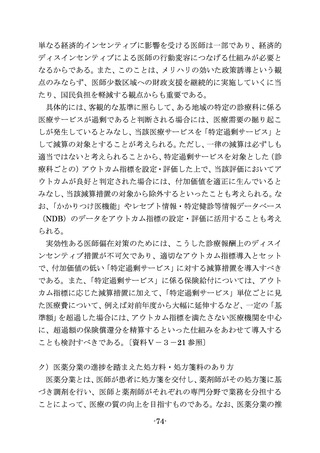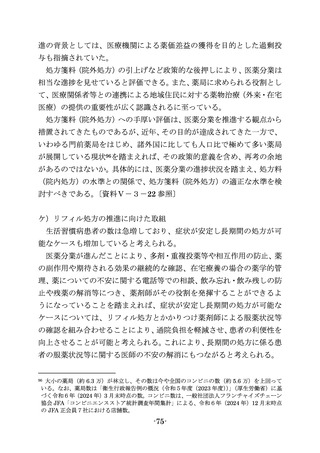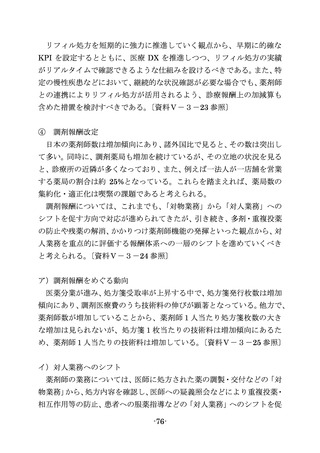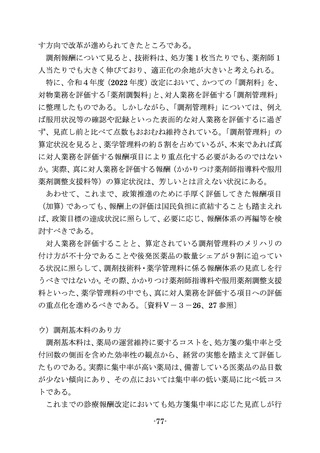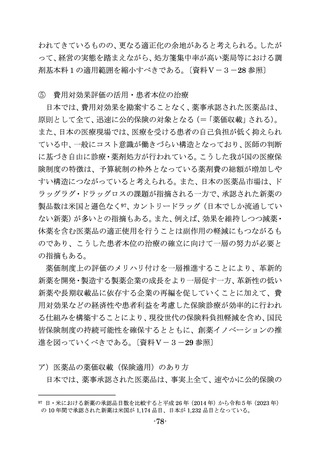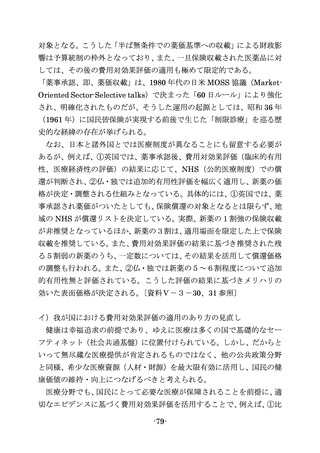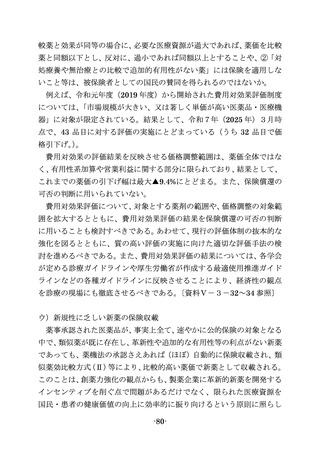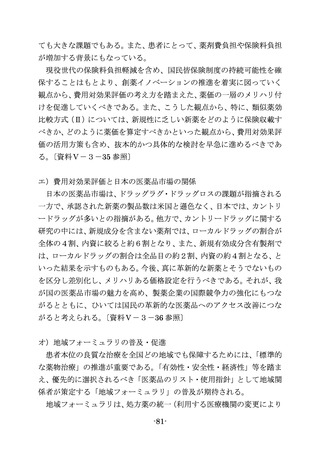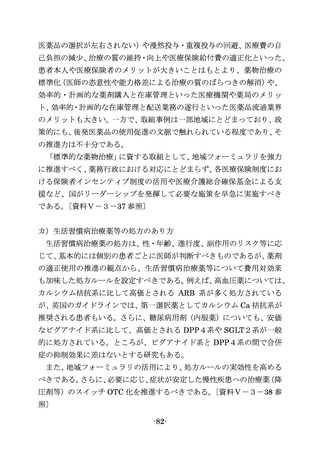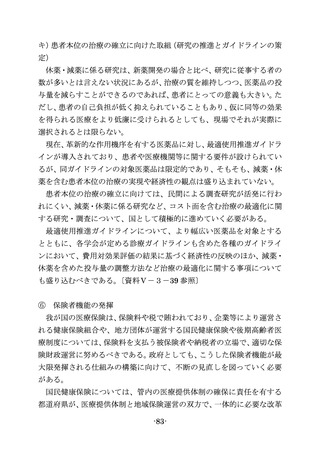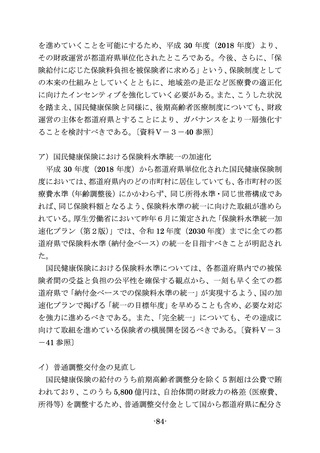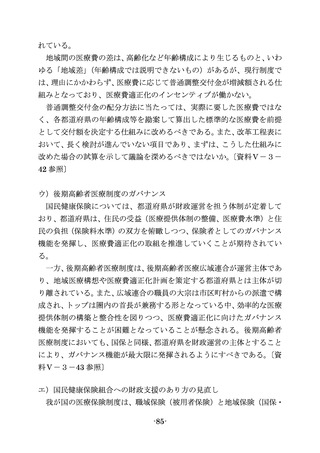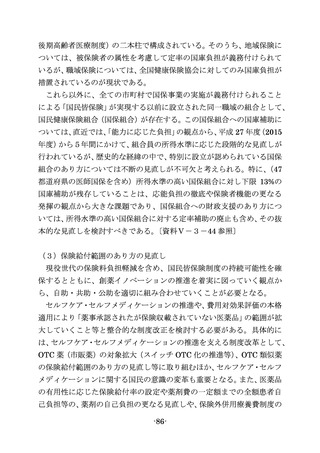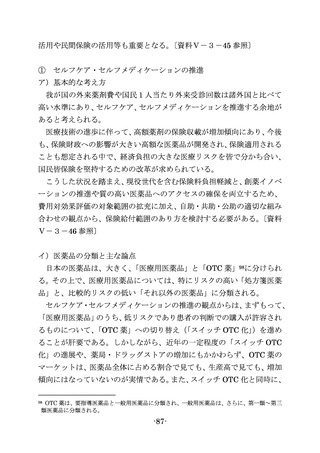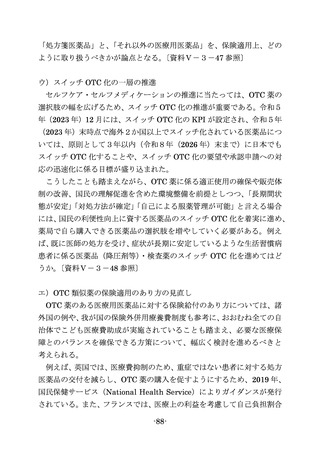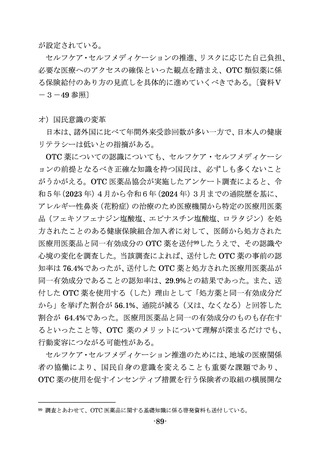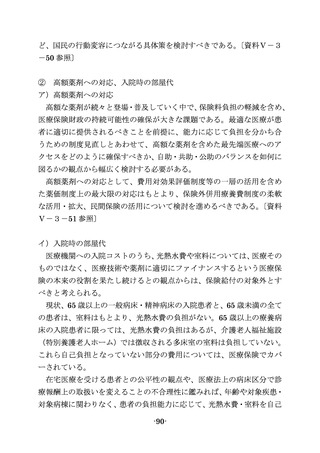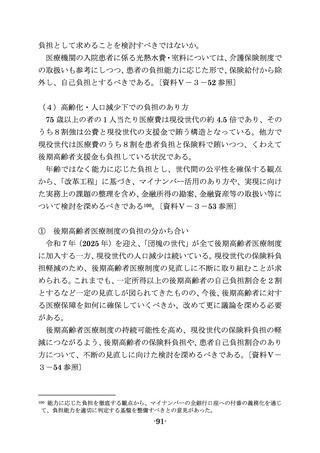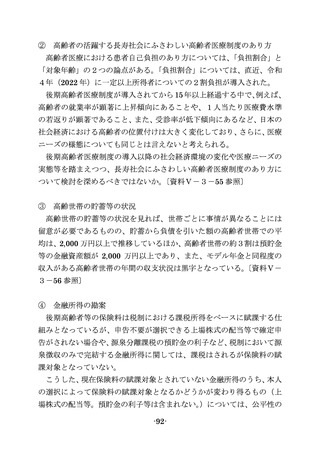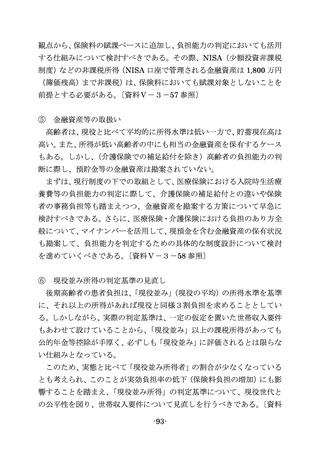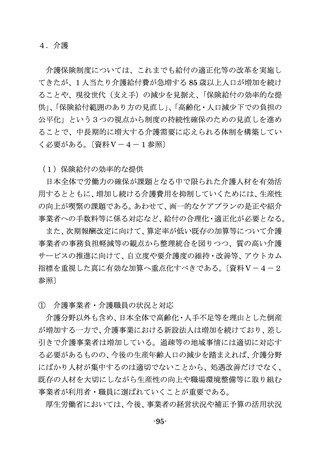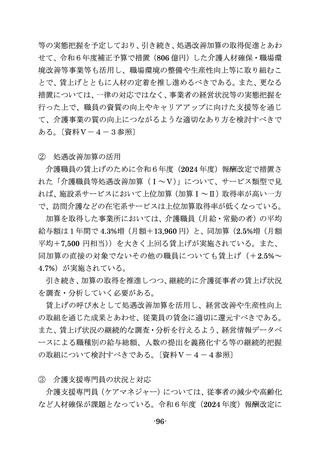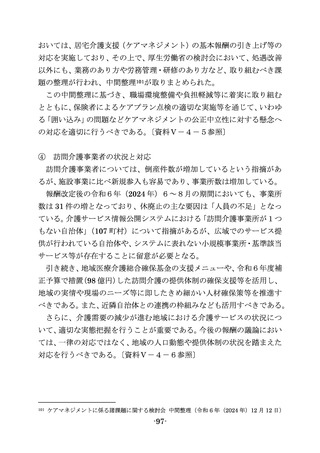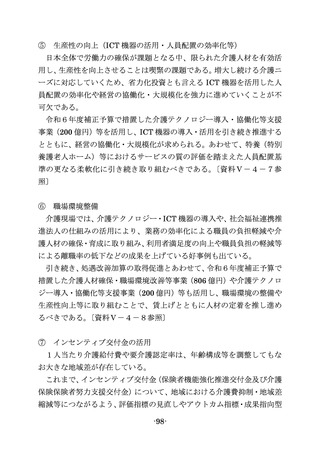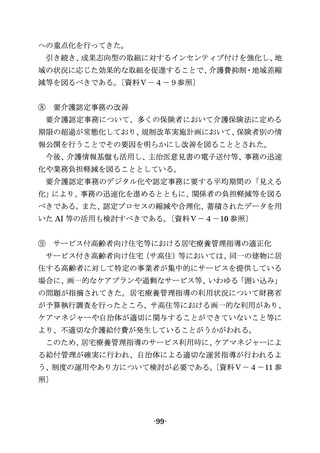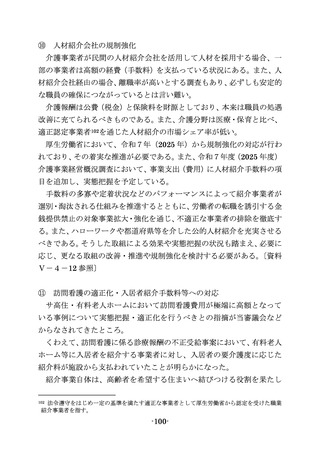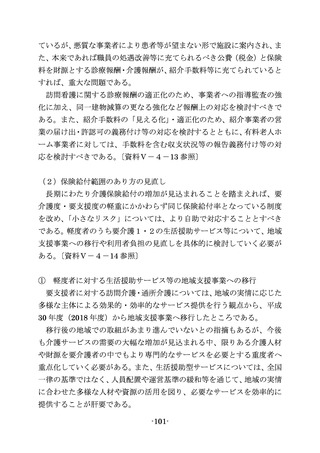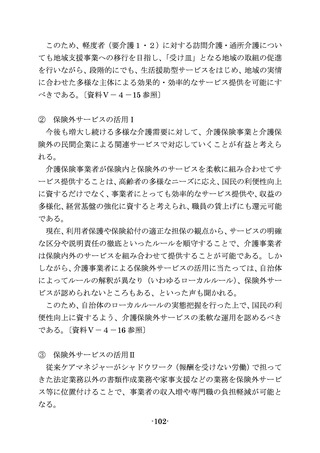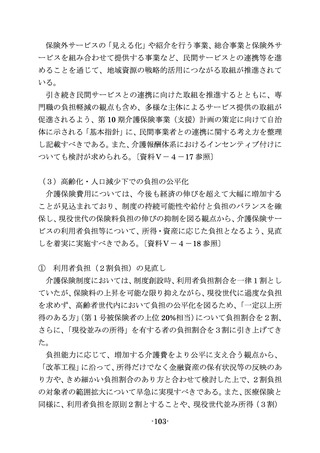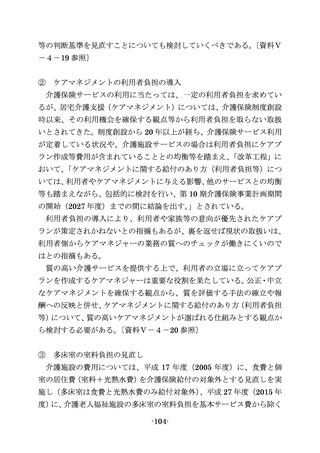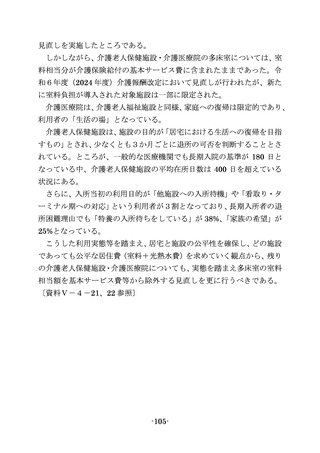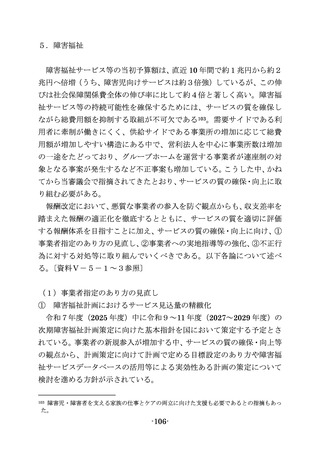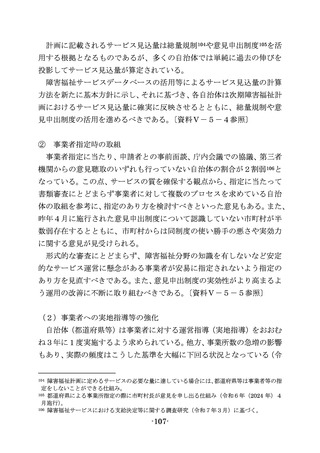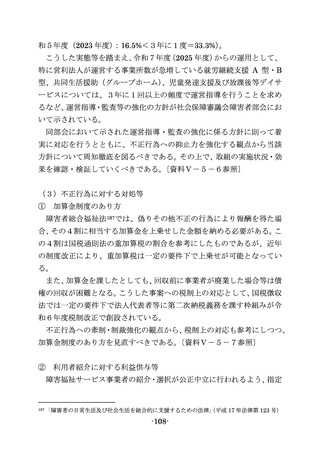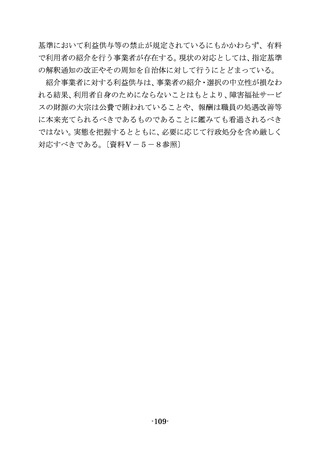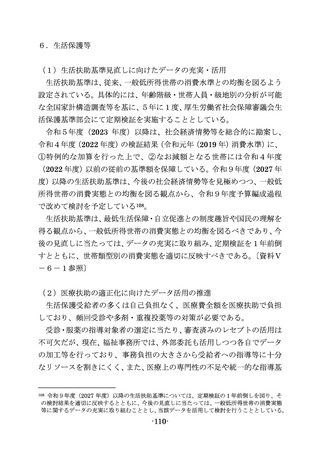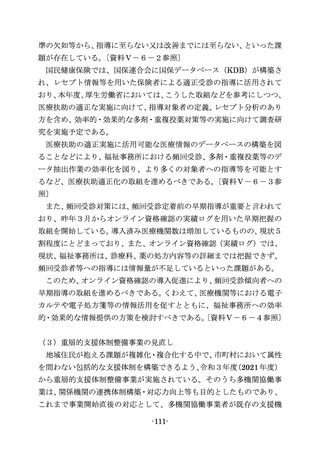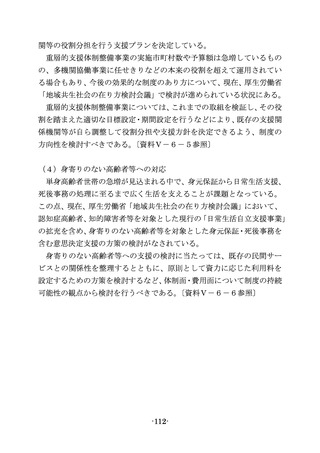激動の世界を見据えたあるべき財政運営 (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20250527/index.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度等分科会(答申・報告書等) 激動の世界を見据えたあるべき財政運営(5/27)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
代に確実に引き継ぐためには、これまで以上に切迫感をもって、持続可能
性の確保に向けて不断に取り組むことが不可欠である。
また、我が国の社会保障制度は、受益と負担の対応関係が明確な社会保
険方式を基本としつつも、現実には相当程度を公費負担に依存し、本来税
財源で賄われるべきその公費負担の財源は全体の約2割を特例公債に依
拠80することで、将来世代への負担の先送りが行われている。こうしたフ
ァイナンスが続いた結果、負担が増加することによる給付への牽制作用
が十分に発揮されず、給付の増加を招いてきた。その結果、足もとで、遅
まきながら保険料負担の増加が強く意識されるようになってきている。
社会保障は保険料と税で支えられており、それらを負担する国民に理
解され、納得されるものでなければ成り立たない。自らが負担した保険
料・税が社会保障分野において納得できる形で使われているか絶えず監
視するとともに、政府に見直しを求めていくことが重要である。そして、
政府はそうした国民の声を真摯に受け止め、改革の方向性や枠組みを不
断に検討していかなければならない。
本章では、こうした諸課題を検証した上で、当面の改革の中心となる医
療・介護のあるべき理想像を示すとともに、各社会保障分野(医療、介護、
障害福祉、生活保護等)で取り組むべき制度改革等について提言する。
(1)社会保障関係費の歳出水準の考え方
政府は、次世代の保険料負担を抑制しつつ、負担能力に応じて、全ての
世代で公平に支え合う「全世代型社会保障」の構築に向けて取り組んでい
るが、いまだ道半ばである。いわゆる「団塊の世代」が全て 75 歳以上と
なる令和7年(2025 年)を迎えたが、引き続き後期高齢者は増加が見込
まれる一方で、生産年齢人口は一貫して急速な減少を続ける。こうした状
況においても、社会保障が、将来世代を含めた全ての世代にとって安心を
提供するセーフティネットとして機能し続けられるようにするため、引
80
令和 7 年度一般会計予算の歳入全体に占める特例公債の割合は 19.0%。
-53-