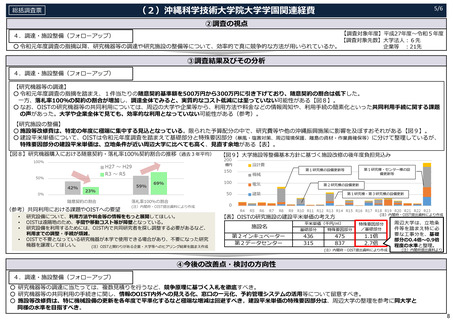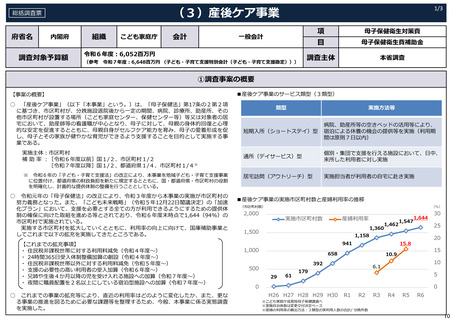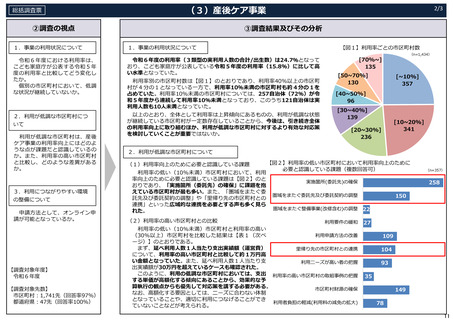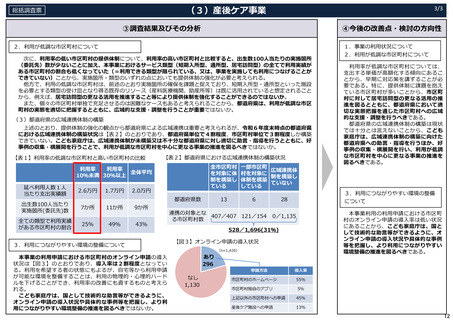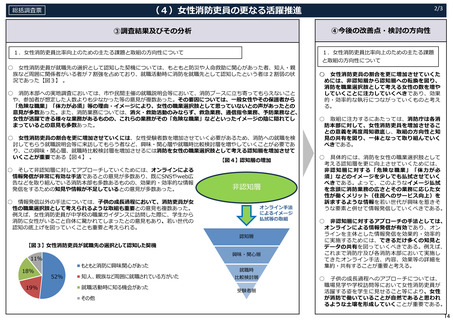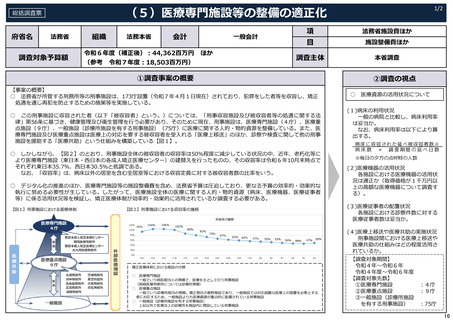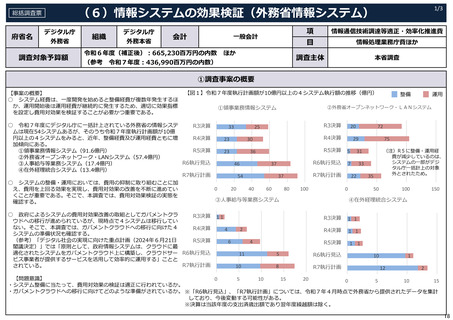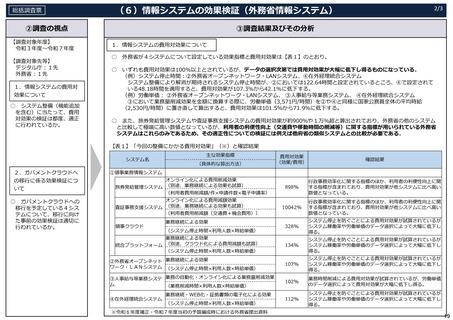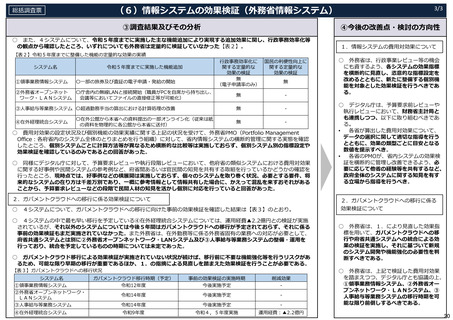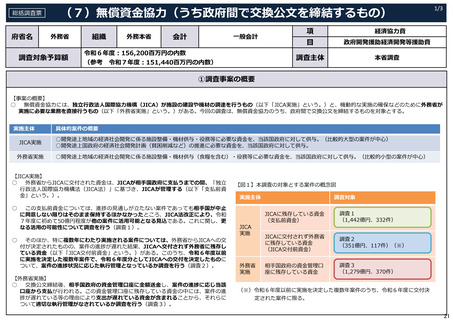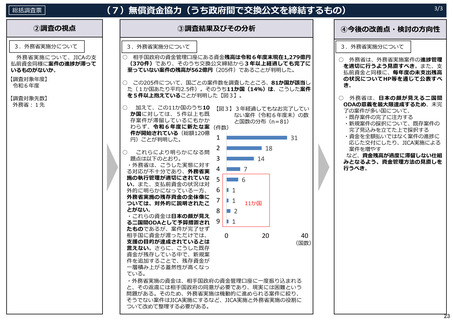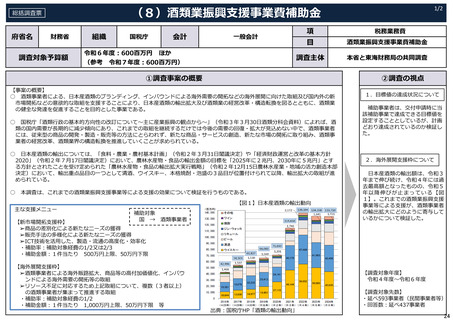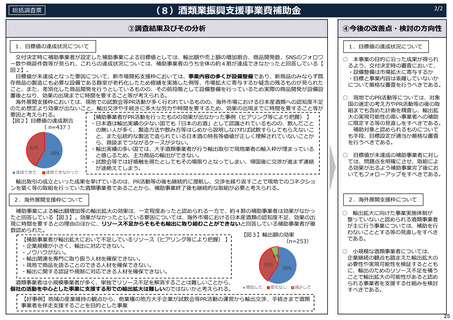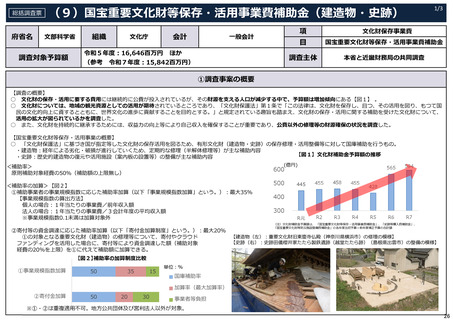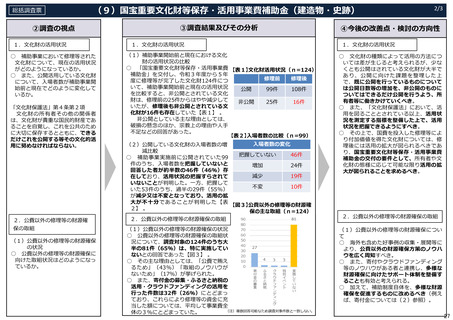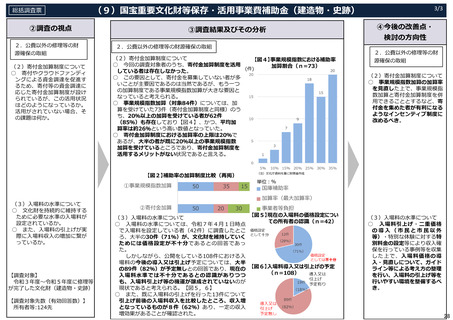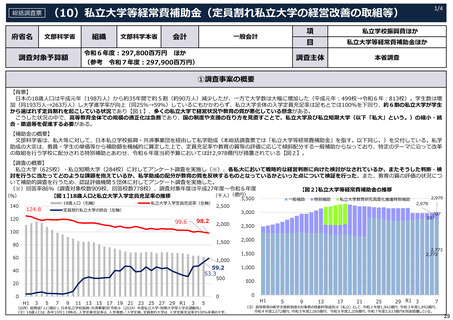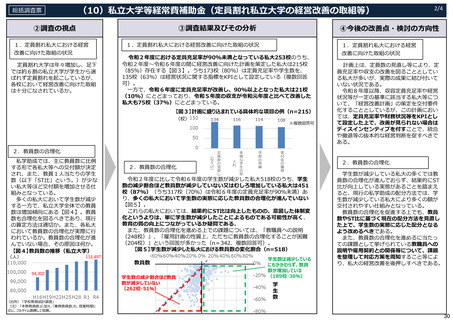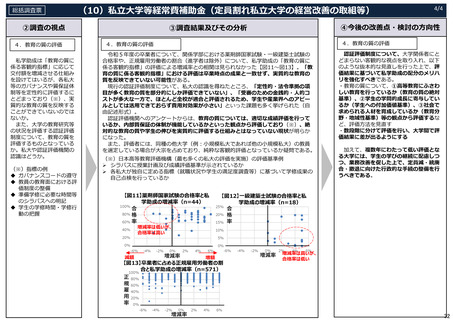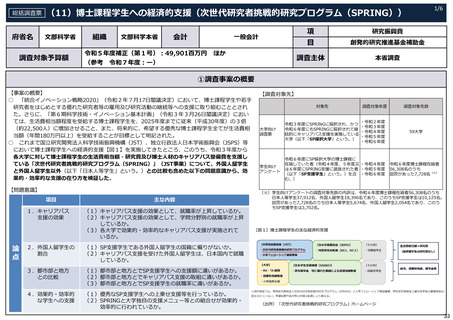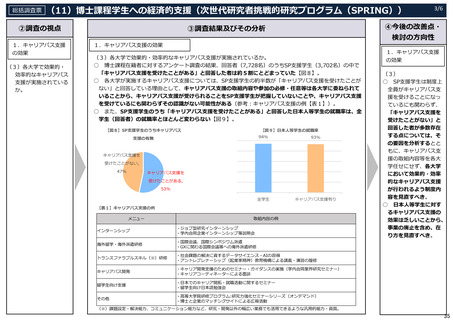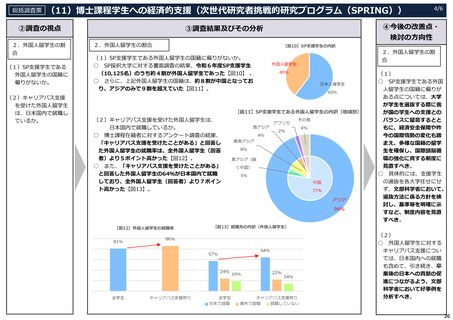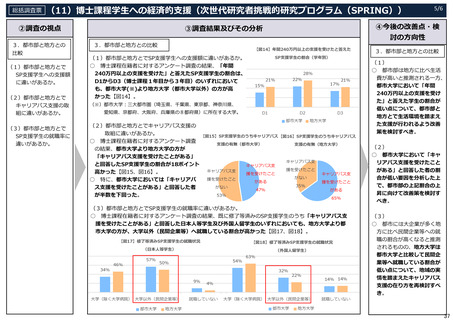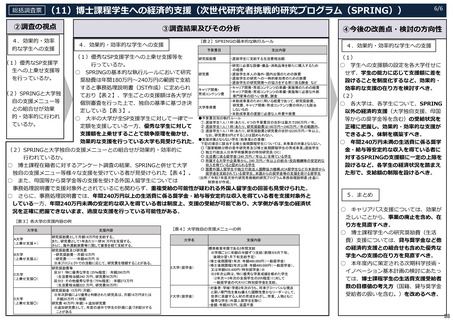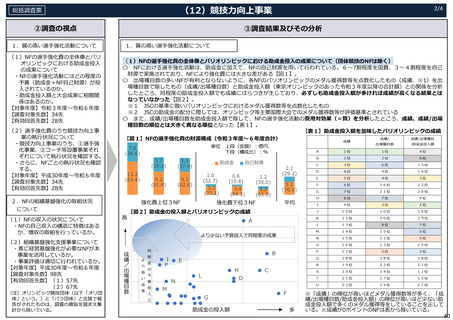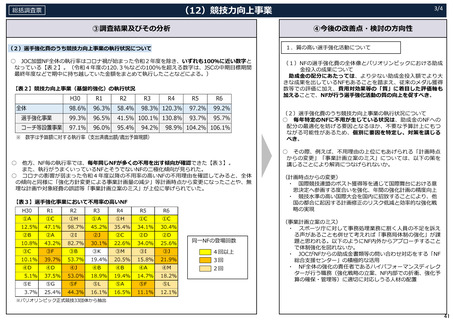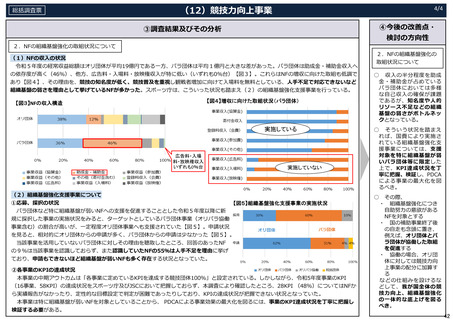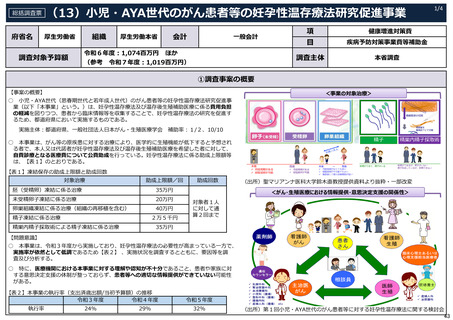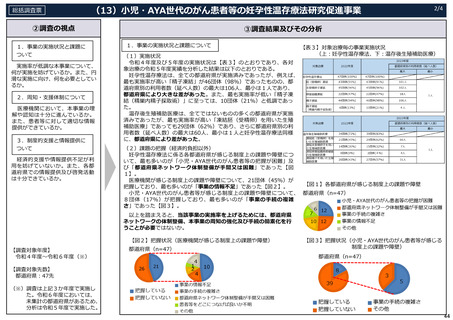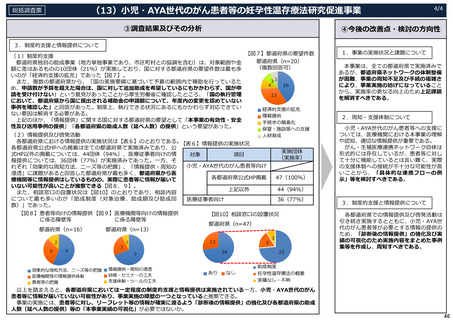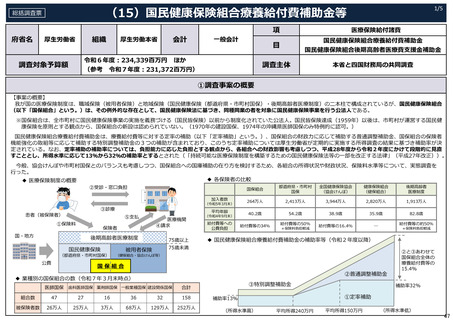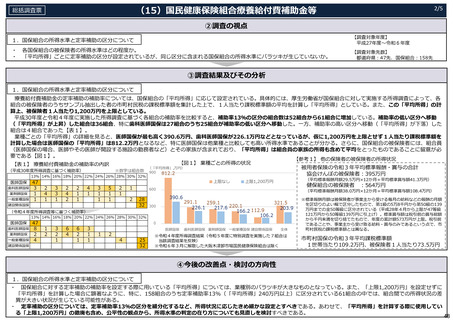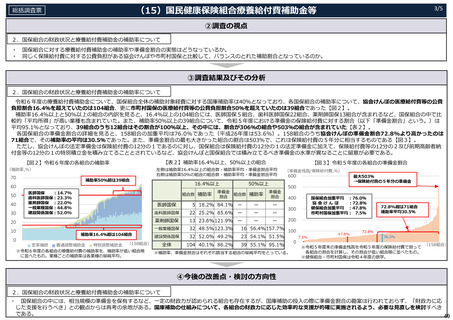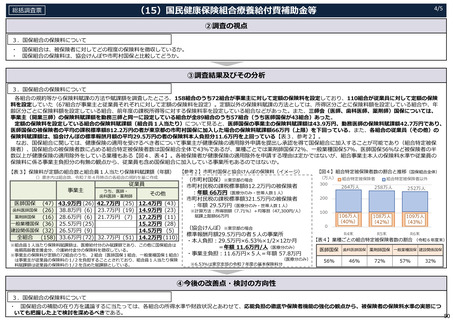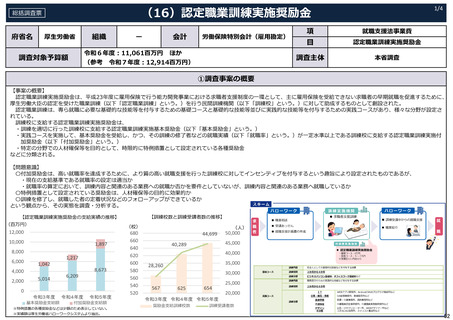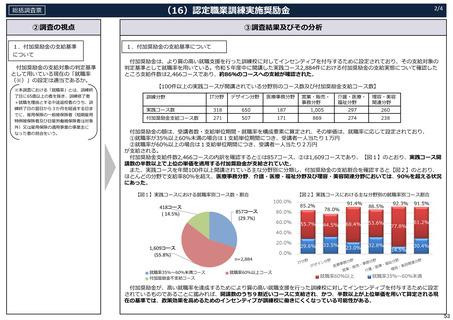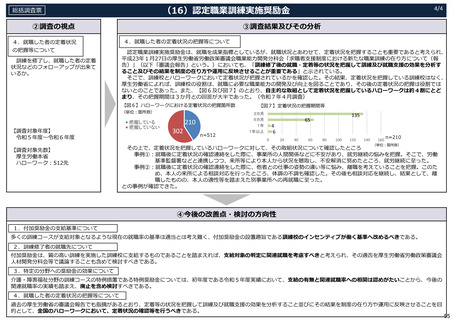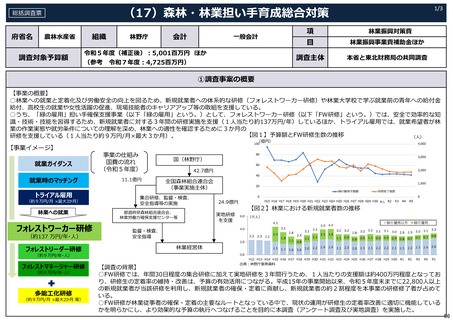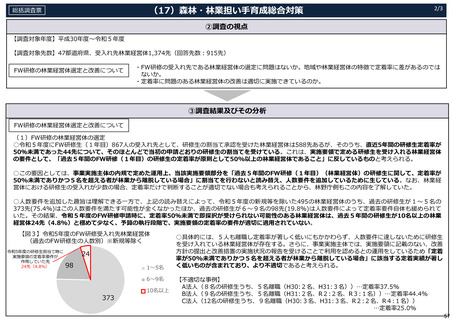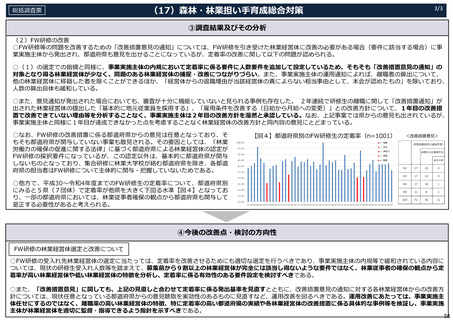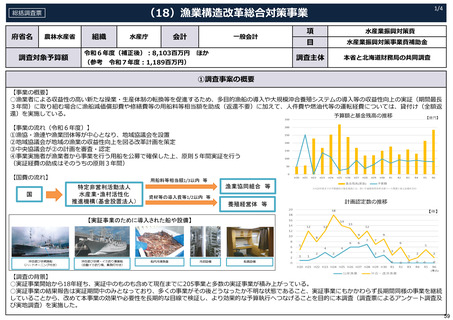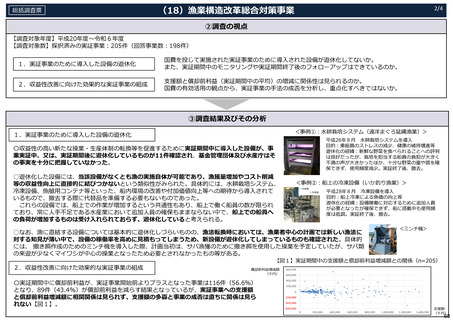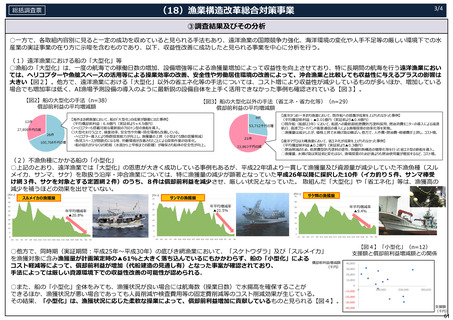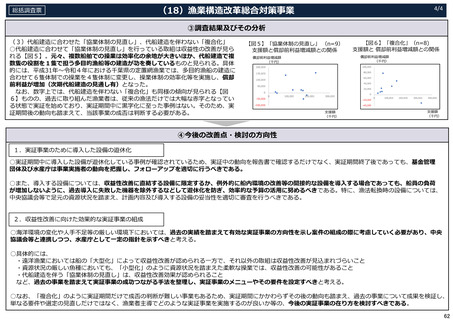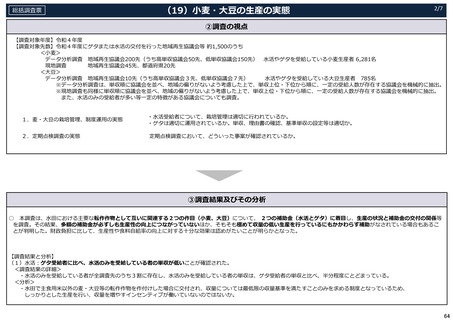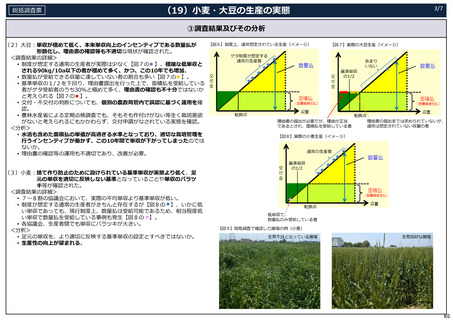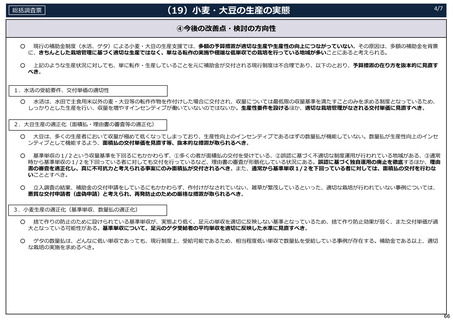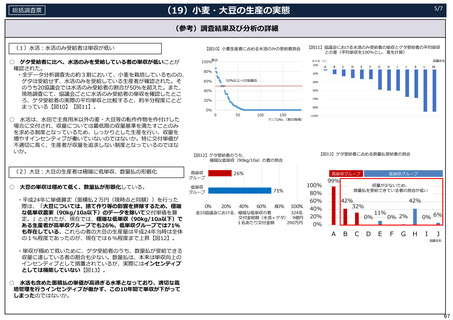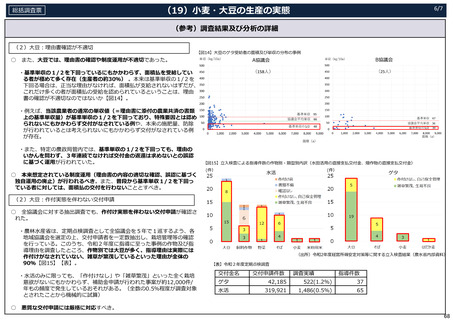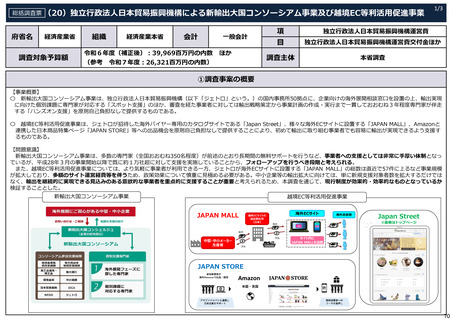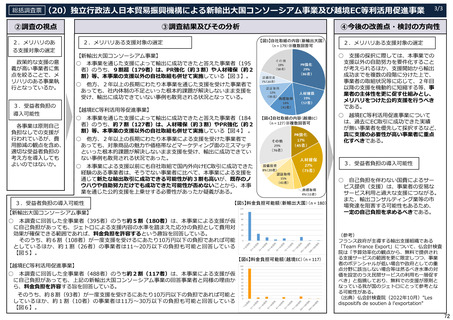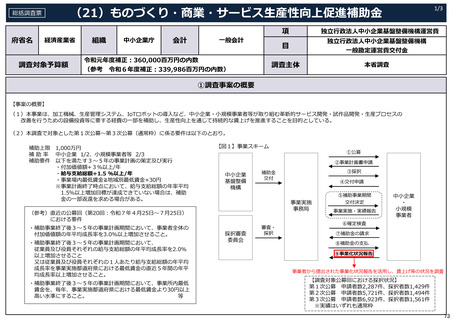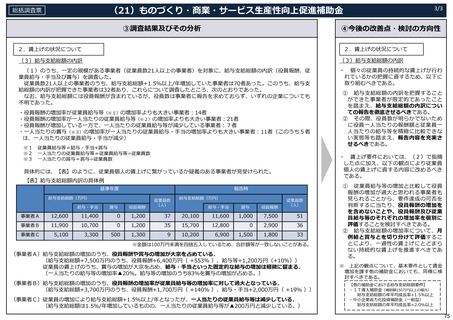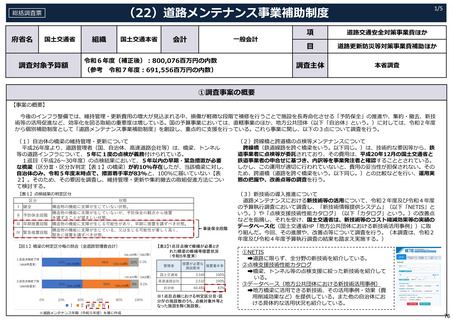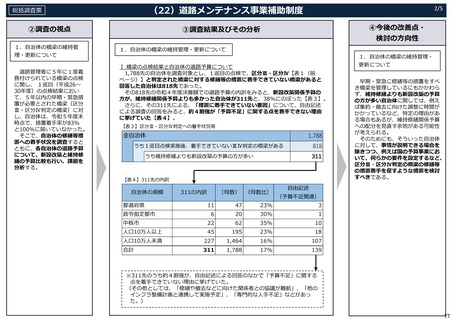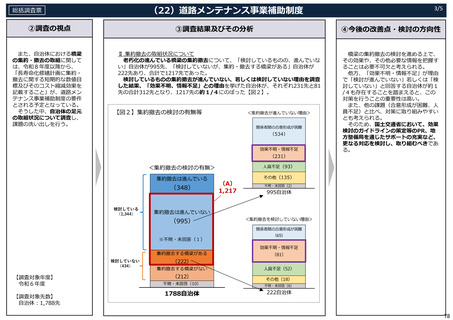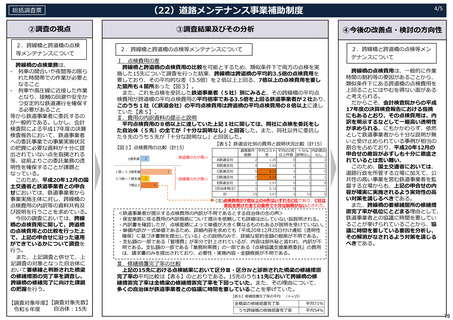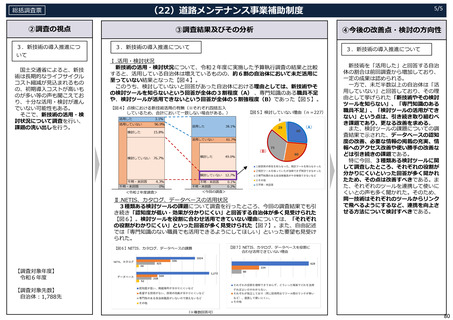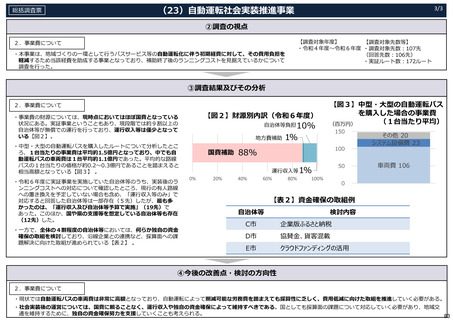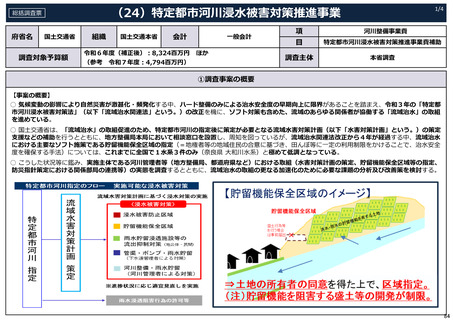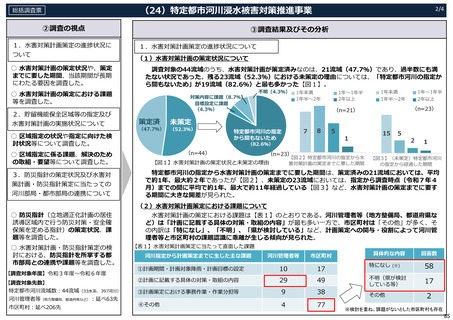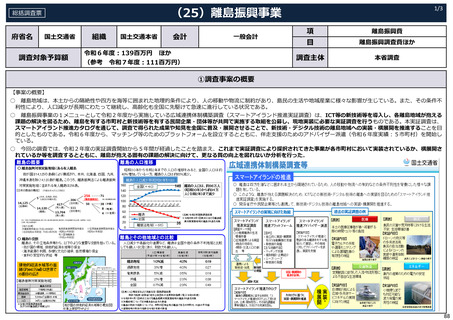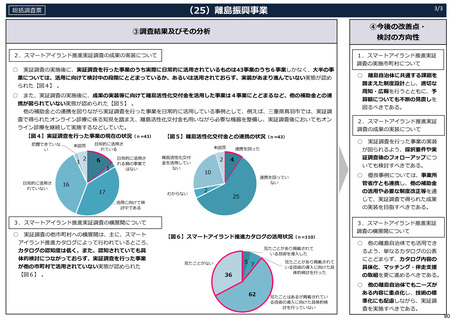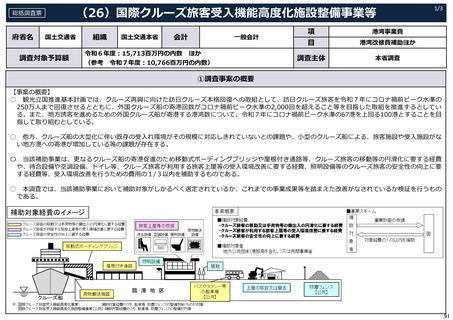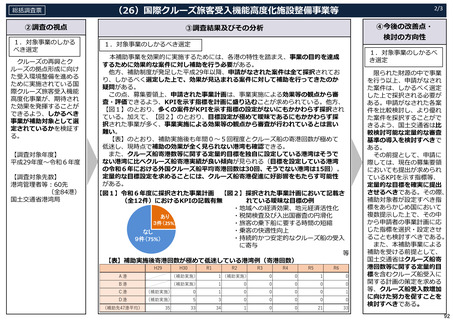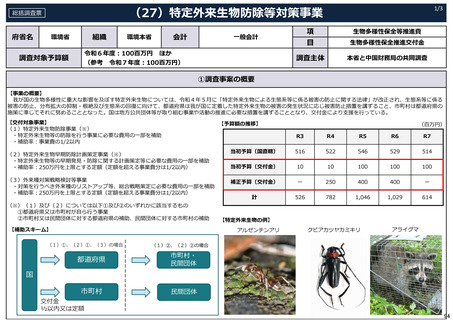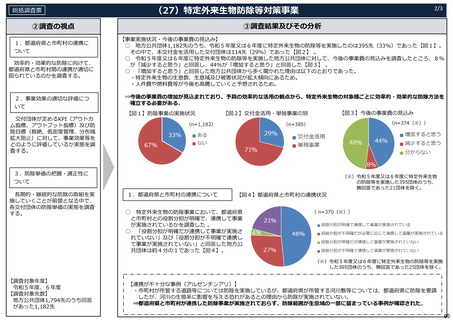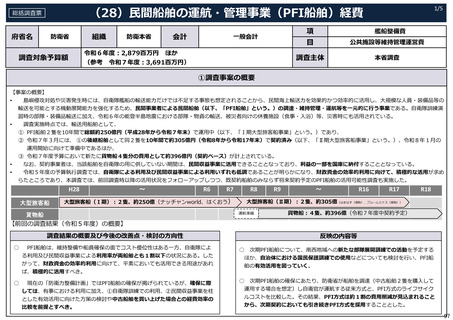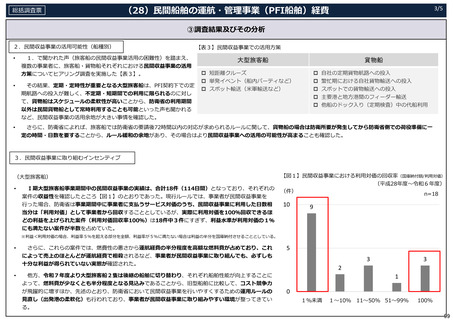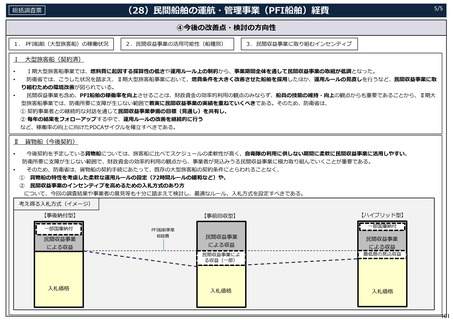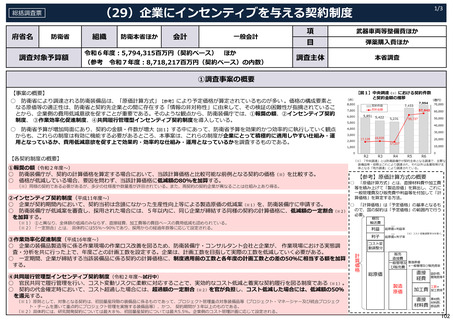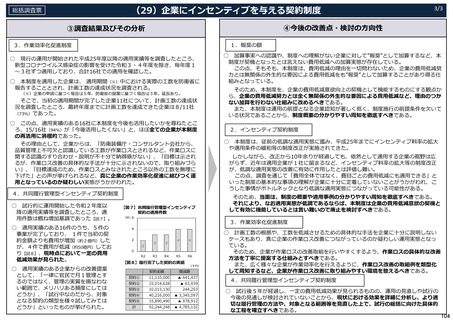よむ、つかう、まなぶ。
予算執行調査資料(総括調査票) (69 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |
| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
総括調査票
(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態
5/7
(参考)調査結果及び分析の詳細
(1)⽔活︓⽔活のみ受給者は単収が低い
○ ゲタ受給者に⽐べ、⽔活のみを受給している者の単収が低いことが
確認された。
・全データ分析調査先の約3割において、⼩⻨を栽培しているものの、
ゲタは受給せず、⽔活のみを受給している⽣産者が確認された。そ
のうち20協議会では⽔活のみ受給者の割合が50%を超えた。また、
現地調査にて、協議会ごとに⽔活のみ受給者の単収を確認したとこ
ろ、ゲタ受給者の実際の平均単収と⽐較すると、約半分程度にとど
まっている【図10】【図11】。
○ ⽔活は、⽔⽥で主⾷⽤⽶以外の⻨・⼤⾖等の転作作物を作付けした
場合に交付され、収量については最低限の収量基準を満たすことのみ
を求める制度となっているため、しっかりとした⽣産を⾏い、収量を
増やすインセンティブが働いていないのではないか。特に交付単価が
不適切に⾼く、⽣産者が収量を追求しない制度となっているのではな
いか。
(2)⼤⾖︓⼤⾖の⽣産者は極端に低単収、数量払の形骸化
○
⼤⾖の単収は極めて低く、数量払が形骸化している。
・平成24年に単価算定(⾯積払2万円(現時点と同額))を⾏った
際は、「⼤⾖については、捨て作り等の影響を排除するため、極端
な低単収農家(90kg/10a以下)のデータを除いて交付単価を算
定。」とされたが、現在では、極端な低単収(90kg/10a以下)で
ある⽣産者が⾼単収グループでも26%、低単収グループでは71%
も存在している。これらの者の⼤⾖の⽣産量は平成24年当時は全体
の1%程度であったのが、現在では6%程度まで上昇【図12】。
【図10】⼩⻨⽣産者に占める⽔活のみの受給者割合
割合
100%
【図11】協議会における⽔活のみ受給者の単収とゲタ受給者の平均単収
との差(平均単収を100%とし、差を計算)
10%
80%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
‐10%
50%以上→20協議会
60%
‐30%
40%
‐50%
20%
‐70%
0%
‐90%
0
50
100
150
サンプルNo.(割合降順)
【図12】ゲタ受給者のうち、
極端な低単収(90kg/10a)の者の割合
‐110%
【図13】ゲタ受給者に占める数量払受給者の割合
⾼単収
グループ
100%
80%
60%
40%
全10協議会における、極端な低単収の者
324名
20%
交付⾦総額(⽔活+ゲタ) 9億円
1名あたり交付⾦額
290万円
0%
低単収
グループ
協議会名
単収差(%)
⾼単収グループ
99%
低単収グループ
収量が少ないため、
数量払を受給できている者の割合が低い
42%
32%
42%
0%
A
B
C
D
11%
E
0% 6%
0% 2%
F
G
H
I
J
協議会名
・単収が極めて低いために、ゲタ受給者のうち、数量払が受給できる
収量に達している者の割合も少ない。数量払は、本来は単収向上の
インセンティブとして措置されているが、実際にはインセンティブ
としては機能していない【図13】。
○ ⽔活も含めた⾯積払の単価が⾼過ぎる⽔準となっており、適切な栽
培管理を⾏うインセンティブが働かず、この10年間で単収が下がって
しまったのではないか。
67
(19)⼩⻨・⼤⾖の⽣産の実態
5/7
(参考)調査結果及び分析の詳細
(1)⽔活︓⽔活のみ受給者は単収が低い
○ ゲタ受給者に⽐べ、⽔活のみを受給している者の単収が低いことが
確認された。
・全データ分析調査先の約3割において、⼩⻨を栽培しているものの、
ゲタは受給せず、⽔活のみを受給している⽣産者が確認された。そ
のうち20協議会では⽔活のみ受給者の割合が50%を超えた。また、
現地調査にて、協議会ごとに⽔活のみ受給者の単収を確認したとこ
ろ、ゲタ受給者の実際の平均単収と⽐較すると、約半分程度にとど
まっている【図10】【図11】。
○ ⽔活は、⽔⽥で主⾷⽤⽶以外の⻨・⼤⾖等の転作作物を作付けした
場合に交付され、収量については最低限の収量基準を満たすことのみ
を求める制度となっているため、しっかりとした⽣産を⾏い、収量を
増やすインセンティブが働いていないのではないか。特に交付単価が
不適切に⾼く、⽣産者が収量を追求しない制度となっているのではな
いか。
(2)⼤⾖︓⼤⾖の⽣産者は極端に低単収、数量払の形骸化
○
⼤⾖の単収は極めて低く、数量払が形骸化している。
・平成24年に単価算定(⾯積払2万円(現時点と同額))を⾏った
際は、「⼤⾖については、捨て作り等の影響を排除するため、極端
な低単収農家(90kg/10a以下)のデータを除いて交付単価を算
定。」とされたが、現在では、極端な低単収(90kg/10a以下)で
ある⽣産者が⾼単収グループでも26%、低単収グループでは71%
も存在している。これらの者の⼤⾖の⽣産量は平成24年当時は全体
の1%程度であったのが、現在では6%程度まで上昇【図12】。
【図10】⼩⻨⽣産者に占める⽔活のみの受給者割合
割合
100%
【図11】協議会における⽔活のみ受給者の単収とゲタ受給者の平均単収
との差(平均単収を100%とし、差を計算)
10%
80%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
‐10%
50%以上→20協議会
60%
‐30%
40%
‐50%
20%
‐70%
0%
‐90%
0
50
100
150
サンプルNo.(割合降順)
【図12】ゲタ受給者のうち、
極端な低単収(90kg/10a)の者の割合
‐110%
【図13】ゲタ受給者に占める数量払受給者の割合
⾼単収
グループ
100%
80%
60%
40%
全10協議会における、極端な低単収の者
324名
20%
交付⾦総額(⽔活+ゲタ) 9億円
1名あたり交付⾦額
290万円
0%
低単収
グループ
協議会名
単収差(%)
⾼単収グループ
99%
低単収グループ
収量が少ないため、
数量払を受給できている者の割合が低い
42%
32%
42%
0%
A
B
C
D
11%
E
0% 6%
0% 2%
F
G
H
I
J
協議会名
・単収が極めて低いために、ゲタ受給者のうち、数量払が受給できる
収量に達している者の割合も少ない。数量払は、本来は単収向上の
インセンティブとして措置されているが、実際にはインセンティブ
としては機能していない【図13】。
○ ⽔活も含めた⾯積払の単価が⾼過ぎる⽔準となっており、適切な栽
培管理を⾏うインセンティブが働かず、この10年間で単収が下がって
しまったのではないか。
67