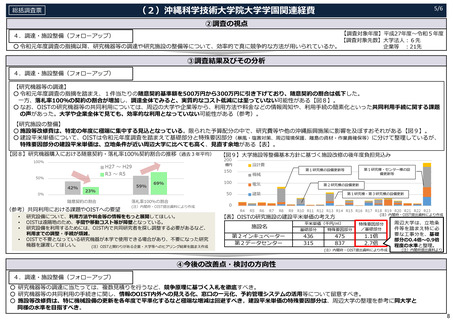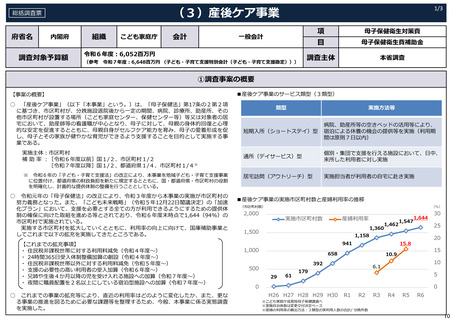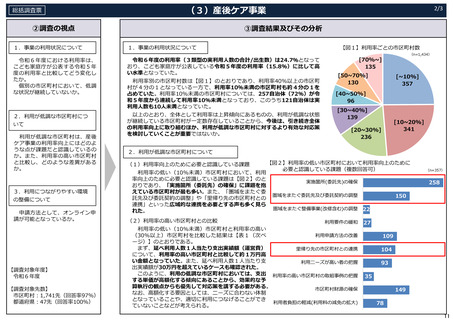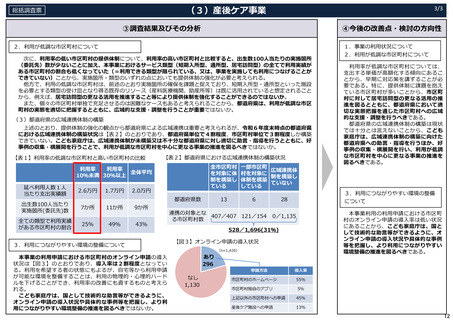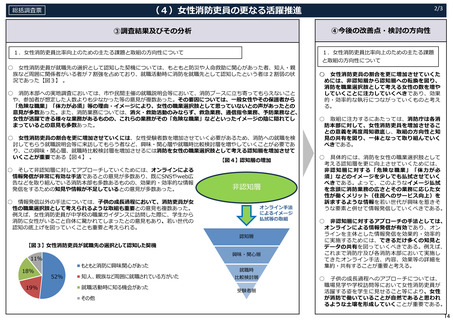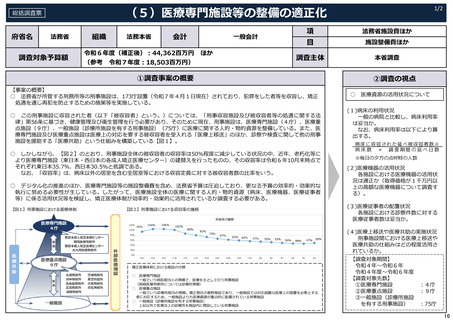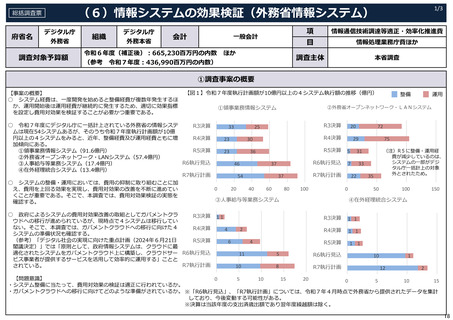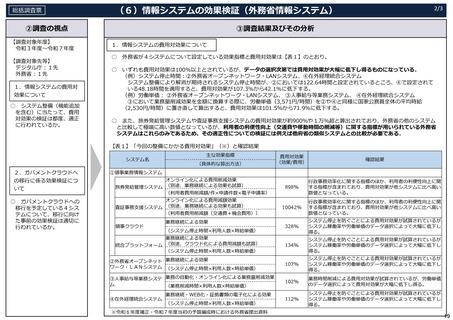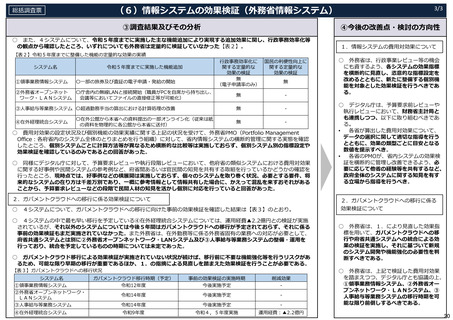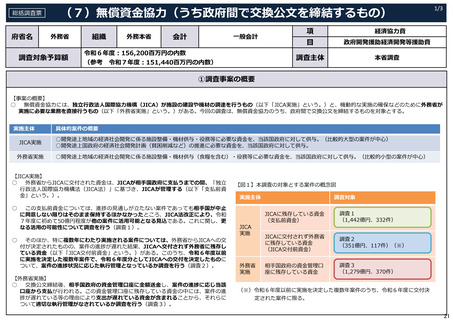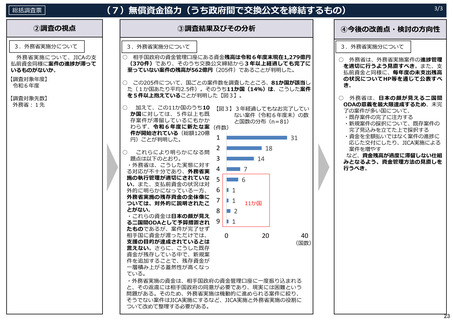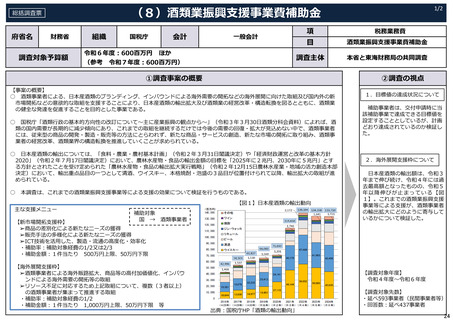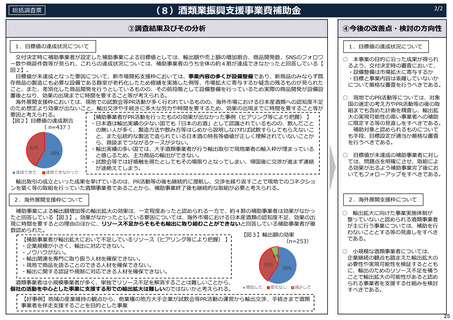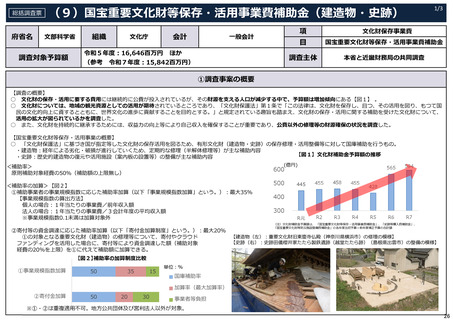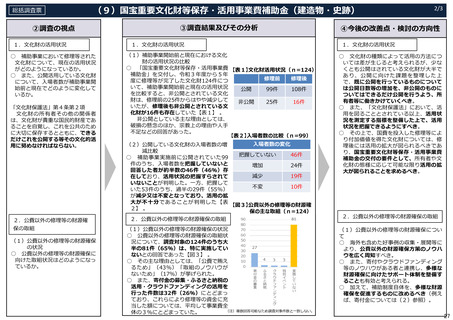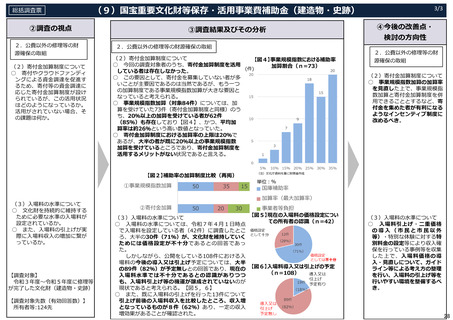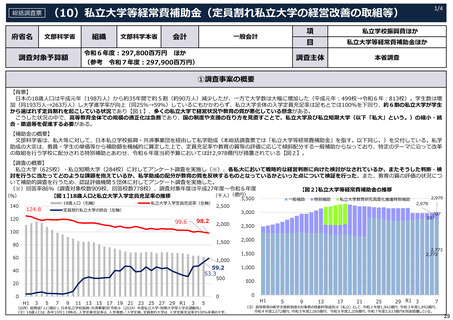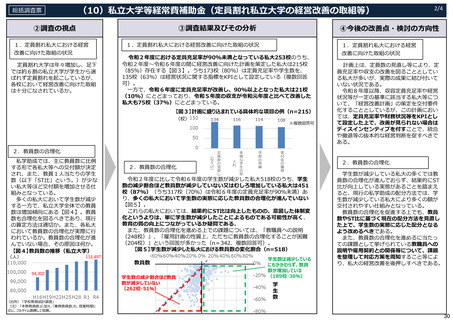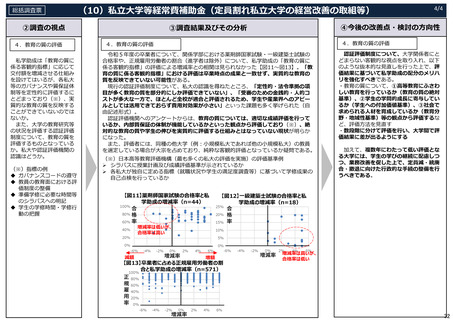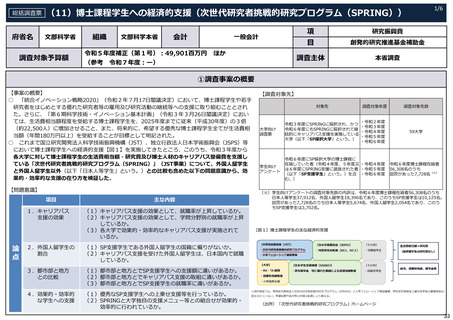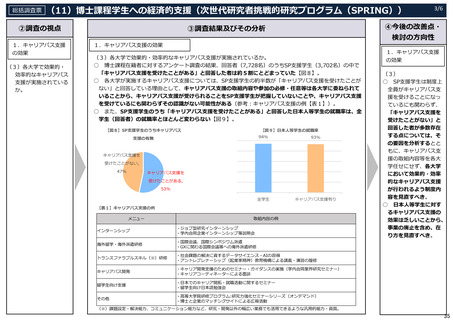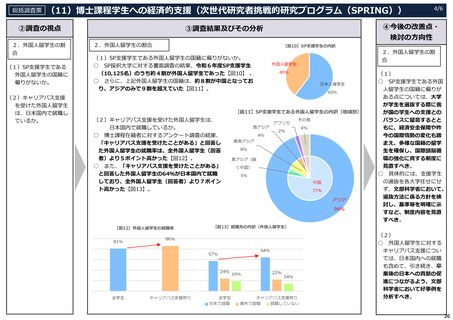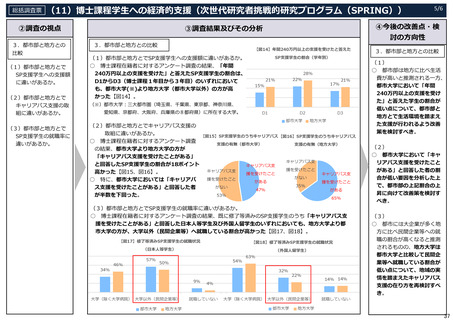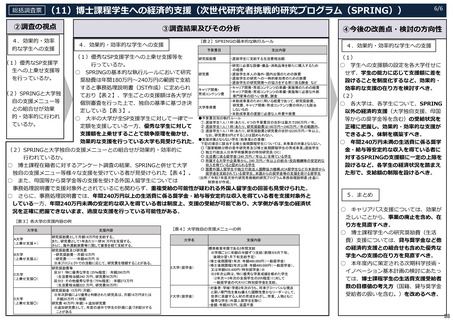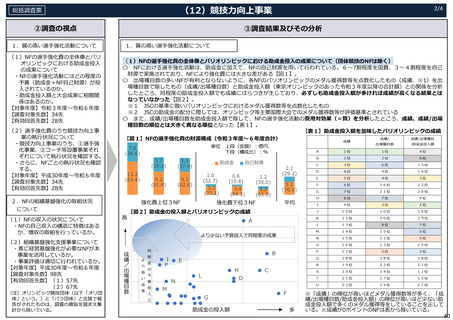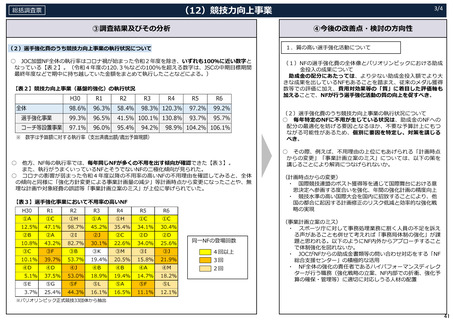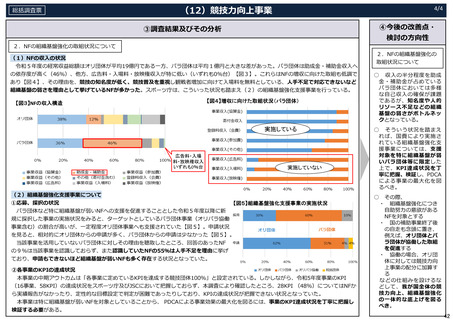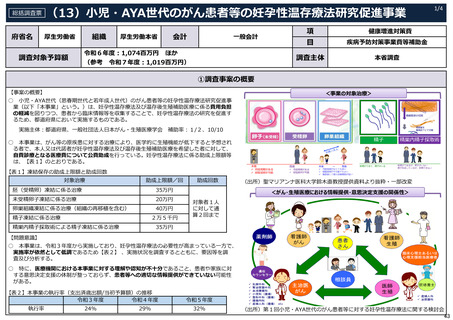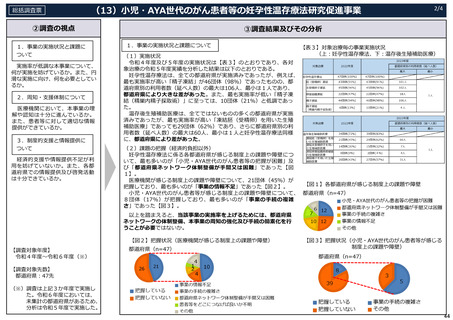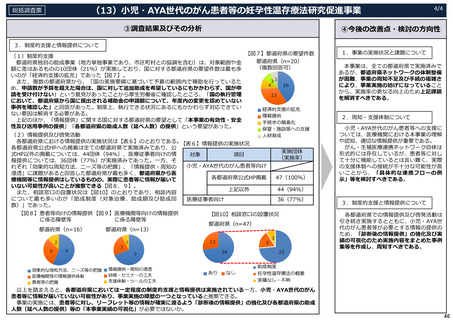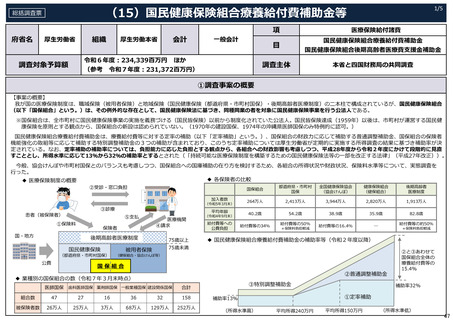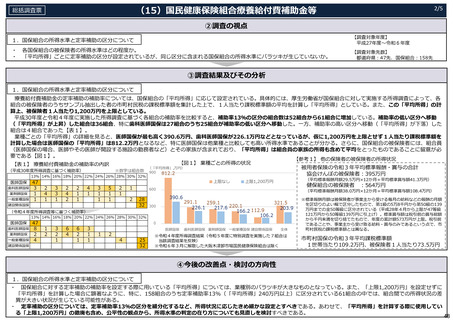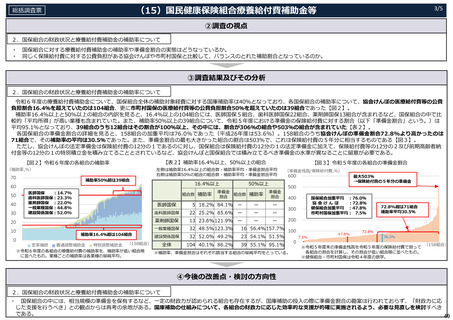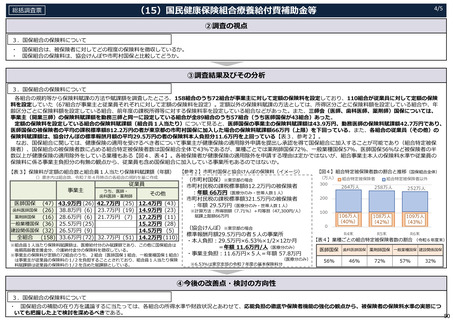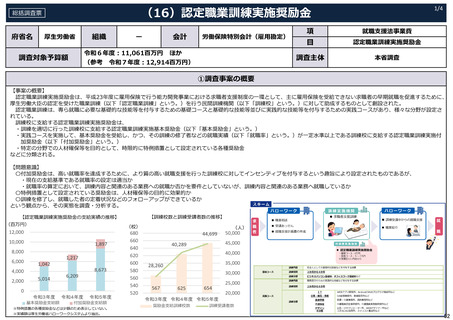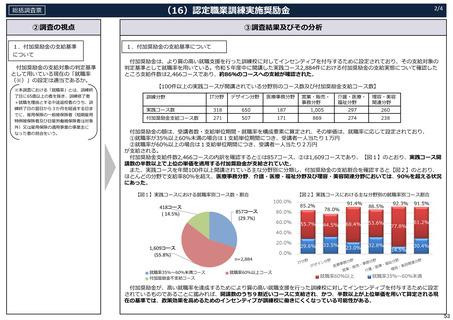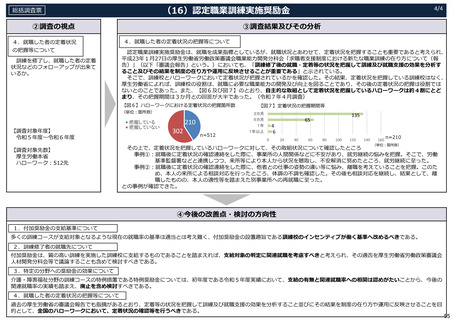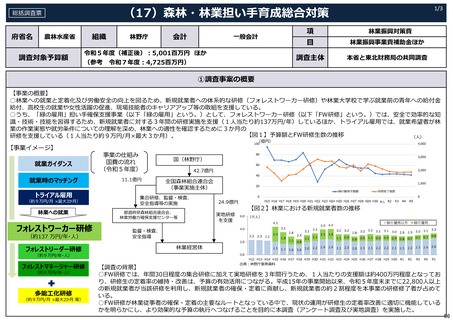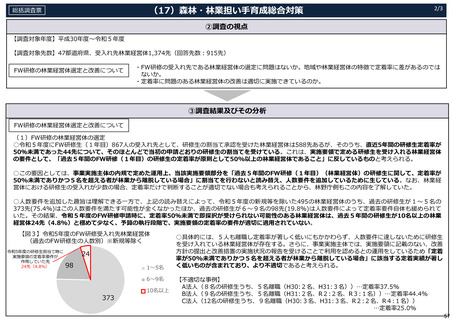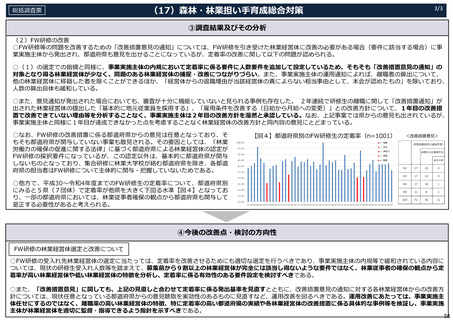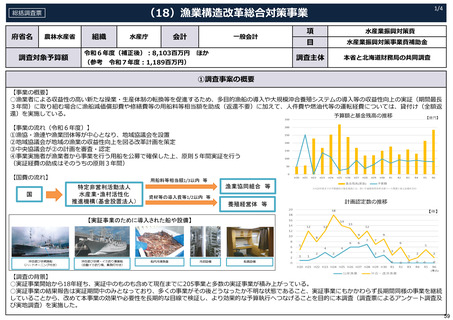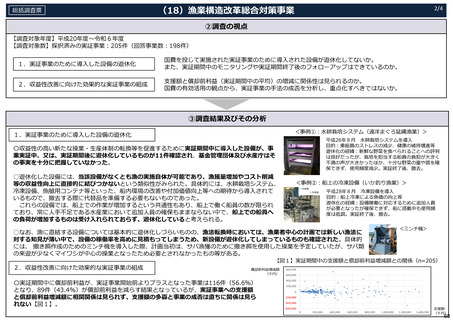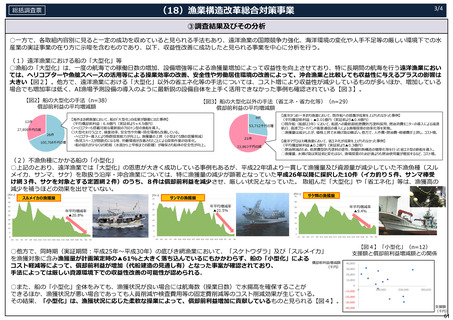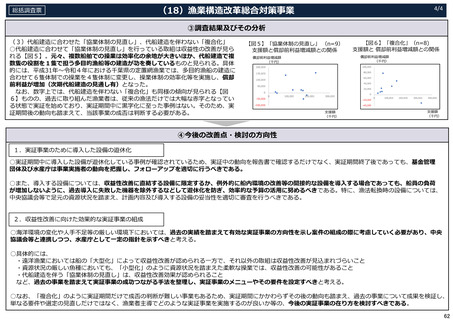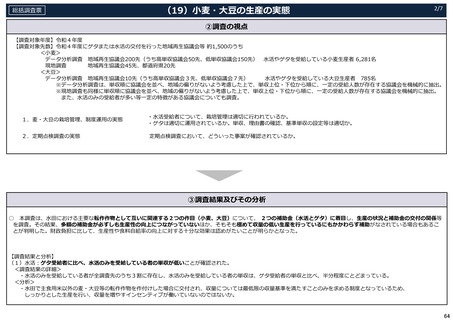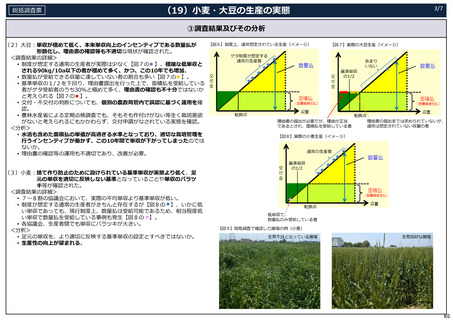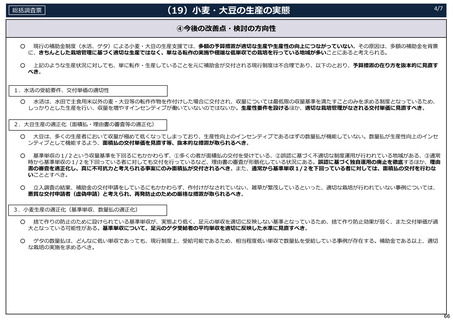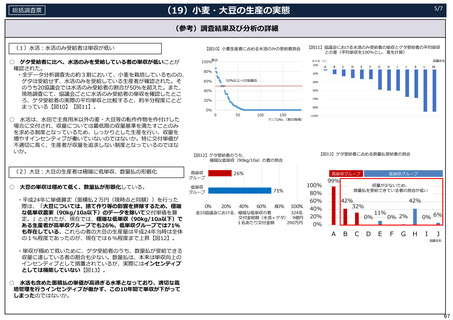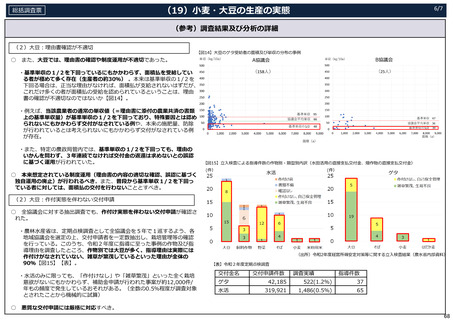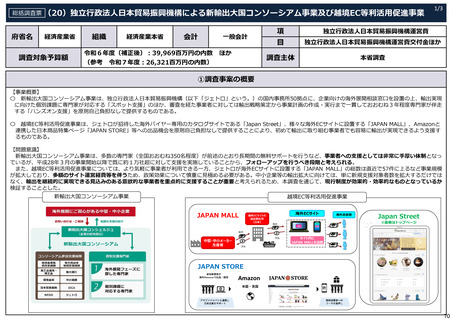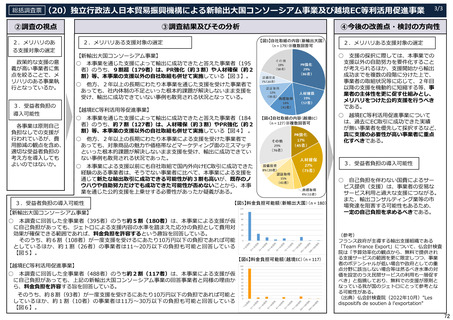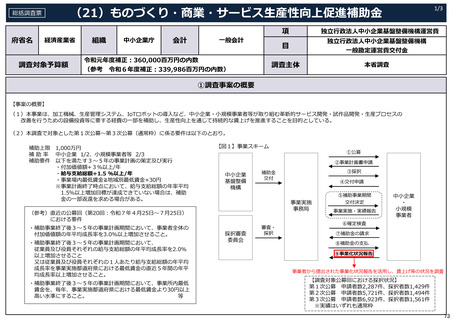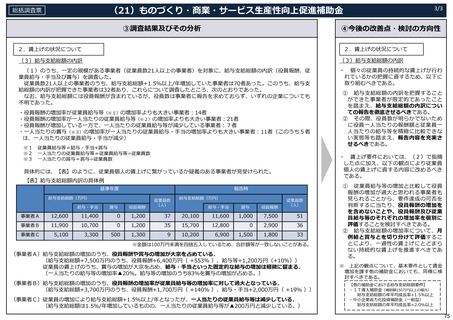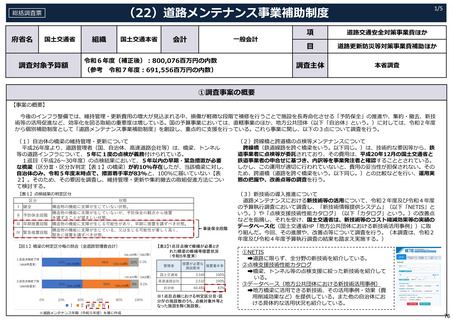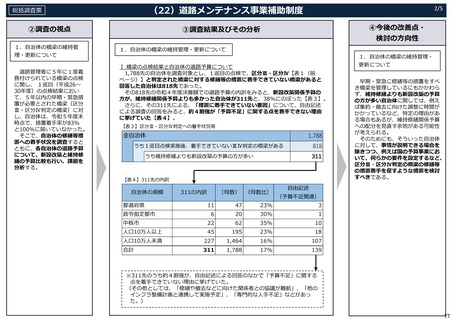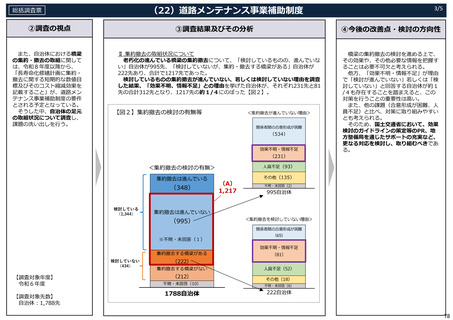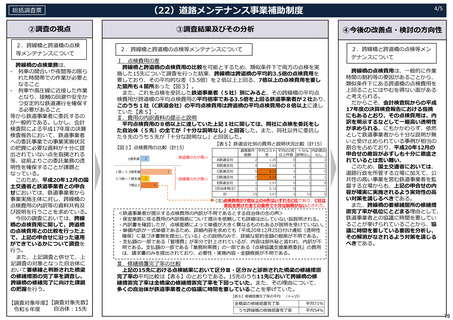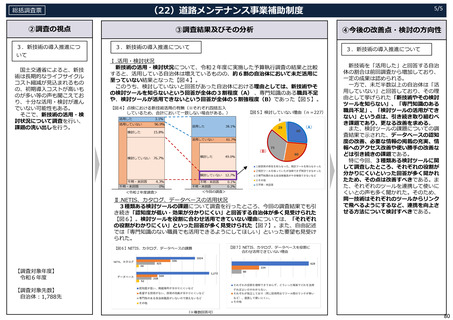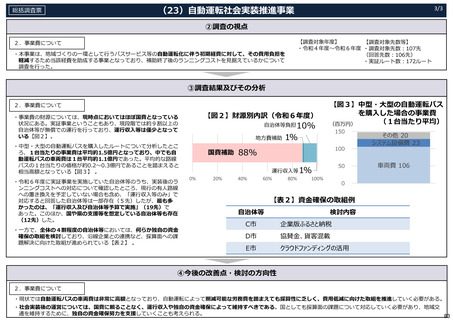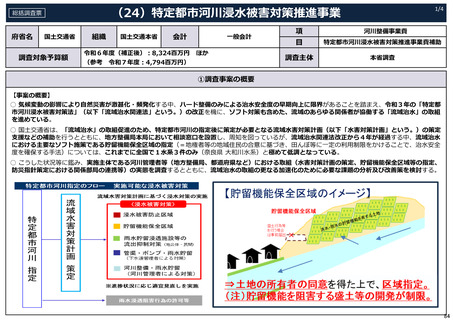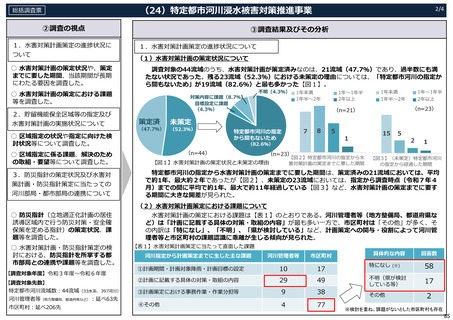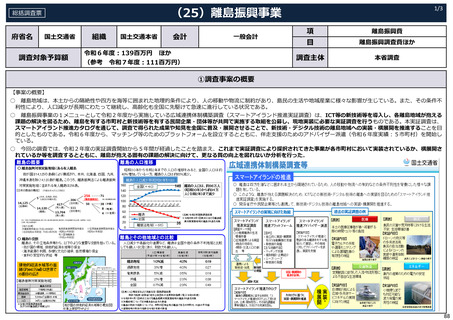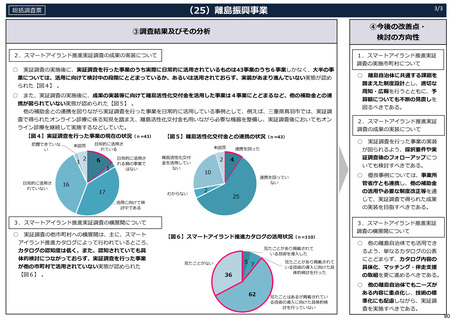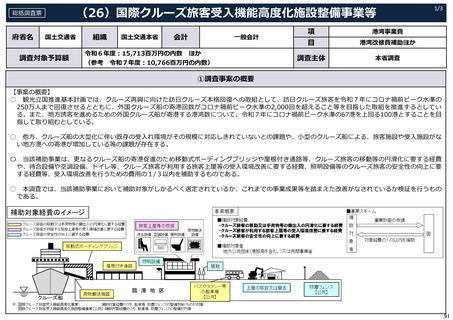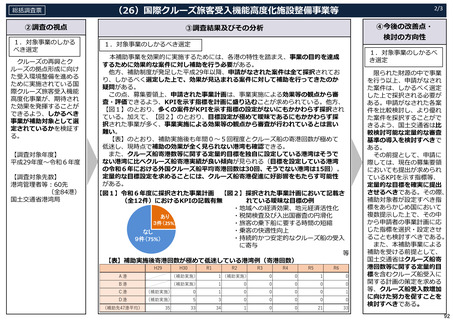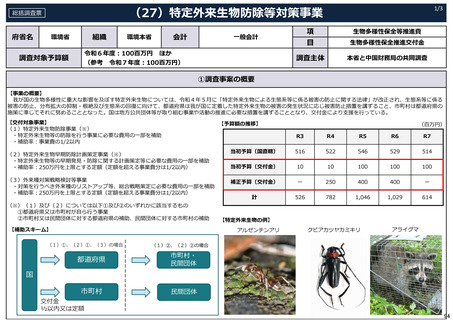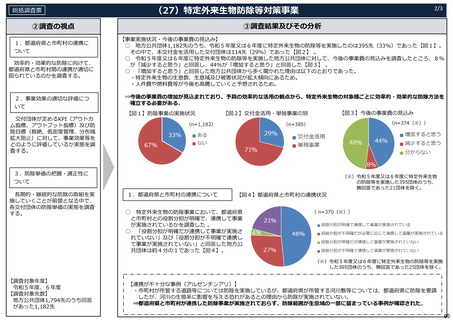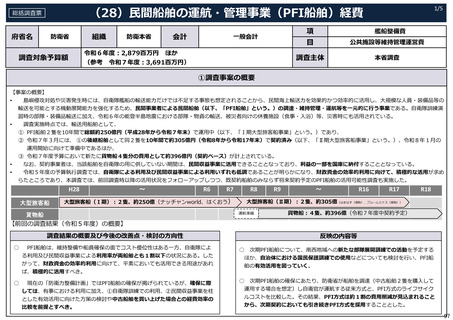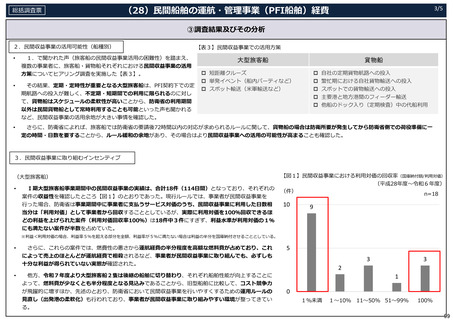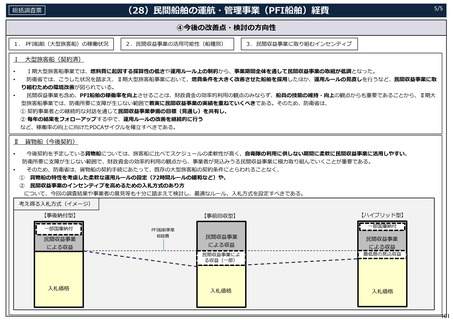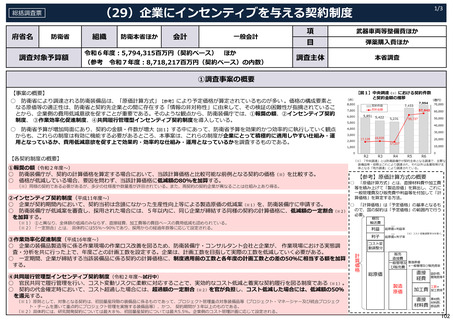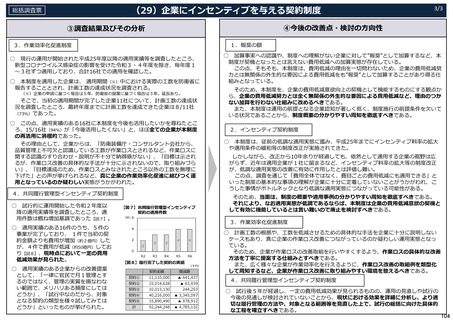よむ、つかう、まなぶ。
予算執行調査資料(総括調査票) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html |
| 出典情報 | 令和7年度 予算執行調査資料(総括調査票)(6/27)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
総括調査票
(1)災害救助費等負担⾦(仮設住宅の早期供与等)
2/3
③調査結果及びその分析
令和6年能登半島地震における仮設住宅建設の遅れに係る背景
①
【参考】発災直後の道路状況及び1⽉4⽇時点での奥能登へのアクセスルート
インフラ・ライフライン等の損傷による主な建設⼯期遅延の要因
・半島を南北に結ぶ主要幹線道路が⾄るところで被災し、仮設住宅の建設⼈員、資材の搬⼊に
相当の時間を要した。
・ライフライン(電気、上下⽔道等)の途絶により、営業している宿泊施設等がなく、建設作
業⼈員が現地に宿泊して作業ができなかった。結果、⾦沢市内のホテルから建設地まで往復
輸送せざるを得ず、1⽇あたりの実作業時間が減少し、⼯期が延びる原因となった。
・物流等を早期に回復させるため、道路復旧⼯事が優先されたことから、仮設住宅の建設に必
要となる砕⽯・アスファルトの調達が困難となった。同様に、⽣コンクリートについても、
近傍のプラントが被災し、調達が困難となった。
②
建設候補地の選定に係る問題
仮設住宅を建設した10市町ではあらかじめ、127か所の建設候補地を選定していたが、以下
の理由から、実際に利⽤した建設候補地は38か所であった【表2】。
・地震により建設候補地の地盤に⻲裂が⼊った
・道路が啓開しておらず、建設候補地まで⾏くことが困難であった
・建設候補地としてリストに掲載されていたが、⼭間地のため整備しないと使⽤できない⼟地であった
そのため、新たに建設候補地を121か所選定したが、事前に検討していない⼟地であったことから、
・ライフライン(電気・上下⽔道)の有無
・安全性(災害被害想定区域内外(液状化・津波・洪⽔・⼟砂災害など))の確認
・利便性(学校、病院、スーパー等へのアクセス)の確認
など、仮設住宅の建設に際し、改めて県と市町との協議が必要となった。また、建設候補地によっては地盤が軟弱である
ことから、地盤改良を⾏う必要があったなど、建設決定までに時間を要した。
③
【表2】⽯川県内の建設候補地の選定及び活⽤状況
合計
建設候補地
127か所
実際に建設した団地数
159ヵ所
うち建設候補地を活⽤
38か所(30%)
災害時における⽯川県の協定締結状況
・建設事業者との「災害時の⽀援協定」において、建設する住宅の仕様や間取り等を事前に決めておくことで、発災時の世帯数に応じた仮設住宅の建設、既設ハウスの活⽤がス
ムーズに⾏われ、被災者への仮設住宅の早期供与が可能となる。このため、⾃治体は可能な限り多くの建設事業者と協定を締結しておくことが重要である【表3】。
・⼀⽅で、⽯川県が発災前に結んでいた⽀援協定はプレハブ建築協会のみであったことから、発災後、迅速に⼤量の仮設住宅を建設するため、他の団体とも⽀援協定を締結した
ものの、その調整に時間を要した。
【表3】関係団体と都道府県の協定締結状況(令和7年4⽉時点)
(注)⽯川県では発災後、新たに8団体と協定を締結しており、全体で9団体となっている。
団 体 名
協定締結状況
協定締結先︓プレハブ建築協会、⽇本ムービングハウス協会、⽇本RV・トレーラーハウス協会、
⽯川県⽊造住宅協会、全国⽊造建設事業協会、⽇本ログハウス協会、⽯川県建団連、
(⼀社)プレハブ建築協会
47都道府県で締結済
⽇本モバイル建築協会、⽇本⽊造住宅産業協会
・令和6年能登半島地震ではムービングハウス・トレーラーハウス等の供与は667⼾と初めて仮設住宅全体の1
割に達したが、本年6⽉より運⽤開始している「災害対応⾞両登録制度」のない状況下だったため、仮設住宅
として活⽤可能な既設のムービングハウス等のストックが少なく、新たに設計・建設を⾏ったなどの理由から
発注から供与まで平均してムービングハウスについては2か⽉弱、トレーラーハウスについては1か⽉程度の
時間を要した。
(⼀社)全国⽊造建設事業協会
45都道府県で締結済
(⼀社)⽇本ムービングハウス協会
24道県で締結済
2
(1)災害救助費等負担⾦(仮設住宅の早期供与等)
2/3
③調査結果及びその分析
令和6年能登半島地震における仮設住宅建設の遅れに係る背景
①
【参考】発災直後の道路状況及び1⽉4⽇時点での奥能登へのアクセスルート
インフラ・ライフライン等の損傷による主な建設⼯期遅延の要因
・半島を南北に結ぶ主要幹線道路が⾄るところで被災し、仮設住宅の建設⼈員、資材の搬⼊に
相当の時間を要した。
・ライフライン(電気、上下⽔道等)の途絶により、営業している宿泊施設等がなく、建設作
業⼈員が現地に宿泊して作業ができなかった。結果、⾦沢市内のホテルから建設地まで往復
輸送せざるを得ず、1⽇あたりの実作業時間が減少し、⼯期が延びる原因となった。
・物流等を早期に回復させるため、道路復旧⼯事が優先されたことから、仮設住宅の建設に必
要となる砕⽯・アスファルトの調達が困難となった。同様に、⽣コンクリートについても、
近傍のプラントが被災し、調達が困難となった。
②
建設候補地の選定に係る問題
仮設住宅を建設した10市町ではあらかじめ、127か所の建設候補地を選定していたが、以下
の理由から、実際に利⽤した建設候補地は38か所であった【表2】。
・地震により建設候補地の地盤に⻲裂が⼊った
・道路が啓開しておらず、建設候補地まで⾏くことが困難であった
・建設候補地としてリストに掲載されていたが、⼭間地のため整備しないと使⽤できない⼟地であった
そのため、新たに建設候補地を121か所選定したが、事前に検討していない⼟地であったことから、
・ライフライン(電気・上下⽔道)の有無
・安全性(災害被害想定区域内外(液状化・津波・洪⽔・⼟砂災害など))の確認
・利便性(学校、病院、スーパー等へのアクセス)の確認
など、仮設住宅の建設に際し、改めて県と市町との協議が必要となった。また、建設候補地によっては地盤が軟弱である
ことから、地盤改良を⾏う必要があったなど、建設決定までに時間を要した。
③
【表2】⽯川県内の建設候補地の選定及び活⽤状況
合計
建設候補地
127か所
実際に建設した団地数
159ヵ所
うち建設候補地を活⽤
38か所(30%)
災害時における⽯川県の協定締結状況
・建設事業者との「災害時の⽀援協定」において、建設する住宅の仕様や間取り等を事前に決めておくことで、発災時の世帯数に応じた仮設住宅の建設、既設ハウスの活⽤がス
ムーズに⾏われ、被災者への仮設住宅の早期供与が可能となる。このため、⾃治体は可能な限り多くの建設事業者と協定を締結しておくことが重要である【表3】。
・⼀⽅で、⽯川県が発災前に結んでいた⽀援協定はプレハブ建築協会のみであったことから、発災後、迅速に⼤量の仮設住宅を建設するため、他の団体とも⽀援協定を締結した
ものの、その調整に時間を要した。
【表3】関係団体と都道府県の協定締結状況(令和7年4⽉時点)
(注)⽯川県では発災後、新たに8団体と協定を締結しており、全体で9団体となっている。
団 体 名
協定締結状況
協定締結先︓プレハブ建築協会、⽇本ムービングハウス協会、⽇本RV・トレーラーハウス協会、
⽯川県⽊造住宅協会、全国⽊造建設事業協会、⽇本ログハウス協会、⽯川県建団連、
(⼀社)プレハブ建築協会
47都道府県で締結済
⽇本モバイル建築協会、⽇本⽊造住宅産業協会
・令和6年能登半島地震ではムービングハウス・トレーラーハウス等の供与は667⼾と初めて仮設住宅全体の1
割に達したが、本年6⽉より運⽤開始している「災害対応⾞両登録制度」のない状況下だったため、仮設住宅
として活⽤可能な既設のムービングハウス等のストックが少なく、新たに設計・建設を⾏ったなどの理由から
発注から供与まで平均してムービングハウスについては2か⽉弱、トレーラーハウスについては1か⽉程度の
時間を要した。
(⼀社)全国⽊造建設事業協会
45都道府県で締結済
(⼀社)⽇本ムービングハウス協会
24道県で締結済
2