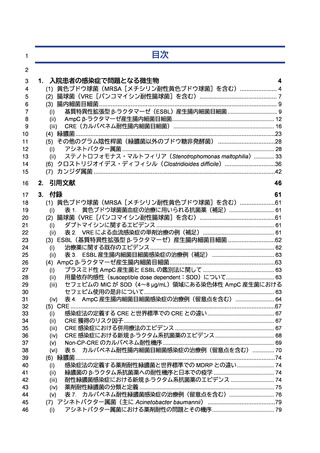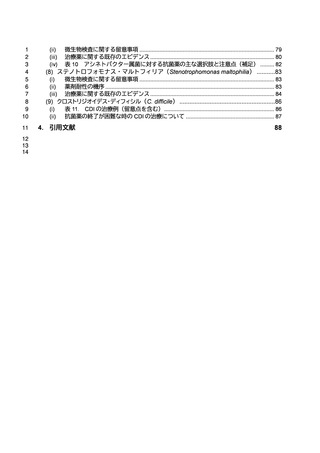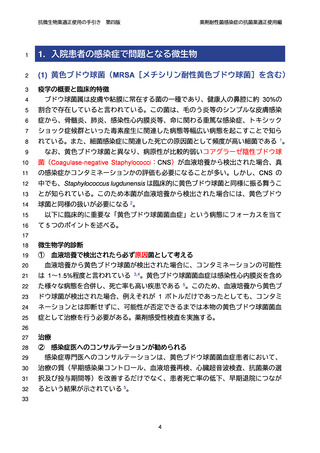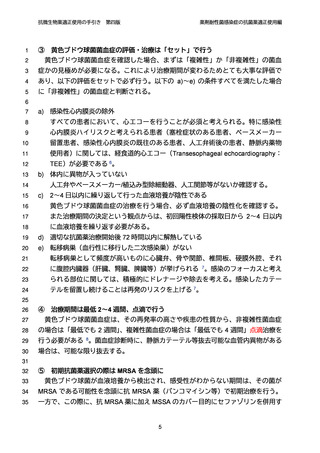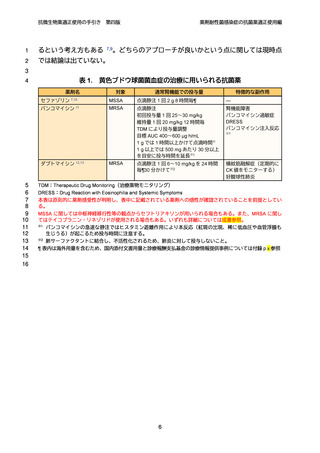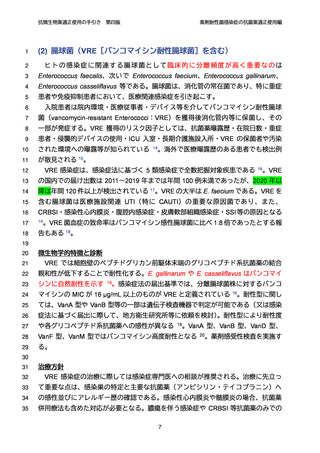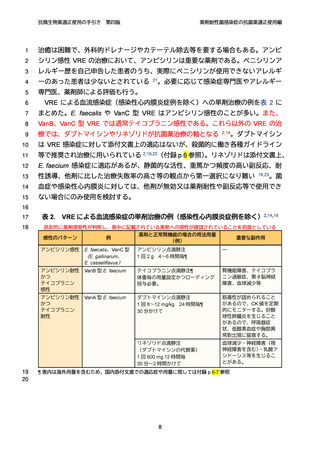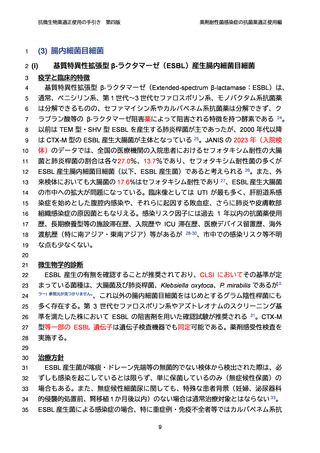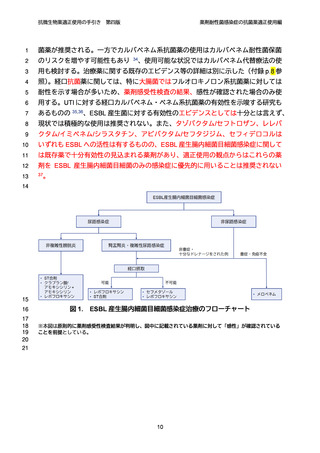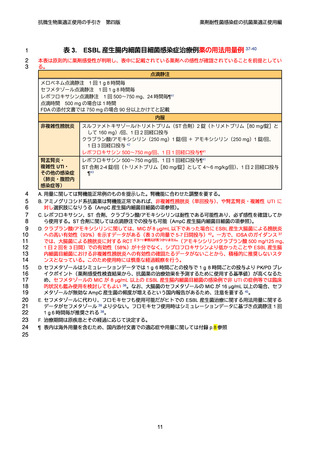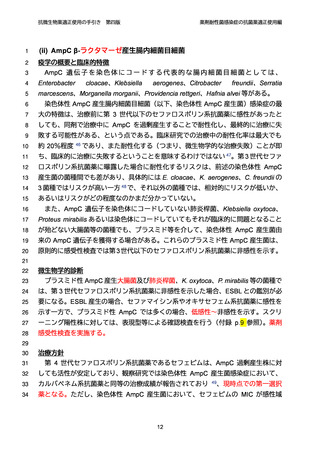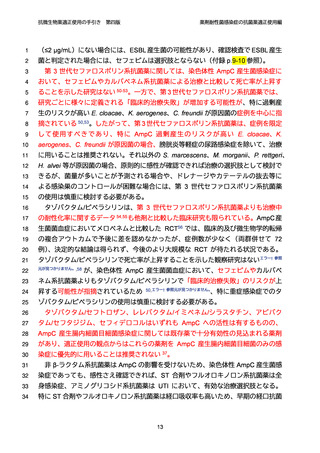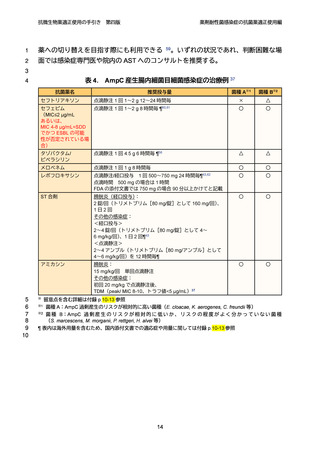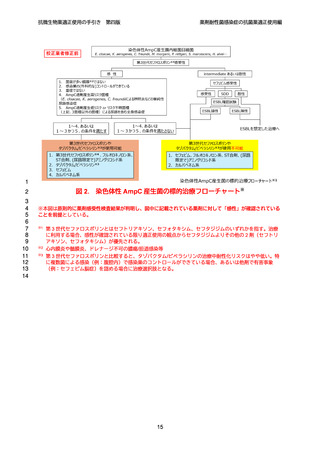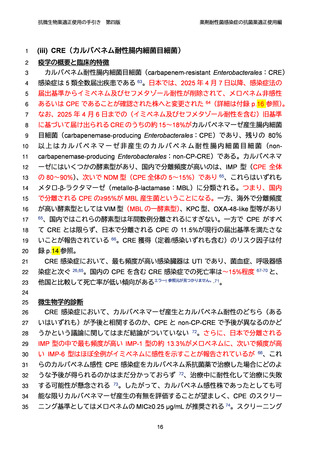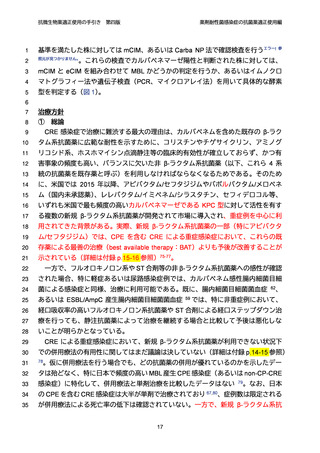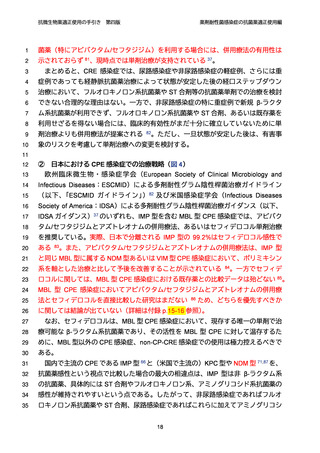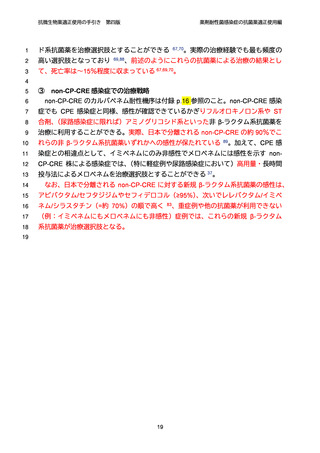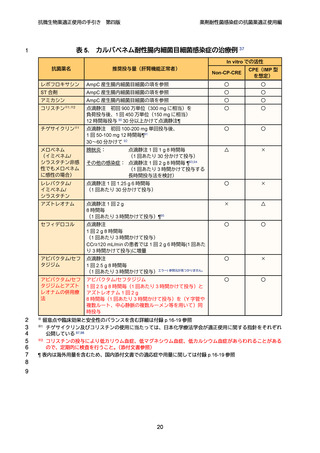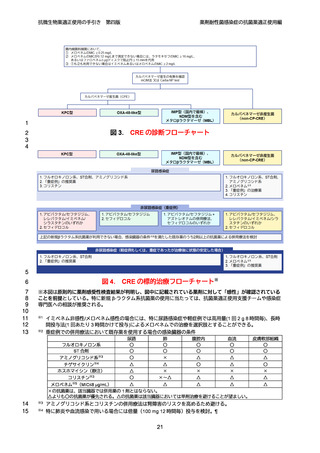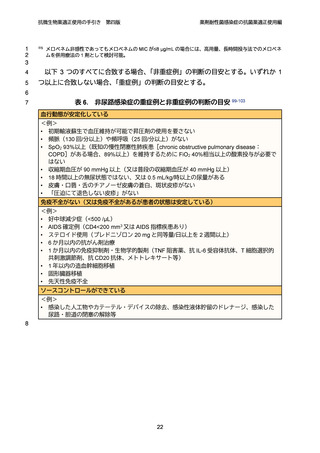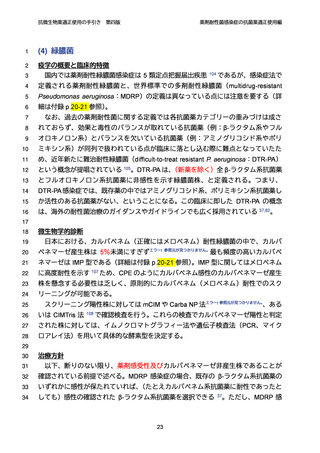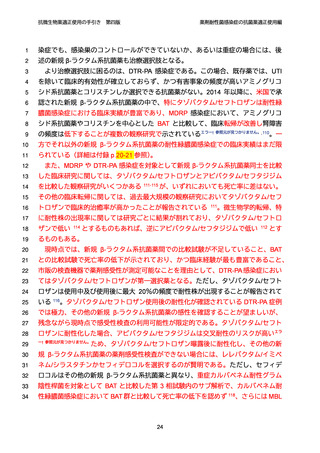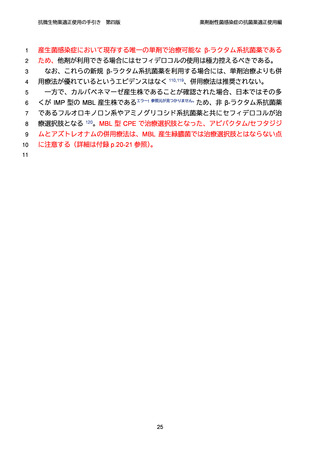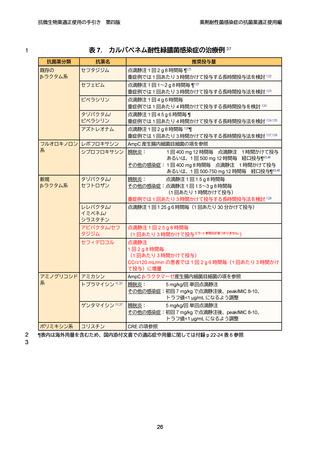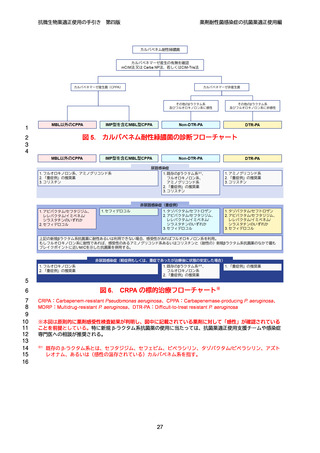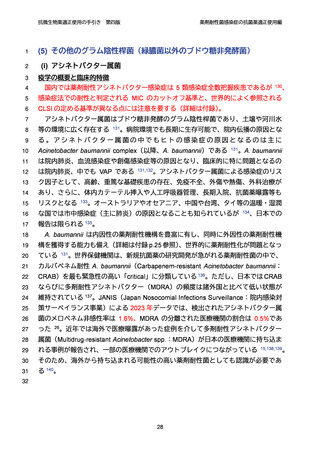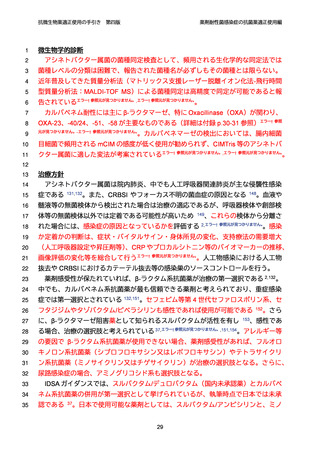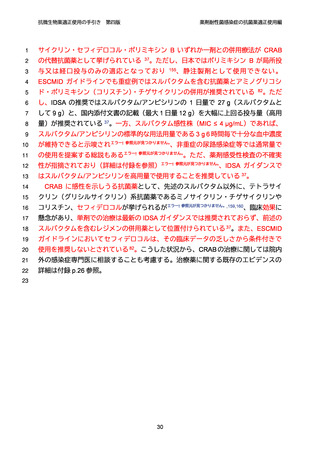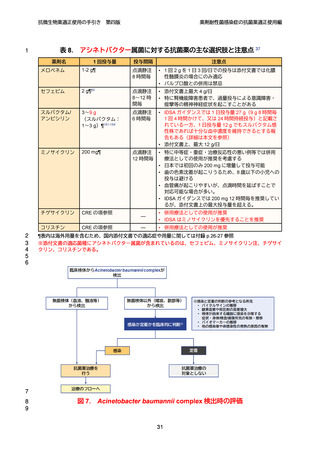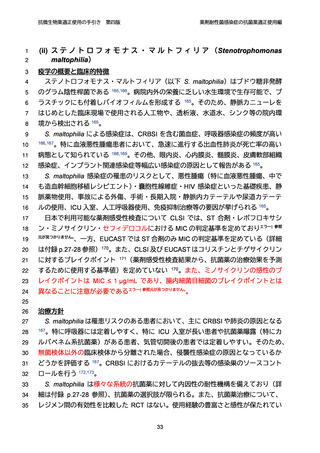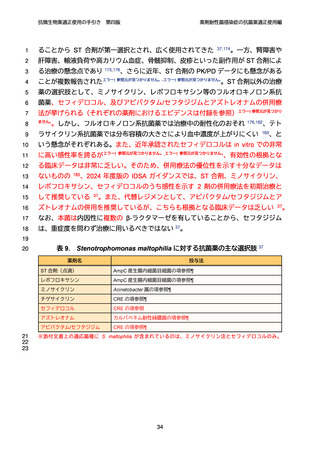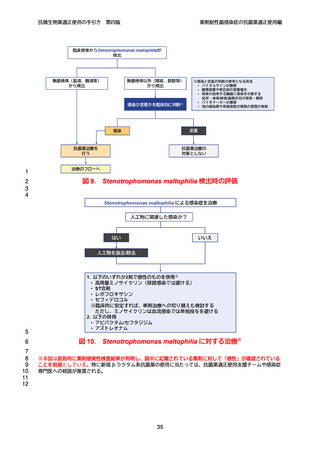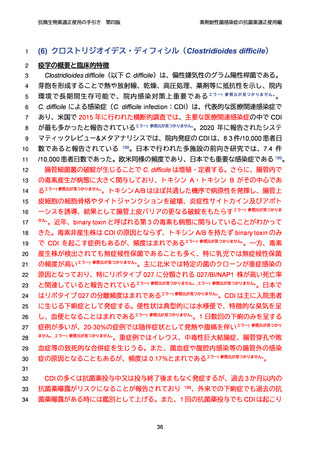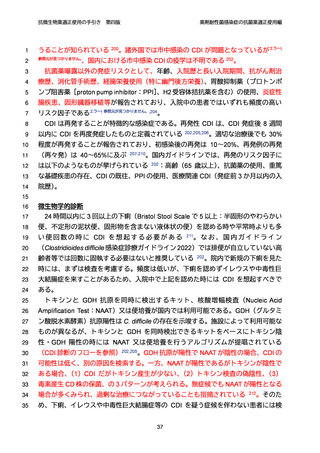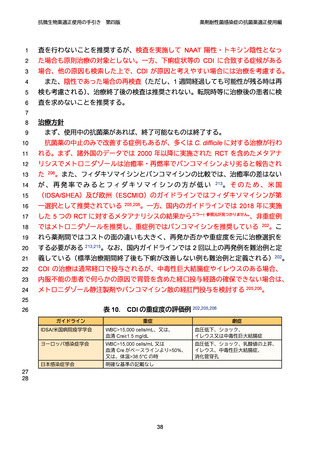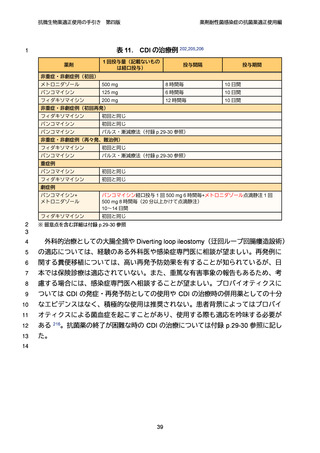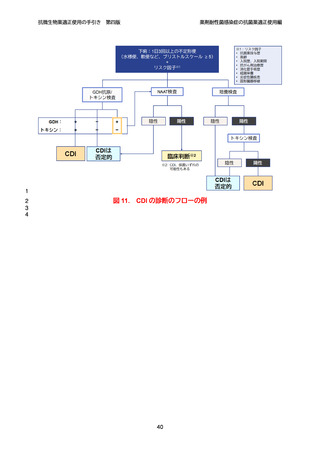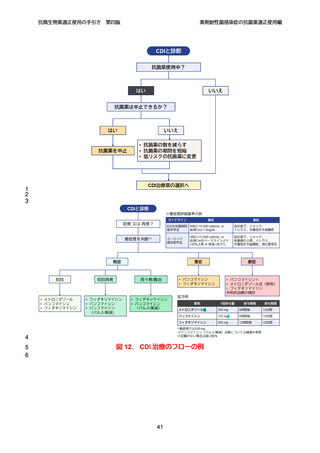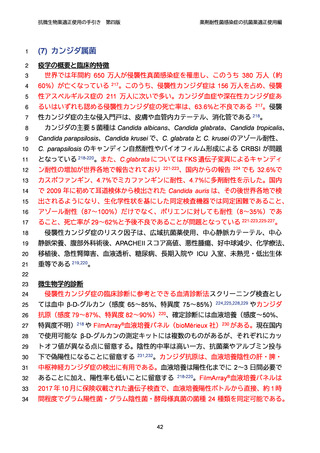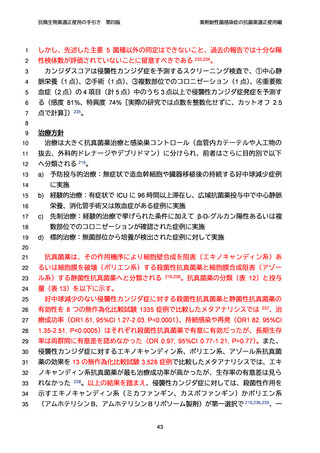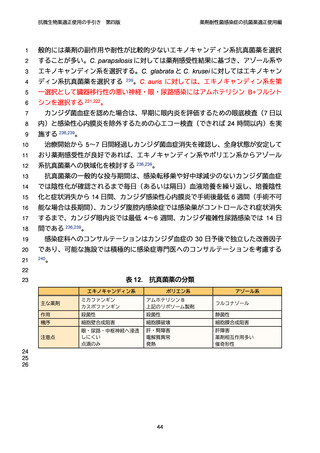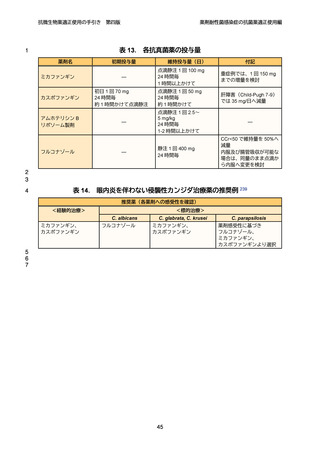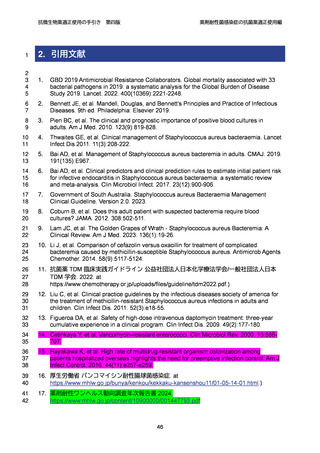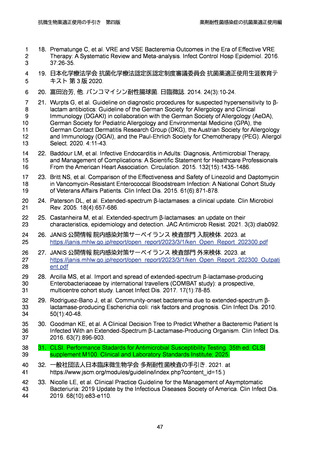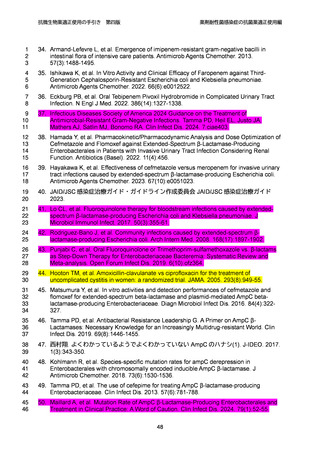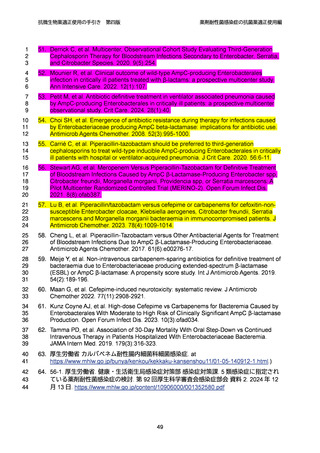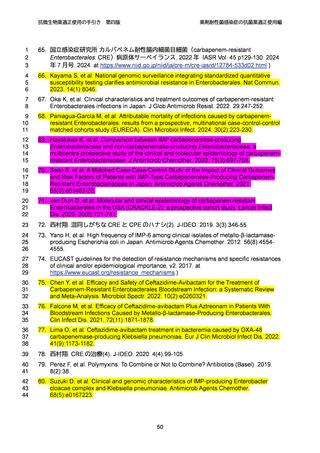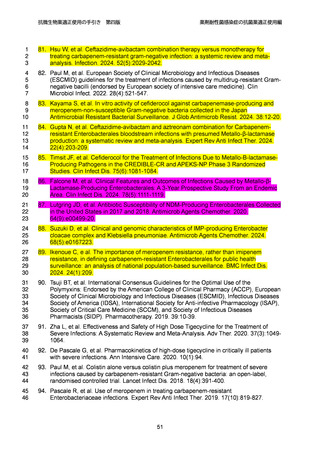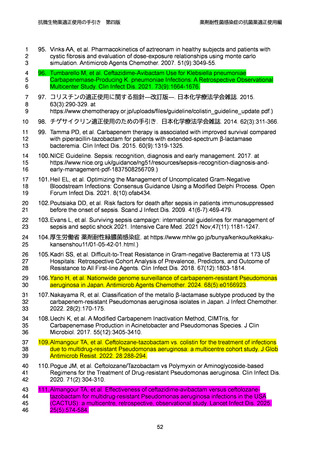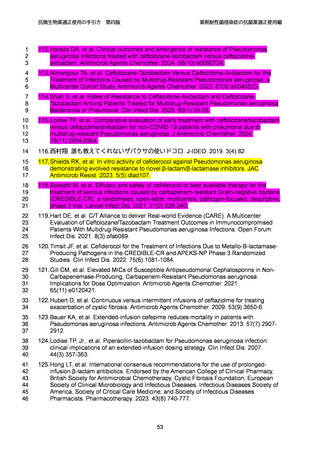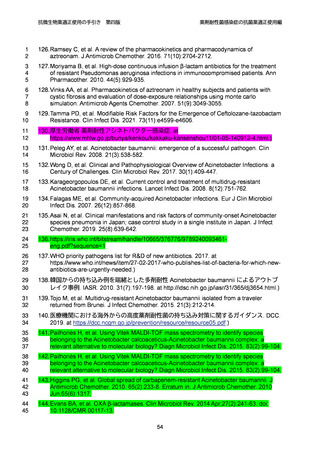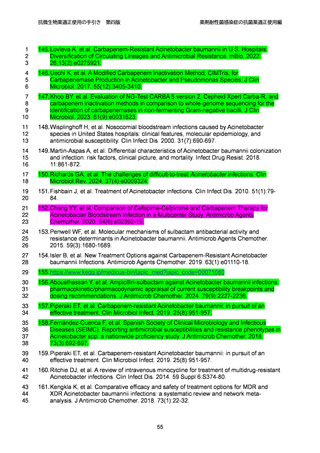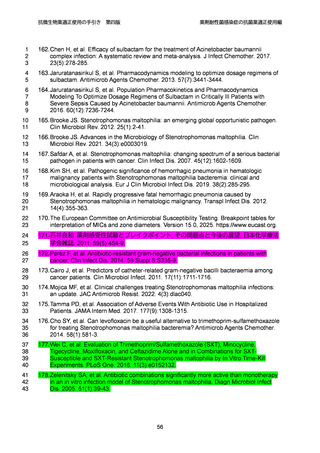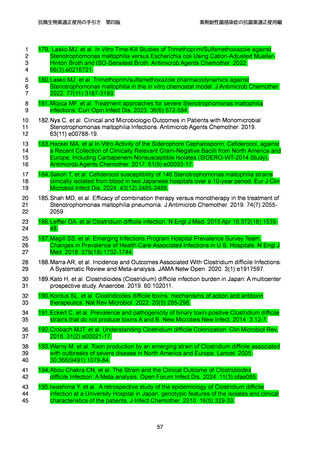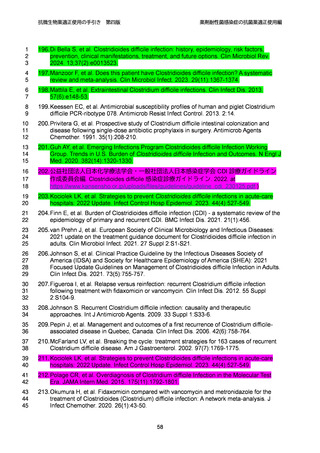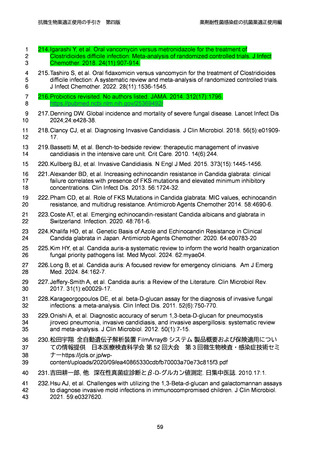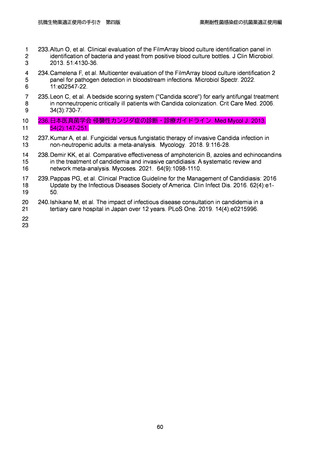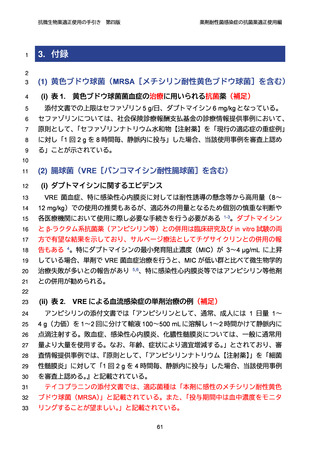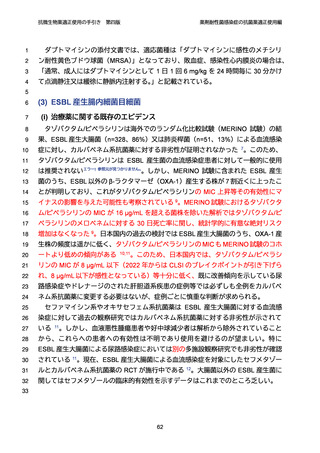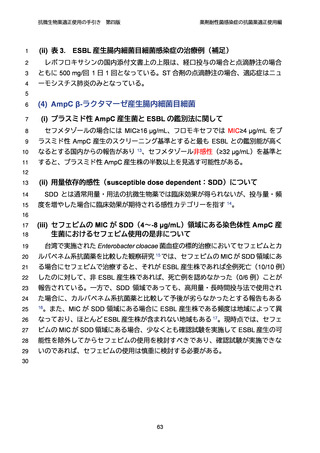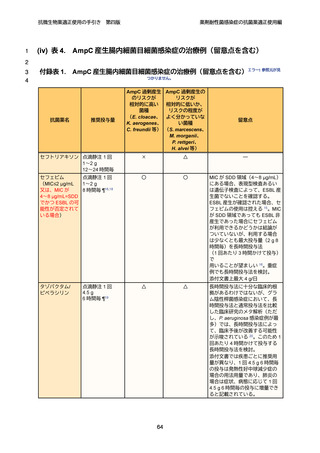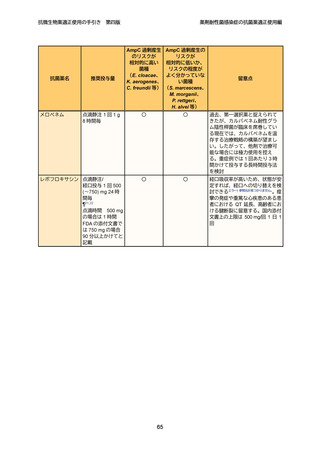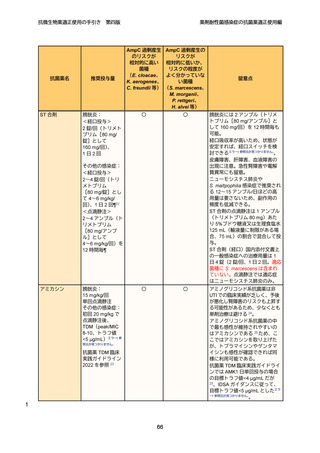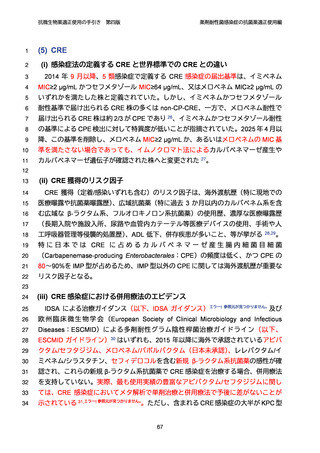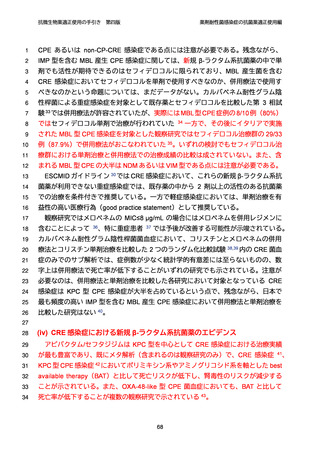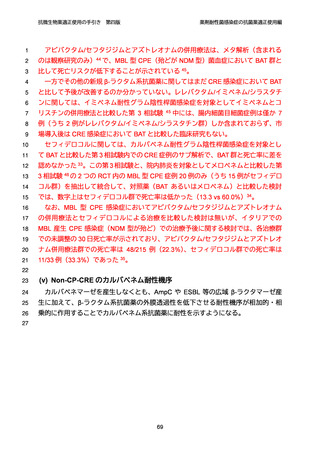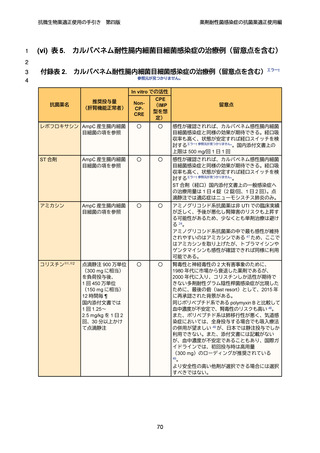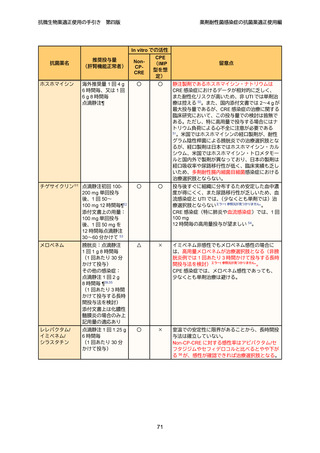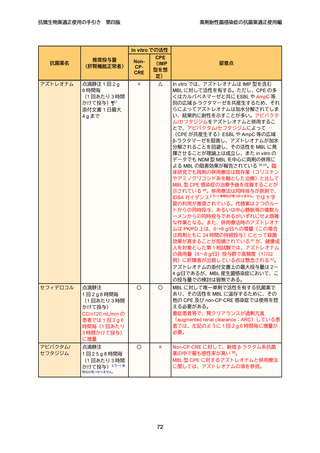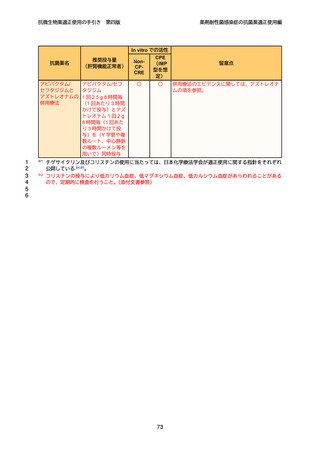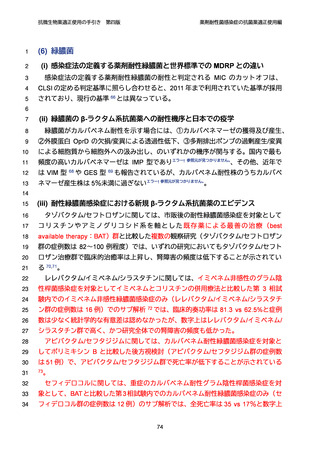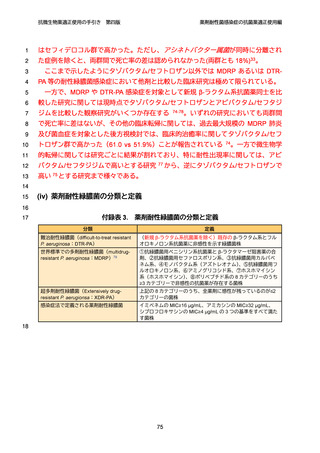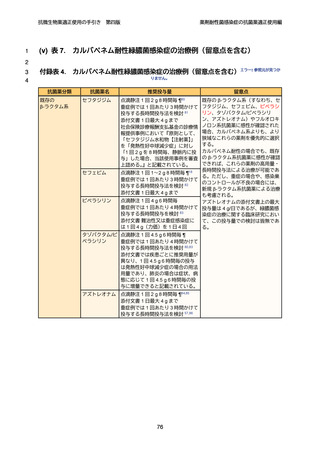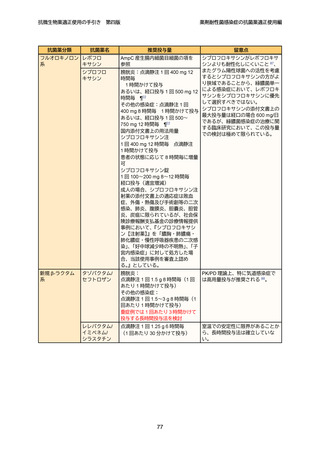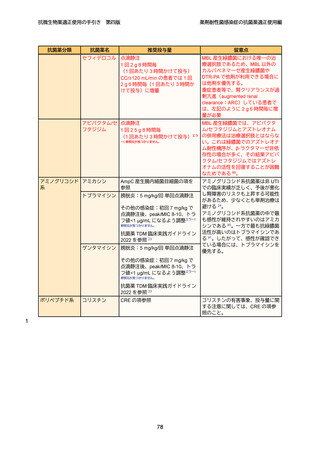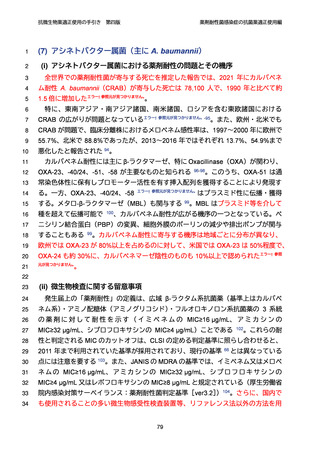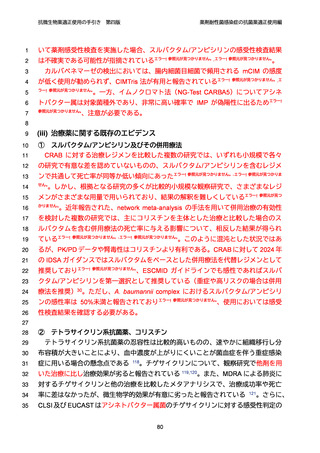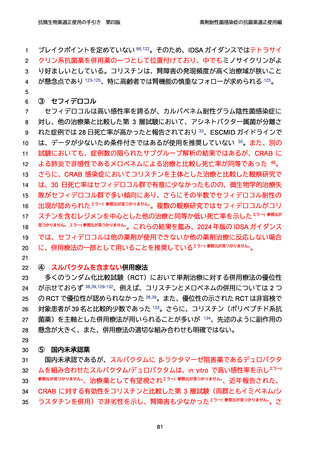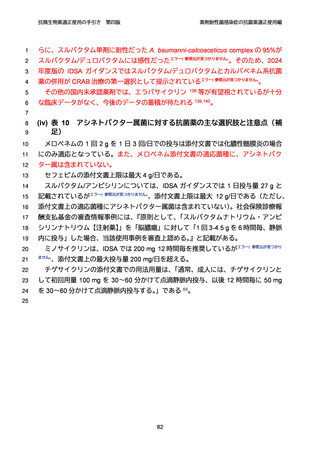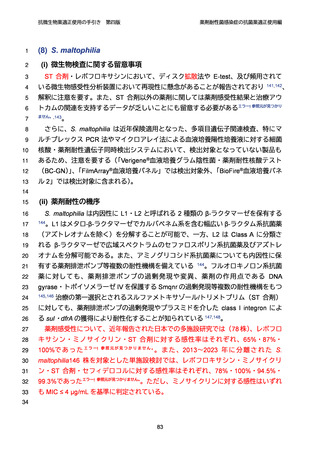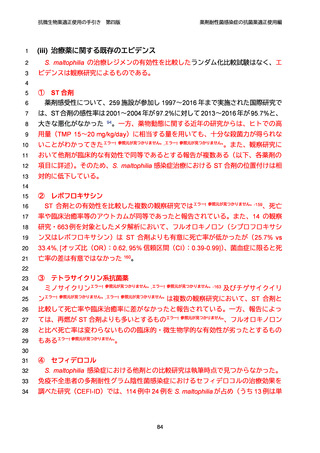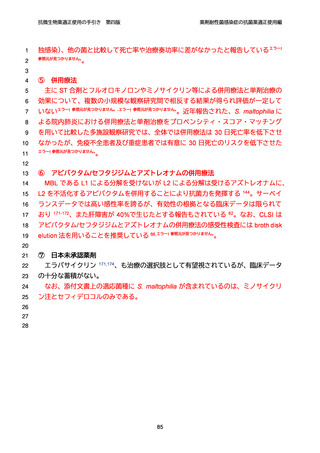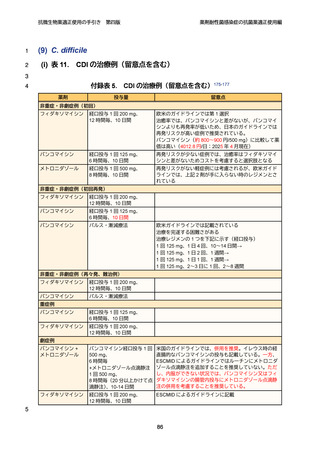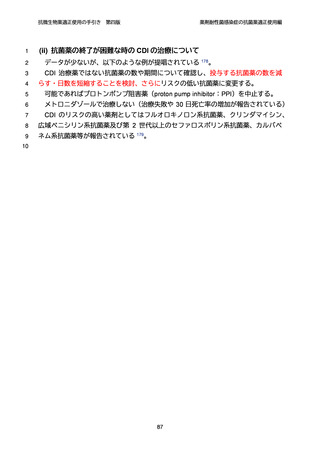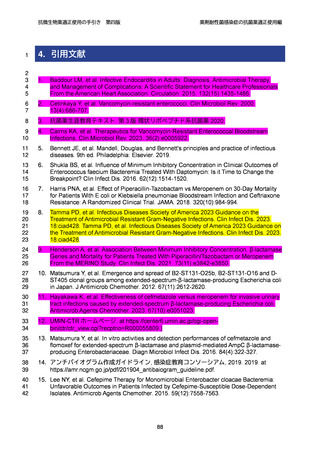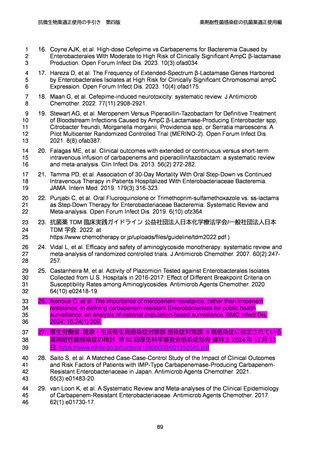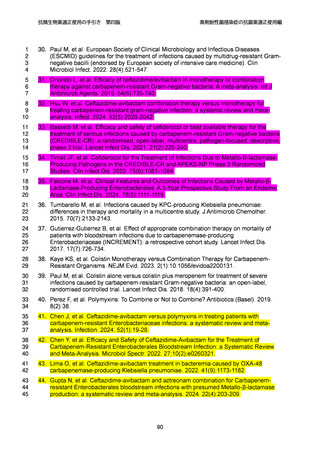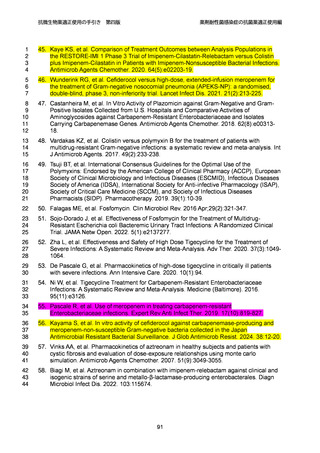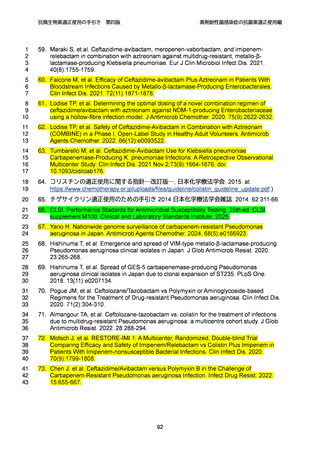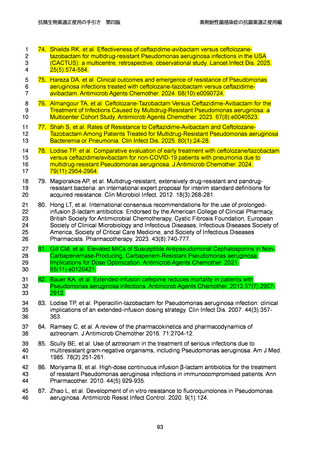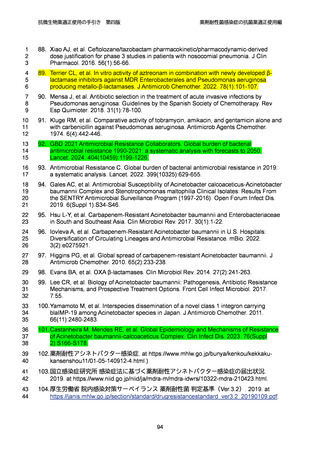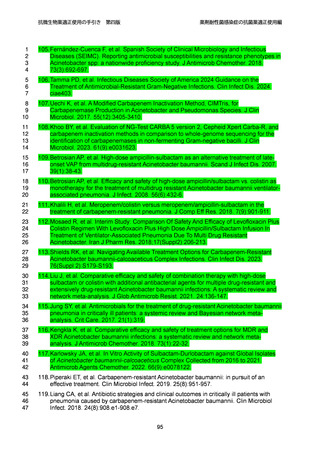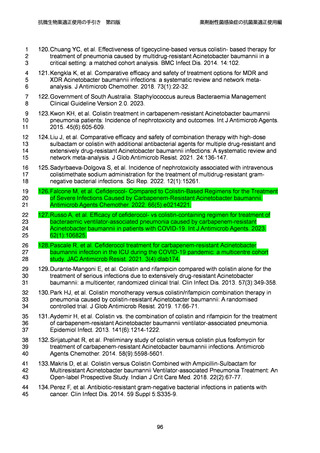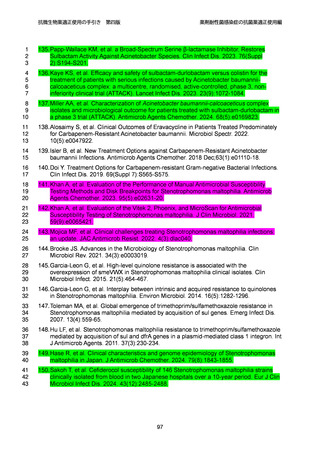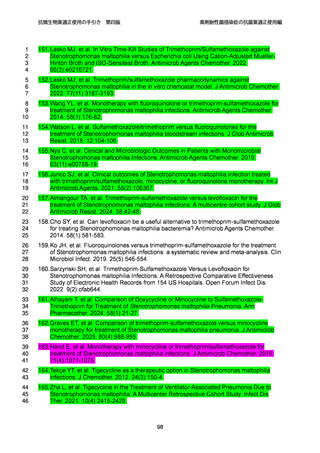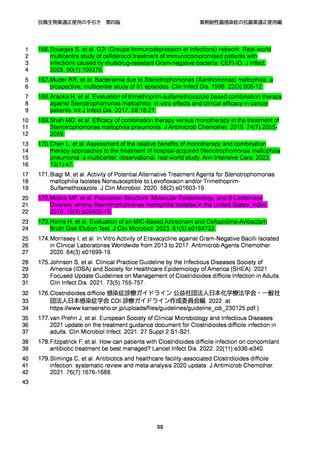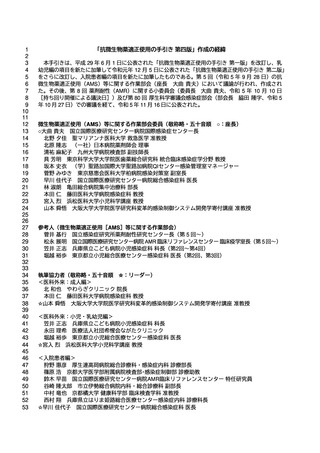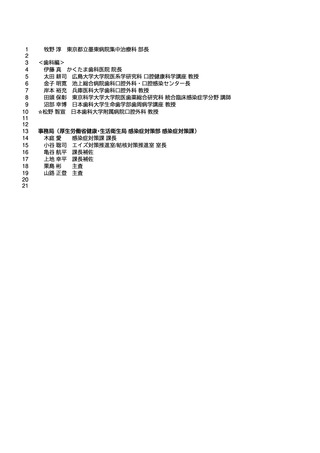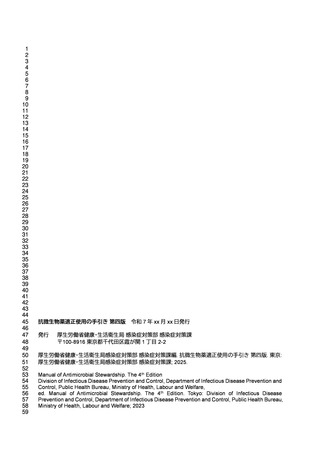よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-3】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
抗微生物薬適正使用の手引き
第四版
薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編
1
1. 入院患者の感染症で問題となる微生物
2
(1) 黄色ブドウ球菌(MRSA[メチシリン耐性黄色ブドウ球菌]を含む)
3
疫学の概要と臨床的特徴
4
ブドウ球菌属は皮膚や粘膜に常在する菌の一種であり、健康人の鼻腔に約 30%の
5
割合で存在していると言われている。この菌は、毛のう炎等のシンプルな皮膚感染
6
症から、骨髄炎、肺炎、感染性心内膜炎等、命に関わる重篤な感染症、トキシック
7
ショック症候群といった毒素産生に関連した病態等幅広い病態を起こすことで知ら
8
れている。また、細菌感染症に関連した死亡の原因菌として頻度が高い細菌である 1。
9
なお、黄色ブドウ球菌と異なり、病原性が比較的弱いコアグラーゼ陰性ブドウ球
10
菌(Coagulase-negative Staphylococci:CNS)が血液培養から検出された場合、真
11
の感染症かコンタミネーションかの評価も必要になることが多い。しかし、CNS の
12
中でも、Staphylococcus lugdunensis は臨床的に黄色ブドウ球菌と同様に振る舞うこ
13
とが知られている。このため本菌が血液培養から検出された場合には、黄色ブドウ
14
球菌と同様の扱いが必要になる 2。
以下に臨床的に重要な「黄色ブドウ球菌菌血症」という病態にフォーカスを当て
15
16
て 5 つのポイントを述べる。
17
18
微生物学的診断
19
①
血液培養で検出されたら必ず原因菌として考える
20
血液培養から黄色ブドウ球菌が検出された場合に、コンタミネーションの可能性
21
は 1~1.5%程度と言われている 3,4。黄色ブドウ球菌菌血症は感染性心内膜炎を含め
22
た様々な病態を合併し、死亡率も高い疾患である 5。このため、血液培養から黄色ブ
23
ドウ球菌が検出された場合、例えそれが 1 ボトルだけであったとしても、コンタミ
24
ネーションとは即断せずに、可能性が否定できるまでは本物の黄色ブドウ球菌菌血
25
症として治療を行う必要がある。薬剤感受性検査を実施する。
26
27
治療
28
②
感染症医へのコンサルテーションが勧められる
29
感染症専門医へのコンサルテーションは、黄色ブドウ球菌菌血症患者において、
30
治療の質(早期感染巣コントロール、血液培養再検、心臓超音波検査、抗菌薬の選
31
択及び投与期間等)を改善するだけでなく、患者死亡率の低下、早期退院につなが
32
るという結果が示されている 5。
33
4
第四版
薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編
1
1. 入院患者の感染症で問題となる微生物
2
(1) 黄色ブドウ球菌(MRSA[メチシリン耐性黄色ブドウ球菌]を含む)
3
疫学の概要と臨床的特徴
4
ブドウ球菌属は皮膚や粘膜に常在する菌の一種であり、健康人の鼻腔に約 30%の
5
割合で存在していると言われている。この菌は、毛のう炎等のシンプルな皮膚感染
6
症から、骨髄炎、肺炎、感染性心内膜炎等、命に関わる重篤な感染症、トキシック
7
ショック症候群といった毒素産生に関連した病態等幅広い病態を起こすことで知ら
8
れている。また、細菌感染症に関連した死亡の原因菌として頻度が高い細菌である 1。
9
なお、黄色ブドウ球菌と異なり、病原性が比較的弱いコアグラーゼ陰性ブドウ球
10
菌(Coagulase-negative Staphylococci:CNS)が血液培養から検出された場合、真
11
の感染症かコンタミネーションかの評価も必要になることが多い。しかし、CNS の
12
中でも、Staphylococcus lugdunensis は臨床的に黄色ブドウ球菌と同様に振る舞うこ
13
とが知られている。このため本菌が血液培養から検出された場合には、黄色ブドウ
14
球菌と同様の扱いが必要になる 2。
以下に臨床的に重要な「黄色ブドウ球菌菌血症」という病態にフォーカスを当て
15
16
て 5 つのポイントを述べる。
17
18
微生物学的診断
19
①
血液培養で検出されたら必ず原因菌として考える
20
血液培養から黄色ブドウ球菌が検出された場合に、コンタミネーションの可能性
21
は 1~1.5%程度と言われている 3,4。黄色ブドウ球菌菌血症は感染性心内膜炎を含め
22
た様々な病態を合併し、死亡率も高い疾患である 5。このため、血液培養から黄色ブ
23
ドウ球菌が検出された場合、例えそれが 1 ボトルだけであったとしても、コンタミ
24
ネーションとは即断せずに、可能性が否定できるまでは本物の黄色ブドウ球菌菌血
25
症として治療を行う必要がある。薬剤感受性検査を実施する。
26
27
治療
28
②
感染症医へのコンサルテーションが勧められる
29
感染症専門医へのコンサルテーションは、黄色ブドウ球菌菌血症患者において、
30
治療の質(早期感染巣コントロール、血液培養再検、心臓超音波検査、抗菌薬の選
31
択及び投与期間等)を改善するだけでなく、患者死亡率の低下、早期退院につなが
32
るという結果が示されている 5。
33
4