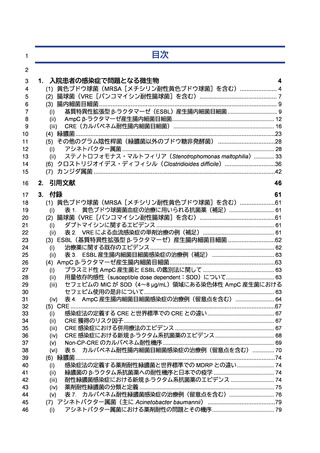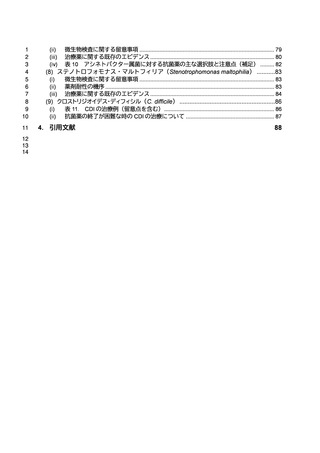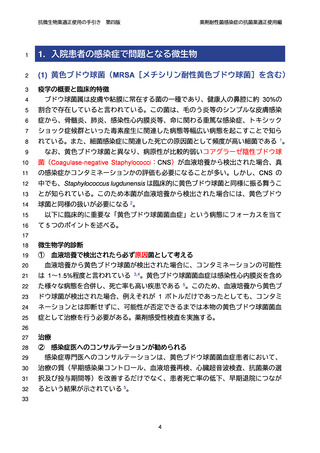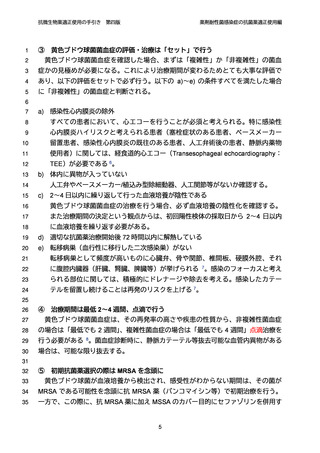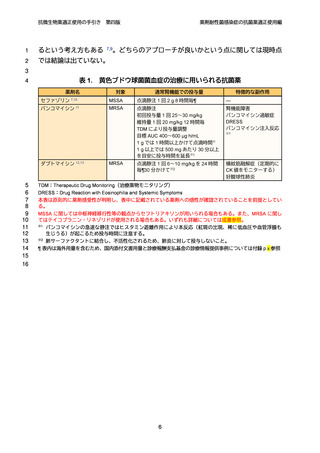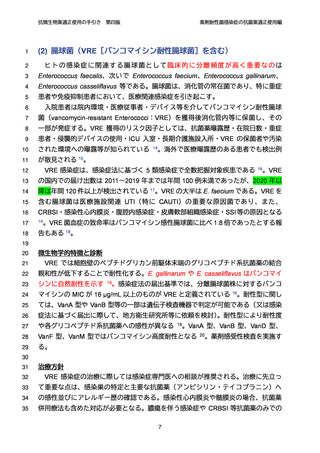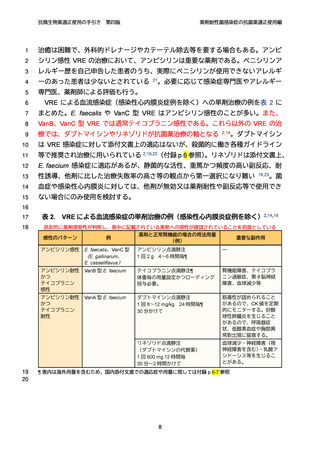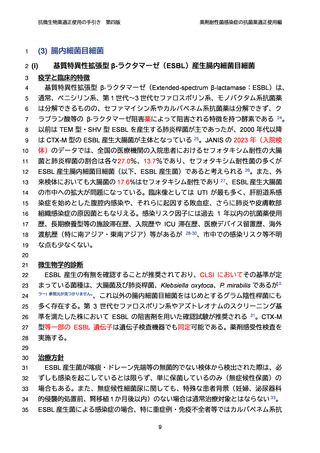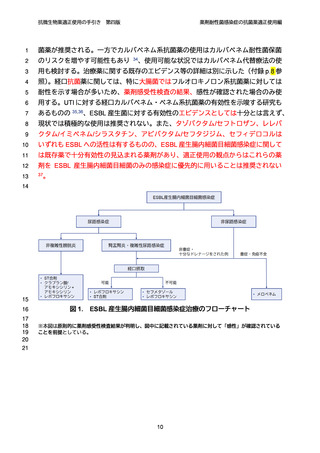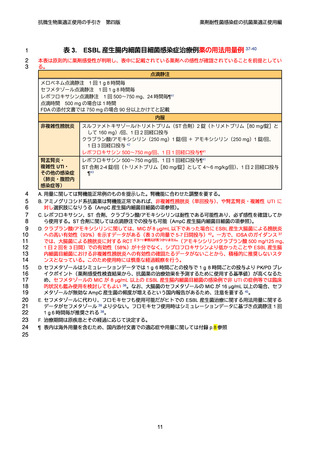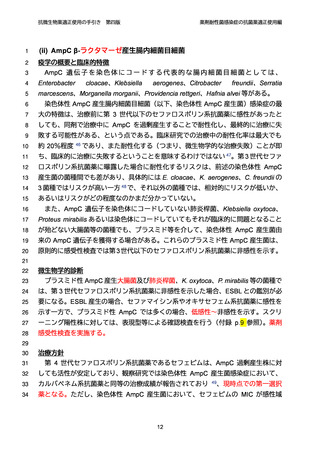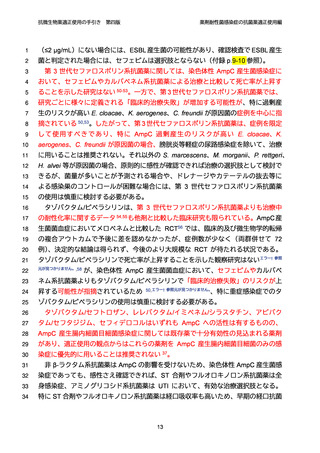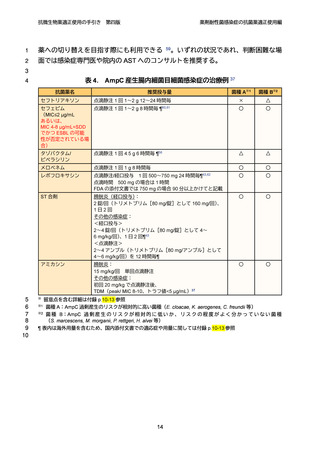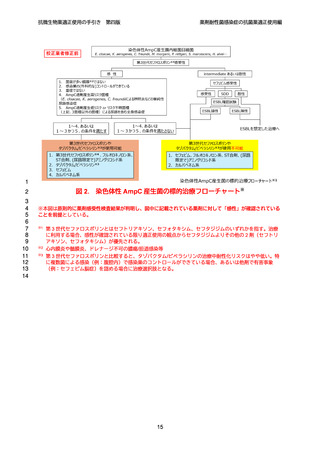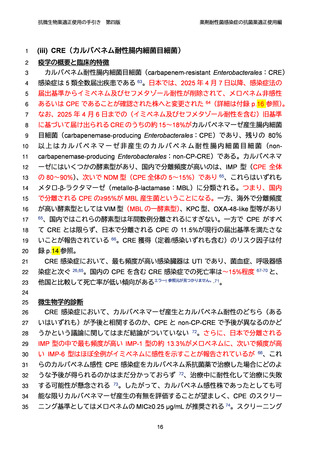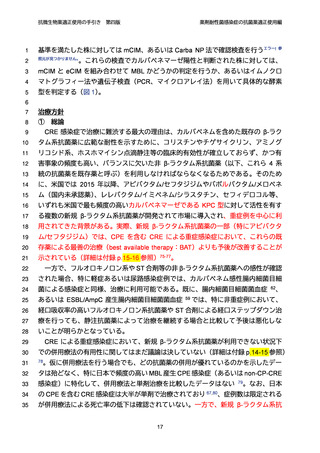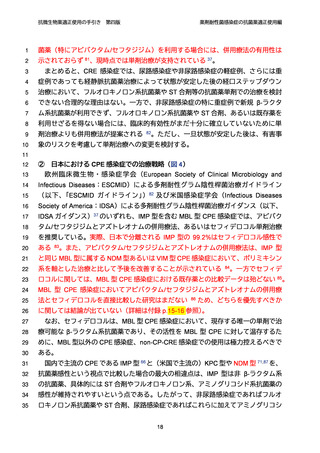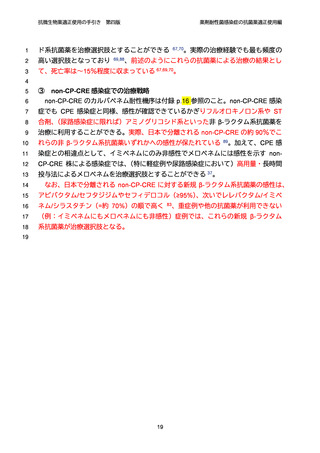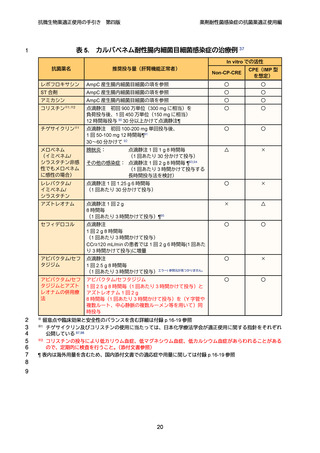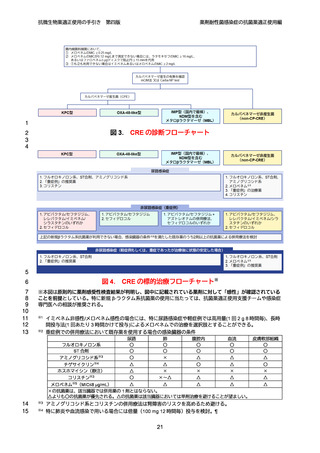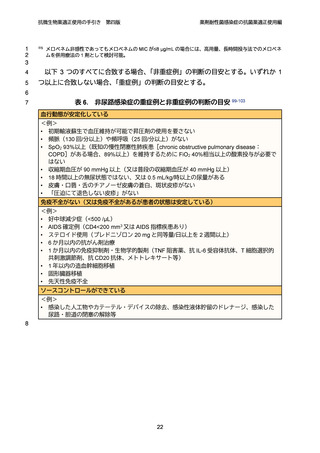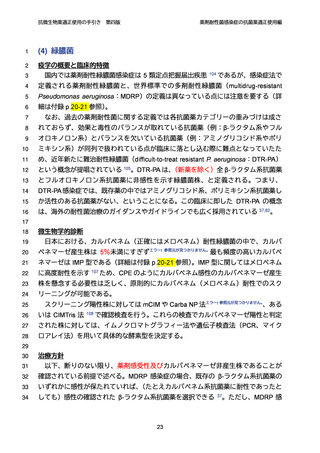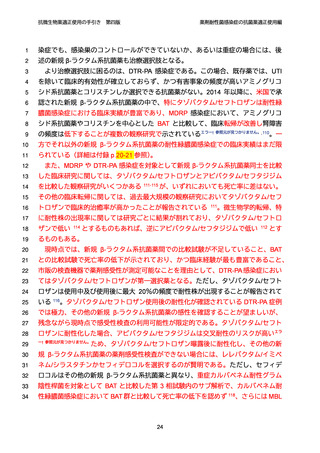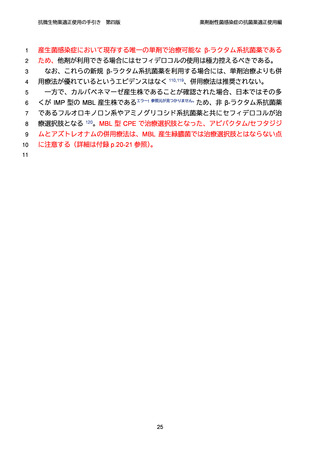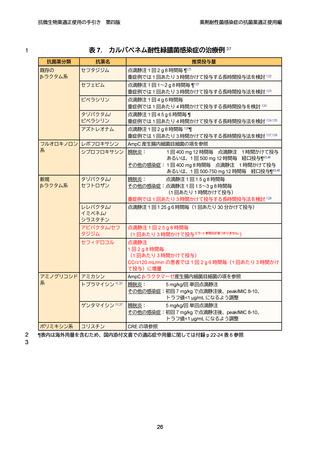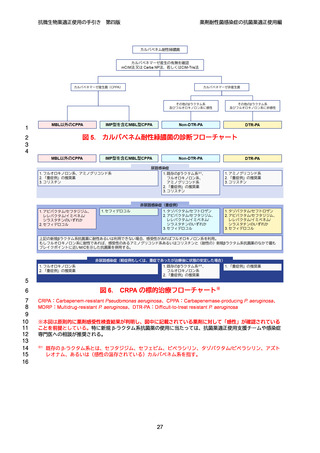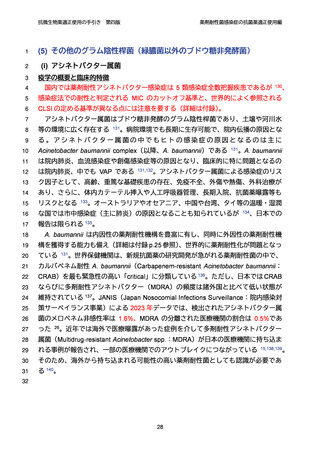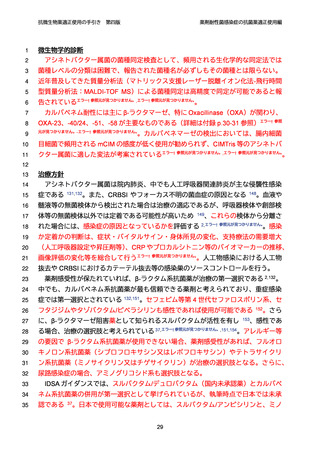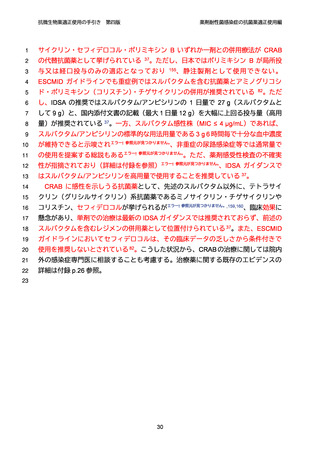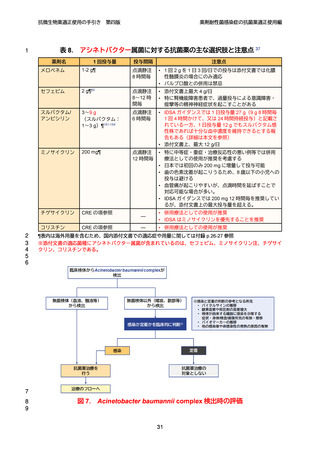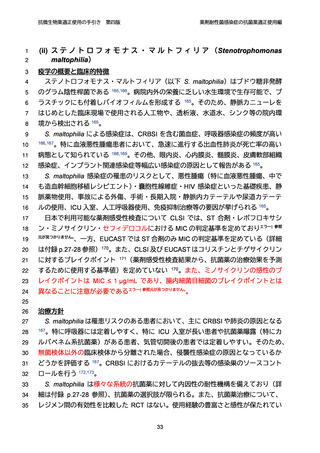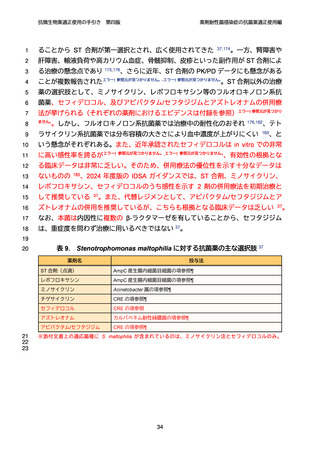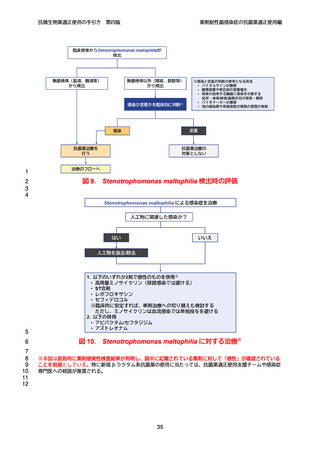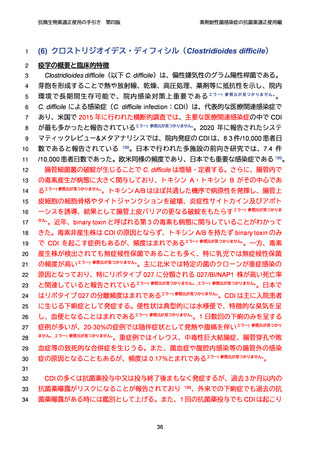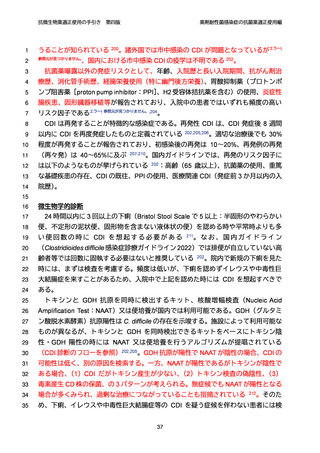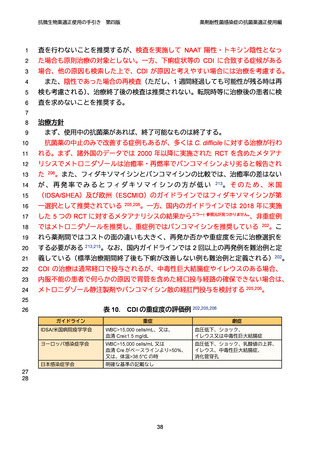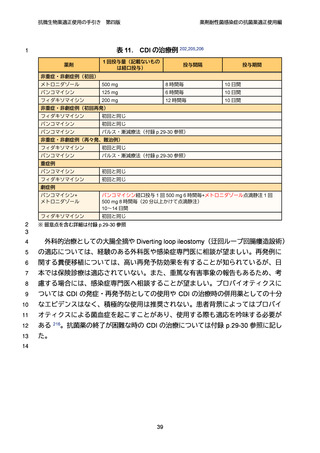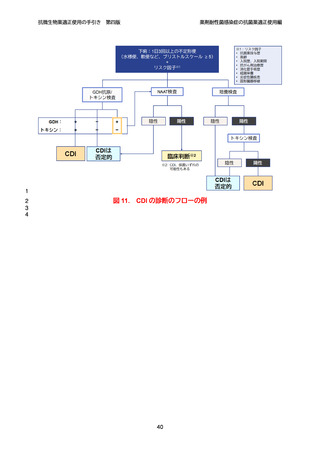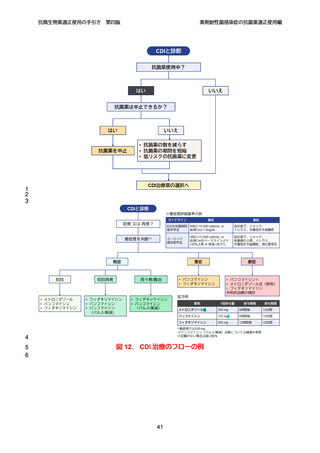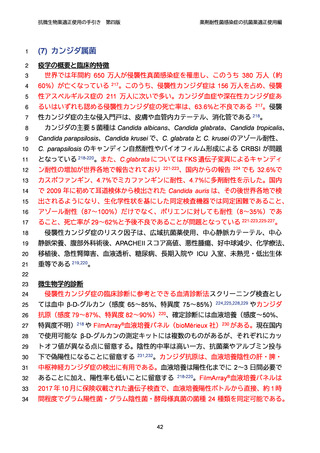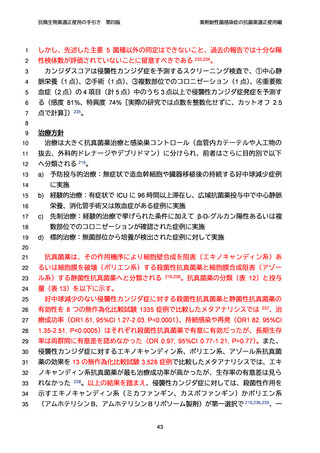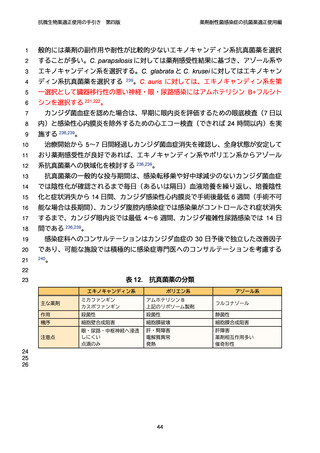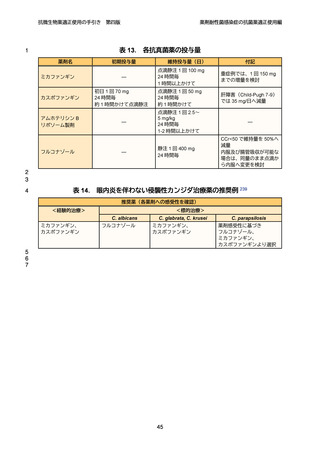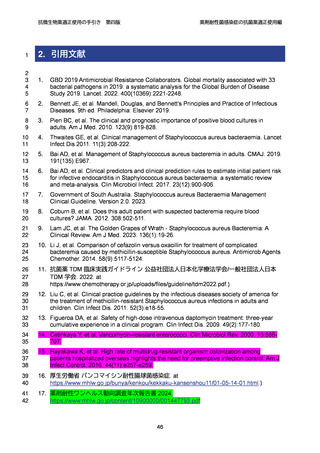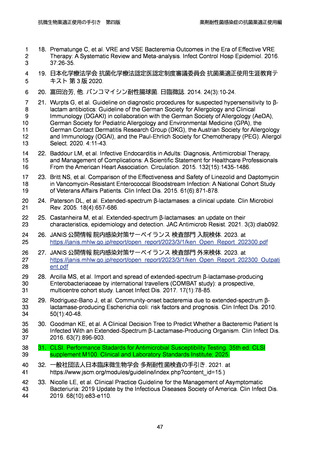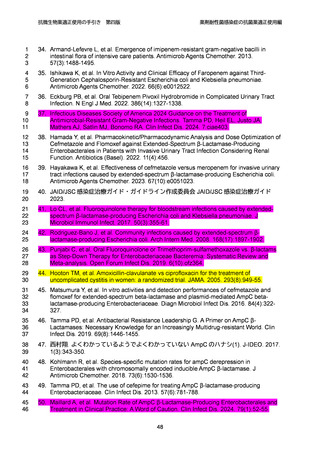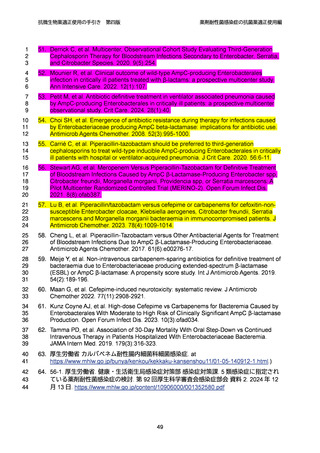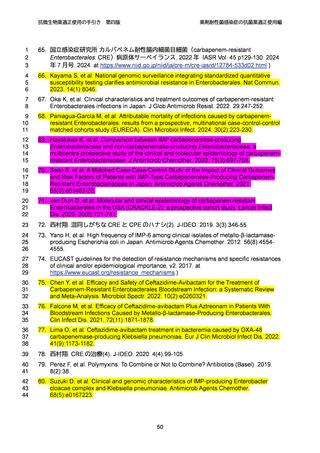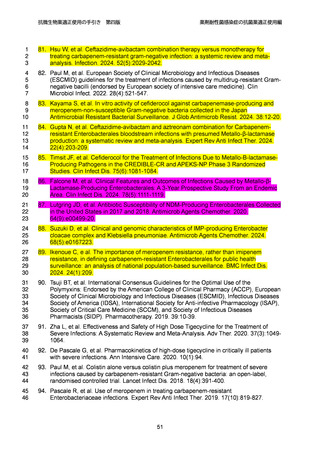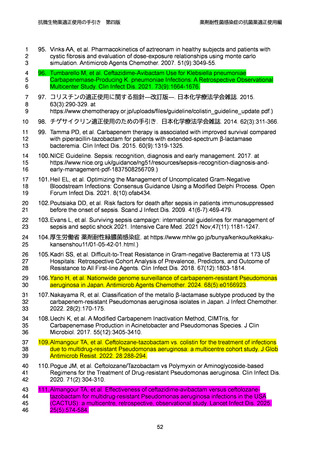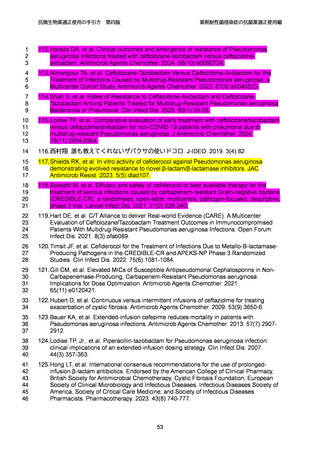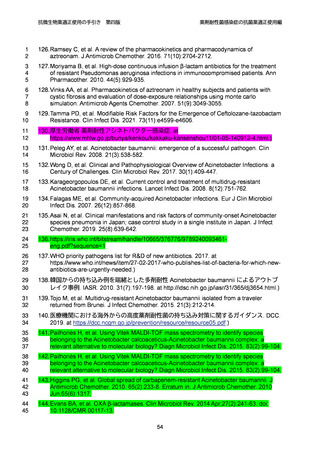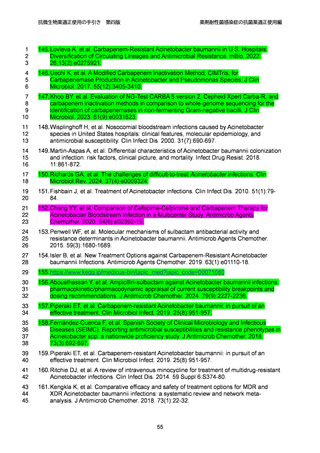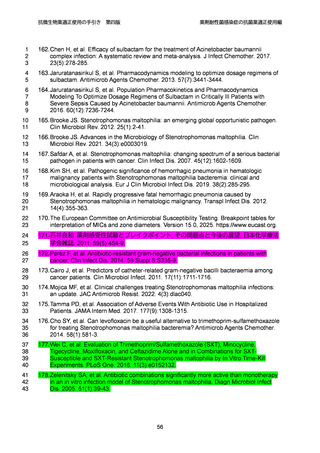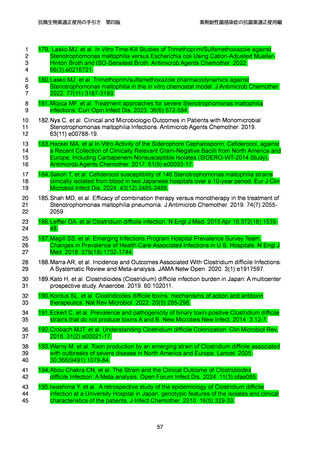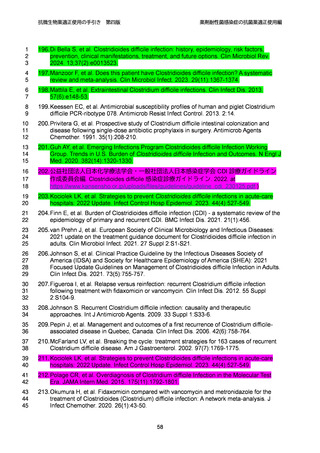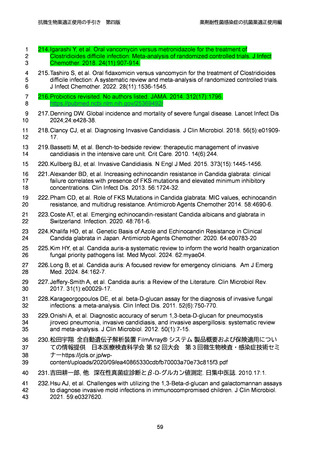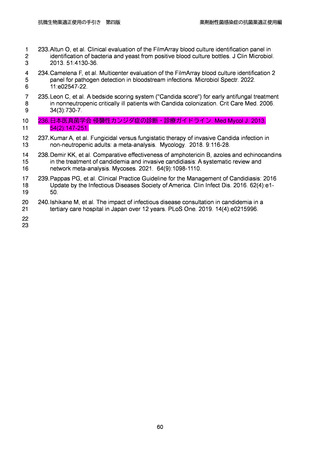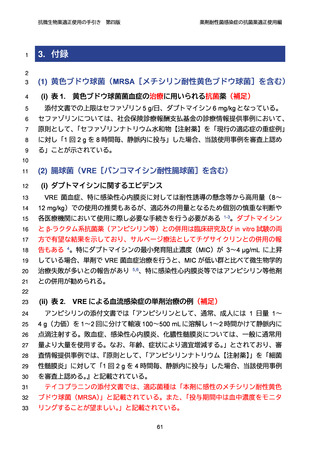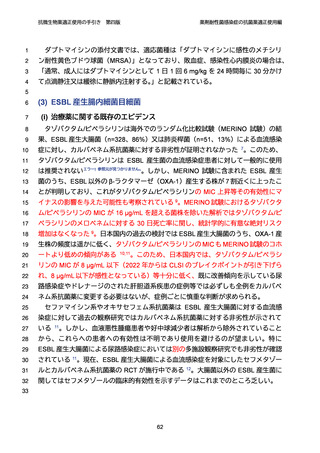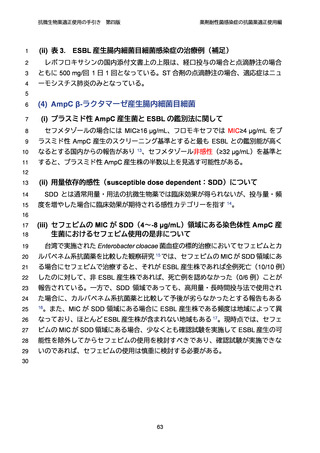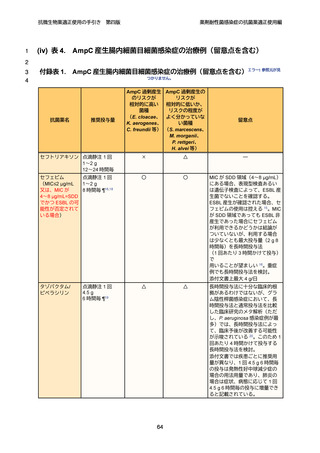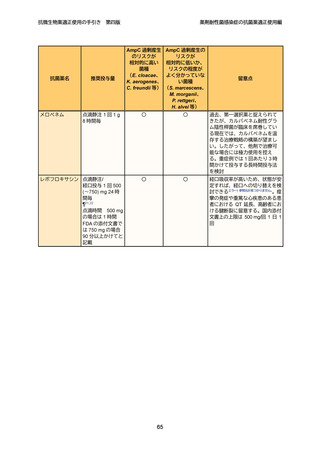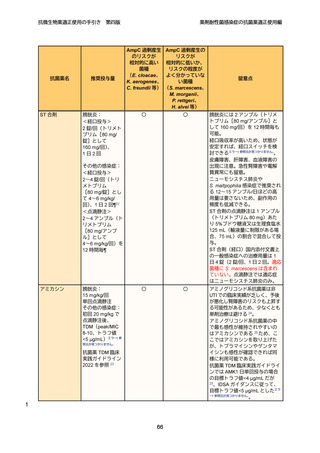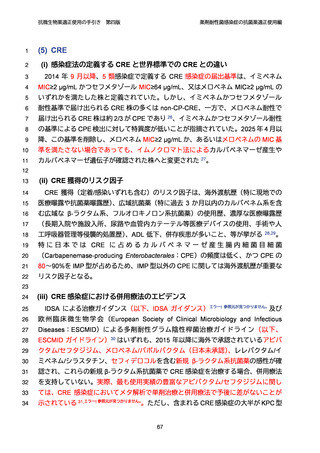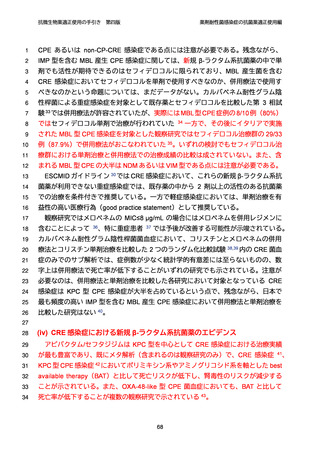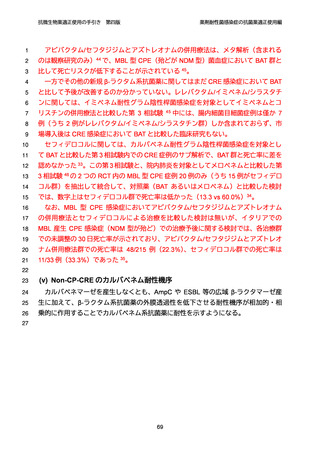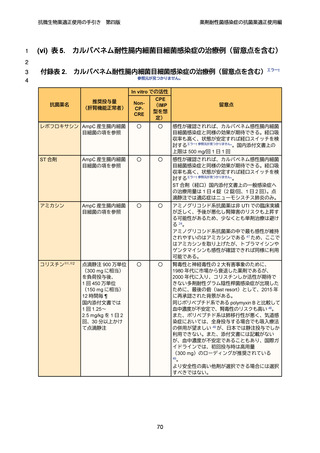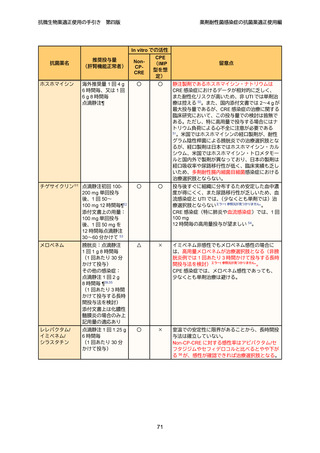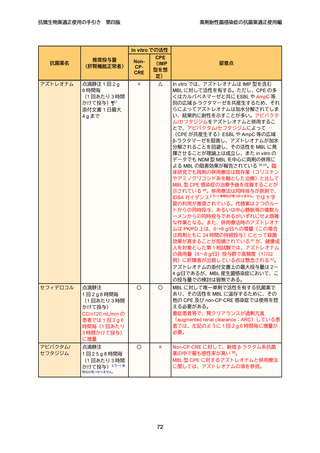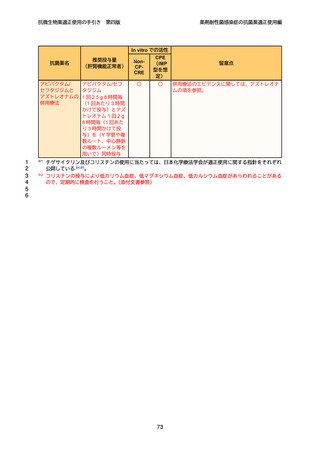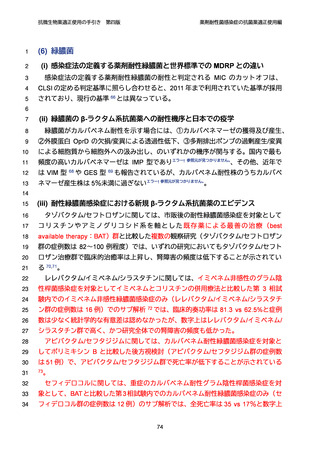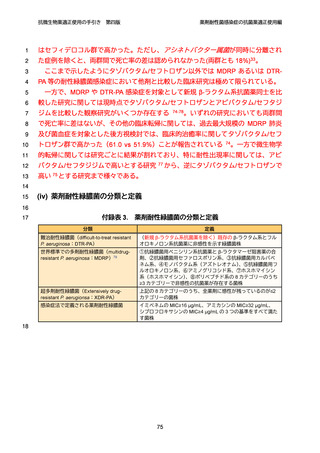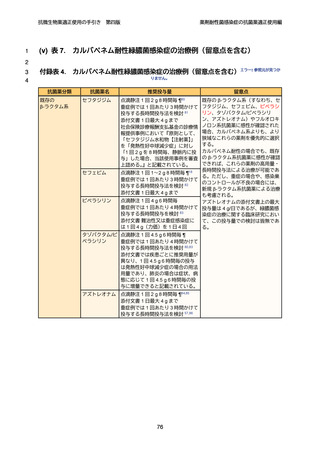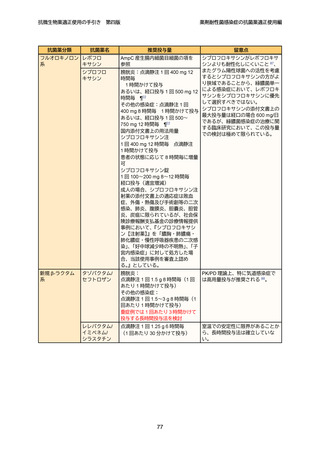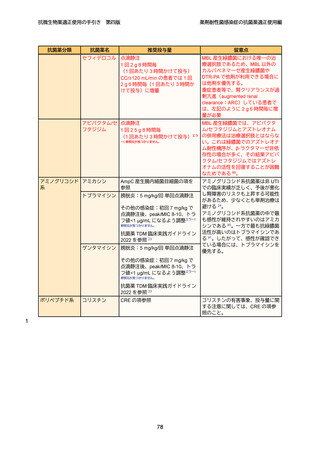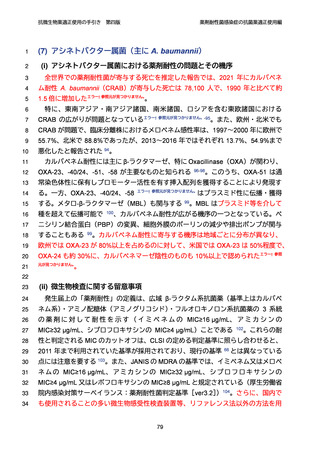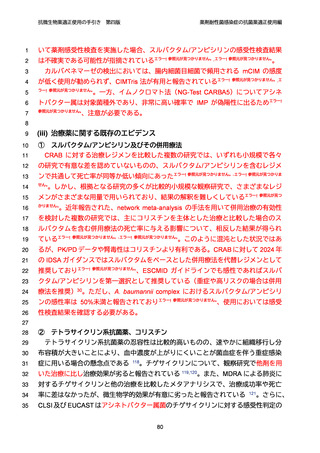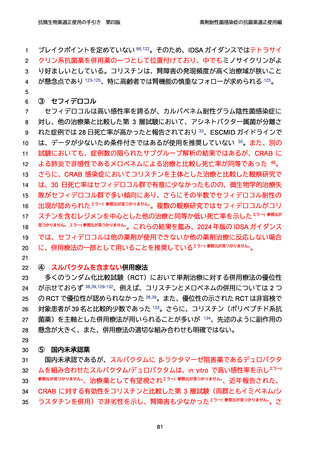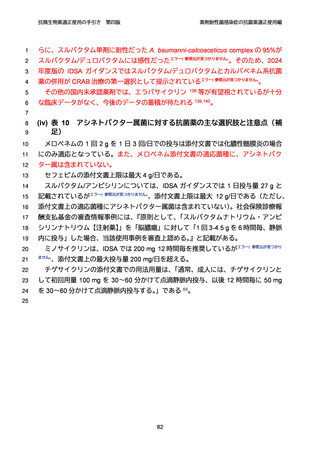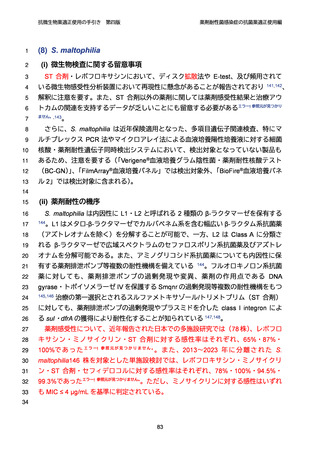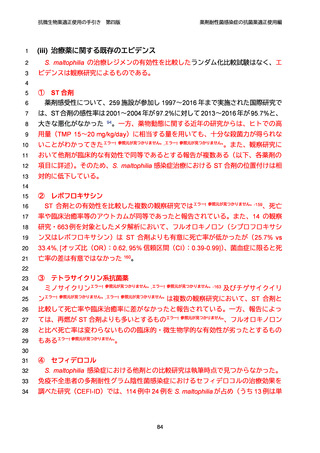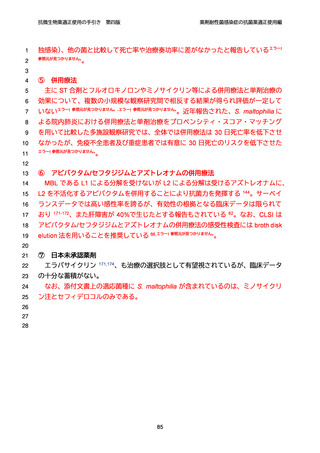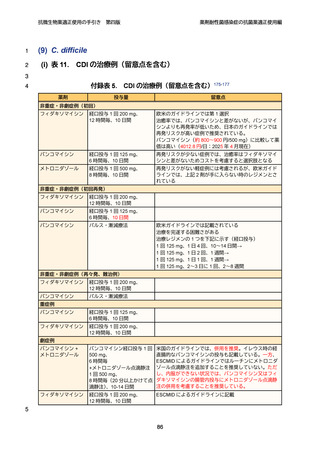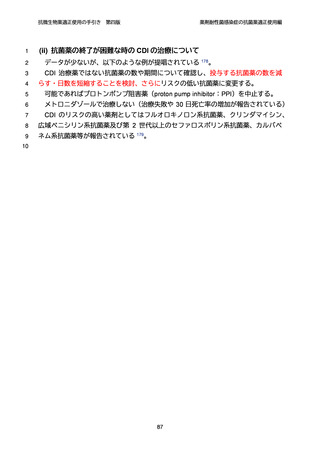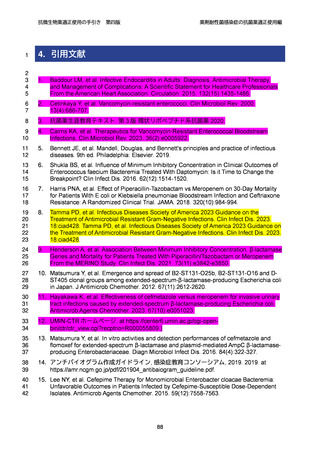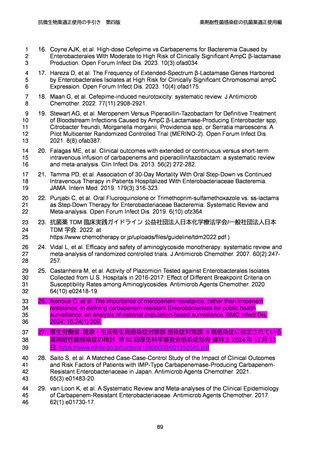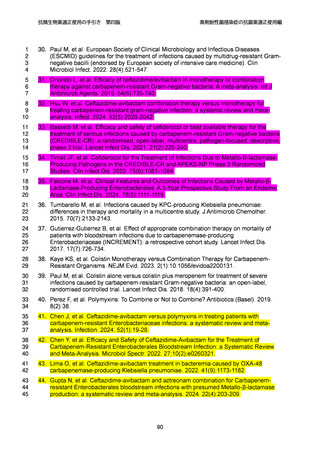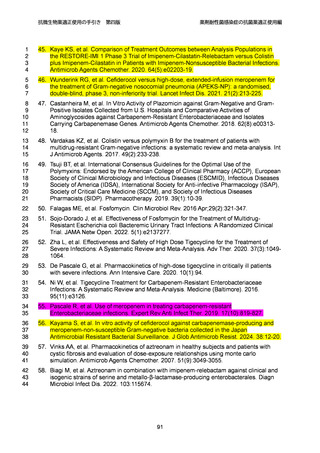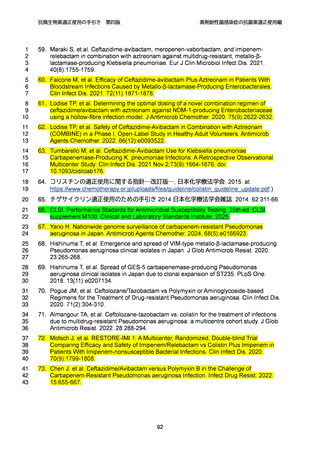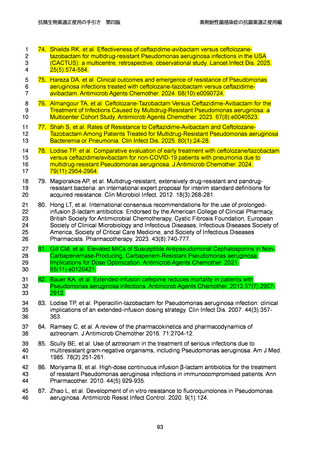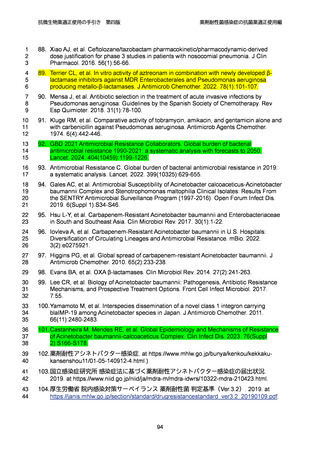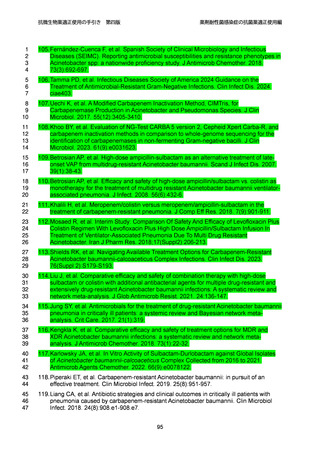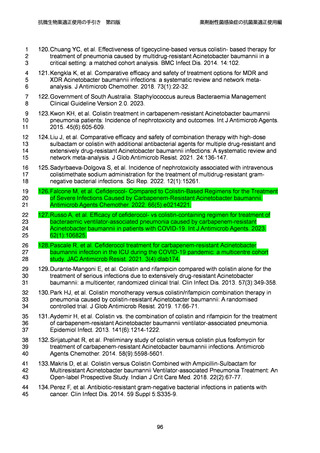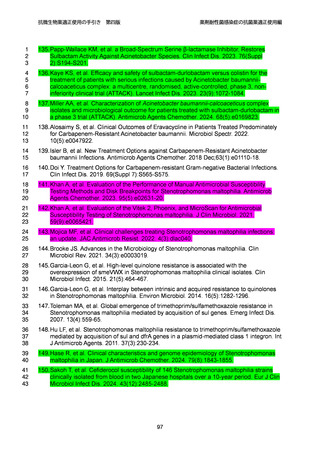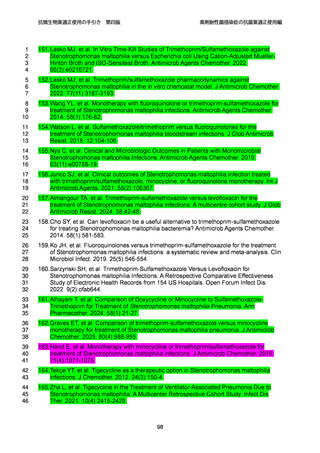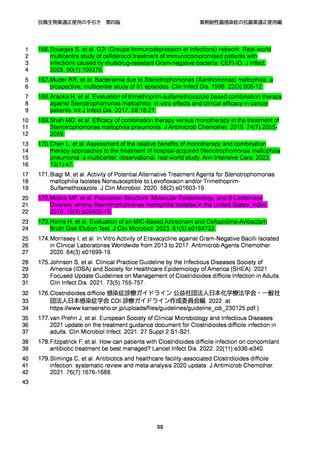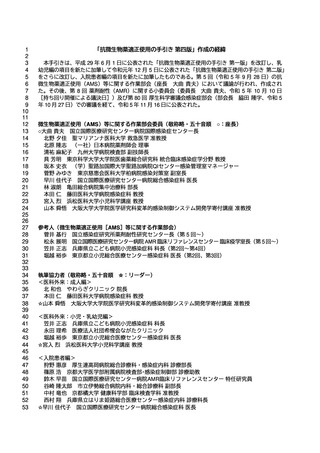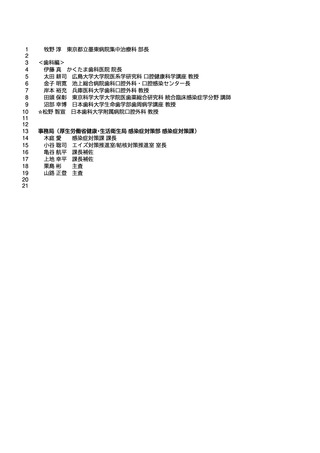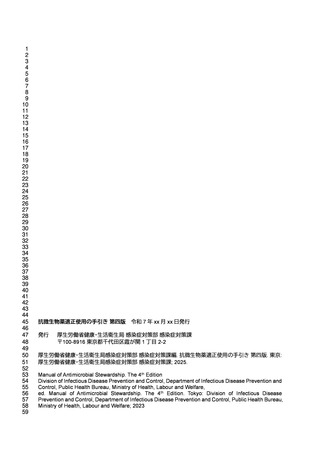よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-3】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
抗微生物薬適正使用の手引き
第四版
薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編
1
(iii) CRE(カルバペネム耐性腸内細菌目細菌)
2
疫学の概要と臨床的特徴
3
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(carbapenem-resistant Enterobacterales:CRE)
4
感染症は 5 類全数届出疾患である 63。日本では、2025 年 4 月 7 日以降、感染症法の
5
届出基準からイミペネム及びセフメタゾール耐性が削除されて、メロぺネム非感性
6
あるいは CPE であることが確認された株へと変更された 64(詳細は付録 p.16 参照)
。
7
なお、2025 年 4 月 6 日までの(イミペネム及びセフメタゾール耐性を含む)旧基準
8
に基づいて届け出られる CRE のうちの約 15~18%がカルバペネマーゼ産生腸内細菌
9
目細菌(carbapenemase-producing Enterobacterales:CPE)であり、残りの 80%
10
以 上 は カ ル バ ペ ネ マ ー ゼ 非 産 生 の カ ル バ ペ ネ ム 耐 性 腸 内 細 菌 目 細 菌 (non-
11
carbapenemase-producing Enterobacterales:non-CP-CRE)である。カルバペネマ
12
ーゼにはいくつかの酵素型があり、国内で分離頻度が高いのは、IMP 型(CPE 全体
13
の 80~90%)、次いで NDM 型(CPE 全体の 5~15%)であり 65、これらはいずれも
14
メタロ-β-ラクタマーゼ(metallo-β-lactamase:MBL)に分類される。つまり、国内
15
で分離される CPE の≥95%が MBL 産生菌ということになる。一方、海外で分離頻度
16
が高い酵素型としては VIM 型(MBL の一酵素型)、KPC 型、OXA-48-like 型等があり
17
65、国内ではこれらの酵素型は年間数例分離されるにすぎない。一方で
18
て CRE とは限らず、日本で分離される CPE の 11.5%が現行の届出基準を満たさな
19
いことが報告されている 66。CRE 獲得(定着/感染いずれも含む)のリスク因子は付
20
録 p.14 参照。
CPE がすべ
21
CRE 感染症において、最も頻度が高い感染臓器は UTI であり、菌血症、呼吸器感
22
染症と次ぐ 26,65。国内の CPE を含む CRE 感染症での死亡率は~15%程度 67-70 と、
23
他国と比較して死亡率が低い傾向があるエラー! 参照元が見つかりません。,71。
24
25
微生物学的診断
26
CRE 感染症において、カルバペネマーゼ産生とカルバペネム耐性のどちら(ある
27
いはいずれも)が予後と相関するのか、CPE と non-CP-CRE で予後が異なるのかど
28
うかという議論に関してはまだ結論がついていない 72。さらに、日本で分離される
29
IMP 型の中で最も頻度が高い IMP-1 型の約 13.3%がメロペネムに、次いで頻度が高
30
い IMP-6 型はほぼ全例がイミペネムに感性を示すことが報告されているが 66、これ
31
らのカルバペネム感性 CPE 感染症をカルバペネム系抗菌薬で治療した場合にどのよ
32
うな予後が得られるのかはまだ分かっておらず 72、治療中に耐性化して治療に失敗
33
する可能性が懸念される 73。したがって、カルバペネム感性株であったとしても可
34
能な限りカルバペネマーゼ産生の有無を評価することが望ましく、CPE のスクリー
35
ニング基準としてはメロペネムの MIC≥0.25 μg/mL が推奨される 74。スクリーニング
16
第四版
薬剤耐性菌感染症の抗菌薬適正使用編
1
(iii) CRE(カルバペネム耐性腸内細菌目細菌)
2
疫学の概要と臨床的特徴
3
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(carbapenem-resistant Enterobacterales:CRE)
4
感染症は 5 類全数届出疾患である 63。日本では、2025 年 4 月 7 日以降、感染症法の
5
届出基準からイミペネム及びセフメタゾール耐性が削除されて、メロぺネム非感性
6
あるいは CPE であることが確認された株へと変更された 64(詳細は付録 p.16 参照)
。
7
なお、2025 年 4 月 6 日までの(イミペネム及びセフメタゾール耐性を含む)旧基準
8
に基づいて届け出られる CRE のうちの約 15~18%がカルバペネマーゼ産生腸内細菌
9
目細菌(carbapenemase-producing Enterobacterales:CPE)であり、残りの 80%
10
以 上 は カ ル バ ペ ネ マ ー ゼ 非 産 生 の カ ル バ ペ ネ ム 耐 性 腸 内 細 菌 目 細 菌 (non-
11
carbapenemase-producing Enterobacterales:non-CP-CRE)である。カルバペネマ
12
ーゼにはいくつかの酵素型があり、国内で分離頻度が高いのは、IMP 型(CPE 全体
13
の 80~90%)、次いで NDM 型(CPE 全体の 5~15%)であり 65、これらはいずれも
14
メタロ-β-ラクタマーゼ(metallo-β-lactamase:MBL)に分類される。つまり、国内
15
で分離される CPE の≥95%が MBL 産生菌ということになる。一方、海外で分離頻度
16
が高い酵素型としては VIM 型(MBL の一酵素型)、KPC 型、OXA-48-like 型等があり
17
65、国内ではこれらの酵素型は年間数例分離されるにすぎない。一方で
18
て CRE とは限らず、日本で分離される CPE の 11.5%が現行の届出基準を満たさな
19
いことが報告されている 66。CRE 獲得(定着/感染いずれも含む)のリスク因子は付
20
録 p.14 参照。
CPE がすべ
21
CRE 感染症において、最も頻度が高い感染臓器は UTI であり、菌血症、呼吸器感
22
染症と次ぐ 26,65。国内の CPE を含む CRE 感染症での死亡率は~15%程度 67-70 と、
23
他国と比較して死亡率が低い傾向があるエラー! 参照元が見つかりません。,71。
24
25
微生物学的診断
26
CRE 感染症において、カルバペネマーゼ産生とカルバペネム耐性のどちら(ある
27
いはいずれも)が予後と相関するのか、CPE と non-CP-CRE で予後が異なるのかど
28
うかという議論に関してはまだ結論がついていない 72。さらに、日本で分離される
29
IMP 型の中で最も頻度が高い IMP-1 型の約 13.3%がメロペネムに、次いで頻度が高
30
い IMP-6 型はほぼ全例がイミペネムに感性を示すことが報告されているが 66、これ
31
らのカルバペネム感性 CPE 感染症をカルバペネム系抗菌薬で治療した場合にどのよ
32
うな予後が得られるのかはまだ分かっておらず 72、治療中に耐性化して治療に失敗
33
する可能性が懸念される 73。したがって、カルバペネム感性株であったとしても可
34
能な限りカルバペネマーゼ産生の有無を評価することが望ましく、CPE のスクリー
35
ニング基準としてはメロペネムの MIC≥0.25 μg/mL が推奨される 74。スクリーニング
16