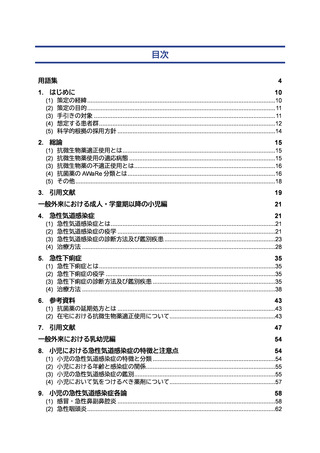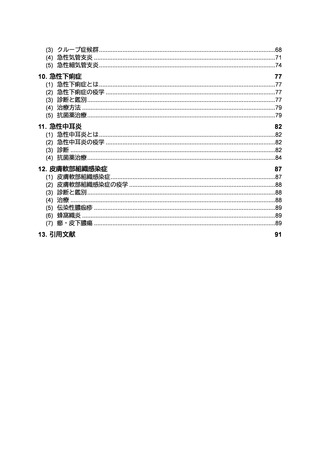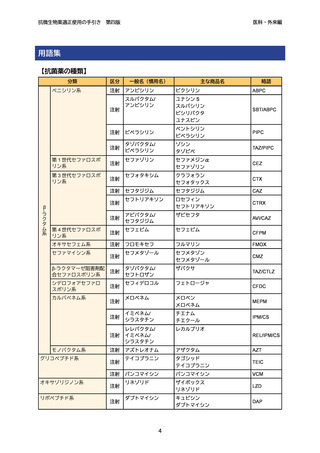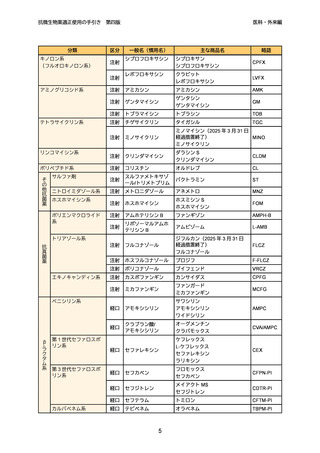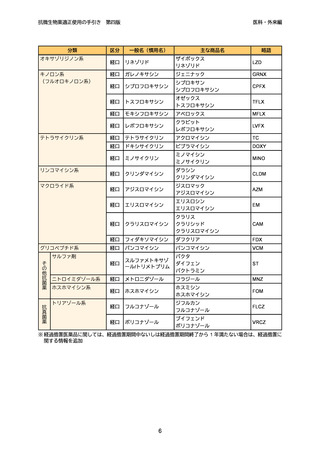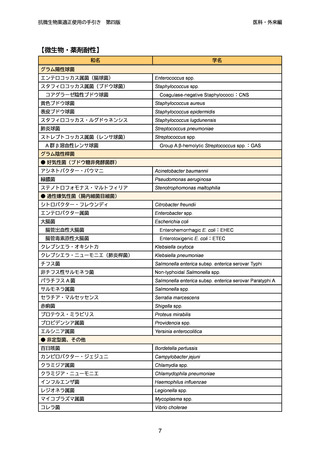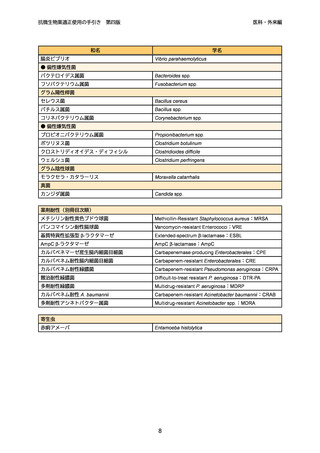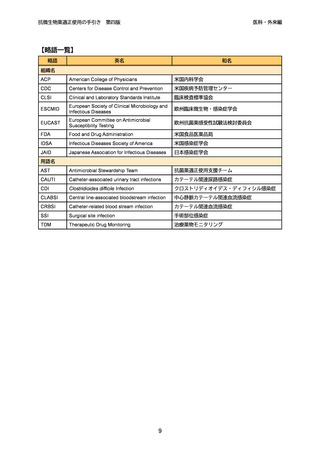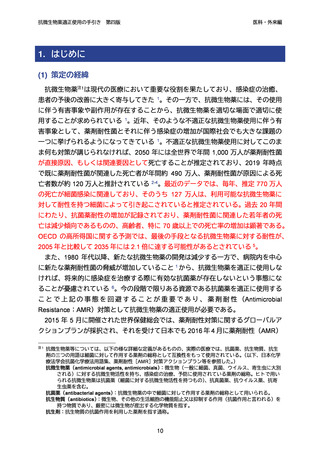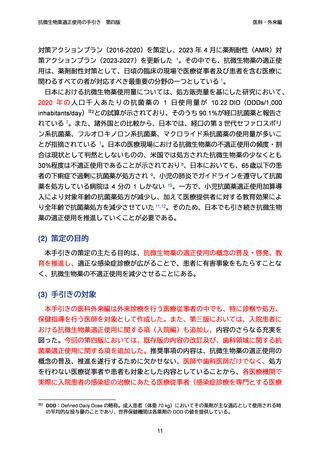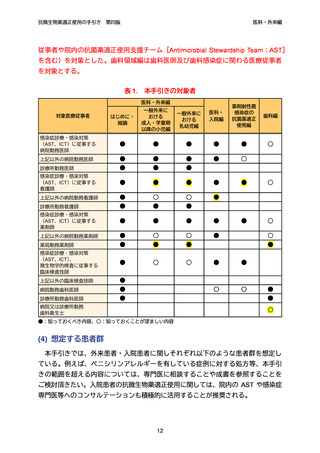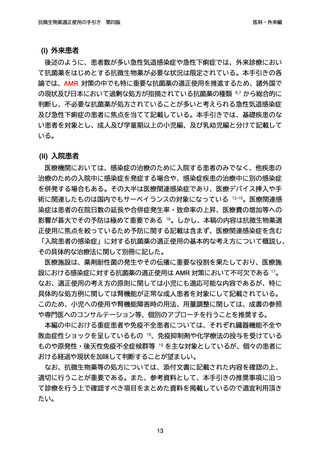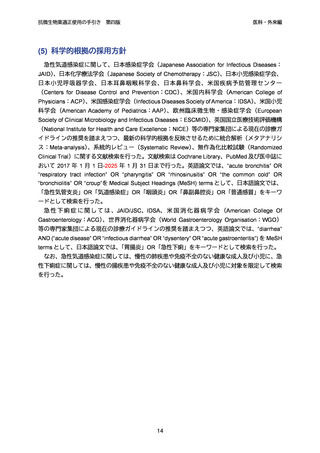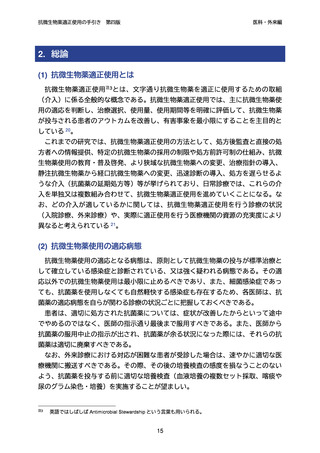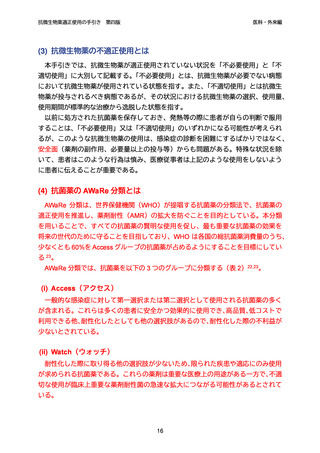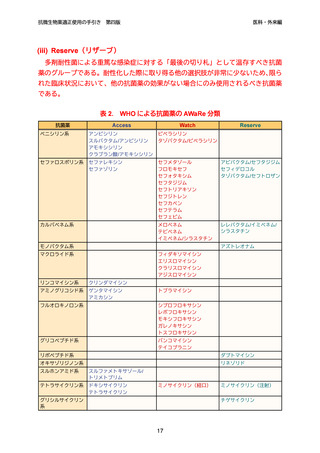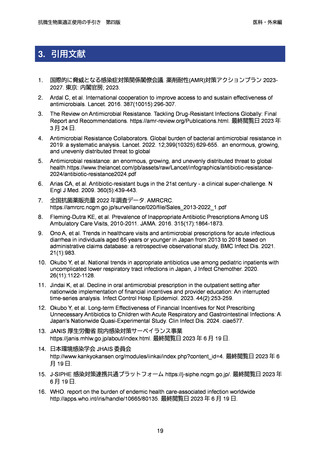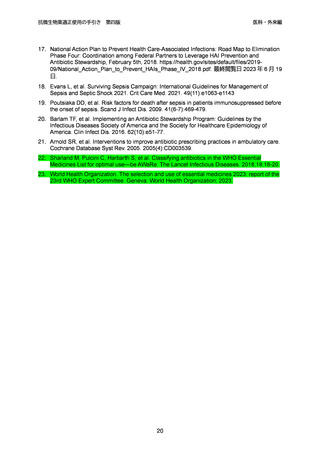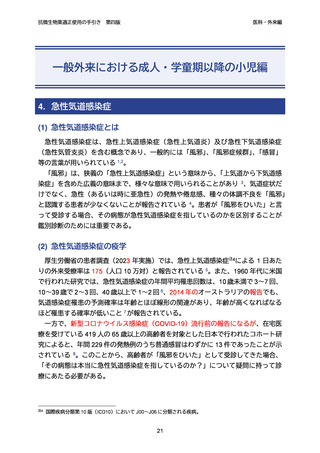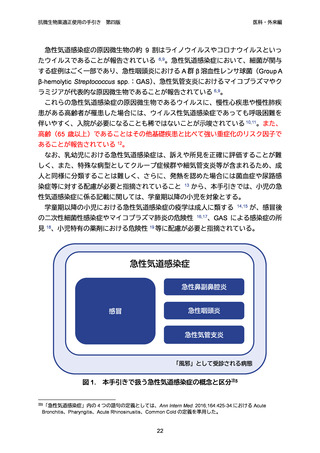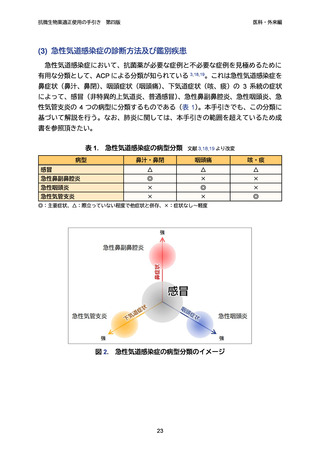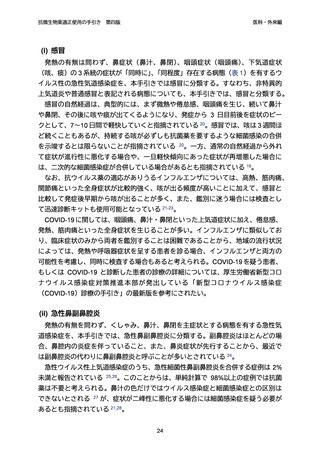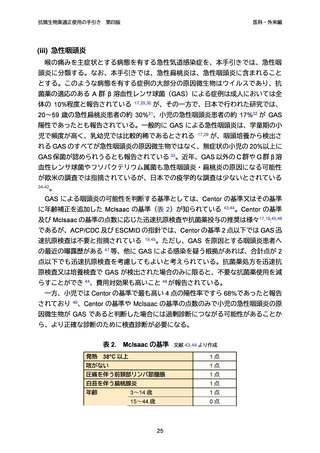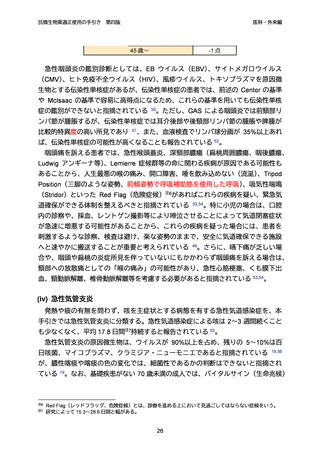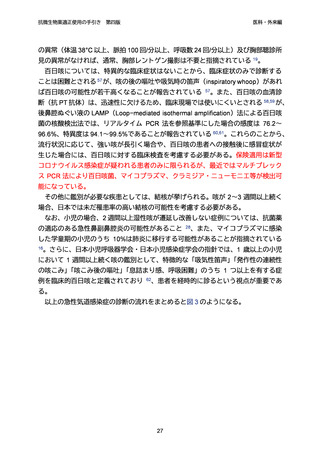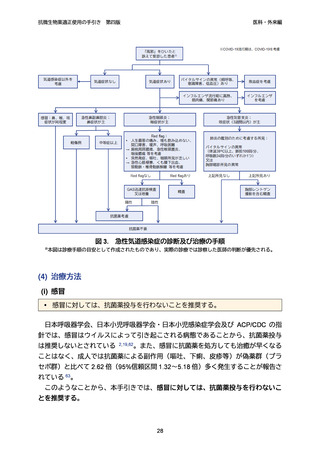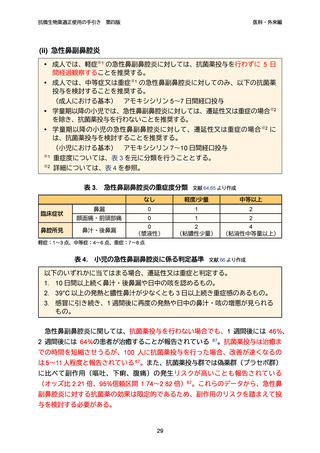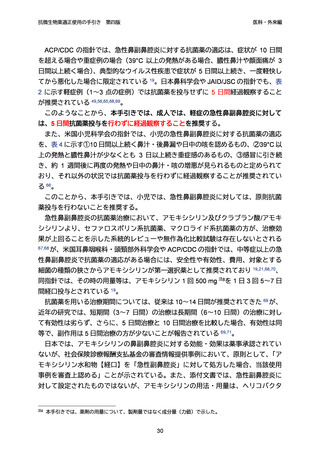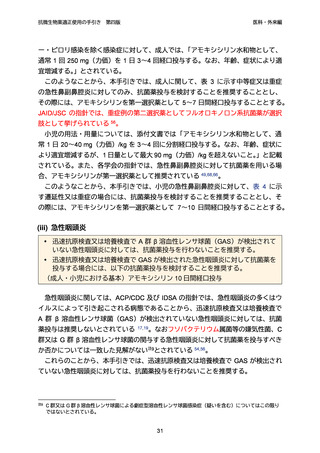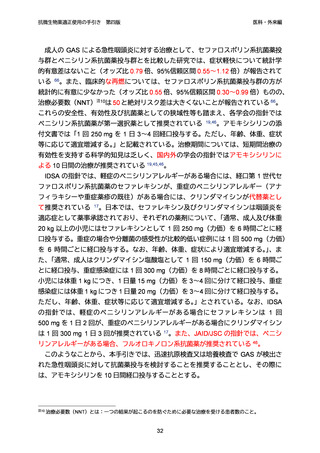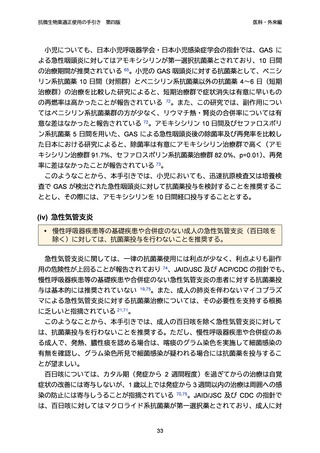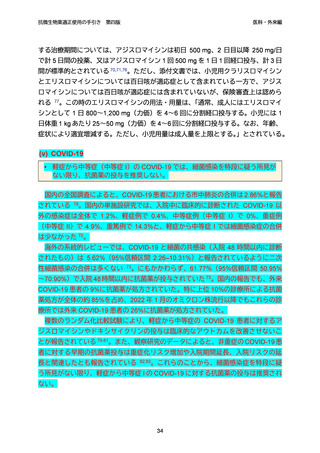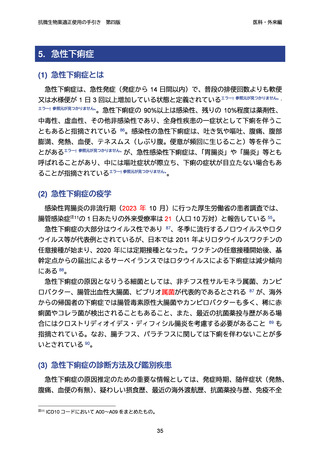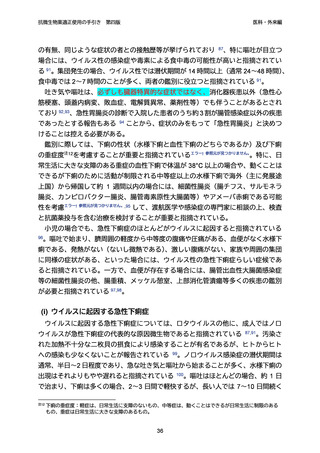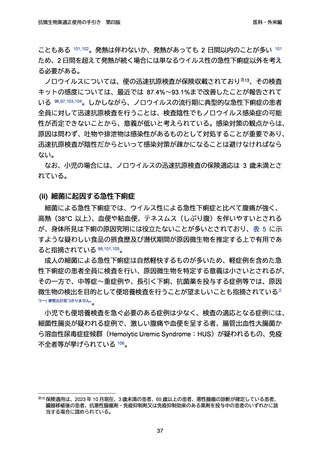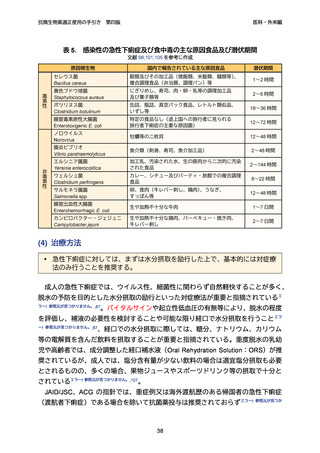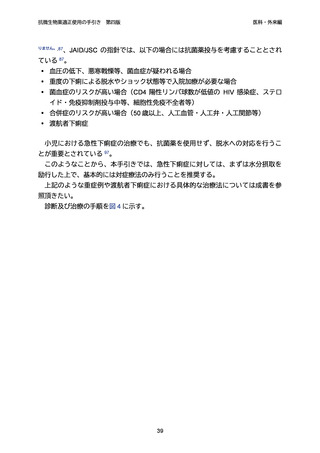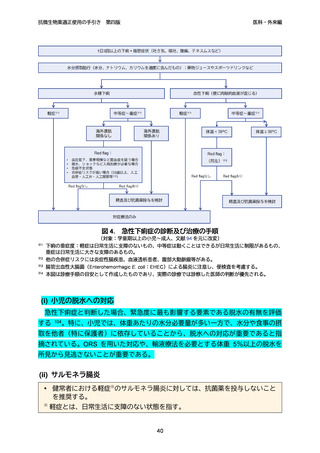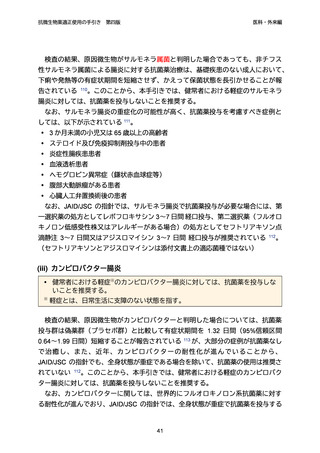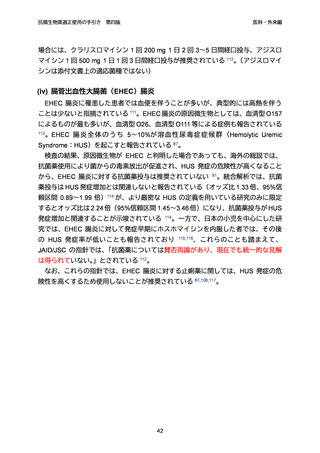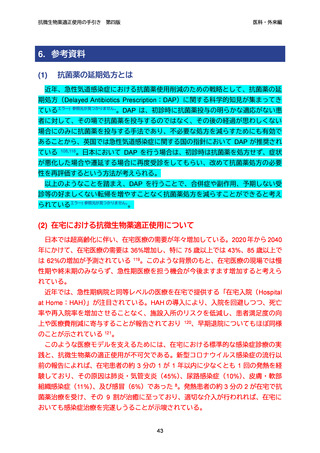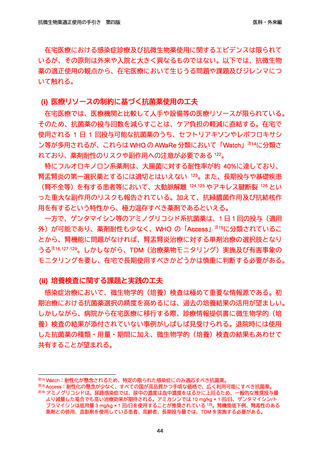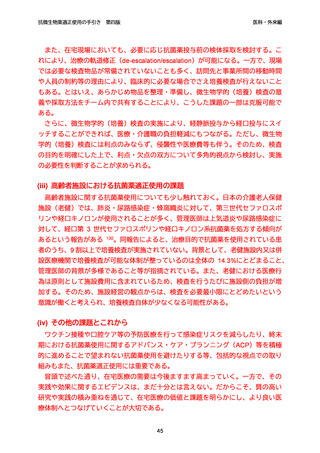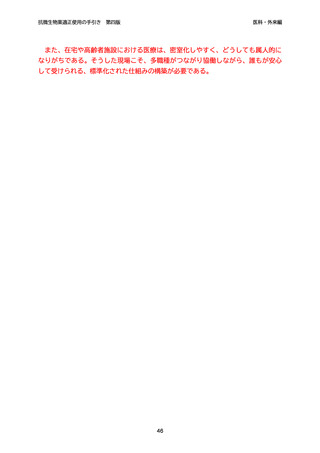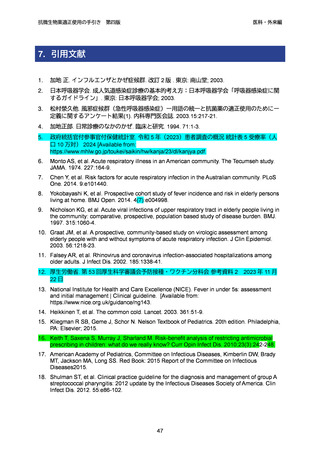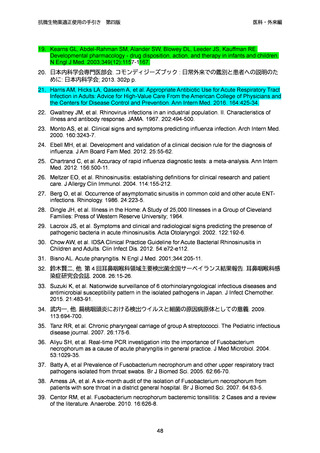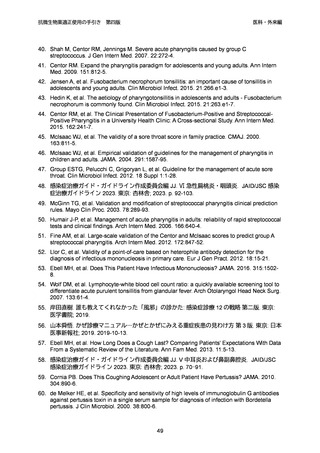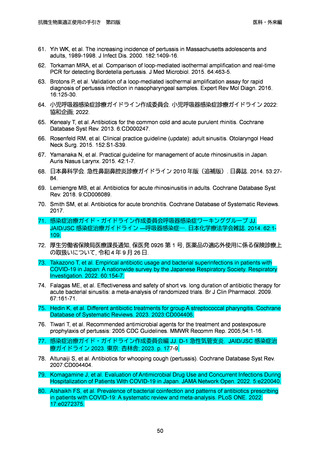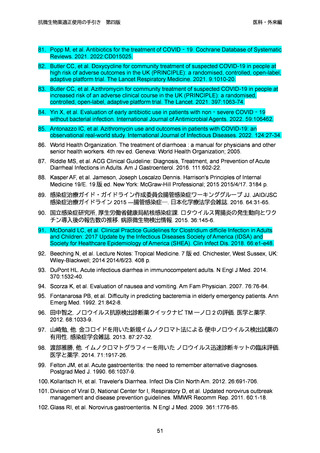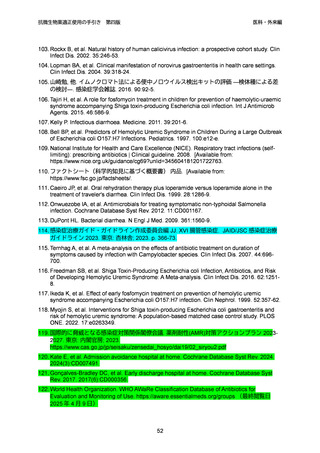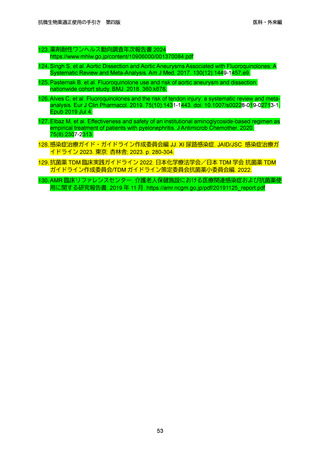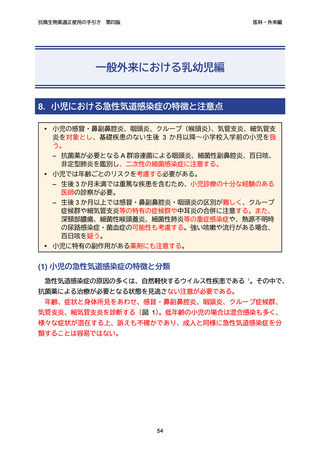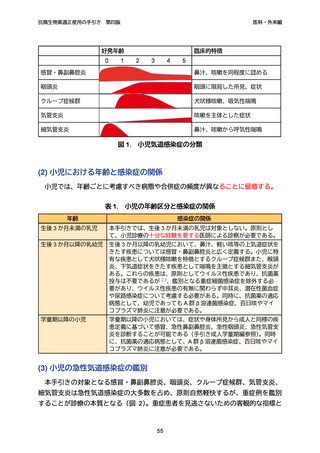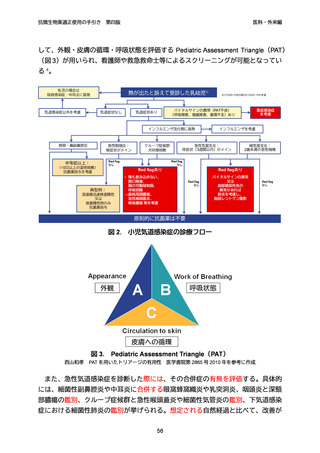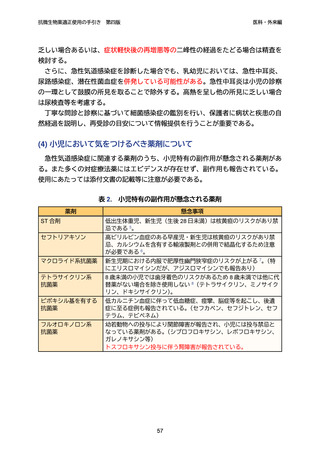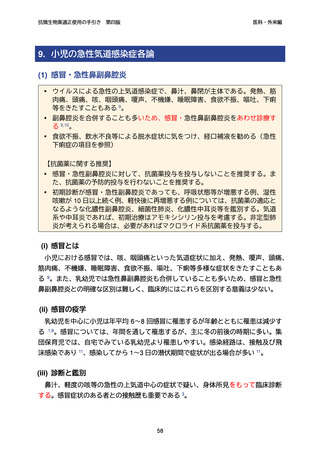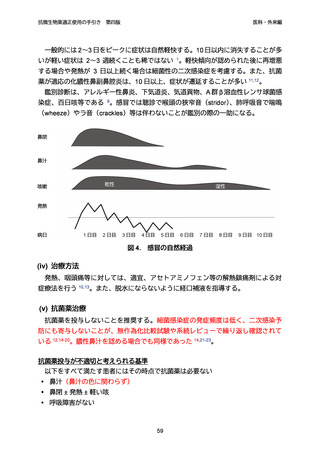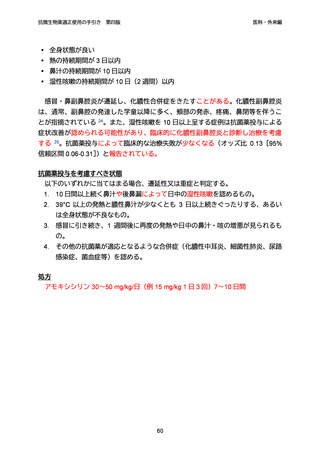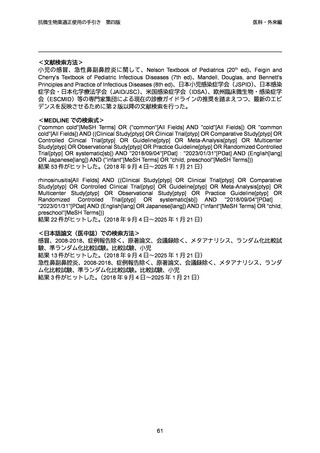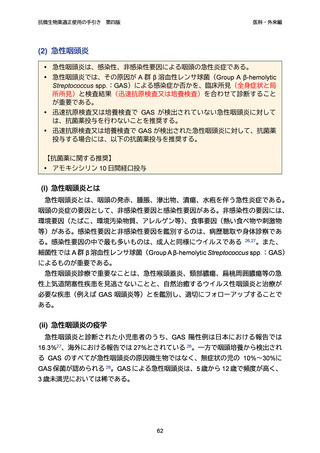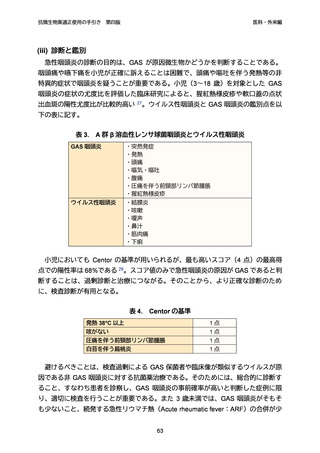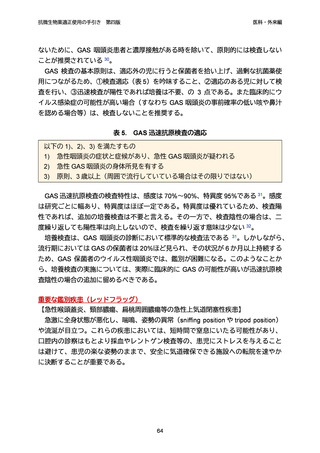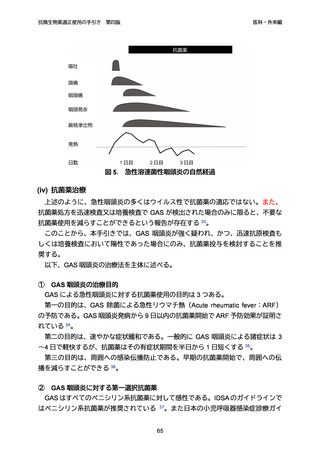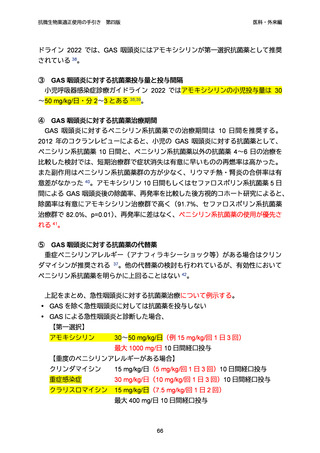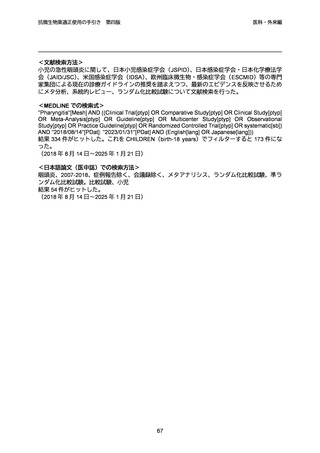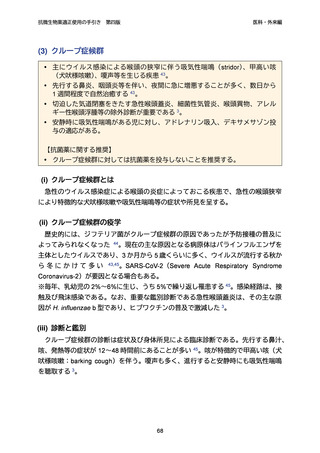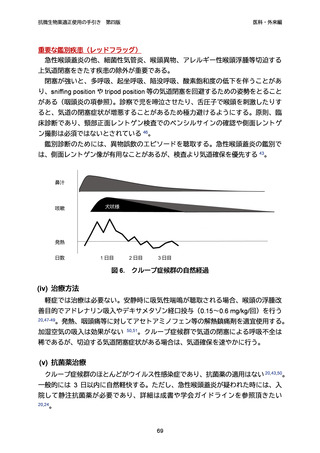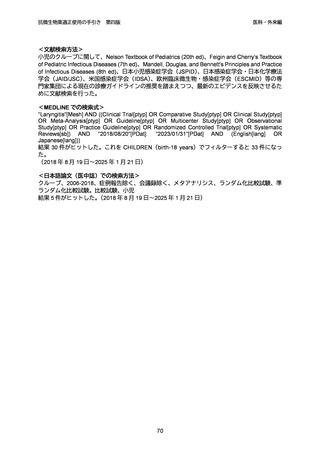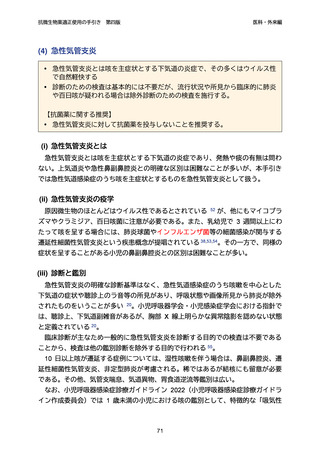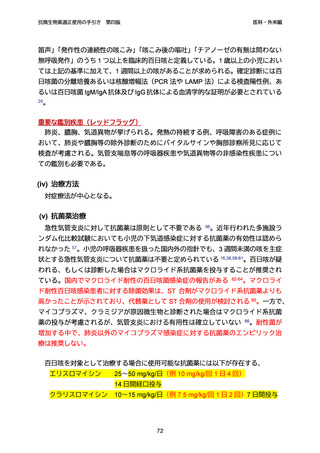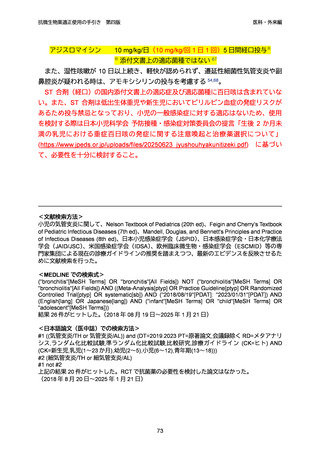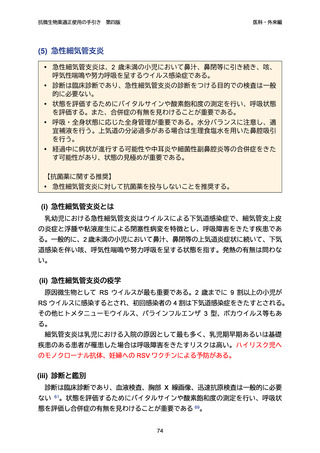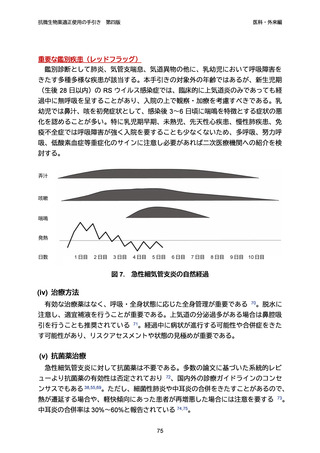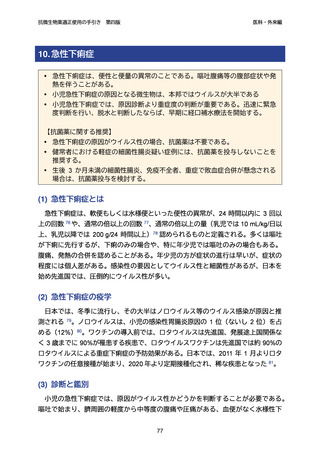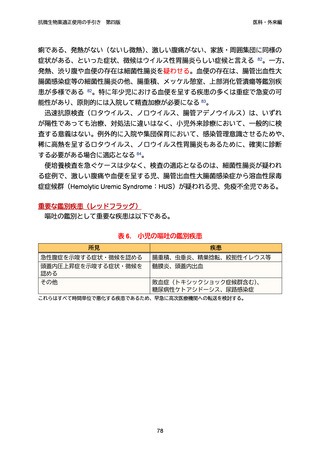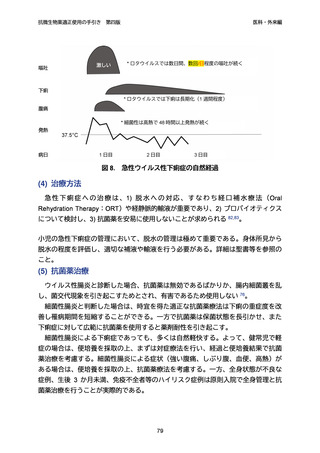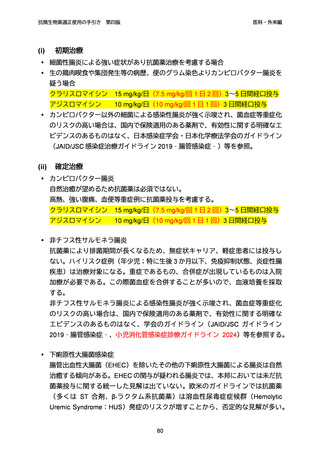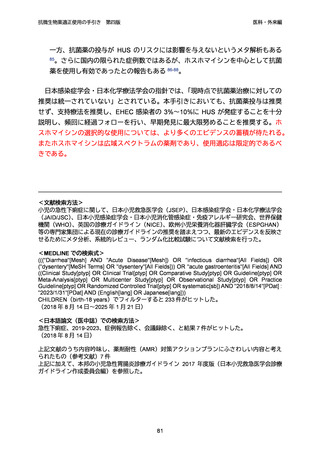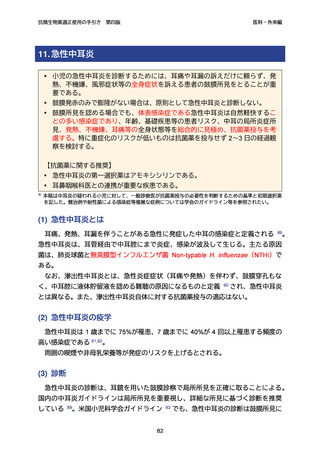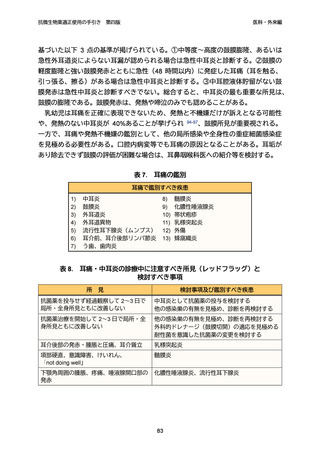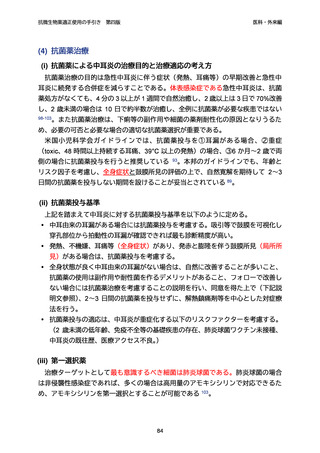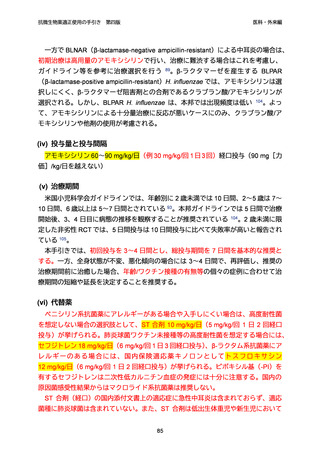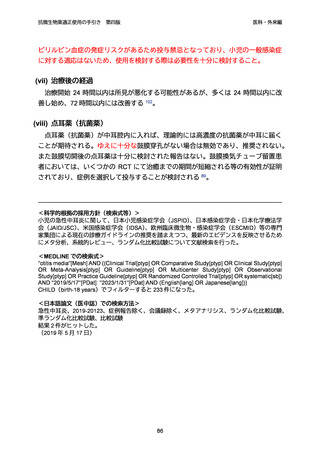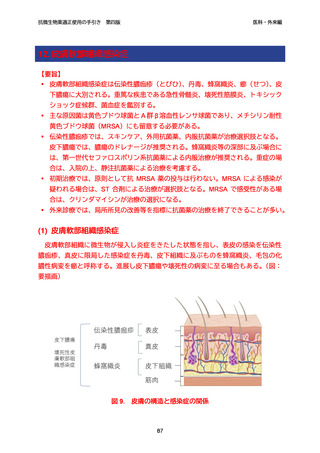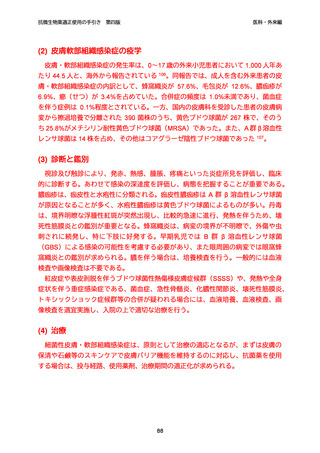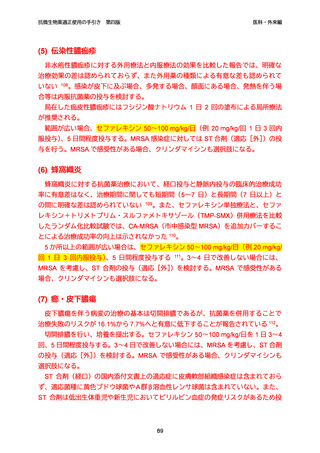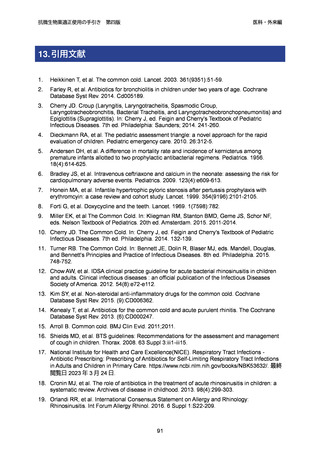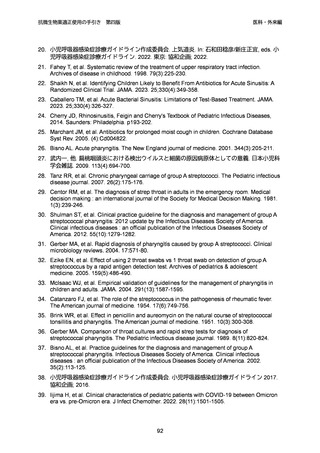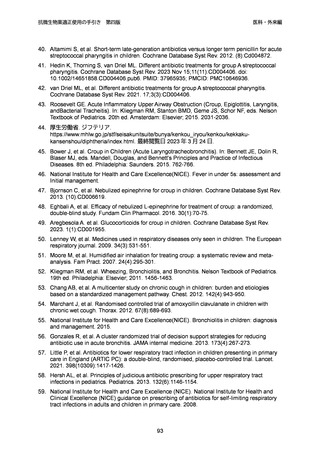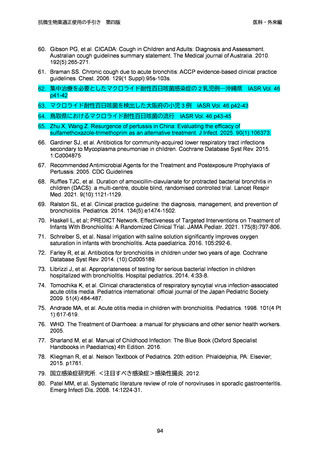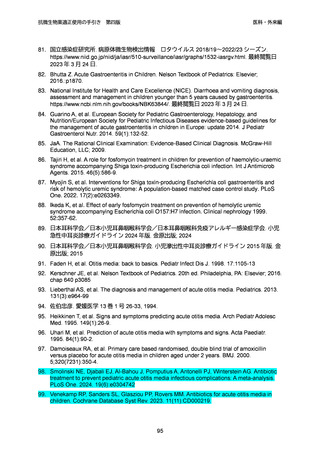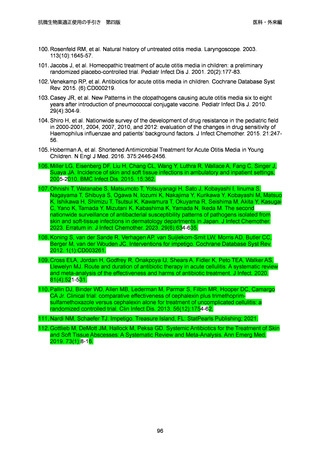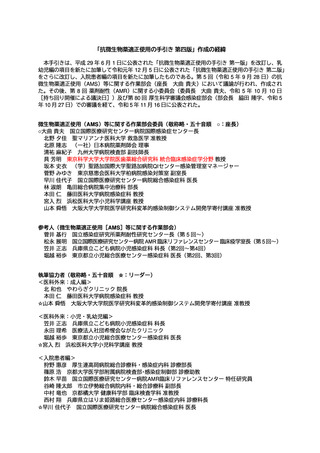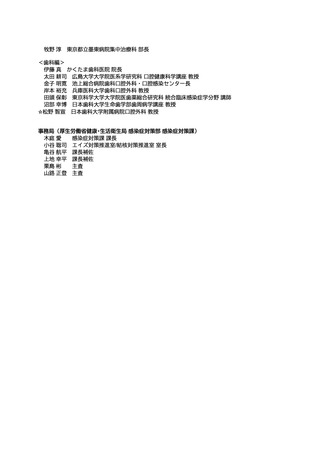よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-1】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・外来編 (79 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
抗微生物薬適正使用の手引き
第四版
激しい
嘔吐
医科・外来編
* ロタウイルスでは数日間、数回/日程度の嘔吐が続く
下痢
* ロタウイルスでは下痢は長期化(1 週間程度)
腹痛
* 細菌性は高熱で 48 時間以上発熱が続く
発熱
37.5°C
病日
1 日目
図 8.
2 日目
3 日目
急性ウイルス性下痢症の自然経過
(4) 治療方法
急 性 下 痢 症 へ の 治 療 は 、1) 脱 水 へ の 対 応 、 す な わ ち 経 口 補 水 療 法 (Oral
Rehydration Therapy:ORT)や経静脈的輸液が重要であり、2) プロバイオティクス
について検討し、3) 抗菌薬を安易に使用しないことが求められる 82,83。
小児の急性下痢症の管理において、脱水の管理は極めて重要である。身体所見から
脱水の程度を評価し、適切な補液や輸液を行う必要がある。詳細は聖書等を参照の
こと。
(5) 抗菌薬治療
ウイルス性腸炎と診断した場合、抗菌薬は無効であるばかりか、腸内細菌叢を乱
し、菌交代現象を引き起こすためとされ、有害であるため使用しない 76。
細菌性腸炎と判断した場合は、時宜を得た適正な抗菌薬療法は下痢の重症度を改
善し罹病期間を短縮することができる。一方で抗菌薬は保菌状態を長引かせ、また
下痢症に対して広範に抗菌薬を使用すると薬剤耐性を引き起こす。
細菌性腸炎による下痢症であっても、多くは自然軽快する。よって、健常児で軽
症の場合は、便培養を採取の上、まずは対症療法を行い、経過と便培養結果で抗菌
薬治療を考慮する。細菌性腸炎による症状(強い腹痛、しぶり腹、血便、高熱)が
ある場合は、便培養を採取の上、抗菌薬療法を考慮する。一方、全身状態が不良な
症例、生後 3 か月未満、免疫不全者等のハイリスク症例は原則入院で全身管理と抗
菌薬治療を行うことが実際的である。
79
第四版
激しい
嘔吐
医科・外来編
* ロタウイルスでは数日間、数回/日程度の嘔吐が続く
下痢
* ロタウイルスでは下痢は長期化(1 週間程度)
腹痛
* 細菌性は高熱で 48 時間以上発熱が続く
発熱
37.5°C
病日
1 日目
図 8.
2 日目
3 日目
急性ウイルス性下痢症の自然経過
(4) 治療方法
急 性 下 痢 症 へ の 治 療 は 、1) 脱 水 へ の 対 応 、 す な わ ち 経 口 補 水 療 法 (Oral
Rehydration Therapy:ORT)や経静脈的輸液が重要であり、2) プロバイオティクス
について検討し、3) 抗菌薬を安易に使用しないことが求められる 82,83。
小児の急性下痢症の管理において、脱水の管理は極めて重要である。身体所見から
脱水の程度を評価し、適切な補液や輸液を行う必要がある。詳細は聖書等を参照の
こと。
(5) 抗菌薬治療
ウイルス性腸炎と診断した場合、抗菌薬は無効であるばかりか、腸内細菌叢を乱
し、菌交代現象を引き起こすためとされ、有害であるため使用しない 76。
細菌性腸炎と判断した場合は、時宜を得た適正な抗菌薬療法は下痢の重症度を改
善し罹病期間を短縮することができる。一方で抗菌薬は保菌状態を長引かせ、また
下痢症に対して広範に抗菌薬を使用すると薬剤耐性を引き起こす。
細菌性腸炎による下痢症であっても、多くは自然軽快する。よって、健常児で軽
症の場合は、便培養を採取の上、まずは対症療法を行い、経過と便培養結果で抗菌
薬治療を考慮する。細菌性腸炎による症状(強い腹痛、しぶり腹、血便、高熱)が
ある場合は、便培養を採取の上、抗菌薬療法を考慮する。一方、全身状態が不良な
症例、生後 3 か月未満、免疫不全者等のハイリスク症例は原則入院で全身管理と抗
菌薬治療を行うことが実際的である。
79