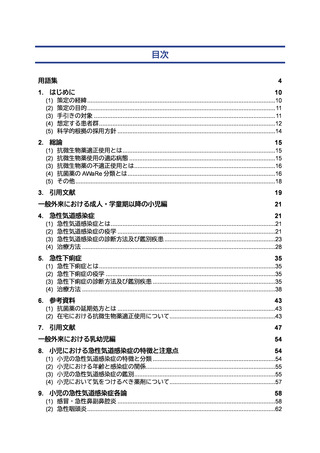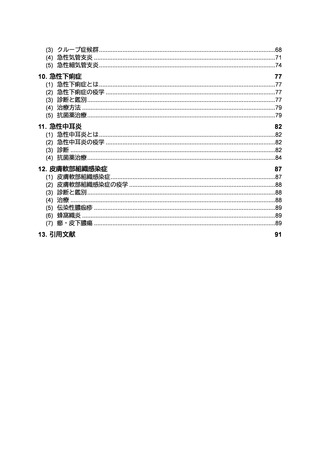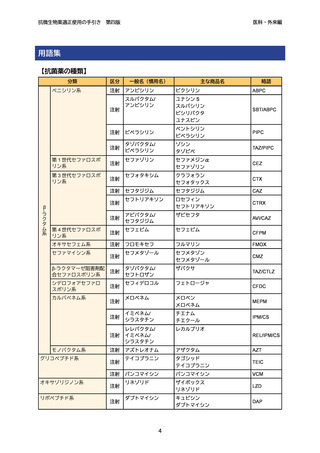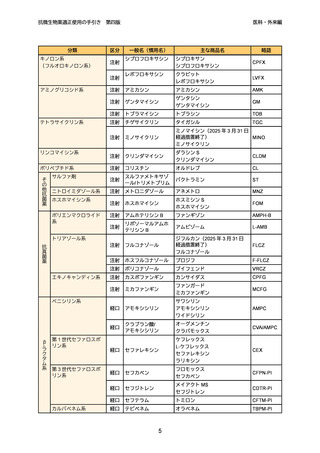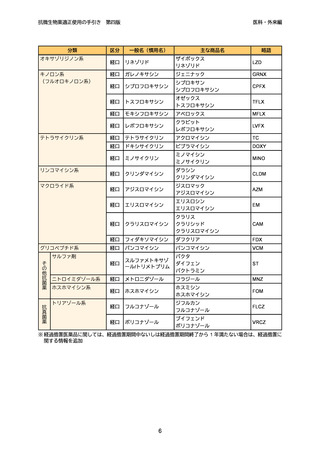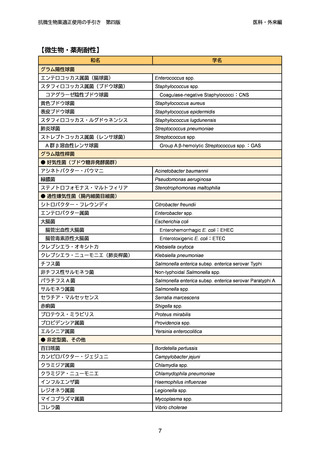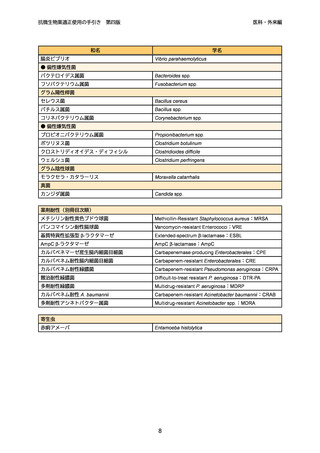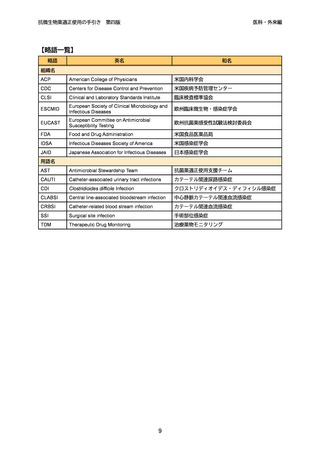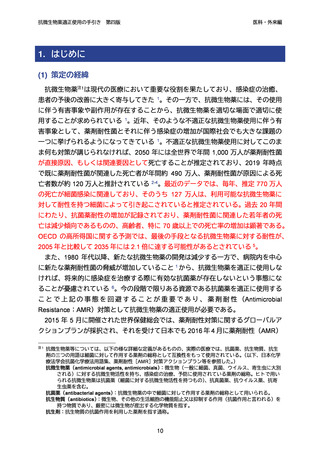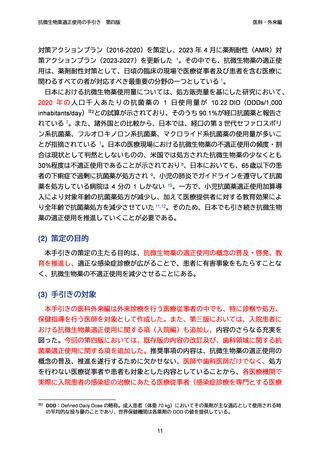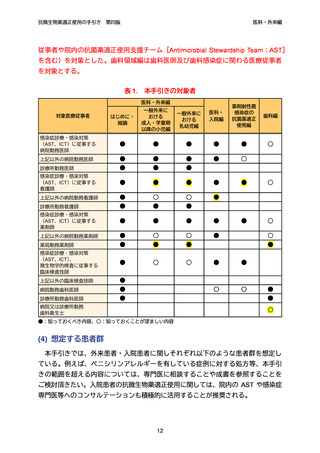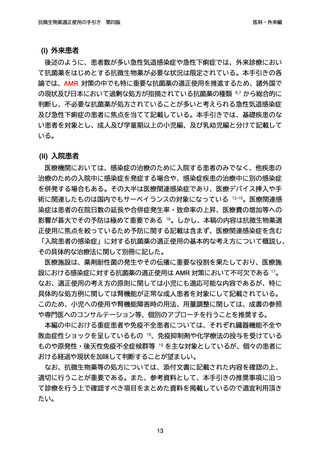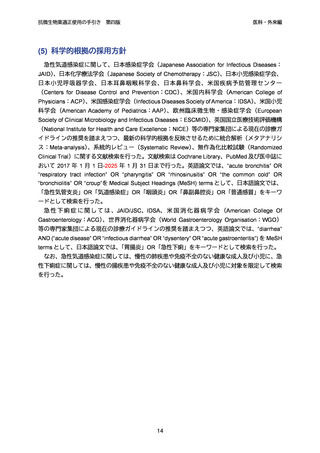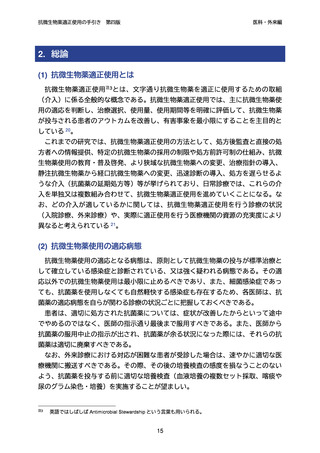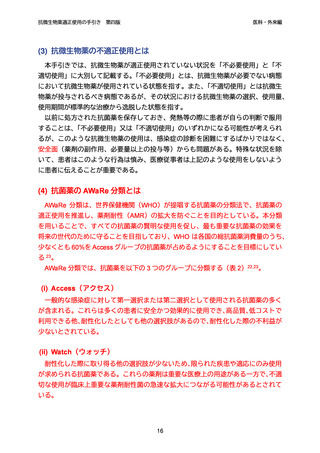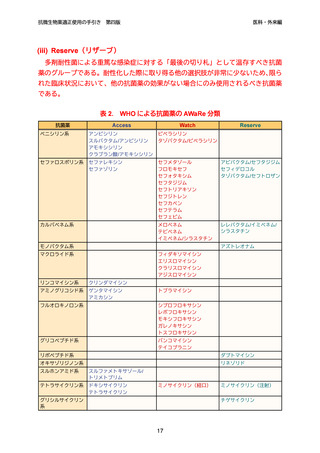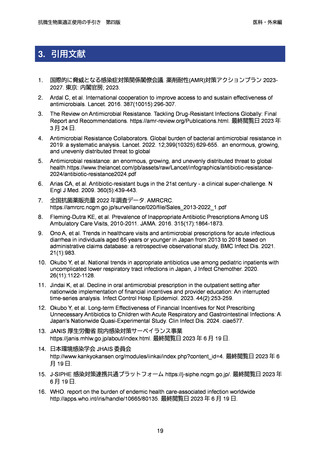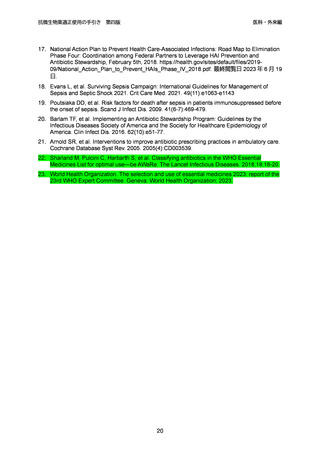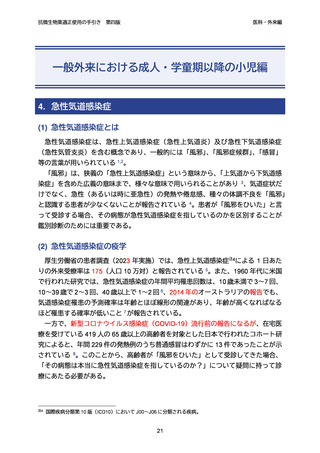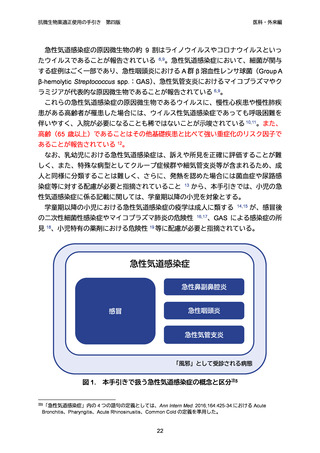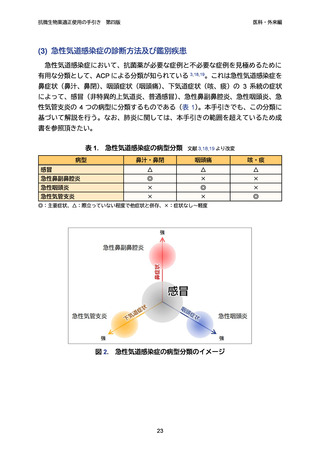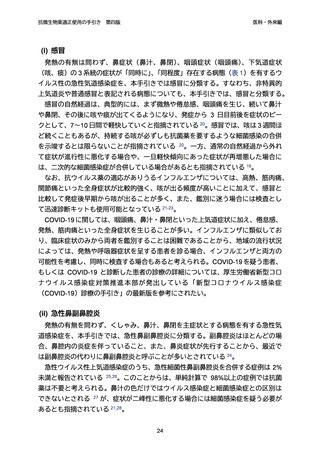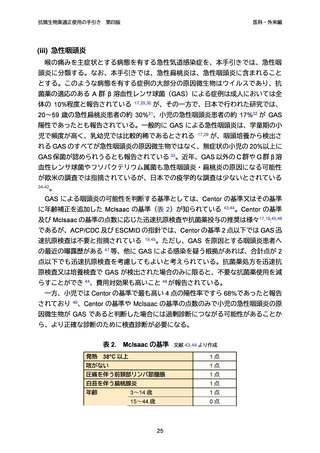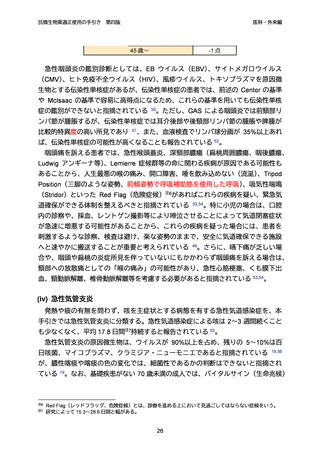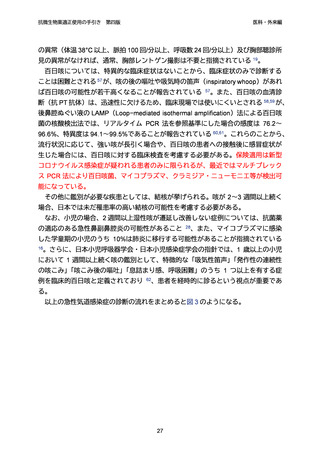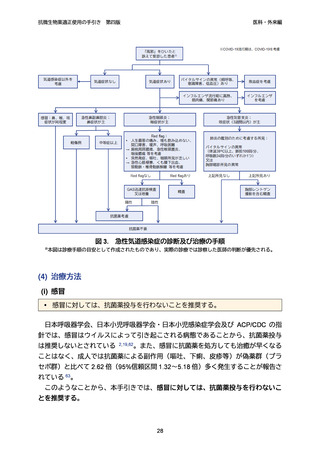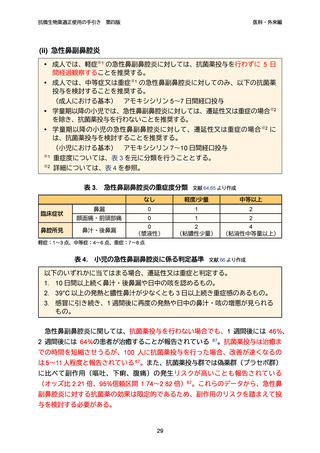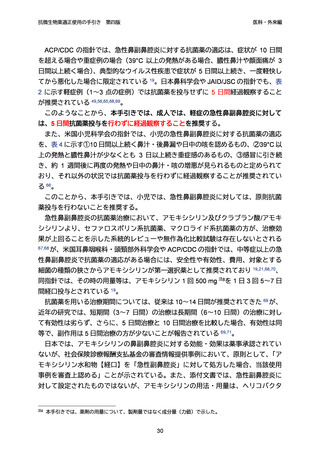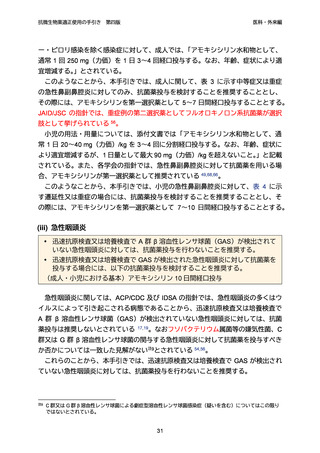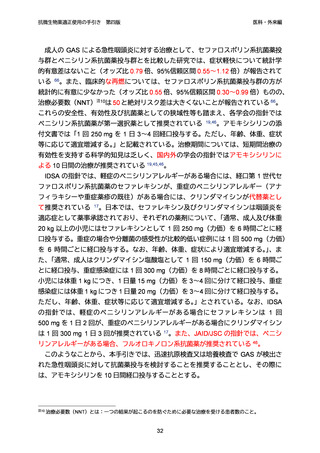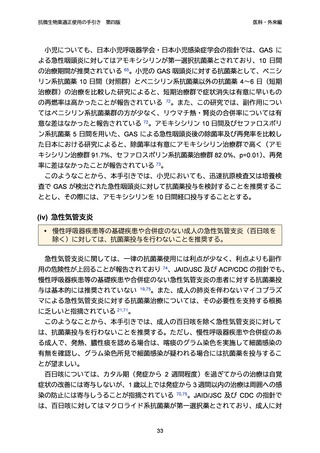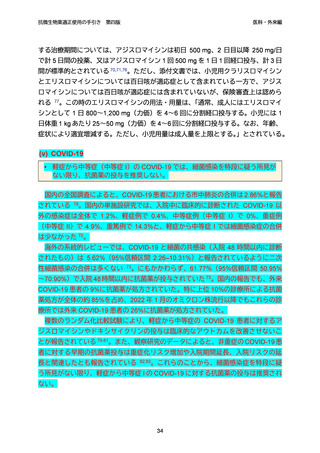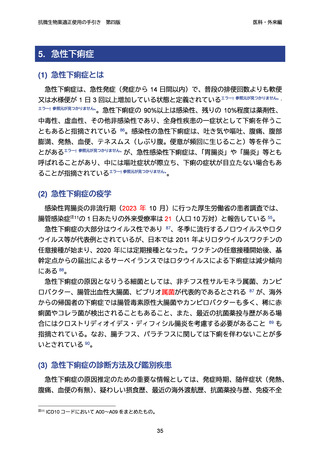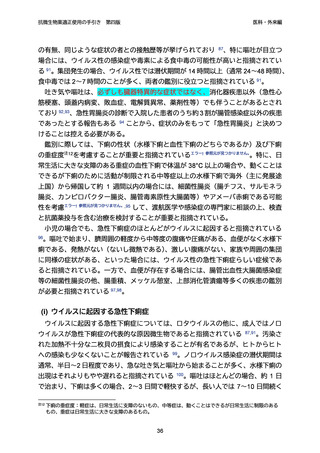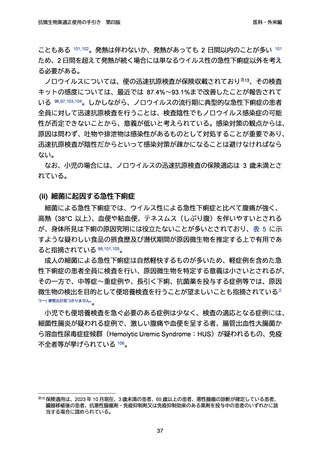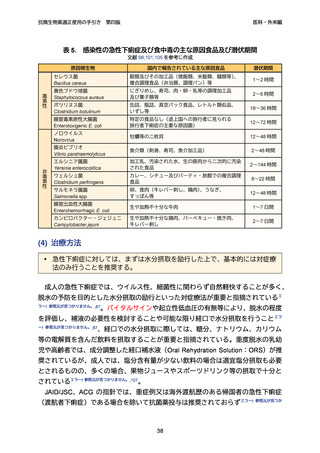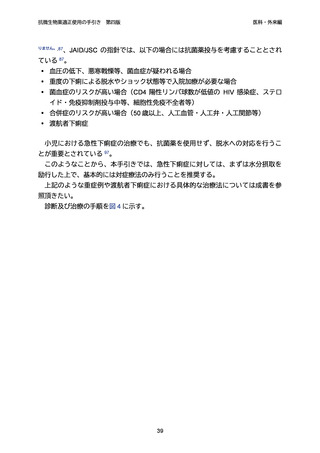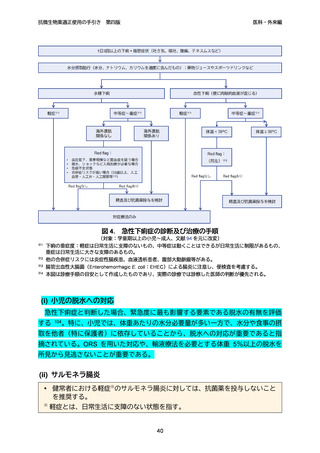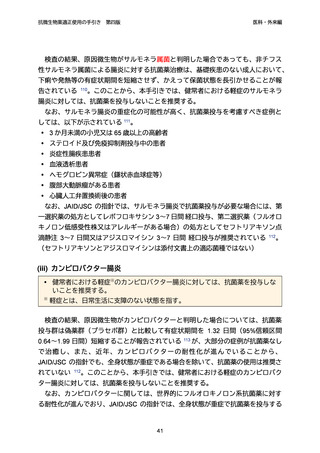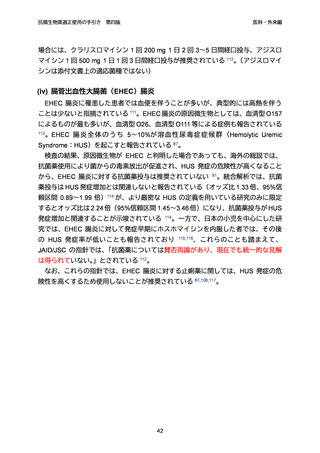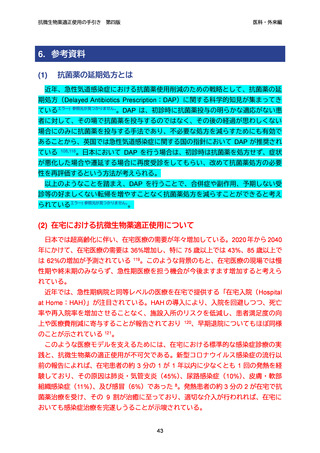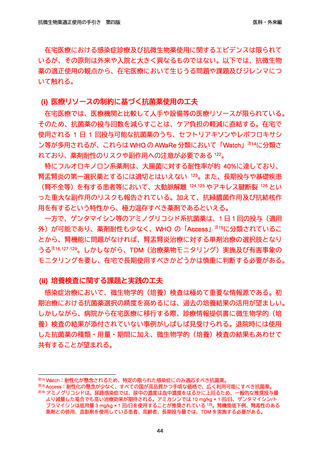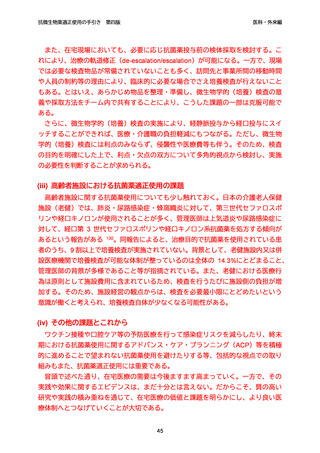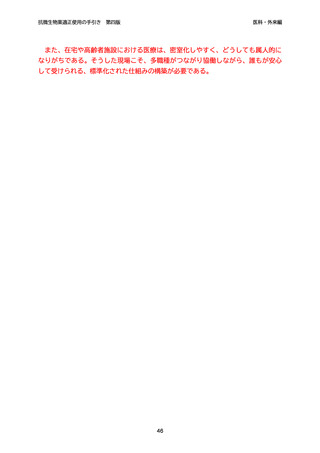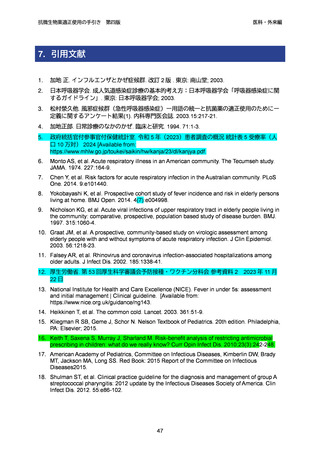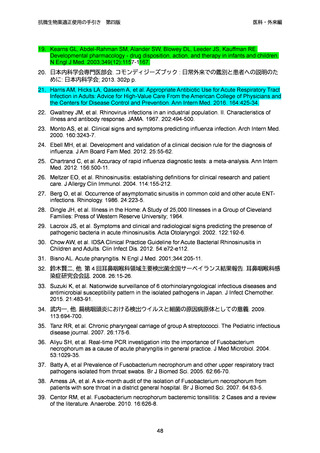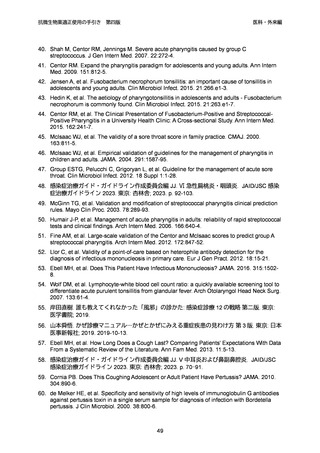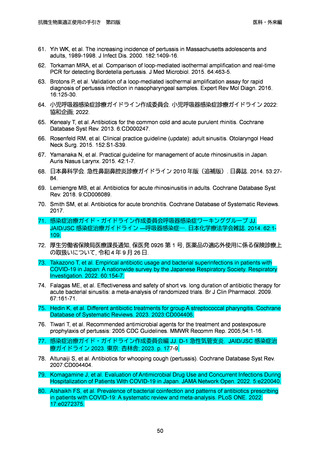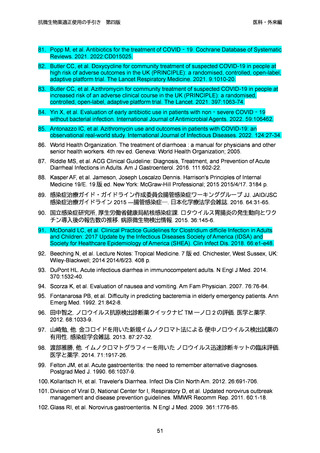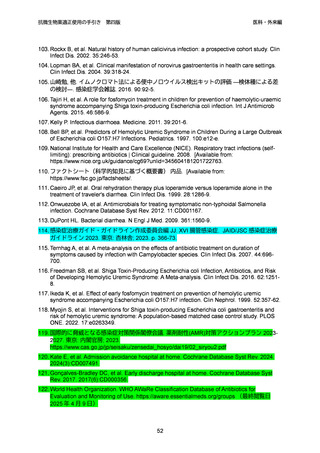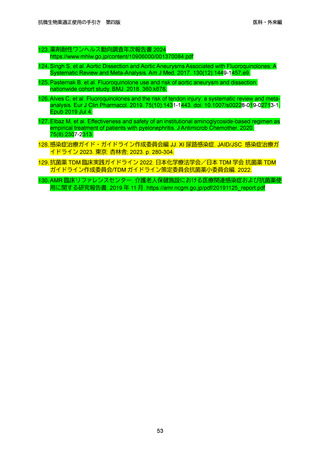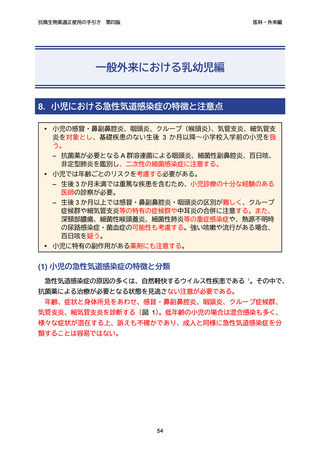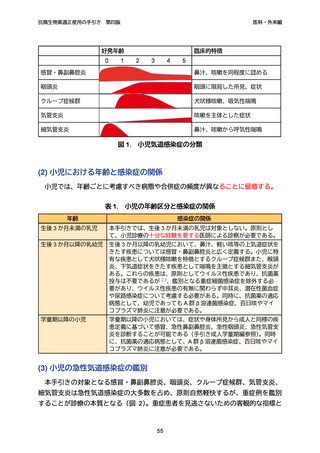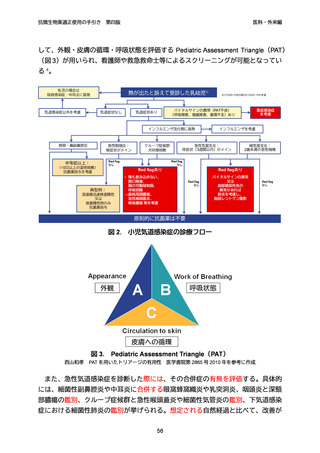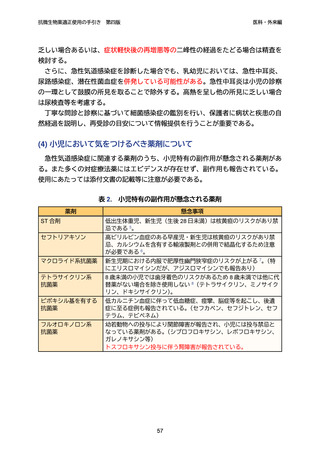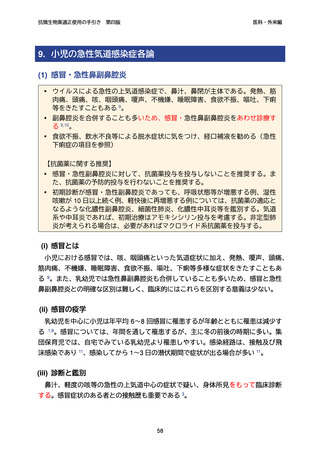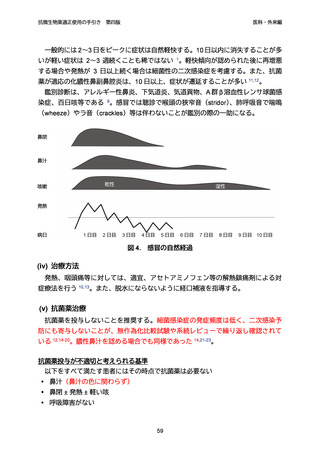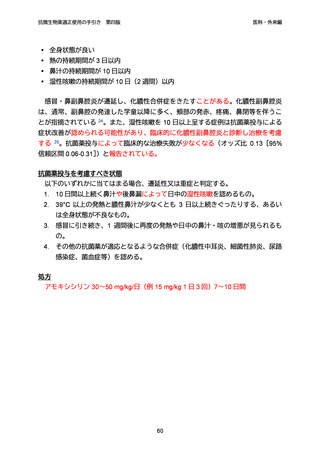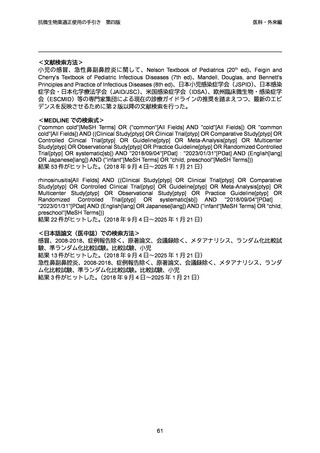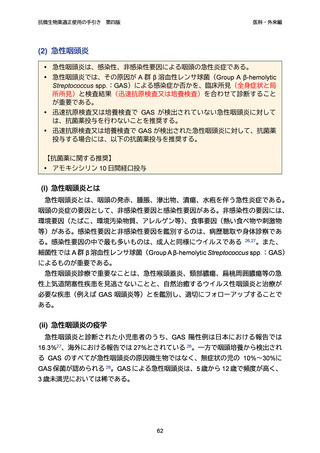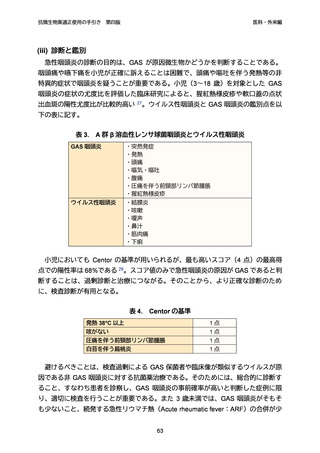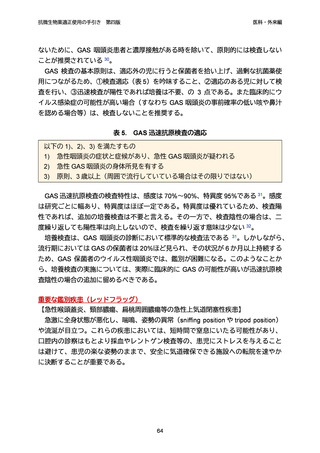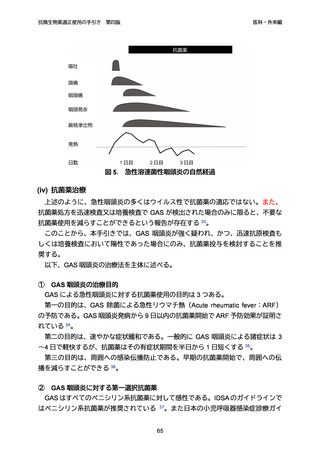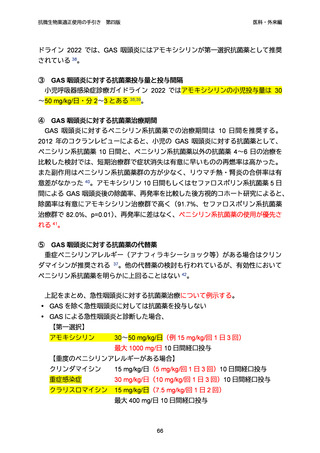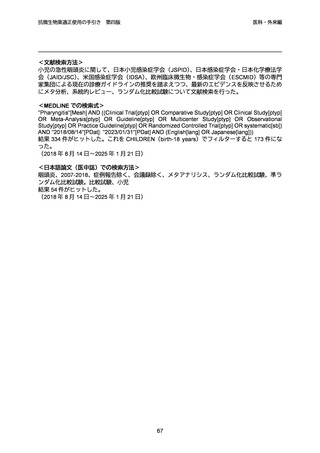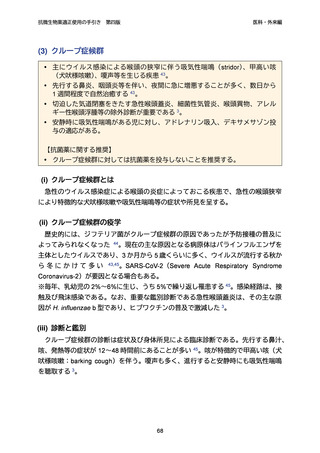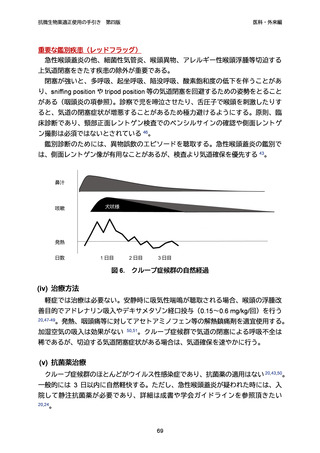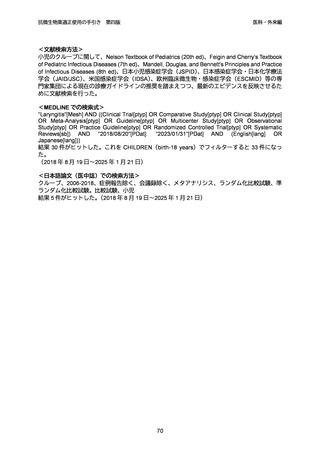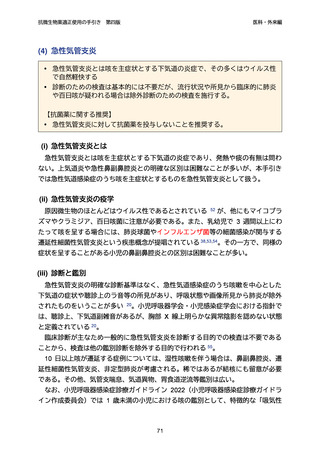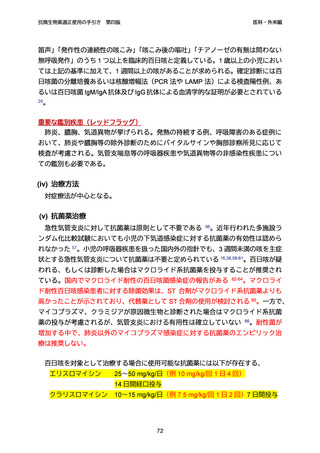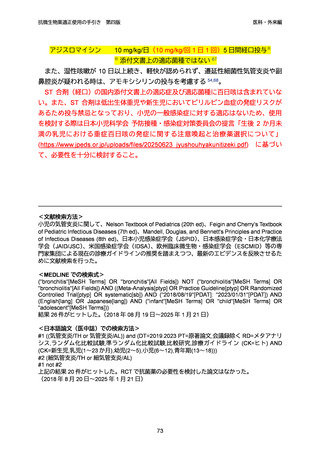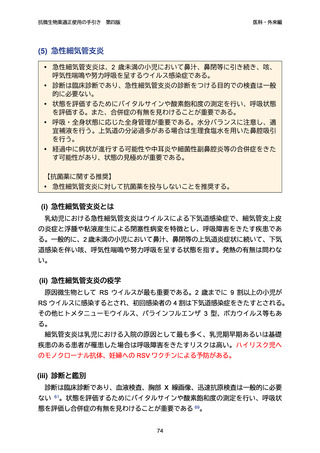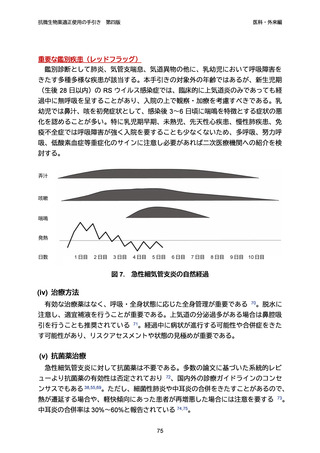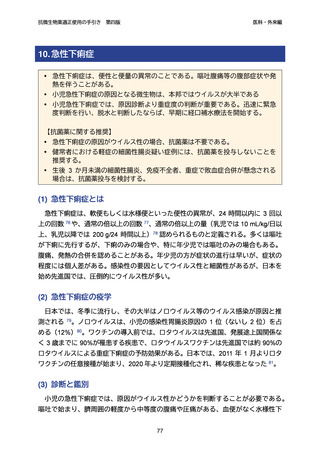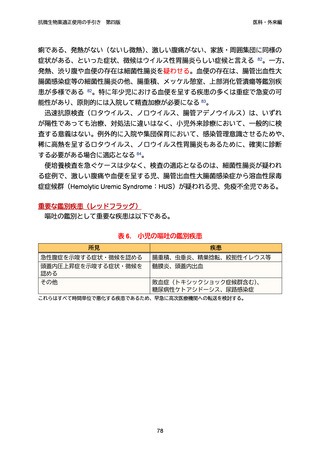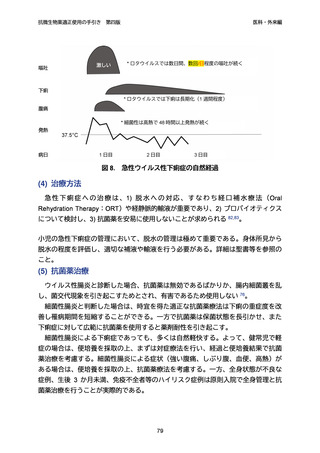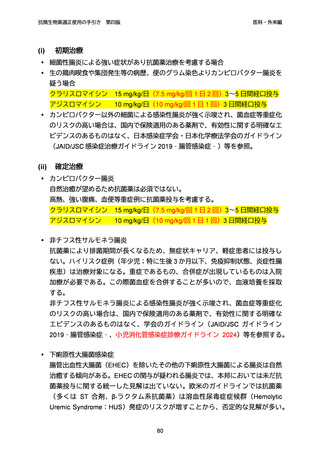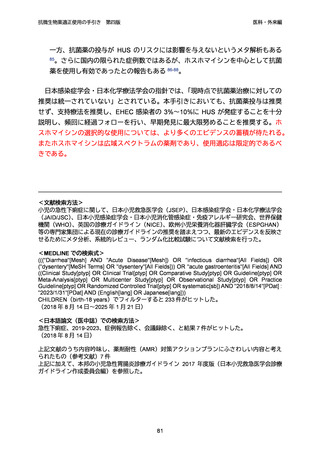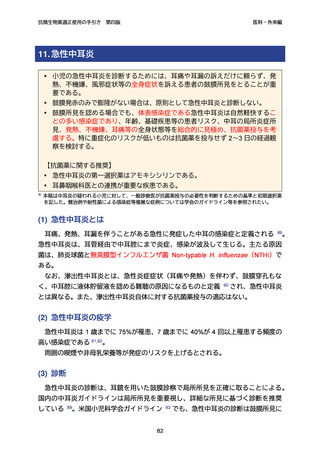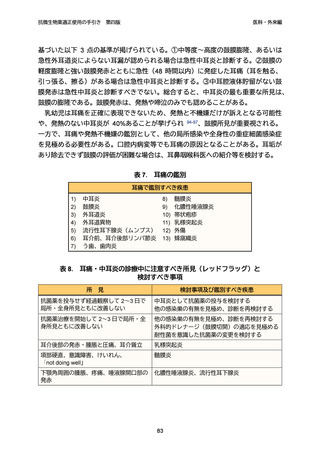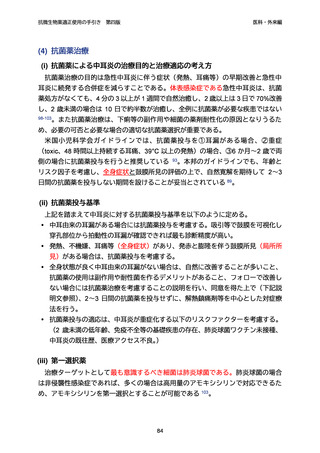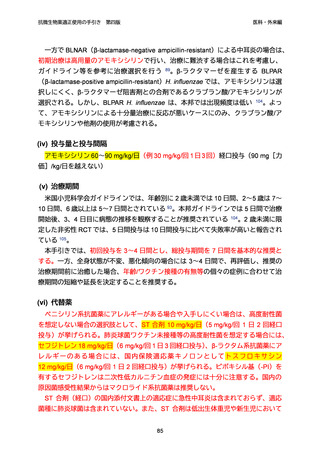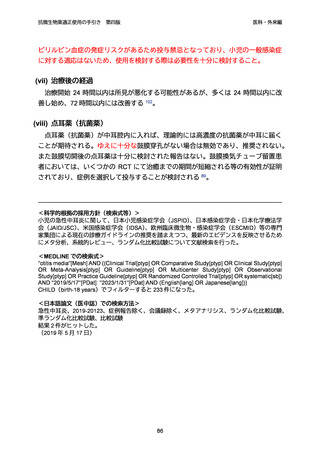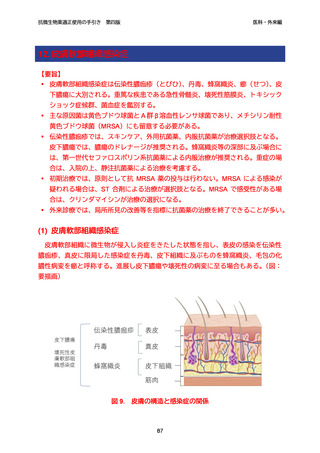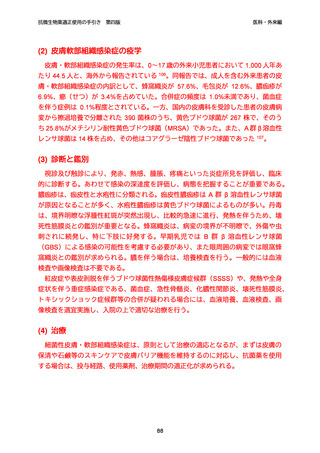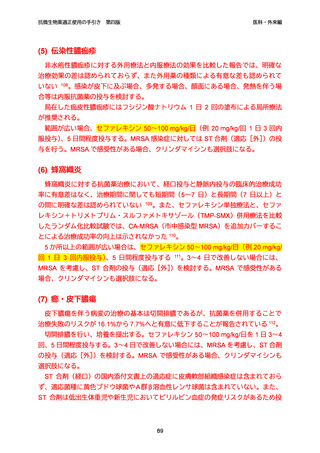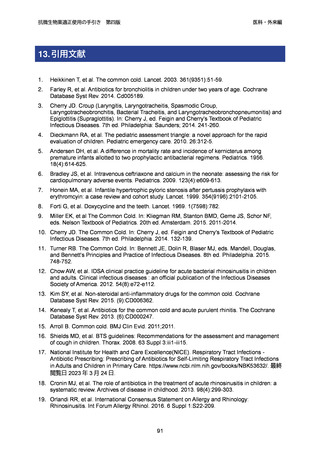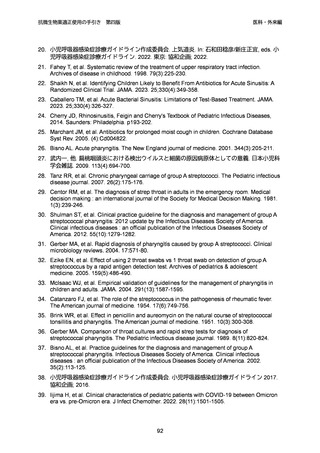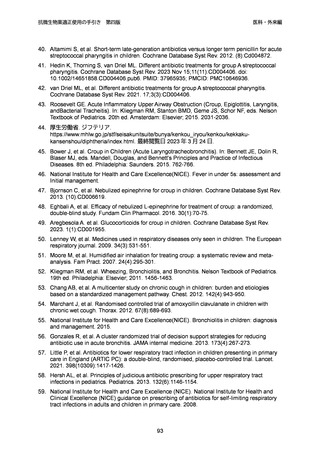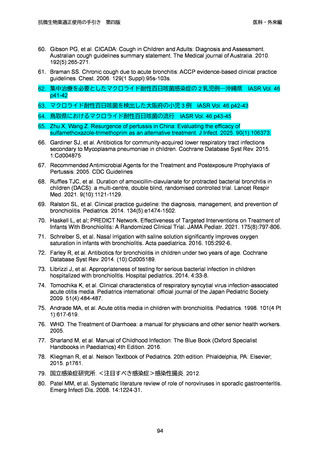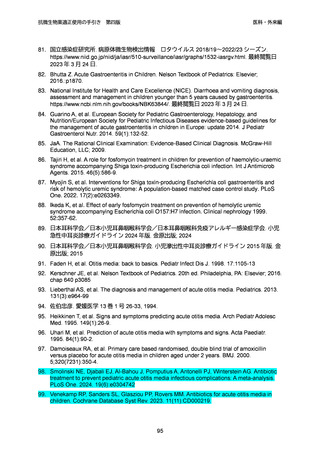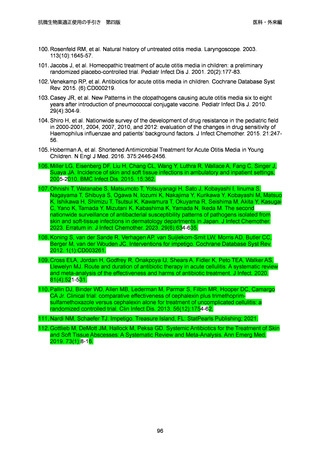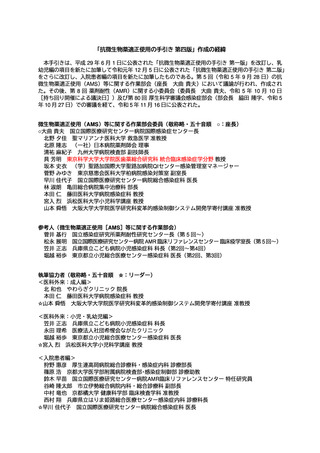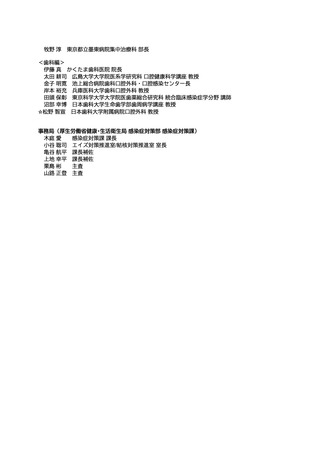よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-1】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・外来編 (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
抗微生物薬適正使用の手引き
第四版
医科・外来編
また、在宅現場においても、必要に応じ抗菌薬投与前の検体採取を検討する。こ
れにより、治療の軌道修正(de-escalation/escalation)が可能になる。一方で、現場
では必要な検査物品が常備されていないことも多く、訪問先と事業所間の移動時間
や人員の制約等の理由により、臨床的に必要な場合でさえ培養検査が行えないこと
もある。とはいえ、あらかじめ物品を整理・準備し、微生物学的(培養)検査の意
義や採取方法をチーム内で共有することにより、こうした課題の一部は克服可能で
ある。
さらに、微生物学的(培養)検査の実施により、経静脈投与から経口投与にスイ
ッチすることができれば、医療・介護職の負担軽減にもつながる。ただし、微生物
学的(培養)検査には利点のみならず、侵襲性や医療費等も伴う。そのため、検査
の目的を明確にした上で、利点・欠点の双方について多角的視点から検討し、実施
の必要性を判断することが求められる。
(iii) 高齢者施設における抗菌薬適正使用の課題
高齢者施設に関する抗菌薬使用についても少し触れておく。日本の介護老人保健
施設(老健)では、肺炎・尿路感染症・蜂窩織炎に対して、第三世代セファロスポ
リンや経口キノロンが使用されることが多く、管理医師は上気道炎や尿路感染症に
対して、経口第 3 世代セファロスポリンや経口キノロン系抗菌薬を処方する傾向が
あるという報告がある 130。同報告によると、治療目的で抗菌薬を使用されている患
者のうち、9 割以上で培養検査が実施されていない。背景として、老健施設内又は併
設医療機関で培養検査が可能な体制が整っているのは全体の 14.3%にとどまること、
管理医師の背景が多様であること等が指摘されている。また、老健における医療行
為は原則として施設費用に含まれているため、検査を行うたびに施設側の負担が増
加する。そのため、施設経営の観点からは、検査を必要最小限にとどめたいという
意識が働くと考えられ、培養検査自体が少なくなる可能性がある。
(iv) その他の課題とこれから
ワクチン接種や口腔ケア等の予防医療を行って感染症リスクを減らしたり、終末
期における抗菌薬使用に関するアドバンス・ケア・プランニング(ACP)等を積極
的に進めることで望まれない抗菌薬使用を避けたりする等、包括的な視点での取り
組みもまた、抗菌薬適正使用には重要である。
冒頭で述べた通り、在宅医療の需要は今後ますます高まっていく。一方で、その
実践や効果に関するエビデンスは、まだ十分とは言えない。だからこそ、質の高い
研究や実践の積み重ねを通じて、在宅医療の価値と課題を明らかにし、より良い医
療体制へとつなげていくことが大切である。
45
第四版
医科・外来編
また、在宅現場においても、必要に応じ抗菌薬投与前の検体採取を検討する。こ
れにより、治療の軌道修正(de-escalation/escalation)が可能になる。一方で、現場
では必要な検査物品が常備されていないことも多く、訪問先と事業所間の移動時間
や人員の制約等の理由により、臨床的に必要な場合でさえ培養検査が行えないこと
もある。とはいえ、あらかじめ物品を整理・準備し、微生物学的(培養)検査の意
義や採取方法をチーム内で共有することにより、こうした課題の一部は克服可能で
ある。
さらに、微生物学的(培養)検査の実施により、経静脈投与から経口投与にスイ
ッチすることができれば、医療・介護職の負担軽減にもつながる。ただし、微生物
学的(培養)検査には利点のみならず、侵襲性や医療費等も伴う。そのため、検査
の目的を明確にした上で、利点・欠点の双方について多角的視点から検討し、実施
の必要性を判断することが求められる。
(iii) 高齢者施設における抗菌薬適正使用の課題
高齢者施設に関する抗菌薬使用についても少し触れておく。日本の介護老人保健
施設(老健)では、肺炎・尿路感染症・蜂窩織炎に対して、第三世代セファロスポ
リンや経口キノロンが使用されることが多く、管理医師は上気道炎や尿路感染症に
対して、経口第 3 世代セファロスポリンや経口キノロン系抗菌薬を処方する傾向が
あるという報告がある 130。同報告によると、治療目的で抗菌薬を使用されている患
者のうち、9 割以上で培養検査が実施されていない。背景として、老健施設内又は併
設医療機関で培養検査が可能な体制が整っているのは全体の 14.3%にとどまること、
管理医師の背景が多様であること等が指摘されている。また、老健における医療行
為は原則として施設費用に含まれているため、検査を行うたびに施設側の負担が増
加する。そのため、施設経営の観点からは、検査を必要最小限にとどめたいという
意識が働くと考えられ、培養検査自体が少なくなる可能性がある。
(iv) その他の課題とこれから
ワクチン接種や口腔ケア等の予防医療を行って感染症リスクを減らしたり、終末
期における抗菌薬使用に関するアドバンス・ケア・プランニング(ACP)等を積極
的に進めることで望まれない抗菌薬使用を避けたりする等、包括的な視点での取り
組みもまた、抗菌薬適正使用には重要である。
冒頭で述べた通り、在宅医療の需要は今後ますます高まっていく。一方で、その
実践や効果に関するエビデンスは、まだ十分とは言えない。だからこそ、質の高い
研究や実践の積み重ねを通じて、在宅医療の価値と課題を明らかにし、より良い医
療体制へとつなげていくことが大切である。
45