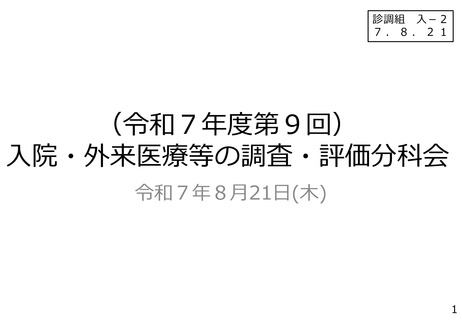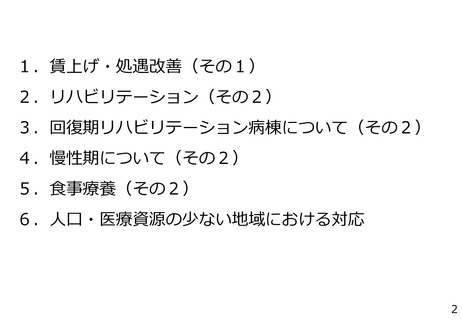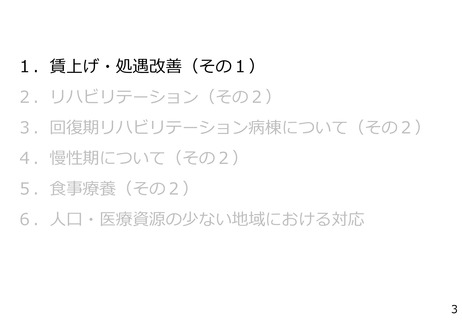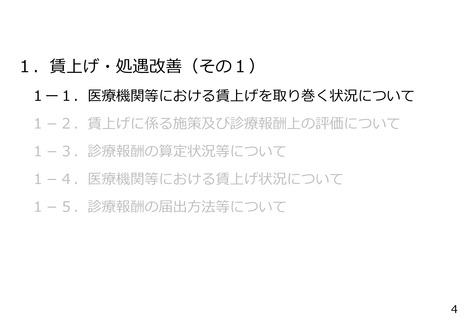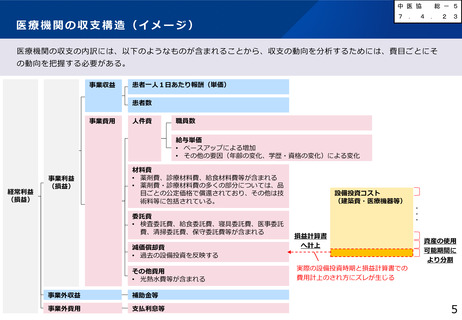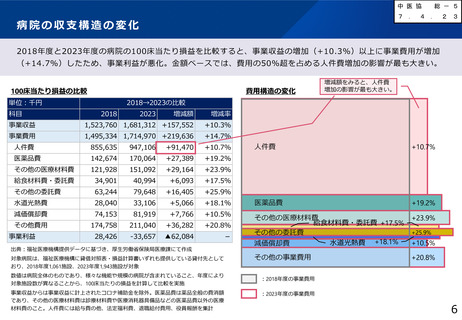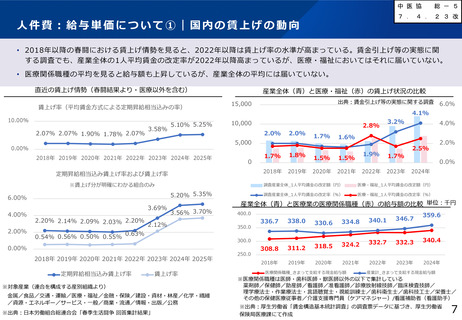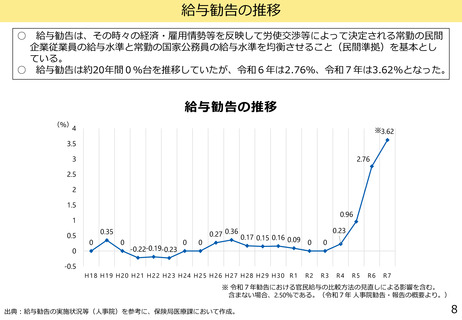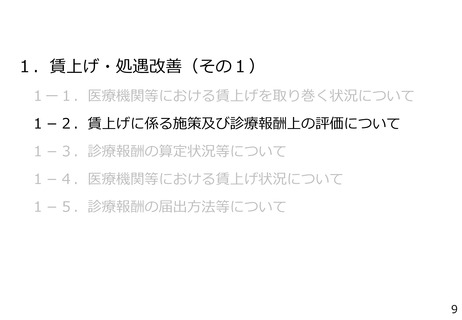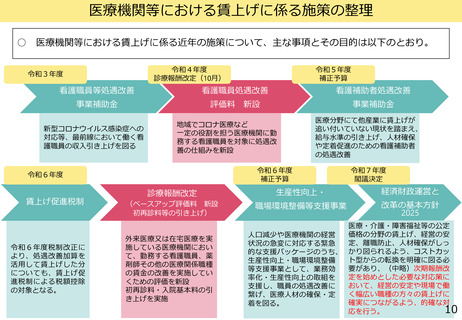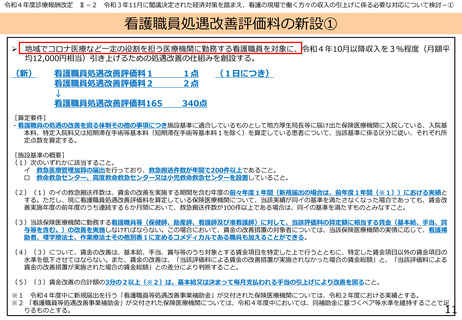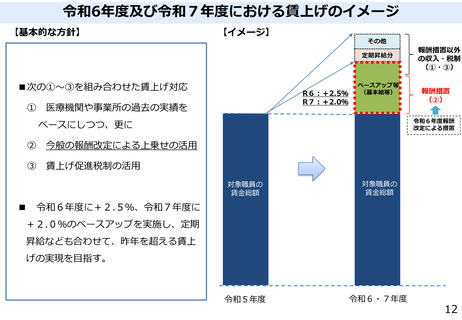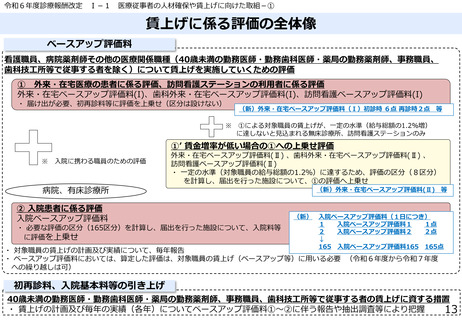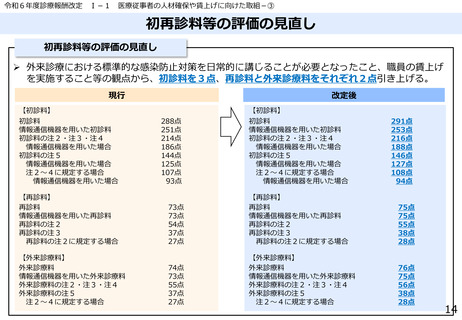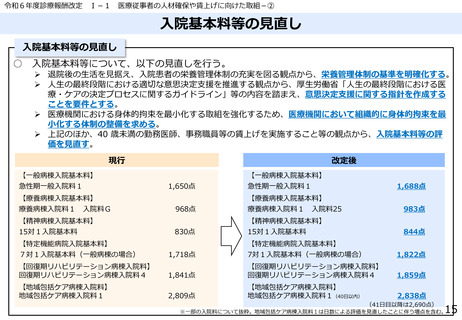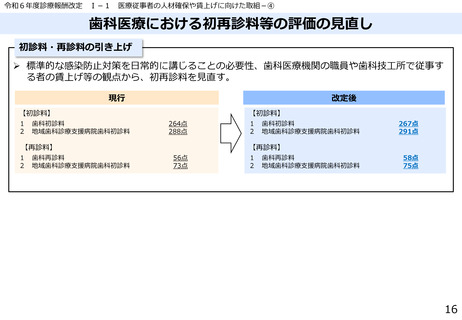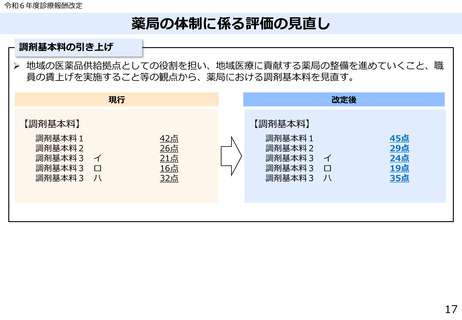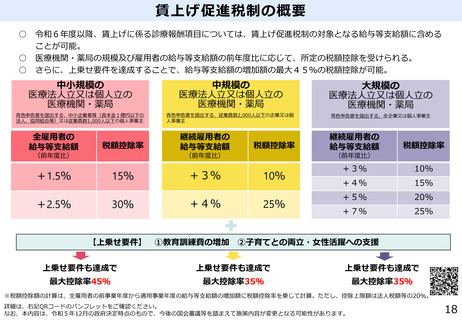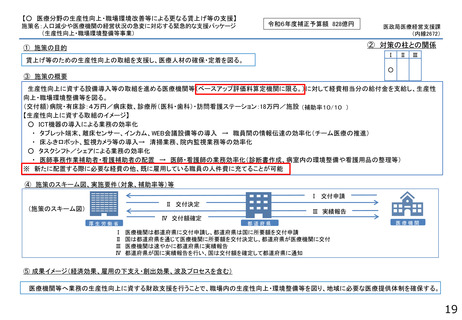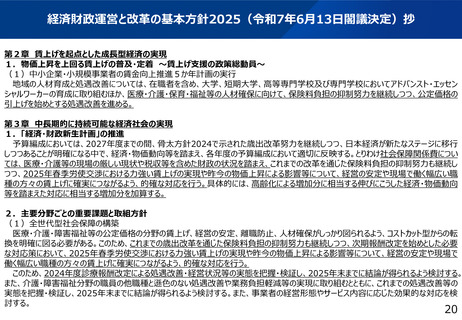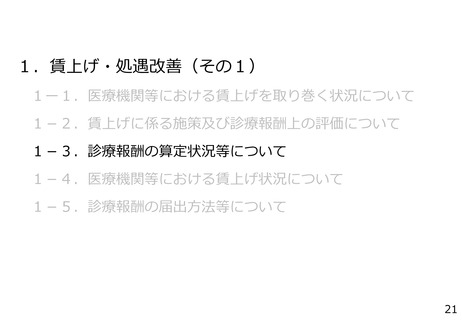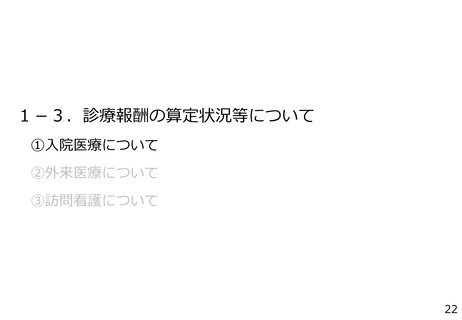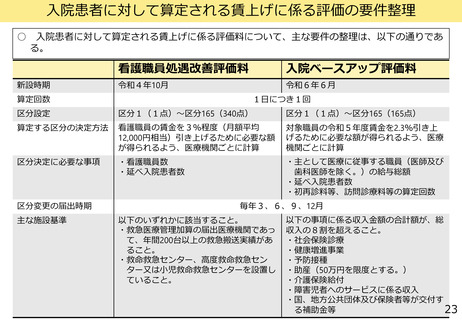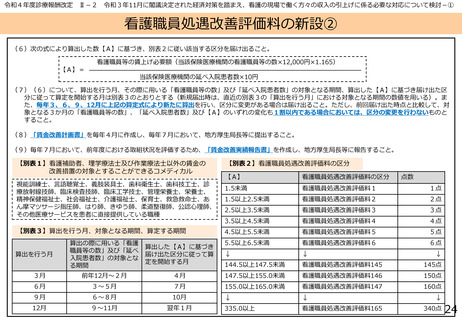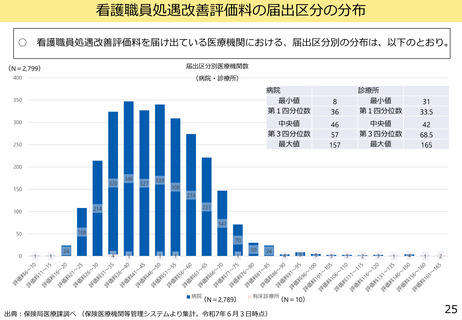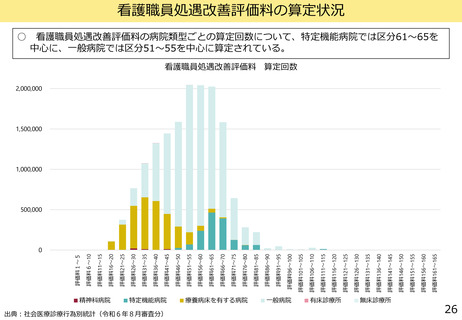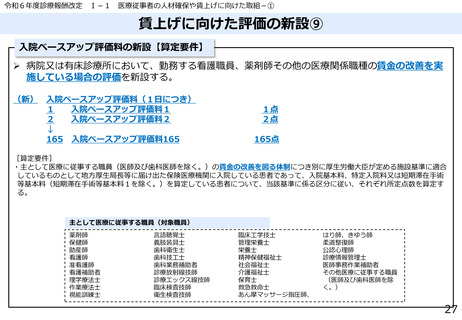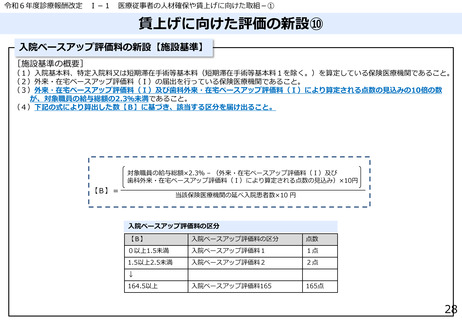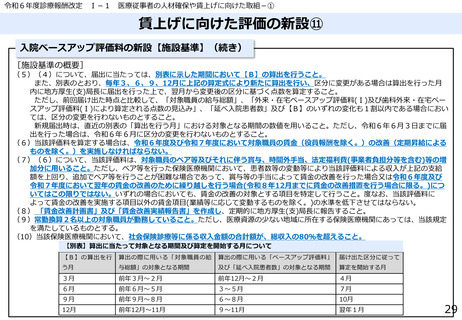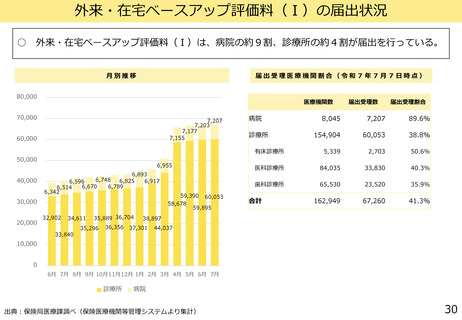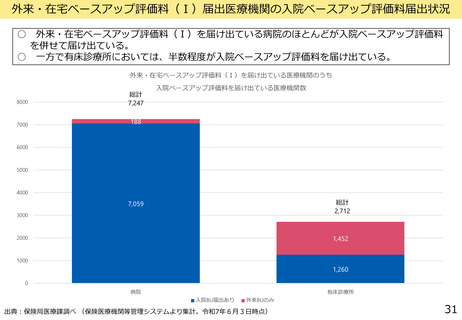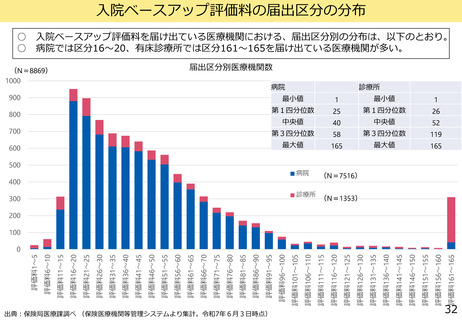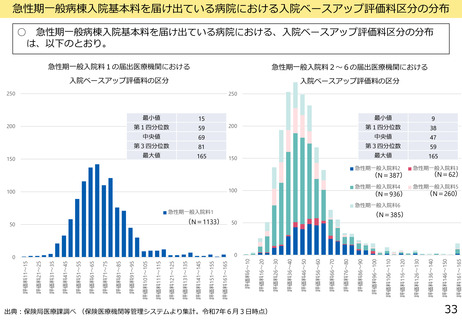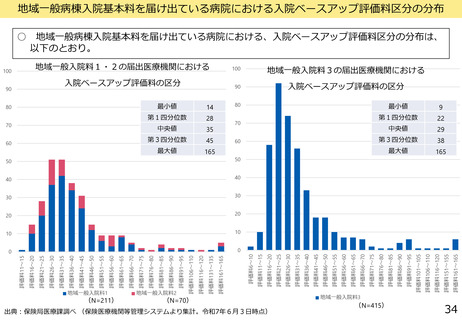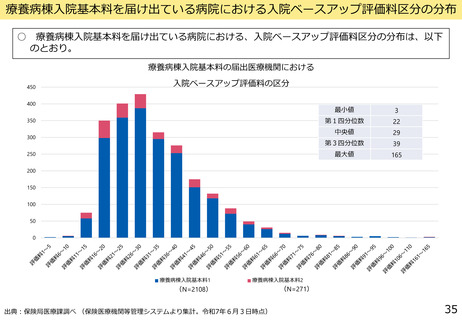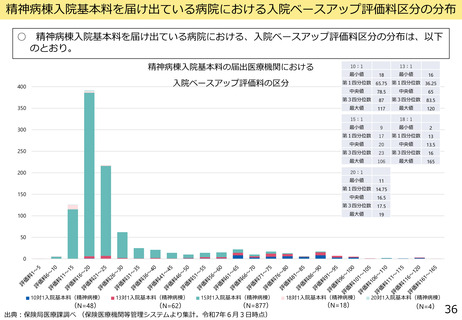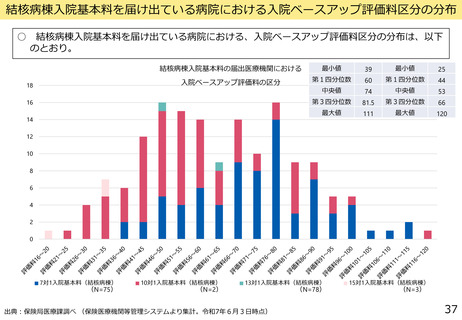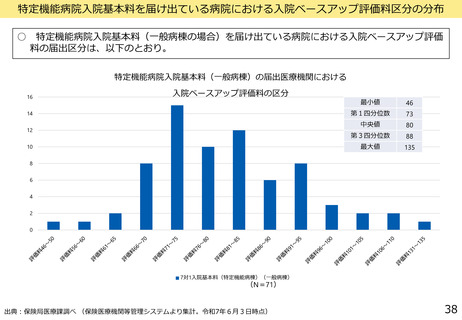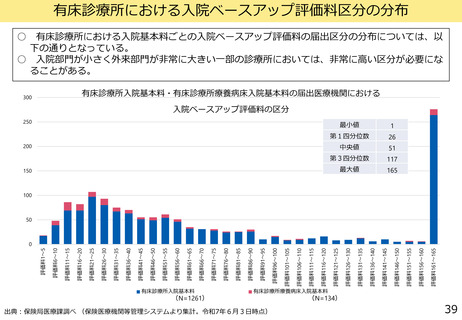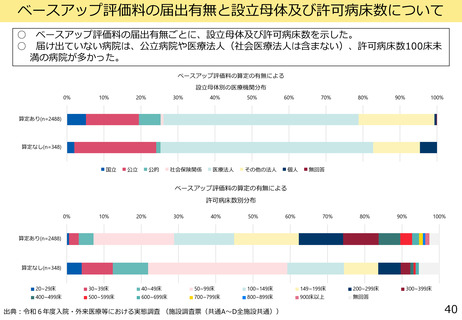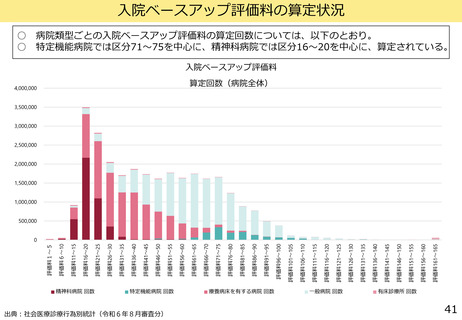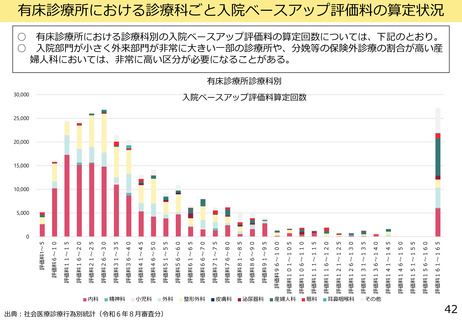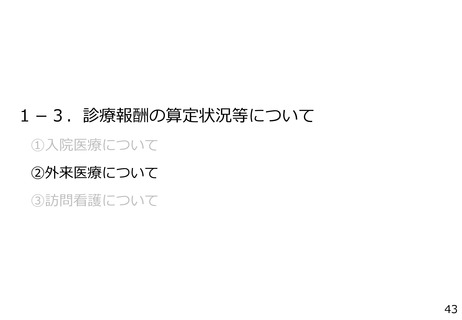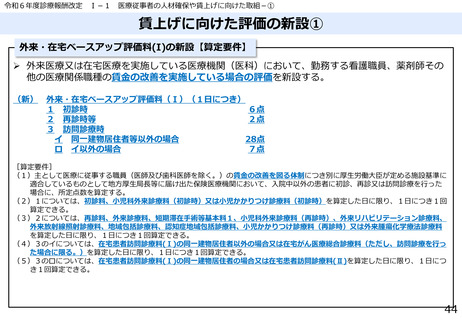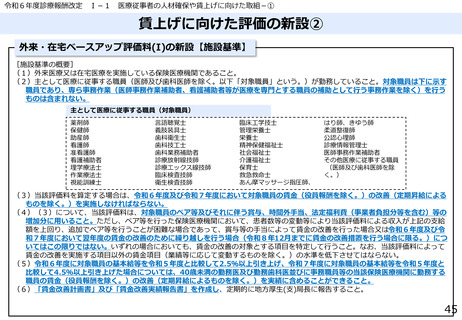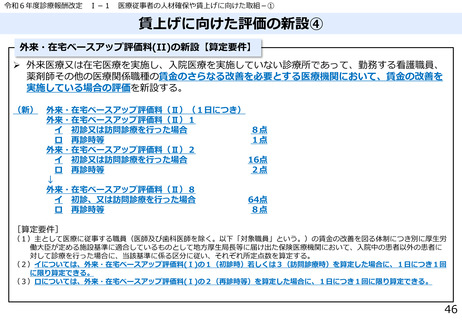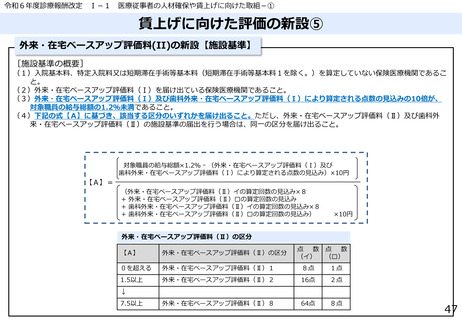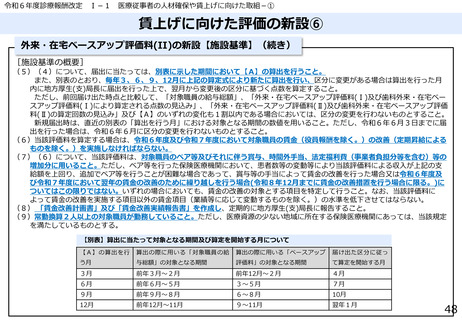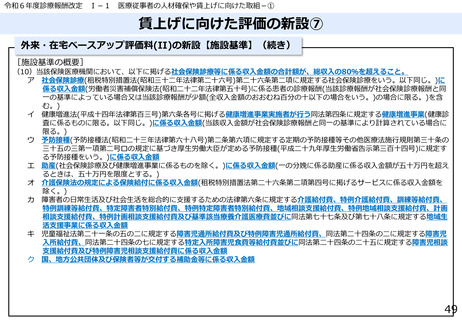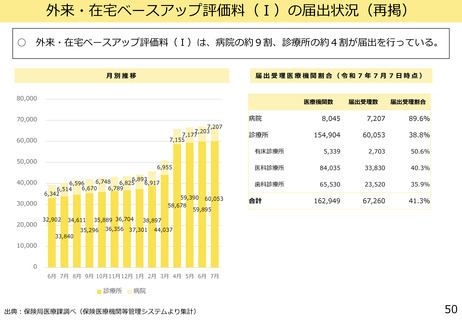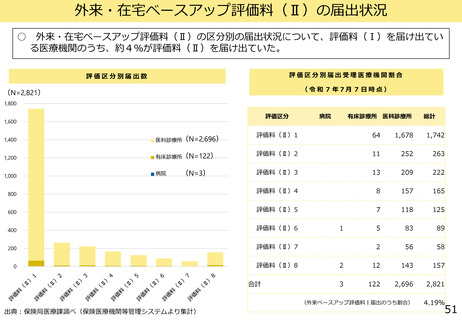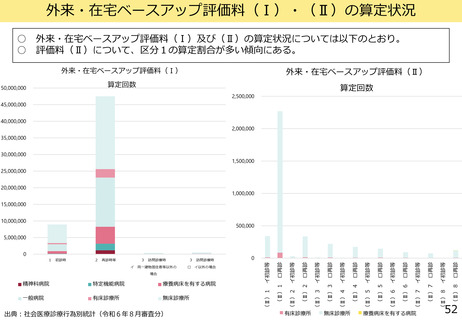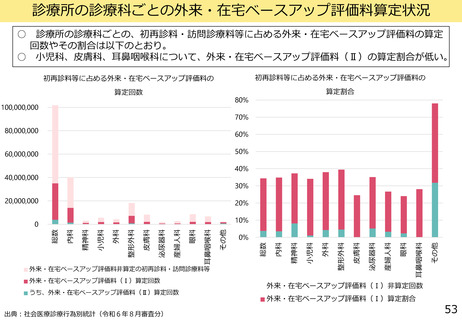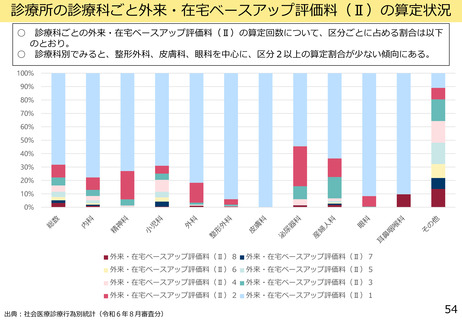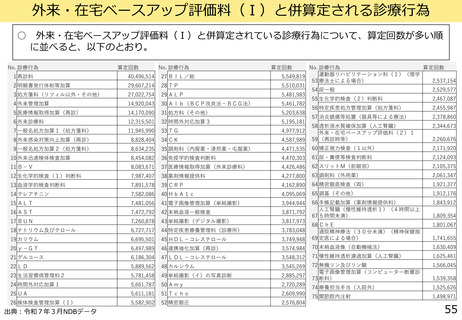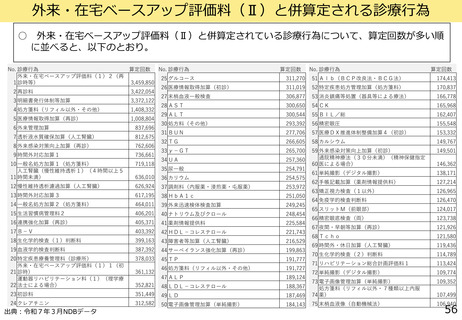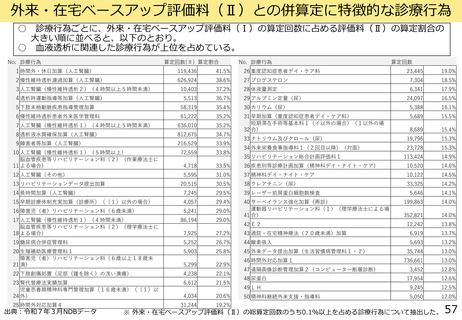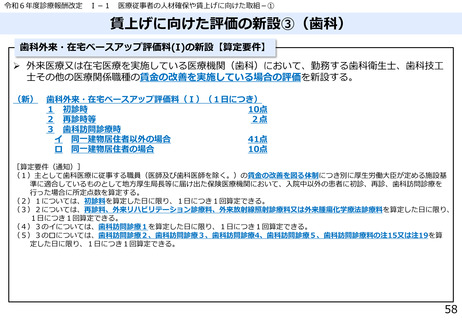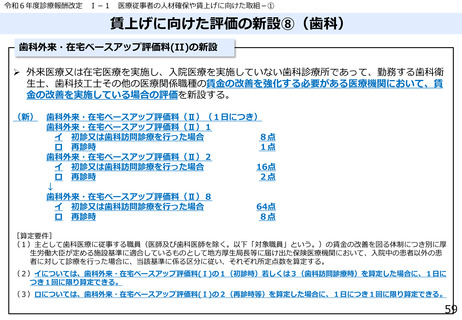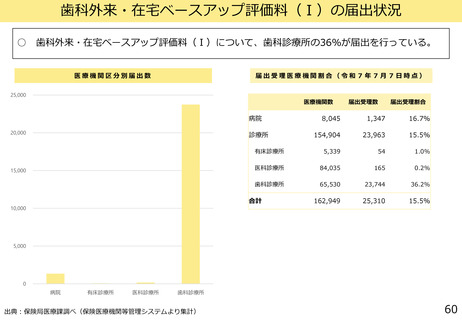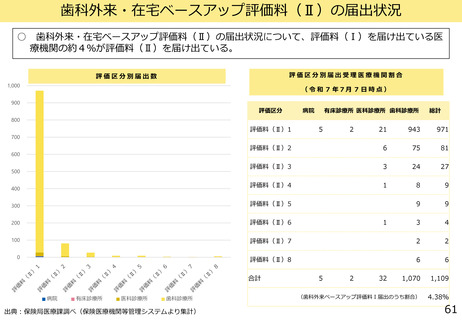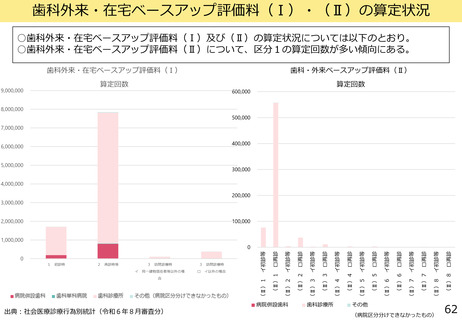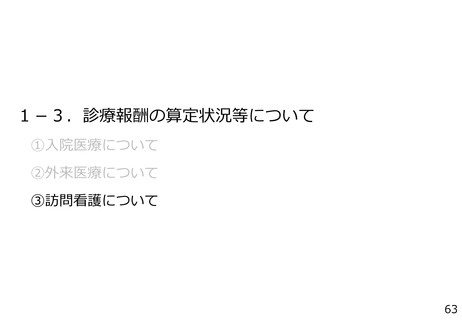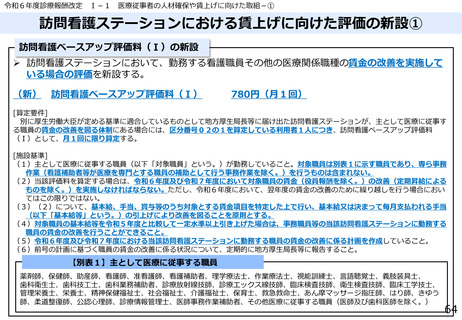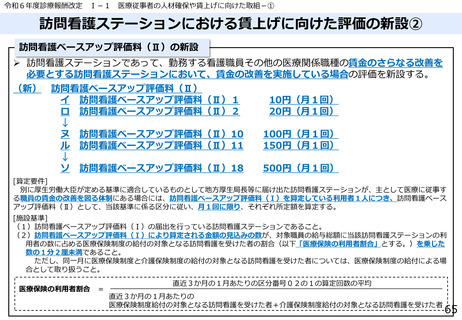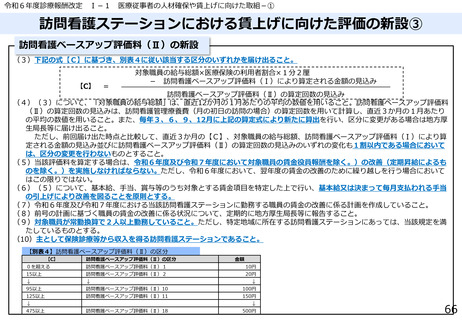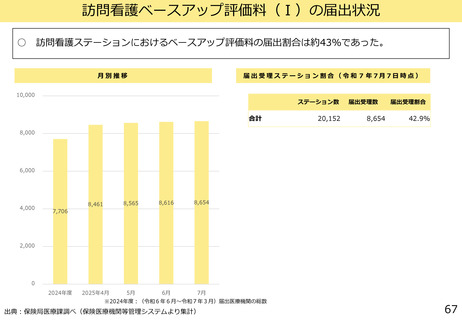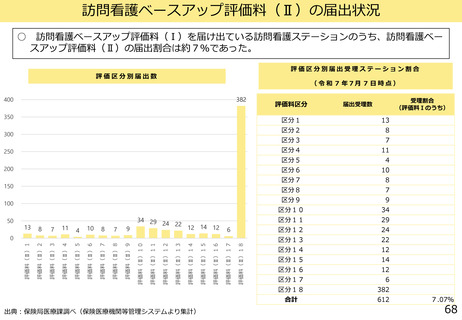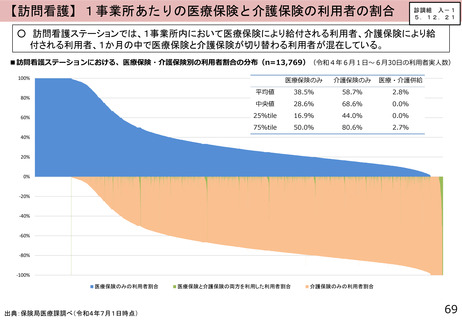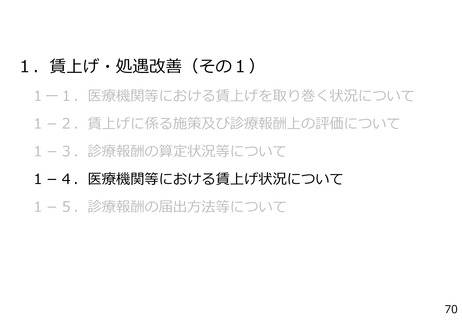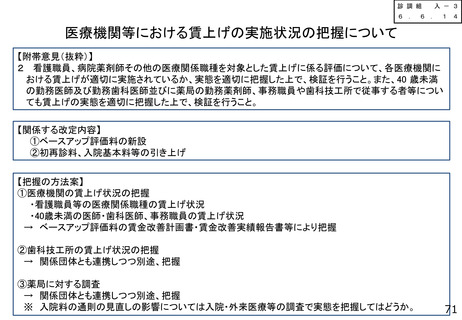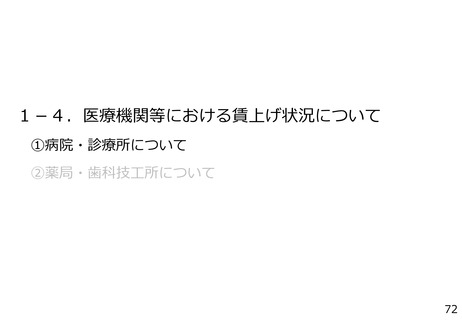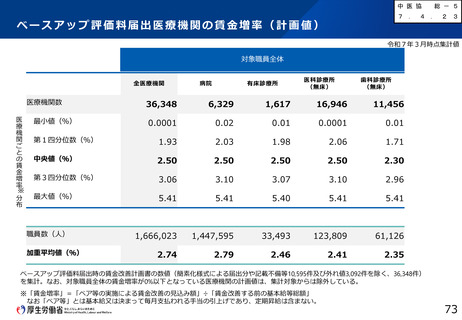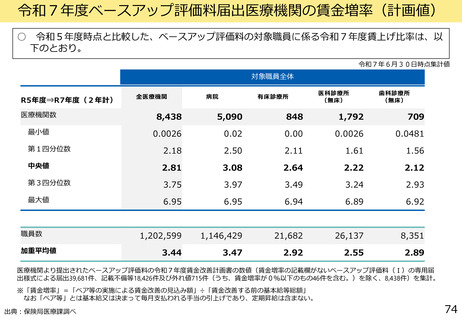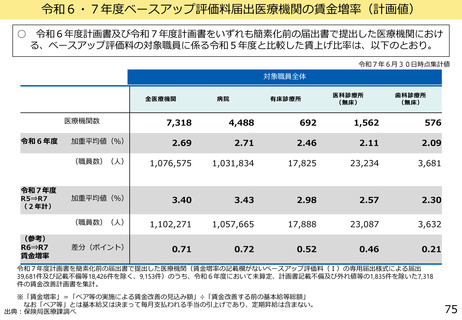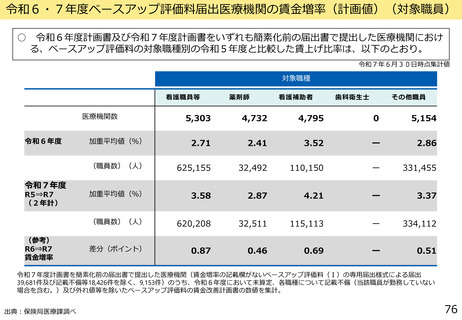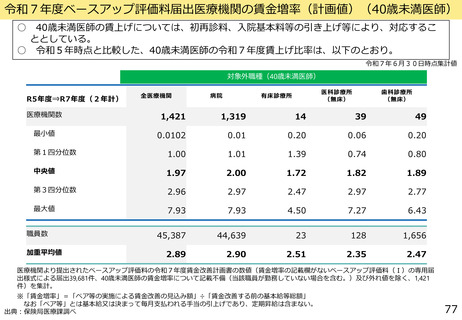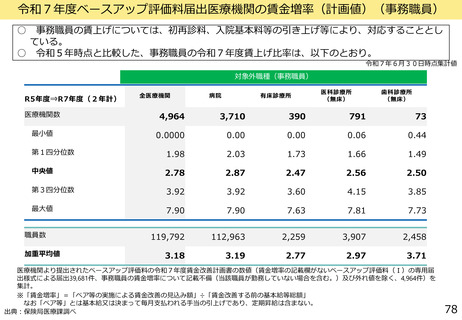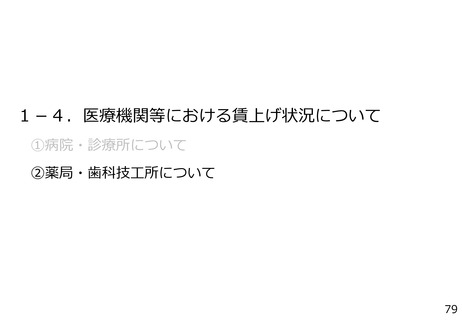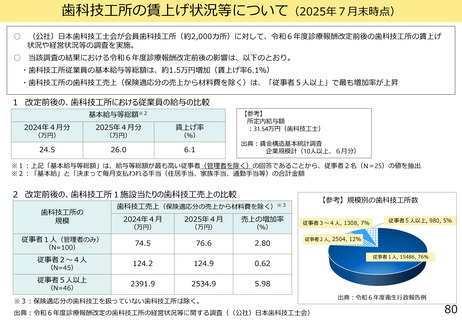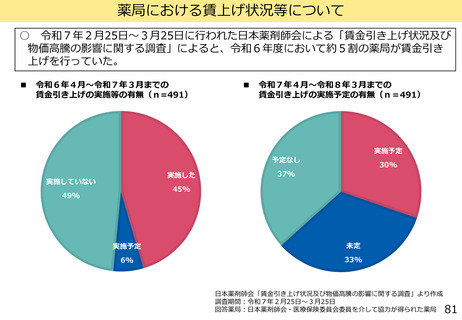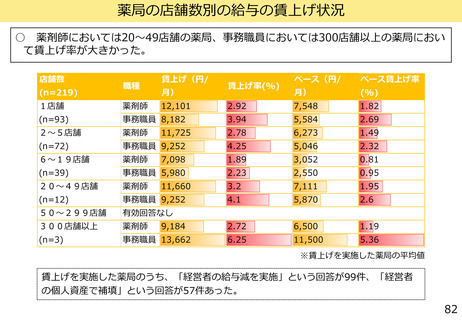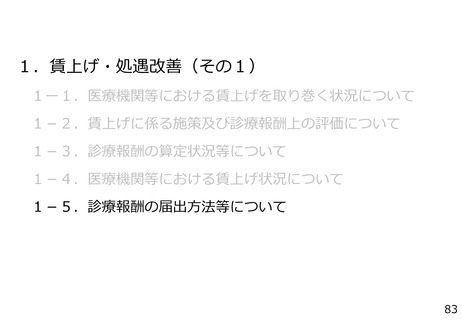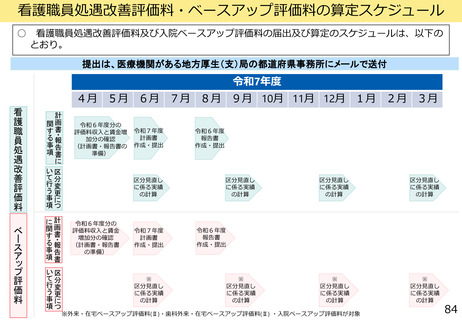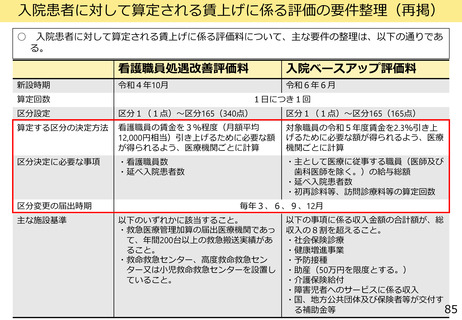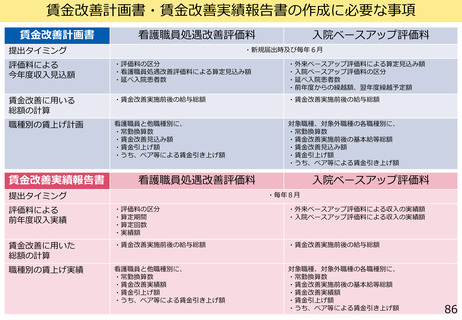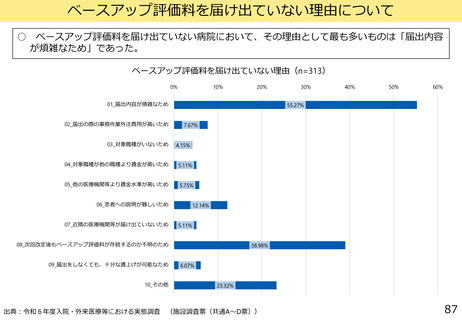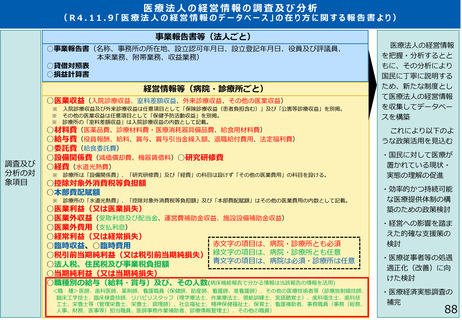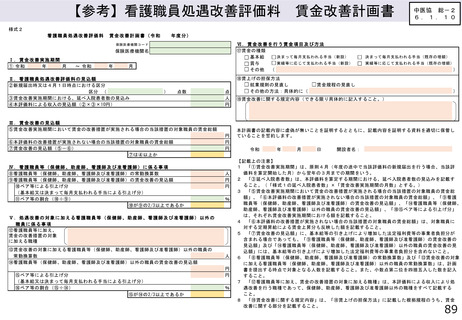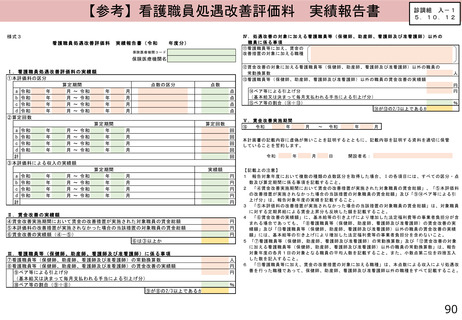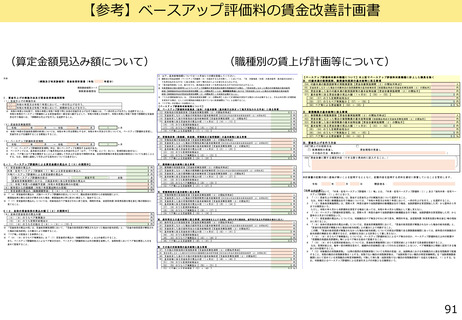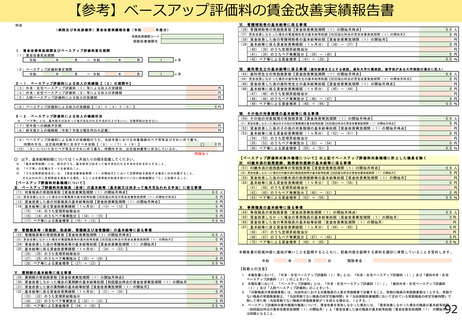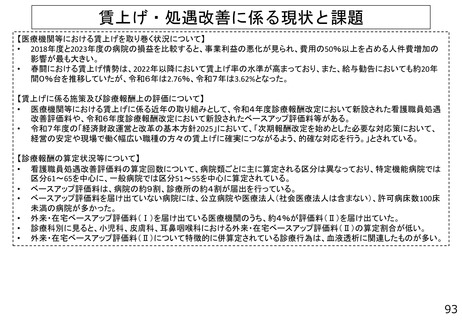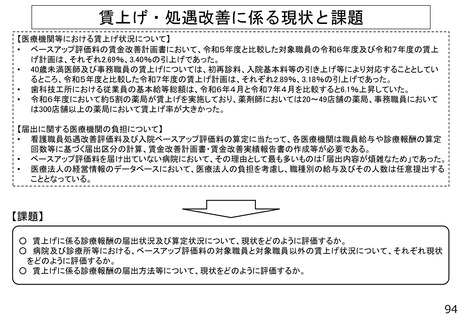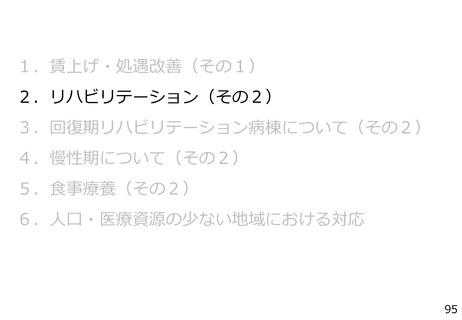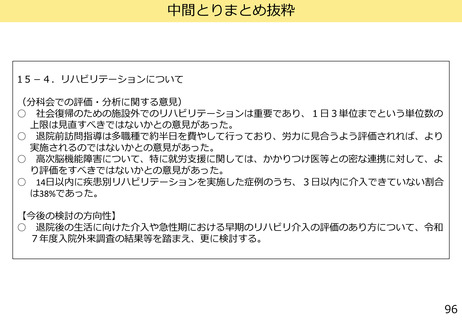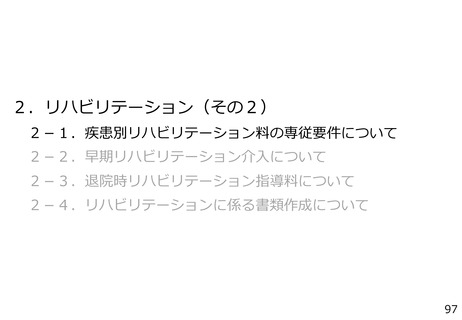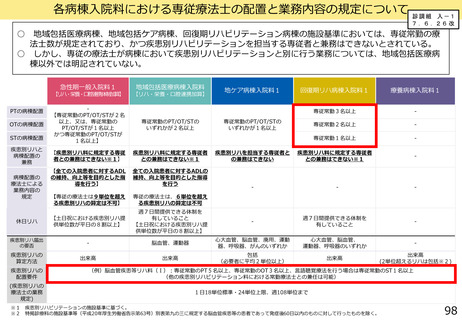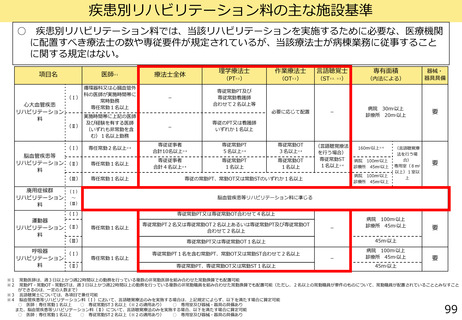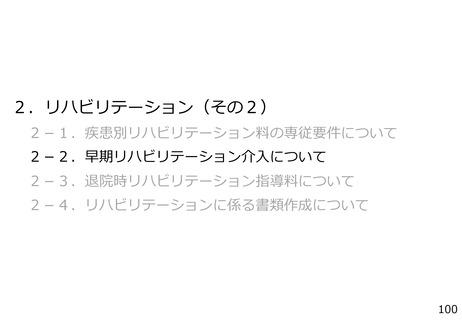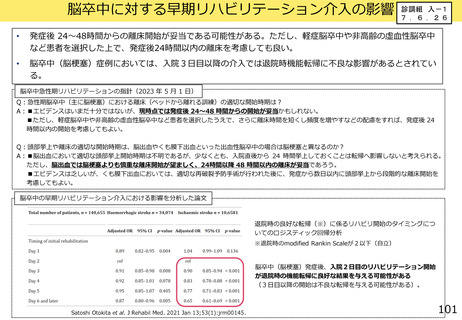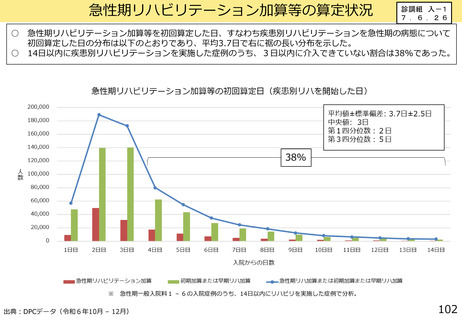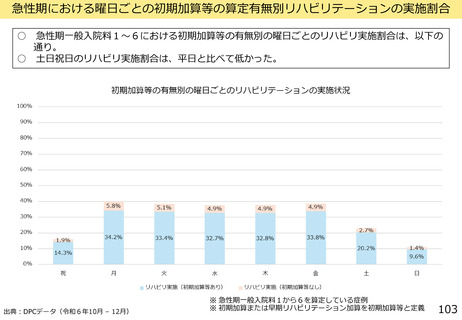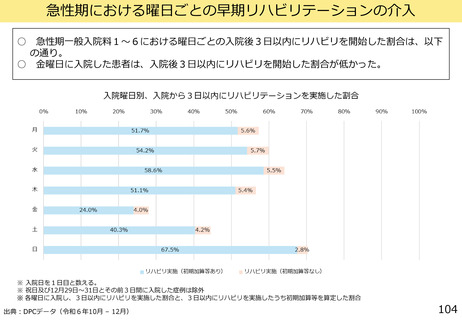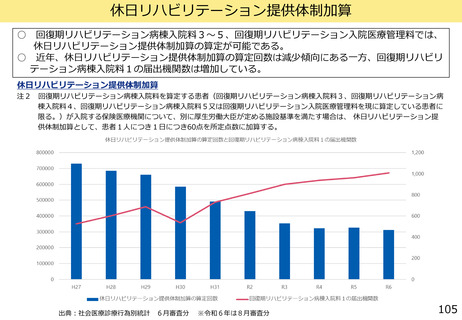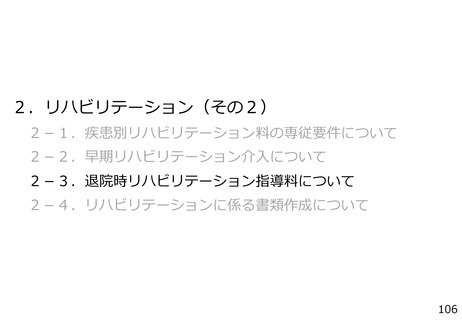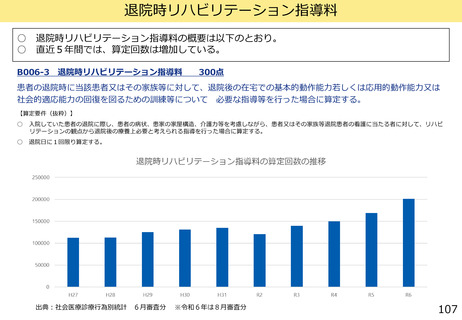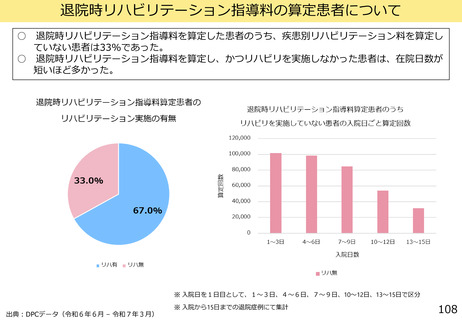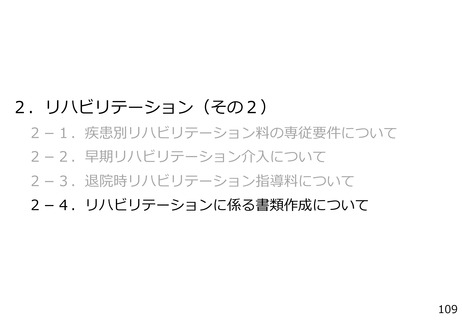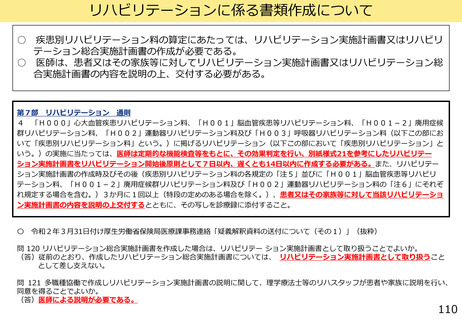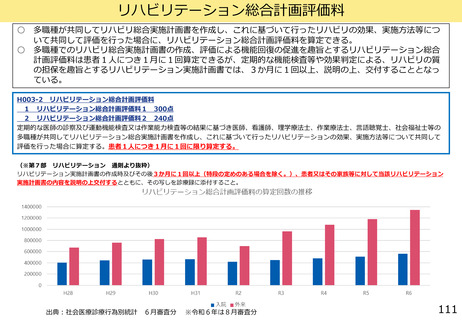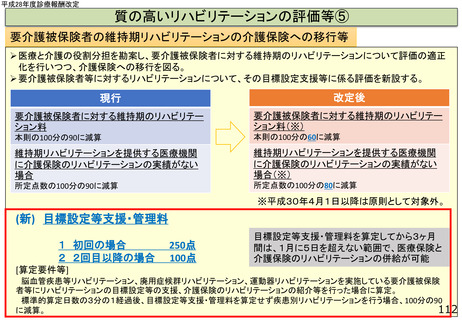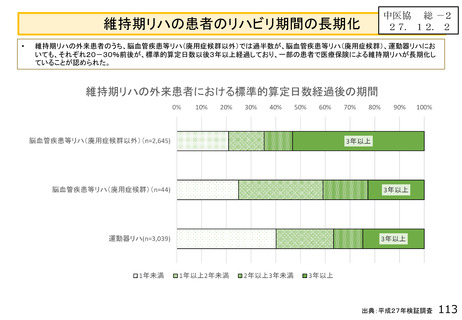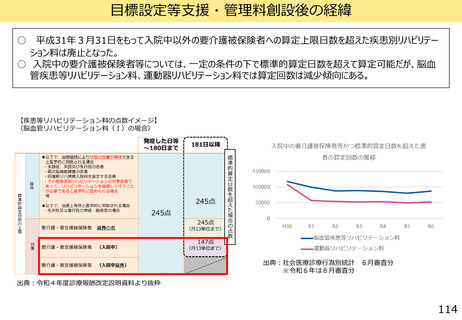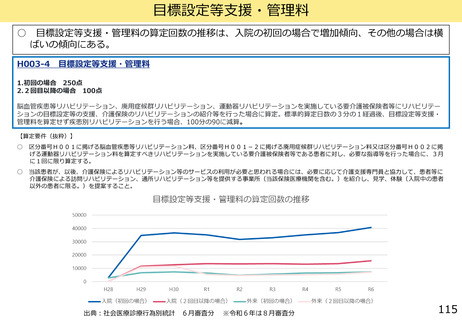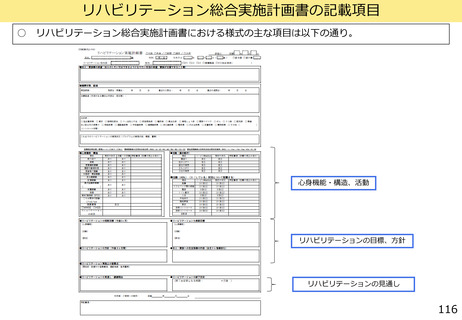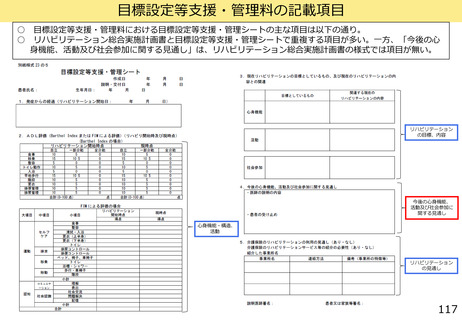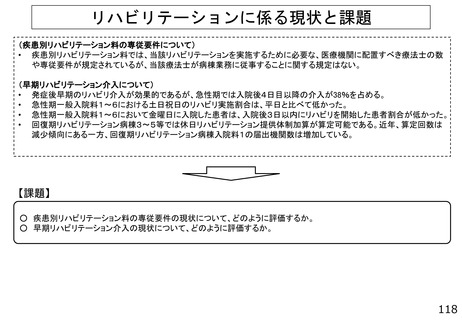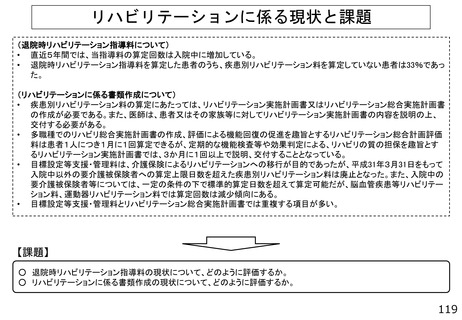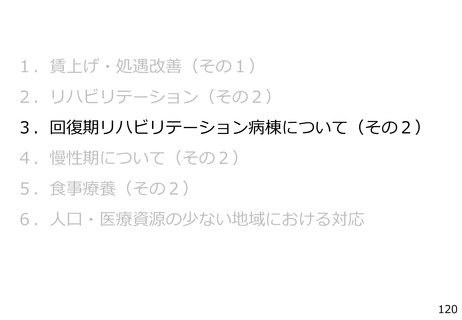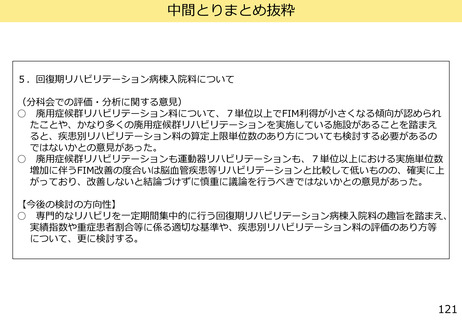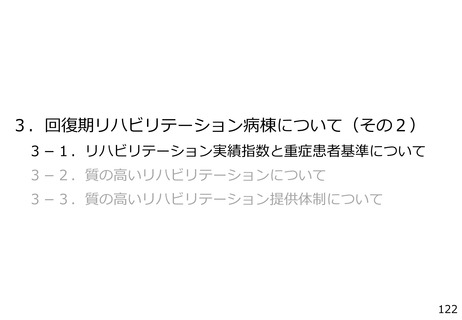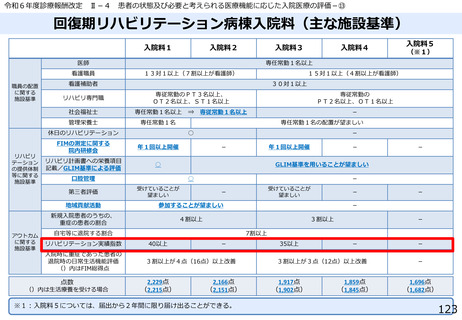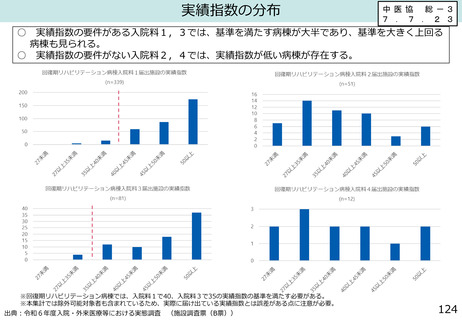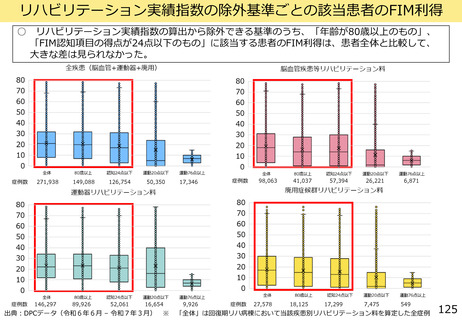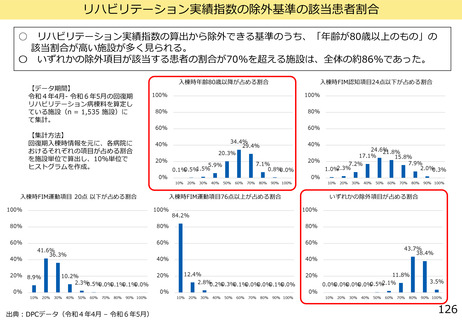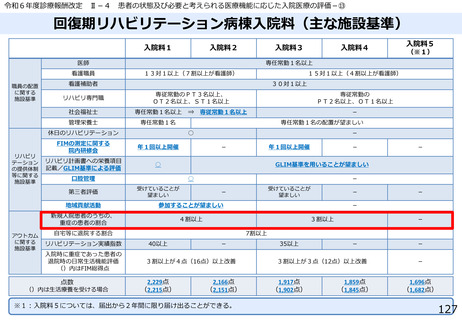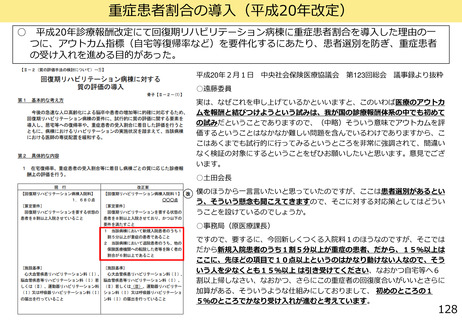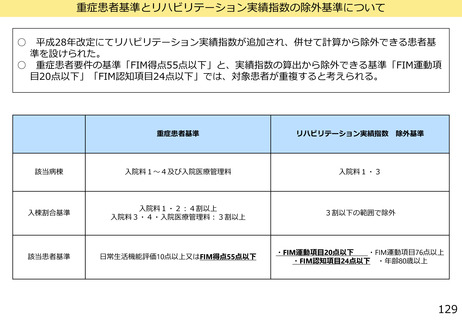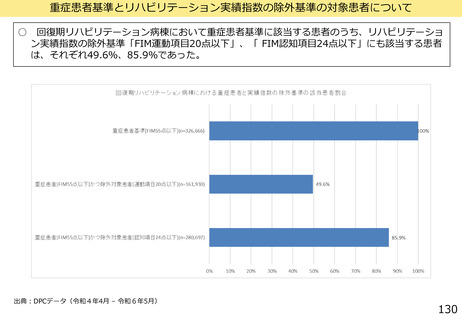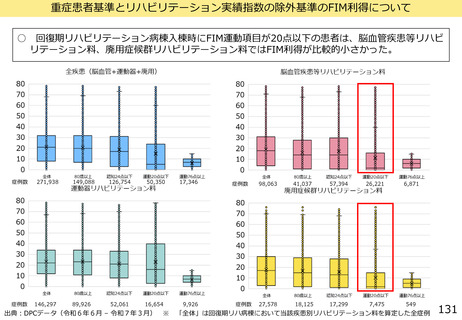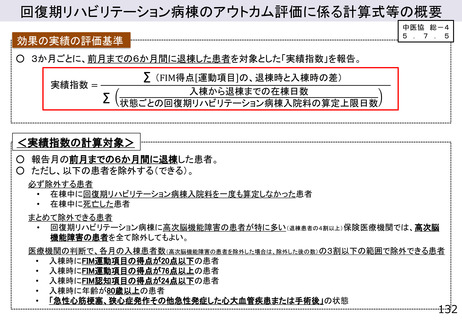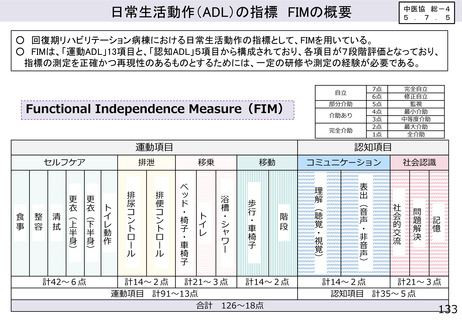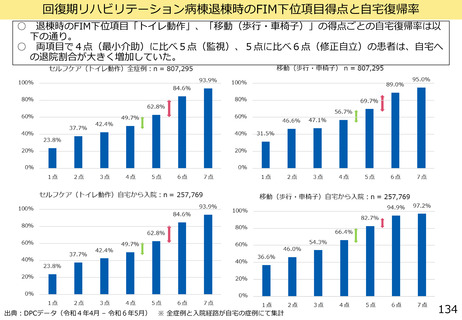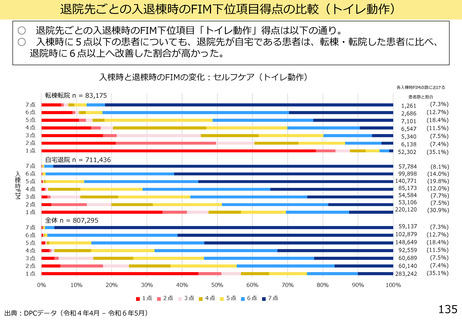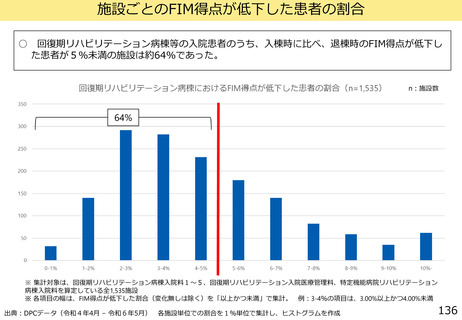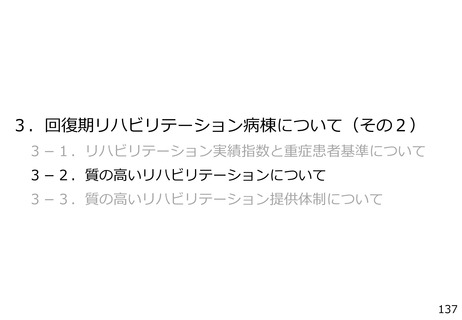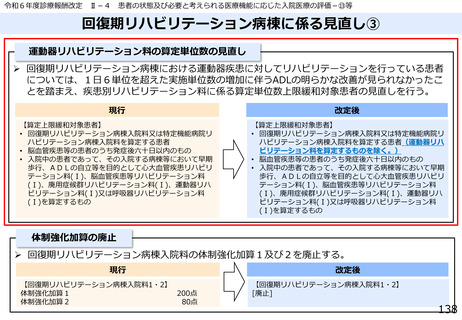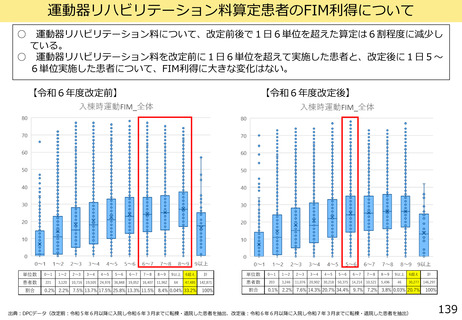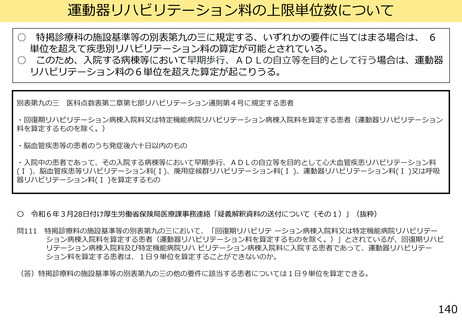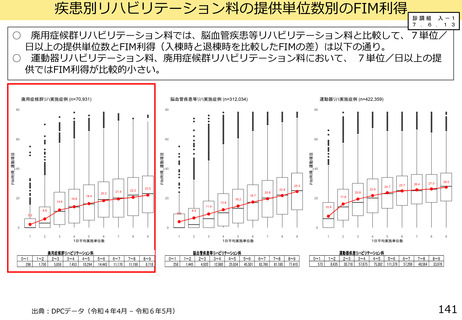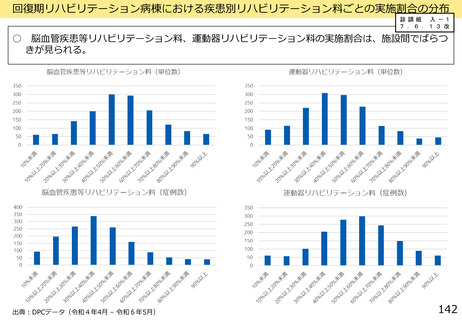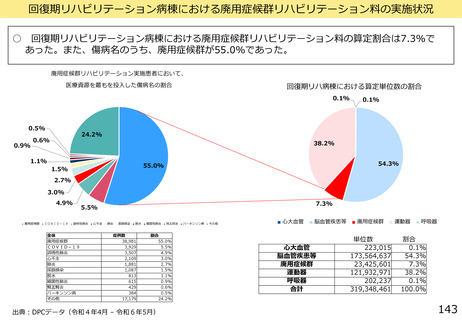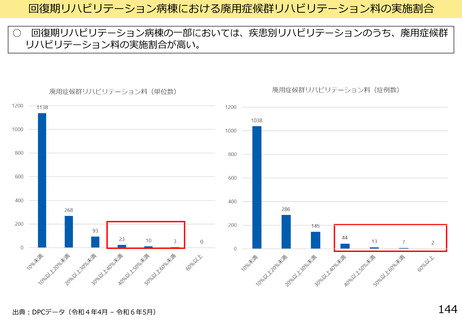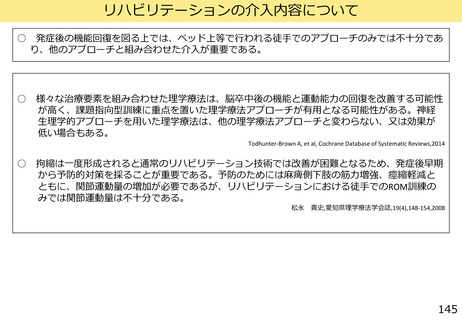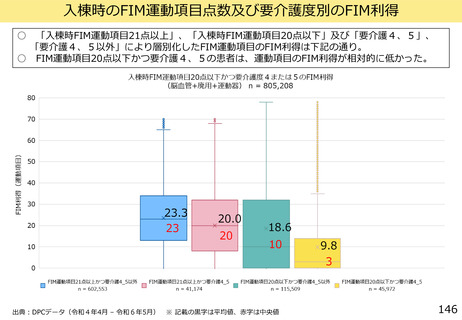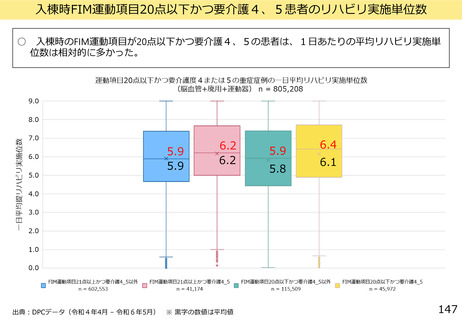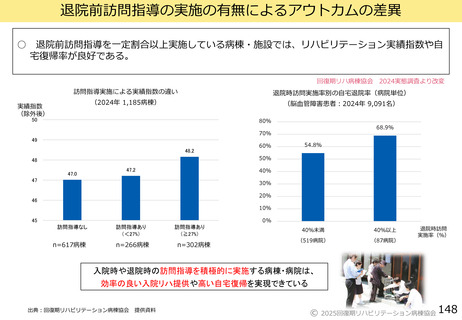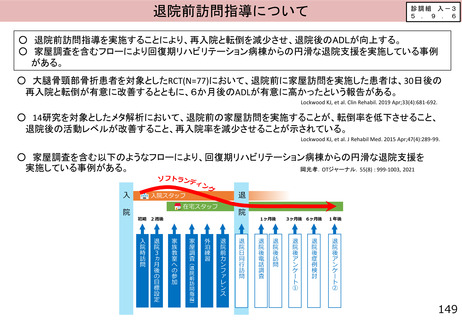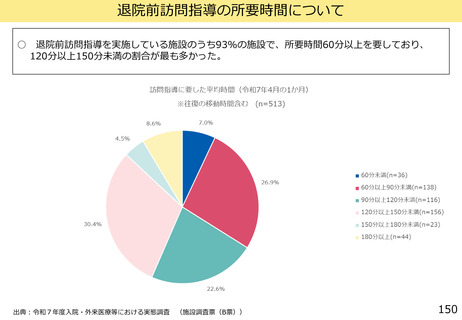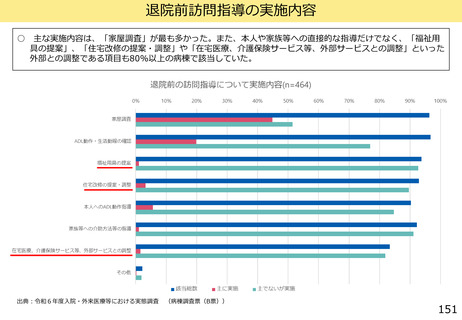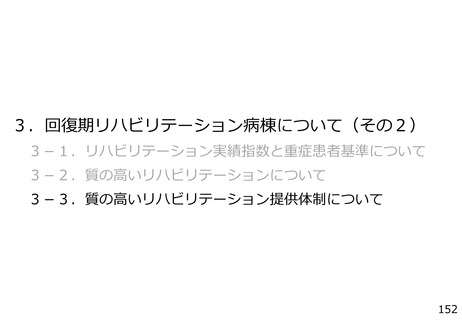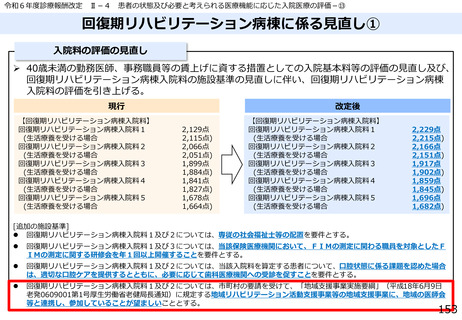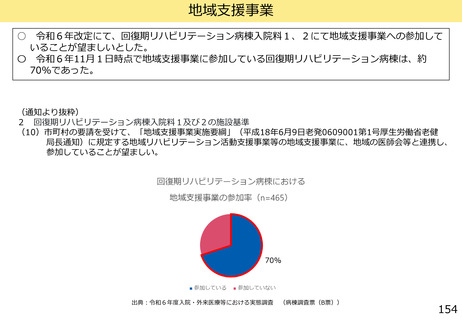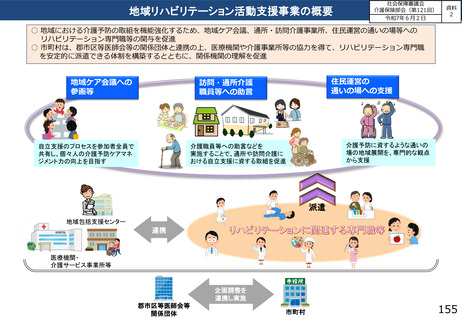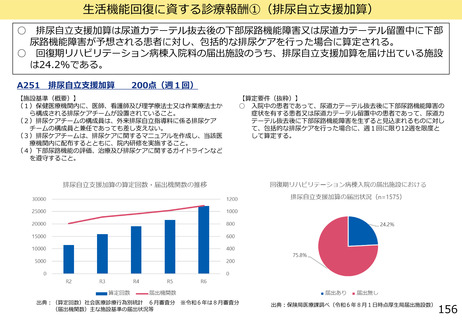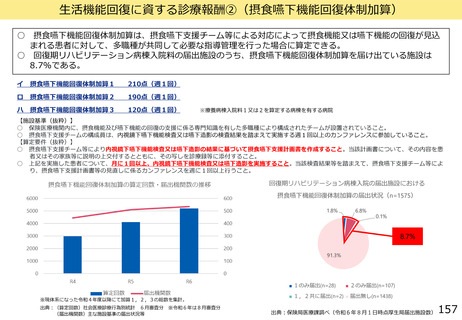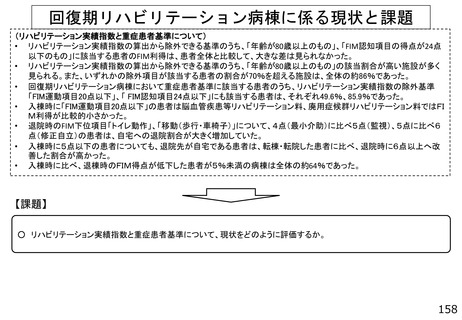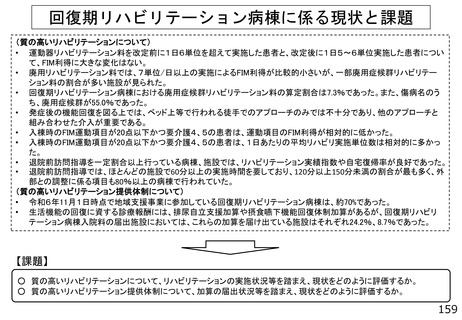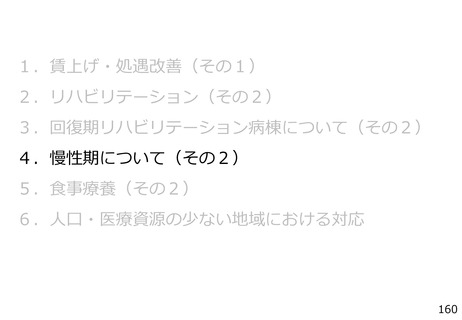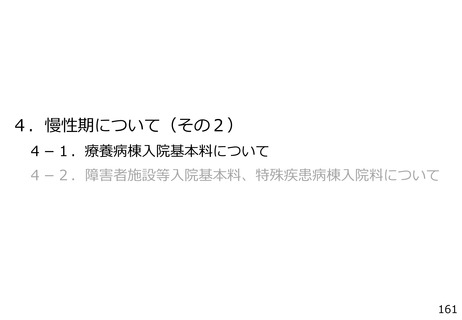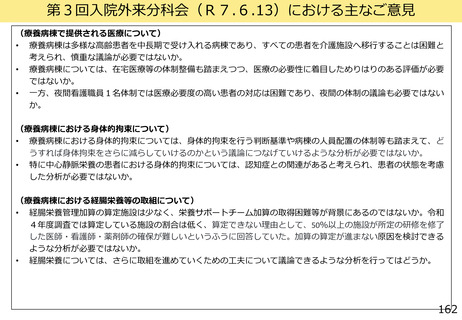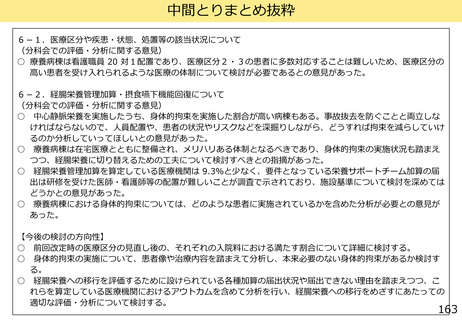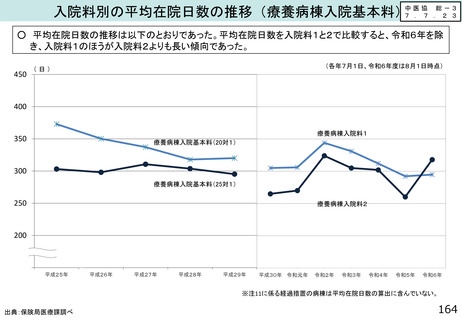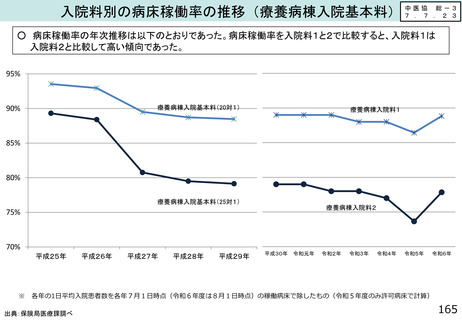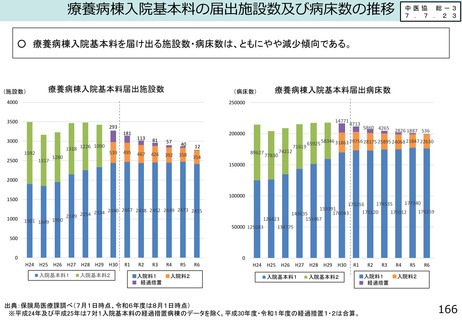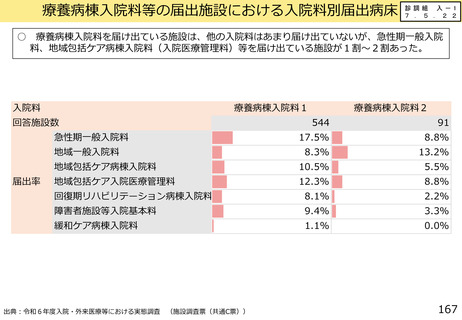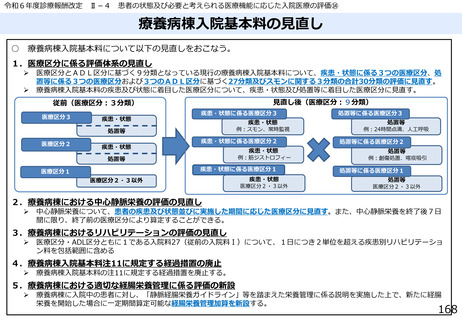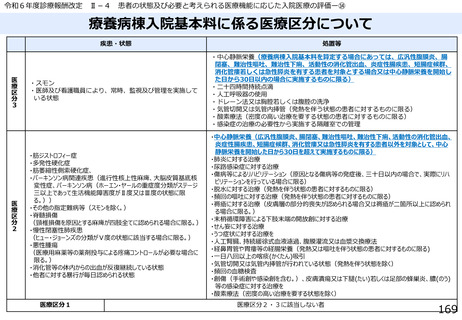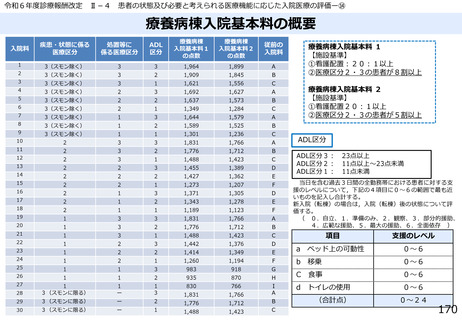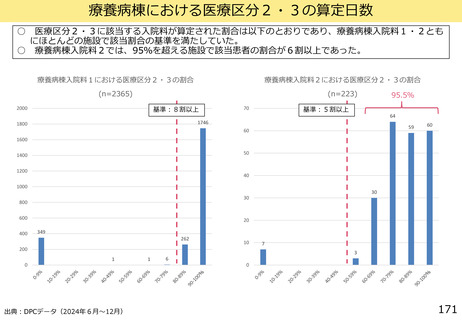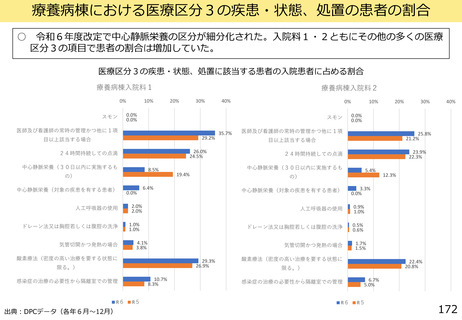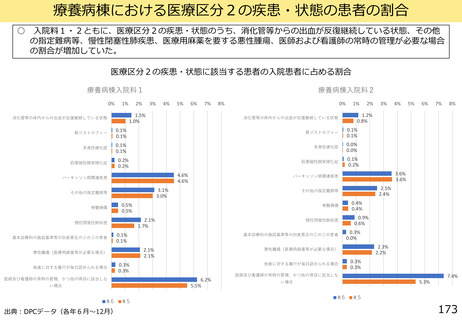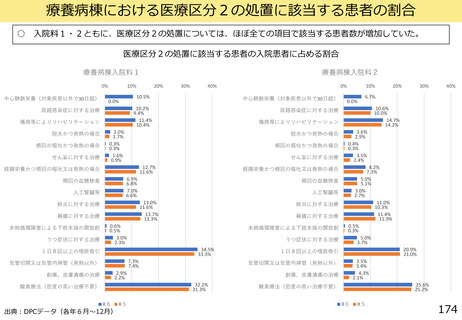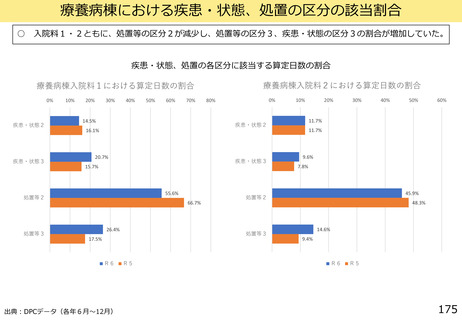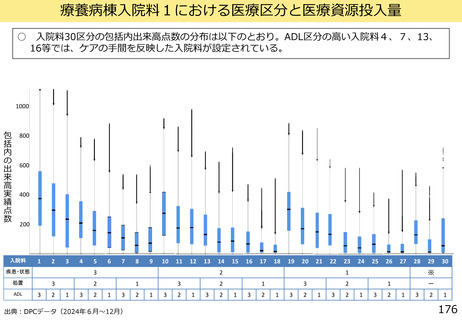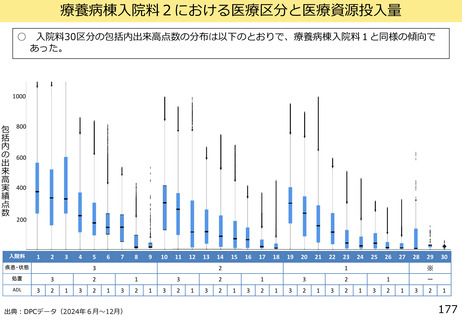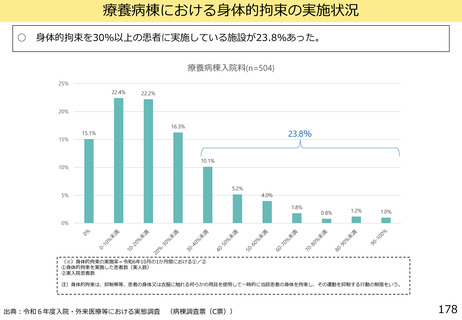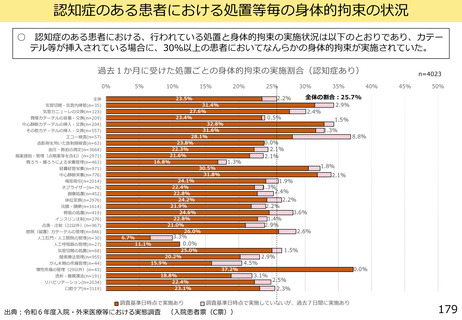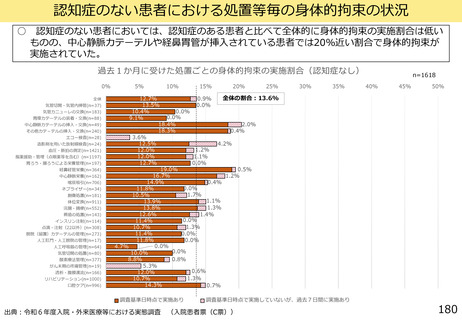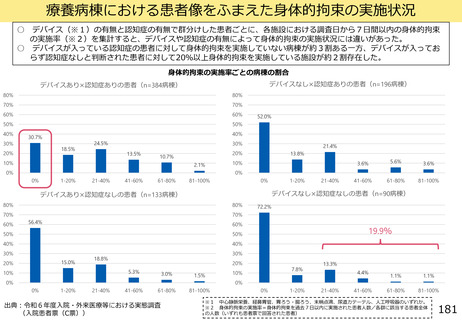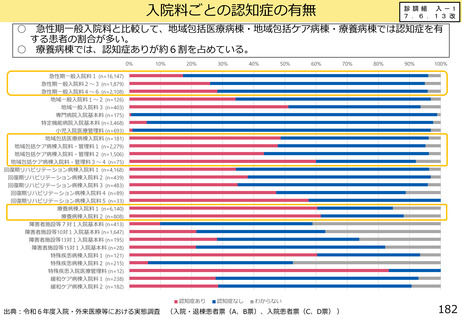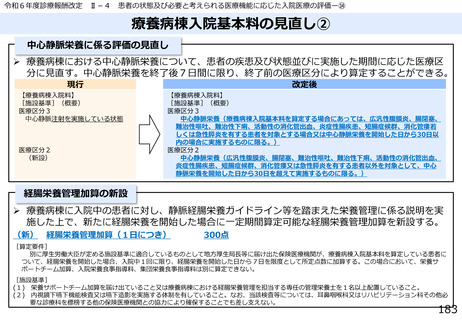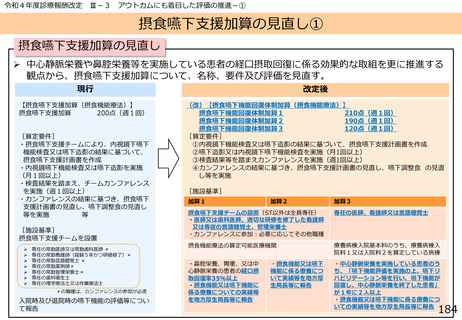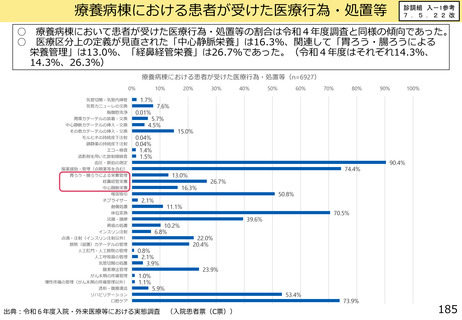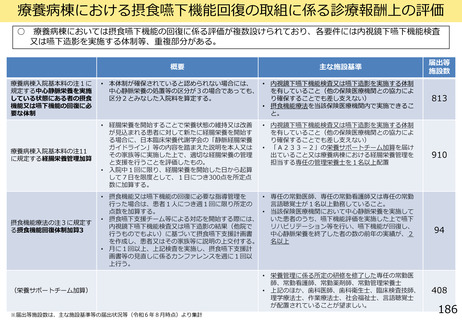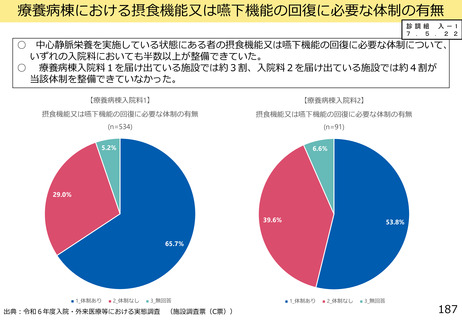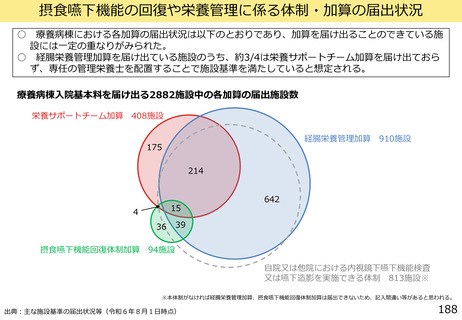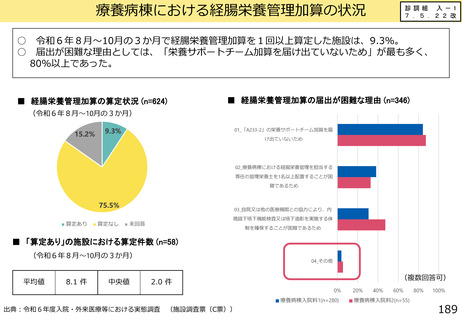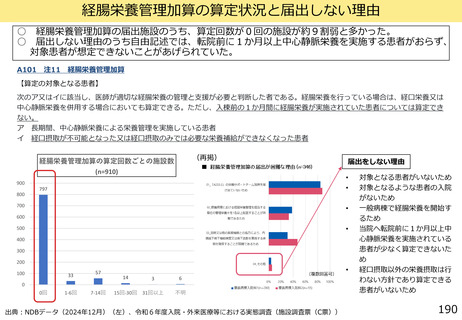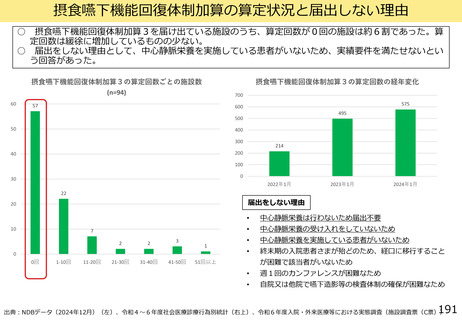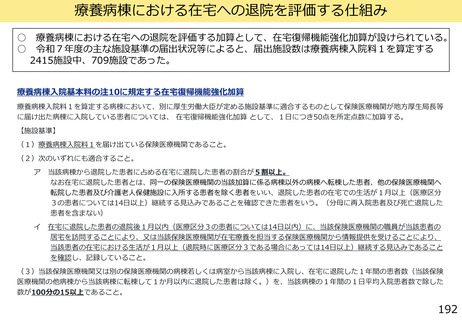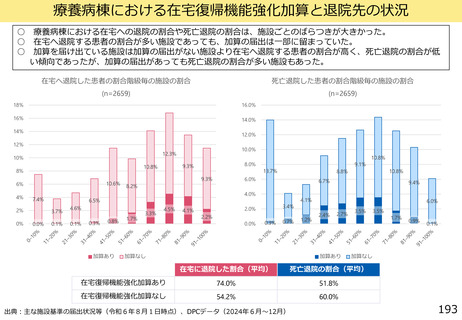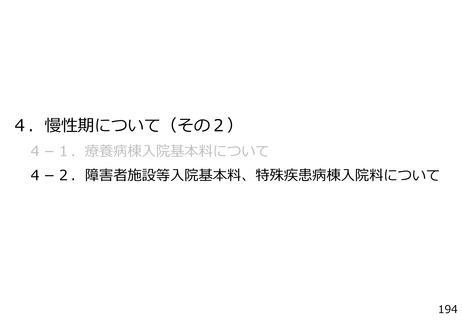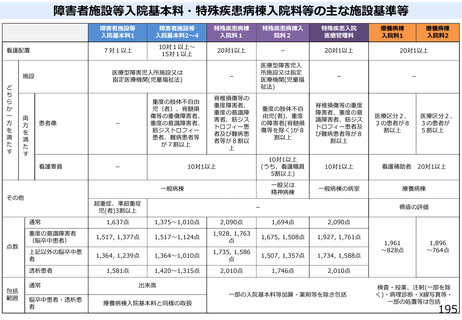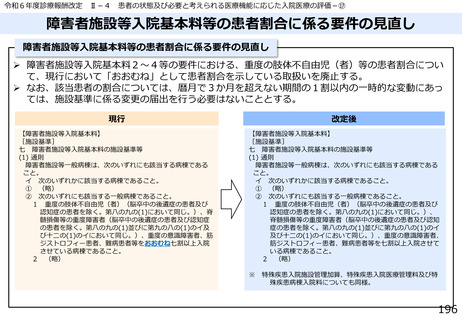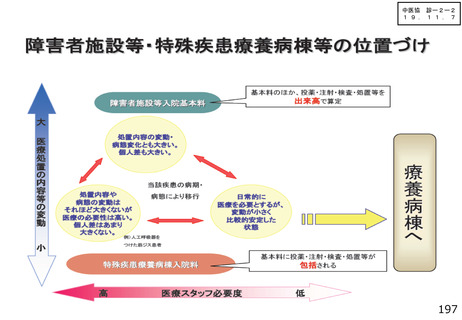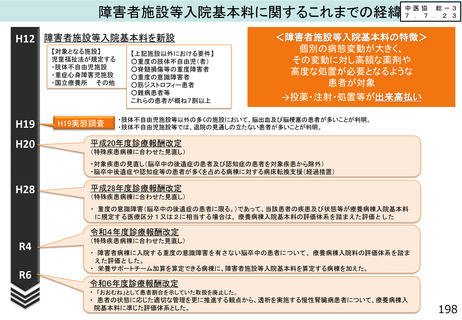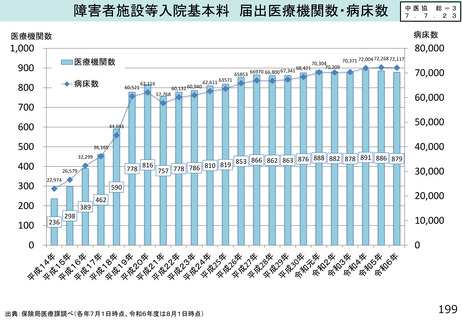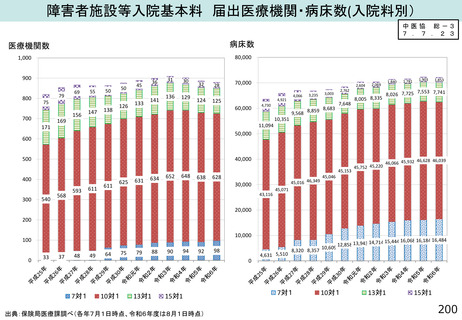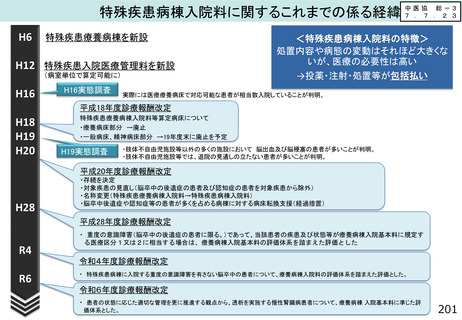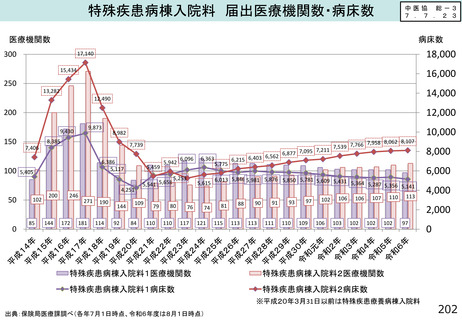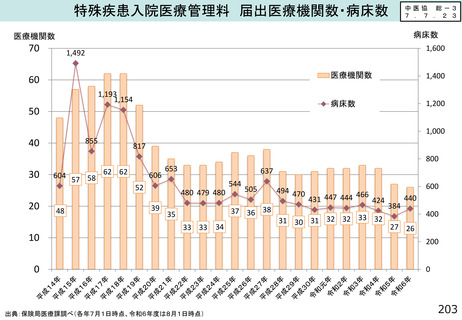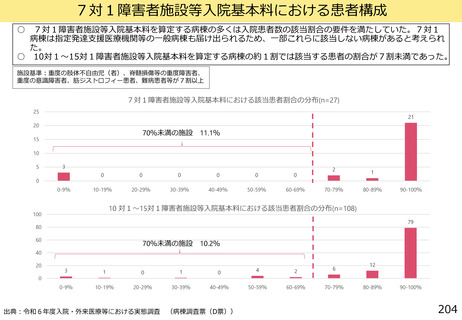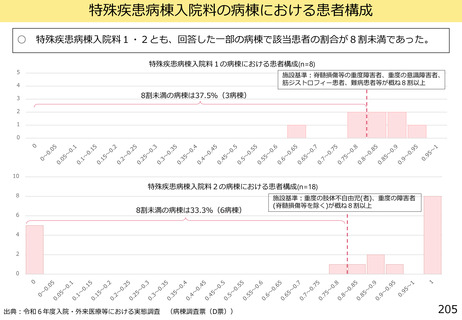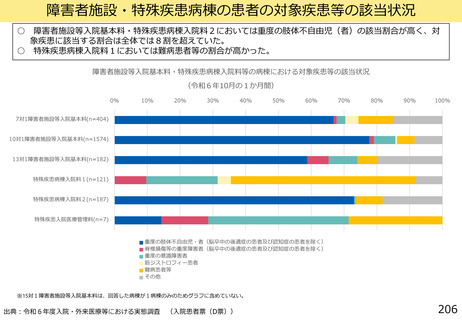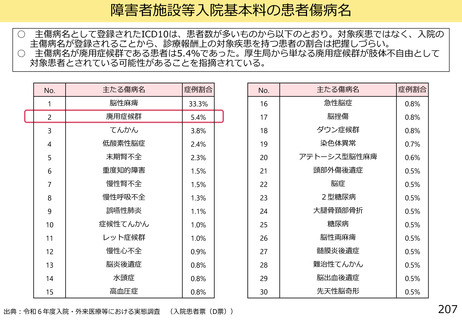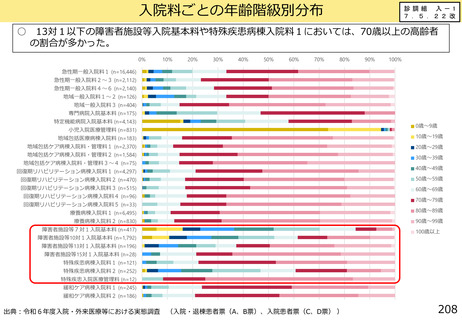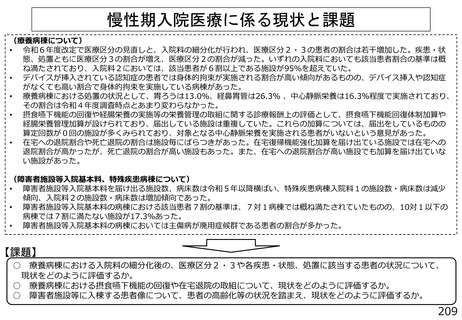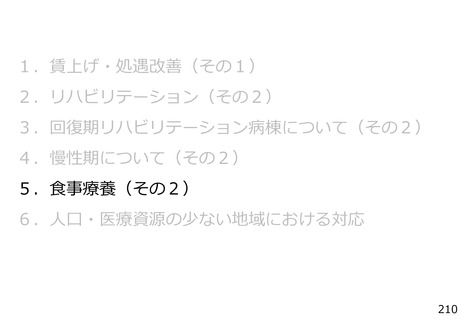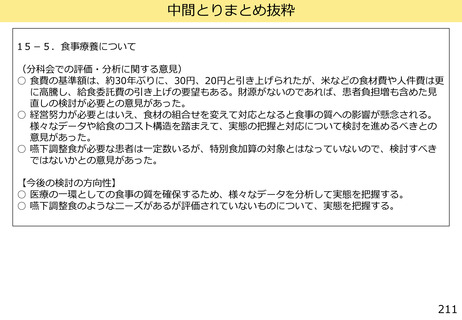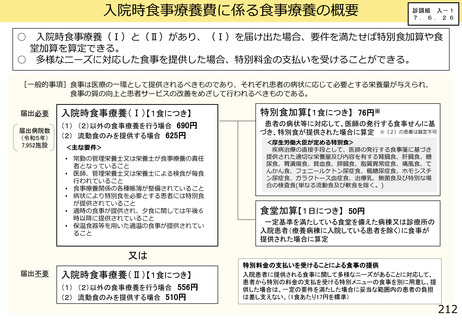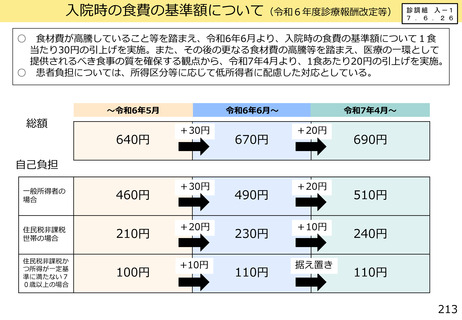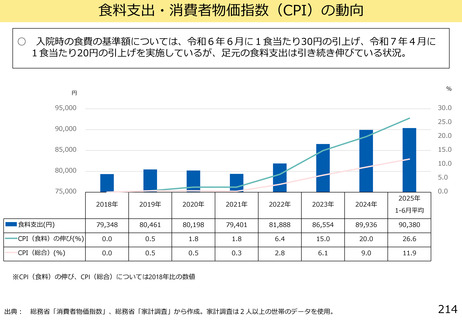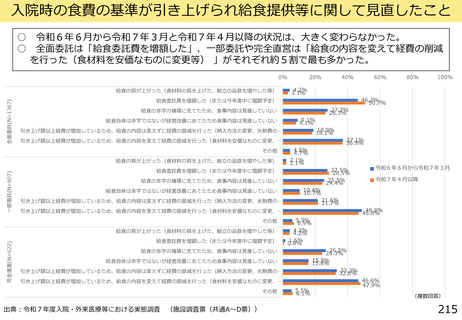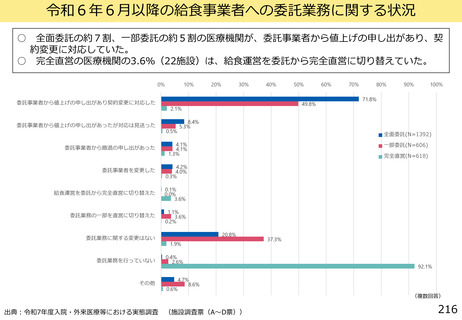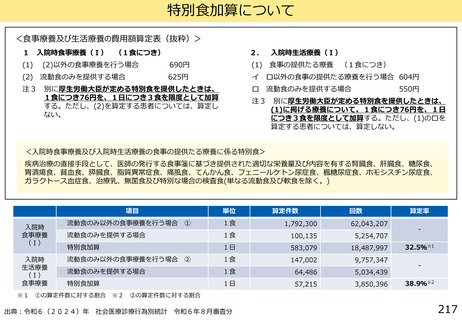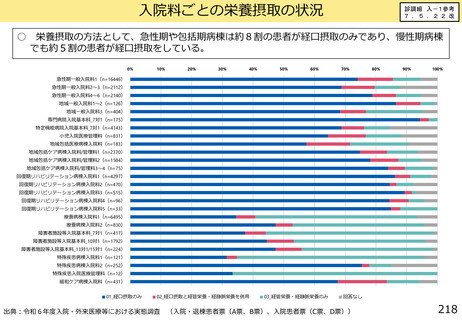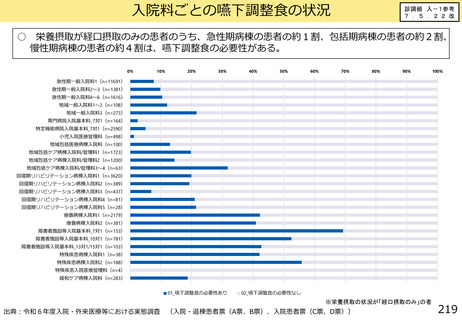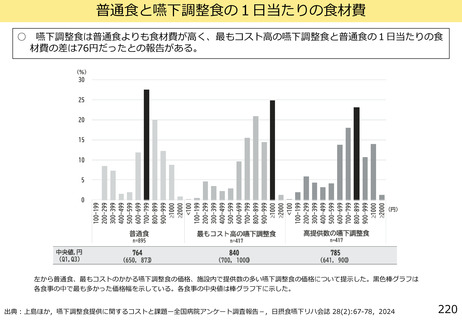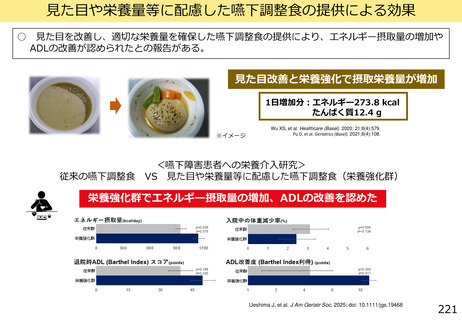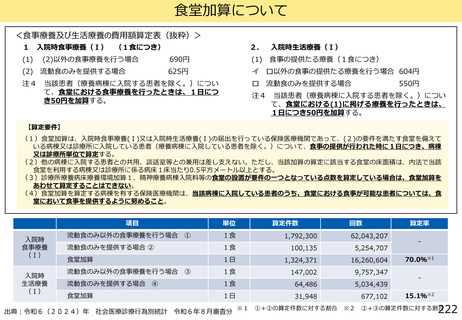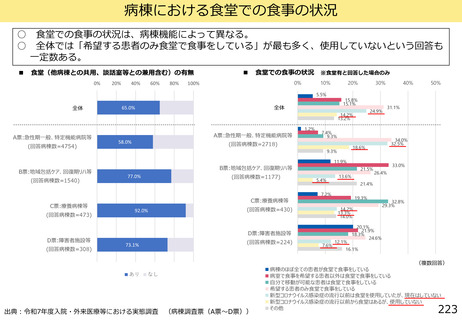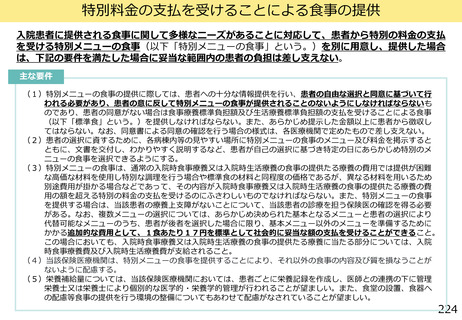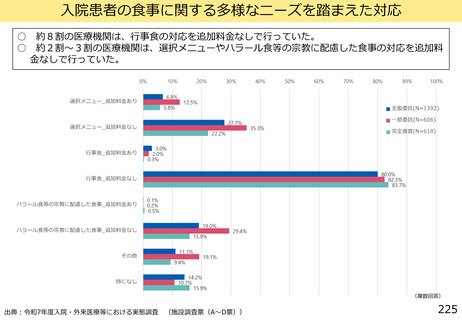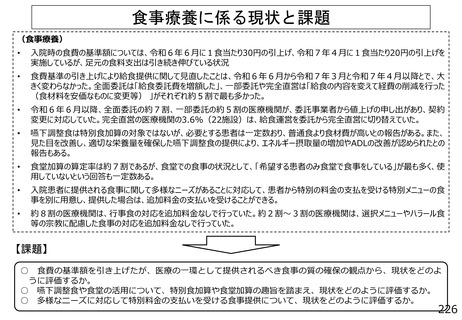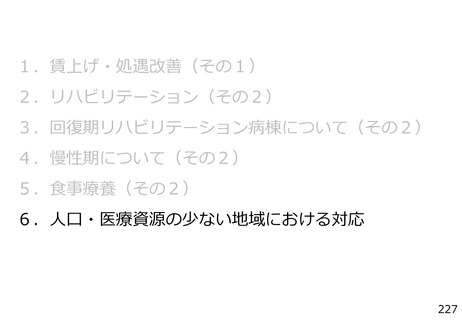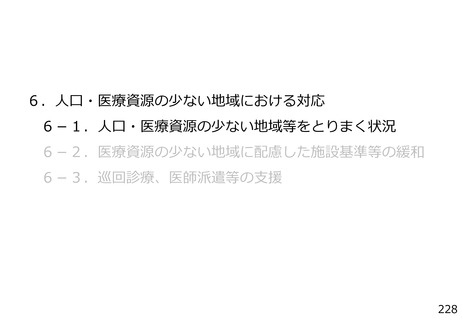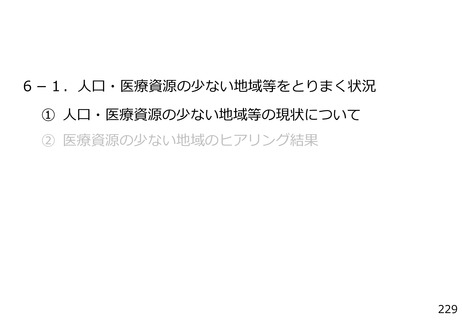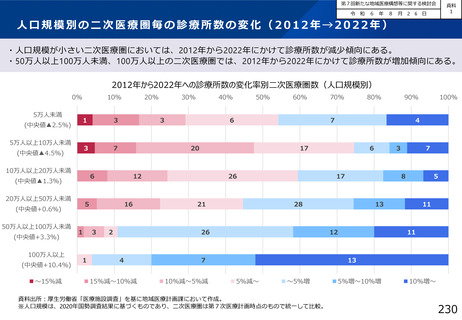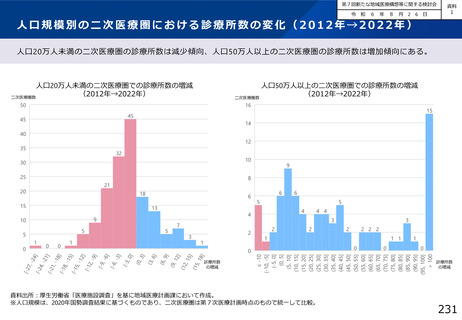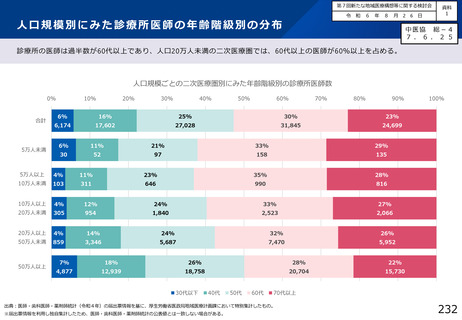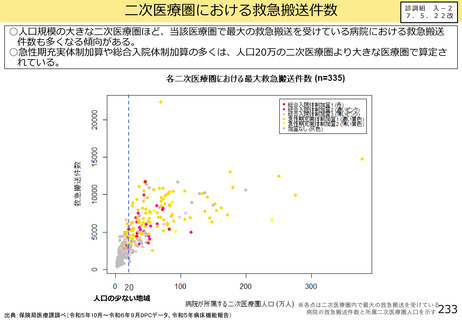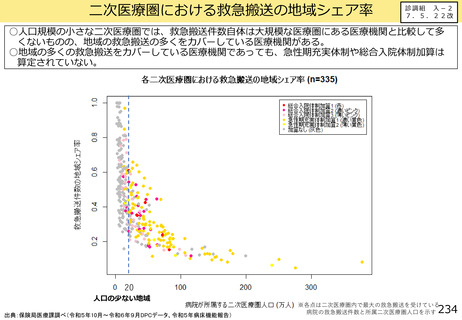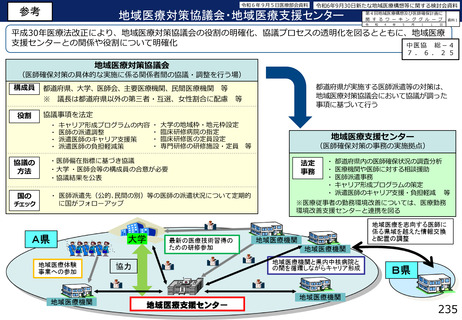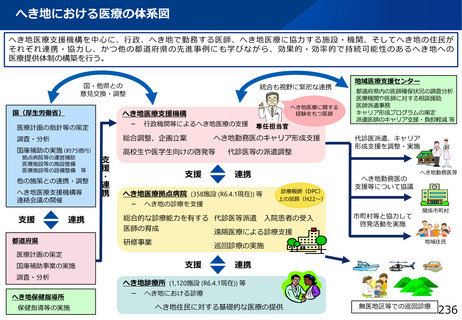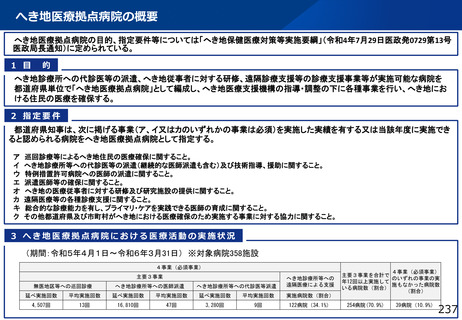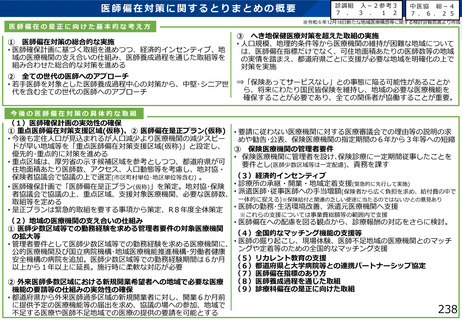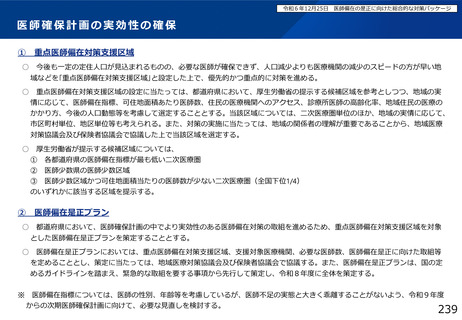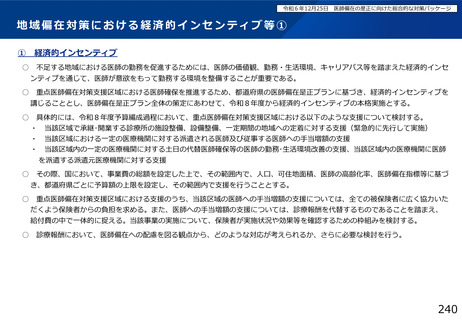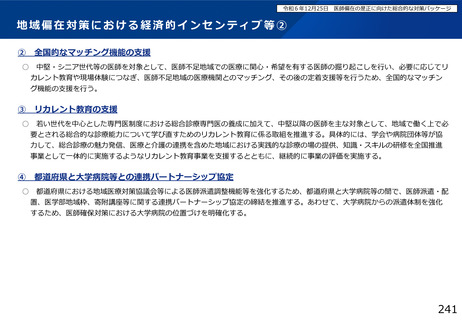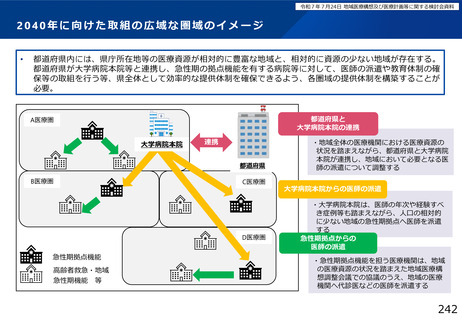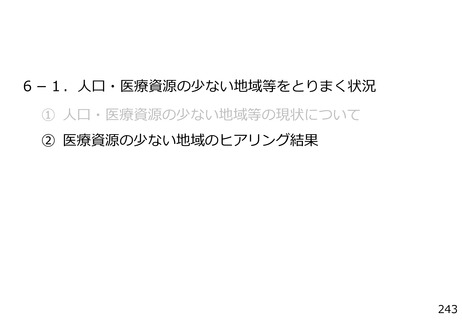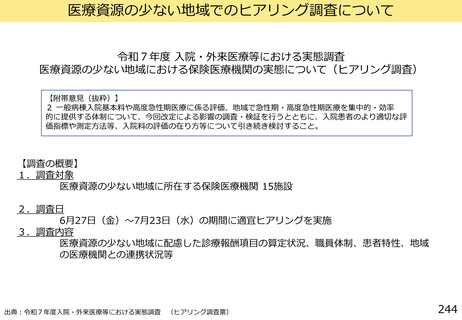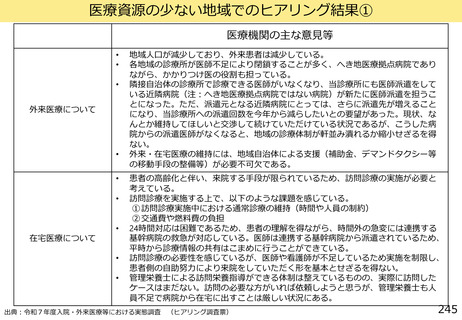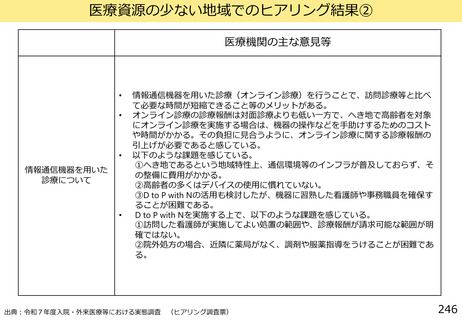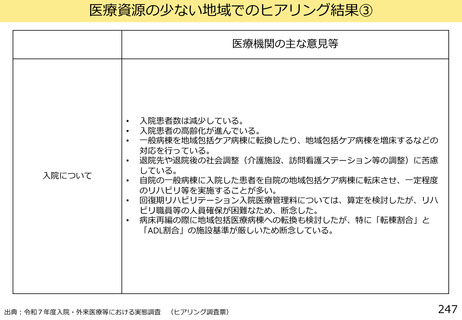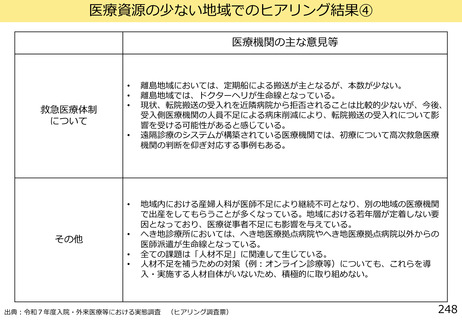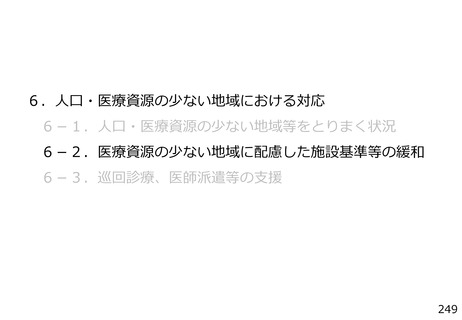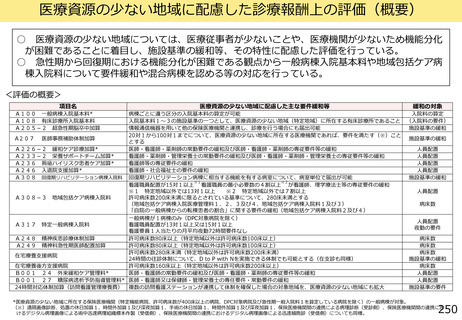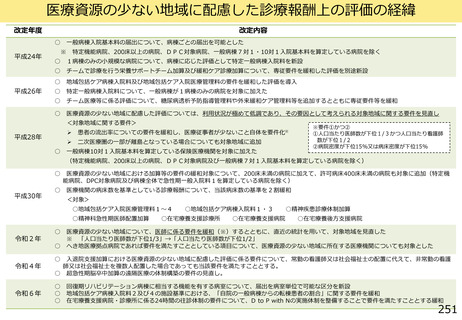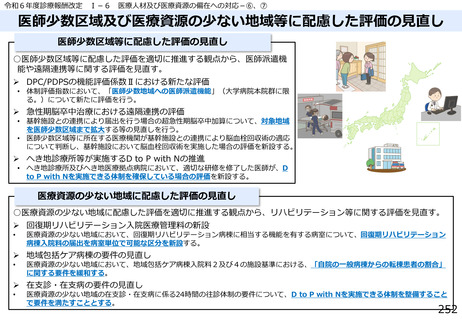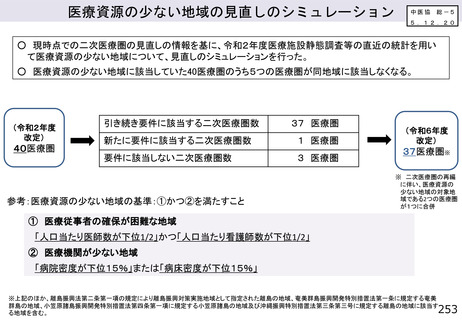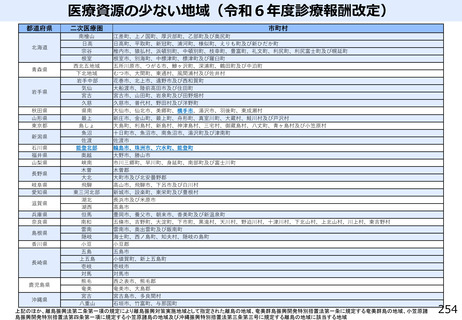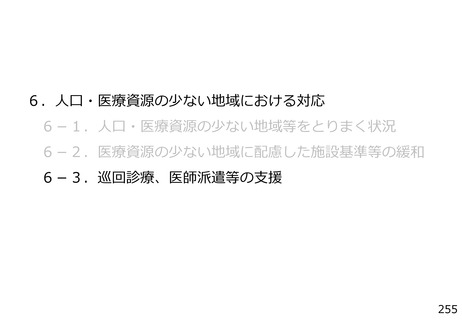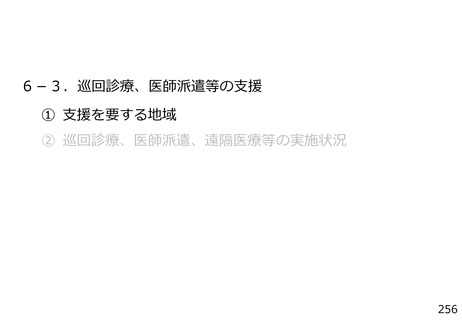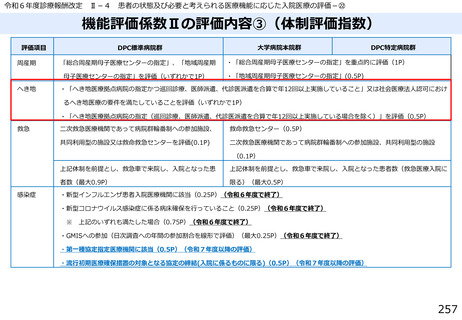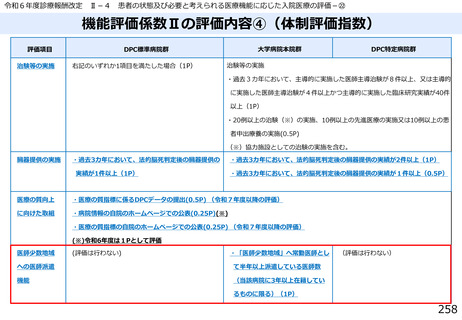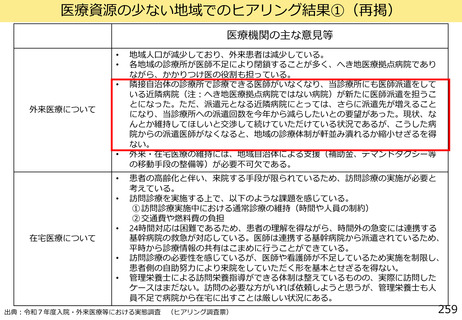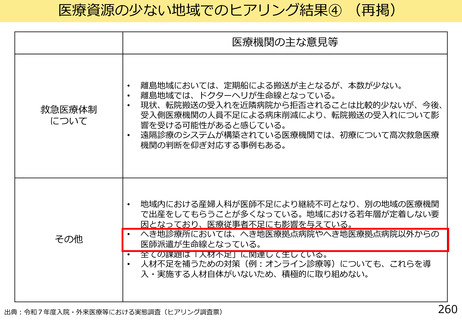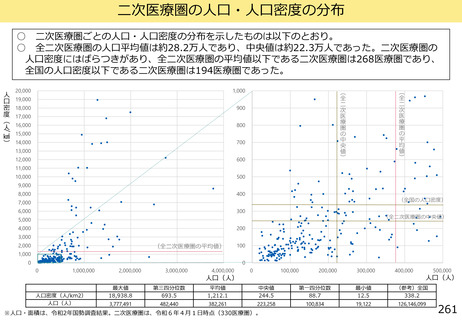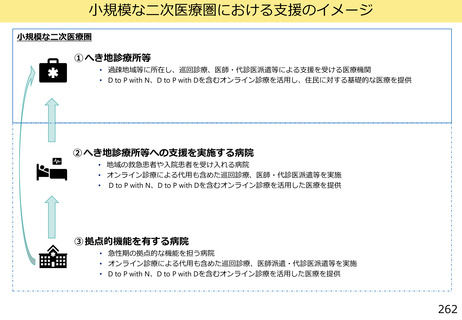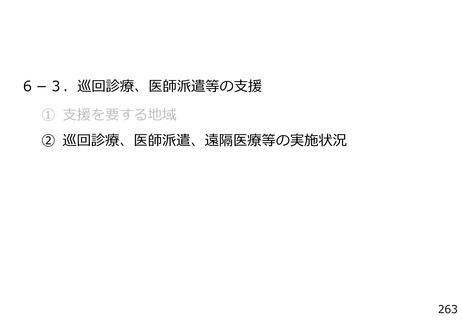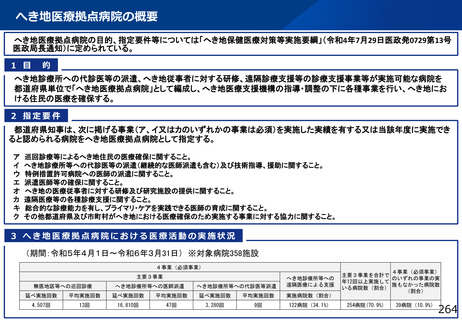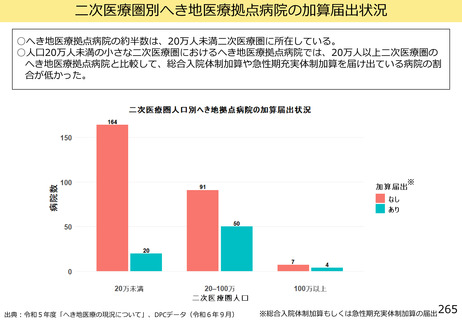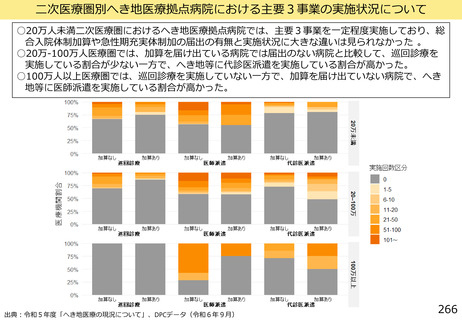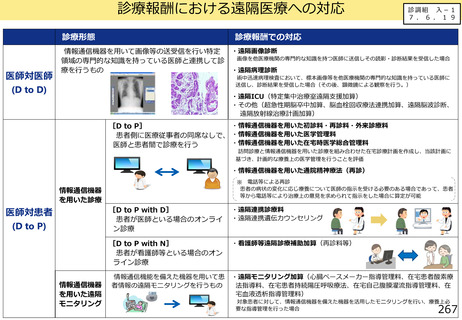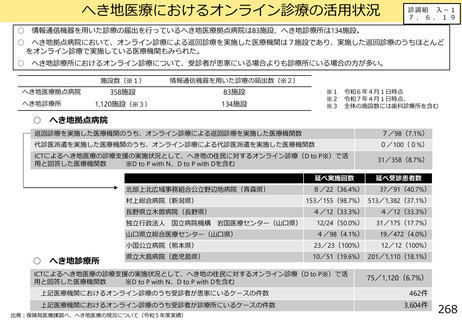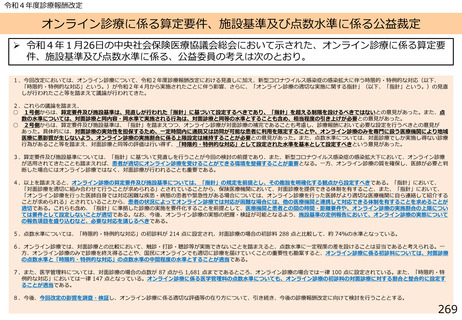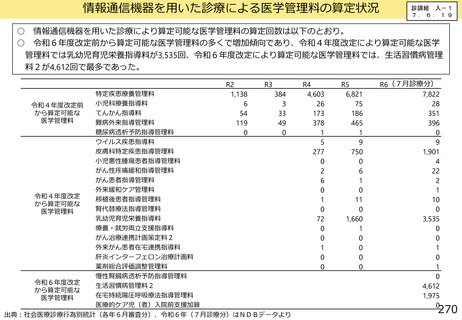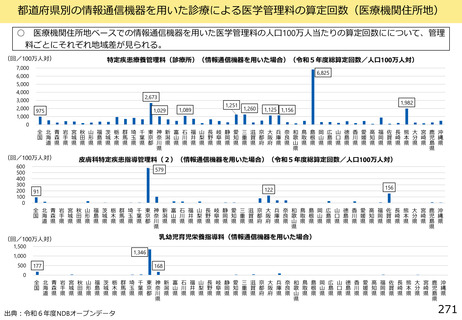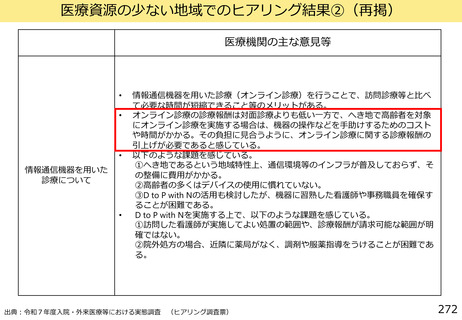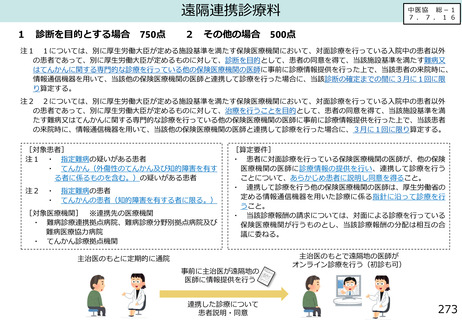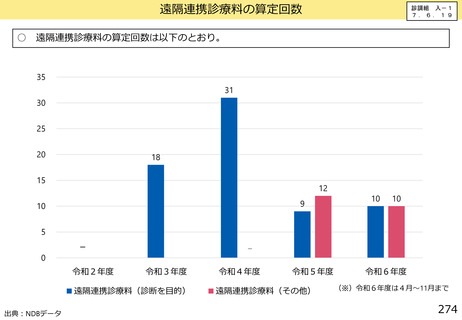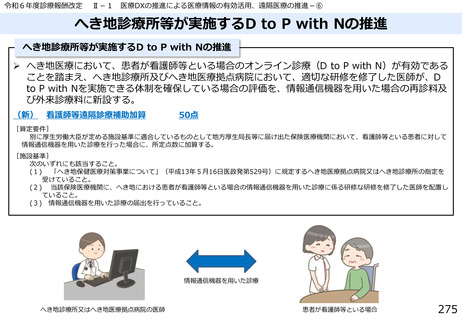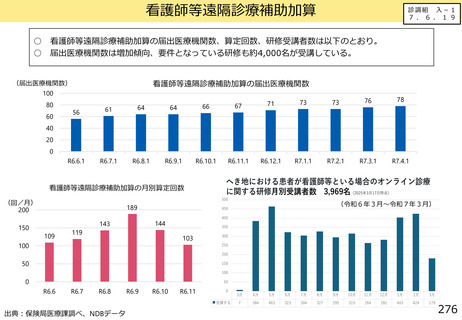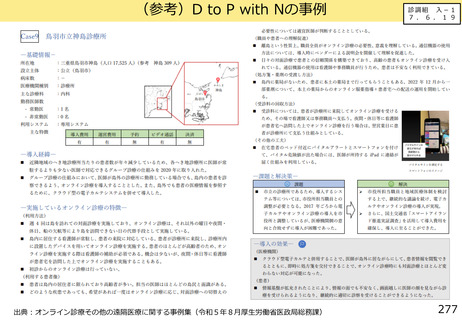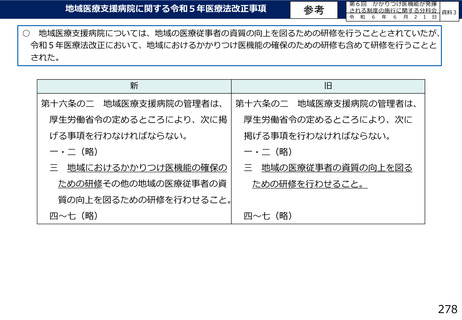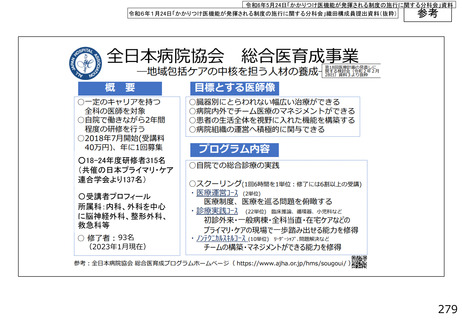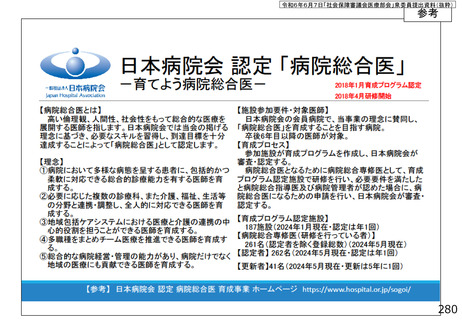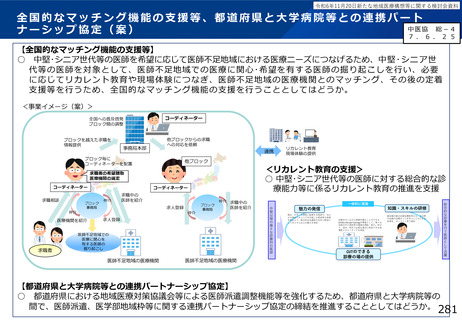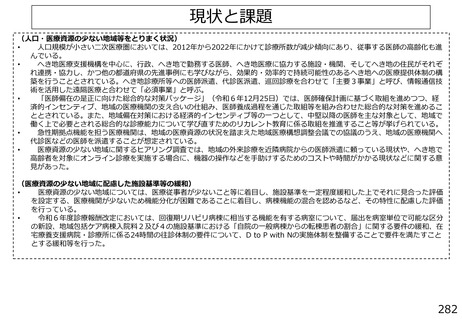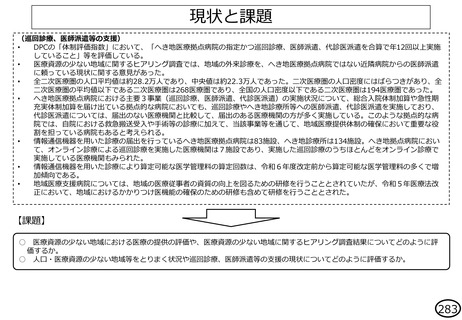入ー2 (145 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00279.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第9回 8/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
発症後の機能回復を図る上では、ベッド上等で行われる徒手でのアプローチのみでは不十分であ
り、他のアプローチと組み合わせた介入が重要である。
○
様々な治療要素を組み合わせた理学療法は、脳卒中後の機能と運動能力の回復を改善する可能性
が高く、課題指向型訓練に重点を置いた理学療法アプローチが有用となる可能性がある。神経
生理学的アプローチを用いた理学療法は、他の理学療法アプローチと変わらない、又は効果が
低い場合もある。
Todhunter-Brown A, et al, Cochrane Database of Systematic Reviews,2014
○
拘縮は一度形成されると通常のリハビリテーション技術では改善が困難となるため、発症後早期
から予防的対策を採ることが重要である。予防のためには麻痺側下肢の筋力増強、痙縮軽減と
ともに、関節運動量の増加が必要であるが、リハビリテーションにおける徒手でのROM訓練の
みでは関節運動量は不十分である。
松永 貴史,愛知県理学療法学会誌,19(4),148-154,2008
145