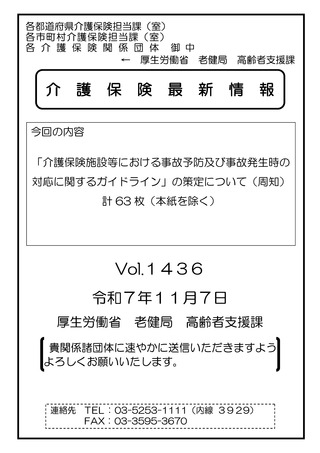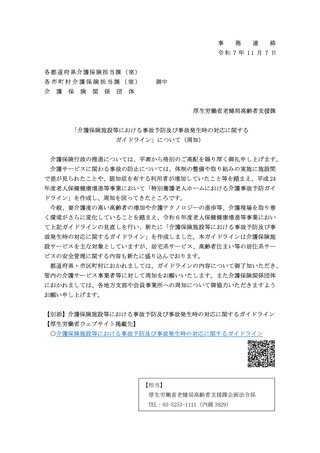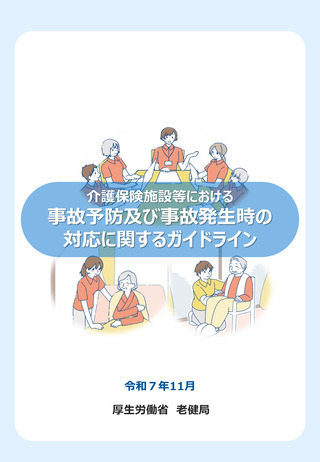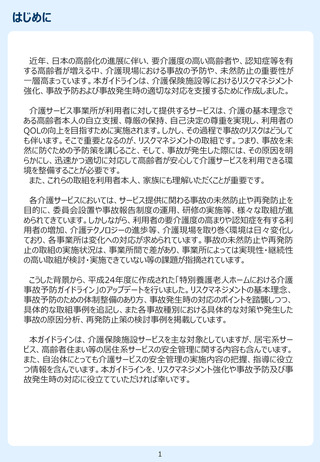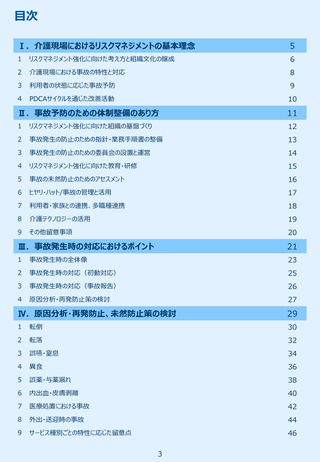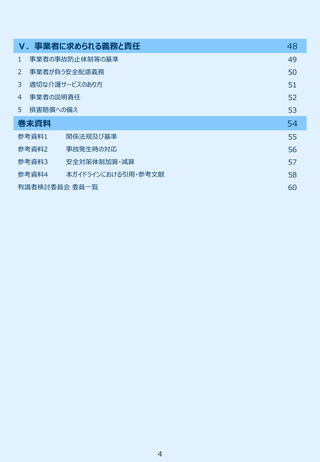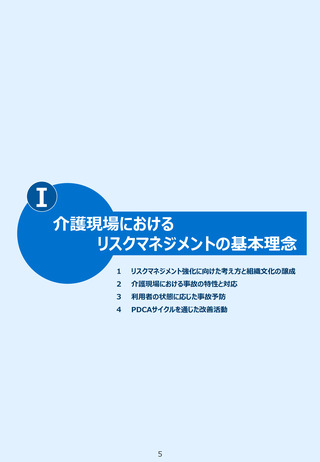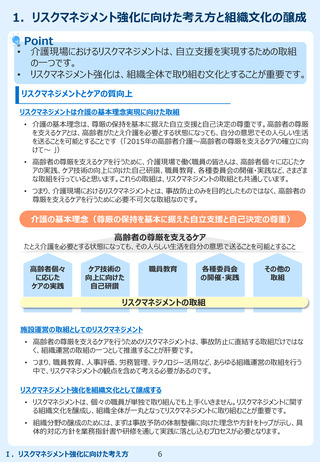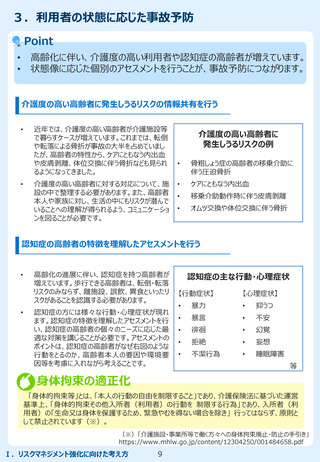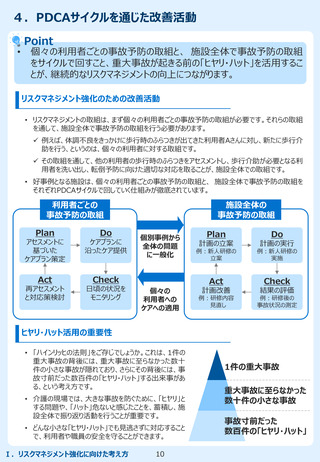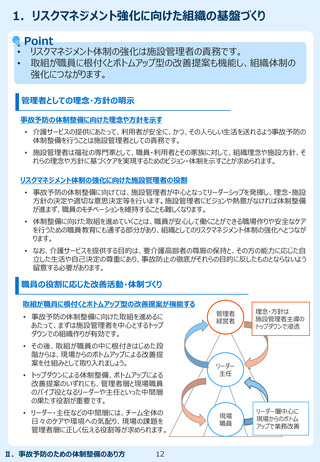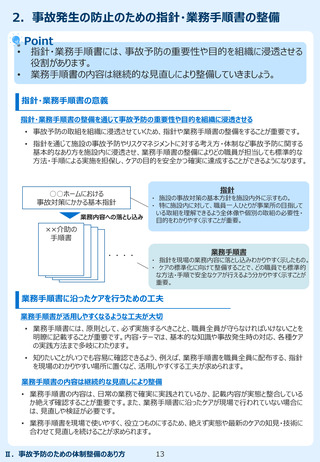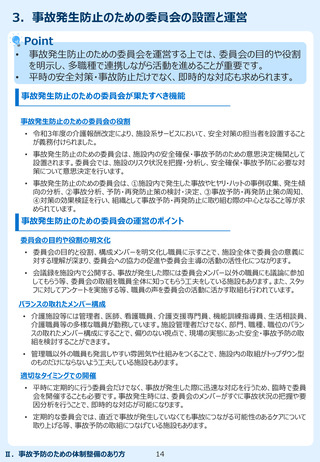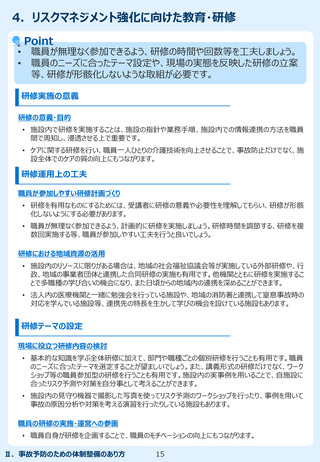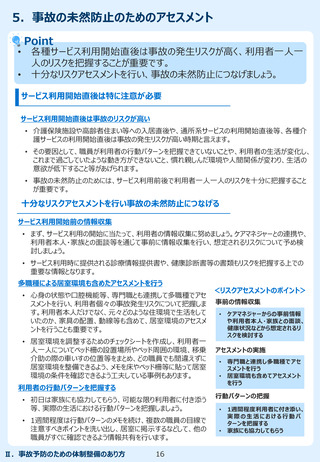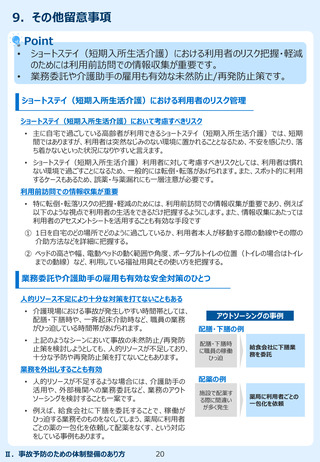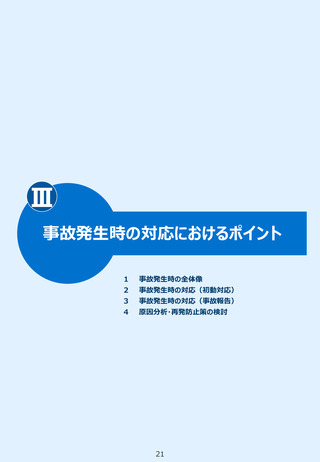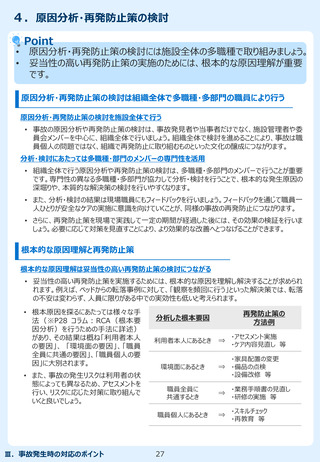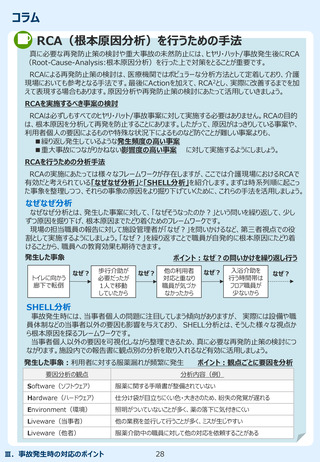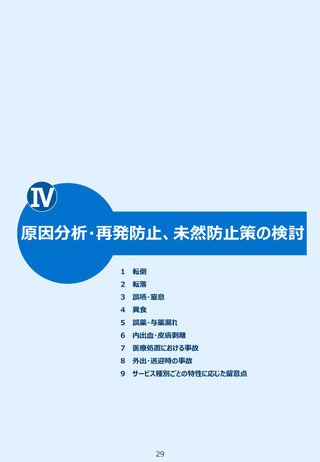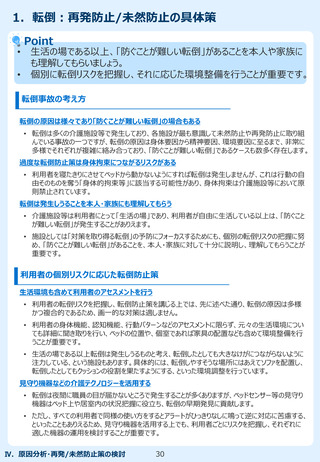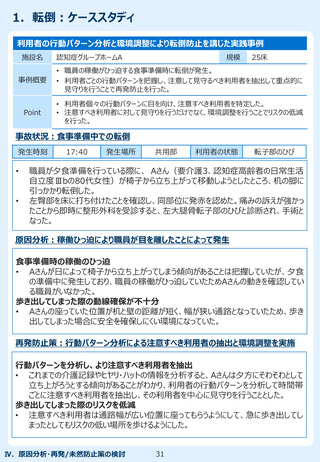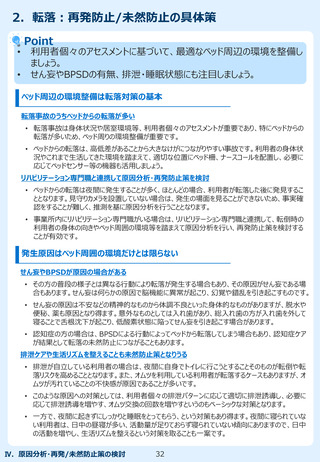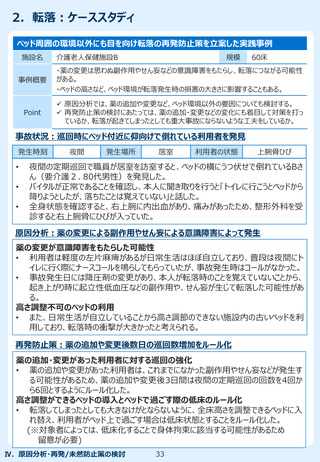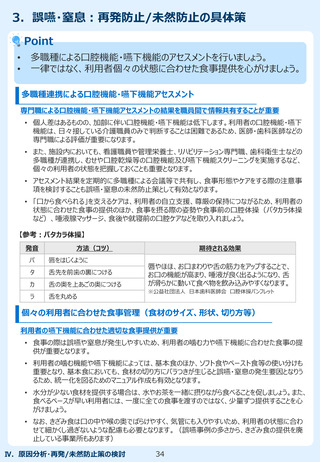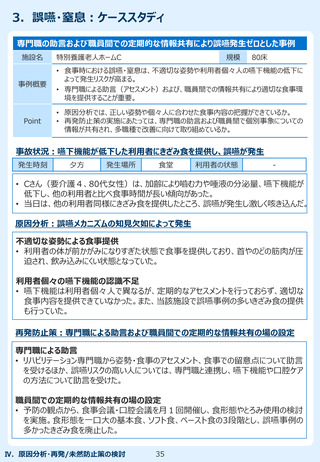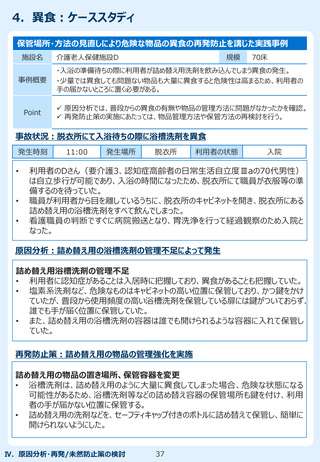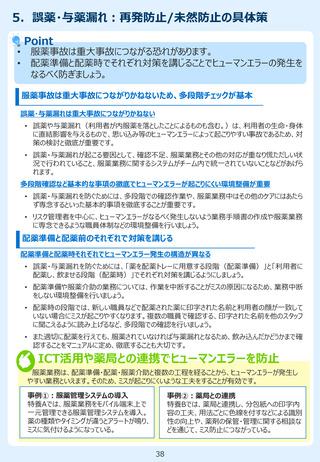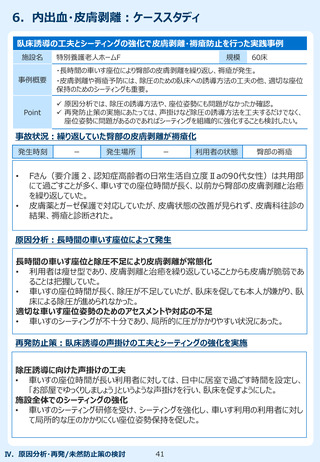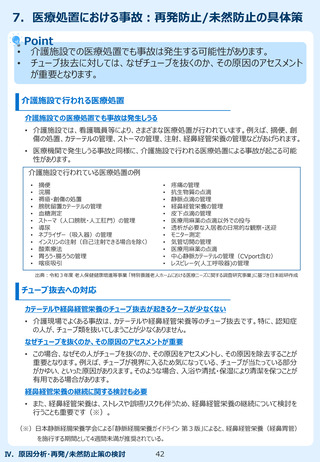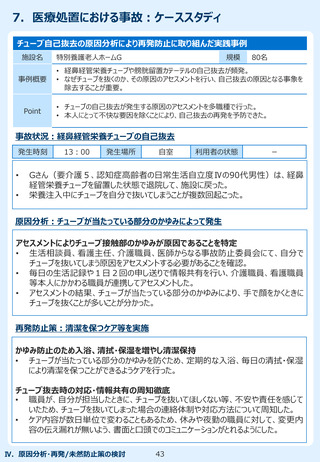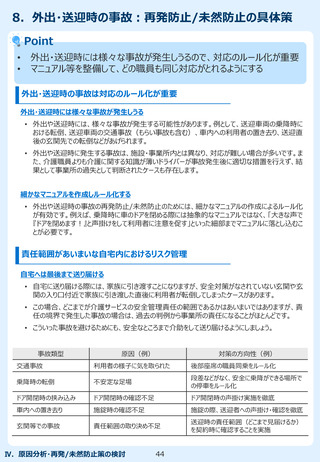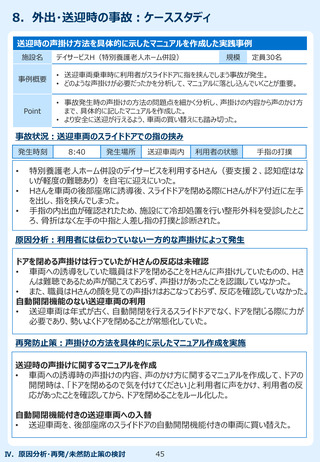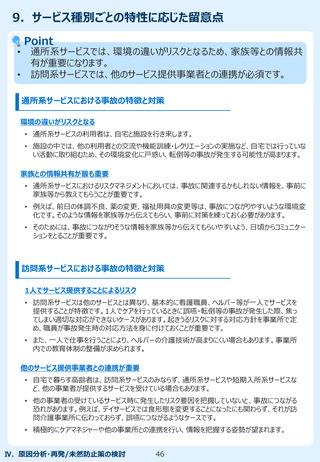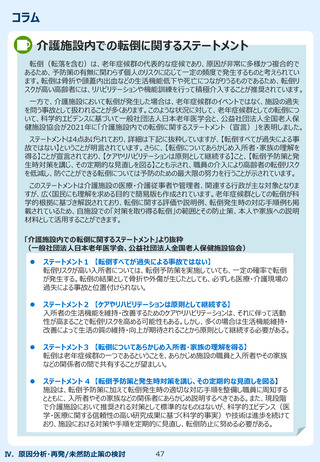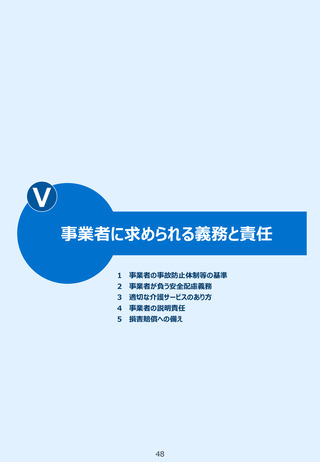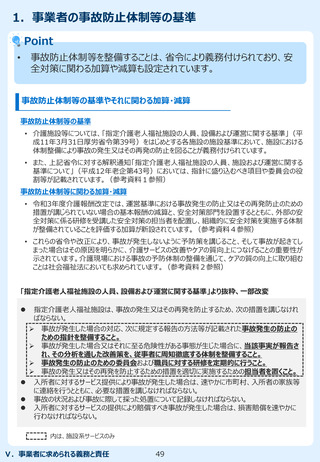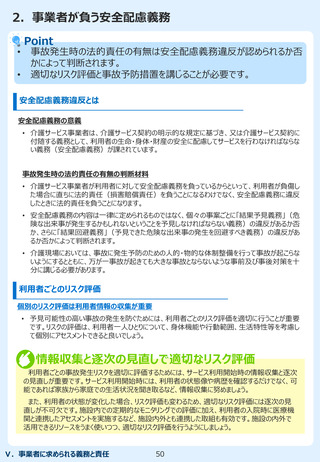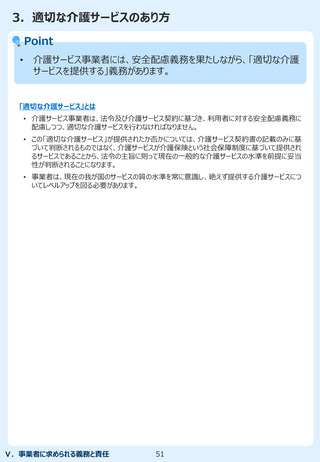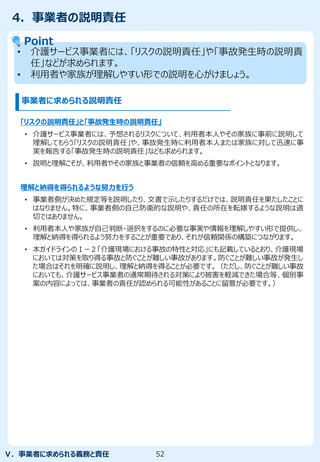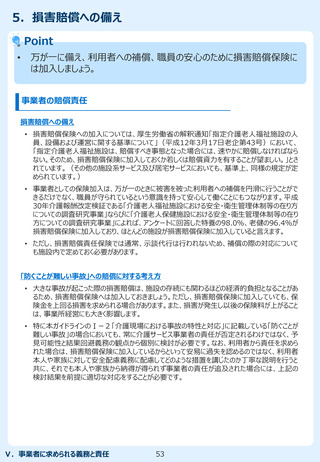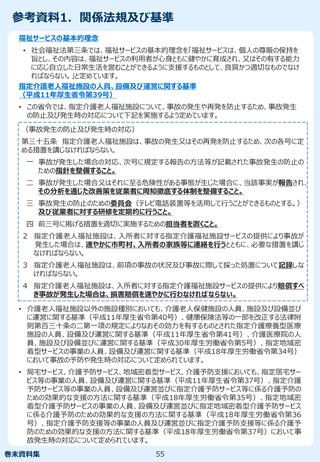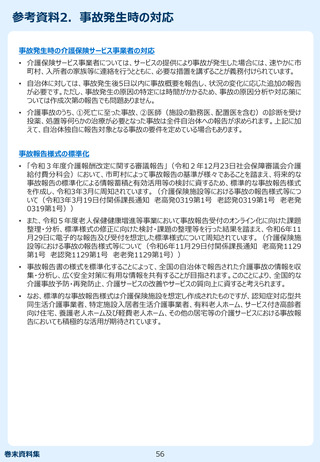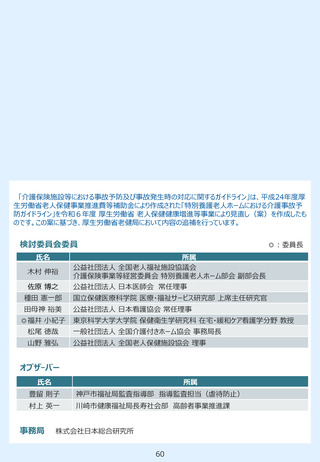よむ、つかう、まなぶ。
介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |
| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2.転落:再発防止/未然防止の具体策
Point
•
•
利用者個々のアセスメントに基づいて、最適なベッド周辺の環境を整備し
ましょう。
せん妄やBPSDの有無、排泄・睡眠状態にも注目しましょう。
ベッド周辺の環境整備は転落対策の基本
転落事故のうちベッドからの転落が多い
• 転落事故は身体状況や居室環境等、利用者個々のアセスメントが重要であり、特にベッドからの
転落が多いため、ベッド周りの環境整備が重要です。
• ベッドからの転落は、高低差があることから大きなけがにつながりやすい事故です。利用者の身体状
況やこれまで生活してきた環境を踏まえて、適切な位置にベッド柵、ナースコールを配置し、必要に
応じてベッドセンサー等の機器も活用しましょう。
リハビリテーション専門職と連携して原因分析・再発防止策を検討
• ベッドからの転落は夜間に発生することが多く、ほとんどの場合、利用者が転落した後に発見するこ
ととなります。見守りカメラを設置していない場合は、発生の場面を見ることができないため、事実確
認をすることが難しく、推測を基に原因分析を行うこととなります。
• 事業所内にリハビリテーション専門職がいる場合は、リハビリテーション専門職と連携して、転倒時の
利用者の身体の向きやベッド周囲の環境等を踏まえて原因分析を行い、再発防止策を検討する
ことが有効です。
発生原因はベッド周囲の環境だけとは限らない
せん妄やBPSDが原因の場合がある
• その方の普段の様子とは異なる行動により転落が発生する場合もあり、その原因がせん妄である場
合もあります。せん妄は何らかの原因で脳機能に異常が起こり、幻覚や錯乱を引き起こすものです。
• せん妄の原因は不安などの精神的なものから体調不良といった身体的なものがありますが、脱水や
便秘、薬も原因となり得ます。意外なものとしては入れ歯があり、総入れ歯の方が入れ歯を外して
寝ることで舌根沈下が起こり、低酸素状態に陥ってせん妄を引き起こす場合があります。
• 認知症の方の場合は、BPSDによる行動によってベッドから転落してしまう場合もあり、認知症ケア
が結果として転落の未然防止につながることもあります。
排泄ケアや生活リズムを整えることも未然防止策となりうる
• 排泄が自立している利用者の場合は、夜間に自身でトイレに行こうとすることそのものが転倒や転
落リスクを高めることとなります。また、オムツを利用している利用者が転落するケースもありますが、オ
ムツが汚れていることの不快感が原因であることが多いです。
• このような原因への対策としては、利用者個々の排泄パターンに応じて適切に排泄誘導し、必要に
応じて排泄誘導を増やす、オムツ交換の回数を増やすというのもベーシックな対策となります。
• 一方で、夜間に起きずにしっかりと睡眠をとってもらう、という対策もあり得ます。夜間に寝られていな
い利用者は、日中の昼寝が多い、活動量が足りておらず寝られていない傾向にありますので、日中
の活動を増やし、生活リズムを整えるという対策を取ることも一案です。
Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討
32
Point
•
•
利用者個々のアセスメントに基づいて、最適なベッド周辺の環境を整備し
ましょう。
せん妄やBPSDの有無、排泄・睡眠状態にも注目しましょう。
ベッド周辺の環境整備は転落対策の基本
転落事故のうちベッドからの転落が多い
• 転落事故は身体状況や居室環境等、利用者個々のアセスメントが重要であり、特にベッドからの
転落が多いため、ベッド周りの環境整備が重要です。
• ベッドからの転落は、高低差があることから大きなけがにつながりやすい事故です。利用者の身体状
況やこれまで生活してきた環境を踏まえて、適切な位置にベッド柵、ナースコールを配置し、必要に
応じてベッドセンサー等の機器も活用しましょう。
リハビリテーション専門職と連携して原因分析・再発防止策を検討
• ベッドからの転落は夜間に発生することが多く、ほとんどの場合、利用者が転落した後に発見するこ
ととなります。見守りカメラを設置していない場合は、発生の場面を見ることができないため、事実確
認をすることが難しく、推測を基に原因分析を行うこととなります。
• 事業所内にリハビリテーション専門職がいる場合は、リハビリテーション専門職と連携して、転倒時の
利用者の身体の向きやベッド周囲の環境等を踏まえて原因分析を行い、再発防止策を検討する
ことが有効です。
発生原因はベッド周囲の環境だけとは限らない
せん妄やBPSDが原因の場合がある
• その方の普段の様子とは異なる行動により転落が発生する場合もあり、その原因がせん妄である場
合もあります。せん妄は何らかの原因で脳機能に異常が起こり、幻覚や錯乱を引き起こすものです。
• せん妄の原因は不安などの精神的なものから体調不良といった身体的なものがありますが、脱水や
便秘、薬も原因となり得ます。意外なものとしては入れ歯があり、総入れ歯の方が入れ歯を外して
寝ることで舌根沈下が起こり、低酸素状態に陥ってせん妄を引き起こす場合があります。
• 認知症の方の場合は、BPSDによる行動によってベッドから転落してしまう場合もあり、認知症ケア
が結果として転落の未然防止につながることもあります。
排泄ケアや生活リズムを整えることも未然防止策となりうる
• 排泄が自立している利用者の場合は、夜間に自身でトイレに行こうとすることそのものが転倒や転
落リスクを高めることとなります。また、オムツを利用している利用者が転落するケースもありますが、オ
ムツが汚れていることの不快感が原因であることが多いです。
• このような原因への対策としては、利用者個々の排泄パターンに応じて適切に排泄誘導し、必要に
応じて排泄誘導を増やす、オムツ交換の回数を増やすというのもベーシックな対策となります。
• 一方で、夜間に起きずにしっかりと睡眠をとってもらう、という対策もあり得ます。夜間に寝られていな
い利用者は、日中の昼寝が多い、活動量が足りておらず寝られていない傾向にありますので、日中
の活動を増やし、生活リズムを整えるという対策を取ることも一案です。
Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討
32