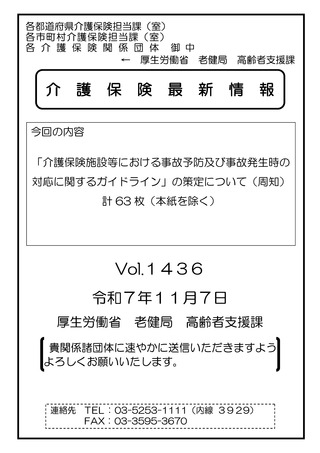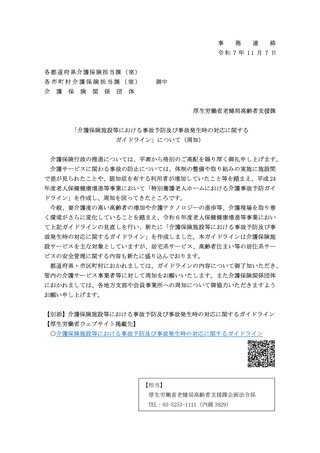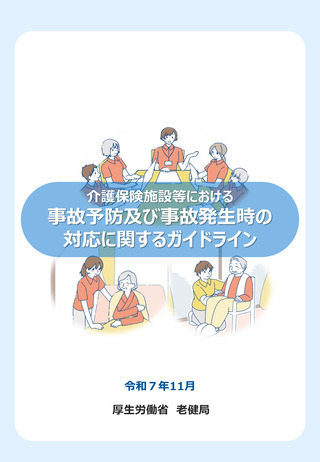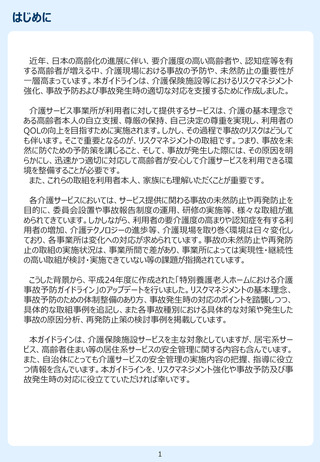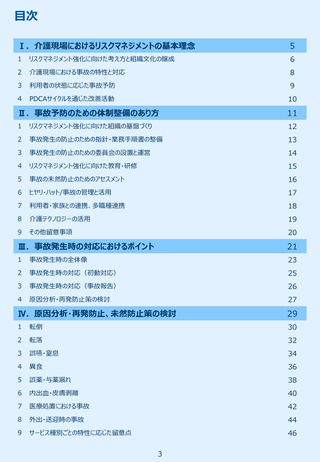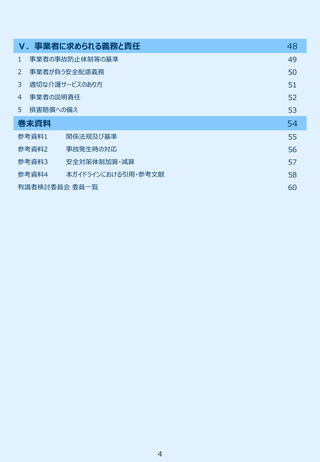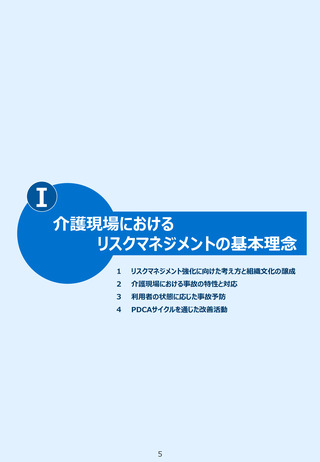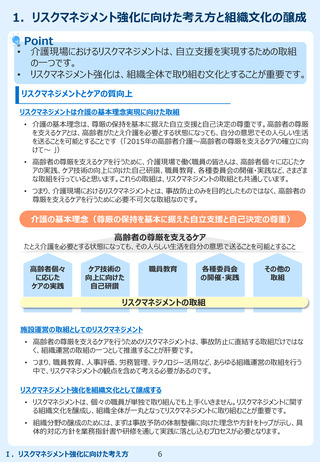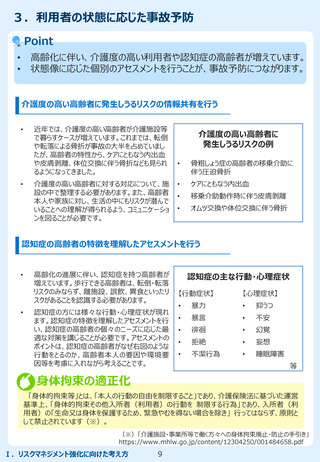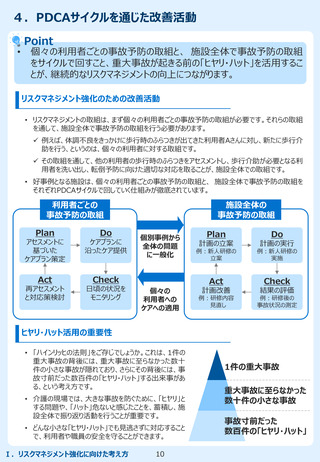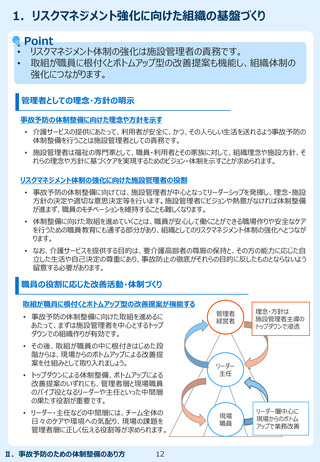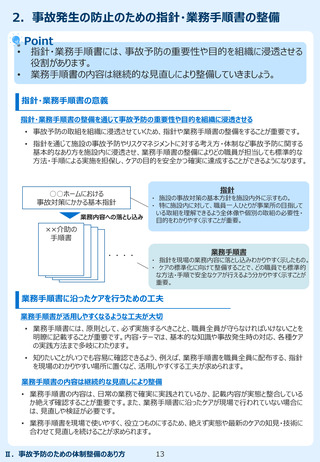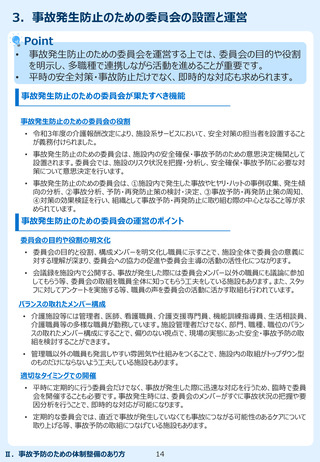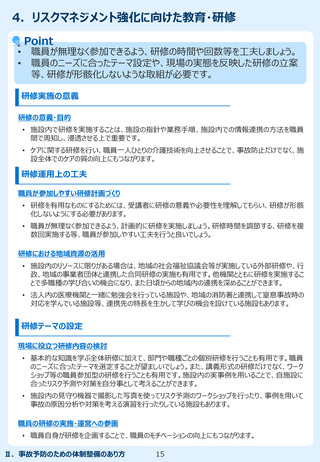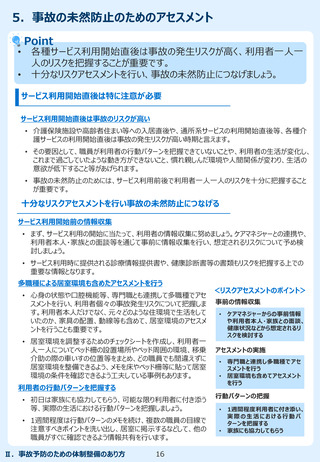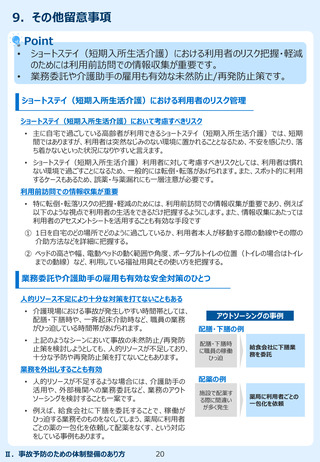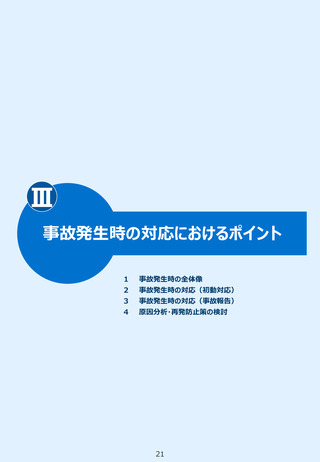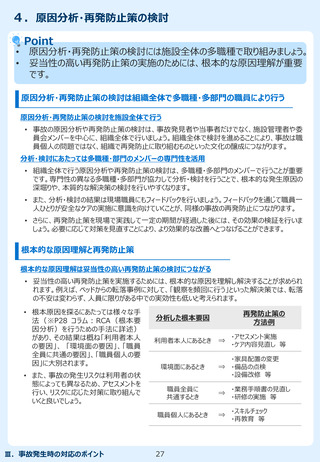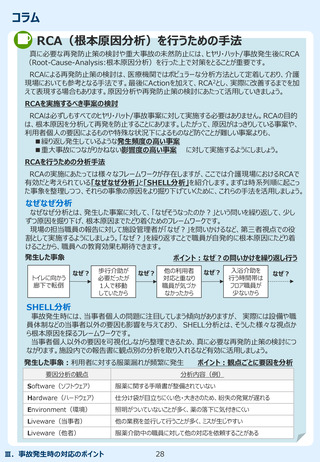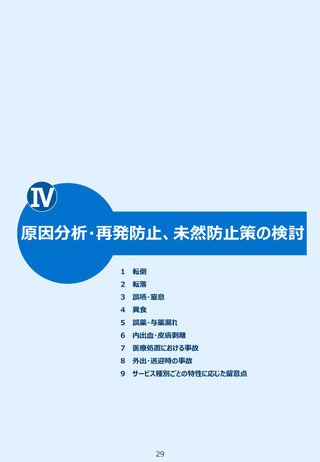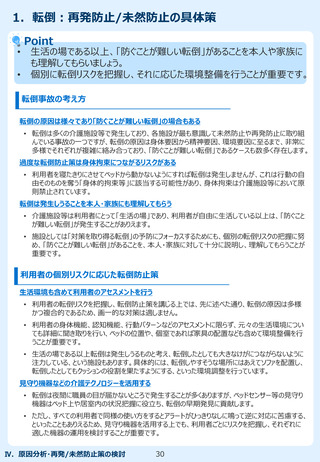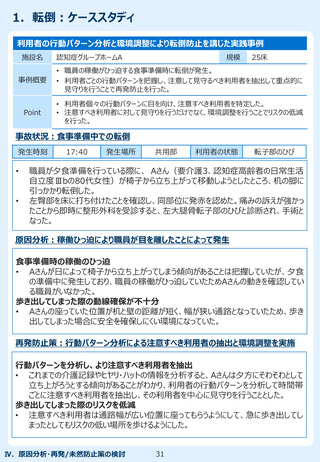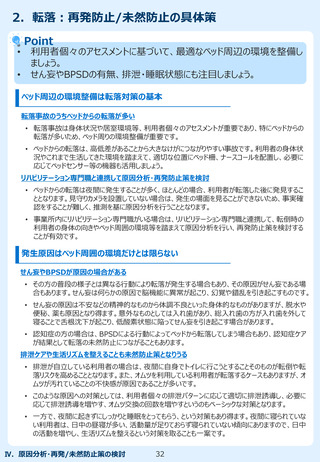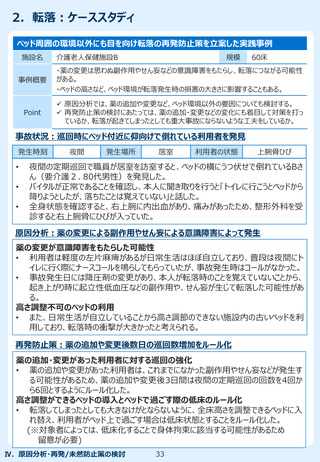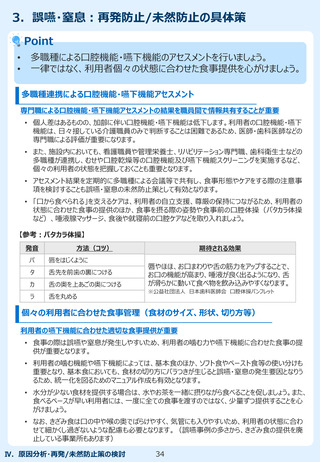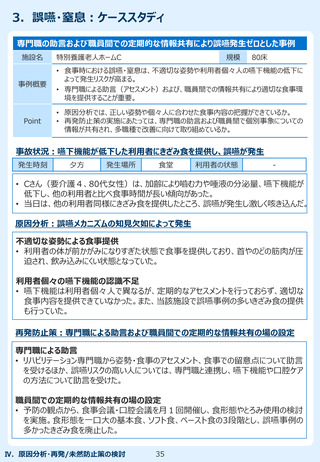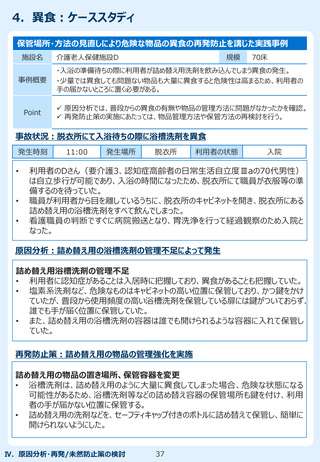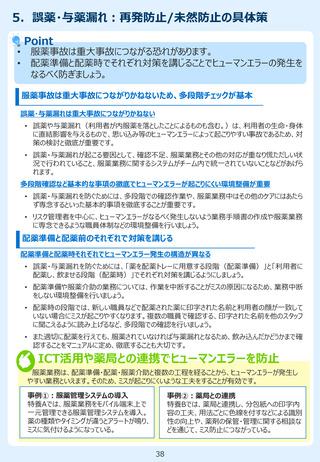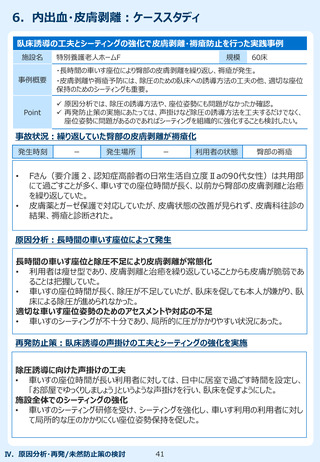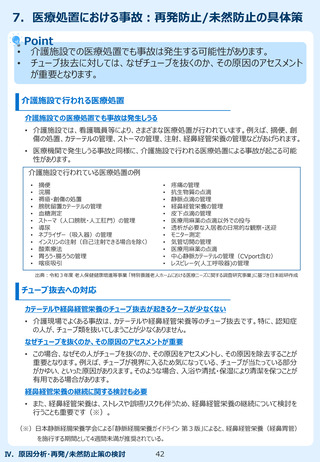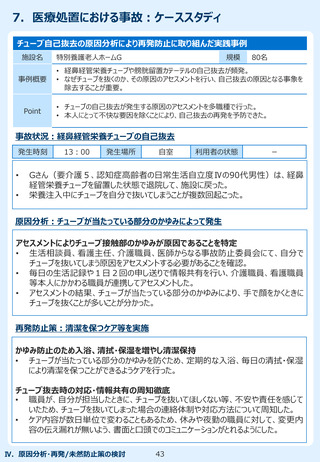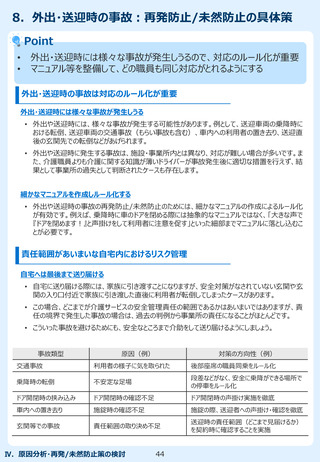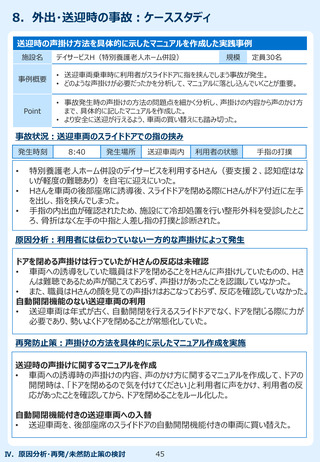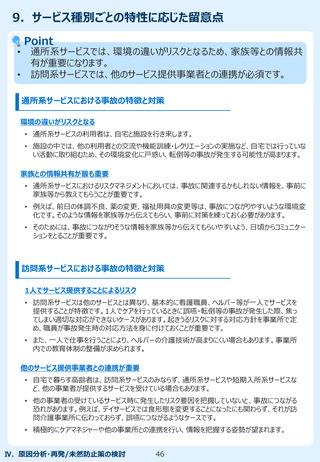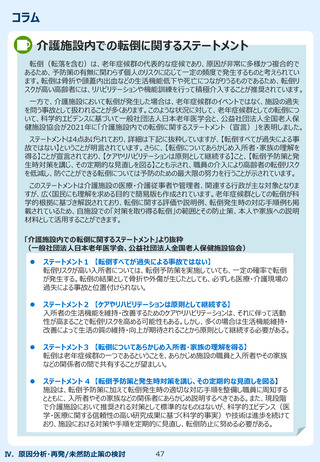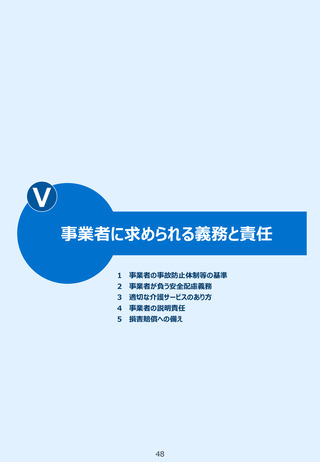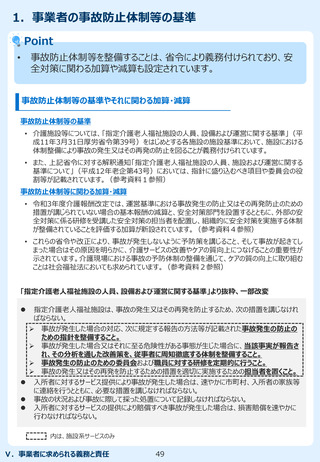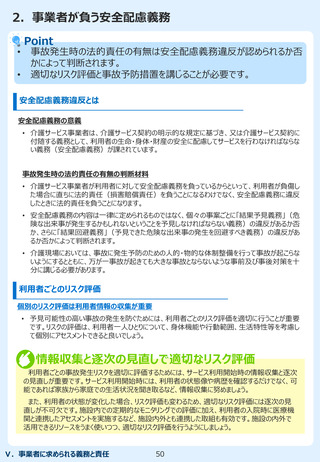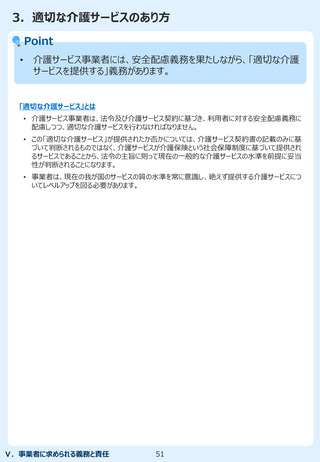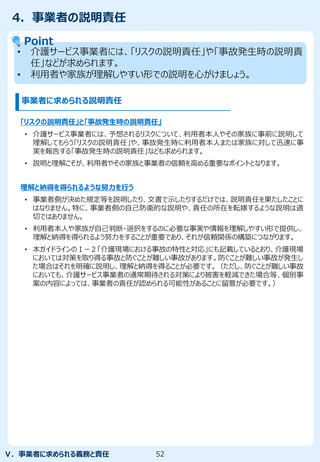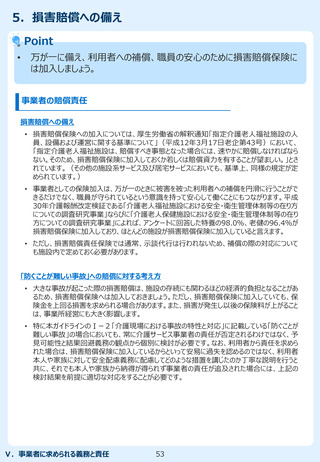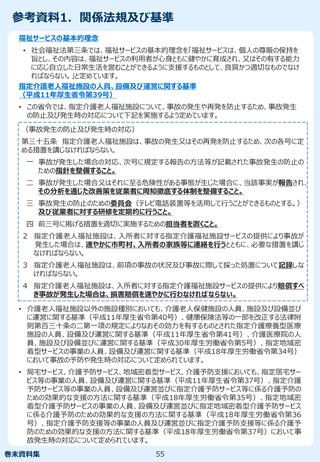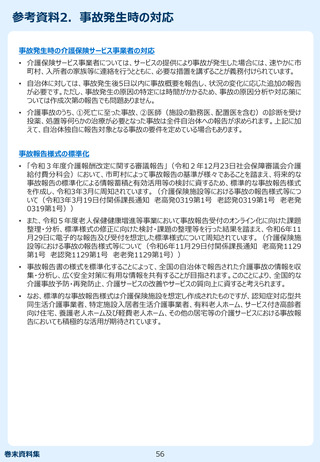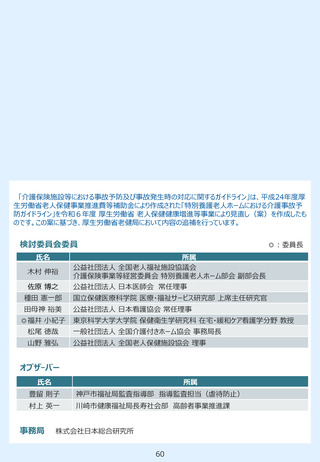よむ、つかう、まなぶ。
介護保険最新情報Vol.1436(「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて(周知)」 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf |
| 出典情報 | 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関する ガイドライン」について(周知)(11/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1.転倒:再発防止/未然防止の具体策
Point
•
•
生活の場である以上、「防ぐことが難しい転倒」があることを本人や家族に
も理解してもらいましょう。
個別に転倒リスクを把握し、それに応じた環境整備を行うことが重要です。
転倒事故の考え方
転倒の原因は様々であり「防ぐことが難しい転倒」の場合もある
• 転倒は多くの介護施設等で発生しており、各施設が最も意識して未然防止や再発防止に取り組
んでいる事故の一つですが、転倒の原因は身体要因から精神要因、環境要因に至るまで、非常に
多様でそれぞれが複雑に絡み合っており、「防ぐことが難しい転倒」であるケースも数多く存在します。
過度な転倒防止策は身体拘束につながるリスクがある
• 利用者を寝たきりにさせてベッドから動かないようにすれば転倒は発生しませんが、これは行動の自
由そのものを奪う「身体的拘束等」に該当する可能性があり、身体拘束は介護施設等において原
則禁止されています。
転倒は発生しうることを本人・家族にも理解してもらう
• 介護施設等は利用者にとって「生活の場」であり、利用者が自由に生活している以上は、「防ぐこと
が難しい転倒」が発生することがありえます。
• 施設としては「対策を取り得る転倒」の予防にフォーカスするためにも、個別の転倒リスクの把握に努
め、「防ぐことが難しい転倒」があることを、本人・家族に対して十分に説明し、理解してもらうことが
重要です。
利用者の個別リスクに応じた転倒防止策
生活環境も含めて利用者のアセスメントを行う
• 利用者の転倒リスクを把握し、転倒防止策を講じる上では、先に述べた通り、転倒の原因は多様
かつ複合的であるため、画一的な対策は適しません。
• 利用者の身体機能、認知機能、行動パターンなどのアセスメントに限らず、元々の生活環境につい
ても詳細に聞き取りを行い、ベッドの位置や、個室であれば家具の配置なども含めて環境整備を行
うことが重要です。
• 生活の場である以上転倒は発生しうるものと考え、転倒したとしても大きなけがにつながらないように
注力している、という施設もあります。具体的には、転倒しやすそうな場所にはあえてソファを配置し、
転倒したとしてもクッションの役割を果たすようにする、といった環境調整を行っています。
見守り機器などの介護テクノロジーを活用する
• 転倒は夜間に職員の目が届かないところで発生することが多くありますが、ベッドセンサー等の見守り
機器はベッド上や居室内の状況把握に役立ち、転倒の早期発見に貢献します。
• ただし、すべての利用者で同様の使い方をするとアラートがひっきりなしに鳴って逆に対応に苦慮する、
といったこともありえるため、見守り機器を活用する上でも、利用者ごとにリスクを把握し、それぞれに
適した機器の運用を検討することが重要です。
Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討
30
Point
•
•
生活の場である以上、「防ぐことが難しい転倒」があることを本人や家族に
も理解してもらいましょう。
個別に転倒リスクを把握し、それに応じた環境整備を行うことが重要です。
転倒事故の考え方
転倒の原因は様々であり「防ぐことが難しい転倒」の場合もある
• 転倒は多くの介護施設等で発生しており、各施設が最も意識して未然防止や再発防止に取り組
んでいる事故の一つですが、転倒の原因は身体要因から精神要因、環境要因に至るまで、非常に
多様でそれぞれが複雑に絡み合っており、「防ぐことが難しい転倒」であるケースも数多く存在します。
過度な転倒防止策は身体拘束につながるリスクがある
• 利用者を寝たきりにさせてベッドから動かないようにすれば転倒は発生しませんが、これは行動の自
由そのものを奪う「身体的拘束等」に該当する可能性があり、身体拘束は介護施設等において原
則禁止されています。
転倒は発生しうることを本人・家族にも理解してもらう
• 介護施設等は利用者にとって「生活の場」であり、利用者が自由に生活している以上は、「防ぐこと
が難しい転倒」が発生することがありえます。
• 施設としては「対策を取り得る転倒」の予防にフォーカスするためにも、個別の転倒リスクの把握に努
め、「防ぐことが難しい転倒」があることを、本人・家族に対して十分に説明し、理解してもらうことが
重要です。
利用者の個別リスクに応じた転倒防止策
生活環境も含めて利用者のアセスメントを行う
• 利用者の転倒リスクを把握し、転倒防止策を講じる上では、先に述べた通り、転倒の原因は多様
かつ複合的であるため、画一的な対策は適しません。
• 利用者の身体機能、認知機能、行動パターンなどのアセスメントに限らず、元々の生活環境につい
ても詳細に聞き取りを行い、ベッドの位置や、個室であれば家具の配置なども含めて環境整備を行
うことが重要です。
• 生活の場である以上転倒は発生しうるものと考え、転倒したとしても大きなけがにつながらないように
注力している、という施設もあります。具体的には、転倒しやすそうな場所にはあえてソファを配置し、
転倒したとしてもクッションの役割を果たすようにする、といった環境調整を行っています。
見守り機器などの介護テクノロジーを活用する
• 転倒は夜間に職員の目が届かないところで発生することが多くありますが、ベッドセンサー等の見守り
機器はベッド上や居室内の状況把握に役立ち、転倒の早期発見に貢献します。
• ただし、すべての利用者で同様の使い方をするとアラートがひっきりなしに鳴って逆に対応に苦慮する、
といったこともありえるため、見守り機器を活用する上でも、利用者ごとにリスクを把握し、それぞれに
適した機器の運用を検討することが重要です。
Ⅳ.原因分析・再発/未然防止策の検討
30