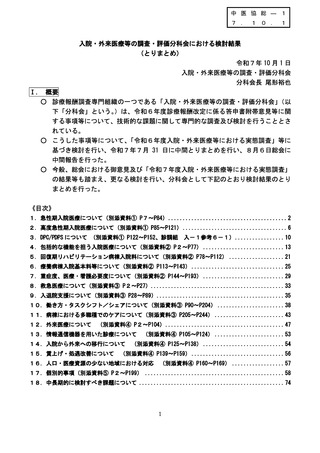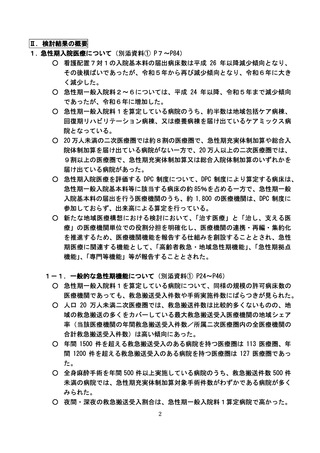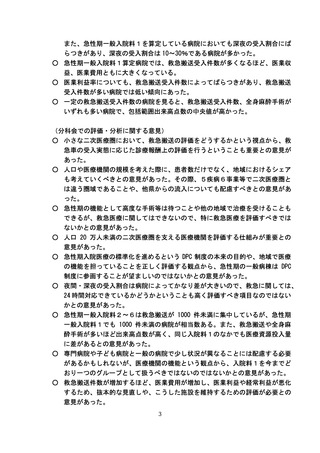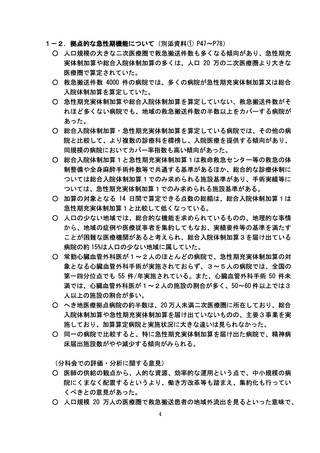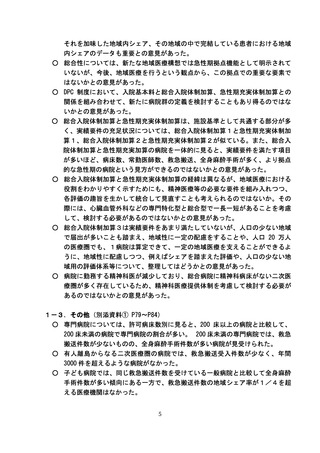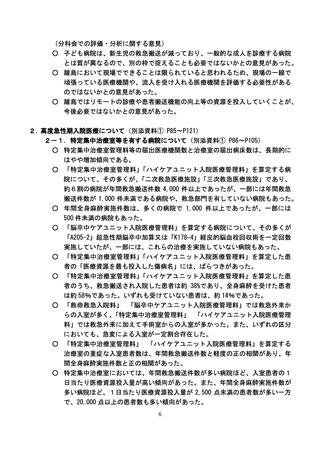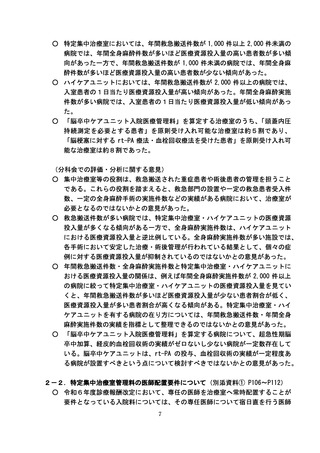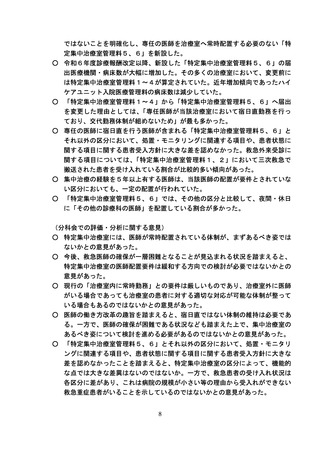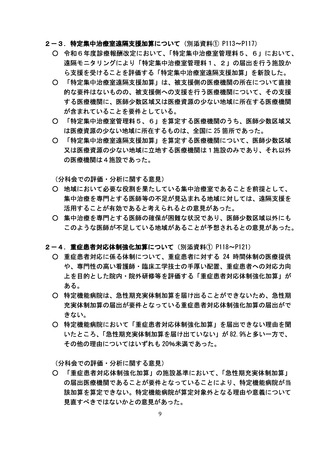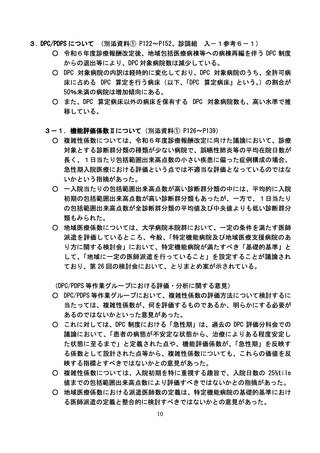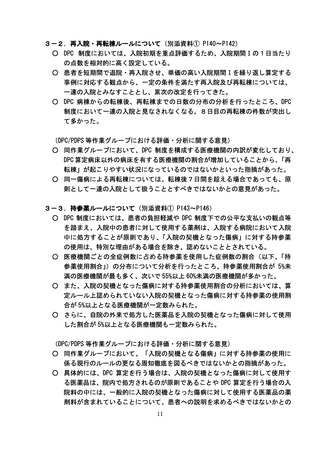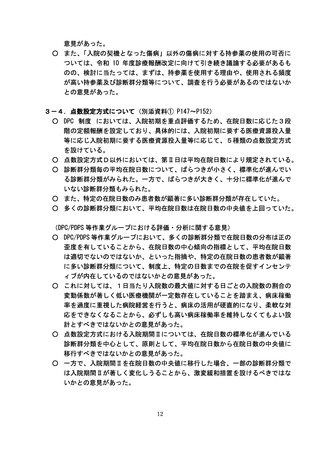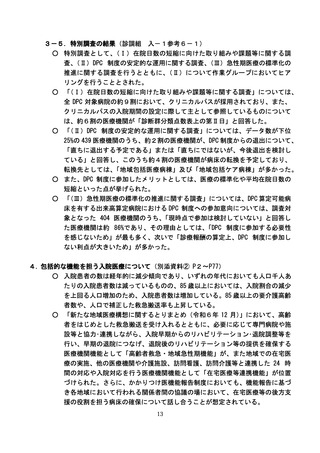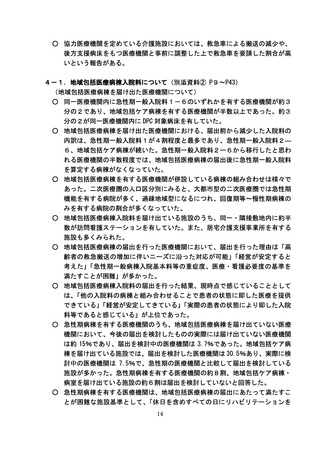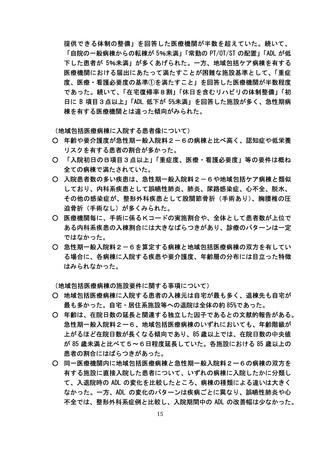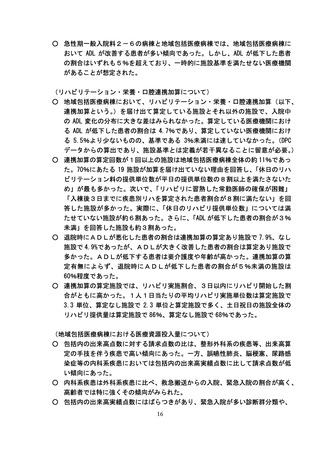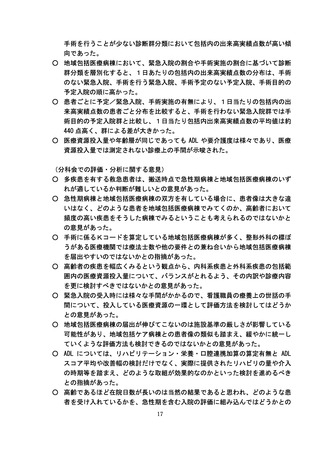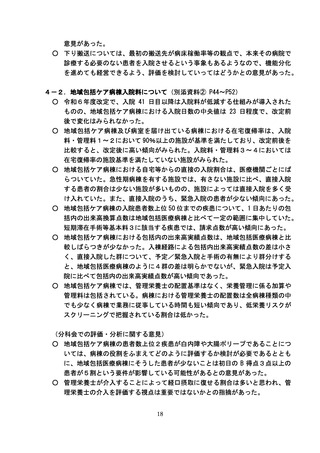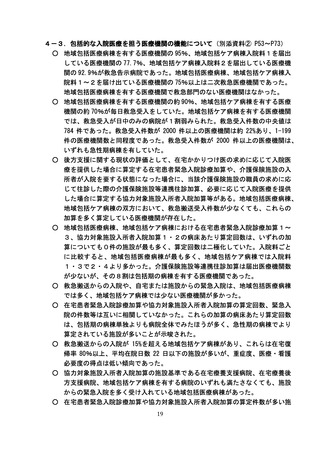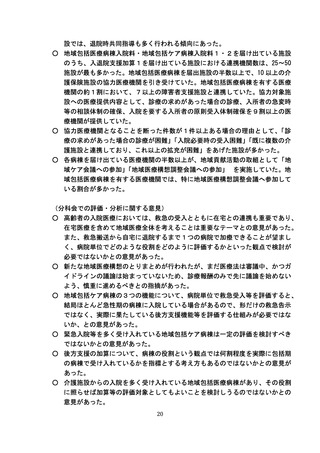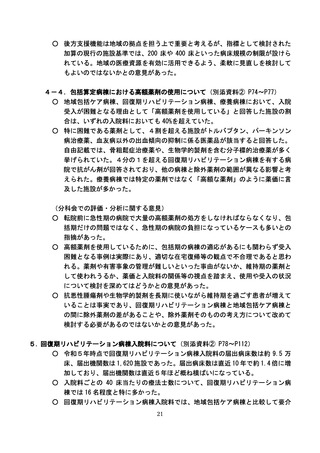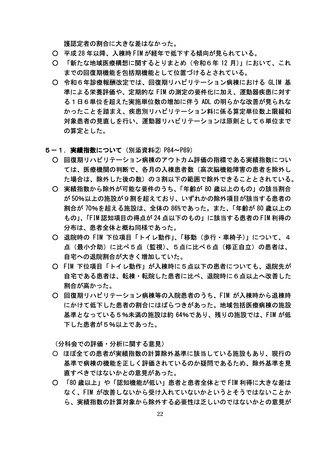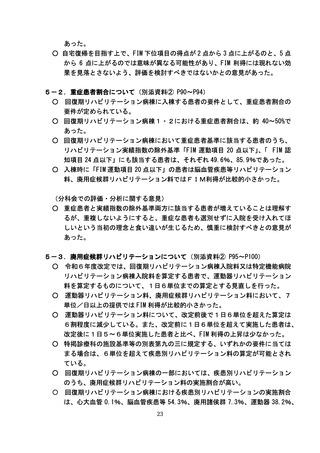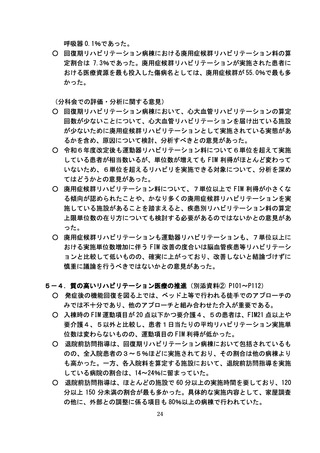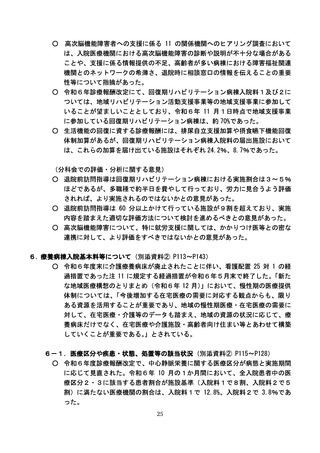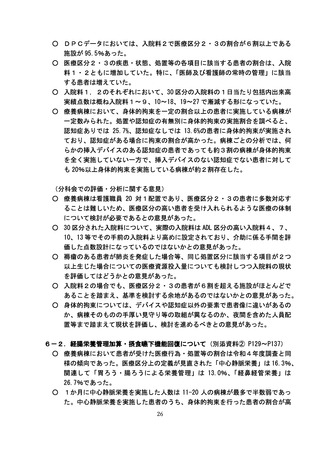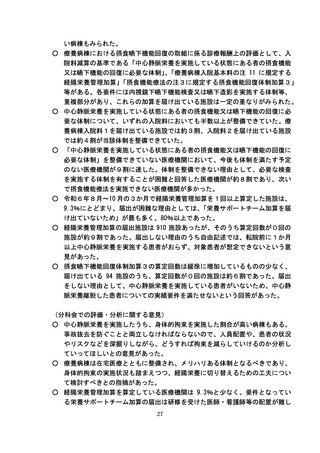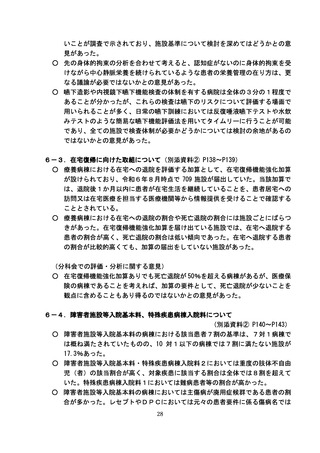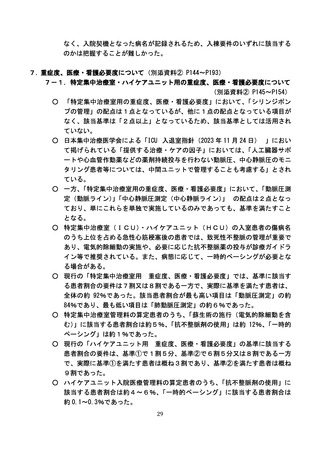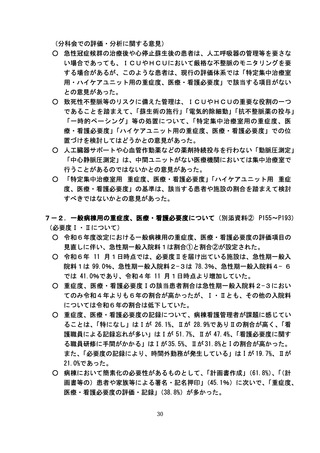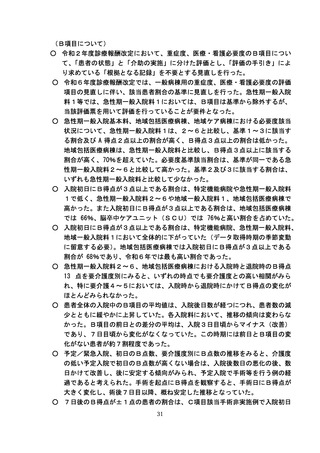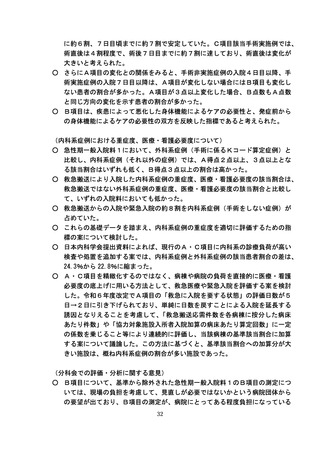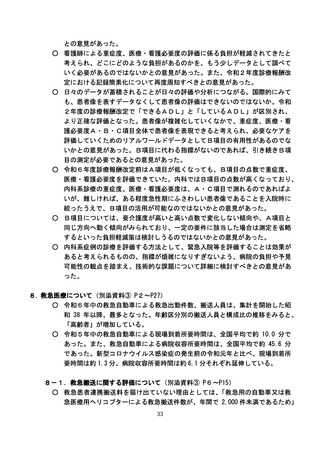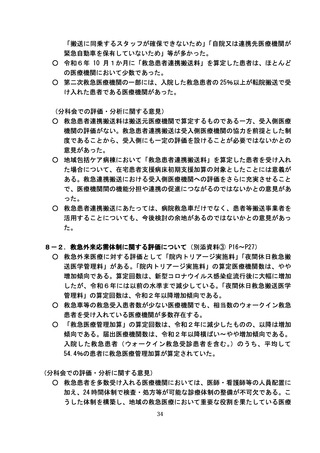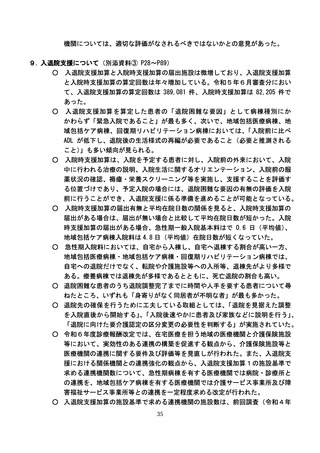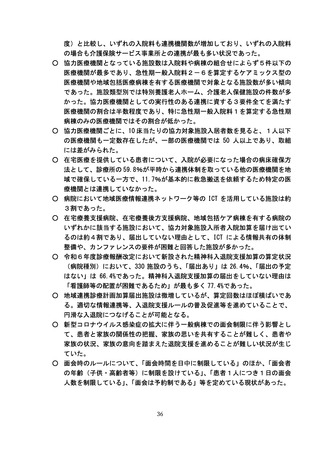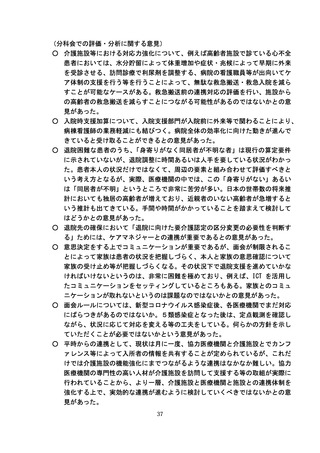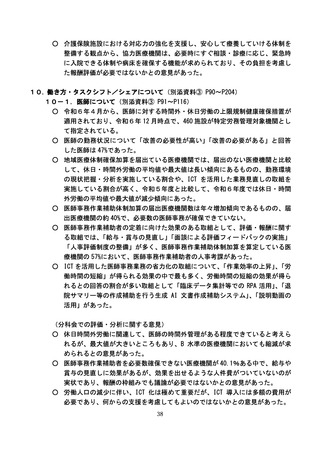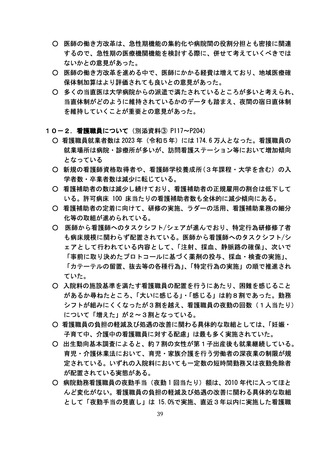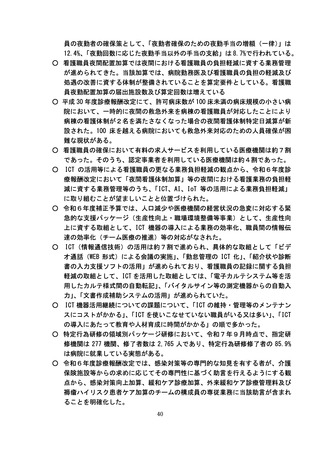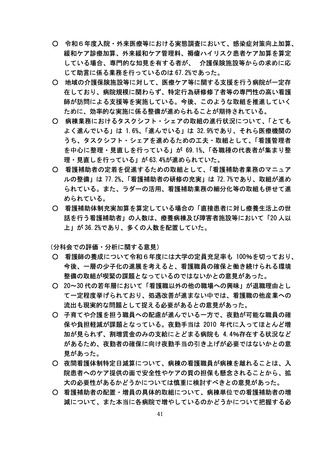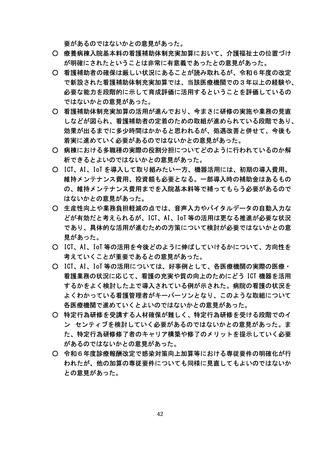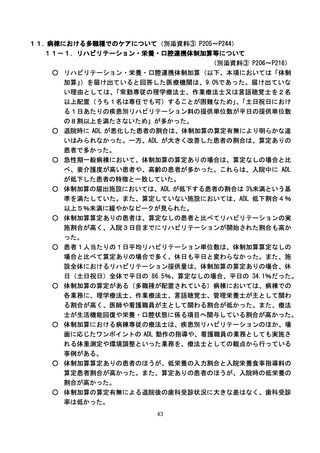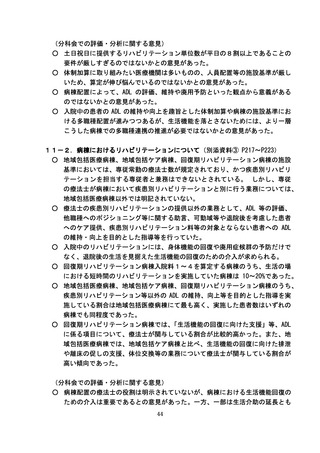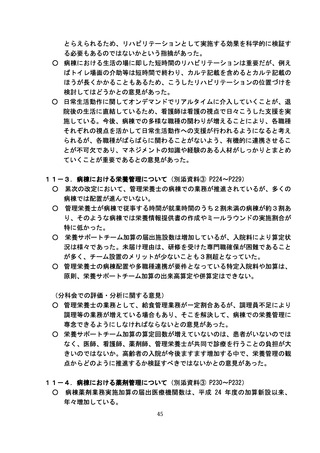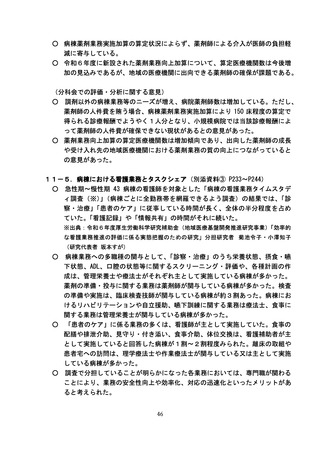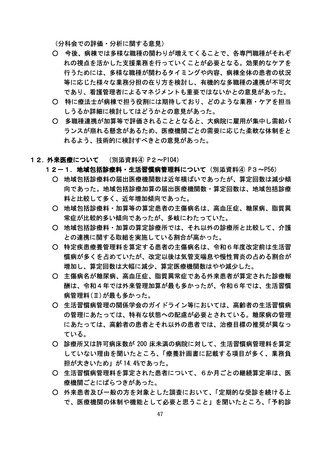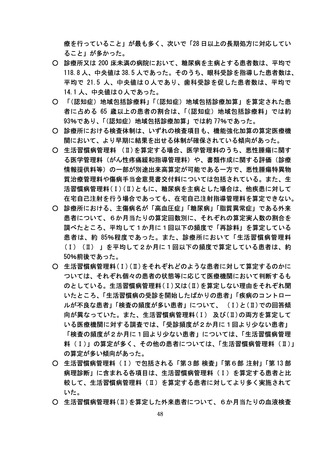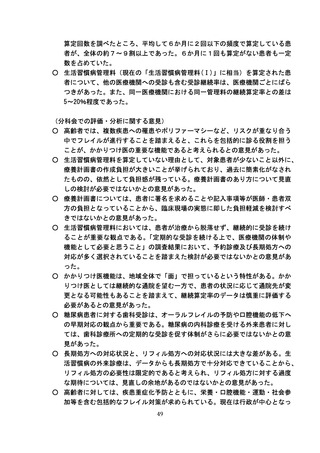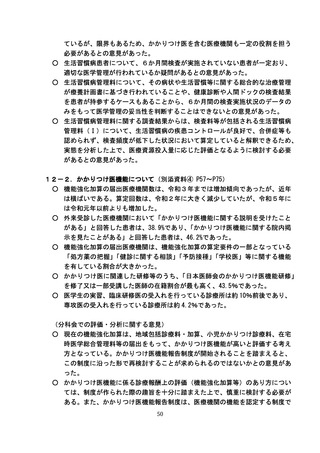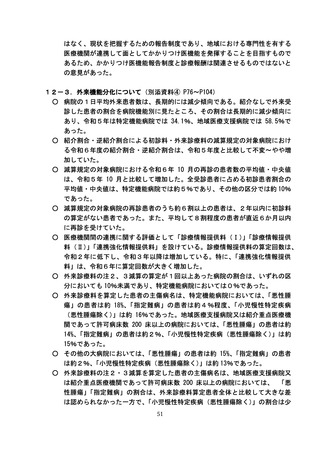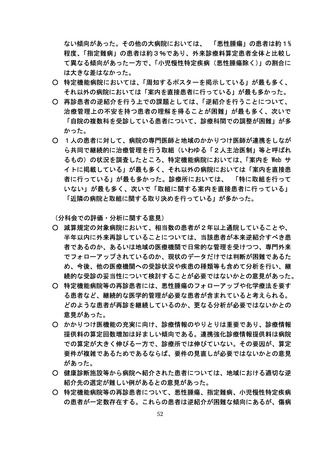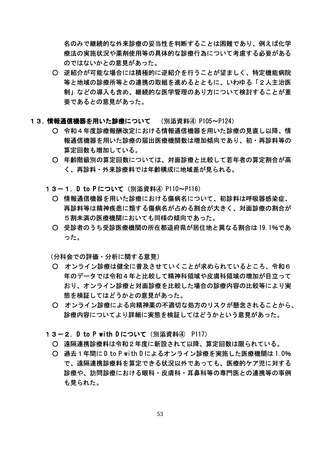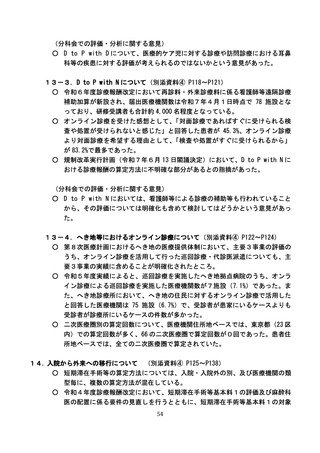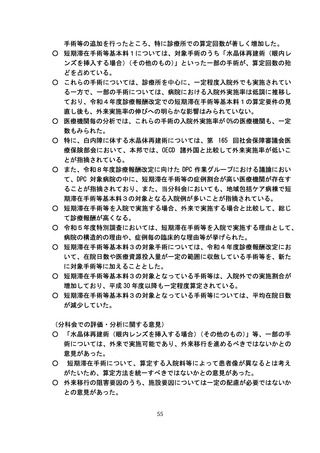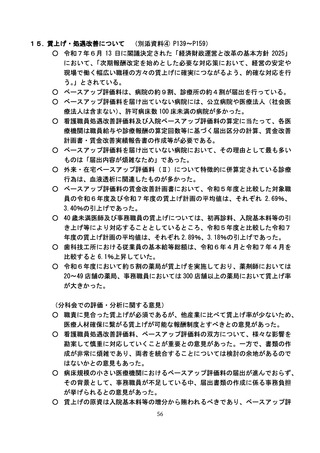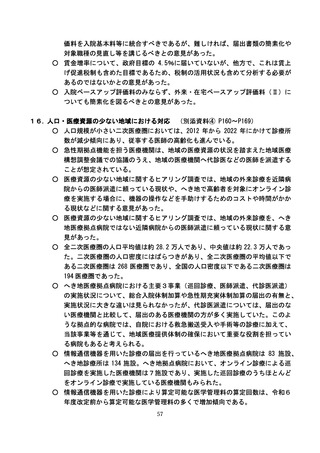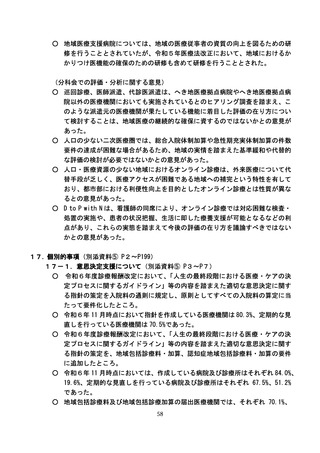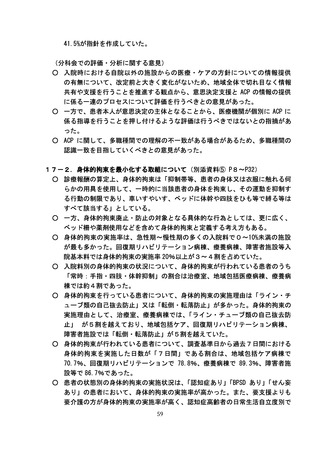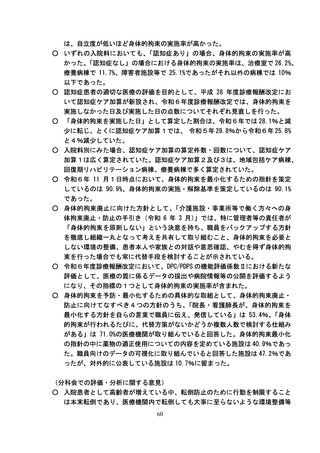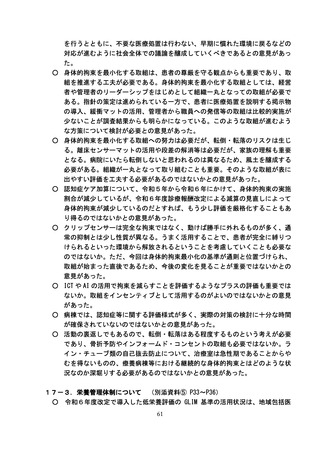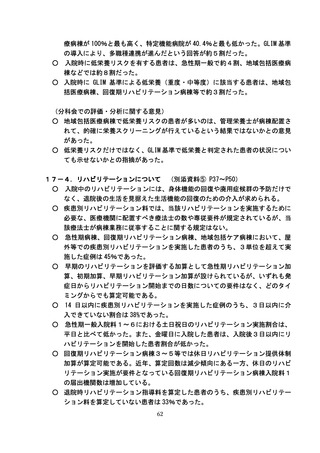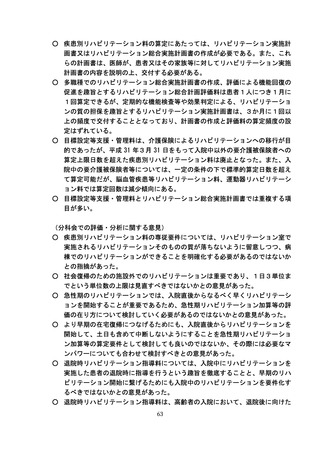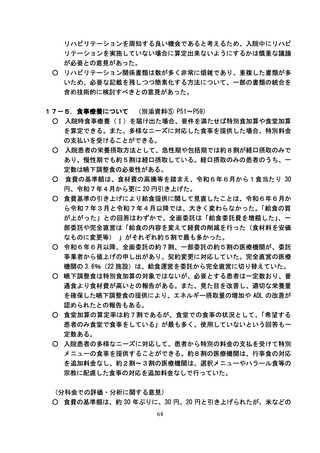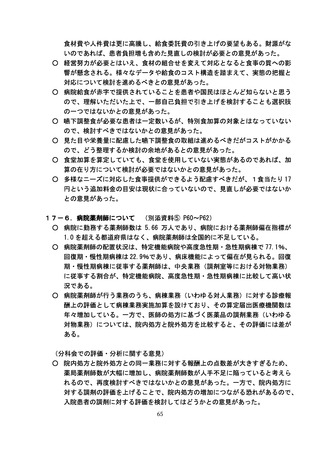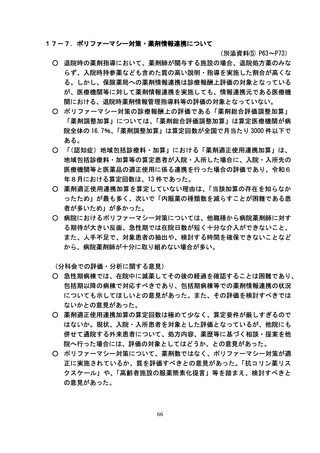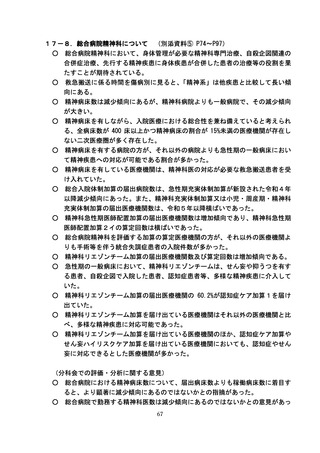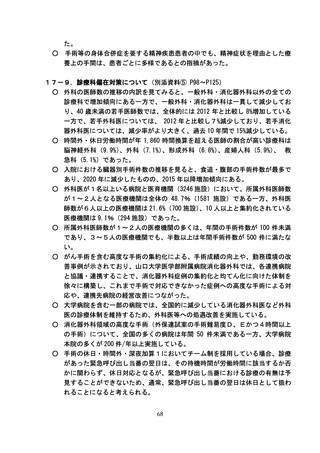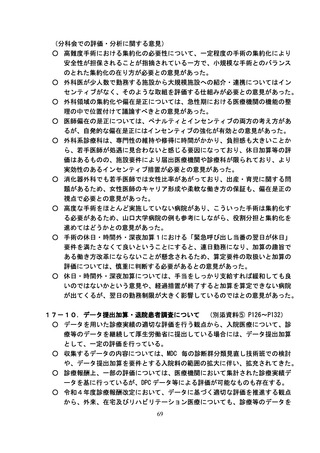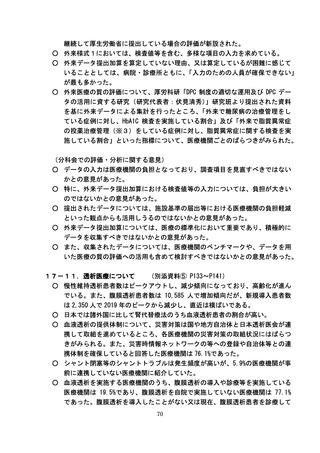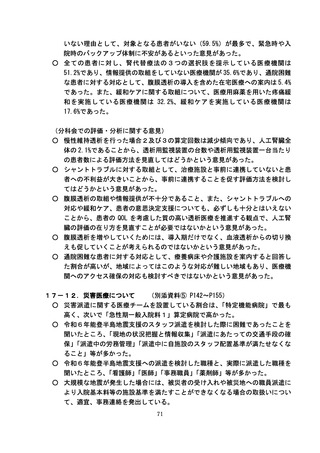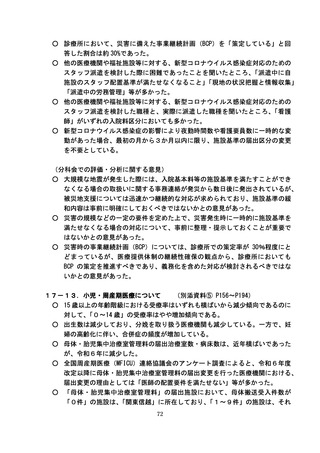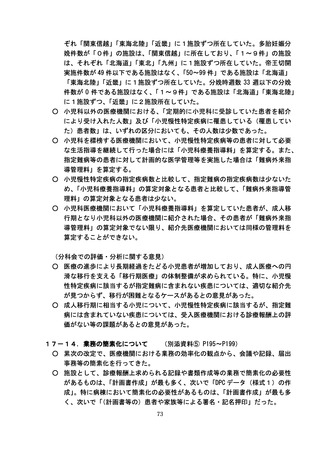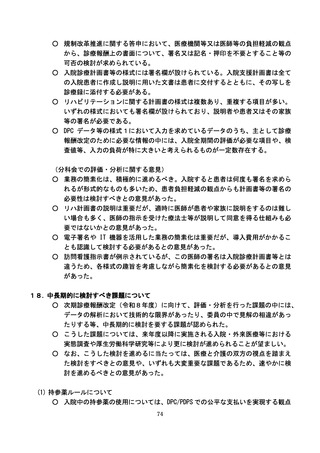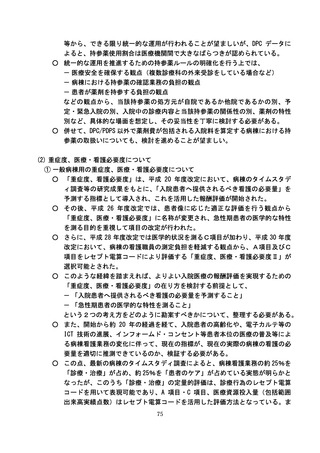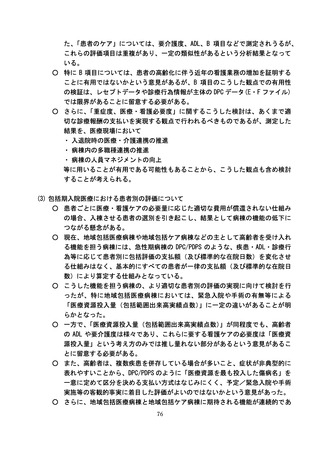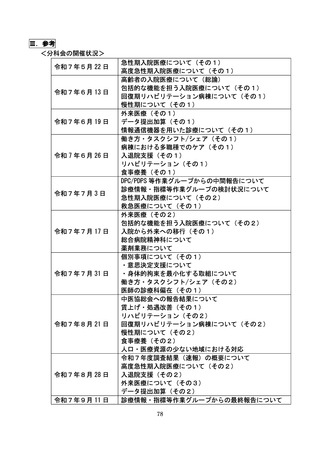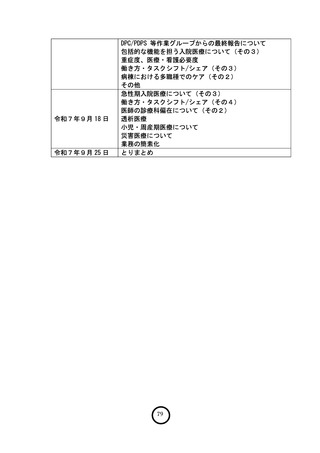よむ、つかう、まなぶ。
総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会における検討結果 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ない傾向があった。その他の大病院においては、 「悪性腫瘍」の患者は約1%
程度、「指定難病」の患者は約3%であり、外来診療料算定患者全体と比較し
て異なる傾向があった一方で、「小児慢性特定疾病(悪性腫瘍除く)」の割合に
は大きな差はなかった。
○ 特定機能病院においては、「周知するポスターを掲示している」が最も多く、
それ以外の病院においては「案内を直接患者に行っている」が最も多かった。
○ 再診患者の逆紹介を行う上での課題としては、「逆紹介を行うことについて、
治療管理上の不安を持つ患者の理解を得ることが困難」が最も多く、次いで
「自院の複数科を受診している患者について、診療科間での調整が困難」が多
かった。
○ 1人の患者に対して、病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携をしなが
ら共同で継続的に治療管理を行う取組(いわゆる「2人主治医制」等と呼ばれ
るもの)の状況を調査したところ、特定機能病院においては、「案内を Web サ
イトに掲載している」が最も多く、それ以外の病院においては「案内を直接患
者に行っている」が最も多かった。診療所においては、 「特に取組を行って
いない」が最も多く、次いで「取組に関する案内を直接患者に行っている」
「近隣の病院と取組に関する取り決めを行っている」が多かった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 減算規定の対象病院において、相当数の患者が2年以上通院していることや、
半年以内に外来再診していることについては、当該患者が本来逆紹介すべき患
者であるのか、あるいは地域の医療機関で日常的な管理を受けつつ、専門外来
でフォローアップされているのか、現状のデータだけでは判断が困難であるた
め、今後、他の医療機関への受診状況や疾患の種類等も含めて分析を行い、継
続的な受診の妥当性について検討することが必要ではないかとの意見があった。
○ 特定機能病院等の再診患者には、悪性腫瘍のフォローアップや化学療法を要す
る患者など、継続的な医学的管理が必要な患者が含まれていると考えられる。
どのような患者が再診を継続しているのか、更なる分析が必要ではないかとの
意見があった。
○ かかりつけ医機能の充実に向け、診療情報のやりとりは重要であり、診療情報
提供料の算定回数増加は好ましい傾向である。連携強化診療情報提供料は病院
での算定が大きく伸びる一方で、診療所では伸びていない。その要因が、算定
要件が複雑であるためであるならば、要件の見直しが必要ではないかとの意見
があった。
○ 健康診断施設等から病院へ紹介された患者については、地域における適切な逆
紹介先の選定が難しい例があるとの意見があった。
○ 特定機能病院等の再診患者について、悪性腫瘍、指定難病、小児慢性特定疾病
の患者が一定数存在する。これらの患者は逆紹介が困難な傾向にあるが、傷病
52
程度、「指定難病」の患者は約3%であり、外来診療料算定患者全体と比較し
て異なる傾向があった一方で、「小児慢性特定疾病(悪性腫瘍除く)」の割合に
は大きな差はなかった。
○ 特定機能病院においては、「周知するポスターを掲示している」が最も多く、
それ以外の病院においては「案内を直接患者に行っている」が最も多かった。
○ 再診患者の逆紹介を行う上での課題としては、「逆紹介を行うことについて、
治療管理上の不安を持つ患者の理解を得ることが困難」が最も多く、次いで
「自院の複数科を受診している患者について、診療科間での調整が困難」が多
かった。
○ 1人の患者に対して、病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携をしなが
ら共同で継続的に治療管理を行う取組(いわゆる「2人主治医制」等と呼ばれ
るもの)の状況を調査したところ、特定機能病院においては、「案内を Web サ
イトに掲載している」が最も多く、それ以外の病院においては「案内を直接患
者に行っている」が最も多かった。診療所においては、 「特に取組を行って
いない」が最も多く、次いで「取組に関する案内を直接患者に行っている」
「近隣の病院と取組に関する取り決めを行っている」が多かった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 減算規定の対象病院において、相当数の患者が2年以上通院していることや、
半年以内に外来再診していることについては、当該患者が本来逆紹介すべき患
者であるのか、あるいは地域の医療機関で日常的な管理を受けつつ、専門外来
でフォローアップされているのか、現状のデータだけでは判断が困難であるた
め、今後、他の医療機関への受診状況や疾患の種類等も含めて分析を行い、継
続的な受診の妥当性について検討することが必要ではないかとの意見があった。
○ 特定機能病院等の再診患者には、悪性腫瘍のフォローアップや化学療法を要す
る患者など、継続的な医学的管理が必要な患者が含まれていると考えられる。
どのような患者が再診を継続しているのか、更なる分析が必要ではないかとの
意見があった。
○ かかりつけ医機能の充実に向け、診療情報のやりとりは重要であり、診療情報
提供料の算定回数増加は好ましい傾向である。連携強化診療情報提供料は病院
での算定が大きく伸びる一方で、診療所では伸びていない。その要因が、算定
要件が複雑であるためであるならば、要件の見直しが必要ではないかとの意見
があった。
○ 健康診断施設等から病院へ紹介された患者については、地域における適切な逆
紹介先の選定が難しい例があるとの意見があった。
○ 特定機能病院等の再診患者について、悪性腫瘍、指定難病、小児慢性特定疾病
の患者が一定数存在する。これらの患者は逆紹介が困難な傾向にあるが、傷病
52