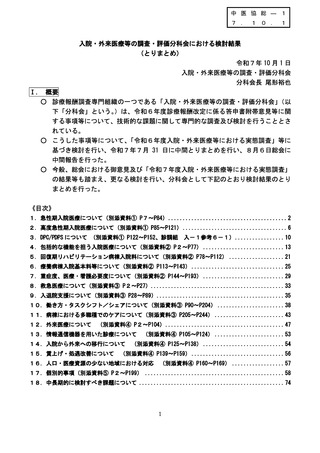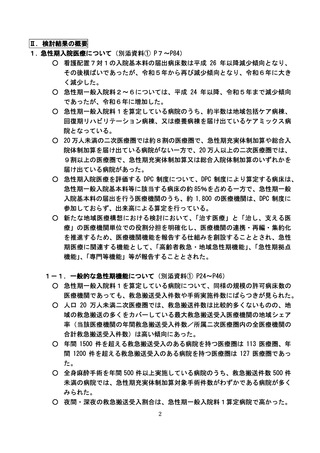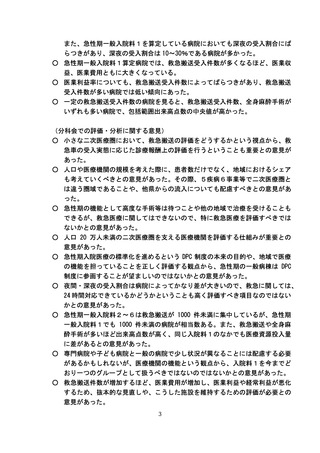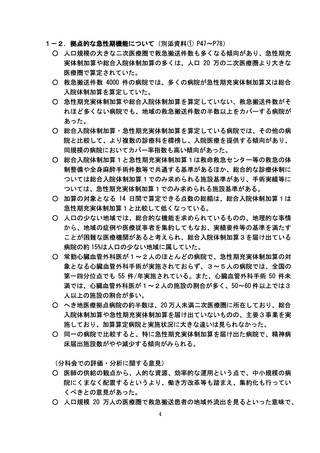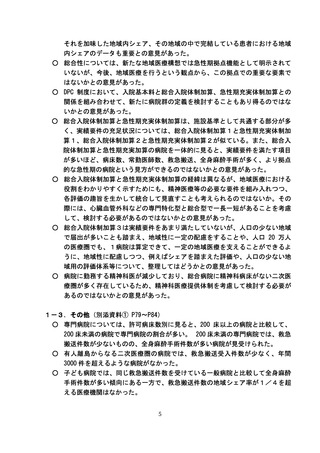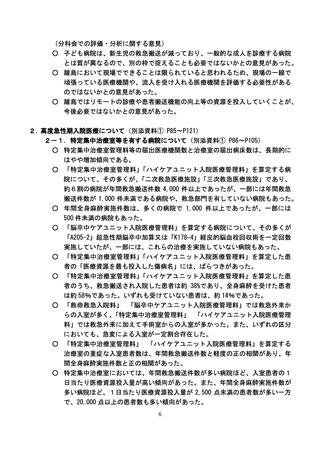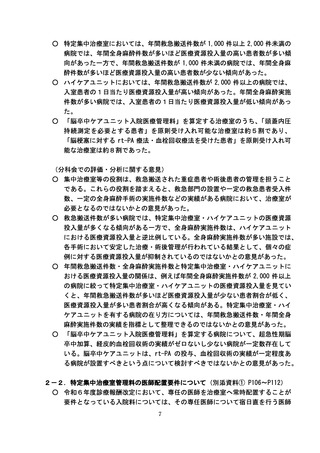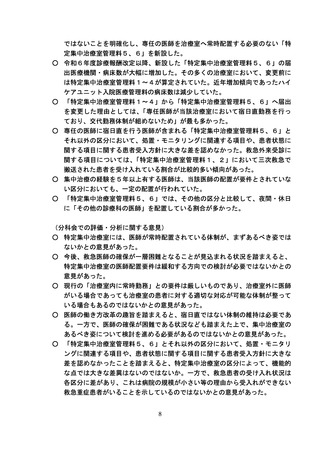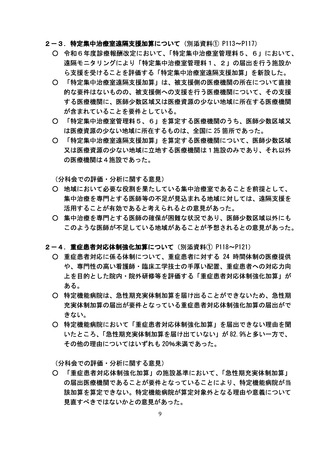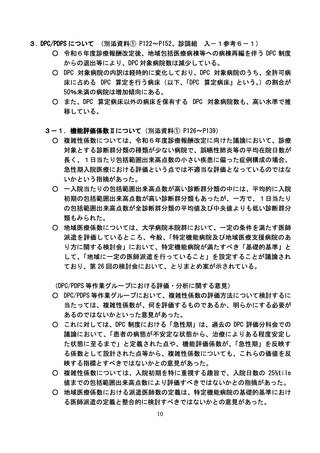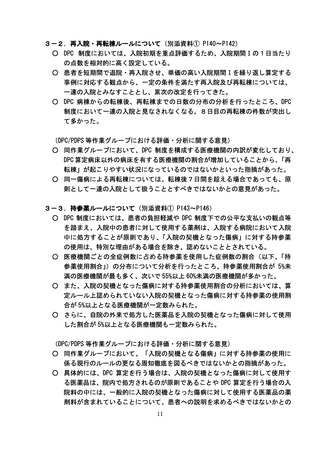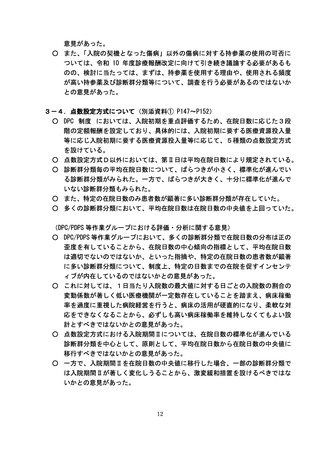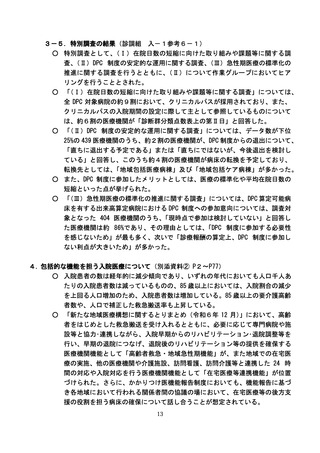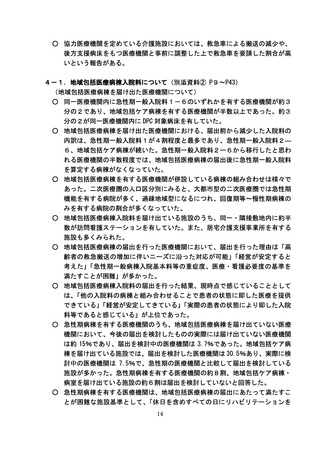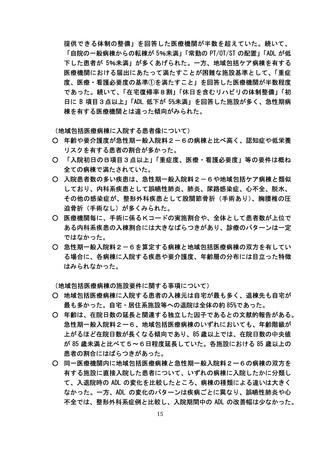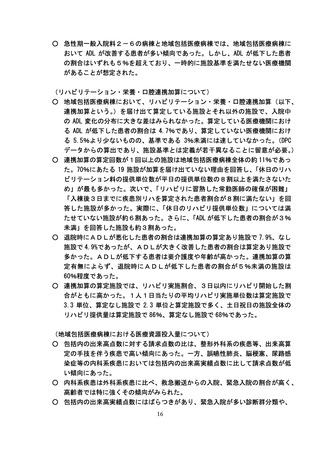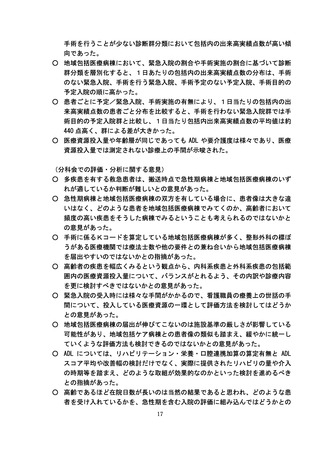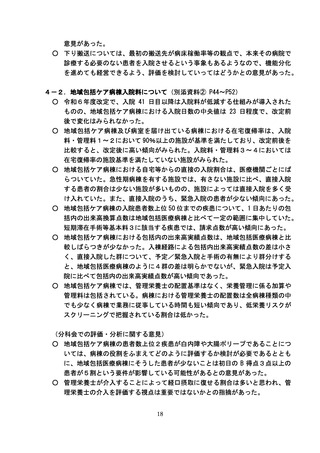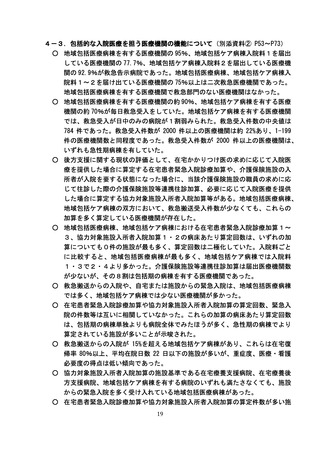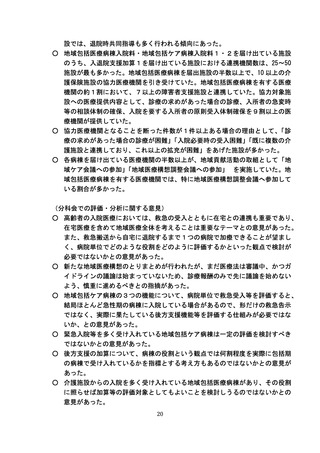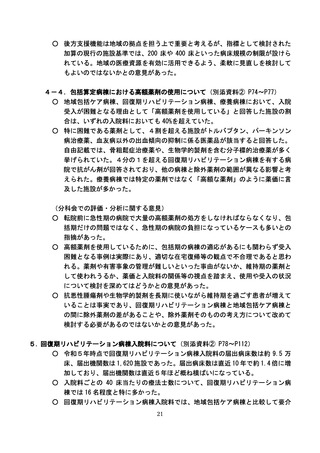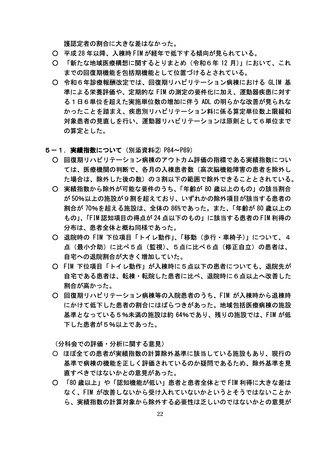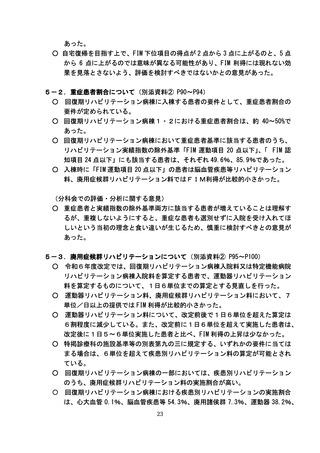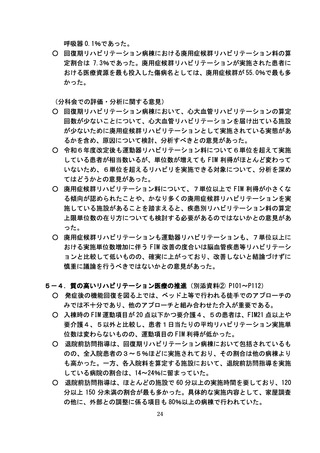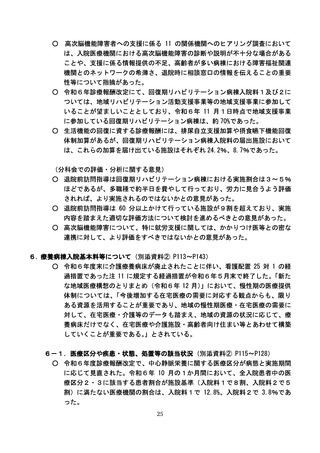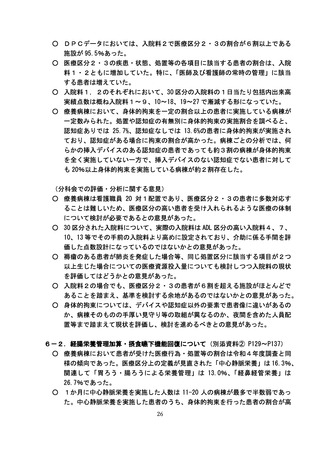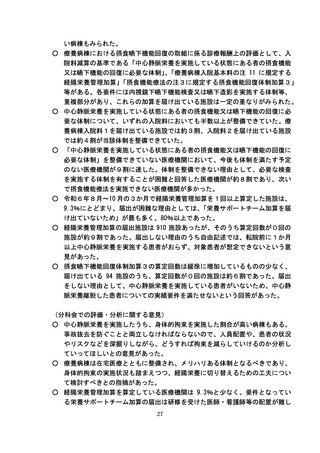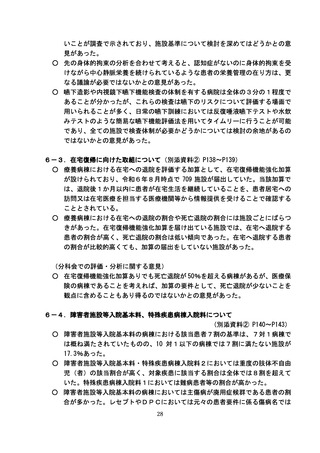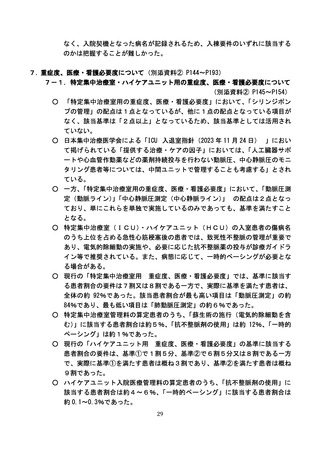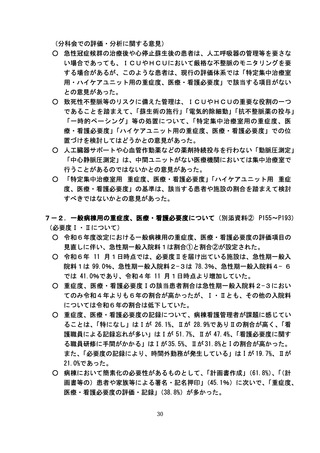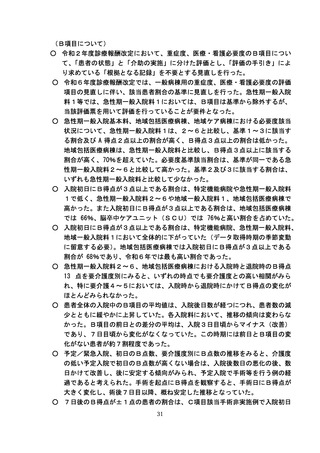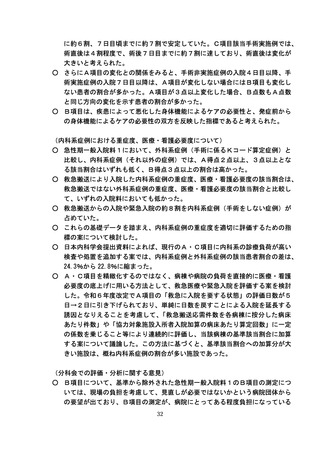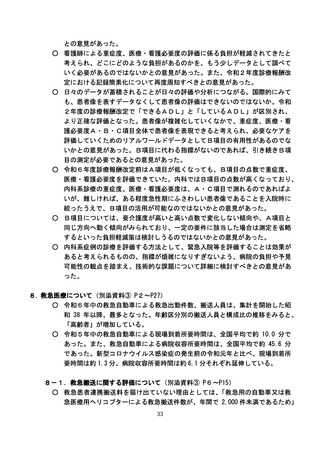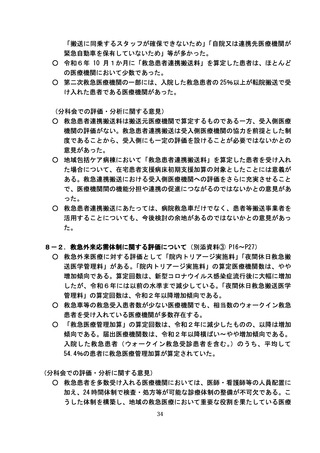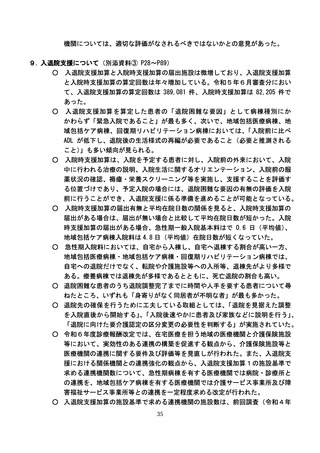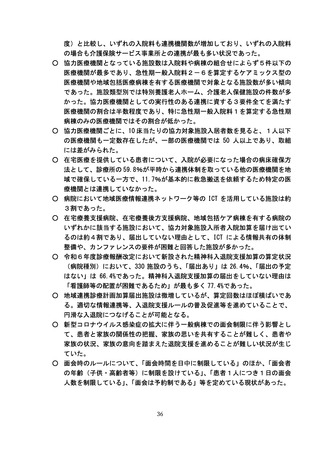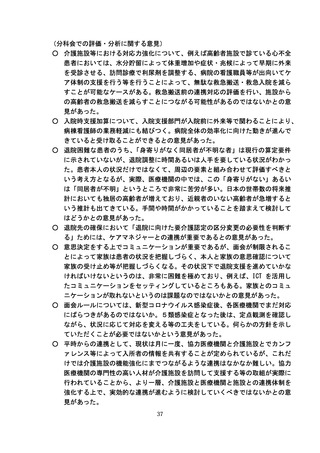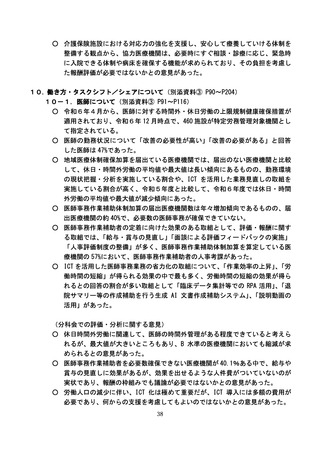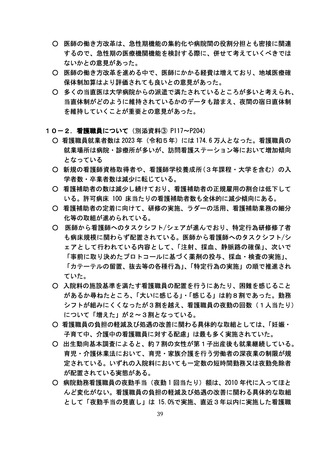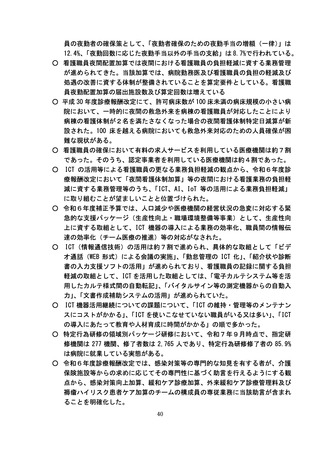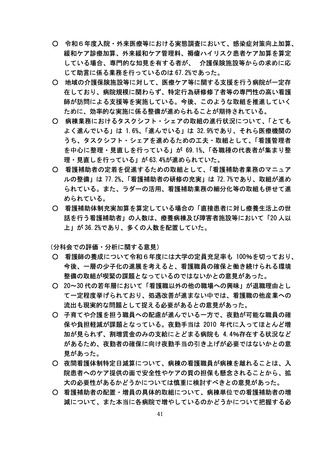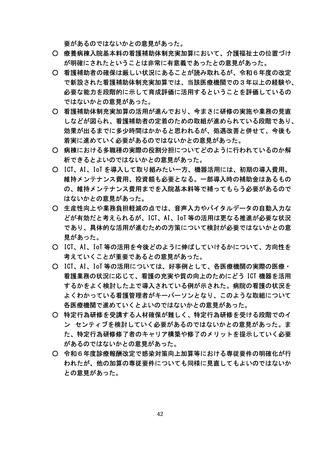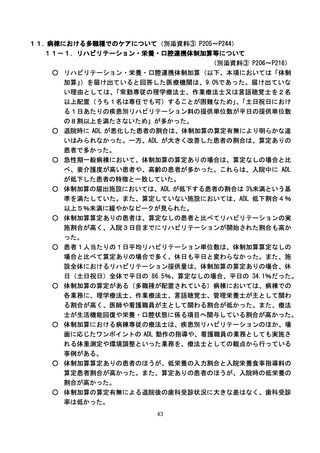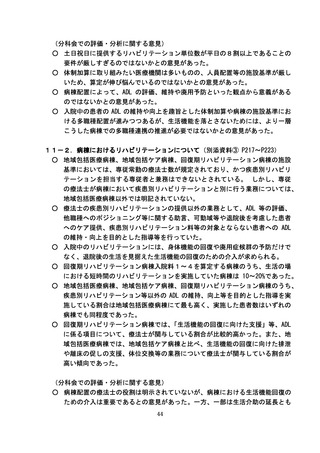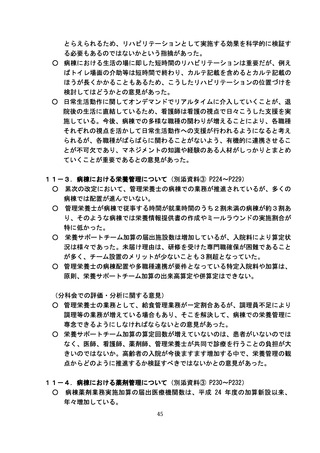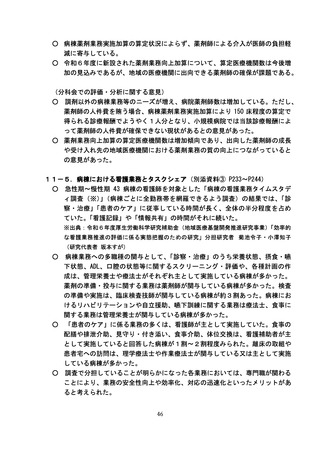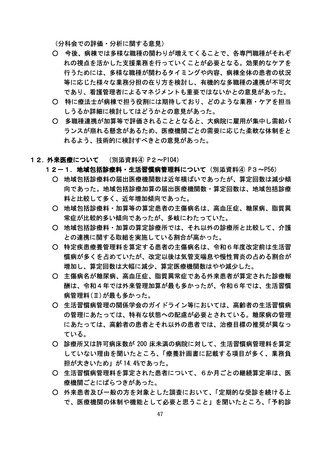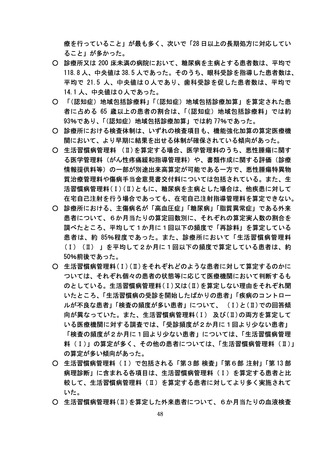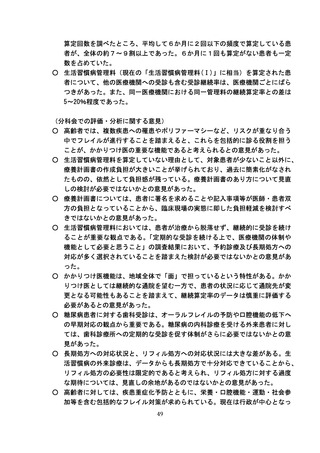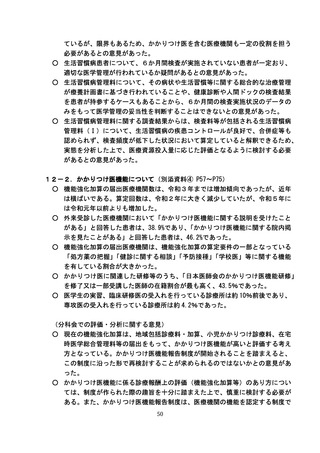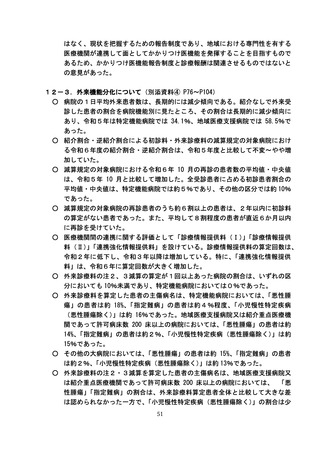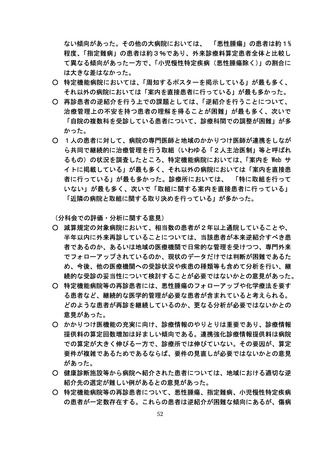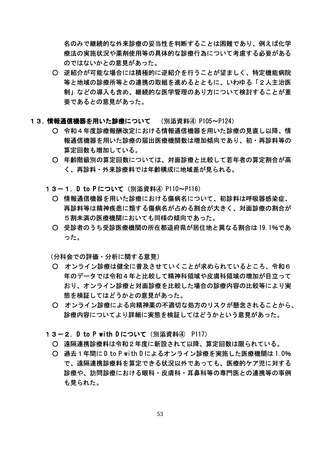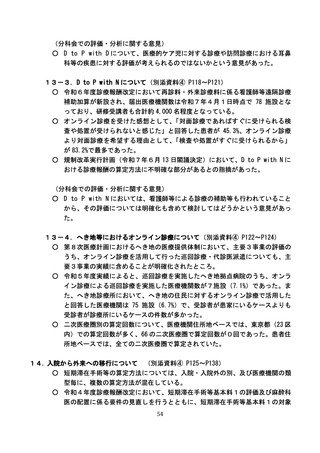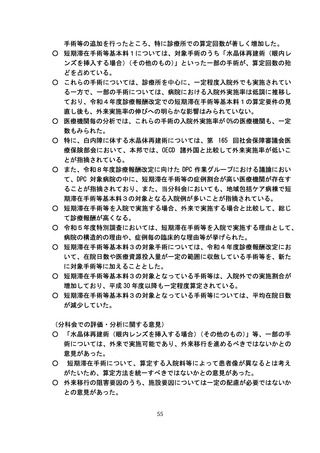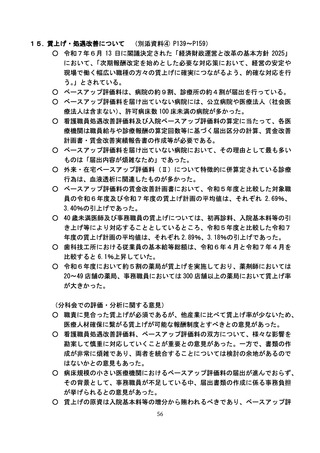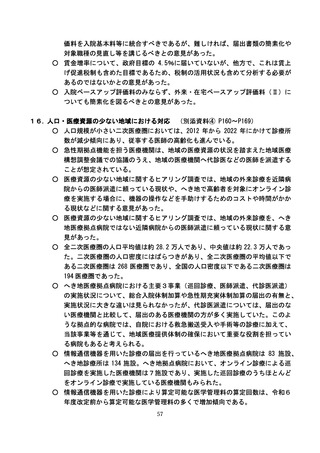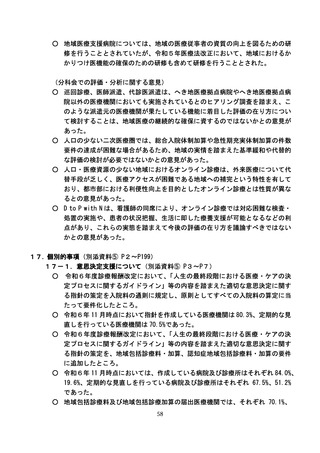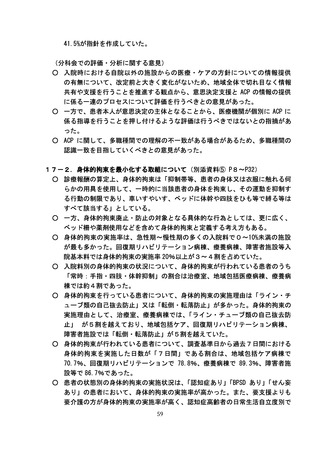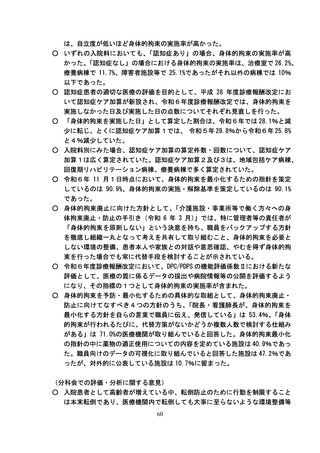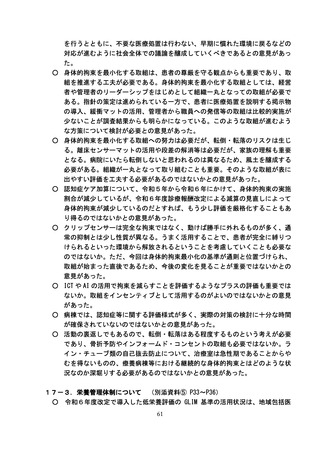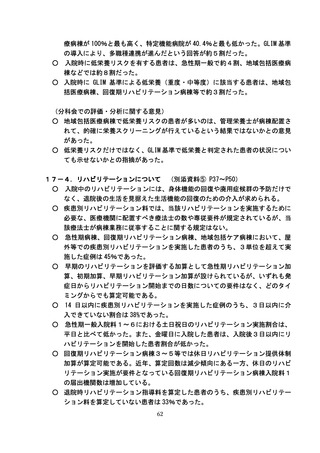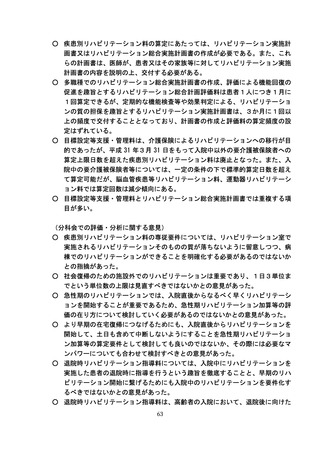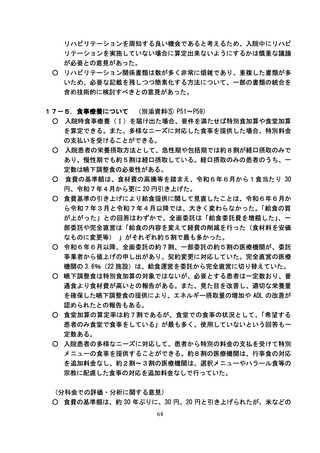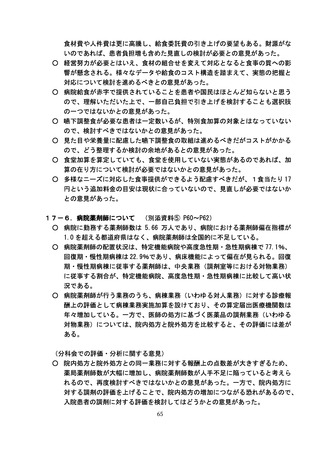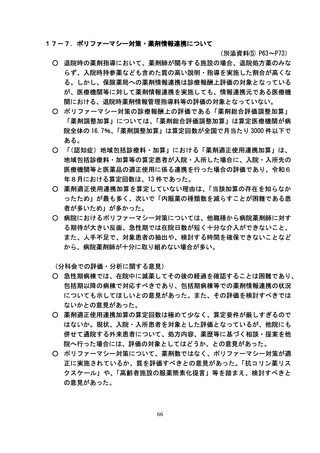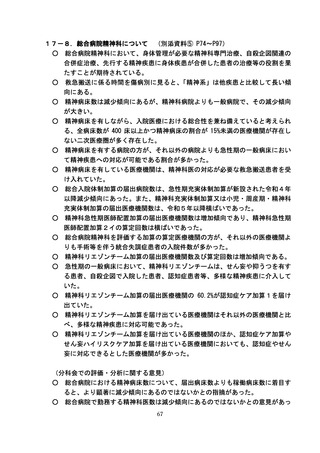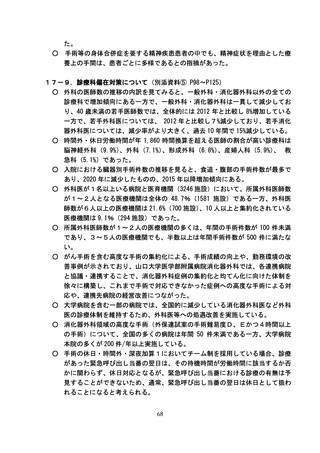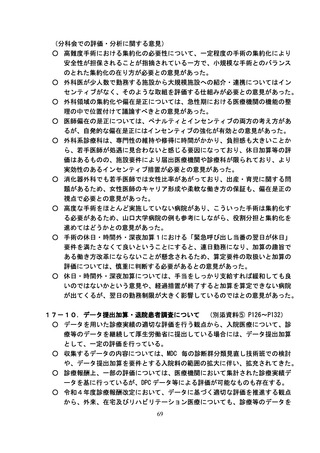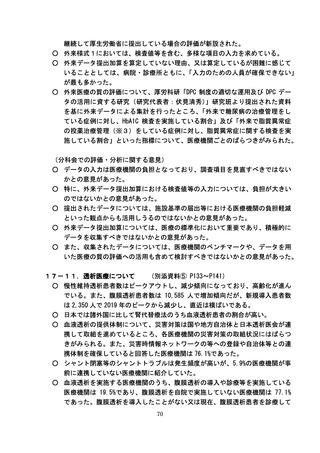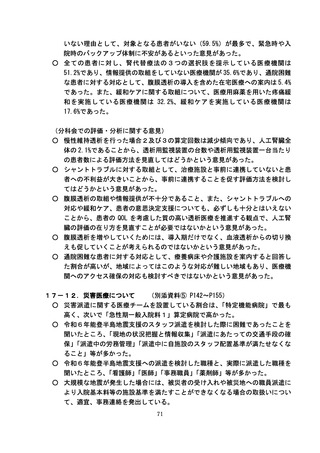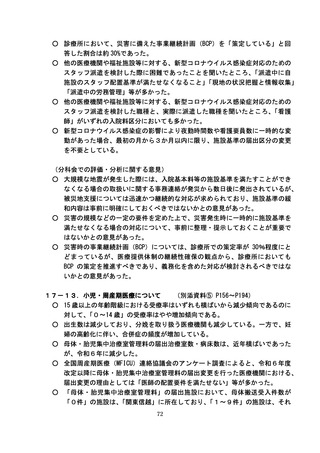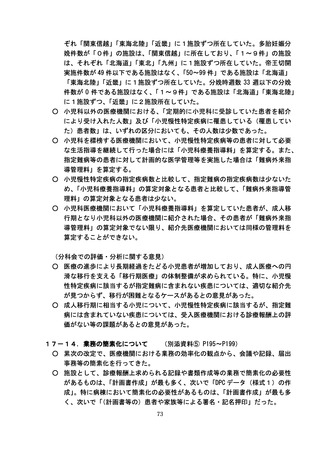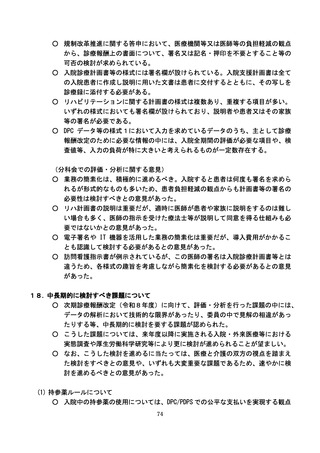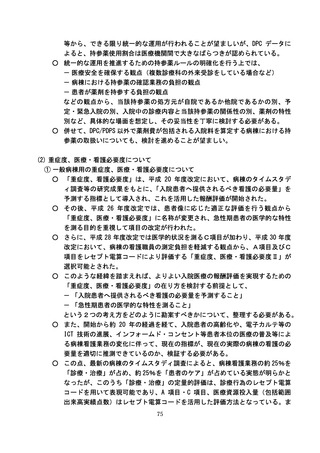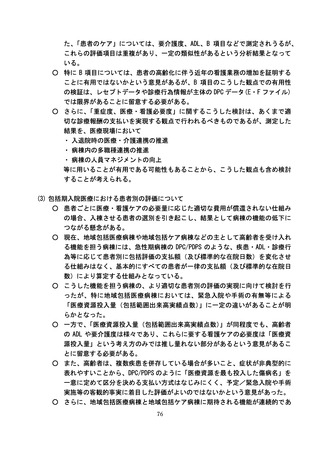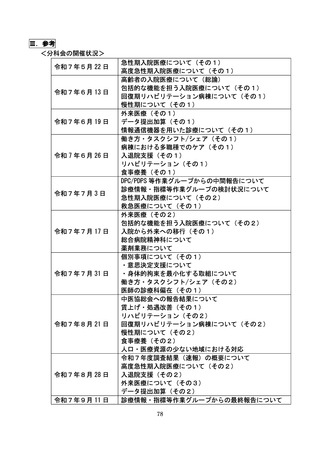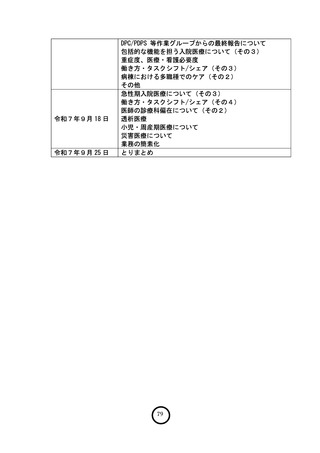よむ、つかう、まなぶ。
総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会における検討結果 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ DPCデータにおいては、入院料2で医療区分2・3の割合が6割以上である
施設が 95.5%あった。
○ 医療区分2・3の疾患・状態、処置等の各項目に該当する患者の割合は、入院
料1・2ともに増加していた。特に、「医師及び看護師の常時の管理」に該当
する患者は増えていた。
○ 入院料1,2のそれぞれにおいて、30 区分の入院料の1日当たり包括内出来高
実績点数は概ね入院料1~9、10~18、19~27 で漸減する形になっていた。
○ 療養病棟において、身体的拘束を一定の割合以上の患者に実施している病棟が
一定数みられた。処置や認知症の有無別に身体的拘束の実施割合を調べると、
認知症ありでは 25.7%、認知症なしでは 13.6%の患者に身体的拘束が実施され
ており、認知症がある場合に拘束の割合が高かった。病棟ごとの分析では、何
らかの挿入デバイスのある認知症の患者であっても約3割の病棟が身体的拘束
を全く実施していない一方で、挿入デバイスのない認知症でない患者に対して
も 20%以上身体的拘束を実施している病棟が約2割存在した。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 療養病棟は看護職員 20 対1配置であり、医療区分2・3の患者に多数対応す
ることは難しいため、医療区分の高い患者を受け入れられるような医療の体制
について検討が必要であるとの意見があった。
○ 30 区分された入院料について、実際の入院料は ADL 区分の高い入院料4、7、
10、13 等でその手前の入院料より高めに設定されており、介助に係る手間を評
価した点数設計になっているのではないかとの意見があった。
○ 褥瘡のある患者が肺炎を発症した場合等、同じ処置区分に該当する項目が2つ
以上生じた場合についての医療資源投入量についても検討しつつ入院料の現状
を評価してはどうかとの意見があった。
○ 入院料2の場合でも、医療区分2・3の患者が6割を超える施設がほとんどで
あることを踏まえ、基準を検討する余地があるのではないかとの意見があった。
○ 身体的拘束については、デバイスや認知症以外の要素で患者像に違いがあるの
か、病棟そのものの手厚い見守り等の取組が異なるのか、夜間を含めた人員配
置等まで踏まえて現状を評価し、検討を進めるべきとの意見があった。
6-2.経腸栄養管理加算・摂食嚥下機能回復について(別添資料② P129~P137)
○ 療養病棟において患者が受けた医療行為・処置等の割合は令和4年度調査と同
様の傾向であった。医療区分上の定義が見直された「中心静脈栄養」は 16.3%、
関連して「胃ろう・腸ろうによる栄養管理」は 13.0%、「経鼻経管栄養」は
26.7%であった。
○ 1か月に中心静脈栄養を実施した人数は 11-20 人の病棟が最多で半数弱であっ
た。中心静脈栄養を実施した患者のうち、身体的拘束を行った患者の割合が高
26
施設が 95.5%あった。
○ 医療区分2・3の疾患・状態、処置等の各項目に該当する患者の割合は、入院
料1・2ともに増加していた。特に、「医師及び看護師の常時の管理」に該当
する患者は増えていた。
○ 入院料1,2のそれぞれにおいて、30 区分の入院料の1日当たり包括内出来高
実績点数は概ね入院料1~9、10~18、19~27 で漸減する形になっていた。
○ 療養病棟において、身体的拘束を一定の割合以上の患者に実施している病棟が
一定数みられた。処置や認知症の有無別に身体的拘束の実施割合を調べると、
認知症ありでは 25.7%、認知症なしでは 13.6%の患者に身体的拘束が実施され
ており、認知症がある場合に拘束の割合が高かった。病棟ごとの分析では、何
らかの挿入デバイスのある認知症の患者であっても約3割の病棟が身体的拘束
を全く実施していない一方で、挿入デバイスのない認知症でない患者に対して
も 20%以上身体的拘束を実施している病棟が約2割存在した。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 療養病棟は看護職員 20 対1配置であり、医療区分2・3の患者に多数対応す
ることは難しいため、医療区分の高い患者を受け入れられるような医療の体制
について検討が必要であるとの意見があった。
○ 30 区分された入院料について、実際の入院料は ADL 区分の高い入院料4、7、
10、13 等でその手前の入院料より高めに設定されており、介助に係る手間を評
価した点数設計になっているのではないかとの意見があった。
○ 褥瘡のある患者が肺炎を発症した場合等、同じ処置区分に該当する項目が2つ
以上生じた場合についての医療資源投入量についても検討しつつ入院料の現状
を評価してはどうかとの意見があった。
○ 入院料2の場合でも、医療区分2・3の患者が6割を超える施設がほとんどで
あることを踏まえ、基準を検討する余地があるのではないかとの意見があった。
○ 身体的拘束については、デバイスや認知症以外の要素で患者像に違いがあるの
か、病棟そのものの手厚い見守り等の取組が異なるのか、夜間を含めた人員配
置等まで踏まえて現状を評価し、検討を進めるべきとの意見があった。
6-2.経腸栄養管理加算・摂食嚥下機能回復について(別添資料② P129~P137)
○ 療養病棟において患者が受けた医療行為・処置等の割合は令和4年度調査と同
様の傾向であった。医療区分上の定義が見直された「中心静脈栄養」は 16.3%、
関連して「胃ろう・腸ろうによる栄養管理」は 13.0%、「経鼻経管栄養」は
26.7%であった。
○ 1か月に中心静脈栄養を実施した人数は 11-20 人の病棟が最多で半数弱であっ
た。中心静脈栄養を実施した患者のうち、身体的拘束を行った患者の割合が高
26