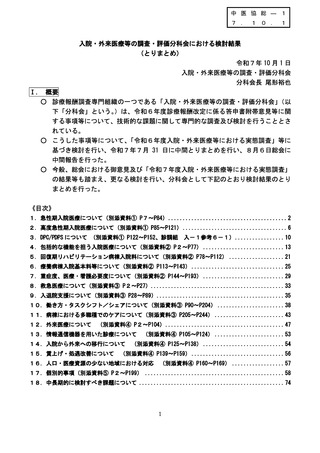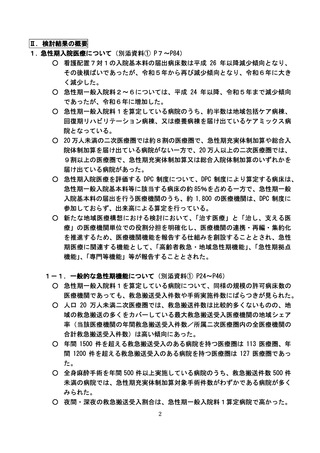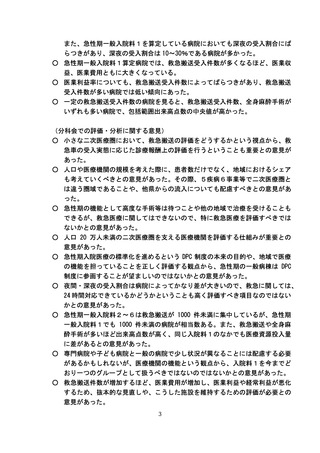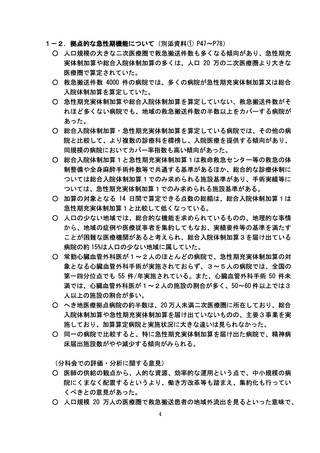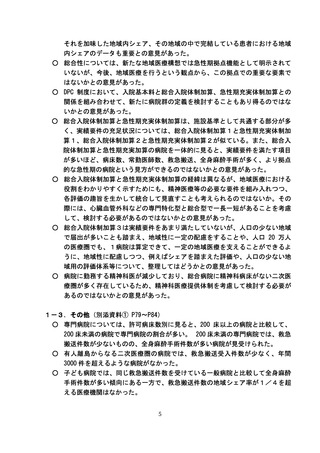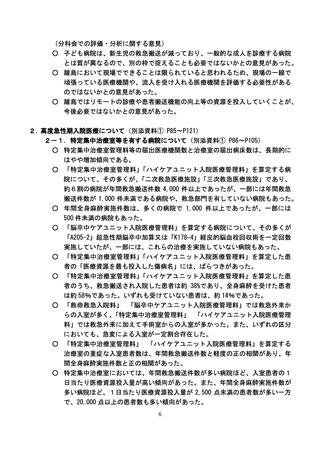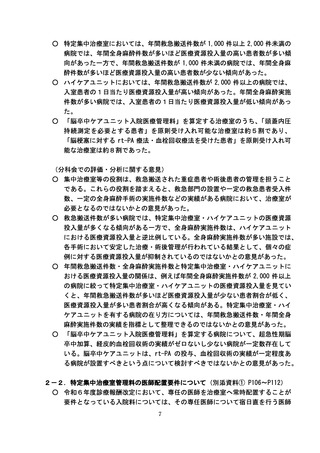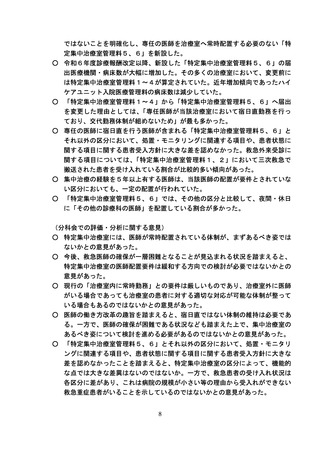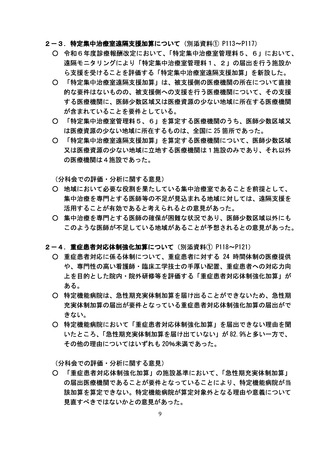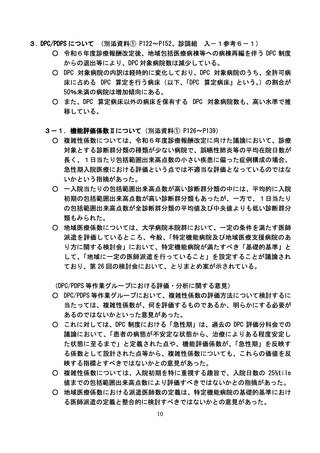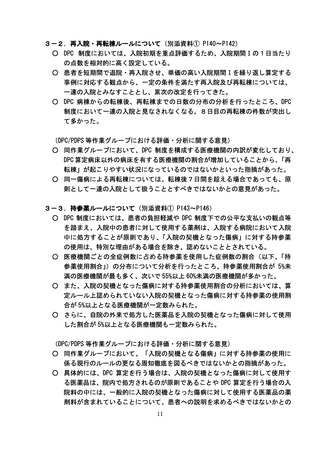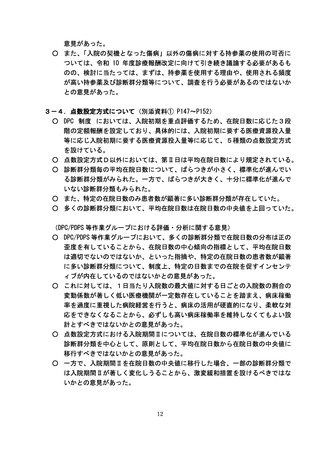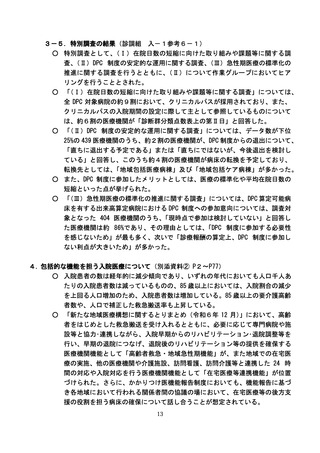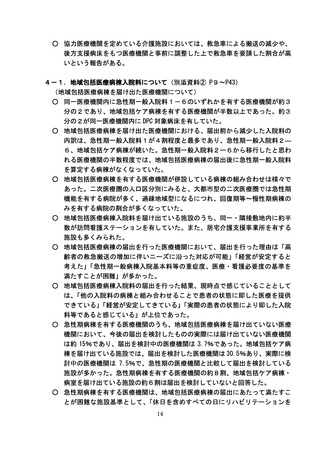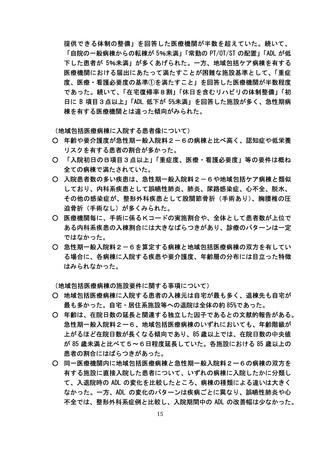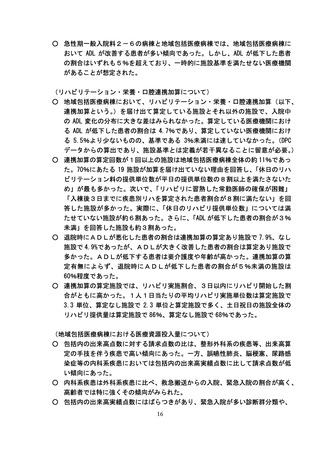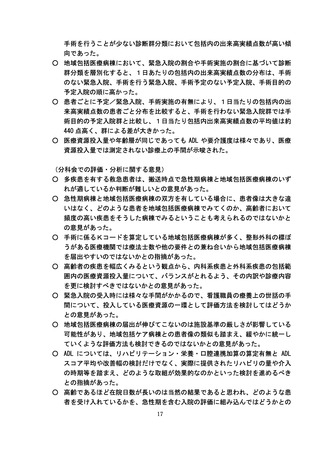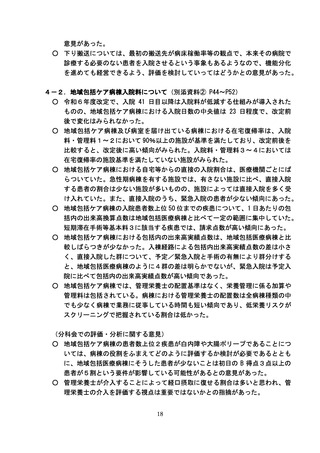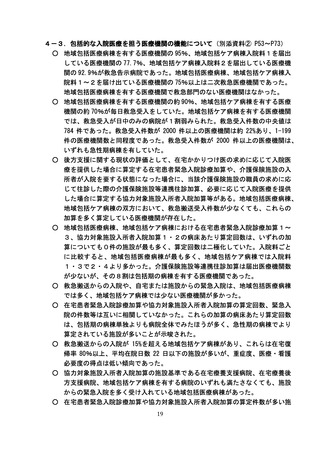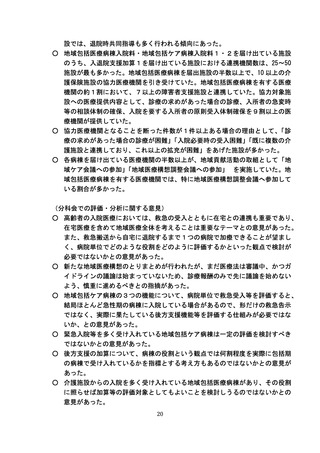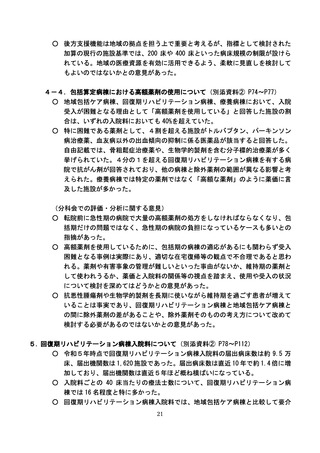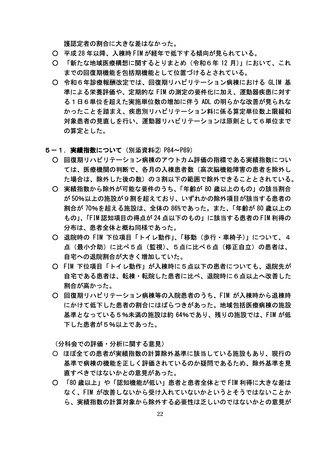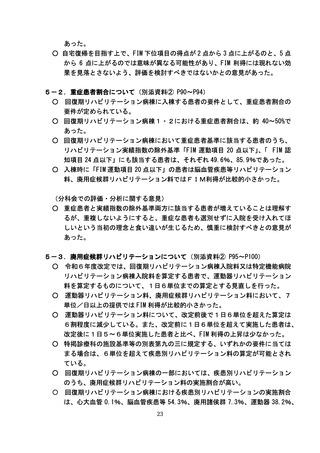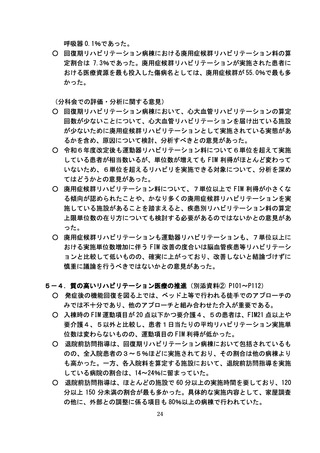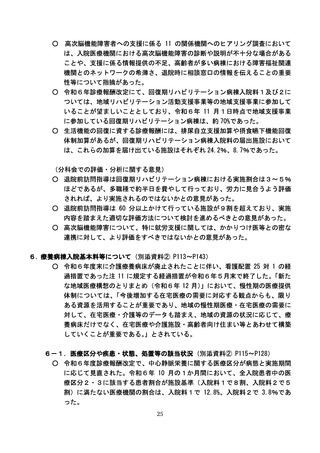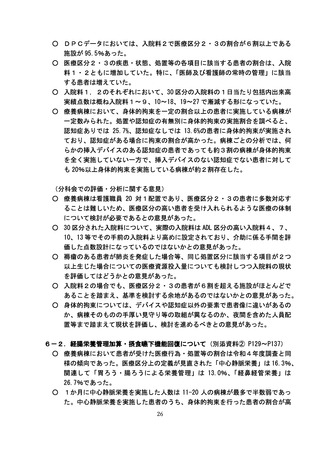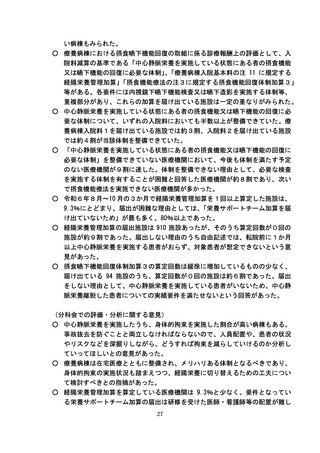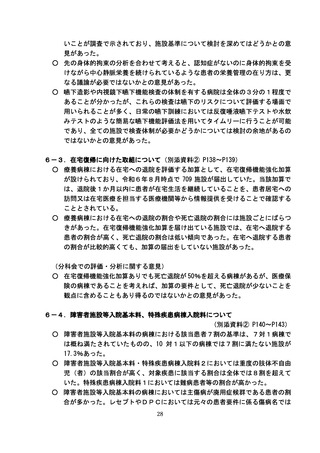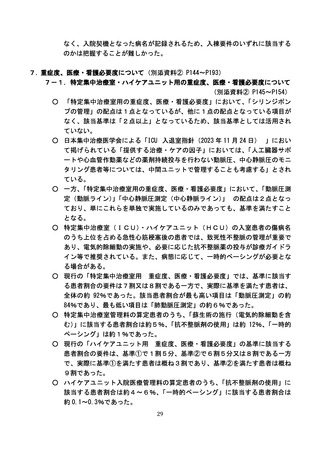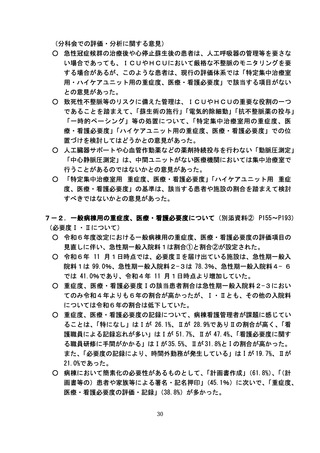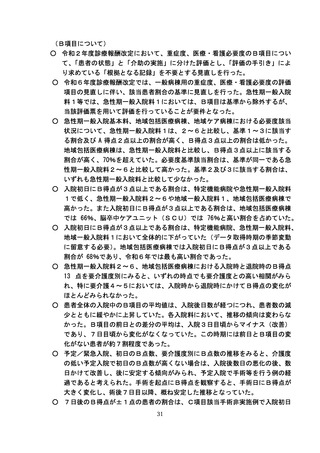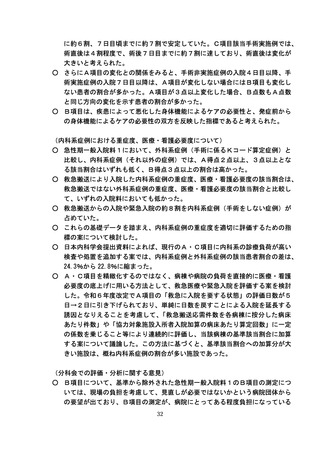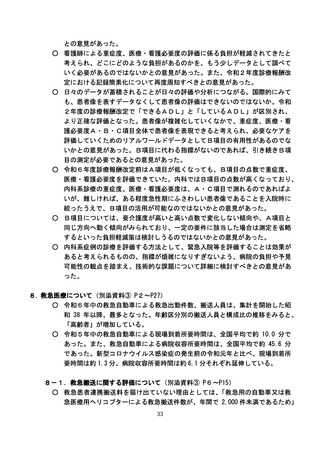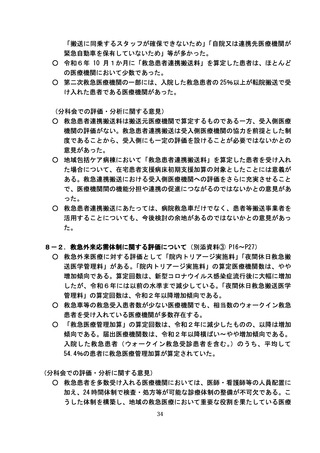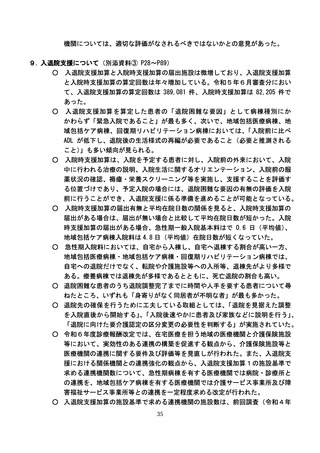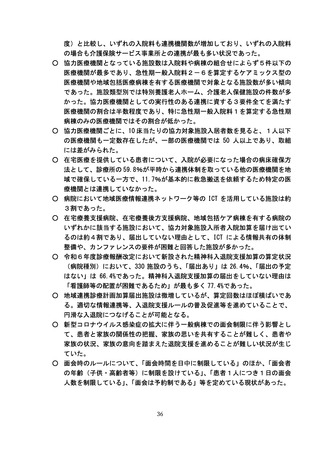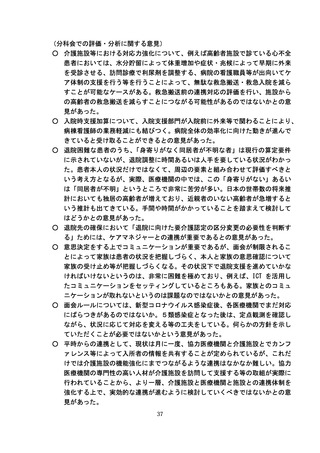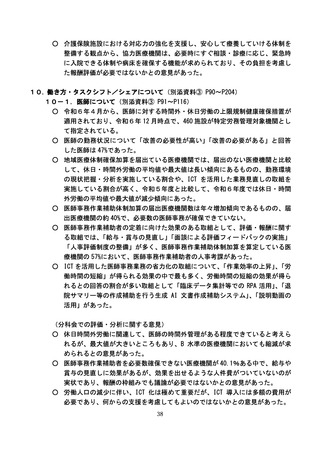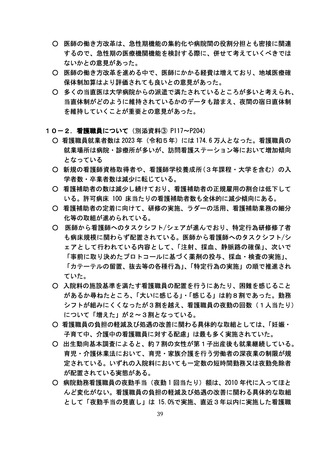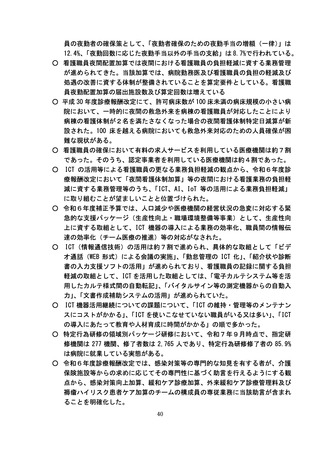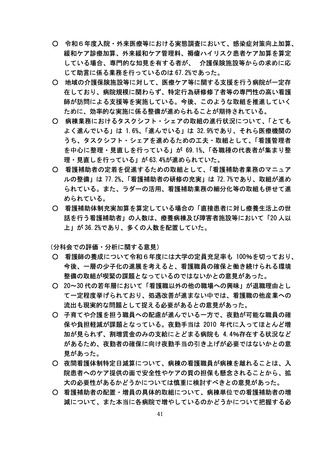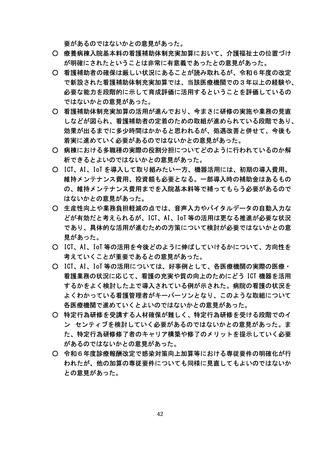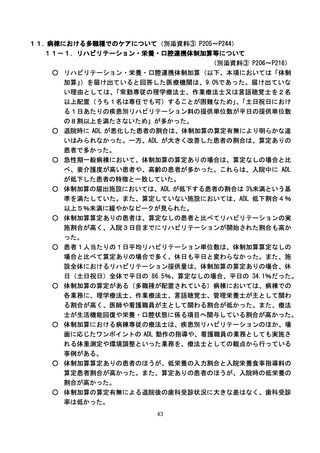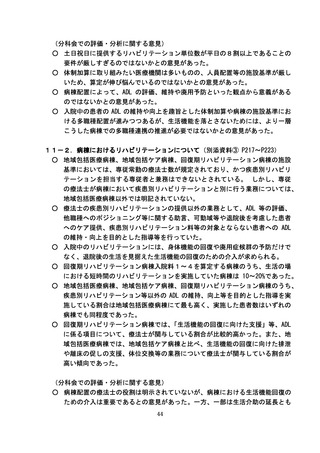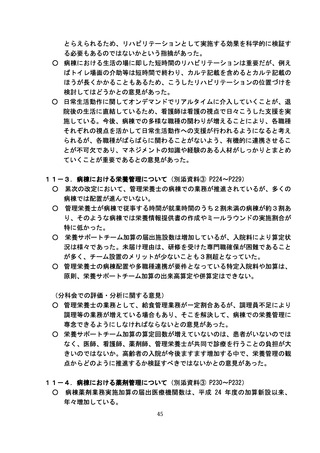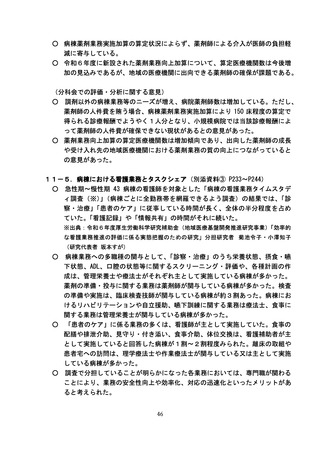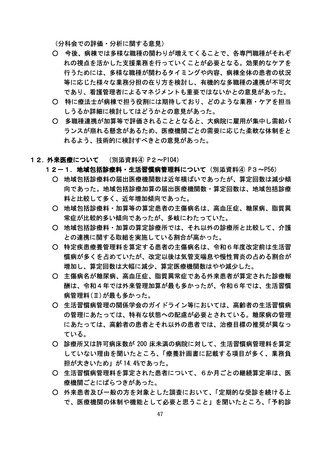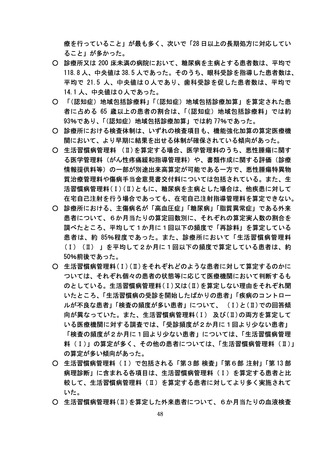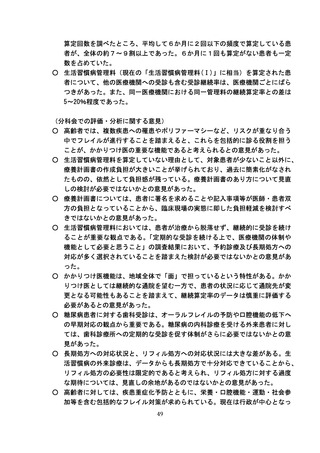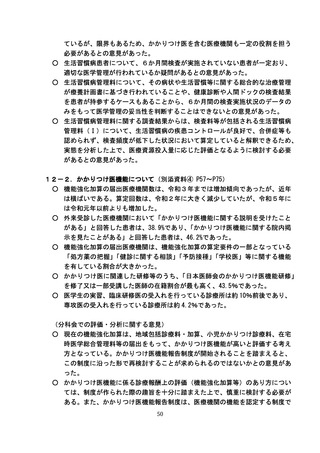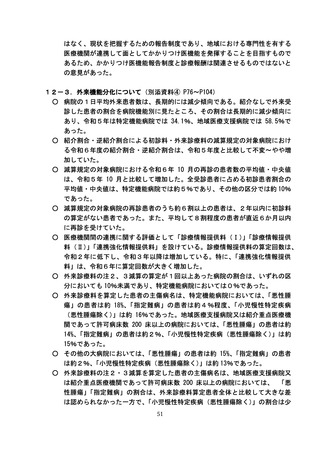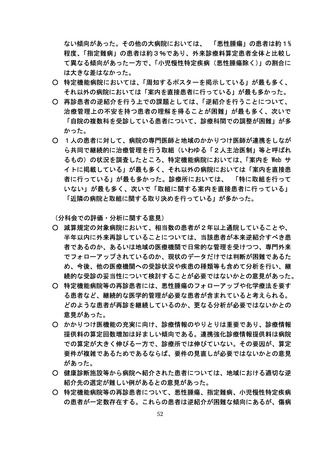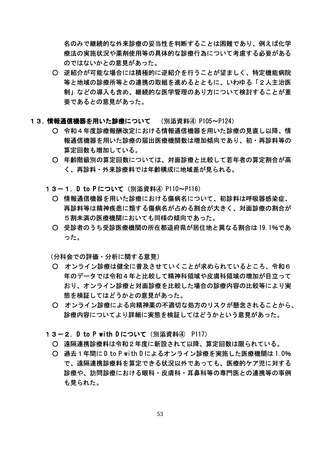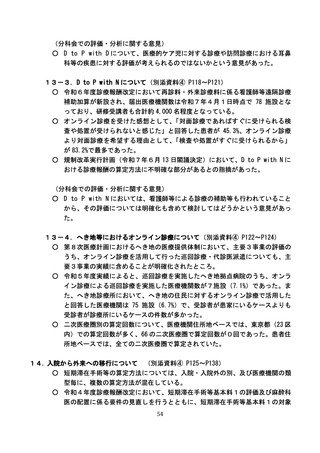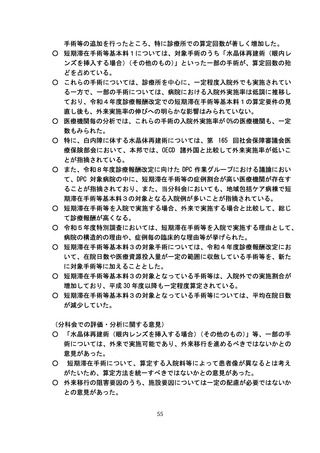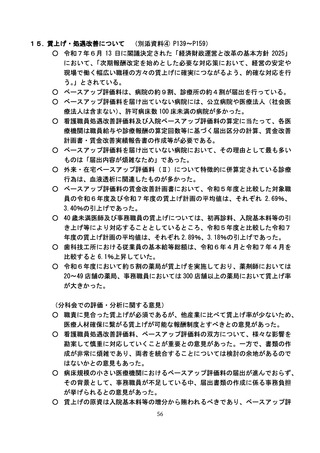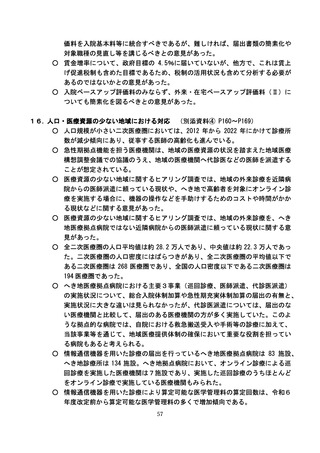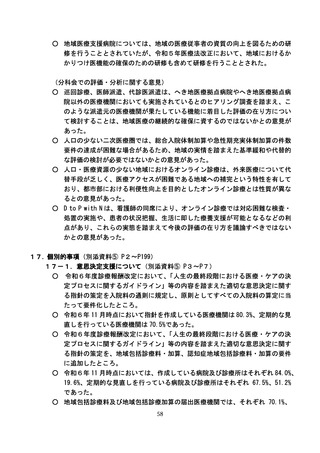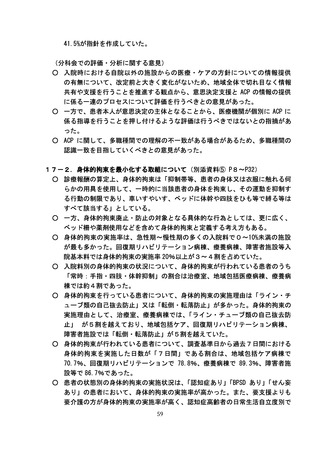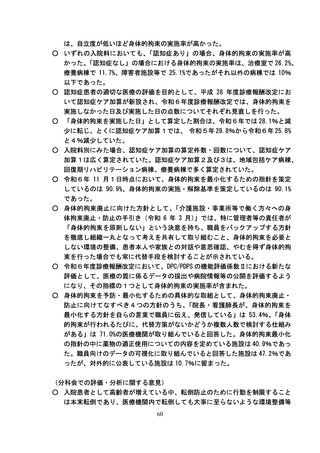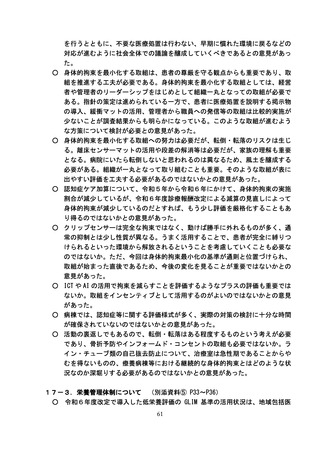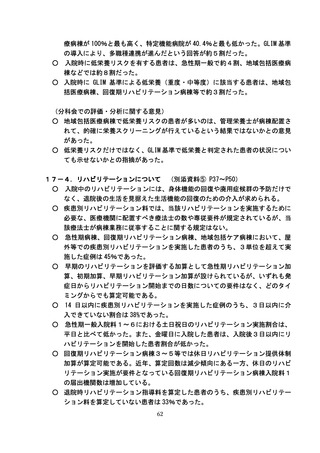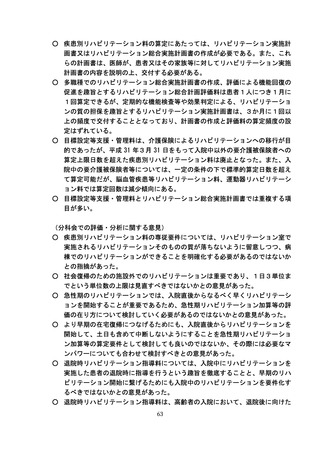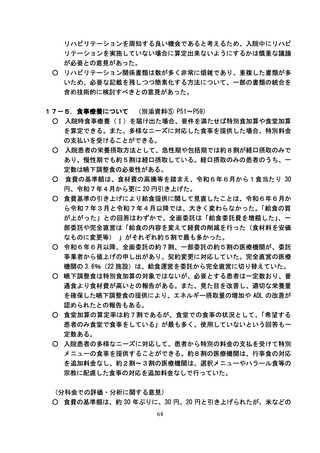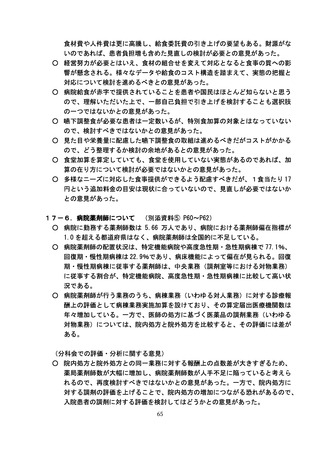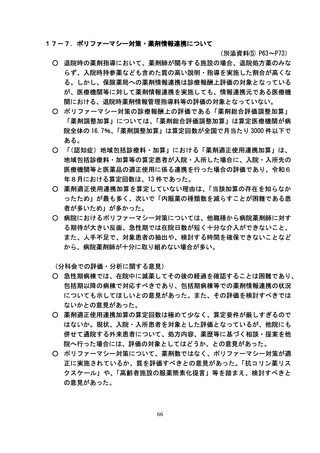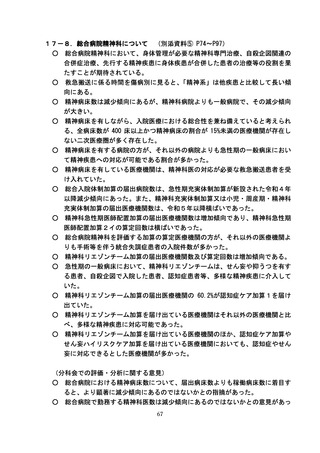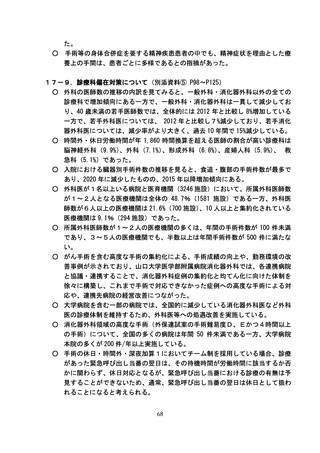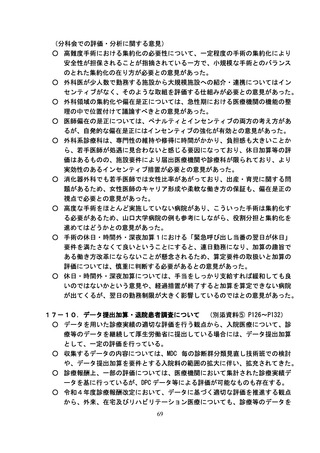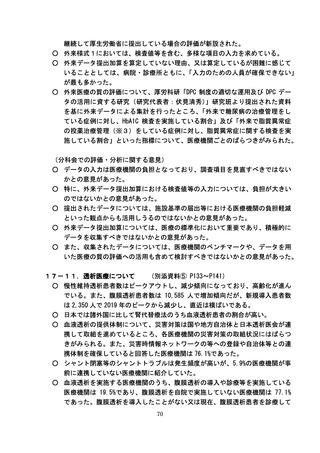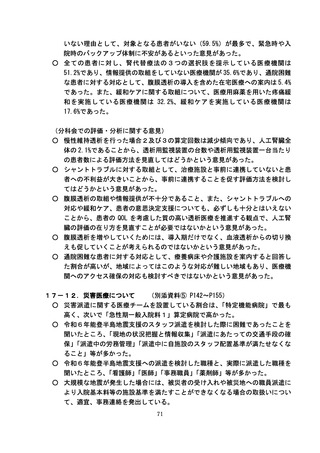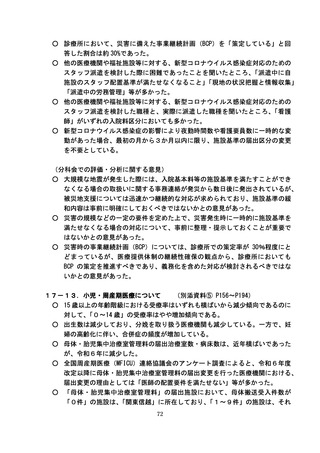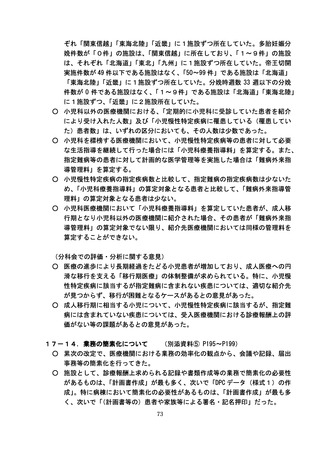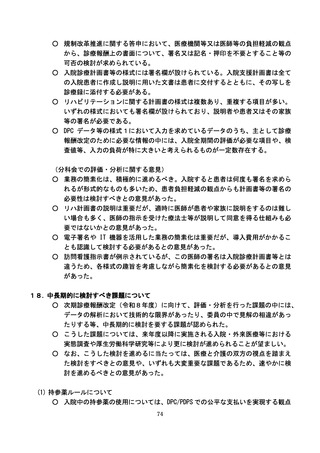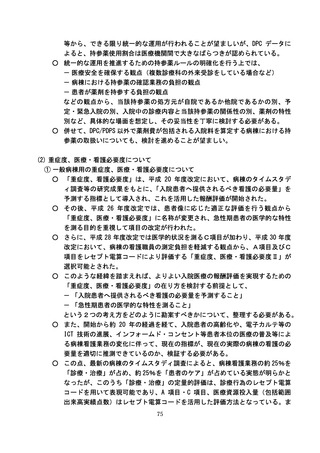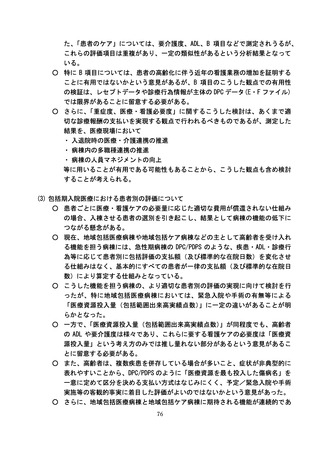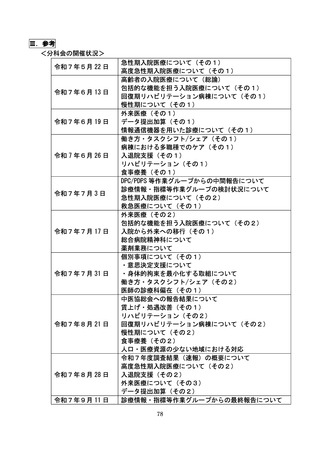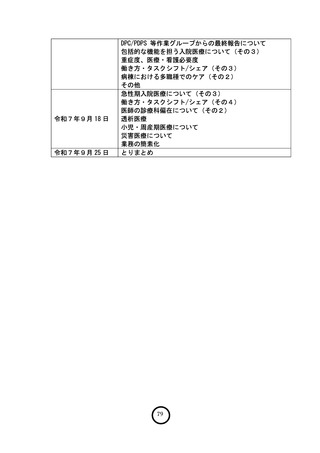よむ、つかう、まなぶ。
総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会における検討結果 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 医師の働き方改革は、急性期機能の集約化や病院間の役割分担とも密接に関連
するので、急性期の医療機関機能を検討する際に、併せて考えていくべきでは
ないかとの意見があった。
○ 医師の働き方改革を進める中で、医師にかかる経費は増えており、地域医療確
保体制加算はより評価されても良いとの意見があった。
○ 多くの当直医は大学病院からの派遣で満たされているところが多いと考えられ、
当直体制がどのように維持されているかのデータも踏まえ、夜間の宿日直体制
を維持していくことが重要との意見があった。
10-2.看護職員について(別添資料③ P117~P204)
○ 看護職員就業者数は 2023 年(令和5年)には 174.6 万人となった。看護職員の
就業場所は病院・診療所が多いが、訪問看護ステーション等において増加傾向
となっている
○ 新規の看護師資格取得者や、看護師学校養成所(3年課程・大学を含む)の入
学者数・卒業者数は減少に転じている。
○ 看護補助者の数は減少し続けており、看護補助者の正規雇用の割合は低下して
いる。許可病床 100 床当たりの看護補助者数も全体的に減少傾向にある。
○ 看護補助者の定着に向けて、研修の実施、ラダーの活用、看護補助業務の細分
化等の取組が進められている。
○
医師から看護師へのタスクシフト/シェアが進んでおり、特定行為研修修了者
も病床規模に関わらず配置されている。医師から看護師へのタスクシフト/シ
ェアとして行われている内容として、「注射、採血、静脈路の確保」、次いで
「事前に取り決めたプロトコールに基づく薬剤の投与、採血・検査の実施」、
「カテーテルの留置、抜去等の各種行為」、「特定行為の実施」の順で推進され
ていた。
○ 入院料の施設基準を満たす看護職員の配置を行うにあたり、困難を感じること
があるか尋ねたところ、「大いに感じる」・「感じる」は約8割であった。勤務
シフトが組みにくくなったが3割を越え、看護職員の夜勤の回数(1人当たり)
について「増えた」が2~3割となっている。
○ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関わる具体的な取組としては、「妊娠・
子育て中、介護中の看護職員に対する配慮」は最も多く実施されていた。
○ 出生動向基本調査によると、約7割の女性が第1子出産後も就業継続している。
育児・介護休業法において、育児・家族介護を行う労働者の深夜業の制限が規
定されている。いずれの入院料においても一定数の短時間勤務又は夜勤免除者
が配置されている実態がある。
○ 病院勤務看護職員の夜勤手当(夜勤 1 回当たり)額は、2010 年代に入ってほと
んど変化がない。看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関わる具体的な取組
として「夜勤手当の見直し」は 15.0%で実施、直近3年以内に実施した看護職
39
するので、急性期の医療機関機能を検討する際に、併せて考えていくべきでは
ないかとの意見があった。
○ 医師の働き方改革を進める中で、医師にかかる経費は増えており、地域医療確
保体制加算はより評価されても良いとの意見があった。
○ 多くの当直医は大学病院からの派遣で満たされているところが多いと考えられ、
当直体制がどのように維持されているかのデータも踏まえ、夜間の宿日直体制
を維持していくことが重要との意見があった。
10-2.看護職員について(別添資料③ P117~P204)
○ 看護職員就業者数は 2023 年(令和5年)には 174.6 万人となった。看護職員の
就業場所は病院・診療所が多いが、訪問看護ステーション等において増加傾向
となっている
○ 新規の看護師資格取得者や、看護師学校養成所(3年課程・大学を含む)の入
学者数・卒業者数は減少に転じている。
○ 看護補助者の数は減少し続けており、看護補助者の正規雇用の割合は低下して
いる。許可病床 100 床当たりの看護補助者数も全体的に減少傾向にある。
○ 看護補助者の定着に向けて、研修の実施、ラダーの活用、看護補助業務の細分
化等の取組が進められている。
○
医師から看護師へのタスクシフト/シェアが進んでおり、特定行為研修修了者
も病床規模に関わらず配置されている。医師から看護師へのタスクシフト/シ
ェアとして行われている内容として、「注射、採血、静脈路の確保」、次いで
「事前に取り決めたプロトコールに基づく薬剤の投与、採血・検査の実施」、
「カテーテルの留置、抜去等の各種行為」、「特定行為の実施」の順で推進され
ていた。
○ 入院料の施設基準を満たす看護職員の配置を行うにあたり、困難を感じること
があるか尋ねたところ、「大いに感じる」・「感じる」は約8割であった。勤務
シフトが組みにくくなったが3割を越え、看護職員の夜勤の回数(1人当たり)
について「増えた」が2~3割となっている。
○ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関わる具体的な取組としては、「妊娠・
子育て中、介護中の看護職員に対する配慮」は最も多く実施されていた。
○ 出生動向基本調査によると、約7割の女性が第1子出産後も就業継続している。
育児・介護休業法において、育児・家族介護を行う労働者の深夜業の制限が規
定されている。いずれの入院料においても一定数の短時間勤務又は夜勤免除者
が配置されている実態がある。
○ 病院勤務看護職員の夜勤手当(夜勤 1 回当たり)額は、2010 年代に入ってほと
んど変化がない。看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関わる具体的な取組
として「夜勤手当の見直し」は 15.0%で実施、直近3年以内に実施した看護職
39