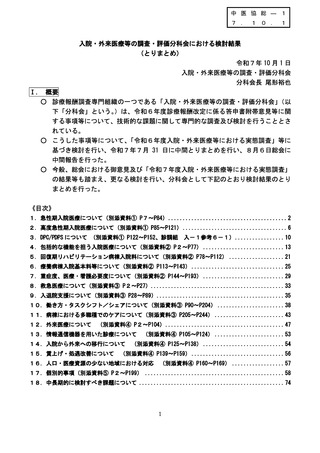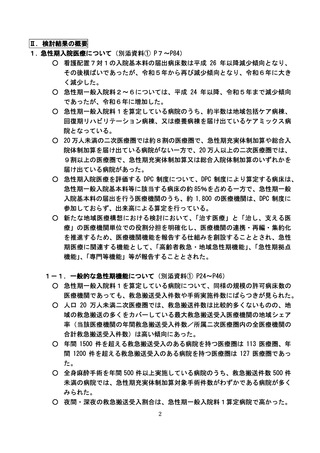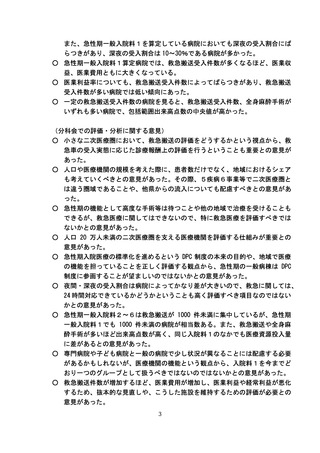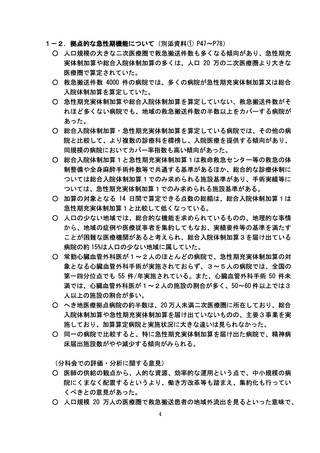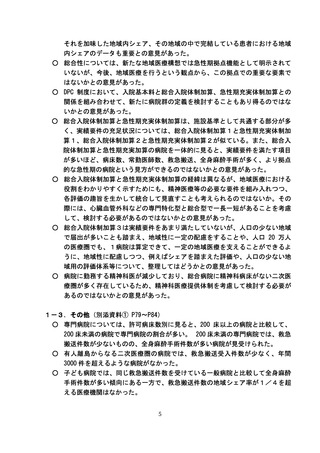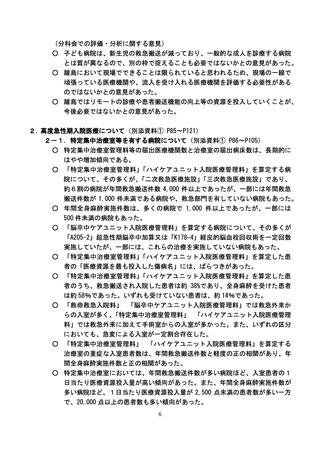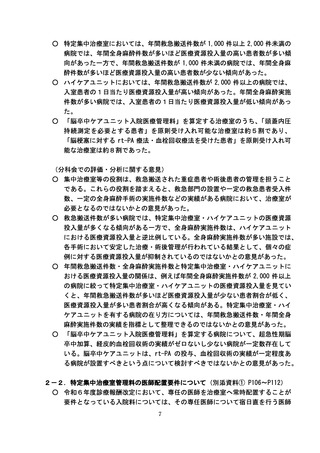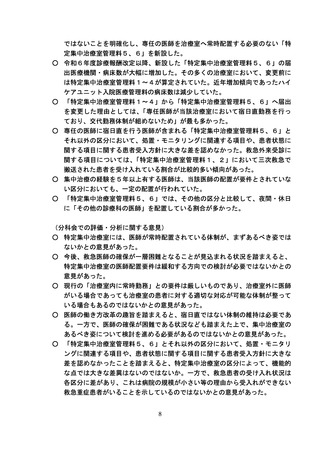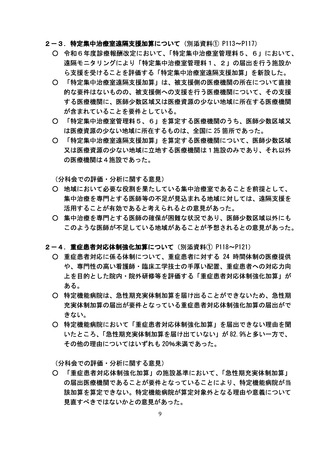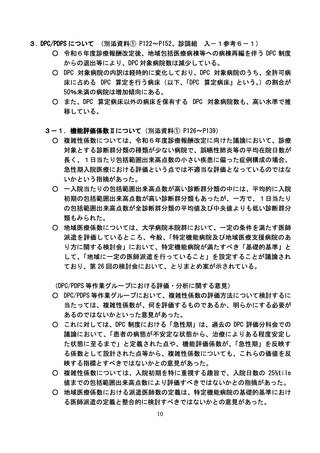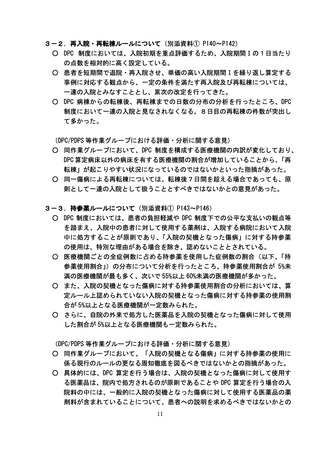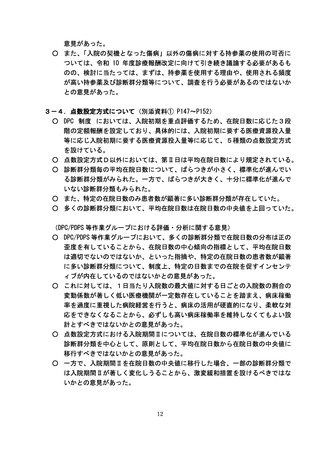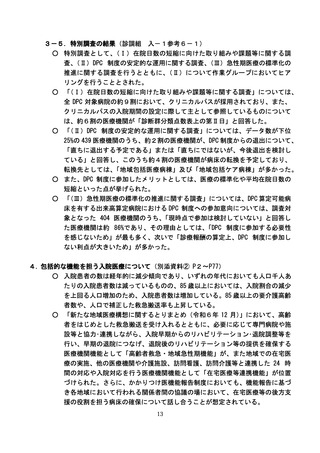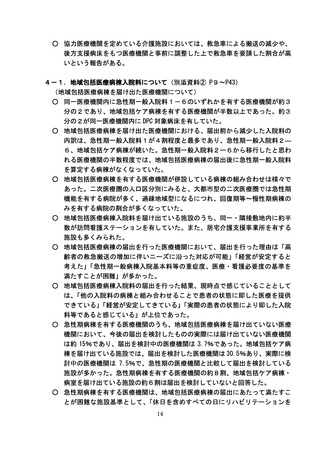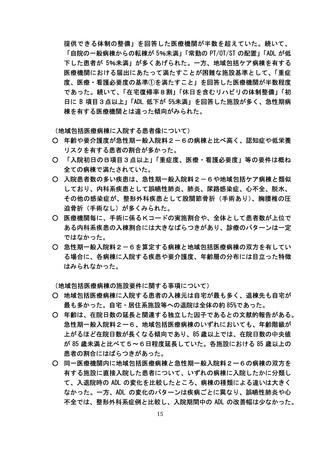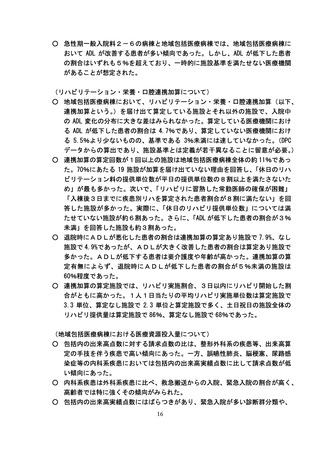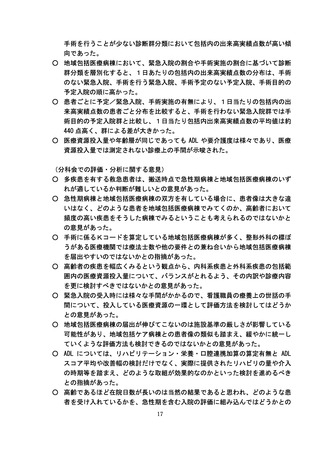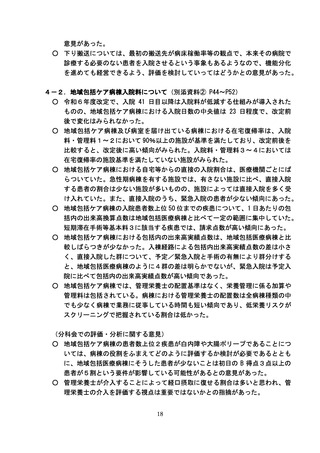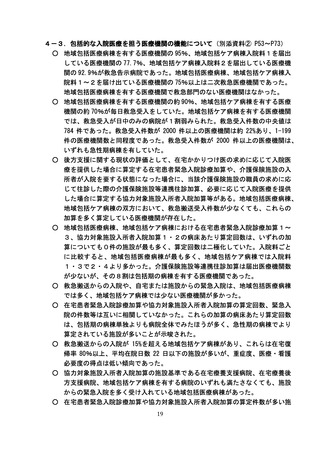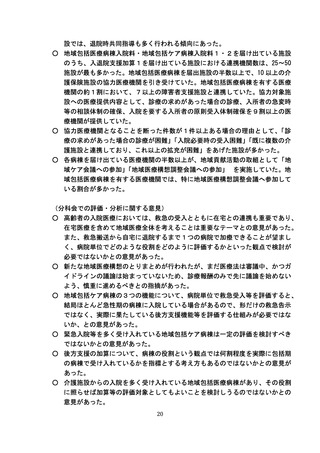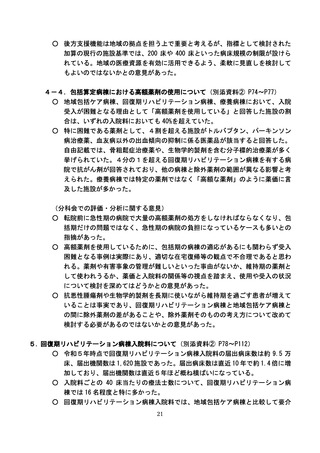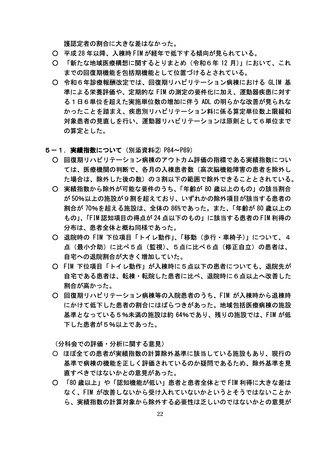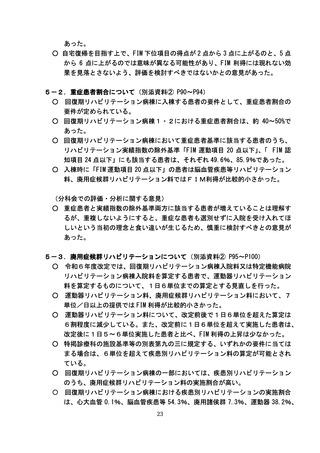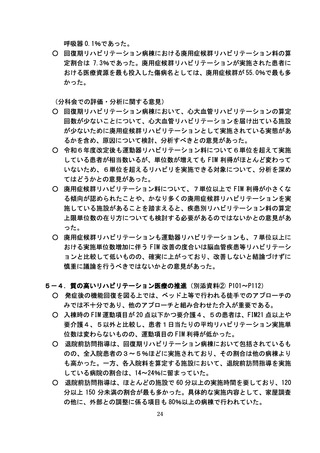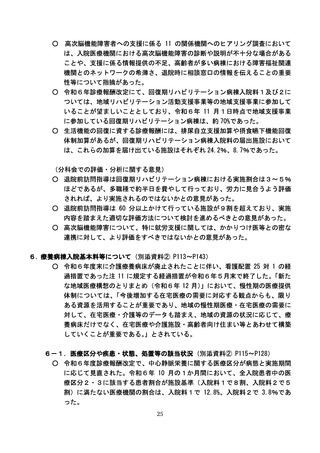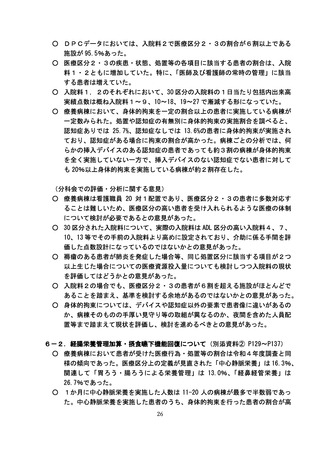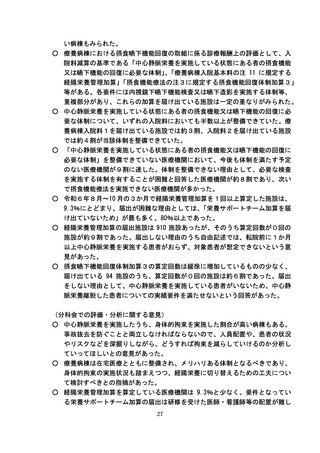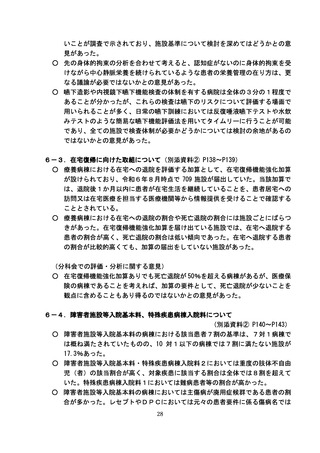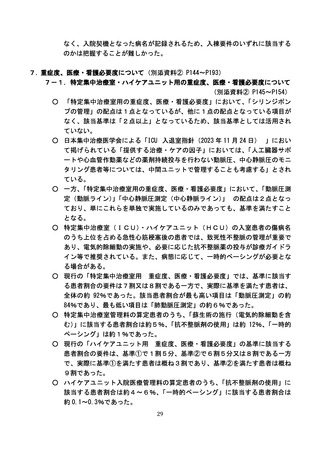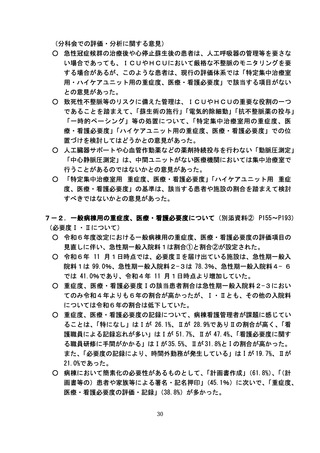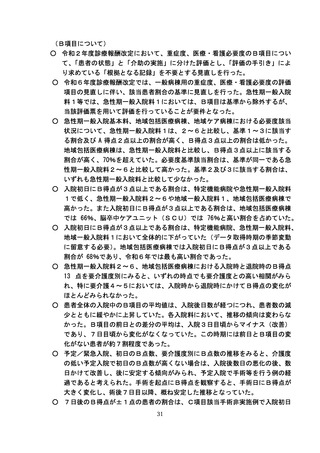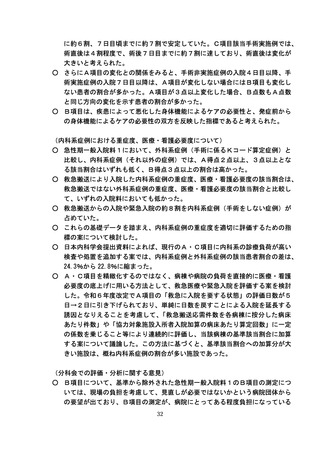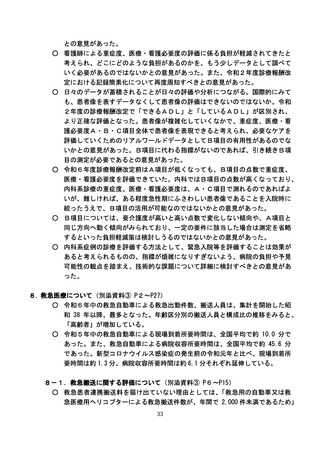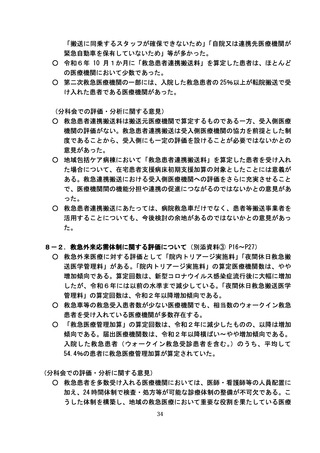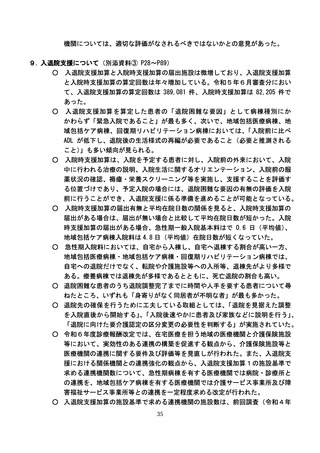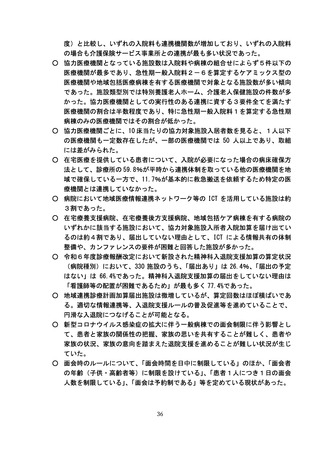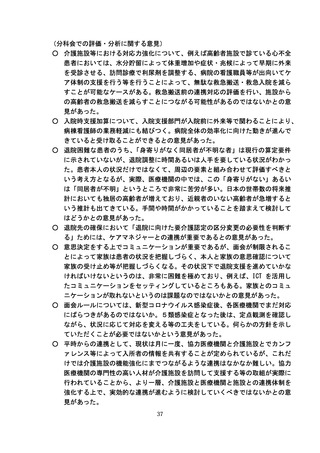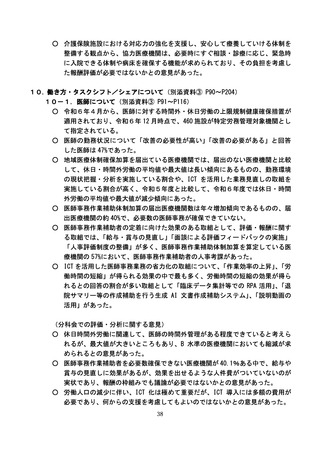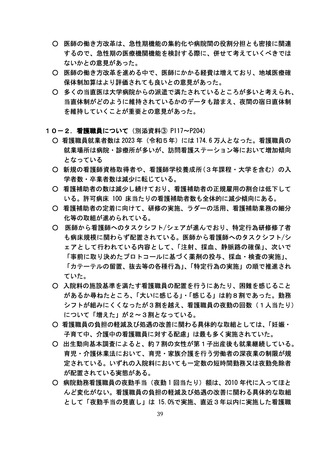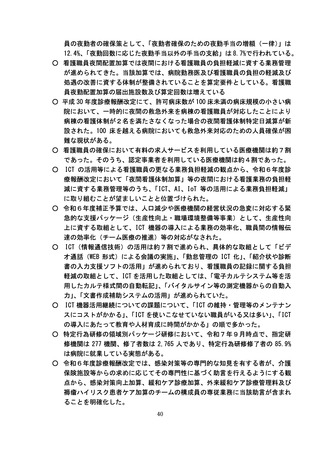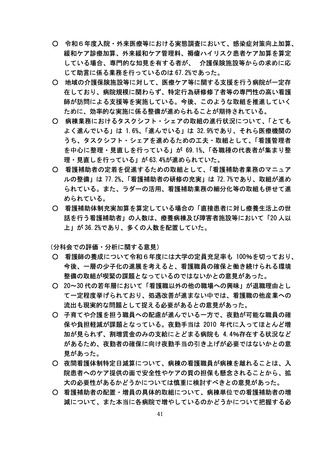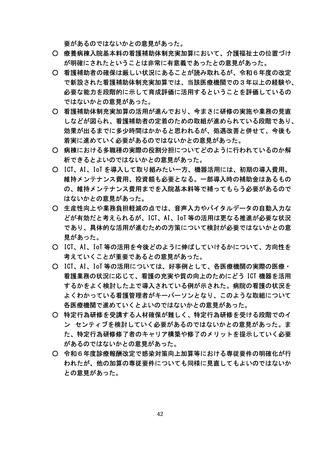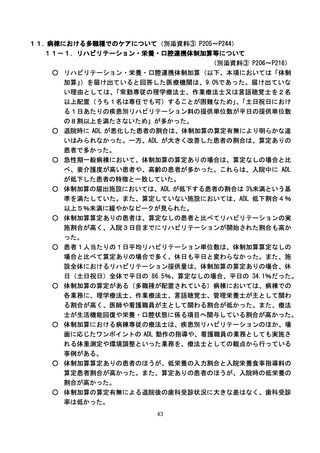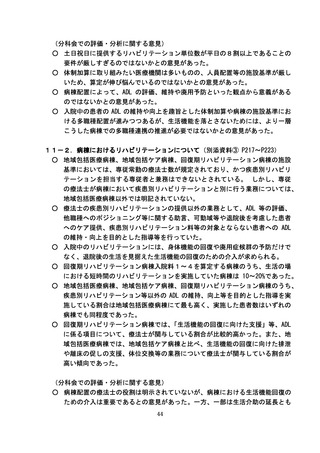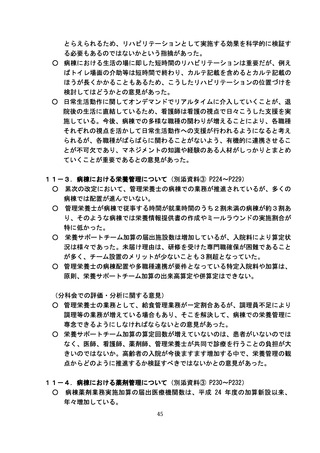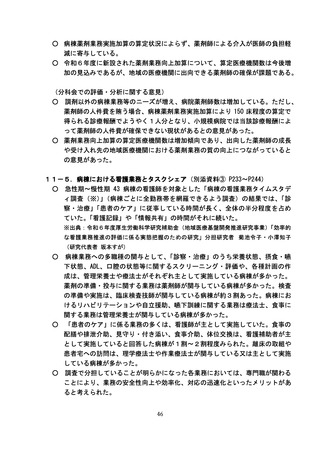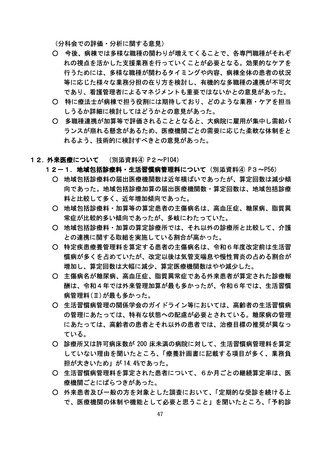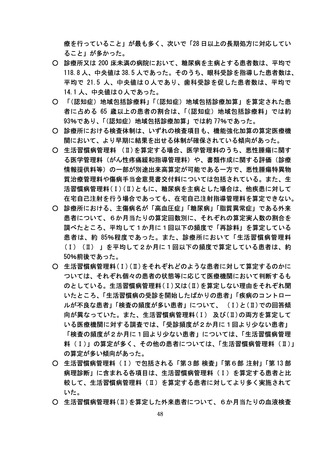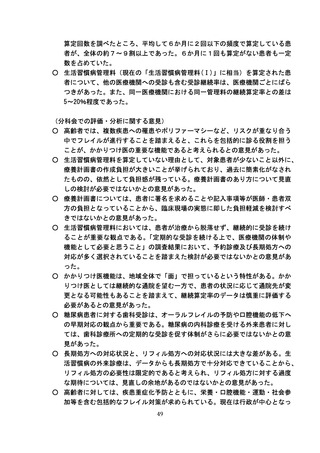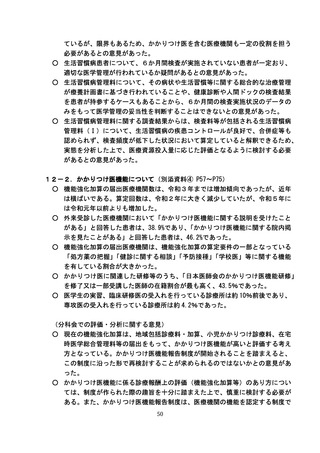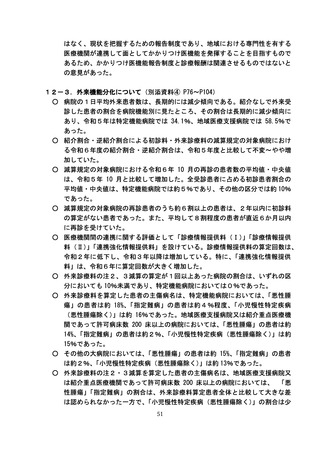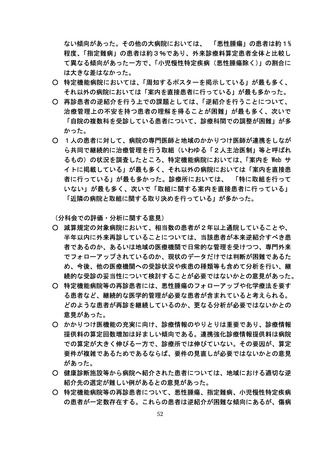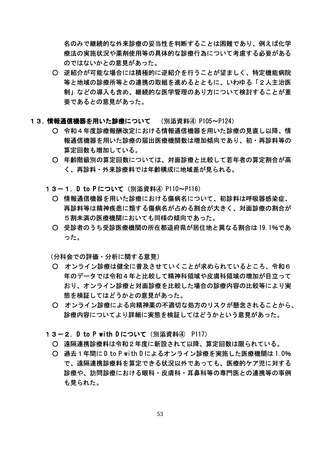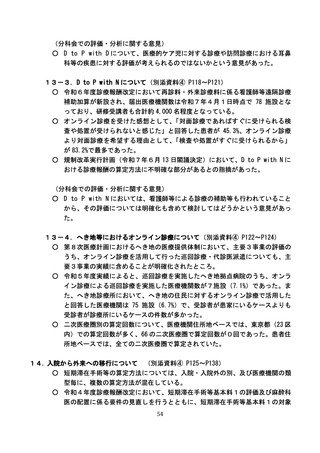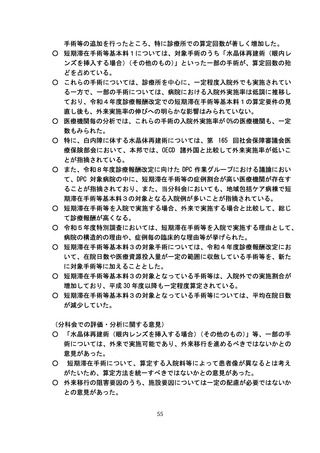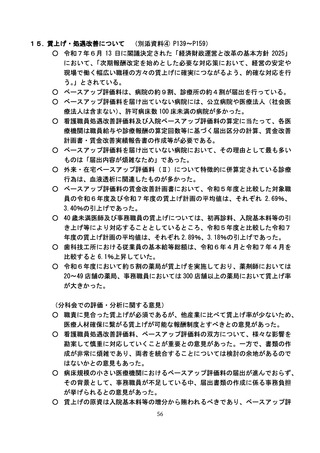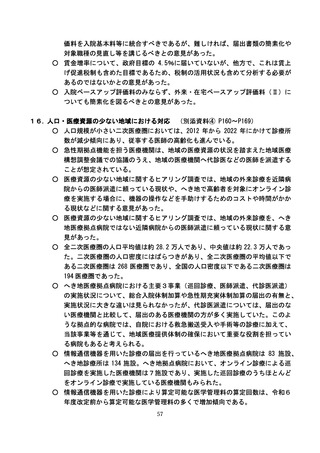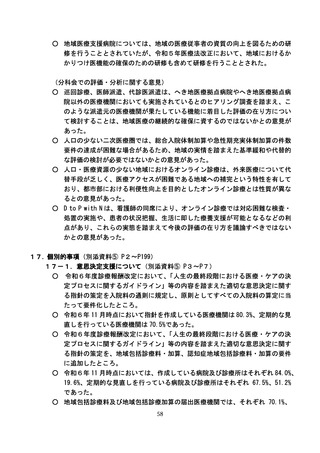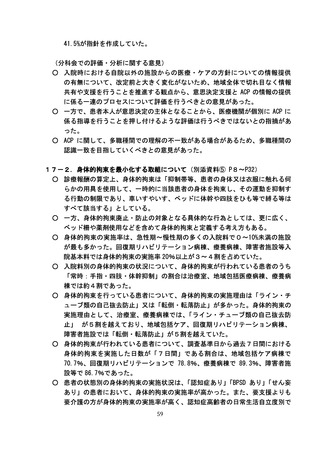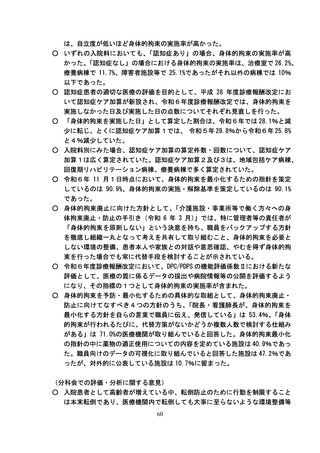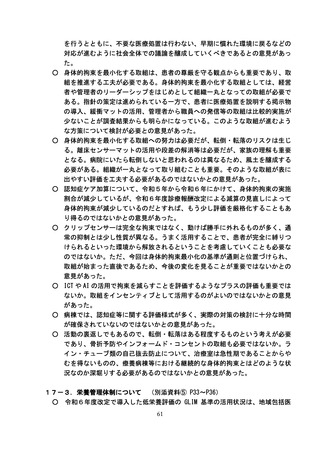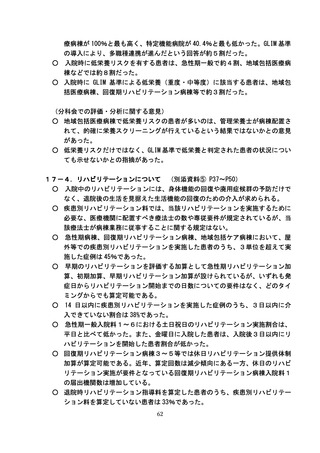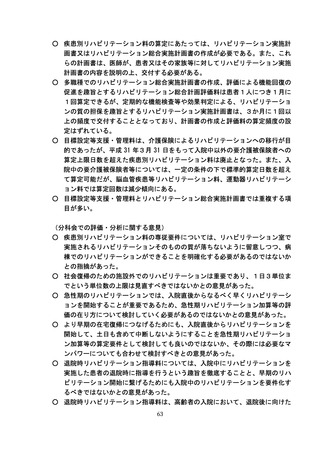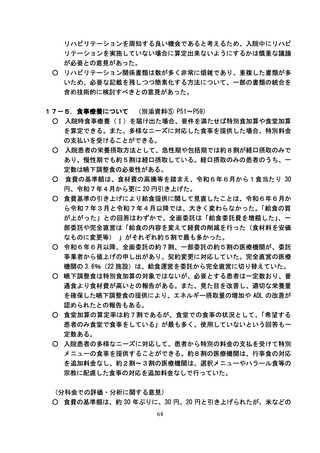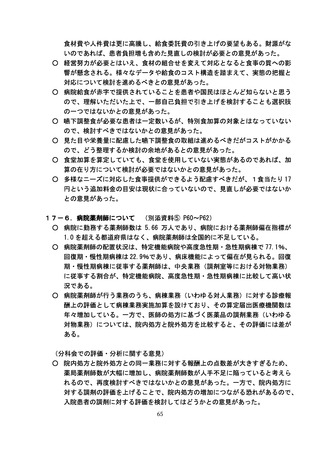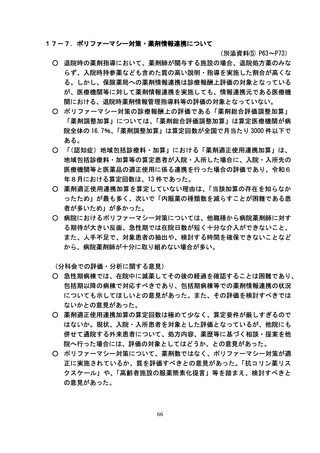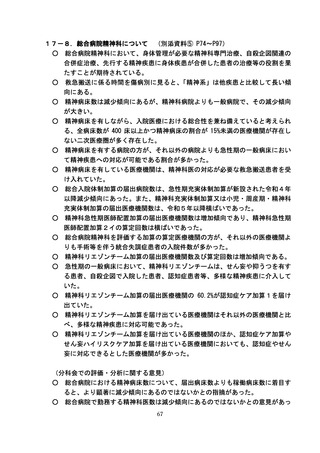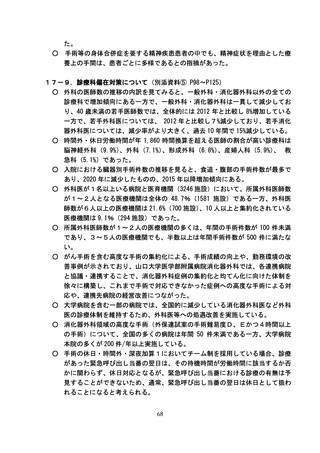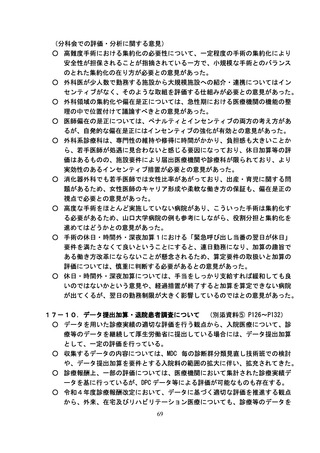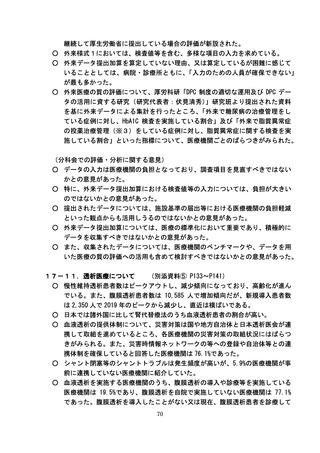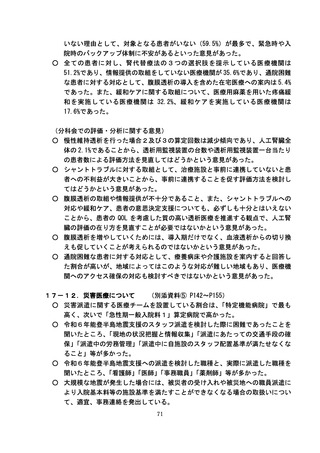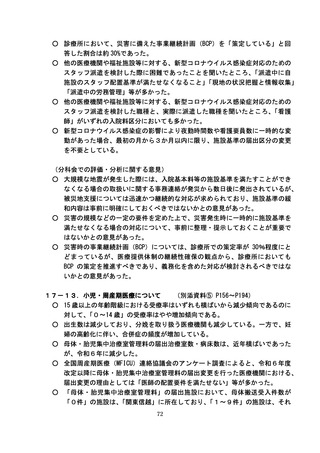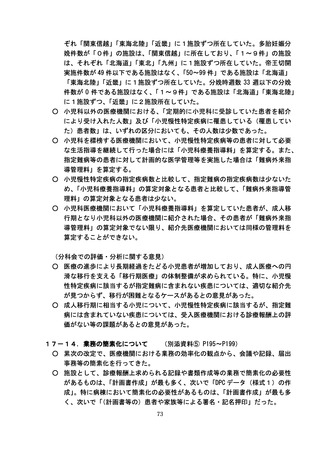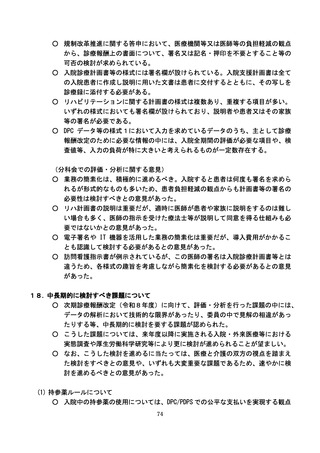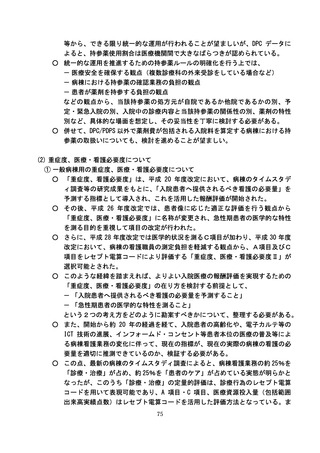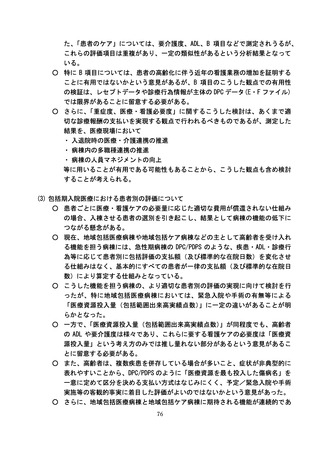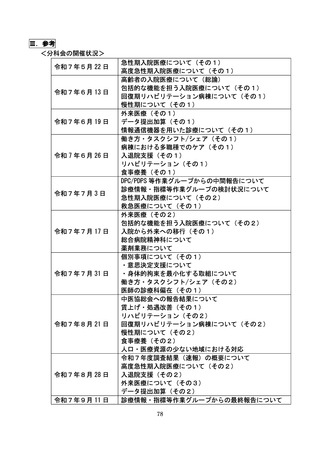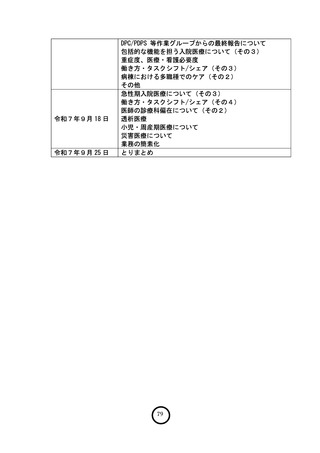よむ、つかう、まなぶ。
総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会における検討結果 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
に約6割、7日目頃までに約7割で安定していた。C項目該当手術実施例では、
術直後は4割程度で、術後7日目までに約7割に達しており、術直後は変化が
大きいと考えられた。
○ さらにA項目の変化との関係をみると、手術非実施症例の入院4日目以降、手
術実施症例の入院7日目以降は、A項目が変化しない場合にはB項目も変化し
ない患者の割合が多かった。A項目が3点以上変化した場合、B点数もA点数
と同じ方向の変化を示す患者の割合が多かった。
○ B項目は、疾患によって悪化した身体機能によるケアの必要性と、発症前から
の身体機能によるケアの必要性の双方を反映した指標であると考えられた。
(内科系症例における重症度、医療・看護必要度について)
○ 急性期一般入院料1において、外科系症例(手術に係るKコード算定症例)と
比較し、内科系症例(それ以外の症例)では、A得点2点以上、3点以上とな
る該当割合はいずれも低く、B得点3点以上の割合は高かった。
○ 救急搬送により入院した内科系症例の重症度、医療・看護必要度の該当割合は、
救急搬送ではない外科系症例の重症度、医療・看護必要度の該当割合と比較し
て、いずれの入院料においても低かった。
○ 救急搬送からの入院や緊急入院の約8割を内科系症例(手術をしない症例)が
占めていた。
○ これらの基礎データを踏まえ、内科系症例の重症度を適切に評価するための指
標の案について検討した。
○ 日本内科学会提出資料によれば、現行のA・C項目に内科系の診療負荷が高い
検査や処置を追加する案では、内科系症例と外科系症例の該当患者割合の差は、
24.3%から 22.8%に縮まった。
○ A・C項目を精緻化するのではなく、病棟や病院の負荷を直接的に医療・看護
必要度の底上げに用いる方法として、救急医療や緊急入院を評価する案を検討
した。令和6年度改定でA項目の「救急に入院を要する状態」の評価日数が5
日→2日に引き下げられており、単純に日数を戻すことによる入院を延長する
誘因となりえることを考慮して、「救急搬送応需件数を各病棟に按分した病床
あたり件数」や「協力対象施設入所者入院加算の病床あたり算定回数」に一定
の係数を乗じること等により連続的に評価し、当該病棟の基準該当割合に加算
する案について議論した。この方法に基づくと、基準該当割合への加算分が大
きい施設は、概ね内科系症例の割合が多い施設であった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ B項目について、基準から除外された急性期一般入院料1のB項目の測定につ
いては、現場の負担を考慮して、見直しが必要ではないかという病院団体から
の要望が出ており、B項目の測定が、病院にとってある程度負担になっている
32
術直後は4割程度で、術後7日目までに約7割に達しており、術直後は変化が
大きいと考えられた。
○ さらにA項目の変化との関係をみると、手術非実施症例の入院4日目以降、手
術実施症例の入院7日目以降は、A項目が変化しない場合にはB項目も変化し
ない患者の割合が多かった。A項目が3点以上変化した場合、B点数もA点数
と同じ方向の変化を示す患者の割合が多かった。
○ B項目は、疾患によって悪化した身体機能によるケアの必要性と、発症前から
の身体機能によるケアの必要性の双方を反映した指標であると考えられた。
(内科系症例における重症度、医療・看護必要度について)
○ 急性期一般入院料1において、外科系症例(手術に係るKコード算定症例)と
比較し、内科系症例(それ以外の症例)では、A得点2点以上、3点以上とな
る該当割合はいずれも低く、B得点3点以上の割合は高かった。
○ 救急搬送により入院した内科系症例の重症度、医療・看護必要度の該当割合は、
救急搬送ではない外科系症例の重症度、医療・看護必要度の該当割合と比較し
て、いずれの入院料においても低かった。
○ 救急搬送からの入院や緊急入院の約8割を内科系症例(手術をしない症例)が
占めていた。
○ これらの基礎データを踏まえ、内科系症例の重症度を適切に評価するための指
標の案について検討した。
○ 日本内科学会提出資料によれば、現行のA・C項目に内科系の診療負荷が高い
検査や処置を追加する案では、内科系症例と外科系症例の該当患者割合の差は、
24.3%から 22.8%に縮まった。
○ A・C項目を精緻化するのではなく、病棟や病院の負荷を直接的に医療・看護
必要度の底上げに用いる方法として、救急医療や緊急入院を評価する案を検討
した。令和6年度改定でA項目の「救急に入院を要する状態」の評価日数が5
日→2日に引き下げられており、単純に日数を戻すことによる入院を延長する
誘因となりえることを考慮して、「救急搬送応需件数を各病棟に按分した病床
あたり件数」や「協力対象施設入所者入院加算の病床あたり算定回数」に一定
の係数を乗じること等により連続的に評価し、当該病棟の基準該当割合に加算
する案について議論した。この方法に基づくと、基準該当割合への加算分が大
きい施設は、概ね内科系症例の割合が多い施設であった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ B項目について、基準から除外された急性期一般入院料1のB項目の測定につ
いては、現場の負担を考慮して、見直しが必要ではないかという病院団体から
の要望が出ており、B項目の測定が、病院にとってある程度負担になっている
32