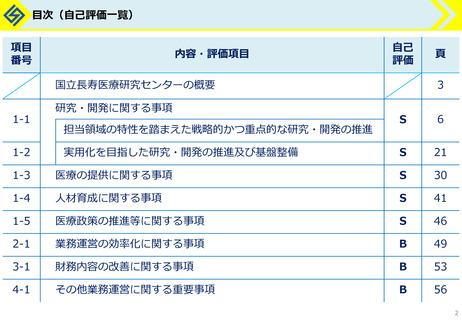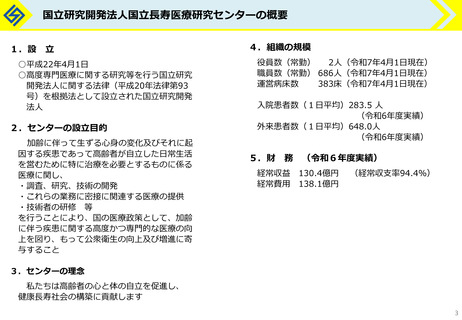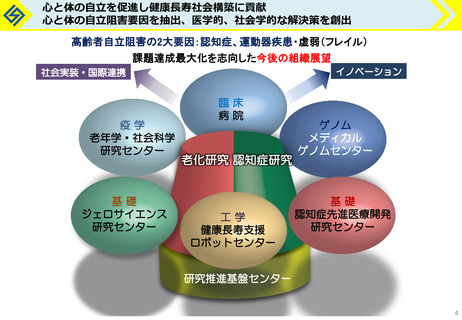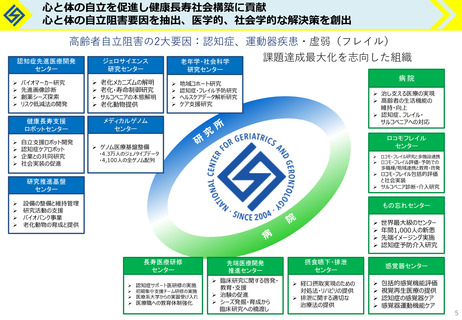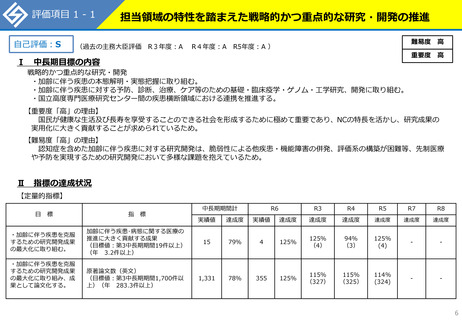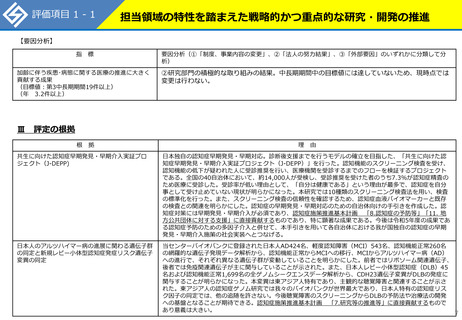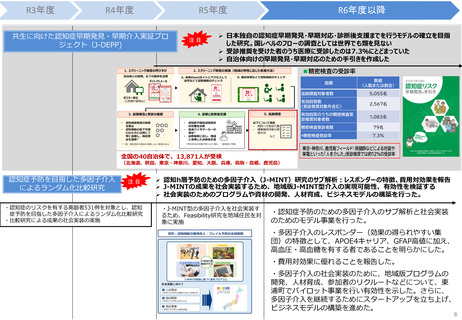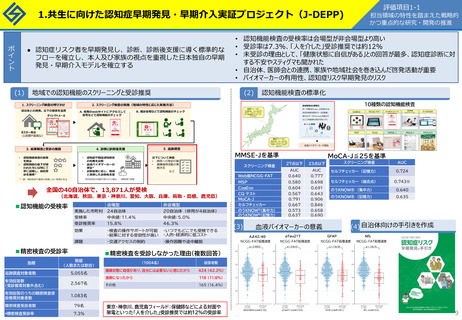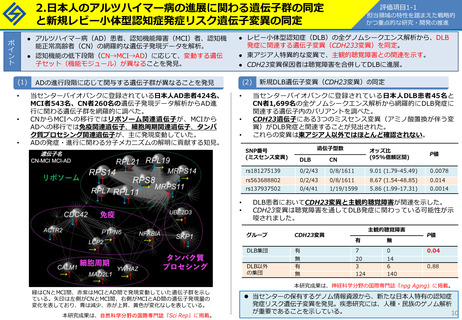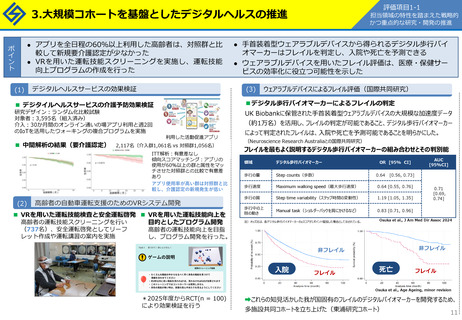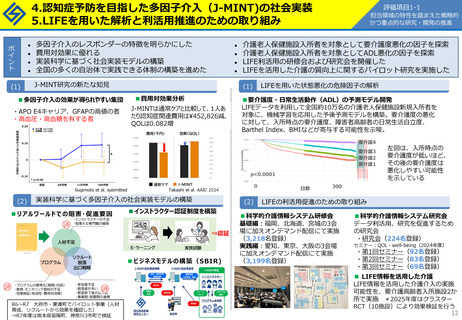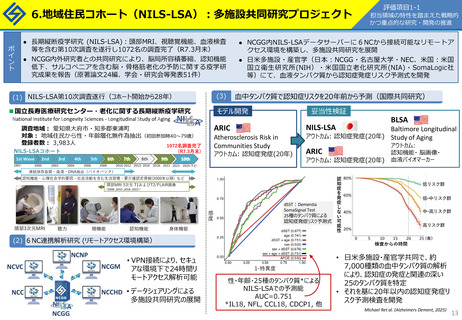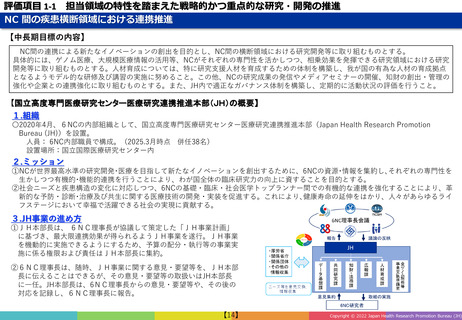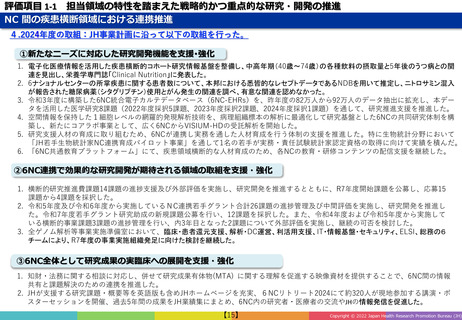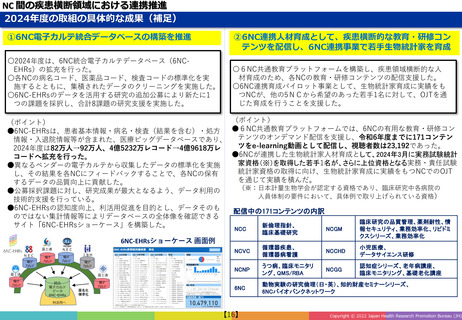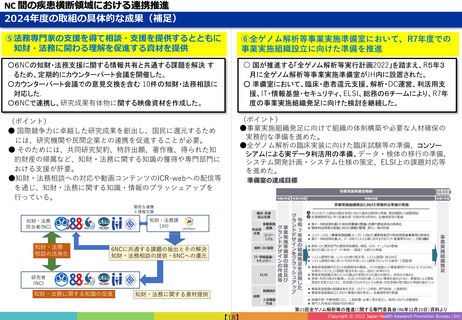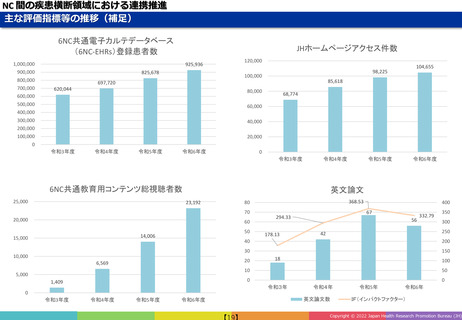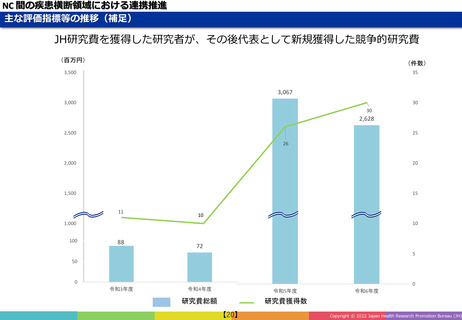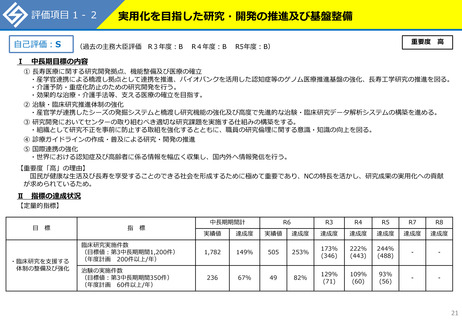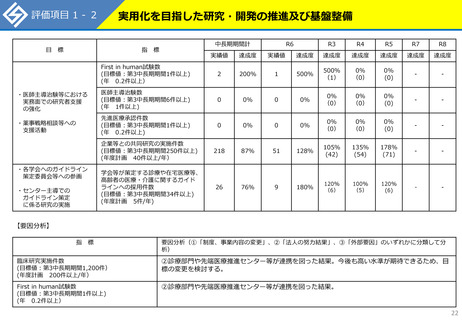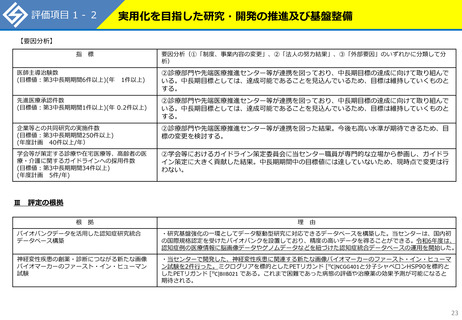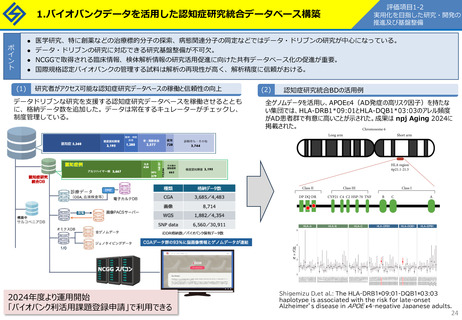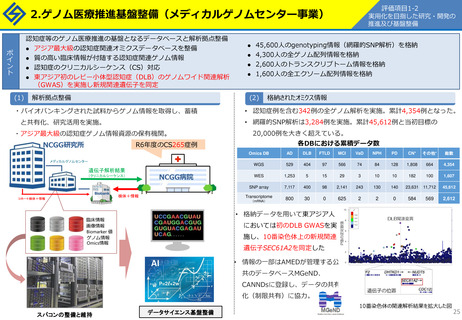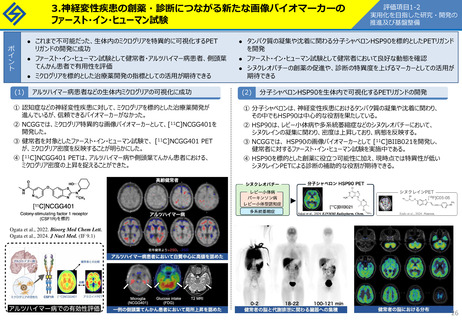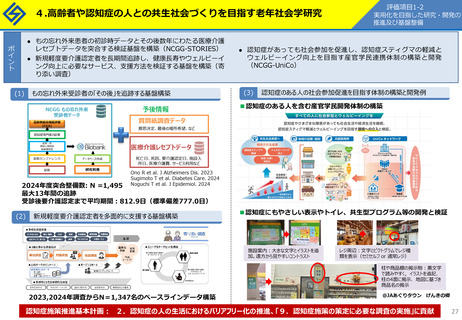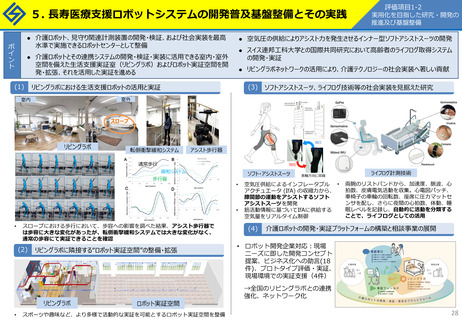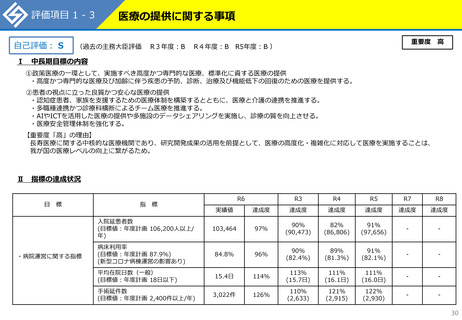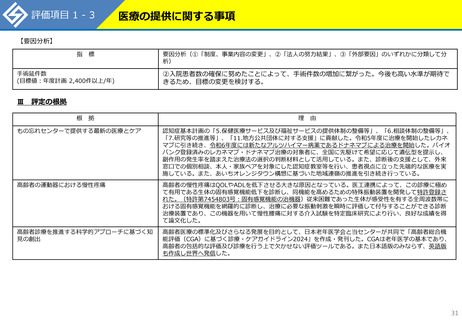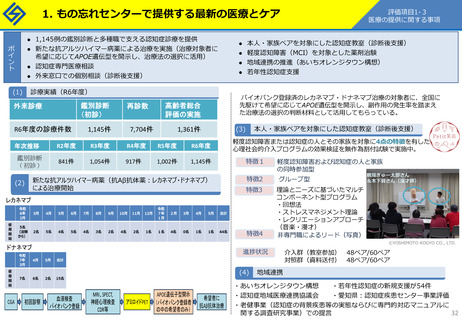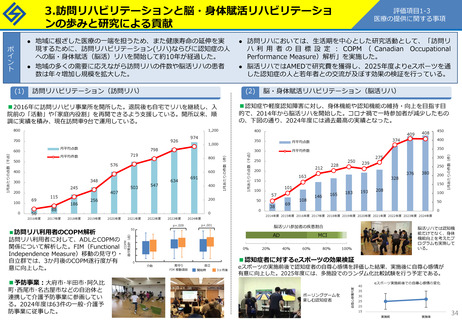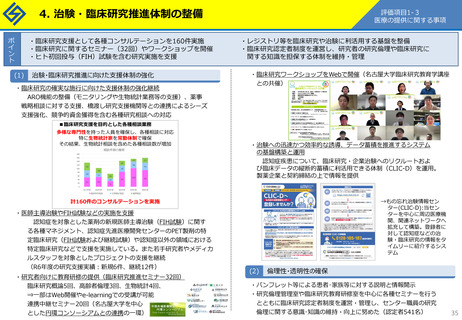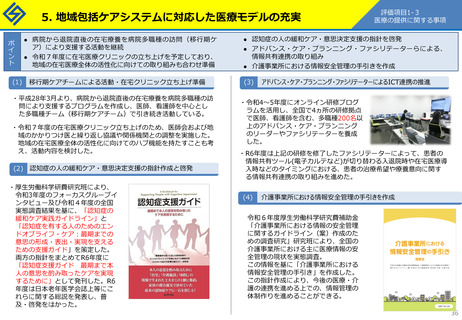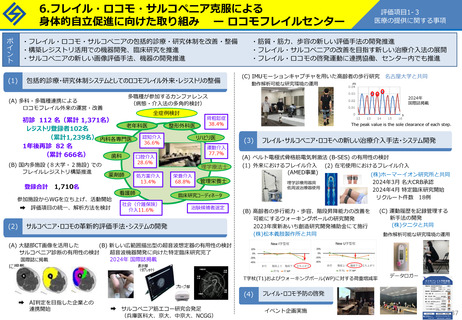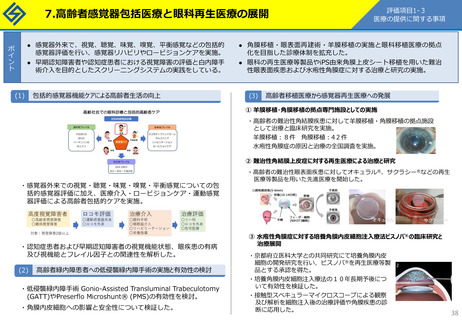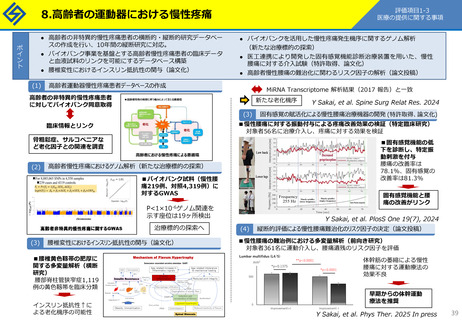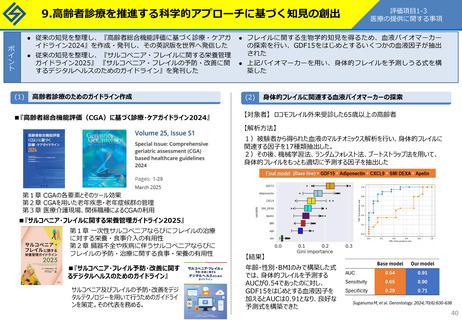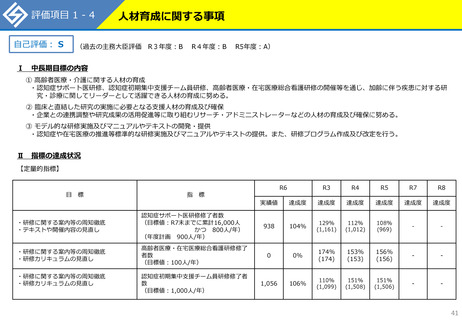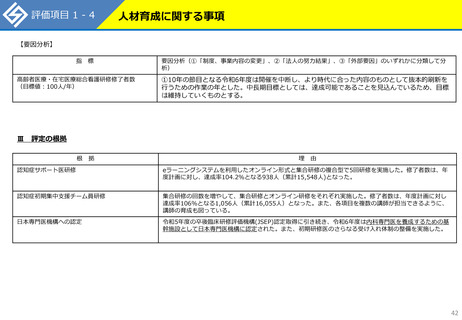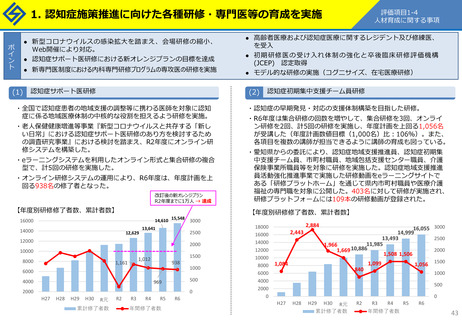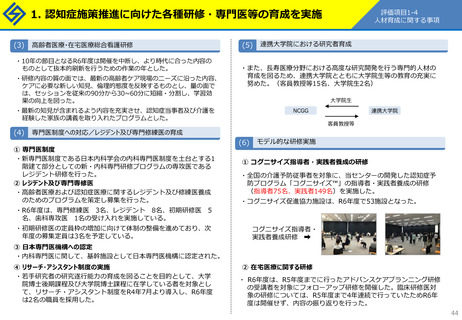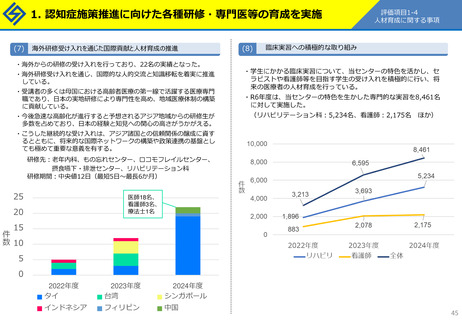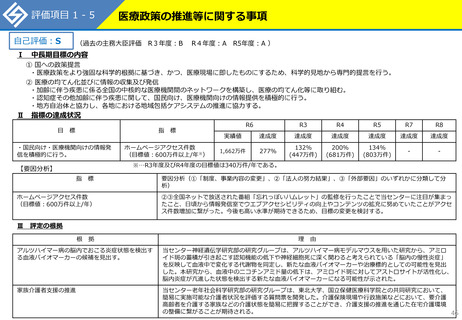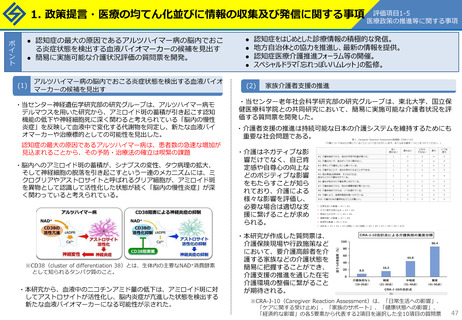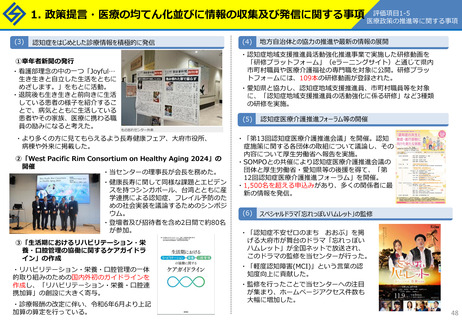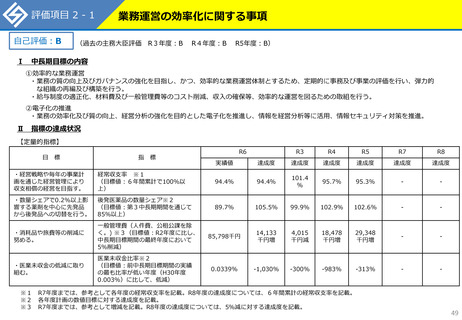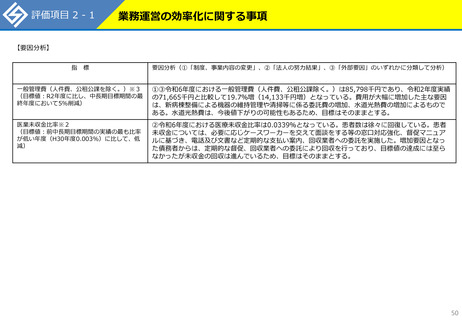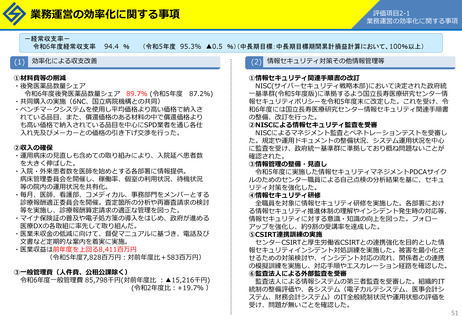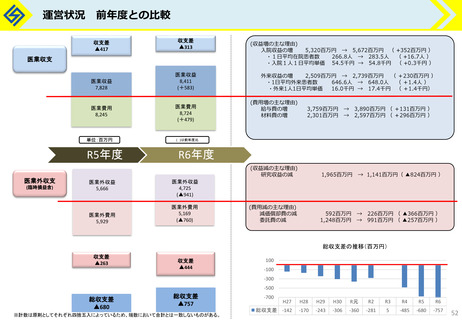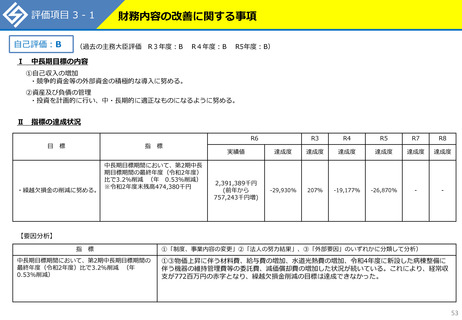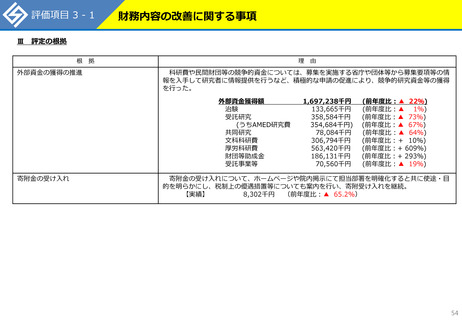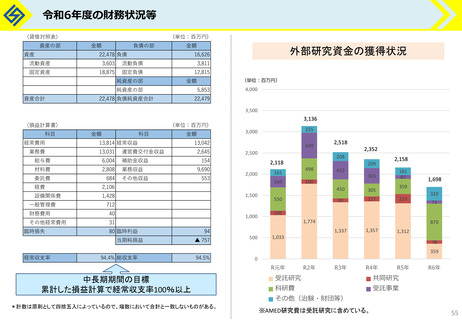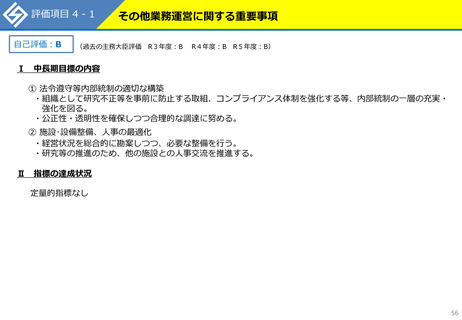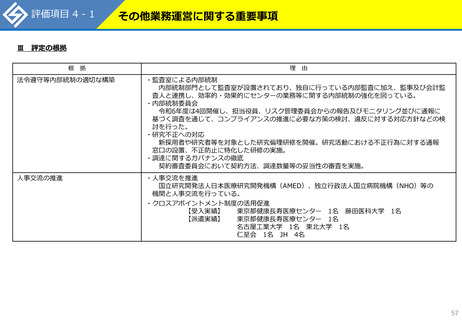よむ、つかう、まなぶ。
資料1‐2 令和6年度 業務実績概要説明資料 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |
| 出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
心と体の自立を促進し健康長寿社会構築に貢献
心と体の自立阻害要因を抽出、医学的、社会学的な解決策を創出
高齢者自立阻害の2大要因:認知症、運動器疾患・虚弱(フレイル)
課題達成最大化を志向した組織
認知症先進医療開発
ジェロサイエンス
老年学・社会科学
センター
➢ バイオマーカー研究
➢ 先進画像診断
➢ 創薬シーズ探索
➢ リスク低減法の開発
健康長寿支援
ロボットセンター
➢ 自立支援ロボット開発
➢ 認知症ケアロボット
➢ 企業との共同研究
➢ 社会実装の促進
研究センター
研究センター
➢ 老化メカニズムの解明
➢ 老化・寿命制御研究
➢ 地域コホート研究
➢ 老化動物提供
➢ ケア支援研究
➢ サルコペニアの本態解明
病院
➢ 認知症・フレイル予防研究
➢ ヘルスケアデータ解析研究
➢ 治し支える医療の実現
➢ 高齢者の生活機能の
維持・向上
➢ 認知症、フレイル・
サルコペニアへの対応
メディカルゲノム
センター
ロコモフレイル
センター
➢ ゲノム医療基盤整備
・4.3万人のジェノタイプデータ
・4,100人の全ゲノム配列
➢
➢ ロコモ・フレイル包括的評価
と社会実装
➢ サルコペニア診断・介入研究
研究推進基盤
センター
➢
➢
➢
➢
ロコモ・フレイル研究と多施設連携
➢ ロコモ・フレイル評価・予防での
多職種/地域連携と教育・啓発
設備の整備と維持管理
研究活動の支援
バイオバンク事業
老化動物の育成と提供
もの忘れセンター
➢ 世界最大級のセンター
➢ 年間1,000人の新患
➢ 先端イメージング実施
➢ 認知症予防介入研究
長寿医療研修
センター
➢ 認知症サポート医研修の実施
➢ 初期集中支援チーム研修の実施
➢ 医療系大学からの実習受け入れ
➢ 医療職への教育体制強化
先端医療開発
推進センター
摂食嚥下・排泄
センター
感覚器センター
➢ 臨床研究に関する啓発・
教育・支援
➢ 治験の促進
➢ シーズ発掘・育成から
臨床研究への橋渡し
➢ 経口摂取実現のための
対処法・リハビリの提供
➢ 排泄に関する適切な
治療法の提供
➢ 包括的感覚機能評価
➢ 視覚再生医療の提供
➢ 認知症の感覚器ケア
➢ 感覚器運動機能ケア
5
心と体の自立阻害要因を抽出、医学的、社会学的な解決策を創出
高齢者自立阻害の2大要因:認知症、運動器疾患・虚弱(フレイル)
課題達成最大化を志向した組織
認知症先進医療開発
ジェロサイエンス
老年学・社会科学
センター
➢ バイオマーカー研究
➢ 先進画像診断
➢ 創薬シーズ探索
➢ リスク低減法の開発
健康長寿支援
ロボットセンター
➢ 自立支援ロボット開発
➢ 認知症ケアロボット
➢ 企業との共同研究
➢ 社会実装の促進
研究センター
研究センター
➢ 老化メカニズムの解明
➢ 老化・寿命制御研究
➢ 地域コホート研究
➢ 老化動物提供
➢ ケア支援研究
➢ サルコペニアの本態解明
病院
➢ 認知症・フレイル予防研究
➢ ヘルスケアデータ解析研究
➢ 治し支える医療の実現
➢ 高齢者の生活機能の
維持・向上
➢ 認知症、フレイル・
サルコペニアへの対応
メディカルゲノム
センター
ロコモフレイル
センター
➢ ゲノム医療基盤整備
・4.3万人のジェノタイプデータ
・4,100人の全ゲノム配列
➢
➢ ロコモ・フレイル包括的評価
と社会実装
➢ サルコペニア診断・介入研究
研究推進基盤
センター
➢
➢
➢
➢
ロコモ・フレイル研究と多施設連携
➢ ロコモ・フレイル評価・予防での
多職種/地域連携と教育・啓発
設備の整備と維持管理
研究活動の支援
バイオバンク事業
老化動物の育成と提供
もの忘れセンター
➢ 世界最大級のセンター
➢ 年間1,000人の新患
➢ 先端イメージング実施
➢ 認知症予防介入研究
長寿医療研修
センター
➢ 認知症サポート医研修の実施
➢ 初期集中支援チーム研修の実施
➢ 医療系大学からの実習受け入れ
➢ 医療職への教育体制強化
先端医療開発
推進センター
摂食嚥下・排泄
センター
感覚器センター
➢ 臨床研究に関する啓発・
教育・支援
➢ 治験の促進
➢ シーズ発掘・育成から
臨床研究への橋渡し
➢ 経口摂取実現のための
対処法・リハビリの提供
➢ 排泄に関する適切な
治療法の提供
➢ 包括的感覚機能評価
➢ 視覚再生医療の提供
➢ 認知症の感覚器ケア
➢ 感覚器運動機能ケア
5