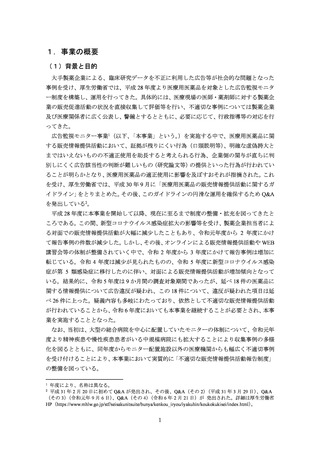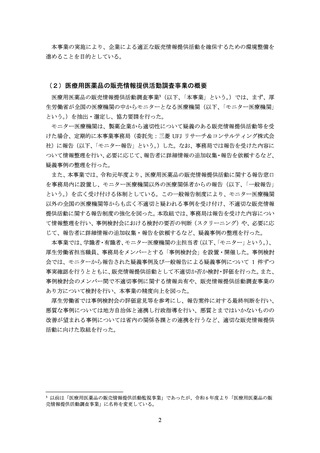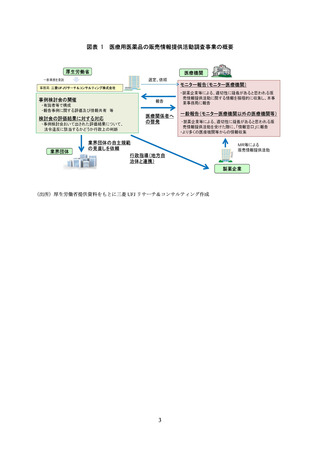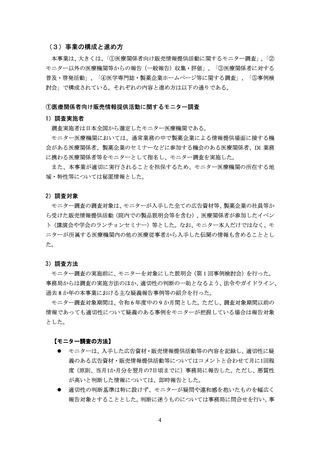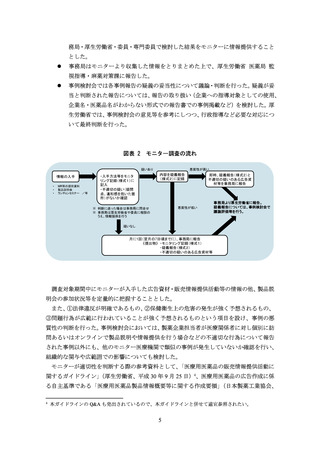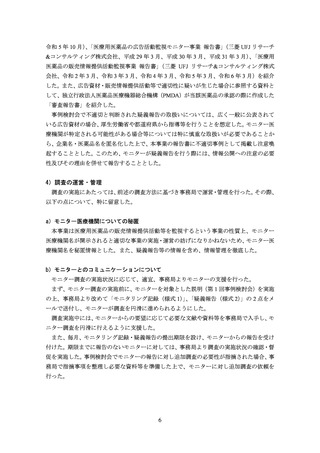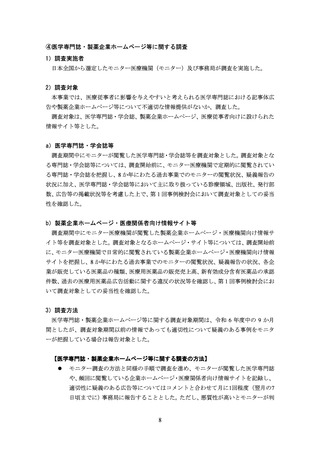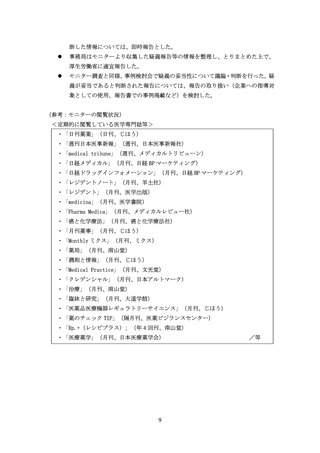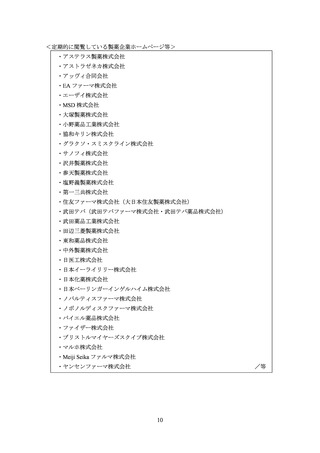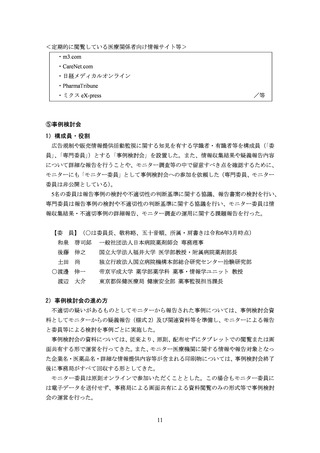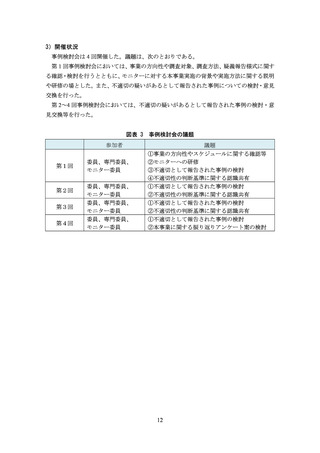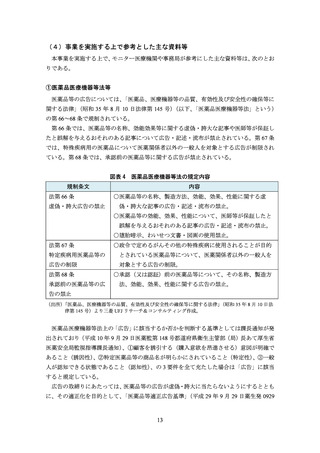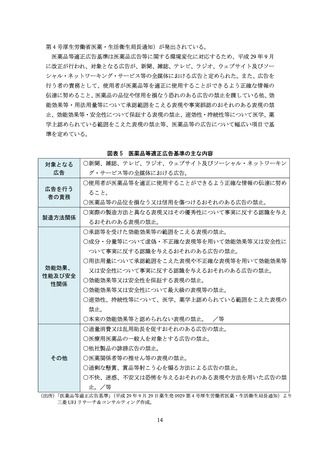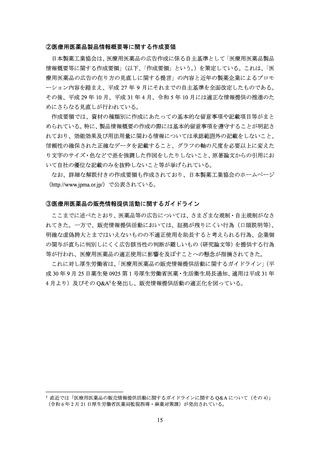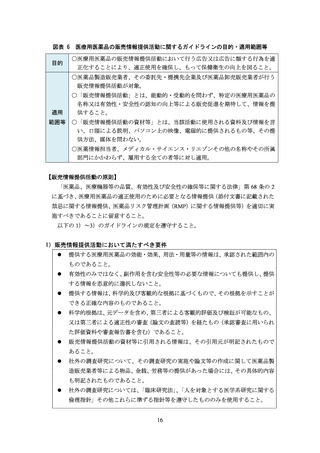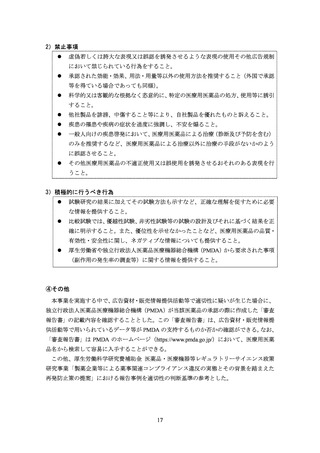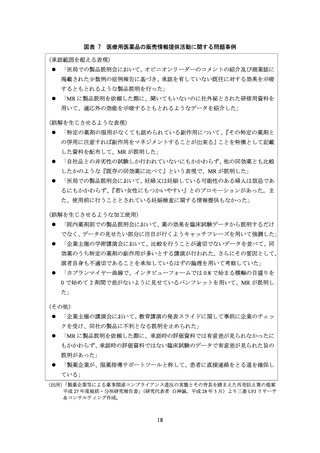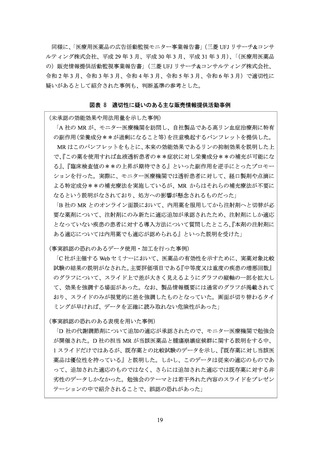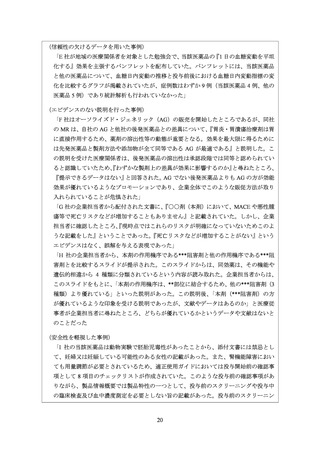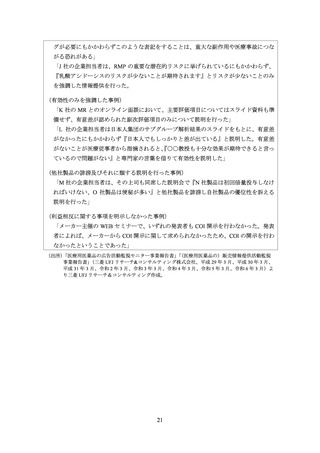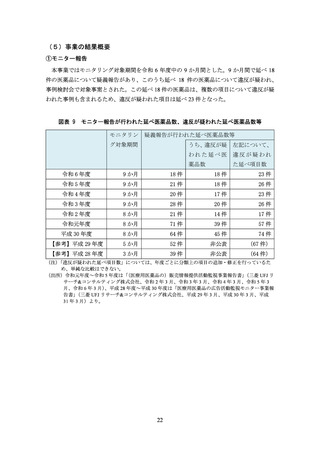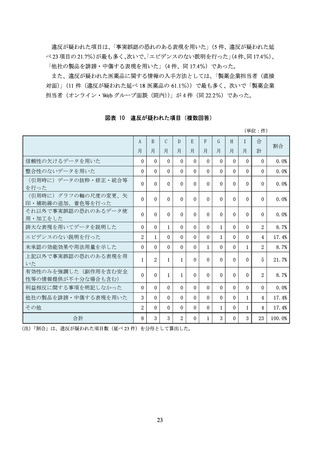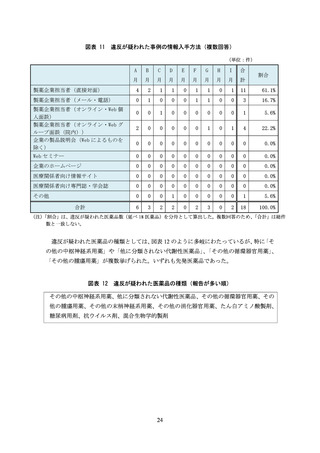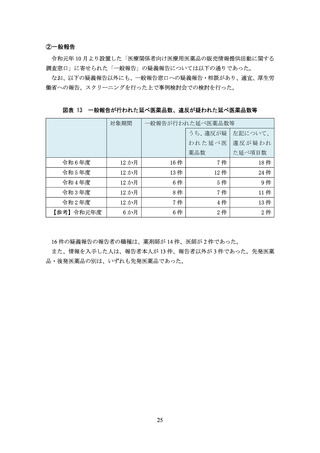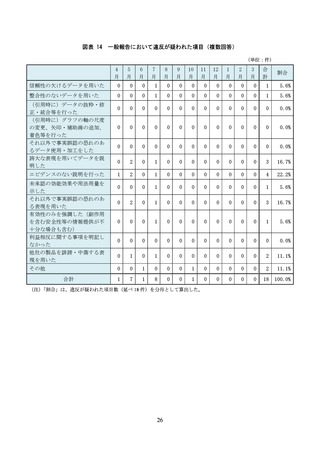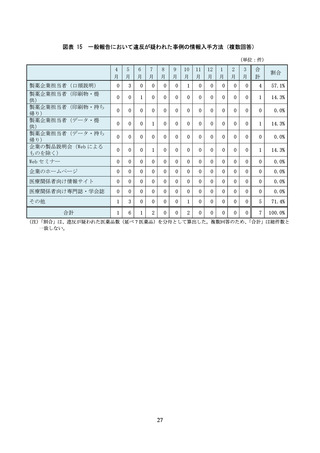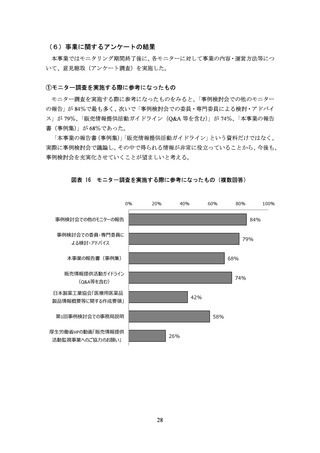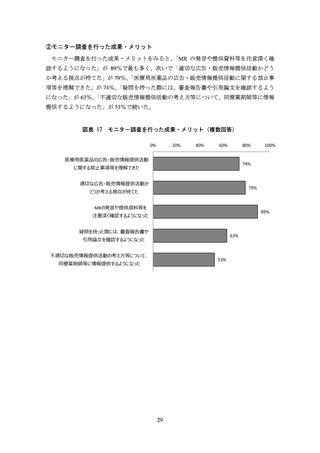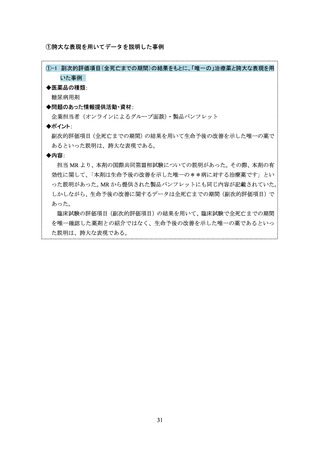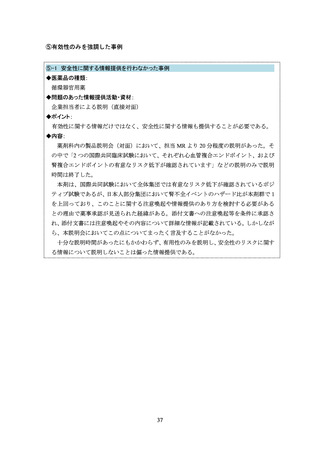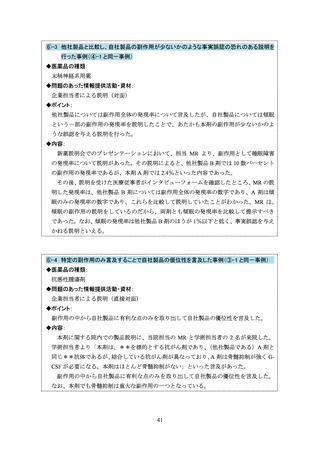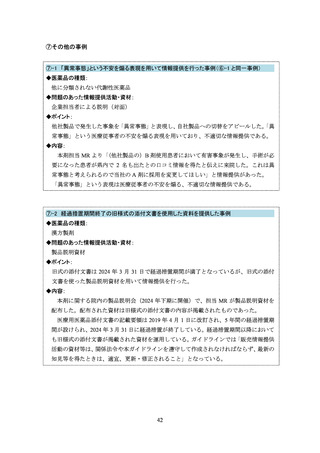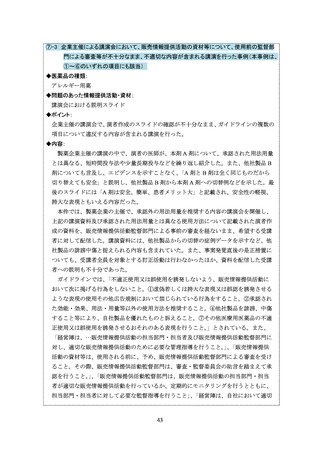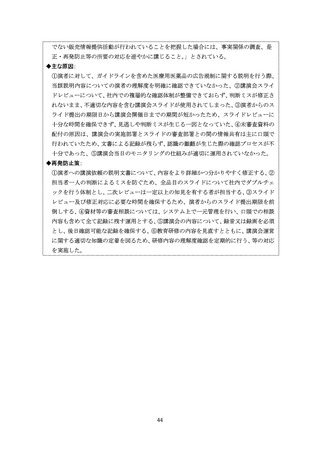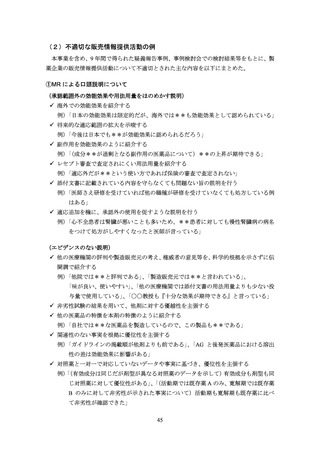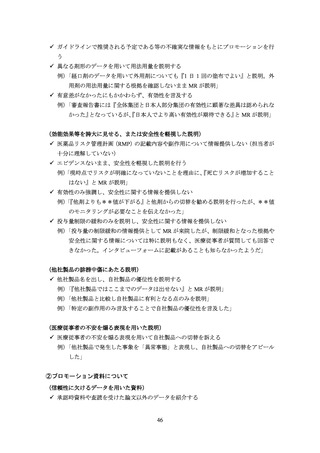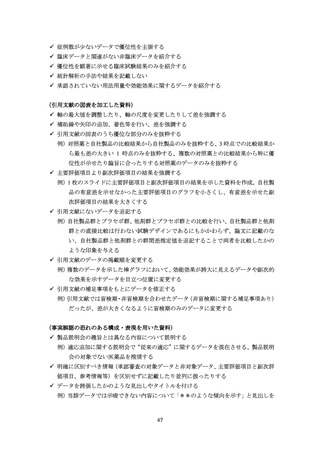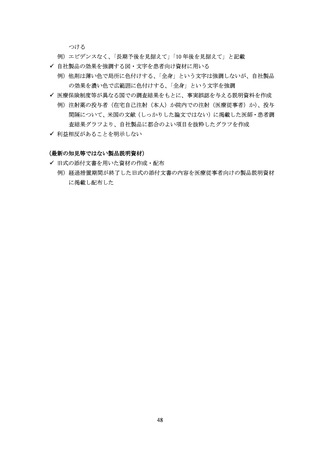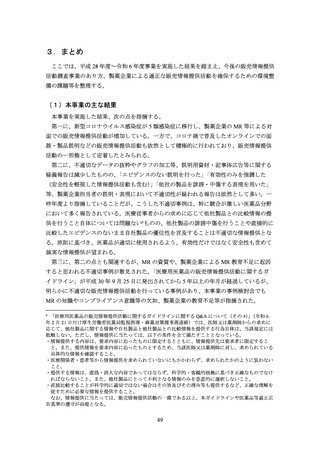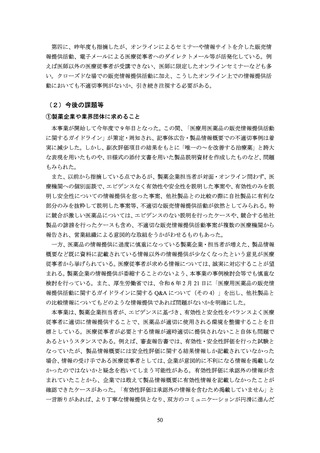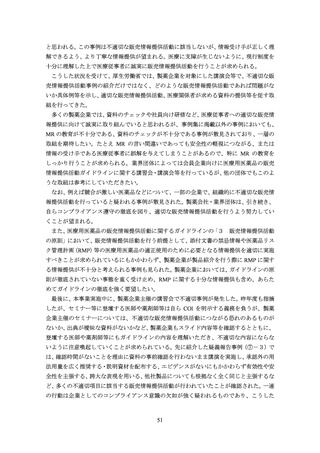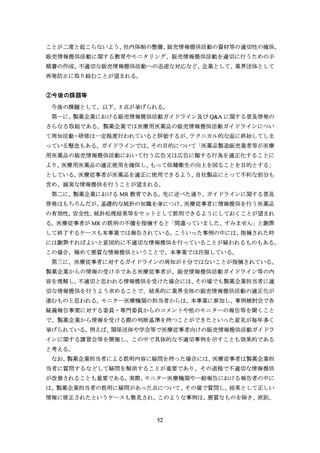よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |
| 出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ことが二度と起こらないよう、社内体制の整備、販売情報提供活動の資材等の適切性の確保、
販売情報提供活動に関する教育やモニタリング、販売情報提供活動を適切に行うための手
順書の作成、不適切な販売情報提供活動への迅速な対応など、企業として、業界団体として
再発防止に取り組むことが望まれる。
②今後の課題等
今後の課題として、以下、5 点が挙げられる。
第一に、製薬企業における販売情報提供活動ガイドライン及び Q&A に関する普及啓発の
さらなる取組である。製薬企業では医療用医薬品の販売情報提供活動ガイドラインについ
て周知活動・研修は一定程度行われていると評価するが、テクニカル的な面に終始してしま
っている懸念もある。ガイドラインでは、その目的について「医薬品製造販売業者等が医療
用医薬品の販売情報提供活動において行う広告又は広告に類する行為を適正化することに
より、医療用医薬品の適正使用を確保し、もって保健衛生の向上を図ることを目的とする」
としている。医療従事者が医薬品を適正に使用できるよう、自社製品にとって不利な部分も
含め、誠実な情報提供を行うことが望まれる。
第二に、製薬企業における MR 教育である。先に述べた通り、ガイドラインに関する普及
啓発はもちろんだが、基礎的な統計の知識を身につけ、医療従事者に情報提供を行う医薬品
の有効性、安全性、統計処理結果等をセットとして説明できるようにしておくことが望まれ
る。医療従事者が MR の説明の不備を指摘すると「間違っていました、すみません」と謝罪
して終了するケースも本事業では報告されている。こういった事例の中には、指摘された時
には謝罪すればよいと意図的に不適切な情報提供を行っていることが疑われるものもある。
この場合、極めて悪質な情報提供ということで、本事業では注視している。
第三に、医療従事者に対するガイドラインの周知が十分ではないことが指摘されている。
製薬企業からの情報の受け手である医療従事者が、販売情報提供活動ガイドライン等の内
容を理解し、不適切と思われる情報提供を受けた場合には、その場でも製薬企業担当者に適
切な情報提供を行うよう求めることで、結果的に業界全体の販売情報提供活動の適正化が
進むものと思われる。モニター医療機関の担当者からは、本事業に参加し、事例検討会で各
疑義報告事案に対する委員・専門委員からのコメントや他のモニターの報告等を聞くこと
で、製薬企業から情報を受ける際の判断基準を持つことができたといった意見が毎年多く
挙げられている。例えば、関係団体や学会等で医療従事者向けの販売情報提供活動ガイドラ
インに関する講習会等を開催し、この中で具体的な不適切事例を示すことも効果的である
と考える。
なお、製薬企業担当者による説明内容に疑問を持った場合には、医療従事者は製薬企業担
当者に質問するなどして疑問を解消することが重要であり、その過程で不適切な情報提供
が改善されることも重要である。実際、モニター医療機関や一般報告における報告者の中に
は、製薬企業担当者の説明に疑問があった点について、その場で質問し、結果として正しい
情報に修正されたというケースも散見され、このような事例は、悪質なものを除き、原則、
52
販売情報提供活動に関する教育やモニタリング、販売情報提供活動を適切に行うための手
順書の作成、不適切な販売情報提供活動への迅速な対応など、企業として、業界団体として
再発防止に取り組むことが望まれる。
②今後の課題等
今後の課題として、以下、5 点が挙げられる。
第一に、製薬企業における販売情報提供活動ガイドライン及び Q&A に関する普及啓発の
さらなる取組である。製薬企業では医療用医薬品の販売情報提供活動ガイドラインについ
て周知活動・研修は一定程度行われていると評価するが、テクニカル的な面に終始してしま
っている懸念もある。ガイドラインでは、その目的について「医薬品製造販売業者等が医療
用医薬品の販売情報提供活動において行う広告又は広告に類する行為を適正化することに
より、医療用医薬品の適正使用を確保し、もって保健衛生の向上を図ることを目的とする」
としている。医療従事者が医薬品を適正に使用できるよう、自社製品にとって不利な部分も
含め、誠実な情報提供を行うことが望まれる。
第二に、製薬企業における MR 教育である。先に述べた通り、ガイドラインに関する普及
啓発はもちろんだが、基礎的な統計の知識を身につけ、医療従事者に情報提供を行う医薬品
の有効性、安全性、統計処理結果等をセットとして説明できるようにしておくことが望まれ
る。医療従事者が MR の説明の不備を指摘すると「間違っていました、すみません」と謝罪
して終了するケースも本事業では報告されている。こういった事例の中には、指摘された時
には謝罪すればよいと意図的に不適切な情報提供を行っていることが疑われるものもある。
この場合、極めて悪質な情報提供ということで、本事業では注視している。
第三に、医療従事者に対するガイドラインの周知が十分ではないことが指摘されている。
製薬企業からの情報の受け手である医療従事者が、販売情報提供活動ガイドライン等の内
容を理解し、不適切と思われる情報提供を受けた場合には、その場でも製薬企業担当者に適
切な情報提供を行うよう求めることで、結果的に業界全体の販売情報提供活動の適正化が
進むものと思われる。モニター医療機関の担当者からは、本事業に参加し、事例検討会で各
疑義報告事案に対する委員・専門委員からのコメントや他のモニターの報告等を聞くこと
で、製薬企業から情報を受ける際の判断基準を持つことができたといった意見が毎年多く
挙げられている。例えば、関係団体や学会等で医療従事者向けの販売情報提供活動ガイドラ
インに関する講習会等を開催し、この中で具体的な不適切事例を示すことも効果的である
と考える。
なお、製薬企業担当者による説明内容に疑問を持った場合には、医療従事者は製薬企業担
当者に質問するなどして疑問を解消することが重要であり、その過程で不適切な情報提供
が改善されることも重要である。実際、モニター医療機関や一般報告における報告者の中に
は、製薬企業担当者の説明に疑問があった点について、その場で質問し、結果として正しい
情報に修正されたというケースも散見され、このような事例は、悪質なものを除き、原則、
52