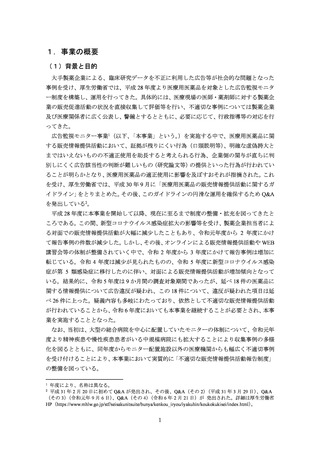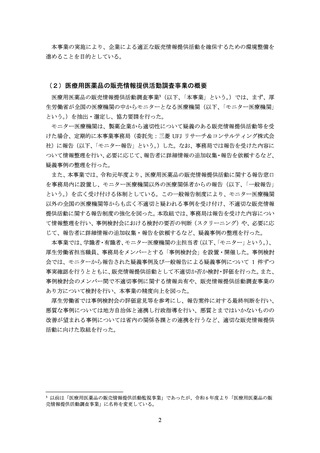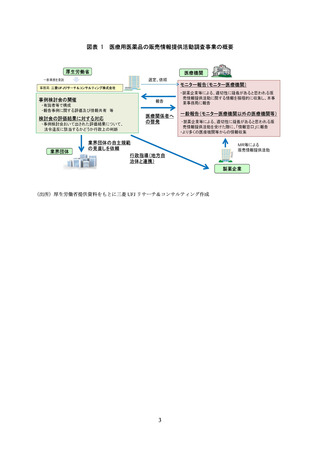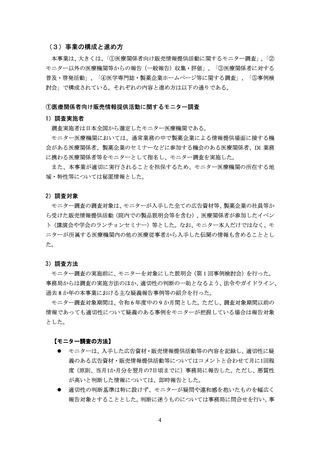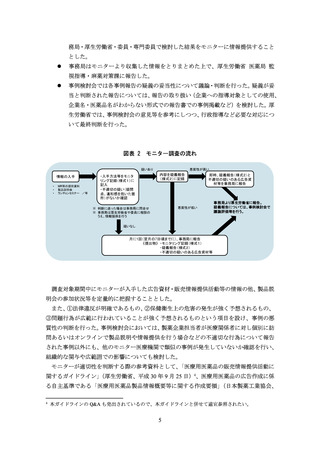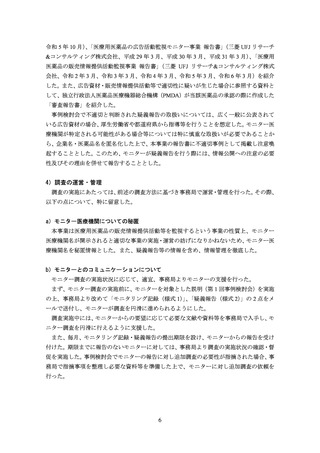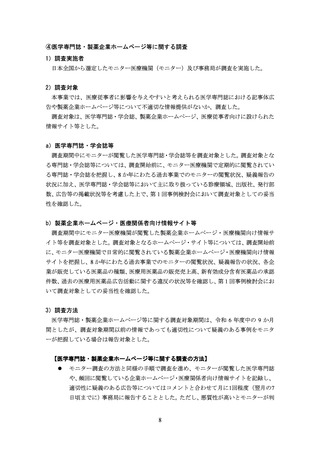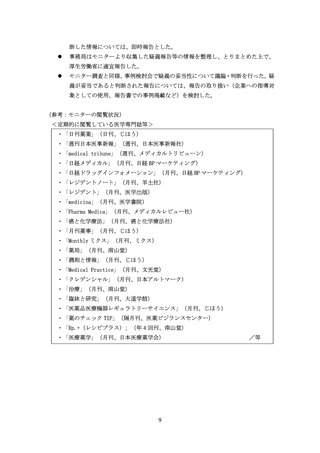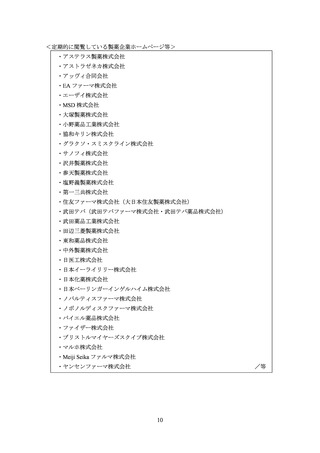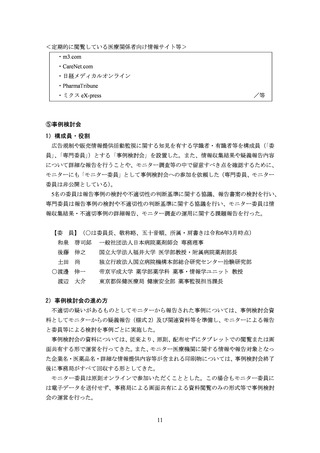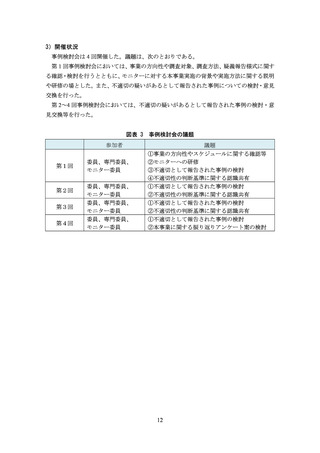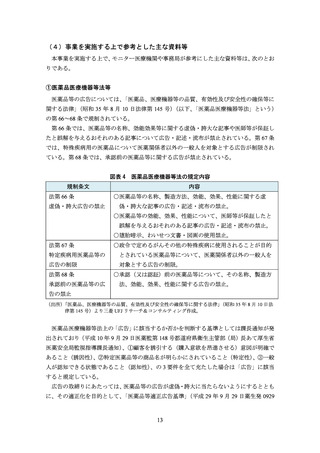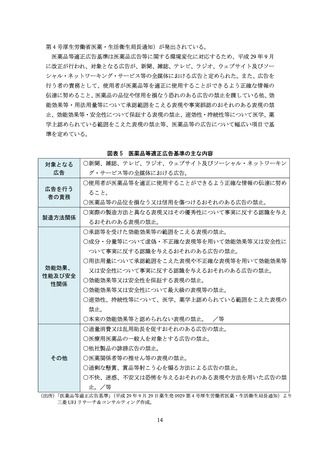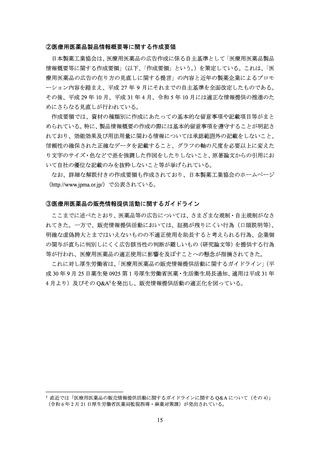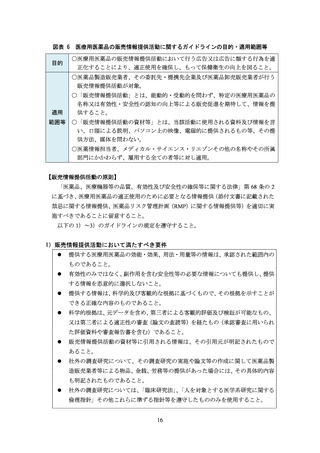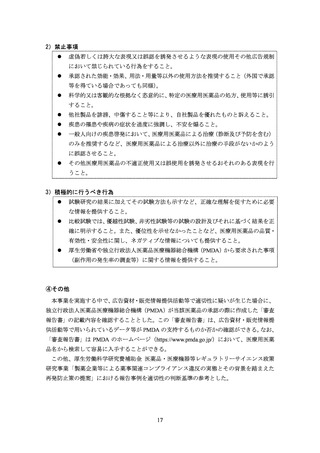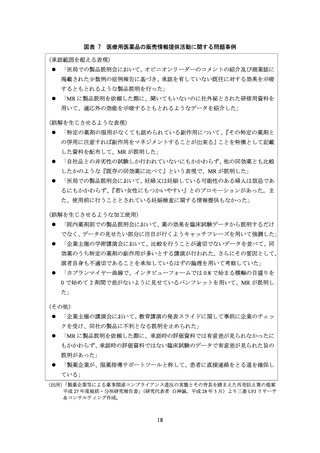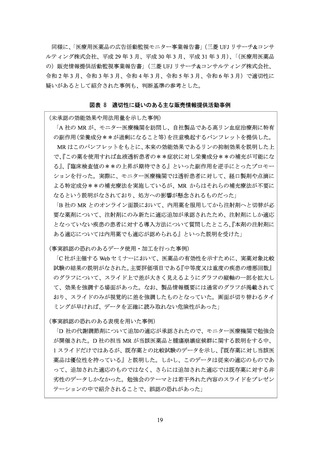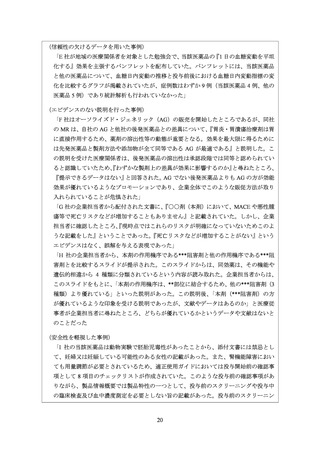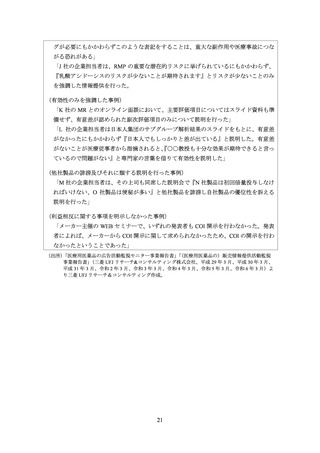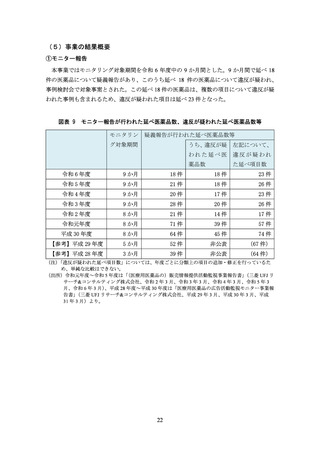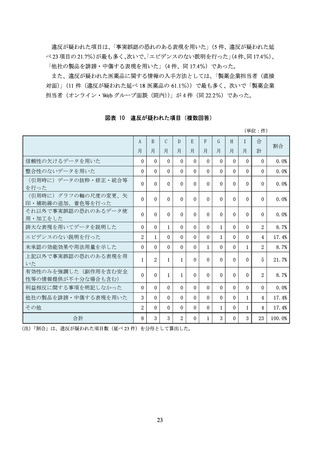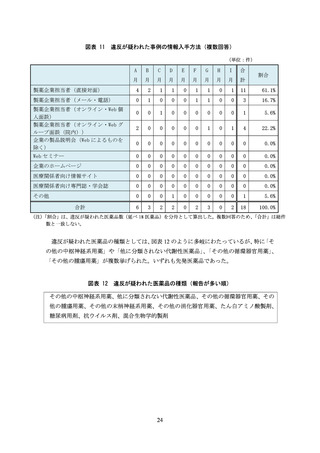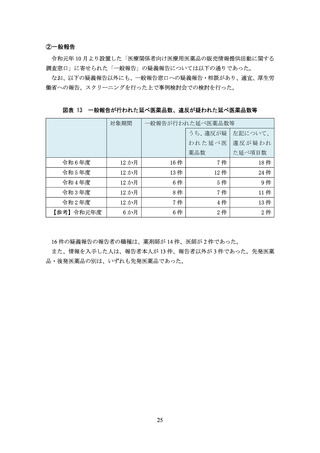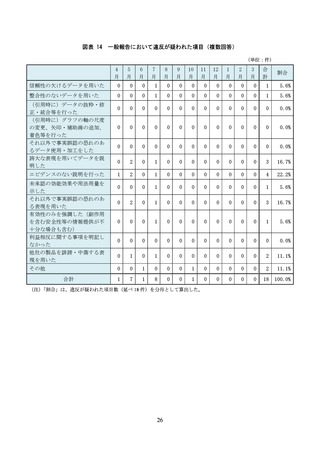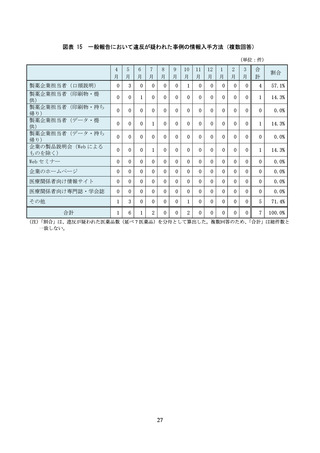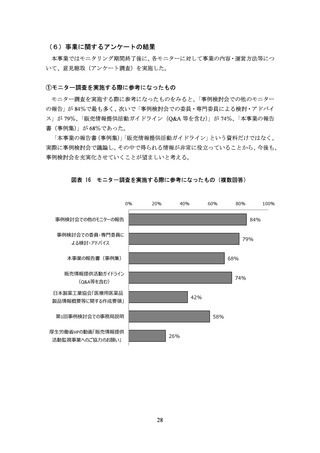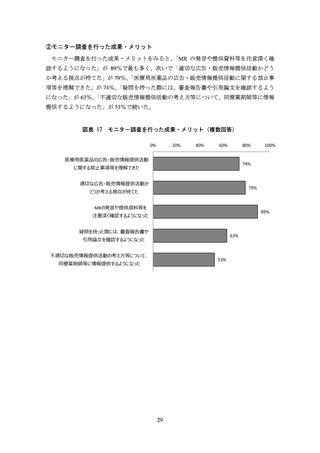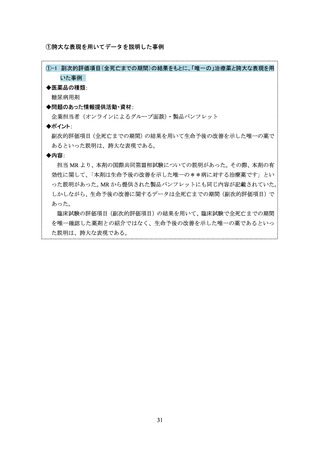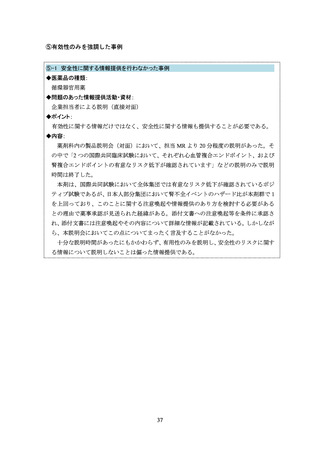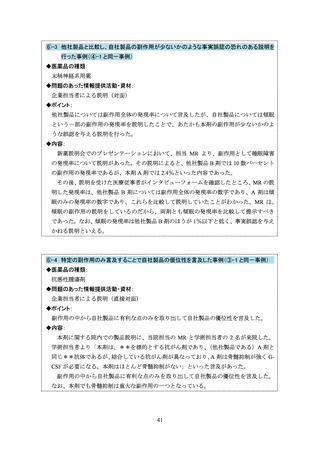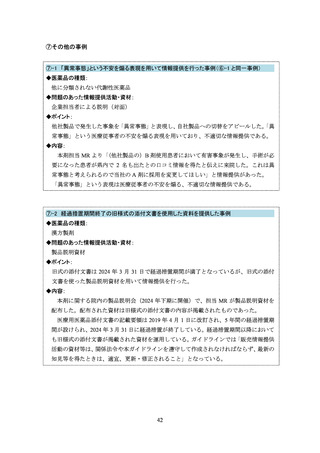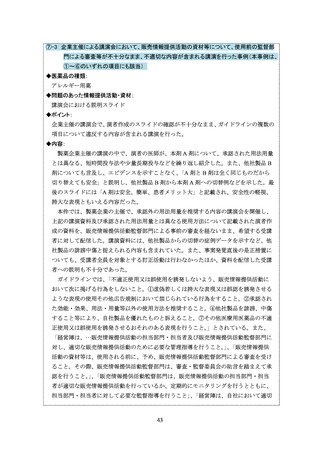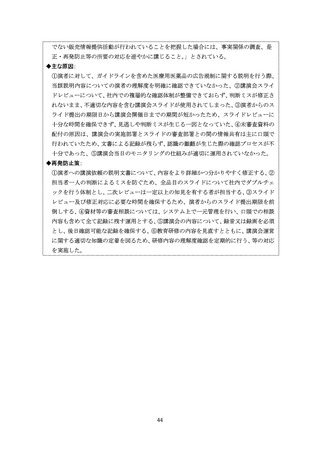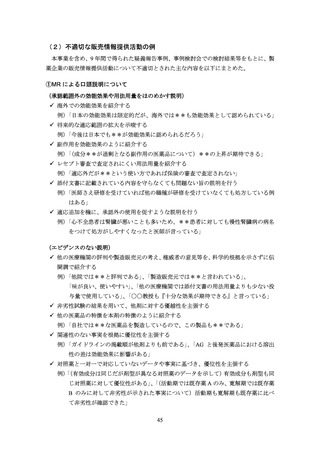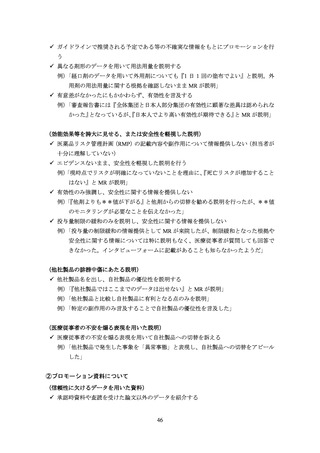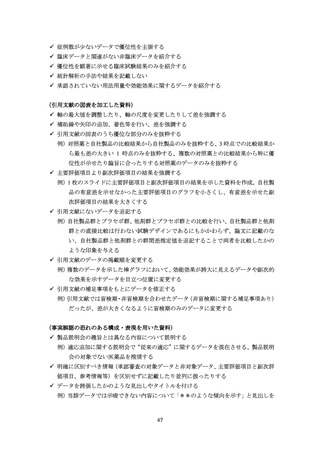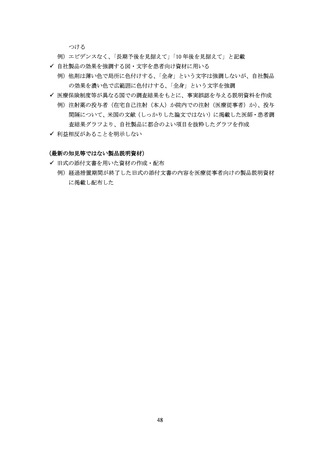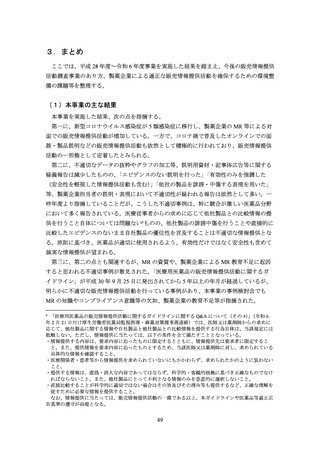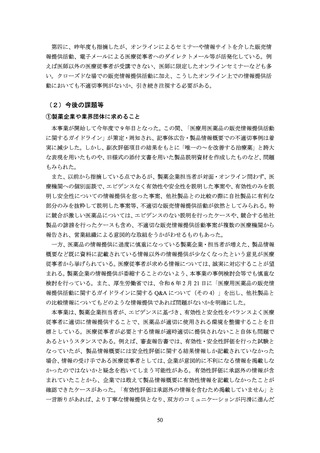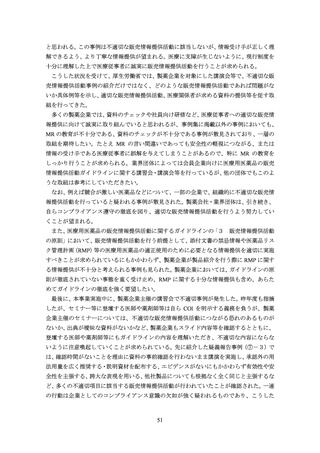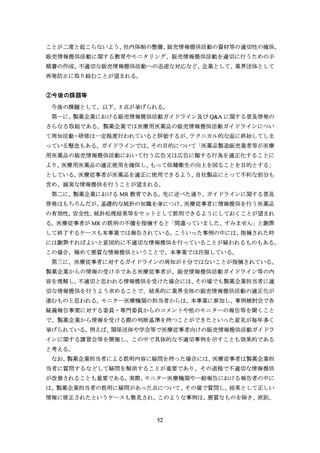よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度 医療用医薬品の販売情報提供活動調査事業報告書 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0725-1.html |
| 出典情報 | 令和6年度販売情報提供活動調査事業報告書について(7/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第四に、昨年度も指摘したが、オンラインによるセミナーや情報サイトを介した販売情
報提供活動、電子メールによる医療従事者へのダイレクトメール等が活発化している。例
えば医師以外の医療従事者が受講できない、医師に限定したオンラインセミナーなども多
い。クローズドな場での販売情報提供活動に加え、こうしたオンライン上での情報提供活
動においても不適切事例がないか、引き続き注視する必要がある。
(2)今後の課題等
①製薬企業や業界団体に求めること
本事業が開始して今年度で 9 年目となった。この間、「医療用医薬品の販売情報提供活動
に関するガイドライン」が策定・周知され、記事体広告・製品情報概要での不適切事例は着
実に減少した。しかし、副次評価項目の結果をもとに「唯一の~を改善する治療薬」と誇大
な表現を用いたものや、旧様式の添付文書を用いた製品説明資材を作成したものなど、問題
もみられた。
また、以前から指摘している点であるが、製薬企業担当者が対面・オンライン問わず、医
療機関への個別面談で、エビデンスなく有効性や安全性を説明した事案や、有効性のみを説
明し安全性についての情報提供を怠った事案、他社製品との比較の際に自社製品に有利な
部分のみを抜粋して説明した事案等、不適切な販売情報提供活動が依然としてみられる。特
に競合が激しい医薬品については、エビデンスのない説明を行ったケースや、競合する他社
製品の誹謗を行ったケースも含め、不適切な販売情報提供活動事案が複数の医療機関から
報告され、営業組織による意図的な取組をうかがわせるものもあった。
一方、医薬品の情報提供に過度に慎重になっている製薬企業・担当者が増えた、製品情報
概要など既に資料に記載されている情報以外の情報提供が少なくなったという意見が医療
従事者から挙げられている。医療従事者が求める情報については、誠実に対応することが望
まれる。製薬企業の情報提供が委縮することのないよう、本事業の事例検討会等でも慎重な
検討を行っている。また、厚生労働省では、令和 6 年 2 月 21 日に「医療用医薬品の販売情
報提供活動に関するガイドラインに関する Q&A について(その 4)」を出し、他社製品と
の比較情報についてもどのような情報提供であれば問題がないかを明確にした。
本事業は、製薬企業担当者が、エビデンスに基づき、有効性と安全性をバランスよく医療
従事者に適切に情報提供することで、医薬品が適切に使用される環境を整備することを目
標としている。医療従事者が必要とする情報が適時適切に提供されないこと自体も問題で
あるというスタンスである。例えば、審査報告書では、有効性・安全性評価を行った試験と
なっていたが、製品情報概要には安全性評価に関する結果情報しか記載されていなかった
場合、情報の受け手である医療従事者としては、企業が意図的に不利になる情報を掲載しな
かったのではないかと疑念を抱いてしまう可能性がある。有効性評価に承認外の情報が含
まれていたことから、企業では敢えて製品情報概要に有効性情報を記載しなかったことが
確認できたケースがあった。「有効性評価は承認外の情報を含むため掲載していません」と
一言断りがあれば、より丁寧な情報提供となり、双方のコミュニケーションが円滑に進んだ
50
報提供活動、電子メールによる医療従事者へのダイレクトメール等が活発化している。例
えば医師以外の医療従事者が受講できない、医師に限定したオンラインセミナーなども多
い。クローズドな場での販売情報提供活動に加え、こうしたオンライン上での情報提供活
動においても不適切事例がないか、引き続き注視する必要がある。
(2)今後の課題等
①製薬企業や業界団体に求めること
本事業が開始して今年度で 9 年目となった。この間、「医療用医薬品の販売情報提供活動
に関するガイドライン」が策定・周知され、記事体広告・製品情報概要での不適切事例は着
実に減少した。しかし、副次評価項目の結果をもとに「唯一の~を改善する治療薬」と誇大
な表現を用いたものや、旧様式の添付文書を用いた製品説明資材を作成したものなど、問題
もみられた。
また、以前から指摘している点であるが、製薬企業担当者が対面・オンライン問わず、医
療機関への個別面談で、エビデンスなく有効性や安全性を説明した事案や、有効性のみを説
明し安全性についての情報提供を怠った事案、他社製品との比較の際に自社製品に有利な
部分のみを抜粋して説明した事案等、不適切な販売情報提供活動が依然としてみられる。特
に競合が激しい医薬品については、エビデンスのない説明を行ったケースや、競合する他社
製品の誹謗を行ったケースも含め、不適切な販売情報提供活動事案が複数の医療機関から
報告され、営業組織による意図的な取組をうかがわせるものもあった。
一方、医薬品の情報提供に過度に慎重になっている製薬企業・担当者が増えた、製品情報
概要など既に資料に記載されている情報以外の情報提供が少なくなったという意見が医療
従事者から挙げられている。医療従事者が求める情報については、誠実に対応することが望
まれる。製薬企業の情報提供が委縮することのないよう、本事業の事例検討会等でも慎重な
検討を行っている。また、厚生労働省では、令和 6 年 2 月 21 日に「医療用医薬品の販売情
報提供活動に関するガイドラインに関する Q&A について(その 4)」を出し、他社製品と
の比較情報についてもどのような情報提供であれば問題がないかを明確にした。
本事業は、製薬企業担当者が、エビデンスに基づき、有効性と安全性をバランスよく医療
従事者に適切に情報提供することで、医薬品が適切に使用される環境を整備することを目
標としている。医療従事者が必要とする情報が適時適切に提供されないこと自体も問題で
あるというスタンスである。例えば、審査報告書では、有効性・安全性評価を行った試験と
なっていたが、製品情報概要には安全性評価に関する結果情報しか記載されていなかった
場合、情報の受け手である医療従事者としては、企業が意図的に不利になる情報を掲載しな
かったのではないかと疑念を抱いてしまう可能性がある。有効性評価に承認外の情報が含
まれていたことから、企業では敢えて製品情報概要に有効性情報を記載しなかったことが
確認できたケースがあった。「有効性評価は承認外の情報を含むため掲載していません」と
一言断りがあれば、より丁寧な情報提供となり、双方のコミュニケーションが円滑に進んだ
50