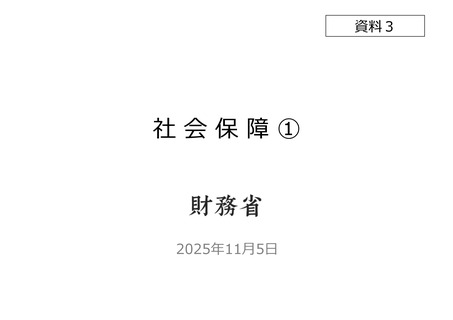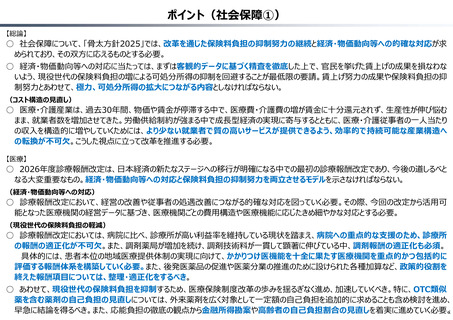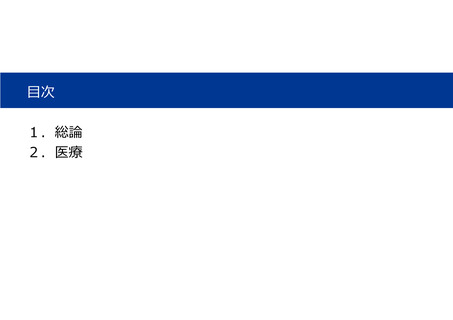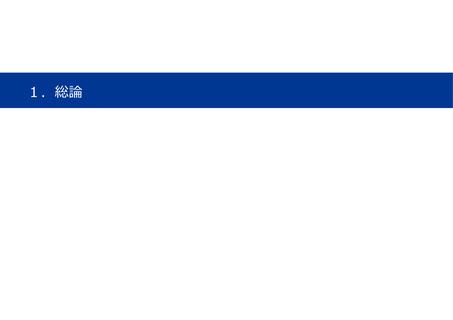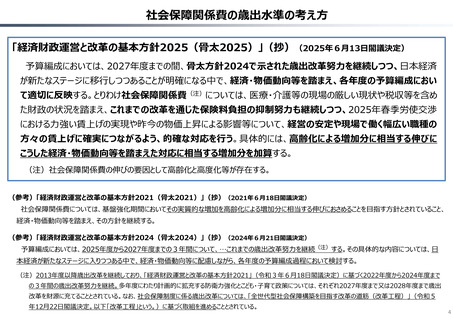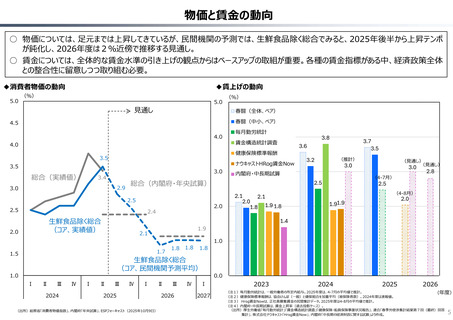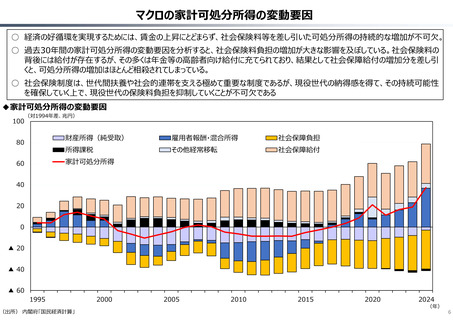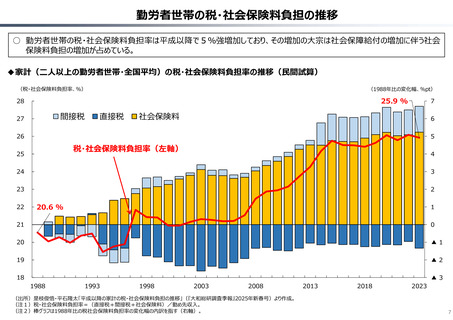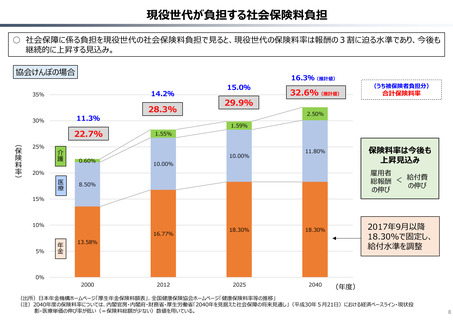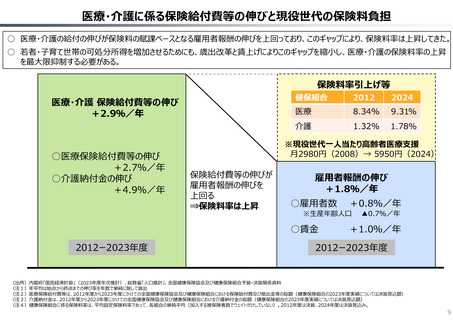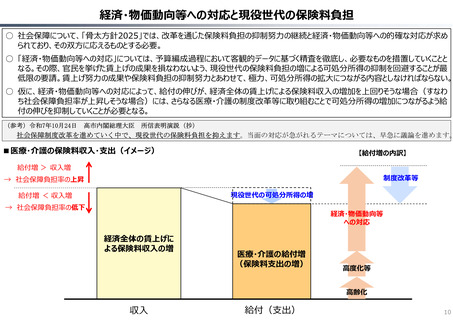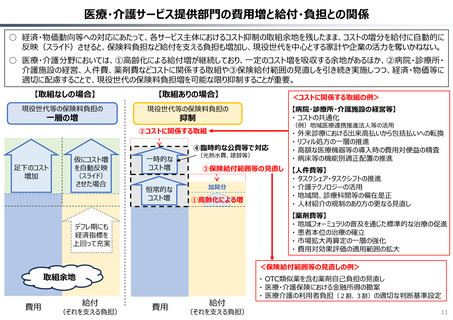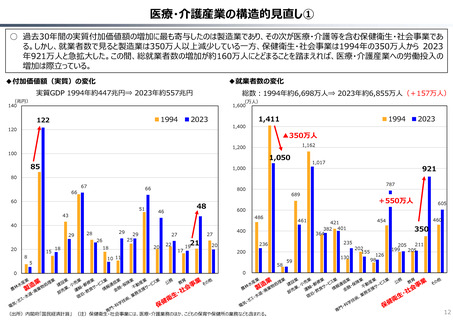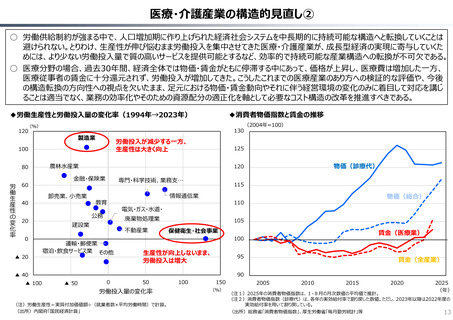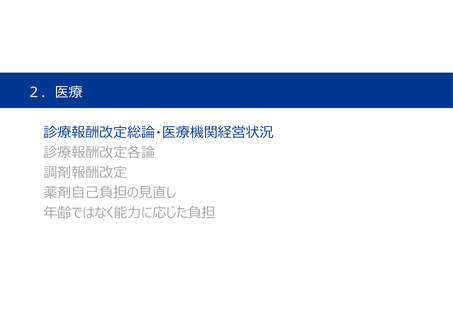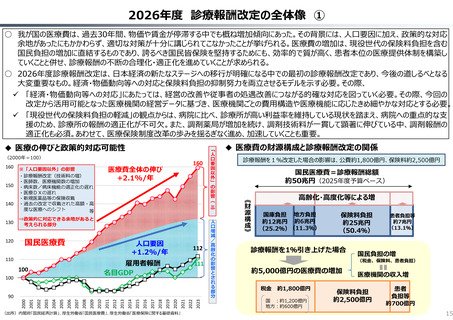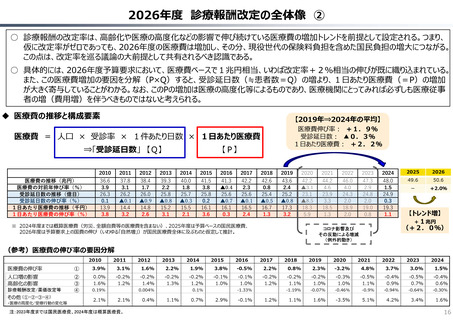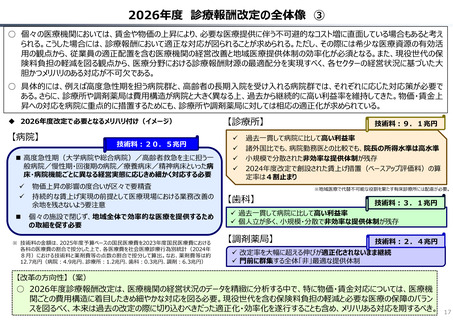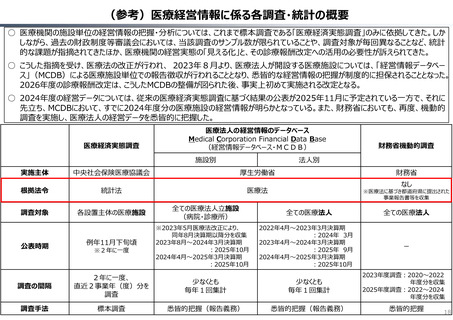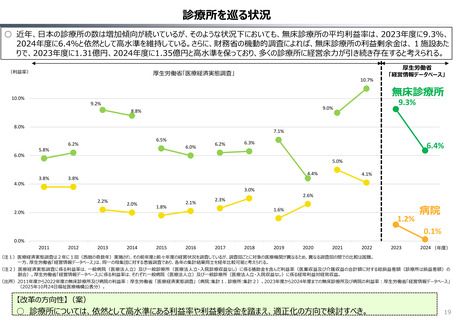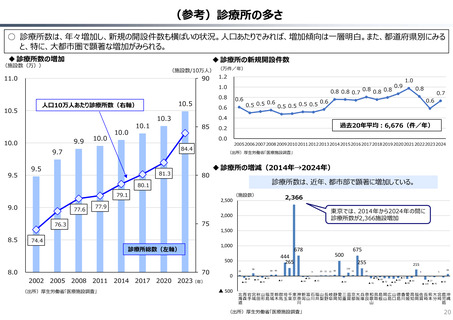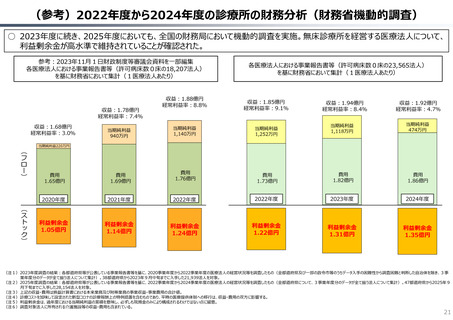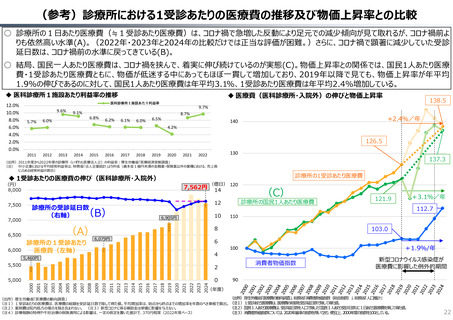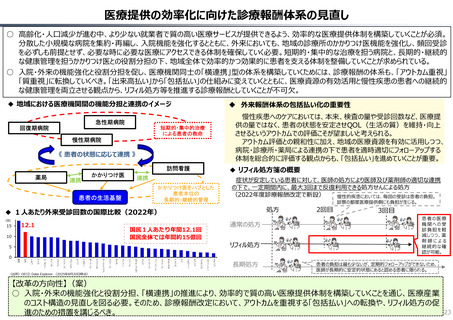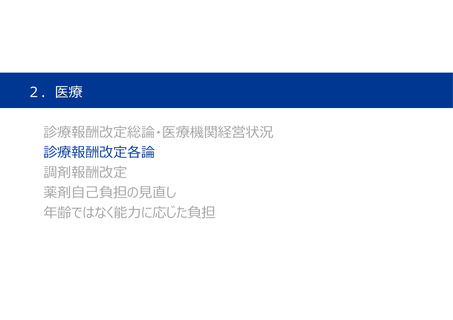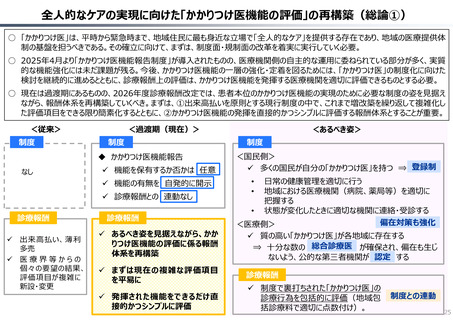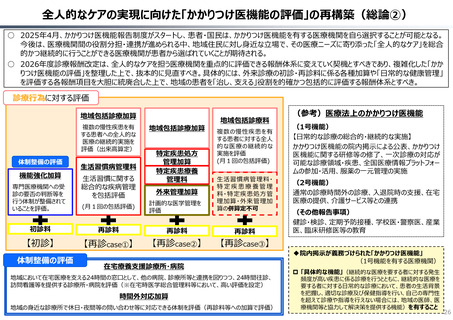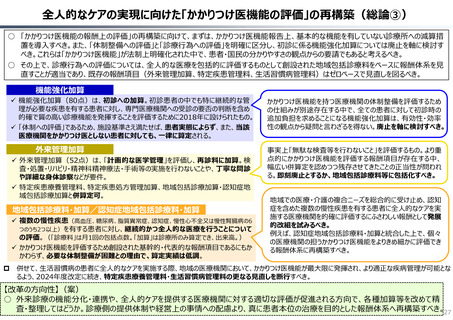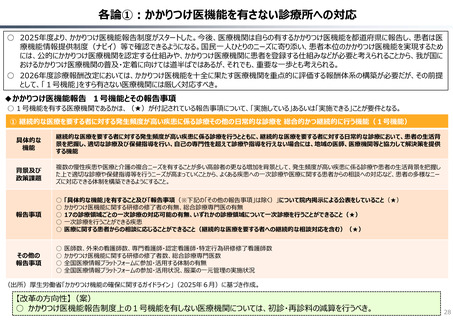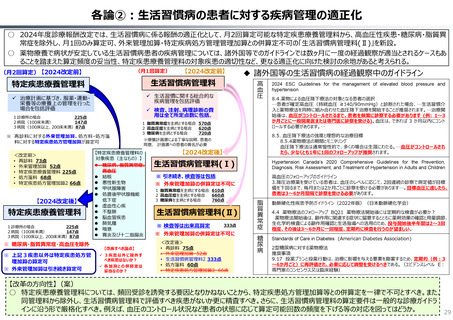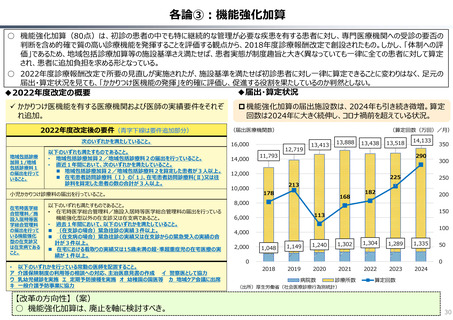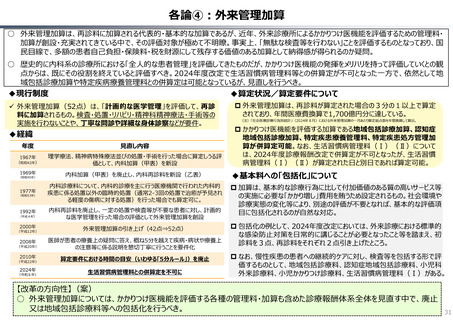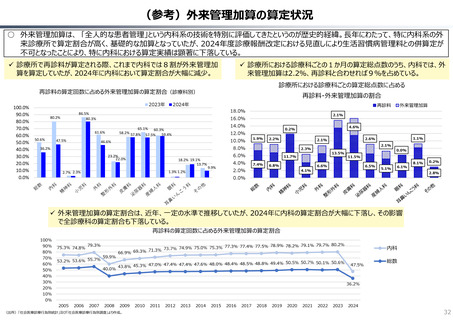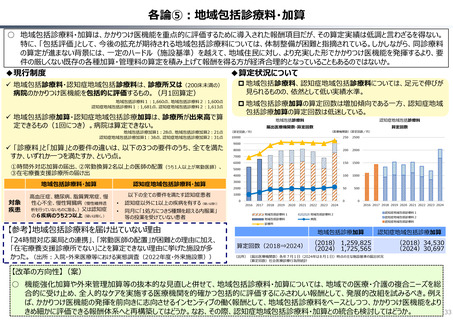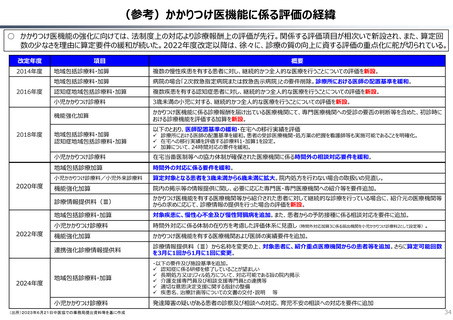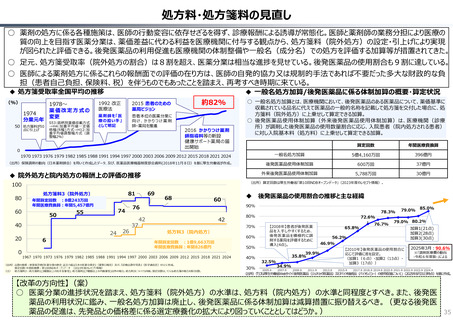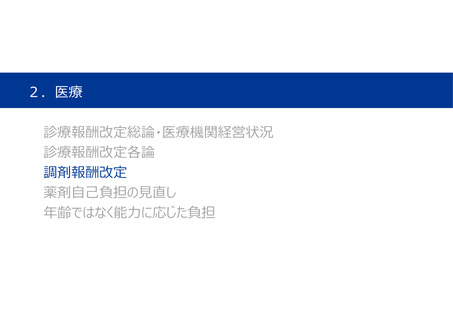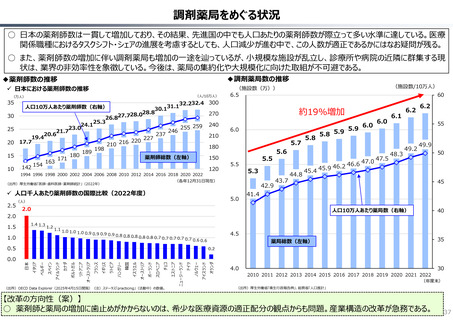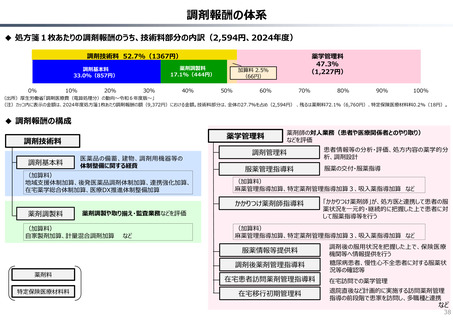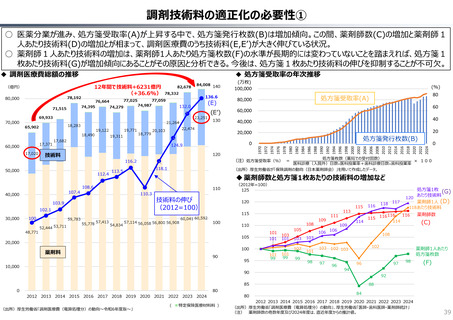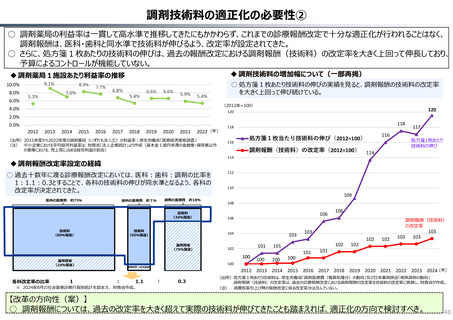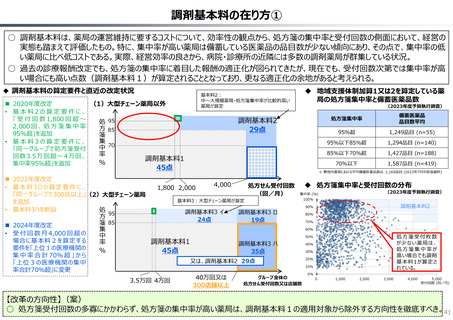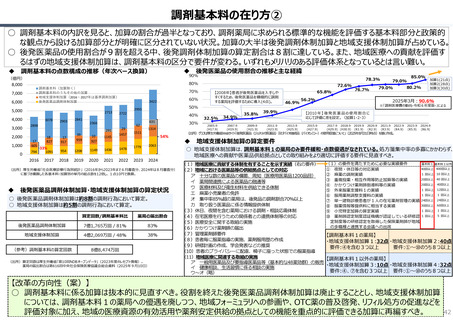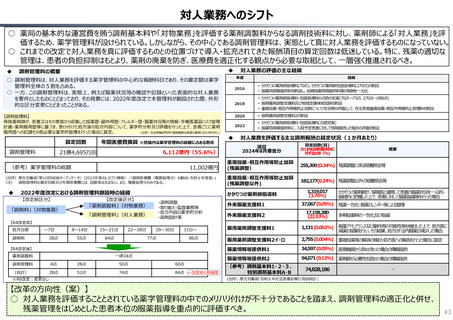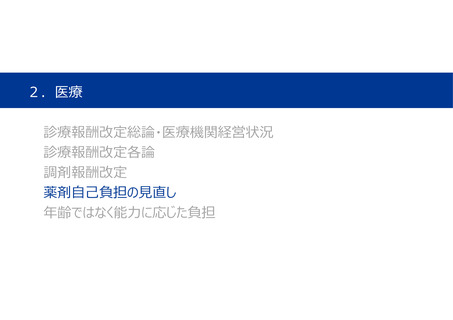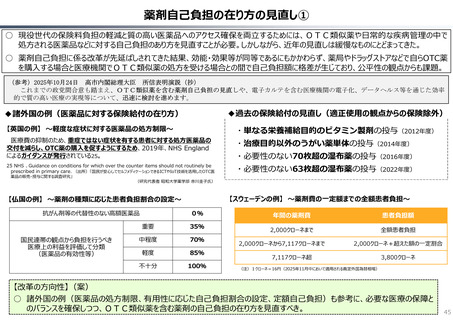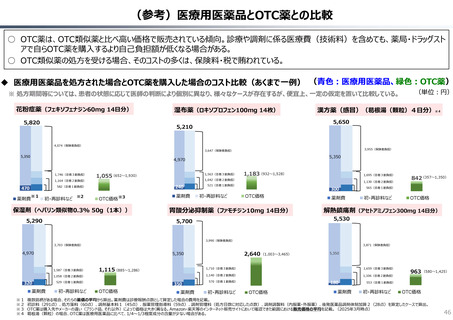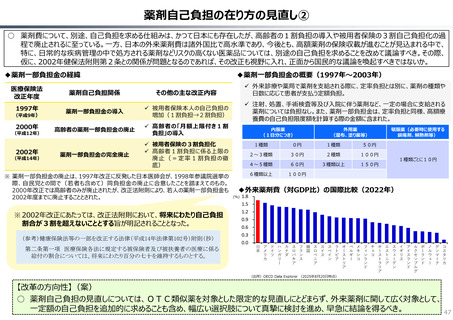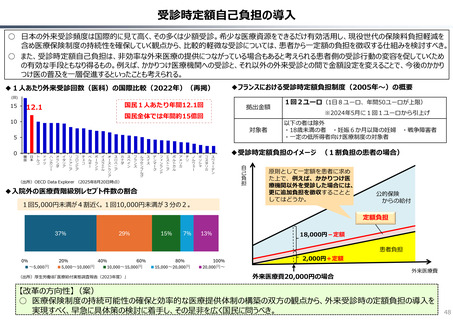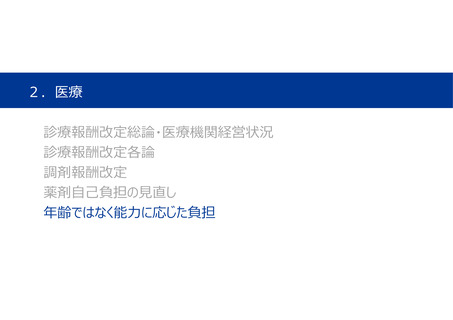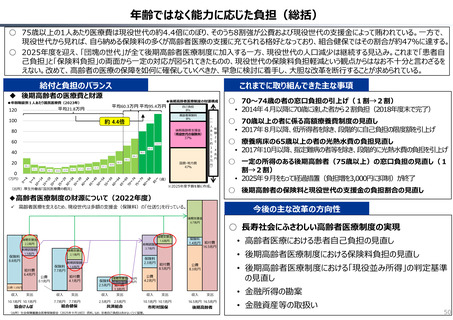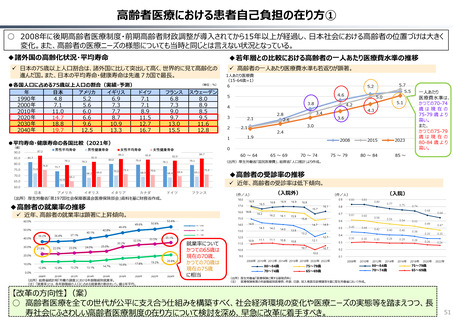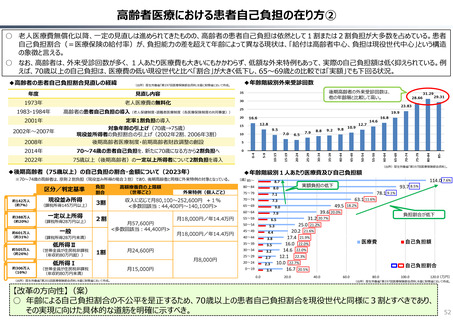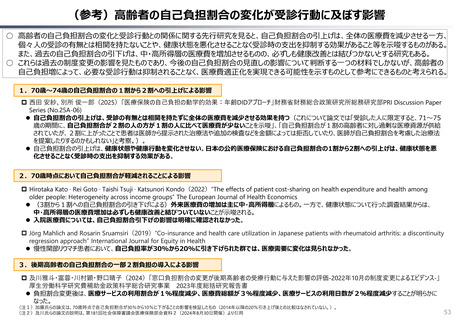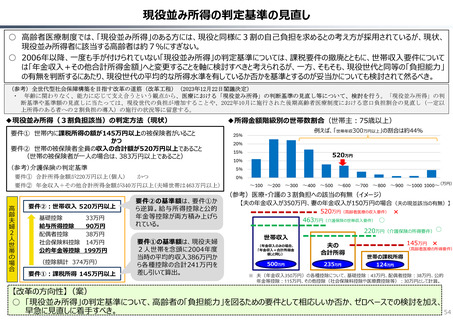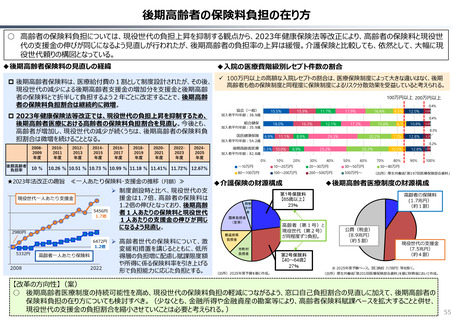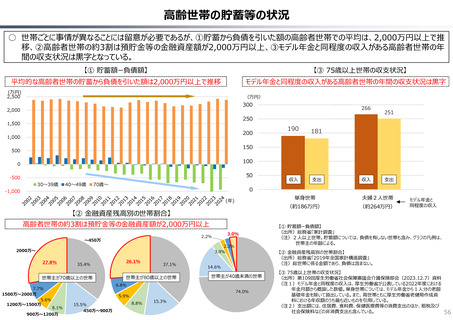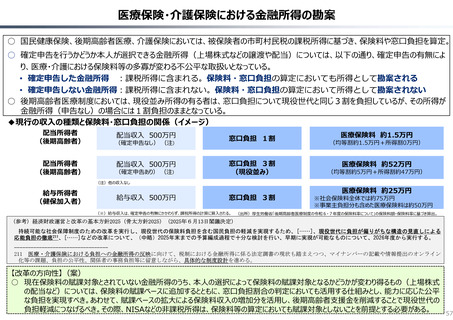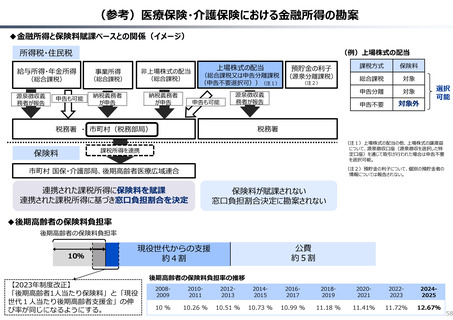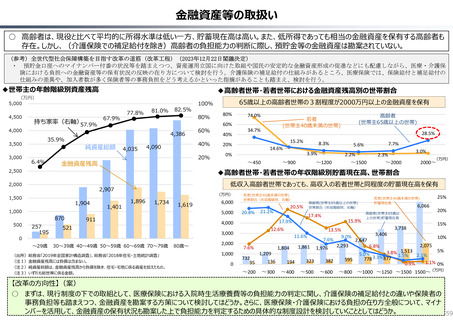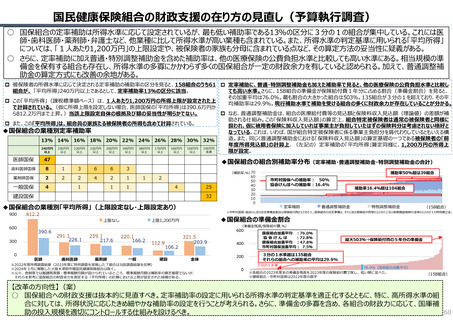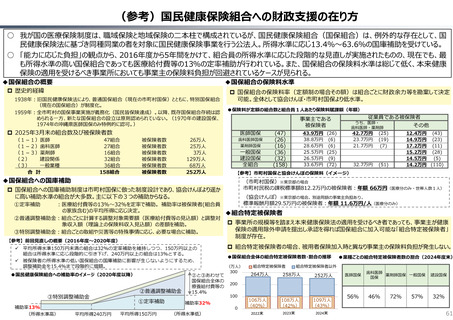よむ、つかう、まなぶ。
資料3 社会保障① (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)高齢者の自己負担割合の変化が受診行動に及ぼす影響
○ 高齢者の自己負担割合の変化と受診行動との関係に関する先行研究を見ると、自己負担割合の引上げは、全体の医療費を減少させる一方、
個々人の受診の有無とは相関を持たないことや、健康状態を悪化させることなく受診時の支出を抑制する効果があること等を示唆するものがある。
また、過去の自己負担割合の引下げは、中・高所得層の医療費を増加させるものの、必ずしも健康改善とは結びつかないとする研究もある。
○ これらは過去の制度変更の影響を見たものであり、今後の自己負担割合の見直しの影響について判断する一つの材料でしかないが、高齢者の
自己負担増によって、必要な受診行動は抑制されることなく、医療費適正化を実現できる可能性を示すものとして参考にできるものと考えられる。
1.70歳~74歳の自己負担割合の1割から2割への引上げによる影響
西田 安紗、別所 俊一郎(2025)「医療保険の自己負担の動学的効果:年齢DIDアプローチ」財務省財務総合政策研究所総務研究部PRI Discussion Paper
Series (No.25A-06)
自己負担割合の引上げは、受診の有無とは相関を持たずに全体の医療費を減少させる効果を持つ(これについて論文では「受診した人に限定すると、71~75
歳の期間に、自己負担割合が2割の人の方が1割の人に比べて医療費が少ないことを示唆」、「自己負担割合が1割の高齢者に対し過剰な医療資源が供給
されていたが、2割に上がったことで患者は医師から提示された治療法や追加の検査などを金額によっては拒否していたり、医師が自己負担割合を考慮した治療法
を提案したりするのかもしれない」と考察。)。
自己負担割合の引上げは、健康状態や健康行動を変化させない。日本の公的医療保険における自己負担割合の1割から2割への引上げは、健康状態を悪
化させることなく受診時の支出を抑制する効果がある。
2.70歳時点において自己負担割合が軽減されることによる影響
Hirotaka Kato · Rei Goto · Taishi Tsuji · Katsunori Kondo(2022)“The effects of patient cost-sharing on health expenditure and health among
older people: Heterogeneity across income groups“ The European Journal of Health Economics
(3割から1割への自己負担割合の引き下げによる)外来医療費の増加は主に中・高所得層によるもの。一方で、健康状態について行った調査結果からは、
中・高所得層の医療費増加は必ずしも健康改善と結びついていないことが示唆される。
入院医療費については、自己負担割合引下げの影響は明確に確認されなかった。
Jörg Mahlich and Rosarin Sruamsiri(2019)“Co-insurance and health care utilization in Japanese patients with rheumatoid arthritis: a discontinuity
regression approach” International Journal for Equity in Health
慢性関節リウマチ患者において、自己負担率が30%から20%に引き下げられた群では、医療需要に変化は見られなかった。
3.後期高齢者の自己負担割合の一部2割負担の導入による影響
及川雅斗・富蓉・川村顕・野口晴子(2024)「窓口負担割合の変更が後期高齢者の受療行動に与えた影響の評価-2022年10月の制度変更によるエビデンス-」
厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業 2023年度総括研究報告書
負担割合変更後は、医療サービスの利用割合が1%程度減少、医療費総額が3%程度減少、医療サービスの利用日数が2%程度減少することが明らかに
なった。
(注1)加藤氏らの論文は、70歳時点で自己負担割合が30%から10%に下がることの影響を検証したもの(2014年以降の20%引き上げ後との比較はなされていない。)。
(注2)及川氏らの論文の説明は、第181回社会保障審議会医療保険部会資料2(2024年8月30日開催)より引用
53
○ 高齢者の自己負担割合の変化と受診行動との関係に関する先行研究を見ると、自己負担割合の引上げは、全体の医療費を減少させる一方、
個々人の受診の有無とは相関を持たないことや、健康状態を悪化させることなく受診時の支出を抑制する効果があること等を示唆するものがある。
また、過去の自己負担割合の引下げは、中・高所得層の医療費を増加させるものの、必ずしも健康改善とは結びつかないとする研究もある。
○ これらは過去の制度変更の影響を見たものであり、今後の自己負担割合の見直しの影響について判断する一つの材料でしかないが、高齢者の
自己負担増によって、必要な受診行動は抑制されることなく、医療費適正化を実現できる可能性を示すものとして参考にできるものと考えられる。
1.70歳~74歳の自己負担割合の1割から2割への引上げによる影響
西田 安紗、別所 俊一郎(2025)「医療保険の自己負担の動学的効果:年齢DIDアプローチ」財務省財務総合政策研究所総務研究部PRI Discussion Paper
Series (No.25A-06)
自己負担割合の引上げは、受診の有無とは相関を持たずに全体の医療費を減少させる効果を持つ(これについて論文では「受診した人に限定すると、71~75
歳の期間に、自己負担割合が2割の人の方が1割の人に比べて医療費が少ないことを示唆」、「自己負担割合が1割の高齢者に対し過剰な医療資源が供給
されていたが、2割に上がったことで患者は医師から提示された治療法や追加の検査などを金額によっては拒否していたり、医師が自己負担割合を考慮した治療法
を提案したりするのかもしれない」と考察。)。
自己負担割合の引上げは、健康状態や健康行動を変化させない。日本の公的医療保険における自己負担割合の1割から2割への引上げは、健康状態を悪
化させることなく受診時の支出を抑制する効果がある。
2.70歳時点において自己負担割合が軽減されることによる影響
Hirotaka Kato · Rei Goto · Taishi Tsuji · Katsunori Kondo(2022)“The effects of patient cost-sharing on health expenditure and health among
older people: Heterogeneity across income groups“ The European Journal of Health Economics
(3割から1割への自己負担割合の引き下げによる)外来医療費の増加は主に中・高所得層によるもの。一方で、健康状態について行った調査結果からは、
中・高所得層の医療費増加は必ずしも健康改善と結びついていないことが示唆される。
入院医療費については、自己負担割合引下げの影響は明確に確認されなかった。
Jörg Mahlich and Rosarin Sruamsiri(2019)“Co-insurance and health care utilization in Japanese patients with rheumatoid arthritis: a discontinuity
regression approach” International Journal for Equity in Health
慢性関節リウマチ患者において、自己負担率が30%から20%に引き下げられた群では、医療需要に変化は見られなかった。
3.後期高齢者の自己負担割合の一部2割負担の導入による影響
及川雅斗・富蓉・川村顕・野口晴子(2024)「窓口負担割合の変更が後期高齢者の受療行動に与えた影響の評価-2022年10月の制度変更によるエビデンス-」
厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業 2023年度総括研究報告書
負担割合変更後は、医療サービスの利用割合が1%程度減少、医療費総額が3%程度減少、医療サービスの利用日数が2%程度減少することが明らかに
なった。
(注1)加藤氏らの論文は、70歳時点で自己負担割合が30%から10%に下がることの影響を検証したもの(2014年以降の20%引き上げ後との比較はなされていない。)。
(注2)及川氏らの論文の説明は、第181回社会保障審議会医療保険部会資料2(2024年8月30日開催)より引用
53