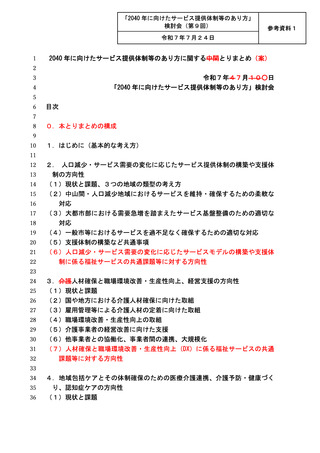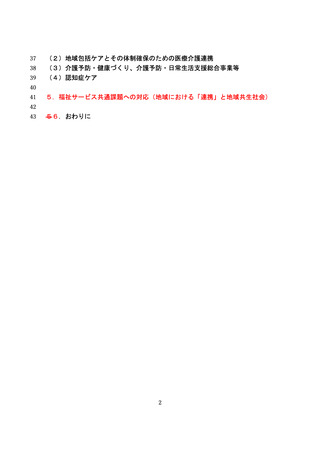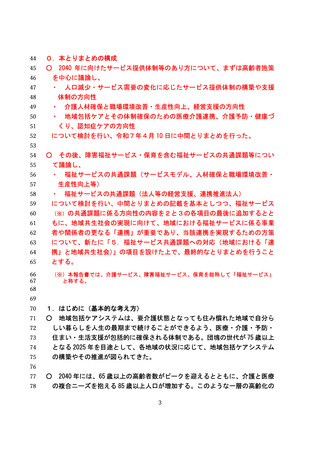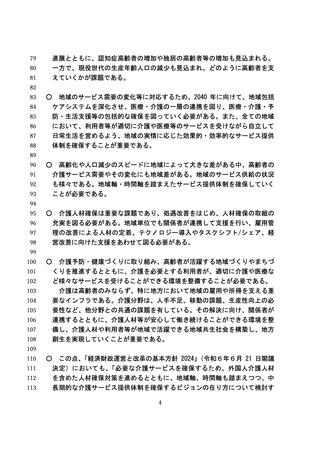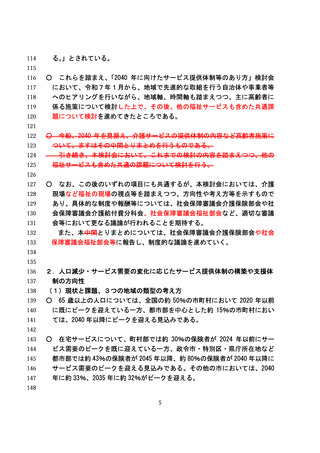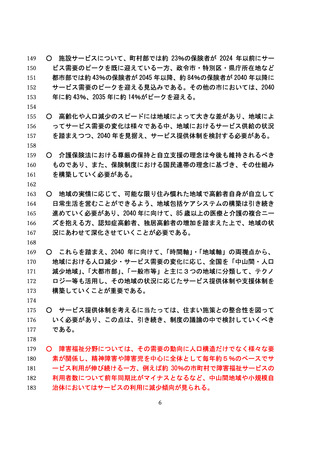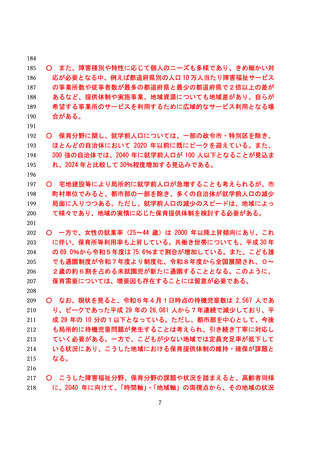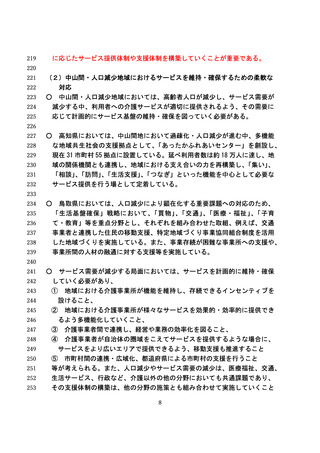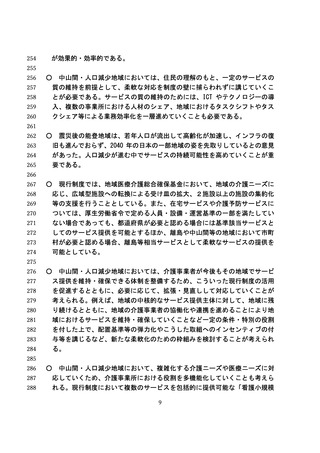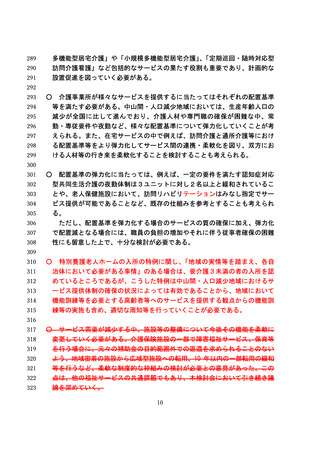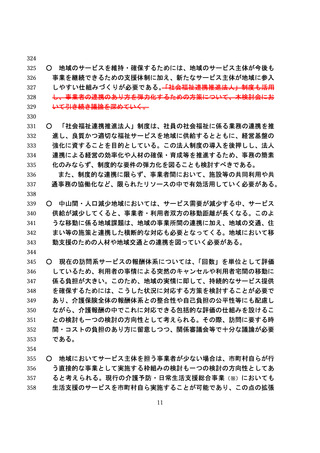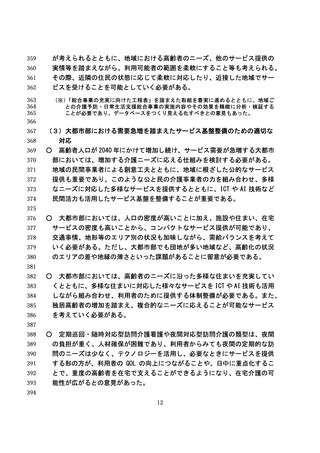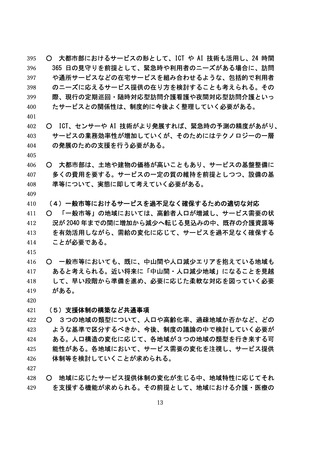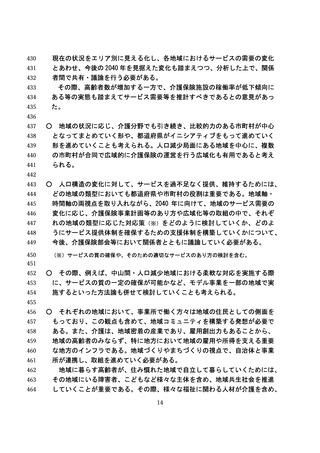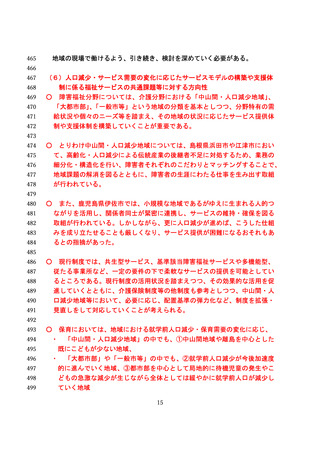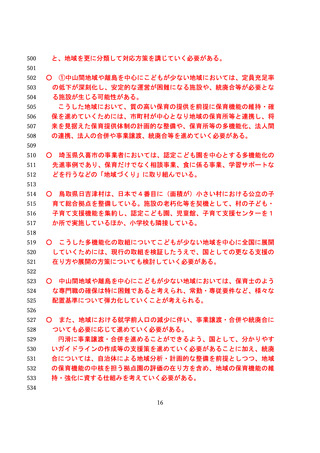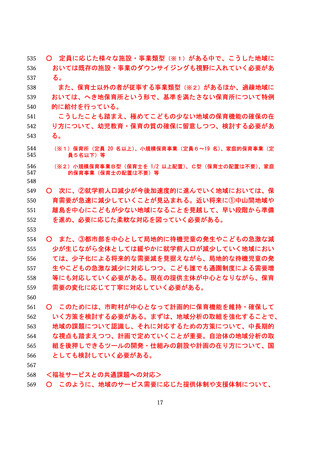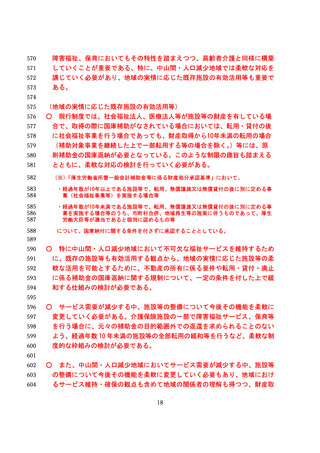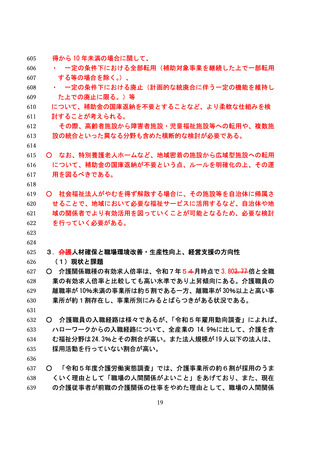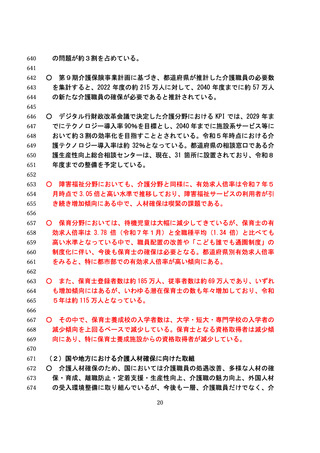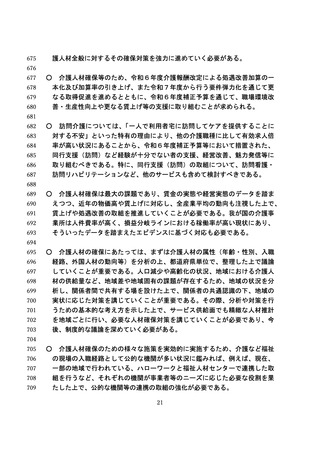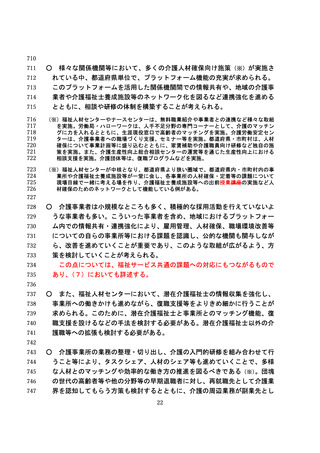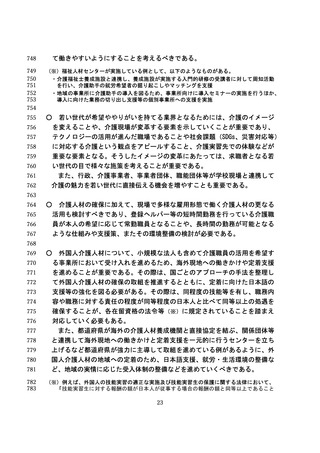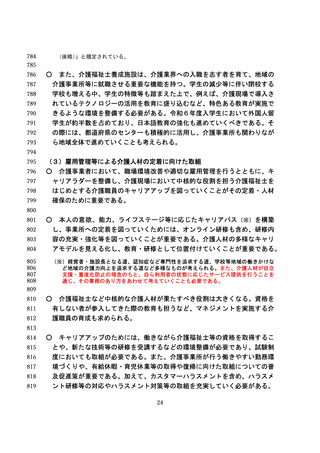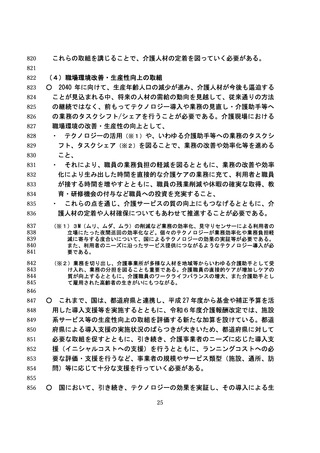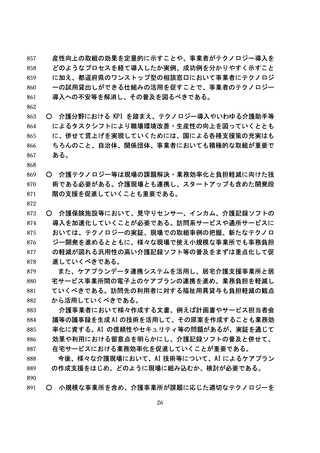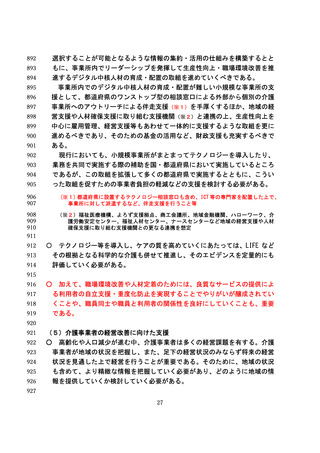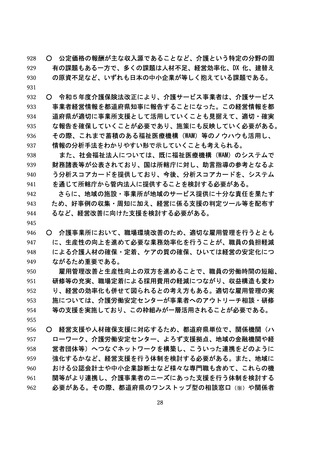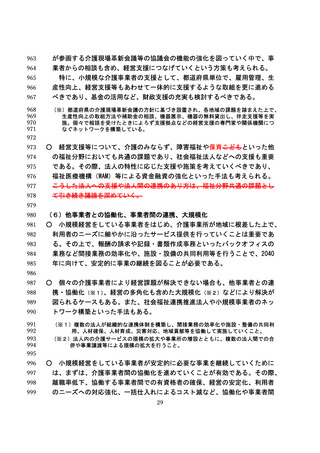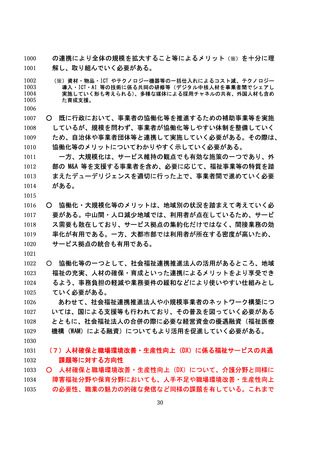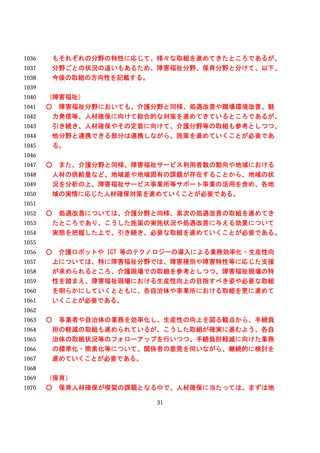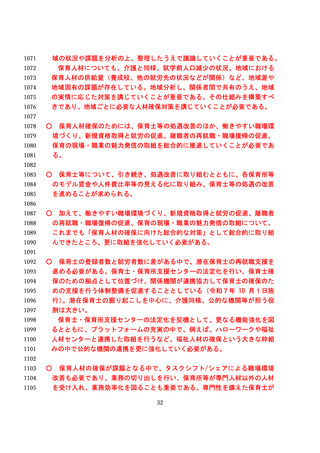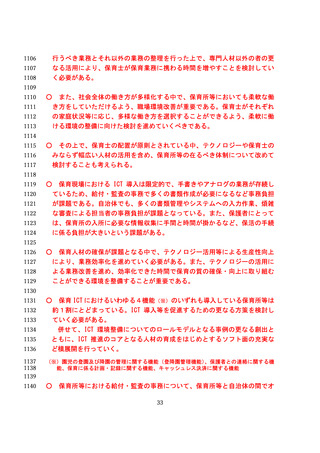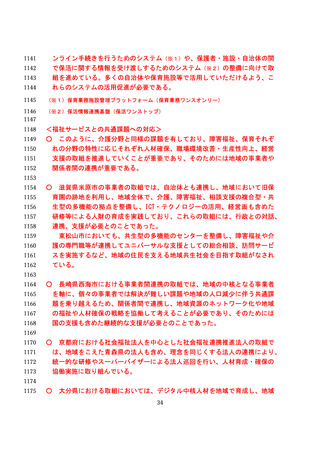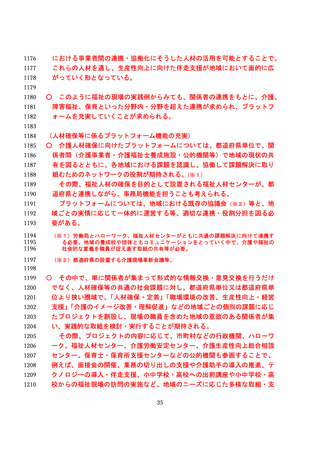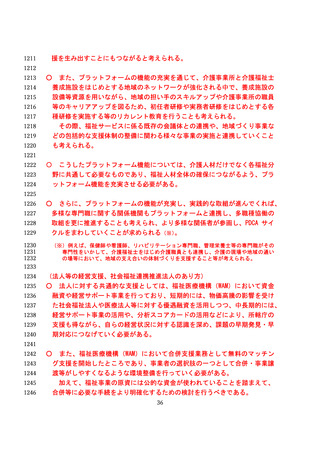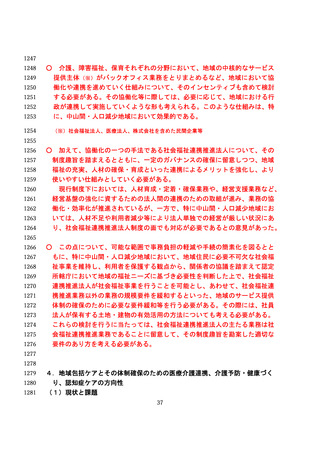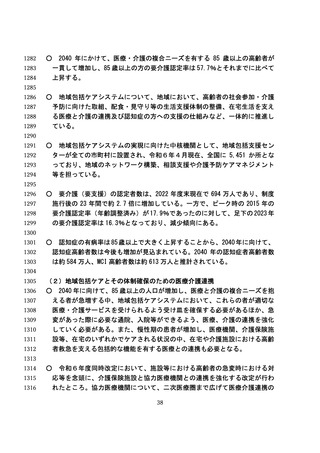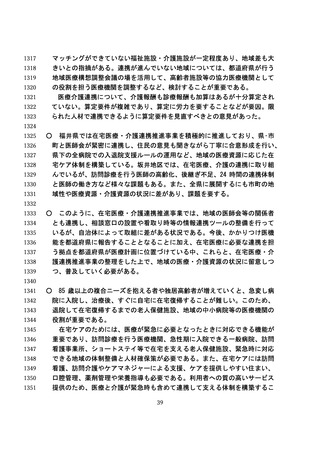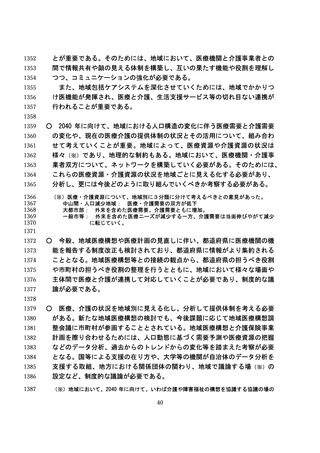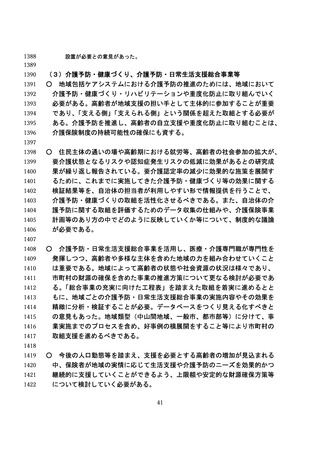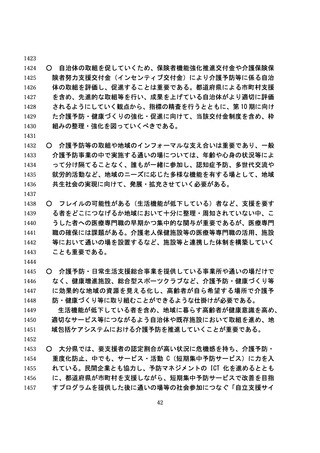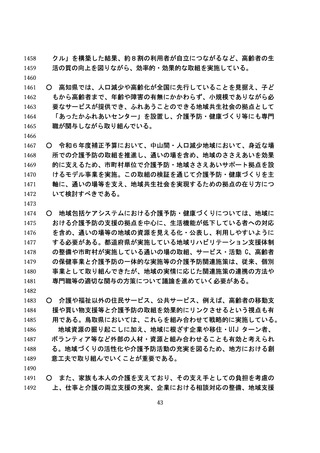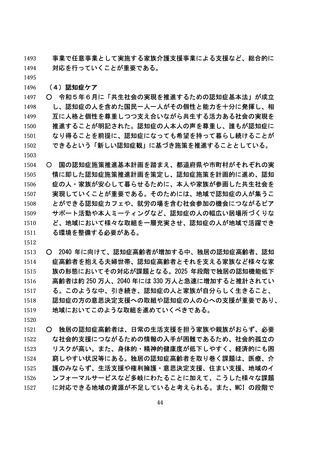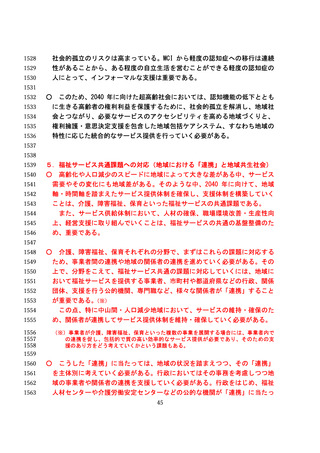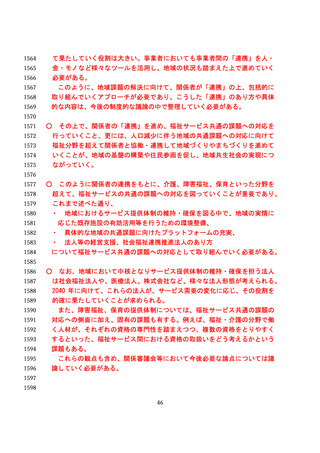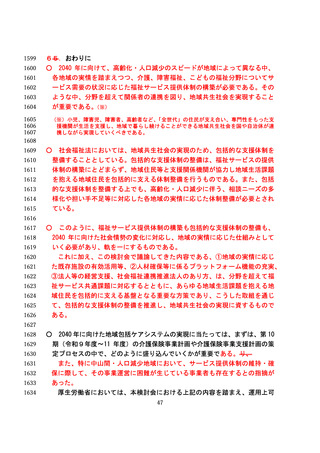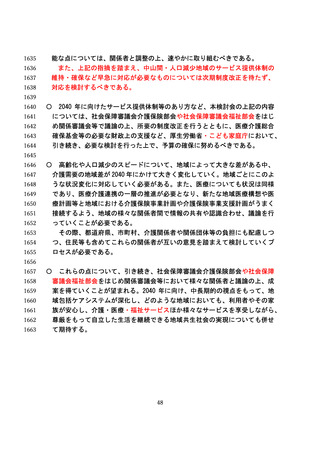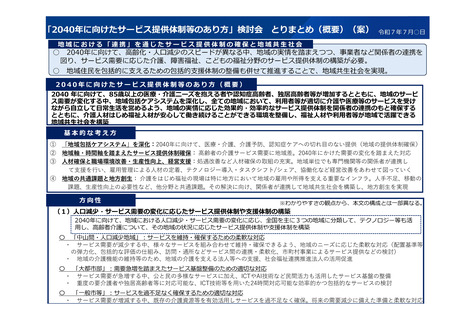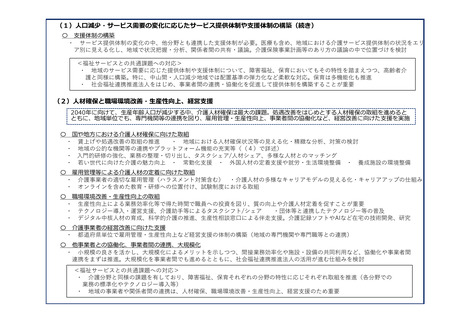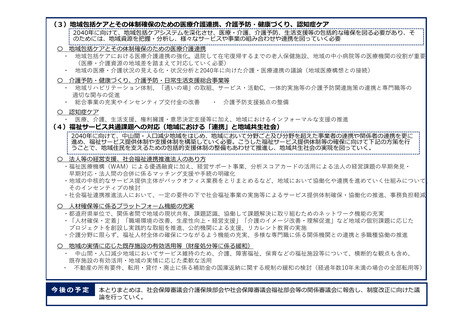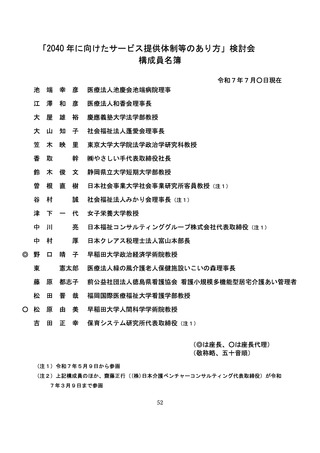よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(案)<中間とりまとめからの変更点> (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59876.html |
| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第9回 7/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
184
185
186
187
188
189
190
○ また、障害種別や特性に応じて個人のニーズも多様であり、きめ細かい対
応が必要となる中、例えば都道府県別の人口 10 万人当たり障害福祉サービス
の事業所数や従事者数が最多の都道府県と最少の都道府県で2倍以上の差が
あるなど、提供体制や実施事業、地域資源についても地域差があり、自らが
希望する事業所のサービスを利用するために広域的なサービス利用となる場
合がある。
191
192
193
194
195
○ 保育分野に関し、就学前人口については、一部の政令市・特別区を除き、
ほとんどの自治体において 2020 年以前に既にピークを迎えている。また、
300 強の自治体では、2040 年に就学前人口が 100 人以下となることが見込ま
れ、2024 年と比較して 30%程度増加する見込みである。
196
197
198
199
200
○ 宅地建設等により局所的に就学前人口が急増することも考えられるが、市
町村単位でみると、都市部の一部を除き、多くの自治体が就学前人口の減少
局面に入りつつある。ただし、就学前人口の減少のスピードは、地域によっ
て様々であり、地域の実情に応じた保育提供体制を検討する必要がある。
201
202
203
204
205
206
207
○ 一方で、女性の就業率(25~44 歳)は 2000 年以降上昇傾向にあり、これ
に伴い、保育所等利用率も上昇している。共働き世帯についても、平成 30 年
の 69.0%から令和5年度は 75.6%まで割合が増加している。また、こども誰
でも通園制度が令和7年度より制度化、令和8年度から全国展開され、0~
2歳の約6割を占める未就園児が新たに通園することとなる。このように、
保育需要については、増要因も存在することには留意が必要である。
208
209
210
211
212
213
214
215
○ なお、現状を見ると、令和6年4月1日時点の待機児童数は 2,567 人であ
り、ピークであった平成 29 年の 26,081 人から7年連続で減少しており、平
成 29 年の 10 分の1以下となっている。ただし、都市部を中心として、今後
も局所的に待機児童問題が発生することは考えられ、引き続き丁寧に対応し
ていく必要がある。一方で、こどもが少ない地域では定員充足率が低下して
いる状況にあり、こうした地域における保育提供体制の維持・確保が課題と
なる。
216
217
218
○ こうした障害福祉分野、保育分野の課題や状況を踏まえると、高齢者同様
に、2040 年に向けて、「時間軸」・「地域軸」の両視点から、その地域の状況
7
185
186
187
188
189
190
○ また、障害種別や特性に応じて個人のニーズも多様であり、きめ細かい対
応が必要となる中、例えば都道府県別の人口 10 万人当たり障害福祉サービス
の事業所数や従事者数が最多の都道府県と最少の都道府県で2倍以上の差が
あるなど、提供体制や実施事業、地域資源についても地域差があり、自らが
希望する事業所のサービスを利用するために広域的なサービス利用となる場
合がある。
191
192
193
194
195
○ 保育分野に関し、就学前人口については、一部の政令市・特別区を除き、
ほとんどの自治体において 2020 年以前に既にピークを迎えている。また、
300 強の自治体では、2040 年に就学前人口が 100 人以下となることが見込ま
れ、2024 年と比較して 30%程度増加する見込みである。
196
197
198
199
200
○ 宅地建設等により局所的に就学前人口が急増することも考えられるが、市
町村単位でみると、都市部の一部を除き、多くの自治体が就学前人口の減少
局面に入りつつある。ただし、就学前人口の減少のスピードは、地域によっ
て様々であり、地域の実情に応じた保育提供体制を検討する必要がある。
201
202
203
204
205
206
207
○ 一方で、女性の就業率(25~44 歳)は 2000 年以降上昇傾向にあり、これ
に伴い、保育所等利用率も上昇している。共働き世帯についても、平成 30 年
の 69.0%から令和5年度は 75.6%まで割合が増加している。また、こども誰
でも通園制度が令和7年度より制度化、令和8年度から全国展開され、0~
2歳の約6割を占める未就園児が新たに通園することとなる。このように、
保育需要については、増要因も存在することには留意が必要である。
208
209
210
211
212
213
214
215
○ なお、現状を見ると、令和6年4月1日時点の待機児童数は 2,567 人であ
り、ピークであった平成 29 年の 26,081 人から7年連続で減少しており、平
成 29 年の 10 分の1以下となっている。ただし、都市部を中心として、今後
も局所的に待機児童問題が発生することは考えられ、引き続き丁寧に対応し
ていく必要がある。一方で、こどもが少ない地域では定員充足率が低下して
いる状況にあり、こうした地域における保育提供体制の維持・確保が課題と
なる。
216
217
218
○ こうした障害福祉分野、保育分野の課題や状況を踏まえると、高齢者同様
に、2040 年に向けて、「時間軸」・「地域軸」の両視点から、その地域の状況
7