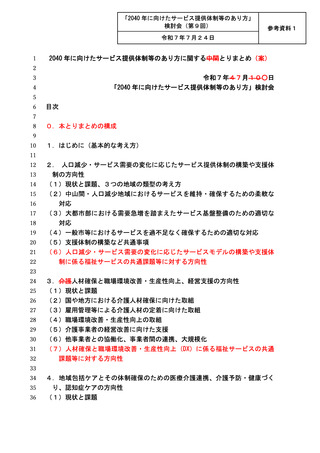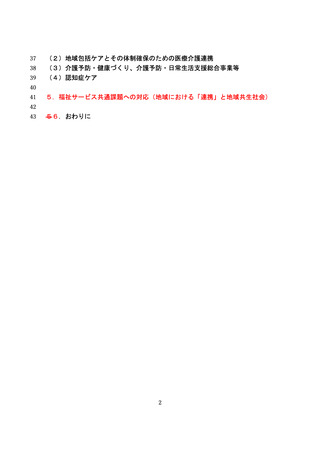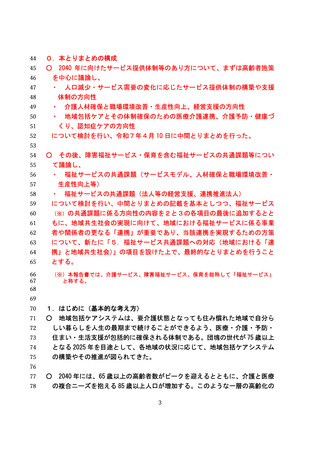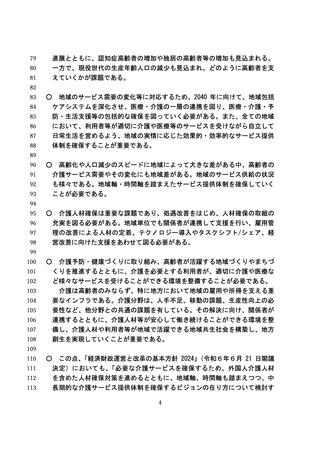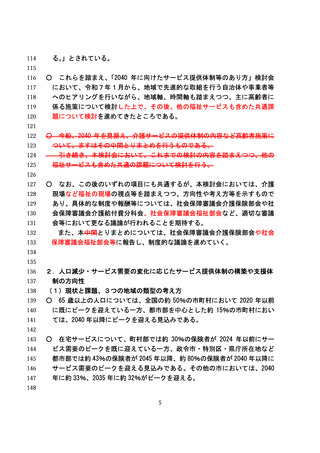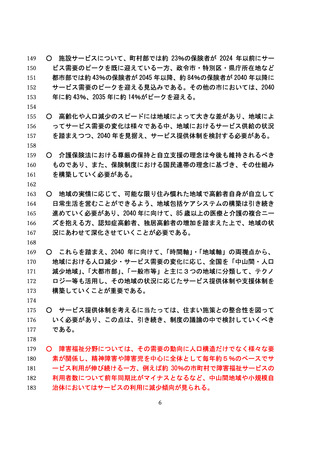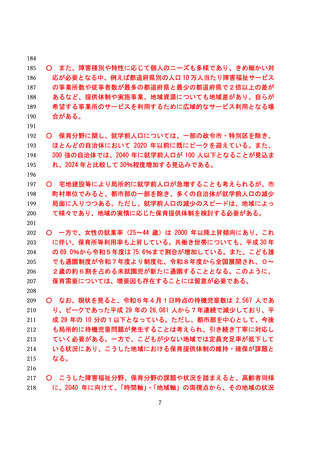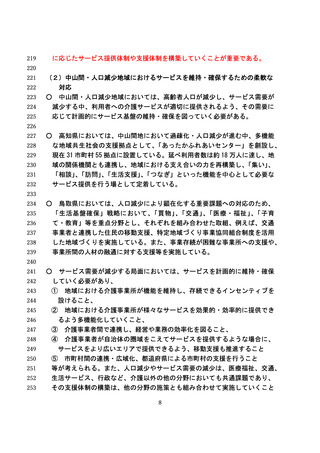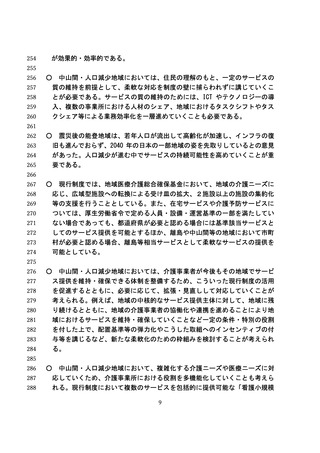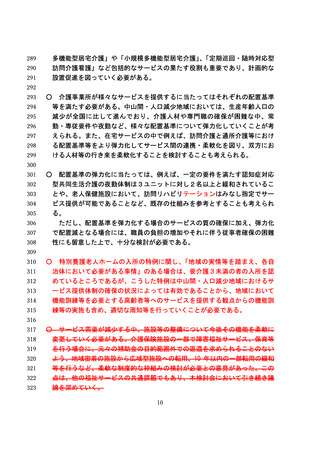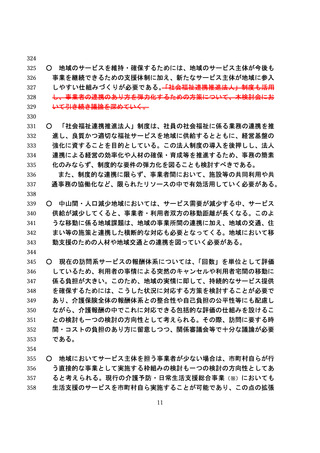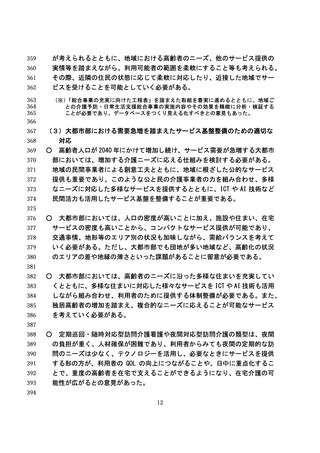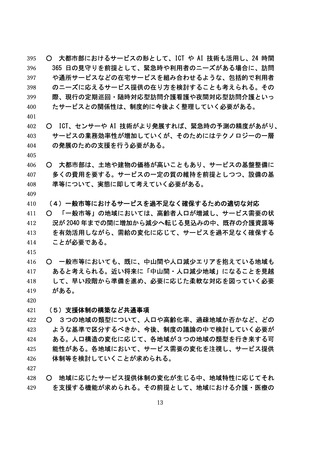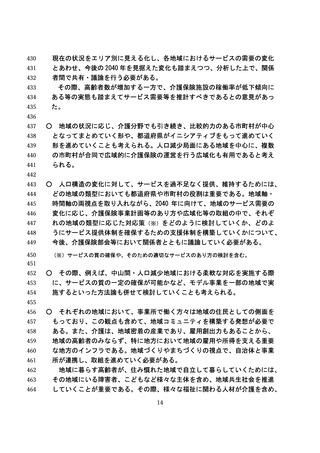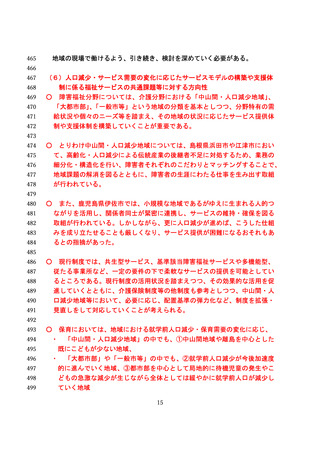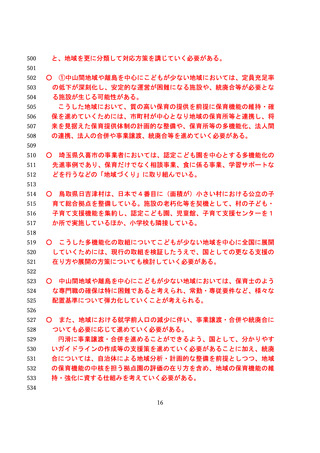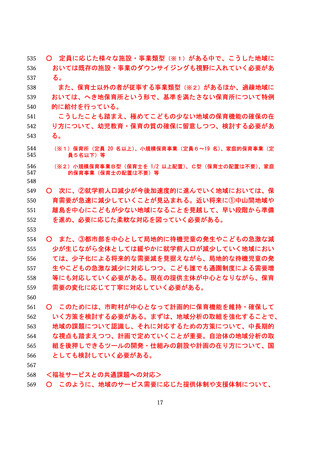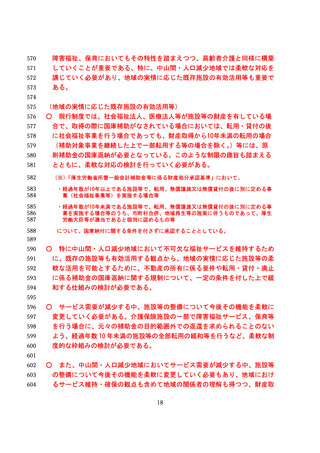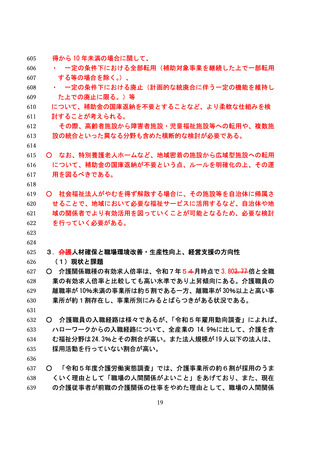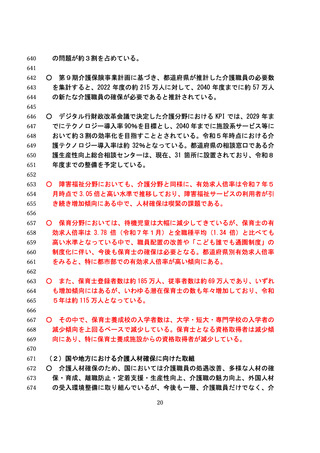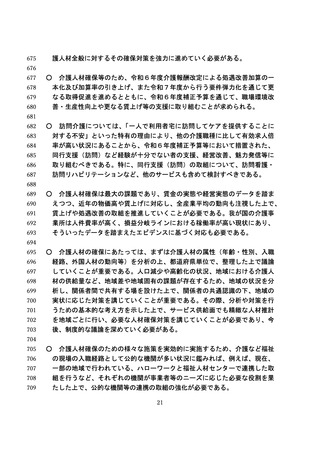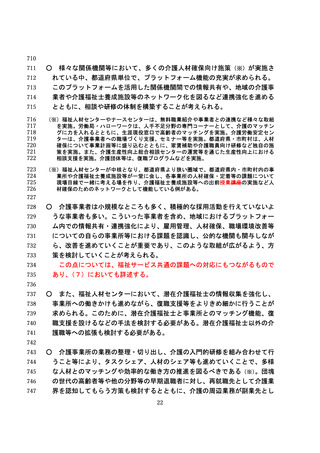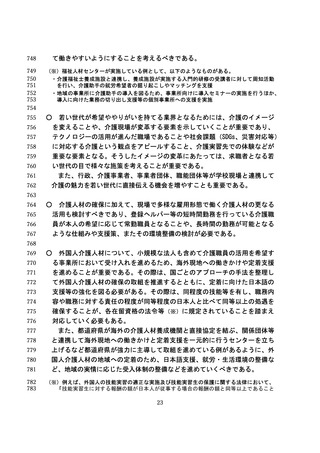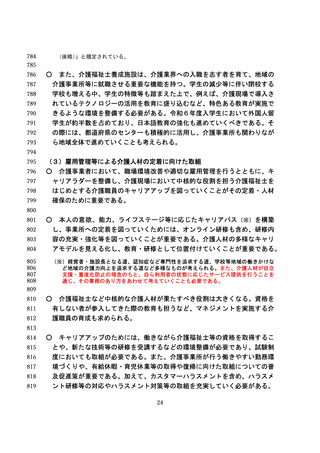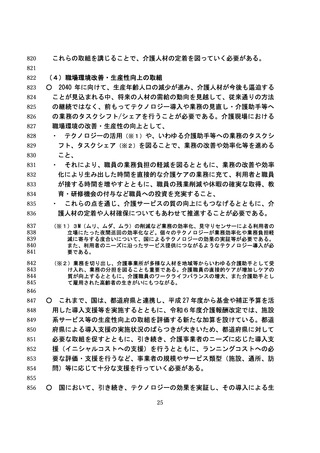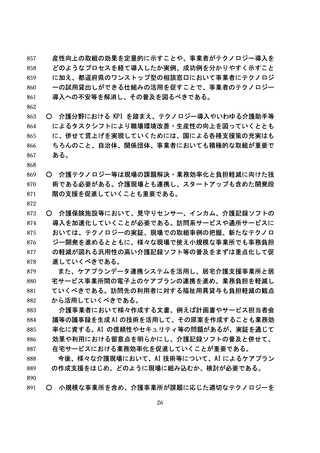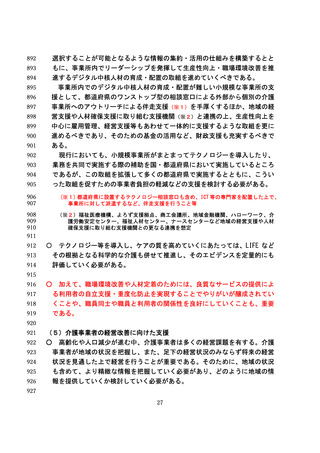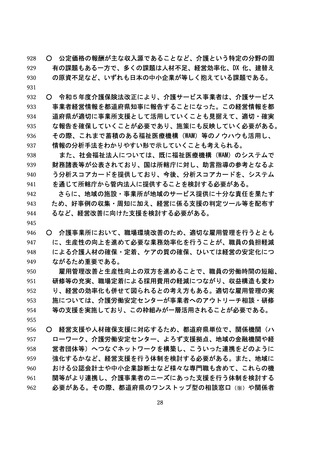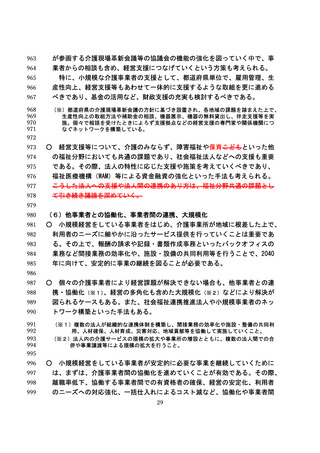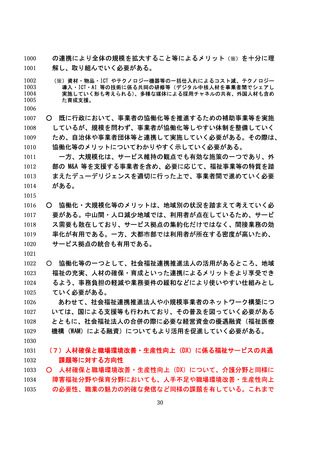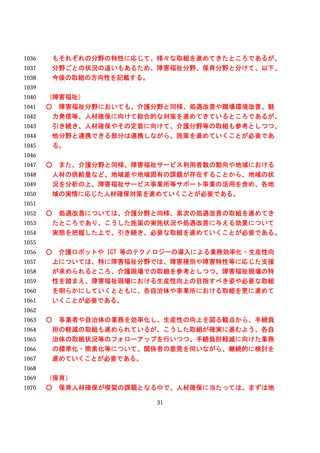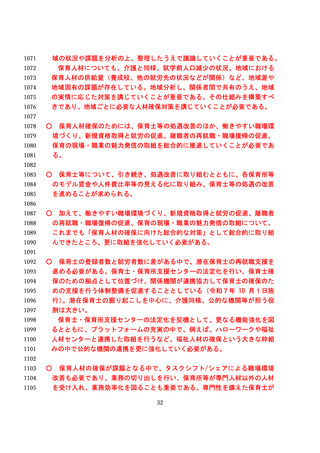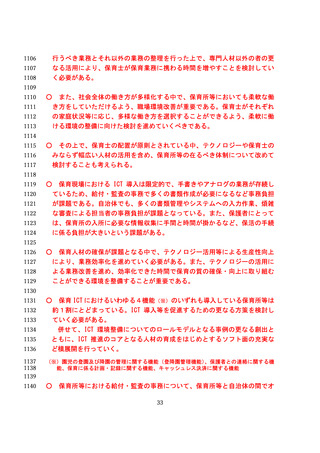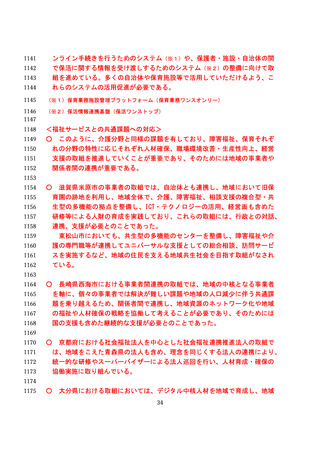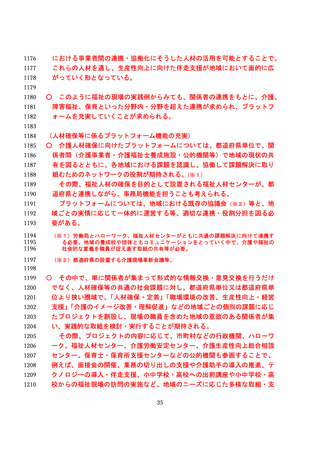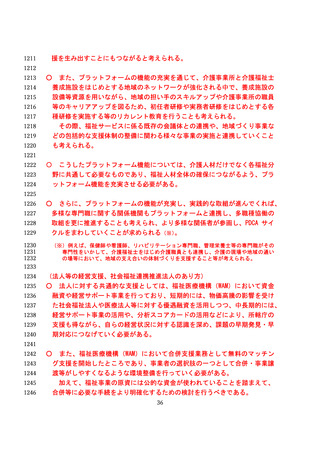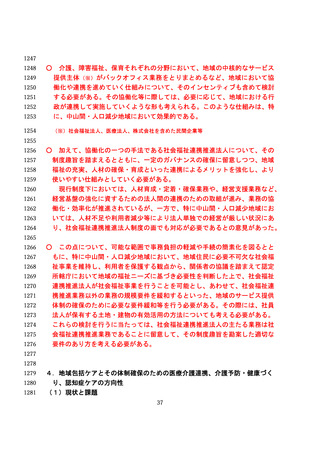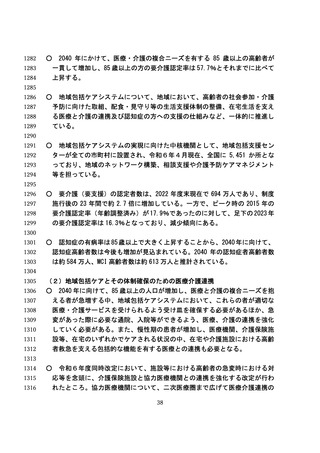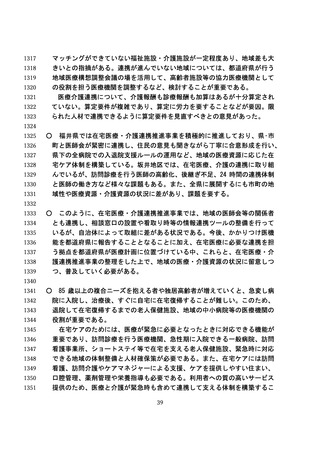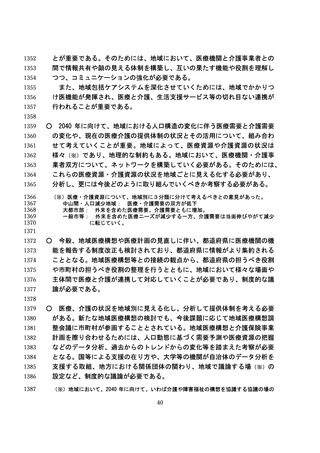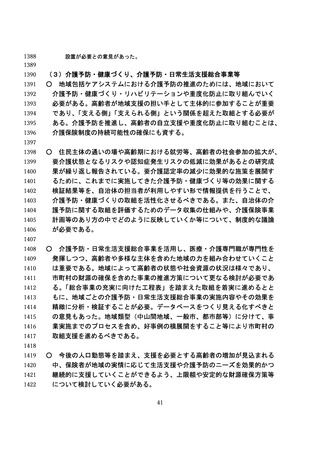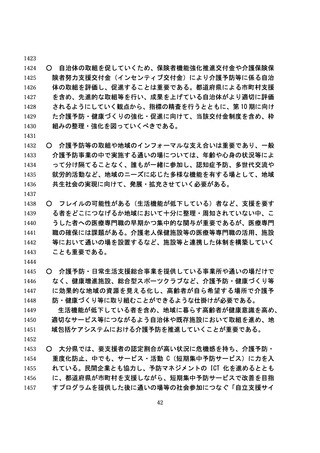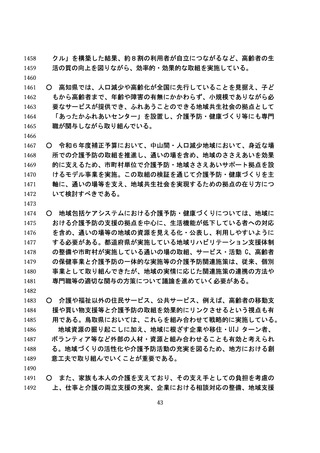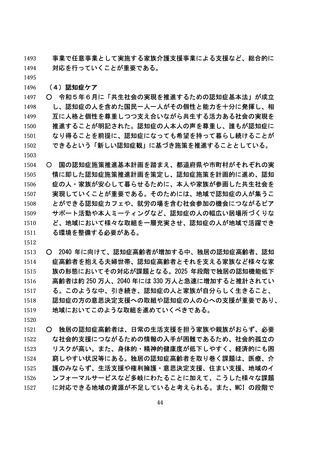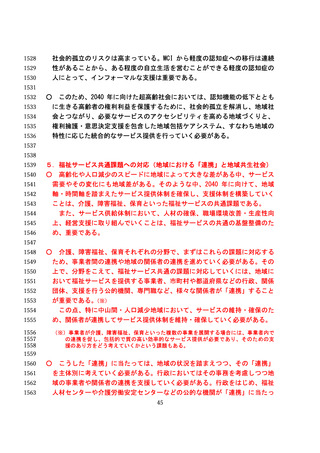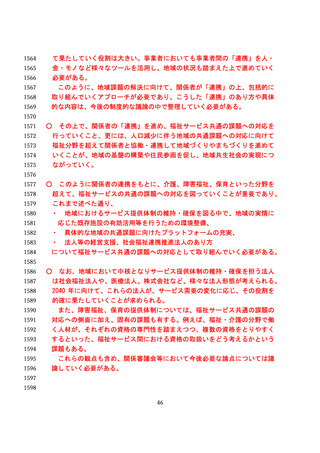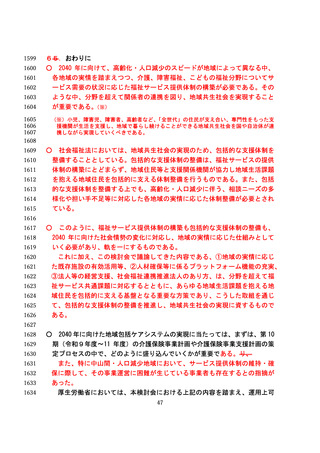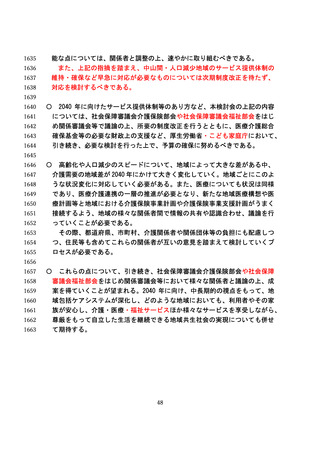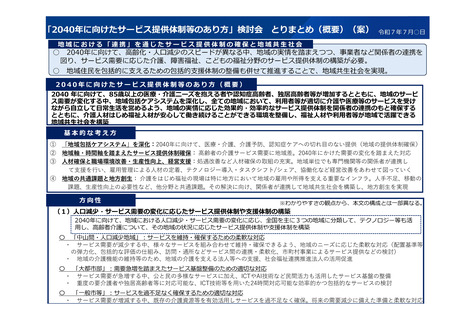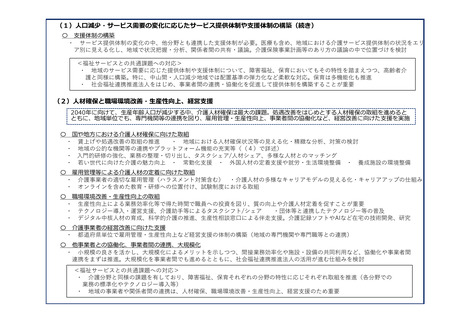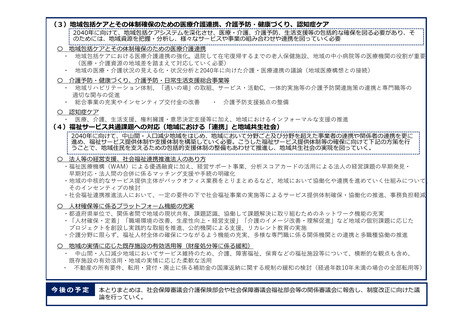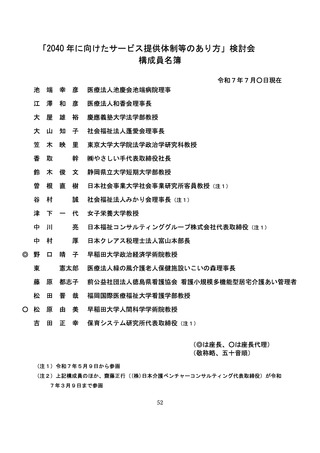よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(案)<中間とりまとめからの変更点> (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59876.html |
| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第9回 7/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
が参画する介護現場革新会議等の協議会の機能の強化を図っていく中で、事
業者からの相談も含め、経営支援につなげていくという方策も考えられる。
特に、小規模な介護事業者の支援として、都道府県単位で、雇用管理、生
産性向上、経営支援等もあわせて一体的に支援するような取組を更に進める
べきであり、基金の活用など、財政支援の充実も検討するべきである。
(※)都道府県の介護現場革新会議の方針に基づき設置され、各地域の課題を踏まえた上で、
生産性向上の取組方法や補助金の相談、機器展示、機器の無料貸出し、伴走支援等を実
施。個々で相談を受けたときによろず支援拠点などの経営支援の専門家や関係機関につ
なぐネットワークを構築している。
○ 経営支援等について、介護のみならず、障害福祉や保育こどもといった他
の福祉分野においても共通の課題であり、社会福祉法人などへの支援も重要
である。その際、法人の特性に応じた支援や施策を考えていくべきであり、
福祉医療機構(WAM)等による資金融資の強化といった手法も考えられる。
こうした法人への支援や法人間の連携のあり方は、福祉分野共通の課題とし
て引き続き議論を深めていく。
979
980
981
982
983
984
985
(6)他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化
○ 小規模経営をしている事業者をはじめ、介護事業所が地域に根差した上で、
利用者のニーズに細やかに沿ったサービス提供を行っていくことは重要であ
る。その上で、報酬の請求や記録・書類作成事務といったバックオフィスの
業務など間接業務の効率化や、施設・設備の共同利用等を行うことで、2040
年に向けて、安定的に事業の継続を図ることが必要である。
986
987
988
989
990
○ 個々の介護事業者により経営課題が解決できない場合も、他事業者との連
携・協働化(※1)、経営の多角化も含めた大規模化(※2)などにより解決が
図られるケースもある。また、社会福祉連携推進法人や小規模事業者のネッ
トワーク構築といった手法もある。
991
992
993
994
995
(※1)複数の法人が組織的な連携体制を構築し、間接業務の効率化や施設・整備の共同利
用、人材確保、人材育成、災害対応、地域貢献等を協働して実施していくこと。
(※2)法人内の介護サービスの規模の拡大や事業所の増設とともに、複数の法人間での合
併や事業譲渡等による規模の拡大を行うこと。
996
○ 小規模経営をしている事業者が安定的に必要な事業を継続していくために
は、まずは、介護事業者間の協働化を進めていくことが有効である。その際、
離職率低下、協働する事業者間での有資格者の確保、経営の安定化、利用者
のニーズへの対応強化、一括仕入れによるコスト減など、協働化や事業者間
997
998
999
29
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
が参画する介護現場革新会議等の協議会の機能の強化を図っていく中で、事
業者からの相談も含め、経営支援につなげていくという方策も考えられる。
特に、小規模な介護事業者の支援として、都道府県単位で、雇用管理、生
産性向上、経営支援等もあわせて一体的に支援するような取組を更に進める
べきであり、基金の活用など、財政支援の充実も検討するべきである。
(※)都道府県の介護現場革新会議の方針に基づき設置され、各地域の課題を踏まえた上で、
生産性向上の取組方法や補助金の相談、機器展示、機器の無料貸出し、伴走支援等を実
施。個々で相談を受けたときによろず支援拠点などの経営支援の専門家や関係機関につ
なぐネットワークを構築している。
○ 経営支援等について、介護のみならず、障害福祉や保育こどもといった他
の福祉分野においても共通の課題であり、社会福祉法人などへの支援も重要
である。その際、法人の特性に応じた支援や施策を考えていくべきであり、
福祉医療機構(WAM)等による資金融資の強化といった手法も考えられる。
こうした法人への支援や法人間の連携のあり方は、福祉分野共通の課題とし
て引き続き議論を深めていく。
979
980
981
982
983
984
985
(6)他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化
○ 小規模経営をしている事業者をはじめ、介護事業所が地域に根差した上で、
利用者のニーズに細やかに沿ったサービス提供を行っていくことは重要であ
る。その上で、報酬の請求や記録・書類作成事務といったバックオフィスの
業務など間接業務の効率化や、施設・設備の共同利用等を行うことで、2040
年に向けて、安定的に事業の継続を図ることが必要である。
986
987
988
989
990
○ 個々の介護事業者により経営課題が解決できない場合も、他事業者との連
携・協働化(※1)、経営の多角化も含めた大規模化(※2)などにより解決が
図られるケースもある。また、社会福祉連携推進法人や小規模事業者のネッ
トワーク構築といった手法もある。
991
992
993
994
995
(※1)複数の法人が組織的な連携体制を構築し、間接業務の効率化や施設・整備の共同利
用、人材確保、人材育成、災害対応、地域貢献等を協働して実施していくこと。
(※2)法人内の介護サービスの規模の拡大や事業所の増設とともに、複数の法人間での合
併や事業譲渡等による規模の拡大を行うこと。
996
○ 小規模経営をしている事業者が安定的に必要な事業を継続していくために
は、まずは、介護事業者間の協働化を進めていくことが有効である。その際、
離職率低下、協働する事業者間での有資格者の確保、経営の安定化、利用者
のニーズへの対応強化、一括仕入れによるコスト減など、協働化や事業者間
997
998
999
29