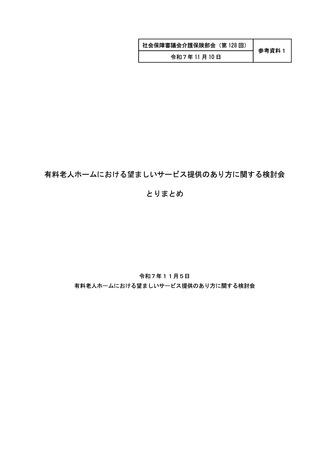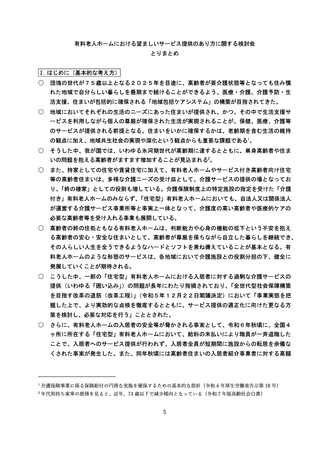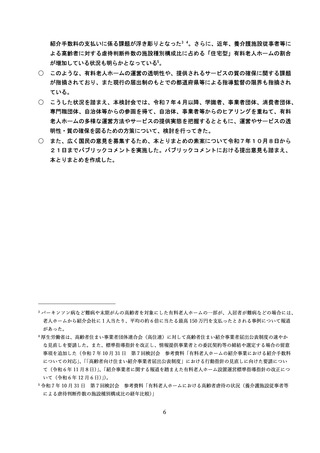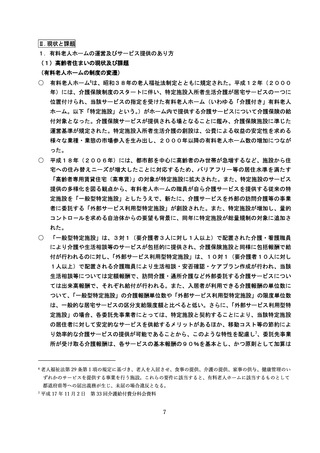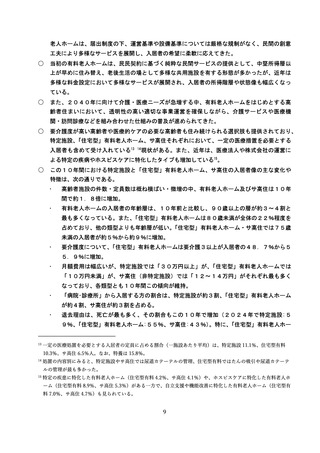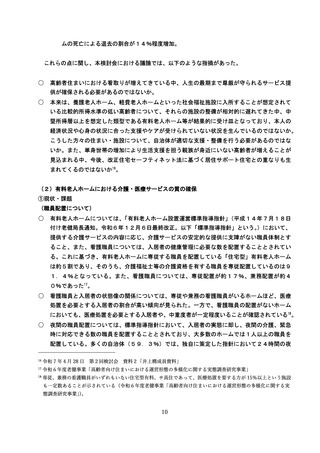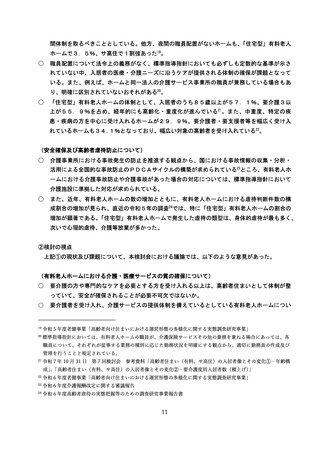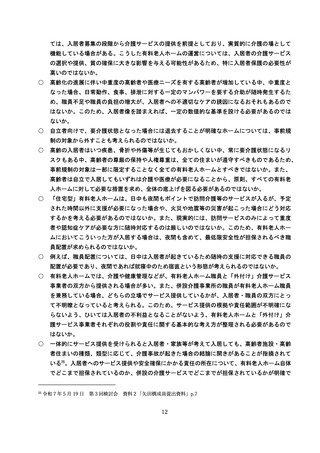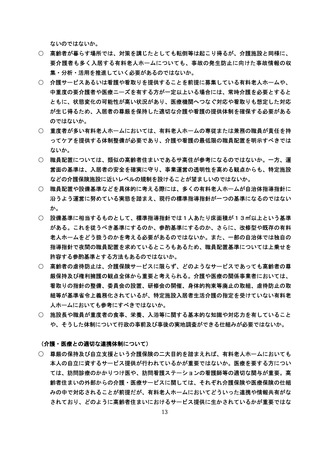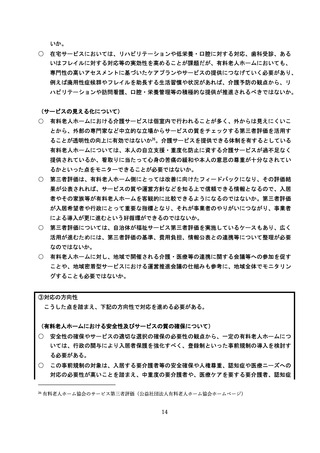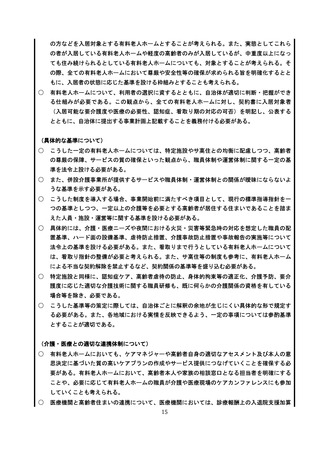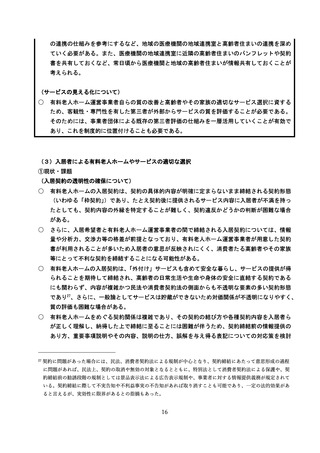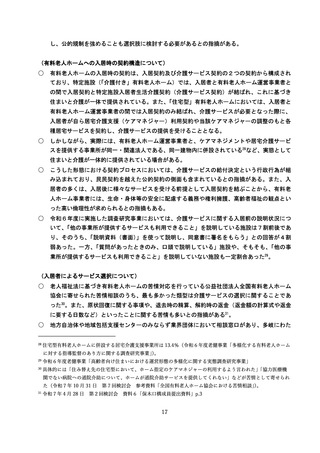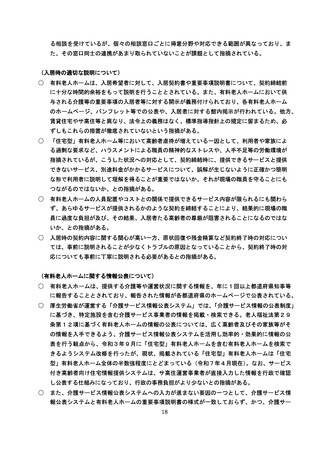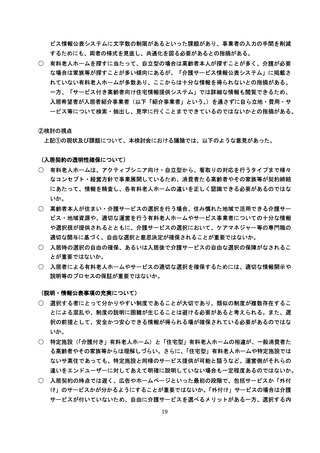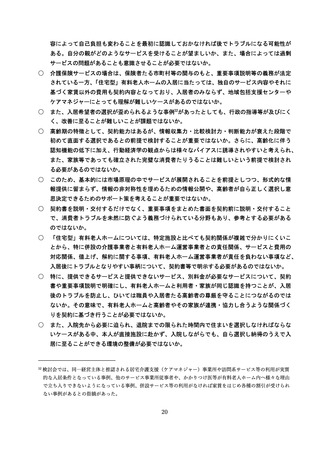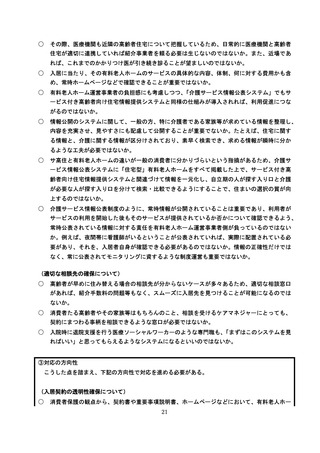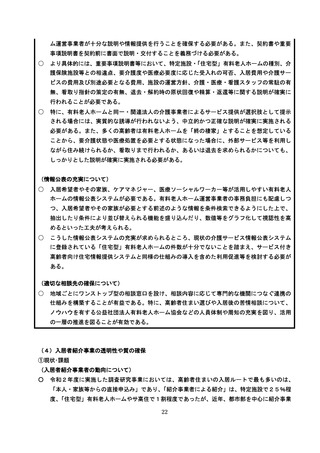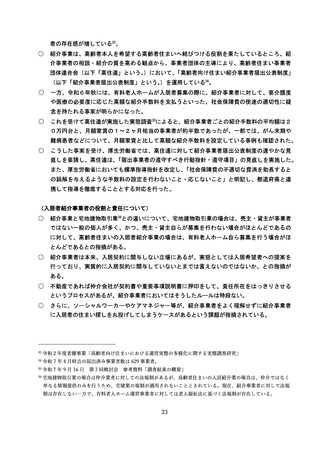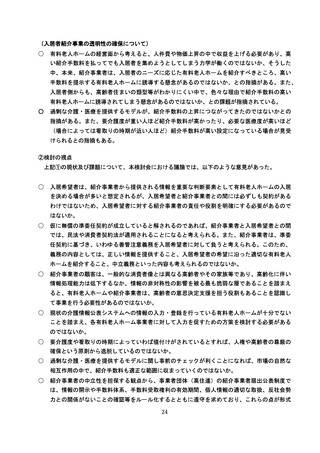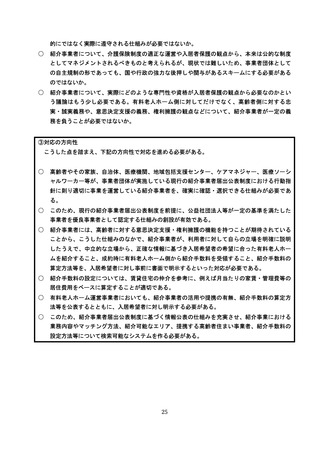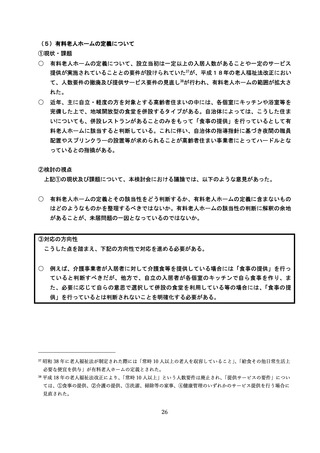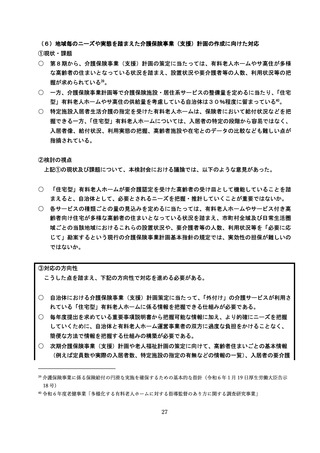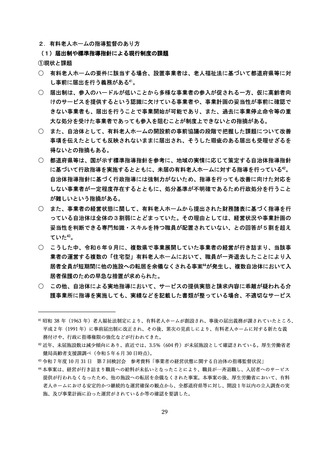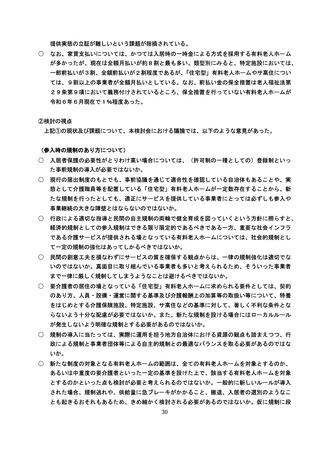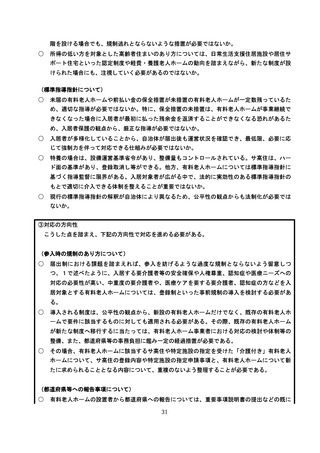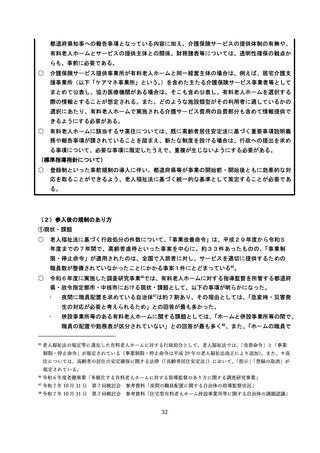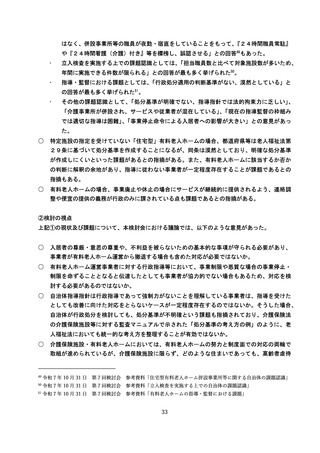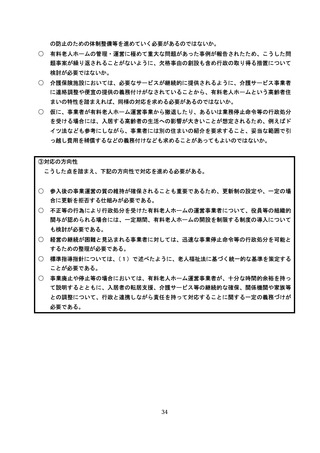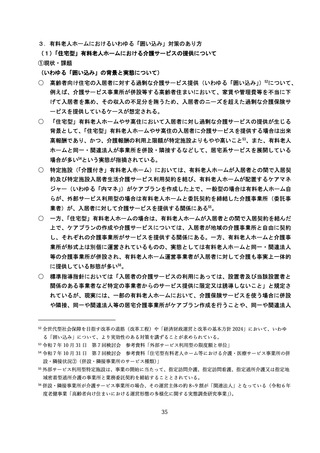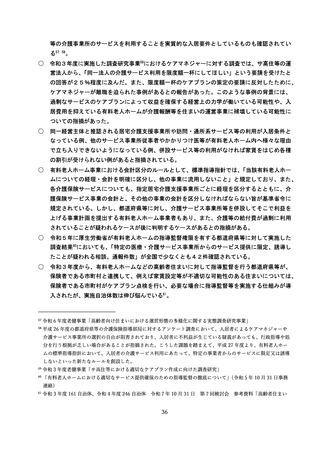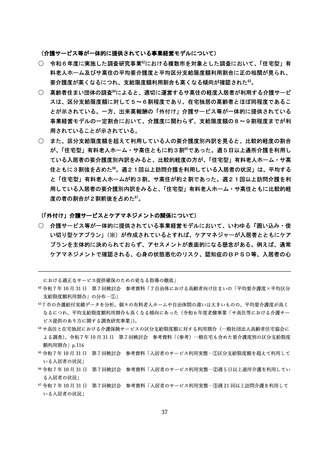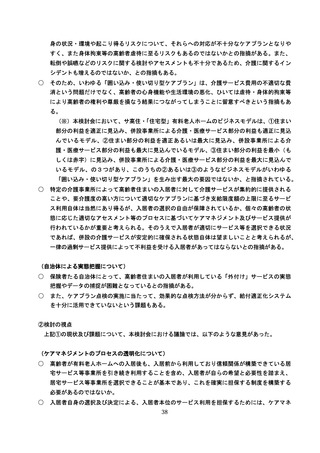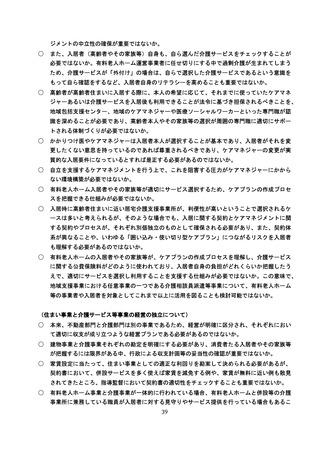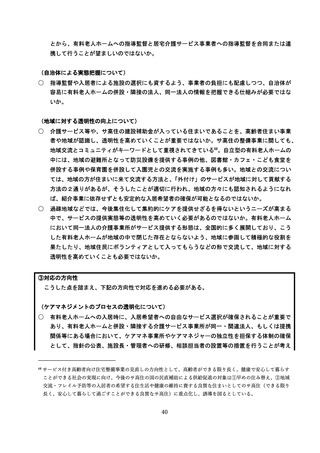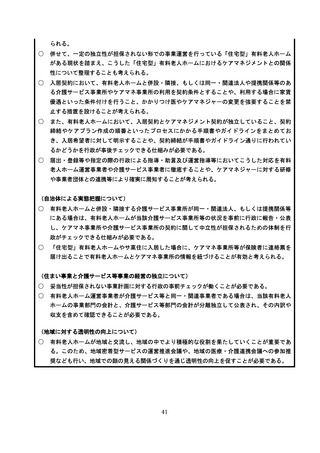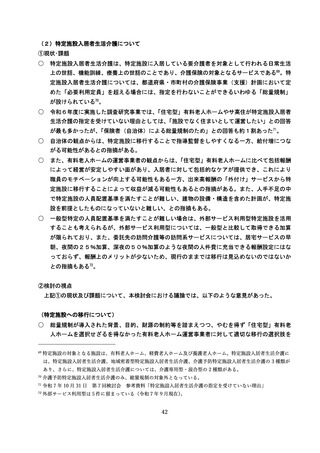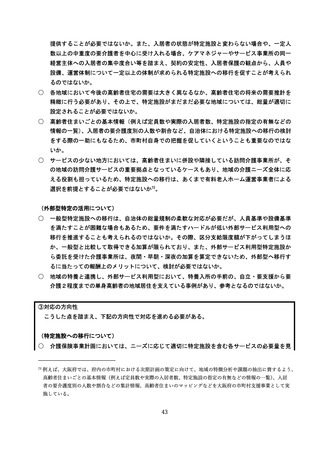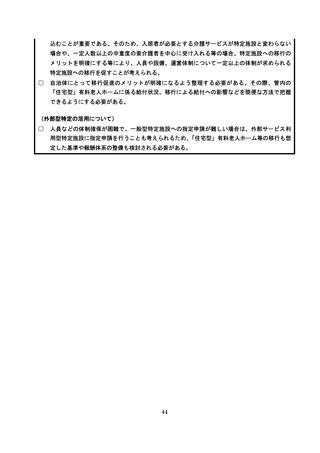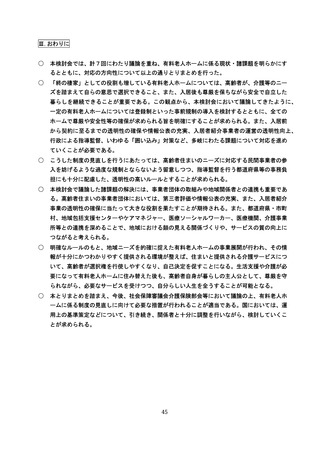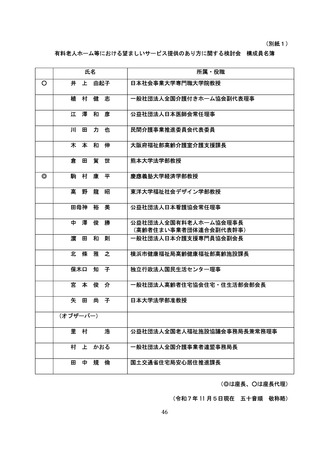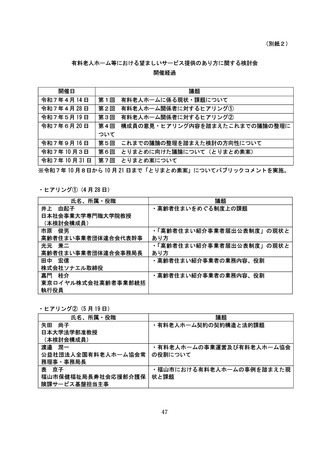よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
適用しないこととなっている。
○
平成23年(2011年)には、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者居住安
定法」という。)が改正され、国土交通省所管の高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、
高齢者向け優良賃貸住宅の3つの高齢者向け賃貸住宅を統合した上で、介護・医療と連携し、
高齢者が安心して生活できるバリアフリー住宅を供給促進する観点から、国土交通省と厚生労
働省の共管の制度として、サービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」という。)が創設され
た。サ高住の96.3%は食事の提供を行っており、サ高住の大半が有料老人ホームにも該当
している8。
○
このように、有料老人ホームは、老人福祉法に基づく規制のほか、介護保険制度の特定施設入
居者生活介護の指定を受けた場合は介護保険法の規制に服し、また、サ高住の登録を受けた有
料老人ホームは、高齢者居住安定法に基づく規制に服している。なお、サ高住の登録を受けた
有料老人ホームについては、高齢者居住安定法に基づき、有料老人ホームの届出は不要となっ
ている。
(有料老人ホームの役割の変遷)
○
有料老人ホームは、急速に増加してきた高齢者住まいのニーズに柔軟かつ機動的に対応し、大
きく増加してきた9 10。特に大都市部においては、新たに特別養護老人ホーム(以下「特養」と
いう。)等を整備できるような公共用地が少ない中、民間のネットワークを活用した土地取得・
借上げやディベロッパーとの連携を通じ迅速な開設が行われてきた。この10年程度(201
6年~2023年)で、大都市部においてはサ高住が自立者・軽度者の主な受け皿と、また、
「住宅型」有料老人ホームが要介護者の主な受け皿となってきた。一方、町村部において、要
介護者は地域の特養に入所し、軽度の方は、特定施設や「住宅型」有料老人ホームが受け皿と
なっている傾向がある11。
○
有料老人ホームをはじめとする民間サービスについては、これまで、行政による指導と民間事
業者自身による自主的な対応を車の両輪として、サービスの質の向上等が図られてきた12。有料
8
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(令和 6 年 3 月末時点)
9
2014 年から 2024 年の 10 年間で、有料老人ホームの施設数は 9,581 件から 17,246 件、入居者数は 387,666 人から
673,689 人と増加しており、サ高住の施設数は 4,932 件から 8,311 件、⼾数は 158,579 ⼾から 288,424 ⼾と増加。
(出典:有料老人ホームについては、厚生労働省老健局の調査結果(令和6年6月末時点)
、サ高住については、
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」による(令和6年9月末時点)
。
10
特定施設入居者生活介護のうち、一般型は、4,555 施設(280,669 人)
、外部サービス利用型は5施設(141 人)と、
一般型が圧倒的に多くを占めている(厚生労働省老健局の調査結果(令和6年6月末時点)
。
11
令和7年 10 月 31 日
第7回検討会 参考資料「地域別要介護度別入居者数(人数積み上げ)−2016 年と 2023 年
の比較」
12
1987 年(昭和 62 年)国の福祉関係3審議会合同企画分科会意見具申において、
「⺠間事業者の創造性、効率性を
損なうことのないよう十分配慮しつつ、国、地方を通ずる行政による適切な指導とあいまって、サービス供給者で
ある⺠間事業者⾃⾝がその倫理を確⽴し、高齢者の信頼にこたえるとともに高齢者の心身の特性に十分配慮すると
いう認識のもとでサービスの質の向上を図るための自主的な措置をとることが求められる。
」とされた。
8
○
平成23年(2011年)には、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者居住安
定法」という。)が改正され、国土交通省所管の高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、
高齢者向け優良賃貸住宅の3つの高齢者向け賃貸住宅を統合した上で、介護・医療と連携し、
高齢者が安心して生活できるバリアフリー住宅を供給促進する観点から、国土交通省と厚生労
働省の共管の制度として、サービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」という。)が創設され
た。サ高住の96.3%は食事の提供を行っており、サ高住の大半が有料老人ホームにも該当
している8。
○
このように、有料老人ホームは、老人福祉法に基づく規制のほか、介護保険制度の特定施設入
居者生活介護の指定を受けた場合は介護保険法の規制に服し、また、サ高住の登録を受けた有
料老人ホームは、高齢者居住安定法に基づく規制に服している。なお、サ高住の登録を受けた
有料老人ホームについては、高齢者居住安定法に基づき、有料老人ホームの届出は不要となっ
ている。
(有料老人ホームの役割の変遷)
○
有料老人ホームは、急速に増加してきた高齢者住まいのニーズに柔軟かつ機動的に対応し、大
きく増加してきた9 10。特に大都市部においては、新たに特別養護老人ホーム(以下「特養」と
いう。)等を整備できるような公共用地が少ない中、民間のネットワークを活用した土地取得・
借上げやディベロッパーとの連携を通じ迅速な開設が行われてきた。この10年程度(201
6年~2023年)で、大都市部においてはサ高住が自立者・軽度者の主な受け皿と、また、
「住宅型」有料老人ホームが要介護者の主な受け皿となってきた。一方、町村部において、要
介護者は地域の特養に入所し、軽度の方は、特定施設や「住宅型」有料老人ホームが受け皿と
なっている傾向がある11。
○
有料老人ホームをはじめとする民間サービスについては、これまで、行政による指導と民間事
業者自身による自主的な対応を車の両輪として、サービスの質の向上等が図られてきた12。有料
8
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(令和 6 年 3 月末時点)
9
2014 年から 2024 年の 10 年間で、有料老人ホームの施設数は 9,581 件から 17,246 件、入居者数は 387,666 人から
673,689 人と増加しており、サ高住の施設数は 4,932 件から 8,311 件、⼾数は 158,579 ⼾から 288,424 ⼾と増加。
(出典:有料老人ホームについては、厚生労働省老健局の調査結果(令和6年6月末時点)
、サ高住については、
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」による(令和6年9月末時点)
。
10
特定施設入居者生活介護のうち、一般型は、4,555 施設(280,669 人)
、外部サービス利用型は5施設(141 人)と、
一般型が圧倒的に多くを占めている(厚生労働省老健局の調査結果(令和6年6月末時点)
。
11
令和7年 10 月 31 日
第7回検討会 参考資料「地域別要介護度別入居者数(人数積み上げ)−2016 年と 2023 年
の比較」
12
1987 年(昭和 62 年)国の福祉関係3審議会合同企画分科会意見具申において、
「⺠間事業者の創造性、効率性を
損なうことのないよう十分配慮しつつ、国、地方を通ずる行政による適切な指導とあいまって、サービス供給者で
ある⺠間事業者⾃⾝がその倫理を確⽴し、高齢者の信頼にこたえるとともに高齢者の心身の特性に十分配慮すると
いう認識のもとでサービスの質の向上を図るための自主的な措置をとることが求められる。
」とされた。
8