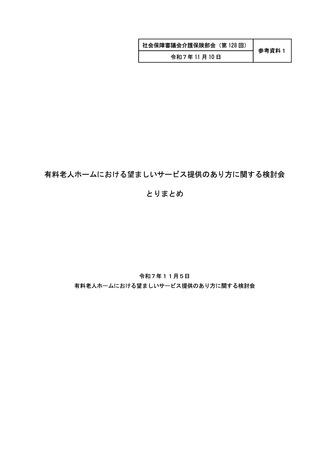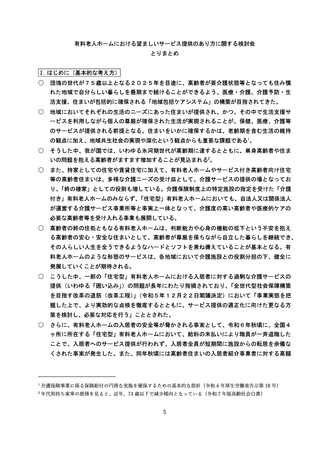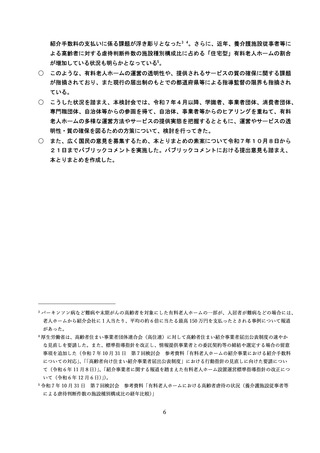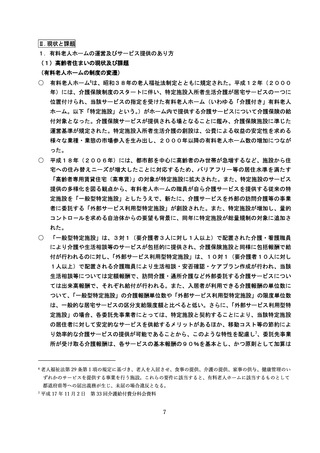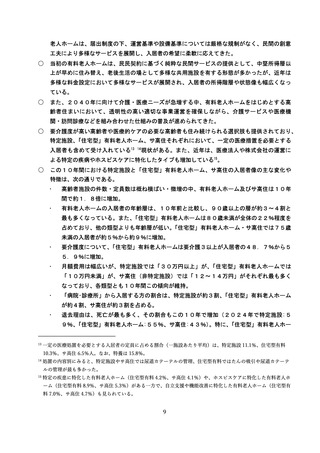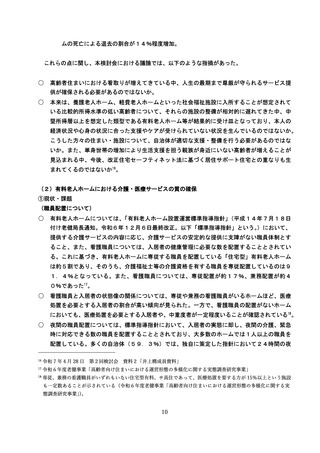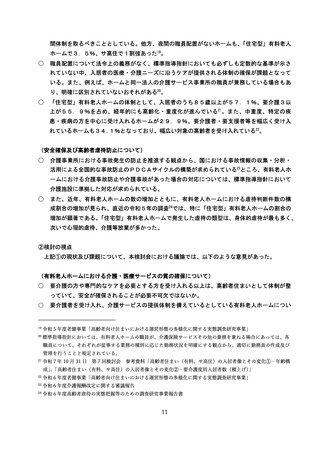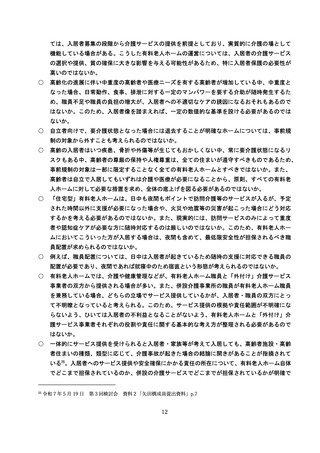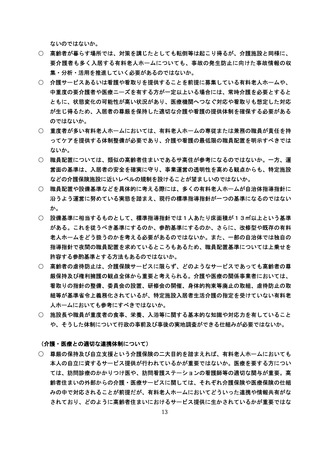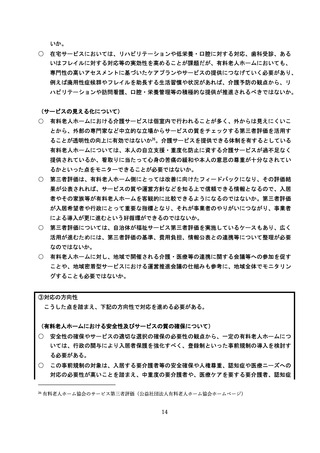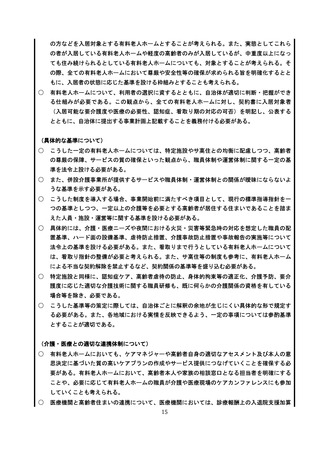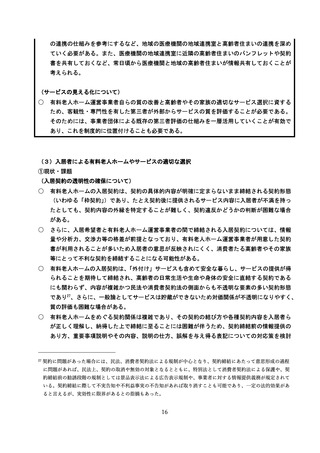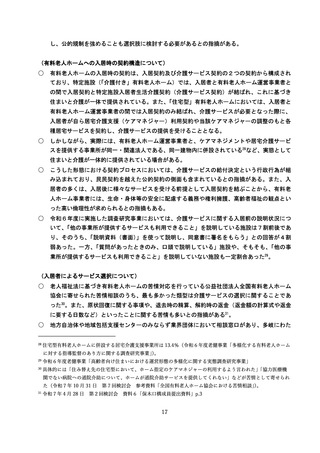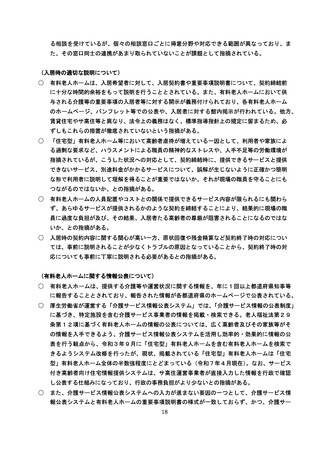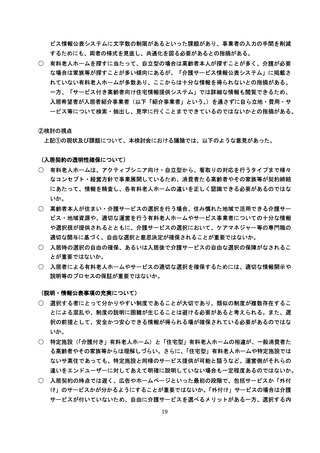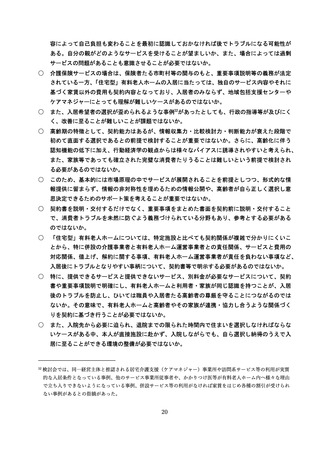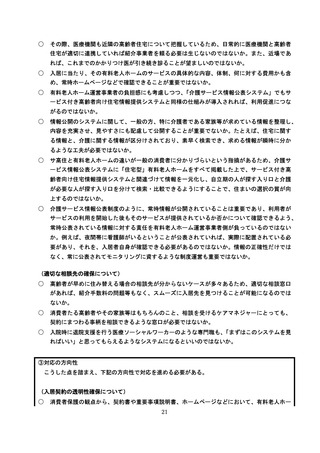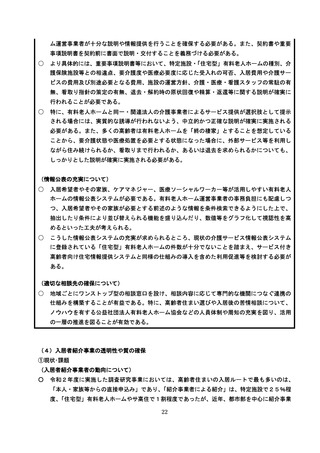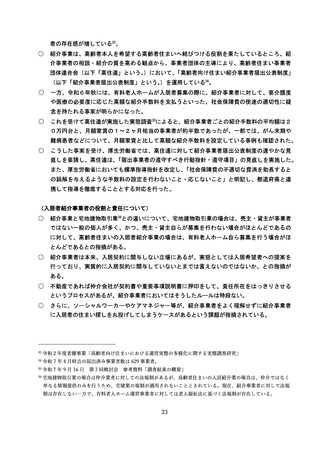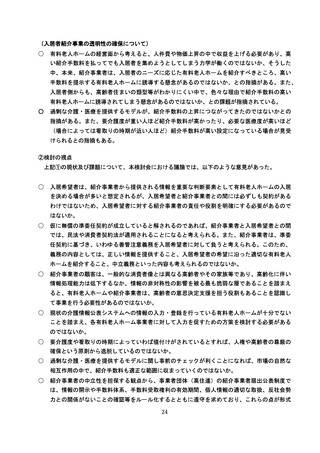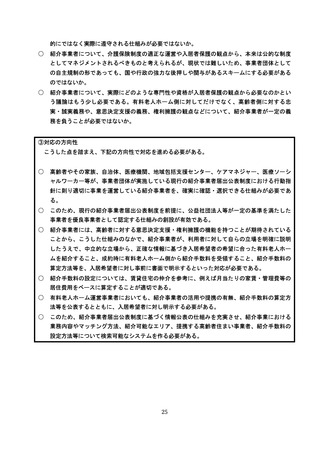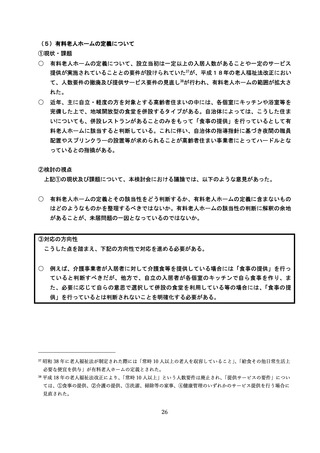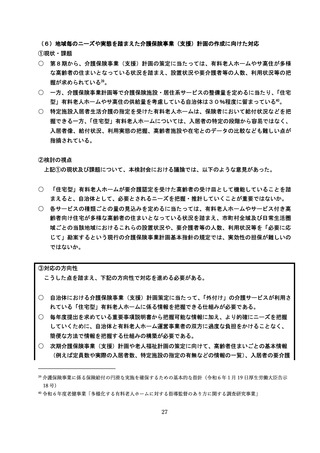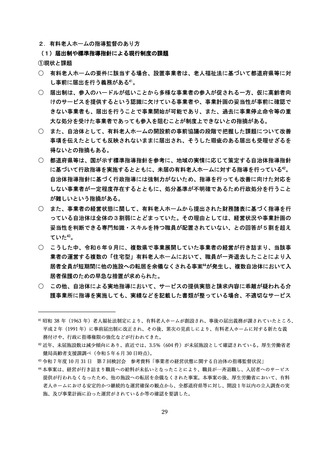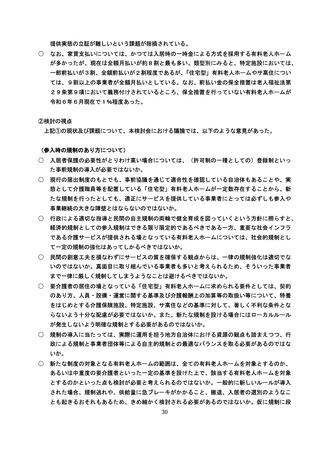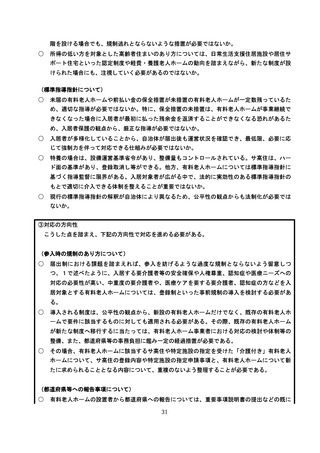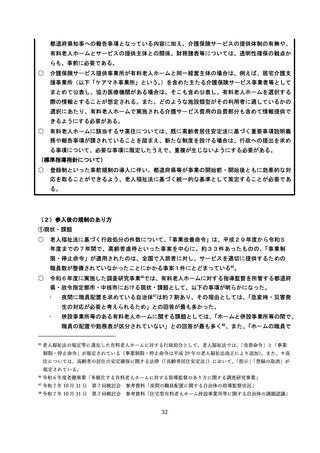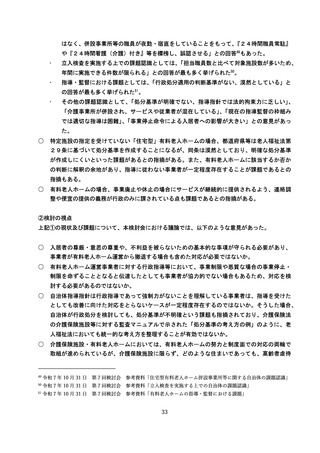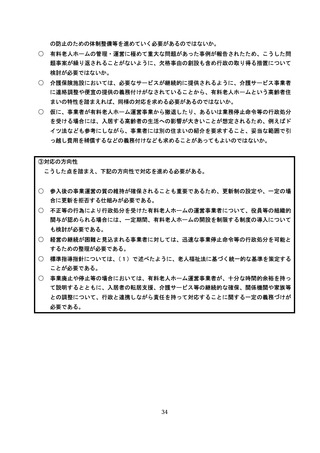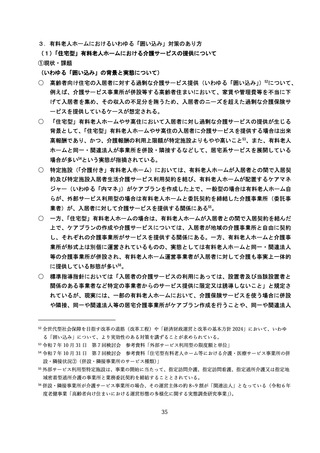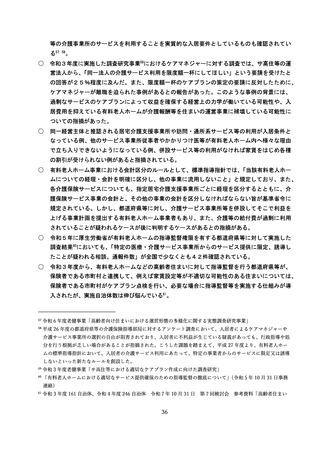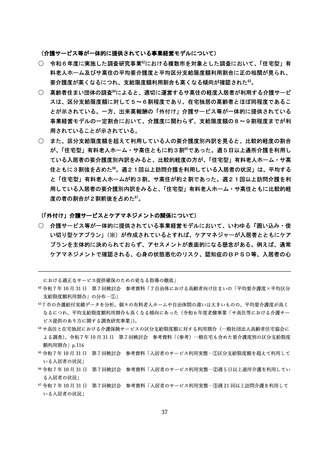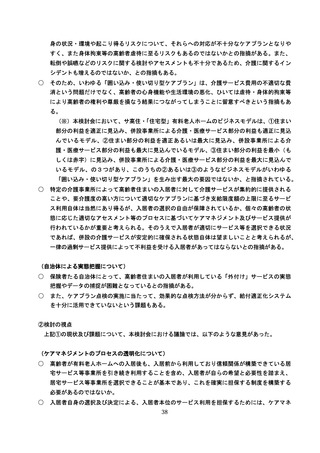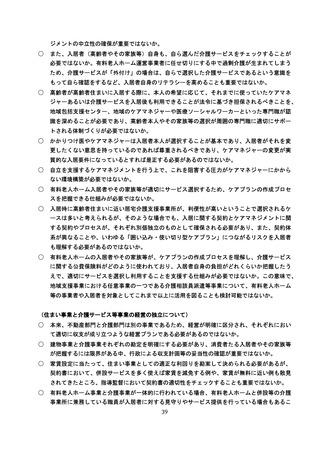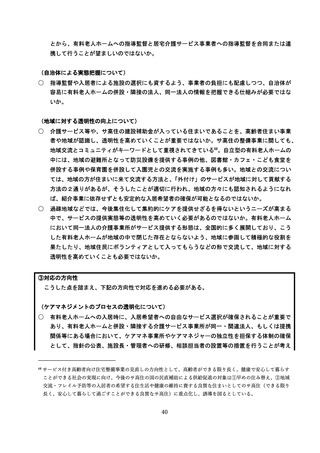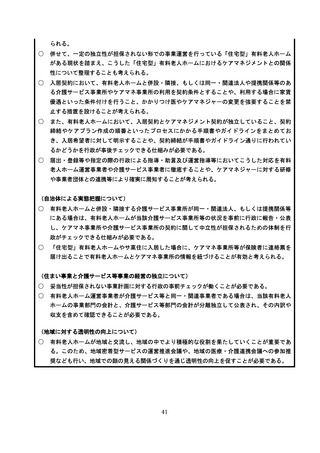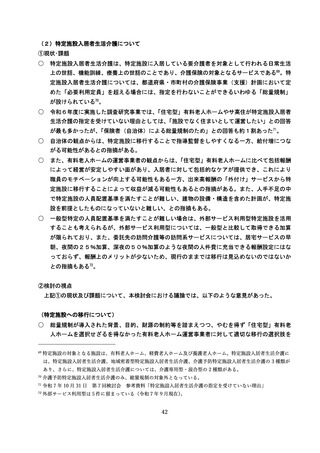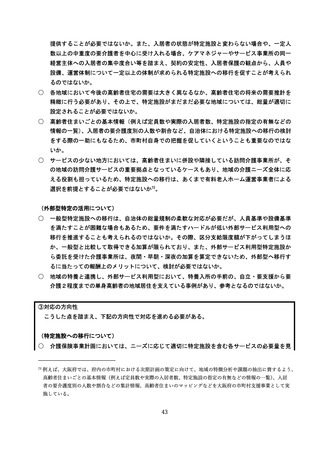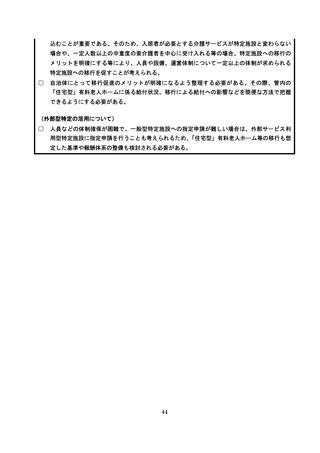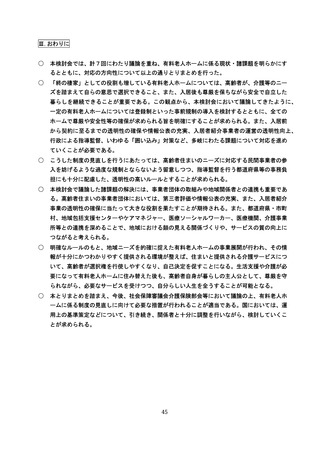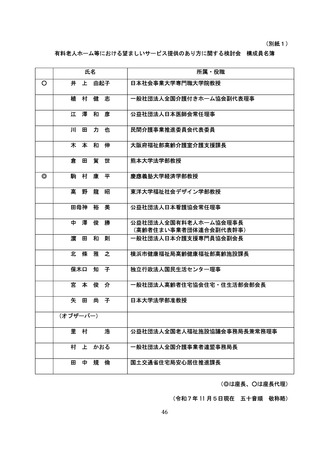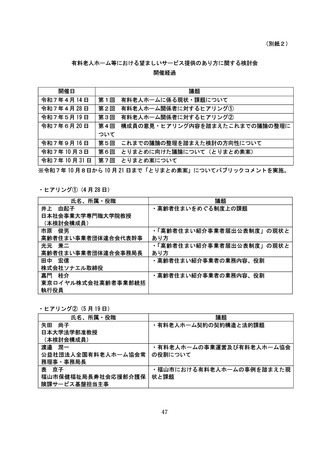よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
いか。
○
在宅サービスにおいては、リハビリテーションや低栄養・口腔に対する対応、歯科受診、ある
いはフレイルに対する対応等の実効性を高めることが課題だが、有料老人ホームにおいても、
専門性の高いアセスメントに基づいたケアプランやサービスの提供につなげていく必要があり、
例えば廃用性症候群やフレイルを助長する生活習慣や状況があれば、介護予防の観点から、リ
ハビリテーションや訪問看護、口腔・栄養管理等の積極的な提供が推進されるべきではないか。
(サービスの見える化について)
○
有料老人ホームにおける介護サービスは個室内で行われることが多く、外からは見えにくいこ
とから、外部の専門家など中立的な立場からサービスの質をチェックする第三者評価を活用す
ることが透明性の向上に有効ではないか26。介護サービスを提供できる体制を有するとしている
有料老人ホームについては、本人の自立支援・重度化防止に資する介護サービスが過不足なく
提供されているか、看取りに当たって心身の苦痛の緩和や本人の意思の尊重が十分なされてい
るかといった点をモニターできることが必要ではないか。
○
第三者評価は、有料老人ホーム側にとっては改善に向けたフィードバックになり、その評価結
果が公表されれば、サービスの質や運営方針などを知る上で信頼できる情報となるので、入居
者やその家族等が有料老人ホームを客観的に比較できるようになるのではないか。第三者評価
が入居希望者や行政にとって重要な指標となり、それが事業者のやりがいにつながり、事業者
による導入が更に進むという好循環ができるのではないか。
○
第三者評価については、自治体が福祉サービス第三者評価を実施しているケースもあり、広く
活用が進むためには、第三者評価の基準、費用負担、情報公表との連携等について整理が必要
なのではないか。
○
有料老人ホームに対し、地域で開催される介護・医療等の連携に関する会議等への参加を促す
ことや、地域密着型サービスにおける運営推進会議の仕組みも参考に、地域全体でモニタリン
グすることも必要ではないか。
③対応の方向性
こうした点を踏まえ、下記の方向性で対応を進める必要がある。
(有料老人ホームにおける安全性及びサービスの質の確保について)
○
安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性の観点から、一定の有料老人ホームにつ
いては、行政の関与により入居者保護を強化すべく、登録制といった事前規制の導入を検討す
る必要がある。
○
この事前規制の対象は、入居する要介護者等の安全確保や人権尊重、認知症や医療ニーズへの
対応の必要性が高いことを踏まえ、中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症
26
有料老人ホーム協会のサービス第三者評価(公益社団法人有料老人ホーム協会ホームページ)
14
○
在宅サービスにおいては、リハビリテーションや低栄養・口腔に対する対応、歯科受診、ある
いはフレイルに対する対応等の実効性を高めることが課題だが、有料老人ホームにおいても、
専門性の高いアセスメントに基づいたケアプランやサービスの提供につなげていく必要があり、
例えば廃用性症候群やフレイルを助長する生活習慣や状況があれば、介護予防の観点から、リ
ハビリテーションや訪問看護、口腔・栄養管理等の積極的な提供が推進されるべきではないか。
(サービスの見える化について)
○
有料老人ホームにおける介護サービスは個室内で行われることが多く、外からは見えにくいこ
とから、外部の専門家など中立的な立場からサービスの質をチェックする第三者評価を活用す
ることが透明性の向上に有効ではないか26。介護サービスを提供できる体制を有するとしている
有料老人ホームについては、本人の自立支援・重度化防止に資する介護サービスが過不足なく
提供されているか、看取りに当たって心身の苦痛の緩和や本人の意思の尊重が十分なされてい
るかといった点をモニターできることが必要ではないか。
○
第三者評価は、有料老人ホーム側にとっては改善に向けたフィードバックになり、その評価結
果が公表されれば、サービスの質や運営方針などを知る上で信頼できる情報となるので、入居
者やその家族等が有料老人ホームを客観的に比較できるようになるのではないか。第三者評価
が入居希望者や行政にとって重要な指標となり、それが事業者のやりがいにつながり、事業者
による導入が更に進むという好循環ができるのではないか。
○
第三者評価については、自治体が福祉サービス第三者評価を実施しているケースもあり、広く
活用が進むためには、第三者評価の基準、費用負担、情報公表との連携等について整理が必要
なのではないか。
○
有料老人ホームに対し、地域で開催される介護・医療等の連携に関する会議等への参加を促す
ことや、地域密着型サービスにおける運営推進会議の仕組みも参考に、地域全体でモニタリン
グすることも必要ではないか。
③対応の方向性
こうした点を踏まえ、下記の方向性で対応を進める必要がある。
(有料老人ホームにおける安全性及びサービスの質の確保について)
○
安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の必要性の観点から、一定の有料老人ホームにつ
いては、行政の関与により入居者保護を強化すべく、登録制といった事前規制の導入を検討す
る必要がある。
○
この事前規制の対象は、入居する要介護者等の安全確保や人権尊重、認知症や医療ニーズへの
対応の必要性が高いことを踏まえ、中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症
26
有料老人ホーム協会のサービス第三者評価(公益社団法人有料老人ホーム協会ホームページ)
14