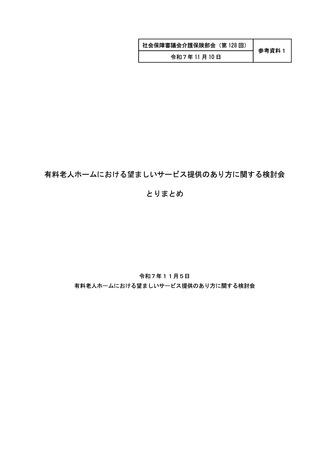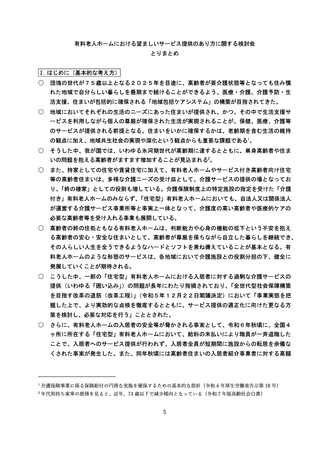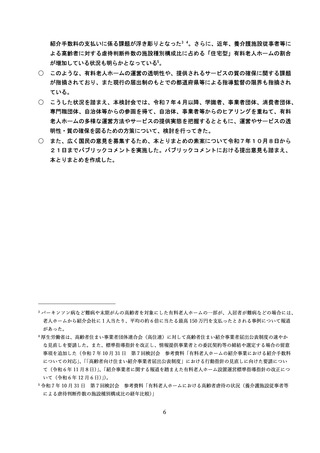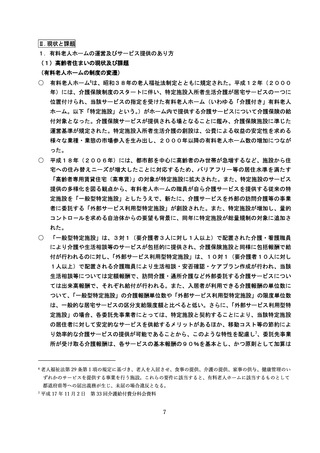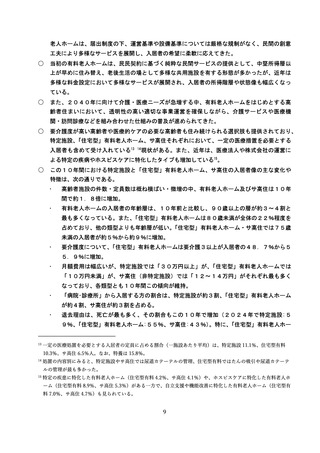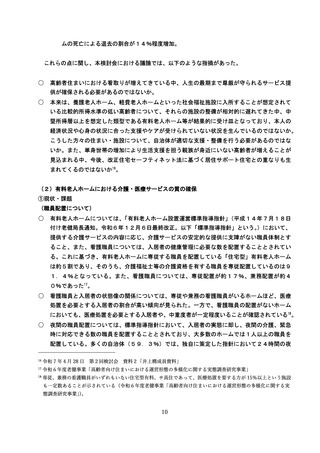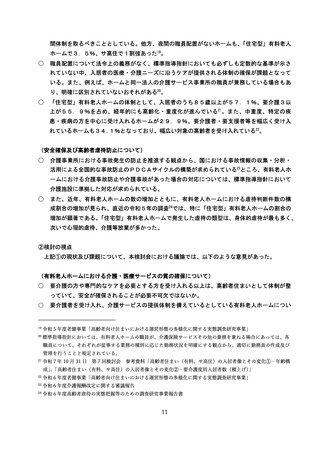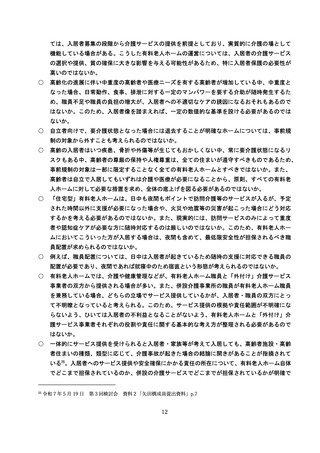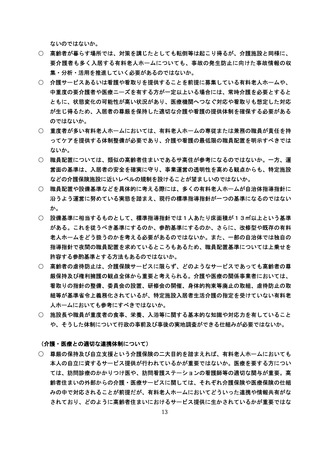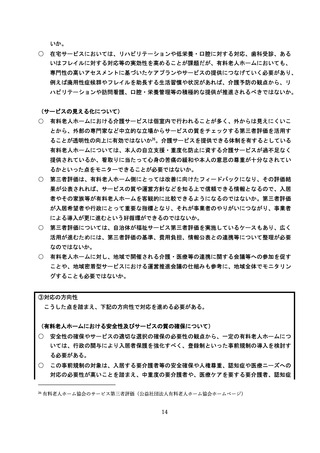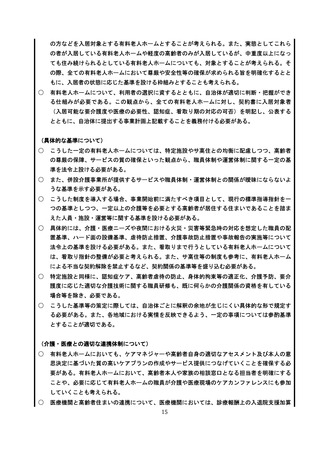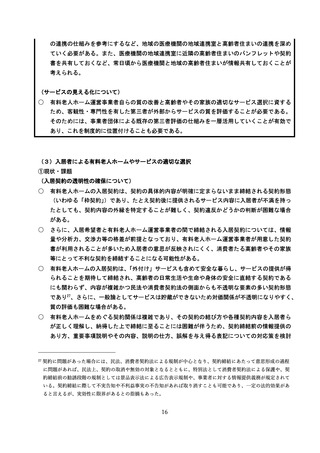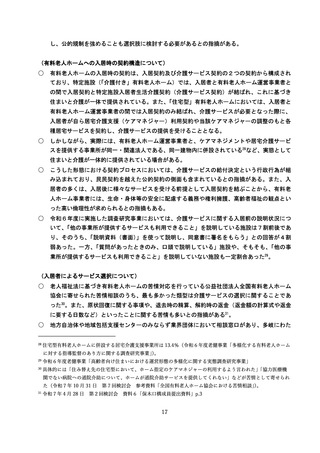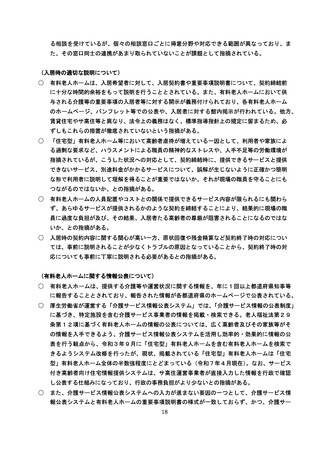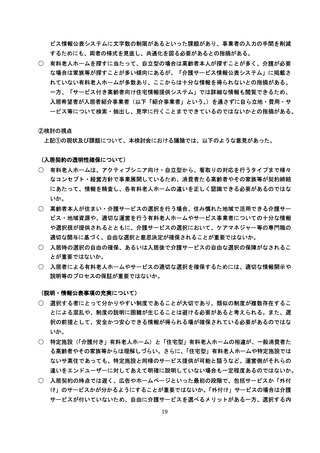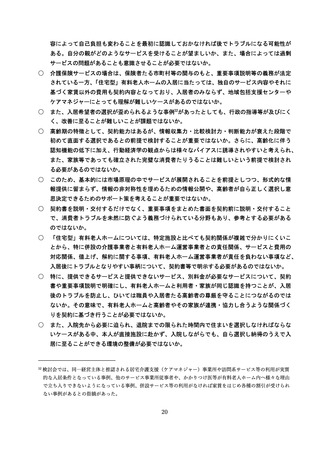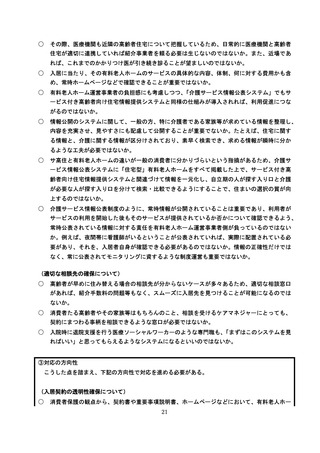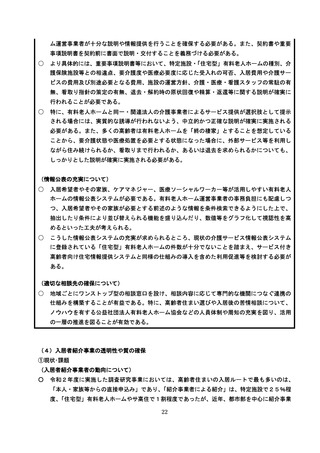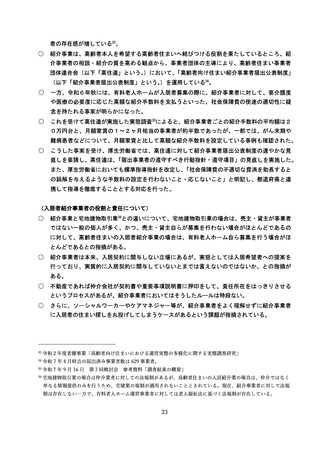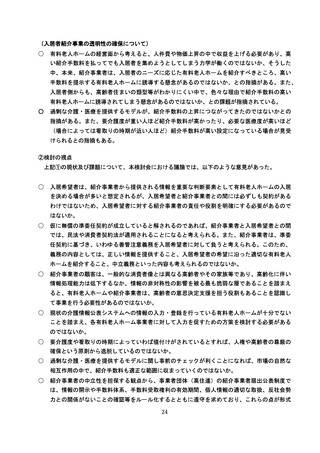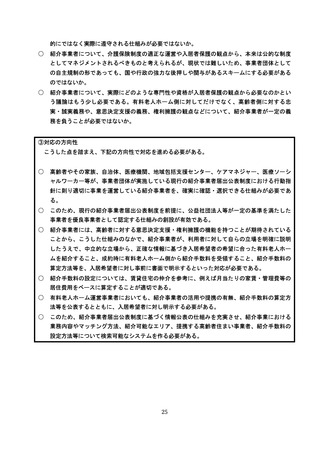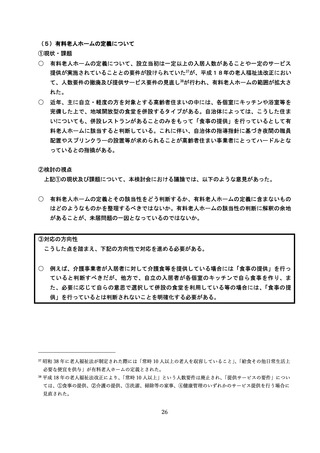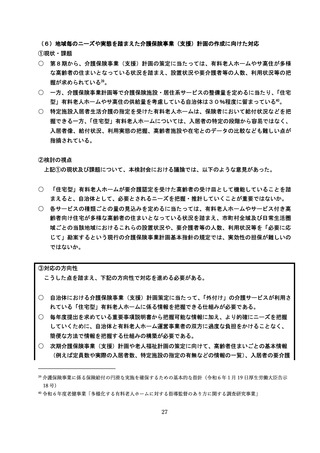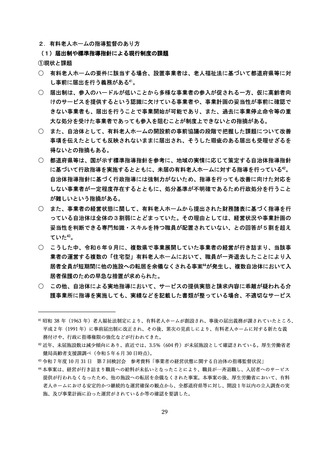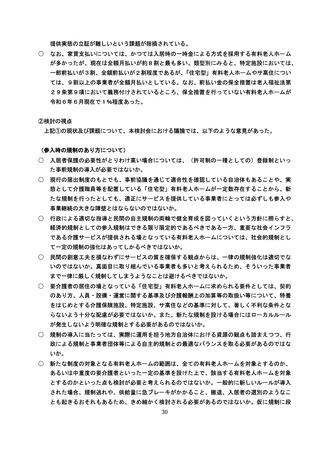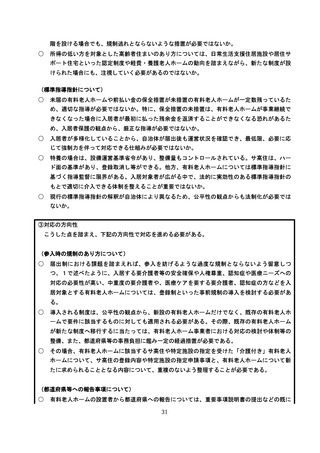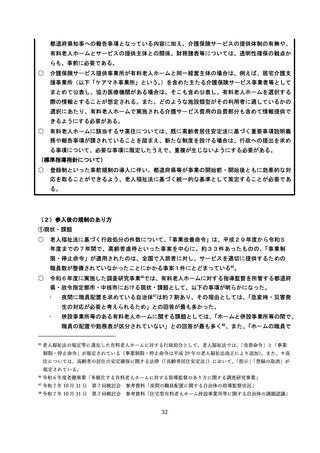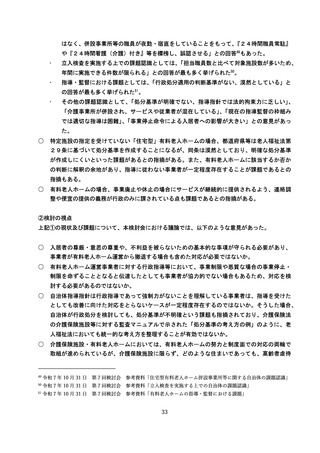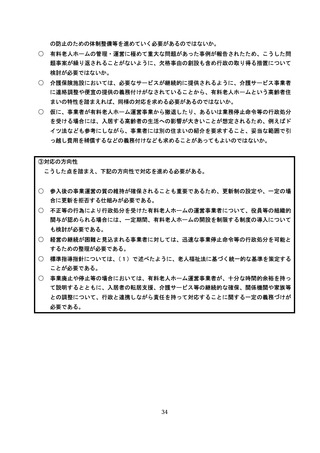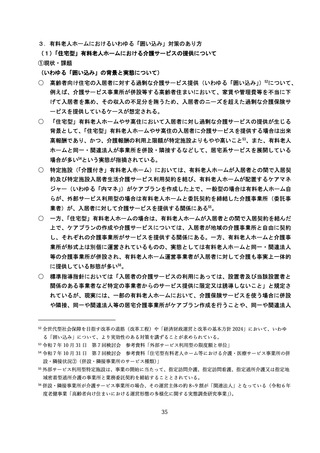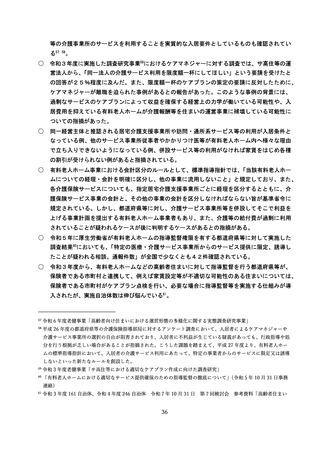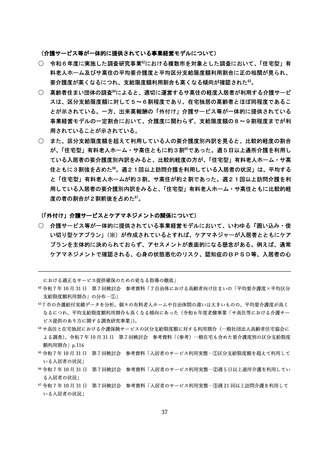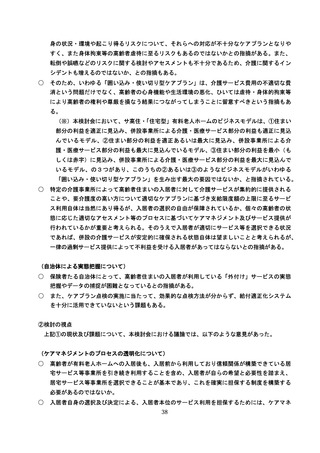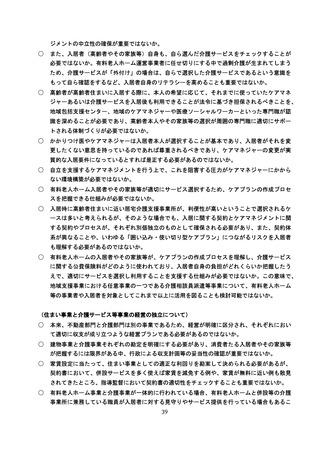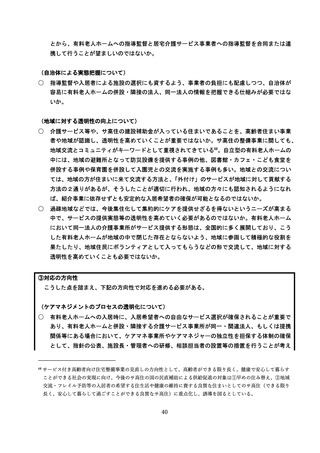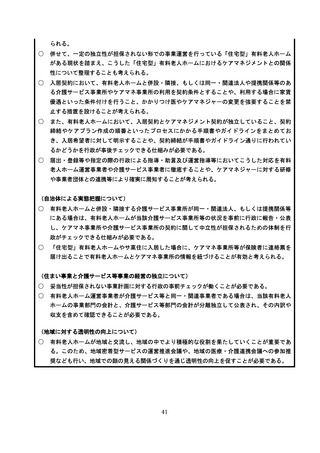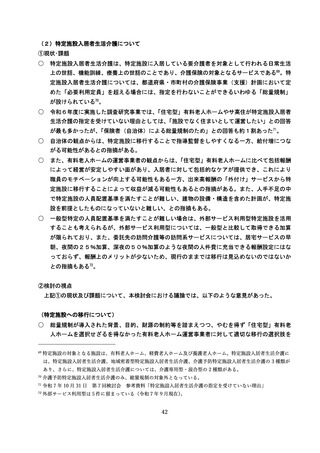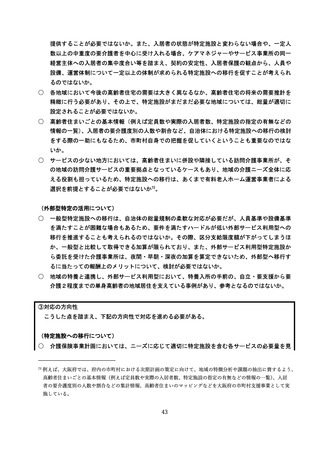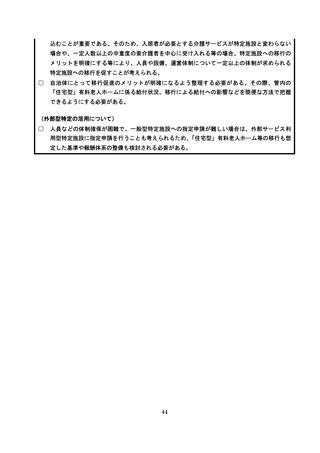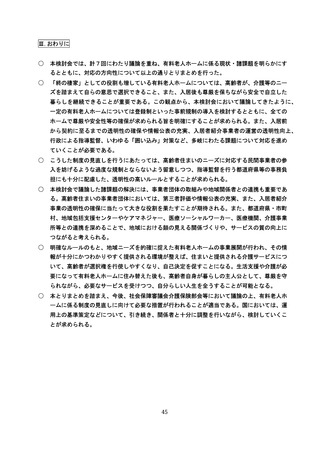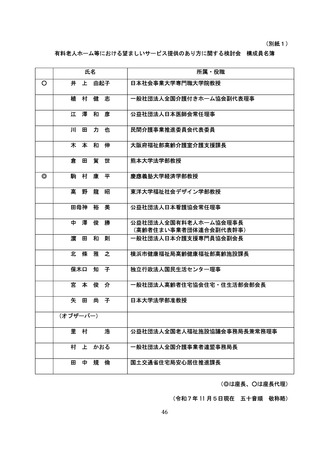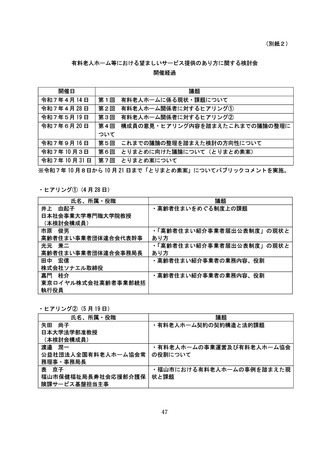よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
提供実態の立証が難しいという課題が指摘されている。
○
なお、家賃支払いについては、かつては入居時の一時金による方式を採用する有料老人ホーム
が多かったが、現在は全額月払いが約8割と最も多い。類型別にみると、特定施設においては、
一部前払いが3割、全額前払いが2割程度であるが、「住宅型」有料老人ホームやサ高住につい
ては、9割以上の事業者が全額月払いとしている。なお、前払い金の保全措置は老人福祉法第
29条第9項において義務付けされているところ、保全措置を行っていない有料老人ホームが
令和6年6月現在で1%程度あった。
②検討の視点
上記①の現状及び課題について、本検討会における議論では、以下のような意見があった。
(参入時の規制のあり方について)
○
入居者保護の必要性がとりわけ高い場合については、(許可制の一種としての)登録制といっ
た事前規制の導入が必要ではないか。
○
現行の届出制度のもとでも、事前協議を通じて適合性を確認している自治体もあることや、実
態として介護職員等を配置している「住宅型」有料老人ホームが一定数存在することから、新
たな規制を行ったとしても、適正にサービスを提供している事業者にとっては必ずしも参入や
事業継続の大きな障壁とはならないのではないか。
○
行政による適切な指導と民間の自主規制の両輪で健全育成を図っていくという方針に照らすと、
経済的規制としての参入規制はできる限り限定的であるべきである一方、重要な社会インフラ
である介護サービスが提供される場となっている有料老人ホームについては、社会的規制とし
て一定の規制の強化はあってしかるべきではないか。
○
民間の創意工夫を損なわずにサービスの質を確保する観点からは、一律の規制強化は適切でな
いのではないか。真面目に取り組んでいる事業者も多いと考えられるため、そういった事業者
まで一律に厳しく規制してしまうようなことは避けるべきではないか。
○
要介護者の居住の場となっている「住宅型」有料老人ホームに求められる要件としては、契約
のあり方、人員・設備・運営に関する基準及び介護報酬上の加算等の取扱い等について、特養
をはじめとする介護保険施設、特定施設、サ高住などの基準に対して、著しく不利な条件とな
らないよう十分な配慮が必要ではないか。また、新たな規制を設ける場合にはローカルルール
が発生しないよう明確な規制とする必要があるのではないか。
○
規制の導入に当たっては、実際に運用を担う地方自治体における資源の観点も踏まえつつ、行
政による規制と事業者団体等による自主的規制との最適なバランスを取る必要があるのではな
いか。
○
新たな制度の対象となる有料老人ホームの範囲は、全ての有料老人ホームを対象とするのか、
あるいは中重度の要介護者といった一定の基準を設けた上で、該当する有料老人ホームを対象
とするのかといった点も検討が必要と考えられるのではないか。一般的に新しいルールが導入
された場合、規制逃れや、供給量に急ブレーキがかかること、撤退、入居者の選別のようなこ
とも起きるおそれもあるため、きめ細かく検討される必要があるのではないか。仮に規制に段
30
○
なお、家賃支払いについては、かつては入居時の一時金による方式を採用する有料老人ホーム
が多かったが、現在は全額月払いが約8割と最も多い。類型別にみると、特定施設においては、
一部前払いが3割、全額前払いが2割程度であるが、「住宅型」有料老人ホームやサ高住につい
ては、9割以上の事業者が全額月払いとしている。なお、前払い金の保全措置は老人福祉法第
29条第9項において義務付けされているところ、保全措置を行っていない有料老人ホームが
令和6年6月現在で1%程度あった。
②検討の視点
上記①の現状及び課題について、本検討会における議論では、以下のような意見があった。
(参入時の規制のあり方について)
○
入居者保護の必要性がとりわけ高い場合については、(許可制の一種としての)登録制といっ
た事前規制の導入が必要ではないか。
○
現行の届出制度のもとでも、事前協議を通じて適合性を確認している自治体もあることや、実
態として介護職員等を配置している「住宅型」有料老人ホームが一定数存在することから、新
たな規制を行ったとしても、適正にサービスを提供している事業者にとっては必ずしも参入や
事業継続の大きな障壁とはならないのではないか。
○
行政による適切な指導と民間の自主規制の両輪で健全育成を図っていくという方針に照らすと、
経済的規制としての参入規制はできる限り限定的であるべきである一方、重要な社会インフラ
である介護サービスが提供される場となっている有料老人ホームについては、社会的規制とし
て一定の規制の強化はあってしかるべきではないか。
○
民間の創意工夫を損なわずにサービスの質を確保する観点からは、一律の規制強化は適切でな
いのではないか。真面目に取り組んでいる事業者も多いと考えられるため、そういった事業者
まで一律に厳しく規制してしまうようなことは避けるべきではないか。
○
要介護者の居住の場となっている「住宅型」有料老人ホームに求められる要件としては、契約
のあり方、人員・設備・運営に関する基準及び介護報酬上の加算等の取扱い等について、特養
をはじめとする介護保険施設、特定施設、サ高住などの基準に対して、著しく不利な条件とな
らないよう十分な配慮が必要ではないか。また、新たな規制を設ける場合にはローカルルール
が発生しないよう明確な規制とする必要があるのではないか。
○
規制の導入に当たっては、実際に運用を担う地方自治体における資源の観点も踏まえつつ、行
政による規制と事業者団体等による自主的規制との最適なバランスを取る必要があるのではな
いか。
○
新たな制度の対象となる有料老人ホームの範囲は、全ての有料老人ホームを対象とするのか、
あるいは中重度の要介護者といった一定の基準を設けた上で、該当する有料老人ホームを対象
とするのかといった点も検討が必要と考えられるのではないか。一般的に新しいルールが導入
された場合、規制逃れや、供給量に急ブレーキがかかること、撤退、入居者の選別のようなこ
とも起きるおそれもあるため、きめ細かく検討される必要があるのではないか。仮に規制に段
30