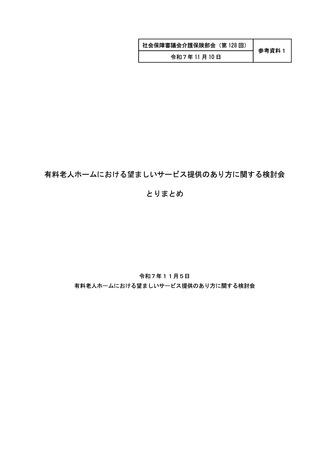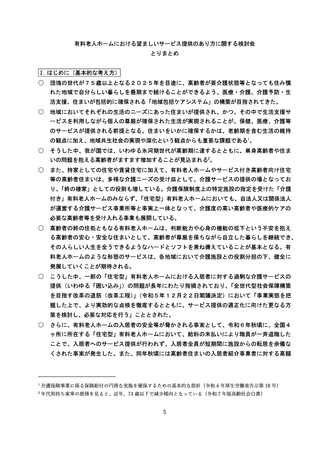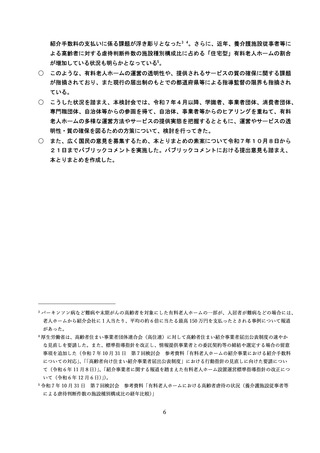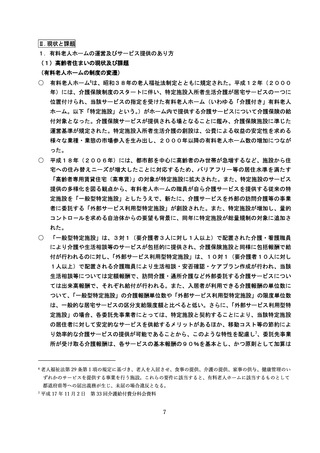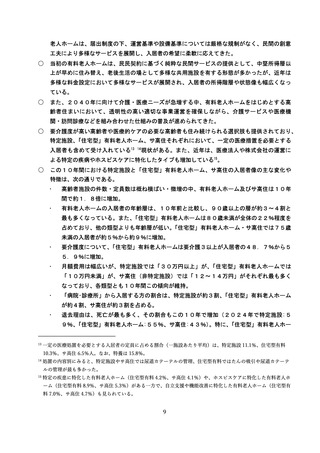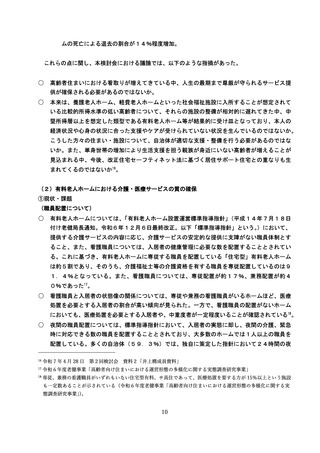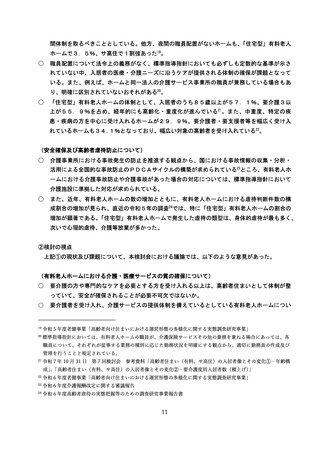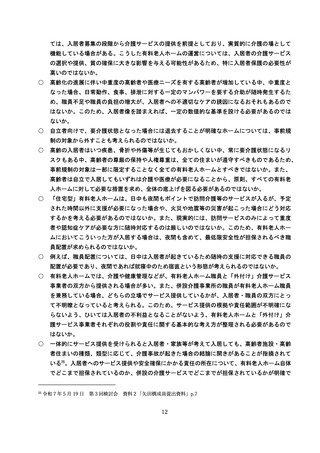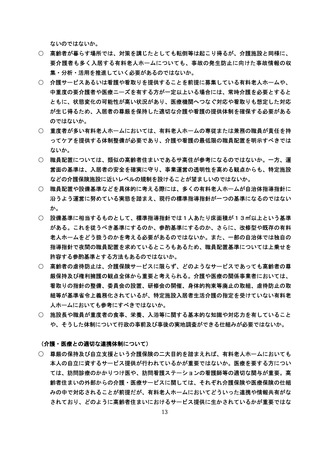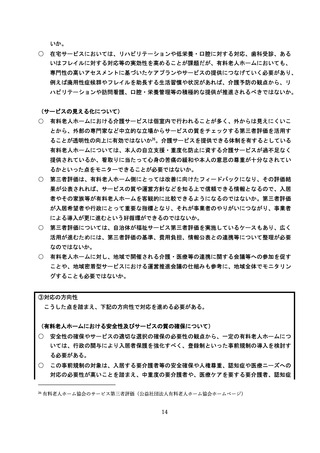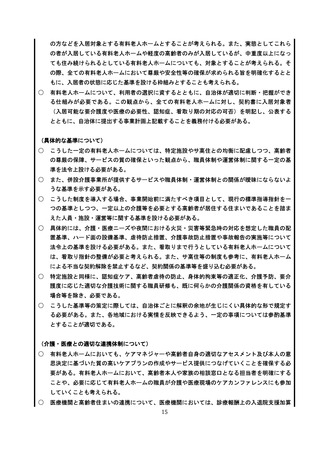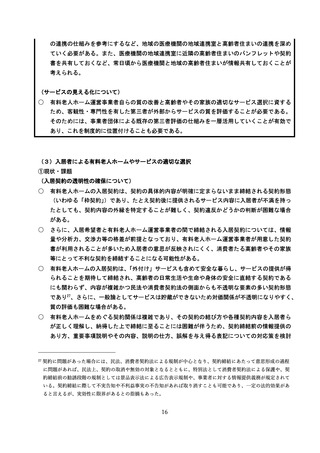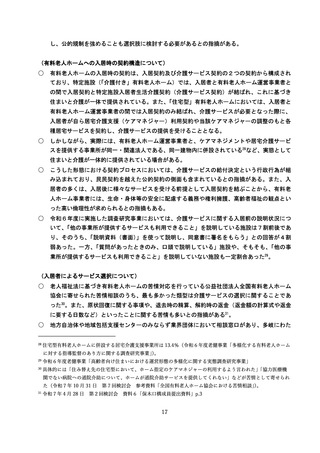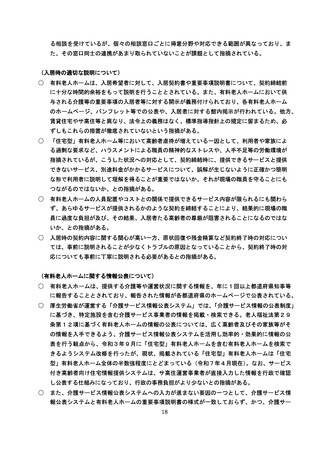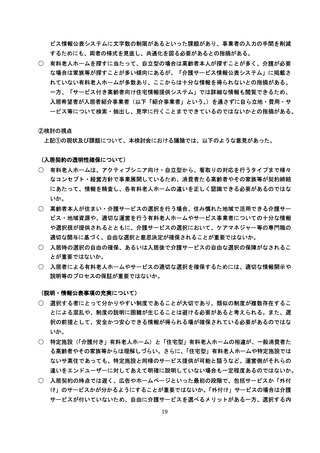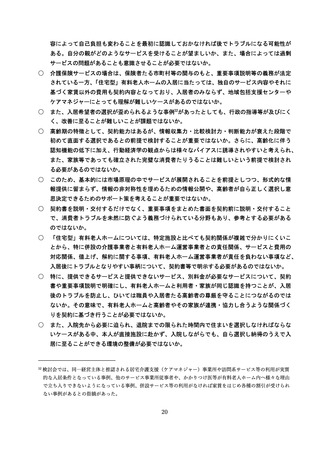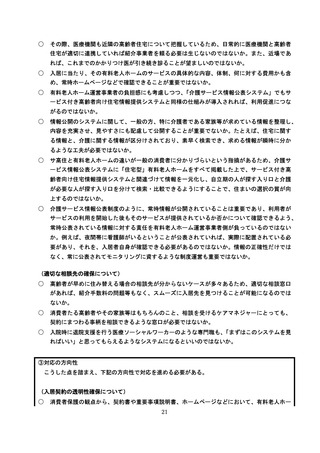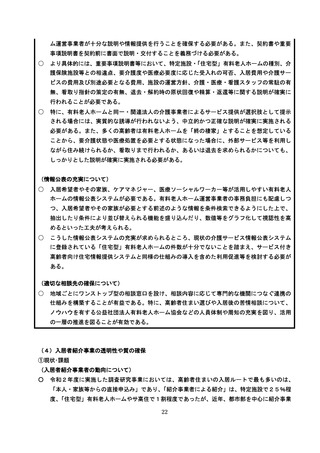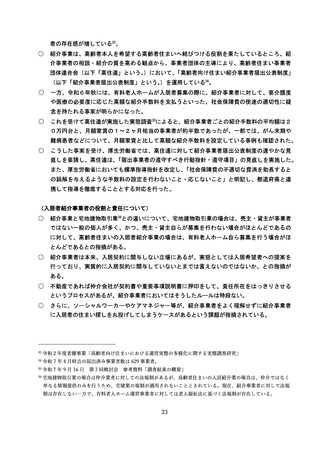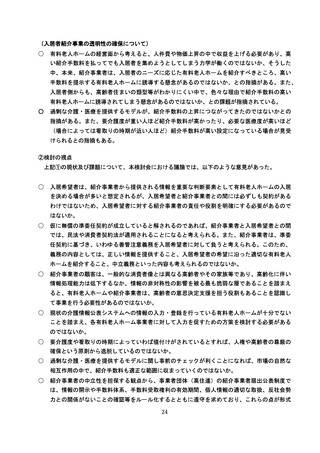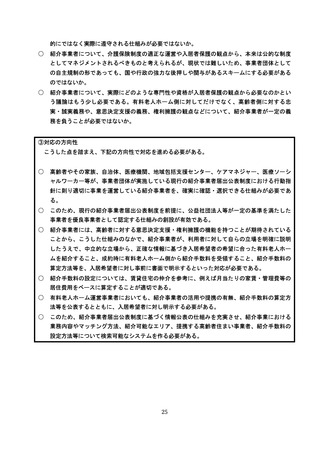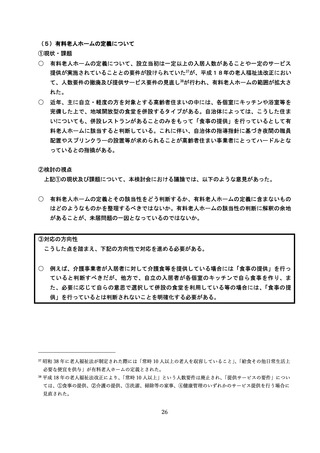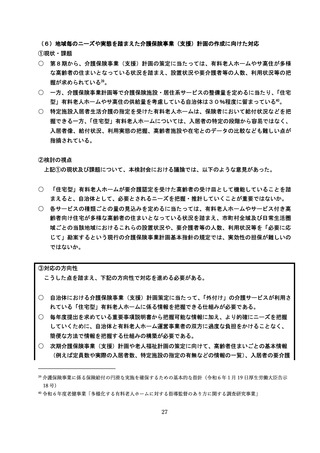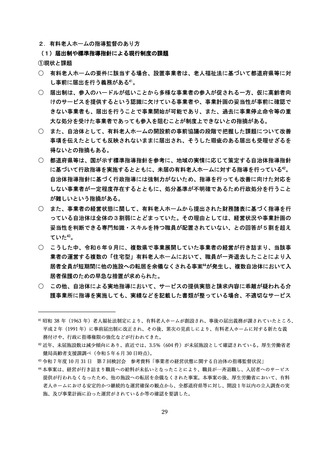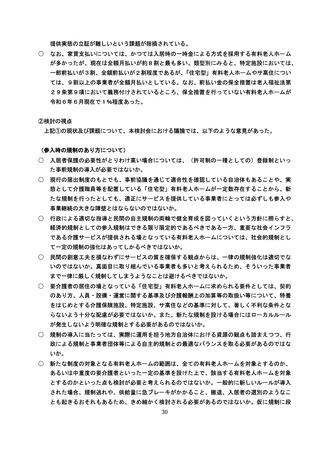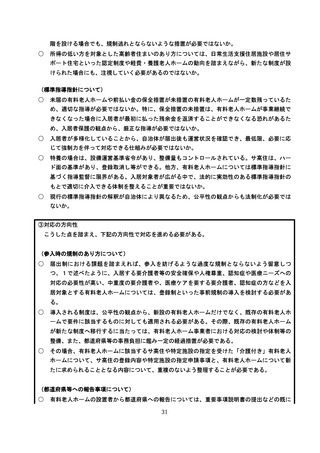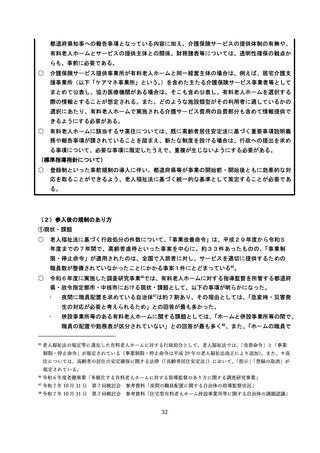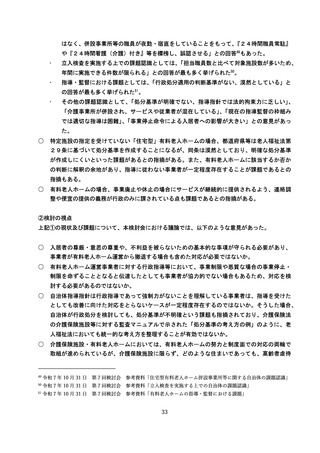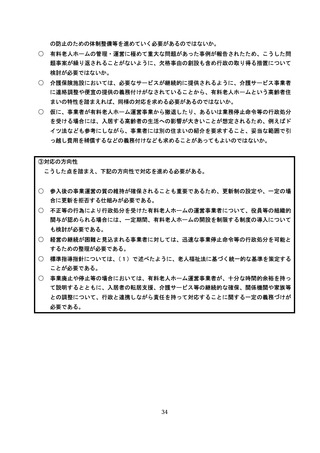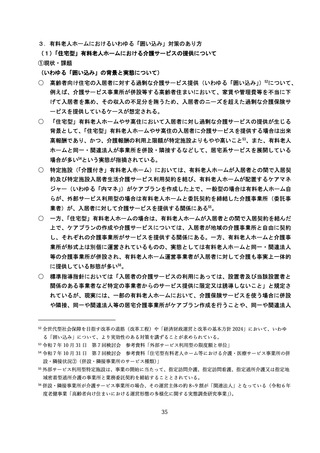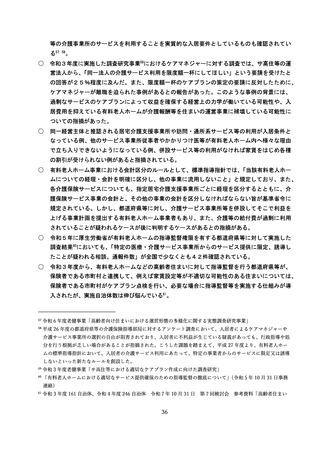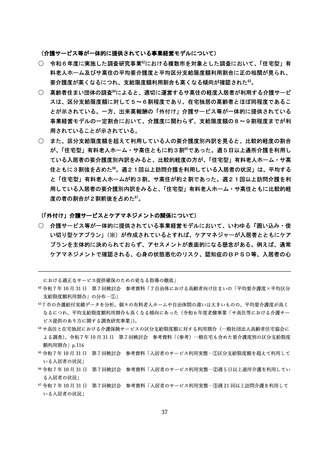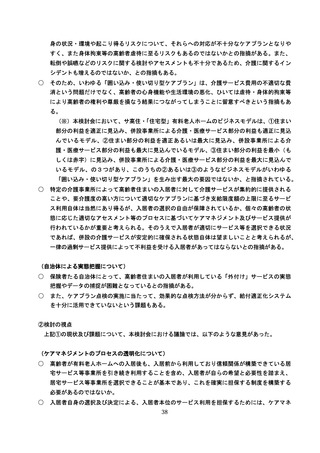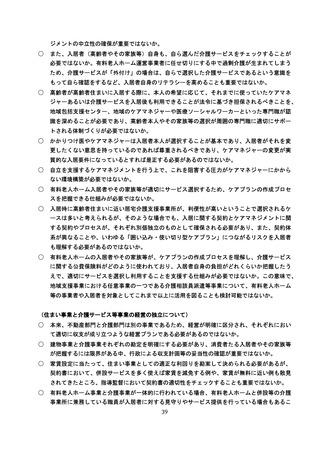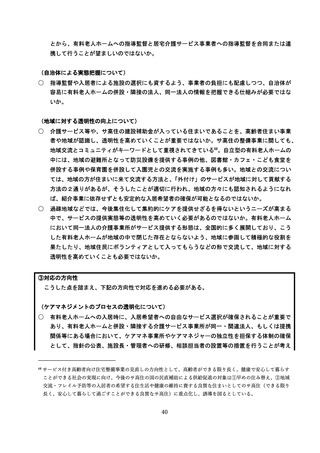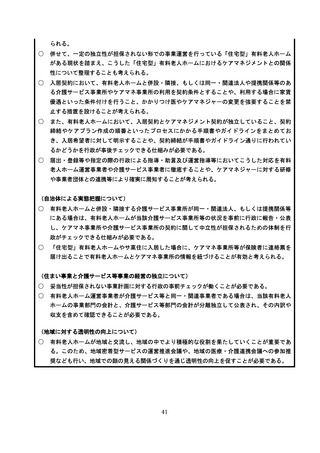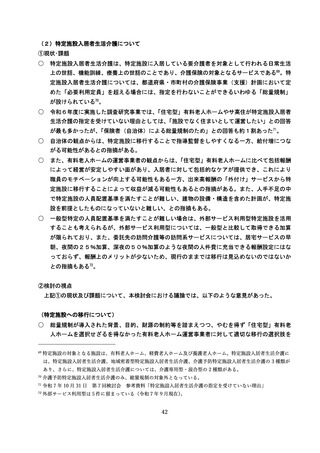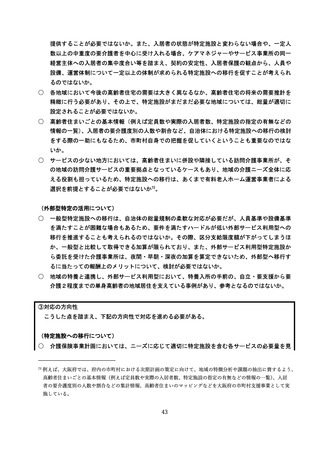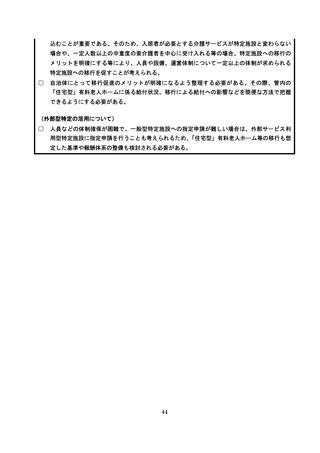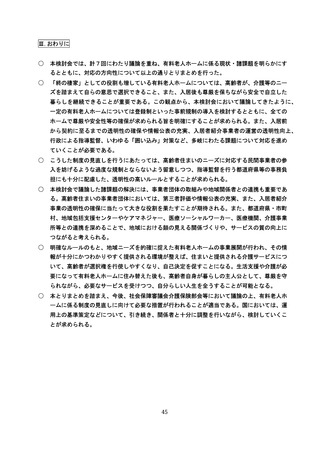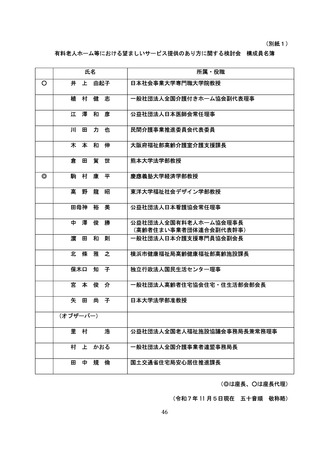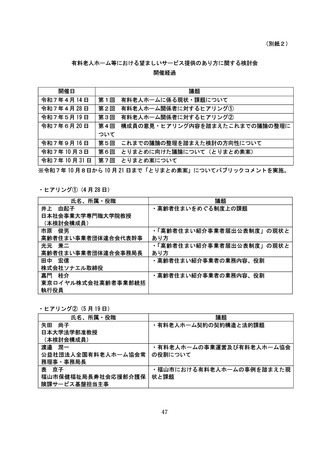よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
容によって自己負担も変わることを最初に認識しておかなければ後でトラブルになる可能性が
ある。自分の親がどのようなサービスを受けることが望ましいか、また、場合によっては過剰
サービスの問題があることも意識させることが必要ではないか。
○
介護保険サービスの場合は、保険者たる市町村等の関与のもと、重要事項説明等の義務が法定
されている一方、「住宅型」有料老人ホームの入居に当たっては、独自のサービス内容やそれに
基づく家賃以外の費用も契約内容となっており、入居者のみならず、地域包括支援センターや
ケアマネジャーにとっても理解が難しいケースがあるのではないか。
○
また、入居希望者の選択が歪められるような事例32があったとしても、行政の指導等が及びにく
く、改善に至ることが難しいことが課題ではないか。
○
高齢期の特徴として、契約能力はあるが、情報収集力・比較検討力・判断能力が衰えた段階で
初めて直面する選択であるとの前提で検討することが重要ではないか。さらに、高齢化に伴う
認知機能の低下に加え、行動経済学の観点からは様々なバイアスに誘導されやすいと考えられ、
また、家族等であっても確立された完璧な消費者たりうることは難しいという前提で検討され
る必要があるのではないか。
○
このため、基本的には市場原理の中でサービスが展開されることを前提としつつ、形式的な情
報提供に留まらず、情報の非対称性を埋めるための情報公開や、高齢者が自ら正しく選択し意
思決定できるためのサポート策を考えることが重要ではないか。
○
契約書を説明・交付するだけでなく、重要事項をまとめた書面を契約前に説明・交付すること
で、消費者トラブルを未然に防ぐよう義務づけられている分野もあり、参考とする必要がある
のではないか。
○
「住宅型」有料老人ホームについては、特定施設と比べても契約関係が複雑で分かりにくいこ
とから、特に併設の介護事業者と有料老人ホーム運営事業者との責任関係、サービスと費用の
対応関係、値上げ、解約に関する事項、有料老人ホーム運営事業者が責任を負わない事項など、
入居後にトラブルとなりやすい事柄について、契約書等で明示する必要があるのではないか。
○
特に、提供できるサービスと提供できないサービス、別料金が必要なサービスについて、契約
書や重要事項説明で明確にし、有料老人ホームと利用者・家族が同じ認識を持つことが、入居
後のトラブルを防止し、ひいては職員や入居者たる高齢者の尊厳を守ることにつながるのでは
ないか。その意味で、有料老人ホームと高齢者やその家族が連携・協力し合うような関係づく
りを契約に基づき行うことが必要ではないか。
○
また、入院先から必要に迫られ、退院までの限られた時間内で住まいを選択しなければならな
いケースがある中、本人が直接施設に赴かず、入院しながらでも、自ら選択し納得のうえで入
居に至ることができる環境の整備が必要ではないか。
32
検討会では、同一経営主体と推認される居宅介護支援(ケアマネジャー)事業所や訪問系サービス等の利用が実質
的な入居条件となっている事例、他のサービス事業所従事者や、かかりつけ医等が有料老人ホーム内へ様々な理由
で立ち入りできないようになっている事例、併設サービス等の利用がなければ家賃をはじめ各種の割引が受けられ
ない事例があるとの指摘があった。
20
ある。自分の親がどのようなサービスを受けることが望ましいか、また、場合によっては過剰
サービスの問題があることも意識させることが必要ではないか。
○
介護保険サービスの場合は、保険者たる市町村等の関与のもと、重要事項説明等の義務が法定
されている一方、「住宅型」有料老人ホームの入居に当たっては、独自のサービス内容やそれに
基づく家賃以外の費用も契約内容となっており、入居者のみならず、地域包括支援センターや
ケアマネジャーにとっても理解が難しいケースがあるのではないか。
○
また、入居希望者の選択が歪められるような事例32があったとしても、行政の指導等が及びにく
く、改善に至ることが難しいことが課題ではないか。
○
高齢期の特徴として、契約能力はあるが、情報収集力・比較検討力・判断能力が衰えた段階で
初めて直面する選択であるとの前提で検討することが重要ではないか。さらに、高齢化に伴う
認知機能の低下に加え、行動経済学の観点からは様々なバイアスに誘導されやすいと考えられ、
また、家族等であっても確立された完璧な消費者たりうることは難しいという前提で検討され
る必要があるのではないか。
○
このため、基本的には市場原理の中でサービスが展開されることを前提としつつ、形式的な情
報提供に留まらず、情報の非対称性を埋めるための情報公開や、高齢者が自ら正しく選択し意
思決定できるためのサポート策を考えることが重要ではないか。
○
契約書を説明・交付するだけでなく、重要事項をまとめた書面を契約前に説明・交付すること
で、消費者トラブルを未然に防ぐよう義務づけられている分野もあり、参考とする必要がある
のではないか。
○
「住宅型」有料老人ホームについては、特定施設と比べても契約関係が複雑で分かりにくいこ
とから、特に併設の介護事業者と有料老人ホーム運営事業者との責任関係、サービスと費用の
対応関係、値上げ、解約に関する事項、有料老人ホーム運営事業者が責任を負わない事項など、
入居後にトラブルとなりやすい事柄について、契約書等で明示する必要があるのではないか。
○
特に、提供できるサービスと提供できないサービス、別料金が必要なサービスについて、契約
書や重要事項説明で明確にし、有料老人ホームと利用者・家族が同じ認識を持つことが、入居
後のトラブルを防止し、ひいては職員や入居者たる高齢者の尊厳を守ることにつながるのでは
ないか。その意味で、有料老人ホームと高齢者やその家族が連携・協力し合うような関係づく
りを契約に基づき行うことが必要ではないか。
○
また、入院先から必要に迫られ、退院までの限られた時間内で住まいを選択しなければならな
いケースがある中、本人が直接施設に赴かず、入院しながらでも、自ら選択し納得のうえで入
居に至ることができる環境の整備が必要ではないか。
32
検討会では、同一経営主体と推認される居宅介護支援(ケアマネジャー)事業所や訪問系サービス等の利用が実質
的な入居条件となっている事例、他のサービス事業所従事者や、かかりつけ医等が有料老人ホーム内へ様々な理由
で立ち入りできないようになっている事例、併設サービス等の利用がなければ家賃をはじめ各種の割引が受けられ
ない事例があるとの指摘があった。
20