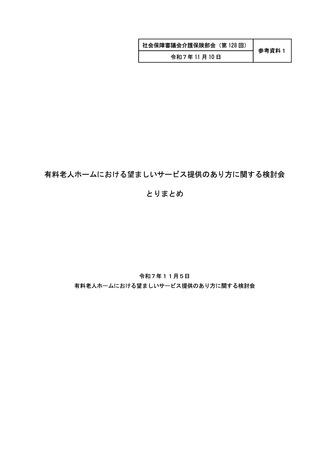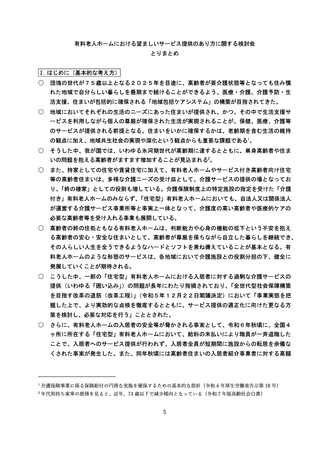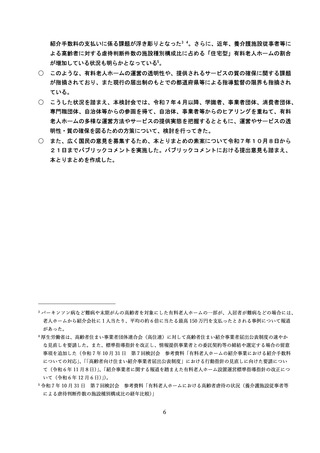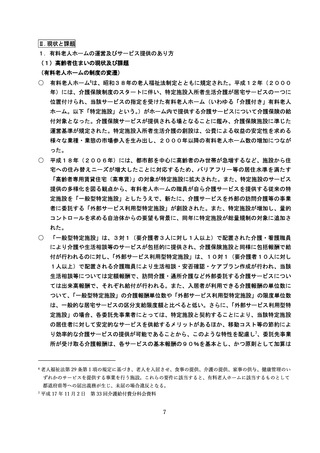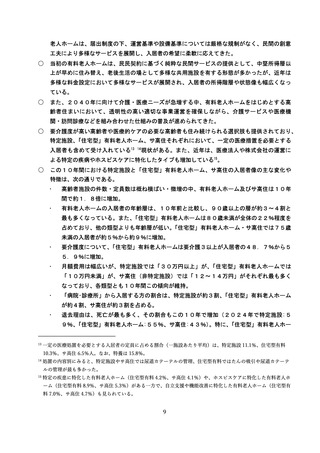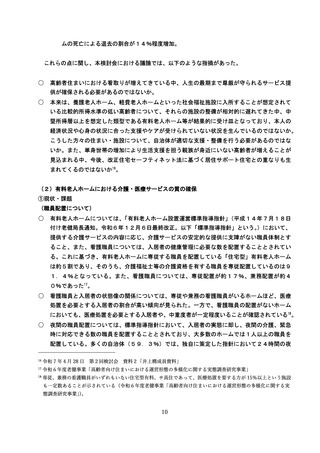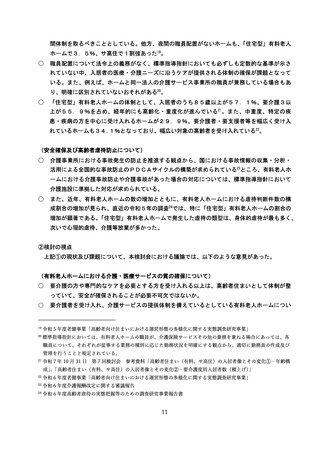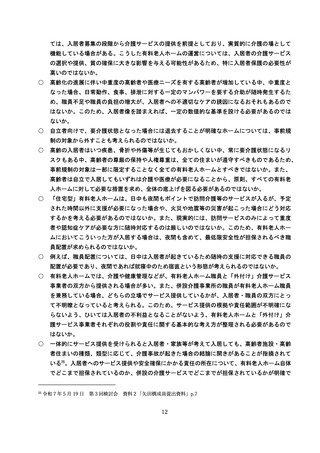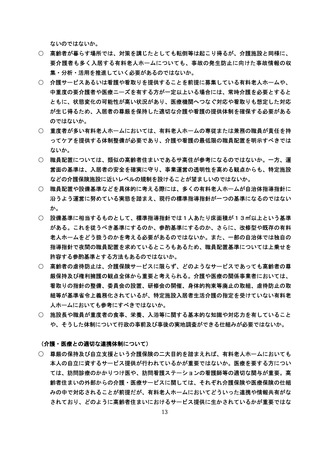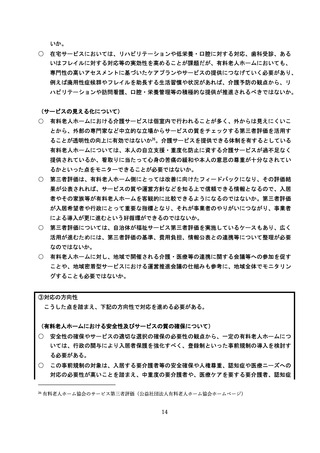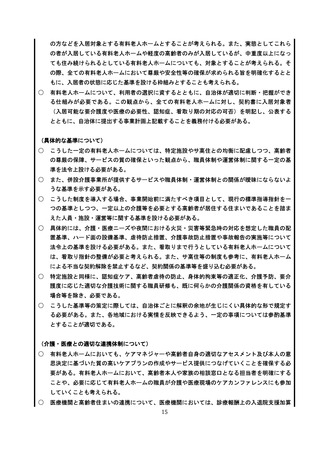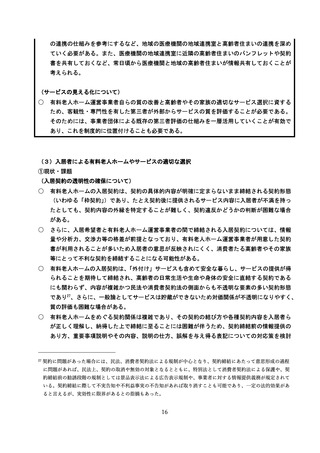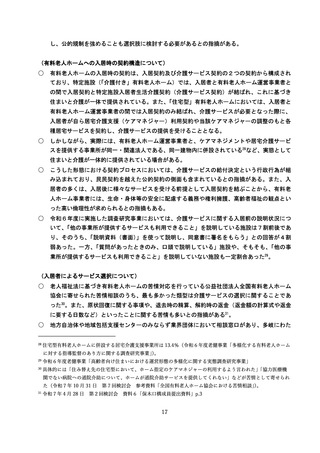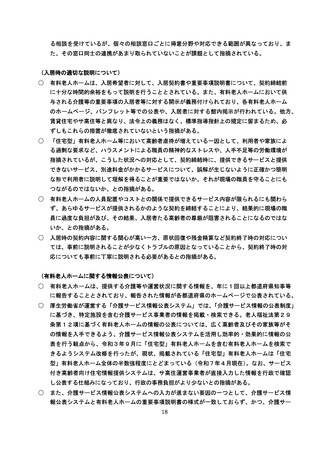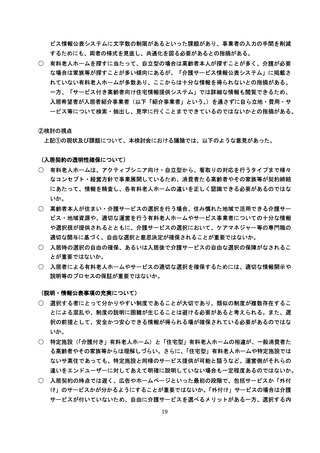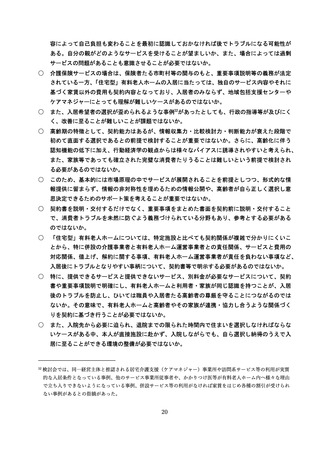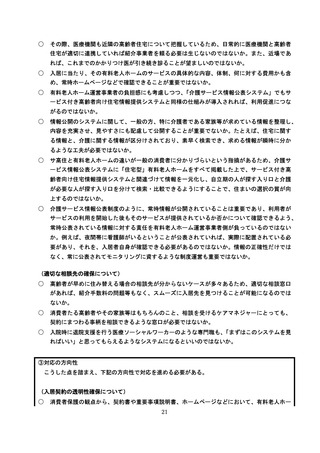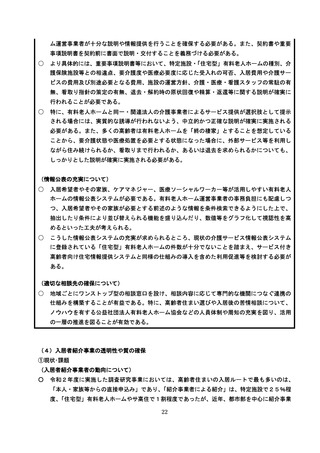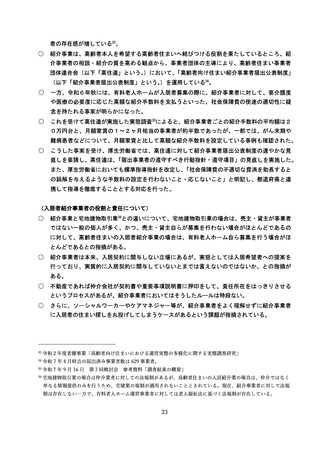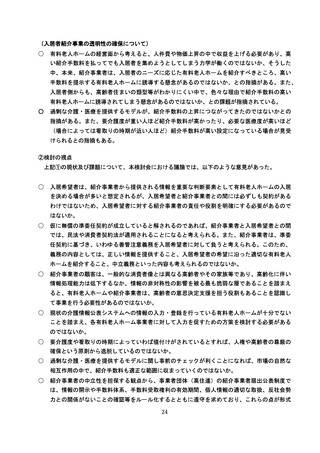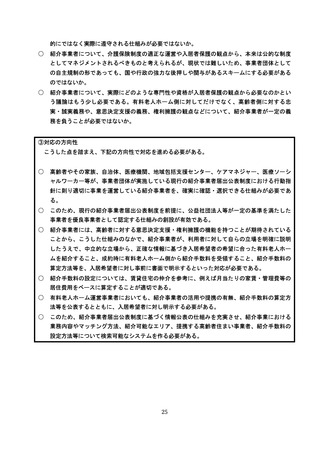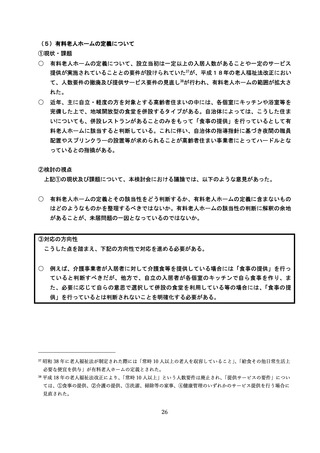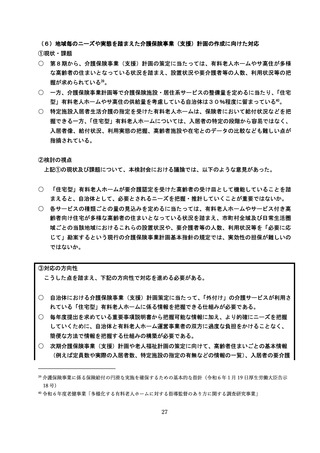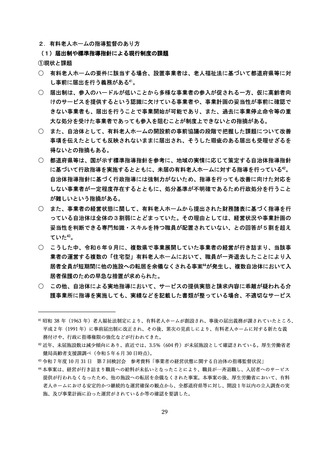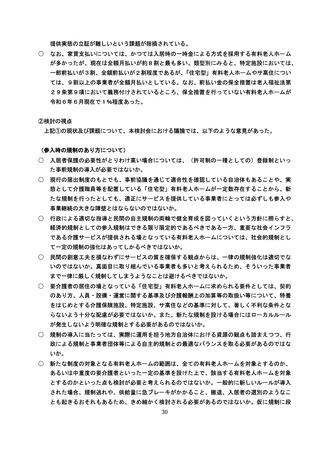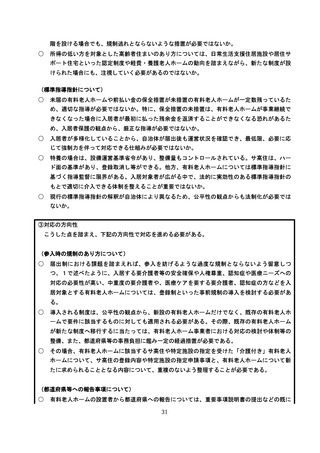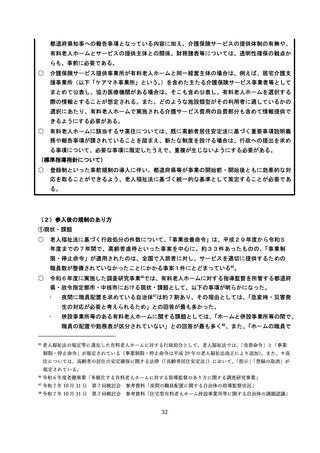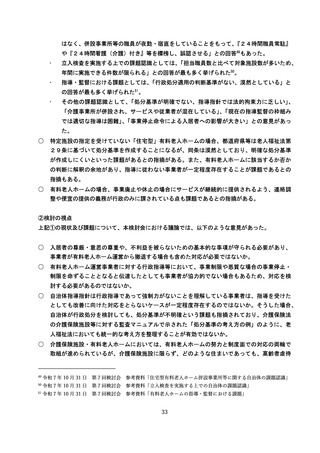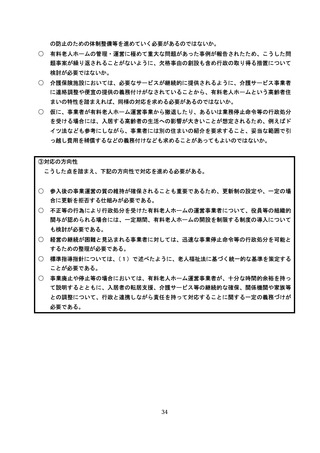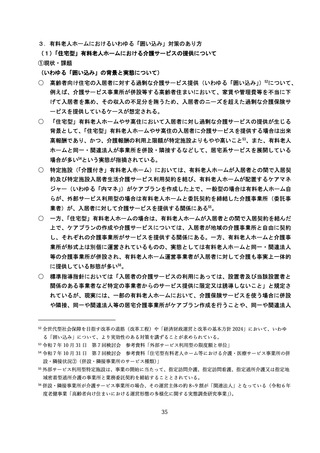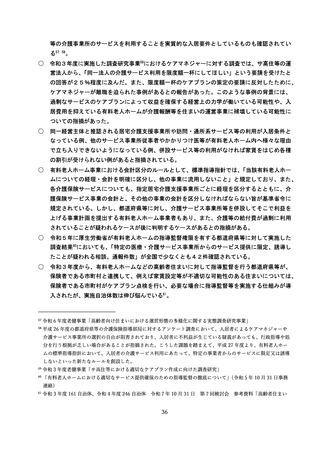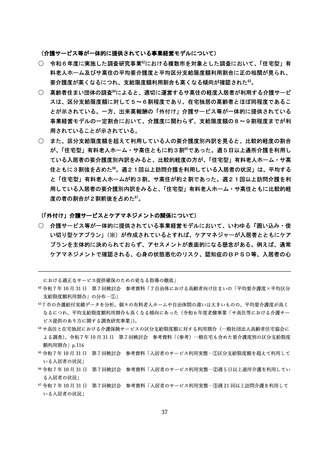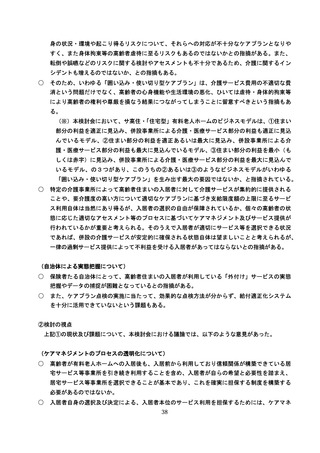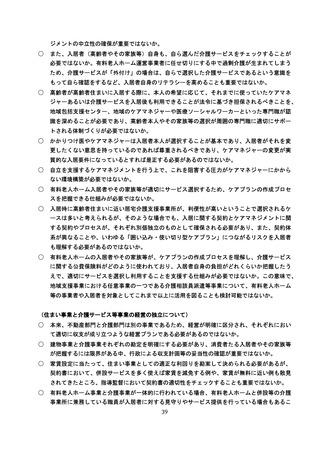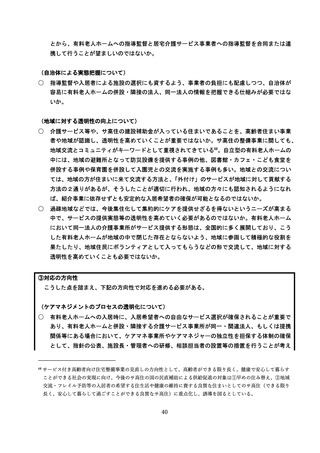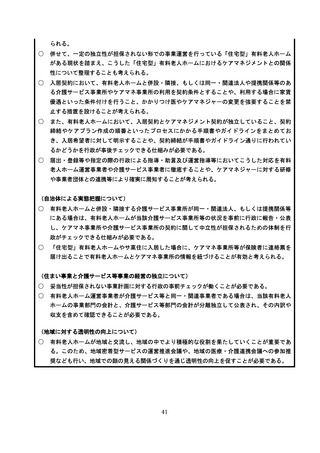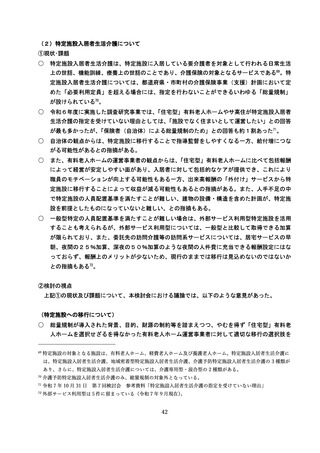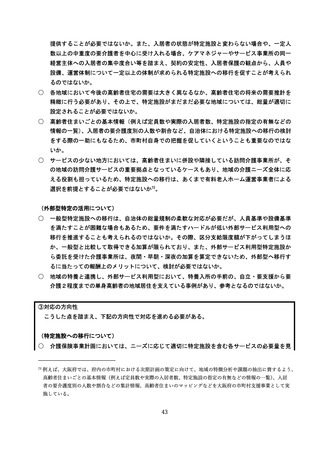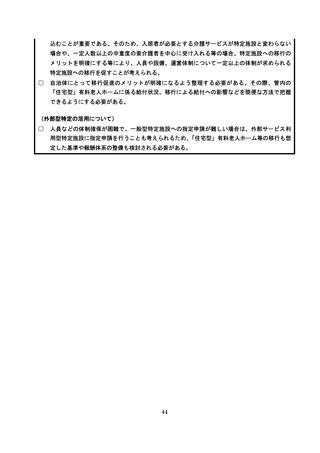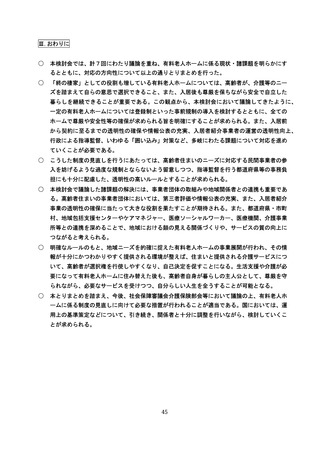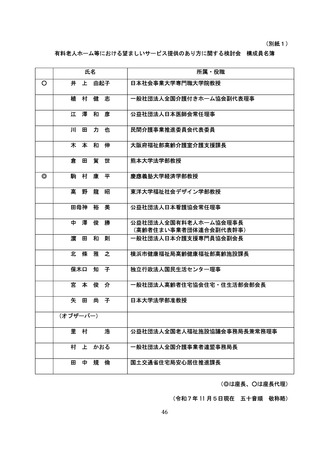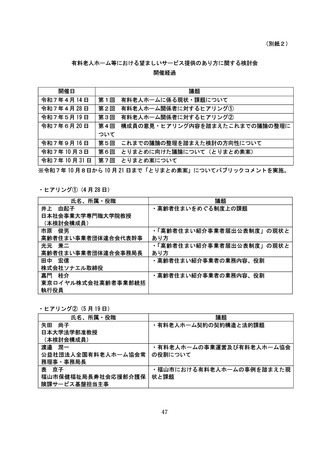よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ては、入居者募集の段階から介護サービスの提供を前提としており、実質的に介護の場として
機能している場合がある。こうした有料老人ホームの運営については、入居者の介護サービス
の選択や提供、質の確保に大きな影響を与える可能性があるため、特に入居者保護の必要性が
高いのではないか。
○
高齢化の進展に伴い中重度の高齢者や医療ニーズを有する高齢者が増加している中、中重度と
なった場合、日常動作、食事、排泄に対する一定のマンパワーを要する介助が随時発生するた
め、職員不足や職員の負担の増大が、入居者への不適切なケアの誘因になるおそれもあるので
はないか。このため、入居者像を踏まえれば、一定の数値的な基準を設ける必要があるのでは
ないか。
○
自立者向けで、要介護状態となった場合には退去することが明確なホームについては、事前規
制の対象から外すことも考えられるのではないか。
○
高齢の入居者はいつ疾患、骨折や外傷等が生じてもおかしくない中、常に要介護状態になるリ
スクもある中、高齢者の尊厳の保持や人権尊重は、全ての住まいが遵守すべきものであるため、
事前規制の対象は一部に限定することなく全ての有料老人ホームとすべきではないか。また、
高齢者は自立で入居してもいずれは介護や医療が必要になることから、原則、すべての有料老
人ホームに対して必要な措置を求め、全体の底上げを図る必要があるのではないか。
○
「住宅型」有料老人ホームは、日中も夜間もポイントで訪問介護等のサービスが入るが、予定
された時間以外に支援が必要になった場合や、火災や地震等の災害が起こった場合にどう対応
するかを考える必要があるのではないか。また、現実的には、訪問サービスのみによって重度
者や認知症ケアが必要な方に随時対応するのは厳しいのではないか。このため、有料老人ホー
ムにおいてこういった方が入居する場合は、夜間も含めて、最低限安全性が担保されるべき職
員配置が求められるのではないか。
○
例えば、職員配置については、日中は入居者が起きているため随時の支援に対応できる職員の
配置が必要であり、夜間であれば就寝中のため宿直という形態が考えられるのではないか。
○
有料老人ホームでは、介護や健康管理などが、有料老人ホーム職員と「外付け」介護サービス
事業者の双方から提供される場合が多い。また、併設介護事業所の職員が有料老人ホーム職員
を兼務している場合、どちらの立場でサービス提供しているかが、入居者・職員の双方にとっ
て不明瞭となっていると考えられる。このため、サービス提供の根拠や責任範囲が不明確にな
らないよう、ひいては入居者の不利益となることがないよう、有料老人ホームと「外付け」介
護サービス事業者それぞれの役割や責任に関する基本的な考え方が整理される必要があるので
はないか。
○
一体的にサービス提供を受けられると入居者・家族等が考えて入居しても、高齢者施設・高齢
者住まいの種類、類型に応じて、介護事故が起きた場合の結論に開きがあることが指摘されて
いる25。入居者へのサービス提供や安全確保にかかる責任の所在について、有料老人ホーム自体
でどこまで担保されているのか、併設の介護サービスでどこまでが担保されているかが明確で
25
令和7年5月 19 日
第3回検討会 資料2「矢田構成員提出資料」p.7
12
機能している場合がある。こうした有料老人ホームの運営については、入居者の介護サービス
の選択や提供、質の確保に大きな影響を与える可能性があるため、特に入居者保護の必要性が
高いのではないか。
○
高齢化の進展に伴い中重度の高齢者や医療ニーズを有する高齢者が増加している中、中重度と
なった場合、日常動作、食事、排泄に対する一定のマンパワーを要する介助が随時発生するた
め、職員不足や職員の負担の増大が、入居者への不適切なケアの誘因になるおそれもあるので
はないか。このため、入居者像を踏まえれば、一定の数値的な基準を設ける必要があるのでは
ないか。
○
自立者向けで、要介護状態となった場合には退去することが明確なホームについては、事前規
制の対象から外すことも考えられるのではないか。
○
高齢の入居者はいつ疾患、骨折や外傷等が生じてもおかしくない中、常に要介護状態になるリ
スクもある中、高齢者の尊厳の保持や人権尊重は、全ての住まいが遵守すべきものであるため、
事前規制の対象は一部に限定することなく全ての有料老人ホームとすべきではないか。また、
高齢者は自立で入居してもいずれは介護や医療が必要になることから、原則、すべての有料老
人ホームに対して必要な措置を求め、全体の底上げを図る必要があるのではないか。
○
「住宅型」有料老人ホームは、日中も夜間もポイントで訪問介護等のサービスが入るが、予定
された時間以外に支援が必要になった場合や、火災や地震等の災害が起こった場合にどう対応
するかを考える必要があるのではないか。また、現実的には、訪問サービスのみによって重度
者や認知症ケアが必要な方に随時対応するのは厳しいのではないか。このため、有料老人ホー
ムにおいてこういった方が入居する場合は、夜間も含めて、最低限安全性が担保されるべき職
員配置が求められるのではないか。
○
例えば、職員配置については、日中は入居者が起きているため随時の支援に対応できる職員の
配置が必要であり、夜間であれば就寝中のため宿直という形態が考えられるのではないか。
○
有料老人ホームでは、介護や健康管理などが、有料老人ホーム職員と「外付け」介護サービス
事業者の双方から提供される場合が多い。また、併設介護事業所の職員が有料老人ホーム職員
を兼務している場合、どちらの立場でサービス提供しているかが、入居者・職員の双方にとっ
て不明瞭となっていると考えられる。このため、サービス提供の根拠や責任範囲が不明確にな
らないよう、ひいては入居者の不利益となることがないよう、有料老人ホームと「外付け」介
護サービス事業者それぞれの役割や責任に関する基本的な考え方が整理される必要があるので
はないか。
○
一体的にサービス提供を受けられると入居者・家族等が考えて入居しても、高齢者施設・高齢
者住まいの種類、類型に応じて、介護事故が起きた場合の結論に開きがあることが指摘されて
いる25。入居者へのサービス提供や安全確保にかかる責任の所在について、有料老人ホーム自体
でどこまで担保されているのか、併設の介護サービスでどこまでが担保されているかが明確で
25
令和7年5月 19 日
第3回検討会 資料2「矢田構成員提出資料」p.7
12