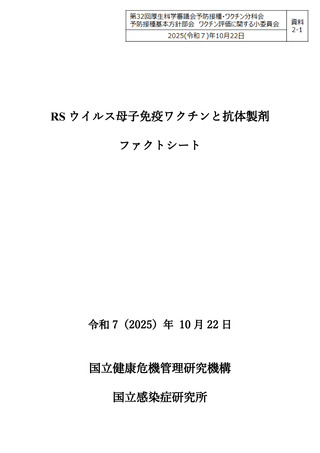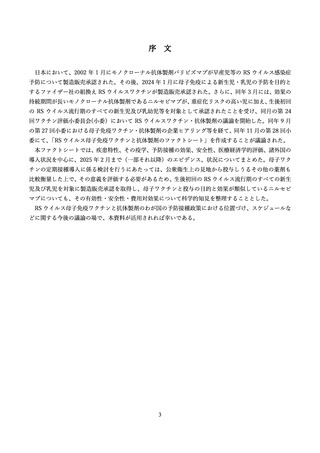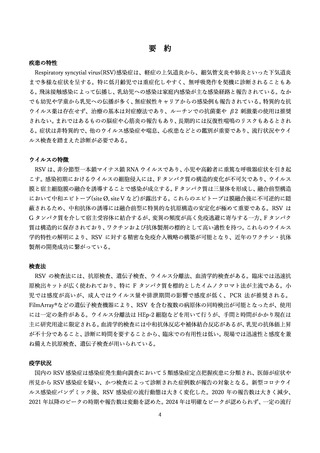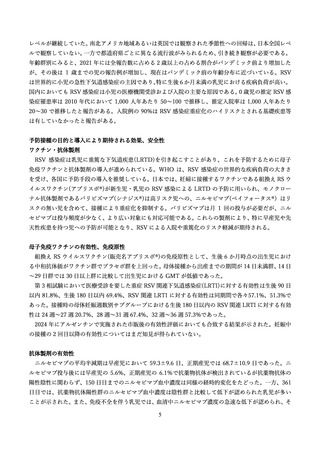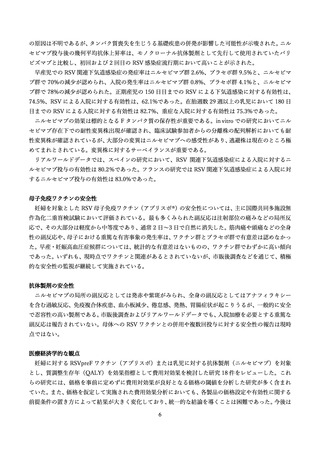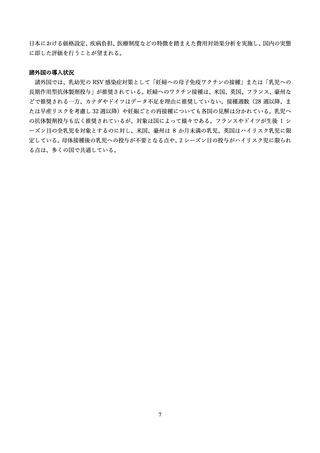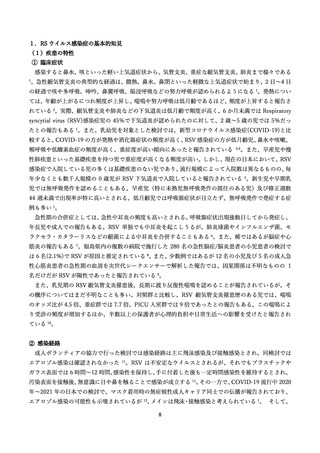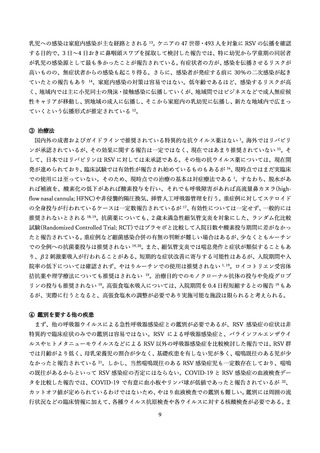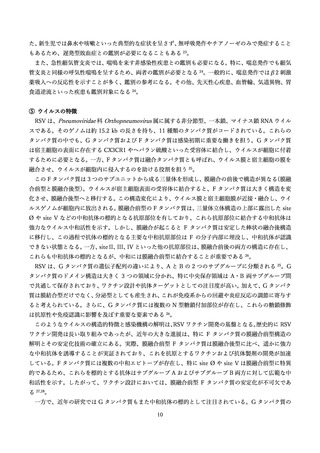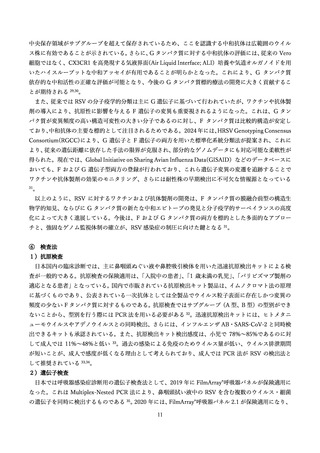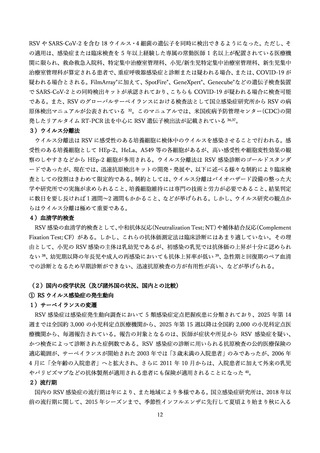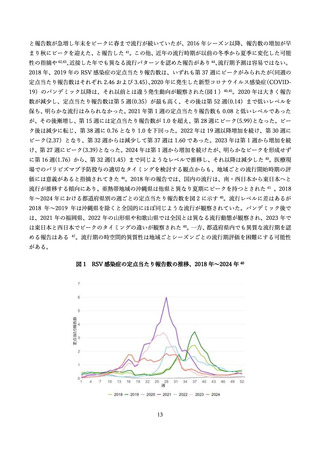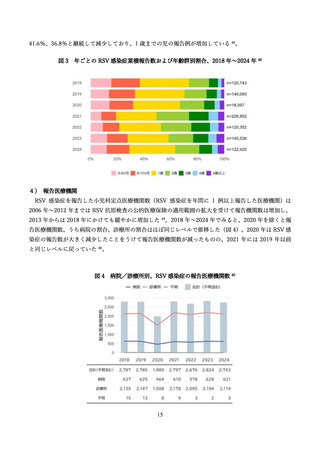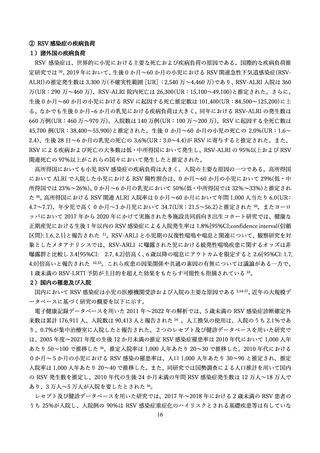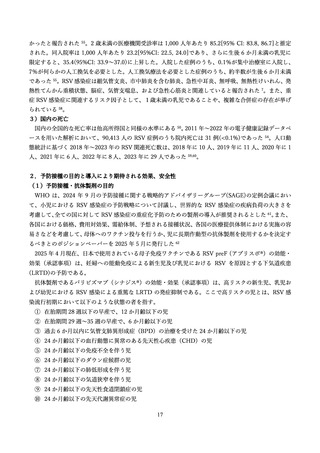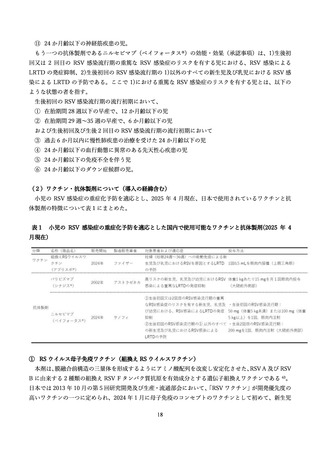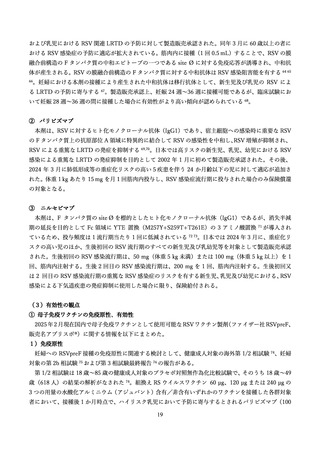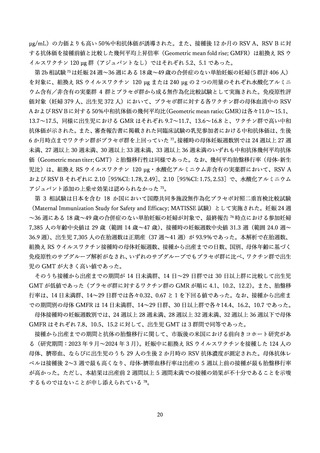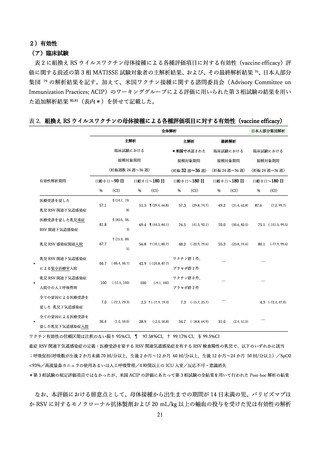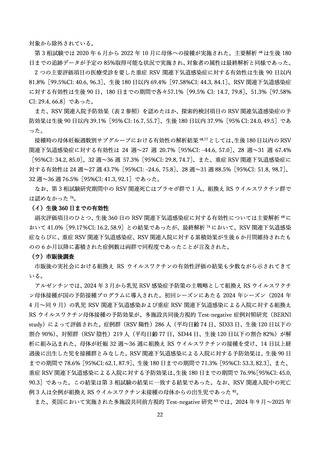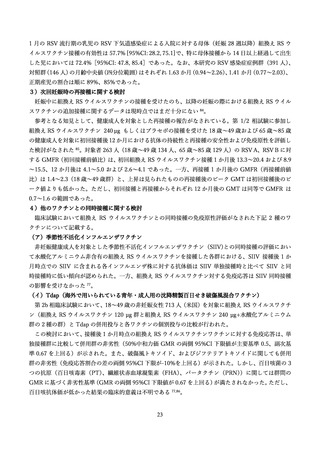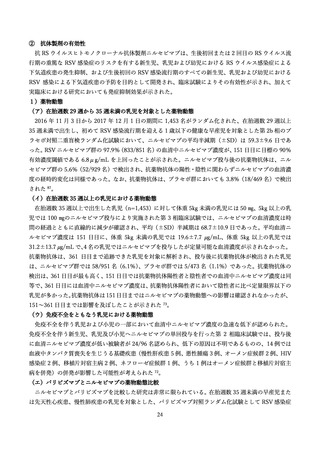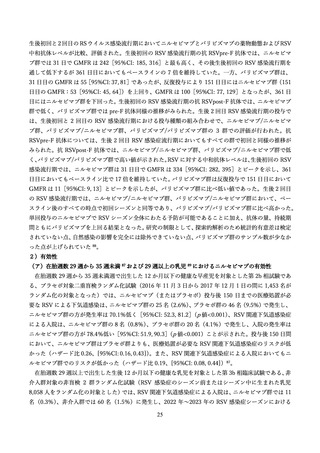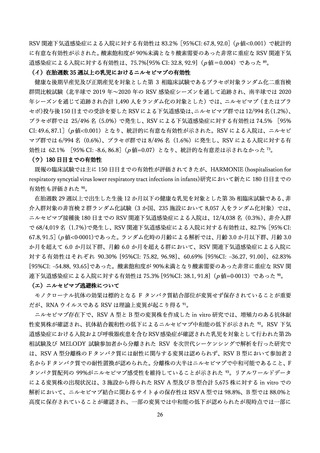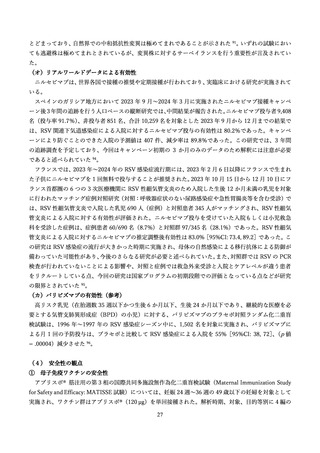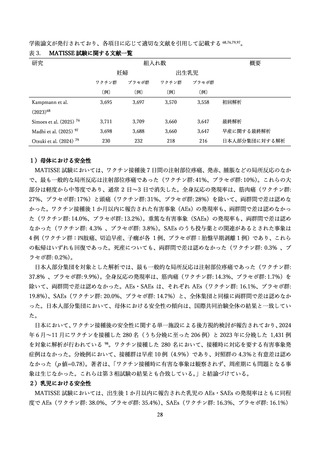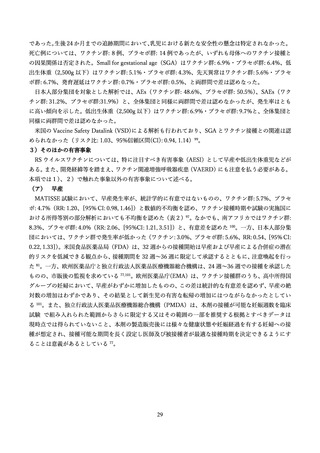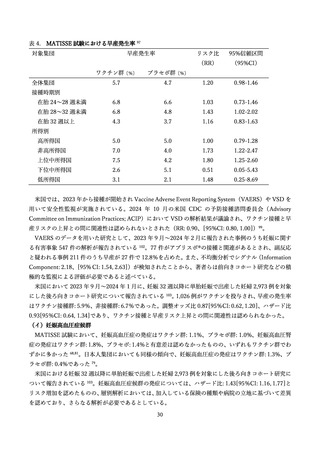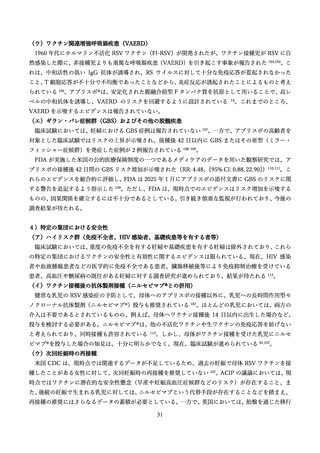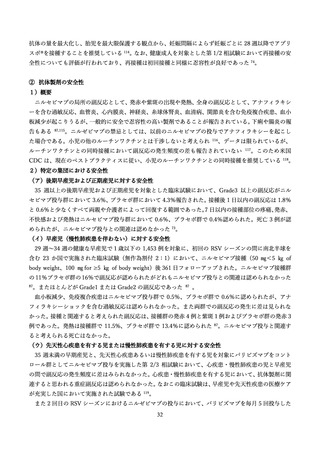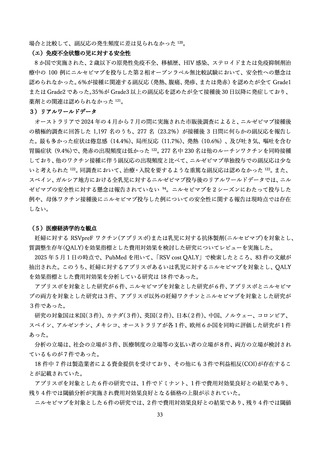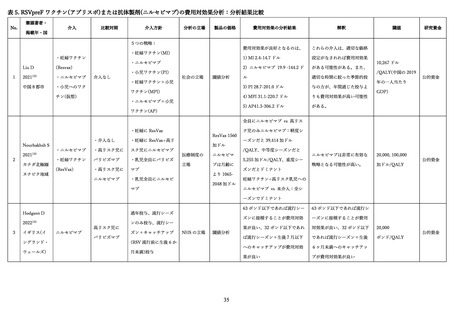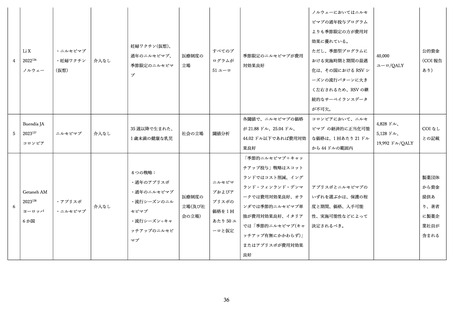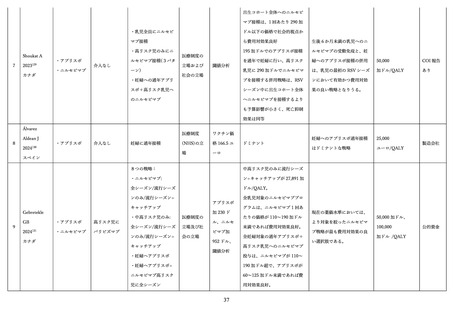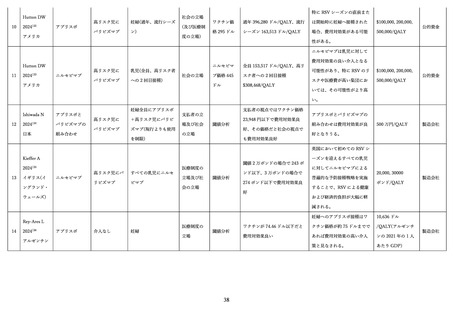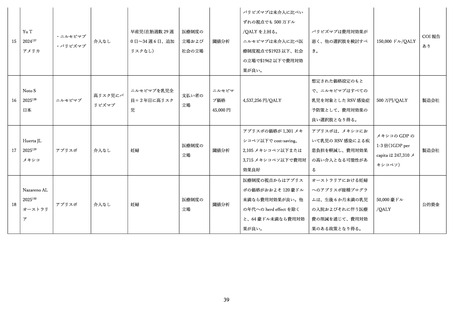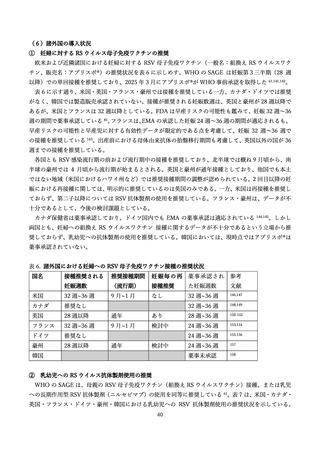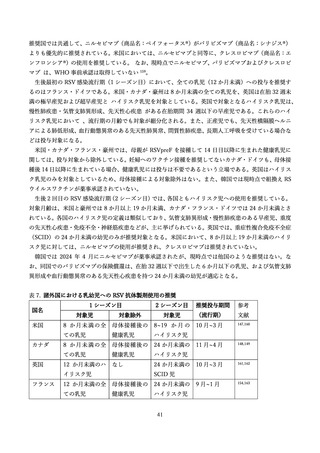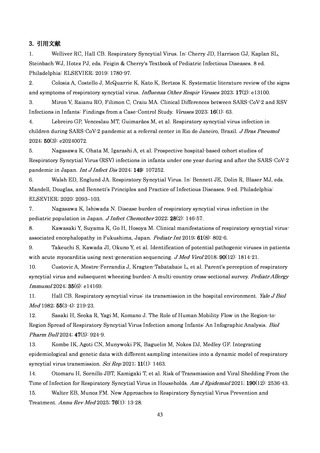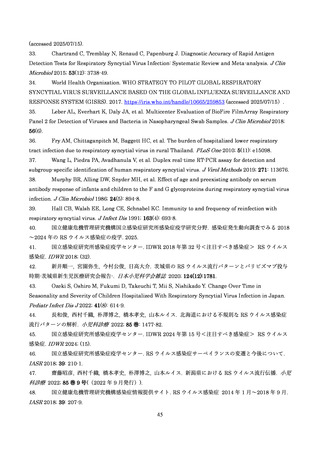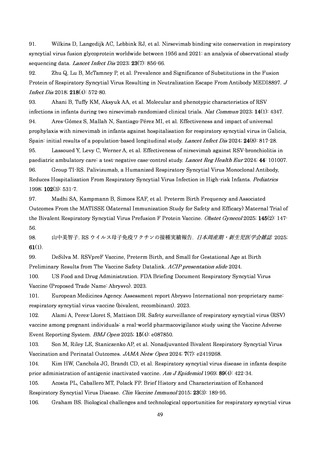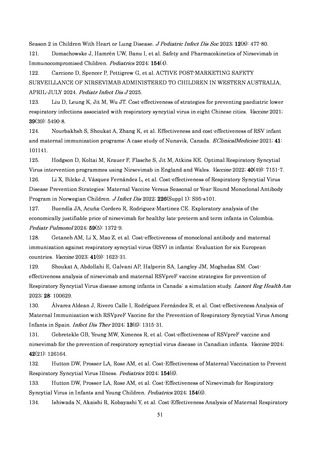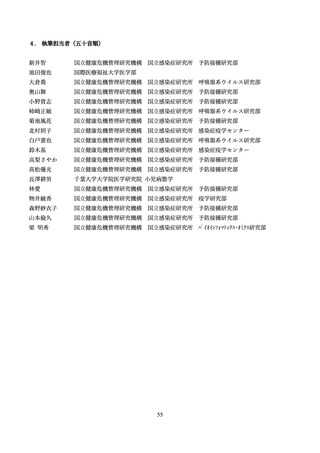よむ、つかう、まなぶ。
05資料2-1森野委員提出資料(RSウイルス母子免疫ワクチンと抗体製剤ファクトシート) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64997.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第32回 10/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
乳児への感染は家庭内感染が主な経路とされる 13。ケニアの 47 世帯・493 人を対象に RSV の伝播を確認
する目的で、3 日~4 日おきに鼻咽頭スワブを採取して検討した報告では、特に幼児から学童期の同居者
が乳児の感染源として最も多かったことが報告されている。有症状者の方が、感染を伝播させるリスクが
高いものの、無症状者からの感染も起こり得る。さらに、感染者が発症する前に 30%の二次感染が起き
ていたとの報告もあり 14、家庭内感染の対策は容易ではない。低年齢であるほど、感染するリスクが高
く、地域内では主に小児同士の飛沫・接触感染に伝播していくが、地域間ではビジネスなどで成人無症候
性キャリアが移動し、別地域の成人に伝播し、そこから家庭内の乳幼児に伝播し、新たな地域内で広まっ
ていくという伝播形式が推定されている 12。
③ 治療法
国内外の成書およびガイドラインで推奨されている特異的な抗ウイルス薬はない 1。海外ではリバビリ
ンが承認されているが、その効果に関する報告は一定ではなく、現在ではあまり推奨されていない 15。そ
して、日本ではリバビリンは RSV に対しては未承認である。その他の抗ウイルス薬については、現在開
発が進められており、臨床試験では有効性が報告され始めているものもあるが 16、現時点ではまだ実臨床
での使用には至っていない。そのため、現時点での治療の基本は対症療法である 1。すなわち、脱水があ
れば補液を、酸素化の低下があれば酸素投与を行い、それでも呼吸障害があれば高流量鼻カヌラ(highflow nasal cannula; HFNC)や非侵襲的陽圧換気、挿管人工呼吸器管理を行う。重症例に対してステロイド
の全身投与が行われているケースは一定数報告されているが 17、有効性については一定せず、一般的には
推奨されないとされる 18, 19。抗菌薬についても、2 歳未満急性細気管支炎を対象にした、ランダム化比較
試験(Randomized Controlled Trial; RCT)ではプラセボと比較して入院日数や酸素投与期間に差がなかっ
たと報告されている。重症例など細菌感染合併の有無の判断が難しい場合はあるが、少なくともルーチン
での全例への抗菌薬投与は推奨されない 19, 20。また、細気管支炎では喘息発作と症状が類似することもあ
り、β2 刺激薬吸入が行われることがある。短期的な症状改善に寄与する可能性はあるが、入院期間や入
院率の低下については確認されず、やはりルーチンでの使用は推奨されない 1, 19。ロイコトリエン受容体
拮抗薬や理学療法についても推奨はされない 19。治療目的でのモノクローナル抗体の投与や免疫グロブ
リンの投与も推奨されない 19。高張食塩水吸入については、入院期間を 0.4 日程短縮するとの報告 19 もあ
るが、実際に行うとなると、高張食塩水の調整が必要であり実施可能な施設は限られると考えられる。
④ 鑑別を要する他の疾患
まず、他の呼吸器ウイルスによる急性呼吸器感染症との鑑別が必要であるが、RSV 感染症の症状は非
特異的で臨床症状のみでの鑑別は容易ではない。RSV による呼吸器感染症と、パラインフルエンザウイ
ルスやヒトメタニューモウイルスなどによる RSV 以外の呼吸器感染症を比較検討した報告では、RSV 群
では月齢がより低く、母乳栄養児の割合が少なく、基礎疾患を有しない児が多く、喘鳴既往のある児が少
なかったと報告されている 21。しかし、当然喘鳴既往のある RSV 感染症児も一定数存在しており、喘鳴
の既往があるからといって RSV 感染症の否定にはならない。COVID-19 と RSV 感染症の血液検査デー
タを比較した報告では、COVID-19 で有意に血小板やリンパ球が低値であったと報告されているが 22、
カットオフ値が定められているわけではないため、やはり血液検査での鑑別も難しい。鑑別には周囲の流
行状況などの臨床情報に加えて、各種ウイルス抗原検査や各ウイルスに対する核酸検査が必要である。ま
9
する目的で、3 日~4 日おきに鼻咽頭スワブを採取して検討した報告では、特に幼児から学童期の同居者
が乳児の感染源として最も多かったことが報告されている。有症状者の方が、感染を伝播させるリスクが
高いものの、無症状者からの感染も起こり得る。さらに、感染者が発症する前に 30%の二次感染が起き
ていたとの報告もあり 14、家庭内感染の対策は容易ではない。低年齢であるほど、感染するリスクが高
く、地域内では主に小児同士の飛沫・接触感染に伝播していくが、地域間ではビジネスなどで成人無症候
性キャリアが移動し、別地域の成人に伝播し、そこから家庭内の乳幼児に伝播し、新たな地域内で広まっ
ていくという伝播形式が推定されている 12。
③ 治療法
国内外の成書およびガイドラインで推奨されている特異的な抗ウイルス薬はない 1。海外ではリバビリ
ンが承認されているが、その効果に関する報告は一定ではなく、現在ではあまり推奨されていない 15。そ
して、日本ではリバビリンは RSV に対しては未承認である。その他の抗ウイルス薬については、現在開
発が進められており、臨床試験では有効性が報告され始めているものもあるが 16、現時点ではまだ実臨床
での使用には至っていない。そのため、現時点での治療の基本は対症療法である 1。すなわち、脱水があ
れば補液を、酸素化の低下があれば酸素投与を行い、それでも呼吸障害があれば高流量鼻カヌラ(highflow nasal cannula; HFNC)や非侵襲的陽圧換気、挿管人工呼吸器管理を行う。重症例に対してステロイド
の全身投与が行われているケースは一定数報告されているが 17、有効性については一定せず、一般的には
推奨されないとされる 18, 19。抗菌薬についても、2 歳未満急性細気管支炎を対象にした、ランダム化比較
試験(Randomized Controlled Trial; RCT)ではプラセボと比較して入院日数や酸素投与期間に差がなかっ
たと報告されている。重症例など細菌感染合併の有無の判断が難しい場合はあるが、少なくともルーチン
での全例への抗菌薬投与は推奨されない 19, 20。また、細気管支炎では喘息発作と症状が類似することもあ
り、β2 刺激薬吸入が行われることがある。短期的な症状改善に寄与する可能性はあるが、入院期間や入
院率の低下については確認されず、やはりルーチンでの使用は推奨されない 1, 19。ロイコトリエン受容体
拮抗薬や理学療法についても推奨はされない 19。治療目的でのモノクローナル抗体の投与や免疫グロブ
リンの投与も推奨されない 19。高張食塩水吸入については、入院期間を 0.4 日程短縮するとの報告 19 もあ
るが、実際に行うとなると、高張食塩水の調整が必要であり実施可能な施設は限られると考えられる。
④ 鑑別を要する他の疾患
まず、他の呼吸器ウイルスによる急性呼吸器感染症との鑑別が必要であるが、RSV 感染症の症状は非
特異的で臨床症状のみでの鑑別は容易ではない。RSV による呼吸器感染症と、パラインフルエンザウイ
ルスやヒトメタニューモウイルスなどによる RSV 以外の呼吸器感染症を比較検討した報告では、RSV 群
では月齢がより低く、母乳栄養児の割合が少なく、基礎疾患を有しない児が多く、喘鳴既往のある児が少
なかったと報告されている 21。しかし、当然喘鳴既往のある RSV 感染症児も一定数存在しており、喘鳴
の既往があるからといって RSV 感染症の否定にはならない。COVID-19 と RSV 感染症の血液検査デー
タを比較した報告では、COVID-19 で有意に血小板やリンパ球が低値であったと報告されているが 22、
カットオフ値が定められているわけではないため、やはり血液検査での鑑別も難しい。鑑別には周囲の流
行状況などの臨床情報に加えて、各種ウイルス抗原検査や各ウイルスに対する核酸検査が必要である。ま
9