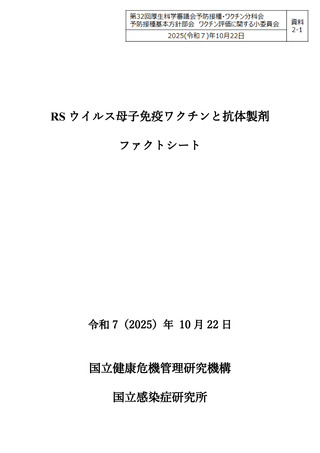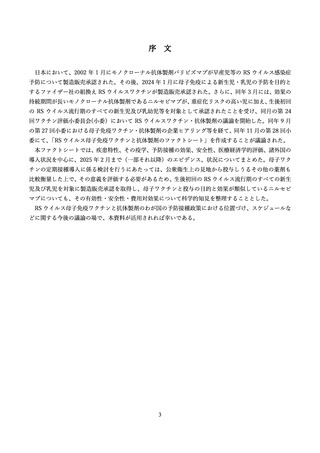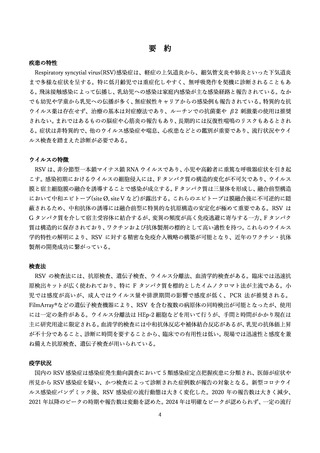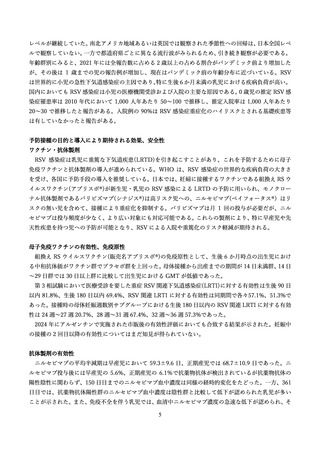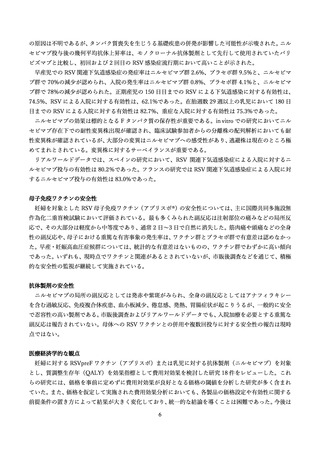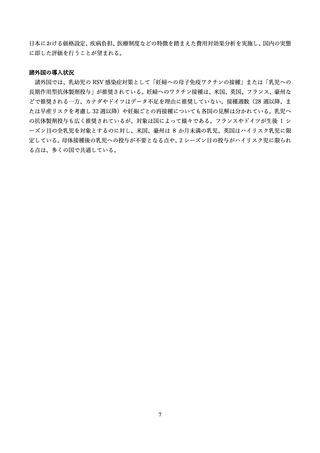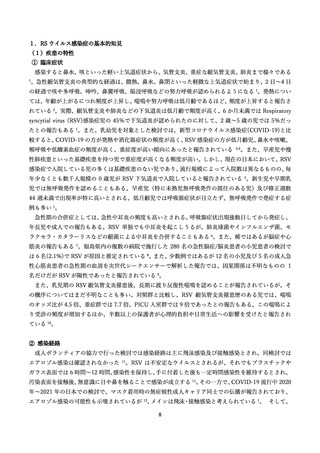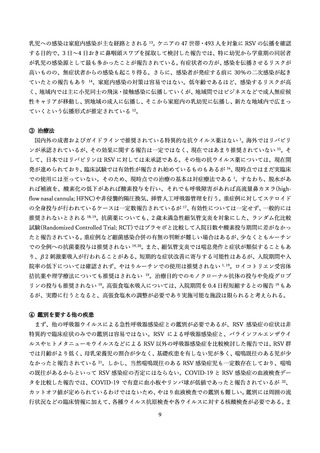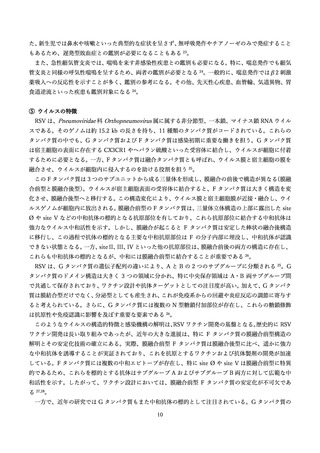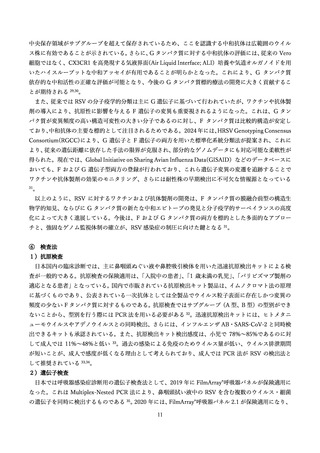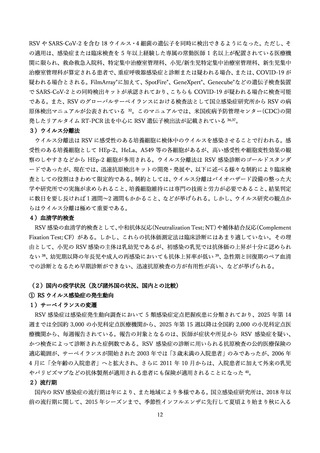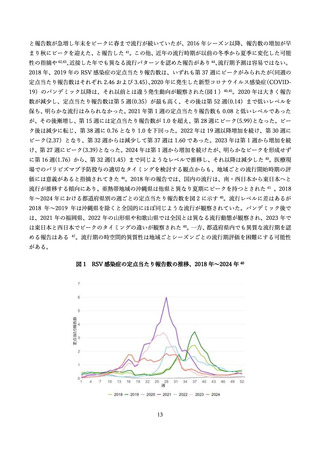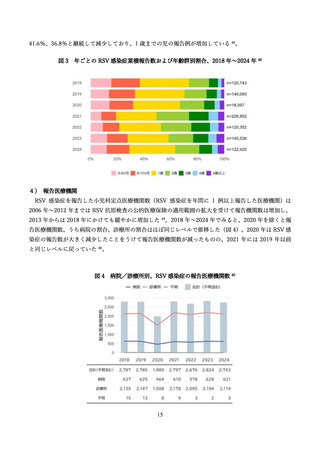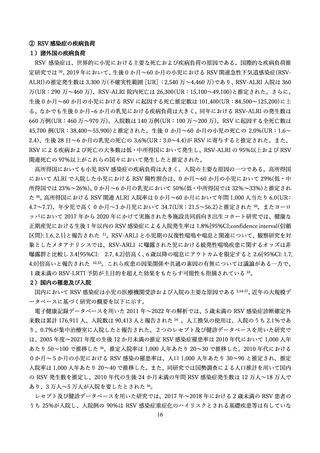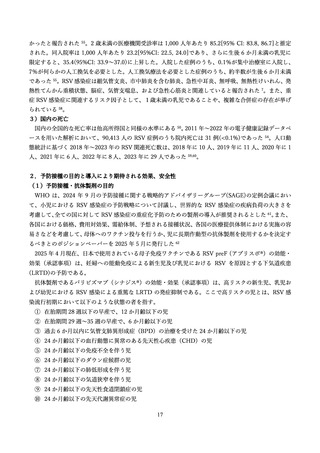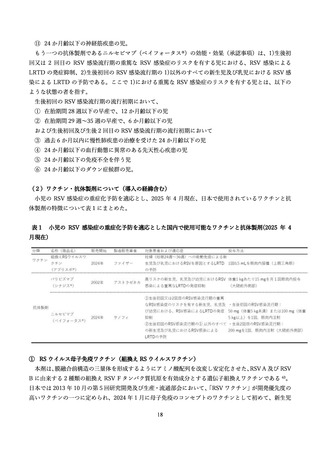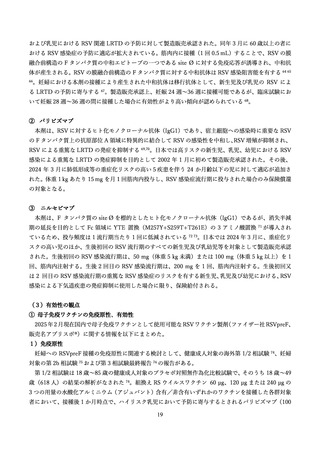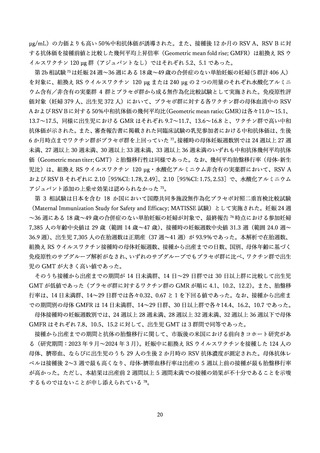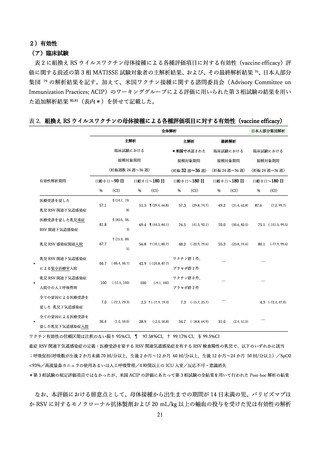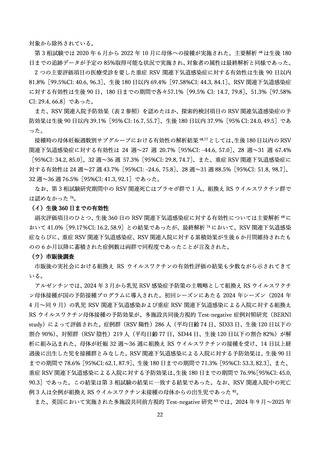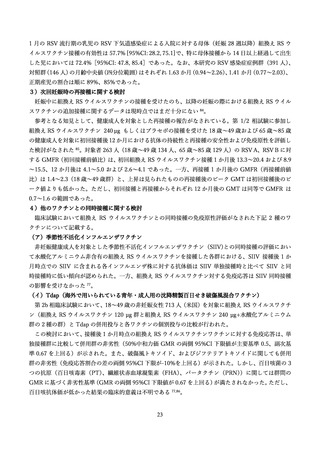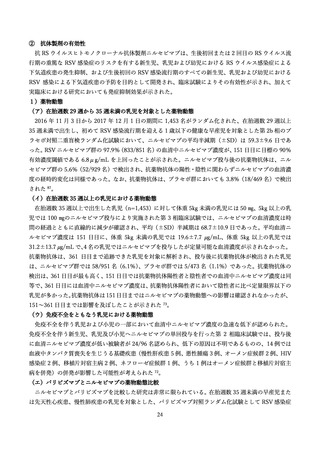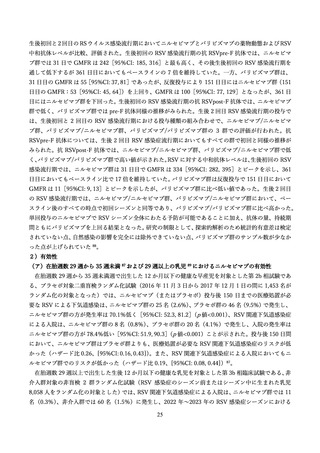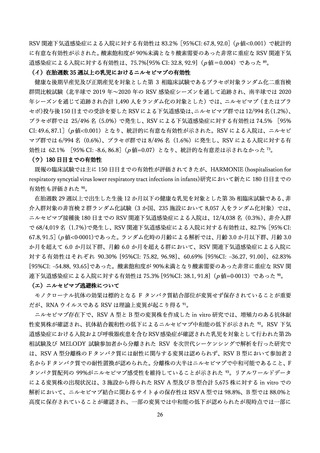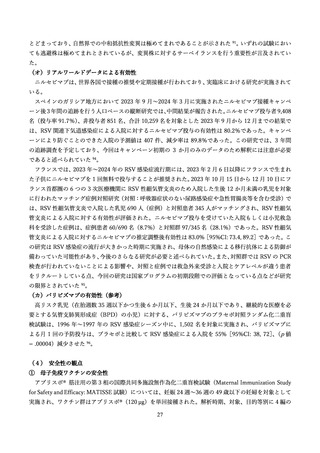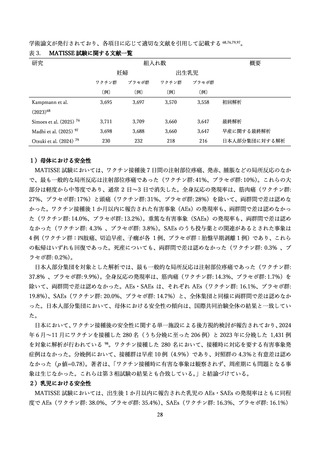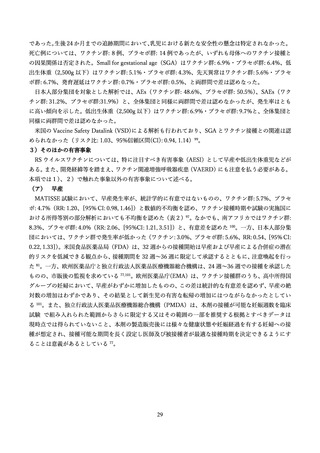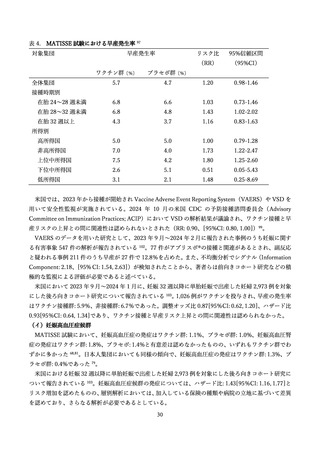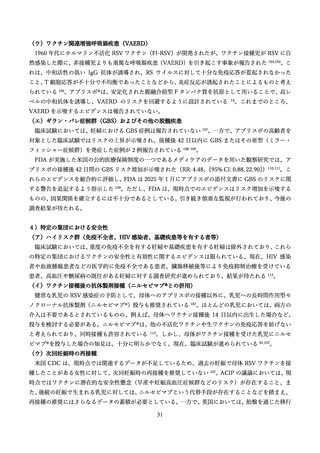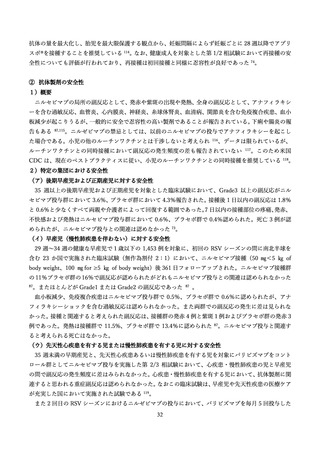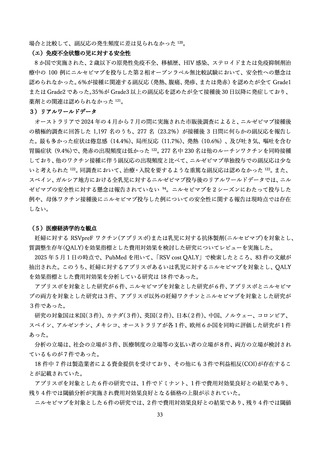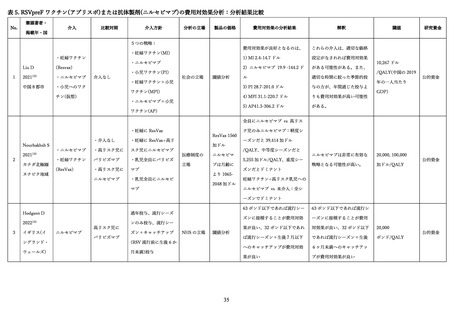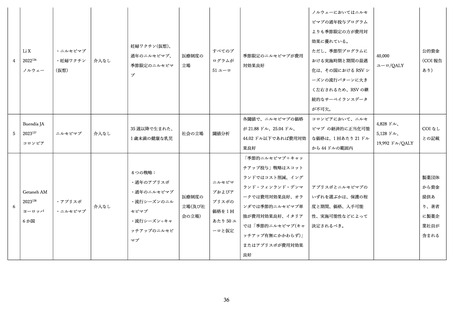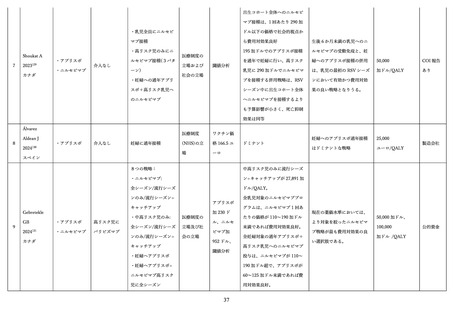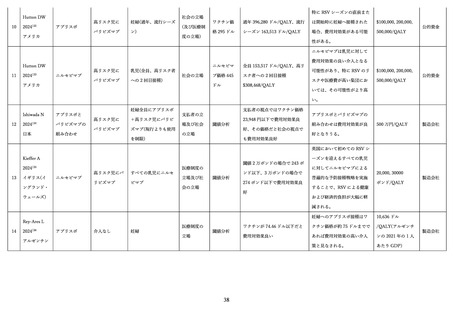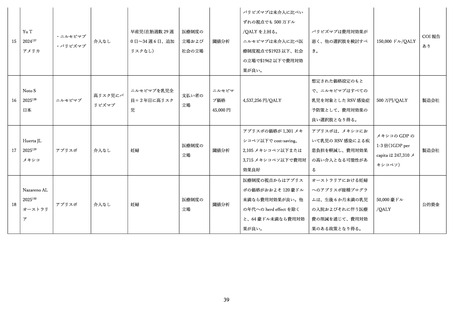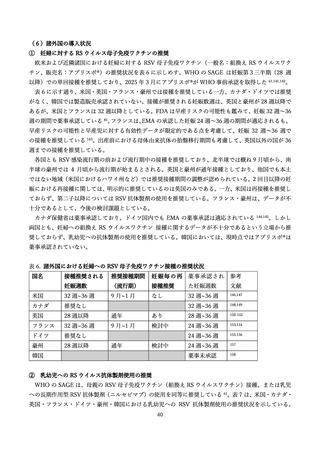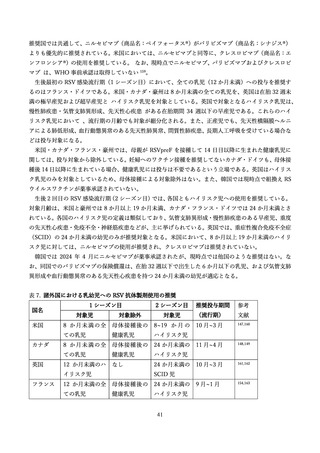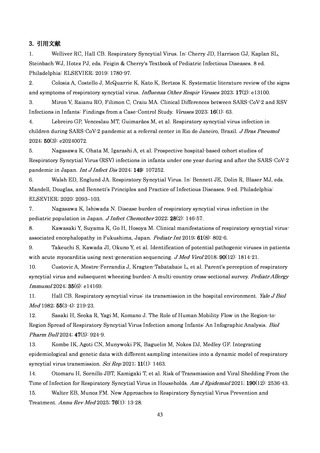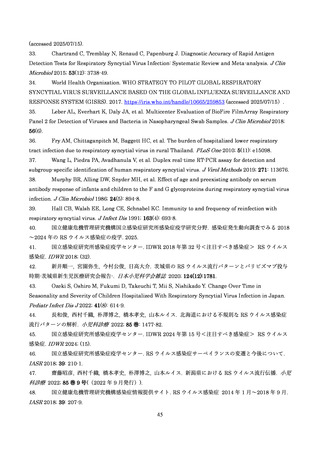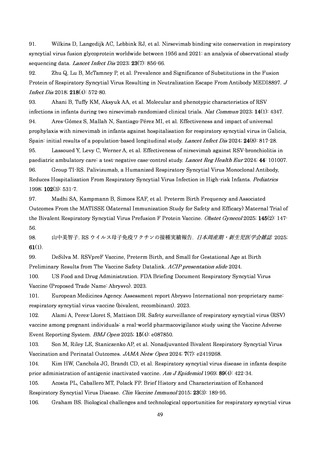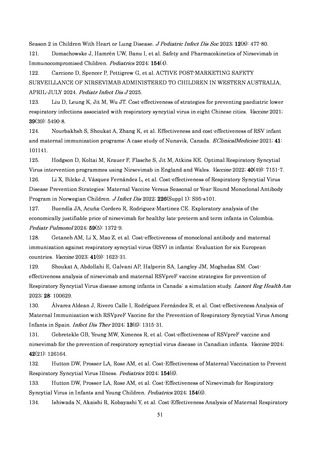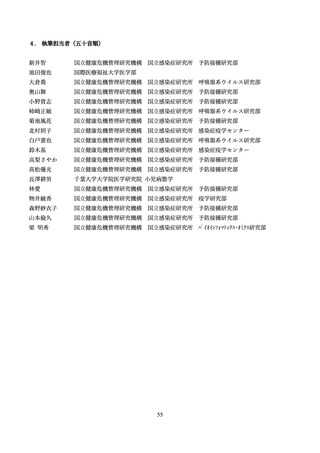よむ、つかう、まなぶ。
05資料2-1森野委員提出資料(RSウイルス母子免疫ワクチンと抗体製剤ファクトシート) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64997.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第32回 10/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1.RS ウイルス感染症の基本的知見
(1)疾患の特性
① 臨床症状
感染すると鼻水、咳といった軽い上気道症状から、気管支炎、重症な細気管支炎、肺炎まで様々である
。急性細気管支炎の典型的な経過は、微熱、鼻水、鼻閉といった軽微な上気道症状で始まり、2 日~4 日
1
の経過で咳や多呼吸、呻吟、鼻翼呼吸、陥没呼吸などの努力呼吸が認められるようになる 1。発熱につい
ては、年齢が上がるにつれ頻度が上昇し、喘鳴や努力呼吸は低月齢であるほど、頻度が上昇すると報告さ
れている 2。実際、細気管支炎や肺炎などの下気道炎は低月齢で頻度が高く、6 か月未満では Respiratory
syncytial virus (RSV)感染症児の 45%で下気道炎が認められたのに対して、2 歳~5 歳の児では 5%だっ
たとの報告もある 1。また、乳幼児を対象とした検討では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と比
較すると、COVID-19 の方が発熱や消化器症状の頻度が高く、RSV 感染症の方が低月齢児、鼻水や咳嗽、
頻呼吸や低酸素血症の頻度が高く、重症度が高い傾向にあったと報告されている 3,4。また、早産児や慢
性肺疾患といった基礎疾患を持つ児で重症度が高くなる頻度が高い。しかし、現在の日本において、RSV
感染症で入院している児の多くは基礎疾患のない児であり、流行規模によって入院数は異なるものの、毎
年少なくとも数千人規模の 0 歳児が RSV 下気道炎で入院していると報告されている 5。新生児や早期乳
児では無呼吸発作を認めることもある。早産児 (特に未熟児無呼吸発作の既往のある児) 及び修正週数
44 週未満で出現率が特に高いとされる。低月齢児では呼吸器症状が目立たず、無呼吸発作で発症する症
例も多い 1。
急性期の合併症としては、急性中耳炎の頻度も高いとされる。呼吸器症状出現後数日してから発症し、
年長児や成人での報告もある。RSV 単独でも中耳炎を起こしうるが、肺炎球菌やインフルエンザ菌、モ
ラクセラ・カタラーリスなどの細菌による中耳炎を合併することもある 6。また、稀ではあるが脳症や心
筋炎の報告もある 7。福島県内の複数の病院で施行した 280 名の急性脳症/脳炎患者の小児患者の検討で
は 6 名(2.1%)で RSV が原因と推定されている 8。また、少数例ではあるが 12 名の小児及び 5 名の成人急
性心筋炎患者の急性期の血清を次世代シークエンサーで解析した報告では、因果関係は不明なものの 1
名だけだが RSV が陽性であったと報告されている 9。
また、乳児期の RSV 細気管支炎罹患後、長期に渡り反復性喘鳴を認めることが報告されているが、そ
の機序についてはまだ不明なことも多い。対照群と比較し、RSV 細気管支炎罹患歴のある児では、喘鳴
のオッズ比が 4.5 倍、重症群では 7.7 倍、PICU 入室群では 9 倍であったとの報告もある。この喘鳴によ
り受診の頻度が増加するほか、半数以上の保護者が心理的負担や日常生活への影響を受けたと報告され
ている 10。
② 感染経路
成人ボランティアの協力で行った検討では感染経路は主に飛沫感染及び接触感染とされ、同検討では
エアロゾル感染は確認されなかった 11。RSV は不安定なウイルスとされるが、それでもプラスチックや
ガラス表面では 6 時間~12 時間、感染性を保持し、手に付着した後も一定時間感染性を維持するとされ、
汚染表面を接触後、無意識に目や鼻を触ることで感染が成立する 11。その一方で、COVID-19 流行中 2020
年~2021 年の日本での検討で、マスク着用時の無症候性成人キャリア同士での伝播が報告されており、
エアロゾル感染の可能性も示唆されているが 12、メインは飛沫・接触感染と考えられている 1。 そして、
8
(1)疾患の特性
① 臨床症状
感染すると鼻水、咳といった軽い上気道症状から、気管支炎、重症な細気管支炎、肺炎まで様々である
。急性細気管支炎の典型的な経過は、微熱、鼻水、鼻閉といった軽微な上気道症状で始まり、2 日~4 日
1
の経過で咳や多呼吸、呻吟、鼻翼呼吸、陥没呼吸などの努力呼吸が認められるようになる 1。発熱につい
ては、年齢が上がるにつれ頻度が上昇し、喘鳴や努力呼吸は低月齢であるほど、頻度が上昇すると報告さ
れている 2。実際、細気管支炎や肺炎などの下気道炎は低月齢で頻度が高く、6 か月未満では Respiratory
syncytial virus (RSV)感染症児の 45%で下気道炎が認められたのに対して、2 歳~5 歳の児では 5%だっ
たとの報告もある 1。また、乳幼児を対象とした検討では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と比
較すると、COVID-19 の方が発熱や消化器症状の頻度が高く、RSV 感染症の方が低月齢児、鼻水や咳嗽、
頻呼吸や低酸素血症の頻度が高く、重症度が高い傾向にあったと報告されている 3,4。また、早産児や慢
性肺疾患といった基礎疾患を持つ児で重症度が高くなる頻度が高い。しかし、現在の日本において、RSV
感染症で入院している児の多くは基礎疾患のない児であり、流行規模によって入院数は異なるものの、毎
年少なくとも数千人規模の 0 歳児が RSV 下気道炎で入院していると報告されている 5。新生児や早期乳
児では無呼吸発作を認めることもある。早産児 (特に未熟児無呼吸発作の既往のある児) 及び修正週数
44 週未満で出現率が特に高いとされる。低月齢児では呼吸器症状が目立たず、無呼吸発作で発症する症
例も多い 1。
急性期の合併症としては、急性中耳炎の頻度も高いとされる。呼吸器症状出現後数日してから発症し、
年長児や成人での報告もある。RSV 単独でも中耳炎を起こしうるが、肺炎球菌やインフルエンザ菌、モ
ラクセラ・カタラーリスなどの細菌による中耳炎を合併することもある 6。また、稀ではあるが脳症や心
筋炎の報告もある 7。福島県内の複数の病院で施行した 280 名の急性脳症/脳炎患者の小児患者の検討で
は 6 名(2.1%)で RSV が原因と推定されている 8。また、少数例ではあるが 12 名の小児及び 5 名の成人急
性心筋炎患者の急性期の血清を次世代シークエンサーで解析した報告では、因果関係は不明なものの 1
名だけだが RSV が陽性であったと報告されている 9。
また、乳児期の RSV 細気管支炎罹患後、長期に渡り反復性喘鳴を認めることが報告されているが、そ
の機序についてはまだ不明なことも多い。対照群と比較し、RSV 細気管支炎罹患歴のある児では、喘鳴
のオッズ比が 4.5 倍、重症群では 7.7 倍、PICU 入室群では 9 倍であったとの報告もある。この喘鳴によ
り受診の頻度が増加するほか、半数以上の保護者が心理的負担や日常生活への影響を受けたと報告され
ている 10。
② 感染経路
成人ボランティアの協力で行った検討では感染経路は主に飛沫感染及び接触感染とされ、同検討では
エアロゾル感染は確認されなかった 11。RSV は不安定なウイルスとされるが、それでもプラスチックや
ガラス表面では 6 時間~12 時間、感染性を保持し、手に付着した後も一定時間感染性を維持するとされ、
汚染表面を接触後、無意識に目や鼻を触ることで感染が成立する 11。その一方で、COVID-19 流行中 2020
年~2021 年の日本での検討で、マスク着用時の無症候性成人キャリア同士での伝播が報告されており、
エアロゾル感染の可能性も示唆されているが 12、メインは飛沫・接触感染と考えられている 1。 そして、
8