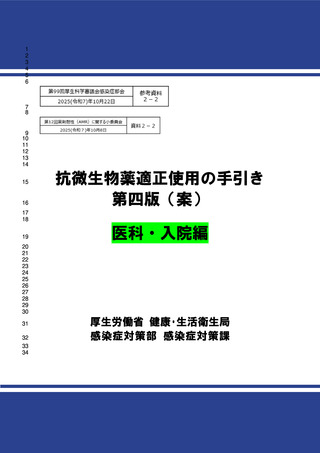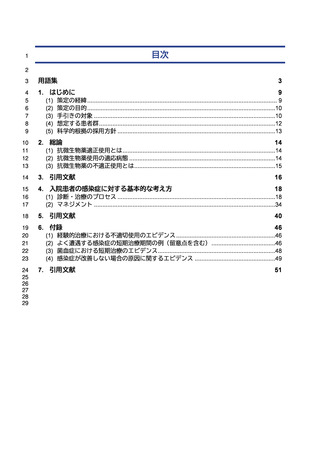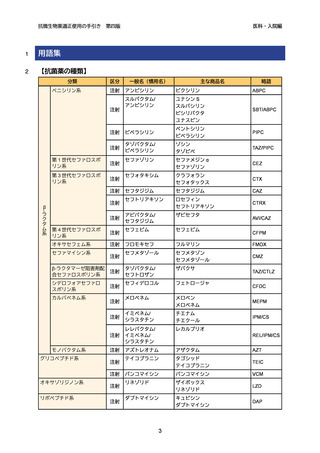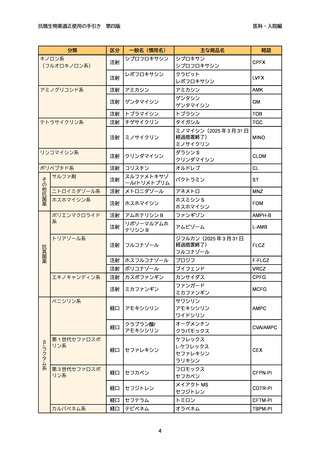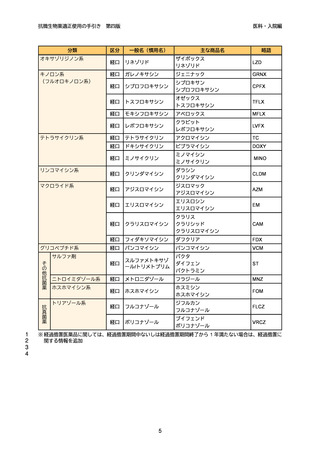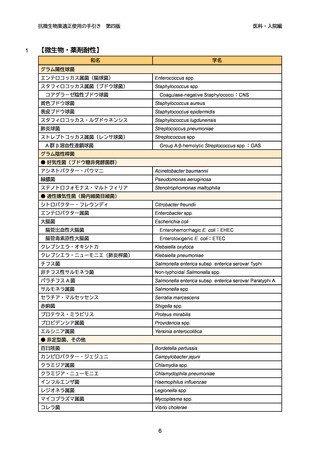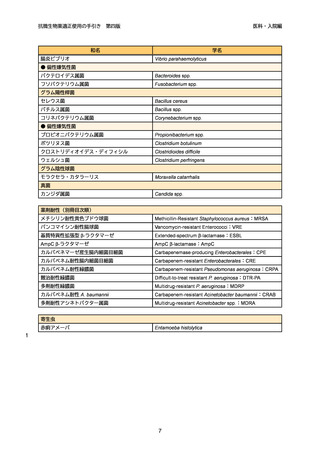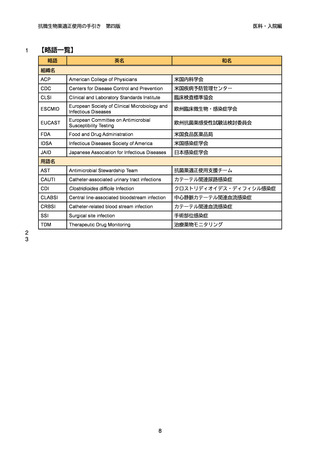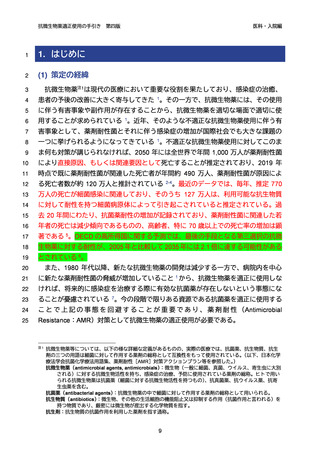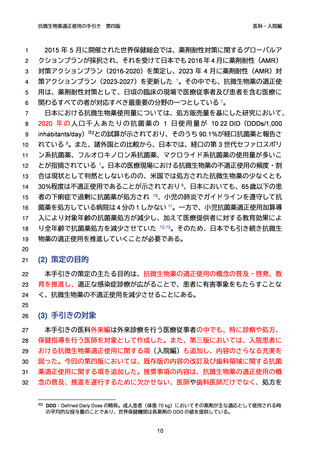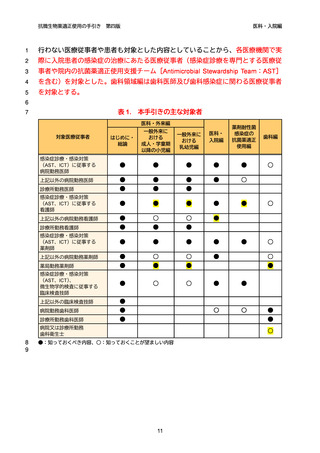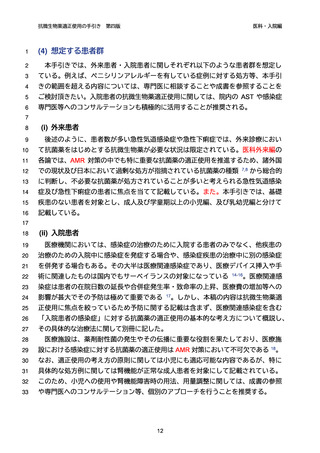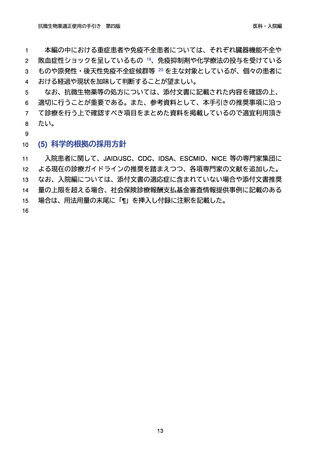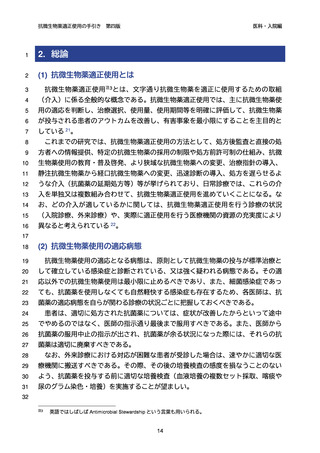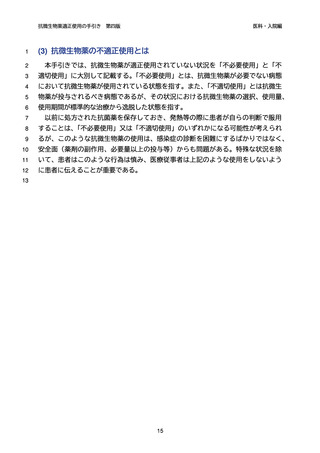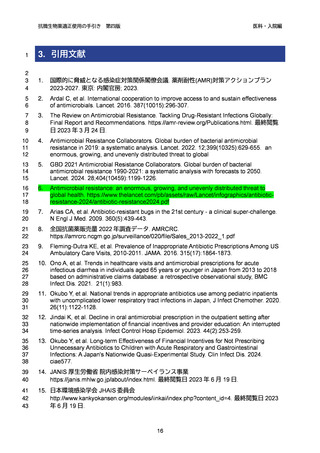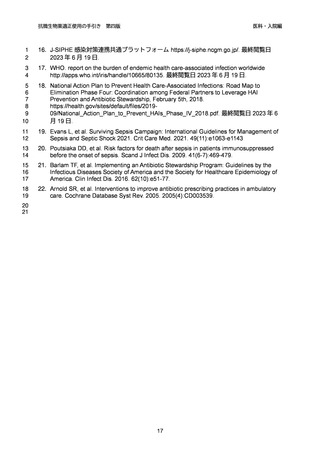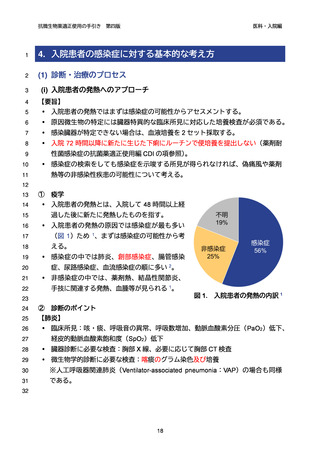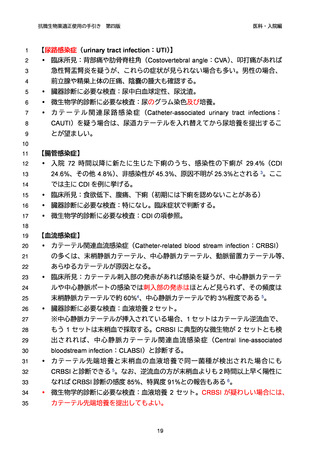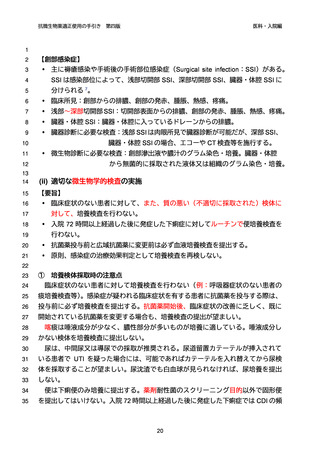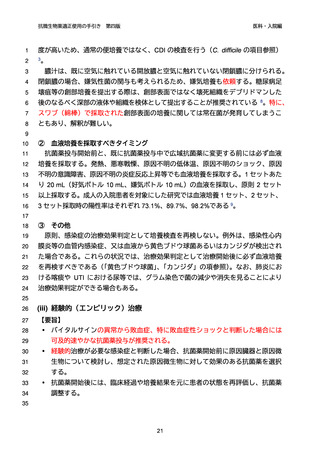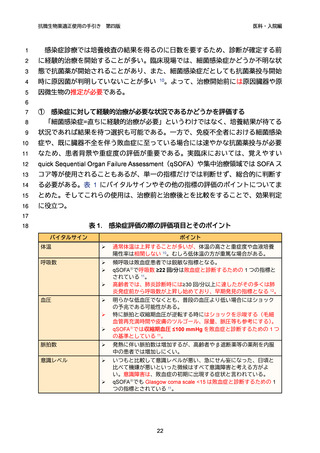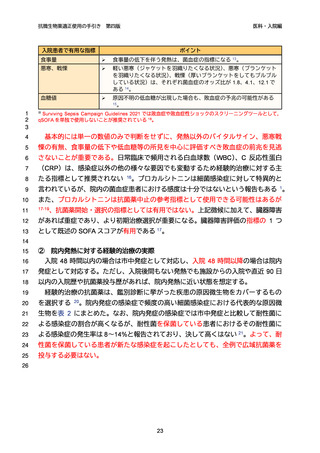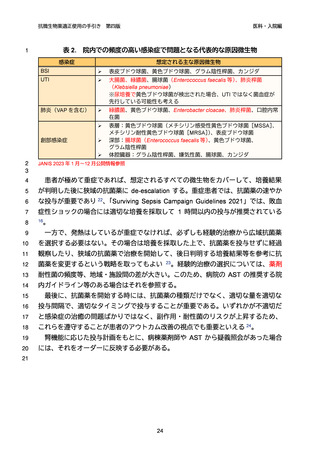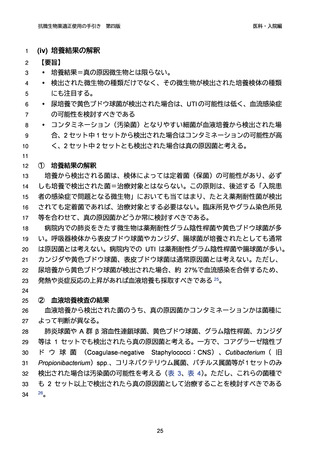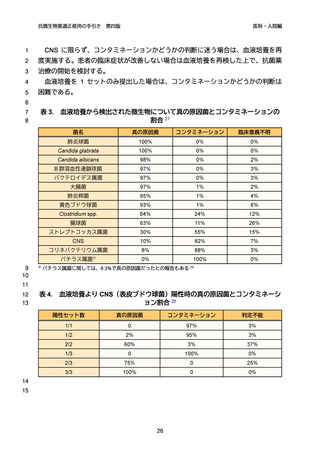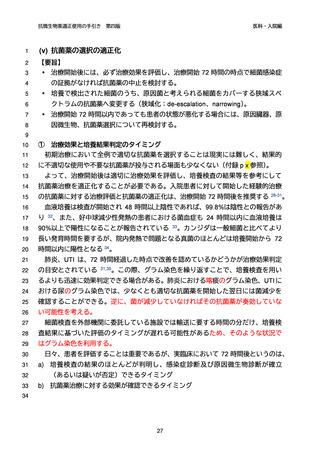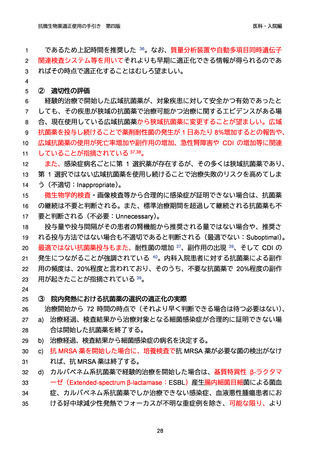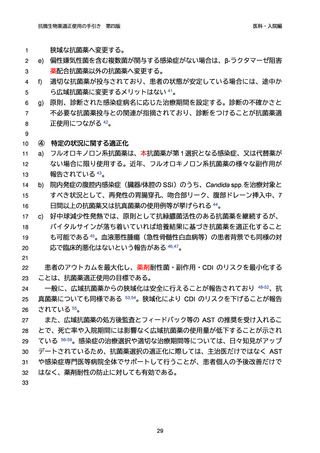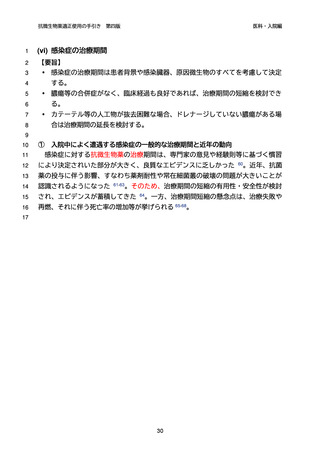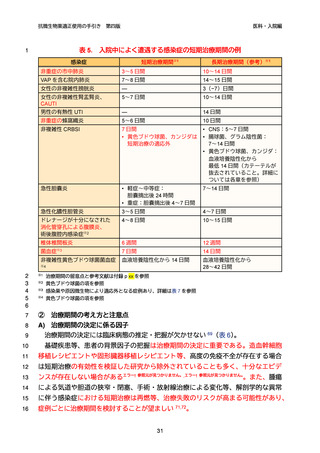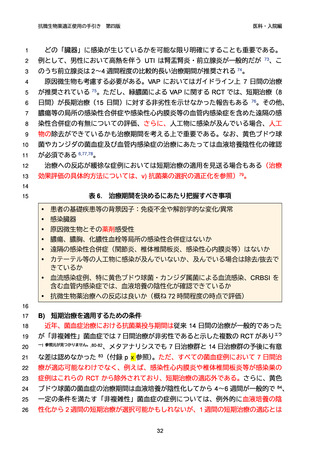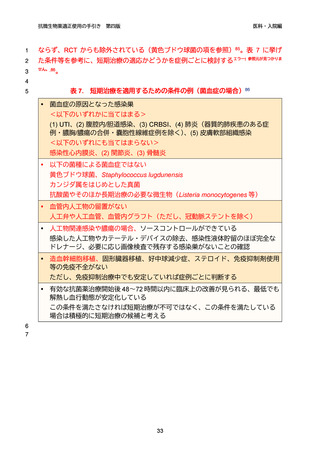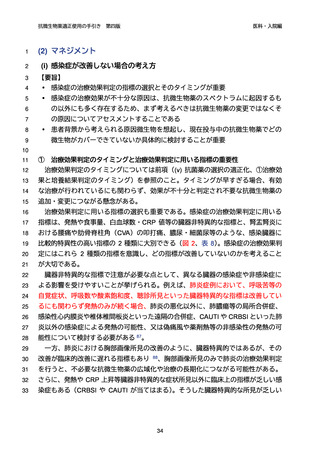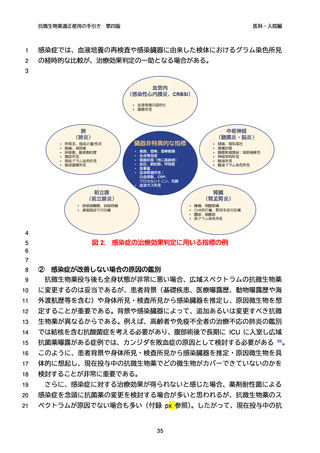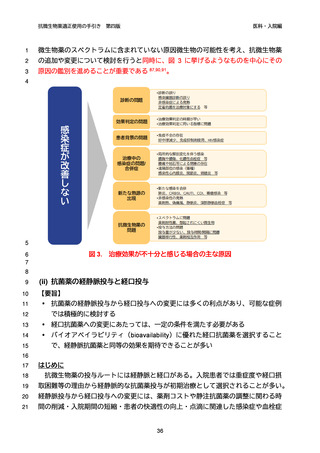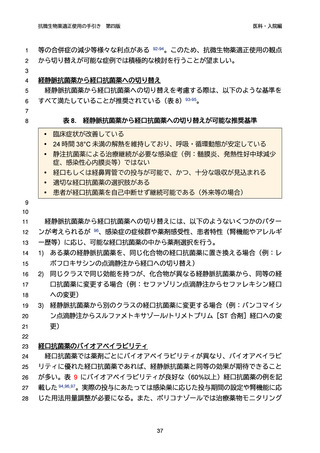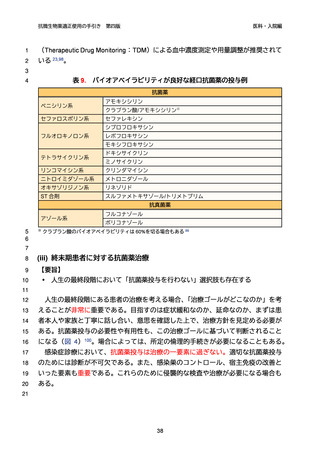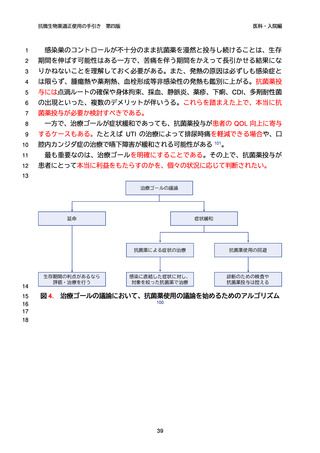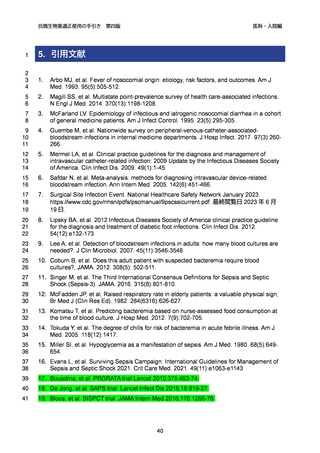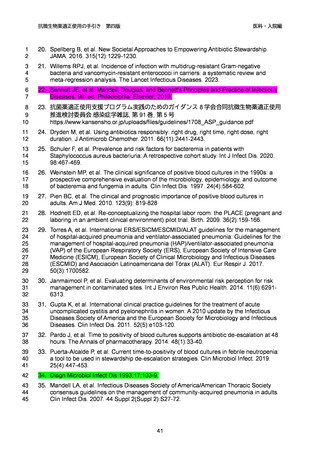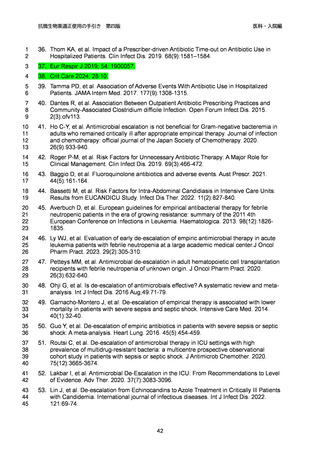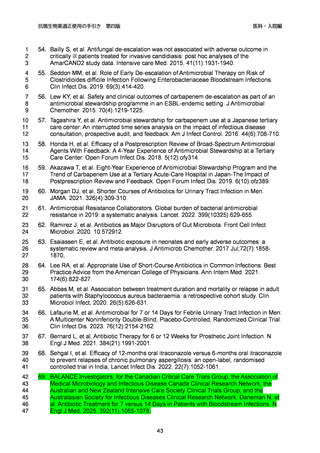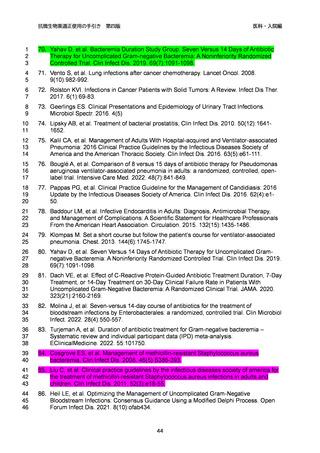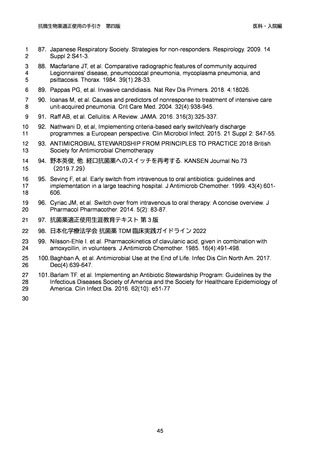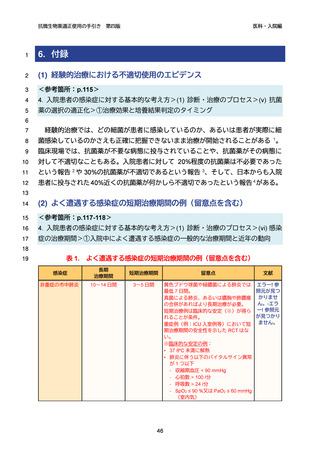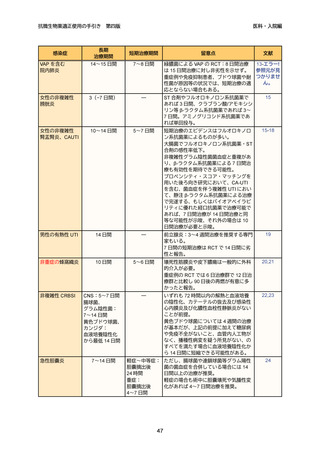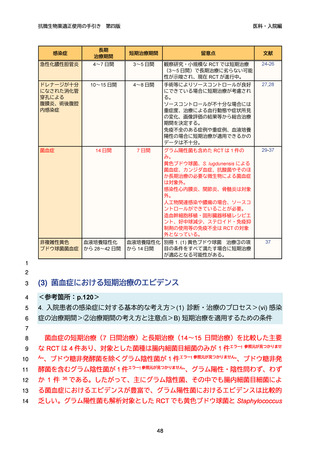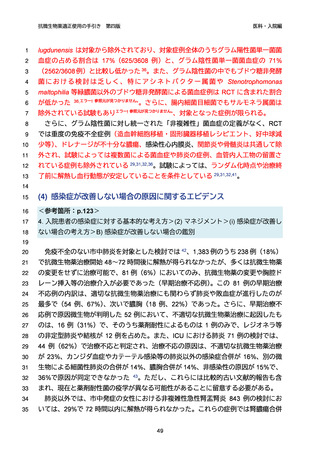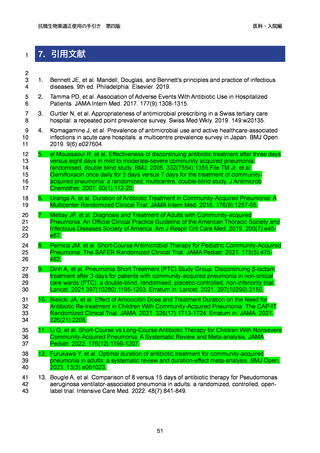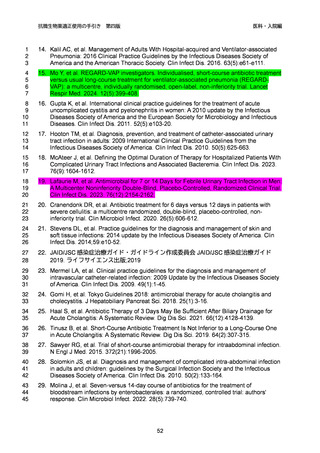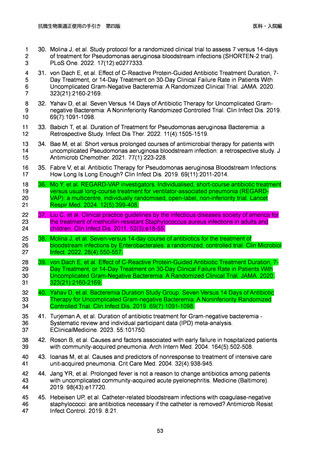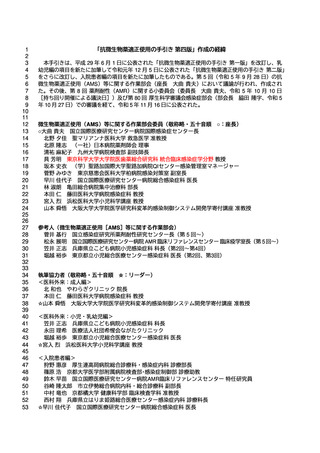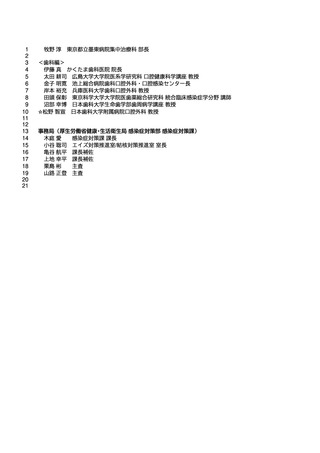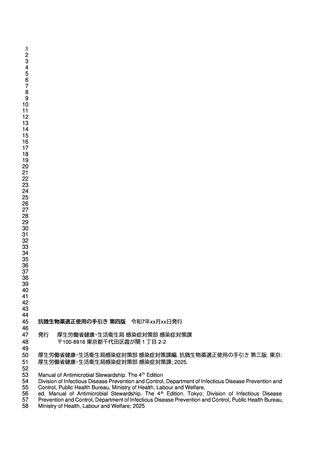よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
抗微生物薬適正使用の手引き
e) 偏性嫌気性菌を含む複数菌が関与する感染症がない場合は、β-ラクタマーゼ阻害
薬配合抗菌薬以外の抗菌薬へ変更する。
3
4
医科・入院編
狭域な抗菌薬へ変更する。
1
2
第四版
適切な抗菌薬が投与されており、患者の状態が安定している場合には、途中か
f)
ら広域抗菌薬に変更するメリットはない 41。
5
6
g) 原則、診断された感染症病名に応じた治療期間を設定する。診断の不確かさと
7
不必要な抗菌薬投与との関連が指摘されており、診断をつけることが抗菌薬適
8
正使用につながる 42。
9
10
④
特定の状況に関する適正化
11
a) フルオロキノロン系抗菌薬は、本抗菌薬が第 1 選択となる感染症、又は代替薬が
12
ない場合に限り使用する。近年、フルオロキノロン系抗菌薬の様々な副作用が
13
報告されている 43。
14
b) 院内発症の腹腔内感染症(臓器/体腔の SSI)のうち、Candida spp.を治療対象と
15
すべき状況として、再発性の胃腸穿孔、吻合部リーク、腹部ドレーン挿入中、7
16
日間以上の抗菌薬又は抗真菌薬の使用例等が挙げられる 44。
17
c)
好中球減少性発熱では、原則として抗緑膿菌活性のある抗菌薬を継続するが、
18
バイタルサインが落ち着いていれば培養結果に基づき抗菌薬を適正化すること
19
も可能である 45。血液悪性腫瘍(急性骨髄性白血病等)の患者背景でも同様の対
20
応で臨床的悪化はないという報告がある 46,47。
21
22
23
患者のアウトカムを最大化し、薬剤耐性菌・副作用・CDI のリスクを最小化する
ことは、抗菌薬適正使用の目標である。
24
一般に、広域抗菌薬からの狭域化は安全に行えることが報告されており 48-52、抗
25
真菌薬についても同様である 53,54。狭域化により CDI のリスクを下げることが報告
26
されている 55。
27
また、広域抗菌薬の処方後監査とフィードバック等の AST の推奨を受け入れるこ
28
とで、死亡率や入院期間には影響なく広域抗菌薬の使用量が低下することが示され
29
ている 56-59。感染症の治療選択や適切な治療期間等については、日々知見がアップ
30
デートされているため、抗菌薬選択の適正化に際しては、主治医だけではなく AST
31
や感染症専門医等病院全体でサポートして行うことが、患者個人の予後改善だけで
32
はなく、薬剤耐性の防止に対しても有効である。
33
29
e) 偏性嫌気性菌を含む複数菌が関与する感染症がない場合は、β-ラクタマーゼ阻害
薬配合抗菌薬以外の抗菌薬へ変更する。
3
4
医科・入院編
狭域な抗菌薬へ変更する。
1
2
第四版
適切な抗菌薬が投与されており、患者の状態が安定している場合には、途中か
f)
ら広域抗菌薬に変更するメリットはない 41。
5
6
g) 原則、診断された感染症病名に応じた治療期間を設定する。診断の不確かさと
7
不必要な抗菌薬投与との関連が指摘されており、診断をつけることが抗菌薬適
8
正使用につながる 42。
9
10
④
特定の状況に関する適正化
11
a) フルオロキノロン系抗菌薬は、本抗菌薬が第 1 選択となる感染症、又は代替薬が
12
ない場合に限り使用する。近年、フルオロキノロン系抗菌薬の様々な副作用が
13
報告されている 43。
14
b) 院内発症の腹腔内感染症(臓器/体腔の SSI)のうち、Candida spp.を治療対象と
15
すべき状況として、再発性の胃腸穿孔、吻合部リーク、腹部ドレーン挿入中、7
16
日間以上の抗菌薬又は抗真菌薬の使用例等が挙げられる 44。
17
c)
好中球減少性発熱では、原則として抗緑膿菌活性のある抗菌薬を継続するが、
18
バイタルサインが落ち着いていれば培養結果に基づき抗菌薬を適正化すること
19
も可能である 45。血液悪性腫瘍(急性骨髄性白血病等)の患者背景でも同様の対
20
応で臨床的悪化はないという報告がある 46,47。
21
22
23
患者のアウトカムを最大化し、薬剤耐性菌・副作用・CDI のリスクを最小化する
ことは、抗菌薬適正使用の目標である。
24
一般に、広域抗菌薬からの狭域化は安全に行えることが報告されており 48-52、抗
25
真菌薬についても同様である 53,54。狭域化により CDI のリスクを下げることが報告
26
されている 55。
27
また、広域抗菌薬の処方後監査とフィードバック等の AST の推奨を受け入れるこ
28
とで、死亡率や入院期間には影響なく広域抗菌薬の使用量が低下することが示され
29
ている 56-59。感染症の治療選択や適切な治療期間等については、日々知見がアップ
30
デートされているため、抗菌薬選択の適正化に際しては、主治医だけではなく AST
31
や感染症専門医等病院全体でサポートして行うことが、患者個人の予後改善だけで
32
はなく、薬剤耐性の防止に対しても有効である。
33
29