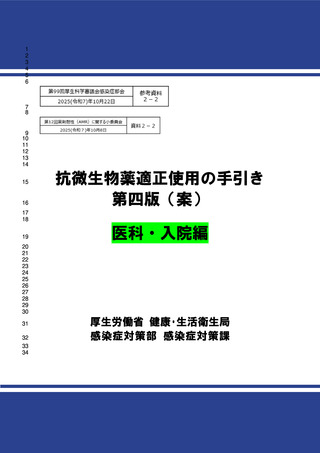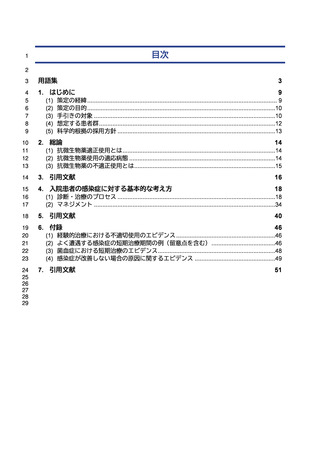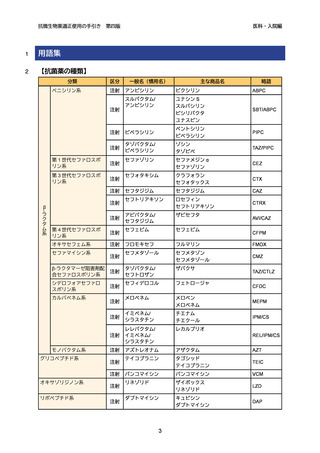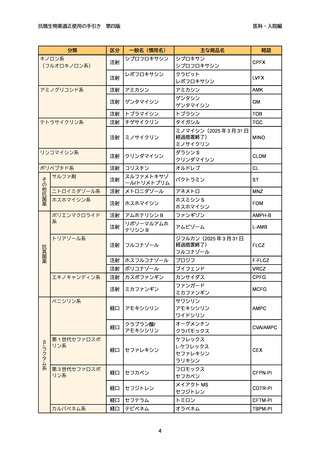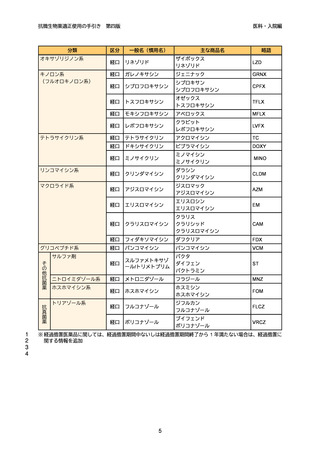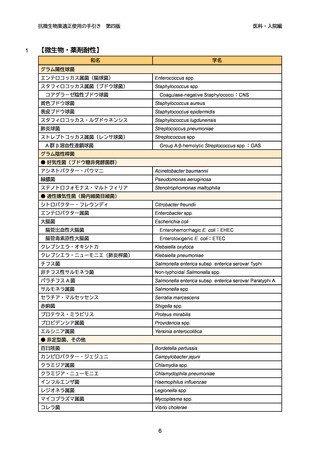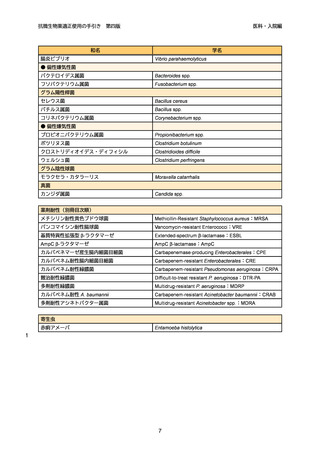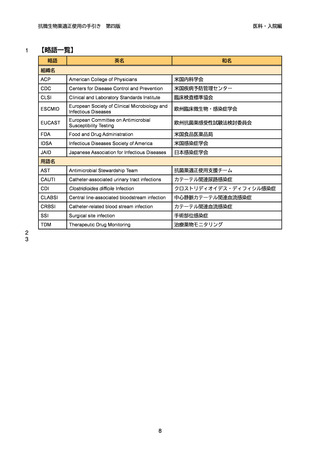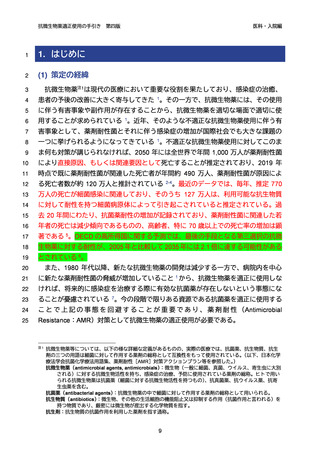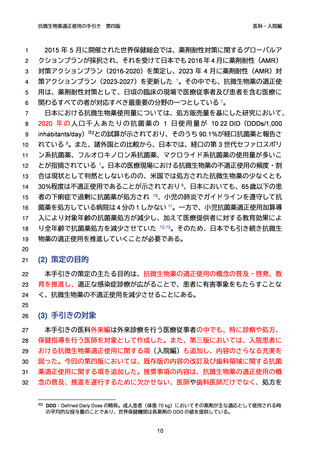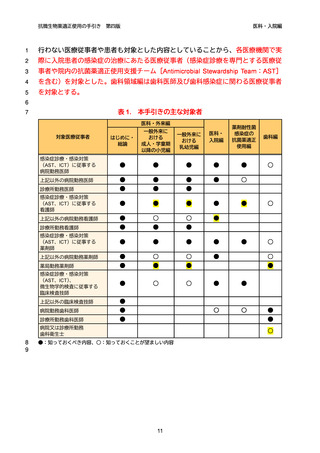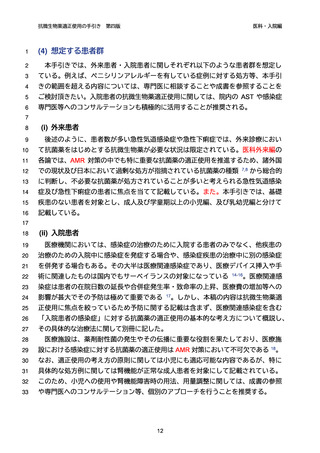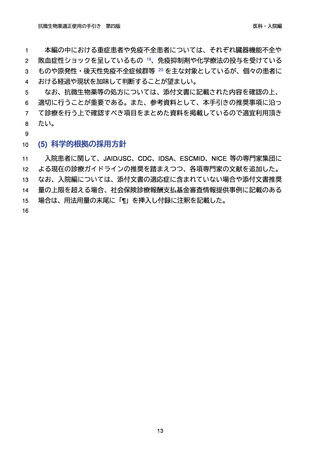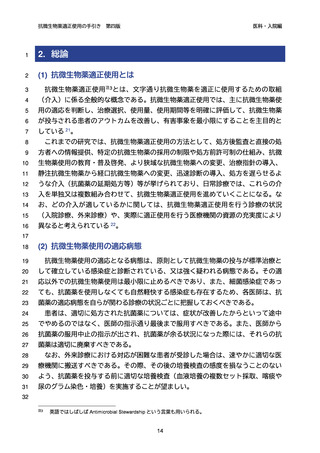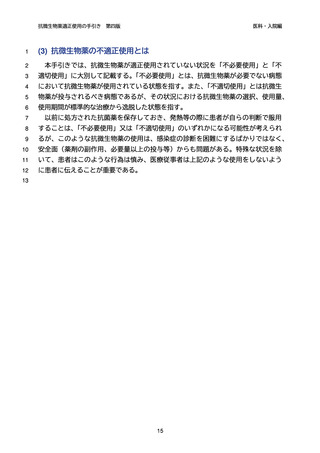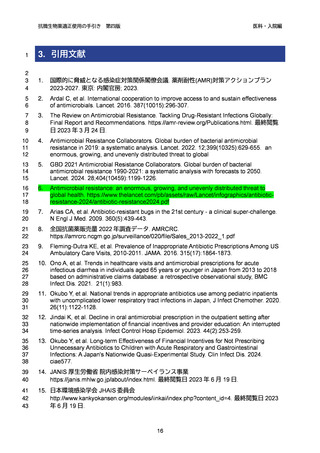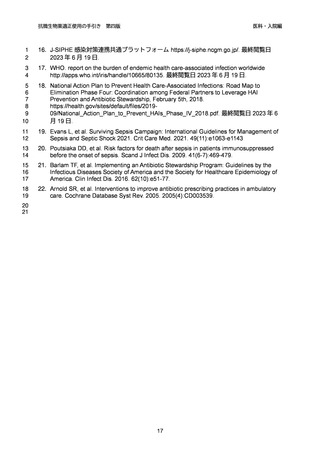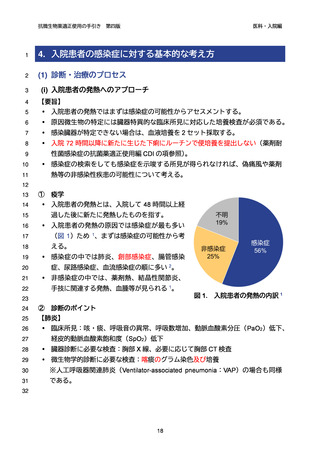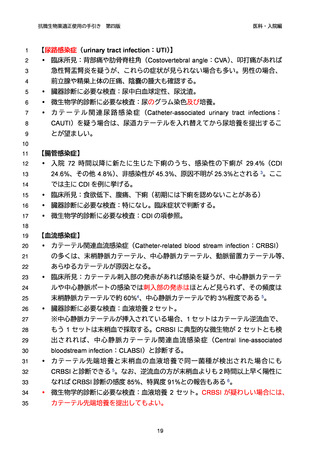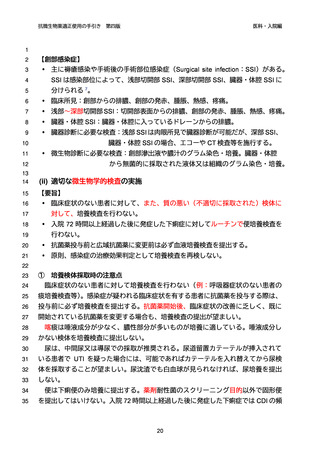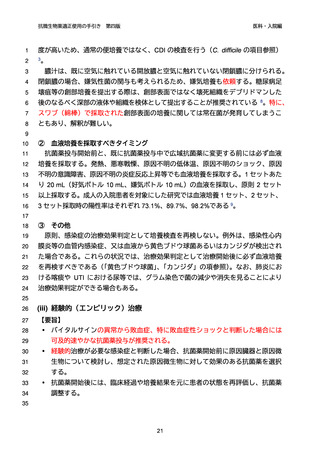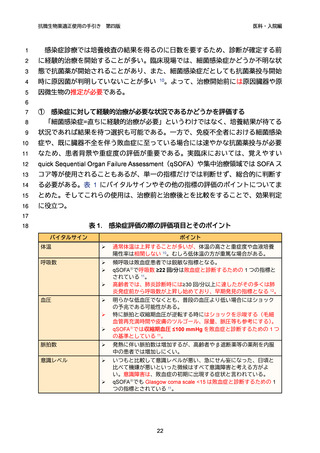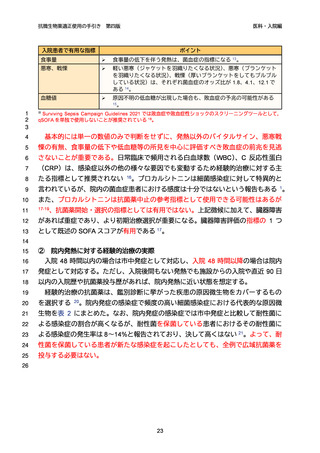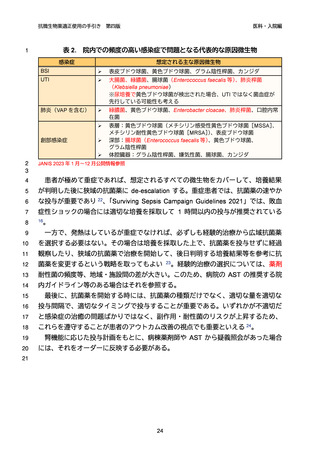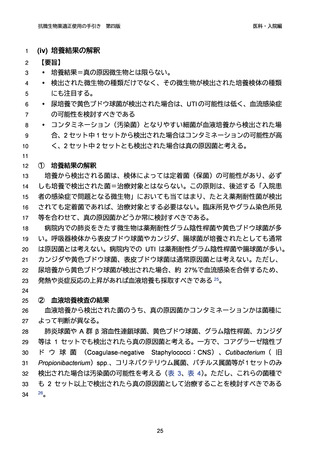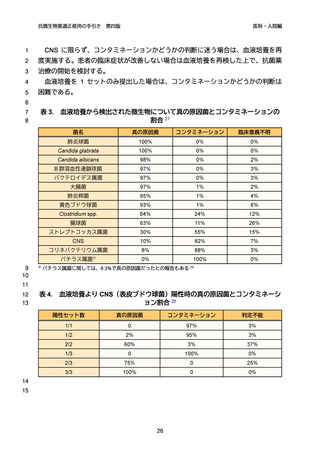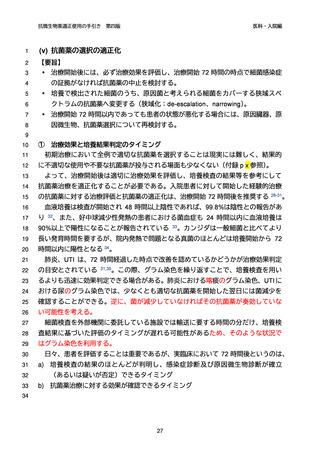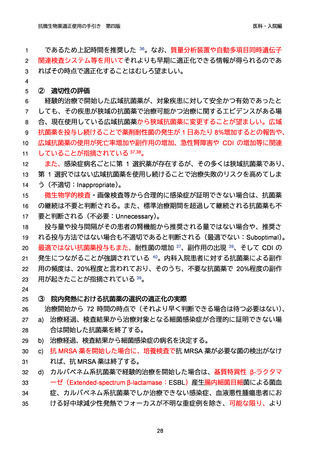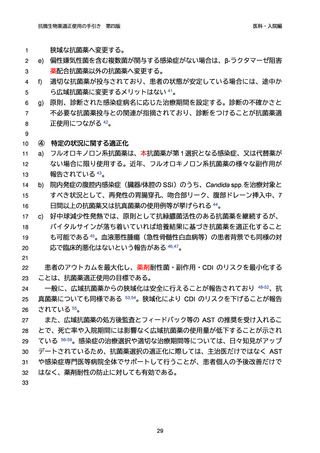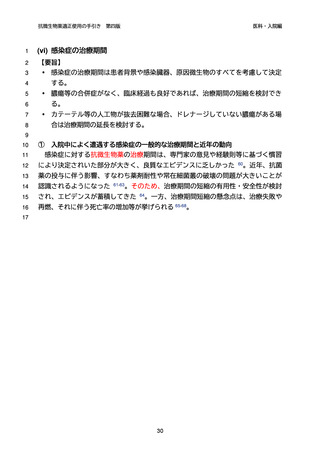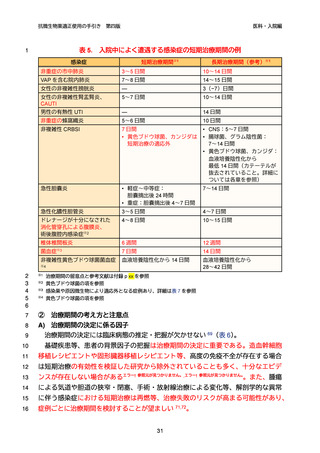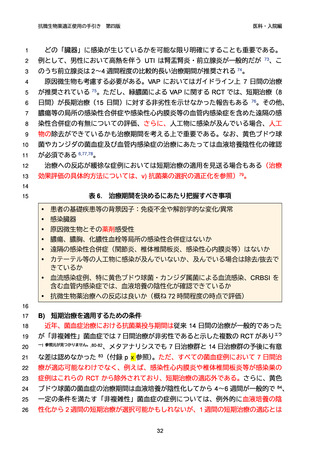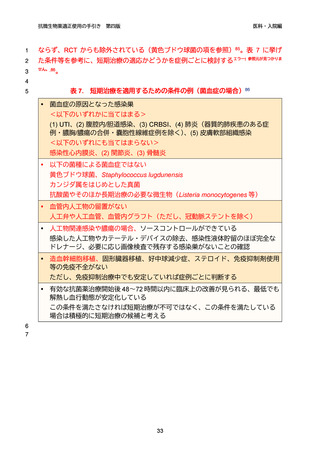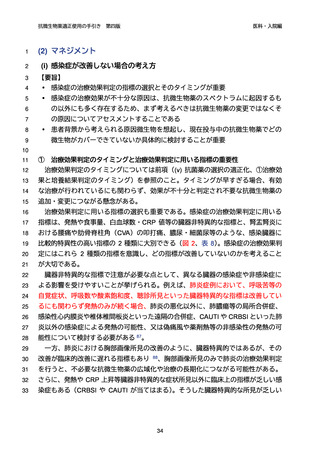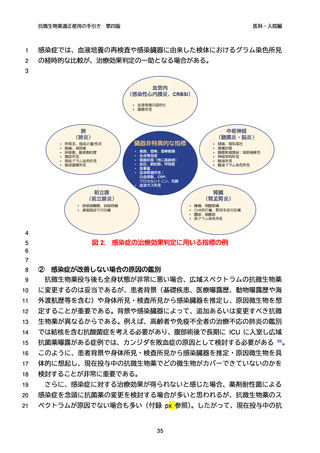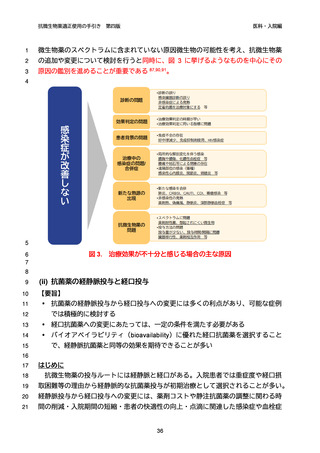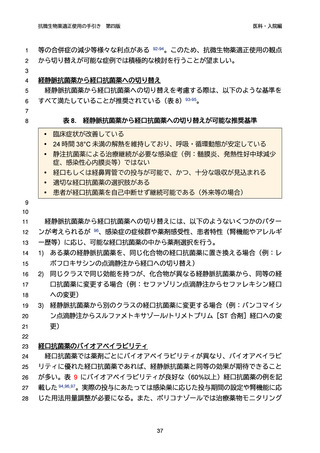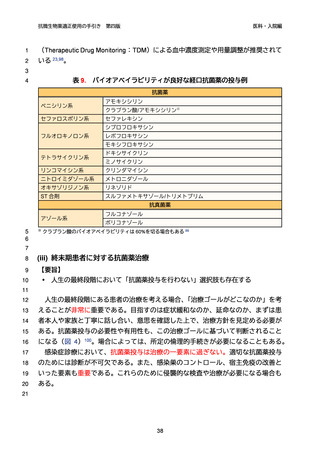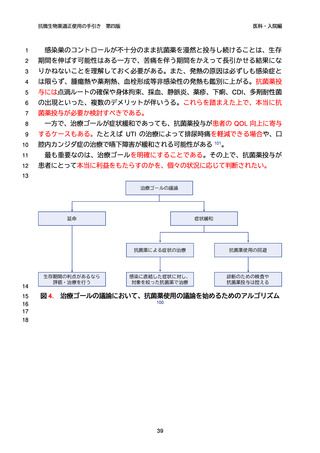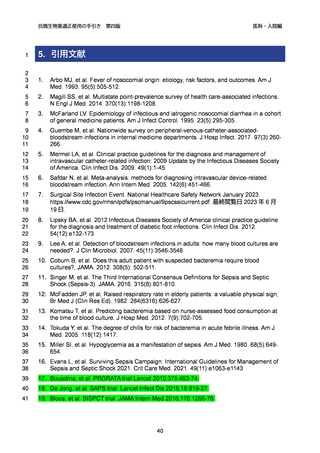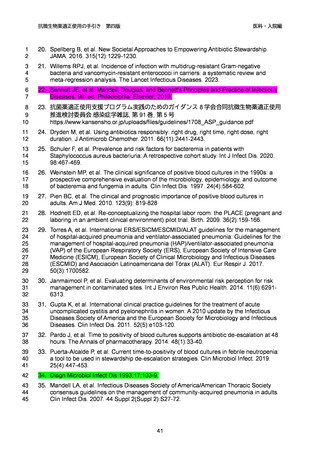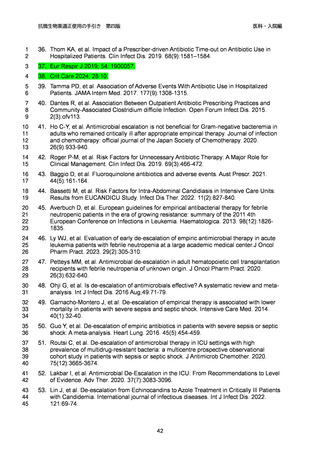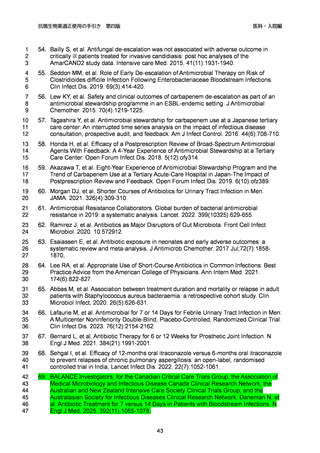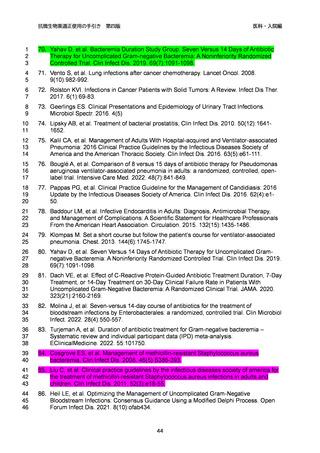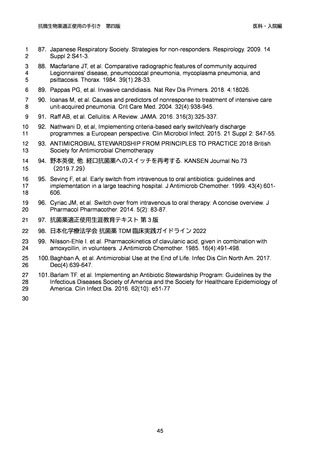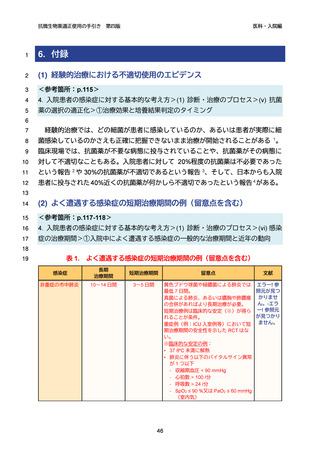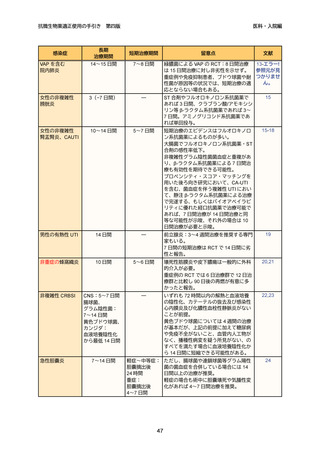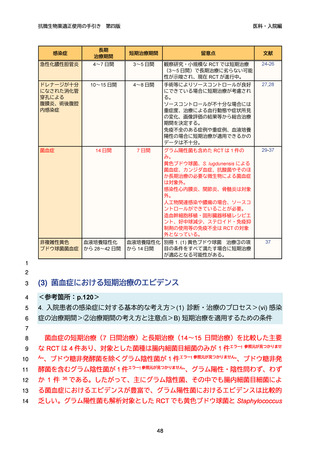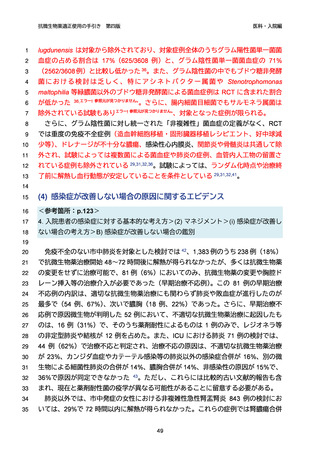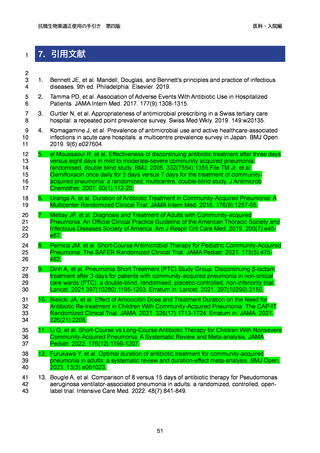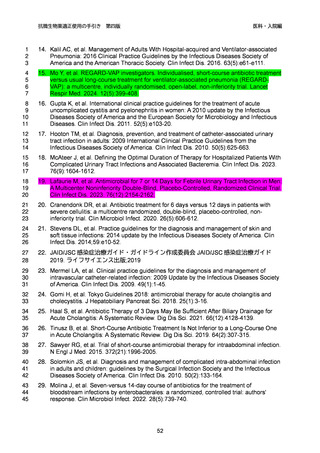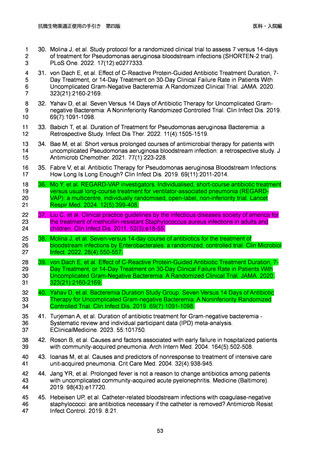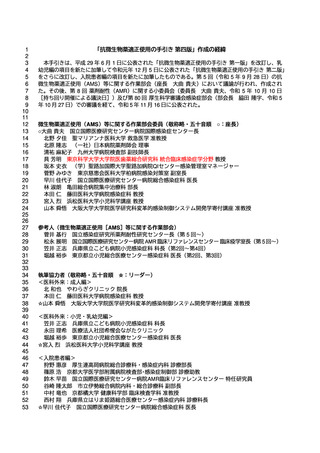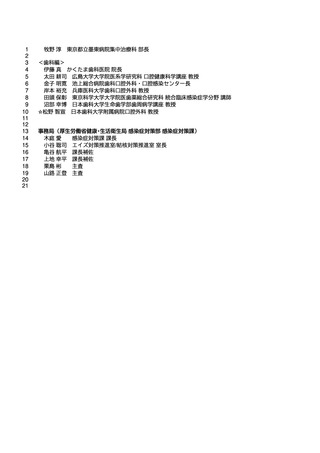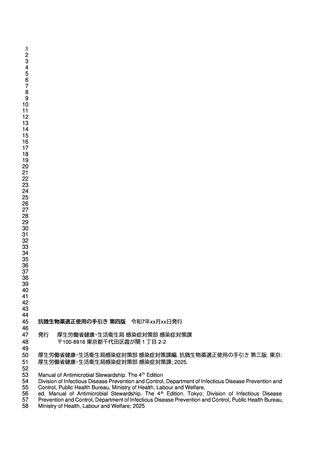よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
抗微生物薬適正使用の手引き
第四版
医科・入院編
1
であるため上記時間を推奨した 36。なお、質量分析装置や自動多項目同時遺伝子
2
関連検査システム等を用いてそれよりも早期に適正化できる情報が得られるのであ
3
ればその時点で適正化することはむしろ望ましい。
4
5
②
適切性の評価
6
経験的治療で開始した広域抗菌薬が、対象疾患に対して安全かつ有効であったと
7
しても、その疾患が狭域の抗菌薬で治療可能かつ治療に関するエビデンスがある場
8
合、現在使用している広域抗菌薬から狭域抗菌薬に変更することが望ましい。広域
9
抗菌薬を投与し続けることで薬剤耐性菌の発生が 1 日あたり 8%増加するとの報告や、
10
広域抗菌薬の使用が死亡率増加や副作用の増加、急性腎障害や CDI の増加等に関連
11
していることが指摘されている 37,38。
また、感染症病名ごとに第 1 選択薬が存在するが、その多くは狭域抗菌薬であり、
12
13
第 1 選択ではない広域抗菌薬を使用し続けることで治療失敗のリスクを高めてしま
14
う(不適切:Inappropriate)。
15
微生物学的検査・画像検査等から合理的に感染症が証明できない場合は、抗菌薬
16
の継続は不要と判断される。また、標準治療期間を超過して継続される抗菌薬も不
17
要と判断される(不必要:Unnecessary)。
18
投与量や投与間隔がその患者の腎機能から推奨される量ではない場合や、推奨さ
19
れる投与方法ではない場合も不適切であると判断される(最適でない:Suboptimal)。
20
最適ではない抗菌薬投与もまた、耐性菌の増加 37、副作用の出現 39、そして CDI の
21
発生につながることが強調されている 40。内科入院患者に対する抗菌薬による副作
22
用の頻度は、20%程度と言われており、そのうち、不要な抗菌薬で 20%程度の副作
23
用が起きたことが指摘されている 39。
24
25
③
治療開始から 72 時間の時点で(それより早く判断できる場合は待つ必要はない)、
26
27
院内発熱における抗菌薬の選択の適正化の実際
a) 治療経過、検査結果から治療対象となる細菌感染症が合理的に証明できない場
合は開始した抗菌薬を終了する。
28
29
b) 治療経過、検査結果から細菌感染症の病名を決定する。
30
c)
31
抗 MRSA 薬を開始した場合に、培養検査で抗 MRSA 薬が必要な菌の検出がなけ
れば、抗 MRSA 薬は終了する。
32
d) カルバペネム系抗菌薬で経験的治療を開始した場合は、基質特異性 β-ラクタマ
33
ーゼ(Extended-spectrum β-lactamase:ESBL)産生腸内細菌目細菌による菌血
34
症、カルバペネム系抗菌薬でしか治療できない感染症、血液悪性腫瘍患者にお
35
ける好中球減少性発熱でフォーカスが不明な重症例を除き、可能な限り、より
28
第四版
医科・入院編
1
であるため上記時間を推奨した 36。なお、質量分析装置や自動多項目同時遺伝子
2
関連検査システム等を用いてそれよりも早期に適正化できる情報が得られるのであ
3
ればその時点で適正化することはむしろ望ましい。
4
5
②
適切性の評価
6
経験的治療で開始した広域抗菌薬が、対象疾患に対して安全かつ有効であったと
7
しても、その疾患が狭域の抗菌薬で治療可能かつ治療に関するエビデンスがある場
8
合、現在使用している広域抗菌薬から狭域抗菌薬に変更することが望ましい。広域
9
抗菌薬を投与し続けることで薬剤耐性菌の発生が 1 日あたり 8%増加するとの報告や、
10
広域抗菌薬の使用が死亡率増加や副作用の増加、急性腎障害や CDI の増加等に関連
11
していることが指摘されている 37,38。
また、感染症病名ごとに第 1 選択薬が存在するが、その多くは狭域抗菌薬であり、
12
13
第 1 選択ではない広域抗菌薬を使用し続けることで治療失敗のリスクを高めてしま
14
う(不適切:Inappropriate)。
15
微生物学的検査・画像検査等から合理的に感染症が証明できない場合は、抗菌薬
16
の継続は不要と判断される。また、標準治療期間を超過して継続される抗菌薬も不
17
要と判断される(不必要:Unnecessary)。
18
投与量や投与間隔がその患者の腎機能から推奨される量ではない場合や、推奨さ
19
れる投与方法ではない場合も不適切であると判断される(最適でない:Suboptimal)。
20
最適ではない抗菌薬投与もまた、耐性菌の増加 37、副作用の出現 39、そして CDI の
21
発生につながることが強調されている 40。内科入院患者に対する抗菌薬による副作
22
用の頻度は、20%程度と言われており、そのうち、不要な抗菌薬で 20%程度の副作
23
用が起きたことが指摘されている 39。
24
25
③
治療開始から 72 時間の時点で(それより早く判断できる場合は待つ必要はない)、
26
27
院内発熱における抗菌薬の選択の適正化の実際
a) 治療経過、検査結果から治療対象となる細菌感染症が合理的に証明できない場
合は開始した抗菌薬を終了する。
28
29
b) 治療経過、検査結果から細菌感染症の病名を決定する。
30
c)
31
抗 MRSA 薬を開始した場合に、培養検査で抗 MRSA 薬が必要な菌の検出がなけ
れば、抗 MRSA 薬は終了する。
32
d) カルバペネム系抗菌薬で経験的治療を開始した場合は、基質特異性 β-ラクタマ
33
ーゼ(Extended-spectrum β-lactamase:ESBL)産生腸内細菌目細菌による菌血
34
症、カルバペネム系抗菌薬でしか治療できない感染症、血液悪性腫瘍患者にお
35
ける好中球減少性発熱でフォーカスが不明な重症例を除き、可能な限り、より
28