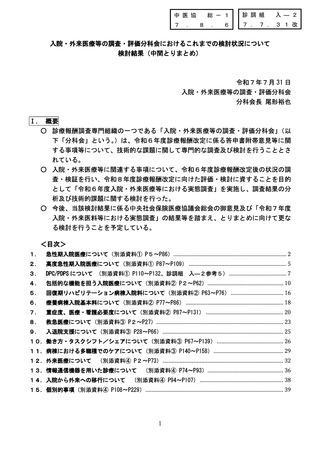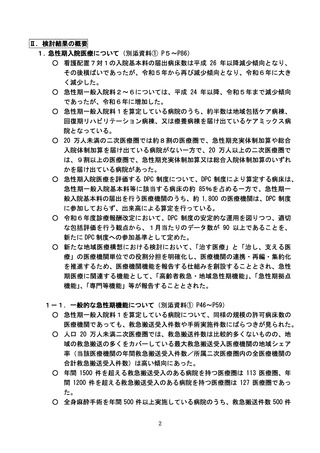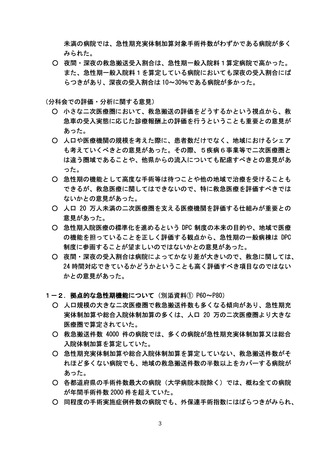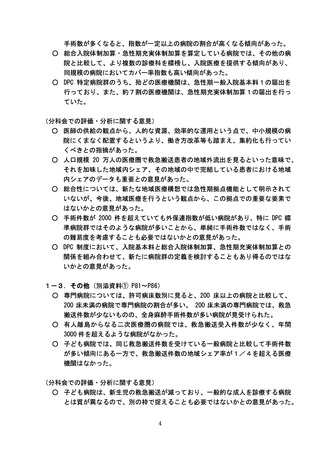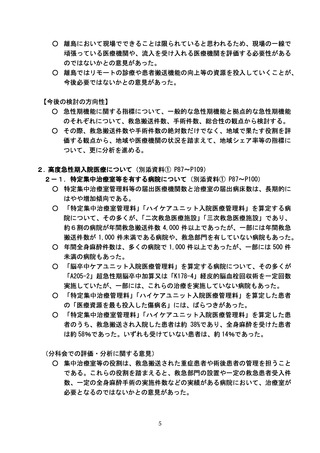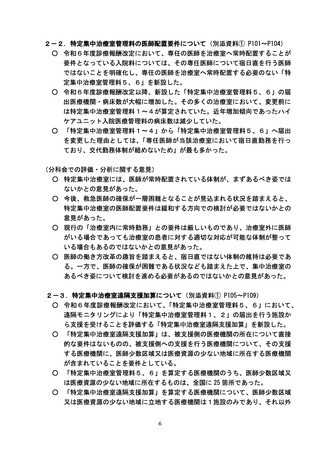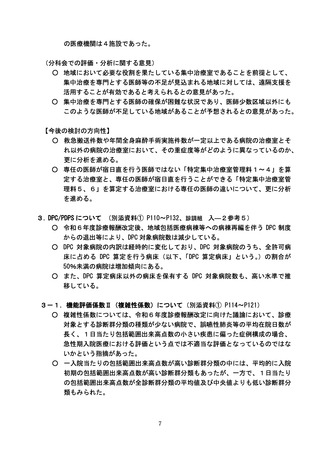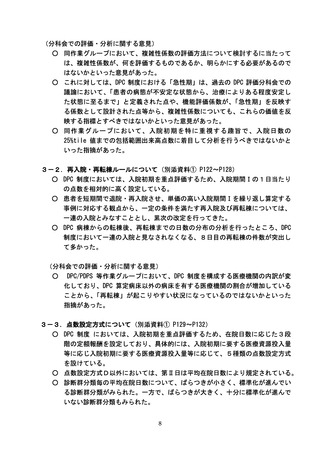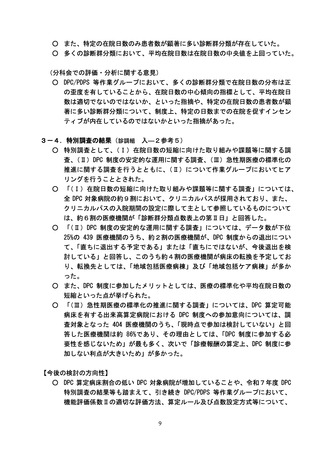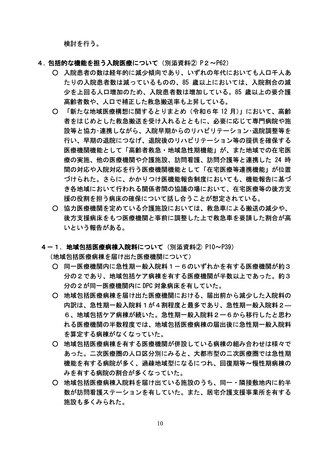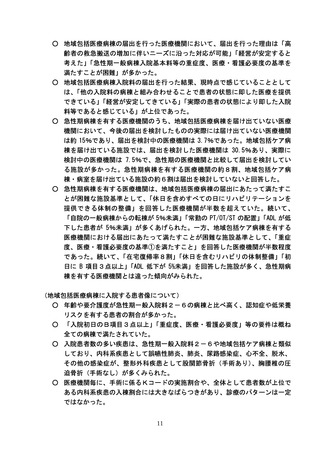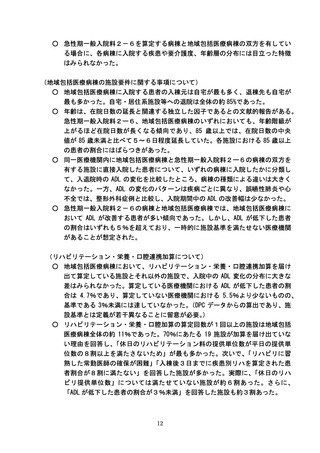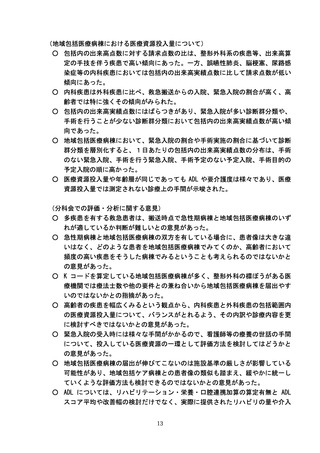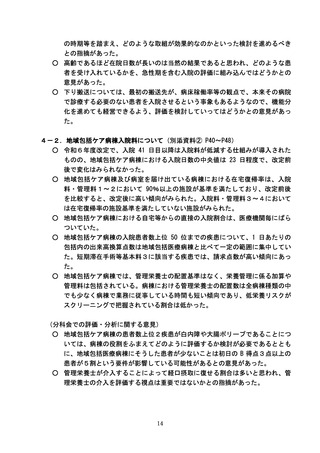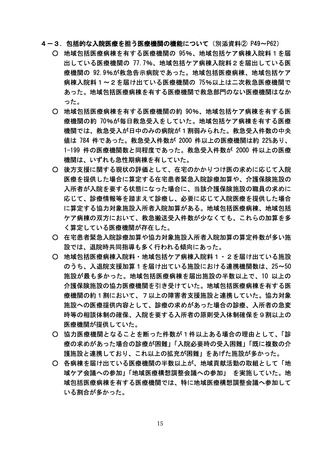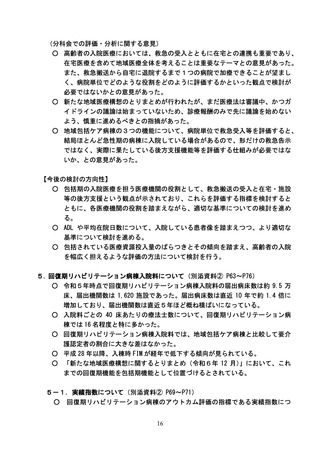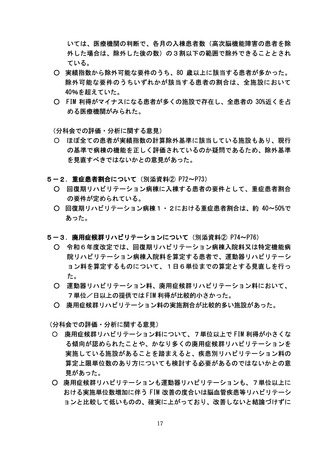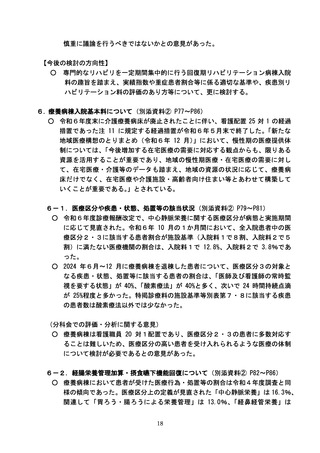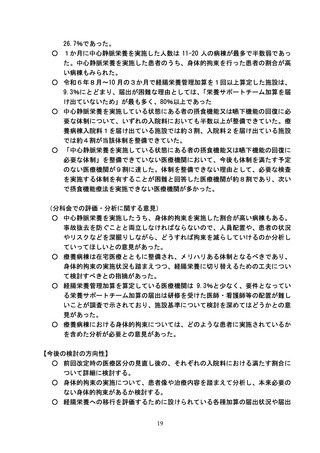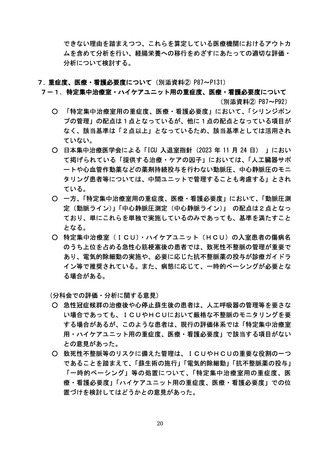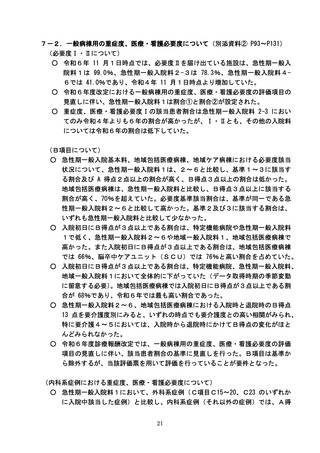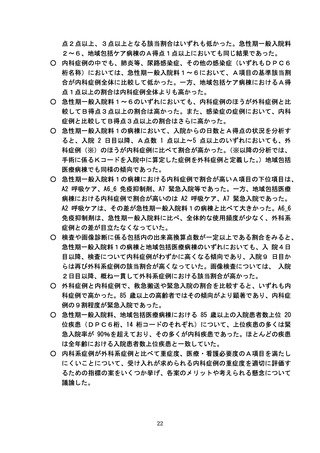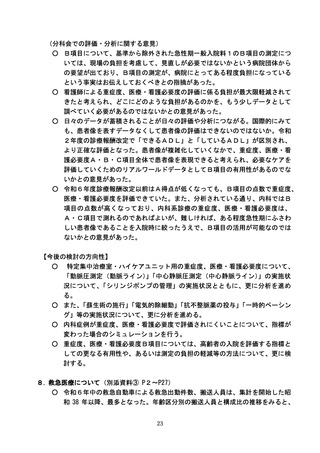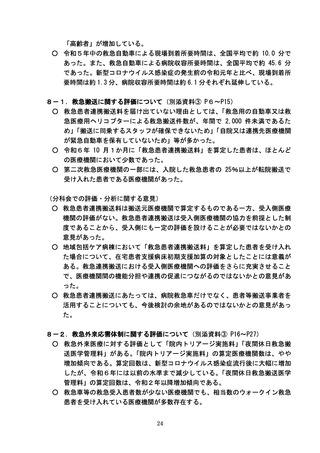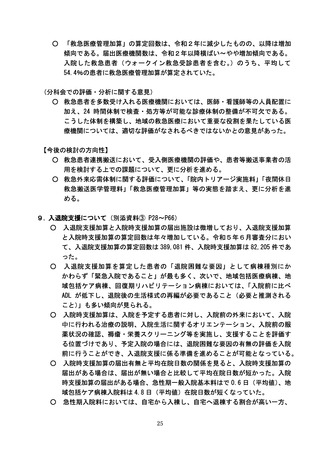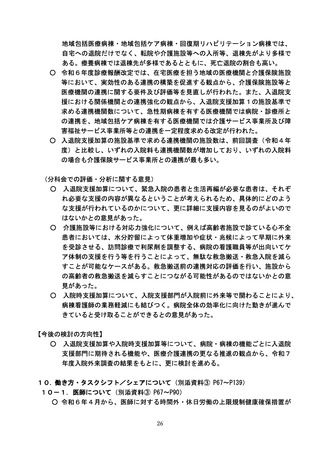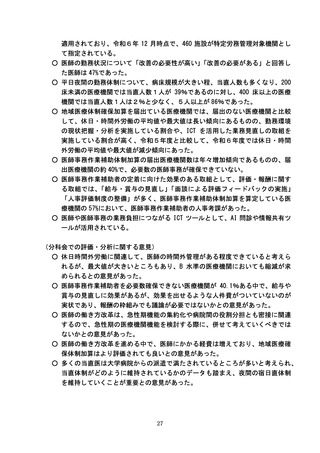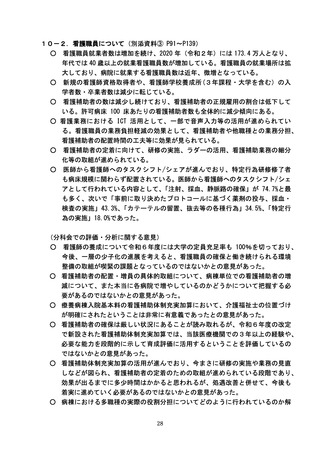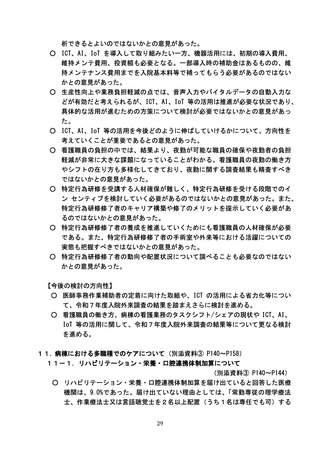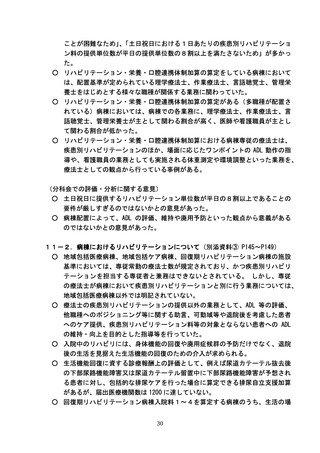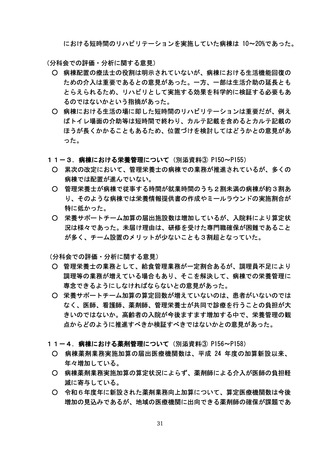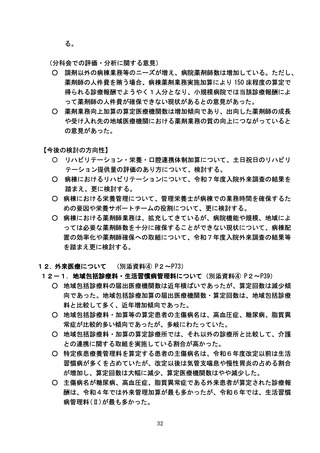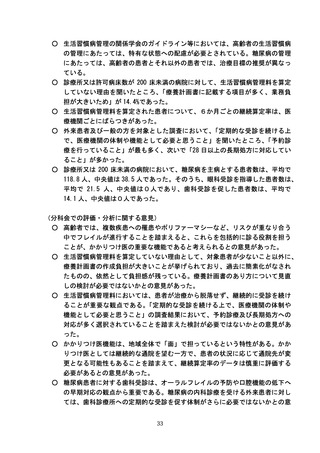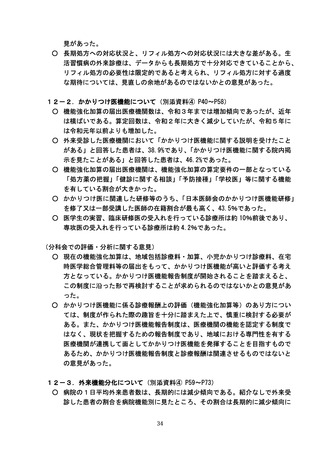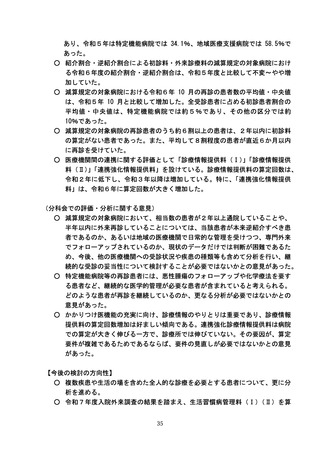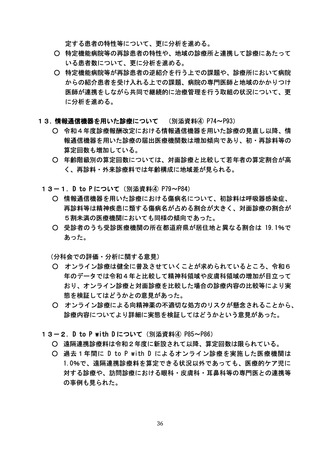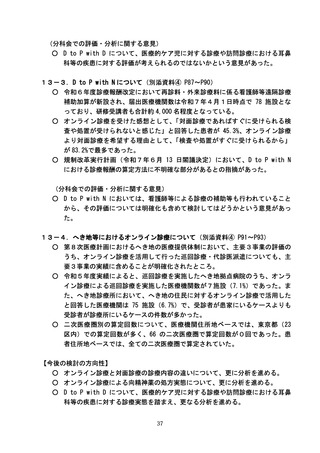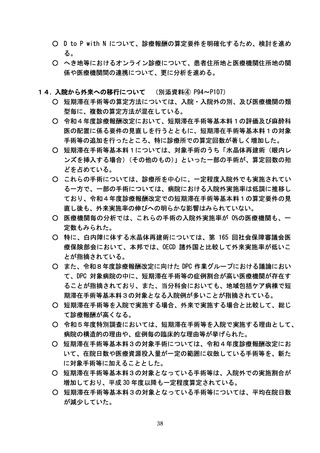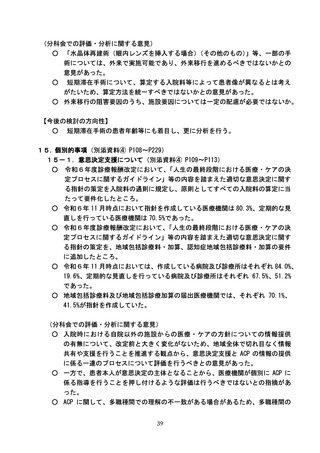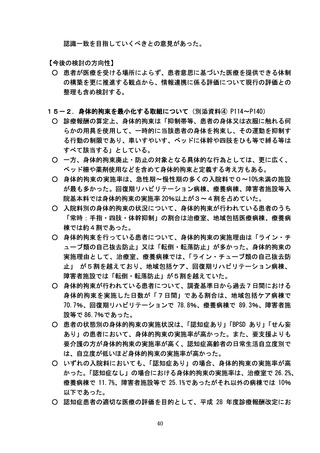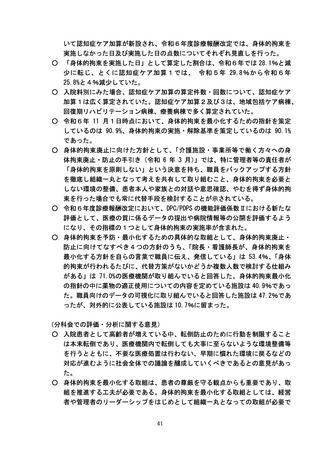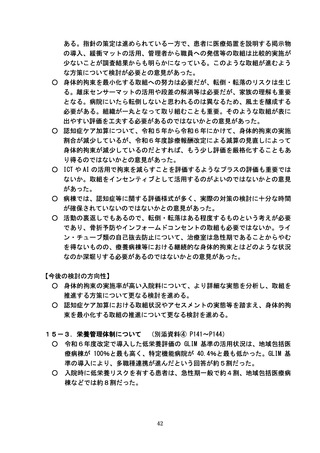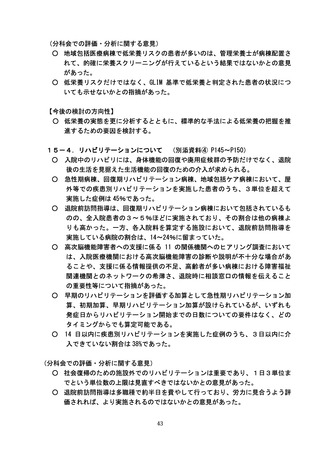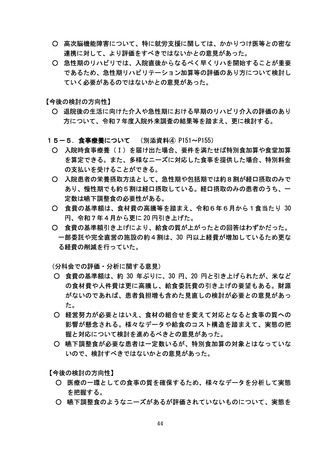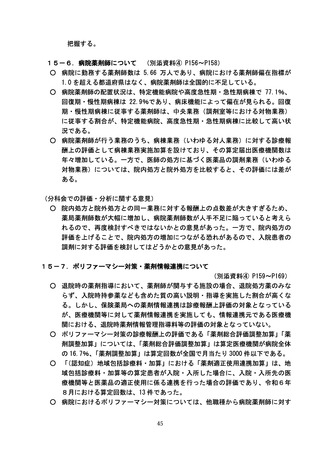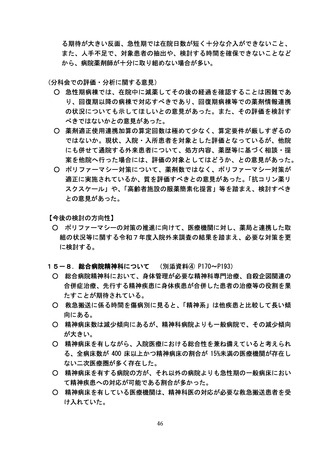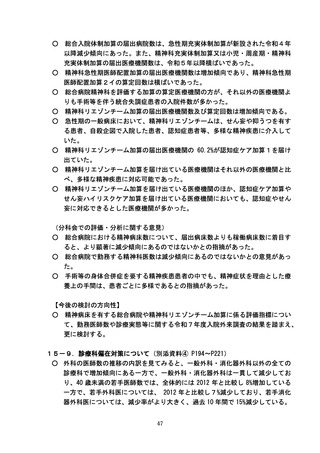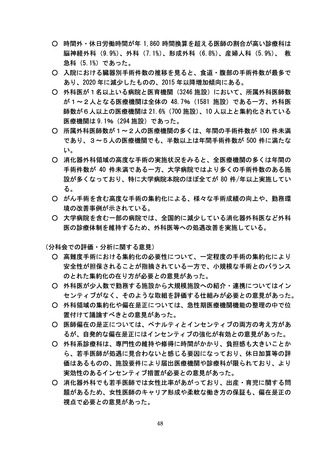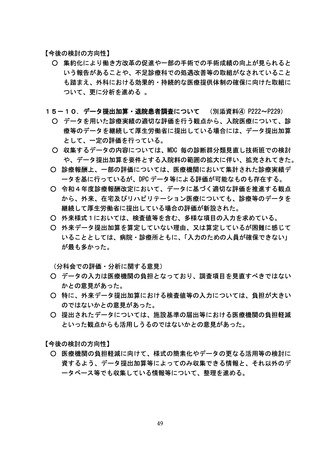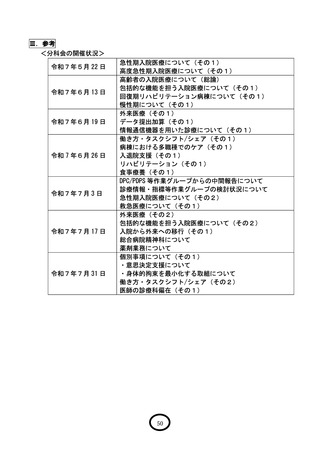よむ、つかう、まなぶ。
総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
10-2.看護職員について(別添資料③ P91~P139)
○ 看護職員就業者数は増加を続け、2020 年(令和2年)には 173.4 万人となり、
年代では 40 歳以上の就業看護職員数が増加している。看護職員の就業場所は拡
大しており、病院に就業する看護職員数は近年、微増となっている。
○ 新規の看護師資格取得者や、看護師学校養成所(3年課程・大学を含む)の入
学者数・卒業者数は減少に転じている。
○ 看護補助者の数は減少し続けており、看護補助者の正規雇用の割合は低下して
いる。許可病床 100 床あたりの看護補助者数も全体的に減少傾向にある。
○ 看護業務における ICT 活用として、一部で音声入力等の活用が進められてい
る。看護職員の業務負担軽減の効果として、看護補助者や他職種との業務分担、
看護補助者の配置時間の工夫等に効果が見られている。
○ 看護補助者の定着に向けて、研修の実施、ラダーの活用、看護補助業務の細分
化等の取組が進められている。
○ 医師から看護師へのタスクシフト/シェアが進んでおり、特定行為研修修了者
も病床規模に関わらず配置されている。医師から看護師へのタスクシフト/シェ
アとして行われている内容として、「注射、採血、静脈路の確保」が 74.7%と最
も多く、次いで「事前に取り決めたプロトコールに基づく薬剤の投与、採血・
検査の実施」43.3%、「カテーテルの留置、抜去等の各種行為」34.5%、「特定行
為の実施」18.0%であった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 看護師の養成について令和6年度には大学の定員充足率も 100%を切っており、
今後、一層の少子化の進展を考えると、看護職員の確保と働き続けられる環境
整備の取組が喫緊の課題となっているのではないかとの意見があった。
○ 看護補助者の配置・増員の具体的取組について、病棟単位での看護補助者の増
減について、また本当に各病院で増やしているのかどうかについて把握する必
要があるのではないかとの意見があった。
○ 療養病棟入院基本料の看護補助体制充実加算において、介護福祉士の位置づけ
が明確にされたということは非常に有意義であったとの意見があった。
○ 看護補助者の確保は厳しい状況にあることが読み取れるが、令和6年度の改定
で新設された看護補助体制充実加算では、当該医療機関での3年以上の経験や、
必要な能力を段階的に示して育成評価に活用するということを評価しているの
ではないかとの意見があった。
○ 看護補助体制充実加算の活用が進んでおり、今まさに研修の実施や業務の見直
しなどが図られ、看護補助者の定着のための取組が進められている段階であり、
効果が出るまでに多少時間はかかると思われるが、処遇改善と併せて、今後も
着実に進めていく必要があるのではないかとの意見があった。
○ 病棟における多職種の実際の役割分担についてどのように行われているのか解
28
○ 看護職員就業者数は増加を続け、2020 年(令和2年)には 173.4 万人となり、
年代では 40 歳以上の就業看護職員数が増加している。看護職員の就業場所は拡
大しており、病院に就業する看護職員数は近年、微増となっている。
○ 新規の看護師資格取得者や、看護師学校養成所(3年課程・大学を含む)の入
学者数・卒業者数は減少に転じている。
○ 看護補助者の数は減少し続けており、看護補助者の正規雇用の割合は低下して
いる。許可病床 100 床あたりの看護補助者数も全体的に減少傾向にある。
○ 看護業務における ICT 活用として、一部で音声入力等の活用が進められてい
る。看護職員の業務負担軽減の効果として、看護補助者や他職種との業務分担、
看護補助者の配置時間の工夫等に効果が見られている。
○ 看護補助者の定着に向けて、研修の実施、ラダーの活用、看護補助業務の細分
化等の取組が進められている。
○ 医師から看護師へのタスクシフト/シェアが進んでおり、特定行為研修修了者
も病床規模に関わらず配置されている。医師から看護師へのタスクシフト/シェ
アとして行われている内容として、「注射、採血、静脈路の確保」が 74.7%と最
も多く、次いで「事前に取り決めたプロトコールに基づく薬剤の投与、採血・
検査の実施」43.3%、「カテーテルの留置、抜去等の各種行為」34.5%、「特定行
為の実施」18.0%であった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 看護師の養成について令和6年度には大学の定員充足率も 100%を切っており、
今後、一層の少子化の進展を考えると、看護職員の確保と働き続けられる環境
整備の取組が喫緊の課題となっているのではないかとの意見があった。
○ 看護補助者の配置・増員の具体的取組について、病棟単位での看護補助者の増
減について、また本当に各病院で増やしているのかどうかについて把握する必
要があるのではないかとの意見があった。
○ 療養病棟入院基本料の看護補助体制充実加算において、介護福祉士の位置づけ
が明確にされたということは非常に有意義であったとの意見があった。
○ 看護補助者の確保は厳しい状況にあることが読み取れるが、令和6年度の改定
で新設された看護補助体制充実加算では、当該医療機関での3年以上の経験や、
必要な能力を段階的に示して育成評価に活用するということを評価しているの
ではないかとの意見があった。
○ 看護補助体制充実加算の活用が進んでおり、今まさに研修の実施や業務の見直
しなどが図られ、看護補助者の定着のための取組が進められている段階であり、
効果が出るまでに多少時間はかかると思われるが、処遇改善と併せて、今後も
着実に進めていく必要があるのではないかとの意見があった。
○ 病棟における多職種の実際の役割分担についてどのように行われているのか解
28