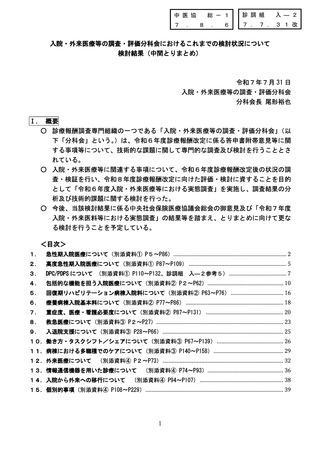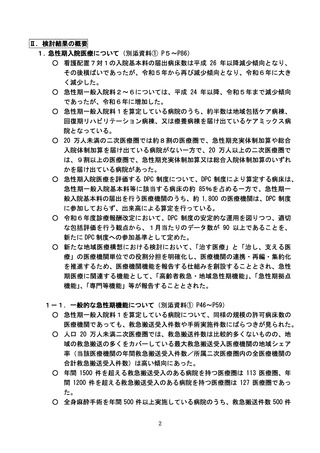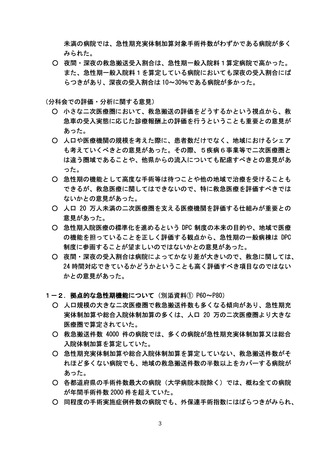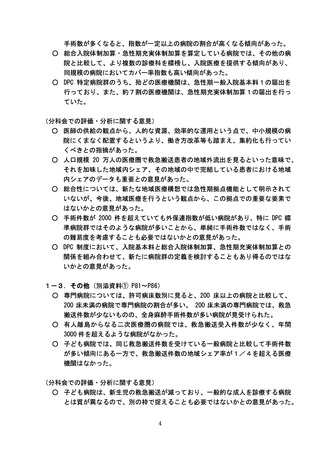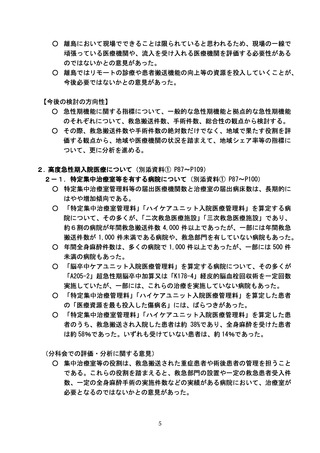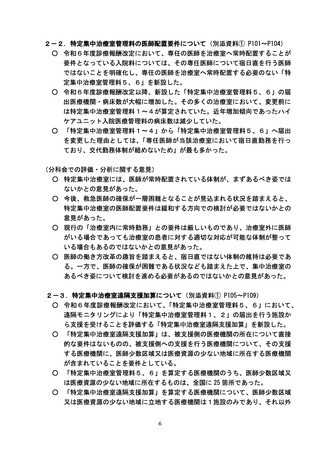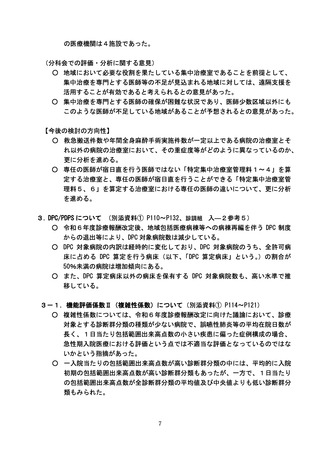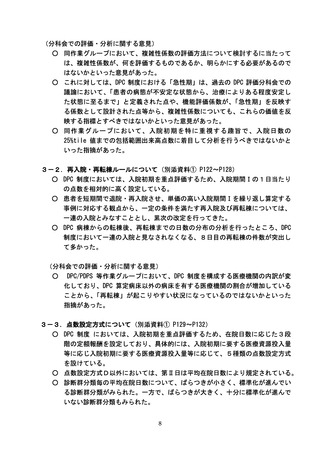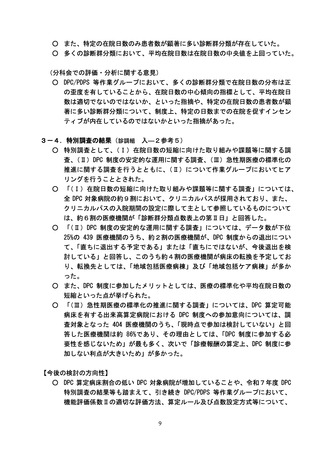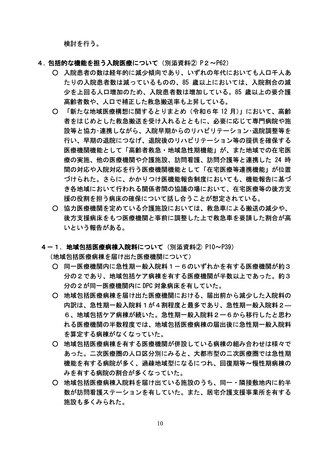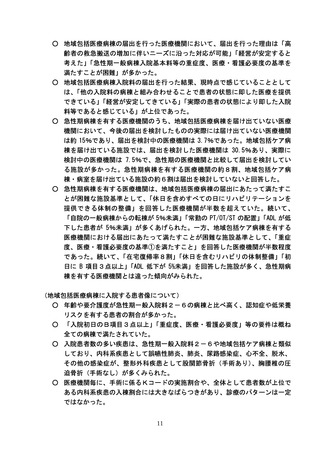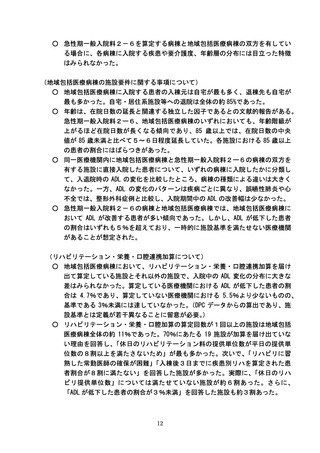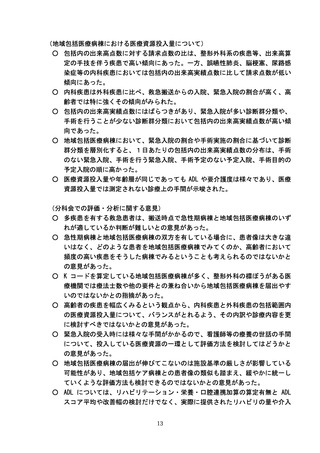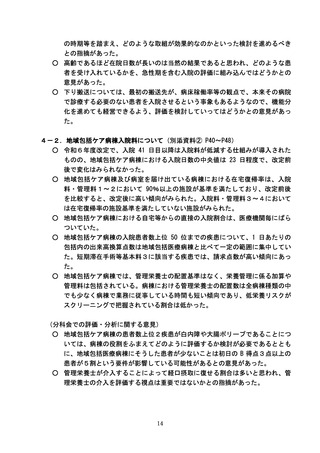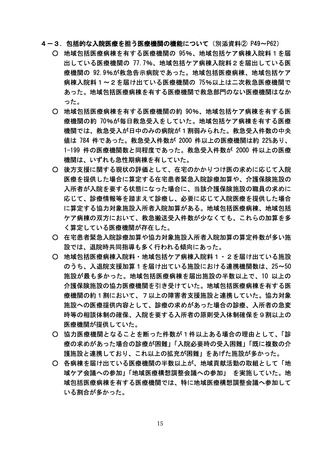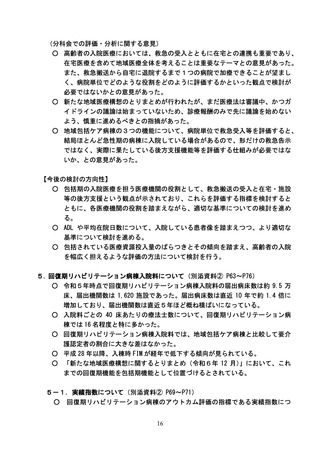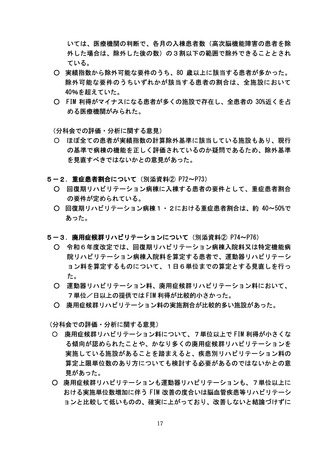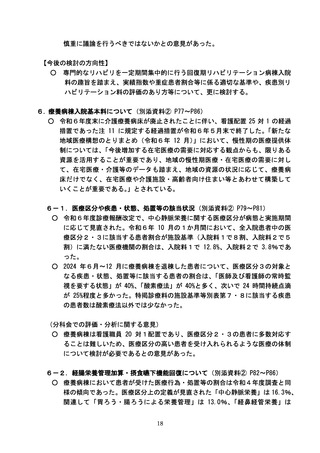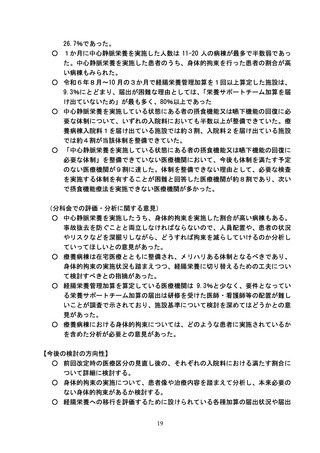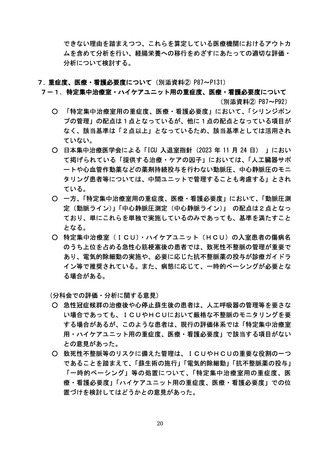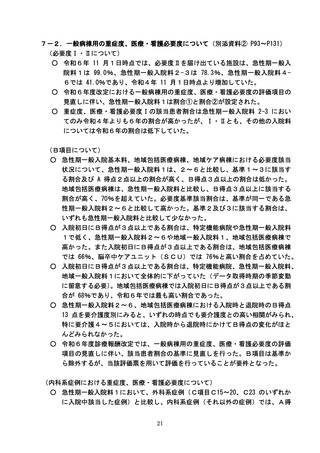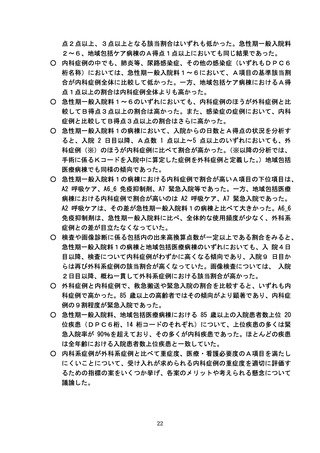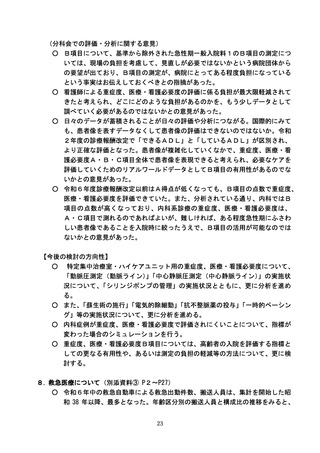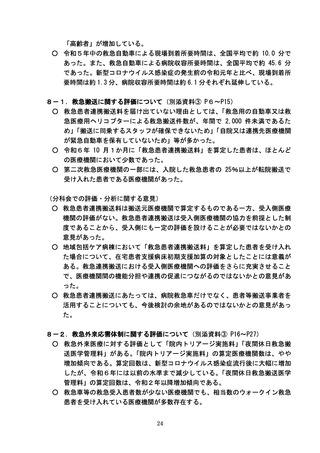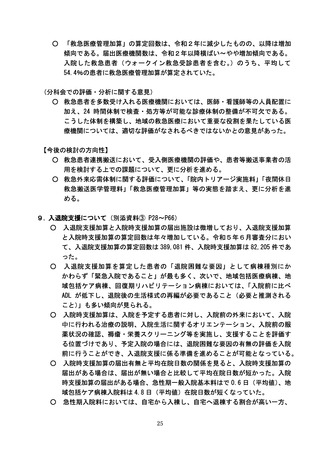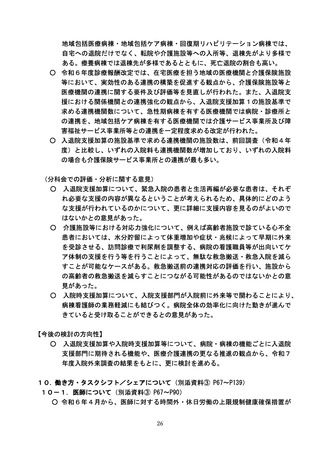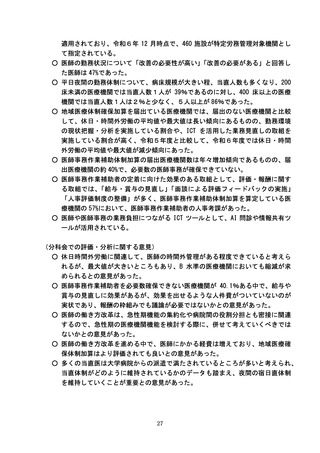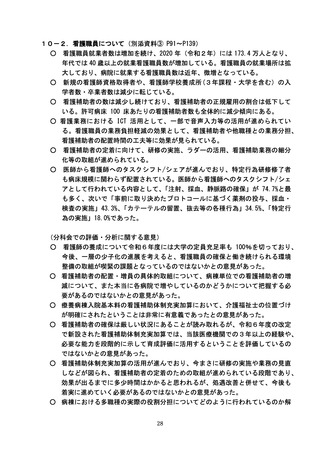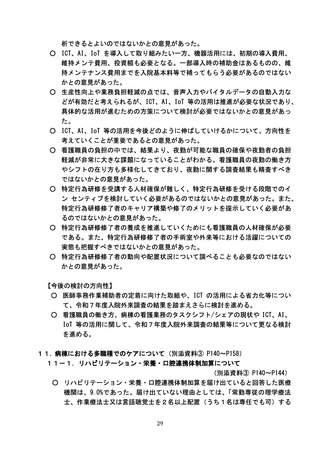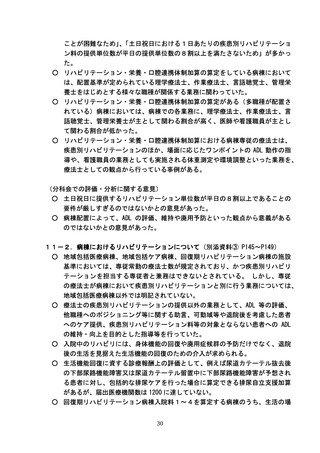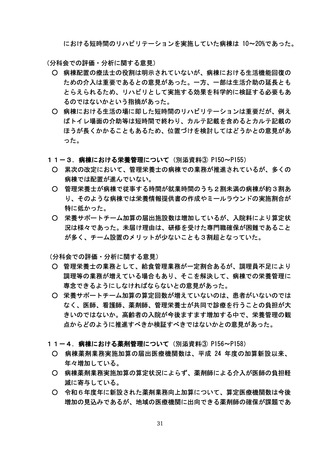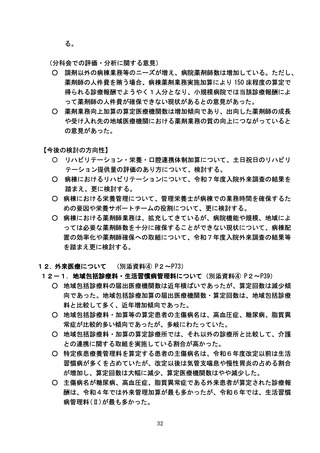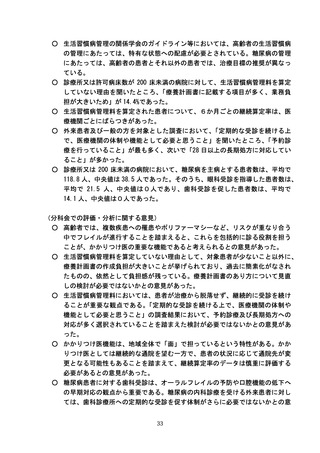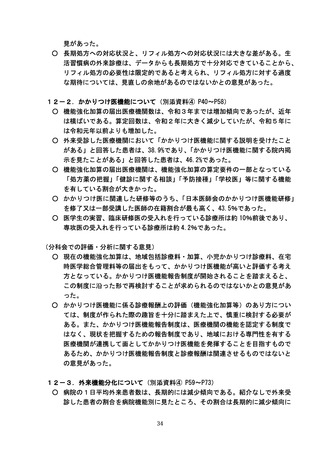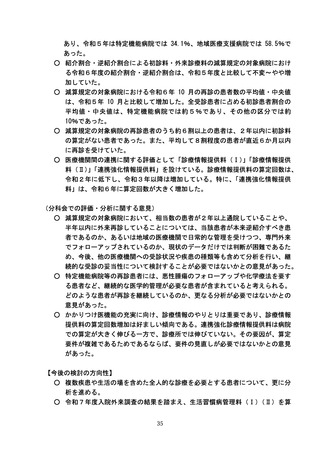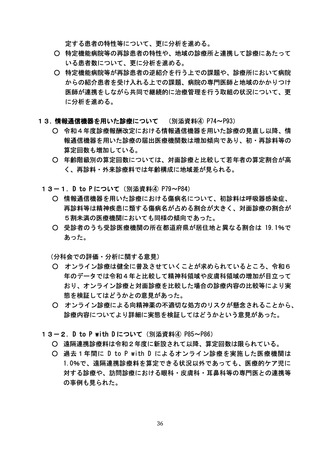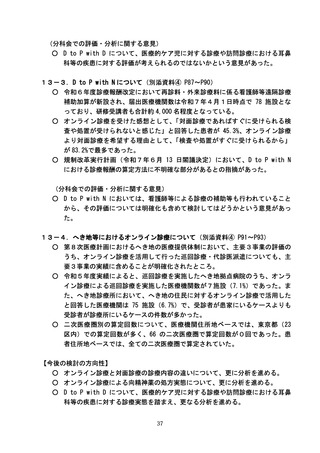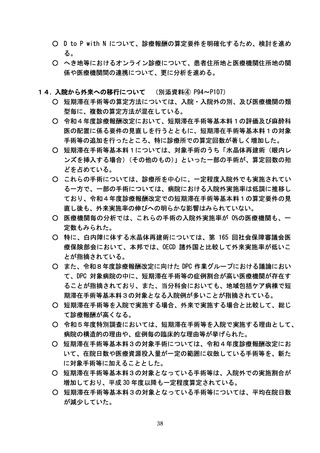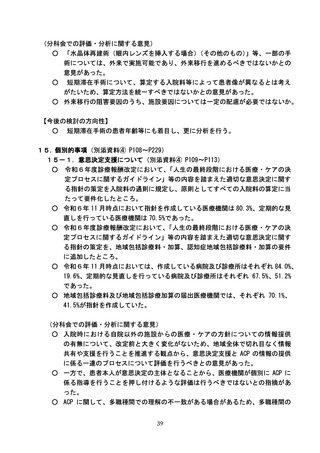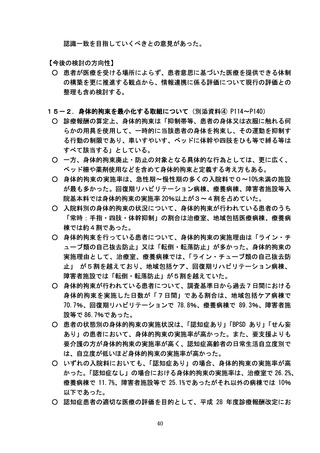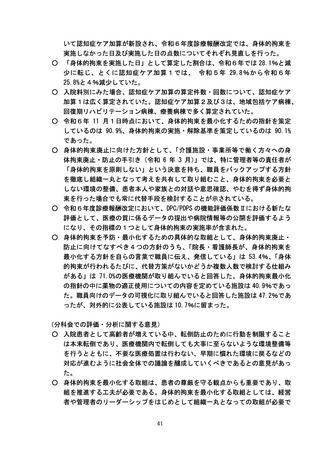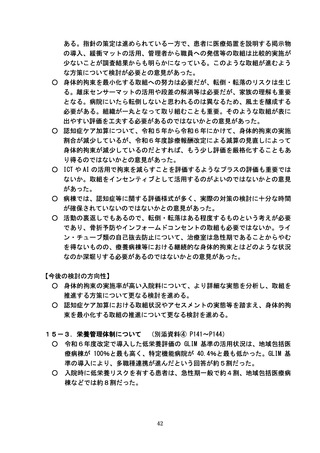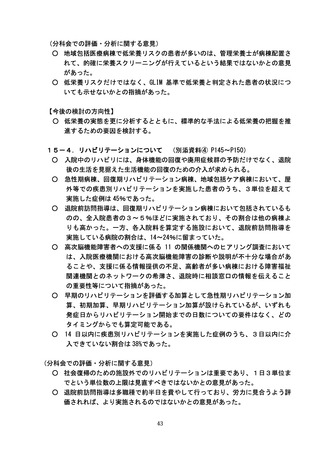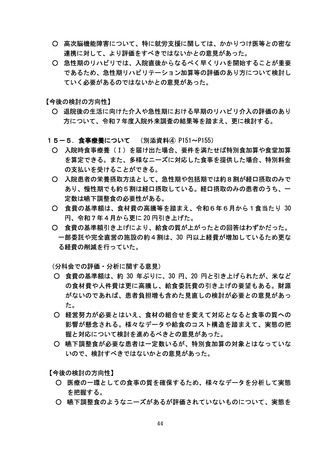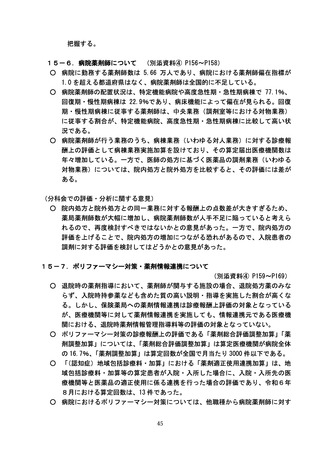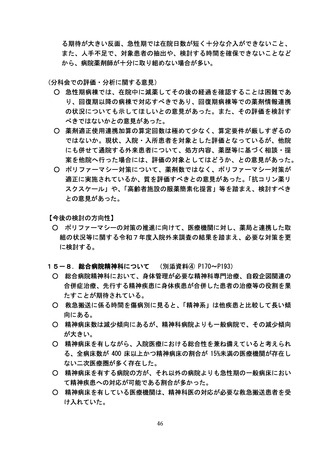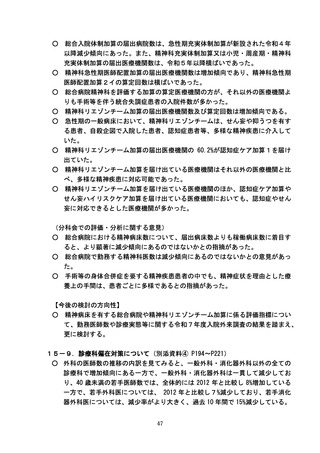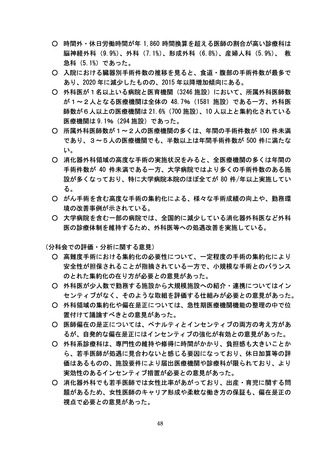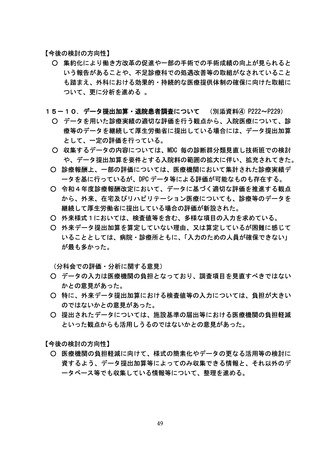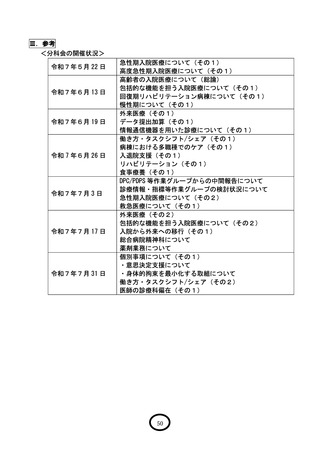よむ、つかう、まなぶ。
総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「高齢者」が増加している。
○ 令和5年中の救急自動車による現場到着所要時間は、全国平均で約 10.0 分で
あった。また、救急自動車による病院収容所要時間は、全国平均で約 45.6 分
であった。新型コロナウイルス感染症の発生前の令和元年と比べ、現場到着所
要時間は約 1.3 分、病院収容所要時間は約 6.1 分それぞれ延伸している。
8-1.救急搬送に関する評価について(別添資料③ P6~P15)
○ 救急患者連携搬送料を届け出ていない理由としては、「救急用の自動車又は救
急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件未満であるた
め」「搬送に同乗するスタッフが確保できないため」「自院又は連携先医療機関
が緊急自動車を保有していないため」等が多かった。
○ 令和6年 10 月1か月に「救急患者連携搬送料」を算定した患者は、ほとんど
の医療機関において少数であった。
○ 第二次救急医療機関の一部には、入院した救急患者の 25%以上が転院搬送で
受け入れた患者である医療機関があった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 救急患者連携搬送料は搬送元医療機関で算定するものである一方、受入側医療
機関の評価がない。救急患者連携搬送は受入側医療機関の協力を前提とした制
度であることから、受入側にも一定の評価を設けることが必要ではないかとの
意見があった。
○ 地域包括ケア病棟において「救急患者連携搬送料」を算定した患者を受け入れ
た場合について、在宅患者支援病床初期支援加算の対象としたことには意義が
ある。救急連携搬送における受入側医療機関への評価をさらに充実させること
で、医療機関間の機能分担や連携の促進につながるのではないかとの意見があ
った。
○ 救急患者連携搬送にあたっては、病院救急車だけでなく、患者等搬送事業者を
活用することについても、今後検討の余地があるのではないかとの意見があっ
た。
8-2.救急外来応需体制に関する評価について(別添資料③ P16~P27)
○ 救急外来医療に対する評価として「院内トリアージ実施料」「夜間休日救急搬
送医学管理料」がある。「院内トリアージ実施料」の算定医療機関数は、やや
増加傾向である。算定回数は、新型コロナウイルス感染症流行後に大幅に増加
したが、令和6年には以前の水準まで減少している。「夜間休日救急搬送医学
管理料」の算定回数は、令和2年以降増加傾向である。
○ 救急車等の救急受入患者数が少ない医療機関でも、相当数のウォークイン救急
患者を受け入れている医療機関が多数存在する。
24
○ 令和5年中の救急自動車による現場到着所要時間は、全国平均で約 10.0 分で
あった。また、救急自動車による病院収容所要時間は、全国平均で約 45.6 分
であった。新型コロナウイルス感染症の発生前の令和元年と比べ、現場到着所
要時間は約 1.3 分、病院収容所要時間は約 6.1 分それぞれ延伸している。
8-1.救急搬送に関する評価について(別添資料③ P6~P15)
○ 救急患者連携搬送料を届け出ていない理由としては、「救急用の自動車又は救
急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件未満であるた
め」「搬送に同乗するスタッフが確保できないため」「自院又は連携先医療機関
が緊急自動車を保有していないため」等が多かった。
○ 令和6年 10 月1か月に「救急患者連携搬送料」を算定した患者は、ほとんど
の医療機関において少数であった。
○ 第二次救急医療機関の一部には、入院した救急患者の 25%以上が転院搬送で
受け入れた患者である医療機関があった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 救急患者連携搬送料は搬送元医療機関で算定するものである一方、受入側医療
機関の評価がない。救急患者連携搬送は受入側医療機関の協力を前提とした制
度であることから、受入側にも一定の評価を設けることが必要ではないかとの
意見があった。
○ 地域包括ケア病棟において「救急患者連携搬送料」を算定した患者を受け入れ
た場合について、在宅患者支援病床初期支援加算の対象としたことには意義が
ある。救急連携搬送における受入側医療機関への評価をさらに充実させること
で、医療機関間の機能分担や連携の促進につながるのではないかとの意見があ
った。
○ 救急患者連携搬送にあたっては、病院救急車だけでなく、患者等搬送事業者を
活用することについても、今後検討の余地があるのではないかとの意見があっ
た。
8-2.救急外来応需体制に関する評価について(別添資料③ P16~P27)
○ 救急外来医療に対する評価として「院内トリアージ実施料」「夜間休日救急搬
送医学管理料」がある。「院内トリアージ実施料」の算定医療機関数は、やや
増加傾向である。算定回数は、新型コロナウイルス感染症流行後に大幅に増加
したが、令和6年には以前の水準まで減少している。「夜間休日救急搬送医学
管理料」の算定回数は、令和2年以降増加傾向である。
○ 救急車等の救急受入患者数が少ない医療機関でも、相当数のウォークイン救急
患者を受け入れている医療機関が多数存在する。
24