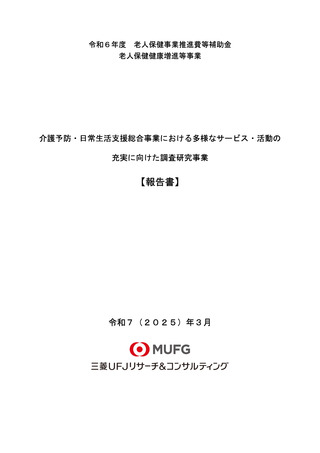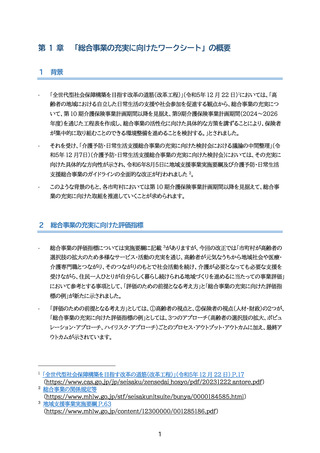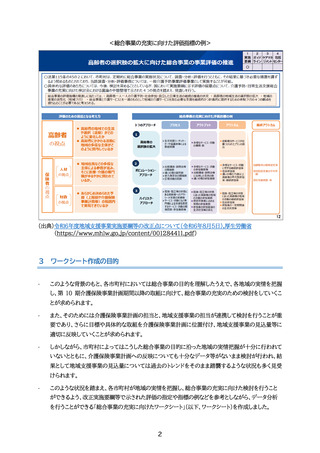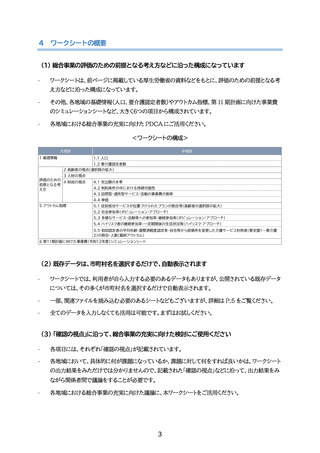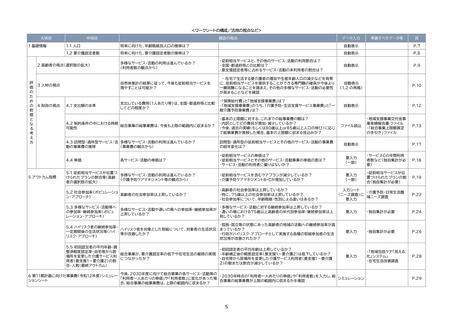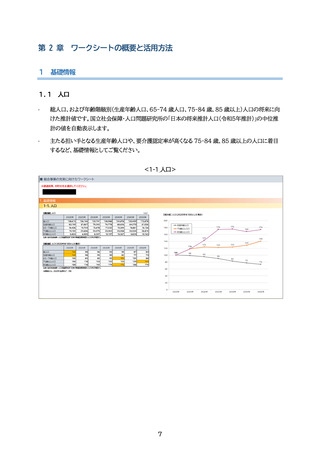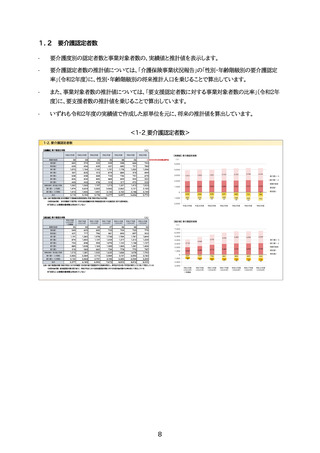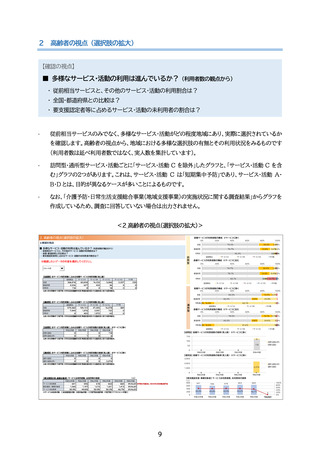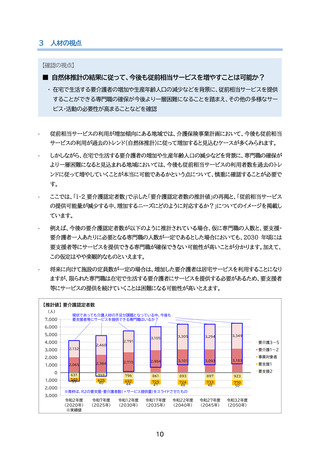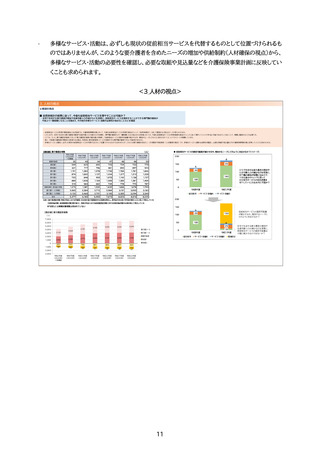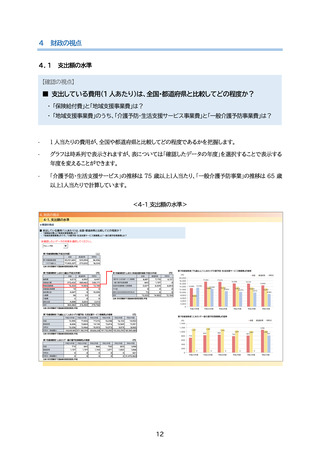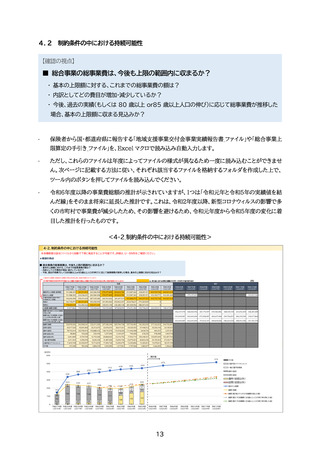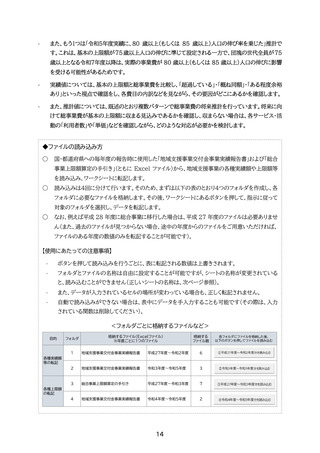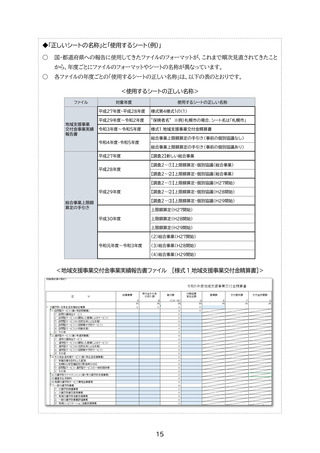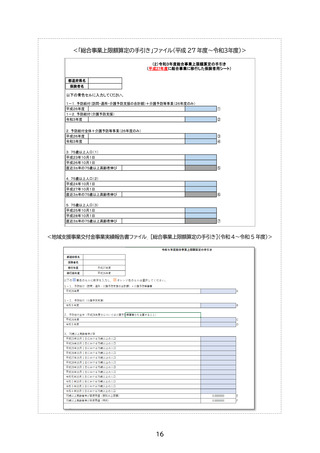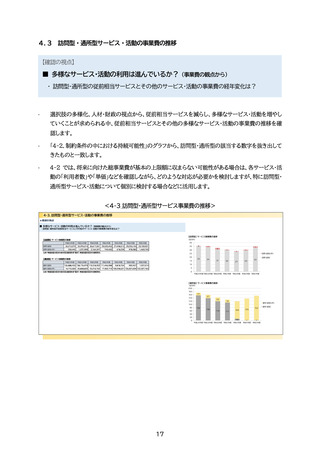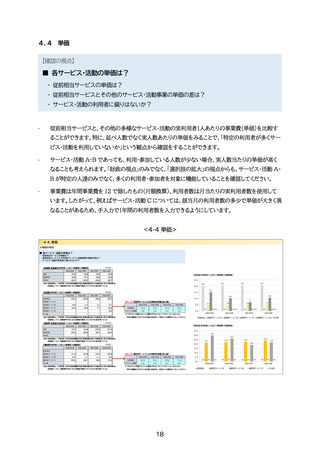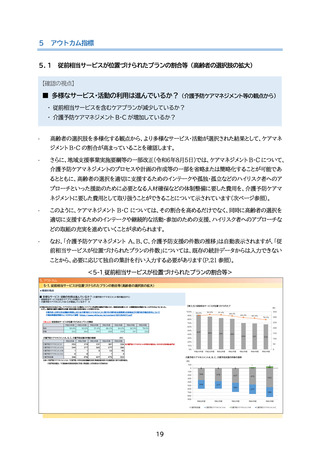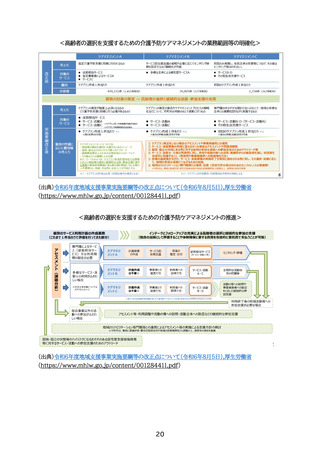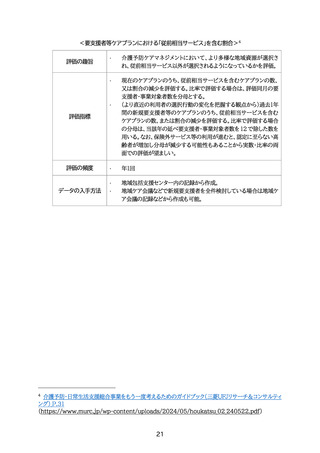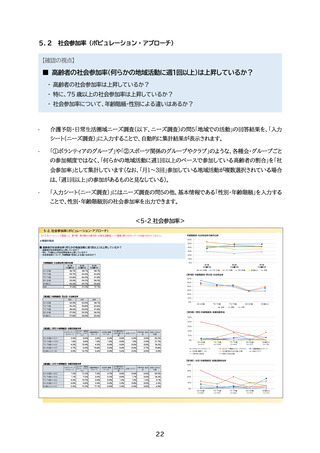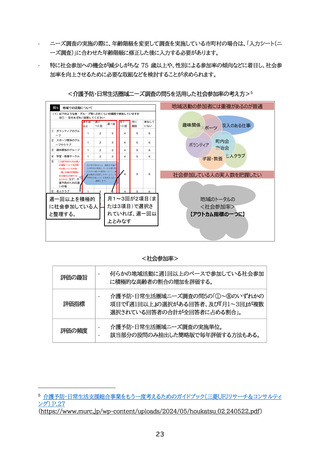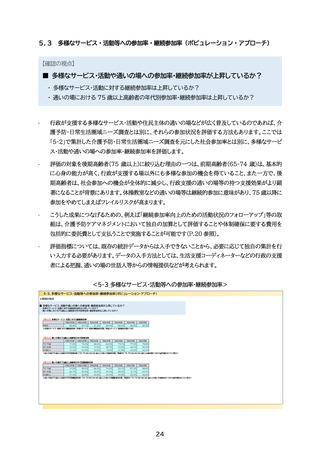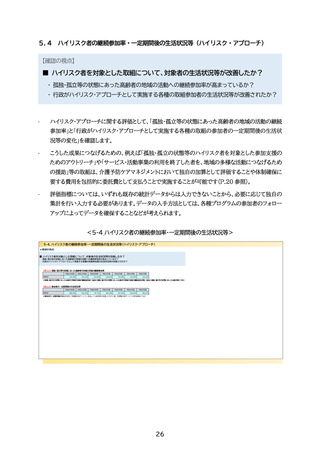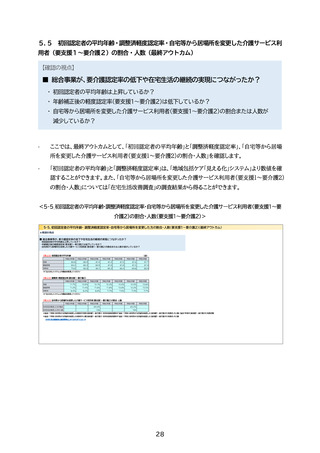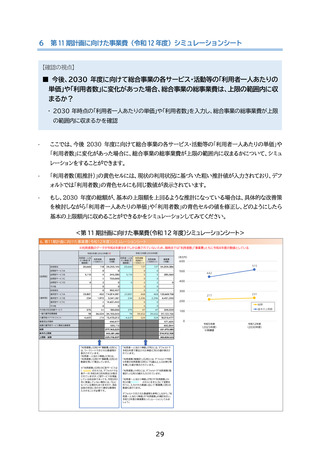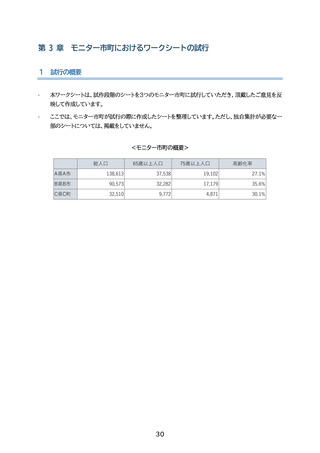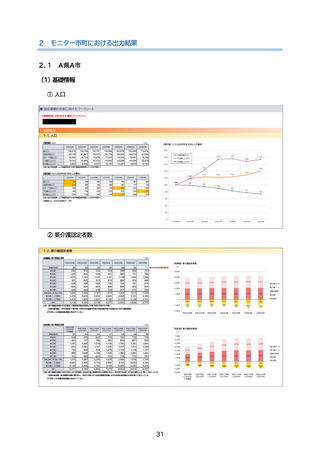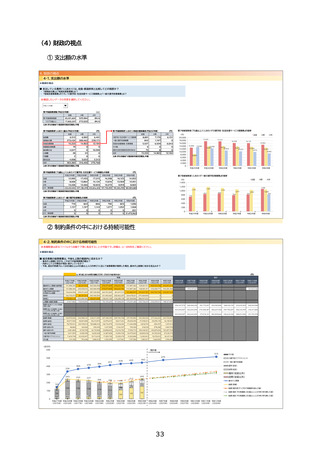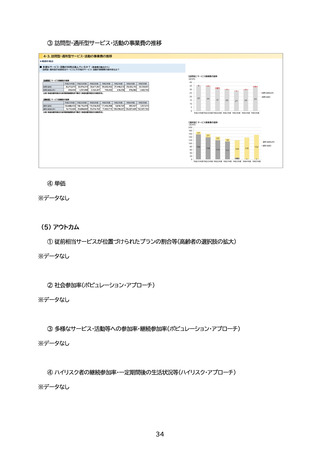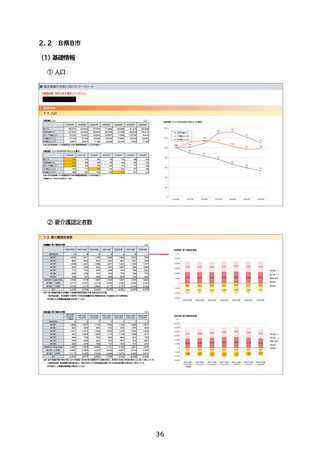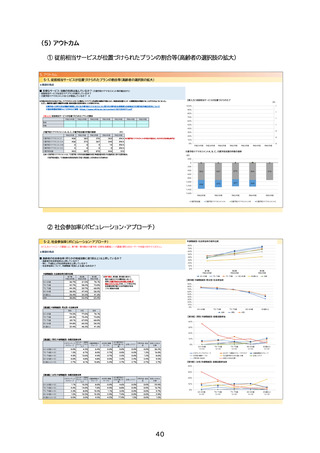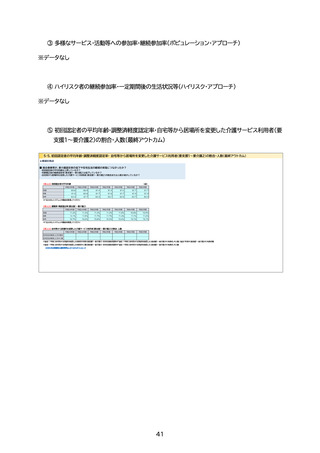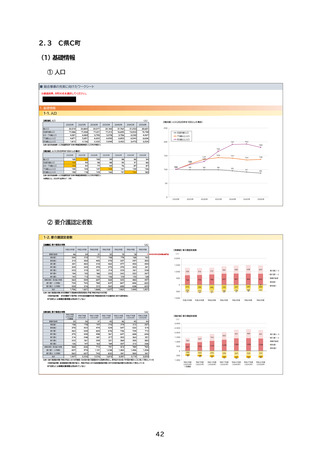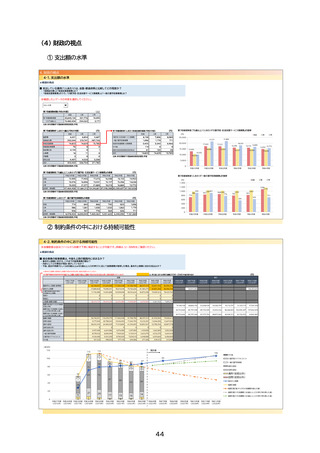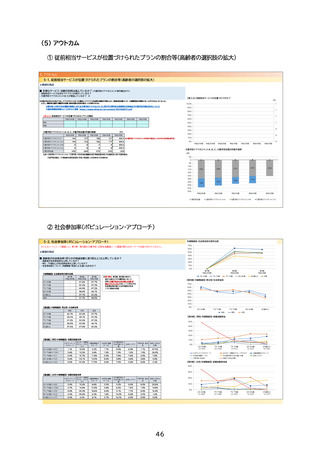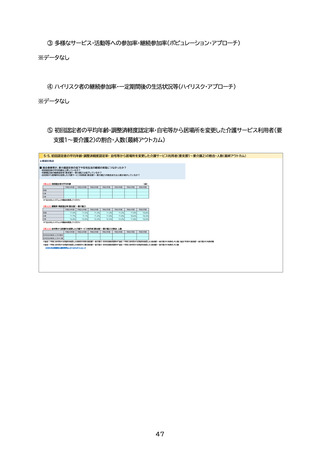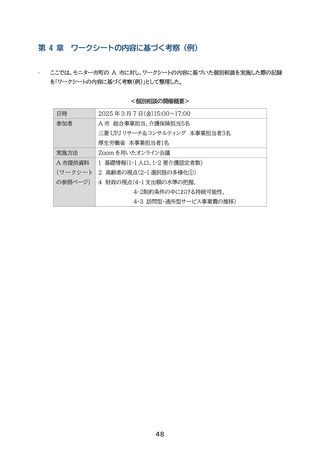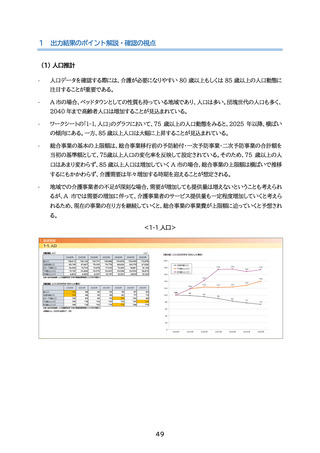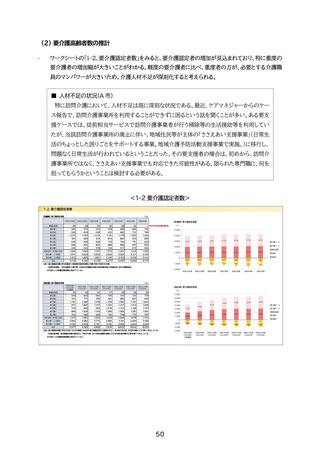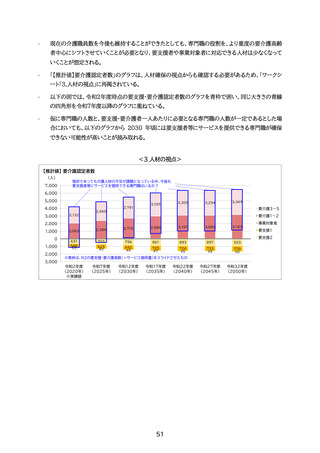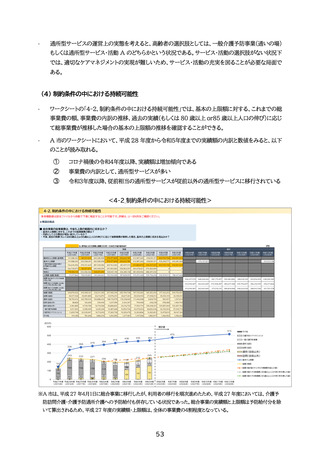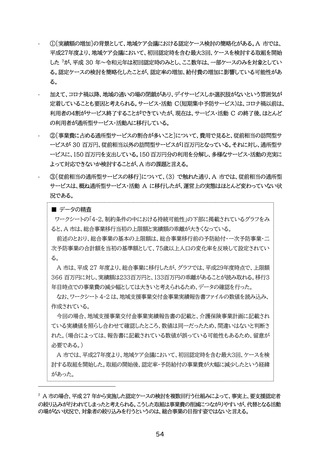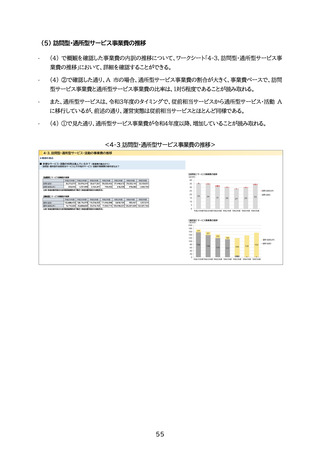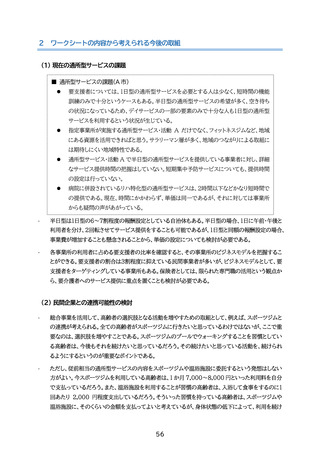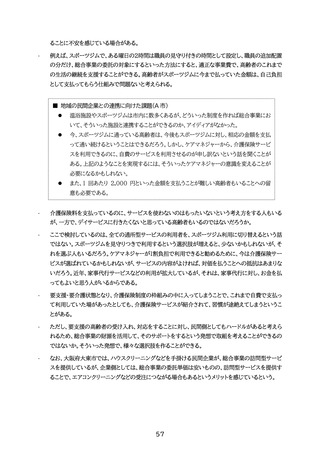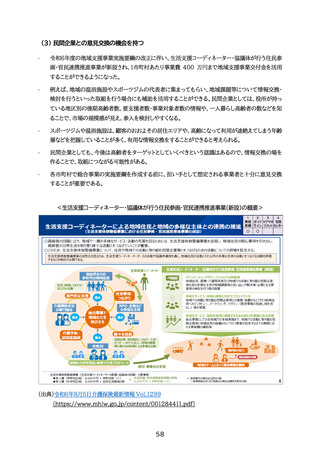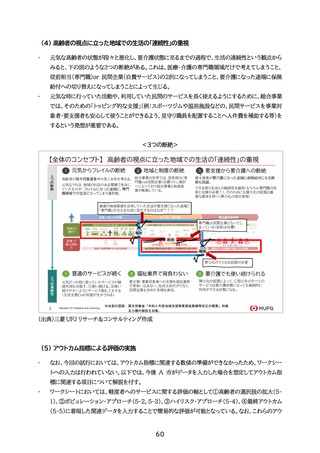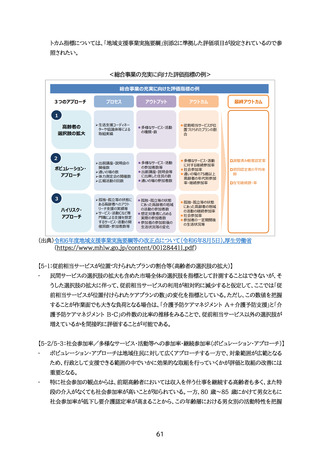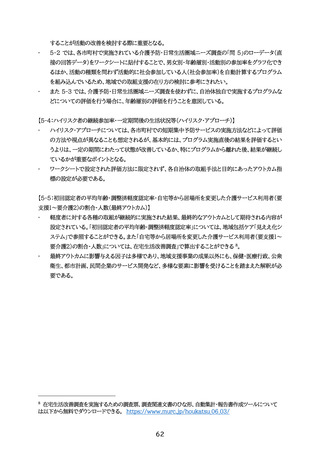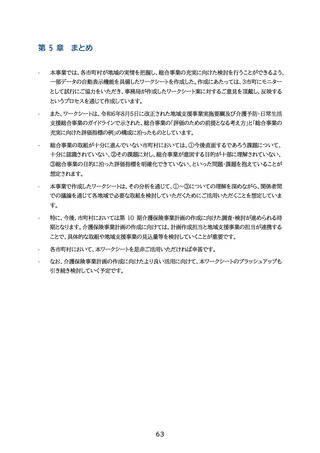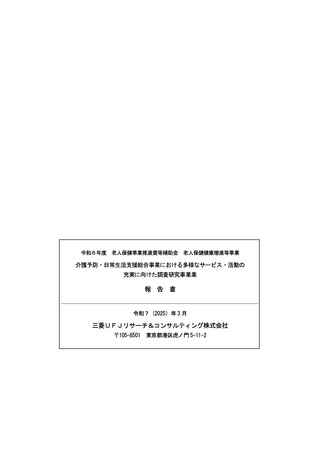よむ、つかう、まなぶ。
総合事業の充実に向けたワークシート(2025年7月10日更新) (60 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 総合事業の充実に向けたワークシート(7/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2 ワークシートの内容から考えられる今後の取組
(1) 現在の通所型サービスの課題
■ 通所型サービスの課題(A 市)
要支援者については、1日型の通所型サービスを必要とする人は少なく、短時間の機能
訓練のみで十分というケースもある。半日型の通所型サービスの希望が多く、空き待ち
の状況になっているため、デイサービスの一部の要素のみで十分な人も1日型の通所型
サービスを利用するという状況が生じている。
指定事業所が実施する通所型サービス・活動 A だけでなく、フィットネスジムなど、地域
にある資源を活用できればと思う。サラリーマン層が多く、地域のつながりによる取組に
は期待しにくい地域特性である。
通所型サービス・活動 A で半日型の通所型サービスを提供している事業者に対し、詳細
なサービス提供時間の把握はしていない。短期集中予防サービスについても、提供時間
の設定は行っていない。
病院に併設されているリハ特化型の通所型サービスは、2時間以下などかなり短時間で
の提供である。現在、時間にかかわらず、単価は同一であるが、それに対しては事業所
からも疑問の声があがっている。
·
半日型は1日型の6~7割程度の報酬設定としている自治体もある。半日型の場合、1日に午前・午後と
利用者を分け、2回転させてサービス提供をすることも可能であるが、1日型と同額の報酬設定の場合、
事業費が増加することも懸念されることから、単価の設定についても検討が必要である。
·
各事業所の利用者に占める要支援者の比率を確認すると、その事業所のビジネスモデルを把握するこ
とができる。要支援者の割合は3割程度に抑えている民間事業者が多いが、ビジネスモデルとして、要
支援者をターゲティングしている事業所もある。保険者としては、限られた専門職の活用という観点か
ら、要介護者へのサービス提供に重点を置くことも検討が必要である。
(2) 民間企業との連携可能性の検討
·
総合事業を活用して、高齢者の選択肢となる活動を増やすための取組として、例えば、スポーツジムと
の連携が考えられる。全ての高齢者がスポーツジムに行きたいと思っているわけではないが、ここで重
要なのは、選択肢を増やすことである。スポーツジムのプールでウォーキングすることを習慣としてい
る高齢者は、今後もそれを続けたいと思っているだろう。その続けたいと思っている活動を、続けられ
るようにするというのが重要なポイントである。
·
ただし、従前相当の通所型サービスの内容をスポーツジムや温浴施設に委託するという発想はしない
方がよい。今スポーツジムを利用している高齢者は、1 か月 7,000~8,000 円といった利用料を自分
で支払っているだろう。また、温浴施設を利用することが習慣の高齢者は、入浴して食事をするのに1
回あたり 2,000 円程度支出しているだろう。そういった習慣を持っている高齢者は、スポーツジムや
温浴施設に、そのくらいの金額を支払ってよいと考えているが、身体状態の低下によって、利用を続け
56
(1) 現在の通所型サービスの課題
■ 通所型サービスの課題(A 市)
要支援者については、1日型の通所型サービスを必要とする人は少なく、短時間の機能
訓練のみで十分というケースもある。半日型の通所型サービスの希望が多く、空き待ち
の状況になっているため、デイサービスの一部の要素のみで十分な人も1日型の通所型
サービスを利用するという状況が生じている。
指定事業所が実施する通所型サービス・活動 A だけでなく、フィットネスジムなど、地域
にある資源を活用できればと思う。サラリーマン層が多く、地域のつながりによる取組に
は期待しにくい地域特性である。
通所型サービス・活動 A で半日型の通所型サービスを提供している事業者に対し、詳細
なサービス提供時間の把握はしていない。短期集中予防サービスについても、提供時間
の設定は行っていない。
病院に併設されているリハ特化型の通所型サービスは、2時間以下などかなり短時間で
の提供である。現在、時間にかかわらず、単価は同一であるが、それに対しては事業所
からも疑問の声があがっている。
·
半日型は1日型の6~7割程度の報酬設定としている自治体もある。半日型の場合、1日に午前・午後と
利用者を分け、2回転させてサービス提供をすることも可能であるが、1日型と同額の報酬設定の場合、
事業費が増加することも懸念されることから、単価の設定についても検討が必要である。
·
各事業所の利用者に占める要支援者の比率を確認すると、その事業所のビジネスモデルを把握するこ
とができる。要支援者の割合は3割程度に抑えている民間事業者が多いが、ビジネスモデルとして、要
支援者をターゲティングしている事業所もある。保険者としては、限られた専門職の活用という観点か
ら、要介護者へのサービス提供に重点を置くことも検討が必要である。
(2) 民間企業との連携可能性の検討
·
総合事業を活用して、高齢者の選択肢となる活動を増やすための取組として、例えば、スポーツジムと
の連携が考えられる。全ての高齢者がスポーツジムに行きたいと思っているわけではないが、ここで重
要なのは、選択肢を増やすことである。スポーツジムのプールでウォーキングすることを習慣としてい
る高齢者は、今後もそれを続けたいと思っているだろう。その続けたいと思っている活動を、続けられ
るようにするというのが重要なポイントである。
·
ただし、従前相当の通所型サービスの内容をスポーツジムや温浴施設に委託するという発想はしない
方がよい。今スポーツジムを利用している高齢者は、1 か月 7,000~8,000 円といった利用料を自分
で支払っているだろう。また、温浴施設を利用することが習慣の高齢者は、入浴して食事をするのに1
回あたり 2,000 円程度支出しているだろう。そういった習慣を持っている高齢者は、スポーツジムや
温浴施設に、そのくらいの金額を支払ってよいと考えているが、身体状態の低下によって、利用を続け
56