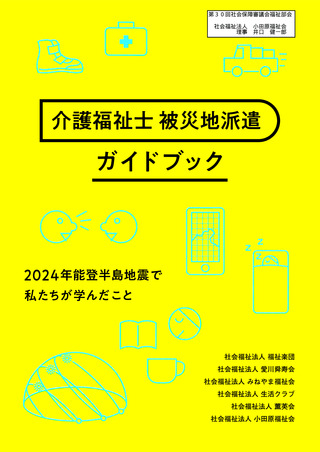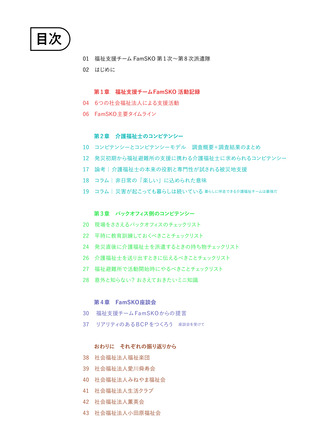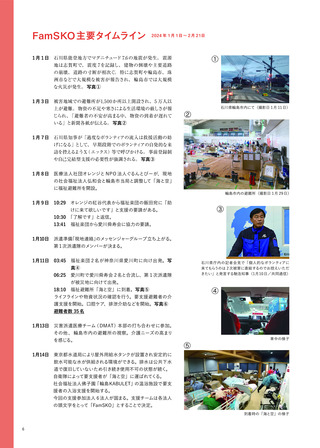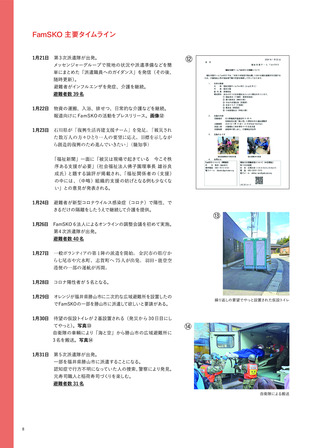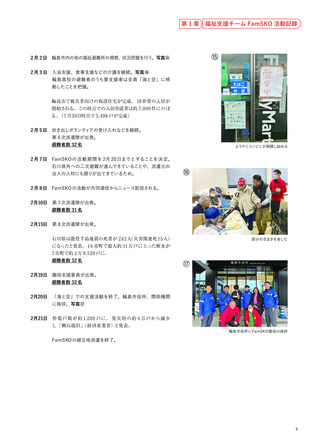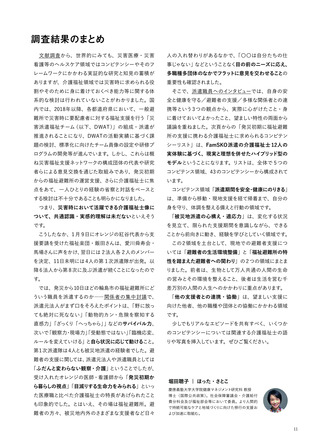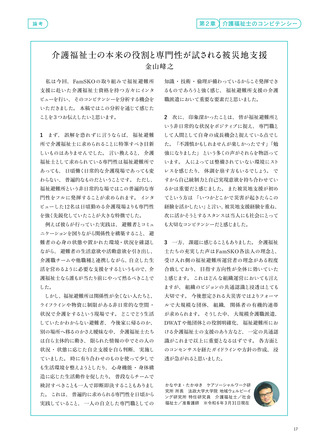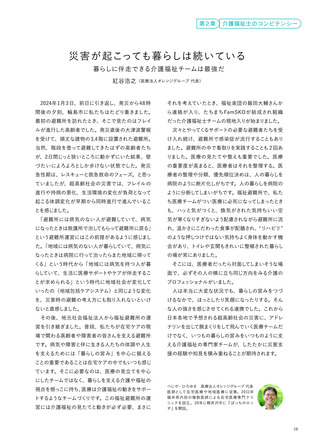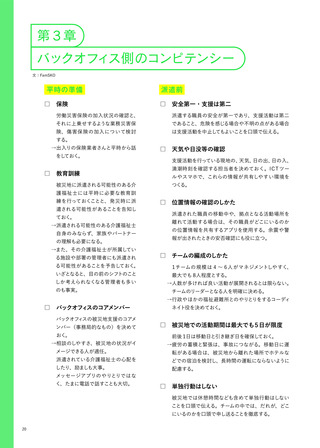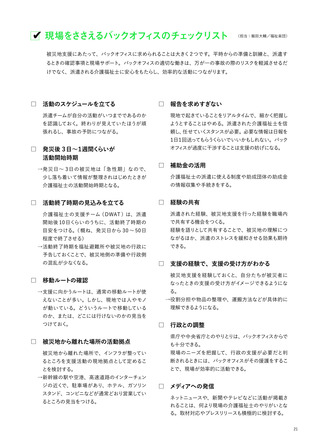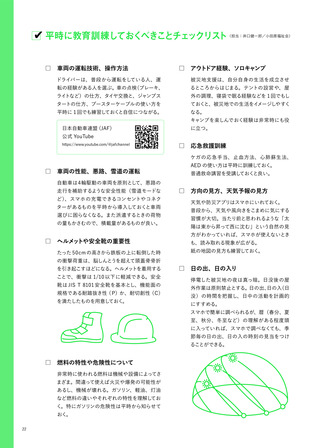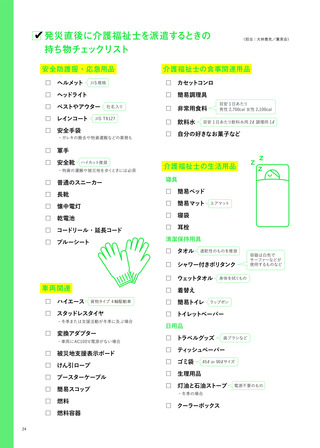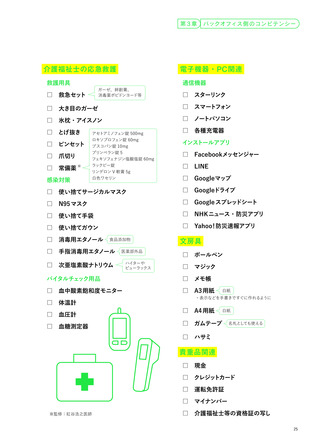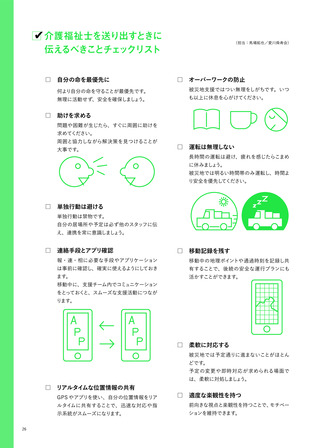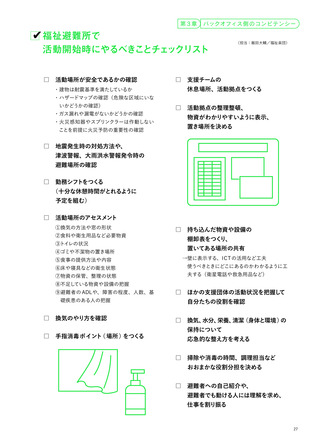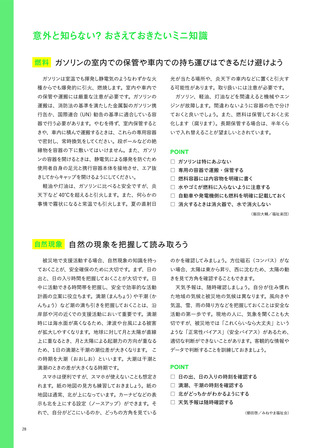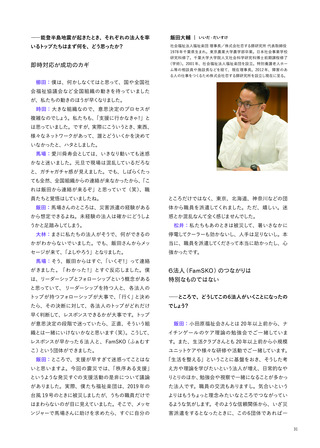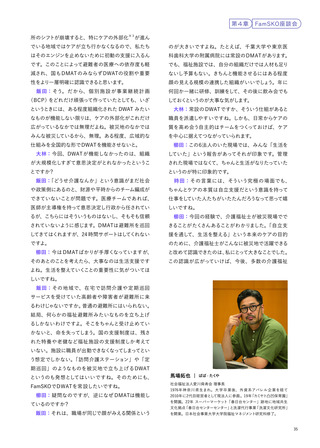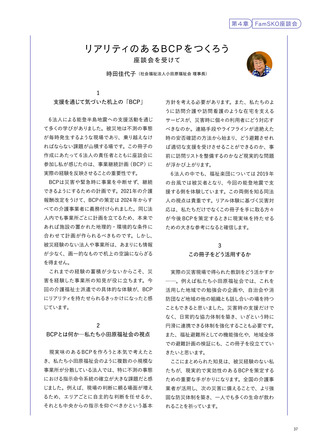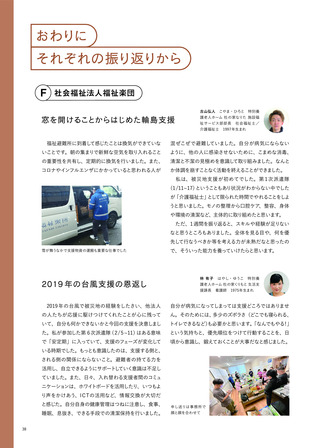よむ、つかう、まなぶ。
井口委員提出資料 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
おわりに それぞれの振り返りから
S
社会福祉法人生活クラブ
支援の思いは今も続いている
能登支援の話があったとき「行きたい」とすぐに思
牛坂さよ子 うしざか・さよこ 重
心通所さくら
まれ
看護師
1954年生
だったと思います。
いました。看護師として50年以上、様々な職場で多職
知り合った独居の被災者が気になり、今も月に1回
種協働の経験があること、20数年登山を続けており体
は輪島に行っています。支援の継続はまだまだ必要だ
力にそれなりに自信があり、また登山関係の道具や食
と行くたびに感じます。私も、自分が参加できるボラン
料はそのまま活用できると考えました。
ティアを模索している日々です。
私達が参加したところは高齢者の住居型施設でし
あるもので栄養バランスを考える食事
た。そこでは汚物処理(断水の為、凝固剤を入れた袋
を毎回便座にセットします)
、ポリタンクで室内へ水を
運び入れる作業、救援物資を車で取りに行く、入浴施
設へ送迎して入浴介助…などを繰り返し行ないました。
それと並行して避難者の方に寄り添い、精神面、健
康面、認知状態、ADL などを見守り、必要に応じて
援助します。それを介護福祉士、看護師、P T などが
協同して支援していきます。他の小中学校などの避難
所とは環境、コミュニティーのあり方が違った避難所
平時からの備えが大切
秋山 洋
あきやま・ひろし デイ
サービスセンター流山
級
1974 年生まれ
ヘルパー 2
日ごろから体調管理に気を配っていましたが、支援
とコーディネーターを中心に連携をとり、次の新しい生
に入ることになり更に徹底して心身共に万全な状態にし
活の為に活動していました。介護の専門職として技術
ました。それは、人の力が必要だから、人や場所を守
や知識を使い、介護度や体調に関わらず、全ての被災
る為に。
された方のケアに入りました。
現地に着いて見たものは、生活するには極めて困難
ケアをしながら学んだ事は、電気と水の確保。避難
な場所と、そこで復興の為に頑張っている人々。医師
所のゴミや物資や備品の環境整備。ストレスを増やさ
ない空間作り。 しっかりした口腔ケア。 レクリエーショ
ン。会議に参加し行政と連携をとる。今いる全員と連
携をとらないと復興できない事。そして自身から考え
行動する事など。他にも多くの学びがありました。
活動を終えて思うことは、やはり平時から私生活も
仕事も体調管理をし、心身ともに万全でいること。介
護技能も知識も雑学も自身の能力を十分発揮できるよ
う備えること。各地で起こった災害から復興までの歴史
を知っておくこと。私ももっと備えていればもっと多くの
自衛隊が要介護者を移送する
活動ができたと心から思います。
41
S
社会福祉法人生活クラブ
支援の思いは今も続いている
能登支援の話があったとき「行きたい」とすぐに思
牛坂さよ子 うしざか・さよこ 重
心通所さくら
まれ
看護師
1954年生
だったと思います。
いました。看護師として50年以上、様々な職場で多職
知り合った独居の被災者が気になり、今も月に1回
種協働の経験があること、20数年登山を続けており体
は輪島に行っています。支援の継続はまだまだ必要だ
力にそれなりに自信があり、また登山関係の道具や食
と行くたびに感じます。私も、自分が参加できるボラン
料はそのまま活用できると考えました。
ティアを模索している日々です。
私達が参加したところは高齢者の住居型施設でし
あるもので栄養バランスを考える食事
た。そこでは汚物処理(断水の為、凝固剤を入れた袋
を毎回便座にセットします)
、ポリタンクで室内へ水を
運び入れる作業、救援物資を車で取りに行く、入浴施
設へ送迎して入浴介助…などを繰り返し行ないました。
それと並行して避難者の方に寄り添い、精神面、健
康面、認知状態、ADL などを見守り、必要に応じて
援助します。それを介護福祉士、看護師、P T などが
協同して支援していきます。他の小中学校などの避難
所とは環境、コミュニティーのあり方が違った避難所
平時からの備えが大切
秋山 洋
あきやま・ひろし デイ
サービスセンター流山
級
1974 年生まれ
ヘルパー 2
日ごろから体調管理に気を配っていましたが、支援
とコーディネーターを中心に連携をとり、次の新しい生
に入ることになり更に徹底して心身共に万全な状態にし
活の為に活動していました。介護の専門職として技術
ました。それは、人の力が必要だから、人や場所を守
や知識を使い、介護度や体調に関わらず、全ての被災
る為に。
された方のケアに入りました。
現地に着いて見たものは、生活するには極めて困難
ケアをしながら学んだ事は、電気と水の確保。避難
な場所と、そこで復興の為に頑張っている人々。医師
所のゴミや物資や備品の環境整備。ストレスを増やさ
ない空間作り。 しっかりした口腔ケア。 レクリエーショ
ン。会議に参加し行政と連携をとる。今いる全員と連
携をとらないと復興できない事。そして自身から考え
行動する事など。他にも多くの学びがありました。
活動を終えて思うことは、やはり平時から私生活も
仕事も体調管理をし、心身ともに万全でいること。介
護技能も知識も雑学も自身の能力を十分発揮できるよ
う備えること。各地で起こった災害から復興までの歴史
を知っておくこと。私ももっと備えていればもっと多くの
自衛隊が要介護者を移送する
活動ができたと心から思います。
41