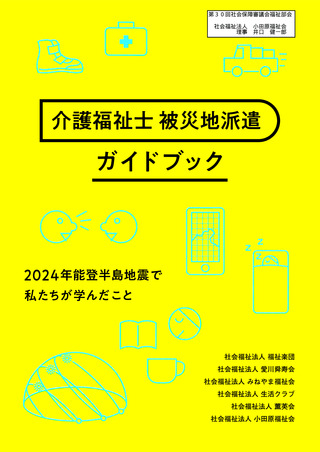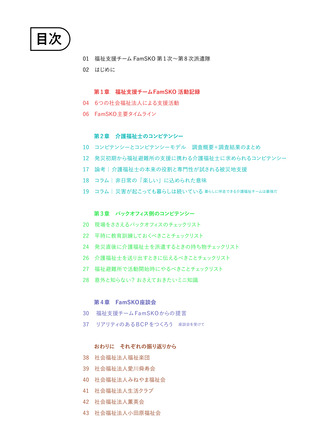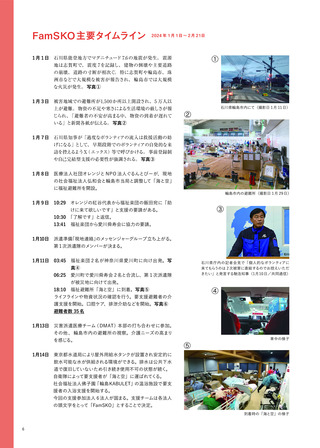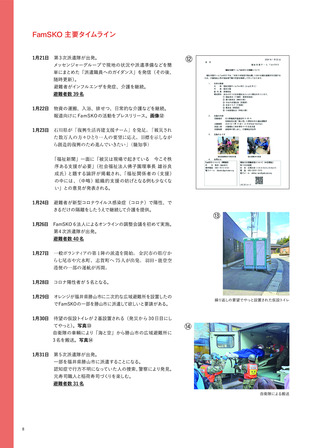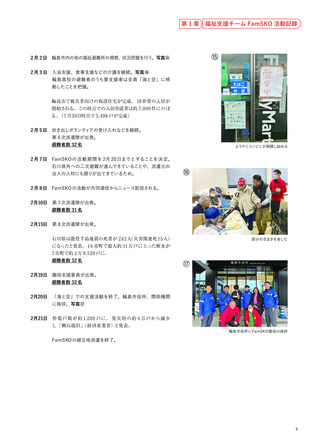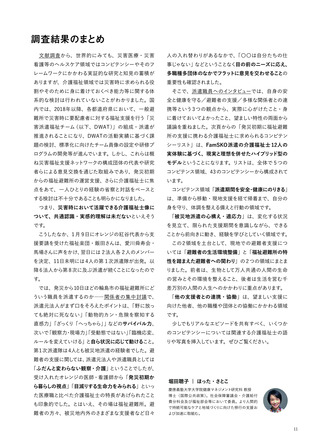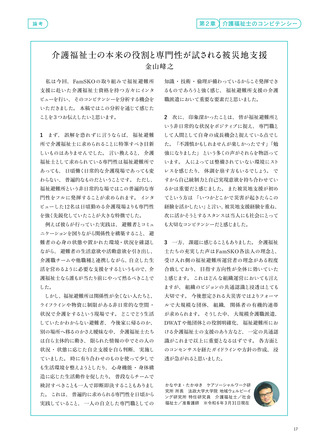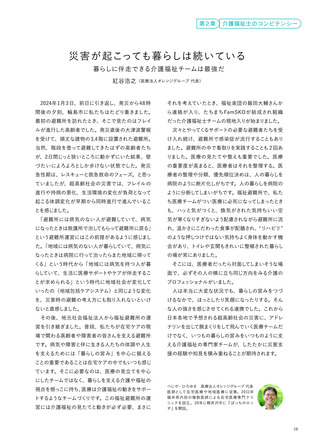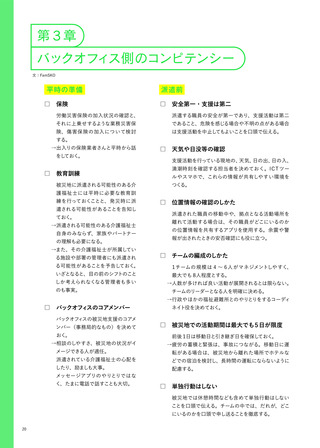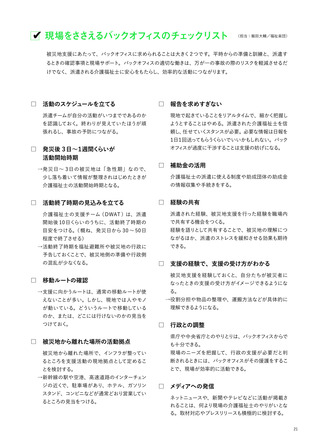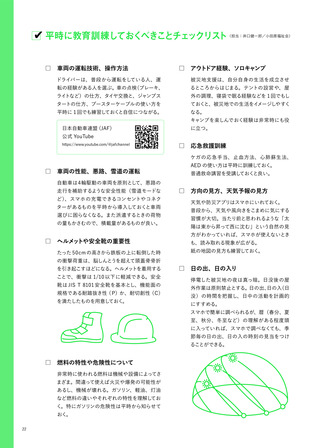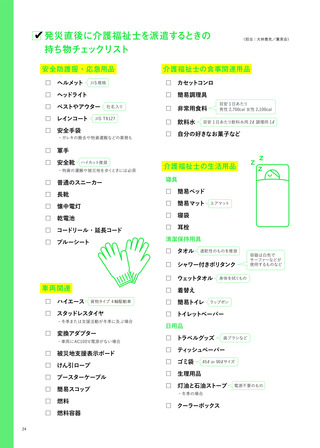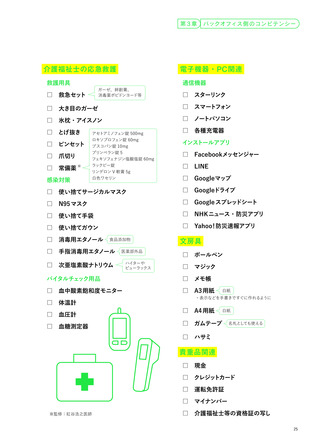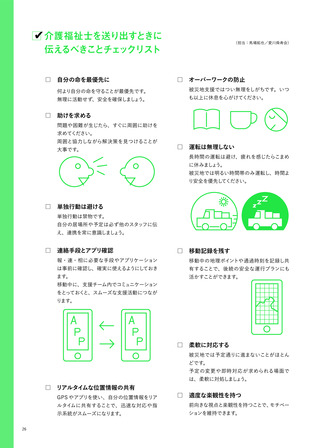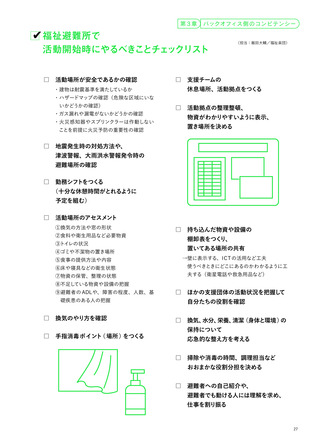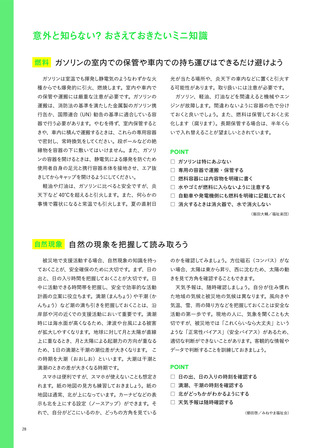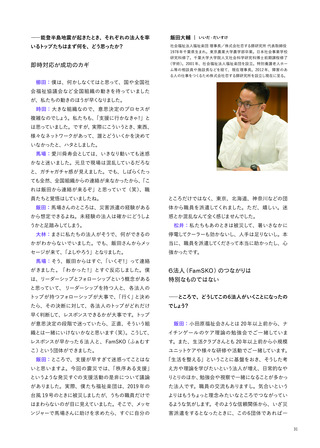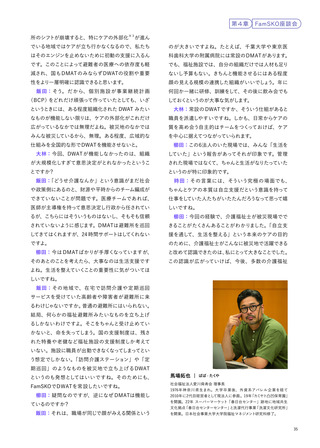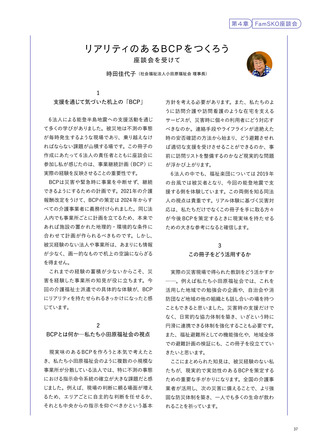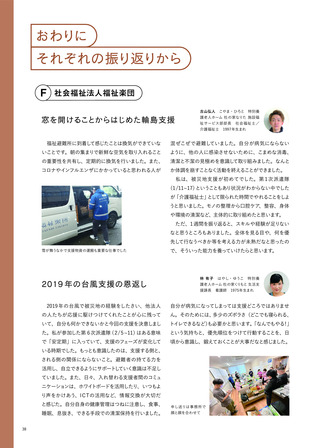よむ、つかう、まなぶ。
井口委員提出資料 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4章
FamSKO座談会
所のシフトが崩壊すると、特にケアの外部化※ 3 が進ん
でいる地域ではケアが立ち行かなくなるので、私たち
のが大きいですよね。たとえば、千葉大学や東京医
はそのエンジンを止めないために初動の支援に入るん
科歯科大学の附属病院には常設のDMATがあります。
です。このことによって避難者の医療への依存度も軽
でも、福祉施設では、自分の組織だけでは人材も足り
減され、国もDMATのみならずDWATの役割や重要
ないし予算もない。きちんと機能させるにはある程度
性をより一層明確に認識できると思います。
顔の見える規模の連携した組織がいいでしょう。年に
飯田:そう。だから、個別施設が事業継続計画
(BCP)をどれだけ頑張って作っていたとしても、いざ
何回か一緒に研修、訓練をして、その後に飲み会でも
しておくというのが大事な気がします。
というときには、ある程度組織化された DWAT みたい
大林:常設の DWATですか、そういう仕組があると
なものが機能しない限りは、ケアの外部化がこれだけ
職員を派遣しやすいですね。しかも、日常からケアの
広がっているなかでは無理だよね。被災地のなかでは
質を高め会う自主的はチームをつくっておけば、ケア
みんな被災しているから、無理。ある程度、広域的な
を中心に据えてつながっていられます。
仕組みを全国的な形でDWATを機能させないと。
櫛田:この6法人のいた現場では、みんな「生活を
大林:今回、DWATが機能しなかったのは、組織
していた」という報告があってそれが印象です。管理
が大規模化しすぎて意思決定がとれなかったというこ
された現場ではなくて、ちゃんと生活がなりたっていた
とですか?
というのが特に印象的です。
飯田:
「どうせ介護なんか」という意識がまだ社会
時田:その言葉には、そういう究極の場面でも、
や政策側にあるのと、財源や平時からのチーム編成が
ちゃんとケアの本質は自立支援だという意識を持って
できていないことが問題です。医療チームであれば、
仕事をしていた人たちがいたたんだろうなって思って嬉
医師が主導権を持って意思決定し行政から任されてい
しいですね。
るが、こちらにはそういうものはないし、そもそも信頼
櫛田:今回の経験で、介護福祉士が被災現場でで
されていないように感じます。DMATは避難所を巡回
きることがたくさんあることがわかりました。
「自立支
してきてはくれますが、24 時間サポートはしてくれない
援を通して、生活を整える」という本来のケアの目的
ですよ。
のために、介護福祉士がこんなに被災地で活躍できる
櫛田:今は DMAT ばかりが手厚くなっていますが、
と改めて認識できたのは、私にとって大きなことでした。
そのあとのことを考えたら、大事なのは生活支援です
この認識が広がっていけば、今後、多数の介護福祉
よね。生活を整えていくことの重要性に気がついてほ
しいですね。
飯田:その地域で、在宅で訪問介護や定期巡回
サービスを受けていた高齢者や障害者が避難所に来
るわけじゃないですか。普通の避難所にはいられない。
結局、何らかの福祉避難所みたいなものを立ち上げ
るしかないわけですよ。そこをちゃんと受け止めてい
かないと、命を失ってしまう。国の支援制度は、残さ
れた特養や老健など福祉施設の支援制度しか考えて
いない。施設に職員が出勤できなくなってしまってとい
う想定でしかない。
「訪問介護ステーション」や「定
期巡回」のようなものを被災地で立ち上げるDWAT
というのも発想としてはいいですね。そのためにも、
FamSKOでDWATを常設したいですね。
櫛田:疑問なのですが、逆になぜ DMATは機能し
ているのですか?
飯田:それは、職場が同じで顔がみえる関係という
馬場拓也|ばば · たくや
社会福祉法人愛川舜寿会 理事長
1976年神奈川県生まれ。大学卒業後、外資系アパレル 企業を経て
2010年に2代目経営者として現法人に参画 。19年「カミヤト凸凹保育園」
を開園。22年 スーパーマーケット「春日台センター」跡地に地域共生
文化拠点「春日台センターセンター」と洗濯代行事業「洗濯文化研究所」
を開業。日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科修了。
35
FamSKO座談会
所のシフトが崩壊すると、特にケアの外部化※ 3 が進ん
でいる地域ではケアが立ち行かなくなるので、私たち
のが大きいですよね。たとえば、千葉大学や東京医
はそのエンジンを止めないために初動の支援に入るん
科歯科大学の附属病院には常設のDMATがあります。
です。このことによって避難者の医療への依存度も軽
でも、福祉施設では、自分の組織だけでは人材も足り
減され、国もDMATのみならずDWATの役割や重要
ないし予算もない。きちんと機能させるにはある程度
性をより一層明確に認識できると思います。
顔の見える規模の連携した組織がいいでしょう。年に
飯田:そう。だから、個別施設が事業継続計画
(BCP)をどれだけ頑張って作っていたとしても、いざ
何回か一緒に研修、訓練をして、その後に飲み会でも
しておくというのが大事な気がします。
というときには、ある程度組織化された DWAT みたい
大林:常設の DWATですか、そういう仕組があると
なものが機能しない限りは、ケアの外部化がこれだけ
職員を派遣しやすいですね。しかも、日常からケアの
広がっているなかでは無理だよね。被災地のなかでは
質を高め会う自主的はチームをつくっておけば、ケア
みんな被災しているから、無理。ある程度、広域的な
を中心に据えてつながっていられます。
仕組みを全国的な形でDWATを機能させないと。
櫛田:この6法人のいた現場では、みんな「生活を
大林:今回、DWATが機能しなかったのは、組織
していた」という報告があってそれが印象です。管理
が大規模化しすぎて意思決定がとれなかったというこ
された現場ではなくて、ちゃんと生活がなりたっていた
とですか?
というのが特に印象的です。
飯田:
「どうせ介護なんか」という意識がまだ社会
時田:その言葉には、そういう究極の場面でも、
や政策側にあるのと、財源や平時からのチーム編成が
ちゃんとケアの本質は自立支援だという意識を持って
できていないことが問題です。医療チームであれば、
仕事をしていた人たちがいたたんだろうなって思って嬉
医師が主導権を持って意思決定し行政から任されてい
しいですね。
るが、こちらにはそういうものはないし、そもそも信頼
櫛田:今回の経験で、介護福祉士が被災現場でで
されていないように感じます。DMATは避難所を巡回
きることがたくさんあることがわかりました。
「自立支
してきてはくれますが、24 時間サポートはしてくれない
援を通して、生活を整える」という本来のケアの目的
ですよ。
のために、介護福祉士がこんなに被災地で活躍できる
櫛田:今は DMAT ばかりが手厚くなっていますが、
と改めて認識できたのは、私にとって大きなことでした。
そのあとのことを考えたら、大事なのは生活支援です
この認識が広がっていけば、今後、多数の介護福祉
よね。生活を整えていくことの重要性に気がついてほ
しいですね。
飯田:その地域で、在宅で訪問介護や定期巡回
サービスを受けていた高齢者や障害者が避難所に来
るわけじゃないですか。普通の避難所にはいられない。
結局、何らかの福祉避難所みたいなものを立ち上げ
るしかないわけですよ。そこをちゃんと受け止めてい
かないと、命を失ってしまう。国の支援制度は、残さ
れた特養や老健など福祉施設の支援制度しか考えて
いない。施設に職員が出勤できなくなってしまってとい
う想定でしかない。
「訪問介護ステーション」や「定
期巡回」のようなものを被災地で立ち上げるDWAT
というのも発想としてはいいですね。そのためにも、
FamSKOでDWATを常設したいですね。
櫛田:疑問なのですが、逆になぜ DMATは機能し
ているのですか?
飯田:それは、職場が同じで顔がみえる関係という
馬場拓也|ばば · たくや
社会福祉法人愛川舜寿会 理事長
1976年神奈川県生まれ。大学卒業後、外資系アパレル 企業を経て
2010年に2代目経営者として現法人に参画 。19年「カミヤト凸凹保育園」
を開園。22年 スーパーマーケット「春日台センター」跡地に地域共生
文化拠点「春日台センターセンター」と洗濯代行事業「洗濯文化研究所」
を開業。日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科修了。
35