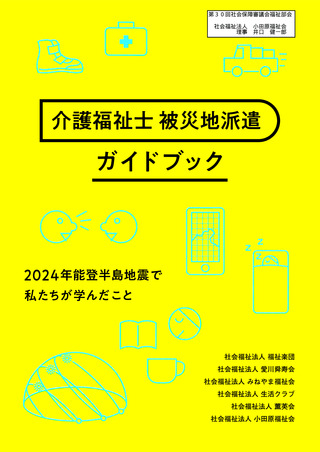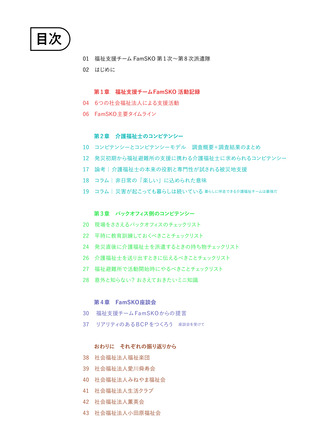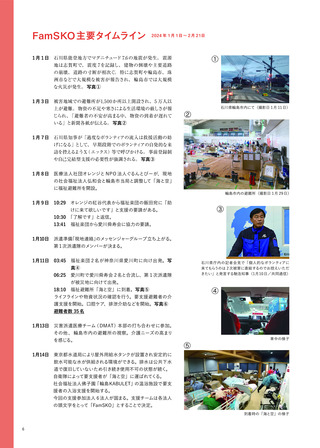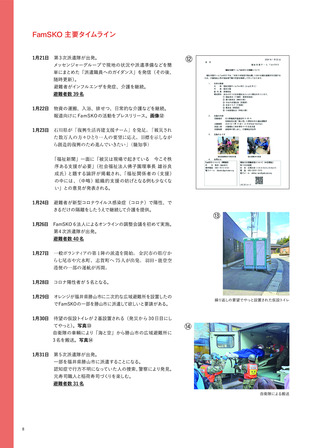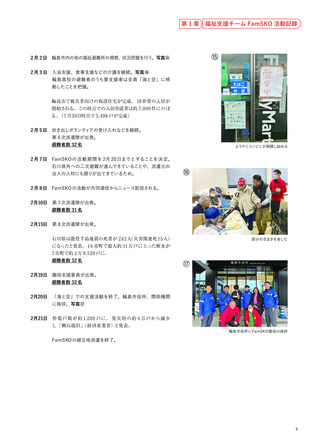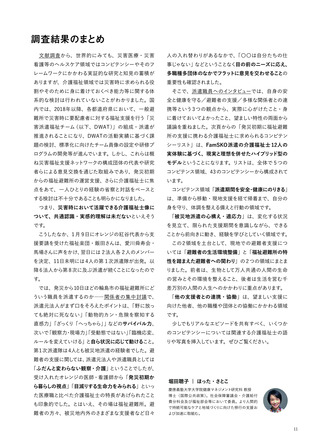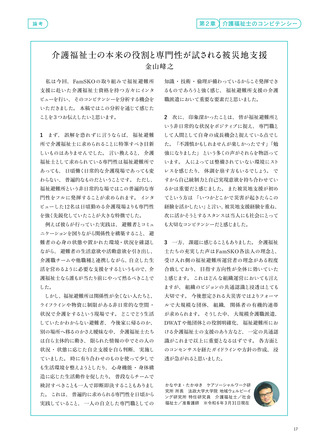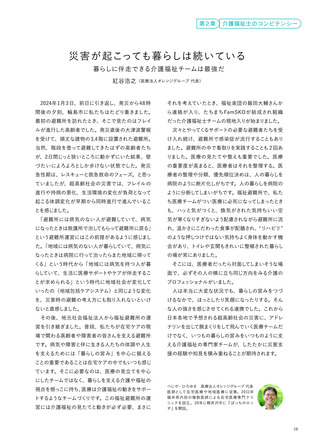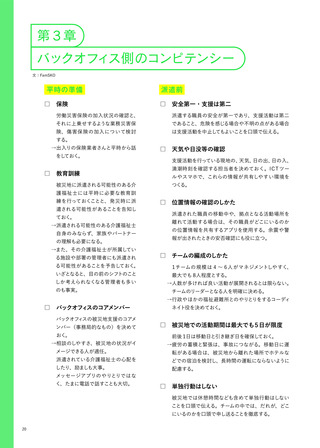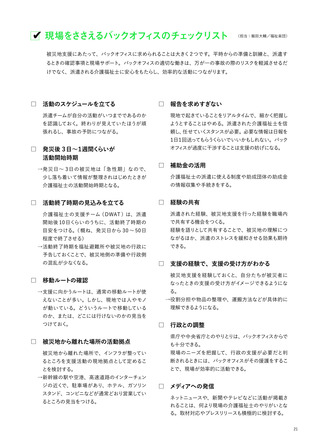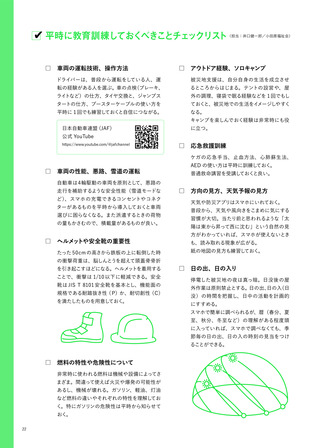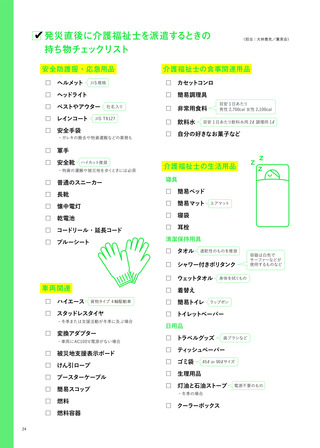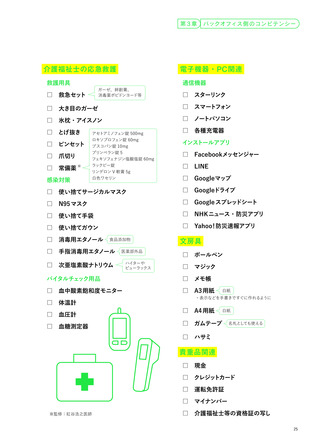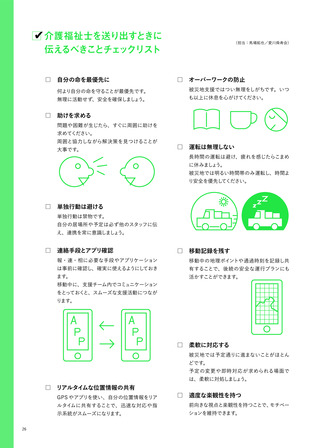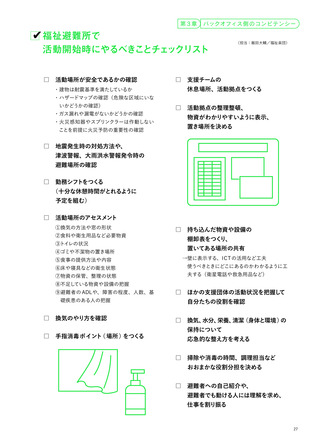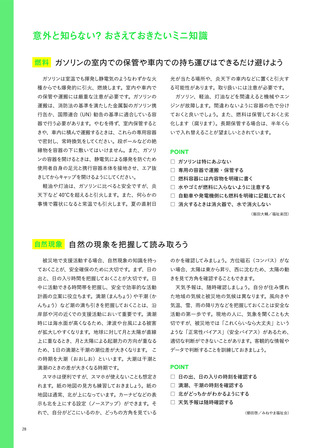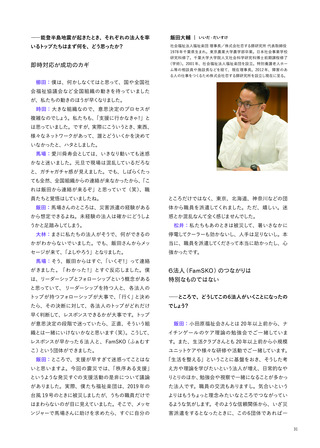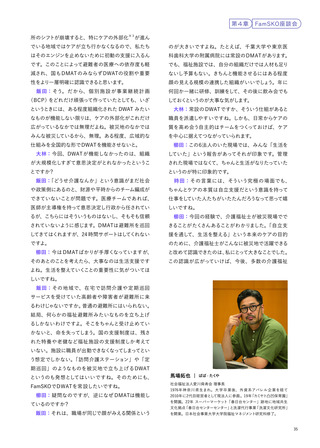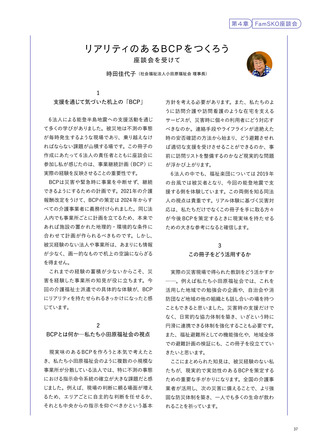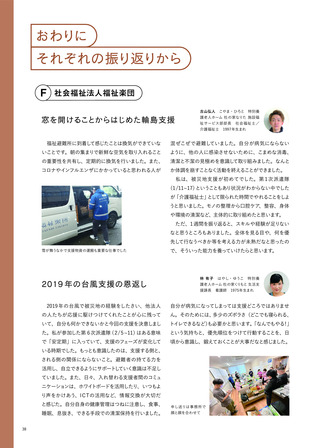よむ、つかう、まなぶ。
井口委員提出資料 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
士を擁する社会福祉法人は、こいつら災害で活躍でき
ずきちんとやりとりできる行政マンがいない。混乱も相
るぞと確信し、自信を持って「行ってこい!」って送り
当あったと思いますが主体性が感じられないという印
だせるようになります。こういう機会を通じて、介護福
象があります。輪島市役所の人だと思っていたら、そ
祉士の専門性を社会に発信していきたい。
の人は全然違う自治体の人でヘルプだったということ
時田:時たま思うのですが、介護職が全国一斉にス
トライキをしたらどうなるか。
を撤収日に知るという珍事件もありました。こうしたこ
とは、輪島市に特有のことではなくて、全国の自治体
一同:大笑い
に蔓延している課題だと思います。立ち上げた福祉避
時田:ストライキしたら、生活が、社会が成り立た
難所にトイレがなくて、仮設トイレの設置を要求しても
ないですよ。そのくらい介護というのは大事で、介護
全く動いてもらえない。福祉避難所にトイレがないって
があって暮らしがあるのです。
信じられますか。3週間なかった。厚生労働省と直談
馬場:そうですね。福祉そのものの再定義の必要
があります。福祉は、日常の質を問うものです。今の
行政は、被災地支援を浅く見ている。暮らしに立脚し
ていることを示していかないと。
判してようやく設置されました。直談判していなかった
ら、最後まで設置されていないと思いますよ。
時田:そういう弱小自治体が被災したら本当に大
変。生き残れない。広域連携って必要です。
大林:今回の被災地支援の報告会をしたところ、二
大林:私のところでは、災害派遣が終わって、事後
の足を踏んでいた組織と、災害支援協定を結ぶことに
報告の法人研修をやったんですね。町の担当者とか議
なりました。こうやって経験を語っていくことで、新た
員も来てくれて、輪島でどんなことをやってきたか、介
なつながりができて、広がりができていくことが嬉しい。
護福祉士がどんな活躍をしたっていう報告をしました。
松井:どこか、リアリティがない、災害が起こるとは
実は、何年か前から災害支援協定を町で結びましょう
思っていない、そんな若い職員に、災害は必ず起こる
よと投げかけていたんですけど、あまり町も関心を示
と浸透させるのは本当に難しいですが、この経験を少
さなくてそのままズルズルしていたのですが、今回の報
しでも多くの人に届けて、「自分の地域で起こったらど
告会参加した後に、結びましょうとなりました。介護福
うするか」というリアルな学びにつなげてもらえたらい
祉士の活躍が伝えられて、彼らが必要だということが
いです。
わかってもらえてすごい嬉しかったです。
飯田:今回、地方自治体の衰弱というのを感じまし
飯田:僕は、
自分でもなんで災害の支援するのかなっ
た。輪島市役所と何回かやり取りして思ったのは、ま
て考えるのは、自分たちが支援してもらったからです。
いつ、助ける側が助けられる側になるかわかりません。
災害とはそういうものです。そして、助けてもらった経
験がある人たちは、それをいつか誰かに返すでしょう。
平時から、こうやって広い意味での信頼関係をつくっ
ていきたいですね。ですから、できる範囲で、自分が
持っている資源を使ってそのときのために行動し続け
たいですね。
時田:介護事業所が有事の際に事業を継続できる
よう定めておくBCP が、2021年の介護報酬改定で義
務付けられました。いざという時に使える、質の高い
リアルな BCP にするためにも、自分たちの組織だけ
で BCP 対策を策定するのではなく、互いに補完しあう
松井千佳|まつい · ちか
社会福祉法人生活クラブ 常務理事
1968 年愛知県生まれ。友人に紹介され 2000 年に特別養護老人ホー
ム風の村(現生活クラブ風の村特養ホーム八街)に入職。当時は栄
養士として勤務していたが、現在は総務部長として事業本部に勤務。
災害支援の際はバックオフィスを担当することが多い。
36
複数の団体で共助しあった、今回の事例を役立ててほ
しいですね。
ずきちんとやりとりできる行政マンがいない。混乱も相
るぞと確信し、自信を持って「行ってこい!」って送り
当あったと思いますが主体性が感じられないという印
だせるようになります。こういう機会を通じて、介護福
象があります。輪島市役所の人だと思っていたら、そ
祉士の専門性を社会に発信していきたい。
の人は全然違う自治体の人でヘルプだったということ
時田:時たま思うのですが、介護職が全国一斉にス
トライキをしたらどうなるか。
を撤収日に知るという珍事件もありました。こうしたこ
とは、輪島市に特有のことではなくて、全国の自治体
一同:大笑い
に蔓延している課題だと思います。立ち上げた福祉避
時田:ストライキしたら、生活が、社会が成り立た
難所にトイレがなくて、仮設トイレの設置を要求しても
ないですよ。そのくらい介護というのは大事で、介護
全く動いてもらえない。福祉避難所にトイレがないって
があって暮らしがあるのです。
信じられますか。3週間なかった。厚生労働省と直談
馬場:そうですね。福祉そのものの再定義の必要
があります。福祉は、日常の質を問うものです。今の
行政は、被災地支援を浅く見ている。暮らしに立脚し
ていることを示していかないと。
判してようやく設置されました。直談判していなかった
ら、最後まで設置されていないと思いますよ。
時田:そういう弱小自治体が被災したら本当に大
変。生き残れない。広域連携って必要です。
大林:今回の被災地支援の報告会をしたところ、二
大林:私のところでは、災害派遣が終わって、事後
の足を踏んでいた組織と、災害支援協定を結ぶことに
報告の法人研修をやったんですね。町の担当者とか議
なりました。こうやって経験を語っていくことで、新た
員も来てくれて、輪島でどんなことをやってきたか、介
なつながりができて、広がりができていくことが嬉しい。
護福祉士がどんな活躍をしたっていう報告をしました。
松井:どこか、リアリティがない、災害が起こるとは
実は、何年か前から災害支援協定を町で結びましょう
思っていない、そんな若い職員に、災害は必ず起こる
よと投げかけていたんですけど、あまり町も関心を示
と浸透させるのは本当に難しいですが、この経験を少
さなくてそのままズルズルしていたのですが、今回の報
しでも多くの人に届けて、「自分の地域で起こったらど
告会参加した後に、結びましょうとなりました。介護福
うするか」というリアルな学びにつなげてもらえたらい
祉士の活躍が伝えられて、彼らが必要だということが
いです。
わかってもらえてすごい嬉しかったです。
飯田:今回、地方自治体の衰弱というのを感じまし
飯田:僕は、
自分でもなんで災害の支援するのかなっ
た。輪島市役所と何回かやり取りして思ったのは、ま
て考えるのは、自分たちが支援してもらったからです。
いつ、助ける側が助けられる側になるかわかりません。
災害とはそういうものです。そして、助けてもらった経
験がある人たちは、それをいつか誰かに返すでしょう。
平時から、こうやって広い意味での信頼関係をつくっ
ていきたいですね。ですから、できる範囲で、自分が
持っている資源を使ってそのときのために行動し続け
たいですね。
時田:介護事業所が有事の際に事業を継続できる
よう定めておくBCP が、2021年の介護報酬改定で義
務付けられました。いざという時に使える、質の高い
リアルな BCP にするためにも、自分たちの組織だけ
で BCP 対策を策定するのではなく、互いに補完しあう
松井千佳|まつい · ちか
社会福祉法人生活クラブ 常務理事
1968 年愛知県生まれ。友人に紹介され 2000 年に特別養護老人ホー
ム風の村(現生活クラブ風の村特養ホーム八街)に入職。当時は栄
養士として勤務していたが、現在は総務部長として事業本部に勤務。
災害支援の際はバックオフィスを担当することが多い。
36
複数の団体で共助しあった、今回の事例を役立ててほ
しいですね。