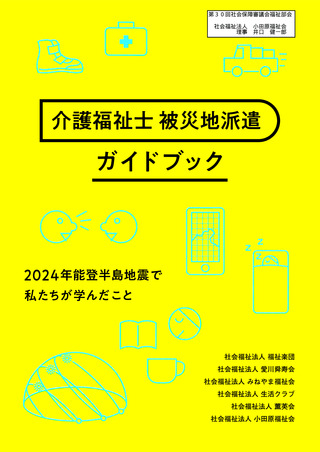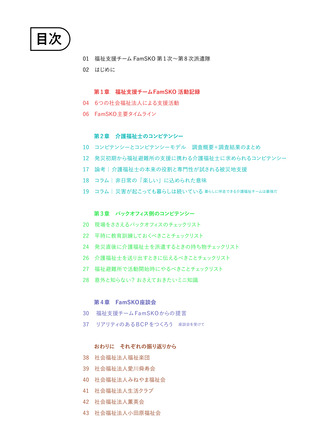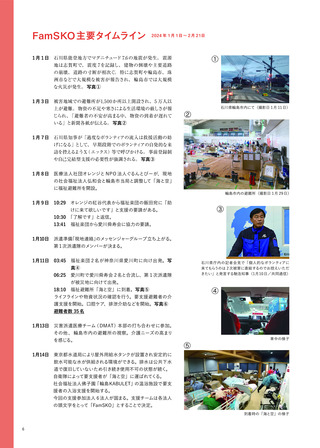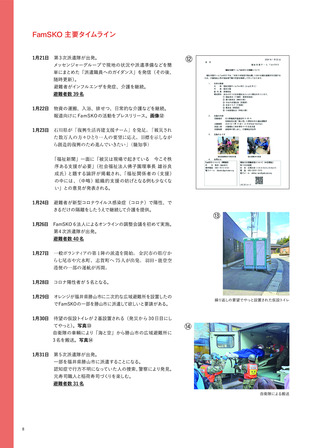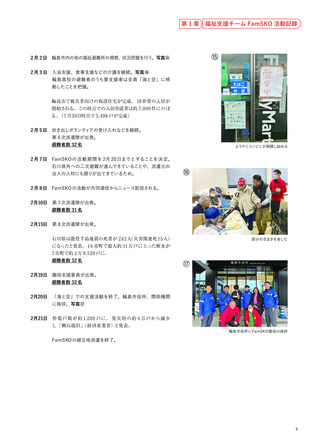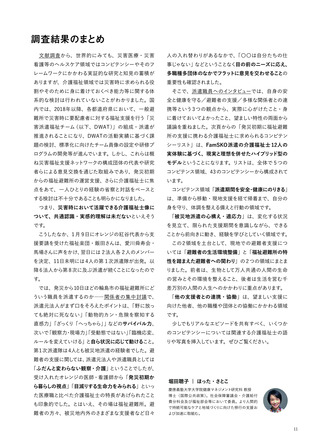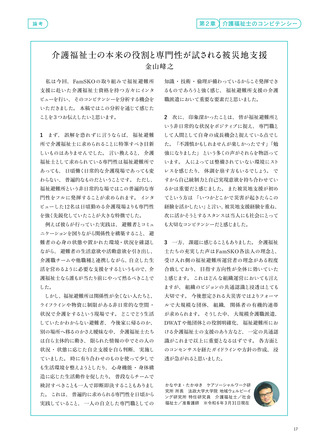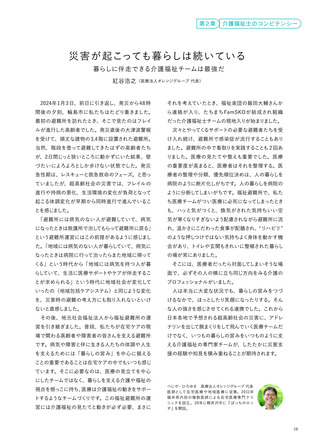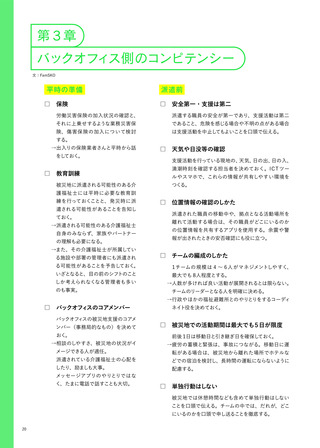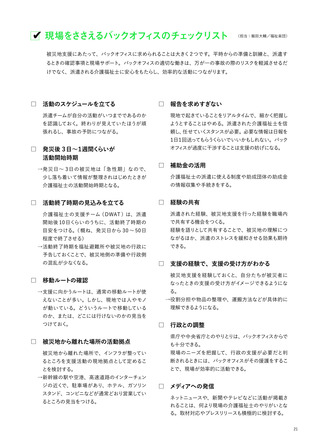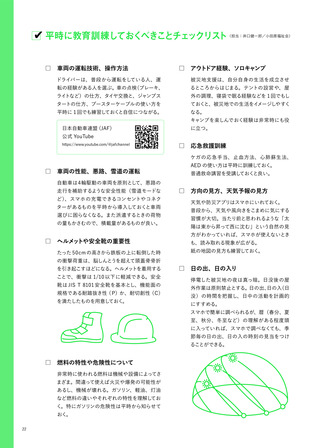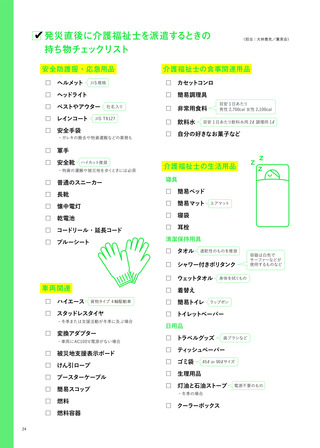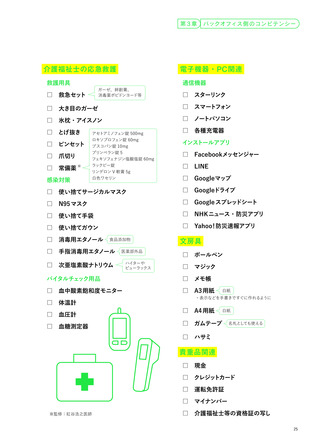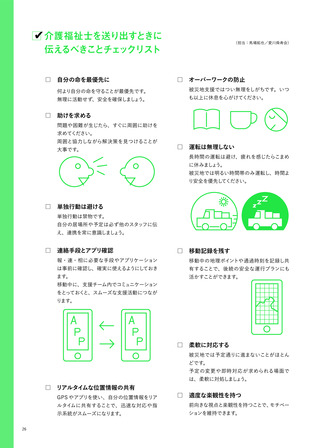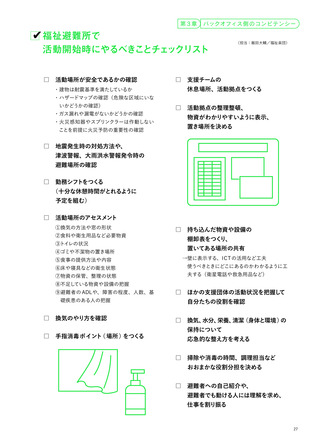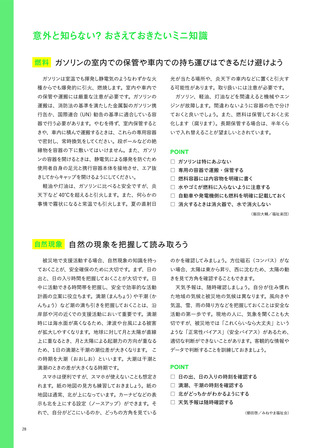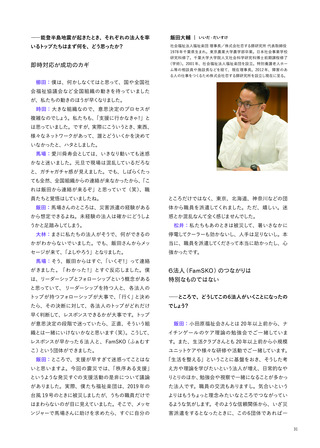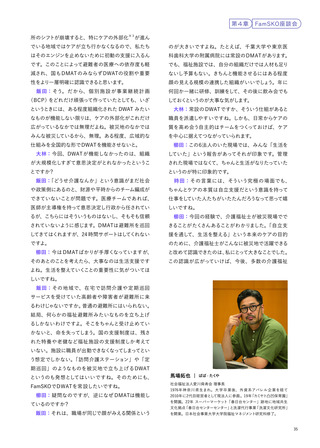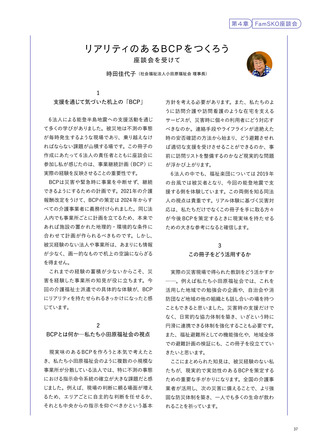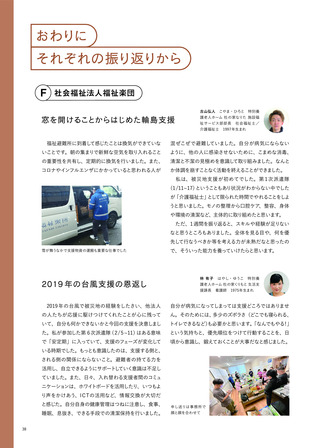よむ、つかう、まなぶ。
井口委員提出資料 (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4章
FamSKO座談会
櫛田 啓|くしだ · たすく
社会福祉法人みねやま福祉会 常務理事
1982年京都府京丹後市生まれ。学生時代はサッカーに明け暮れたが、
恩師の一言から「福祉」の道を志すことに。大阪や福岡での生活を経
支え合うというのが福祉本来の考え方なはずです。
櫛田:支援活動に参加することで、職員同士の信
て 10 年ぶりに帰郷し、故郷の衰退に直面。世代や疾患、障がいの有
頼が深まりました。共同して支援活動を行うことで、職
の社会づくりを通じて、人々のこころ豊かで安心・安全な暮らしへ貢献
員同士の連携が強化され、信頼関係が深まります。
無に関わらず、地域の中で人と人の支え合いを大切にする「ごちゃまぜ」
する活動をする。
松井:私たちの各事業所には、
「防災委員会」があ
るんですけど、この間その集まりがあって、FamSKO
に参加した人が事業所の防災委員長だったりするんで
すよ。そのときの経験を、そこで話してたりしたので、
行った経験が広がっていると思いましたね。
馬場:被災地支援の経験って、やっぱり言葉で伝え
られない部分が確かにあるんだと思います。リアルな
被災地派遣って、
「マイスター的」なもので、行かない
とわからない。でも、行った人の背中を見て何か影響
みたいなのはあったんでしょうね。戦地からぼろぼろ
になって帰ってきて終わっちゃうのではなく、組織が組
織として経験を吸収する形があるといいですね。
飯田:そういう点では、支援活動の経験をただの個
人の経験にとどめず、組織全体で共有する工夫をしま
とか、ちょっと違うところはあったかなと思いますけど、
したね。例えば、Slackのオープンチャンネルで、被
やっぱり正直言って、求められている職員と手を挙げ
災地へ派遣をした職員にエールを贈るチャンネルを
る職員が一致しない場合がありましたね。
作ったんです。介護職員は発信が苦手な傾向があるの
馬場:何か災害が起きたときにまず最初に、この人が
行くんだろうなという目星みたいなのはないんですか。
ですが、このチャンネルはみんなが書き込むんです。
残った人が「被災地支援を引き受けてくれてありがとう
松井:目星はありますね。ちょっと今機能しないん
ございます」とか「慣れない環境で無理はしないで」
ですけど災害があったときのために、登録するような
など次々に書き込んでいました。本当に何かみんなが
制度は作ってはあるんです。しかし、結局それもしばら
自分の言葉で書き込んで、それが 200 以上のメッセー
く何もないと機能しないんですよね。「もうその人退職
ジになって。僕は一人ひとりが言葉を持ってるんだなっ
してます」とかがあって。
てちょっと感動したんですよ。ただし、冷静さも必要で
馬場:なるほど、組織が大きいからといって、簡単
した。支援の目的を明確にしていかないと。
に人を出せるというわけではないんですよね。大きけ
時田:非日常の体験で終わってはいけないわね。
れば大きいほど、体制を維持するのにも体力がいるな
何かあったときに瞬時に体が動く心が動くそういう職員
かで、よく派遣してくれたと思います。一方、派遣しな
たちであってほしいと思います。行った人だけを英雄に
い組織はその理由に「行かせる側にも責任がある」と
してはいけないという点には注意しましたね。支援に
リスクをいう。
行かずに残った人にも現場で役割があります。日常で
時田:
「何かあったらどうするのか?」という人もい
も心と身体が動くという職員を育成するのが、リーダー
ますね。ただでさえ、平時から人が足りないから出せ
の役割です。特に私たちのような中規模の組織では、
ないと言います。しかし、派遣によって人が減ってもい
個々のメンバーが持つ経験が組織全体の強みとなりま
つもと同じことができるというのが、残された職員にと
す。災害支援を通じて得たさまざまな教訓を、日常業
ても大事な経験になります。みんなで協力したら、な
務に活かすことが重要です。
んとかなったという思いを共にしたとき、職員が個々に
成長し、組織全体が成長します。自分の組織のことだ
−−−避難所で行った支援は「地域における生活支援」
け考えていたら成長がありません。それに、助け合う、
だった
33
FamSKO座談会
櫛田 啓|くしだ · たすく
社会福祉法人みねやま福祉会 常務理事
1982年京都府京丹後市生まれ。学生時代はサッカーに明け暮れたが、
恩師の一言から「福祉」の道を志すことに。大阪や福岡での生活を経
支え合うというのが福祉本来の考え方なはずです。
櫛田:支援活動に参加することで、職員同士の信
て 10 年ぶりに帰郷し、故郷の衰退に直面。世代や疾患、障がいの有
頼が深まりました。共同して支援活動を行うことで、職
の社会づくりを通じて、人々のこころ豊かで安心・安全な暮らしへ貢献
員同士の連携が強化され、信頼関係が深まります。
無に関わらず、地域の中で人と人の支え合いを大切にする「ごちゃまぜ」
する活動をする。
松井:私たちの各事業所には、
「防災委員会」があ
るんですけど、この間その集まりがあって、FamSKO
に参加した人が事業所の防災委員長だったりするんで
すよ。そのときの経験を、そこで話してたりしたので、
行った経験が広がっていると思いましたね。
馬場:被災地支援の経験って、やっぱり言葉で伝え
られない部分が確かにあるんだと思います。リアルな
被災地派遣って、
「マイスター的」なもので、行かない
とわからない。でも、行った人の背中を見て何か影響
みたいなのはあったんでしょうね。戦地からぼろぼろ
になって帰ってきて終わっちゃうのではなく、組織が組
織として経験を吸収する形があるといいですね。
飯田:そういう点では、支援活動の経験をただの個
人の経験にとどめず、組織全体で共有する工夫をしま
とか、ちょっと違うところはあったかなと思いますけど、
したね。例えば、Slackのオープンチャンネルで、被
やっぱり正直言って、求められている職員と手を挙げ
災地へ派遣をした職員にエールを贈るチャンネルを
る職員が一致しない場合がありましたね。
作ったんです。介護職員は発信が苦手な傾向があるの
馬場:何か災害が起きたときにまず最初に、この人が
行くんだろうなという目星みたいなのはないんですか。
ですが、このチャンネルはみんなが書き込むんです。
残った人が「被災地支援を引き受けてくれてありがとう
松井:目星はありますね。ちょっと今機能しないん
ございます」とか「慣れない環境で無理はしないで」
ですけど災害があったときのために、登録するような
など次々に書き込んでいました。本当に何かみんなが
制度は作ってはあるんです。しかし、結局それもしばら
自分の言葉で書き込んで、それが 200 以上のメッセー
く何もないと機能しないんですよね。「もうその人退職
ジになって。僕は一人ひとりが言葉を持ってるんだなっ
してます」とかがあって。
てちょっと感動したんですよ。ただし、冷静さも必要で
馬場:なるほど、組織が大きいからといって、簡単
した。支援の目的を明確にしていかないと。
に人を出せるというわけではないんですよね。大きけ
時田:非日常の体験で終わってはいけないわね。
れば大きいほど、体制を維持するのにも体力がいるな
何かあったときに瞬時に体が動く心が動くそういう職員
かで、よく派遣してくれたと思います。一方、派遣しな
たちであってほしいと思います。行った人だけを英雄に
い組織はその理由に「行かせる側にも責任がある」と
してはいけないという点には注意しましたね。支援に
リスクをいう。
行かずに残った人にも現場で役割があります。日常で
時田:
「何かあったらどうするのか?」という人もい
も心と身体が動くという職員を育成するのが、リーダー
ますね。ただでさえ、平時から人が足りないから出せ
の役割です。特に私たちのような中規模の組織では、
ないと言います。しかし、派遣によって人が減ってもい
個々のメンバーが持つ経験が組織全体の強みとなりま
つもと同じことができるというのが、残された職員にと
す。災害支援を通じて得たさまざまな教訓を、日常業
ても大事な経験になります。みんなで協力したら、な
務に活かすことが重要です。
んとかなったという思いを共にしたとき、職員が個々に
成長し、組織全体が成長します。自分の組織のことだ
−−−避難所で行った支援は「地域における生活支援」
け考えていたら成長がありません。それに、助け合う、
だった
33