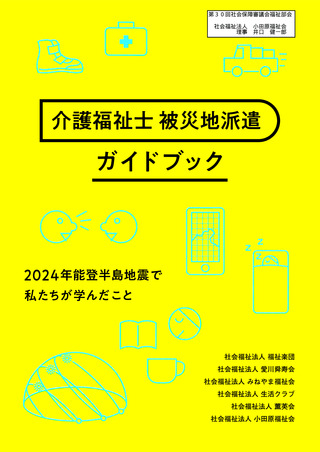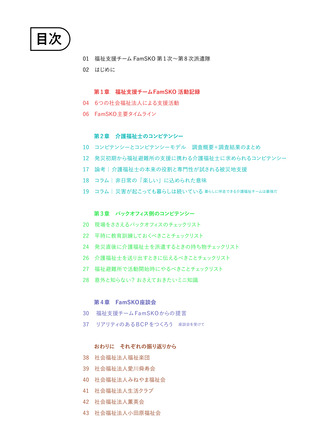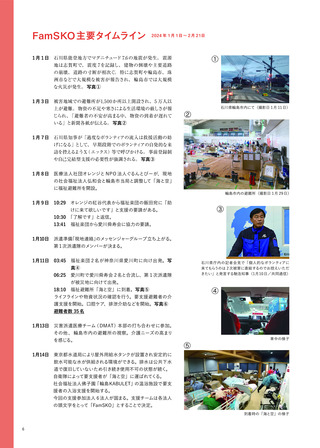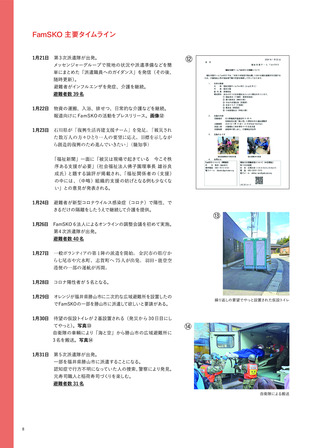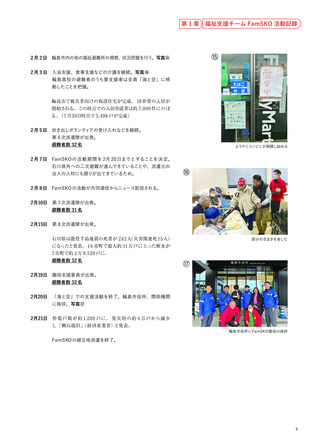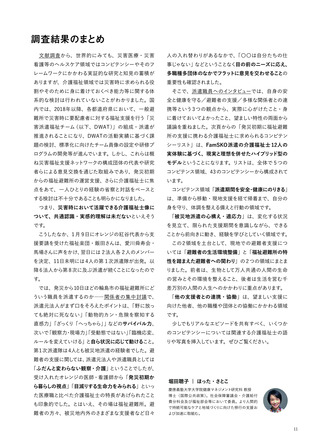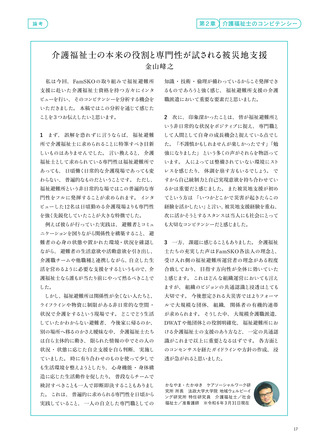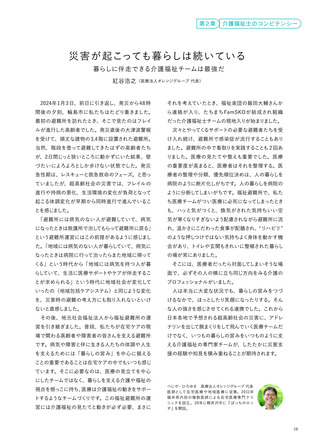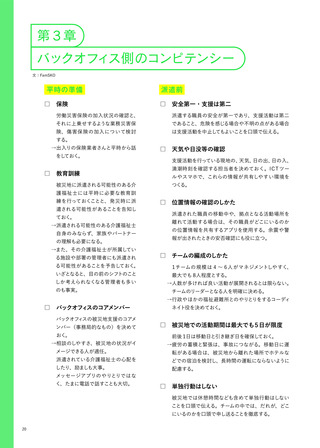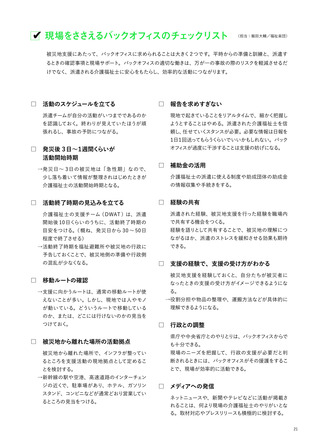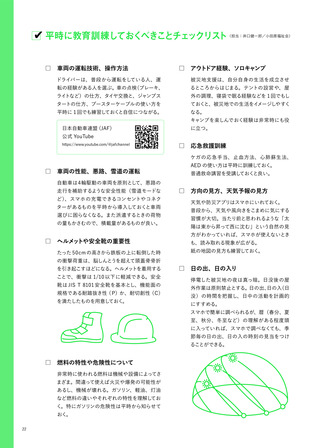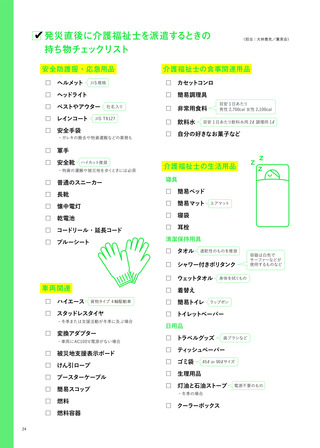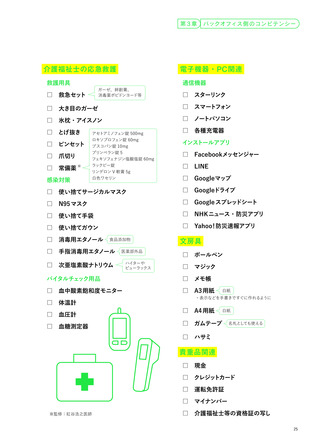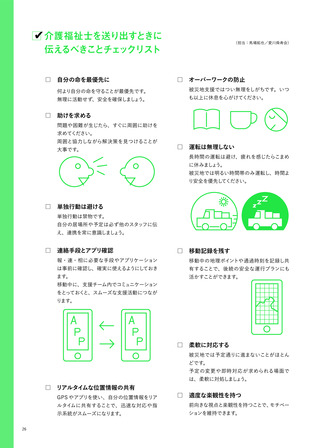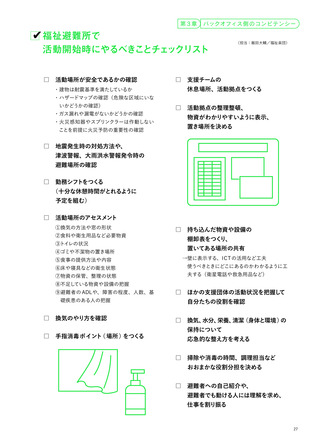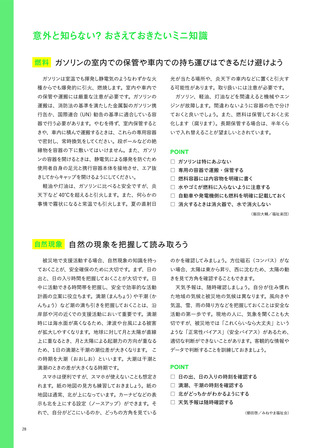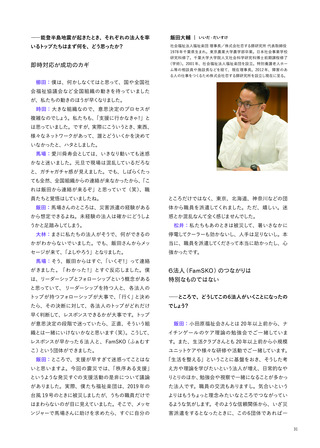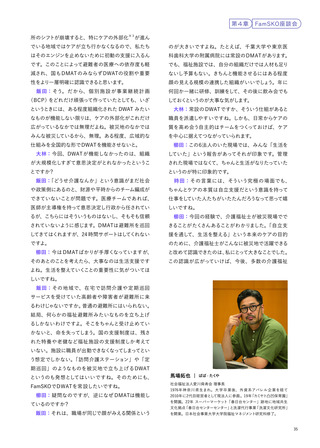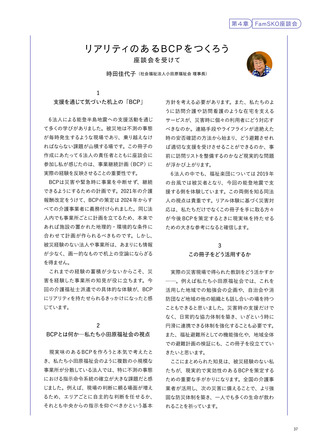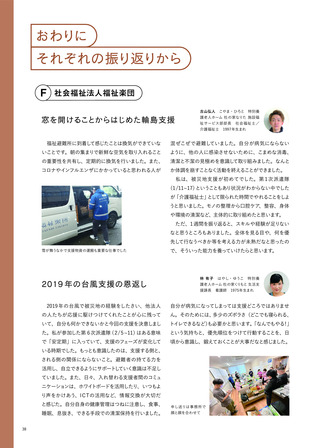よむ、つかう、まなぶ。
井口委員提出資料 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
緒にやれると思って、お誘いをしました。
時田:今、社会福祉法人って継続的に事業をするた
めに、ビジネスの視点から連携とか大規模化という方
向にきています。しかし、福祉楽団さんとはそういうこ
とで始まった関係ではありません。大規模化が社会福
祉法人にとって本当にあるべき姿かわかりません。い
い仕事ができる担保にはならないと思っています。お
互い、日頃の活動に共感するところがあって、つながっ
大事で、それができた6法人が行ったというわけです。
−−−6法人( FamSKO )が行くことになった。次にトッ
プが考えるのは、誰を派遣するか。
支援活動が職員の成長の場となる
時田:連絡をもらって、すぐに「行く人?」って職員
ている関係です。本質的なところでつながっているチー
に聞きました。手を挙げたのは、災害派遣の経験が
ムです。
ある職員か、これまで機会がなくて行けなくて悔しい
馬場:特別なスキルやノウハウではなく、平時から
思いをした人でした。行った経験がある職員は、台風
つながりがあって、ケアへの思いを同じくしていたから
19 号の際の派遣の経験をいまだに語ります。被災地
できたのです。日常の中で築いてきた関係性が、いざ
支援経験は望んでできる経験ではありません。彼らの
というときにどれだけ重要かが今回の経験で分かりま
良い学びになっています。
した。特にこの6法人が特殊なことをしていたわけで
はないんです。
飯田:しかし、未経験の法人同士だと、なかなか支
援に踏み出せないっていうところもあります。その点、
FamSKOの中には、災害支援の経験値がある法人が
大林:非日常の経験ですし、職員の経験値がぐっと
上がるめったにない機会です。そういう面では誰を派
遣させるかが大事ですね。でも、すぐ、
誰を行かせるかっ
て頭にすぐに思い浮かびます。
櫛田:FamSKO では、人がほしいとき、「介護福祉
複数いますので、「じゃあ、福祉楽団の声かけに乗っ
士を2人出せますか?」という感じでメッセージがきま
かれる!」みたいな安心感もあるのかなって思ったりは
した。でも、他の大きな組織からは「性別、職歴、資格」
します。そうやって経験が広がっていけばいいですね。
などの縛りがあって、その条件に合った人を派遣しなく
どのみち、災害というのは、いつかは起きてしまうも
てはならず、やりにくいなと思っていました。もちろん、
のですから。
派遣する職員の管理はある程度必要でしょうが、私た
馬場:あとは、トップのスムーズな判断でしょうね。
ちが行く目的は、
「避難者の生活を整えること」が第一
「行くよ! 人を出せるよ」というトップの迅速な判断が
です。「性別、職歴、資格」で人材を選ぶのではなく、
想定外の現場でどう創造的に動けるコンピテンシーを
持った職員なのか、そっちが大事だと思います。
飯田:行かせる人を決めたら、次に考えるのは、誰
と誰の組み合わせがいいか。職員の育成のためにも、
3 年目の若手とベテランの組み合わせとかね。この法
人とこの法人の職員は大丈夫そうとか。
(笑)
櫛田:メッセンジャーでグループを作ったのがよかっ
たです。どんな人が行くのか、
プロフィールも顔もわかっ
たので、
初対面の「はじめまして」でも安心できました。
松井:私たち組織は、支援のスタートは切れないけ
ど、飯田さんから声をかけられて、人は出せると思っ
ていました。1,800人がいる組織ですから。しかし、現
大林喬充|おおばやし · たかみつ
社会福祉法人薫英会 常務理事/障害者支援施設薫英荘 施設長
1987 年群馬県生まれ。大学卒業後、ウェディング・セレモニー業界に
てプランナー、営業マネージャーなどを経験。父の急逝をきっかけに福
祉を志し現法人へ入職。障害者支援施設の生活支援員、特養の介護職
員等を経て現在に至る。地域を考える「よしおかイドバタベース」運営。
32
場から求められている介護福祉士の資格がある人材
と、行きたいと手を挙げる人材が異なるということが
あって、頭を悩ませました。介護福祉士ではないヘル
パーの資格のみの職員を出したりとか、看護師の職員
を出したりとか、圧倒的に年齢層が高い職員が出たり
時田:今、社会福祉法人って継続的に事業をするた
めに、ビジネスの視点から連携とか大規模化という方
向にきています。しかし、福祉楽団さんとはそういうこ
とで始まった関係ではありません。大規模化が社会福
祉法人にとって本当にあるべき姿かわかりません。い
い仕事ができる担保にはならないと思っています。お
互い、日頃の活動に共感するところがあって、つながっ
大事で、それができた6法人が行ったというわけです。
−−−6法人( FamSKO )が行くことになった。次にトッ
プが考えるのは、誰を派遣するか。
支援活動が職員の成長の場となる
時田:連絡をもらって、すぐに「行く人?」って職員
ている関係です。本質的なところでつながっているチー
に聞きました。手を挙げたのは、災害派遣の経験が
ムです。
ある職員か、これまで機会がなくて行けなくて悔しい
馬場:特別なスキルやノウハウではなく、平時から
思いをした人でした。行った経験がある職員は、台風
つながりがあって、ケアへの思いを同じくしていたから
19 号の際の派遣の経験をいまだに語ります。被災地
できたのです。日常の中で築いてきた関係性が、いざ
支援経験は望んでできる経験ではありません。彼らの
というときにどれだけ重要かが今回の経験で分かりま
良い学びになっています。
した。特にこの6法人が特殊なことをしていたわけで
はないんです。
飯田:しかし、未経験の法人同士だと、なかなか支
援に踏み出せないっていうところもあります。その点、
FamSKOの中には、災害支援の経験値がある法人が
大林:非日常の経験ですし、職員の経験値がぐっと
上がるめったにない機会です。そういう面では誰を派
遣させるかが大事ですね。でも、すぐ、
誰を行かせるかっ
て頭にすぐに思い浮かびます。
櫛田:FamSKO では、人がほしいとき、「介護福祉
複数いますので、「じゃあ、福祉楽団の声かけに乗っ
士を2人出せますか?」という感じでメッセージがきま
かれる!」みたいな安心感もあるのかなって思ったりは
した。でも、他の大きな組織からは「性別、職歴、資格」
します。そうやって経験が広がっていけばいいですね。
などの縛りがあって、その条件に合った人を派遣しなく
どのみち、災害というのは、いつかは起きてしまうも
てはならず、やりにくいなと思っていました。もちろん、
のですから。
派遣する職員の管理はある程度必要でしょうが、私た
馬場:あとは、トップのスムーズな判断でしょうね。
ちが行く目的は、
「避難者の生活を整えること」が第一
「行くよ! 人を出せるよ」というトップの迅速な判断が
です。「性別、職歴、資格」で人材を選ぶのではなく、
想定外の現場でどう創造的に動けるコンピテンシーを
持った職員なのか、そっちが大事だと思います。
飯田:行かせる人を決めたら、次に考えるのは、誰
と誰の組み合わせがいいか。職員の育成のためにも、
3 年目の若手とベテランの組み合わせとかね。この法
人とこの法人の職員は大丈夫そうとか。
(笑)
櫛田:メッセンジャーでグループを作ったのがよかっ
たです。どんな人が行くのか、
プロフィールも顔もわかっ
たので、
初対面の「はじめまして」でも安心できました。
松井:私たち組織は、支援のスタートは切れないけ
ど、飯田さんから声をかけられて、人は出せると思っ
ていました。1,800人がいる組織ですから。しかし、現
大林喬充|おおばやし · たかみつ
社会福祉法人薫英会 常務理事/障害者支援施設薫英荘 施設長
1987 年群馬県生まれ。大学卒業後、ウェディング・セレモニー業界に
てプランナー、営業マネージャーなどを経験。父の急逝をきっかけに福
祉を志し現法人へ入職。障害者支援施設の生活支援員、特養の介護職
員等を経て現在に至る。地域を考える「よしおかイドバタベース」運営。
32
場から求められている介護福祉士の資格がある人材
と、行きたいと手を挙げる人材が異なるということが
あって、頭を悩ませました。介護福祉士ではないヘル
パーの資格のみの職員を出したりとか、看護師の職員
を出したりとか、圧倒的に年齢層が高い職員が出たり