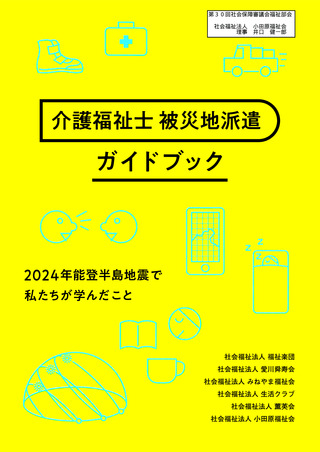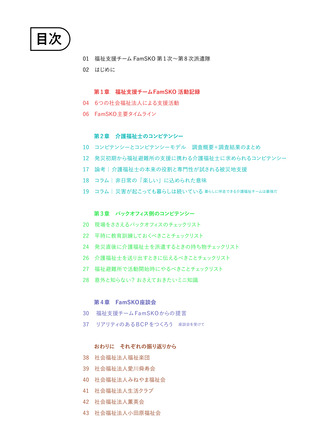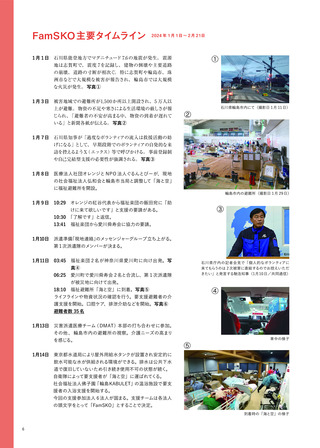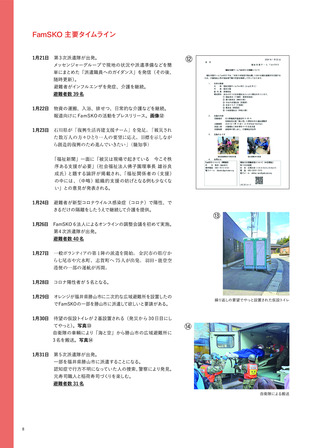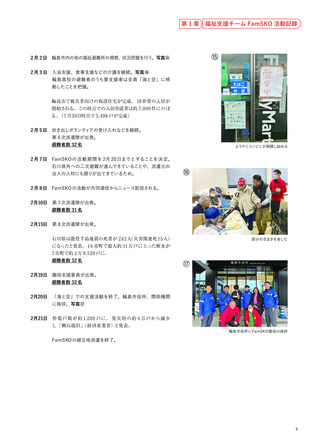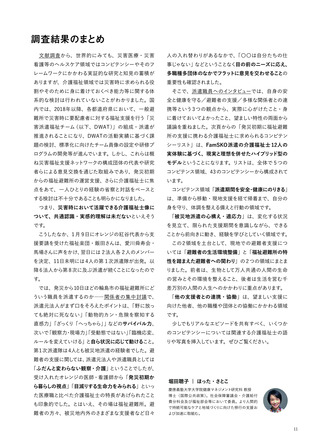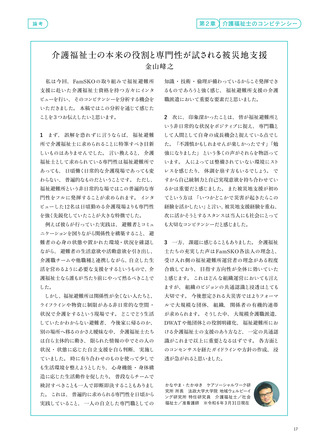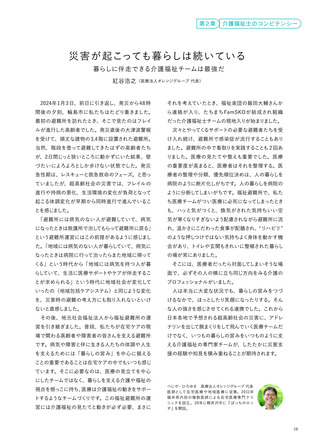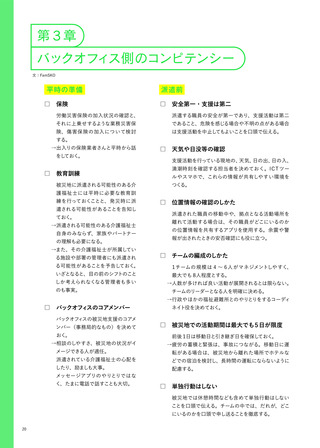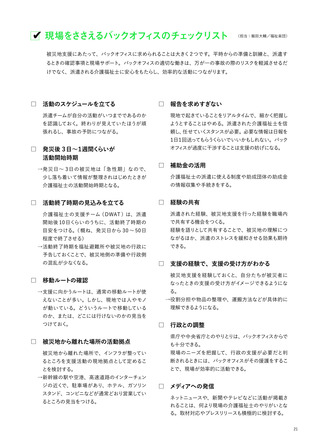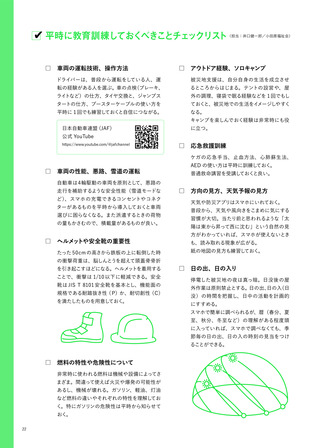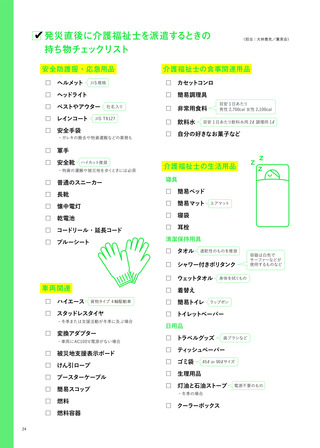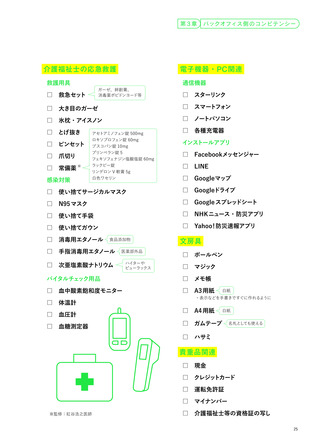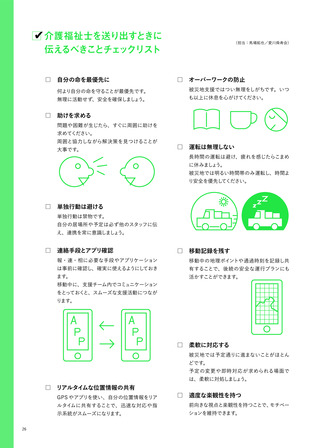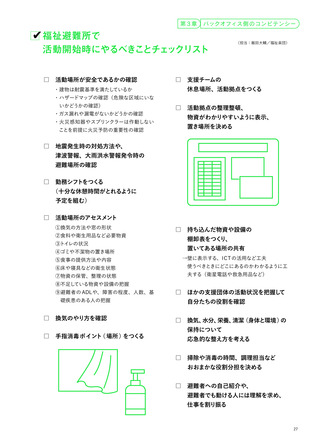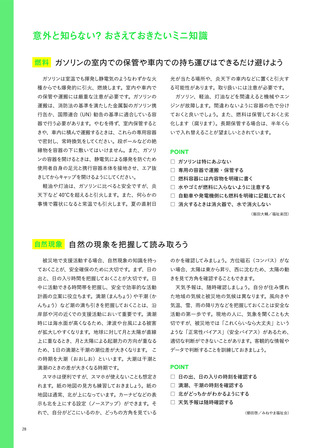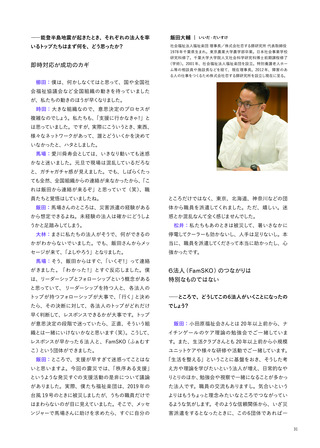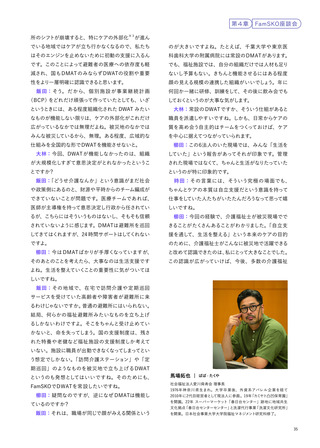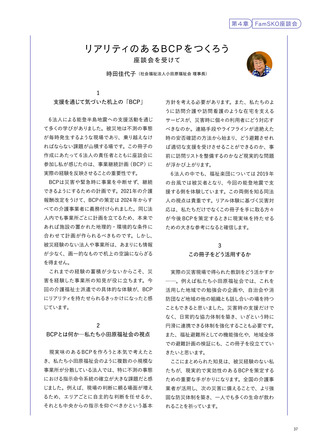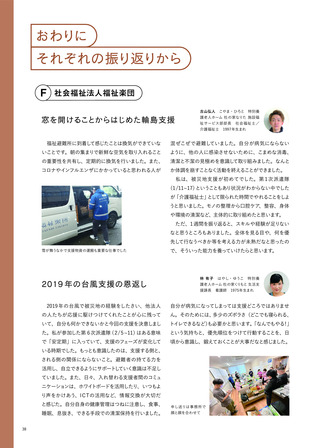よむ、つかう、まなぶ。
井口委員提出資料 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4章
FamSKO座談会
リアリティのあるB C P をつくろう
座 談 会を受けて
時田佳代子(社会福祉法人小田原福祉会 理事長)
1
支援を通じて気づいた机上の「BCP」
方針を考える必要があります。また、私たちのよ
うに訪問介護や訪問看護のような在宅を支える
6 法人による能登半島地震への支援活動を通じ
サービスが、災害時に個々の利用者にどう対応す
て多くの学びがありました。被災地は不測の事態
べきなのか。連絡手段やライフラインが途絶えた
が毎時発生するような現場であり、乗り越えなけ
時の安否確認の方法から始まり、どう避難させれ
ればならない課題が山積する場です。この冊子の
ば適切な支援を受けさせることができるのか、事
作成にあたって 6 法人の責任者とともに座談会に
前に訪問リストを整備するのかなど現実的な問題
参加し私が感じたのは、事業継続計画(BCP)に
が浮かび上がります。
実際の経験を反映させることの重要性です。
6 法人の中でも、福祉楽団については 2019 年
BCPは災害や緊急時に事業を中断せず、継続
の台風では被災者となり、今回の能登地震で支
できるようにするための計画です。2021年の介護
援する側を体験しています。この両側を知る同法
報酬改定をうけて、BCPの策定は 2024 年からす
人の視点は貴重です。リアル体験に基づく災害対
べての介護事業者に義務付けられました。同じ法
応は、私たちだけでなくこの冊子を手に取る方々
人内でも事業所ごとに計画を立てるため、本来で
が今後 BCPを策定するときに現実味を持たせる
あれば施設の置かれた地理的・環境的な条件に
ための大きな参考になると確信します。
合わせて計画が作られるべきものです。しかし、
被災経験のない法人や事業所は、あまりにも情報
が少なく、画一的なもので机上の空論にならざる
を得ません。
3
この冊子をどう活用するか
これまでの経験の蓄積が少ないからこそ、災
実際の災害現場で得られた教訓をどう活かすか
害を経験した事業所の知見が役に立ちます。今
──。例えば私たち小田原福祉会では、これを
回の介護福祉士派遣での具体的な体験が、BCP
活用した地域での勉強会の企画や、自治会や消
にリアリティを持たせられるきっかけになったと感
防団など地域の他の組織とも話し合いの場を持つ
じています。
こともできると思いました。災害時の支援だけで
なく、日常的な協力体制を築き、いざという時に
2
BCPとは何か─私たち小田原福祉会の視点
円滑に連携できる体制を強化することも必要です。
また、福祉避難所としての機能強化や、地域全体
での避難計画の検証にも、この冊子を役立ててい
現実味のあるBCPを作ろうと本気で考えたと
きたいと思います。
き、私たち小田原福祉会のように複数の小規模な
ここにまとめられた知見は、被災経験のない私
事業所が分散している法人では、特に不測の事態
たちが、現実的で実効性のあるBCPを策定する
における指示命令系統の確立が大きな課題だと感
ための重要な手がかりになります。全国の介護事
じました。例えば、現場の判断に頼る場面が増え
業者が活用し、次の災害に備えることで、より強
るため、エリアごとに自主的な判断を任せるか、
固な防災体制を築き、一人でも多くの生命が救わ
それとも中央からの指示を仰ぐべきかという基本
れることを祈っています。
37
FamSKO座談会
リアリティのあるB C P をつくろう
座 談 会を受けて
時田佳代子(社会福祉法人小田原福祉会 理事長)
1
支援を通じて気づいた机上の「BCP」
方針を考える必要があります。また、私たちのよ
うに訪問介護や訪問看護のような在宅を支える
6 法人による能登半島地震への支援活動を通じ
サービスが、災害時に個々の利用者にどう対応す
て多くの学びがありました。被災地は不測の事態
べきなのか。連絡手段やライフラインが途絶えた
が毎時発生するような現場であり、乗り越えなけ
時の安否確認の方法から始まり、どう避難させれ
ればならない課題が山積する場です。この冊子の
ば適切な支援を受けさせることができるのか、事
作成にあたって 6 法人の責任者とともに座談会に
前に訪問リストを整備するのかなど現実的な問題
参加し私が感じたのは、事業継続計画(BCP)に
が浮かび上がります。
実際の経験を反映させることの重要性です。
6 法人の中でも、福祉楽団については 2019 年
BCPは災害や緊急時に事業を中断せず、継続
の台風では被災者となり、今回の能登地震で支
できるようにするための計画です。2021年の介護
援する側を体験しています。この両側を知る同法
報酬改定をうけて、BCPの策定は 2024 年からす
人の視点は貴重です。リアル体験に基づく災害対
べての介護事業者に義務付けられました。同じ法
応は、私たちだけでなくこの冊子を手に取る方々
人内でも事業所ごとに計画を立てるため、本来で
が今後 BCPを策定するときに現実味を持たせる
あれば施設の置かれた地理的・環境的な条件に
ための大きな参考になると確信します。
合わせて計画が作られるべきものです。しかし、
被災経験のない法人や事業所は、あまりにも情報
が少なく、画一的なもので机上の空論にならざる
を得ません。
3
この冊子をどう活用するか
これまでの経験の蓄積が少ないからこそ、災
実際の災害現場で得られた教訓をどう活かすか
害を経験した事業所の知見が役に立ちます。今
──。例えば私たち小田原福祉会では、これを
回の介護福祉士派遣での具体的な体験が、BCP
活用した地域での勉強会の企画や、自治会や消
にリアリティを持たせられるきっかけになったと感
防団など地域の他の組織とも話し合いの場を持つ
じています。
こともできると思いました。災害時の支援だけで
なく、日常的な協力体制を築き、いざという時に
2
BCPとは何か─私たち小田原福祉会の視点
円滑に連携できる体制を強化することも必要です。
また、福祉避難所としての機能強化や、地域全体
での避難計画の検証にも、この冊子を役立ててい
現実味のあるBCPを作ろうと本気で考えたと
きたいと思います。
き、私たち小田原福祉会のように複数の小規模な
ここにまとめられた知見は、被災経験のない私
事業所が分散している法人では、特に不測の事態
たちが、現実的で実効性のあるBCPを策定する
における指示命令系統の確立が大きな課題だと感
ための重要な手がかりになります。全国の介護事
じました。例えば、現場の判断に頼る場面が増え
業者が活用し、次の災害に備えることで、より強
るため、エリアごとに自主的な判断を任せるか、
固な防災体制を築き、一人でも多くの生命が救わ
それとも中央からの指示を仰ぐべきかという基本
れることを祈っています。
37