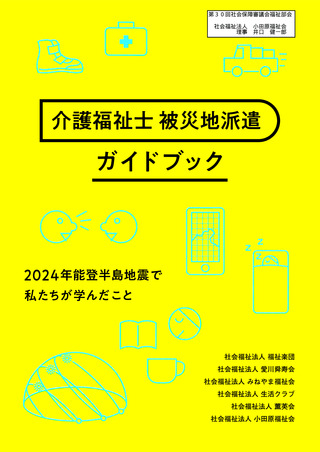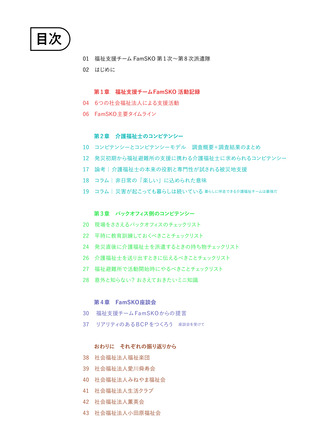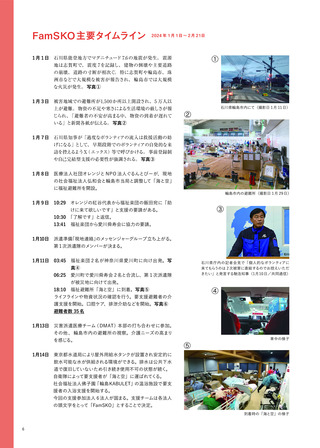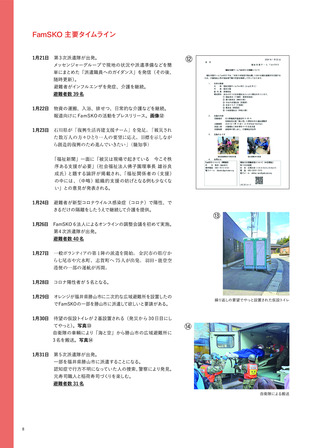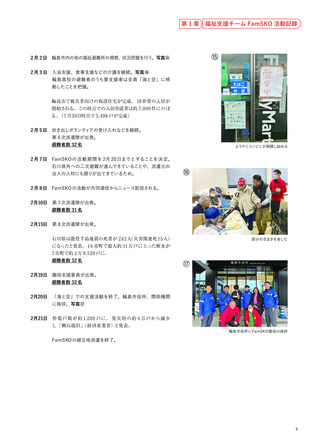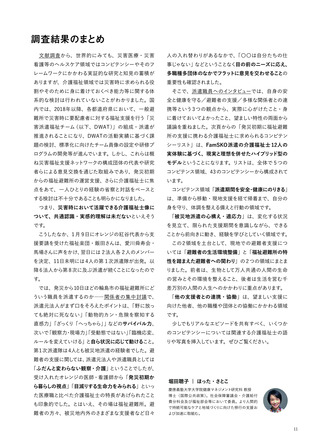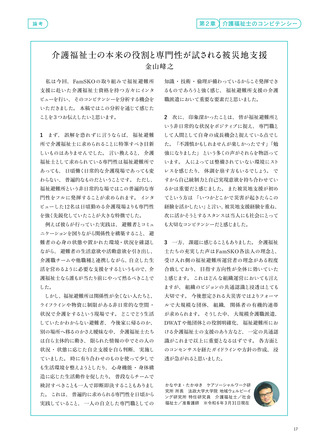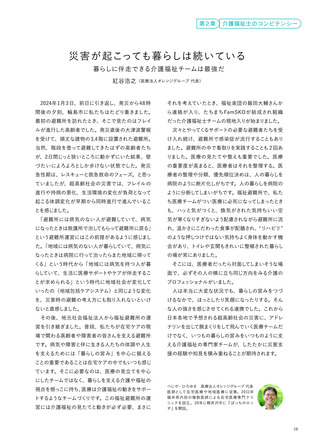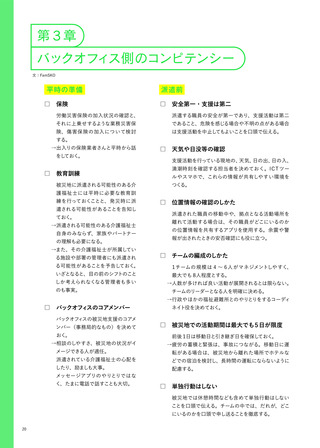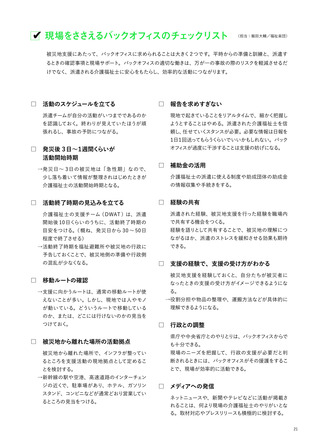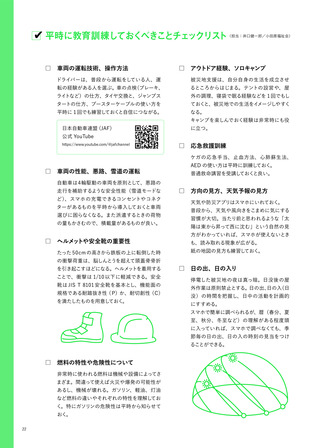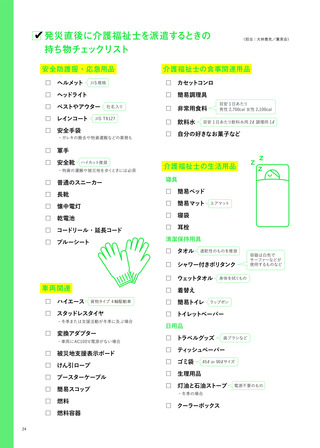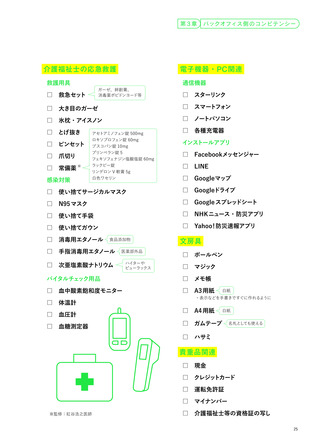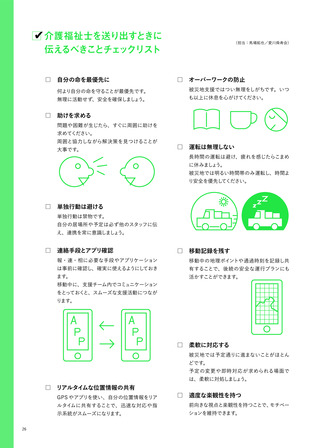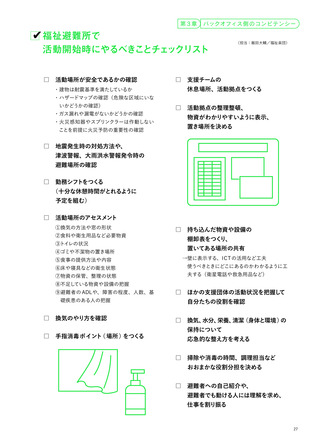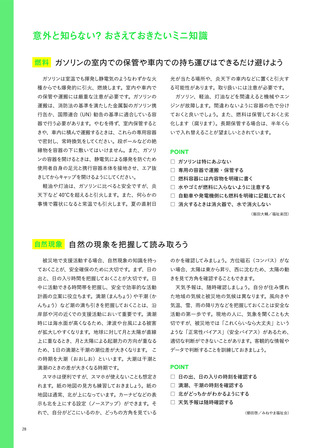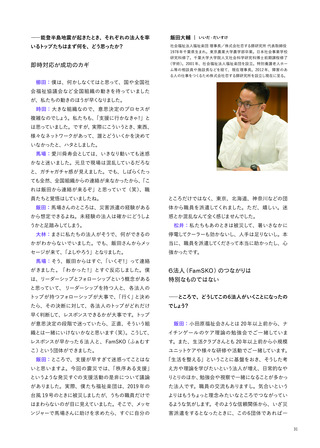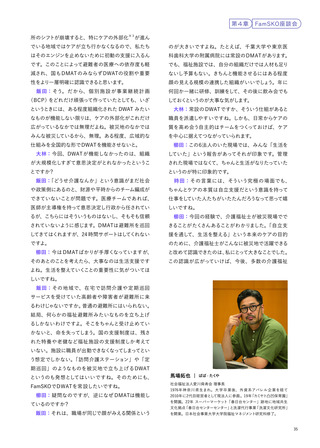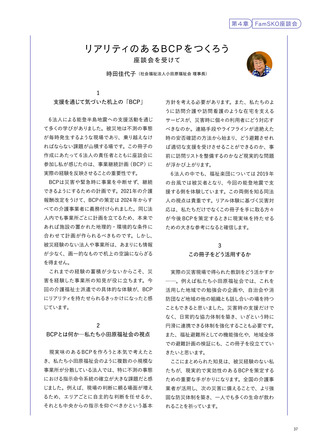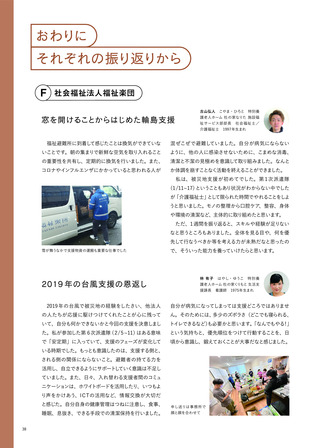よむ、つかう、まなぶ。
井口委員提出資料 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
コラム
非日常の「楽しい」に込められた意味
上垣喜寛(記者・映画監督)
「楽しい」という言葉は、時に軽い娯楽や瞬間的
の厳しい環境で、自らの限界に挑戦し、そこに新た
な喜びを連想させます。しかし、この言葉の持つ意
な発見や成長を見出すことで得られる深い満足感で
味にじっくりと向き合うと、もっと深い意味があること
す。アリストテレスは「エウダイモニア(真の幸福)
」
に気づかされます。古代の哲学者たちは、瞬間的な
を、人間が自身の能力を最大限に発揮し、徳を追求
快楽を超えた「幸福」について議論を交わしてきまし
することにあると考えました。介護福祉士たちが非日
た。彼らが追い求めたのは、学びや成長を通じて得
常で感じた充実感は、この考えに近い「幸福」の一
られる内面的な満足感でした。日常の行動や困難に
形態といえるのかもしれません。
直面する中で、自らの進化や成熟を感じるとき、初
めて本当の「楽しさ」が実感できるといいます。
現代でも、災害支援という非日常の厳しい現場で
介護福祉士たちが感じた「楽しい」は、この深い満
足感と一致しています。未知の環境に挑むことで得ら
れる思いがけない学び、そして日常で培ったスキル
が新たな状況で発揮される瞬間に感じられるもので
す。
令和 6 年能登半島地震の被災地に、6 法人の介護
福祉士たちは向かいました。ある介護福祉士は、被
災地に向かう道中で他愛のない会話を楽しみました。
非日常の被災地で日常を取り戻していく。ホッとできる環境
を取り戻す姿を見られるのは、悦びであり楽しさでもある。
初対面でありながら、同じ目的を共有し、共に支援
に向かう「仲間」としての結びつきが生まれていまし
た。現地では、通常は辛いはずの車中泊をも楽しむ
姿も見られました。何度も被災地支援に参加している
人は、「次はどんな状況か」と、未知の状況に心を
躍らせました。これらの姿勢は、単なる「助ける」こ
とを超え、自らの可能性を広げる機会として捉えてい
る証です。
一方で、派遣する側の経営者は、
「楽しい」という
感覚はさておき、被災地に入ってもポジティブな姿勢
を持ち続けられる職員を選びました。派遣される職
職員の活動記録に残る 1 枚の写真。避難者が描いてくれた似
顔絵だ。
「楽しい」の一言の背景には、現地での様々な出会
いや交流の記憶がある。
員に求められる資質として、コミュニケーション能力
や新しい経験から学び取ろうとする意欲が重要視さ
れています。これは、厳しい現場で成果を出すため
に欠かせない要素です。
介護福祉士たちが語る「楽しい」という言葉は、
日常的な娯楽とは異なります。被災地という非日常
18
うえがき・よしひろ 記者・映画監督
2008 年からフリー記者として取材を続ける。14
年に NPO法人「自伐型林業推進協会」を設立。
映画『 壊れゆく森から、持続する森へ 』を監修。
非日常の「楽しい」に込められた意味
上垣喜寛(記者・映画監督)
「楽しい」という言葉は、時に軽い娯楽や瞬間的
の厳しい環境で、自らの限界に挑戦し、そこに新た
な喜びを連想させます。しかし、この言葉の持つ意
な発見や成長を見出すことで得られる深い満足感で
味にじっくりと向き合うと、もっと深い意味があること
す。アリストテレスは「エウダイモニア(真の幸福)
」
に気づかされます。古代の哲学者たちは、瞬間的な
を、人間が自身の能力を最大限に発揮し、徳を追求
快楽を超えた「幸福」について議論を交わしてきまし
することにあると考えました。介護福祉士たちが非日
た。彼らが追い求めたのは、学びや成長を通じて得
常で感じた充実感は、この考えに近い「幸福」の一
られる内面的な満足感でした。日常の行動や困難に
形態といえるのかもしれません。
直面する中で、自らの進化や成熟を感じるとき、初
めて本当の「楽しさ」が実感できるといいます。
現代でも、災害支援という非日常の厳しい現場で
介護福祉士たちが感じた「楽しい」は、この深い満
足感と一致しています。未知の環境に挑むことで得ら
れる思いがけない学び、そして日常で培ったスキル
が新たな状況で発揮される瞬間に感じられるもので
す。
令和 6 年能登半島地震の被災地に、6 法人の介護
福祉士たちは向かいました。ある介護福祉士は、被
災地に向かう道中で他愛のない会話を楽しみました。
非日常の被災地で日常を取り戻していく。ホッとできる環境
を取り戻す姿を見られるのは、悦びであり楽しさでもある。
初対面でありながら、同じ目的を共有し、共に支援
に向かう「仲間」としての結びつきが生まれていまし
た。現地では、通常は辛いはずの車中泊をも楽しむ
姿も見られました。何度も被災地支援に参加している
人は、「次はどんな状況か」と、未知の状況に心を
躍らせました。これらの姿勢は、単なる「助ける」こ
とを超え、自らの可能性を広げる機会として捉えてい
る証です。
一方で、派遣する側の経営者は、
「楽しい」という
感覚はさておき、被災地に入ってもポジティブな姿勢
を持ち続けられる職員を選びました。派遣される職
職員の活動記録に残る 1 枚の写真。避難者が描いてくれた似
顔絵だ。
「楽しい」の一言の背景には、現地での様々な出会
いや交流の記憶がある。
員に求められる資質として、コミュニケーション能力
や新しい経験から学び取ろうとする意欲が重要視さ
れています。これは、厳しい現場で成果を出すため
に欠かせない要素です。
介護福祉士たちが語る「楽しい」という言葉は、
日常的な娯楽とは異なります。被災地という非日常
18
うえがき・よしひろ 記者・映画監督
2008 年からフリー記者として取材を続ける。14
年に NPO法人「自伐型林業推進協会」を設立。
映画『 壊れゆく森から、持続する森へ 』を監修。