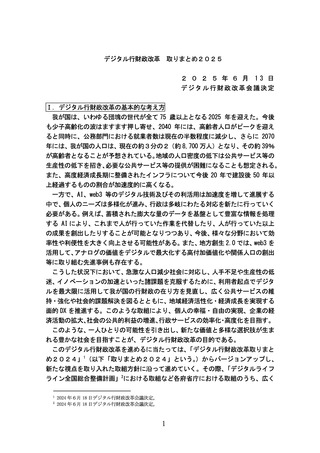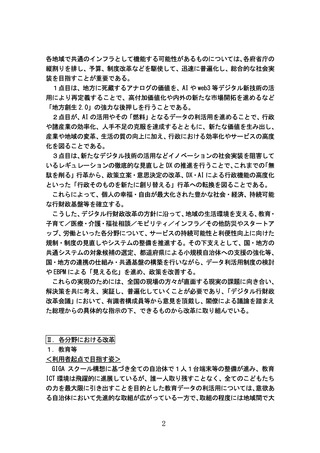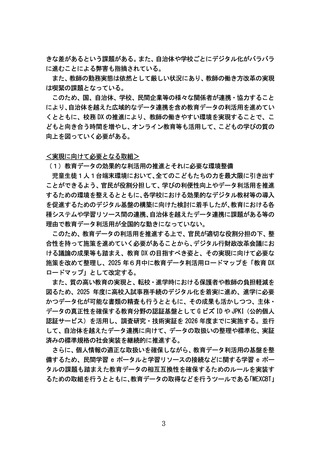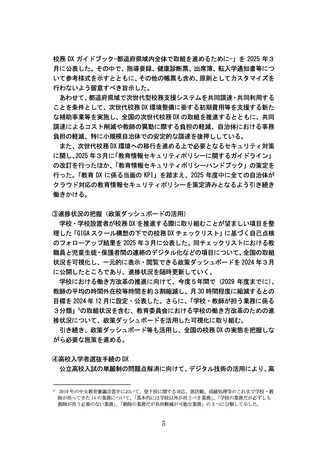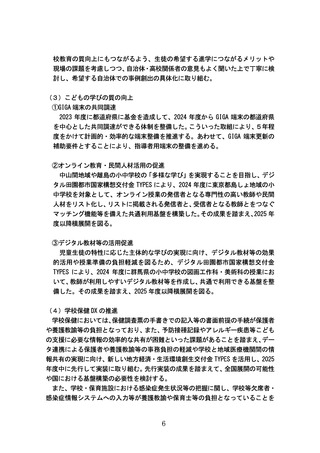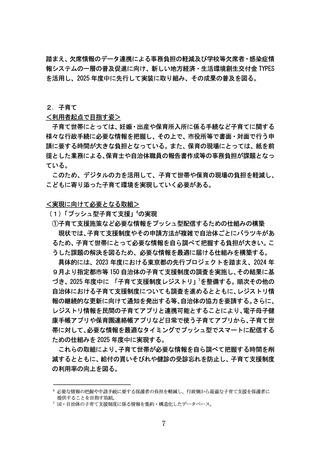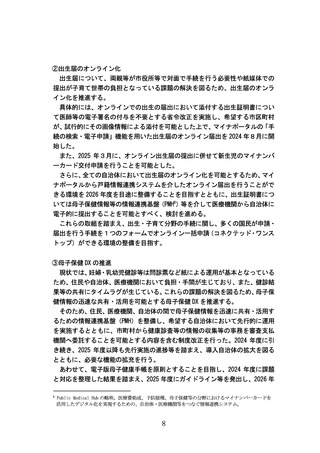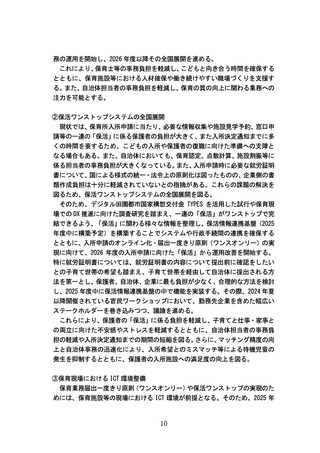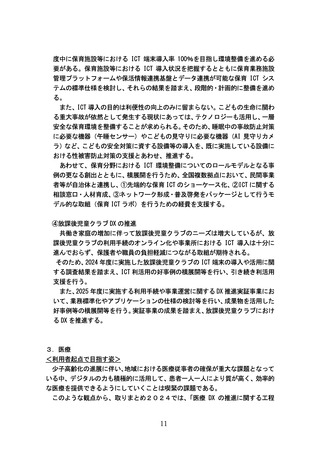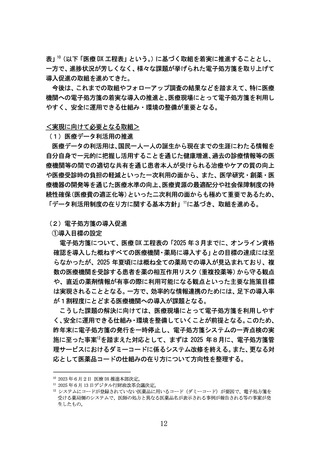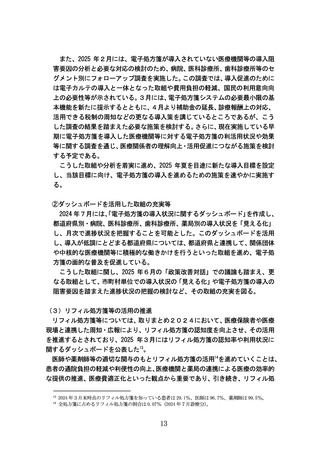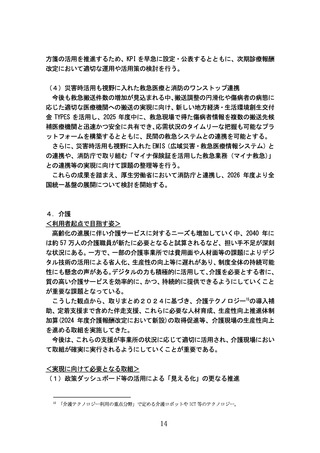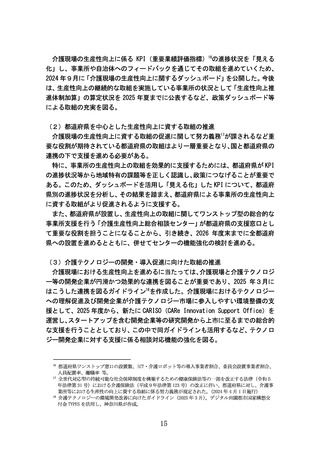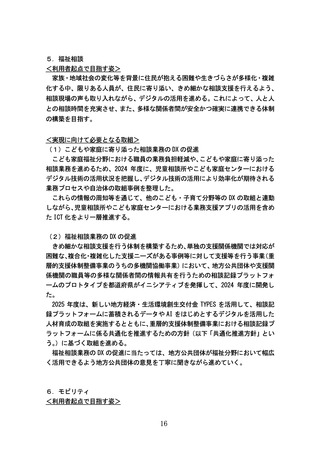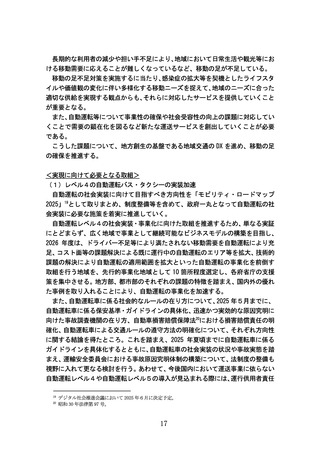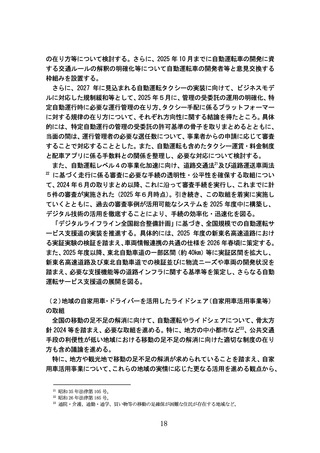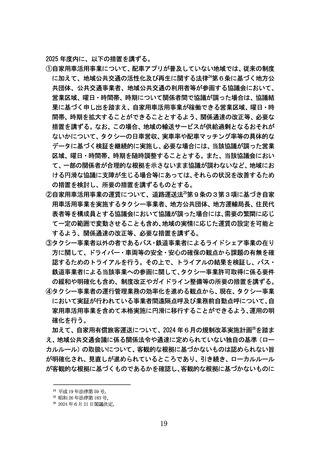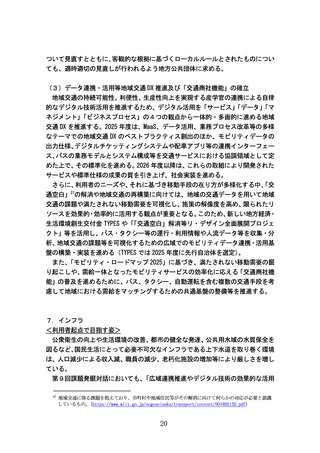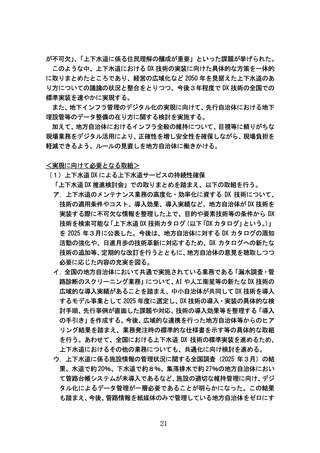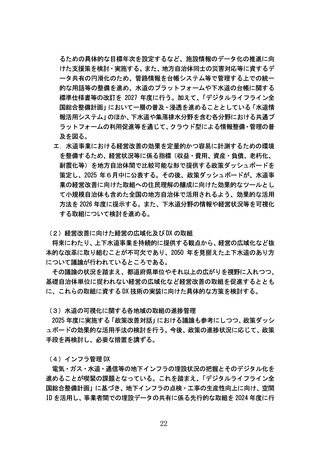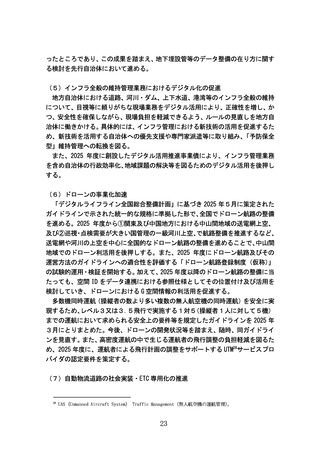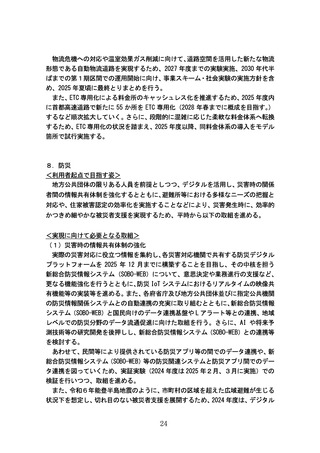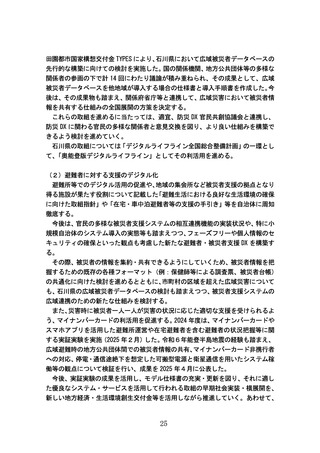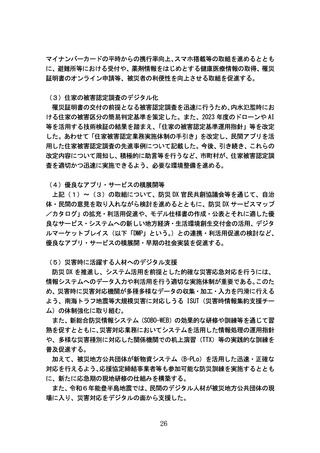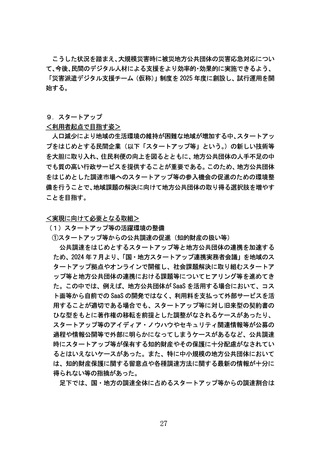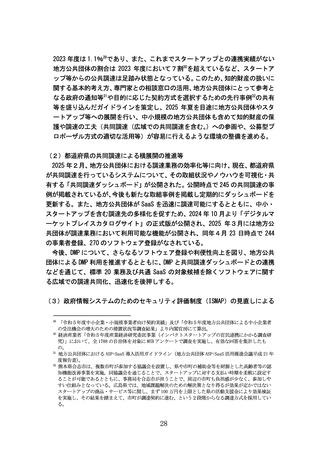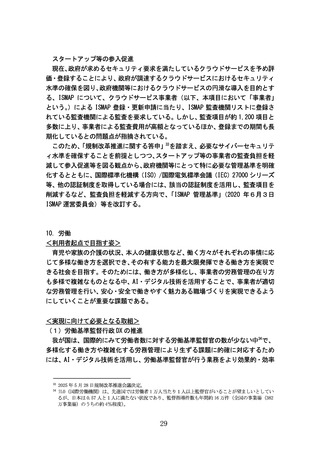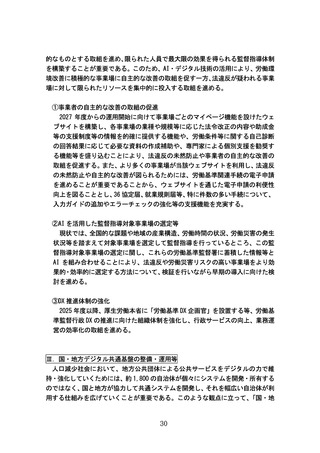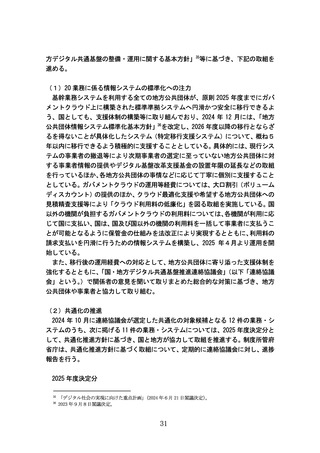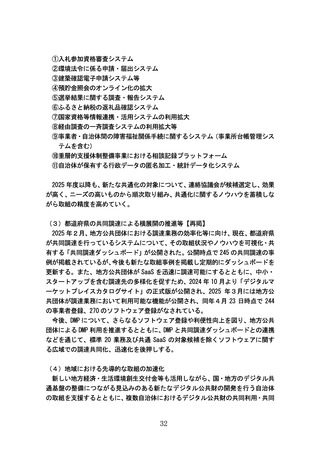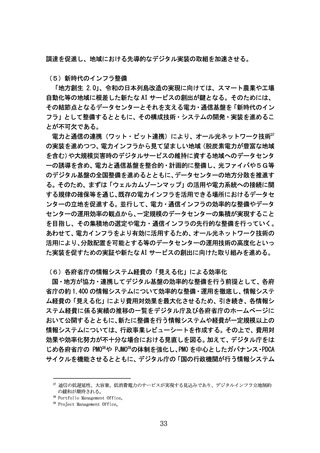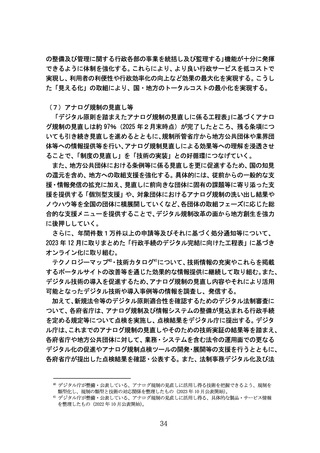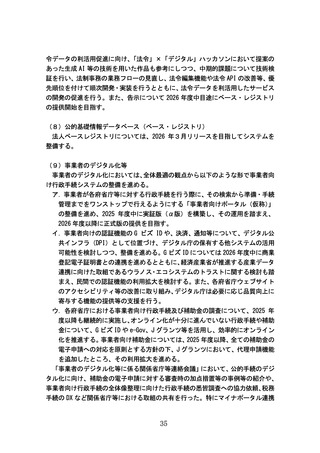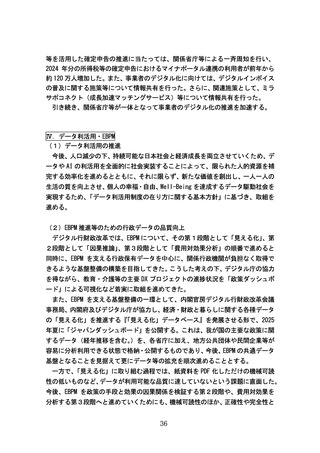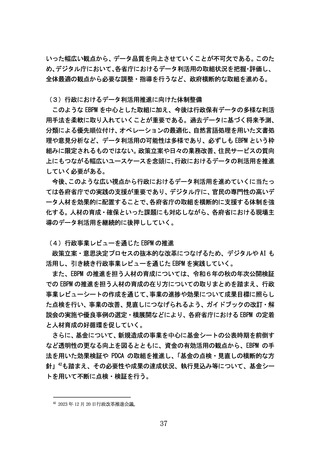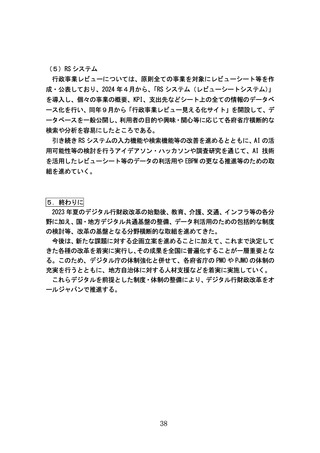よむ、つかう、まなぶ。
デジタル行財政改革 取りまとめ2025(令和7年6月13日デジタル行財政改革会議決定) 本文 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html |
| 出典情報 | デジタル行財政改革 取りまとめ2025(6/13)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
マイナンバーカードの平時からの携行率向上、スマホ搭載等の取組を進めるととも
に、避難所等における受付や、薬剤情報をはじめとする健康医療情報の取得、罹災
証明書のオンライン申請等、被災者の利便性を向上させる取組を促進する。
(3)住家の被害認定調査のデジタル化
罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査を迅速に行うため、内水氾濫時にお
ける住家の被害区分の簡易判定基準を策定した。また、2023 年度のドローンや AI
等を活用する技術検証の結果を踏まえ、
「住家の被害認定基準運用指針」等を改定
した。あわせて「住家被害認定業務実施体制の手引き」を改定し、民間アプリを活
用した住家被害認定調査の先進事例について記載した。今後、引き続き、これらの
改定内容について周知し、積極的に助言等を行うなど、市町村が、住家被害認定調
査を適切かつ迅速に実施できるよう、必要な環境整備を進める。
(4)優良なアプリ・サービスの横展開等
上記(1)~(3)の取組について、防災 DX 官民共創協議会等を通じて、自治
体・民間の意見を取り入れながら検討を進めるとともに、防災 DX サービスマップ
/カタログ」の拡充・利活用促進や、モデル仕様書の作成・公表とそれに適した優
良なサービス・システムへの新しい地方経済・生活環境創生交付金の活用、デジタ
ルマーケットプレイス(以下「DMP」という。
)との連携・利活用促進の検討など、
優良なアプリ・サービスの横展開・早期の社会実装を促進する。
(5)災害時に活躍する人材へのデジタル支援
防災 DX を推進し、システム活用を前提とした的確な災害応急対応を行うには、
情報システムへのデータ入力や利活用を行う適切な実施体制が重要である。このた
め、災害時に災害対応機関が多種多様なデータの収集・加工・入力を円滑に行える
よう、南海トラフ地震等大規模災害に対応しうる ISUT(災害時情報集約支援チー
ム)の体制強化に取り組む。
また、新総合防災情報システム(SOBO-WEB)の効果的な研修や訓練等を通じて習
熟を促すとともに、災害対応業務においてシステムを活用した情報処理の運用指針
や、多様な災害種別に対応した関係機関での机上演習(TTX)等の実践的な訓練を
普及促進する。
加えて、被災地方公共団体が新物資システム(B-PLo)を活用した迅速・正確な
対応を行えるよう、応援協定締結事業者等も参加可能な防災訓練を実施するととも
に、新たに応急期の現地研修の仕組みを構築する。
また、令和6年能登半島地震では、民間のデジタル人材が被災地方公共団体の現
場に入り、災害対応をデジタルの面から支援した。
26
に、避難所等における受付や、薬剤情報をはじめとする健康医療情報の取得、罹災
証明書のオンライン申請等、被災者の利便性を向上させる取組を促進する。
(3)住家の被害認定調査のデジタル化
罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査を迅速に行うため、内水氾濫時にお
ける住家の被害区分の簡易判定基準を策定した。また、2023 年度のドローンや AI
等を活用する技術検証の結果を踏まえ、
「住家の被害認定基準運用指針」等を改定
した。あわせて「住家被害認定業務実施体制の手引き」を改定し、民間アプリを活
用した住家被害認定調査の先進事例について記載した。今後、引き続き、これらの
改定内容について周知し、積極的に助言等を行うなど、市町村が、住家被害認定調
査を適切かつ迅速に実施できるよう、必要な環境整備を進める。
(4)優良なアプリ・サービスの横展開等
上記(1)~(3)の取組について、防災 DX 官民共創協議会等を通じて、自治
体・民間の意見を取り入れながら検討を進めるとともに、防災 DX サービスマップ
/カタログ」の拡充・利活用促進や、モデル仕様書の作成・公表とそれに適した優
良なサービス・システムへの新しい地方経済・生活環境創生交付金の活用、デジタ
ルマーケットプレイス(以下「DMP」という。
)との連携・利活用促進の検討など、
優良なアプリ・サービスの横展開・早期の社会実装を促進する。
(5)災害時に活躍する人材へのデジタル支援
防災 DX を推進し、システム活用を前提とした的確な災害応急対応を行うには、
情報システムへのデータ入力や利活用を行う適切な実施体制が重要である。このた
め、災害時に災害対応機関が多種多様なデータの収集・加工・入力を円滑に行える
よう、南海トラフ地震等大規模災害に対応しうる ISUT(災害時情報集約支援チー
ム)の体制強化に取り組む。
また、新総合防災情報システム(SOBO-WEB)の効果的な研修や訓練等を通じて習
熟を促すとともに、災害対応業務においてシステムを活用した情報処理の運用指針
や、多様な災害種別に対応した関係機関での机上演習(TTX)等の実践的な訓練を
普及促進する。
加えて、被災地方公共団体が新物資システム(B-PLo)を活用した迅速・正確な
対応を行えるよう、応援協定締結事業者等も参加可能な防災訓練を実施するととも
に、新たに応急期の現地研修の仕組みを構築する。
また、令和6年能登半島地震では、民間のデジタル人材が被災地方公共団体の現
場に入り、災害対応をデジタルの面から支援した。
26