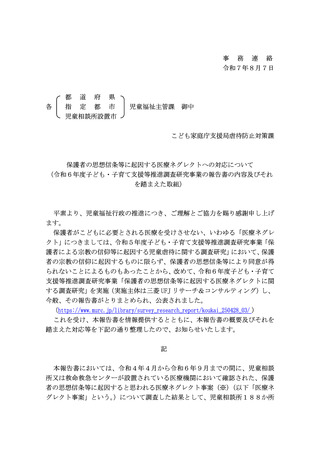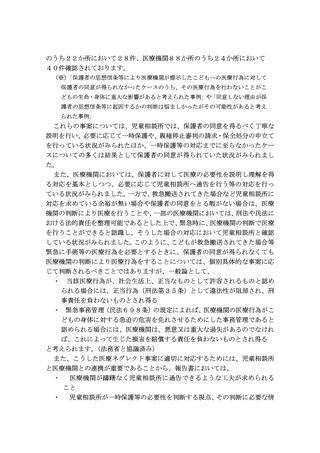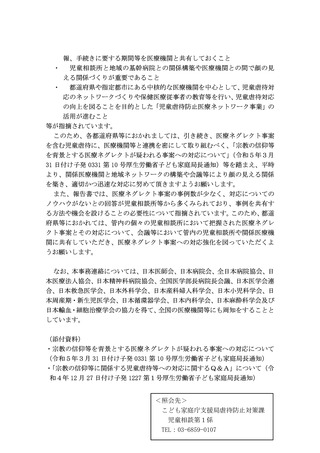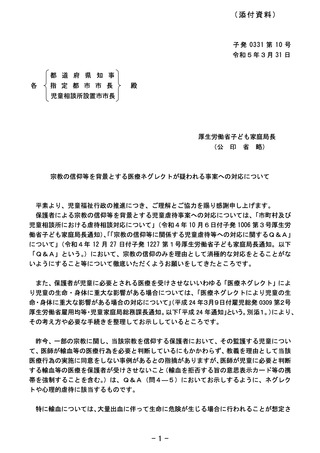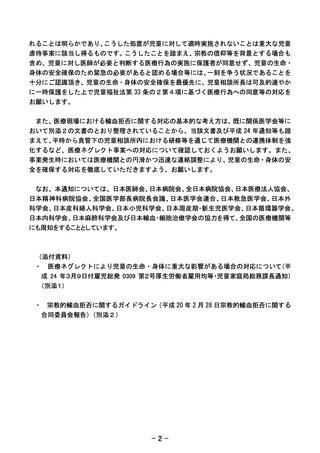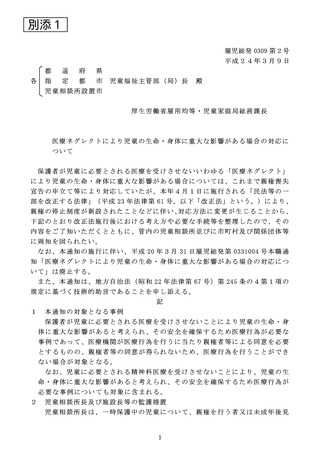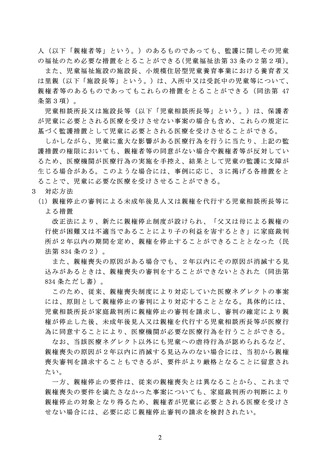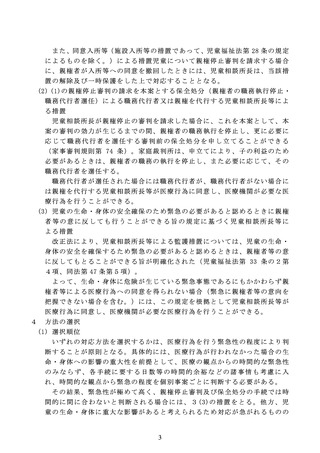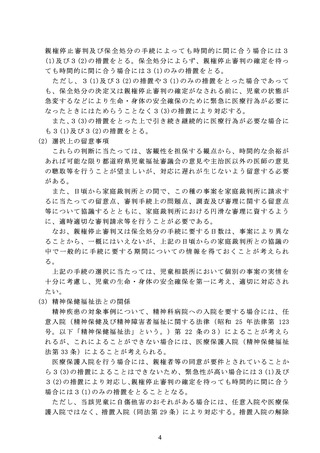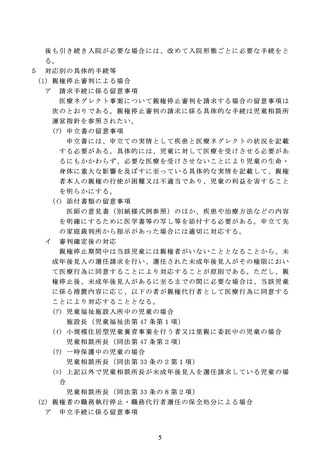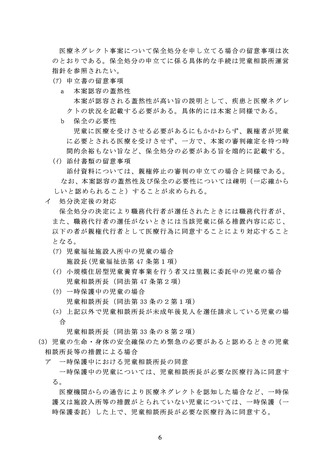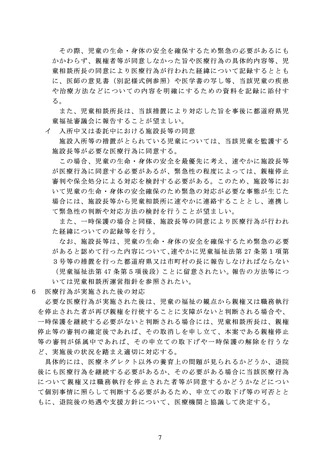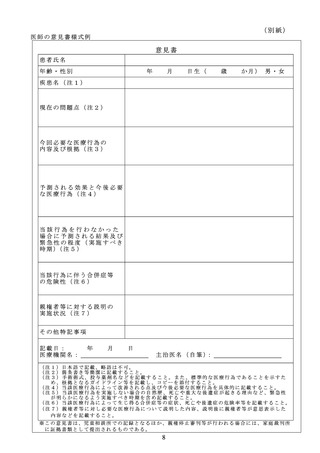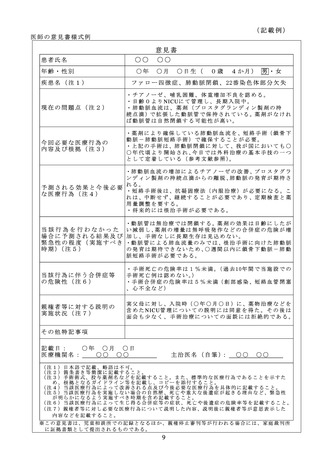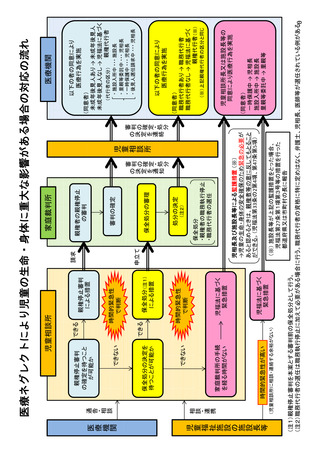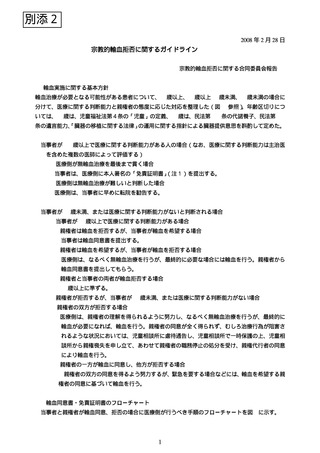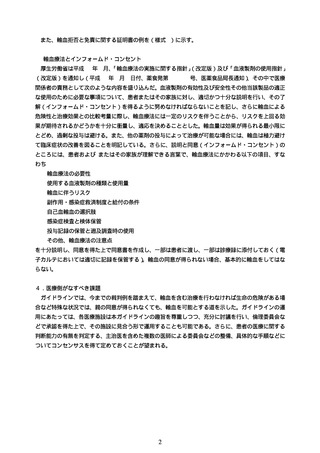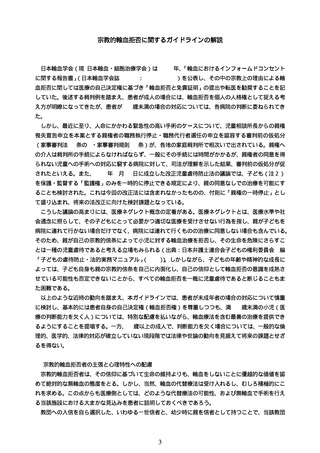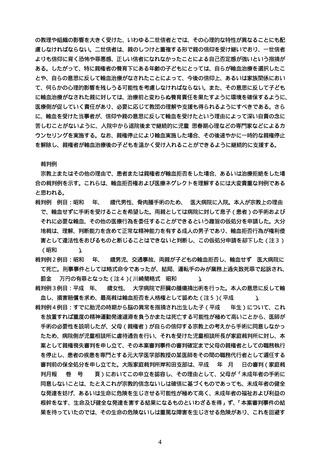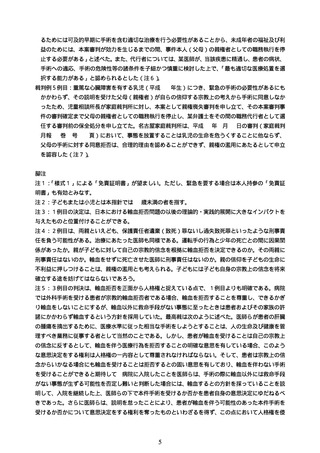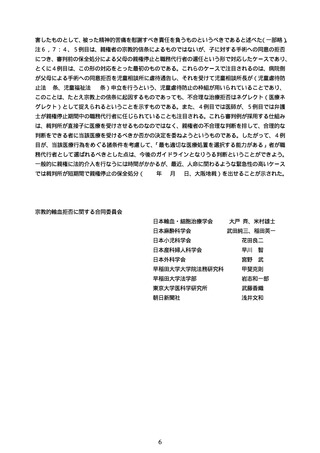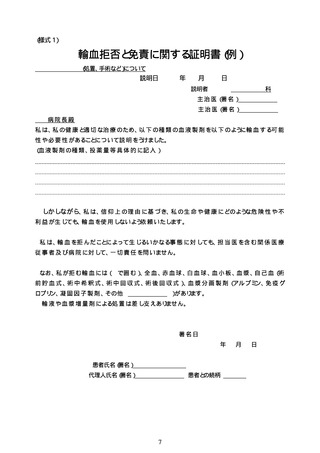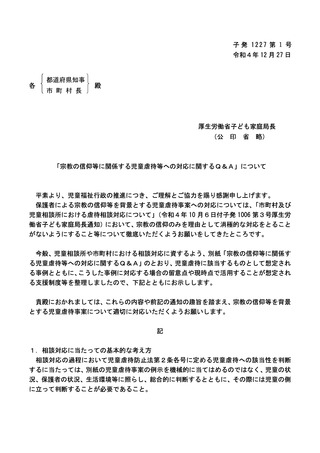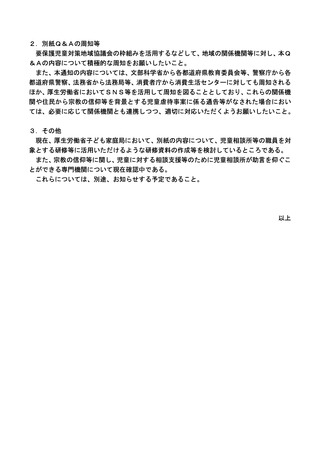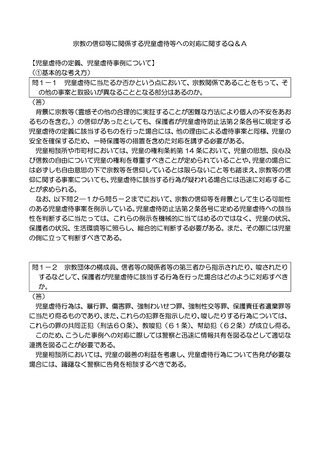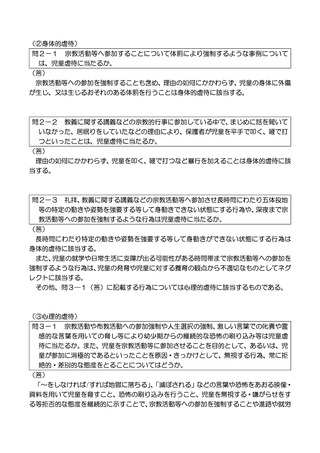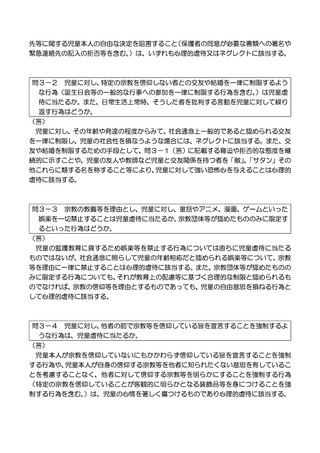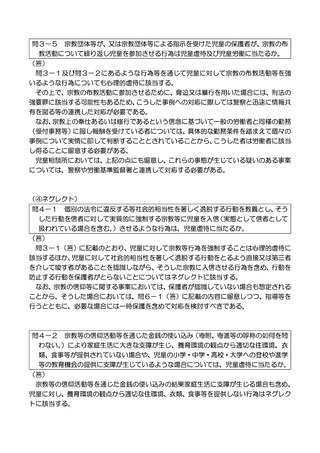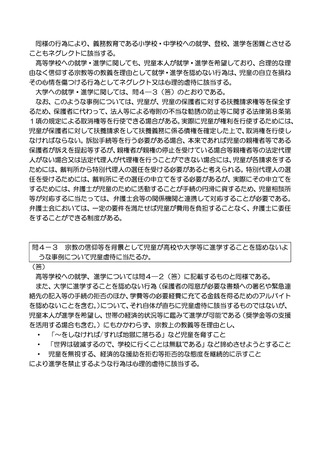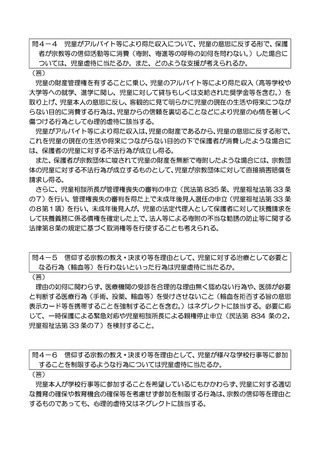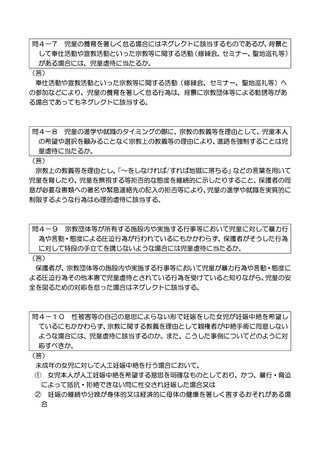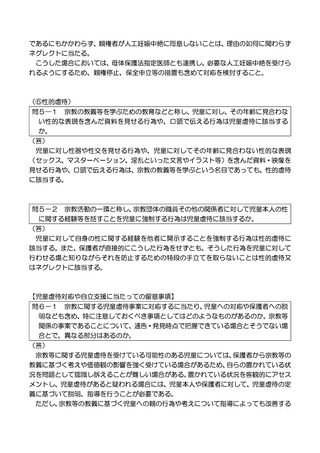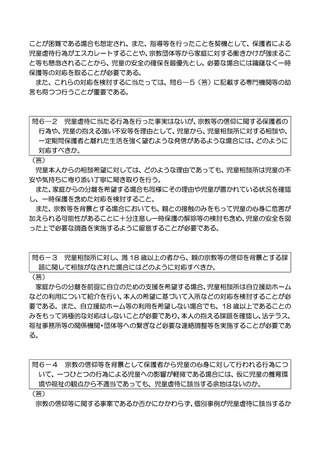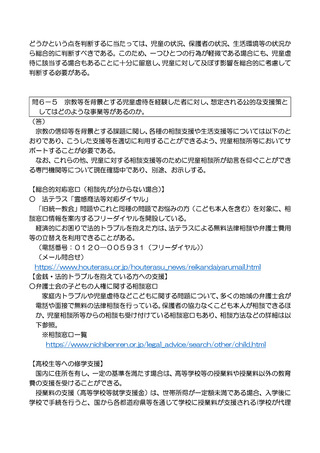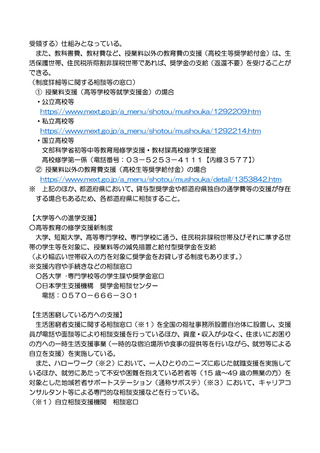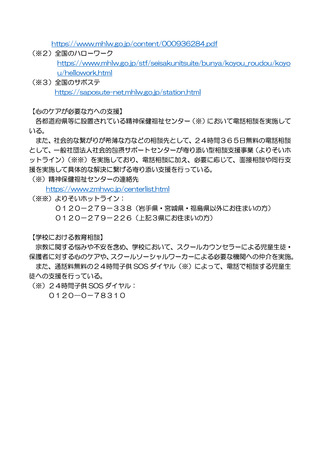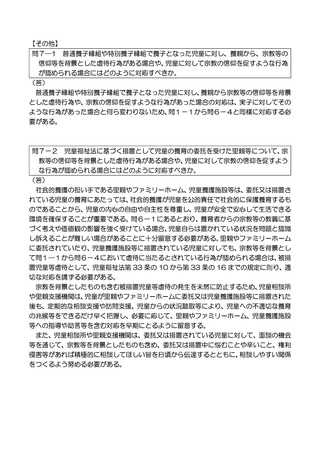よむ、つかう、まなぶ。
保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【その他】
問7―1 普通養子縁組や特別養子縁組で養子となった児童に対し、養親から、宗教等の
信仰等を背景とした虐待行為がある場合や、児童に対して宗教の信仰を促すような行為
が認められる場合にはどのように対応すべきか。
(答)
普通養子縁組や特別養子縁組で養子となった児童に対し、養親から宗教等の信仰等を背景
とした虐待行為や、宗教の信仰を促すような行為があった場合の対応は、実子に対してその
ような行為があった場合と何ら変わりないため、問1-1から問6-4と同様に対応する必
要がある。
問7-2 児童福祉法に基づく措置として児童の養育の委託を受けた里親等について、宗
教等の信仰等を背景とした虐待行為がある場合や、児童に対して宗教の信仰を促すよう
な行為が認められる場合にはどのように対応すべきか。
(答)
社会的養護の担い手である里親やファミリーホーム、児童養護施設等は、委託又は措置さ
れている児童の養育にあたっては、社会的養護が児童を公的責任で社会的に保護養育するも
のであることから、児童の内心の自由や自主性を尊重し、児童が安全で安心して生活できる
環境を確保することが重要である。問6-1にあるとおり、養育者からの宗教等の教義に基
づく考えや価値観の影響を強く受けている場合、児童自らは置かれている状況を問題と認識
し訴えることが難しい場合があることに十分留意する必要がある。里親やファミリーホーム
に委託されていたり、児童養護施設等に措置されている児童に対しても、宗教等を背景とし
て問1―1から問6-4において虐待に当たるとされている行為が認められる場合は、被措
置児童等虐待として、児童福祉法第 33 条の 10 から第 33 条の 16 までの規定に則り、適
切な対応を講ずる必要がある。
宗教を背景としたものも含む被措置児童等虐待の発生を未然に防止するため、児童相談所
や里親支援機関は、児童が里親やファミリーホームに委託又は児童養護施設等に措置された
後も、定期的な相談支援や訪問支援、児童からの状況聴取等により、児童への不適切な養育
の兆候等をできるだけ早く把握し、必要に応じて、里親やファミリーホーム、児童養護施設
等への指導や助言等を含む対応を早期にとるように留意する。
また、児童相談所や里親支援機関は、委託又は措置されている児童に対して、面談の機会
等を通じて、宗教等を背景としたものも含め、委託又は措置中に悩むことや辛いこと、権利
侵害等があれば積極的に相談してほしい旨を日頃から伝達するとともに、相談しやすい関係
をつくるよう努める必要がある。
問7―1 普通養子縁組や特別養子縁組で養子となった児童に対し、養親から、宗教等の
信仰等を背景とした虐待行為がある場合や、児童に対して宗教の信仰を促すような行為
が認められる場合にはどのように対応すべきか。
(答)
普通養子縁組や特別養子縁組で養子となった児童に対し、養親から宗教等の信仰等を背景
とした虐待行為や、宗教の信仰を促すような行為があった場合の対応は、実子に対してその
ような行為があった場合と何ら変わりないため、問1-1から問6-4と同様に対応する必
要がある。
問7-2 児童福祉法に基づく措置として児童の養育の委託を受けた里親等について、宗
教等の信仰等を背景とした虐待行為がある場合や、児童に対して宗教の信仰を促すよう
な行為が認められる場合にはどのように対応すべきか。
(答)
社会的養護の担い手である里親やファミリーホーム、児童養護施設等は、委託又は措置さ
れている児童の養育にあたっては、社会的養護が児童を公的責任で社会的に保護養育するも
のであることから、児童の内心の自由や自主性を尊重し、児童が安全で安心して生活できる
環境を確保することが重要である。問6-1にあるとおり、養育者からの宗教等の教義に基
づく考えや価値観の影響を強く受けている場合、児童自らは置かれている状況を問題と認識
し訴えることが難しい場合があることに十分留意する必要がある。里親やファミリーホーム
に委託されていたり、児童養護施設等に措置されている児童に対しても、宗教等を背景とし
て問1―1から問6-4において虐待に当たるとされている行為が認められる場合は、被措
置児童等虐待として、児童福祉法第 33 条の 10 から第 33 条の 16 までの規定に則り、適
切な対応を講ずる必要がある。
宗教を背景としたものも含む被措置児童等虐待の発生を未然に防止するため、児童相談所
や里親支援機関は、児童が里親やファミリーホームに委託又は児童養護施設等に措置された
後も、定期的な相談支援や訪問支援、児童からの状況聴取等により、児童への不適切な養育
の兆候等をできるだけ早く把握し、必要に応じて、里親やファミリーホーム、児童養護施設
等への指導や助言等を含む対応を早期にとるように留意する。
また、児童相談所や里親支援機関は、委託又は措置されている児童に対して、面談の機会
等を通じて、宗教等を背景としたものも含め、委託又は措置中に悩むことや辛いこと、権利
侵害等があれば積極的に相談してほしい旨を日頃から伝達するとともに、相談しやすい関係
をつくるよう努める必要がある。