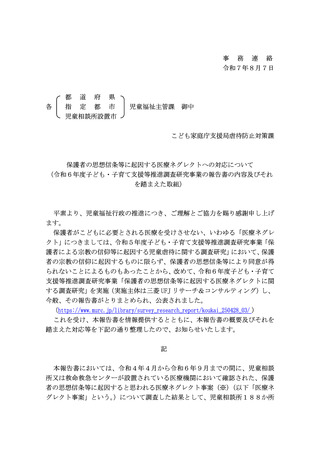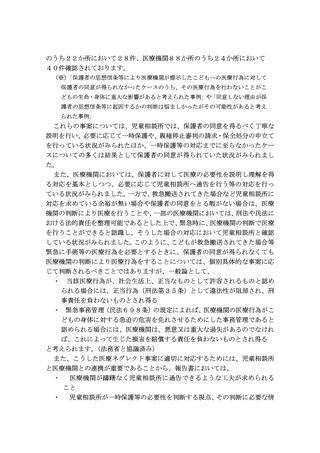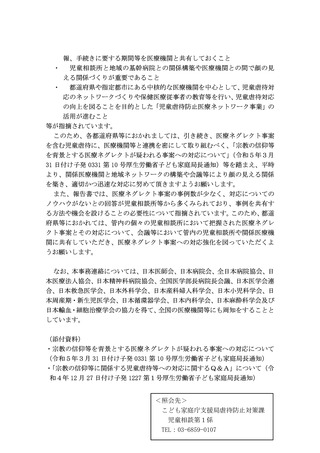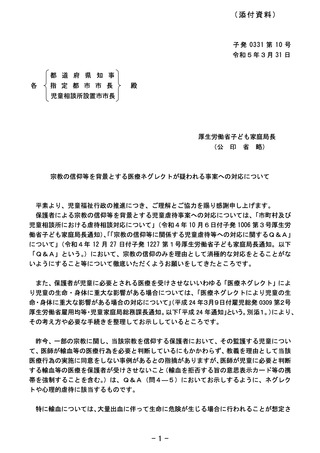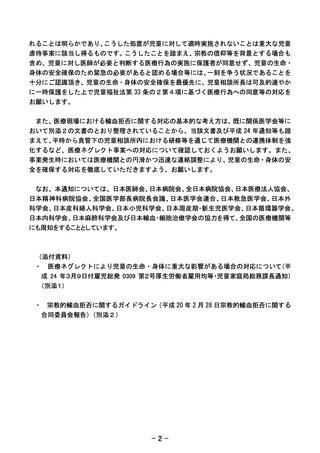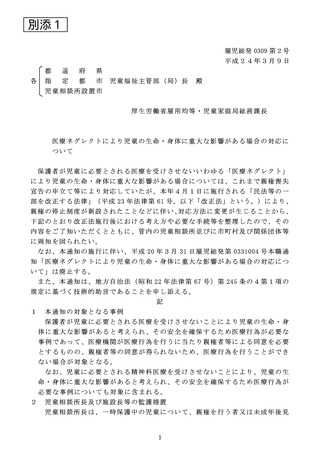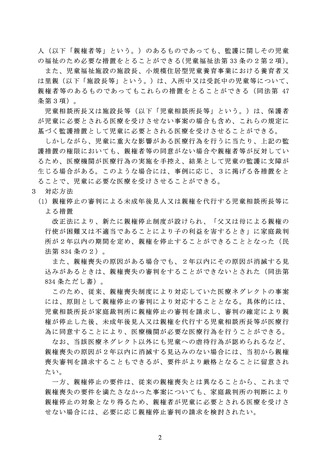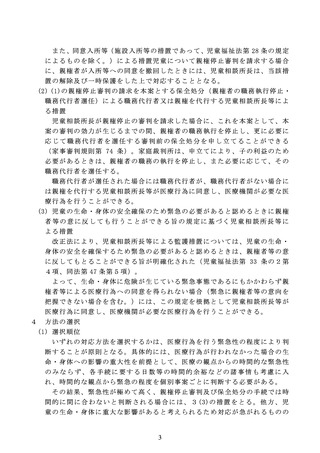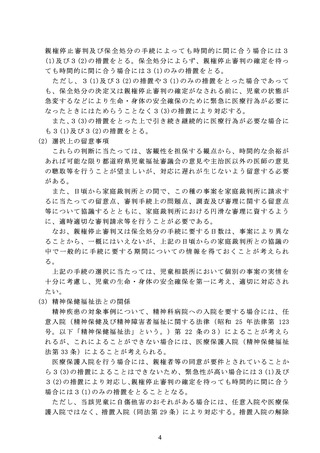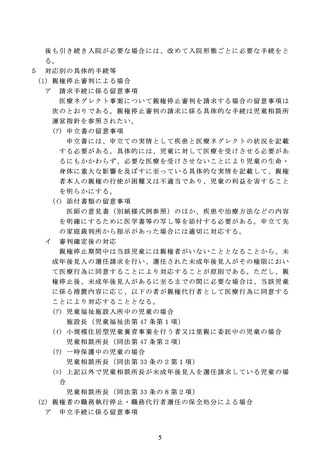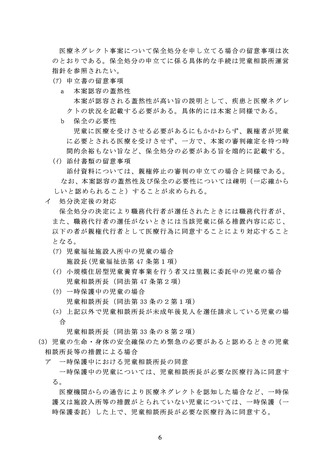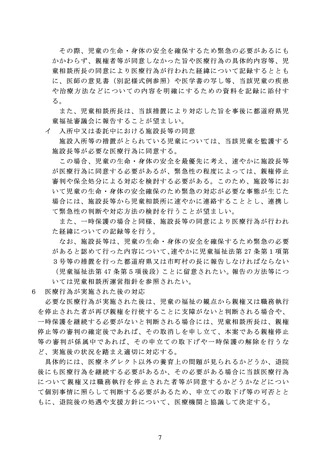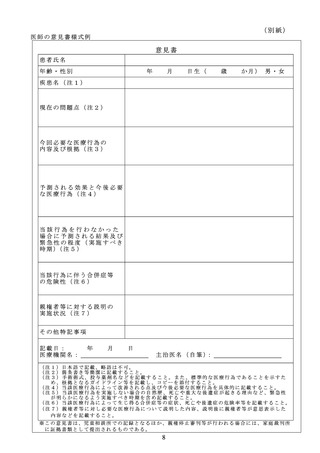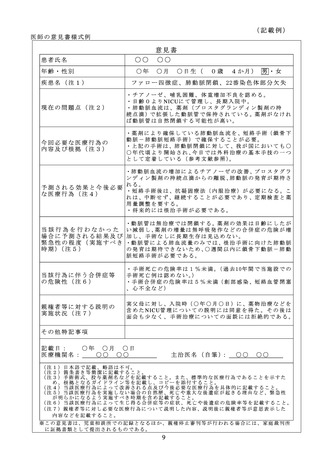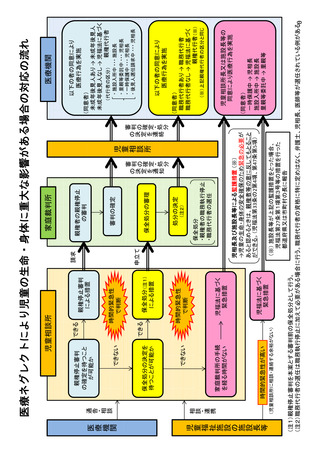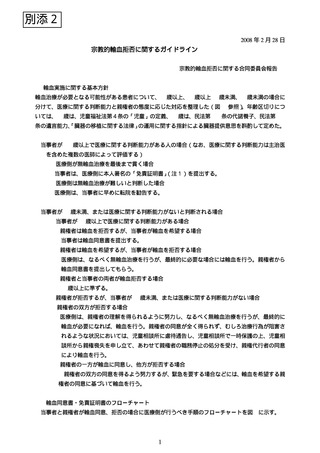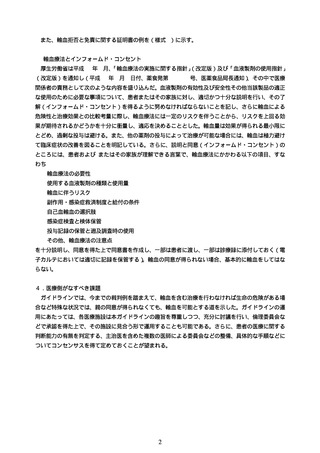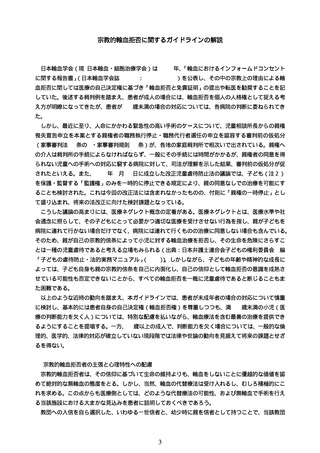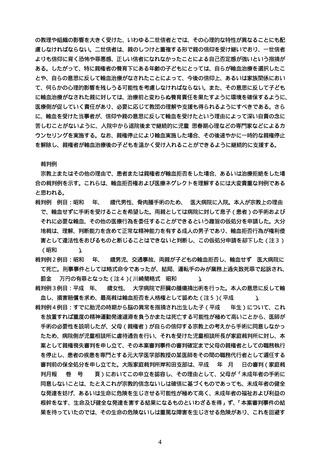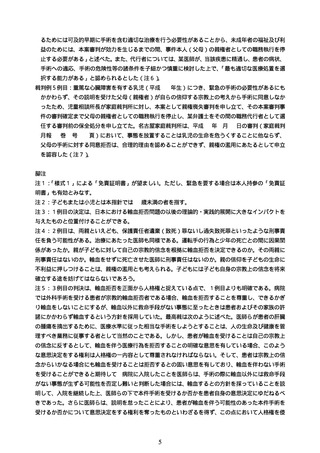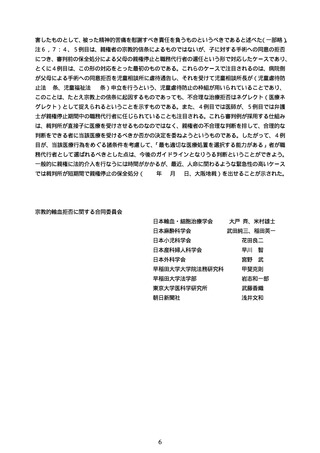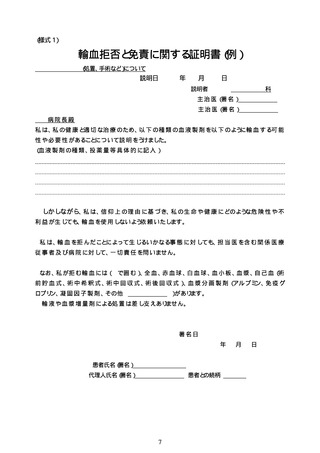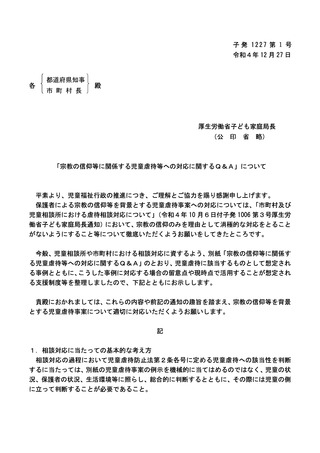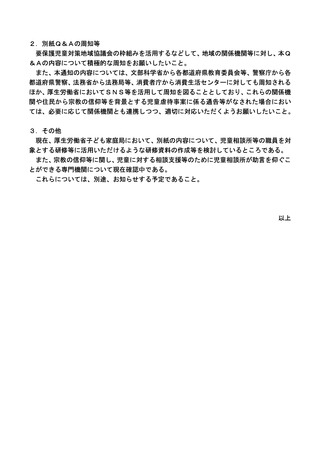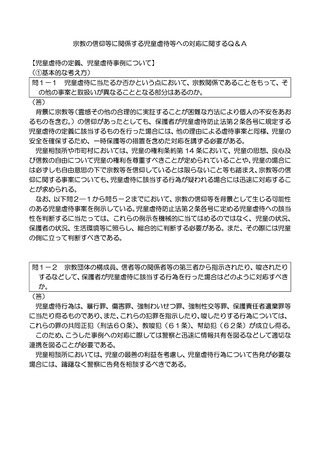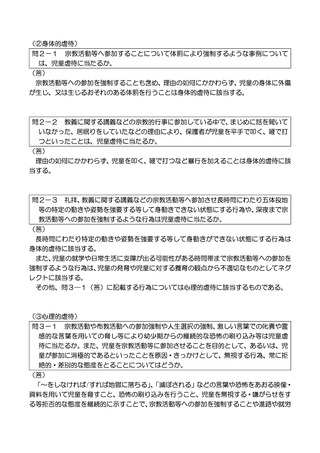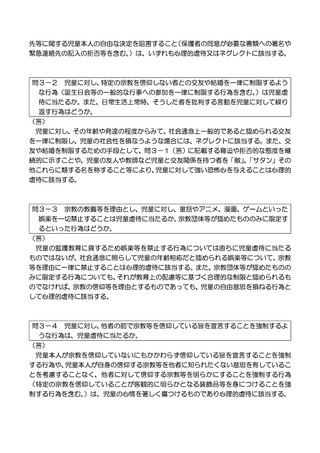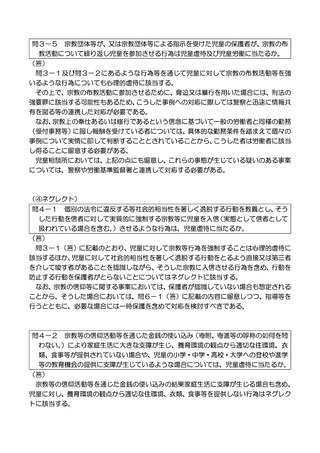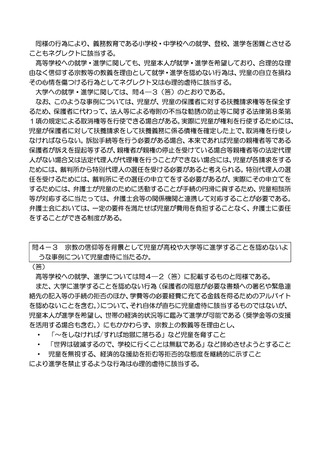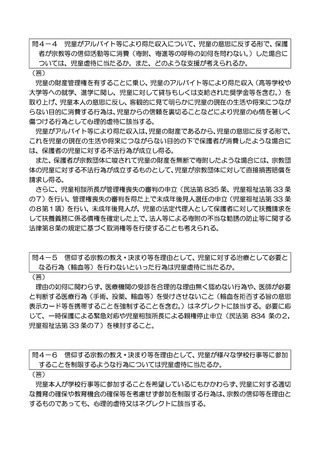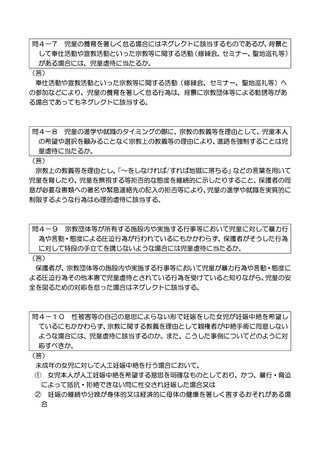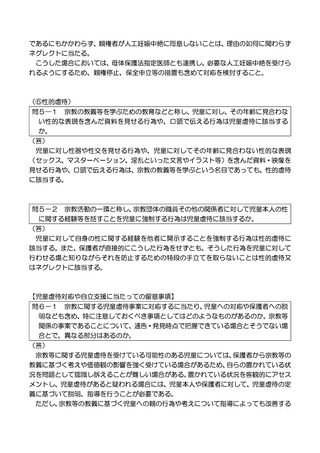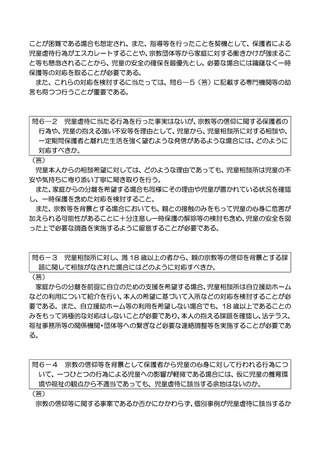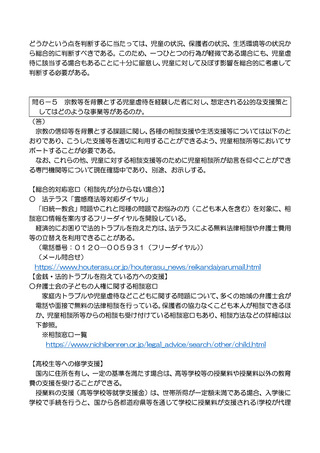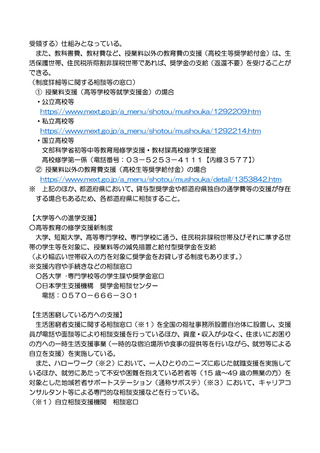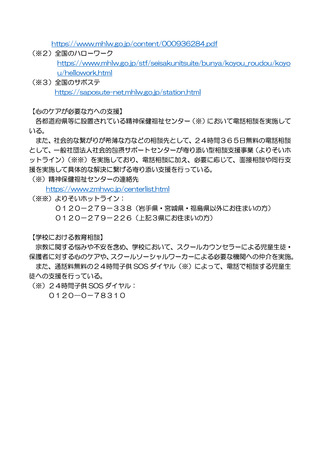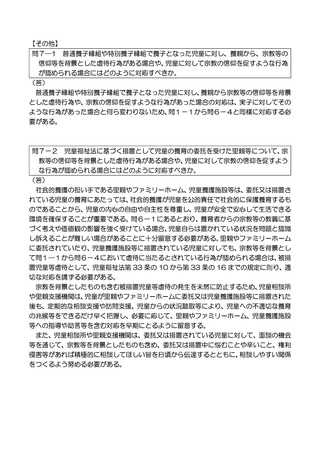よむ、つかう、まなぶ。
保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別添2
2008 年 2 月 28 日
宗教的輸血拒否に関するガイドライン
宗教的輸血拒否に関する合同委員会報告
1. 輸血実施に関する基本方針
輸血治療が必要となる可能性がある患者について、18 歳以上、15 歳以上 18 歳未満、15 歳未満の場合に
分けて、医療に関する判断能力と親権者の態度に応じた対応を整理した(図 1 参照)
。年齢区切りにつ
いては、18 歳は、児童福祉法第4条の「児童」の定義、15 歳は、民法第 797 条の代諾養子、民法第 961
条の遺言能力、
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針による臓器提供意思を斟酌して定めた。
1)当事者が 18 歳以上で医療に関する判断能力がある人の場合(なお、医療に関する判断能力は主治医
を含めた複数の医師によって評価する)
(1) 医療側が無輸血治療を最後まで貫く場合
当事者は、医療側に本人署名の「免責証明書」
(注1)を提出する。
(2) 医療側は無輸血治療が難しいと判断した場合
医療側は、当事者に早めに転院を勧告する。
2)当事者が 18 歳未満、または医療に関する判断能力がないと判断される場合
(1) 当事者が 15 歳以上で医療に関する判断能力がある場合
① 親権者は輸血を拒否するが、当事者が輸血を希望する場合
当事者は輸血同意書を提出する。
② 親権者は輸血を希望するが、当事者が輸血を拒否する場合
医療側は、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に必要な場合には輸血を行う。親権者から
輸血同意書を提出してもらう。
③ 親権者と当事者の両者が輸血拒否する場合
18 歳以上に準ずる。
(2) 親権者が拒否するが、当事者が 15 歳未満、または医療に関する判断能力がない場合
①親権者の双方が拒否する場合
医療側は、親権者の理解を得られるように努力し、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に
輸血が必要になれば、輸血を行う。親権者の同意が全く得られず、むしろ治療行為が阻害さ
れるような状況においては、児童相談所に虐待通告し、児童相談所で一時保護の上、児童相
談所から親権喪失を申し立て、あわせて親権者の職務停止の処分を受け、親権代行者の同意
により輸血を行う。
②親権者の一方が輸血に同意し、他方が拒否する場合
親権者の双方の同意を得るよう努力するが、緊急を要する場合などには、輸血を希望する親
権者の同意に基づいて輸血を行う。
2. 輸血同意書・免責証明書のフローチャート
当事者と親権者が輸血同意、拒否の場合に医療側が行うべき手順のフローチャートを図 1 に示す。
1
2008 年 2 月 28 日
宗教的輸血拒否に関するガイドライン
宗教的輸血拒否に関する合同委員会報告
1. 輸血実施に関する基本方針
輸血治療が必要となる可能性がある患者について、18 歳以上、15 歳以上 18 歳未満、15 歳未満の場合に
分けて、医療に関する判断能力と親権者の態度に応じた対応を整理した(図 1 参照)
。年齢区切りにつ
いては、18 歳は、児童福祉法第4条の「児童」の定義、15 歳は、民法第 797 条の代諾養子、民法第 961
条の遺言能力、
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針による臓器提供意思を斟酌して定めた。
1)当事者が 18 歳以上で医療に関する判断能力がある人の場合(なお、医療に関する判断能力は主治医
を含めた複数の医師によって評価する)
(1) 医療側が無輸血治療を最後まで貫く場合
当事者は、医療側に本人署名の「免責証明書」
(注1)を提出する。
(2) 医療側は無輸血治療が難しいと判断した場合
医療側は、当事者に早めに転院を勧告する。
2)当事者が 18 歳未満、または医療に関する判断能力がないと判断される場合
(1) 当事者が 15 歳以上で医療に関する判断能力がある場合
① 親権者は輸血を拒否するが、当事者が輸血を希望する場合
当事者は輸血同意書を提出する。
② 親権者は輸血を希望するが、当事者が輸血を拒否する場合
医療側は、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に必要な場合には輸血を行う。親権者から
輸血同意書を提出してもらう。
③ 親権者と当事者の両者が輸血拒否する場合
18 歳以上に準ずる。
(2) 親権者が拒否するが、当事者が 15 歳未満、または医療に関する判断能力がない場合
①親権者の双方が拒否する場合
医療側は、親権者の理解を得られるように努力し、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に
輸血が必要になれば、輸血を行う。親権者の同意が全く得られず、むしろ治療行為が阻害さ
れるような状況においては、児童相談所に虐待通告し、児童相談所で一時保護の上、児童相
談所から親権喪失を申し立て、あわせて親権者の職務停止の処分を受け、親権代行者の同意
により輸血を行う。
②親権者の一方が輸血に同意し、他方が拒否する場合
親権者の双方の同意を得るよう努力するが、緊急を要する場合などには、輸血を希望する親
権者の同意に基づいて輸血を行う。
2. 輸血同意書・免責証明書のフローチャート
当事者と親権者が輸血同意、拒否の場合に医療側が行うべき手順のフローチャートを図 1 に示す。
1