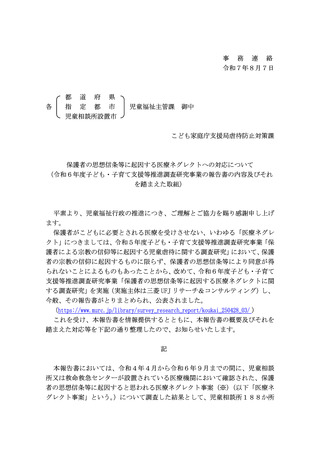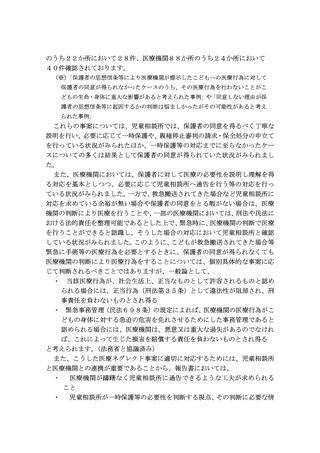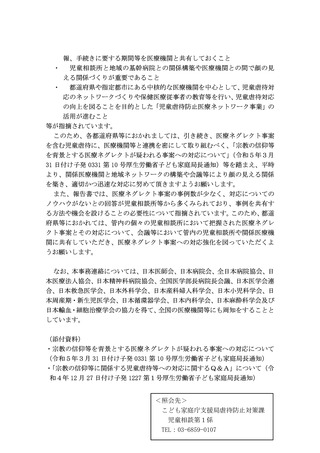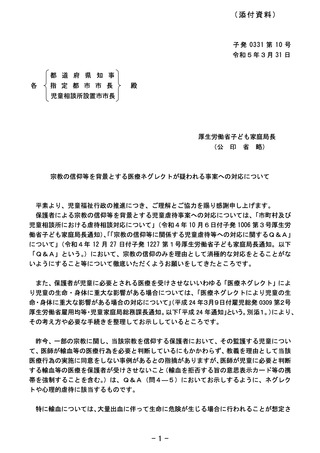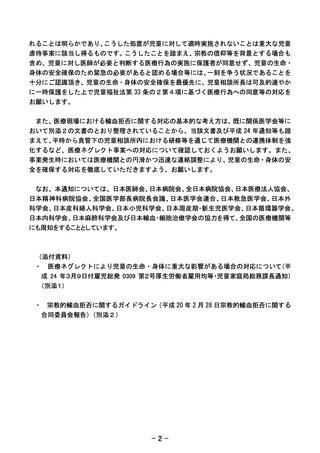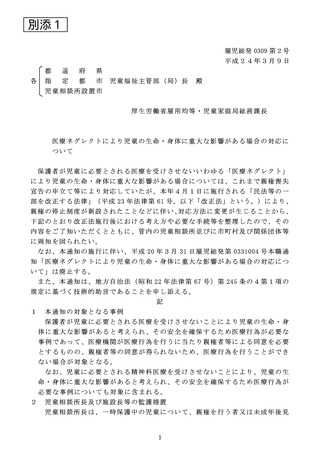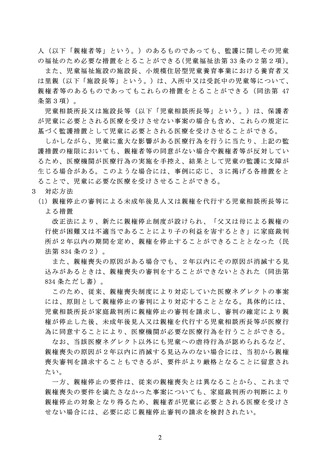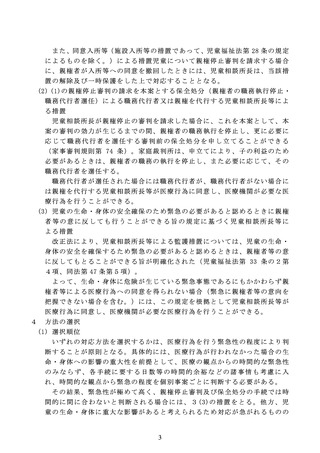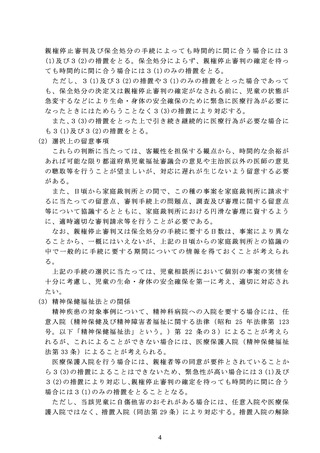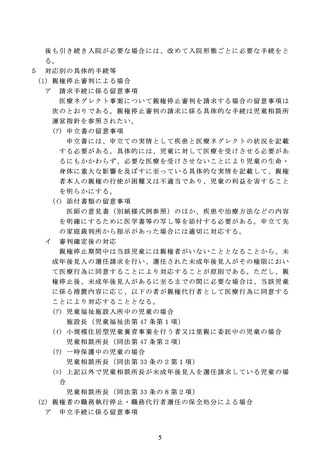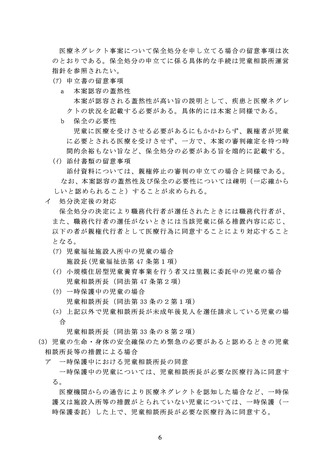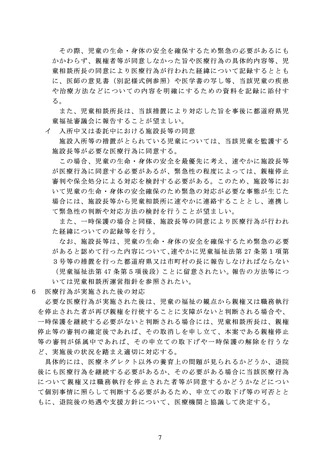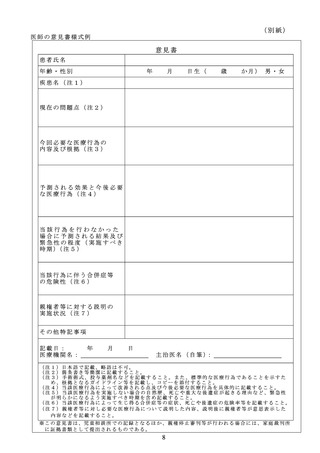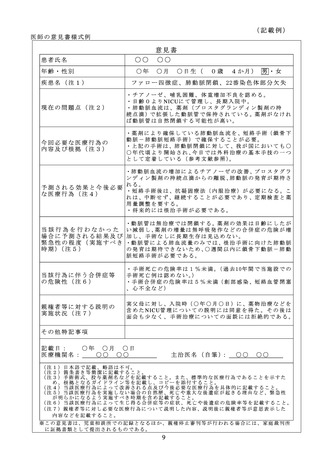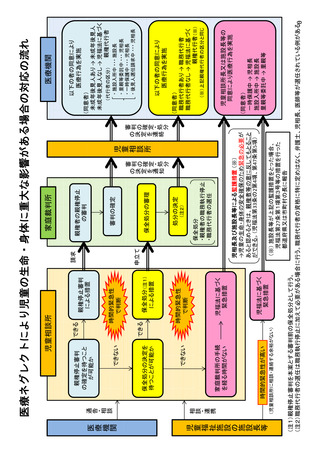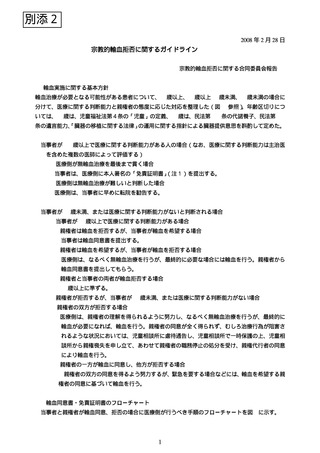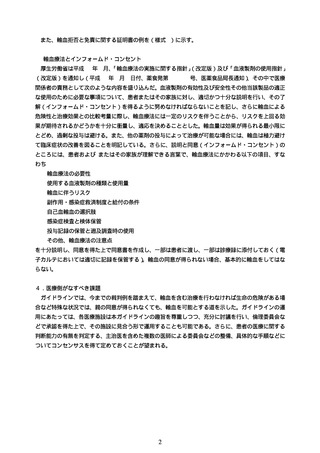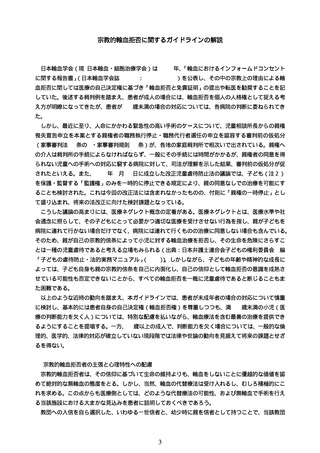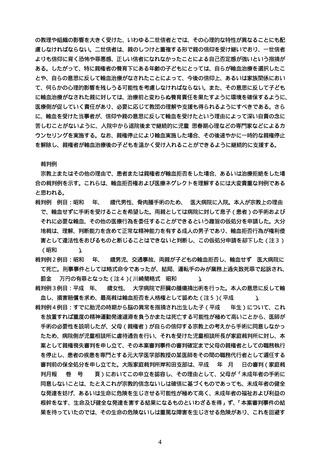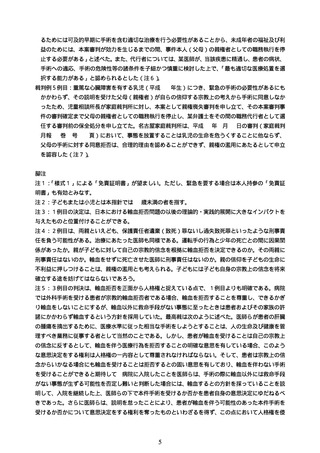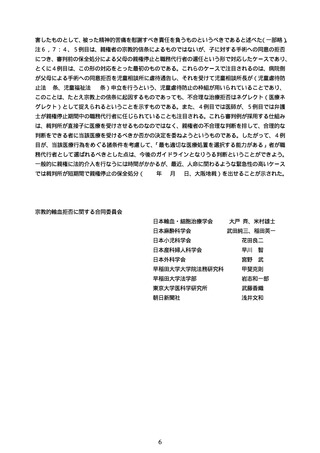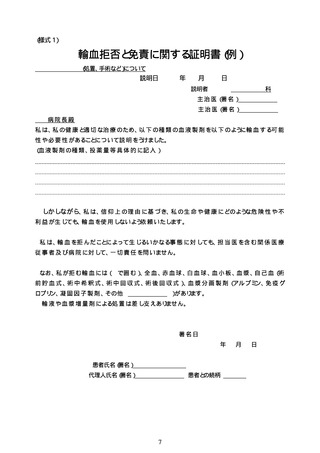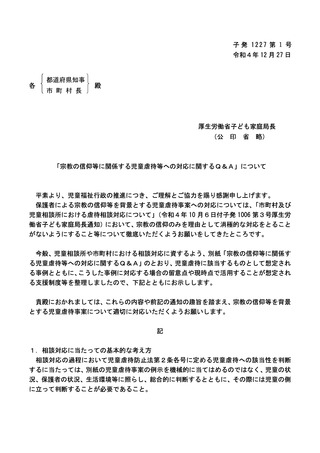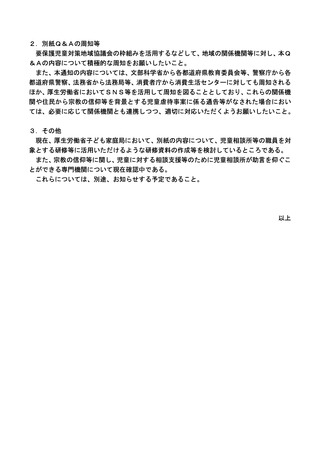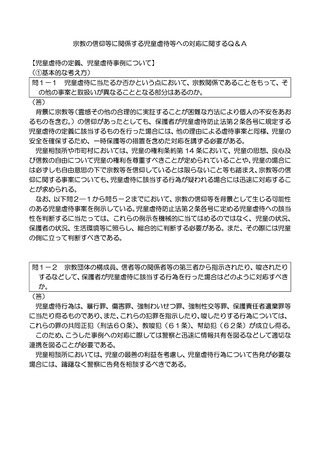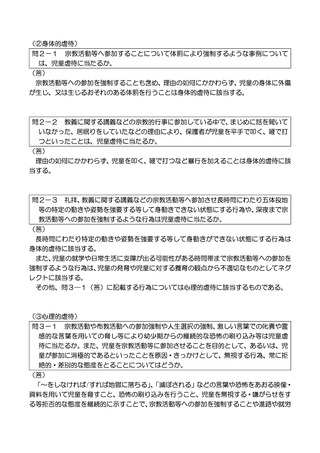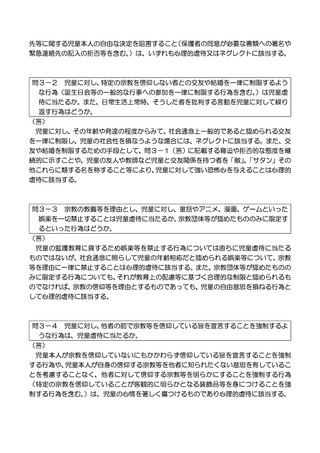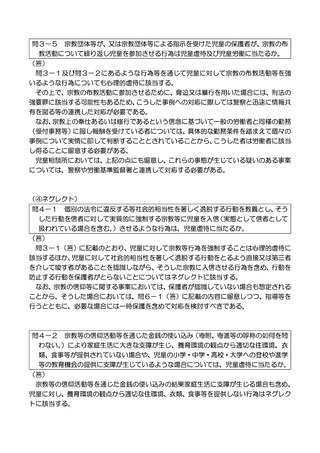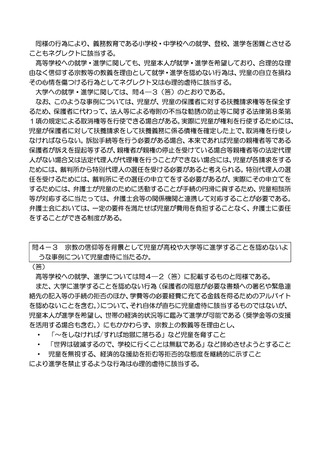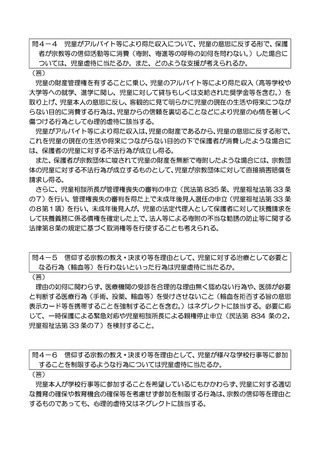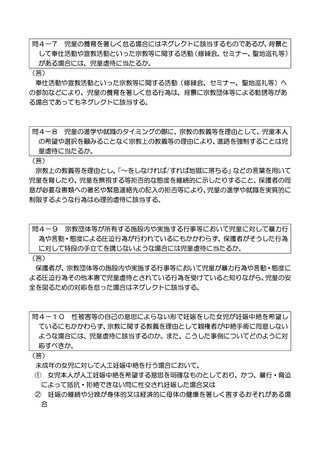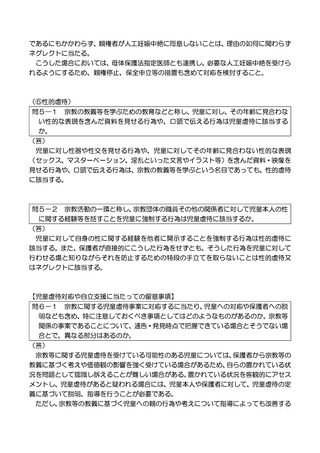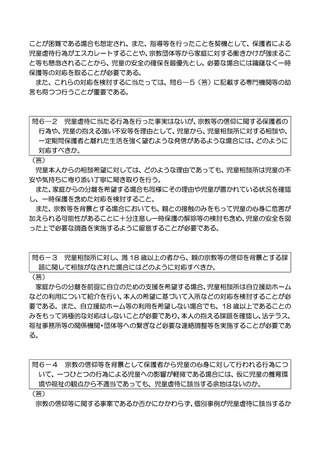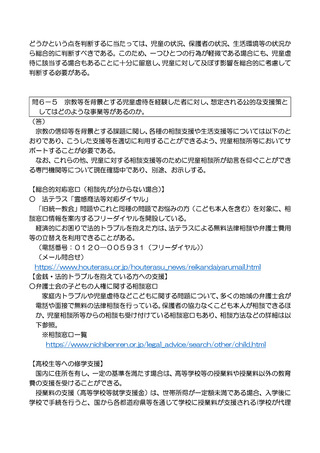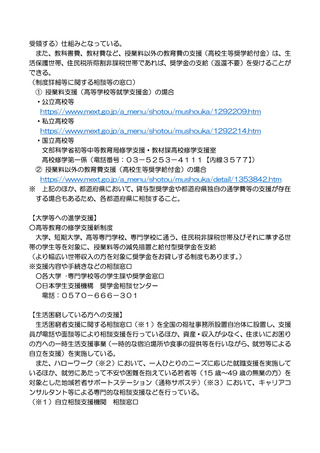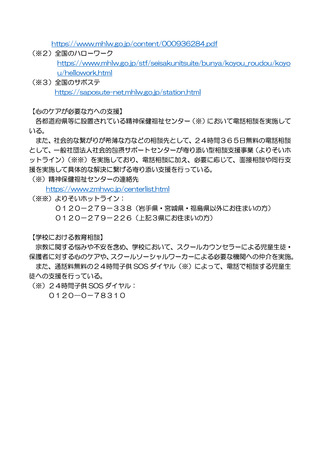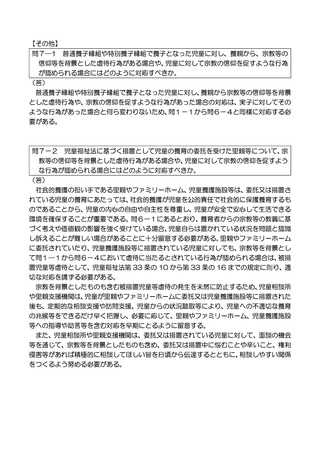よむ、つかう、まなぶ。
保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
問3-5 宗教団体等が、又は宗教団体等による指示を受けた児童の保護者が、宗教の布
教活動について繰り返し児童を参加させる行為は児童虐待及び児童労働に当たるか。
(答)
問3-1及び問3-2にあるような行為等を通じて児童に対して宗教の布教活動等を強
いるような行為についても心理的虐待に該当する。
その上で、宗教の布教活動に参加させるために、脅迫又は暴行を用いた場合には、刑法の
強要罪に該当する可能性もあるため、こうした事例への対応に際しては警察と迅速に情報共
有を図る等の連携した対応が必要である。
なお、宗教上の奉仕あるいは修行であるという信念に基づいて一般の労働者と同様の勤務
(受付事務等)に服し報酬を受けている者については、具体的な勤務条件を踏まえて個々の
事例について実情に即して判断することとされていることから、こうした者は労働者に該当
し得ることに留意する必要がある。
児童相談所においては、上記の点にも留意し、これらの事態が生じている疑いのある事案
については、警察や労働基準監督署と連携して対応する必要がある。
(④ネグレクト)
問4-1 個別の法令に違反する等社会的相当性を著しく逸脱する行動を教義とし、そう
した行動を信者に対して実質的に強制する宗教等に児童を入信(実態として信者として
扱われている場合を含む。)させるような行為は、児童虐待に当たるか。
(答)
問3-1(答)に記載のとおり、児童に対して宗教等行為を強制することは心理的虐待に
該当するほか、児童に対して社会的相当性を著しく逸脱する行動をとるよう直接又は第三者
を介して唆す者があることを認識しながら、そうした宗教に入信させる行為を含め、行動を
防止する行動を保護者がとらないことについてはネグレクトに該当する。
なお、宗教の信仰等に関する事案においては、保護者が認識していない場合も想定される
ことから、そうした場合においては、問6-1(答)に記載の内容に留意しつつ、指導等を
行うとともに、必要な場合には一時保護を含めて対応を検討すべきである。
問4-2 宗教等の信仰活動等を通じた金銭の使い込み(寄附、寄進等の呼称の如何を問
わない。)により家庭生活に大きな支障が生じ、養育環境の観点から適切な住環境、衣
類、食事等が提供されていない場合や、児童の小学・中学・高校・大学への登校や進学
等の教育機会の提供に支障が生じているような場合については、児童虐待に当たるか。
(答)
宗教等の信仰活動等を通じた金銭の使い込みの結果家庭生活に支障が生じる場合も含め、
児童に対し、養育環境の観点から適切な住環境、衣類、食事等を提供しない行為はネグレク
トに該当する。
教活動について繰り返し児童を参加させる行為は児童虐待及び児童労働に当たるか。
(答)
問3-1及び問3-2にあるような行為等を通じて児童に対して宗教の布教活動等を強
いるような行為についても心理的虐待に該当する。
その上で、宗教の布教活動に参加させるために、脅迫又は暴行を用いた場合には、刑法の
強要罪に該当する可能性もあるため、こうした事例への対応に際しては警察と迅速に情報共
有を図る等の連携した対応が必要である。
なお、宗教上の奉仕あるいは修行であるという信念に基づいて一般の労働者と同様の勤務
(受付事務等)に服し報酬を受けている者については、具体的な勤務条件を踏まえて個々の
事例について実情に即して判断することとされていることから、こうした者は労働者に該当
し得ることに留意する必要がある。
児童相談所においては、上記の点にも留意し、これらの事態が生じている疑いのある事案
については、警察や労働基準監督署と連携して対応する必要がある。
(④ネグレクト)
問4-1 個別の法令に違反する等社会的相当性を著しく逸脱する行動を教義とし、そう
した行動を信者に対して実質的に強制する宗教等に児童を入信(実態として信者として
扱われている場合を含む。)させるような行為は、児童虐待に当たるか。
(答)
問3-1(答)に記載のとおり、児童に対して宗教等行為を強制することは心理的虐待に
該当するほか、児童に対して社会的相当性を著しく逸脱する行動をとるよう直接又は第三者
を介して唆す者があることを認識しながら、そうした宗教に入信させる行為を含め、行動を
防止する行動を保護者がとらないことについてはネグレクトに該当する。
なお、宗教の信仰等に関する事案においては、保護者が認識していない場合も想定される
ことから、そうした場合においては、問6-1(答)に記載の内容に留意しつつ、指導等を
行うとともに、必要な場合には一時保護を含めて対応を検討すべきである。
問4-2 宗教等の信仰活動等を通じた金銭の使い込み(寄附、寄進等の呼称の如何を問
わない。)により家庭生活に大きな支障が生じ、養育環境の観点から適切な住環境、衣
類、食事等が提供されていない場合や、児童の小学・中学・高校・大学への登校や進学
等の教育機会の提供に支障が生じているような場合については、児童虐待に当たるか。
(答)
宗教等の信仰活動等を通じた金銭の使い込みの結果家庭生活に支障が生じる場合も含め、
児童に対し、養育環境の観点から適切な住環境、衣類、食事等を提供しない行為はネグレク
トに該当する。