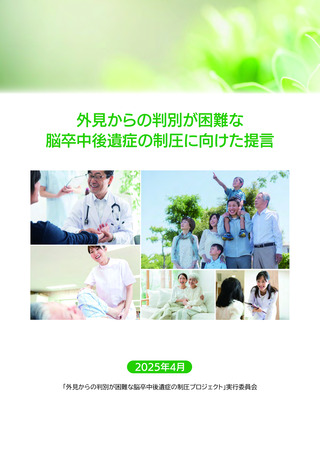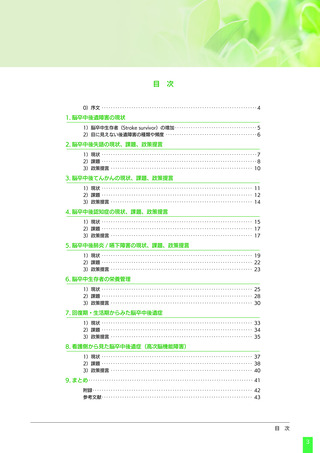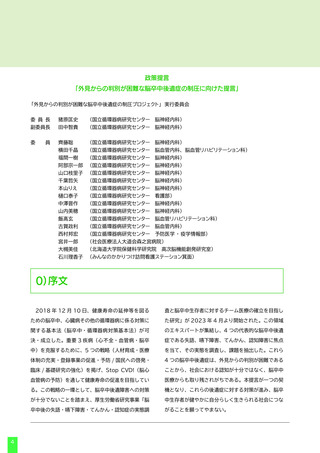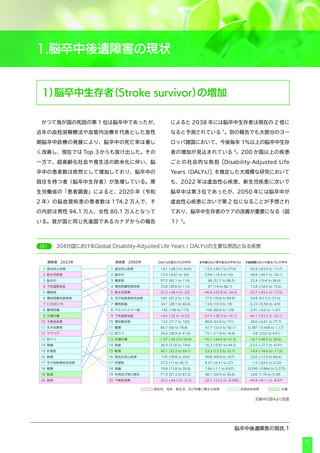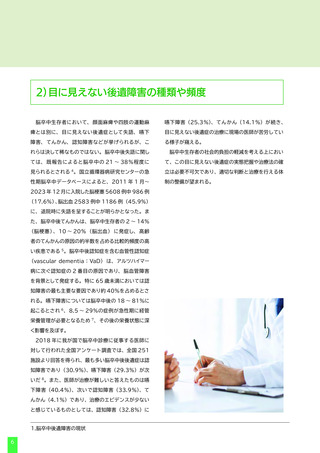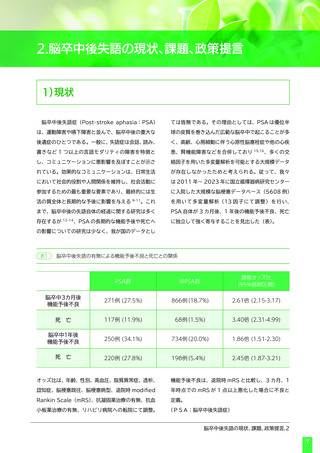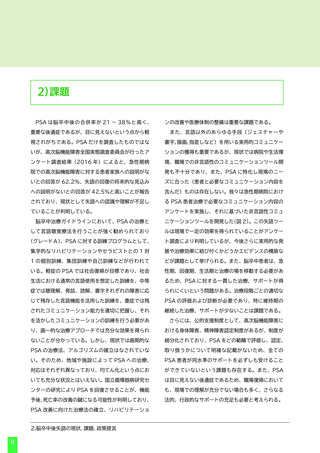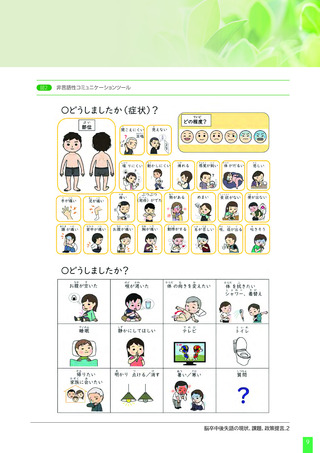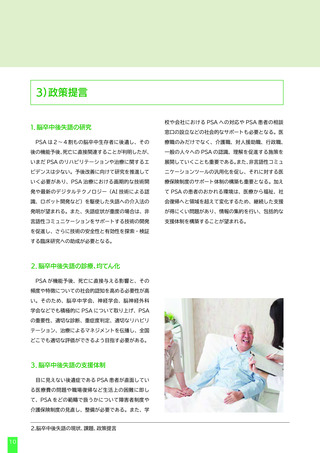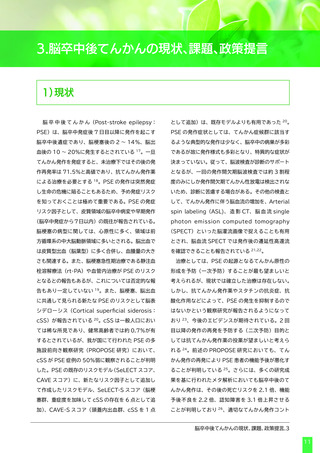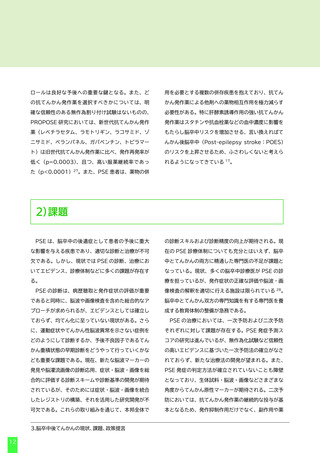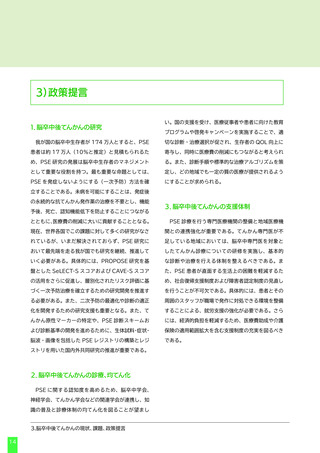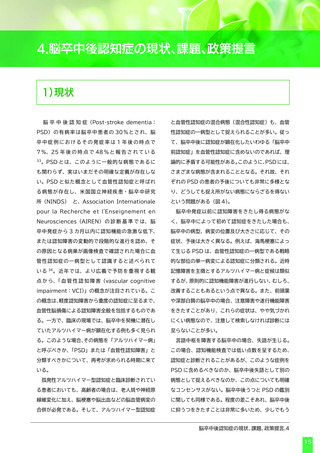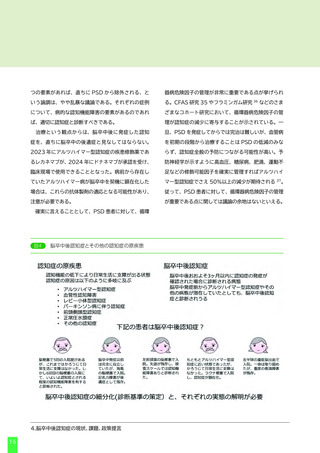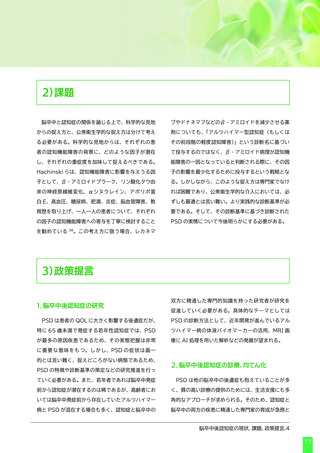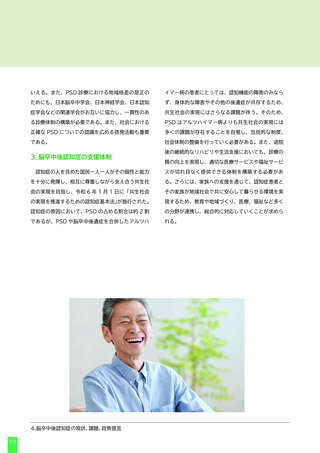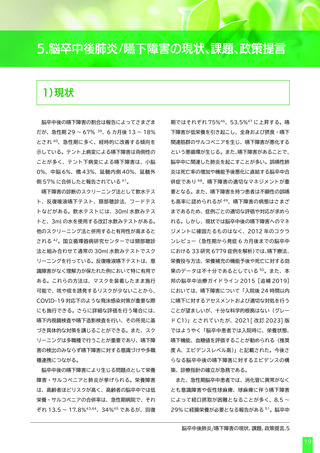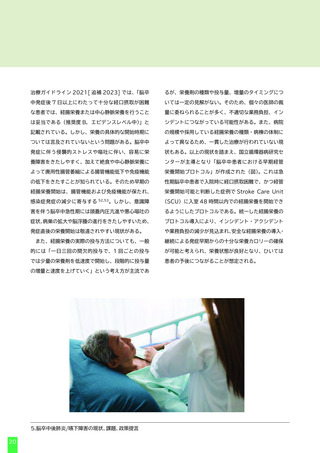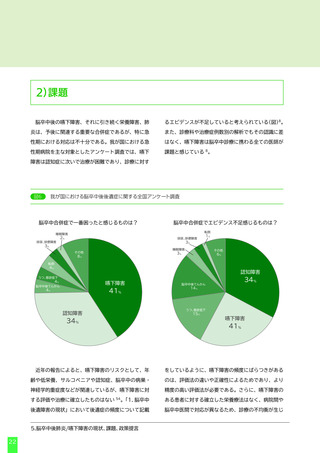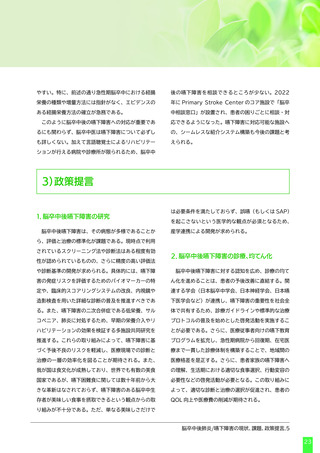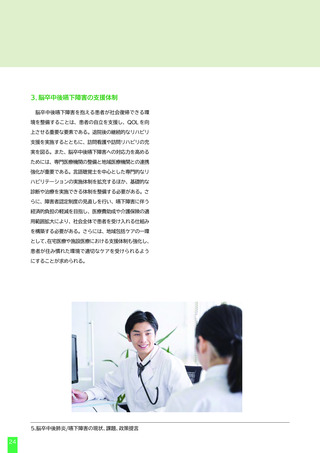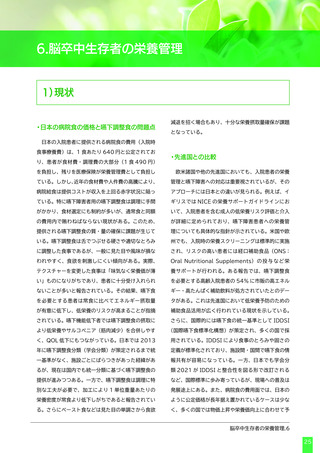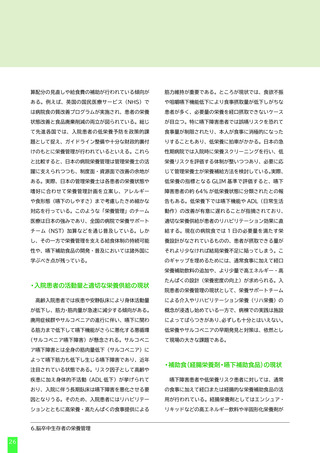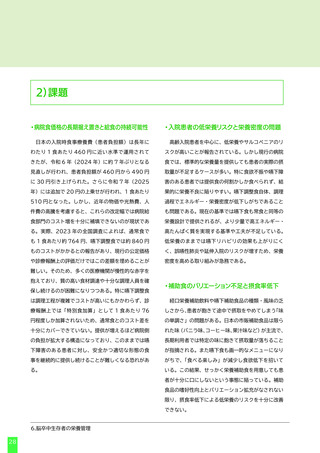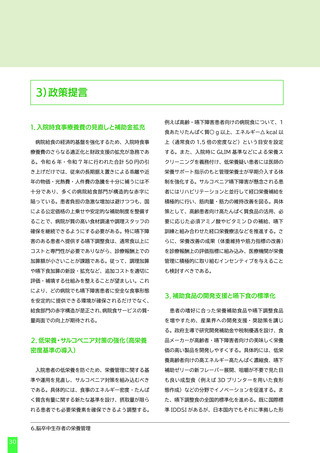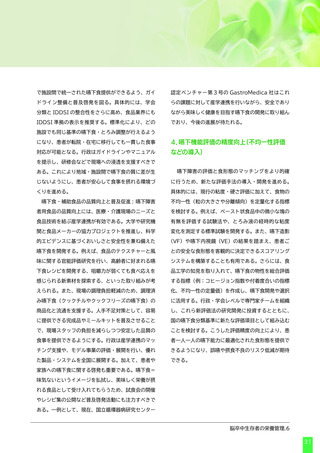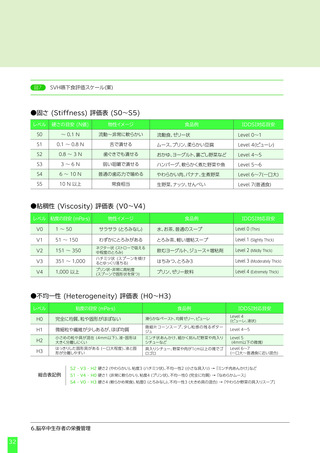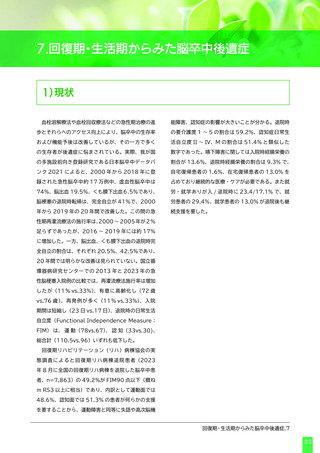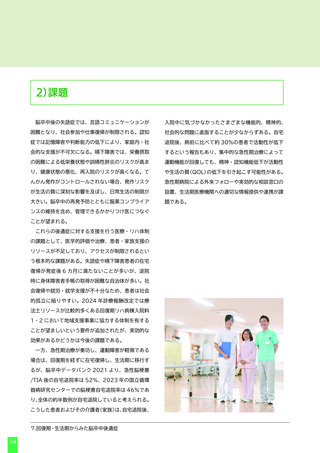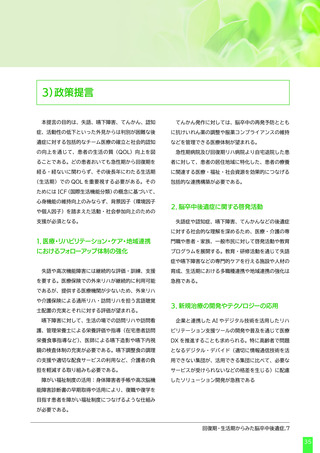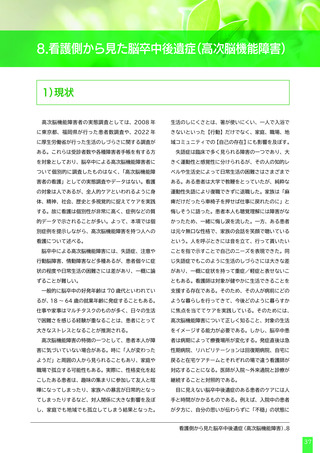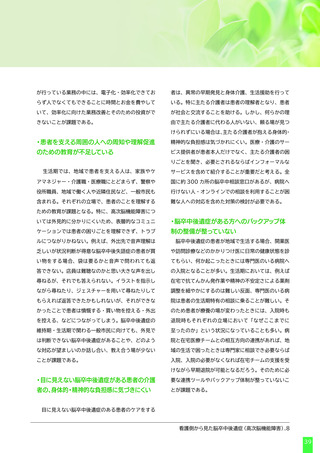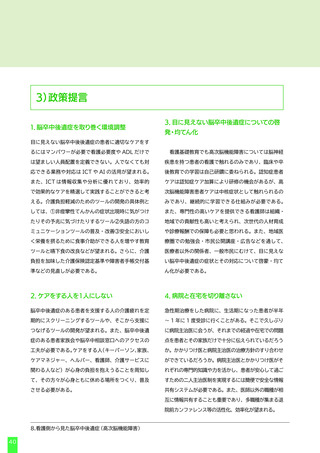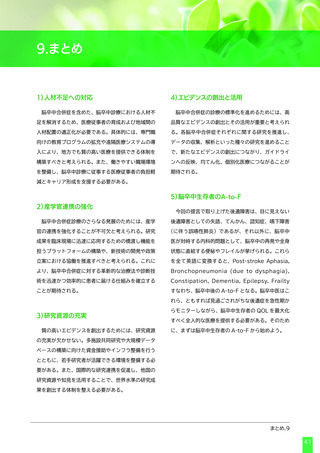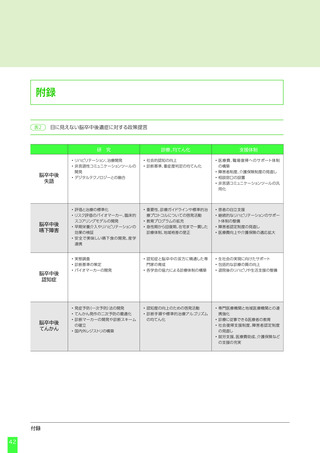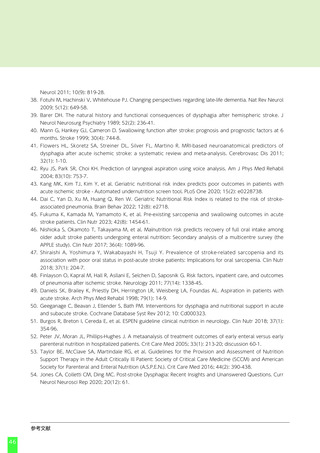よむ、つかう、まなぶ。
外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |
| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
なった際には、その患者だけに看護師 1 名ないし2
の専門職以外には家族や一般市民などが担うこととな
名が付き添うことになる。すると夕食時の忙しい時間
る。ある外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の患者
帯に人手が足りず、仕方なくその患者に鎮静・抑制を
の生活を支える家族は、思い通りにならないと暴言暴
検討しなければ他の患者も含め安全が守れなくなる。
力を行う患者がレスパイトのために行ったショートス
また、嚥下障害のある患者に安全に食事ができるよう
テイ先のスタッフにも暴力を行った事実から、介護を
に直接嚥下訓練(食事介助)をするときには、1 人以
他者に委譲することに申し訳なさを感じ、患者のペー
上の専門職が 30 分程度つきっきりとなるためマンパ
スに振り回され疲弊しつつも、他者への助けを求めら
ワーが不足すると十分な時間直接嚥下訓練に当てるこ
れないことがあった。このように、家族や介護を担う
とができなくなる。また、専門職が食事介助しなくて
人が「自分がやらないと。自分が我慢すればよい」と
もよい状態の患者にも、限られた専門職で対応しなけ
不安や悩みを抱え込んでしまいかねない。看護師やそ
ればならないときは、介助の時間が限られて十分な量
の他脳卒中に精通した専門職は患者に影響を与える家
の食事が摂れないこともあった。
族も看護ケアの対象と捉え家族の相談相手となり得
家族看護の視点で見ると、患者は家族の一員で、家
る。全ての脳卒中患者に対するシームレスな医療・介
族は患者の言動の影響を色濃く受け、また家族も患者
護・福祉連携を充実させるための、脳卒中相談窓口は
に影響を与えている存在である。維持期や生活期に
2024 年 10 月時点で全国に約 300 カ所あり、悩
なると、看護師や介護職が担っていた日常生活におけ
める患者および家族を救うことを期待されている。
る支援は、訪問介護や訪問看護、ケアマネジャーなど
2)課題
・マンパワー不足
反映しきれず、さらに 2024 年の改訂では 7:1 病
目に見えない脳卒中後遺症のケアにはマンパワーが
棟(急性期一般入院料1)で評価する看護必要度から
必要である。脳卒中後遺症に関する知識をもった医療
「B 項目」が無くなる。脳卒中後遺症のある患者を支
者が 1 人、患者のそばに居たとしても、患者の状態
えるマンパワーを反映させる指標としては厳しく、ま
や思いを汲み取り適切に対応するには時間がかかるこ
た適切な人員配置に導く指標が乏しいことが課題であ
とが多い。入院病棟における看護職員の配置基準は、
る。介護保険認定調査では認知機能や社会的行動、認
「重症度・医療看護必要度」
、
「入院期間」
、
「在宅復帰率」
知症高齢者自立度で評価するがそれで十分なのか検討
で決められている。目に見えない脳卒中後遺症の患者
の余地がある。病院や施設・在宅において、医師・看
にかかるマンパワーは重症度・医療看護必要度の「B
護師・セラピスト・介護士などの専門職や事務員など
8.看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害)
38
項目」
(患者の ADL や従命・危険行動を評価)では
の専門職以外には家族や一般市民などが担うこととな
名が付き添うことになる。すると夕食時の忙しい時間
る。ある外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の患者
帯に人手が足りず、仕方なくその患者に鎮静・抑制を
の生活を支える家族は、思い通りにならないと暴言暴
検討しなければ他の患者も含め安全が守れなくなる。
力を行う患者がレスパイトのために行ったショートス
また、嚥下障害のある患者に安全に食事ができるよう
テイ先のスタッフにも暴力を行った事実から、介護を
に直接嚥下訓練(食事介助)をするときには、1 人以
他者に委譲することに申し訳なさを感じ、患者のペー
上の専門職が 30 分程度つきっきりとなるためマンパ
スに振り回され疲弊しつつも、他者への助けを求めら
ワーが不足すると十分な時間直接嚥下訓練に当てるこ
れないことがあった。このように、家族や介護を担う
とができなくなる。また、専門職が食事介助しなくて
人が「自分がやらないと。自分が我慢すればよい」と
もよい状態の患者にも、限られた専門職で対応しなけ
不安や悩みを抱え込んでしまいかねない。看護師やそ
ればならないときは、介助の時間が限られて十分な量
の他脳卒中に精通した専門職は患者に影響を与える家
の食事が摂れないこともあった。
族も看護ケアの対象と捉え家族の相談相手となり得
家族看護の視点で見ると、患者は家族の一員で、家
る。全ての脳卒中患者に対するシームレスな医療・介
族は患者の言動の影響を色濃く受け、また家族も患者
護・福祉連携を充実させるための、脳卒中相談窓口は
に影響を与えている存在である。維持期や生活期に
2024 年 10 月時点で全国に約 300 カ所あり、悩
なると、看護師や介護職が担っていた日常生活におけ
める患者および家族を救うことを期待されている。
る支援は、訪問介護や訪問看護、ケアマネジャーなど
2)課題
・マンパワー不足
反映しきれず、さらに 2024 年の改訂では 7:1 病
目に見えない脳卒中後遺症のケアにはマンパワーが
棟(急性期一般入院料1)で評価する看護必要度から
必要である。脳卒中後遺症に関する知識をもった医療
「B 項目」が無くなる。脳卒中後遺症のある患者を支
者が 1 人、患者のそばに居たとしても、患者の状態
えるマンパワーを反映させる指標としては厳しく、ま
や思いを汲み取り適切に対応するには時間がかかるこ
た適切な人員配置に導く指標が乏しいことが課題であ
とが多い。入院病棟における看護職員の配置基準は、
る。介護保険認定調査では認知機能や社会的行動、認
「重症度・医療看護必要度」
、
「入院期間」
、
「在宅復帰率」
知症高齢者自立度で評価するがそれで十分なのか検討
で決められている。目に見えない脳卒中後遺症の患者
の余地がある。病院や施設・在宅において、医師・看
にかかるマンパワーは重症度・医療看護必要度の「B
護師・セラピスト・介護士などの専門職や事務員など
8.看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害)
38
項目」
(患者の ADL や従命・危険行動を評価)では